特集の意図
シャルコーによって最初の報告が行われてからちょうど150年。筋萎縮性側索硬化症(ALS)は依然として難病である。しかし,分子病態や原因遺伝子が明らかにされ,“治せる病気”へと一歩ずつ着実に進んでいる。複数の治験が現在進行中であり,2019年におけるALSを取り巻く現状,そして今後の展望について多方面から論じる。
雑誌目次
BRAIN and NERVE-神経研究の進歩71巻11号
2019年11月発行
雑誌目次
増大特集 ALS2019
扉 フリーアクセス
ページ範囲:P.1126 - P.1127
ALSの疫学と発症リスク
著者: 成田有吾
ページ範囲:P.1129 - P.1137
ALSの最近の疫学的報告を中心に紹介した。発症率・有病率は,東アジアで低く,欧米白人で高く,日本はその中間と推定された。男女比は1.3〜1.6倍で男性に高く,加齢による増加を確認した。1997〜2015年度の本邦のALS医療受給者証所持者数を集計し,日本のALS診療ガイドライン(2013)上の,発症率1.1〜2.5,有病率7.0〜8.5(人/10万人/年)の見積りは妥当と判断された。ALS発症リスクとして喫煙が挙げられたが,他要因についてはさらなる検討が必要であった。
診断基準と電気診断の変遷
著者: 野寺裕之
ページ範囲:P.1138 - P.1144
ALSの診断基準はいくつかあるが,改訂El Escorial診断基準が最も多く用いられてきた。早期例での検出力に問題があることから,針筋電図による線維束収縮電位を積極的に取り入れたAwaji電気診断基準が提唱され,下位運動ニューロン障害が鋭敏に検出できるようになった。さらに,上位運動ニューロン障害の整合性を高めたUpdated Awaji診断基準が提唱されたり,線維束収縮を超音波で検出したりすることで,より早期例の検出を可能とする診断基準が制定されようとしている。
Split Hand—ALSに特徴的な神経徴候
著者: 澁谷和幹
ページ範囲:P.1145 - P.1151
Split handとは,母指球筋や第一背側骨間筋が萎縮するのに対し,小指球筋が比較的保たれる現象を指す。この所見は,筋萎縮性側索硬化症(ALS)に特異的に認められると考えられている。本論ではsplit handを含め,ALSに特徴的な筋力低下や筋萎縮の分布,神経徴候を概説し,これらの徴候の背景病態やALS診断における有用性を考察する。
ALSの病理
著者: 吉田眞理
ページ範囲:P.1152 - P.1168
筋萎縮性側索硬化症(ALS)は病理学的に上位運動ニューロン(UMN)と下位運動ニューロン(LMN)がさまざまな程度の組合せで障害される疾患である。孤発性ALSのLMNではTDP-43の核内局在が消失し,細胞質に異常に凝集して封入体を形成する。TDP-43の封入体は運動ニューロン系を超えて神経細胞とグリア細胞に分布する。病変の進展機序に,TDP-43のプリオン病様蛋白伝播仮説が提唱されている。
家族性ALS
著者: 鈴木直輝 , 西山亜由美 , 加藤昌昭 , 割田仁 , 青木正志
ページ範囲:P.1169 - P.1181
筋萎縮性側索硬化症(ALS)の約10%を占める家族性ALSの解析を通じて20以上の病因遺伝子が明らかになっている。本総説では日本人の家族性ALSで頻度の高い病因遺伝子を中心にその臨床的な特徴をまとめる。近年明らかになった家族性ALS病因遺伝子の機能異常は蛋白恒常性維持機構の破綻,RNA代謝異常,軸索病態・細胞骨格異常といった分子病態に収斂してきており,家族性ALSの病態解明とそれを基盤にした治療開発の現状にも触れる。
TDP-43封入体から解くALSの分子病態
著者: 坪口晋太朗 , 石原智彦 , 須貝章弘 , 横関明男 , 小野寺理
ページ範囲:P.1183 - P.1189
TDP-43蛋白質の封入体形成機構は,筋萎縮性側索硬化症(ALS)の主要な分子病態機序である。ALS原因遺伝子の機能解析から,TDP-43封入体形成にはストレス顆粒形成,蛋白質分解機構,TDP-43蛋白質の自己調節機構の破綻などが関わることが見出された。これらの解明された分子病態に基づく,ALS治療方法の確立が期待される。
C9orf72—日本のALS/FTDにおけるインパクト
著者: 富山弘幸
ページ範囲:P.1190 - P.1208
2011年にC9orf72遺伝子のイントロン1内の6塩基(GGGGCC)繰り返し配列の伸長変異(HRE)が,白人の孤発性および家族性筋萎縮性側索硬化症(ALS)そして前頭側頭型認知症(FTD)の最も頻度の高い原因であると報告された。日本のALS患者群では,C9orf72変異陽性例は孤発性ALSの0.2%,家族性ALSの約2.6%で,紀伊半島の多発地帯の解析では20%(3/15)と高頻度であった。われわれは詳細な家族歴を確認し,孤発性および家族性ALS/FTDにおいて,C9orf72をはじめ病因そして病態を探っていくべきである。
プリオノイド仮説の現状
著者: 野中隆
ページ範囲:P.1209 - P.1214
多くの神経変性疾患においてプリオン様凝集体が細胞間を伝播するというプリオノイド仮説が注目されている。タウ,αシヌクレイン,TDP-43などの凝集性蛋白質が細胞内で凝集体を形成し,これらが細胞間を伝播して細胞内でシードとして機能することが多数報告されている。そのメカニズムの詳細は明らかになっていないが,それらの細胞間伝播を抑制することは新たな治療法の開発につながることが期待される。
ALSにおける患者レジストリの役割—JaCALSなど
著者: 熱田直樹 , 中村亮一 , 林直毅 , 藤内玄規 , 勝野雅央 , 祖父江元
ページ範囲:P.1215 - P.1225
ALS患者に適切な診療とケアを提供し,治療開発を推進するために,患者レジストリの果たし得る役割は大きい。わが国のALS患者レジストリJaCALSからは多様なALS患者の自然歴,遺伝的背景,進行・予後に関わる臨床的,遺伝的背景が示され,生体試料を活用した病態解明,創薬の取組みも行われている。今後さらに大規模症例数を生かしたリアルワールドエビデンスの創出が試みられる予定である。
ALSとFTD
著者: 渡辺保裕
ページ範囲:P.1227 - P.1235
筋萎縮性側索硬化症(ALS)と前頭側頭型認知症(FTD)はしばしば合併する。言語障害型FTDの進行性非流暢性失語症(PNFA)と意味性認知症(SD)はそれぞれ特有の進行性失語症状を呈する。行動障害型FTDの認知機能障害の特徴は,遂行機能障害,語流暢性の障害,言語機能の障害である。行動異常は早期から無関心(アパシー)や脱抑制などが認められる。ALSではFTDの基準を満たさない軽度の認知機能障害,行動異常はさらに高頻度に認められる。これらの神経・精神症状を適切に評価し,非薬物的および薬物的介入につなげることが重要である。
紀伊ALS/PDCの現状2019
著者: 小久保康昌
ページ範囲:P.1236 - P.1244
紀伊半島の筋萎縮性側索硬化症/パーキンソン認知症複合(紀伊ALS/PDC)の2015年以降の最近の知見として,毛髪中の遷移元素解析,ドパミンPET,多発地区でのライフスタイルの変化,神経毒BMAA解析,migration症例,18例の神経病理,小脳のタウ病理,ニトロ化ストレス解析,optinurin病理,タウPET,の各論文について概説した。また,現時点での病因に関して考察した。多発地区では,同じ環境に少数の発症者と多くの非発症者が存在することや短期間多発地に居住した転出者に発症例がいる一方,90年以上居住しても発症していない住民もあり,環境要因への単純な曝露のみを原因とすることには無理がある。このような現象の遺伝学的な説明として,rare-disease and rare-variantモデルが提唱されている。さらに,ここ数十年に起きた多発地区での疾患頻度の減少という事実は神経変性疾患がなんらかの介入によって病態修飾し得るということを示唆しており,本疾患のrisk遺伝子と環境要因を突き止めることは,神経変性疾患全般の予防や早期介入に寄与するものと期待される。
エダラボンを用いた新規ALS治療
著者: 山下徹 , 阿部康二
ページ範囲:P.1245 - P.1251
1993年に家族性ALSの原因遺伝子として活性酸素分解酵素であるSOD1遺伝子の変異が発見され,フリーラジカル障害がALS病態に深く関わることが示唆された。そこで急性期脳梗塞治療に認可されていたフリーラジカル除去薬エダラボンを用いたALS患者への臨床治験が行われ,症状進行抑制効果を認めたことを受け2015年6月に新規治療薬として認可された。本稿では,当科が取り組んできたALS治療新規開発に向けた基礎・臨床研究の成果をご紹介する。
HGFによる治療法開発
著者: 青木正志 , 割田仁 , 加藤昌昭 , 鈴木直輝
ページ範囲:P.1253 - P.1260
われわれはALSに対する新規治療法の開発のために,ALSラットに対して肝細胞増殖因子(HGF)蛋白の髄腔内持続投与を行い,明確な治療効果を確認した。さらにマーモセットおよびカニクイザルに対するHGF蛋白の髄腔内持続投与による安全性(毒性)および薬物動態試験を行った。東北大学病院におけるALS患者に対する第Ⅰ相試験を経て,現在,大阪大学との2施設で医師主導治験による第Ⅱ相試験を行っている。
メコバラミン
著者: 和泉唯信 , 沖良祐 , 桑原聡 , 梶龍兒
ページ範囲:P.1261 - P.1269
高用量メコバラミンは臨床経験をとおして筋萎縮性側索硬化症(ALS)に対する有効性が示唆され,第Ⅱ/Ⅲ相試験(E0302-J081-761)において部分解析ではあるが発症1年以内のALS患者に対して生存期間延長とALS機能評価スケール(ALSFRS-R)合計点数の低下の抑制効果が認められた。今回われわれは発症1年以内のALS患者に対する高用量メコバラミン(E0302)の有効性・安全性の検証を目的として「高用量E0302の筋萎縮性側索硬化症に対する第Ⅲ相試験—医師主導治験—」(JETALS)を開始した。本治験は前向き,多施設共同,プラセボ対象,二重盲検,ランダム化比較第Ⅲ相試験であり,国内25施設が参加する。128例の被験者に対して16週にわたりE0302 50mgもしくはプラセボの週2回筋肉注射を行う。主要評価項目は割付日から16週目までのALSFRS-R合計点数の変化量である。症例登録期間は2017年11月〜2019年9月であり,2020年3月に治験終了予定である。有効性が確認され早期に承認されることが期待される。
孤発性ALSに対するペランパネル
著者: 相澤仁志 , 郭伸
ページ範囲:P.1270 - P.1278
孤発性筋萎縮性側索硬化症(ALS)の運動ニューロンではAMPA型グルタミン酸受容体を構成しているGluA2のQ/R部位の編集率が低下しており,AMPA受容体を介したCa2+流入が過剰となり,最終的に運動ニューロン死に至ると考えられる。実際,AMPA受容体拮抗薬ペランパネルの全身投与は,ALSの病態モデルマウスの病態進行を有意に阻止した。現在,孤発性ALSを対象としたペランパネルの無作為化二重盲検臨床試験を行い,2020年春にはその結果が得られる。
ロピニロール塩酸塩—iPS細胞創薬
著者: 髙橋愼一 , 森本悟 , 福島弘明 , 中原仁 , 岡野栄之
ページ範囲:P.1279 - P.1288
2018年12月より,筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者に対するロピニロール塩酸塩の安全性・忍容性および有効性を探索するプラセボ対照,二重盲検期および非盲検継続投与期から成る第Ⅰ/Ⅱa相試験を開始した。ロピニロール塩酸塩は,家族性および孤発性ALS患者の疾患特異的iPS細胞(iPSC)を用いて作成された脊髄運動ニューロンのin vitro疾患表現型を抑制し得る薬剤として,1,232種類の既存薬ライブラリーからスクリーニングされた薬剤であり,本試験の成否は今後のiPSC創薬研究の試金石となる。
ALSにおける免疫療法開発の現状と展望
著者: 漆谷真 , 玉木良高 , 引網亮太 , 南山素三雄
ページ範囲:P.1289 - P.1301
筋萎縮性側索硬化症(ALS)の病態において変異SOD1やTDP-43を代表とするミスフォールド蛋白質は細胞内外で多彩な病的パスウェイの原因となる。ワクチンや抗体分子を用いた免疫療法は特定の構造のみを標的とすることが可能なため有力な分子標的治療であるが,ミスフォールド蛋白質の主座が細胞内外のいずれかによってアプローチが異なり,細胞外蛋白質には全長抗体,細胞内蛋白質には一本鎖抗体(scFv)の開発研究が進んでいる。
症例報告
デュプュイトラン拘縮を合併した遠位型頸椎症性筋萎縮症の1例
著者: 伏屋公晴 , 吉倉延亮 , 大野陽哉 , 竹腰顕 , 木村暁夫 , 下畑享良
ページ範囲:P.1303 - P.1307
左手指の伸展障害を呈した75歳,男性の症例を経験した。デュプュイトラン拘縮により,手指の伸展制限を認めたが,それのみでは説明がつかない母指の外転や手関節伸展の障害を認めた。筋力低下の分布からは,C7,C8,Th1髄節に筋力低下があり,針筋電図でも同部位に脱神経所見を認め,遠位型頸椎症性筋萎縮症の合併と診断した。デュプュイトラン拘縮と遠位型頸椎症性筋萎縮症は,ともに手指の伸展が障害される疾患で症状が類似していることから,両者が合併した場合,いずれかを見落とす可能性がある。デュプュイトラン拘縮では手掌の数珠状の硬結が,遠位型頸椎症性筋萎縮症では髄節性の筋力低下や,針筋電図検査による障害部位の分布が診断に有用である。
現代神経科学の源流・11
伊藤正男【中編】
著者: 宮下保司 , 酒井邦嘉
ページ範囲:P.1309 - P.1313
伊藤研究室の隆盛
酒井 伊藤先生が1962年に帰国されてからのご研究は,どのようにして実ったのでしょうか。
宮下 1964年から,日本での研究の論文が出始めます。記念碑的な論文が1つありまして,『Experientia』というジャーナルに出た1964年の論文1)です。小脳を刺激すると,ダイテルス核の細胞に抑制性のシナプス後電位が出たという発見です。その電位が単シナプスに対応する短い潜時で出たので,小脳の主要な出力が抑制性ということになり,これは予想外の結果でした。
連載 臨床で役立つ末梢神経病理の読み方・考え方・8
MAG抗体陽性ニューロパチー
著者: 佐藤亮太 , 神田隆
ページ範囲:P.1315 - P.1319
はじめに
M蛋白血症は,異常に増殖した形質細胞,あるいはB細胞から免疫グロブリンやその構成成分が単クローン性に産生分泌された状態である。加齢に伴ってM蛋白血症の有病率は高くなり,健常高齢者の数%にM蛋白血症が確認される。M蛋白血症をきたす代表的な疾患は多発性骨髄腫やAL(amyloid light-chain)アミロイドーシスがあるが,M蛋白血症患者の中に髄鞘蛋白であるミエリン随伴性糖蛋白質(myelin-associated glycoprotein:MAG)に対する自己抗体を保有している一群が存在する。MAG抗体を実験動物に受動免疫させるとニューロパチーをきたすことが確認されており,MAG抗体はニューロパチーの原因であることが証明されている。連載第8回となる今回は,MAG抗体陽性ニューロパチーに特徴的な腓腹神経病理所見を提示する。
特別記事
せりか基金ってなに?—『宇宙兄弟』から生まれたALS研究支援の取組み フリーアクセス
ページ範囲:P.1320 - P.1321
ALS治療開発の研究を支援する「せりか基金」。漫画『宇宙兄弟』から生まれたこの活動は,多くの支援に支えられ,3年目を迎えた。この基金が生まれた背景や現状,これからの展望を,代表の黒川久里子さんにうかがった。
書評
「図説 医学の歴史」—坂井建雄【著】 フリーアクセス
著者: 北村聖
ページ範囲:P.1308 - P.1308
同級生の坂井建雄教授が2年余りの歳月をかけて『図説 医学の歴史』という渾身の1冊を上梓した。坂井氏の本業は解剖学である。学生時代から解剖学教室に入りびたりの生粋の解剖学者である。卒業後,それぞれの道に専念し接点があまりなかったが,再度会合したのが医学史の分野であった。聞くところによると,ヴェサリウスの解剖学から歴史に興味を持ったそうであるが,私が読んだ「魯迅と藤野厳九郎博士の時代の解剖学講義」の研究は秀逸であった。2012年に坂井博士の編集による『日本医学教育史』(東北大学出版会)が出版されて以来,より親しくさせていただいている。坂井博士は恩師養老孟司先生と同様,博学であると同時に,好奇心に満ちている。自分の知りたいことを調べて書籍化していると感じる。
さて,本書は表題が示しているとおり写真や図版が多い。特に古典の図版の引用が多いが,驚くなかれ,その多くは坂井博士自身が所有されている書籍からの引用である。2次文献ではなく,原則原典に当たるという姿勢は全編を貫く理念であり,それが読む者を圧倒する。まさしく「膨大な原典資料の解読による画期的な医学史(本書の帯)」である。また,史跡の写真も坂井博士自らが撮影したものが多く,医学史の現場にも足を運んだことがよくわかる。また,書中に「医学史上の人と場所」というコラムが挿入されており,オアシスのような味わいを出している。内容もさることながら,人選が面白く,医学史上の大家から市中の名医(荻野久作など)までが取り上げられている。
「医療英会話キーワード辞典 そのまま使える16000例文」—森島祐子,仁木久恵,Flaminia Miyamasu【著】 フリーアクセス
著者: 川名正敏
ページ範囲:P.1314 - P.1314
最近の外国人旅行者の増加,そして今後の外国人労働者の受け入れ拡大が議論される中,医療現場における外国人への対応は喫緊の課題になっています。
筑波大学の森島祐子先生らが2006年に発刊された本書の兄貴(姉貴)分である『そのまま使える 病院英語表現5000』は,外来,救急現場,病棟などさまざまな場所で大活躍しており,私もこの本の大ファンの1人です。外国人の患者さんに対して最初のコンタクトを取る際に,受付,外来診察室,手術室など,それぞれの関連ページを開いてそこに記載されている文章を読み上げれば(場合によってはお見せすれば)よいということで,多職種の人たちがあまりちゅうちょせずに外国人の患者さんとのコミュニケーションを取れるようになってきました。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.1123 - P.1123
欧文目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.1124 - P.1124
お知らせ 公益信託 時実利彦記念脳研究助成基金 時実利彦記念賞 2020年度申請者の募集 フリーアクセス
ページ範囲:P.1137 - P.1137
バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.1326 - P.1326
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.1327 - P.1327
あとがき フリーアクセス
著者: 神田隆
ページ範囲:P.1328 - P.1328
今年も脳神経内科の専門医試験が終了し,199人の専門医が新たに誕生しました。リタイアする先生方の数を差し引きすると遅々とした増え方で,日本に脳神経内科専門医が充足するまでにはいまだ道遠しという感がありますが,毎年200人前後の新専門医がコンスタントに誕生しているのはとてもよいことだと思います。私は10年以上この試験に問題作成の委員として関与しており,専門医認定委員長を拝命してから今年で3年目です。1〜4月頭まで平均7回の日曜日全日を問題作成に充てるというハードな委員会で,7月に面接試験が終わると本当に肩の荷が下りた感じがします。委員会の席上ではそれぞれの専門分野の先生が常識と思っていることとその他の先生との認識の乖離が新鮮で,委員会で発せられる専門家の意見はとてもよい勉強になります。この委員会を通じてつくづく感じることは脳神経内科の守備範囲の広さ,common diseaseから難病まで関わる疾患の多彩さで,この1点だけをとってみても基本診療科としての要件を十分満たしていると思います。先生方はどのようにお考えになりますでしょうか。
今月の増大特集はALSです。表紙には,ALSに罹患しキャリアが終焉したニューヨーク・ヤンキースのスラッガー,ルー・ゲーリック(Henry Louis Gehrig;1903.6.13-1941.6.2)のカリカチュアをイラストレーターの長場 雄さんに描いていただきました。米国でこの病気が「ルー・ゲーリック病」と称されて一般の市民にもよく理解されていることは読者の皆様もよくご存知と思いますが,アイス・バケツ・チャレンジなどと並んで,この疾患を一般の人々にもよく理解していただこうという努力は今後日本でも必要なことだろうと思います。既にALSを発症していたと考えられる1938年のシーズンにも,ゲーリックは打率.295,29本塁打,114打点という優秀な成績を残していますが,アスリートであること,頭頸部に外傷歴があることがALSのリスクを増すという説はおそらく真実であろうと思います。外傷とTDP-43蓄積との間のリンクは今後どのように解明されていくのでしょうか。
基本情報
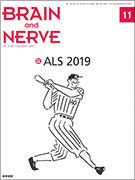
バックナンバー
76巻12号(2024年12月発行)
特集 芸術家と神経学Ⅱ
76巻11号(2024年11月発行)
特集 ALS 2024
76巻10号(2024年10月発行)
特集 どうして効くんだろう
76巻9号(2024年9月発行)
特集 治療可能な認知症としてのアルツハイマー病
76巻8号(2024年8月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である—revisited
76巻7号(2024年7月発行)
特集 ニューロ・バイオイメージング—技術と応用
76巻6号(2024年6月発行)
特集 注意と注意障害
76巻5号(2024年5月発行)
増大特集 末梢神経・筋肉の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
76巻4号(2024年4月発行)
特集 神経病理最前線
76巻3号(2024年3月発行)
特集 きちんと説明ができますか?
76巻2号(2024年2月発行)
特集 特発性正常圧水頭症の現在
76巻1号(2024年1月発行)
特集 新時代の重症筋無力症と関連疾患の診療
75巻12号(2023年12月発行)
特集 アガサ・クリスティーと神経毒
75巻11号(2023年11月発行)
特集 アロスタシス—ホメオスタシスを超えて
75巻10号(2023年10月発行)
特集 メタバースへの招待
75巻9号(2023年9月発行)
特集 妊娠と神経疾患
75巻8号(2023年8月発行)
特集 アルツハイマー病は本当に早期発見できるのか
75巻7号(2023年7月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part2 末梢編
75巻6号(2023年6月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part1 中枢編
75巻5号(2023年5月発行)
増大特集 神経・精神領域の薬剤ハンドブック
75巻4号(2023年4月発行)
特集 All About Epilepsy
75巻3号(2023年3月発行)
特集 慢性疼痛
75巻2号(2023年2月発行)
特集 多系統萎縮症の新診断基準とこれからの診療
75巻1号(2023年1月発行)
特集 よく出会う不随意運動を知る
74巻12号(2022年12月発行)
特集 映画を観て精神・神経疾患を知る
74巻11号(2022年11月発行)
特集 RFC1遺伝子関連スペクトラム障害
74巻10号(2022年10月発行)
特集 ウイルス性脳炎・脳症2022
74巻9号(2022年9月発行)
特集 動的環境への適応系としての歩行
74巻8号(2022年8月発行)
特集 迷走神経の不思議
74巻7号(2022年7月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識2022
74巻6号(2022年6月発行)
特集 脳神経内科医に求められる移行医療
74巻5号(2022年5月発行)
増大特集 次の一手—神経筋疾患難治例をどのように治療するか
74巻4号(2022年4月発行)
特集 脳科学リテラシーを高めるために
74巻3号(2022年3月発行)
特集 中枢性自律神経障害update
74巻2号(2022年2月発行)
特集 温度を感じる脳と身体の科学
74巻1号(2022年1月発行)
特集 脳神経内科医のキャリアパスとリーダーシップ
73巻12号(2021年12月発行)
特集 芸術家と神経学
73巻11号(2021年11月発行)
特集 「目」の神経学
73巻10号(2021年10月発行)
特集 中枢神経・末梢神経の悪性リンパ腫
73巻9号(2021年9月発行)
特集 脳卒中治療に必要な基礎知識
73巻8号(2021年8月発行)
特集 脳腸相関—脳-身体の双方向性制御
73巻7号(2021年7月発行)
特集 グリアと神経—相補的な制御系として
73巻6号(2021年6月発行)
特集 Lower Spine Neurology
73巻5号(2021年5月発行)
増大特集 中枢神経の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
73巻4号(2021年4月発行)
特集 片頭痛・群発頭痛治療の新たな夜明け
73巻3号(2021年3月発行)
特集 マルチリンガルブレイン
73巻2号(2021年2月発行)
特集 筋炎と壊死性筋症
73巻1号(2021年1月発行)
特集 Neuro-Oncology
72巻12号(2020年12月発行)
特集 超高齢期の精神神経疾患を診る
72巻11号(2020年11月発行)
増大特集 脳の発振現象—基礎から臨床へ
72巻10号(2020年10月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識
72巻9号(2020年9月発行)
特集 皮質性小脳萎縮症へのアプローチ
72巻8号(2020年8月発行)
特集 サルコイドーシス
72巻7号(2020年7月発行)
増大特集 神経倫理ハンドブック
72巻6号(2020年6月発行)
特集 前頭側頭葉変性症の今日的理解
72巻5号(2020年5月発行)
特集 多発性硬化症の現在と未来
72巻4号(2020年4月発行)
増大特集 神経疾患の診断における落とし穴—誤診を避けるために
72巻3号(2020年3月発行)
特集 でこぼこの脳の中でおしくらまんじゅうする脳機能
72巻2号(2020年2月発行)
特集 αシヌクレイノパチーの新たな展開
72巻1号(2020年1月発行)
特集 神経難病をクスリで治す—薬物開発の現況と近未来への展望
71巻12号(2019年12月発行)
特集 小脳と大脳—Masao Itoのレガシー
71巻11号(2019年11月発行)
増大特集 ALS2019
71巻10号(2019年10月発行)
特集 認知症と遺伝
71巻9号(2019年9月発行)
特集 神経疾患のドラッグ・リポジショニング—新時代へ
71巻8号(2019年8月発行)
特集 パーキンソン病診療の現在地—200年の変遷と新規治療
71巻7号(2019年7月発行)
増大特集 人工知能と神経科学
71巻6号(2019年6月発行)
特集 補体標的治療の現状と展望
71巻5号(2019年5月発行)
特集 NPSLE
71巻4号(2019年4月発行)
増大特集 神経学のための皮膚アトラス
71巻3号(2019年3月発行)
特集 Spine Neurology
71巻2号(2019年2月発行)
特集 “スポーツ”を生み出す脳
71巻1号(2019年1月発行)
特集 人工知能の医療応用Update
70巻12号(2018年12月発行)
特集 主訴に沿う—俯瞰し収束する画像診断の目
70巻11号(2018年11月発行)
増大特集 脳科学で解き明かす精神神経症候
70巻10号(2018年10月発行)
特集 「左脳と右脳」の現在
70巻9号(2018年9月発行)
特集 脳神経内科診療に役立つ精神科の知識
70巻8号(2018年8月発行)
特集 レヴィ小体型認知症の新知見
70巻7号(2018年7月発行)
増大特集 記憶と忘却に関わる脳のしくみ—分子機構から健忘の症候まで
70巻6号(2018年6月発行)
特集 芸術を生み出す脳
70巻5号(2018年5月発行)
特集 非アルツハイマー型認知症の病理学
70巻4号(2018年4月発行)
増大特集 Antibody Update 2018
70巻3号(2018年3月発行)
特集 『認知症疾患診療ガイドライン2017』を読み解く
70巻2号(2018年2月発行)
特集 知っておきたい神経感染症
70巻1号(2018年1月発行)
特集 筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群の今
69巻12号(2017年12月発行)
特集 運動異常症をみる—Web動画付録つき
69巻11号(2017年11月発行)
増大特集 こころの時間学の未来
69巻10号(2017年10月発行)
特集 成人てんかん—知っておきたい6つのトピック
69巻9号(2017年9月発行)
特集 ミクログリアと精神・神経疾患
69巻8号(2017年8月発行)
特集 遺伝性脊髄小脳失調症の病態と治療展望
69巻7号(2017年7月発行)
増大特集 あしたのアルツハイマー病治療
69巻6号(2017年6月発行)
特集 局在病変の神経心理学
69巻5号(2017年5月発行)
特集 Voxel-Based Morphometry—体積からわかること
69巻4号(2017年4月発行)
増大特集 ブロードマン領野の現在地
69巻3号(2017年3月発行)
特集 磁気刺激の新たな展開
69巻2号(2017年2月発行)
特集 Stroke-Like Diseases—鑑別時に注意を要する5病態
69巻1号(2017年1月発行)
特集 近年注目されている白質脳症
68巻12号(2016年12月発行)
特集 炎症性神経・筋疾患の新たな展開
68巻11号(2016年11月発行)
増大特集 連合野ハンドブック
68巻10号(2016年10月発行)
特集 アディクション—行動の嗜癖
68巻9号(2016年9月発行)
特集 自己免疫性脳炎・脳症
68巻8号(2016年8月発行)
特集 こころと汗
68巻7号(2016年7月発行)
増大特集 認知症の危険因子と防御因子
68巻6号(2016年6月発行)
特集 脳とフローラ
68巻5号(2016年5月発行)
特集 手の症候学—生理学・解剖学からみた新知見
68巻4号(2016年4月発行)
増大特集 治せる認知症
68巻3号(2016年3月発行)
特集 末梢神経の血管炎
68巻2号(2016年2月発行)
特集 筋疾患の認知機能障害
68巻1号(2016年1月発行)
特集 シャルコー・マリー・トゥース病
67巻12号(2015年12月発行)
特集 視床と高次脳機能
67巻11号(2015年11月発行)
増大特集 ギラン・バレー症候群のすべて—100年の軌跡
67巻10号(2015年10月発行)
特集 非・日常生活の脳科学
67巻9号(2015年9月発行)
特集 酵素補充療法
67巻8号(2015年8月発行)
特集 神経難病の終末期医療
67巻7号(2015年7月発行)
増大特集 神経疾患と感染症update
67巻6号(2015年6月発行)
特集 脳と「質感」
67巻5号(2015年5月発行)
特集 NCSE(非痙攣性てんかん重積状態)
67巻4号(2015年4月発行)
増大特集 大脳皮質vs.大脳白質
67巻3号(2015年3月発行)
特集 中枢神経の血管炎
67巻2号(2015年2月発行)
特集 「食べる」を考える
67巻1号(2015年1月発行)
特集 ニューロトキシコロジー
66巻12号(2014年12月発行)
特集 Orthopaedic Neurology—神経内科と整形外科の狭間で
66巻11号(2014年11月発行)
増大特集 神経症候学は神経学の“魂”である
66巻10号(2014年10月発行)
特集 分子を撃つ 神経疾患治療の新しい水平線
66巻9号(2014年9月発行)
特集 痙縮の臨床神経学
66巻8号(2014年8月発行)
特集 神経系の悪性リンパ腫update
66巻7号(2014年7月発行)
増大特集 アミロイド関連神経疾患のすべて―封入体筋炎からアルツハイマー病まで
66巻6号(2014年6月発行)
特集 ミラーニューロン
66巻5号(2014年5月発行)
特集 アセチルコリンと神経疾患―100年目の現在地
66巻4号(2014年4月発行)
増大特集 タッチ・ビジョン・アクション
66巻3号(2014年3月発行)
特集 神経筋疾患の超音波診断
66巻2号(2014年2月発行)
特集 糖尿病の神経学revisited
66巻1号(2014年1月発行)
特集 日常生活の脳科学
65巻12号(2013年12月発行)
特集 プロテイノパチーの神経病理学
65巻11号(2013年11月発行)
増大特集 Close Encounters―臨床神経学と臨床免疫学の遭遇と未来
65巻10号(2013年10月発行)
特集 神経系の発達メカニズム―最近の話題
65巻9号(2013年9月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である―現状と展望
65巻8号(2013年8月発行)
特集 こころの時間学―現在・過去・未来の起源を求めて
65巻7号(2013年7月発行)
増大特集 あしたの脳梗塞
65巻6号(2013年6月発行)
特集 見せる・仕分ける―脳機能解析の新手法
65巻5号(2013年5月発行)
特集 てんかん―新しいパースペクティブ
65巻4号(2013年4月発行)
増大特集 Antibody Update
65巻3号(2013年3月発行)
特集 次世代シーケンサーによる神経変性疾患の解析と展望
65巻2号(2013年2月発行)
特集 血液脳関門研究の進歩
65巻1号(2013年1月発行)
特集 Corticobasal Syndrome
64巻12号(2012年12月発行)
特集 The Border-Land of Dementia
64巻11号(2012年11月発行)
増大特集 痛みの神経学―末梢神経から脳まで
64巻10号(2012年10月発行)
特集 辺縁系をめぐって
64巻9号(2012年9月発行)
特集 高次脳機能イメージングの脳科学への新展開
64巻8号(2012年8月発行)
特集 線条体の基礎と臨床
64巻7号(2012年7月発行)
増大特集 顔認知の脳内機構
64巻6号(2012年6月発行)
特集 睡眠と覚醒の脳内機構
64巻5号(2012年5月発行)
特集 神経疾患のバイオマーカー
64巻4号(2012年4月発行)
増大特集 パーキンソン病の新しい側面
64巻3号(2012年3月発行)
特集 アカデミアから新規治療の実現へ―トランスレーショナルリサーチの現状
64巻2号(2012年2月発行)
特集 生物学的精神医学の進歩
64巻1号(2012年1月発行)
特集 iPS細胞と神経疾患
63巻12号(2011年12月発行)
特集 神経心理学と画像解析の融合
63巻11号(2011年11月発行)
増大特集 筋疾患update
63巻10号(2011年10月発行)
特集 緩徐進行性高次脳機能障害の病態
63巻9号(2011年9月発行)
特集 脳卒中の最新画像診断
63巻8号(2011年8月発行)
特集 日本人の発見した神経症候
63巻7号(2011年7月発行)
増大特集 神経筋接合部―基礎から臨床まで
63巻6号(2011年6月発行)
特集 ニューロパチー
63巻5号(2011年5月発行)
特集 神経系と血管内リンパ腫
63巻4号(2011年4月発行)
増大特集 てんかんの新しい治療
63巻3号(2011年3月発行)
特集 サイバーナイフ治療
63巻2号(2011年2月発行)
特集 続・日本人の発見した神経疾患
63巻1号(2011年1月発行)
特集 血管腫
62巻12号(2010年12月発行)
特集 頸部頸動脈狭窄症の診断と治療
62巻11号(2010年11月発行)
増大特集 歩行とその異常
62巻10号(2010年10月発行)
特集 ブレインバンク
62巻9号(2010年9月発行)
特集 視神経脊髄炎(NMO)update
62巻8号(2010年8月発行)
特集 辺縁系脳炎
62巻7号(2010年7月発行)
増大特集 アルツハイマー病―研究と診療の進歩
62巻6号(2010年6月発行)
特集 改正臓器移植法の問題点とその対応
62巻5号(2010年5月発行)
特集 神経画像のピットフォール―見落としと読み過ぎ
62巻4号(2010年4月発行)
特集 傍腫瘍性神経筋疾患update
62巻3号(2010年3月発行)
特集 神経回路解析法の最近の進歩
62巻2号(2010年2月発行)
特集 ニューロリハビリテーションの最前線
62巻1号(2010年1月発行)
特集 神経救急
61巻12号(2009年12月発行)
特集 Somatotopy再考
61巻11号(2009年11月発行)
特集 前頭側頭葉変性症
61巻10号(2009年10月発行)
特集 片頭痛の予防療法
61巻9号(2009年9月発行)
特集 脳血管障害治療の進歩
61巻8号(2009年8月発行)
特集 神経・筋疾患の分子標的治療
61巻7号(2009年7月発行)
特集 脳腫瘍研究の最前線―遺伝子解析から治療まで
61巻6号(2009年6月発行)
特集 脊椎・脊髄外科の最近の進歩
61巻5号(2009年5月発行)
特集 Restless legs syndrome
61巻4号(2009年4月発行)
特集 大脳基底核―分子基盤から臨床まで
61巻3号(2009年3月発行)
特集 Microneurography(微小神経電図法)の臨床応用
61巻2号(2009年2月発行)
特集 神経系の再興感染症と輸入感染症
61巻1号(2009年1月発行)
特集 脳神経倫理
60巻12号(2008年12月発行)
特集 痙縮
60巻11号(2008年11月発行)
特集 脳卒中と遺伝子
60巻10号(2008年10月発行)
特集 若年者の脳卒中
60巻9号(2008年9月発行)
特集 知・情・意の神経学
60巻8号(2008年8月発行)
特集 脳硬膜動静脈瘻
60巻7号(2008年7月発行)
増大特集 学習と記憶――基礎と臨床
60巻6号(2008年6月発行)
特集 Crow-深瀬症候群(POEMS症候群)
60巻5号(2008年5月発行)
特集 「痛み」の研究と治療の最前線
60巻4号(2008年4月発行)
増大特集 神経系の発生とその異常
60巻3号(2008年3月発行)
特集 特発性正常圧水頭症(iNPH)―最近の話題
60巻2号(2008年2月発行)
特集 がん治療と神経障害
60巻1号(2008年1月発行)
特集 日本人の発見した神経疾患
59巻12号(2007年12月発行)
特集 損傷神経の再生―温存的治療法の開発
59巻11号(2007年11月発行)
特集 手根管症候群をめぐって
59巻10号(2007年10月発行)
増大特集 ALS―研究と診療の進歩
59巻9号(2007年9月発行)
特集 パーキンソン病の認知機能障害
59巻8号(2007年8月発行)
特集 パーキンソン病の分子遺伝学―最近の知見
59巻7号(2007年7月発行)
増大特集 情報伝達処理におけるグリアの機能と異常
59巻6号(2007年6月発行)
特集 職業性神経障害の新しい展開
59巻5号(2007年5月発行)
特集 脳画像最前線
59巻4号(2007年4月発行)
増大特集 最近注目される脳神経疾患治療の研究
59巻3号(2007年3月発行)
特集 分子イメージング
59巻2号(2007年2月発行)
特集 進行性多巣性白質脳症の新しい展開―PMLが治る時代へ向けて
59巻1号(2007年1月発行)
特集 高次視覚研究の最近の進歩
