神経系には集団発振現象と同期化現象があることが以前より知られています。そして,脳の機能発現や自己組織化には,それが生理的であれ病的であれ,このような発振現象が場となって起こることが次第にわかってきました。本特集では,このような神経系の集団発振現象に焦点を絞って,最近の所見に基づいて多面的に検討します。
本特集は神経系の集団振動現象を階層性,病態と介入,解析技法と数理モデルの観点から下記の4つのパートで構成され,脳の発振現象を包括的に解説しています。
雑誌目次
BRAIN and NERVE-神経研究の進歩72巻11号
2020年11月発行
雑誌目次
増大特集 脳の発振現象—基礎から臨床へ
扉 フリーアクセス
ページ範囲:P.1121 - P.1121
特集の構成 フリーアクセス
著者: 虫明元
ページ範囲:P.1123 - P.1125
PART1 脳における振動現象の細胞レベルの理解
まずPART1の細胞レベルの振動理解では4つテーマを取り上げます。受容体,チャネル,分子機構というミクロレベルの振動メカニズムを解説します。
細胞発振から集団発振へのモーダルシフトにおけるCl--GABAシステムの関わり
著者: 福田敦夫
ページ範囲:P.1127 - P.1134
GABAA受容体作用はCl-濃度勾配に依存し,成熟脳ではCl-流入による過分極・抑制であるが,未成熟な脳では脱分極(Cl-流出)である。Cl-ホメオダイナミクスは抑制と興奮を切り替えて,細胞および細胞集団の発振現象におけるモーダルシフトを起こす。このGABA作用のモーダルシフトは,正常な脳発達に必要な一方で,成熟脳で逆説的に誘導されることもあり,モーダルシフトの障害は,種々の神経発達障害の病因・病態となり得る。
ドーパミンおよびNMDA受容体と大脳基底核回路の機能解析
著者: 齊藤奈英 , 笹岡俊邦
ページ範囲:P.1135 - P.1142
大脳基底核のドーパミン(DA)は運動制御に重要な役割を持ち,DA欠乏はパーキンソン病に見られるように運動障害を引き起こす。DAはD1受容体(D1R)を介して直接路神経を活性化し,D2受容体(D2R)を介して間接路神経を阻害する。DA情報伝達の役割の理解のため,D1R,D2Rの遺伝子操作マウスによる運動制御,神経活動,記憶学習に関する最近の研究を概説し,大脳基底核の発振現象への関与も紹介する。
中枢時計・視交叉上核によるサーカディアンリズム発振のメカニズム
著者: 三枝理博
ページ範囲:P.1143 - P.1150
生命活動の多くが,約24時間周期のサーカディアン(概日)リズムを示す。哺乳類では視床下部の視交叉上核(SCN)が,体内時計中枢(中枢時計)として機能し,環境の昼夜サイクルに同調した時刻情報を全身に発信する。本論ではまず,SCNの分子,細胞,および解剖学的構造を概説する。続いて,SCNニューロンのタイプによる機能の違いに関する最近の研究を紹介し,SCN神経ネットワークのメカニズムについて考察する。
神経細胞のresonance特性に関わるイオンチャネル
著者: 橋本浩一
ページ範囲:P.1151 - P.1157
ある種の神経細胞には,特性の周期を持つシナプス入力などを大きな膜電位として出力する,resonance特性という電気的な特性を持つものがある。本総説では,resonance特性の発現に関わるイオンチャネルについて,特にげっ歯類での研究について概説する。
ネットワーク病としてのパーキンソン病
著者: 南部篤 , 知見聡美
ページ範囲:P.1159 - P.1171
パーキンソン病において,ドパミンの減少が大脳基底核ネットワークにどのような変化をもたらし,症状発現に至るのかについて,3つの説を紹介する。①大脳基底核の平均発射頻度の変化(発射頻度説),②大脳基底核における発振活動や同期活動(発射パターン説),③大脳皮質に由来する大脳基底核の動的神経活動の変化(動的活動説)である。本小論では,これら3説のうちどれがパーキンソン病の病態をより説明できるかという観点から,批判的に検討したい。
前頭葉における文脈依存性の振動現象
著者: 虫明元
ページ範囲:P.1173 - P.1182
前頭葉には運動野と前頭前野が含まれ,機能的には関連しつつもその階層的に異なっている。具体的には細胞活動も振動現象も,異なる行動文脈に依存している。一方で,振動現象には,抑制性と興奮性のバランスが重要であることがわかってきている。特に抑制性機能を担う抑制細胞には多様性があり,機能的にも異なる側面を担っている。本論では前頭葉の領野としての振動と細胞活動,さらには振動を担う局所回路の複数の振動様式のメカニズムを総説する。
神経振動と脳のネットワーク病
著者: 飛松省三
ページ範囲:P.1183 - P.1194
神経振動は,中枢神経系の律動的・自発的な電気活動ないし外的刺激に対する反応である。遠隔領域にある神経系の振動現象による病的相互作用が精神・神経疾患の脳内基盤ではないかという作業仮説を検証するために,時間・空間分解能に優れた脳磁図や高密度脳波による事象関連電位(磁場)を記録した。疾患研究から,脳内ネットワークの動的な機能不全が「ネットワーク病」という概念で捉えることができることを示した。
視床を介した脳のグローバルな回路
著者: 高田則雄
ページ範囲:P.1195 - P.1205
脳全体は動的で多様な活動を示す。この生理学的なしくみは何だろうか。この問いに答えるための手掛かりとして,大脳基底核や小脳を含む脳のグローバルな回路群について解剖学的な知見をまとめた。それらの回路群には情報の集散地である視床が常に登場する。回路の基本構造として「平行回路」がある。平行回路間の相互作用は,情報の収束や発散,平行回路の切替えを通じてなされていると示唆される。
グリア・ニューロンから見る,ヒト脳における部分てんかん発作の発振現象
著者: 中谷光良 , 池田昭夫
ページ範囲:P.1207 - P.1221
脳はさまざまな帯域の脳波活動をつくり出す精巧な超LSI回路であり,これが発作的に暴走した状態のひとつとして知られるのがてんかん発作である。もっぱら神経細胞の過剰興奮に起因するとされてきたが,近年ではこれまで静的細胞とみなされていたグリア細胞が担う,てんかん原性獲得における重要な役割が注目されている。本稿では,発振現象から見る,てんかんにおけるグリア細胞と神経細胞(ニューロン)の両者の相補的・共起的な働きについて概説を行う。
ヒト脳発振操作による動的ネットワークの制御と臨床応用
著者: 小金丸聡子 , 神作憲司 , 美馬達哉
ページ範囲:P.1223 - P.1237
ヒト脳発振現象が脳波にて初めて記録されてから既に約100年が経ち,現在では脳発振を操作する非侵襲的手法が開発された。この脳発振操作は,ヒトの行動や認知を変容させること,さらに「オシロセラピー」として疾患治療法となることが報告されてきた。本総説では,ヒト二足歩行中の脳発振を操作し,歩行障害を回復させたわれわれの知見を中心に,脳発振の生理学的機序,ヒト行動・認知の変容,オシロセラピーについて,概説する。
TMSによるヒト神経ネットワークへの介入
著者: 宇川義一
ページ範囲:P.1239 - P.1246
TMS介入研究の一部を紹介する。“QPS(quadripulse stimulation)”の紹介,“visuo-motor sequence learning”におけるpre-SMA,SMAの役割分担の証明,“negative compatibility effect”におけるSMA関与の証明,「パーキンソン病への治療介入」の紹介,「腰部刺激による歩行誘導の紹介」,“back propagation potential”による1.5msの発火頻度について解説する。
Triad TMS of Human Motor Cortex
著者: 花島律子 , 宇川義一
ページ範囲:P.1247 - P.1253
経頭蓋磁気刺激を用いて,ヒトの一次運動野の内的リズムに関する分析を施行した。閾値以下の3発刺激と閾値以上の試験刺激1発を一定の刺激間隔で与えたときの運動誘発電位の振幅を検討したところ,25ms間隔(すなわち40Hz)でのみ皮質内促通が誘発され,運動野のリズム特性との関係が推察された。神経疾患ではその促通の消失もしくはリズムの変化が生じており,本刺激法は,運動野のリズム特性を検討する1つの方法となる。
拘束条件付き自己組織化理論に基づく機能分化に関する情報論的基盤の解明
著者: 津田一郎
ページ範囲:P.1255 - P.1262
脳神経系の発達過程に着目し,機能分化,機能分割に対するネットワークモデルを提案する。ネットワークシステム全体にかかる拘束条件によってシステムに機能要素(機能単位)が生成される過程に着目する。神経細胞の分化,機能モジュールの分化,感覚ニューロンの特異性の分化を扱い,計算結果に基づきそれぞれに対して仮説を提案する。
脳領域間の機能的結合の解析
著者: 北野勝則
ページ範囲:P.1263 - P.1273
認知機能は複数の脳領域が関与すると考えられるため,そのしくみを理解するには,脳領域間の情報伝達を明らかにする必要がある。機能的結合解析は,脳活動の領域間の統計的相関や因果的関係で定める機能的結合により脳活動動態を明らかにする解析方法である。本論では,機能的結合解析について概説し,代表的な手法を紹介する。そして,応用事例として,機能的結合解析に基づく神経疾患の診断へ向けた取組みについて紹介する。
力学系の考え方—導入的紹介とドーパミン・強化学習に関わる研究への適用例
著者: 加藤郁佳 , 森田賢治
ページ範囲:P.1275 - P.1282
振動・リズム現象をはじめとした神経システムの振舞いを調べるうえで,力学系(dynamical system)の考え方が有用である。本論では,前半でその導入的な紹介を,筆者の1人の講義資料に基づきつつ試みる。後半では,そうした力学系の考え方を用いた,筆者らが行ったドーパミン・強化学習に関わる研究を紹介する。具体的には,学習された価値の減衰を仮定して,ドーパミンの減少による動機づけへの影響の1つの機序を提案した研究を紹介する。
「阿吽の呼吸」の神経基盤
著者: 本田学
ページ範囲:P.1283 - P.1293
指揮者やメトロノームなしに複数の演奏者が自律的に同期をとり,「阿吽の呼吸」で一糸乱れぬ演奏を実現する音楽表現が,地球上のさまざまな文化圏に数多く存在する。その典型例としてインドネシア・バリ島の祭祀芸能ケチャを取り上げ,ケチャ演奏中の複数人から脳波同時計測を行ったところ,演奏前に比較し演奏中と演奏後には,脳波の個体間同期が増強することがわかった。脳機能の同期と社会や文化との関わりについて考察する。
総説
短時間持続性片側神経痛様頭痛発作(SUNHA)の臨床
著者: 菊井祥二 , 團野大介 , 竹島多賀夫
ページ範囲:P.1295 - P.1306
短時間持続性片側神経痛様頭痛発作(SUNHA)は短時間で重度の頭痛発作と同側の自律神経症状を特徴とする。SUNHAには結膜充血と流涙の両方を有するSUNCTとどちらか一方を有するSUNAが含まれる。難治性であるが,リドカイン持続静注とラモトリギンが最も効果的である。薬剤抵抗例では,三叉神経に対する微小血管減圧やニューロモジュレーションが試みられている。SUNCT,SUNAと三叉神経痛には臨床的,治療的,放射線学的に重複があり,国際頭痛分類第3版では別疾患であるが,同じ障害の連続体を構成する可能性も議論されている。
書評
「臨床研究の教科書 第2版—研究デザインとデータ処理のポイント」—川村 孝【著】 フリーアクセス
著者: 岩田健太郎
ページ範囲:P.1307 - P.1307
ぼくは臨床研究そのものの専門家ではなく,臨床研究の専門家の知見から学び,研究をしている一医者にすぎない。車をつくったり直したりする能力はまるでないが,運転はしている次第。だから本書を上から「批評する」資格はなく,本書を活用してきた読者の1人として「これは一読の価値がありまっせ」とオススメすることしかできない。よって,書評ではなく推薦文である。
2016年に本書初版が出たときは,知人に勧められて買い求めた。内容もさることながら,文体が素晴らしいと思った。こういう比較が適切なのかは知らないが,しかし主観的にそう感じたので仕方がないから書くが,経済学者の森嶋通夫※の本を読むようなクリスピーな文体だった。本当にこの領域の世界内を熟知している人が,しかし冗長な説明はすべてそぎ落として要諦だけ読ませるような文体だ。今年,新しい第2版を読んでその意を新たにした。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.1119 - P.1119
欧文目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.1120 - P.1120
バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.1312 - P.1312
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.1313 - P.1313
あとがき フリーアクセス
著者: 酒井邦嘉
ページ範囲:P.1314 - P.1314
昨年秋にゴッホの足跡を訪ねてフランスを旅行した。パリのオルセー美術館でゴッホの作品群を鑑賞した後,《ひまわり》で有名な南仏アルル,そして《糸杉》で知られるサン=レミ=ド=プロヴァンスへ。再びパリに戻り,ゴッホ終焉の地,オヴェール=シュル=オワーズを訪れた。いまから130年ほど前,ゴッホは33〜37歳という晩年にこれらの地に移り住んだのだった。
ゴッホが絵を描き続けたのは10年ほどだが,作品は2,000点を超えると言う。その創作活動の前半はオランダとベルギーで,後半はフランスで生活したのだが,フランス移住が転機となって,色彩に満ち溢れる絵を描くようになった。ゴッホの作品を丹念に観ていくと,大胆な色使いや力強い筆致だけでなく,極めて緻密で繊細な描写に目を奪われる。ゴッホは同時に膨大な素描を残しており,油彩画とまったく同じ構図のものもあって,その確かな観察眼と技巧を確認することができる。
基本情報
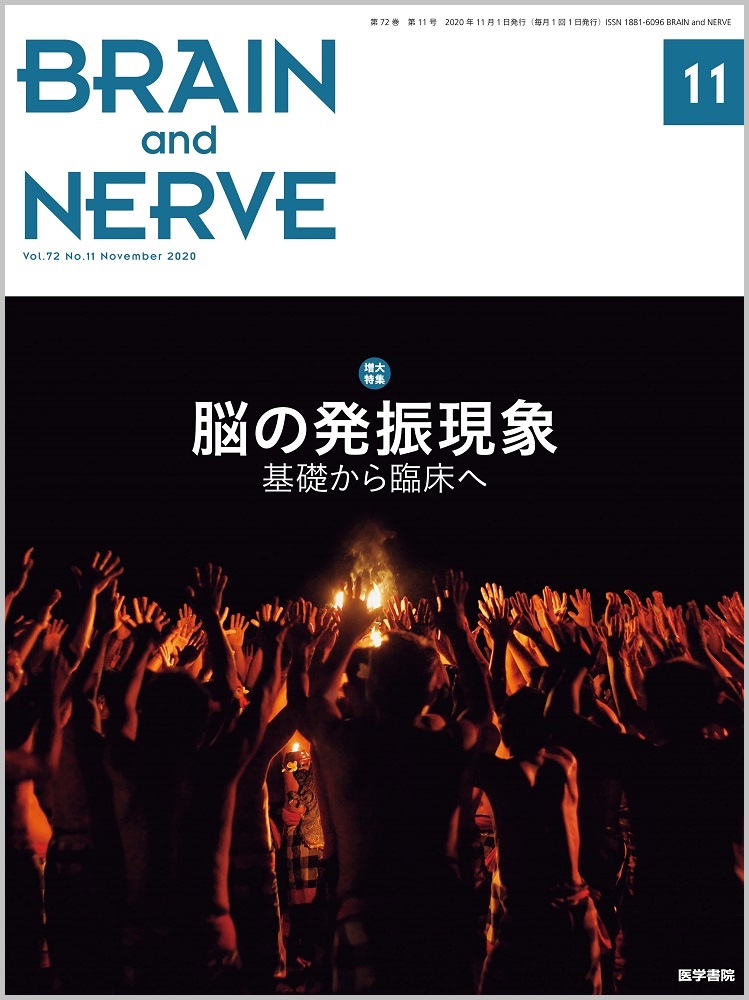
バックナンバー
76巻12号(2024年12月発行)
特集 芸術家と神経学Ⅱ
76巻11号(2024年11月発行)
特集 ALS 2024
76巻10号(2024年10月発行)
特集 どうして効くんだろう
76巻9号(2024年9月発行)
特集 治療可能な認知症としてのアルツハイマー病
76巻8号(2024年8月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である—revisited
76巻7号(2024年7月発行)
特集 ニューロ・バイオイメージング—技術と応用
76巻6号(2024年6月発行)
特集 注意と注意障害
76巻5号(2024年5月発行)
増大特集 末梢神経・筋肉の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
76巻4号(2024年4月発行)
特集 神経病理最前線
76巻3号(2024年3月発行)
特集 きちんと説明ができますか?
76巻2号(2024年2月発行)
特集 特発性正常圧水頭症の現在
76巻1号(2024年1月発行)
特集 新時代の重症筋無力症と関連疾患の診療
75巻12号(2023年12月発行)
特集 アガサ・クリスティーと神経毒
75巻11号(2023年11月発行)
特集 アロスタシス—ホメオスタシスを超えて
75巻10号(2023年10月発行)
特集 メタバースへの招待
75巻9号(2023年9月発行)
特集 妊娠と神経疾患
75巻8号(2023年8月発行)
特集 アルツハイマー病は本当に早期発見できるのか
75巻7号(2023年7月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part2 末梢編
75巻6号(2023年6月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part1 中枢編
75巻5号(2023年5月発行)
増大特集 神経・精神領域の薬剤ハンドブック
75巻4号(2023年4月発行)
特集 All About Epilepsy
75巻3号(2023年3月発行)
特集 慢性疼痛
75巻2号(2023年2月発行)
特集 多系統萎縮症の新診断基準とこれからの診療
75巻1号(2023年1月発行)
特集 よく出会う不随意運動を知る
74巻12号(2022年12月発行)
特集 映画を観て精神・神経疾患を知る
74巻11号(2022年11月発行)
特集 RFC1遺伝子関連スペクトラム障害
74巻10号(2022年10月発行)
特集 ウイルス性脳炎・脳症2022
74巻9号(2022年9月発行)
特集 動的環境への適応系としての歩行
74巻8号(2022年8月発行)
特集 迷走神経の不思議
74巻7号(2022年7月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識2022
74巻6号(2022年6月発行)
特集 脳神経内科医に求められる移行医療
74巻5号(2022年5月発行)
増大特集 次の一手—神経筋疾患難治例をどのように治療するか
74巻4号(2022年4月発行)
特集 脳科学リテラシーを高めるために
74巻3号(2022年3月発行)
特集 中枢性自律神経障害update
74巻2号(2022年2月発行)
特集 温度を感じる脳と身体の科学
74巻1号(2022年1月発行)
特集 脳神経内科医のキャリアパスとリーダーシップ
73巻12号(2021年12月発行)
特集 芸術家と神経学
73巻11号(2021年11月発行)
特集 「目」の神経学
73巻10号(2021年10月発行)
特集 中枢神経・末梢神経の悪性リンパ腫
73巻9号(2021年9月発行)
特集 脳卒中治療に必要な基礎知識
73巻8号(2021年8月発行)
特集 脳腸相関—脳-身体の双方向性制御
73巻7号(2021年7月発行)
特集 グリアと神経—相補的な制御系として
73巻6号(2021年6月発行)
特集 Lower Spine Neurology
73巻5号(2021年5月発行)
増大特集 中枢神経の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
73巻4号(2021年4月発行)
特集 片頭痛・群発頭痛治療の新たな夜明け
73巻3号(2021年3月発行)
特集 マルチリンガルブレイン
73巻2号(2021年2月発行)
特集 筋炎と壊死性筋症
73巻1号(2021年1月発行)
特集 Neuro-Oncology
72巻12号(2020年12月発行)
特集 超高齢期の精神神経疾患を診る
72巻11号(2020年11月発行)
増大特集 脳の発振現象—基礎から臨床へ
72巻10号(2020年10月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識
72巻9号(2020年9月発行)
特集 皮質性小脳萎縮症へのアプローチ
72巻8号(2020年8月発行)
特集 サルコイドーシス
72巻7号(2020年7月発行)
増大特集 神経倫理ハンドブック
72巻6号(2020年6月発行)
特集 前頭側頭葉変性症の今日的理解
72巻5号(2020年5月発行)
特集 多発性硬化症の現在と未来
72巻4号(2020年4月発行)
増大特集 神経疾患の診断における落とし穴—誤診を避けるために
72巻3号(2020年3月発行)
特集 でこぼこの脳の中でおしくらまんじゅうする脳機能
72巻2号(2020年2月発行)
特集 αシヌクレイノパチーの新たな展開
72巻1号(2020年1月発行)
特集 神経難病をクスリで治す—薬物開発の現況と近未来への展望
71巻12号(2019年12月発行)
特集 小脳と大脳—Masao Itoのレガシー
71巻11号(2019年11月発行)
増大特集 ALS2019
71巻10号(2019年10月発行)
特集 認知症と遺伝
71巻9号(2019年9月発行)
特集 神経疾患のドラッグ・リポジショニング—新時代へ
71巻8号(2019年8月発行)
特集 パーキンソン病診療の現在地—200年の変遷と新規治療
71巻7号(2019年7月発行)
増大特集 人工知能と神経科学
71巻6号(2019年6月発行)
特集 補体標的治療の現状と展望
71巻5号(2019年5月発行)
特集 NPSLE
71巻4号(2019年4月発行)
増大特集 神経学のための皮膚アトラス
71巻3号(2019年3月発行)
特集 Spine Neurology
71巻2号(2019年2月発行)
特集 “スポーツ”を生み出す脳
71巻1号(2019年1月発行)
特集 人工知能の医療応用Update
70巻12号(2018年12月発行)
特集 主訴に沿う—俯瞰し収束する画像診断の目
70巻11号(2018年11月発行)
増大特集 脳科学で解き明かす精神神経症候
70巻10号(2018年10月発行)
特集 「左脳と右脳」の現在
70巻9号(2018年9月発行)
特集 脳神経内科診療に役立つ精神科の知識
70巻8号(2018年8月発行)
特集 レヴィ小体型認知症の新知見
70巻7号(2018年7月発行)
増大特集 記憶と忘却に関わる脳のしくみ—分子機構から健忘の症候まで
70巻6号(2018年6月発行)
特集 芸術を生み出す脳
70巻5号(2018年5月発行)
特集 非アルツハイマー型認知症の病理学
70巻4号(2018年4月発行)
増大特集 Antibody Update 2018
70巻3号(2018年3月発行)
特集 『認知症疾患診療ガイドライン2017』を読み解く
70巻2号(2018年2月発行)
特集 知っておきたい神経感染症
70巻1号(2018年1月発行)
特集 筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群の今
69巻12号(2017年12月発行)
特集 運動異常症をみる—Web動画付録つき
69巻11号(2017年11月発行)
増大特集 こころの時間学の未来
69巻10号(2017年10月発行)
特集 成人てんかん—知っておきたい6つのトピック
69巻9号(2017年9月発行)
特集 ミクログリアと精神・神経疾患
69巻8号(2017年8月発行)
特集 遺伝性脊髄小脳失調症の病態と治療展望
69巻7号(2017年7月発行)
増大特集 あしたのアルツハイマー病治療
69巻6号(2017年6月発行)
特集 局在病変の神経心理学
69巻5号(2017年5月発行)
特集 Voxel-Based Morphometry—体積からわかること
69巻4号(2017年4月発行)
増大特集 ブロードマン領野の現在地
69巻3号(2017年3月発行)
特集 磁気刺激の新たな展開
69巻2号(2017年2月発行)
特集 Stroke-Like Diseases—鑑別時に注意を要する5病態
69巻1号(2017年1月発行)
特集 近年注目されている白質脳症
68巻12号(2016年12月発行)
特集 炎症性神経・筋疾患の新たな展開
68巻11号(2016年11月発行)
増大特集 連合野ハンドブック
68巻10号(2016年10月発行)
特集 アディクション—行動の嗜癖
68巻9号(2016年9月発行)
特集 自己免疫性脳炎・脳症
68巻8号(2016年8月発行)
特集 こころと汗
68巻7号(2016年7月発行)
増大特集 認知症の危険因子と防御因子
68巻6号(2016年6月発行)
特集 脳とフローラ
68巻5号(2016年5月発行)
特集 手の症候学—生理学・解剖学からみた新知見
68巻4号(2016年4月発行)
増大特集 治せる認知症
68巻3号(2016年3月発行)
特集 末梢神経の血管炎
68巻2号(2016年2月発行)
特集 筋疾患の認知機能障害
68巻1号(2016年1月発行)
特集 シャルコー・マリー・トゥース病
67巻12号(2015年12月発行)
特集 視床と高次脳機能
67巻11号(2015年11月発行)
増大特集 ギラン・バレー症候群のすべて—100年の軌跡
67巻10号(2015年10月発行)
特集 非・日常生活の脳科学
67巻9号(2015年9月発行)
特集 酵素補充療法
67巻8号(2015年8月発行)
特集 神経難病の終末期医療
67巻7号(2015年7月発行)
増大特集 神経疾患と感染症update
67巻6号(2015年6月発行)
特集 脳と「質感」
67巻5号(2015年5月発行)
特集 NCSE(非痙攣性てんかん重積状態)
67巻4号(2015年4月発行)
増大特集 大脳皮質vs.大脳白質
67巻3号(2015年3月発行)
特集 中枢神経の血管炎
67巻2号(2015年2月発行)
特集 「食べる」を考える
67巻1号(2015年1月発行)
特集 ニューロトキシコロジー
66巻12号(2014年12月発行)
特集 Orthopaedic Neurology—神経内科と整形外科の狭間で
66巻11号(2014年11月発行)
増大特集 神経症候学は神経学の“魂”である
66巻10号(2014年10月発行)
特集 分子を撃つ 神経疾患治療の新しい水平線
66巻9号(2014年9月発行)
特集 痙縮の臨床神経学
66巻8号(2014年8月発行)
特集 神経系の悪性リンパ腫update
66巻7号(2014年7月発行)
増大特集 アミロイド関連神経疾患のすべて―封入体筋炎からアルツハイマー病まで
66巻6号(2014年6月発行)
特集 ミラーニューロン
66巻5号(2014年5月発行)
特集 アセチルコリンと神経疾患―100年目の現在地
66巻4号(2014年4月発行)
増大特集 タッチ・ビジョン・アクション
66巻3号(2014年3月発行)
特集 神経筋疾患の超音波診断
66巻2号(2014年2月発行)
特集 糖尿病の神経学revisited
66巻1号(2014年1月発行)
特集 日常生活の脳科学
65巻12号(2013年12月発行)
特集 プロテイノパチーの神経病理学
65巻11号(2013年11月発行)
増大特集 Close Encounters―臨床神経学と臨床免疫学の遭遇と未来
65巻10号(2013年10月発行)
特集 神経系の発達メカニズム―最近の話題
65巻9号(2013年9月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である―現状と展望
65巻8号(2013年8月発行)
特集 こころの時間学―現在・過去・未来の起源を求めて
65巻7号(2013年7月発行)
増大特集 あしたの脳梗塞
65巻6号(2013年6月発行)
特集 見せる・仕分ける―脳機能解析の新手法
65巻5号(2013年5月発行)
特集 てんかん―新しいパースペクティブ
65巻4号(2013年4月発行)
増大特集 Antibody Update
65巻3号(2013年3月発行)
特集 次世代シーケンサーによる神経変性疾患の解析と展望
65巻2号(2013年2月発行)
特集 血液脳関門研究の進歩
65巻1号(2013年1月発行)
特集 Corticobasal Syndrome
64巻12号(2012年12月発行)
特集 The Border-Land of Dementia
64巻11号(2012年11月発行)
増大特集 痛みの神経学―末梢神経から脳まで
64巻10号(2012年10月発行)
特集 辺縁系をめぐって
64巻9号(2012年9月発行)
特集 高次脳機能イメージングの脳科学への新展開
64巻8号(2012年8月発行)
特集 線条体の基礎と臨床
64巻7号(2012年7月発行)
増大特集 顔認知の脳内機構
64巻6号(2012年6月発行)
特集 睡眠と覚醒の脳内機構
64巻5号(2012年5月発行)
特集 神経疾患のバイオマーカー
64巻4号(2012年4月発行)
増大特集 パーキンソン病の新しい側面
64巻3号(2012年3月発行)
特集 アカデミアから新規治療の実現へ―トランスレーショナルリサーチの現状
64巻2号(2012年2月発行)
特集 生物学的精神医学の進歩
64巻1号(2012年1月発行)
特集 iPS細胞と神経疾患
63巻12号(2011年12月発行)
特集 神経心理学と画像解析の融合
63巻11号(2011年11月発行)
増大特集 筋疾患update
63巻10号(2011年10月発行)
特集 緩徐進行性高次脳機能障害の病態
63巻9号(2011年9月発行)
特集 脳卒中の最新画像診断
63巻8号(2011年8月発行)
特集 日本人の発見した神経症候
63巻7号(2011年7月発行)
増大特集 神経筋接合部―基礎から臨床まで
63巻6号(2011年6月発行)
特集 ニューロパチー
63巻5号(2011年5月発行)
特集 神経系と血管内リンパ腫
63巻4号(2011年4月発行)
増大特集 てんかんの新しい治療
63巻3号(2011年3月発行)
特集 サイバーナイフ治療
63巻2号(2011年2月発行)
特集 続・日本人の発見した神経疾患
63巻1号(2011年1月発行)
特集 血管腫
62巻12号(2010年12月発行)
特集 頸部頸動脈狭窄症の診断と治療
62巻11号(2010年11月発行)
増大特集 歩行とその異常
62巻10号(2010年10月発行)
特集 ブレインバンク
62巻9号(2010年9月発行)
特集 視神経脊髄炎(NMO)update
62巻8号(2010年8月発行)
特集 辺縁系脳炎
62巻7号(2010年7月発行)
増大特集 アルツハイマー病―研究と診療の進歩
62巻6号(2010年6月発行)
特集 改正臓器移植法の問題点とその対応
62巻5号(2010年5月発行)
特集 神経画像のピットフォール―見落としと読み過ぎ
62巻4号(2010年4月発行)
特集 傍腫瘍性神経筋疾患update
62巻3号(2010年3月発行)
特集 神経回路解析法の最近の進歩
62巻2号(2010年2月発行)
特集 ニューロリハビリテーションの最前線
62巻1号(2010年1月発行)
特集 神経救急
61巻12号(2009年12月発行)
特集 Somatotopy再考
61巻11号(2009年11月発行)
特集 前頭側頭葉変性症
61巻10号(2009年10月発行)
特集 片頭痛の予防療法
61巻9号(2009年9月発行)
特集 脳血管障害治療の進歩
61巻8号(2009年8月発行)
特集 神経・筋疾患の分子標的治療
61巻7号(2009年7月発行)
特集 脳腫瘍研究の最前線―遺伝子解析から治療まで
61巻6号(2009年6月発行)
特集 脊椎・脊髄外科の最近の進歩
61巻5号(2009年5月発行)
特集 Restless legs syndrome
61巻4号(2009年4月発行)
特集 大脳基底核―分子基盤から臨床まで
61巻3号(2009年3月発行)
特集 Microneurography(微小神経電図法)の臨床応用
61巻2号(2009年2月発行)
特集 神経系の再興感染症と輸入感染症
61巻1号(2009年1月発行)
特集 脳神経倫理
60巻12号(2008年12月発行)
特集 痙縮
60巻11号(2008年11月発行)
特集 脳卒中と遺伝子
60巻10号(2008年10月発行)
特集 若年者の脳卒中
60巻9号(2008年9月発行)
特集 知・情・意の神経学
60巻8号(2008年8月発行)
特集 脳硬膜動静脈瘻
60巻7号(2008年7月発行)
増大特集 学習と記憶――基礎と臨床
60巻6号(2008年6月発行)
特集 Crow-深瀬症候群(POEMS症候群)
60巻5号(2008年5月発行)
特集 「痛み」の研究と治療の最前線
60巻4号(2008年4月発行)
増大特集 神経系の発生とその異常
60巻3号(2008年3月発行)
特集 特発性正常圧水頭症(iNPH)―最近の話題
60巻2号(2008年2月発行)
特集 がん治療と神経障害
60巻1号(2008年1月発行)
特集 日本人の発見した神経疾患
59巻12号(2007年12月発行)
特集 損傷神経の再生―温存的治療法の開発
59巻11号(2007年11月発行)
特集 手根管症候群をめぐって
59巻10号(2007年10月発行)
増大特集 ALS―研究と診療の進歩
59巻9号(2007年9月発行)
特集 パーキンソン病の認知機能障害
59巻8号(2007年8月発行)
特集 パーキンソン病の分子遺伝学―最近の知見
59巻7号(2007年7月発行)
増大特集 情報伝達処理におけるグリアの機能と異常
59巻6号(2007年6月発行)
特集 職業性神経障害の新しい展開
59巻5号(2007年5月発行)
特集 脳画像最前線
59巻4号(2007年4月発行)
増大特集 最近注目される脳神経疾患治療の研究
59巻3号(2007年3月発行)
特集 分子イメージング
59巻2号(2007年2月発行)
特集 進行性多巣性白質脳症の新しい展開―PMLが治る時代へ向けて
59巻1号(2007年1月発行)
特集 高次視覚研究の最近の進歩
