特集の意図
多発性硬化症(MS)は日本でも患者数が着実に増えており,疾患修飾薬として既に6剤が使用可能となっている。しかし,欧米で使用可能となっている薬剤がすべて日本に上陸している状況にはなく,診断・治療においてはいまだ大きな問題を抱えたままである。本特集では疫学,診断基準,画像,認知機能障害,治療という多角的な視点から,現時点の最新知見をエキスパートに解説していただく。
雑誌目次
BRAIN and NERVE-神経研究の進歩72巻5号
2020年05月発行
雑誌目次
特集 多発性硬化症の現在と未来
扉 フリーアクセス
ページ範囲:P.465 - P.465
多発性硬化症の疫学—多発性硬化症は本当に増えているか
著者: 越智博文
ページ範囲:P.467 - P.484
多発性硬化症の有病率や患者数は世界的に増加傾向であり,特に若年女性での増加が著しい。女性を中心に見られたライフスタイルの変化が増加に関係している可能性が考えられるが,単一の生活環境因子は明らかになっていない。一方で,罹患率については報告が少ないものの,横ばいないしは低下傾向とする報告も少なくない。発症リスクの推移を追跡するためには,同一手法を用いて標準化された罹患率調査を継続する必要がある。
多発性硬化症の診断基準—McDonald診断基準2017を読み解く
著者: 中島一郎
ページ範囲:P.485 - P.491
McDonald診断基準は多発性硬化症の診断基準であり,従来は異なる症状による臨床的発作が時間をおいて2回以上必要だったものを,MRIを用いて空間的・時間的多発性を証明することを可能にした。なお,この診断基準はclinically isolated syndrome患者に適用されるものであり,他疾患を鑑別するものではない。その適用について概説する。
多発性硬化症のMRI—診断ツール,バイオマーカー,副作用モニタリングツールとしての役割
著者: 三木幸雄
ページ範囲:P.493 - P.508
多発性硬化症(MS)で用いられる画像診断はMRIであり,国際的に広く用いられているMcDonald診断基準においても非常に重要な位置を占めている。多発性硬化症におけるMRIの重要な役割に,診断,イメージングバイオマーカーおよび疾患修飾薬による副作用のモニタリングがある。本論文では,MSにおけるMRIのこれらの役割について,最近の知見を含めて述べる。
多発性硬化症における認知機能障害—どのように評価して対応するか
著者: 新野正明 , 宮﨑雄生
ページ範囲:P.509 - P.515
多発性硬化症(MS)の神経症状の1つとして,認知機能障害が注目されつつある。MSでは,特に注意・集中・情報処理などの認知機能が障害されやすく,それを評価できるバッテリーを用いることが求められる。この症状に対してさまざまな試みが行われているが,現在まで確立した治療はない。本論では,MSにおける認知機能障害を概説し,この症状に対してどのようにアプローチしていくかを考えていきたい。
今後の多発性硬化症治療の方向性—新規疾患修飾薬が加わって
著者: 近藤誉之
ページ範囲:P.517 - P.523
多発性硬化症疾患修飾薬は,インターフェロンβ製剤2剤,グラチラマー酢酸塩,フマル酸ジメチル,フィンゴリモド,ナタリズマブに加えて,2021年には,抗CD20抗体ofatumumab,スフィンゴシン-1-リン酸受容体調節薬siponimodの承認が見込まれている。安全性や「再発のない進行」も含めた疾患活動性を評価しながら障害進行の抑制可能な薬剤の選択が重要である。国内開発中のOCHについても触れる。
総説
アミロイドβ,タウの脳間質液濃度への影響要因
著者: 栗原正典 , 坂内太郎 , 岩田淳
ページ範囲:P.525 - P.531
アルツハイマー病(AD)において,脳間質はアミロイドβ(Aβ)オリゴマー・凝集体が存在する部位として重要である。またタウ凝集体は神経細胞内に存在するが,タウ凝集は細胞間を伝播することが判明し,脳間質液中のタウも注目されている。本総説では,ADの病態に重要なAβ・タウの脳間質液濃度へ影響を与える要因について,疫学データからADとの関連が知られるものを中心に,これまでの知見をまとめる。
素潜りに伴う中枢神経障害
著者: 合志清隆 , 玉木英樹 , FrédéricLemaître , 森松嘉孝 , 石竹達也
ページ範囲:P.533 - P.539
わが国の素潜り漁業者である「アマ」に脳卒中様の神経症状が見られることがあり,さらにアマの頭部MRIでは虚血性病変が高率に確認される傾向にある。素潜りが繰り返されると血管内に気泡が発生し,これによる動脈ガス塞栓が脳病変の主な原因と推測されている。しかし,素潜りで見られる神経障害,さらに脳病変の発生機序は明らかではなく,詳細な検討に加えて脳血管障害の1つとして病態解明が必要である。
症例報告
脳脊髄液中のJCV-DNA遺伝子検査が2回とも陰性であったが,開頭脳生検で診断確定したHIV関連進行性多巣性白質脳症の1例
著者: 北崎佑樹 , 岩﨑博道 , 北井隆平 , 高橋健太 , 中道一生 , 濱野忠則
ページ範囲:P.541 - P.546
症例は36歳男性。亜急性に進行する小脳性運動失調で受診した。頭部MRIで左小脳半球と右頭頂葉深部白質に病変を認めた。ヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染症例であり,HIV脳症や進行性多巣性白質脳症(PML)が疑われたため,HIV感染に対しARTを開始した。一時的に症状は改善したが,再び神経症状が増悪し,白質病変のMRI Gd造影効果が出現した。HIV関連PML(HIV-PML)による免疫再構築症候群が強く疑われたが,脳脊髄液中JCウイルス(JCV)-DNA検査は2回とも陰性であった。開頭脳生検では,JCVが高copy数存在し,異型リンパ球など悪性リンパ腫を示唆する所見は認めなかったことよりHIV-PMLの診断確定に至った。脳脊髄液中JCV-DNAが繰り返し陰性であっても,PMLが疑われる場合は診断確定のために脳生検も考慮すべきである。
学会印象記
INS 2020—The International Neuropsychological Society 48th Annual Meeting(2020年2月5〜8日,デンバー)
著者: 重宗弥生
ページ範囲:P.547 - P.549
はじめに
2020年2月5〜8日に米国のデンバーで開催された国際神経心理学会第48回年次会議(The International Neuropsychological Society 48th Annual Meeting:INS 2020)に参加しました。INSは,神経・精神疾患患者や脳損傷患者,高齢者を対象に,脳と認知や行動の関係について理解を目指す神経心理学分野において,国際的かつ学際的な研究を推進することを使命とした学会で,毎年2月に北米で年次会議を,7月に北米以外の場所で中間会議を開催しています。年次会議は4日間の日程で参加者は約1,700名,中間会議は3〜4日間の日程で参加者は約400〜800名とのことで,そのどちらも学会員,非学会員,専門家,学生を問わず抄録を投稿し,参加することができます。中間会議の参加者に幅があるのは開催地によって参加人数にばらつきが出ているためでしょう。過去の中間会議の開催地はエルサレム,シドニー,ロンドン,ケープタウン,プラハ,リオデジャネイロでした。個人的には,年次会議の開催地であるシアトル,ボストン,ニューオリンズ,ワシントン,ニューヨークは他の学会でほぼ行ったことがあるので,中間会議のほうが開催地としては魅力的なのですが,規模が約半分から1/4になってしまうことを考えると選択に迷うところです。ただ今回は特に狙って年次会議を選択したわけではなく,年次会議の抄録投稿の時期である8月に,ちょうどそれまで行っていたパーキンソン病患者の内発的動機付けの研究が一段落したので,その研究成果の発表を行うべく参加を決めたのでした。
成田からの直行便で降り立ったデンバー国際空港はうっすら雪に覆われ,ごく稀にしか雪の降らない本州の端っこで育った自分はいやがうえにも気持ちが高まるのを感じました。そのうきうきした気持ちと,長いフライトを終えた安心感から,危うくポスターケースを手荷物として預け入れたまま忘れそうになったのはご愛敬としてください。デンバーは標高1,600mに位置し“Mile High City”とも呼ばれることから,酸素が薄いこともうっかりの一因だったかもしれません。
学会会場であるハイアットリージェンシー・デンバー・アット・コロラドコンベンションセンターは,空港から電車で40分,街中を走る無料バスで10分ほどの道のりでしたが,路線がシンプルでわかりやすかったため,迷うことなくすんなりとたどり着くことができました。今回は学会割引があったことから,贅沢にも学会会場であるハイアットに滞在したのですが,部屋の窓の直下にはコンベンションセンターを覗き込む巨大な青い熊のパブリックアートを,遥か遠くには地平線をなぞるように広がるロッキー山脈を眺めることができました(写真1)。
書評
「《ジェネラリストBOOKS》“問診力”で見逃さない神経症状」—黒川勝己,園生雅弘【著】 フリーアクセス
著者: 砂田芳秀
ページ範囲:P.524 - P.524
著者の黒川勝己先生は,園生雅弘先生の薫陶を受けた電気生理診断を専門とする脳神経内科専門医であるが,臨床現場では一貫して患者第一主義を貫き,自らgeneral neurologyを標榜しているように,そのオールラウンドな臨床能力には定評がある。学生への講義,研修医やかかりつけ医を対象とした彼の講演は大変わかりやすいと高く評価されている。本書は彼が1年にわたって『週刊医学界新聞』に連載し,好評を博した「“問診力”で見逃さない神経症状」というシリーズに総論を加え単行本としてまとめたものである。
神経解剖の複雑さ,鑑別診断の多さ,神経診察の煩雑さのゆえだろうか,神経疾患の診療に苦手意識を持っている研修医やかかりつけ医は多い。本書はそのような方にぜひ一読してもらいたい。本書のユニークな特徴は,神経診察手技や症候学ではなく,問診の仕方にフォーカスしている点にある。頭痛,めまい,しびれ,一過性意識消失などの日常診療で遭遇することの多いコモンな神経症状を取り上げ,見逃してはいけない重篤な神経疾患の鑑別に役立つ,問診のポイントが実際の質問のせりふとともにわかりやすく解説されている。例えば,めまいを訴える患者に対して,「めまいの持続時間」に加え「顔のしびれ感」の有無を聴くことで,椎骨脳底動脈系のTIAを見逃さない。痙攣発作患者の診察に際して,目撃者から「発作中,目は開いていましたか」と聴くことで,てんかん発作を鑑別できる,など。知っているか否かで診療レベルに歴然とした差が出るようなポイントが述べられている。一読いただければ,明日から自信を持ってこうした症状の患者の診療に向き合えるようになるだろう。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.463 - P.463
欧文目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.464 - P.464
バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.554 - P.554
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.555 - P.555
あとがき フリーアクセス
著者: 下畑享良
ページ範囲:P.556 - P.556
新型コロナウィルス感染症(COVID-19)が世界的に猛威を奮っている。図らずも現代の科学や医学について考える機会になった。第1に,未知の疾患の恐怖と向き合いながら,わずか2カ月間で,ウイルスの同定や構造解析,臨床像の分析,そしてランダム化比較試験まで成し遂げ,科学的エビデンスを築いた世界の研究者,医療者の貢献に感動した。特に中国やシンガポールの研究者,医療者の活躍に驚嘆したが,その一方で日本は世界と歴然とした差をつけられてしまったと感じた。長年にわたり科学・医療分野に投資した国とそうでない国の差が如実に現れたように思う。『Nature』誌は数年前から警鐘を鳴らしていた1)が,日本は人口あたりの論文数,大学の研究資金,研究者数,そして博士課程の学生数もいずれも先進国で最低レベルである。私たちは失速した日本の科学の現状を認識し,これからどうすべきかを真剣に考える必要がある。
第2に,緊急時における科学の質の保証について考えさせられた。1つは論文の質の問題である。今回初めてmedRxiv/bioRxivというプレプリントサービスに登録された論文を多数読んだ。これは査読前の医学,生物学分野の論文を受付け,新しい知見の迅速な共有やフィードバックを可能にする利点がある一方,登録論文は玉石混交であり,論文の質を見極める能力がなければ,その共有は誤った情報の流布につながると感じた。もう1つは臨床試験の質の問題である。既に中国では抗HIV薬の効果についてランダム化比較試験による検証を完了し,論文として報告した2)。一方,本邦ではシクレソニド(オルベスコ®)やファビビラビル(アビガン®)の効果の検証が「観察研究」として行われると言う。一刻も早い薬剤の開発が望まれるとは言え,これらの薬剤は未承認薬,適応外薬である。ディオバン事件などを契機として,臨床研究を国の監視下で適正に行うために制定された臨床研究法によって最も規制されるべき「特定臨床研究」に該当する。緊急時という名のもとに,科学の質がないがしろにされることがあってはならない。
基本情報
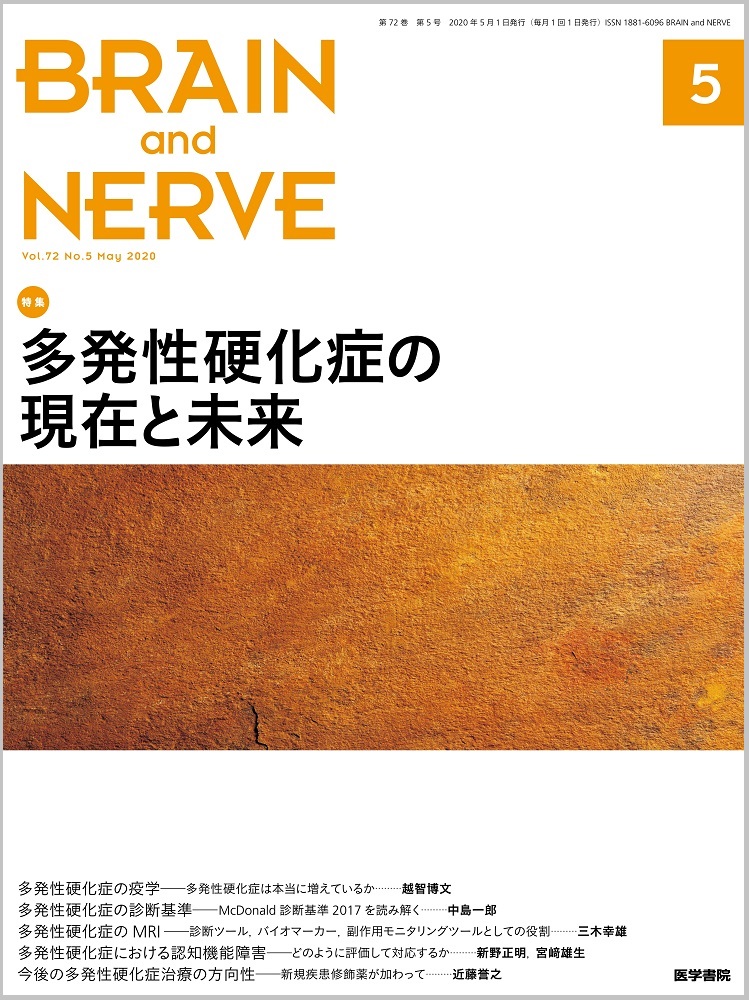
バックナンバー
76巻12号(2024年12月発行)
特集 芸術家と神経学Ⅱ
76巻11号(2024年11月発行)
特集 ALS 2024
76巻10号(2024年10月発行)
特集 どうして効くんだろう
76巻9号(2024年9月発行)
特集 治療可能な認知症としてのアルツハイマー病
76巻8号(2024年8月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である—revisited
76巻7号(2024年7月発行)
特集 ニューロ・バイオイメージング—技術と応用
76巻6号(2024年6月発行)
特集 注意と注意障害
76巻5号(2024年5月発行)
増大特集 末梢神経・筋肉の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
76巻4号(2024年4月発行)
特集 神経病理最前線
76巻3号(2024年3月発行)
特集 きちんと説明ができますか?
76巻2号(2024年2月発行)
特集 特発性正常圧水頭症の現在
76巻1号(2024年1月発行)
特集 新時代の重症筋無力症と関連疾患の診療
75巻12号(2023年12月発行)
特集 アガサ・クリスティーと神経毒
75巻11号(2023年11月発行)
特集 アロスタシス—ホメオスタシスを超えて
75巻10号(2023年10月発行)
特集 メタバースへの招待
75巻9号(2023年9月発行)
特集 妊娠と神経疾患
75巻8号(2023年8月発行)
特集 アルツハイマー病は本当に早期発見できるのか
75巻7号(2023年7月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part2 末梢編
75巻6号(2023年6月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part1 中枢編
75巻5号(2023年5月発行)
増大特集 神経・精神領域の薬剤ハンドブック
75巻4号(2023年4月発行)
特集 All About Epilepsy
75巻3号(2023年3月発行)
特集 慢性疼痛
75巻2号(2023年2月発行)
特集 多系統萎縮症の新診断基準とこれからの診療
75巻1号(2023年1月発行)
特集 よく出会う不随意運動を知る
74巻12号(2022年12月発行)
特集 映画を観て精神・神経疾患を知る
74巻11号(2022年11月発行)
特集 RFC1遺伝子関連スペクトラム障害
74巻10号(2022年10月発行)
特集 ウイルス性脳炎・脳症2022
74巻9号(2022年9月発行)
特集 動的環境への適応系としての歩行
74巻8号(2022年8月発行)
特集 迷走神経の不思議
74巻7号(2022年7月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識2022
74巻6号(2022年6月発行)
特集 脳神経内科医に求められる移行医療
74巻5号(2022年5月発行)
増大特集 次の一手—神経筋疾患難治例をどのように治療するか
74巻4号(2022年4月発行)
特集 脳科学リテラシーを高めるために
74巻3号(2022年3月発行)
特集 中枢性自律神経障害update
74巻2号(2022年2月発行)
特集 温度を感じる脳と身体の科学
74巻1号(2022年1月発行)
特集 脳神経内科医のキャリアパスとリーダーシップ
73巻12号(2021年12月発行)
特集 芸術家と神経学
73巻11号(2021年11月発行)
特集 「目」の神経学
73巻10号(2021年10月発行)
特集 中枢神経・末梢神経の悪性リンパ腫
73巻9号(2021年9月発行)
特集 脳卒中治療に必要な基礎知識
73巻8号(2021年8月発行)
特集 脳腸相関—脳-身体の双方向性制御
73巻7号(2021年7月発行)
特集 グリアと神経—相補的な制御系として
73巻6号(2021年6月発行)
特集 Lower Spine Neurology
73巻5号(2021年5月発行)
増大特集 中枢神経の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
73巻4号(2021年4月発行)
特集 片頭痛・群発頭痛治療の新たな夜明け
73巻3号(2021年3月発行)
特集 マルチリンガルブレイン
73巻2号(2021年2月発行)
特集 筋炎と壊死性筋症
73巻1号(2021年1月発行)
特集 Neuro-Oncology
72巻12号(2020年12月発行)
特集 超高齢期の精神神経疾患を診る
72巻11号(2020年11月発行)
増大特集 脳の発振現象—基礎から臨床へ
72巻10号(2020年10月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識
72巻9号(2020年9月発行)
特集 皮質性小脳萎縮症へのアプローチ
72巻8号(2020年8月発行)
特集 サルコイドーシス
72巻7号(2020年7月発行)
増大特集 神経倫理ハンドブック
72巻6号(2020年6月発行)
特集 前頭側頭葉変性症の今日的理解
72巻5号(2020年5月発行)
特集 多発性硬化症の現在と未来
72巻4号(2020年4月発行)
増大特集 神経疾患の診断における落とし穴—誤診を避けるために
72巻3号(2020年3月発行)
特集 でこぼこの脳の中でおしくらまんじゅうする脳機能
72巻2号(2020年2月発行)
特集 αシヌクレイノパチーの新たな展開
72巻1号(2020年1月発行)
特集 神経難病をクスリで治す—薬物開発の現況と近未来への展望
71巻12号(2019年12月発行)
特集 小脳と大脳—Masao Itoのレガシー
71巻11号(2019年11月発行)
増大特集 ALS2019
71巻10号(2019年10月発行)
特集 認知症と遺伝
71巻9号(2019年9月発行)
特集 神経疾患のドラッグ・リポジショニング—新時代へ
71巻8号(2019年8月発行)
特集 パーキンソン病診療の現在地—200年の変遷と新規治療
71巻7号(2019年7月発行)
増大特集 人工知能と神経科学
71巻6号(2019年6月発行)
特集 補体標的治療の現状と展望
71巻5号(2019年5月発行)
特集 NPSLE
71巻4号(2019年4月発行)
増大特集 神経学のための皮膚アトラス
71巻3号(2019年3月発行)
特集 Spine Neurology
71巻2号(2019年2月発行)
特集 “スポーツ”を生み出す脳
71巻1号(2019年1月発行)
特集 人工知能の医療応用Update
70巻12号(2018年12月発行)
特集 主訴に沿う—俯瞰し収束する画像診断の目
70巻11号(2018年11月発行)
増大特集 脳科学で解き明かす精神神経症候
70巻10号(2018年10月発行)
特集 「左脳と右脳」の現在
70巻9号(2018年9月発行)
特集 脳神経内科診療に役立つ精神科の知識
70巻8号(2018年8月発行)
特集 レヴィ小体型認知症の新知見
70巻7号(2018年7月発行)
増大特集 記憶と忘却に関わる脳のしくみ—分子機構から健忘の症候まで
70巻6号(2018年6月発行)
特集 芸術を生み出す脳
70巻5号(2018年5月発行)
特集 非アルツハイマー型認知症の病理学
70巻4号(2018年4月発行)
増大特集 Antibody Update 2018
70巻3号(2018年3月発行)
特集 『認知症疾患診療ガイドライン2017』を読み解く
70巻2号(2018年2月発行)
特集 知っておきたい神経感染症
70巻1号(2018年1月発行)
特集 筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群の今
69巻12号(2017年12月発行)
特集 運動異常症をみる—Web動画付録つき
69巻11号(2017年11月発行)
増大特集 こころの時間学の未来
69巻10号(2017年10月発行)
特集 成人てんかん—知っておきたい6つのトピック
69巻9号(2017年9月発行)
特集 ミクログリアと精神・神経疾患
69巻8号(2017年8月発行)
特集 遺伝性脊髄小脳失調症の病態と治療展望
69巻7号(2017年7月発行)
増大特集 あしたのアルツハイマー病治療
69巻6号(2017年6月発行)
特集 局在病変の神経心理学
69巻5号(2017年5月発行)
特集 Voxel-Based Morphometry—体積からわかること
69巻4号(2017年4月発行)
増大特集 ブロードマン領野の現在地
69巻3号(2017年3月発行)
特集 磁気刺激の新たな展開
69巻2号(2017年2月発行)
特集 Stroke-Like Diseases—鑑別時に注意を要する5病態
69巻1号(2017年1月発行)
特集 近年注目されている白質脳症
68巻12号(2016年12月発行)
特集 炎症性神経・筋疾患の新たな展開
68巻11号(2016年11月発行)
増大特集 連合野ハンドブック
68巻10号(2016年10月発行)
特集 アディクション—行動の嗜癖
68巻9号(2016年9月発行)
特集 自己免疫性脳炎・脳症
68巻8号(2016年8月発行)
特集 こころと汗
68巻7号(2016年7月発行)
増大特集 認知症の危険因子と防御因子
68巻6号(2016年6月発行)
特集 脳とフローラ
68巻5号(2016年5月発行)
特集 手の症候学—生理学・解剖学からみた新知見
68巻4号(2016年4月発行)
増大特集 治せる認知症
68巻3号(2016年3月発行)
特集 末梢神経の血管炎
68巻2号(2016年2月発行)
特集 筋疾患の認知機能障害
68巻1号(2016年1月発行)
特集 シャルコー・マリー・トゥース病
67巻12号(2015年12月発行)
特集 視床と高次脳機能
67巻11号(2015年11月発行)
増大特集 ギラン・バレー症候群のすべて—100年の軌跡
67巻10号(2015年10月発行)
特集 非・日常生活の脳科学
67巻9号(2015年9月発行)
特集 酵素補充療法
67巻8号(2015年8月発行)
特集 神経難病の終末期医療
67巻7号(2015年7月発行)
増大特集 神経疾患と感染症update
67巻6号(2015年6月発行)
特集 脳と「質感」
67巻5号(2015年5月発行)
特集 NCSE(非痙攣性てんかん重積状態)
67巻4号(2015年4月発行)
増大特集 大脳皮質vs.大脳白質
67巻3号(2015年3月発行)
特集 中枢神経の血管炎
67巻2号(2015年2月発行)
特集 「食べる」を考える
67巻1号(2015年1月発行)
特集 ニューロトキシコロジー
66巻12号(2014年12月発行)
特集 Orthopaedic Neurology—神経内科と整形外科の狭間で
66巻11号(2014年11月発行)
増大特集 神経症候学は神経学の“魂”である
66巻10号(2014年10月発行)
特集 分子を撃つ 神経疾患治療の新しい水平線
66巻9号(2014年9月発行)
特集 痙縮の臨床神経学
66巻8号(2014年8月発行)
特集 神経系の悪性リンパ腫update
66巻7号(2014年7月発行)
増大特集 アミロイド関連神経疾患のすべて―封入体筋炎からアルツハイマー病まで
66巻6号(2014年6月発行)
特集 ミラーニューロン
66巻5号(2014年5月発行)
特集 アセチルコリンと神経疾患―100年目の現在地
66巻4号(2014年4月発行)
増大特集 タッチ・ビジョン・アクション
66巻3号(2014年3月発行)
特集 神経筋疾患の超音波診断
66巻2号(2014年2月発行)
特集 糖尿病の神経学revisited
66巻1号(2014年1月発行)
特集 日常生活の脳科学
65巻12号(2013年12月発行)
特集 プロテイノパチーの神経病理学
65巻11号(2013年11月発行)
増大特集 Close Encounters―臨床神経学と臨床免疫学の遭遇と未来
65巻10号(2013年10月発行)
特集 神経系の発達メカニズム―最近の話題
65巻9号(2013年9月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である―現状と展望
65巻8号(2013年8月発行)
特集 こころの時間学―現在・過去・未来の起源を求めて
65巻7号(2013年7月発行)
増大特集 あしたの脳梗塞
65巻6号(2013年6月発行)
特集 見せる・仕分ける―脳機能解析の新手法
65巻5号(2013年5月発行)
特集 てんかん―新しいパースペクティブ
65巻4号(2013年4月発行)
増大特集 Antibody Update
65巻3号(2013年3月発行)
特集 次世代シーケンサーによる神経変性疾患の解析と展望
65巻2号(2013年2月発行)
特集 血液脳関門研究の進歩
65巻1号(2013年1月発行)
特集 Corticobasal Syndrome
64巻12号(2012年12月発行)
特集 The Border-Land of Dementia
64巻11号(2012年11月発行)
増大特集 痛みの神経学―末梢神経から脳まで
64巻10号(2012年10月発行)
特集 辺縁系をめぐって
64巻9号(2012年9月発行)
特集 高次脳機能イメージングの脳科学への新展開
64巻8号(2012年8月発行)
特集 線条体の基礎と臨床
64巻7号(2012年7月発行)
増大特集 顔認知の脳内機構
64巻6号(2012年6月発行)
特集 睡眠と覚醒の脳内機構
64巻5号(2012年5月発行)
特集 神経疾患のバイオマーカー
64巻4号(2012年4月発行)
増大特集 パーキンソン病の新しい側面
64巻3号(2012年3月発行)
特集 アカデミアから新規治療の実現へ―トランスレーショナルリサーチの現状
64巻2号(2012年2月発行)
特集 生物学的精神医学の進歩
64巻1号(2012年1月発行)
特集 iPS細胞と神経疾患
63巻12号(2011年12月発行)
特集 神経心理学と画像解析の融合
63巻11号(2011年11月発行)
増大特集 筋疾患update
63巻10号(2011年10月発行)
特集 緩徐進行性高次脳機能障害の病態
63巻9号(2011年9月発行)
特集 脳卒中の最新画像診断
63巻8号(2011年8月発行)
特集 日本人の発見した神経症候
63巻7号(2011年7月発行)
増大特集 神経筋接合部―基礎から臨床まで
63巻6号(2011年6月発行)
特集 ニューロパチー
63巻5号(2011年5月発行)
特集 神経系と血管内リンパ腫
63巻4号(2011年4月発行)
増大特集 てんかんの新しい治療
63巻3号(2011年3月発行)
特集 サイバーナイフ治療
63巻2号(2011年2月発行)
特集 続・日本人の発見した神経疾患
63巻1号(2011年1月発行)
特集 血管腫
62巻12号(2010年12月発行)
特集 頸部頸動脈狭窄症の診断と治療
62巻11号(2010年11月発行)
増大特集 歩行とその異常
62巻10号(2010年10月発行)
特集 ブレインバンク
62巻9号(2010年9月発行)
特集 視神経脊髄炎(NMO)update
62巻8号(2010年8月発行)
特集 辺縁系脳炎
62巻7号(2010年7月発行)
増大特集 アルツハイマー病―研究と診療の進歩
62巻6号(2010年6月発行)
特集 改正臓器移植法の問題点とその対応
62巻5号(2010年5月発行)
特集 神経画像のピットフォール―見落としと読み過ぎ
62巻4号(2010年4月発行)
特集 傍腫瘍性神経筋疾患update
62巻3号(2010年3月発行)
特集 神経回路解析法の最近の進歩
62巻2号(2010年2月発行)
特集 ニューロリハビリテーションの最前線
62巻1号(2010年1月発行)
特集 神経救急
61巻12号(2009年12月発行)
特集 Somatotopy再考
61巻11号(2009年11月発行)
特集 前頭側頭葉変性症
61巻10号(2009年10月発行)
特集 片頭痛の予防療法
61巻9号(2009年9月発行)
特集 脳血管障害治療の進歩
61巻8号(2009年8月発行)
特集 神経・筋疾患の分子標的治療
61巻7号(2009年7月発行)
特集 脳腫瘍研究の最前線―遺伝子解析から治療まで
61巻6号(2009年6月発行)
特集 脊椎・脊髄外科の最近の進歩
61巻5号(2009年5月発行)
特集 Restless legs syndrome
61巻4号(2009年4月発行)
特集 大脳基底核―分子基盤から臨床まで
61巻3号(2009年3月発行)
特集 Microneurography(微小神経電図法)の臨床応用
61巻2号(2009年2月発行)
特集 神経系の再興感染症と輸入感染症
61巻1号(2009年1月発行)
特集 脳神経倫理
60巻12号(2008年12月発行)
特集 痙縮
60巻11号(2008年11月発行)
特集 脳卒中と遺伝子
60巻10号(2008年10月発行)
特集 若年者の脳卒中
60巻9号(2008年9月発行)
特集 知・情・意の神経学
60巻8号(2008年8月発行)
特集 脳硬膜動静脈瘻
60巻7号(2008年7月発行)
増大特集 学習と記憶――基礎と臨床
60巻6号(2008年6月発行)
特集 Crow-深瀬症候群(POEMS症候群)
60巻5号(2008年5月発行)
特集 「痛み」の研究と治療の最前線
60巻4号(2008年4月発行)
増大特集 神経系の発生とその異常
60巻3号(2008年3月発行)
特集 特発性正常圧水頭症(iNPH)―最近の話題
60巻2号(2008年2月発行)
特集 がん治療と神経障害
60巻1号(2008年1月発行)
特集 日本人の発見した神経疾患
59巻12号(2007年12月発行)
特集 損傷神経の再生―温存的治療法の開発
59巻11号(2007年11月発行)
特集 手根管症候群をめぐって
59巻10号(2007年10月発行)
増大特集 ALS―研究と診療の進歩
59巻9号(2007年9月発行)
特集 パーキンソン病の認知機能障害
59巻8号(2007年8月発行)
特集 パーキンソン病の分子遺伝学―最近の知見
59巻7号(2007年7月発行)
増大特集 情報伝達処理におけるグリアの機能と異常
59巻6号(2007年6月発行)
特集 職業性神経障害の新しい展開
59巻5号(2007年5月発行)
特集 脳画像最前線
59巻4号(2007年4月発行)
増大特集 最近注目される脳神経疾患治療の研究
59巻3号(2007年3月発行)
特集 分子イメージング
59巻2号(2007年2月発行)
特集 進行性多巣性白質脳症の新しい展開―PMLが治る時代へ向けて
59巻1号(2007年1月発行)
特集 高次視覚研究の最近の進歩
