特集の意図
前頭側頭葉変性症(FTLD)は非常に多様な行動症状・言語症状を呈し,現時点で疾患特異的バイオマーカーはなく,患者は病識を欠くことも多いため,他の認知症性疾患や精神疾患との鑑別診断が難しい疾患である。しかしながら,脳画像とともにその多様な症候を丁寧に紐解いていくことで正確な診断にたどり着き,早期治療や有効なケアを行うことができる。そこで,本特集ではFTLDについて,その概念や原因遺伝子,病理類型・臨床類型それぞれの差異などをあらゆる角度から解説し,正確な診断を導く方法を探る。
雑誌目次
BRAIN and NERVE-神経研究の進歩72巻6号
2020年06月発行
雑誌目次
特集 前頭側頭葉変性症の今日的理解
扉 フリーアクセス
ページ範囲:P.559 - P.559
前頭側頭葉変性症概念の歴史的変遷
著者: 川勝忍 , 小林良太 , 坂本和貴 , 大谷浩一
ページ範囲:P.561 - P.573
前頭側頭葉変性症(FTLD)の概念は,ピックが側頭葉や前頭葉の限局性脳萎縮で局在的な症状を呈すると指摘し,のちにそれがピック病と命名されたことに始まる。その後長年,ピック球の有無はピック病の診断には無関係とされてきたが,現在ではピック球を有する症例のみをピック病と呼ぶ。ピックの症例は左側頭葉萎縮例が多く,実はピック病ではなく意味性認知症に相当しTDP-43病理が疑われる。当初のピック病は現在のFTDと同義で多様な背景病理を持っている。
前頭側頭葉変性症の臨床-病理-遺伝子相関
著者: 渡辺亮平 , 新井哲明
ページ範囲:P.575 - P.583
前頭側頭葉変性症(FTLD)とは,前頭・側頭葉に限局性の萎縮をきたし,行動障害や言語症状などを呈する疾患群の総称である。病理学的には,主としてタウ,TDP-43,FUSのいずれかの細胞内蓄積が認められる。FTLDの症候は多様であるが,近年の病理生化学的および遺伝学的研究の進歩により,臨床-病理-遺伝子の相関関係が明らかになってきており,本症の早期診断法や治療法開発につながると期待される。
行動型前頭側頭型認知症の症候学
著者: 品川俊一郎
ページ範囲:P.585 - P.592
前頭側頭葉変性症の中核的な臨床類型である行動型前頭側頭型認知症では,前頭葉の損傷に伴って脱抑制や意欲低下,共感性の欠如,常同行動,食行動の変化といった多彩な社会行動の変容が病初期から出現し,緩徐に進行する。疾患特異的なバイオマーカーは存在せず,画像診断や認知機能検査も補助的な位置付けであり,診断は行動症状の評価が基本となる。診断基準は有用であるが,精神疾患を含む他の病態との鑑別診断が困難な場合があり,過剰診断や過小診断に陥りやすいため,注意が必要である。
意味性認知症—診断のポイント
著者: 小森憲治郎
ページ範囲:P.593 - P.610
意味性認知症(SD)は,前頭側頭葉変性症により意味記憶が選択的かつ進行性に障害される臨床症候群である。意味記憶の障害は,言語,相貌や対象の認知などさまざまな認知領域に現れる。側頭葉萎縮の左右差によって現れる症候に特徴があり,左優位萎縮例では,単語の意味を問い返す語義失語が顕著である。一方,右優位萎縮例では,既知相貌に特徴的な全体視の障害である相貌失認が特徴的である。また,対象概念そのものの理解障害による失行様の症状も現れる。行動障害は初期には目立たないことが多いが,語義失語例に特徴的な行動変化は初診時にも観察される。神経画像診断,意味記憶障害の評価に加え,このSD特有の行動変化に注目することが臨床診断上有用である。
原発性進行性失語の分類と診断—今日のコンセンサスと問題点
著者: 大槻美佳
ページ範囲:P.611 - P.621
原発性進行性失語(PPA)の概念と変遷を前頭側頭葉変性症との関係から整理し,診断に必要な要素的言語症候(文産生障害,発語失行,音韻性錯語,喚語障害,単語の理解障害,復唱障害)を概説した。さらに,PPAの3つの臨床類型(非流暢/失文法型PPA,意味型PPA,語減少型PPA)の症候と病巣を,Gorno-Tempiniらの診断基準(2011)に準拠して述べ,病理所見との関係についても紹介した。
前頭側頭葉変性症への対応と支援
著者: 森康治 , 佐藤俊介 , 宮脇英子 , 池田学
ページ範囲:P.623 - P.632
前頭側頭葉変性症(FTLD)は,行動障害のため既存の介護サービスが利用しづらく,比較的若年者に多いため,経済的支援の必要性も高い。臨床サブタイプのうち,行動異常型前頭側頭型認知症と意味性認知症は2015年に指定難病となった。本論では,指定難病の利用を含めた支援,特徴的な症候への対応とケアについて述べる。最後に進行中のFTLDに関するコホート研究であるFTLD-Jの現状を紹介する。
総説
光を使って読み解く意欲行動の神経基盤
著者: 吉田慶多朗
ページ範囲:P.637 - P.642
物事に意欲的に取り組む,という意欲行動の背景には,ゴールに向かう行動の選択,行動の開始,行動の継続という過程を経て目標の達成にいたる。では,それぞれの過程を制御する脳領域はどこだろうか。神経科学の分野では,こうした問いに答えるために,神経活動を観察,または操作する技術が磨かれてきた。本総説では,光観察技術と光操作技術を両輪とすることで見えてきた意欲行動の神経基盤を概説する。
原著
音読課題において異なる誤反応パターンを示した純粋発語失行例の検討
著者: 山田晃司 , 橋本竜作 , 幅寺慎也
ページ範囲:P.643 - P.651
音読に際して異なる誤りを呈した2例の純粋発語失行例を報告した。症例Aは多彩な音の誤り(置換・歪み・省略)を生じ,症例Bは主に長母音の省略とピッチの誤りを認めた。2例の病巣部位は,左中心前回の中で異なっており,症例Aは左中心前回の前壁を除く後部からやや深部に,症例Bは左中前頭回および中心前回前部を含む深部白質であった。誤りのパターンを中心前回での病巣の違いから検討した。
書評
「外傷性脳損傷ハンドブック—診断と治療・評価・後遺症の管理 現場で役立つ臨床マニュアル」—アルシニェガス,ザスラー,ヴァンダープローグ,ジャフィ【編】 松村 明【総監訳】 羽田康司,丸島愛樹【監訳】 フリーアクセス
著者: 鈴木倫保
ページ範囲:P.635 - P.635
この度,筑波大学脳神経外科学教授の松村明先生の総監訳による本書を拝読する機会を得て,目から鱗が4,5枚落ちた。本書は,正に本邦脳神経外傷治療の欠落点,即ち外傷性脳損傷(TBI)後のメンタルヘルス・リハビリテーションの問題を長年にわたり悩み抜いた訳者の方々が,米国のアルシニェガスを中心とした編者らによる治療マニュアルを紹介することによって,欠落点を埋め直す取り組みと理解された。その内容がTBIの急性期病態や治療の項目がごく僅かである事に驚かれる読者も居られよう。しかし,編者が大部を割いて記している,TBI慢性期の認知・感情・行動・感覚・運動障害の疫学,評価,治療こそが本邦においては,これまで等閑にされていた欠落点であった。更に,それらによって二次的に引き起こされる精神的・社会心理的なメンタルヘルスの悪化は,言わずもがなであろう。
TBIに立ち向かう救急医や脳神経外科医は,急性期治療を100%行えば,患者を外来で自分たちが診る必要は無いと考えているだろうが,患者や家族にとっては急性期病院を退院したその日から,長い長い慢性期の治療が始まることを思い起こす必要がある。読者も脳神経外科医や救急医等の急性期の医師ばかりでは無く,リハビリテーション・精神科等慢性期治療に携わる医師,及び看護師,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,臨床心理士,心理学者等の多職種を対象としており,大変わかりやすく記載されている。そのために,世界中で新たな公衆衛生学上の大問題としてクロースアップされているTBI慢性期治療に携わる本邦の医療従事者にとっても,大きな福音となるだろう。
「スパルタ病理塾—あなたの臨床を変える! 病理標本の読み方」—小島伊織【執筆】 フリーアクセス
著者: 市原真
ページ範囲:P.636 - P.636
冒頭3ページ目で,私は早くも心をツカまれた。
「内科では『初めに疾患ありき』の内科学の他に『初めに症候ありき』の内科診断学を勉強する時間が学生時代に十分あったのに,病理については『初めに疾患ありき』の病理学の授業はあっても『初めに所見ありき』の病理診断学をしっかり勉強する時間は設けられていなかったのです」。
「新訂 うまい英語で医学論文を書くコツ—世界の一流誌に採択されるノウハウ」—植村研一【著】 フリーアクセス
著者: 鈴木康之
ページ範囲:P.653 - P.653
私が初めて本格的な英語論文を書いたのは1986年でした。当時,論文執筆に関するテキストはほとんどなく,他の論文の表現や構成を参考にしながら,四苦八苦して継ぎはぎの英作文をしていた記憶しかありません。本書で植村研一先生が強調しておられる“comfortable English”にはほど遠いものでした。当時,本書があったら私の苦労の何割かは軽減し,ワンランク上の雑誌に掲載できていたことでしょう。近年,論文執筆に関するテキストは随分多くなりましたが,本書は次の3点でとても魅力的です。
①医学研究者・医学英語教育者・雑誌編集者・同時通訳者としての長年の経験に基づいて,「どのような論文が一流誌に採択されるか?」を熟知した植村先生が,まるで直接語りかけてくださるように,歯切れよくポイントを示しています。植村先生のお話を一度でも聞いたことのある方は,特に実感されるでしょう。植村先生の頭に蓄積されてきた智慧とノウハウを学びとってほしいと思います。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.557 - P.557
欧文目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.558 - P.558
バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.658 - P.658
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.659 - P.659
あとがき フリーアクセス
著者: 虫明元
ページ範囲:P.660 - P.660
本号の特集は「前頭側頭葉変性症の今日的理解」ということで,大変興味深く読ませていただいた。脳の変性症というとアルツハイマー型認知症がよく知られている。またレヴィ小体型認知症も次第によく知られるようになってきた。それらに比べると今回特集されている前頭側頭葉変性症は専門家でもわかりにくい印象がある。特集してまとめることで,この分野の勉強にもなり,理解が進み大変ありがたいと思われた。脳の変性症はどのタイプも基本的にはネットワーク病であり,脳の1つの領域ではなく,ネットワークとして障害を受けるため,1つの領域の機能と障害だけでは理解できない難しさがあることが各論からはよくわかる。このような難しさは実は脳に関しては本質的な問題と思われる。
脳研究のこれまでの膨大な成果からも,脳の働きを理解する際に大きな問題となるのは,部分と全体の課題である。すなわち脳のある領域としての働きは,その領域を含む他の領域とのネットワークの総和として働き,さらには人としての社会の中での働きの理解と段階的に進められると思われる。一方で,部分としての特定の脳部位の理解とそのような脳の部分の総和としての働きが,人としての全体の働きと等価ではないのではないかというのが部分と全体の問題の本質である。
基本情報
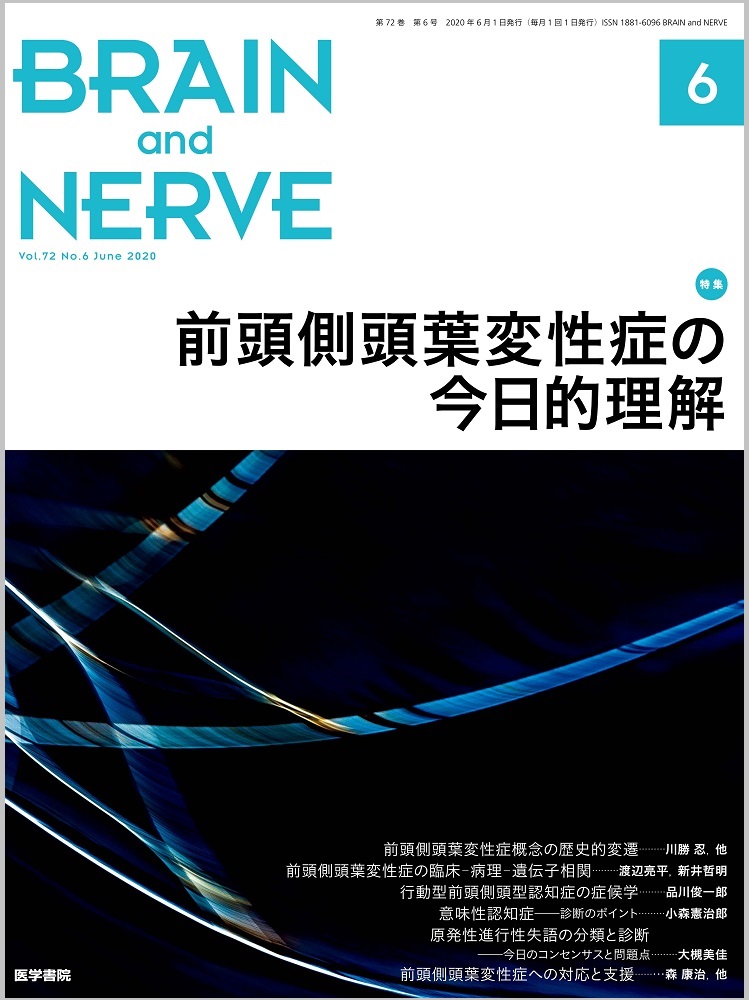
バックナンバー
76巻12号(2024年12月発行)
特集 芸術家と神経学Ⅱ
76巻11号(2024年11月発行)
特集 ALS 2024
76巻10号(2024年10月発行)
特集 どうして効くんだろう
76巻9号(2024年9月発行)
特集 治療可能な認知症としてのアルツハイマー病
76巻8号(2024年8月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である—revisited
76巻7号(2024年7月発行)
特集 ニューロ・バイオイメージング—技術と応用
76巻6号(2024年6月発行)
特集 注意と注意障害
76巻5号(2024年5月発行)
増大特集 末梢神経・筋肉の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
76巻4号(2024年4月発行)
特集 神経病理最前線
76巻3号(2024年3月発行)
特集 きちんと説明ができますか?
76巻2号(2024年2月発行)
特集 特発性正常圧水頭症の現在
76巻1号(2024年1月発行)
特集 新時代の重症筋無力症と関連疾患の診療
75巻12号(2023年12月発行)
特集 アガサ・クリスティーと神経毒
75巻11号(2023年11月発行)
特集 アロスタシス—ホメオスタシスを超えて
75巻10号(2023年10月発行)
特集 メタバースへの招待
75巻9号(2023年9月発行)
特集 妊娠と神経疾患
75巻8号(2023年8月発行)
特集 アルツハイマー病は本当に早期発見できるのか
75巻7号(2023年7月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part2 末梢編
75巻6号(2023年6月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part1 中枢編
75巻5号(2023年5月発行)
増大特集 神経・精神領域の薬剤ハンドブック
75巻4号(2023年4月発行)
特集 All About Epilepsy
75巻3号(2023年3月発行)
特集 慢性疼痛
75巻2号(2023年2月発行)
特集 多系統萎縮症の新診断基準とこれからの診療
75巻1号(2023年1月発行)
特集 よく出会う不随意運動を知る
74巻12号(2022年12月発行)
特集 映画を観て精神・神経疾患を知る
74巻11号(2022年11月発行)
特集 RFC1遺伝子関連スペクトラム障害
74巻10号(2022年10月発行)
特集 ウイルス性脳炎・脳症2022
74巻9号(2022年9月発行)
特集 動的環境への適応系としての歩行
74巻8号(2022年8月発行)
特集 迷走神経の不思議
74巻7号(2022年7月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識2022
74巻6号(2022年6月発行)
特集 脳神経内科医に求められる移行医療
74巻5号(2022年5月発行)
増大特集 次の一手—神経筋疾患難治例をどのように治療するか
74巻4号(2022年4月発行)
特集 脳科学リテラシーを高めるために
74巻3号(2022年3月発行)
特集 中枢性自律神経障害update
74巻2号(2022年2月発行)
特集 温度を感じる脳と身体の科学
74巻1号(2022年1月発行)
特集 脳神経内科医のキャリアパスとリーダーシップ
73巻12号(2021年12月発行)
特集 芸術家と神経学
73巻11号(2021年11月発行)
特集 「目」の神経学
73巻10号(2021年10月発行)
特集 中枢神経・末梢神経の悪性リンパ腫
73巻9号(2021年9月発行)
特集 脳卒中治療に必要な基礎知識
73巻8号(2021年8月発行)
特集 脳腸相関—脳-身体の双方向性制御
73巻7号(2021年7月発行)
特集 グリアと神経—相補的な制御系として
73巻6号(2021年6月発行)
特集 Lower Spine Neurology
73巻5号(2021年5月発行)
増大特集 中枢神経の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
73巻4号(2021年4月発行)
特集 片頭痛・群発頭痛治療の新たな夜明け
73巻3号(2021年3月発行)
特集 マルチリンガルブレイン
73巻2号(2021年2月発行)
特集 筋炎と壊死性筋症
73巻1号(2021年1月発行)
特集 Neuro-Oncology
72巻12号(2020年12月発行)
特集 超高齢期の精神神経疾患を診る
72巻11号(2020年11月発行)
増大特集 脳の発振現象—基礎から臨床へ
72巻10号(2020年10月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識
72巻9号(2020年9月発行)
特集 皮質性小脳萎縮症へのアプローチ
72巻8号(2020年8月発行)
特集 サルコイドーシス
72巻7号(2020年7月発行)
増大特集 神経倫理ハンドブック
72巻6号(2020年6月発行)
特集 前頭側頭葉変性症の今日的理解
72巻5号(2020年5月発行)
特集 多発性硬化症の現在と未来
72巻4号(2020年4月発行)
増大特集 神経疾患の診断における落とし穴—誤診を避けるために
72巻3号(2020年3月発行)
特集 でこぼこの脳の中でおしくらまんじゅうする脳機能
72巻2号(2020年2月発行)
特集 αシヌクレイノパチーの新たな展開
72巻1号(2020年1月発行)
特集 神経難病をクスリで治す—薬物開発の現況と近未来への展望
71巻12号(2019年12月発行)
特集 小脳と大脳—Masao Itoのレガシー
71巻11号(2019年11月発行)
増大特集 ALS2019
71巻10号(2019年10月発行)
特集 認知症と遺伝
71巻9号(2019年9月発行)
特集 神経疾患のドラッグ・リポジショニング—新時代へ
71巻8号(2019年8月発行)
特集 パーキンソン病診療の現在地—200年の変遷と新規治療
71巻7号(2019年7月発行)
増大特集 人工知能と神経科学
71巻6号(2019年6月発行)
特集 補体標的治療の現状と展望
71巻5号(2019年5月発行)
特集 NPSLE
71巻4号(2019年4月発行)
増大特集 神経学のための皮膚アトラス
71巻3号(2019年3月発行)
特集 Spine Neurology
71巻2号(2019年2月発行)
特集 “スポーツ”を生み出す脳
71巻1号(2019年1月発行)
特集 人工知能の医療応用Update
70巻12号(2018年12月発行)
特集 主訴に沿う—俯瞰し収束する画像診断の目
70巻11号(2018年11月発行)
増大特集 脳科学で解き明かす精神神経症候
70巻10号(2018年10月発行)
特集 「左脳と右脳」の現在
70巻9号(2018年9月発行)
特集 脳神経内科診療に役立つ精神科の知識
70巻8号(2018年8月発行)
特集 レヴィ小体型認知症の新知見
70巻7号(2018年7月発行)
増大特集 記憶と忘却に関わる脳のしくみ—分子機構から健忘の症候まで
70巻6号(2018年6月発行)
特集 芸術を生み出す脳
70巻5号(2018年5月発行)
特集 非アルツハイマー型認知症の病理学
70巻4号(2018年4月発行)
増大特集 Antibody Update 2018
70巻3号(2018年3月発行)
特集 『認知症疾患診療ガイドライン2017』を読み解く
70巻2号(2018年2月発行)
特集 知っておきたい神経感染症
70巻1号(2018年1月発行)
特集 筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群の今
69巻12号(2017年12月発行)
特集 運動異常症をみる—Web動画付録つき
69巻11号(2017年11月発行)
増大特集 こころの時間学の未来
69巻10号(2017年10月発行)
特集 成人てんかん—知っておきたい6つのトピック
69巻9号(2017年9月発行)
特集 ミクログリアと精神・神経疾患
69巻8号(2017年8月発行)
特集 遺伝性脊髄小脳失調症の病態と治療展望
69巻7号(2017年7月発行)
増大特集 あしたのアルツハイマー病治療
69巻6号(2017年6月発行)
特集 局在病変の神経心理学
69巻5号(2017年5月発行)
特集 Voxel-Based Morphometry—体積からわかること
69巻4号(2017年4月発行)
増大特集 ブロードマン領野の現在地
69巻3号(2017年3月発行)
特集 磁気刺激の新たな展開
69巻2号(2017年2月発行)
特集 Stroke-Like Diseases—鑑別時に注意を要する5病態
69巻1号(2017年1月発行)
特集 近年注目されている白質脳症
68巻12号(2016年12月発行)
特集 炎症性神経・筋疾患の新たな展開
68巻11号(2016年11月発行)
増大特集 連合野ハンドブック
68巻10号(2016年10月発行)
特集 アディクション—行動の嗜癖
68巻9号(2016年9月発行)
特集 自己免疫性脳炎・脳症
68巻8号(2016年8月発行)
特集 こころと汗
68巻7号(2016年7月発行)
増大特集 認知症の危険因子と防御因子
68巻6号(2016年6月発行)
特集 脳とフローラ
68巻5号(2016年5月発行)
特集 手の症候学—生理学・解剖学からみた新知見
68巻4号(2016年4月発行)
増大特集 治せる認知症
68巻3号(2016年3月発行)
特集 末梢神経の血管炎
68巻2号(2016年2月発行)
特集 筋疾患の認知機能障害
68巻1号(2016年1月発行)
特集 シャルコー・マリー・トゥース病
67巻12号(2015年12月発行)
特集 視床と高次脳機能
67巻11号(2015年11月発行)
増大特集 ギラン・バレー症候群のすべて—100年の軌跡
67巻10号(2015年10月発行)
特集 非・日常生活の脳科学
67巻9号(2015年9月発行)
特集 酵素補充療法
67巻8号(2015年8月発行)
特集 神経難病の終末期医療
67巻7号(2015年7月発行)
増大特集 神経疾患と感染症update
67巻6号(2015年6月発行)
特集 脳と「質感」
67巻5号(2015年5月発行)
特集 NCSE(非痙攣性てんかん重積状態)
67巻4号(2015年4月発行)
増大特集 大脳皮質vs.大脳白質
67巻3号(2015年3月発行)
特集 中枢神経の血管炎
67巻2号(2015年2月発行)
特集 「食べる」を考える
67巻1号(2015年1月発行)
特集 ニューロトキシコロジー
66巻12号(2014年12月発行)
特集 Orthopaedic Neurology—神経内科と整形外科の狭間で
66巻11号(2014年11月発行)
増大特集 神経症候学は神経学の“魂”である
66巻10号(2014年10月発行)
特集 分子を撃つ 神経疾患治療の新しい水平線
66巻9号(2014年9月発行)
特集 痙縮の臨床神経学
66巻8号(2014年8月発行)
特集 神経系の悪性リンパ腫update
66巻7号(2014年7月発行)
増大特集 アミロイド関連神経疾患のすべて―封入体筋炎からアルツハイマー病まで
66巻6号(2014年6月発行)
特集 ミラーニューロン
66巻5号(2014年5月発行)
特集 アセチルコリンと神経疾患―100年目の現在地
66巻4号(2014年4月発行)
増大特集 タッチ・ビジョン・アクション
66巻3号(2014年3月発行)
特集 神経筋疾患の超音波診断
66巻2号(2014年2月発行)
特集 糖尿病の神経学revisited
66巻1号(2014年1月発行)
特集 日常生活の脳科学
65巻12号(2013年12月発行)
特集 プロテイノパチーの神経病理学
65巻11号(2013年11月発行)
増大特集 Close Encounters―臨床神経学と臨床免疫学の遭遇と未来
65巻10号(2013年10月発行)
特集 神経系の発達メカニズム―最近の話題
65巻9号(2013年9月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である―現状と展望
65巻8号(2013年8月発行)
特集 こころの時間学―現在・過去・未来の起源を求めて
65巻7号(2013年7月発行)
増大特集 あしたの脳梗塞
65巻6号(2013年6月発行)
特集 見せる・仕分ける―脳機能解析の新手法
65巻5号(2013年5月発行)
特集 てんかん―新しいパースペクティブ
65巻4号(2013年4月発行)
増大特集 Antibody Update
65巻3号(2013年3月発行)
特集 次世代シーケンサーによる神経変性疾患の解析と展望
65巻2号(2013年2月発行)
特集 血液脳関門研究の進歩
65巻1号(2013年1月発行)
特集 Corticobasal Syndrome
64巻12号(2012年12月発行)
特集 The Border-Land of Dementia
64巻11号(2012年11月発行)
増大特集 痛みの神経学―末梢神経から脳まで
64巻10号(2012年10月発行)
特集 辺縁系をめぐって
64巻9号(2012年9月発行)
特集 高次脳機能イメージングの脳科学への新展開
64巻8号(2012年8月発行)
特集 線条体の基礎と臨床
64巻7号(2012年7月発行)
増大特集 顔認知の脳内機構
64巻6号(2012年6月発行)
特集 睡眠と覚醒の脳内機構
64巻5号(2012年5月発行)
特集 神経疾患のバイオマーカー
64巻4号(2012年4月発行)
増大特集 パーキンソン病の新しい側面
64巻3号(2012年3月発行)
特集 アカデミアから新規治療の実現へ―トランスレーショナルリサーチの現状
64巻2号(2012年2月発行)
特集 生物学的精神医学の進歩
64巻1号(2012年1月発行)
特集 iPS細胞と神経疾患
63巻12号(2011年12月発行)
特集 神経心理学と画像解析の融合
63巻11号(2011年11月発行)
増大特集 筋疾患update
63巻10号(2011年10月発行)
特集 緩徐進行性高次脳機能障害の病態
63巻9号(2011年9月発行)
特集 脳卒中の最新画像診断
63巻8号(2011年8月発行)
特集 日本人の発見した神経症候
63巻7号(2011年7月発行)
増大特集 神経筋接合部―基礎から臨床まで
63巻6号(2011年6月発行)
特集 ニューロパチー
63巻5号(2011年5月発行)
特集 神経系と血管内リンパ腫
63巻4号(2011年4月発行)
増大特集 てんかんの新しい治療
63巻3号(2011年3月発行)
特集 サイバーナイフ治療
63巻2号(2011年2月発行)
特集 続・日本人の発見した神経疾患
63巻1号(2011年1月発行)
特集 血管腫
62巻12号(2010年12月発行)
特集 頸部頸動脈狭窄症の診断と治療
62巻11号(2010年11月発行)
増大特集 歩行とその異常
62巻10号(2010年10月発行)
特集 ブレインバンク
62巻9号(2010年9月発行)
特集 視神経脊髄炎(NMO)update
62巻8号(2010年8月発行)
特集 辺縁系脳炎
62巻7号(2010年7月発行)
増大特集 アルツハイマー病―研究と診療の進歩
62巻6号(2010年6月発行)
特集 改正臓器移植法の問題点とその対応
62巻5号(2010年5月発行)
特集 神経画像のピットフォール―見落としと読み過ぎ
62巻4号(2010年4月発行)
特集 傍腫瘍性神経筋疾患update
62巻3号(2010年3月発行)
特集 神経回路解析法の最近の進歩
62巻2号(2010年2月発行)
特集 ニューロリハビリテーションの最前線
62巻1号(2010年1月発行)
特集 神経救急
61巻12号(2009年12月発行)
特集 Somatotopy再考
61巻11号(2009年11月発行)
特集 前頭側頭葉変性症
61巻10号(2009年10月発行)
特集 片頭痛の予防療法
61巻9号(2009年9月発行)
特集 脳血管障害治療の進歩
61巻8号(2009年8月発行)
特集 神経・筋疾患の分子標的治療
61巻7号(2009年7月発行)
特集 脳腫瘍研究の最前線―遺伝子解析から治療まで
61巻6号(2009年6月発行)
特集 脊椎・脊髄外科の最近の進歩
61巻5号(2009年5月発行)
特集 Restless legs syndrome
61巻4号(2009年4月発行)
特集 大脳基底核―分子基盤から臨床まで
61巻3号(2009年3月発行)
特集 Microneurography(微小神経電図法)の臨床応用
61巻2号(2009年2月発行)
特集 神経系の再興感染症と輸入感染症
61巻1号(2009年1月発行)
特集 脳神経倫理
60巻12号(2008年12月発行)
特集 痙縮
60巻11号(2008年11月発行)
特集 脳卒中と遺伝子
60巻10号(2008年10月発行)
特集 若年者の脳卒中
60巻9号(2008年9月発行)
特集 知・情・意の神経学
60巻8号(2008年8月発行)
特集 脳硬膜動静脈瘻
60巻7号(2008年7月発行)
増大特集 学習と記憶――基礎と臨床
60巻6号(2008年6月発行)
特集 Crow-深瀬症候群(POEMS症候群)
60巻5号(2008年5月発行)
特集 「痛み」の研究と治療の最前線
60巻4号(2008年4月発行)
増大特集 神経系の発生とその異常
60巻3号(2008年3月発行)
特集 特発性正常圧水頭症(iNPH)―最近の話題
60巻2号(2008年2月発行)
特集 がん治療と神経障害
60巻1号(2008年1月発行)
特集 日本人の発見した神経疾患
59巻12号(2007年12月発行)
特集 損傷神経の再生―温存的治療法の開発
59巻11号(2007年11月発行)
特集 手根管症候群をめぐって
59巻10号(2007年10月発行)
増大特集 ALS―研究と診療の進歩
59巻9号(2007年9月発行)
特集 パーキンソン病の認知機能障害
59巻8号(2007年8月発行)
特集 パーキンソン病の分子遺伝学―最近の知見
59巻7号(2007年7月発行)
増大特集 情報伝達処理におけるグリアの機能と異常
59巻6号(2007年6月発行)
特集 職業性神経障害の新しい展開
59巻5号(2007年5月発行)
特集 脳画像最前線
59巻4号(2007年4月発行)
増大特集 最近注目される脳神経疾患治療の研究
59巻3号(2007年3月発行)
特集 分子イメージング
59巻2号(2007年2月発行)
特集 進行性多巣性白質脳症の新しい展開―PMLが治る時代へ向けて
59巻1号(2007年1月発行)
特集 高次視覚研究の最近の進歩
