特集の意図
サルコイドーシスは全身疾患であるが,診断困難例,難治例は神経系に集中している。しかしながら神経サルコイドーシスには特異的な所見が極めて少なく,また,治療に関するエビデンスに乏しいことから,脳神経内科では診断・治療に苦慮する疾患である。本特集では,神経サルコイドーシスに対してどのような診断・治療戦略を立てるべきか,また,どのような場合に神経サルコイドーシスを鑑別診断に挙げるべきなのかという点について論じていただく。
雑誌目次
BRAIN and NERVE-神経研究の進歩72巻8号
2020年08月発行
雑誌目次
特集 サルコイドーシス
扉 フリーアクセス
ページ範囲:P.831 - P.831
脳サルコイドーシス
著者: 髙尾昌樹
ページ範囲:P.833 - P.844
神経サルコイドーシスの中で,特に脳病変を中心にまとめた。脳神経障害,頭痛,意識障害,痙攣など複数の神経症候を呈することが多い。多岐にわたる疾患が鑑別すべき疾患に挙がり,結核,真菌感染症は適切に除外されなければならない。したがって,脳病変からの病理診断が極めて重要であり,積極的に考慮されるべきである。治療としてプレドニゾロンの投与が一般的であり,加えて腫瘍壊死因子αに対するインフリキシマブの有用性が示されている。
脊髄サルコイドーシス
著者: 藤澤美和子 , 古賀道明 , 神田隆
ページ範囲:P.845 - P.853
脊髄サルコイドーシスは,脊髄病変の生検が困難な場合が多く,確定診断を得難い。組織診断以外に特異的な検査所見はなく,臨床症状,細かな全身検索,脊髄以外の可能な部位での生検といった多くの所見を総合して診断精度を高めることを心がけたい。長期間の免疫治療を要する例が多く,診断根拠が乏しい段階での治療開始は極力避け,治療による修飾を受ける前に過不足なく検査を行い,より多くの診断根拠を得る努力が必要である。
末梢神経サルコイドーシス
著者: 古賀道明
ページ範囲:P.855 - P.862
サルコイドニューロパチーの臨床像は非常に多様である。多発性単神経型の分布が典型的であるが,ポリニューロパチー様の分布を示すことも多い。その際にも左右差や神経根障害を反映した四肢近位部優位の症候,末梢神経の分枝レベルの感覚障害,疼痛などの陽性症状を伴う感覚障害があれば,本症を疑う根拠となる。電気生理的には軸索障害が不均一な広がりをもって見られるが,時に脱髄様の変化を示すことから他疾患との鑑別診断が問題となる。
筋サルコイドーシス
著者: 杉江和馬
ページ範囲:P.863 - P.870
筋サルコイドーシスは,非乾酪性類上皮細胞肉芽腫が筋組織内で免疫学的機序により形成される原因不明の肉芽腫性筋炎である。その多くが無症候性で画像検査や筋生検により発見される。症候性(=サルコイドミオパチー)は稀な病態で,進行性の筋力低下や筋萎縮を呈する場合があり,早期診断・早期治療が求められる。診断には画像検査とともに丹念な筋病理解析が必須である。ステロイド治療が第1選択であるが,難治例もあり,依然治療方針は確立しておらず今後の課題である。
脳神経内科領域におけるサルコイドーシスの画像所見
著者: 大平健司 , 横田元
ページ範囲:P.871 - P.882
サルコイドーシスは慢性の肉芽腫性炎症である。若年成人に多いとされているが,すべての年齢で発症する。肺,眼,皮膚を主におかし,神経病変は稀とされているが,剖検例においては25%に神経病変を認める。神経系では髄膜,脳神経,脳,脊髄,下垂体,末梢神経,筋肉をおかす。サルコイドーシスの所見は非特異的であるが,サルコイドーシスの本態は比較的形の揃った微小な肉芽腫とその集簇であり,画像所見もこの微細構造を反映することが多い。本論では各画像モダリティの特徴および各部位における画像所見を解説する。
神経サルコイドーシスの新しい治療
著者: 浅見麻紀 , 松永和人
ページ範囲:P.883 - P.890
神経サルコイドーシスは組織診断が行いづらく確定診断が困難である。また症例数が少ないことから,治療薬のエビデンスに乏しい。他臓器サルコイドーシスと比較し神経サルコイドーシスは治療抵抗性のことが多い。治療の主軸はステロイドであるが,二次治療としてメトトレキサートなどの免疫抑制薬や抗腫瘍壊死因子α(TNF-α)製剤など,自他覚徴候や病勢により考慮していく。
総説
神経難病の在宅医療—難病医療提供体制における在宅診療を担う医療機関の役割
著者: 三五美和 , 中村洋一
ページ範囲:P.893 - P.899
神経難病は根本的な治療方法がなくADL低下が不可避の疾患であるため,患者はなんらかの支援を受けながら長期療養を余儀なくされる。神経難病患者の望む療養生活を切れ目なく支えるために,専門医療機関と地域医療機関のネットワーク構築が進められている。本論では難病医療提供体制における在宅診療を担う医療機関の役割について,実臨床に即して概説する。
症例報告
Guillain-Barré症候群およびその亜型との鑑別を要した両側延髄内側梗塞の1例
著者: 小林聡朗 , 鈴木圭輔 , 竹川英宏 , 渡邉悠児 , 岡村穏 , 鈴木綾乃 , 津久井大介 , 平田幸一
ページ範囲:P.901 - P.905
症例は70歳男性。めまい感,ふらつきを主訴に前医へ救急搬送され,入院翌日に呼吸障害が,第3病日に弛緩性の四肢麻痺が生じ,当院へ転院となった。第1病日に前医で施行した頭部MRI検査では明らかな信号変化はなかった。数日の経過で四肢の筋力低下や呼吸不全が進行性増悪を示したことからGuillain-Barré症候群およびその亜型が鑑別となったが,第6病日の頭部MRI拡散強調画像で両側延髄内側に高信号変化を認め,両側延髄内側梗塞と診断した。進行性に四肢麻痺や呼吸障害が出現する症例では両側延髄内側梗塞を考慮する必要があり,継時的な頭部MRI検査が重要である。
乳児期に脳出血で発症した遺伝性出血性毛細血管拡張症疑いの1例
著者: 樋口直弥 , 宇田恵子 , 溝上泰一朗 , 三溝慎次 , 石黒友也 , 小宮山雅樹 , 西村真二 , 松尾宗明
ページ範囲:P.907 - P.911
遺伝性出血性毛細血管拡張症(HHT)は多臓器における多発性毛細血管拡張を特徴とする疾患である。今回,脳出血で発症した乳児でHHTの家族歴より同疾患を強く疑い,CTAで脳動静脈瘻を確認した。HHTに合併する脳動静脈瘻は年少例,出血による発症例が比較的多い。家族歴からHHTを疑う場合には,無症候例でも早期に画像スクリーニングを行うことで神経予後の向上につながる可能性がある。
書評
「Dr.セザキング直伝! 最強の医学英語学習メソッド[Web動画付]」—瀬嵜智之【著】 フリーアクセス
著者: 山本健人
ページ範囲:P.891 - P.891
『Dr.セザキング直伝! 最強の医学英語学習メソッド[Web動画付]』は,USMLEコンサルタントである「セザキング」こと瀬嵜智之医師が書き下ろした医学英語学習の教科書である。瀬嵜氏は学生時代にUSMLEのSTEP 1に最高スコアで合格し,その後も最難関とされるSTEP 2 CSを含め全STEPに一発合格。現在はUSMLEに特化したオンラインサロンを主宰し,指導した人数は1,000人を超える。
さて,ここまで読んだ方は,まさに才能あふれる超人的な男の遍歴を聞いた気になるかもしれない。だが実は「そうではない」ところが本書の最大の特徴であり,傑出した点である。まず,瀬嵜氏が「トラウマレベル」と語るほど英語が苦手だった過去を披露するところから本書は始まる。むろん,優秀な人物はすべからく謙遜が得意だ。ところが,彼の語る英語遍歴は確かに,想像以上である。高校3年生時の英語の偏差値は30台,現役時代のセンター英語は58%と6割を下回っており,二次試験にわざわざ英語の“ない”医学部を選んだ,という有様なのである。
「緩和ケアレジデントの鉄則」—西 智弘,松本禎久,森 雅紀,山口 崇,柏木秀行【編】 フリーアクセス
著者: 佐々木淳
ページ範囲:P.892 - P.892
僕が在宅医療の世界に足を踏み入れたのは2006年のこと。
医師として9年目。急性期医療に携わりながら,自分の仕事が患者さんを幸せにしているのか悩んでいた大学院生時代,偶然に在宅医療のアルバイトに出合った。人工呼吸器とともに日々をポジティブに生きる人,残された時間が長くないことを知りながらも自分の人生を振り返りながら家族との時間をいとおしむように過ごす人,病院で診てきた「患者」とは違う,「生活者」としてのその人たちの表情を見ることができた。治らない病気や障害があっても,人生の最終段階にあっても,人は最期まで幸せに生き切ることができる。医師としての価値観を揺るがされるような衝撃だった。その半年後,大学院を退学した僕は,最初の在宅療養支援診療所を開設する。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.829 - P.829
欧文目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.830 - P.830
バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.916 - P.916
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.917 - P.917
あとがき フリーアクセス
著者: 髙尾昌樹
ページ範囲:P.918 - P.918
私にとってサルコイドーシスと言えば,学生時代に習った両側肺門部リンパ節腫脹程度の知識で止まったままですし,呼吸器系のサルコイドーシスの患者さんをそれほど多く診療した経験もありません。しかし,脳神経内科という立場では,神経系サルコイドーシスはさまざまな場面で重要です。
本号は,サルコイドーシスの特集です。多くのテキストでは,「神経サルコイドーシス」ということで一括されて書かれることが多いのですが,ここでは脳,脊髄,末梢神経,筋と部位ごとに詳しく書かれています。興味のあるところだけでなく,ぜひすべてに目を通していただきたいと思います。また,画像,治療について最新の情報もまとめられています。サルコイドーシス自体,ものすごく多い疾患ではありませんが,脳に限ってみれば,髄膜炎,髄膜癌腫症,悪性リンパ腫,真菌感染などを鑑別しなければならず,診断が容易ではありません。そもそも鑑別診断のリストにサルコイドーシスを忘れてしまいそうになります。本誌を読んだ後は,サルコイドーシスを積極的に診断できるようになれると思います。
基本情報
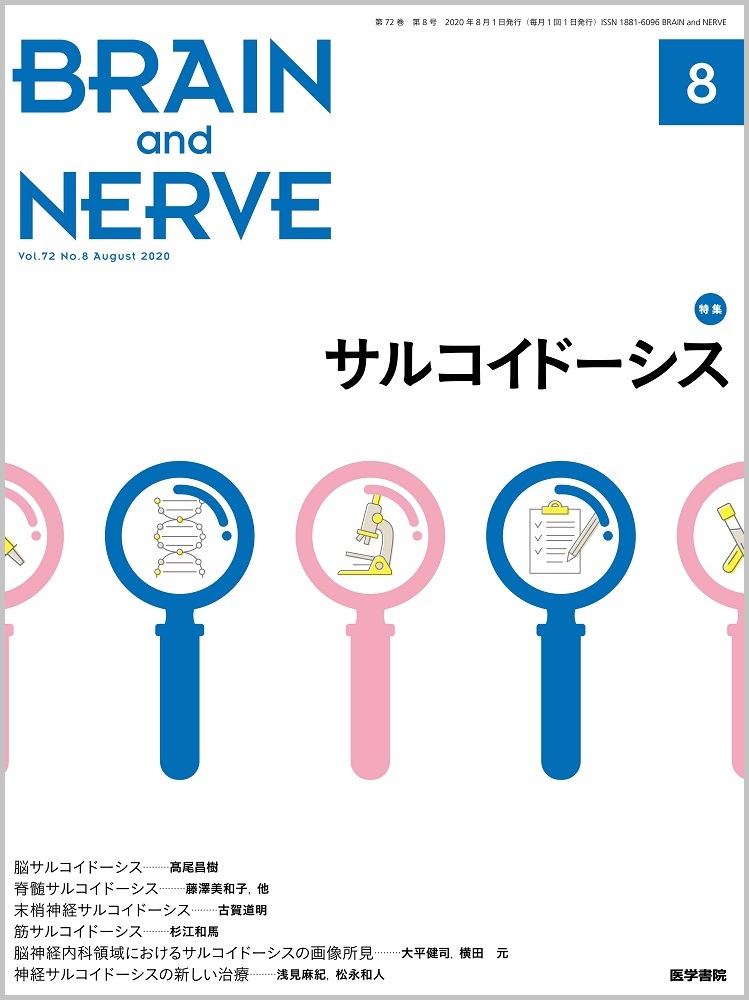
バックナンバー
76巻12号(2024年12月発行)
特集 芸術家と神経学Ⅱ
76巻11号(2024年11月発行)
特集 ALS 2024
76巻10号(2024年10月発行)
特集 どうして効くんだろう
76巻9号(2024年9月発行)
特集 治療可能な認知症としてのアルツハイマー病
76巻8号(2024年8月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である—revisited
76巻7号(2024年7月発行)
特集 ニューロ・バイオイメージング—技術と応用
76巻6号(2024年6月発行)
特集 注意と注意障害
76巻5号(2024年5月発行)
増大特集 末梢神経・筋肉の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
76巻4号(2024年4月発行)
特集 神経病理最前線
76巻3号(2024年3月発行)
特集 きちんと説明ができますか?
76巻2号(2024年2月発行)
特集 特発性正常圧水頭症の現在
76巻1号(2024年1月発行)
特集 新時代の重症筋無力症と関連疾患の診療
75巻12号(2023年12月発行)
特集 アガサ・クリスティーと神経毒
75巻11号(2023年11月発行)
特集 アロスタシス—ホメオスタシスを超えて
75巻10号(2023年10月発行)
特集 メタバースへの招待
75巻9号(2023年9月発行)
特集 妊娠と神経疾患
75巻8号(2023年8月発行)
特集 アルツハイマー病は本当に早期発見できるのか
75巻7号(2023年7月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part2 末梢編
75巻6号(2023年6月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part1 中枢編
75巻5号(2023年5月発行)
増大特集 神経・精神領域の薬剤ハンドブック
75巻4号(2023年4月発行)
特集 All About Epilepsy
75巻3号(2023年3月発行)
特集 慢性疼痛
75巻2号(2023年2月発行)
特集 多系統萎縮症の新診断基準とこれからの診療
75巻1号(2023年1月発行)
特集 よく出会う不随意運動を知る
74巻12号(2022年12月発行)
特集 映画を観て精神・神経疾患を知る
74巻11号(2022年11月発行)
特集 RFC1遺伝子関連スペクトラム障害
74巻10号(2022年10月発行)
特集 ウイルス性脳炎・脳症2022
74巻9号(2022年9月発行)
特集 動的環境への適応系としての歩行
74巻8号(2022年8月発行)
特集 迷走神経の不思議
74巻7号(2022年7月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識2022
74巻6号(2022年6月発行)
特集 脳神経内科医に求められる移行医療
74巻5号(2022年5月発行)
増大特集 次の一手—神経筋疾患難治例をどのように治療するか
74巻4号(2022年4月発行)
特集 脳科学リテラシーを高めるために
74巻3号(2022年3月発行)
特集 中枢性自律神経障害update
74巻2号(2022年2月発行)
特集 温度を感じる脳と身体の科学
74巻1号(2022年1月発行)
特集 脳神経内科医のキャリアパスとリーダーシップ
73巻12号(2021年12月発行)
特集 芸術家と神経学
73巻11号(2021年11月発行)
特集 「目」の神経学
73巻10号(2021年10月発行)
特集 中枢神経・末梢神経の悪性リンパ腫
73巻9号(2021年9月発行)
特集 脳卒中治療に必要な基礎知識
73巻8号(2021年8月発行)
特集 脳腸相関—脳-身体の双方向性制御
73巻7号(2021年7月発行)
特集 グリアと神経—相補的な制御系として
73巻6号(2021年6月発行)
特集 Lower Spine Neurology
73巻5号(2021年5月発行)
増大特集 中枢神経の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
73巻4号(2021年4月発行)
特集 片頭痛・群発頭痛治療の新たな夜明け
73巻3号(2021年3月発行)
特集 マルチリンガルブレイン
73巻2号(2021年2月発行)
特集 筋炎と壊死性筋症
73巻1号(2021年1月発行)
特集 Neuro-Oncology
72巻12号(2020年12月発行)
特集 超高齢期の精神神経疾患を診る
72巻11号(2020年11月発行)
増大特集 脳の発振現象—基礎から臨床へ
72巻10号(2020年10月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識
72巻9号(2020年9月発行)
特集 皮質性小脳萎縮症へのアプローチ
72巻8号(2020年8月発行)
特集 サルコイドーシス
72巻7号(2020年7月発行)
増大特集 神経倫理ハンドブック
72巻6号(2020年6月発行)
特集 前頭側頭葉変性症の今日的理解
72巻5号(2020年5月発行)
特集 多発性硬化症の現在と未来
72巻4号(2020年4月発行)
増大特集 神経疾患の診断における落とし穴—誤診を避けるために
72巻3号(2020年3月発行)
特集 でこぼこの脳の中でおしくらまんじゅうする脳機能
72巻2号(2020年2月発行)
特集 αシヌクレイノパチーの新たな展開
72巻1号(2020年1月発行)
特集 神経難病をクスリで治す—薬物開発の現況と近未来への展望
71巻12号(2019年12月発行)
特集 小脳と大脳—Masao Itoのレガシー
71巻11号(2019年11月発行)
増大特集 ALS2019
71巻10号(2019年10月発行)
特集 認知症と遺伝
71巻9号(2019年9月発行)
特集 神経疾患のドラッグ・リポジショニング—新時代へ
71巻8号(2019年8月発行)
特集 パーキンソン病診療の現在地—200年の変遷と新規治療
71巻7号(2019年7月発行)
増大特集 人工知能と神経科学
71巻6号(2019年6月発行)
特集 補体標的治療の現状と展望
71巻5号(2019年5月発行)
特集 NPSLE
71巻4号(2019年4月発行)
増大特集 神経学のための皮膚アトラス
71巻3号(2019年3月発行)
特集 Spine Neurology
71巻2号(2019年2月発行)
特集 “スポーツ”を生み出す脳
71巻1号(2019年1月発行)
特集 人工知能の医療応用Update
70巻12号(2018年12月発行)
特集 主訴に沿う—俯瞰し収束する画像診断の目
70巻11号(2018年11月発行)
増大特集 脳科学で解き明かす精神神経症候
70巻10号(2018年10月発行)
特集 「左脳と右脳」の現在
70巻9号(2018年9月発行)
特集 脳神経内科診療に役立つ精神科の知識
70巻8号(2018年8月発行)
特集 レヴィ小体型認知症の新知見
70巻7号(2018年7月発行)
増大特集 記憶と忘却に関わる脳のしくみ—分子機構から健忘の症候まで
70巻6号(2018年6月発行)
特集 芸術を生み出す脳
70巻5号(2018年5月発行)
特集 非アルツハイマー型認知症の病理学
70巻4号(2018年4月発行)
増大特集 Antibody Update 2018
70巻3号(2018年3月発行)
特集 『認知症疾患診療ガイドライン2017』を読み解く
70巻2号(2018年2月発行)
特集 知っておきたい神経感染症
70巻1号(2018年1月発行)
特集 筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群の今
69巻12号(2017年12月発行)
特集 運動異常症をみる—Web動画付録つき
69巻11号(2017年11月発行)
増大特集 こころの時間学の未来
69巻10号(2017年10月発行)
特集 成人てんかん—知っておきたい6つのトピック
69巻9号(2017年9月発行)
特集 ミクログリアと精神・神経疾患
69巻8号(2017年8月発行)
特集 遺伝性脊髄小脳失調症の病態と治療展望
69巻7号(2017年7月発行)
増大特集 あしたのアルツハイマー病治療
69巻6号(2017年6月発行)
特集 局在病変の神経心理学
69巻5号(2017年5月発行)
特集 Voxel-Based Morphometry—体積からわかること
69巻4号(2017年4月発行)
増大特集 ブロードマン領野の現在地
69巻3号(2017年3月発行)
特集 磁気刺激の新たな展開
69巻2号(2017年2月発行)
特集 Stroke-Like Diseases—鑑別時に注意を要する5病態
69巻1号(2017年1月発行)
特集 近年注目されている白質脳症
68巻12号(2016年12月発行)
特集 炎症性神経・筋疾患の新たな展開
68巻11号(2016年11月発行)
増大特集 連合野ハンドブック
68巻10号(2016年10月発行)
特集 アディクション—行動の嗜癖
68巻9号(2016年9月発行)
特集 自己免疫性脳炎・脳症
68巻8号(2016年8月発行)
特集 こころと汗
68巻7号(2016年7月発行)
増大特集 認知症の危険因子と防御因子
68巻6号(2016年6月発行)
特集 脳とフローラ
68巻5号(2016年5月発行)
特集 手の症候学—生理学・解剖学からみた新知見
68巻4号(2016年4月発行)
増大特集 治せる認知症
68巻3号(2016年3月発行)
特集 末梢神経の血管炎
68巻2号(2016年2月発行)
特集 筋疾患の認知機能障害
68巻1号(2016年1月発行)
特集 シャルコー・マリー・トゥース病
67巻12号(2015年12月発行)
特集 視床と高次脳機能
67巻11号(2015年11月発行)
増大特集 ギラン・バレー症候群のすべて—100年の軌跡
67巻10号(2015年10月発行)
特集 非・日常生活の脳科学
67巻9号(2015年9月発行)
特集 酵素補充療法
67巻8号(2015年8月発行)
特集 神経難病の終末期医療
67巻7号(2015年7月発行)
増大特集 神経疾患と感染症update
67巻6号(2015年6月発行)
特集 脳と「質感」
67巻5号(2015年5月発行)
特集 NCSE(非痙攣性てんかん重積状態)
67巻4号(2015年4月発行)
増大特集 大脳皮質vs.大脳白質
67巻3号(2015年3月発行)
特集 中枢神経の血管炎
67巻2号(2015年2月発行)
特集 「食べる」を考える
67巻1号(2015年1月発行)
特集 ニューロトキシコロジー
66巻12号(2014年12月発行)
特集 Orthopaedic Neurology—神経内科と整形外科の狭間で
66巻11号(2014年11月発行)
増大特集 神経症候学は神経学の“魂”である
66巻10号(2014年10月発行)
特集 分子を撃つ 神経疾患治療の新しい水平線
66巻9号(2014年9月発行)
特集 痙縮の臨床神経学
66巻8号(2014年8月発行)
特集 神経系の悪性リンパ腫update
66巻7号(2014年7月発行)
増大特集 アミロイド関連神経疾患のすべて―封入体筋炎からアルツハイマー病まで
66巻6号(2014年6月発行)
特集 ミラーニューロン
66巻5号(2014年5月発行)
特集 アセチルコリンと神経疾患―100年目の現在地
66巻4号(2014年4月発行)
増大特集 タッチ・ビジョン・アクション
66巻3号(2014年3月発行)
特集 神経筋疾患の超音波診断
66巻2号(2014年2月発行)
特集 糖尿病の神経学revisited
66巻1号(2014年1月発行)
特集 日常生活の脳科学
65巻12号(2013年12月発行)
特集 プロテイノパチーの神経病理学
65巻11号(2013年11月発行)
増大特集 Close Encounters―臨床神経学と臨床免疫学の遭遇と未来
65巻10号(2013年10月発行)
特集 神経系の発達メカニズム―最近の話題
65巻9号(2013年9月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である―現状と展望
65巻8号(2013年8月発行)
特集 こころの時間学―現在・過去・未来の起源を求めて
65巻7号(2013年7月発行)
増大特集 あしたの脳梗塞
65巻6号(2013年6月発行)
特集 見せる・仕分ける―脳機能解析の新手法
65巻5号(2013年5月発行)
特集 てんかん―新しいパースペクティブ
65巻4号(2013年4月発行)
増大特集 Antibody Update
65巻3号(2013年3月発行)
特集 次世代シーケンサーによる神経変性疾患の解析と展望
65巻2号(2013年2月発行)
特集 血液脳関門研究の進歩
65巻1号(2013年1月発行)
特集 Corticobasal Syndrome
64巻12号(2012年12月発行)
特集 The Border-Land of Dementia
64巻11号(2012年11月発行)
増大特集 痛みの神経学―末梢神経から脳まで
64巻10号(2012年10月発行)
特集 辺縁系をめぐって
64巻9号(2012年9月発行)
特集 高次脳機能イメージングの脳科学への新展開
64巻8号(2012年8月発行)
特集 線条体の基礎と臨床
64巻7号(2012年7月発行)
増大特集 顔認知の脳内機構
64巻6号(2012年6月発行)
特集 睡眠と覚醒の脳内機構
64巻5号(2012年5月発行)
特集 神経疾患のバイオマーカー
64巻4号(2012年4月発行)
増大特集 パーキンソン病の新しい側面
64巻3号(2012年3月発行)
特集 アカデミアから新規治療の実現へ―トランスレーショナルリサーチの現状
64巻2号(2012年2月発行)
特集 生物学的精神医学の進歩
64巻1号(2012年1月発行)
特集 iPS細胞と神経疾患
63巻12号(2011年12月発行)
特集 神経心理学と画像解析の融合
63巻11号(2011年11月発行)
増大特集 筋疾患update
63巻10号(2011年10月発行)
特集 緩徐進行性高次脳機能障害の病態
63巻9号(2011年9月発行)
特集 脳卒中の最新画像診断
63巻8号(2011年8月発行)
特集 日本人の発見した神経症候
63巻7号(2011年7月発行)
増大特集 神経筋接合部―基礎から臨床まで
63巻6号(2011年6月発行)
特集 ニューロパチー
63巻5号(2011年5月発行)
特集 神経系と血管内リンパ腫
63巻4号(2011年4月発行)
増大特集 てんかんの新しい治療
63巻3号(2011年3月発行)
特集 サイバーナイフ治療
63巻2号(2011年2月発行)
特集 続・日本人の発見した神経疾患
63巻1号(2011年1月発行)
特集 血管腫
62巻12号(2010年12月発行)
特集 頸部頸動脈狭窄症の診断と治療
62巻11号(2010年11月発行)
増大特集 歩行とその異常
62巻10号(2010年10月発行)
特集 ブレインバンク
62巻9号(2010年9月発行)
特集 視神経脊髄炎(NMO)update
62巻8号(2010年8月発行)
特集 辺縁系脳炎
62巻7号(2010年7月発行)
増大特集 アルツハイマー病―研究と診療の進歩
62巻6号(2010年6月発行)
特集 改正臓器移植法の問題点とその対応
62巻5号(2010年5月発行)
特集 神経画像のピットフォール―見落としと読み過ぎ
62巻4号(2010年4月発行)
特集 傍腫瘍性神経筋疾患update
62巻3号(2010年3月発行)
特集 神経回路解析法の最近の進歩
62巻2号(2010年2月発行)
特集 ニューロリハビリテーションの最前線
62巻1号(2010年1月発行)
特集 神経救急
61巻12号(2009年12月発行)
特集 Somatotopy再考
61巻11号(2009年11月発行)
特集 前頭側頭葉変性症
61巻10号(2009年10月発行)
特集 片頭痛の予防療法
61巻9号(2009年9月発行)
特集 脳血管障害治療の進歩
61巻8号(2009年8月発行)
特集 神経・筋疾患の分子標的治療
61巻7号(2009年7月発行)
特集 脳腫瘍研究の最前線―遺伝子解析から治療まで
61巻6号(2009年6月発行)
特集 脊椎・脊髄外科の最近の進歩
61巻5号(2009年5月発行)
特集 Restless legs syndrome
61巻4号(2009年4月発行)
特集 大脳基底核―分子基盤から臨床まで
61巻3号(2009年3月発行)
特集 Microneurography(微小神経電図法)の臨床応用
61巻2号(2009年2月発行)
特集 神経系の再興感染症と輸入感染症
61巻1号(2009年1月発行)
特集 脳神経倫理
60巻12号(2008年12月発行)
特集 痙縮
60巻11号(2008年11月発行)
特集 脳卒中と遺伝子
60巻10号(2008年10月発行)
特集 若年者の脳卒中
60巻9号(2008年9月発行)
特集 知・情・意の神経学
60巻8号(2008年8月発行)
特集 脳硬膜動静脈瘻
60巻7号(2008年7月発行)
増大特集 学習と記憶――基礎と臨床
60巻6号(2008年6月発行)
特集 Crow-深瀬症候群(POEMS症候群)
60巻5号(2008年5月発行)
特集 「痛み」の研究と治療の最前線
60巻4号(2008年4月発行)
増大特集 神経系の発生とその異常
60巻3号(2008年3月発行)
特集 特発性正常圧水頭症(iNPH)―最近の話題
60巻2号(2008年2月発行)
特集 がん治療と神経障害
60巻1号(2008年1月発行)
特集 日本人の発見した神経疾患
59巻12号(2007年12月発行)
特集 損傷神経の再生―温存的治療法の開発
59巻11号(2007年11月発行)
特集 手根管症候群をめぐって
59巻10号(2007年10月発行)
増大特集 ALS―研究と診療の進歩
59巻9号(2007年9月発行)
特集 パーキンソン病の認知機能障害
59巻8号(2007年8月発行)
特集 パーキンソン病の分子遺伝学―最近の知見
59巻7号(2007年7月発行)
増大特集 情報伝達処理におけるグリアの機能と異常
59巻6号(2007年6月発行)
特集 職業性神経障害の新しい展開
59巻5号(2007年5月発行)
特集 脳画像最前線
59巻4号(2007年4月発行)
増大特集 最近注目される脳神経疾患治療の研究
59巻3号(2007年3月発行)
特集 分子イメージング
59巻2号(2007年2月発行)
特集 進行性多巣性白質脳症の新しい展開―PMLが治る時代へ向けて
59巻1号(2007年1月発行)
特集 高次視覚研究の最近の進歩
