がんにおける治療法の発展は,目を見張るものがある。新しい治療法の開発も進み,生命的な予後も大きく変わりつつある。そういったなかで,免疫チェックポイント阻害薬など,まったく新しい薬物療法も導入され,いままでになかったタイプの中枢神経系の障害や末梢神経・筋障害といった副作用が生じることも明らかになっている。欧米では,脳神経内科医が“Neuro-Oncology”という形でがん治療に関わるが,わが国ではそういった関わりは限られている。今後,脳神経内科医にとって関与する機会の多くなるがん医療への興味を持っていただくための特集とした。
雑誌目次
BRAIN and NERVE-神経研究の進歩73巻1号
2021年01月発行
雑誌目次
特集 Neuro-Oncology
転移性脳腫瘍
著者: 白畑充章 , 三島一彦
ページ範囲:P.5 - P.11
転移性脳腫瘍は癌や肉腫などの悪性腫瘍が脳に転移した病態である。脳転移は容易に神経機能の悪化を招き,患者のQOLを著しく低下させる。癌の治療成績の向上に伴い,脳転移のコントロールは一段と重要性が増している。近年の放射線療法や薬物療法の発展は転移性脳腫瘍の治療にパラダイムシフトを起こしつつある。本稿では近年のさまざまな治療の進歩によって転換期にある転移性脳腫瘍の臨床像について概説する。
傍腫瘍性神経症候群(Paraneoplastic Neurological Syndrome)
著者: 古和久朋
ページ範囲:P.13 - P.20
傍腫瘍性神経障害(PNS)は腫瘍の遠隔効果により生じる神経筋障害であり,抗神経抗体が出現することから主に免疫介在性の機序により発症するものと推定されている。既に症候群として確立した古典的PNSに加えて,細胞表面上に存在するチャネルなどの膜蛋白の抗原を標的とするPNSの報告も増えつつある。PNSは関連する腫瘍に先行することがあり,PNSを鑑別に挙げることは腫瘍の早期発見,早期介入を可能性にするものであり,臨床的に重要である。
抗がん剤と神経系
著者: 福武敏夫
ページ範囲:P.21 - P.33
本論文では,伝統的な細胞毒性による化学療法や生物学的製剤および分子標的薬を含む抗がん剤治療における末梢および中枢神経系毒性の臨床的様相と部分的に治療について概観する。新規の免疫治療[免疫チェックポイント阻害薬とキメラ抗原受容体T細胞(CAR-T)治療]には触れない。化学療法の神経学的合併症は患者に強い障害を起こすが,抗がん治療を受ける患者の生存期間が長くなり,複雑なレジメンを長い治療期間にわたって受けることから,その頻度は高くなってきている。責任薬剤の中止や用量の見直しによってさらなるあるいは永続的な神経障害を避けうるので,脳神経内科医を含む臨床医は治療関連の神経毒性についてよく知るべきである。
免疫チェックポイント阻害薬による神経関連有害事象—新たな疾患概念の提唱
著者: 関守信 , 鈴木重明
ページ範囲:P.35 - P.46
免疫チェックポイント阻害薬(ICIs)による神経筋関連有害事象は稀ではあるものの時に重篤化することがあり,適切な診断,管理が重要である。髄膜脳炎,多発神経根炎,重症筋無力症,筋炎が特に重要で,これらが免疫関連有害事象として発症した場合,臨床像,経過,検査所見,治療が通常と異なることがあり,正しい理解が求められる。ICIsを中止し,ステロイド治療を行うことが推奨されており,反応性は良好である。
CAR-T細胞療法に関連する中枢神経系合併症
著者: 髙尾昌樹
ページ範囲:P.47 - P.58
キメラ抗原受容体T細胞療法(CAR-T細胞療法)は,日本においてもCD19陽性B細胞性急性リンパ芽球性白血病とびまん性大細胞型B細胞リンパ腫への適応が承認された。CAR-T投与では,サイトカイン放出症候群や,脳症,意識障害,失語,痙攣,運動麻痺,脳浮腫などさまざまな中枢神経合併症(CRES/ICANS)が生じ致命的ですらある。ここではCAR-T細胞療法の神経系合併症の全体像をまとめる。
総説
細胞膜蛋白質のプロテオタイピングに基づく中枢関門の輸送機能と破綻の分子機構
著者: 寺崎哲也
ページ範囲:P.59 - P.78
82%の脳脊髄液がくも膜下腔に存在するが,くも膜上皮細胞の働きは不明であった。この細胞は血液脳関門と同じ薬物排出輸送担体と血液脳関門や血液脳脊髄液関門や血液脊髄関門と異なる種々の輸送担体を大量に発現する。輸送活性は大きく,血液くも膜関門は極めて重要な役割を果たす。定量プロテオミクスの手法を用いて4つの中枢関門の輸送特性と密着結合の違いを概説する。さらに,病態時の関門破綻の分子機構に関する仮説を紹介する。
原著
マンガの文脈による心的状態を反映した脳活動
著者: 八木橋正泰 , 酒井邦嘉
ページ範囲:P.79 - P.87
文脈の効果は言語に限らず視覚でも生じると考えられるが,関与する脳領域は不明である。本研究では,サイレントマンガを用いて視覚刺激のみで誘起される心的状態に着目した。見開きの状態で文脈を保ちながら読む際に両側の視覚野と小脳で有意な活動が見られ,文脈を損なうページの単独提示との直接比較では,活動部位が半側空間無視の責任病巣とほぼ一致した。以上の結果は,高次視覚情報処理が文脈によって促進されることを示唆する。
症例報告
家族性地中海熱に併発し,頭蓋内出血で発症し,その後自然消退したレンズ核線条体動脈瘤の1例
著者: 中崎明日香 , 杉山拓 , 舘澤諒大 , 河野洋之 , 森島穣 , 長内俊也 , 中山若樹 , 数又研
ページ範囲:P.89 - P.93
家族性地中海熱に併発した,レンズ核線条体動脈瘤の稀な1例を経験した。本症に対する外科的治療介入の必要性に関しても文献的考察を加え報告する。症例は家族性地中海熱にて加療中の45歳女性であり,突然の頭痛,めまいを発症し,右尾状核と側脳室内に出血を認めた。脳血管精査で内側レンズ核線条体動脈遠位部に紡錘状動脈瘤を認め,出血源と考えられた。慎重な経過観察にて,動脈瘤は経時的に縮小し,消退が確認された。
連載 臨床神経学プロムナード—60余年を顧みて【新連載】
緒言
著者: 平山惠造
ページ範囲:P.94 - P.96
顧みると,筆者が医学部(旧制)卒業後,当時の制度で1年間のインターンを終えて,冲中内科(東京大学第三内科)に入局したのは1955年であった。病棟での内科学全般について2年間の実地教育(いわゆる病棟勤務)を受けた後,冲中重雄教授から学位研究の課題として「筋萎縮性側索硬化症」が与えられた(1957年)。病棟担当と並行して研究室での研究に取り組むとともに,さらに週1回の「神経外来」に加わり,神経疾患に広く接するようになった。「若年性一側上肢筋萎縮症(のちの平山病)」を診る機会を得たのはこの神経外来であった。
しかし,この頃,日本には「神経学会」はなかった。「神経」に関する学会発表はもっぱら「日本精神神経学会」であった。それには歴史的背景があった。過去において,実は「日本神経学会」が呉秀三(精神科),三浦謹之助(内科)によって設立されたことがあった(1902年)。しかし,その後「精神病」も神経器官の機能障害であるから「精神病」と「神経病」の境はないとして,精神医学の会員が増加し,「日本神経学会」の主流を占めるようになり,1935年に学会の名称が「日本精神神経学会」へと変更されるに至った。この影響は大きく,学会内における「神経学」の存在が徐々に稀薄になり,神経学(臨床,研究)に携わる「内科系」の人々から「神経学」を主体とする学会の設立を要望する気運が高まっていった。上に述べたように筆者が冲中教授から「神経学」の研究を指示されたのがこの頃であった(1957年)。
書評
「《ジェネラリストBOOKS》子どものけいれん&頭痛診療」—二木良夫【著】 フリーアクセス
著者: 児玉和彦
ページ範囲:P.97 - P.97
私は,子どもの診療が得意な総合診療医として,小児診療と総合診療の両分野でお仕事をさせていただいています。数年前,小児の稀な疾患についての症例カンファレンスをする機会をいただいたときに,最初の数分で見事な推論から一発診断をしたのが二木良夫先生でした。本書は,「けいれん」と 「頭痛」 について,米国小児神経科専門医でもある二木先生のあふれんばかりの情熱と,整理された知識と経験が詰め込まれた良書です。
子どもの「けいれん」は,小児科医にとってはコモンディジーズですが,総合診療医としては対処に悩むテーマです。熱性けいれんの対応に自信を持つには,本書にあるフローチャートを見るとよいです。熱性けいれんの子どもを持つ親御さんからのさまざまな質問に答えるためのエビデンスに基づいた説明例が記載されているのも,初学者には親切です。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.1 - P.1
欧文目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.2 - P.2
バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.102 - P.102
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.103 - P.103
あとがき フリーアクセス
著者: 三村將
ページ範囲:P.104 - P.104
2020年11月23日に私にとって大変思い出の深い患者さんが亡くなった。享年62歳,胆管癌であった。彼女は私が米国留学から帰国して東京歯科大学市川総合病院に勤務していた頃,横浜市立市民病院の田辺英先生からの紹介で,精査のために転入院となった方である。30代半ばで発症したヘルペス脳炎で,急性期を過ぎたのち,比較的軽度の前向健忘とともに著明な逆向性健忘が残存していた。この患者さんの症例報告を本誌の前身である『脳と神経』に報告している1)。主なポイントは,顕著な逆向性健忘を呈してはいたが,その中核は極めて個人的なエピソードである自叙伝的記憶の障害であり,一方で社会的出来事(ニュースなど)や個人的意味記憶(担任の先生の名前など)は比較的保たれていた点である。同じく著しい逆向性健忘を示すアルコール性コルサコフ症候群とはパターンが違っていて,これを右海馬の病変に伴う過去の事象に関する視覚情報処理や視覚イメージ想起の低下と関連付けて考えた。
基本情報
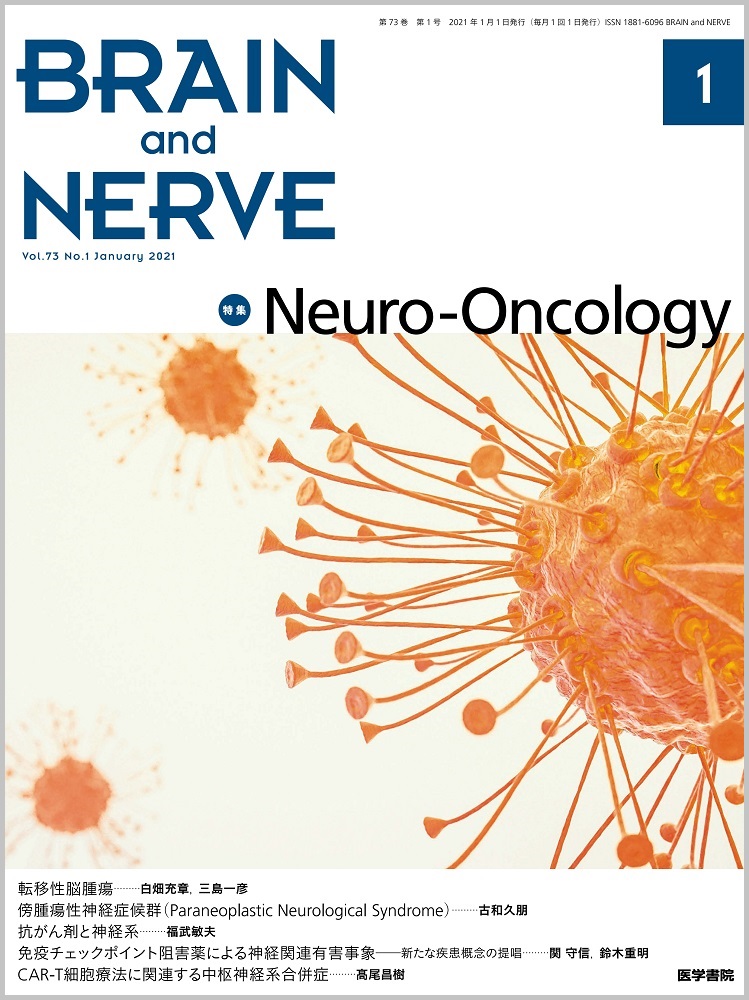
バックナンバー
76巻12号(2024年12月発行)
特集 芸術家と神経学Ⅱ
76巻11号(2024年11月発行)
特集 ALS 2024
76巻10号(2024年10月発行)
特集 どうして効くんだろう
76巻9号(2024年9月発行)
特集 治療可能な認知症としてのアルツハイマー病
76巻8号(2024年8月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である—revisited
76巻7号(2024年7月発行)
特集 ニューロ・バイオイメージング—技術と応用
76巻6号(2024年6月発行)
特集 注意と注意障害
76巻5号(2024年5月発行)
増大特集 末梢神経・筋肉の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
76巻4号(2024年4月発行)
特集 神経病理最前線
76巻3号(2024年3月発行)
特集 きちんと説明ができますか?
76巻2号(2024年2月発行)
特集 特発性正常圧水頭症の現在
76巻1号(2024年1月発行)
特集 新時代の重症筋無力症と関連疾患の診療
75巻12号(2023年12月発行)
特集 アガサ・クリスティーと神経毒
75巻11号(2023年11月発行)
特集 アロスタシス—ホメオスタシスを超えて
75巻10号(2023年10月発行)
特集 メタバースへの招待
75巻9号(2023年9月発行)
特集 妊娠と神経疾患
75巻8号(2023年8月発行)
特集 アルツハイマー病は本当に早期発見できるのか
75巻7号(2023年7月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part2 末梢編
75巻6号(2023年6月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part1 中枢編
75巻5号(2023年5月発行)
増大特集 神経・精神領域の薬剤ハンドブック
75巻4号(2023年4月発行)
特集 All About Epilepsy
75巻3号(2023年3月発行)
特集 慢性疼痛
75巻2号(2023年2月発行)
特集 多系統萎縮症の新診断基準とこれからの診療
75巻1号(2023年1月発行)
特集 よく出会う不随意運動を知る
74巻12号(2022年12月発行)
特集 映画を観て精神・神経疾患を知る
74巻11号(2022年11月発行)
特集 RFC1遺伝子関連スペクトラム障害
74巻10号(2022年10月発行)
特集 ウイルス性脳炎・脳症2022
74巻9号(2022年9月発行)
特集 動的環境への適応系としての歩行
74巻8号(2022年8月発行)
特集 迷走神経の不思議
74巻7号(2022年7月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識2022
74巻6号(2022年6月発行)
特集 脳神経内科医に求められる移行医療
74巻5号(2022年5月発行)
増大特集 次の一手—神経筋疾患難治例をどのように治療するか
74巻4号(2022年4月発行)
特集 脳科学リテラシーを高めるために
74巻3号(2022年3月発行)
特集 中枢性自律神経障害update
74巻2号(2022年2月発行)
特集 温度を感じる脳と身体の科学
74巻1号(2022年1月発行)
特集 脳神経内科医のキャリアパスとリーダーシップ
73巻12号(2021年12月発行)
特集 芸術家と神経学
73巻11号(2021年11月発行)
特集 「目」の神経学
73巻10号(2021年10月発行)
特集 中枢神経・末梢神経の悪性リンパ腫
73巻9号(2021年9月発行)
特集 脳卒中治療に必要な基礎知識
73巻8号(2021年8月発行)
特集 脳腸相関—脳-身体の双方向性制御
73巻7号(2021年7月発行)
特集 グリアと神経—相補的な制御系として
73巻6号(2021年6月発行)
特集 Lower Spine Neurology
73巻5号(2021年5月発行)
増大特集 中枢神経の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
73巻4号(2021年4月発行)
特集 片頭痛・群発頭痛治療の新たな夜明け
73巻3号(2021年3月発行)
特集 マルチリンガルブレイン
73巻2号(2021年2月発行)
特集 筋炎と壊死性筋症
73巻1号(2021年1月発行)
特集 Neuro-Oncology
72巻12号(2020年12月発行)
特集 超高齢期の精神神経疾患を診る
72巻11号(2020年11月発行)
増大特集 脳の発振現象—基礎から臨床へ
72巻10号(2020年10月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識
72巻9号(2020年9月発行)
特集 皮質性小脳萎縮症へのアプローチ
72巻8号(2020年8月発行)
特集 サルコイドーシス
72巻7号(2020年7月発行)
増大特集 神経倫理ハンドブック
72巻6号(2020年6月発行)
特集 前頭側頭葉変性症の今日的理解
72巻5号(2020年5月発行)
特集 多発性硬化症の現在と未来
72巻4号(2020年4月発行)
増大特集 神経疾患の診断における落とし穴—誤診を避けるために
72巻3号(2020年3月発行)
特集 でこぼこの脳の中でおしくらまんじゅうする脳機能
72巻2号(2020年2月発行)
特集 αシヌクレイノパチーの新たな展開
72巻1号(2020年1月発行)
特集 神経難病をクスリで治す—薬物開発の現況と近未来への展望
71巻12号(2019年12月発行)
特集 小脳と大脳—Masao Itoのレガシー
71巻11号(2019年11月発行)
増大特集 ALS2019
71巻10号(2019年10月発行)
特集 認知症と遺伝
71巻9号(2019年9月発行)
特集 神経疾患のドラッグ・リポジショニング—新時代へ
71巻8号(2019年8月発行)
特集 パーキンソン病診療の現在地—200年の変遷と新規治療
71巻7号(2019年7月発行)
増大特集 人工知能と神経科学
71巻6号(2019年6月発行)
特集 補体標的治療の現状と展望
71巻5号(2019年5月発行)
特集 NPSLE
71巻4号(2019年4月発行)
増大特集 神経学のための皮膚アトラス
71巻3号(2019年3月発行)
特集 Spine Neurology
71巻2号(2019年2月発行)
特集 “スポーツ”を生み出す脳
71巻1号(2019年1月発行)
特集 人工知能の医療応用Update
70巻12号(2018年12月発行)
特集 主訴に沿う—俯瞰し収束する画像診断の目
70巻11号(2018年11月発行)
増大特集 脳科学で解き明かす精神神経症候
70巻10号(2018年10月発行)
特集 「左脳と右脳」の現在
70巻9号(2018年9月発行)
特集 脳神経内科診療に役立つ精神科の知識
70巻8号(2018年8月発行)
特集 レヴィ小体型認知症の新知見
70巻7号(2018年7月発行)
増大特集 記憶と忘却に関わる脳のしくみ—分子機構から健忘の症候まで
70巻6号(2018年6月発行)
特集 芸術を生み出す脳
70巻5号(2018年5月発行)
特集 非アルツハイマー型認知症の病理学
70巻4号(2018年4月発行)
増大特集 Antibody Update 2018
70巻3号(2018年3月発行)
特集 『認知症疾患診療ガイドライン2017』を読み解く
70巻2号(2018年2月発行)
特集 知っておきたい神経感染症
70巻1号(2018年1月発行)
特集 筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群の今
69巻12号(2017年12月発行)
特集 運動異常症をみる—Web動画付録つき
69巻11号(2017年11月発行)
増大特集 こころの時間学の未来
69巻10号(2017年10月発行)
特集 成人てんかん—知っておきたい6つのトピック
69巻9号(2017年9月発行)
特集 ミクログリアと精神・神経疾患
69巻8号(2017年8月発行)
特集 遺伝性脊髄小脳失調症の病態と治療展望
69巻7号(2017年7月発行)
増大特集 あしたのアルツハイマー病治療
69巻6号(2017年6月発行)
特集 局在病変の神経心理学
69巻5号(2017年5月発行)
特集 Voxel-Based Morphometry—体積からわかること
69巻4号(2017年4月発行)
増大特集 ブロードマン領野の現在地
69巻3号(2017年3月発行)
特集 磁気刺激の新たな展開
69巻2号(2017年2月発行)
特集 Stroke-Like Diseases—鑑別時に注意を要する5病態
69巻1号(2017年1月発行)
特集 近年注目されている白質脳症
68巻12号(2016年12月発行)
特集 炎症性神経・筋疾患の新たな展開
68巻11号(2016年11月発行)
増大特集 連合野ハンドブック
68巻10号(2016年10月発行)
特集 アディクション—行動の嗜癖
68巻9号(2016年9月発行)
特集 自己免疫性脳炎・脳症
68巻8号(2016年8月発行)
特集 こころと汗
68巻7号(2016年7月発行)
増大特集 認知症の危険因子と防御因子
68巻6号(2016年6月発行)
特集 脳とフローラ
68巻5号(2016年5月発行)
特集 手の症候学—生理学・解剖学からみた新知見
68巻4号(2016年4月発行)
増大特集 治せる認知症
68巻3号(2016年3月発行)
特集 末梢神経の血管炎
68巻2号(2016年2月発行)
特集 筋疾患の認知機能障害
68巻1号(2016年1月発行)
特集 シャルコー・マリー・トゥース病
67巻12号(2015年12月発行)
特集 視床と高次脳機能
67巻11号(2015年11月発行)
増大特集 ギラン・バレー症候群のすべて—100年の軌跡
67巻10号(2015年10月発行)
特集 非・日常生活の脳科学
67巻9号(2015年9月発行)
特集 酵素補充療法
67巻8号(2015年8月発行)
特集 神経難病の終末期医療
67巻7号(2015年7月発行)
増大特集 神経疾患と感染症update
67巻6号(2015年6月発行)
特集 脳と「質感」
67巻5号(2015年5月発行)
特集 NCSE(非痙攣性てんかん重積状態)
67巻4号(2015年4月発行)
増大特集 大脳皮質vs.大脳白質
67巻3号(2015年3月発行)
特集 中枢神経の血管炎
67巻2号(2015年2月発行)
特集 「食べる」を考える
67巻1号(2015年1月発行)
特集 ニューロトキシコロジー
66巻12号(2014年12月発行)
特集 Orthopaedic Neurology—神経内科と整形外科の狭間で
66巻11号(2014年11月発行)
増大特集 神経症候学は神経学の“魂”である
66巻10号(2014年10月発行)
特集 分子を撃つ 神経疾患治療の新しい水平線
66巻9号(2014年9月発行)
特集 痙縮の臨床神経学
66巻8号(2014年8月発行)
特集 神経系の悪性リンパ腫update
66巻7号(2014年7月発行)
増大特集 アミロイド関連神経疾患のすべて―封入体筋炎からアルツハイマー病まで
66巻6号(2014年6月発行)
特集 ミラーニューロン
66巻5号(2014年5月発行)
特集 アセチルコリンと神経疾患―100年目の現在地
66巻4号(2014年4月発行)
増大特集 タッチ・ビジョン・アクション
66巻3号(2014年3月発行)
特集 神経筋疾患の超音波診断
66巻2号(2014年2月発行)
特集 糖尿病の神経学revisited
66巻1号(2014年1月発行)
特集 日常生活の脳科学
65巻12号(2013年12月発行)
特集 プロテイノパチーの神経病理学
65巻11号(2013年11月発行)
増大特集 Close Encounters―臨床神経学と臨床免疫学の遭遇と未来
65巻10号(2013年10月発行)
特集 神経系の発達メカニズム―最近の話題
65巻9号(2013年9月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である―現状と展望
65巻8号(2013年8月発行)
特集 こころの時間学―現在・過去・未来の起源を求めて
65巻7号(2013年7月発行)
増大特集 あしたの脳梗塞
65巻6号(2013年6月発行)
特集 見せる・仕分ける―脳機能解析の新手法
65巻5号(2013年5月発行)
特集 てんかん―新しいパースペクティブ
65巻4号(2013年4月発行)
増大特集 Antibody Update
65巻3号(2013年3月発行)
特集 次世代シーケンサーによる神経変性疾患の解析と展望
65巻2号(2013年2月発行)
特集 血液脳関門研究の進歩
65巻1号(2013年1月発行)
特集 Corticobasal Syndrome
64巻12号(2012年12月発行)
特集 The Border-Land of Dementia
64巻11号(2012年11月発行)
増大特集 痛みの神経学―末梢神経から脳まで
64巻10号(2012年10月発行)
特集 辺縁系をめぐって
64巻9号(2012年9月発行)
特集 高次脳機能イメージングの脳科学への新展開
64巻8号(2012年8月発行)
特集 線条体の基礎と臨床
64巻7号(2012年7月発行)
増大特集 顔認知の脳内機構
64巻6号(2012年6月発行)
特集 睡眠と覚醒の脳内機構
64巻5号(2012年5月発行)
特集 神経疾患のバイオマーカー
64巻4号(2012年4月発行)
増大特集 パーキンソン病の新しい側面
64巻3号(2012年3月発行)
特集 アカデミアから新規治療の実現へ―トランスレーショナルリサーチの現状
64巻2号(2012年2月発行)
特集 生物学的精神医学の進歩
64巻1号(2012年1月発行)
特集 iPS細胞と神経疾患
63巻12号(2011年12月発行)
特集 神経心理学と画像解析の融合
63巻11号(2011年11月発行)
増大特集 筋疾患update
63巻10号(2011年10月発行)
特集 緩徐進行性高次脳機能障害の病態
63巻9号(2011年9月発行)
特集 脳卒中の最新画像診断
63巻8号(2011年8月発行)
特集 日本人の発見した神経症候
63巻7号(2011年7月発行)
増大特集 神経筋接合部―基礎から臨床まで
63巻6号(2011年6月発行)
特集 ニューロパチー
63巻5号(2011年5月発行)
特集 神経系と血管内リンパ腫
63巻4号(2011年4月発行)
増大特集 てんかんの新しい治療
63巻3号(2011年3月発行)
特集 サイバーナイフ治療
63巻2号(2011年2月発行)
特集 続・日本人の発見した神経疾患
63巻1号(2011年1月発行)
特集 血管腫
62巻12号(2010年12月発行)
特集 頸部頸動脈狭窄症の診断と治療
62巻11号(2010年11月発行)
増大特集 歩行とその異常
62巻10号(2010年10月発行)
特集 ブレインバンク
62巻9号(2010年9月発行)
特集 視神経脊髄炎(NMO)update
62巻8号(2010年8月発行)
特集 辺縁系脳炎
62巻7号(2010年7月発行)
増大特集 アルツハイマー病―研究と診療の進歩
62巻6号(2010年6月発行)
特集 改正臓器移植法の問題点とその対応
62巻5号(2010年5月発行)
特集 神経画像のピットフォール―見落としと読み過ぎ
62巻4号(2010年4月発行)
特集 傍腫瘍性神経筋疾患update
62巻3号(2010年3月発行)
特集 神経回路解析法の最近の進歩
62巻2号(2010年2月発行)
特集 ニューロリハビリテーションの最前線
62巻1号(2010年1月発行)
特集 神経救急
61巻12号(2009年12月発行)
特集 Somatotopy再考
61巻11号(2009年11月発行)
特集 前頭側頭葉変性症
61巻10号(2009年10月発行)
特集 片頭痛の予防療法
61巻9号(2009年9月発行)
特集 脳血管障害治療の進歩
61巻8号(2009年8月発行)
特集 神経・筋疾患の分子標的治療
61巻7号(2009年7月発行)
特集 脳腫瘍研究の最前線―遺伝子解析から治療まで
61巻6号(2009年6月発行)
特集 脊椎・脊髄外科の最近の進歩
61巻5号(2009年5月発行)
特集 Restless legs syndrome
61巻4号(2009年4月発行)
特集 大脳基底核―分子基盤から臨床まで
61巻3号(2009年3月発行)
特集 Microneurography(微小神経電図法)の臨床応用
61巻2号(2009年2月発行)
特集 神経系の再興感染症と輸入感染症
61巻1号(2009年1月発行)
特集 脳神経倫理
60巻12号(2008年12月発行)
特集 痙縮
60巻11号(2008年11月発行)
特集 脳卒中と遺伝子
60巻10号(2008年10月発行)
特集 若年者の脳卒中
60巻9号(2008年9月発行)
特集 知・情・意の神経学
60巻8号(2008年8月発行)
特集 脳硬膜動静脈瘻
60巻7号(2008年7月発行)
増大特集 学習と記憶――基礎と臨床
60巻6号(2008年6月発行)
特集 Crow-深瀬症候群(POEMS症候群)
60巻5号(2008年5月発行)
特集 「痛み」の研究と治療の最前線
60巻4号(2008年4月発行)
増大特集 神経系の発生とその異常
60巻3号(2008年3月発行)
特集 特発性正常圧水頭症(iNPH)―最近の話題
60巻2号(2008年2月発行)
特集 がん治療と神経障害
60巻1号(2008年1月発行)
特集 日本人の発見した神経疾患
59巻12号(2007年12月発行)
特集 損傷神経の再生―温存的治療法の開発
59巻11号(2007年11月発行)
特集 手根管症候群をめぐって
59巻10号(2007年10月発行)
増大特集 ALS―研究と診療の進歩
59巻9号(2007年9月発行)
特集 パーキンソン病の認知機能障害
59巻8号(2007年8月発行)
特集 パーキンソン病の分子遺伝学―最近の知見
59巻7号(2007年7月発行)
増大特集 情報伝達処理におけるグリアの機能と異常
59巻6号(2007年6月発行)
特集 職業性神経障害の新しい展開
59巻5号(2007年5月発行)
特集 脳画像最前線
59巻4号(2007年4月発行)
増大特集 最近注目される脳神経疾患治療の研究
59巻3号(2007年3月発行)
特集 分子イメージング
59巻2号(2007年2月発行)
特集 進行性多巣性白質脳症の新しい展開―PMLが治る時代へ向けて
59巻1号(2007年1月発行)
特集 高次視覚研究の最近の進歩
