2014年に本誌で「神経系の悪性リンパ腫update」の特集を行ってから既に7年の時が経過した。いまもなお診断に苦慮することの多い疾患ではあるものの,この間に画像検査や遺伝子解析をはじめとする診断技術の発展があり,また,鑑別診断に有用な多くの所見が蓄積されてきている。治療面では,抗体医薬やBTK阻害薬といった新薬の開発に伴いレジメンが追加されるなど選択肢が広がっており,患者属性に応じた介入が可能となった。本特集をとおして中枢神経・末梢神経のリンパ腫に関する知識をアップデートし,脳神経内科医としてどのようにこの難治性疾患に対峙していくかを考える基礎をつくっていただきたい。
雑誌目次
BRAIN and NERVE-神経研究の進歩73巻10号
2021年10月発行
雑誌目次
特集 中枢神経・末梢神経の悪性リンパ腫
中枢神経系原発悪性リンパ腫—脳神経内科医はどのように向かい合うべきか
著者: 西澤正豊
ページ範囲:P.1067 - P.1074
中枢神経系原発悪性リンパ腫に脳神経内科医はいかに向かい合うべきか,前回の本誌特集からの7年間を踏まえて再考する。診療面で最大の進歩は,リキッドバイオプシー試料を用いたゲノム解析手法の進歩にあり,リアルタイムで腫瘍細胞の動態や治療反応性の解析,新規クローンの早期発見を可能としてきた。しかし,脳神経内科医の役割は依然,診断・治療に直接関わることではなく,早期診断して専門治療チームに委ねることにある。
がん診療における脳神経内科医の役割
著者: 髙尾昌樹
ページ範囲:P.1075 - P.1078
がん治療における脳神経内科医の役割は重要である。Neuro-onclogyは,神経系の原発性腫瘍だけでなく,がんに関連する神経症状,治療に伴う神経症状などに広く関わる新しい分野である。日本においても,脳神経内科医が積極的にがん診療に関わるべきであり,Neuro-oncologistとしての脳神経内科医の育成が必要である。がん患者数の増加とともに,その重要性もますます増えると思われる。
中枢神経系原発悪性リンパ腫—画像診断のポイント
著者: 太田義明
ページ範囲:P.1079 - P.1086
中枢神経系原発悪性リンパ腫(PCNSL)は,脳腫瘍の1〜5%を占めており,CTやMRIなどの従来の画像診断で病変を特定することができる。しかし,グリオーマ,感染症(進行性多巣性白質脳症,トキソプラズマ症),脱髄性疾患(多発性硬化症)などの他の疾患で見られるような非典型的な所見を示す病変の場合,鑑別診断は困難となる。本論では,従来型のCTやMRIとPET-CTを含むadvanced imagingからPCNSLを他の疾患と区別するための画像所見や,予後因子,治療効果,遺伝子変異などの他の特徴を検出するのに役立つ所見を提示する。
血管内大細胞型B細胞リンパ腫(IVLBCL)
著者: 小田真司 , 髙尾昌樹
ページ範囲:P.1087 - P.1097
血管内大細胞型B細胞リンパ腫は節外性B細胞リンパ腫の一型であり,腫瘍細胞が細小血管内で選択的に増殖することを特徴とする疾患である。多様かつ非特異的な症状を呈することから診断に難渋することが多く,いかに本疾患を鑑別に挙げてランダム皮膚生検をはじめとする組織診断を行うかが診断のカギとなる。治療の進歩により早期診断の重要性が高まっているが,病態や機序にはいまだ不明な点も多く,今後の知見の蓄積がまたれる。
末梢神経・筋の悪性リンパ腫
著者: 佐藤亮太
ページ範囲:P.1099 - P.1106
病理診断がリンパ腫の診断の主軸をなすことには変わりないが,遺伝子解析が重要視されつつある。末梢神経・筋のリンパ腫例で臨床データと遺伝子プロファイルの関係を明らかにしていくことができれば,病理診断が困難な症例であっても,遺伝子プロファイルに基づいた診断が可能となる。本論では,リンパ腫浸潤の病態,臨床症状,検査所見について概説し,リンパ腫診断に有用な検査や新たな遺伝子解析の手法について解説する。
中枢神経系原発悪性リンパ腫の治療—2019ガイドラインから
著者: 佐々木重嘉 , 永根基雄
ページ範囲:P.1107 - P.1114
中枢神経系原発悪性リンパ腫の治療として,まず腫瘍の縮小を目的とする寛解導入療法が行われ,その後再発予防を目的とする地固め療法が行われる。治療抵抗例や再発時は二次治療が行われる。寛解導入療法の標準治療はメトトレキサート基盤多剤併用化学療法であり,放射線治療は高齢者を中心に回避や減量が検討される。保険適用下に使用可能となったチラブルチニブや自家幹細胞移植支援大量化学療法の位置付けについて,引き続き検討が望まれる。
総説
三次元組織透明化・染色による神経科学研究の現状と未来への展望
著者: 上田泰己
ページ範囲:P.1117 - P.1137
最先端の組織透明化法は,哺乳類の個々の臓器や体全体のインタクトな組織の細胞解像度の情報を提供する。組織透明化法に光シート顕微鏡による高速撮像と画像解析の自動化とが組み合わさることで,組織検査のコストが削減され,スピードが数桁向上する。さらに,組織透明化の化学は,全臓器の抗体標識を可能にし,厚いヒト組織にも適用可能にする。強力な透明化,標識,イメージング,データ解析を組み合わせることで,科学者たちは,複雑な哺乳類の体や大型のヒト標本の構造的,機能的な細胞情報を加速度的に抽出している。さらに,テラバイト規模のイメージングデータの急速な生成は,大規模データの解析と管理の課題に取り組む効率的な計算アプローチへの高い需要を生み出す。本総説では,組織透明化法が哺乳類の体やヒト標本の偏りのないシステムレベルの俯瞰像をどのようにして提供し得るかを議論し,組織透明化のヒトの神経科学への応用における現在の課題と将来の展望について議論する。
身体症状症および類縁病態の概念と治療戦略
著者: 眞島裕樹
ページ範囲:P.1139 - P.1147
身体症状へのとらわれの疾患である身体症状症,および類縁病態の背景には,さまざまな心理的機序が存在し,治療には精神科的視点が必要である。しかし,当該患者は非精神科を受診し,精神科への紹介は工夫が必要である。紹介が難しい場合であっても,支持的な対応や治療の継続性は重要である。薬物療法の効果は限定的であり,効果的とされる認知行動療法や精神分析的精神療法の適応も容易ではないが,森田療法は比較的施行しやすい。
症例報告
頭蓋外で起始した後下小脳動脈が頭蓋外窓形成部未破裂囊状脳動脈瘤を伴った1例
著者: 太田浩嗣 , 近藤弘久 , 梅村武部 , 山本淳考
ページ範囲:P.1149 - P.1154
後下小脳動脈遠位部の窓形成に脳動脈瘤を認めたものは稀で,脳動脈瘤および後下小脳動脈起始部が頭蓋外に位置していたものは,過去に報告はなかった。症例は71歳女性。突発性難聴の精査目的で,MRI上後下小脳動脈窓形成部に囊状未破裂脳動脈瘤を認めたが,サイズも小さく,無症候性のため経過観察している。後下小脳動脈が窓形成を含め特異的な走行を呈したことから,脳動脈瘤の成因として血行力学的ストレスとともに,血管形成不全の関与も考えられた。
現代神経科学の源流・15
ノーム・チョムスキー【Ⅲ】
著者: 福井直樹 , 酒井邦嘉
ページ範囲:P.1155 - P.1162
構造主義との決別
酒井 さて,ハーバード大学に移ったチョムスキーは,まず何に着手したのでしょう。
福井 その同じ年に,修士論文の最後の改訂をやっています。その改訂では,バー=ヒレル(Yehoshua Bar-Hillel;1915-1975)やハレに会ってヒントを得ました。昔のヘブライ語には現れているけれども,現在のヘブライ語には現れていないものを,「基底形式」という抽象的な形式で設定すれば,現在のヘブライ語の形をうまく説明できるのではないか,というのが『現代ヘブライ語の形態音素論』(1951)(以下,『形態音素論』)の内容です。それはまさに,チョムスキーが10歳の頃に思いついた規則性と同じだった。歴史的な変化を,抽象的な派生過程として現代ヘブライ語の文法に組み入れることによって,最後の改訂が一気にうまくいったわけです。
連載 脳神経内科領域における医学教育の展望—Post/withコロナ時代を見据えて・2
現代の指導医に求められる「支援者的」臨床教育アプローチ
著者: 西城卓也 , 今福輪太郎
ページ範囲:P.1164 - P.1167
はじめに
2020年に始まる新型コロナウイルス感染症(coronavirus disease 2019:COVID-19)のパンデミックは,医学教育の歴史にとってもターニングポイントになり得る衝撃的な出来事です。医療における教育の従来のアプローチは,大きく揺さぶりをかけられICTによる代替・増強・変容・再定義(SAMRモデル)1)により適応することを余儀なくされています。わが国におけるe-learningの導入の必要性は以前から議論されていましたが,いまだかつてこのレベルまで注目されることはありませんでした。今後の5年で,過去20年とは比較にならないほどの大きな変容が起こるでしょう。本稿では,現代の臨床教育に必要な経験学習サイクルの理論と具体例,それに加えてPost/with COVID-19時代に求められる経験学習サイクルを可能な限り占うことを試みたいと思います。
スペシャリストが薦める読んでおくべき名著—ニューロサイエンスを志す人のために・2
統合失調症のモデル動物で検証すべきこの疾患の本質とは何か
著者: 加藤忠史
ページ範囲:P.1168 - P.1169
神経科学領域では,最近,精神疾患の動物モデルの研究が盛んになってきた。
最初のブレークスルーとなったのは,おそらく自閉症のモデルマウス(Nakatani et al, Cell, 2009)だったと思われる。このモデルマウスにおいては,自閉症で最も多く見られる染色体異常である15q11-13をマウスで再現したうえ,行動解析により,当時自閉症の3主徴とされていた,「社会行動の異常」「こだわり」「コミュニケーションの障害」を示した点が画期的であった。現在では,疾患名は自閉スペクトラム症となり,診断基準のまとめ方も,「社会的コミュニケーションおよび対人的相互反応における障害」および「限定された興味」の2つに変わったが,このモデルが疾患の本質を捉えていたことは間違いなく,自閉症という,それまで動物で再現することは難しいと思われた疾患のモデルマウスの作製が可能であるということを示した点で意義があった。
臨床神経学プロムナード—60余年を顧みて・8
上位運動ニューロンは錐体路のみではない—皮質脊髄路,皮質核路(迷行線維)の理解を深める
著者: 平山惠造
ページ範囲:P.1170 - P.1171
先ず,大綱から述べよう。(1)錐体路pyramidal tractとは延髄の錐体pyramisをまとまって通る神経線維群を指す。(2)皮質脊髄路cortico-spinal tractとは大脳運動皮質から脊髄前角へ向う運動神経系の線維集団で,中心前回の上・中部と中心傍小葉前部(即ち四肢運動領域)から脊髄へ下行する運動神経線維群である。(3)皮質核路cortico-nuclear tractの核とは脳神経核を意味するもので(但しⅠ,Ⅱ脳神経核は特異で,これを除く),Ⅲ以下の脳神経核に向う(即ち脊髄に向わない)神経線維群の総合名称である。しかし,脳神経核は脳幹のそれぞれの部位に分れて存在するため,各脳神経核に向う神経線維は(全体として纏まらず)それぞれの経路をとる。そのためこれらを一括して迷行線維と総称する。迷行線維とはDejerine(1901)1)がfibres aberrantes〈F〉と呼称したのに始まるが,英語圏でもaberrant fiberとして用いられている。筆者が「迷行線維」と訳したもので,aberranteとは常軌(普通)ではないの意味で,医学的には異常と訳されることがあるが,ここでは妥当ではない。皮質脊髄路から見ればあちこちへ走行することになるので(迷走神経を避けて)迷行とした。大略は脳脚(中脳)の高さで皮質脊髄路から分離して,それぞれ中脳,橋,延髄の被蓋部を経て,各脳神経核に達する。本稿では図示出来ないので,拙著2)の図,図説を参照されたい。
書評
「がん薬物療法副作用管理マニュアル 第2版」—吉村知哲,田村和夫【監修】 川上和宜,松尾宏一,林 稔展,大橋養賢,小笠原信敬【編】 フリーアクセス
著者: 岩本卓也
ページ範囲:P.1115 - P.1115
「いかに副作用を軽減して治療を継続するか」。われわれががん薬物治療を開始するときに必ず考えることである。いくら最新のがん治療,エビデンスの高い治療であっても,実際に治療に耐えることができなければその恩恵を得ることはできない。また,がん治療に前向きな患者ばかりではなく,副作用への心配から自ら治療の道を閉ざしてしまう方もおり,そのような患者に対しては一層丁寧な説明が必要になる。このようなとき,実践に強い参考書,副作用について素早く整理できる本が手もとにあると心強い。本書は,好評を博した初版の刊行から3年を経て,さらに内容を充実させた第2版であり,医療従事者に求められる副作用管理のポイント,経験に基づくアドバイスが随所に挿入された実践向けの本である。もちろん,患者に要所を押さえた説明をする際にも最適である。
本書は,抗がん薬投与後に発現する主な副作用を取り上げ,その発現率,好発時期,リスク因子,評価方法をまとめている。また,典型的な症例提示もあり,副作用アセスメントの進め方をイメージできる。そして,第2版では,「患者のみかたと捉えかた」 を新設し,腫瘍内科医が身体所見,検査,副作用の評価方法を記載しており,診療の進め方を理解するのに役立つ。また,各論では「味覚障害」「不妊(性機能障害)」「栄養障害」が新たに追加され,「免疫関連有害事象(irAE)」の項目も充実している。
「ウォーモルド内視鏡下鼻副鼻腔・頭蓋底手術」—Peter-John Wormald【原著】 本間明宏,中丸裕爾【監訳】 鈴木正宣【訳者代表】 フリーアクセス
著者: 寺坂俊介
ページ範囲:P.1116 - P.1116
私は脳神経外科医として顕微鏡手術を学び,現在も手術を継続している。北海道大学脳神経外科で初めて内視鏡手術が行われたのは,下垂体腺腫の手術だったと記憶している。私の部下が初めて下垂体腺腫に対して内視鏡手術を行ったときのことはいまでも鮮明に覚えている。私は術衣に着替え顕微鏡とともに手術室内に待機した。手術が難航した際には顕微鏡手術に切り替えるつもりだったからだ。当時の内視鏡はいまよりも解像度が低く,内視鏡手術用の道具も限られていた。顕微鏡手術の倍の手術時間と出血量を要したが,私は一度も手術を替わろうとは思わなかった。自分がどんなに工夫しても顕微鏡下手術では見えなかった海綿静脈洞壁や鞍上部がモニターに映し出されていたからである。
ウォーモルド先生が執筆された本書には内視鏡下手術の利点,特に優れた可視性を最大に生かした手術手技が網羅され,しかもその1つ1つが細部に至るまでしっかりと書かれている。例えば内視鏡下髄液漏閉鎖術の章で紹介されるバスプラグ法などは脂肪の採取の部位,糸のかけ方,使用する道具,術後の管理,腰椎ドレーンを入れた場合はその排液量までが細かく記載されている。「賛否が分かれるかもしれないが」とただし書きをつけたうえで,ウォーモルド先生の手技が紹介されている。本書を読んでいると,このような細かな手術手技や術後管理を学びにかつてはお金と時間を費やして海外にまで行ったのに,と思われる諸兄も多いはずである。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.1063 - P.1063
欧文目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.1064 - P.1064
バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.1176 - P.1176
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.1177 - P.1177
あとがき フリーアクセス
著者: 虫明元
ページ範囲:P.1178 - P.1178
本号は特集「中枢神経・末梢神経の悪性リンパ腫」ということで,基礎の神経科学者としては,臨床研究の最前線を読む貴重な機会であった。筆者の若い頃は中枢神経にはリンパ系はないとのことで,リンパ系の疾患は神経系には縁遠い感じがしていた。しかし2013年にロチェスター大学のネーデルガードらが,脳のリンパ管系をグリンパティック系として命名して以来,脳にもリンパ系があり,大切な役割を担っていることが明らかになりつつある。
リンパ管系は,2つの役割が知られている。すなわち,①毛細血管から漏出した間質液を回収してリンパとして運び,静脈に戻すクリアランス系としての役割,②異物を認識し活性化した免疫細胞や抗原を末梢組織からリンパ節へ輸送し,免疫を開始させる役割の2つである。脳の中の老廃物,例えばアルツハイマー病におけるアミロイドβなどの老廃物は,グリンパティック系が脳外に排出して掃除してくれれば,異常な蓄積を防げるのではないかと期待されている。一方でこの系の働きが低下すれば老廃物が急激に増加することになるわけである。
基本情報
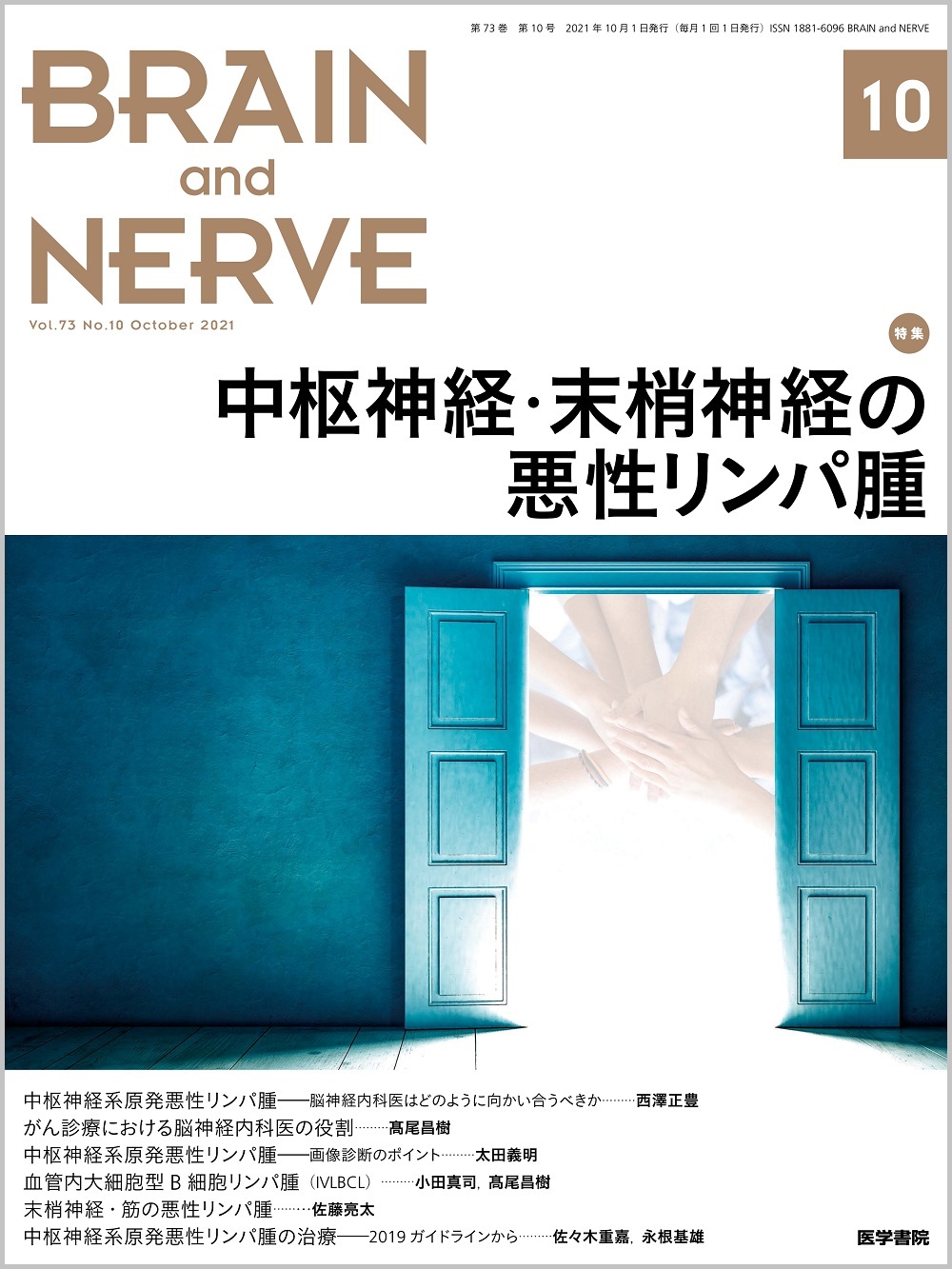
バックナンバー
76巻12号(2024年12月発行)
特集 芸術家と神経学Ⅱ
76巻11号(2024年11月発行)
特集 ALS 2024
76巻10号(2024年10月発行)
特集 どうして効くんだろう
76巻9号(2024年9月発行)
特集 治療可能な認知症としてのアルツハイマー病
76巻8号(2024年8月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である—revisited
76巻7号(2024年7月発行)
特集 ニューロ・バイオイメージング—技術と応用
76巻6号(2024年6月発行)
特集 注意と注意障害
76巻5号(2024年5月発行)
増大特集 末梢神経・筋肉の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
76巻4号(2024年4月発行)
特集 神経病理最前線
76巻3号(2024年3月発行)
特集 きちんと説明ができますか?
76巻2号(2024年2月発行)
特集 特発性正常圧水頭症の現在
76巻1号(2024年1月発行)
特集 新時代の重症筋無力症と関連疾患の診療
75巻12号(2023年12月発行)
特集 アガサ・クリスティーと神経毒
75巻11号(2023年11月発行)
特集 アロスタシス—ホメオスタシスを超えて
75巻10号(2023年10月発行)
特集 メタバースへの招待
75巻9号(2023年9月発行)
特集 妊娠と神経疾患
75巻8号(2023年8月発行)
特集 アルツハイマー病は本当に早期発見できるのか
75巻7号(2023年7月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part2 末梢編
75巻6号(2023年6月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part1 中枢編
75巻5号(2023年5月発行)
増大特集 神経・精神領域の薬剤ハンドブック
75巻4号(2023年4月発行)
特集 All About Epilepsy
75巻3号(2023年3月発行)
特集 慢性疼痛
75巻2号(2023年2月発行)
特集 多系統萎縮症の新診断基準とこれからの診療
75巻1号(2023年1月発行)
特集 よく出会う不随意運動を知る
74巻12号(2022年12月発行)
特集 映画を観て精神・神経疾患を知る
74巻11号(2022年11月発行)
特集 RFC1遺伝子関連スペクトラム障害
74巻10号(2022年10月発行)
特集 ウイルス性脳炎・脳症2022
74巻9号(2022年9月発行)
特集 動的環境への適応系としての歩行
74巻8号(2022年8月発行)
特集 迷走神経の不思議
74巻7号(2022年7月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識2022
74巻6号(2022年6月発行)
特集 脳神経内科医に求められる移行医療
74巻5号(2022年5月発行)
増大特集 次の一手—神経筋疾患難治例をどのように治療するか
74巻4号(2022年4月発行)
特集 脳科学リテラシーを高めるために
74巻3号(2022年3月発行)
特集 中枢性自律神経障害update
74巻2号(2022年2月発行)
特集 温度を感じる脳と身体の科学
74巻1号(2022年1月発行)
特集 脳神経内科医のキャリアパスとリーダーシップ
73巻12号(2021年12月発行)
特集 芸術家と神経学
73巻11号(2021年11月発行)
特集 「目」の神経学
73巻10号(2021年10月発行)
特集 中枢神経・末梢神経の悪性リンパ腫
73巻9号(2021年9月発行)
特集 脳卒中治療に必要な基礎知識
73巻8号(2021年8月発行)
特集 脳腸相関—脳-身体の双方向性制御
73巻7号(2021年7月発行)
特集 グリアと神経—相補的な制御系として
73巻6号(2021年6月発行)
特集 Lower Spine Neurology
73巻5号(2021年5月発行)
増大特集 中枢神経の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
73巻4号(2021年4月発行)
特集 片頭痛・群発頭痛治療の新たな夜明け
73巻3号(2021年3月発行)
特集 マルチリンガルブレイン
73巻2号(2021年2月発行)
特集 筋炎と壊死性筋症
73巻1号(2021年1月発行)
特集 Neuro-Oncology
72巻12号(2020年12月発行)
特集 超高齢期の精神神経疾患を診る
72巻11号(2020年11月発行)
増大特集 脳の発振現象—基礎から臨床へ
72巻10号(2020年10月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識
72巻9号(2020年9月発行)
特集 皮質性小脳萎縮症へのアプローチ
72巻8号(2020年8月発行)
特集 サルコイドーシス
72巻7号(2020年7月発行)
増大特集 神経倫理ハンドブック
72巻6号(2020年6月発行)
特集 前頭側頭葉変性症の今日的理解
72巻5号(2020年5月発行)
特集 多発性硬化症の現在と未来
72巻4号(2020年4月発行)
増大特集 神経疾患の診断における落とし穴—誤診を避けるために
72巻3号(2020年3月発行)
特集 でこぼこの脳の中でおしくらまんじゅうする脳機能
72巻2号(2020年2月発行)
特集 αシヌクレイノパチーの新たな展開
72巻1号(2020年1月発行)
特集 神経難病をクスリで治す—薬物開発の現況と近未来への展望
71巻12号(2019年12月発行)
特集 小脳と大脳—Masao Itoのレガシー
71巻11号(2019年11月発行)
増大特集 ALS2019
71巻10号(2019年10月発行)
特集 認知症と遺伝
71巻9号(2019年9月発行)
特集 神経疾患のドラッグ・リポジショニング—新時代へ
71巻8号(2019年8月発行)
特集 パーキンソン病診療の現在地—200年の変遷と新規治療
71巻7号(2019年7月発行)
増大特集 人工知能と神経科学
71巻6号(2019年6月発行)
特集 補体標的治療の現状と展望
71巻5号(2019年5月発行)
特集 NPSLE
71巻4号(2019年4月発行)
増大特集 神経学のための皮膚アトラス
71巻3号(2019年3月発行)
特集 Spine Neurology
71巻2号(2019年2月発行)
特集 “スポーツ”を生み出す脳
71巻1号(2019年1月発行)
特集 人工知能の医療応用Update
70巻12号(2018年12月発行)
特集 主訴に沿う—俯瞰し収束する画像診断の目
70巻11号(2018年11月発行)
増大特集 脳科学で解き明かす精神神経症候
70巻10号(2018年10月発行)
特集 「左脳と右脳」の現在
70巻9号(2018年9月発行)
特集 脳神経内科診療に役立つ精神科の知識
70巻8号(2018年8月発行)
特集 レヴィ小体型認知症の新知見
70巻7号(2018年7月発行)
増大特集 記憶と忘却に関わる脳のしくみ—分子機構から健忘の症候まで
70巻6号(2018年6月発行)
特集 芸術を生み出す脳
70巻5号(2018年5月発行)
特集 非アルツハイマー型認知症の病理学
70巻4号(2018年4月発行)
増大特集 Antibody Update 2018
70巻3号(2018年3月発行)
特集 『認知症疾患診療ガイドライン2017』を読み解く
70巻2号(2018年2月発行)
特集 知っておきたい神経感染症
70巻1号(2018年1月発行)
特集 筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群の今
69巻12号(2017年12月発行)
特集 運動異常症をみる—Web動画付録つき
69巻11号(2017年11月発行)
増大特集 こころの時間学の未来
69巻10号(2017年10月発行)
特集 成人てんかん—知っておきたい6つのトピック
69巻9号(2017年9月発行)
特集 ミクログリアと精神・神経疾患
69巻8号(2017年8月発行)
特集 遺伝性脊髄小脳失調症の病態と治療展望
69巻7号(2017年7月発行)
増大特集 あしたのアルツハイマー病治療
69巻6号(2017年6月発行)
特集 局在病変の神経心理学
69巻5号(2017年5月発行)
特集 Voxel-Based Morphometry—体積からわかること
69巻4号(2017年4月発行)
増大特集 ブロードマン領野の現在地
69巻3号(2017年3月発行)
特集 磁気刺激の新たな展開
69巻2号(2017年2月発行)
特集 Stroke-Like Diseases—鑑別時に注意を要する5病態
69巻1号(2017年1月発行)
特集 近年注目されている白質脳症
68巻12号(2016年12月発行)
特集 炎症性神経・筋疾患の新たな展開
68巻11号(2016年11月発行)
増大特集 連合野ハンドブック
68巻10号(2016年10月発行)
特集 アディクション—行動の嗜癖
68巻9号(2016年9月発行)
特集 自己免疫性脳炎・脳症
68巻8号(2016年8月発行)
特集 こころと汗
68巻7号(2016年7月発行)
増大特集 認知症の危険因子と防御因子
68巻6号(2016年6月発行)
特集 脳とフローラ
68巻5号(2016年5月発行)
特集 手の症候学—生理学・解剖学からみた新知見
68巻4号(2016年4月発行)
増大特集 治せる認知症
68巻3号(2016年3月発行)
特集 末梢神経の血管炎
68巻2号(2016年2月発行)
特集 筋疾患の認知機能障害
68巻1号(2016年1月発行)
特集 シャルコー・マリー・トゥース病
67巻12号(2015年12月発行)
特集 視床と高次脳機能
67巻11号(2015年11月発行)
増大特集 ギラン・バレー症候群のすべて—100年の軌跡
67巻10号(2015年10月発行)
特集 非・日常生活の脳科学
67巻9号(2015年9月発行)
特集 酵素補充療法
67巻8号(2015年8月発行)
特集 神経難病の終末期医療
67巻7号(2015年7月発行)
増大特集 神経疾患と感染症update
67巻6号(2015年6月発行)
特集 脳と「質感」
67巻5号(2015年5月発行)
特集 NCSE(非痙攣性てんかん重積状態)
67巻4号(2015年4月発行)
増大特集 大脳皮質vs.大脳白質
67巻3号(2015年3月発行)
特集 中枢神経の血管炎
67巻2号(2015年2月発行)
特集 「食べる」を考える
67巻1号(2015年1月発行)
特集 ニューロトキシコロジー
66巻12号(2014年12月発行)
特集 Orthopaedic Neurology—神経内科と整形外科の狭間で
66巻11号(2014年11月発行)
増大特集 神経症候学は神経学の“魂”である
66巻10号(2014年10月発行)
特集 分子を撃つ 神経疾患治療の新しい水平線
66巻9号(2014年9月発行)
特集 痙縮の臨床神経学
66巻8号(2014年8月発行)
特集 神経系の悪性リンパ腫update
66巻7号(2014年7月発行)
増大特集 アミロイド関連神経疾患のすべて―封入体筋炎からアルツハイマー病まで
66巻6号(2014年6月発行)
特集 ミラーニューロン
66巻5号(2014年5月発行)
特集 アセチルコリンと神経疾患―100年目の現在地
66巻4号(2014年4月発行)
増大特集 タッチ・ビジョン・アクション
66巻3号(2014年3月発行)
特集 神経筋疾患の超音波診断
66巻2号(2014年2月発行)
特集 糖尿病の神経学revisited
66巻1号(2014年1月発行)
特集 日常生活の脳科学
65巻12号(2013年12月発行)
特集 プロテイノパチーの神経病理学
65巻11号(2013年11月発行)
増大特集 Close Encounters―臨床神経学と臨床免疫学の遭遇と未来
65巻10号(2013年10月発行)
特集 神経系の発達メカニズム―最近の話題
65巻9号(2013年9月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である―現状と展望
65巻8号(2013年8月発行)
特集 こころの時間学―現在・過去・未来の起源を求めて
65巻7号(2013年7月発行)
増大特集 あしたの脳梗塞
65巻6号(2013年6月発行)
特集 見せる・仕分ける―脳機能解析の新手法
65巻5号(2013年5月発行)
特集 てんかん―新しいパースペクティブ
65巻4号(2013年4月発行)
増大特集 Antibody Update
65巻3号(2013年3月発行)
特集 次世代シーケンサーによる神経変性疾患の解析と展望
65巻2号(2013年2月発行)
特集 血液脳関門研究の進歩
65巻1号(2013年1月発行)
特集 Corticobasal Syndrome
64巻12号(2012年12月発行)
特集 The Border-Land of Dementia
64巻11号(2012年11月発行)
増大特集 痛みの神経学―末梢神経から脳まで
64巻10号(2012年10月発行)
特集 辺縁系をめぐって
64巻9号(2012年9月発行)
特集 高次脳機能イメージングの脳科学への新展開
64巻8号(2012年8月発行)
特集 線条体の基礎と臨床
64巻7号(2012年7月発行)
増大特集 顔認知の脳内機構
64巻6号(2012年6月発行)
特集 睡眠と覚醒の脳内機構
64巻5号(2012年5月発行)
特集 神経疾患のバイオマーカー
64巻4号(2012年4月発行)
増大特集 パーキンソン病の新しい側面
64巻3号(2012年3月発行)
特集 アカデミアから新規治療の実現へ―トランスレーショナルリサーチの現状
64巻2号(2012年2月発行)
特集 生物学的精神医学の進歩
64巻1号(2012年1月発行)
特集 iPS細胞と神経疾患
63巻12号(2011年12月発行)
特集 神経心理学と画像解析の融合
63巻11号(2011年11月発行)
増大特集 筋疾患update
63巻10号(2011年10月発行)
特集 緩徐進行性高次脳機能障害の病態
63巻9号(2011年9月発行)
特集 脳卒中の最新画像診断
63巻8号(2011年8月発行)
特集 日本人の発見した神経症候
63巻7号(2011年7月発行)
増大特集 神経筋接合部―基礎から臨床まで
63巻6号(2011年6月発行)
特集 ニューロパチー
63巻5号(2011年5月発行)
特集 神経系と血管内リンパ腫
63巻4号(2011年4月発行)
増大特集 てんかんの新しい治療
63巻3号(2011年3月発行)
特集 サイバーナイフ治療
63巻2号(2011年2月発行)
特集 続・日本人の発見した神経疾患
63巻1号(2011年1月発行)
特集 血管腫
62巻12号(2010年12月発行)
特集 頸部頸動脈狭窄症の診断と治療
62巻11号(2010年11月発行)
増大特集 歩行とその異常
62巻10号(2010年10月発行)
特集 ブレインバンク
62巻9号(2010年9月発行)
特集 視神経脊髄炎(NMO)update
62巻8号(2010年8月発行)
特集 辺縁系脳炎
62巻7号(2010年7月発行)
増大特集 アルツハイマー病―研究と診療の進歩
62巻6号(2010年6月発行)
特集 改正臓器移植法の問題点とその対応
62巻5号(2010年5月発行)
特集 神経画像のピットフォール―見落としと読み過ぎ
62巻4号(2010年4月発行)
特集 傍腫瘍性神経筋疾患update
62巻3号(2010年3月発行)
特集 神経回路解析法の最近の進歩
62巻2号(2010年2月発行)
特集 ニューロリハビリテーションの最前線
62巻1号(2010年1月発行)
特集 神経救急
61巻12号(2009年12月発行)
特集 Somatotopy再考
61巻11号(2009年11月発行)
特集 前頭側頭葉変性症
61巻10号(2009年10月発行)
特集 片頭痛の予防療法
61巻9号(2009年9月発行)
特集 脳血管障害治療の進歩
61巻8号(2009年8月発行)
特集 神経・筋疾患の分子標的治療
61巻7号(2009年7月発行)
特集 脳腫瘍研究の最前線―遺伝子解析から治療まで
61巻6号(2009年6月発行)
特集 脊椎・脊髄外科の最近の進歩
61巻5号(2009年5月発行)
特集 Restless legs syndrome
61巻4号(2009年4月発行)
特集 大脳基底核―分子基盤から臨床まで
61巻3号(2009年3月発行)
特集 Microneurography(微小神経電図法)の臨床応用
61巻2号(2009年2月発行)
特集 神経系の再興感染症と輸入感染症
61巻1号(2009年1月発行)
特集 脳神経倫理
60巻12号(2008年12月発行)
特集 痙縮
60巻11号(2008年11月発行)
特集 脳卒中と遺伝子
60巻10号(2008年10月発行)
特集 若年者の脳卒中
60巻9号(2008年9月発行)
特集 知・情・意の神経学
60巻8号(2008年8月発行)
特集 脳硬膜動静脈瘻
60巻7号(2008年7月発行)
増大特集 学習と記憶――基礎と臨床
60巻6号(2008年6月発行)
特集 Crow-深瀬症候群(POEMS症候群)
60巻5号(2008年5月発行)
特集 「痛み」の研究と治療の最前線
60巻4号(2008年4月発行)
増大特集 神経系の発生とその異常
60巻3号(2008年3月発行)
特集 特発性正常圧水頭症(iNPH)―最近の話題
60巻2号(2008年2月発行)
特集 がん治療と神経障害
60巻1号(2008年1月発行)
特集 日本人の発見した神経疾患
59巻12号(2007年12月発行)
特集 損傷神経の再生―温存的治療法の開発
59巻11号(2007年11月発行)
特集 手根管症候群をめぐって
59巻10号(2007年10月発行)
増大特集 ALS―研究と診療の進歩
59巻9号(2007年9月発行)
特集 パーキンソン病の認知機能障害
59巻8号(2007年8月発行)
特集 パーキンソン病の分子遺伝学―最近の知見
59巻7号(2007年7月発行)
増大特集 情報伝達処理におけるグリアの機能と異常
59巻6号(2007年6月発行)
特集 職業性神経障害の新しい展開
59巻5号(2007年5月発行)
特集 脳画像最前線
59巻4号(2007年4月発行)
増大特集 最近注目される脳神経疾患治療の研究
59巻3号(2007年3月発行)
特集 分子イメージング
59巻2号(2007年2月発行)
特集 進行性多巣性白質脳症の新しい展開―PMLが治る時代へ向けて
59巻1号(2007年1月発行)
特集 高次視覚研究の最近の進歩
