「目」にはさまざまな光受容体が存在する。その機能は光受容にとどまらず,時間や睡眠など驚くほど幅の広い多様な機能を担っている。また,視覚系の神経基盤の理解につながる錯視・錯覚の原理も少しずつ明らかになってきた。本特集では,視覚に関する話題を中心に,目と神経に関わる最近のトピックスについてエキスパートに論じていただく。
雑誌目次
BRAIN and NERVE-神経研究の進歩73巻11号
2021年11月発行
雑誌目次
特集 「目」の神経学
目の働きはものを「見る」だけではない
著者: 坪田一男 , 鳥居秀成 , 栗原俊英
ページ範囲:P.1185 - P.1191
ヒトは9種類の光受容体を持つが,このうち視覚に使われているものはOPN1の3種類(青,緑,赤の錐体光受容体)とOPN2(星明りなど明るさに高感度の桿体光受容体)の4種類である。したがって5種類の光受容体は非視覚型なのである。これらの中にはブルーライトに吸収極大がありサーカディアンリズムに関係するOPN4や,近視の抑制に関係するOPN5などがある。本論ではこれらの非視覚型光受容体について解説を行う。
概日リズムを位相制御する光受容体
著者: 小島大輔 , 深田吉孝
ページ範囲:P.1193 - P.1199
約24時間周期の体内時計(概日時計)に基づいて,私たちの活動・休息などの概日リズムが刻まれる。自律的な概日リズムは,哺乳類では網膜の光受容により地球の自転周期である24時間に同調する。本論では,概日リズムの光同調に主要な役割を果たす光受容細胞として,光感受性網膜神経節細胞(ipRGC)について詳説する。ipRGCの光受容機構や神経回路,さらにはその多様性について,主にマウスで得られた知見を紹介する。
光による非侵襲的脳機能制御—バイオレットライトとOPN5の新機能
著者: 早野元詞 , 坪田一男
ページ範囲:P.1201 - P.1207
脳機能は日照時間,光量といった「光」の影響を大きく受けており,その影響は睡眠,認知機能,うつ病やパーキンソン病の症状などさまざまな面に表れることが知られている。一方で,光は波長に応じた赤や青などのさまざまな「色」を持ち,そして光の受け手側も視覚情報として「視る」ためだけでなく,非視覚情報のシグナルとして「感じる」といった多様性が存在している。本論では,OPN5といった360〜400nmのバイオレットライト受容体を中心に,眼から脳機能を特異的に制御している最近の知見について紹介したい。
眼は「脳」の窓となり得るか?—認知症バイオマーカーとしての網膜イメージング
著者: 佐々木真理子
ページ範囲:P.1209 - P.1216
眼は神経と血管を直接見ることのできる唯一の臓器である。脳と網膜には類似性があり,網膜イメージングの技術の進歩に伴い,非侵襲的で直接的に脳の病態を評価する手段としての網膜イメージングが注目されている。光干渉断層計・血管撮影は網膜構造や血管の変化と認知機能との関連を明らかにし,人工知能の応用も試みられている。網膜内のアミロイドβの観察など,より認知症特異的な網膜バイオマーカーの開発が期待される。
涙液分泌に関わる神経回路
著者: 中村滋
ページ範囲:P.1217 - P.1223
涙液は涙器より眼表面に分泌される体液であり,その機能から,①眼表面を間断なく潤す基礎分泌,②対処する反射性分泌,③感情の高揚により多量に流れ出る情動性分泌,の3つに分類される。涙液の分泌は,他の多くの末梢分泌器官と同じく,涙器と中枢神経の協調によりその分泌量が調節されている。脳あるいは眼表面からの信号が脳延髄に位置する涙腺中枢である「上唾液核」を興奮させ,遠心性に自律神経による分泌刺激が涙腺に投射する副交感神経を経て,涙腺の涙液分泌機能の活性化を促すと想定されているが不明瞭な点も多い。本論では涙液の分泌様式/役割からの,それぞれの神経回路の役割を記述したい。
奥行きを感じる脳のしくみ—両目はなぜ揃う?
著者: 光藤宏行
ページ範囲:P.1225 - P.1229
ステレオグラムは両眼視に基づいてリアルな奥行きを体験できる非常に身近なツールである。本論では,ステレオグラムの原理と奥行き知覚の基本を解説し,さらに近年の視覚科学的・神経科学的な知見に基づいて,なぜ両目は揃うのかという素朴な疑問を深く探究した。その試みの中で,脳は,奥行き知覚をもたらす水平両眼網膜像差の計算を行いながら,両眼融合のための調整の計算を常に行っているという可能性を描いた。
三次元視覚世界を創る脳の領域
著者: 番浩志
ページ範囲:P.1231 - P.1236
網膜像は二次元であるにもかかわらず,私たちヒトは豊かで安定した三次元視覚世界を即座に知覚できる。では,ヒトが感じる立体感は,脳のどの領域のどのような働きによって再構築されているのだろうか。本論では,立体視の一般的な研究手法を概説し,頭頂間溝に沿って隣接して位置する中・高次の視覚野,V3AとV3B/KOの働きが三次元視覚世界の再構築に重要な役割を果たすことを示した最近の研究成果を紹介したい。
錯視を生じる脳のしくみ—ゼブラフィッシュの運動残効から
著者: 久保郁
ページ範囲:P.1237 - P.1241
錯視は,視界に実在する視覚情報とは異なる視覚が脳内で認識されてしまう現象であり,脳内の視覚情報処理の過程でなんらかの間違いが起こることで生じると考えられている。錯視がどのようなメカニズムで起こるのかという問題は,長年多くの科学者の興味を惹きつけてきた。本論では,脊椎動物モデル・ゼブラフィッシュを使った研究に焦点を絞り,錯視の神経メカニズム,さらには錯視現象を利用した視覚神経回路解析について議論する。
錯視を生み出す視覚のメカニズム—目から脳へ
著者: 吉本早苗 , 竹内龍人
ページ範囲:P.1243 - P.1248
錯視とは,目にしているものがその物理的属性とは異なるように知覚される心理的現象を示す。そのものの実体を前もって知っていても,知覚には反映されない。そのために,錯視の理解は,錯視生成の土台となる視覚系の理解につながる。明暗,運動,色の錯視には,網膜から第一次視覚野に至る初期視覚の神経活動により説明できるものが多い。一方で,大きさの恒常性に基づく三次元的な形状に関する錯視には,高次視覚の関与が想定される。
幻視症候群小辞典—幻視をきたすさまざまな病態
著者: 西尾慶之
ページ範囲:P.1249 - P.1257
幻視はてんかんや片頭痛などの発作性神経疾患,アルコール離脱,抗コリン薬や幻覚薬の使用,神経変性疾患,脳内局所病変,統合失調症スペクトラムなど幅広い病態に関連して出現する。本論では幻視をきたす11の病態に着目し,現象面の特徴と背景にある病態生理について議論する。
総説
ポリコーム群蛋白質を介した脳形成の地図をつくるメカニズム
著者: 山田夏実 , 椙下紘貴
ページ範囲:P.1261 - P.1266
脳が複雑な機能を獲得できるのは,神経幹細胞が遺伝子の転写を正しく制御することで,脳の領域ごとに異なる性質のニューロンやグリア細胞を産生しているからである。モルフォジェンやポリコーム複合体は,領域特異的な遺伝子の転写制御によって,発生初期に脳の地図形成に貢献している。われわれはポリコーム群蛋白質のRING1Bがモルフォジェンの発現を領域特異的に抑制することで脳の背腹軸形成を促すことを明らかにした。
安静時fMRIにおける動的機能結合の臨床応用
著者: 品川和志 , 寺澤悠理 , 梅田聡
ページ範囲:P.1267 - P.1273
安静時fMRIでは,撮像中に均質な心的状態を仮定し,撮像時間全体の平均的な脳の機能的結合を評価する。しかし,安静時であっても,機能的結合は時間経過に伴い変動している場合が多い。そこで,機能的結合の時間的変化の側面に焦点を絞った,動的機能結合(dFC)と呼ばれる指標が提案されている。本総説では,dFCの意義や主な手法,臨床研究への適用例,またその限界について概説し,dFCの臨床応用可能性を示す。
慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー(CIDP)における治療法の選択—免疫グロブリン療法を中心に
著者: 古賀道明 , 飯島正博 , 福島卓 , 海田賢一
ページ範囲:P.1275 - P.1284
慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー(CIDP)の病態は多様で,臨床経過や治療反応性も患者により異なる。したがって,治療開始後の臨床経過に応じて有効性を客観的に判定し,治療内容の妥当性や適正な投与量,投与間隔などを決定する必要がある。本総説ではCIDP治療の各段階における的確な選択のために,考慮すべき点や近年研究が進んでいる免疫グロブリン療法を中心に参考となる研究結果について述べる。
現代神経科学の源流・16
ノーム・チョムスキー【Ⅳ】
著者: 福井直樹 , 酒井邦嘉
ページ範囲:P.1285 - P.1288
反戦運動と生成意味論の時代
酒井 その後チョムスキーは,ベトナム戦争を機にかなり政治運動に力を入れていきます。
福井 1964年からベトナム反戦運動に本格的に関与しますが,それを決意するにあたって,もうそれまでみたいに研究に集中はできないだろうということで,どの研究を残すか,かなり真剣に考えたようです。
反戦運動を始めた頃には既にマサチューセッツ工科大学(以下,MIT)の正教授でしたから,そう簡単に解雇はされないはずなのですが,それでも禁固とかになると,最終的には解雇される可能性がある。そういうところまで考えて,研究対象を絞っています。奥さんのキャロルがハーバード大学の大学院に戻って,チョムスキーが大学を解雇されてしまったときには彼女が働いて家族を養うというところまで計画していました。
連載 脳神経内科領域における医学教育の展望—Post/withコロナ時代を見据えて・3
臨床教育アプローチを裏付ける教育理論
著者: 今福輪太郎 , 西城卓也
ページ範囲:P.1290 - P.1293
はじめに
前回(Vol.2;73巻10号pp1164-1167)は,臨床教育のすべての基本となる「経験」について,経験学習サイクルを総論的枠組みとしてご紹介しました。本稿では,その臨床教育の根底にある理論的基盤を理解するため,まず成人の学習者としての特性に関する成人学習理論,次に指導者による効果的教育アプローチを理論化した認知的徒弟制を,概説したいと思います。
臨床神経学プロムナード—60余年を顧みて・9
「若年性一側上肢筋萎縮症〔後の平山病〕」の英文原著論文をめぐる三様の評価
著者: 平山惠造
ページ範囲:P.1294 - P.1295
少し前置きがある。本症の記述は筆者の学位論文(1959年11月)1)の一部に付記する形で示したのに始まるが,その翌月には本症単独の論文を12例を以って発表した2)。「病因は不明であるが,従来知られている疾患にはみられない臨床的特徴を呈するものとして,若年性一側上肢筋萎縮症と仮称し,将来,剖検を待って解明されるものと思われる」と結んだ。発表後の本邦での評価は区区で,脊髄性進行性筋萎縮症の亜型説や,頸椎症説,外傷説など,本症の独立性を認めるものは乏しかった。しかし更に症例も増え,20例に及ぶ観察から英文での発表を冲中重雄教授の許可を得て,英文雑誌に投稿し,受理された3)。1963年8月のことであった。それは筆者がフランス政府給費留学生として出発する(9月)直前で,論文別刷を受け取る間もなく渡航した。
書評
「神経眼科学を学ぶ人のために 第3版」—三村 治【著】 フリーアクセス
著者: 村上晶
ページ範囲:P.1258 - P.1258
私自身,神経眼科学については,系統立った教育を受けないまま,眼科医として仕事をしている。したがって,この領域は正直言ってあまり得意ではない。苦手と言ってもよいかもしれない。そういう私が頼りにしている1冊が,三村治先生の執筆による『神経眼科学を学ぶ人のために』である。おそらく,神経眼科を基本から学ぶ入門書としても,どう診断するか迷う症例の答えを探すときにも多くの眼科医が手に取っているのではと思う。
今回,改訂第3版が発刊され,これまで以上に見やすいイラストと懇切丁寧に解説された臨床画像が満載されており,さらに頼もしい1冊になっている。専門外の者にとっては,神経眼科疾患を前にして,どう診察を始めてよいか迷うことが少なくない。そういう気持ちを察するかのように,診断のコツ,そして優先すべき検査を明解に記述くださっているのがありがたい。余裕のないときは,ボールドで印刷されているところに注意を払って読んでいくことで大切なことを逃さずに要点を整理できる構成になっている。治療についても,最初の一手からその後の経過の見方まで,豊富な経験と最新の知見をもとにポイントを絞った形で記載されている。エビデンスの蓄積がまたれるような新しい知見や,専門家の視点で注目している事柄の記載がコラム「Close Up」として各所にちりばめられているのでじっくり読み込む楽しみもある。
「総合内科マニュアル 第2版」—八重樫牧人,佐藤暁幸【監修】 亀田総合病院【編】 フリーアクセス
著者: 森川暢
ページ範囲:P.1260 - P.1260
ついに『総合内科マニュアル(亀マニュ)』が改訂された。実は,私は亀マニュのファンだ。医師3年目のときに総合診療の後期研修を始めたが,本当に右も左もわからなかった。多少は内科の知識を持っている自信があったが,それは粉々に打ち砕かれた。かといって,同期や先輩のようにUpToDate®を紐解き知識を増やすような甲斐性もなく,仕事にひたすら追われていた。
当時,私は常に2つのマニュアルをポケットに入れていた。1つは『診察エッセンシャルズ』という診断学に特化したマニュアルであった。しかし,内科マネジメントについても同様にマニュアルが必要であった。結果的に,私が選んだ相棒は亀マニュだった。ベットサイドで診療し,亀マニュを見るという日々をひたすら繰り返した。いつしか,亀マニュは自分の血肉となり携帯はしなくなった。ただ,その後の自分の内科マネジメントの原則や原理は亀マニュが基本となっていることに変わりはない。そして,今回の改訂である。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.1181 - P.1181
欧文目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.1182 - P.1182
バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.1300 - P.1300
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.1301 - P.1301
あとがき フリーアクセス
著者: 酒井邦嘉
ページ範囲:P.1302 - P.1302
オンライン中継に必要なWebカメラとして,動画機能のついたミラーレス一眼カメラが広く使われるようになった。ミラーレスは一眼レフより小型なのに十分高画質であり,豊富な交換レンズによる画角調整や,レンズの絞りによる背景ぼかしが手軽にコントロールできる。ミニ三脚で机上にカメラを置く場合,焦点距離(ライカ判換算)が35mmの広角レンズを使えば,絞りが2.8程度で効果的な映像が得られる。ちなみに筆者は,「SIGMA fp」とライカの「Elmarit-R」(宮本製作所のマウントアダプターを併用)を使っている。
カメラのレンズ設計では,さまざまな収差をいかに抑えるかが難題だった。色収差の軽減には特殊ガラスを用いた「アポクロマートレンズ」,球面収差の除去には「非球面レンズ」,被写体距離による収差の変化にはレンズ群の相対位置を変える「フローティング・フォーカス機構」という技術革新があった。いまや,この3つをすべて備えたレンズも増えている。ただし,明るいレンズは重く大型になってしまい,焦点距離が50mmの標準レンズで1kg近いものも珍しくない。それでは携行性が悪くスナップ写真などに向かないから,小型化の工夫も同時に必要となる。さらに「レンズの味」を追求すると,焦点の合っていない背景の美しさも大切であり,「ボケ」という写真用語は既に世界共通語(bokeh)となっている。
基本情報
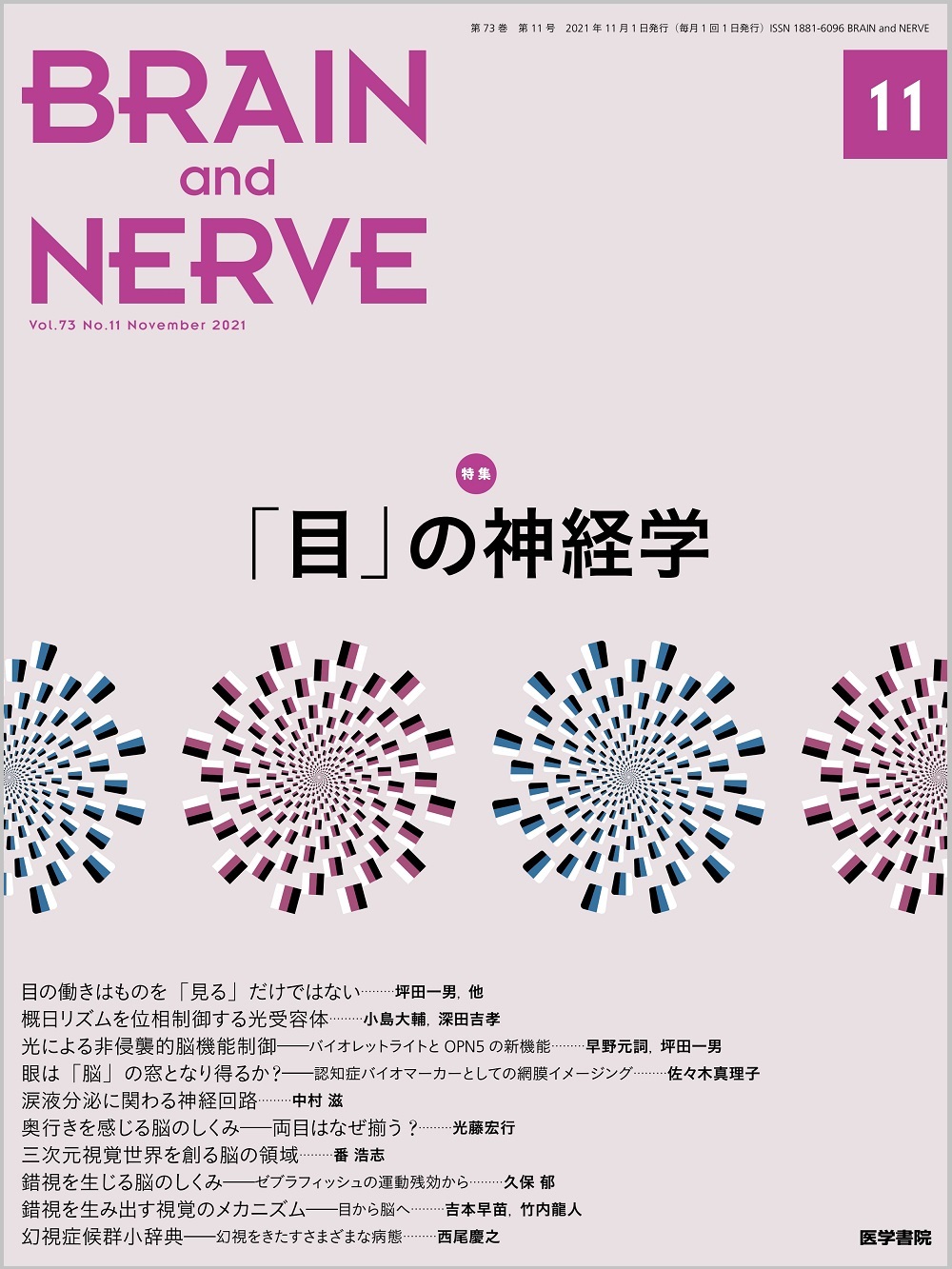
バックナンバー
76巻12号(2024年12月発行)
特集 芸術家と神経学Ⅱ
76巻11号(2024年11月発行)
特集 ALS 2024
76巻10号(2024年10月発行)
特集 どうして効くんだろう
76巻9号(2024年9月発行)
特集 治療可能な認知症としてのアルツハイマー病
76巻8号(2024年8月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である—revisited
76巻7号(2024年7月発行)
特集 ニューロ・バイオイメージング—技術と応用
76巻6号(2024年6月発行)
特集 注意と注意障害
76巻5号(2024年5月発行)
増大特集 末梢神経・筋肉の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
76巻4号(2024年4月発行)
特集 神経病理最前線
76巻3号(2024年3月発行)
特集 きちんと説明ができますか?
76巻2号(2024年2月発行)
特集 特発性正常圧水頭症の現在
76巻1号(2024年1月発行)
特集 新時代の重症筋無力症と関連疾患の診療
75巻12号(2023年12月発行)
特集 アガサ・クリスティーと神経毒
75巻11号(2023年11月発行)
特集 アロスタシス—ホメオスタシスを超えて
75巻10号(2023年10月発行)
特集 メタバースへの招待
75巻9号(2023年9月発行)
特集 妊娠と神経疾患
75巻8号(2023年8月発行)
特集 アルツハイマー病は本当に早期発見できるのか
75巻7号(2023年7月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part2 末梢編
75巻6号(2023年6月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part1 中枢編
75巻5号(2023年5月発行)
増大特集 神経・精神領域の薬剤ハンドブック
75巻4号(2023年4月発行)
特集 All About Epilepsy
75巻3号(2023年3月発行)
特集 慢性疼痛
75巻2号(2023年2月発行)
特集 多系統萎縮症の新診断基準とこれからの診療
75巻1号(2023年1月発行)
特集 よく出会う不随意運動を知る
74巻12号(2022年12月発行)
特集 映画を観て精神・神経疾患を知る
74巻11号(2022年11月発行)
特集 RFC1遺伝子関連スペクトラム障害
74巻10号(2022年10月発行)
特集 ウイルス性脳炎・脳症2022
74巻9号(2022年9月発行)
特集 動的環境への適応系としての歩行
74巻8号(2022年8月発行)
特集 迷走神経の不思議
74巻7号(2022年7月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識2022
74巻6号(2022年6月発行)
特集 脳神経内科医に求められる移行医療
74巻5号(2022年5月発行)
増大特集 次の一手—神経筋疾患難治例をどのように治療するか
74巻4号(2022年4月発行)
特集 脳科学リテラシーを高めるために
74巻3号(2022年3月発行)
特集 中枢性自律神経障害update
74巻2号(2022年2月発行)
特集 温度を感じる脳と身体の科学
74巻1号(2022年1月発行)
特集 脳神経内科医のキャリアパスとリーダーシップ
73巻12号(2021年12月発行)
特集 芸術家と神経学
73巻11号(2021年11月発行)
特集 「目」の神経学
73巻10号(2021年10月発行)
特集 中枢神経・末梢神経の悪性リンパ腫
73巻9号(2021年9月発行)
特集 脳卒中治療に必要な基礎知識
73巻8号(2021年8月発行)
特集 脳腸相関—脳-身体の双方向性制御
73巻7号(2021年7月発行)
特集 グリアと神経—相補的な制御系として
73巻6号(2021年6月発行)
特集 Lower Spine Neurology
73巻5号(2021年5月発行)
増大特集 中枢神経の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
73巻4号(2021年4月発行)
特集 片頭痛・群発頭痛治療の新たな夜明け
73巻3号(2021年3月発行)
特集 マルチリンガルブレイン
73巻2号(2021年2月発行)
特集 筋炎と壊死性筋症
73巻1号(2021年1月発行)
特集 Neuro-Oncology
72巻12号(2020年12月発行)
特集 超高齢期の精神神経疾患を診る
72巻11号(2020年11月発行)
増大特集 脳の発振現象—基礎から臨床へ
72巻10号(2020年10月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識
72巻9号(2020年9月発行)
特集 皮質性小脳萎縮症へのアプローチ
72巻8号(2020年8月発行)
特集 サルコイドーシス
72巻7号(2020年7月発行)
増大特集 神経倫理ハンドブック
72巻6号(2020年6月発行)
特集 前頭側頭葉変性症の今日的理解
72巻5号(2020年5月発行)
特集 多発性硬化症の現在と未来
72巻4号(2020年4月発行)
増大特集 神経疾患の診断における落とし穴—誤診を避けるために
72巻3号(2020年3月発行)
特集 でこぼこの脳の中でおしくらまんじゅうする脳機能
72巻2号(2020年2月発行)
特集 αシヌクレイノパチーの新たな展開
72巻1号(2020年1月発行)
特集 神経難病をクスリで治す—薬物開発の現況と近未来への展望
71巻12号(2019年12月発行)
特集 小脳と大脳—Masao Itoのレガシー
71巻11号(2019年11月発行)
増大特集 ALS2019
71巻10号(2019年10月発行)
特集 認知症と遺伝
71巻9号(2019年9月発行)
特集 神経疾患のドラッグ・リポジショニング—新時代へ
71巻8号(2019年8月発行)
特集 パーキンソン病診療の現在地—200年の変遷と新規治療
71巻7号(2019年7月発行)
増大特集 人工知能と神経科学
71巻6号(2019年6月発行)
特集 補体標的治療の現状と展望
71巻5号(2019年5月発行)
特集 NPSLE
71巻4号(2019年4月発行)
増大特集 神経学のための皮膚アトラス
71巻3号(2019年3月発行)
特集 Spine Neurology
71巻2号(2019年2月発行)
特集 “スポーツ”を生み出す脳
71巻1号(2019年1月発行)
特集 人工知能の医療応用Update
70巻12号(2018年12月発行)
特集 主訴に沿う—俯瞰し収束する画像診断の目
70巻11号(2018年11月発行)
増大特集 脳科学で解き明かす精神神経症候
70巻10号(2018年10月発行)
特集 「左脳と右脳」の現在
70巻9号(2018年9月発行)
特集 脳神経内科診療に役立つ精神科の知識
70巻8号(2018年8月発行)
特集 レヴィ小体型認知症の新知見
70巻7号(2018年7月発行)
増大特集 記憶と忘却に関わる脳のしくみ—分子機構から健忘の症候まで
70巻6号(2018年6月発行)
特集 芸術を生み出す脳
70巻5号(2018年5月発行)
特集 非アルツハイマー型認知症の病理学
70巻4号(2018年4月発行)
増大特集 Antibody Update 2018
70巻3号(2018年3月発行)
特集 『認知症疾患診療ガイドライン2017』を読み解く
70巻2号(2018年2月発行)
特集 知っておきたい神経感染症
70巻1号(2018年1月発行)
特集 筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群の今
69巻12号(2017年12月発行)
特集 運動異常症をみる—Web動画付録つき
69巻11号(2017年11月発行)
増大特集 こころの時間学の未来
69巻10号(2017年10月発行)
特集 成人てんかん—知っておきたい6つのトピック
69巻9号(2017年9月発行)
特集 ミクログリアと精神・神経疾患
69巻8号(2017年8月発行)
特集 遺伝性脊髄小脳失調症の病態と治療展望
69巻7号(2017年7月発行)
増大特集 あしたのアルツハイマー病治療
69巻6号(2017年6月発行)
特集 局在病変の神経心理学
69巻5号(2017年5月発行)
特集 Voxel-Based Morphometry—体積からわかること
69巻4号(2017年4月発行)
増大特集 ブロードマン領野の現在地
69巻3号(2017年3月発行)
特集 磁気刺激の新たな展開
69巻2号(2017年2月発行)
特集 Stroke-Like Diseases—鑑別時に注意を要する5病態
69巻1号(2017年1月発行)
特集 近年注目されている白質脳症
68巻12号(2016年12月発行)
特集 炎症性神経・筋疾患の新たな展開
68巻11号(2016年11月発行)
増大特集 連合野ハンドブック
68巻10号(2016年10月発行)
特集 アディクション—行動の嗜癖
68巻9号(2016年9月発行)
特集 自己免疫性脳炎・脳症
68巻8号(2016年8月発行)
特集 こころと汗
68巻7号(2016年7月発行)
増大特集 認知症の危険因子と防御因子
68巻6号(2016年6月発行)
特集 脳とフローラ
68巻5号(2016年5月発行)
特集 手の症候学—生理学・解剖学からみた新知見
68巻4号(2016年4月発行)
増大特集 治せる認知症
68巻3号(2016年3月発行)
特集 末梢神経の血管炎
68巻2号(2016年2月発行)
特集 筋疾患の認知機能障害
68巻1号(2016年1月発行)
特集 シャルコー・マリー・トゥース病
67巻12号(2015年12月発行)
特集 視床と高次脳機能
67巻11号(2015年11月発行)
増大特集 ギラン・バレー症候群のすべて—100年の軌跡
67巻10号(2015年10月発行)
特集 非・日常生活の脳科学
67巻9号(2015年9月発行)
特集 酵素補充療法
67巻8号(2015年8月発行)
特集 神経難病の終末期医療
67巻7号(2015年7月発行)
増大特集 神経疾患と感染症update
67巻6号(2015年6月発行)
特集 脳と「質感」
67巻5号(2015年5月発行)
特集 NCSE(非痙攣性てんかん重積状態)
67巻4号(2015年4月発行)
増大特集 大脳皮質vs.大脳白質
67巻3号(2015年3月発行)
特集 中枢神経の血管炎
67巻2号(2015年2月発行)
特集 「食べる」を考える
67巻1号(2015年1月発行)
特集 ニューロトキシコロジー
66巻12号(2014年12月発行)
特集 Orthopaedic Neurology—神経内科と整形外科の狭間で
66巻11号(2014年11月発行)
増大特集 神経症候学は神経学の“魂”である
66巻10号(2014年10月発行)
特集 分子を撃つ 神経疾患治療の新しい水平線
66巻9号(2014年9月発行)
特集 痙縮の臨床神経学
66巻8号(2014年8月発行)
特集 神経系の悪性リンパ腫update
66巻7号(2014年7月発行)
増大特集 アミロイド関連神経疾患のすべて―封入体筋炎からアルツハイマー病まで
66巻6号(2014年6月発行)
特集 ミラーニューロン
66巻5号(2014年5月発行)
特集 アセチルコリンと神経疾患―100年目の現在地
66巻4号(2014年4月発行)
増大特集 タッチ・ビジョン・アクション
66巻3号(2014年3月発行)
特集 神経筋疾患の超音波診断
66巻2号(2014年2月発行)
特集 糖尿病の神経学revisited
66巻1号(2014年1月発行)
特集 日常生活の脳科学
65巻12号(2013年12月発行)
特集 プロテイノパチーの神経病理学
65巻11号(2013年11月発行)
増大特集 Close Encounters―臨床神経学と臨床免疫学の遭遇と未来
65巻10号(2013年10月発行)
特集 神経系の発達メカニズム―最近の話題
65巻9号(2013年9月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である―現状と展望
65巻8号(2013年8月発行)
特集 こころの時間学―現在・過去・未来の起源を求めて
65巻7号(2013年7月発行)
増大特集 あしたの脳梗塞
65巻6号(2013年6月発行)
特集 見せる・仕分ける―脳機能解析の新手法
65巻5号(2013年5月発行)
特集 てんかん―新しいパースペクティブ
65巻4号(2013年4月発行)
増大特集 Antibody Update
65巻3号(2013年3月発行)
特集 次世代シーケンサーによる神経変性疾患の解析と展望
65巻2号(2013年2月発行)
特集 血液脳関門研究の進歩
65巻1号(2013年1月発行)
特集 Corticobasal Syndrome
64巻12号(2012年12月発行)
特集 The Border-Land of Dementia
64巻11号(2012年11月発行)
増大特集 痛みの神経学―末梢神経から脳まで
64巻10号(2012年10月発行)
特集 辺縁系をめぐって
64巻9号(2012年9月発行)
特集 高次脳機能イメージングの脳科学への新展開
64巻8号(2012年8月発行)
特集 線条体の基礎と臨床
64巻7号(2012年7月発行)
増大特集 顔認知の脳内機構
64巻6号(2012年6月発行)
特集 睡眠と覚醒の脳内機構
64巻5号(2012年5月発行)
特集 神経疾患のバイオマーカー
64巻4号(2012年4月発行)
増大特集 パーキンソン病の新しい側面
64巻3号(2012年3月発行)
特集 アカデミアから新規治療の実現へ―トランスレーショナルリサーチの現状
64巻2号(2012年2月発行)
特集 生物学的精神医学の進歩
64巻1号(2012年1月発行)
特集 iPS細胞と神経疾患
63巻12号(2011年12月発行)
特集 神経心理学と画像解析の融合
63巻11号(2011年11月発行)
増大特集 筋疾患update
63巻10号(2011年10月発行)
特集 緩徐進行性高次脳機能障害の病態
63巻9号(2011年9月発行)
特集 脳卒中の最新画像診断
63巻8号(2011年8月発行)
特集 日本人の発見した神経症候
63巻7号(2011年7月発行)
増大特集 神経筋接合部―基礎から臨床まで
63巻6号(2011年6月発行)
特集 ニューロパチー
63巻5号(2011年5月発行)
特集 神経系と血管内リンパ腫
63巻4号(2011年4月発行)
増大特集 てんかんの新しい治療
63巻3号(2011年3月発行)
特集 サイバーナイフ治療
63巻2号(2011年2月発行)
特集 続・日本人の発見した神経疾患
63巻1号(2011年1月発行)
特集 血管腫
62巻12号(2010年12月発行)
特集 頸部頸動脈狭窄症の診断と治療
62巻11号(2010年11月発行)
増大特集 歩行とその異常
62巻10号(2010年10月発行)
特集 ブレインバンク
62巻9号(2010年9月発行)
特集 視神経脊髄炎(NMO)update
62巻8号(2010年8月発行)
特集 辺縁系脳炎
62巻7号(2010年7月発行)
増大特集 アルツハイマー病―研究と診療の進歩
62巻6号(2010年6月発行)
特集 改正臓器移植法の問題点とその対応
62巻5号(2010年5月発行)
特集 神経画像のピットフォール―見落としと読み過ぎ
62巻4号(2010年4月発行)
特集 傍腫瘍性神経筋疾患update
62巻3号(2010年3月発行)
特集 神経回路解析法の最近の進歩
62巻2号(2010年2月発行)
特集 ニューロリハビリテーションの最前線
62巻1号(2010年1月発行)
特集 神経救急
61巻12号(2009年12月発行)
特集 Somatotopy再考
61巻11号(2009年11月発行)
特集 前頭側頭葉変性症
61巻10号(2009年10月発行)
特集 片頭痛の予防療法
61巻9号(2009年9月発行)
特集 脳血管障害治療の進歩
61巻8号(2009年8月発行)
特集 神経・筋疾患の分子標的治療
61巻7号(2009年7月発行)
特集 脳腫瘍研究の最前線―遺伝子解析から治療まで
61巻6号(2009年6月発行)
特集 脊椎・脊髄外科の最近の進歩
61巻5号(2009年5月発行)
特集 Restless legs syndrome
61巻4号(2009年4月発行)
特集 大脳基底核―分子基盤から臨床まで
61巻3号(2009年3月発行)
特集 Microneurography(微小神経電図法)の臨床応用
61巻2号(2009年2月発行)
特集 神経系の再興感染症と輸入感染症
61巻1号(2009年1月発行)
特集 脳神経倫理
60巻12号(2008年12月発行)
特集 痙縮
60巻11号(2008年11月発行)
特集 脳卒中と遺伝子
60巻10号(2008年10月発行)
特集 若年者の脳卒中
60巻9号(2008年9月発行)
特集 知・情・意の神経学
60巻8号(2008年8月発行)
特集 脳硬膜動静脈瘻
60巻7号(2008年7月発行)
増大特集 学習と記憶――基礎と臨床
60巻6号(2008年6月発行)
特集 Crow-深瀬症候群(POEMS症候群)
60巻5号(2008年5月発行)
特集 「痛み」の研究と治療の最前線
60巻4号(2008年4月発行)
増大特集 神経系の発生とその異常
60巻3号(2008年3月発行)
特集 特発性正常圧水頭症(iNPH)―最近の話題
60巻2号(2008年2月発行)
特集 がん治療と神経障害
60巻1号(2008年1月発行)
特集 日本人の発見した神経疾患
59巻12号(2007年12月発行)
特集 損傷神経の再生―温存的治療法の開発
59巻11号(2007年11月発行)
特集 手根管症候群をめぐって
59巻10号(2007年10月発行)
増大特集 ALS―研究と診療の進歩
59巻9号(2007年9月発行)
特集 パーキンソン病の認知機能障害
59巻8号(2007年8月発行)
特集 パーキンソン病の分子遺伝学―最近の知見
59巻7号(2007年7月発行)
増大特集 情報伝達処理におけるグリアの機能と異常
59巻6号(2007年6月発行)
特集 職業性神経障害の新しい展開
59巻5号(2007年5月発行)
特集 脳画像最前線
59巻4号(2007年4月発行)
増大特集 最近注目される脳神経疾患治療の研究
59巻3号(2007年3月発行)
特集 分子イメージング
59巻2号(2007年2月発行)
特集 進行性多巣性白質脳症の新しい展開―PMLが治る時代へ向けて
59巻1号(2007年1月発行)
特集 高次視覚研究の最近の進歩
