片頭痛・群発頭痛に対して,ゲパントや抗CGRP抗体などのCGRP関連薬剤,ニューロモデュレーション治療などが臨床応用され,まさに新たな夜明けを迎えている。しかし急性期治療と予防療法の使い分けなど,専門医に対してもこれらの治療についての情報が十分に届いていない状況である。これらの治療法を理解するための基本的知識,臨床試験のエビデンス,ならびに使用方法や本邦における見通しについて学ぶ機会としたい。脳神経内科医をはじめとして総合診療医,小児科医,脳神経外科医,ペインクリニシャンなど頭痛診療に関わる多くの医師にも読んでいただきたい。
雑誌目次
BRAIN and NERVE-神経研究の進歩73巻4号
2021年04月発行
雑誌目次
特集 片頭痛・群発頭痛治療の新たな夜明け
片頭痛のメカニズム—予兆とCGRP/CGRP受容体拮抗薬に関連して
著者: 粟木悦子 , 竹島多賀夫
ページ範囲:P.303 - P.313
片頭痛の発症メカニズムはいまだ不明である。予兆は一連の片頭痛発作の中で最初に認められる症状であり,その研究は片頭痛発生源解明につながるとして近年あらためて関心が高まっている。特に予兆症状と視床下部との関連が示唆されている。また,片頭痛メカニズムにおけるカルシトニン遺伝子関連ペプチドの役割について,血管拡張,神経性炎症,末梢感作といった末梢作用のみならず,光過敏,中枢感作,皮質拡延性抑制などと関連する中枢作用についても多くの知見が集まりつつある。
ゲパントとディタン
著者: 古和久典
ページ範囲:P.315 - P.325
近年,カルシトニン遺伝子関連ペプチド(CGRP)が片頭痛発作の症状に主たる役割を果たしており,発作予防や治療を考えるうえでCGRPシグナル伝達の遮断が有効であることが示唆されるようになった。2つの新たなクラスの治療薬,ゲパントとディタンは,ともにCGRP放出抑制効果を有している一方で,従来のトリプタン系薬が有する血管収縮作用は持っていない。心血管の危険因子を持つ患者やトリプタンに反応しない患者に対して投与可能な薬剤として,わが国においても臨床現場での登場がまたれている。
CGRP関連抗体の片頭痛治療への応用
著者: 柴田護
ページ範囲:P.327 - P.337
片頭痛は有病率が高く,個々の患者のQOLが大きく障害されることから,社会全体に与える経済的悪影響は甚大である。片頭痛は視床下部,大脳皮質,三叉神経系などの機能異常に基づく神経疾患である。従来の片頭痛発作予防治療薬は疾患特異的に開発されたものではなく,十分な効果が得られないことも多い。カルシトニン遺伝子関連ペプチド(CGRP)が片頭痛病態に深く関与することが明らかとなり,CGRP関連抗体による治療法が脚光を浴びている。
片頭痛・群発頭痛治療における非侵襲的ニューロモデュレーション
著者: 團野大介
ページ範囲:P.339 - P.346
片頭痛・群発頭痛の薬物治療は不十分な治療効果や有害事象によるアドヒアランス低下が問題となっている。一方,非侵襲的ニューロモデュレーションは手術不要で比較的安価であり重篤な有害事象がないため,近年注目を集めつつある。経皮的三叉神経刺激装置,および経頭蓋磁気刺激装置が片頭痛の急性期治療および予防療法に,非侵襲的迷走神経刺激装置が片頭痛・群発頭痛の急性期治療および予防療法に有効である。
群発頭痛の新しい治療
著者: 今井昇
ページ範囲:P.347 - P.355
抗カルシトニン遺伝子関連ペプチドモノクローナル抗体薬であるガルカネズマブは,プラセボ対照無作為化二重盲検比較試験(RCT)で有効性と安全性が認められ,米国食品医薬品局で反復性群発頭痛の予防薬として承認されている。また,翼口蓋神経節刺激療法は,慢性群発頭痛の急性期治療としてRCTで有効性と安全性が確認されている。本論では,これらの治療法の作用機序,臨床試験での結果,臨床での使用方法,本邦における見通しについて概説する。
総説
双極性障害の原因を探る—ミトコンドリア仮説とその先
著者: 加藤忠史
ページ範囲:P.359 - P.367
双極性障害ではゲノム要因の関与などは明らかであるが,その病態についてはいまだ不明な点が多い。われわれは2000年にミトコンドリア機能障害仮説を提案し,その検証を進めてきた。その結果,ミトコンドリアDNA(mtDNA)多型がミトコンドリア内Ca2+濃度に影響すること,mtDNA変異が脳に蓄積するマウス(変異Polgトランスジェニックマウス)ではミトコンドリアのCa2+取込みおよび細胞内Ca2+シグナリングが変化し,自発性の反復性抑うつエピソードを呈することなどを見出した。このマウスにおいて,変異mtDNAが蓄積している部位を探索した結果,視床室傍核に最も多く蓄積していることを見出した。視床室傍核の神経回路操作により,同様の反復性の低活動状態が出現することから,視床室傍核が双極性障害の原因に関わっている可能性が考えられた。
神経性食思不振症に対する機能的脳神経外科治療
著者: 小原亘太郎 , 平孝臣 , 堀澤士朗 , 川俣貴一
ページ範囲:P.369 - P.377
神経性食思不振症はボディーイメージの歪みから極端な体重減少をきたす重篤な精神疾患で,薬剤加療や心理療法などでは改善が得られない場合も少なくない。本邦では現在,精神疾患に対する脳神経外科的治療はまったく行われていないが,諸外国では難治性精神疾患に対してさまざまな機能的脳神経外科治療が行われ,有効性が報告されてきた。神経性食思不振症に対して行われた脳神経機能への介入治療の中で代表的なものを紹介する。
症例報告
側副血行路起始部(A1)と前交通動脈に未破裂脳動脈瘤を伴う無症候性aplastic or twig-like middle cerebral artery—動脈硬化性頭蓋内血管多発狭窄を合併した1例
著者: 副島航介 , 日宇健 , 塩崎絵理 , 小川由夏 , 伊藤健大 , 本田和也 , 諸藤陽一 , 川原一郎 , 小野智憲 , 原口渉 , 堤圭介
ページ範囲:P.379 - P.388
無症候性Ap/T-MCAの側副血行路起始部(A1)に発生した未破裂A1動脈瘤を経験した。当初動脈硬化性病変と捉えていたが,詳細な画像検査と術中所見からAp/T-MCAと診断した。動脈瘤破裂による出血例が多い破格であり,二次的に動脈硬化が合併している可能性にも留意すべきである。小型でも破裂しやすく,未破裂動脈瘤には積極的なバイパス併用根治術もオプションの1つとなり得るが,さらなる知見の集積が必要である。
連載 臨床神経学プロムナード—60余年を顧みて・2
易しそうで難しい腱反射—Babinskiの原著:必読と言われる所以
著者: 平山惠造
ページ範囲:P.389 - P.391
腱反射検査法(診察法)は足底皮膚反射と並んでBabinski(1912)1)の大きな業績の一つである。彼の業績集(1934)の冒頭に相次いで収録されている。しかし腱反射の検討は彼以前に既に始まっていたようで(一説には1875年頃と言われる),実際にCharcotの「火曜講義」(1892)2)の中の挿絵の隅にハンマーが描かれているものがある。また,Charcotの「金曜講義」に再録されているJoffroyとの筋萎縮性側索硬化症(ALS)の最初の報告例(1869)3)の臨床記述の中に「前腕背面に軽い打撃を加えると指(複数)や手全体に著明な伸展運動を来たす」という記述がある。まさに指伸筋群の腱反射亢進を示している。
Babinskiが本格的に腱反射の臨床的研究に取り組んだ背景には当時Charcotが取り組んでいたいわゆるヒステリー性麻痺と器質的運動麻痺との鑑別にあったようであるが,Charcotの没後に,もっと広く腱反射そのものの研究に取り組んだ。その徹底振りは原著を見れば一目瞭然である。腱反射の歴史から始まり,動物実験による生理学的所見に触れた後で,腱反射の診察法を説き,健常な場合からいろいろな病態における解説を行っている。彼はこれを1912年10月から11月にかけ,4回に分けてPitié病院で講義した1)(上記の業績集で49頁を占めている)。その全訳が雑誌「内科」(1960)1)に収載されているので容易に知ることが出来よう。
書評
「—レジデントのための—感染症診療マニュアル 第4版」—青木 眞【著】 フリーアクセス
著者: 岩田健太郎
ページ範囲:P.357 - P.357
本書の第3版が出たときも書評を書かせていただいたが(2015年),力を込めすぎついつい長文になってしまった(https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/84707#tab4)。今回は「800〜1,400字で」,と編集部から注文がついている。宴席でスピーチが長すぎるおじさんがあらかじめくぎを刺されている様相だが,その「宴席」もいずれ死語になるやもしれぬ今日この頃だ。
というわけで,今回は短く書かせていただく。
「—医療者のための—成功するメンタリングガイド」—徳田安春【監訳】 フリーアクセス
著者: 和足孝之
ページ範囲:P.358 - P.358
むさぼるように読んでしまった。一言で言うと,本気で悔しい。書籍を読んで悔しいと感じることはそうそうないが,今回ばかりは,今までの医師人生で苦労して,本気で悩んだことや,嬉しいこと悲しいこと,研修医や医学生が急激に成長して部分的に自分を超えた瞬間のアノ複雑な心境までも,これまで時間をかけてようやく感得してきた経験値(誰にも言わずにこっそり隠し持っていたもの)を完全に勝手に暴露された気がした。
メンターが行うべき実践手法や考え方,そのいちいちすべてが,自分が優れたメンターを観察して苦労して学んだこと,数多くのメンティー達と接したときに生じた悩みや,研修医や医学生が抱えていることが多い相談内容にぴったりとフィットしているのだ。何を隠そう,大学教員である自分は一時期やる気がない(ように見える?)医学生や研修医に対してすごく悩んだ。若さゆえの過ちというやつか,誰にでも公平にできるだけ丁寧なよい教育を‼ と鼻息荒く取り組んでいた。結果的に,うまくいかず苦しかった。しかしある日,原著者のDr. Chopra & Dr. Saintが発表した「メンターが心得るべき6つの事」という論文を読んで自分の考えは完全に間違っていたと悟った。その答えは本書の中にあるので,ぜひ手に取って読んでほしい。
お知らせ
第32回日本末梢神経学会学術集会 フリーアクセス
ページ範囲:P.346 - P.346
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.299 - P.299
欧文目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.300 - P.300
バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.396 - P.396
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.397 - P.397
あとがき フリーアクセス
著者: 虫明元
ページ範囲:P.398 - P.398
今月の特集の「片頭痛・群発頭痛治療の新たな夜明け」は,治療に焦点を絞りつつ,その原因となる神経機構に関しても理解が進んでいることを実感した。具体的には脳血管の拡張・収縮に関わる多様な神経ペプチドの理解,画像解析などからの大脳皮質〜脳幹の片頭痛の各ステージでの詳細な解析,神経モデュレーション法の効果が及ぶ神経基盤の理解など,治療法を紹介しながらも新しい病態理解の道が示されている。
一方で,システム生理学的な立場として,このような複雑な病態の起こるメカニズムはどのようになっているのかが知りたいと思った。生理学ではホメオスタシスというメカニズムがあり,身体内外の環境からの外乱・ストレスに対して,内部環境を保持する機構が知られている。脳の場合は,神経活動,代謝,血流が絶妙に調整され,必要な部位に必要なものが届けられ,一定環境を守るように調節されている。一方でホメオスタシスを構成するどこかの感受性が,繰り返されるストレスに対して,次第に変化をして動的に適応することも知られている。しかし,その適応の仕方には個人個人の感受性の違いがあり,レジリエンスより脆弱性が表に出るとき,適応は望ましくない方向に振れる場合があることが知られている。
基本情報
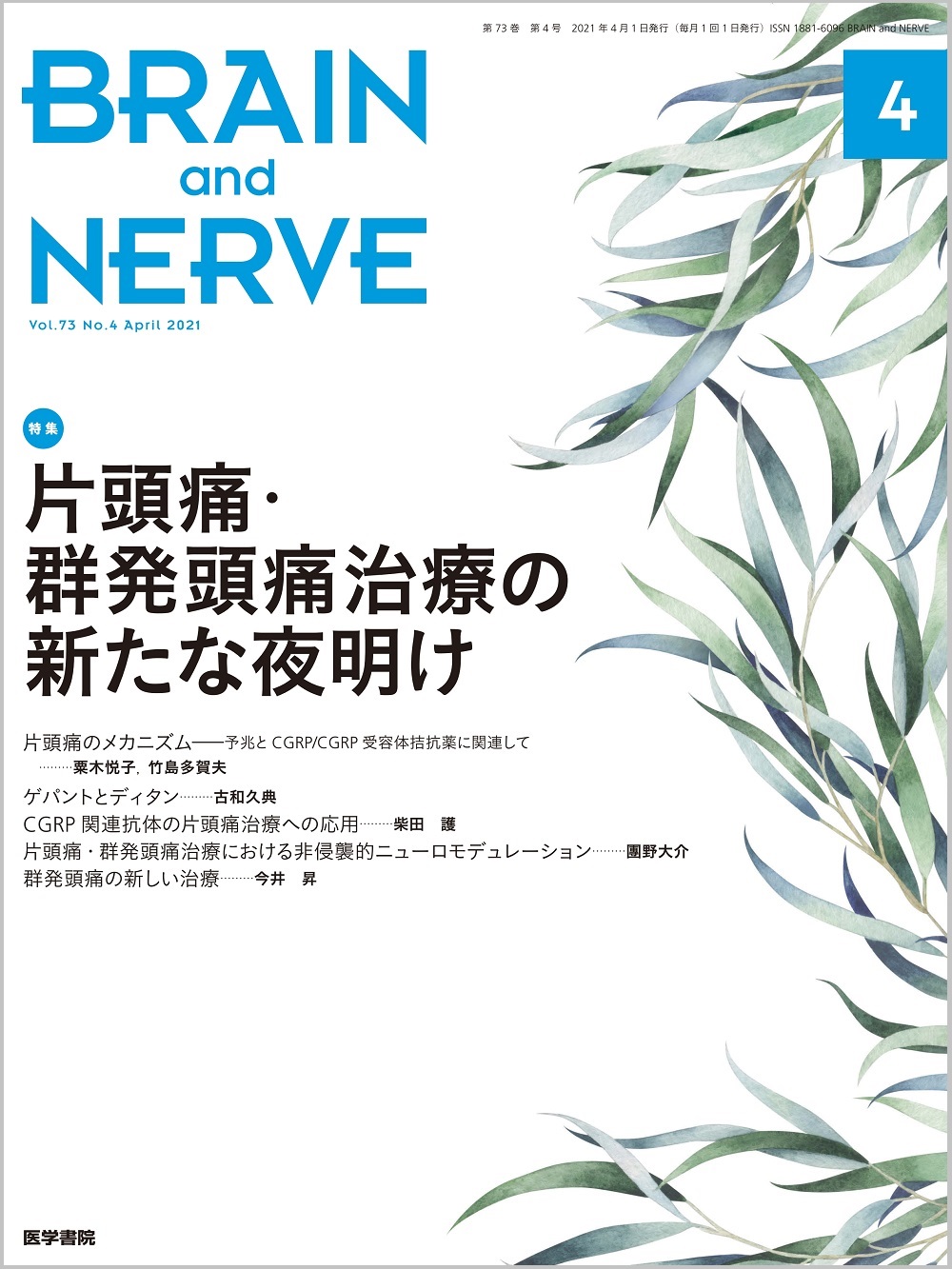
バックナンバー
76巻12号(2024年12月発行)
特集 芸術家と神経学Ⅱ
76巻11号(2024年11月発行)
特集 ALS 2024
76巻10号(2024年10月発行)
特集 どうして効くんだろう
76巻9号(2024年9月発行)
特集 治療可能な認知症としてのアルツハイマー病
76巻8号(2024年8月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である—revisited
76巻7号(2024年7月発行)
特集 ニューロ・バイオイメージング—技術と応用
76巻6号(2024年6月発行)
特集 注意と注意障害
76巻5号(2024年5月発行)
増大特集 末梢神経・筋肉の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
76巻4号(2024年4月発行)
特集 神経病理最前線
76巻3号(2024年3月発行)
特集 きちんと説明ができますか?
76巻2号(2024年2月発行)
特集 特発性正常圧水頭症の現在
76巻1号(2024年1月発行)
特集 新時代の重症筋無力症と関連疾患の診療
75巻12号(2023年12月発行)
特集 アガサ・クリスティーと神経毒
75巻11号(2023年11月発行)
特集 アロスタシス—ホメオスタシスを超えて
75巻10号(2023年10月発行)
特集 メタバースへの招待
75巻9号(2023年9月発行)
特集 妊娠と神経疾患
75巻8号(2023年8月発行)
特集 アルツハイマー病は本当に早期発見できるのか
75巻7号(2023年7月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part2 末梢編
75巻6号(2023年6月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part1 中枢編
75巻5号(2023年5月発行)
増大特集 神経・精神領域の薬剤ハンドブック
75巻4号(2023年4月発行)
特集 All About Epilepsy
75巻3号(2023年3月発行)
特集 慢性疼痛
75巻2号(2023年2月発行)
特集 多系統萎縮症の新診断基準とこれからの診療
75巻1号(2023年1月発行)
特集 よく出会う不随意運動を知る
74巻12号(2022年12月発行)
特集 映画を観て精神・神経疾患を知る
74巻11号(2022年11月発行)
特集 RFC1遺伝子関連スペクトラム障害
74巻10号(2022年10月発行)
特集 ウイルス性脳炎・脳症2022
74巻9号(2022年9月発行)
特集 動的環境への適応系としての歩行
74巻8号(2022年8月発行)
特集 迷走神経の不思議
74巻7号(2022年7月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識2022
74巻6号(2022年6月発行)
特集 脳神経内科医に求められる移行医療
74巻5号(2022年5月発行)
増大特集 次の一手—神経筋疾患難治例をどのように治療するか
74巻4号(2022年4月発行)
特集 脳科学リテラシーを高めるために
74巻3号(2022年3月発行)
特集 中枢性自律神経障害update
74巻2号(2022年2月発行)
特集 温度を感じる脳と身体の科学
74巻1号(2022年1月発行)
特集 脳神経内科医のキャリアパスとリーダーシップ
73巻12号(2021年12月発行)
特集 芸術家と神経学
73巻11号(2021年11月発行)
特集 「目」の神経学
73巻10号(2021年10月発行)
特集 中枢神経・末梢神経の悪性リンパ腫
73巻9号(2021年9月発行)
特集 脳卒中治療に必要な基礎知識
73巻8号(2021年8月発行)
特集 脳腸相関—脳-身体の双方向性制御
73巻7号(2021年7月発行)
特集 グリアと神経—相補的な制御系として
73巻6号(2021年6月発行)
特集 Lower Spine Neurology
73巻5号(2021年5月発行)
増大特集 中枢神経の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
73巻4号(2021年4月発行)
特集 片頭痛・群発頭痛治療の新たな夜明け
73巻3号(2021年3月発行)
特集 マルチリンガルブレイン
73巻2号(2021年2月発行)
特集 筋炎と壊死性筋症
73巻1号(2021年1月発行)
特集 Neuro-Oncology
72巻12号(2020年12月発行)
特集 超高齢期の精神神経疾患を診る
72巻11号(2020年11月発行)
増大特集 脳の発振現象—基礎から臨床へ
72巻10号(2020年10月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識
72巻9号(2020年9月発行)
特集 皮質性小脳萎縮症へのアプローチ
72巻8号(2020年8月発行)
特集 サルコイドーシス
72巻7号(2020年7月発行)
増大特集 神経倫理ハンドブック
72巻6号(2020年6月発行)
特集 前頭側頭葉変性症の今日的理解
72巻5号(2020年5月発行)
特集 多発性硬化症の現在と未来
72巻4号(2020年4月発行)
増大特集 神経疾患の診断における落とし穴—誤診を避けるために
72巻3号(2020年3月発行)
特集 でこぼこの脳の中でおしくらまんじゅうする脳機能
72巻2号(2020年2月発行)
特集 αシヌクレイノパチーの新たな展開
72巻1号(2020年1月発行)
特集 神経難病をクスリで治す—薬物開発の現況と近未来への展望
71巻12号(2019年12月発行)
特集 小脳と大脳—Masao Itoのレガシー
71巻11号(2019年11月発行)
増大特集 ALS2019
71巻10号(2019年10月発行)
特集 認知症と遺伝
71巻9号(2019年9月発行)
特集 神経疾患のドラッグ・リポジショニング—新時代へ
71巻8号(2019年8月発行)
特集 パーキンソン病診療の現在地—200年の変遷と新規治療
71巻7号(2019年7月発行)
増大特集 人工知能と神経科学
71巻6号(2019年6月発行)
特集 補体標的治療の現状と展望
71巻5号(2019年5月発行)
特集 NPSLE
71巻4号(2019年4月発行)
増大特集 神経学のための皮膚アトラス
71巻3号(2019年3月発行)
特集 Spine Neurology
71巻2号(2019年2月発行)
特集 “スポーツ”を生み出す脳
71巻1号(2019年1月発行)
特集 人工知能の医療応用Update
70巻12号(2018年12月発行)
特集 主訴に沿う—俯瞰し収束する画像診断の目
70巻11号(2018年11月発行)
増大特集 脳科学で解き明かす精神神経症候
70巻10号(2018年10月発行)
特集 「左脳と右脳」の現在
70巻9号(2018年9月発行)
特集 脳神経内科診療に役立つ精神科の知識
70巻8号(2018年8月発行)
特集 レヴィ小体型認知症の新知見
70巻7号(2018年7月発行)
増大特集 記憶と忘却に関わる脳のしくみ—分子機構から健忘の症候まで
70巻6号(2018年6月発行)
特集 芸術を生み出す脳
70巻5号(2018年5月発行)
特集 非アルツハイマー型認知症の病理学
70巻4号(2018年4月発行)
増大特集 Antibody Update 2018
70巻3号(2018年3月発行)
特集 『認知症疾患診療ガイドライン2017』を読み解く
70巻2号(2018年2月発行)
特集 知っておきたい神経感染症
70巻1号(2018年1月発行)
特集 筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群の今
69巻12号(2017年12月発行)
特集 運動異常症をみる—Web動画付録つき
69巻11号(2017年11月発行)
増大特集 こころの時間学の未来
69巻10号(2017年10月発行)
特集 成人てんかん—知っておきたい6つのトピック
69巻9号(2017年9月発行)
特集 ミクログリアと精神・神経疾患
69巻8号(2017年8月発行)
特集 遺伝性脊髄小脳失調症の病態と治療展望
69巻7号(2017年7月発行)
増大特集 あしたのアルツハイマー病治療
69巻6号(2017年6月発行)
特集 局在病変の神経心理学
69巻5号(2017年5月発行)
特集 Voxel-Based Morphometry—体積からわかること
69巻4号(2017年4月発行)
増大特集 ブロードマン領野の現在地
69巻3号(2017年3月発行)
特集 磁気刺激の新たな展開
69巻2号(2017年2月発行)
特集 Stroke-Like Diseases—鑑別時に注意を要する5病態
69巻1号(2017年1月発行)
特集 近年注目されている白質脳症
68巻12号(2016年12月発行)
特集 炎症性神経・筋疾患の新たな展開
68巻11号(2016年11月発行)
増大特集 連合野ハンドブック
68巻10号(2016年10月発行)
特集 アディクション—行動の嗜癖
68巻9号(2016年9月発行)
特集 自己免疫性脳炎・脳症
68巻8号(2016年8月発行)
特集 こころと汗
68巻7号(2016年7月発行)
増大特集 認知症の危険因子と防御因子
68巻6号(2016年6月発行)
特集 脳とフローラ
68巻5号(2016年5月発行)
特集 手の症候学—生理学・解剖学からみた新知見
68巻4号(2016年4月発行)
増大特集 治せる認知症
68巻3号(2016年3月発行)
特集 末梢神経の血管炎
68巻2号(2016年2月発行)
特集 筋疾患の認知機能障害
68巻1号(2016年1月発行)
特集 シャルコー・マリー・トゥース病
67巻12号(2015年12月発行)
特集 視床と高次脳機能
67巻11号(2015年11月発行)
増大特集 ギラン・バレー症候群のすべて—100年の軌跡
67巻10号(2015年10月発行)
特集 非・日常生活の脳科学
67巻9号(2015年9月発行)
特集 酵素補充療法
67巻8号(2015年8月発行)
特集 神経難病の終末期医療
67巻7号(2015年7月発行)
増大特集 神経疾患と感染症update
67巻6号(2015年6月発行)
特集 脳と「質感」
67巻5号(2015年5月発行)
特集 NCSE(非痙攣性てんかん重積状態)
67巻4号(2015年4月発行)
増大特集 大脳皮質vs.大脳白質
67巻3号(2015年3月発行)
特集 中枢神経の血管炎
67巻2号(2015年2月発行)
特集 「食べる」を考える
67巻1号(2015年1月発行)
特集 ニューロトキシコロジー
66巻12号(2014年12月発行)
特集 Orthopaedic Neurology—神経内科と整形外科の狭間で
66巻11号(2014年11月発行)
増大特集 神経症候学は神経学の“魂”である
66巻10号(2014年10月発行)
特集 分子を撃つ 神経疾患治療の新しい水平線
66巻9号(2014年9月発行)
特集 痙縮の臨床神経学
66巻8号(2014年8月発行)
特集 神経系の悪性リンパ腫update
66巻7号(2014年7月発行)
増大特集 アミロイド関連神経疾患のすべて―封入体筋炎からアルツハイマー病まで
66巻6号(2014年6月発行)
特集 ミラーニューロン
66巻5号(2014年5月発行)
特集 アセチルコリンと神経疾患―100年目の現在地
66巻4号(2014年4月発行)
増大特集 タッチ・ビジョン・アクション
66巻3号(2014年3月発行)
特集 神経筋疾患の超音波診断
66巻2号(2014年2月発行)
特集 糖尿病の神経学revisited
66巻1号(2014年1月発行)
特集 日常生活の脳科学
65巻12号(2013年12月発行)
特集 プロテイノパチーの神経病理学
65巻11号(2013年11月発行)
増大特集 Close Encounters―臨床神経学と臨床免疫学の遭遇と未来
65巻10号(2013年10月発行)
特集 神経系の発達メカニズム―最近の話題
65巻9号(2013年9月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である―現状と展望
65巻8号(2013年8月発行)
特集 こころの時間学―現在・過去・未来の起源を求めて
65巻7号(2013年7月発行)
増大特集 あしたの脳梗塞
65巻6号(2013年6月発行)
特集 見せる・仕分ける―脳機能解析の新手法
65巻5号(2013年5月発行)
特集 てんかん―新しいパースペクティブ
65巻4号(2013年4月発行)
増大特集 Antibody Update
65巻3号(2013年3月発行)
特集 次世代シーケンサーによる神経変性疾患の解析と展望
65巻2号(2013年2月発行)
特集 血液脳関門研究の進歩
65巻1号(2013年1月発行)
特集 Corticobasal Syndrome
64巻12号(2012年12月発行)
特集 The Border-Land of Dementia
64巻11号(2012年11月発行)
増大特集 痛みの神経学―末梢神経から脳まで
64巻10号(2012年10月発行)
特集 辺縁系をめぐって
64巻9号(2012年9月発行)
特集 高次脳機能イメージングの脳科学への新展開
64巻8号(2012年8月発行)
特集 線条体の基礎と臨床
64巻7号(2012年7月発行)
増大特集 顔認知の脳内機構
64巻6号(2012年6月発行)
特集 睡眠と覚醒の脳内機構
64巻5号(2012年5月発行)
特集 神経疾患のバイオマーカー
64巻4号(2012年4月発行)
増大特集 パーキンソン病の新しい側面
64巻3号(2012年3月発行)
特集 アカデミアから新規治療の実現へ―トランスレーショナルリサーチの現状
64巻2号(2012年2月発行)
特集 生物学的精神医学の進歩
64巻1号(2012年1月発行)
特集 iPS細胞と神経疾患
63巻12号(2011年12月発行)
特集 神経心理学と画像解析の融合
63巻11号(2011年11月発行)
増大特集 筋疾患update
63巻10号(2011年10月発行)
特集 緩徐進行性高次脳機能障害の病態
63巻9号(2011年9月発行)
特集 脳卒中の最新画像診断
63巻8号(2011年8月発行)
特集 日本人の発見した神経症候
63巻7号(2011年7月発行)
増大特集 神経筋接合部―基礎から臨床まで
63巻6号(2011年6月発行)
特集 ニューロパチー
63巻5号(2011年5月発行)
特集 神経系と血管内リンパ腫
63巻4号(2011年4月発行)
増大特集 てんかんの新しい治療
63巻3号(2011年3月発行)
特集 サイバーナイフ治療
63巻2号(2011年2月発行)
特集 続・日本人の発見した神経疾患
63巻1号(2011年1月発行)
特集 血管腫
62巻12号(2010年12月発行)
特集 頸部頸動脈狭窄症の診断と治療
62巻11号(2010年11月発行)
増大特集 歩行とその異常
62巻10号(2010年10月発行)
特集 ブレインバンク
62巻9号(2010年9月発行)
特集 視神経脊髄炎(NMO)update
62巻8号(2010年8月発行)
特集 辺縁系脳炎
62巻7号(2010年7月発行)
増大特集 アルツハイマー病―研究と診療の進歩
62巻6号(2010年6月発行)
特集 改正臓器移植法の問題点とその対応
62巻5号(2010年5月発行)
特集 神経画像のピットフォール―見落としと読み過ぎ
62巻4号(2010年4月発行)
特集 傍腫瘍性神経筋疾患update
62巻3号(2010年3月発行)
特集 神経回路解析法の最近の進歩
62巻2号(2010年2月発行)
特集 ニューロリハビリテーションの最前線
62巻1号(2010年1月発行)
特集 神経救急
61巻12号(2009年12月発行)
特集 Somatotopy再考
61巻11号(2009年11月発行)
特集 前頭側頭葉変性症
61巻10号(2009年10月発行)
特集 片頭痛の予防療法
61巻9号(2009年9月発行)
特集 脳血管障害治療の進歩
61巻8号(2009年8月発行)
特集 神経・筋疾患の分子標的治療
61巻7号(2009年7月発行)
特集 脳腫瘍研究の最前線―遺伝子解析から治療まで
61巻6号(2009年6月発行)
特集 脊椎・脊髄外科の最近の進歩
61巻5号(2009年5月発行)
特集 Restless legs syndrome
61巻4号(2009年4月発行)
特集 大脳基底核―分子基盤から臨床まで
61巻3号(2009年3月発行)
特集 Microneurography(微小神経電図法)の臨床応用
61巻2号(2009年2月発行)
特集 神経系の再興感染症と輸入感染症
61巻1号(2009年1月発行)
特集 脳神経倫理
60巻12号(2008年12月発行)
特集 痙縮
60巻11号(2008年11月発行)
特集 脳卒中と遺伝子
60巻10号(2008年10月発行)
特集 若年者の脳卒中
60巻9号(2008年9月発行)
特集 知・情・意の神経学
60巻8号(2008年8月発行)
特集 脳硬膜動静脈瘻
60巻7号(2008年7月発行)
増大特集 学習と記憶――基礎と臨床
60巻6号(2008年6月発行)
特集 Crow-深瀬症候群(POEMS症候群)
60巻5号(2008年5月発行)
特集 「痛み」の研究と治療の最前線
60巻4号(2008年4月発行)
増大特集 神経系の発生とその異常
60巻3号(2008年3月発行)
特集 特発性正常圧水頭症(iNPH)―最近の話題
60巻2号(2008年2月発行)
特集 がん治療と神経障害
60巻1号(2008年1月発行)
特集 日本人の発見した神経疾患
59巻12号(2007年12月発行)
特集 損傷神経の再生―温存的治療法の開発
59巻11号(2007年11月発行)
特集 手根管症候群をめぐって
59巻10号(2007年10月発行)
増大特集 ALS―研究と診療の進歩
59巻9号(2007年9月発行)
特集 パーキンソン病の認知機能障害
59巻8号(2007年8月発行)
特集 パーキンソン病の分子遺伝学―最近の知見
59巻7号(2007年7月発行)
増大特集 情報伝達処理におけるグリアの機能と異常
59巻6号(2007年6月発行)
特集 職業性神経障害の新しい展開
59巻5号(2007年5月発行)
特集 脳画像最前線
59巻4号(2007年4月発行)
増大特集 最近注目される脳神経疾患治療の研究
59巻3号(2007年3月発行)
特集 分子イメージング
59巻2号(2007年2月発行)
特集 進行性多巣性白質脳症の新しい展開―PMLが治る時代へ向けて
59巻1号(2007年1月発行)
特集 高次視覚研究の最近の進歩
