神経系の構成要素であるニューロンとグリアはともに約150年前に発見され,これまでの研究によってニューロンの機能や役割については理解が深まってきたが,グリアについては研究が進んでこなかった。しかし,近年の光遺伝学をはじめとした研究技術の発展により,正常脳あるいは精神神経疾患をモデルとした病態脳でのグリアの振舞いが明らかになってきた。本特集では,こうしたグリアの動態を,構成要素であるアストロサイト,オリゴデンドロサイト,ミクログリアそれぞれについて論じていただく。
雑誌目次
BRAIN and NERVE-神経研究の進歩73巻7号
2021年07月発行
雑誌目次
特集 グリアと神経—相補的な制御系として
先端技術が明かすアストロサイトの回路・行動における機能
著者: 出羽健一 , 長井淳
ページ範囲:P.755 - P.768
最も数の多いグリアであるアストロサイトは,無数の微細突起を介してニューロンやシナプスに接触する。約150年前にニューロンと一緒に発見され,長い間単なる支持細胞とみなされてきた。近年の遺伝学,光学,蛋白質工学の進展は,アストロサイト研究に必要なツールを提供した。本論では,これまでのツールの留意点,改善された実験ツール,それらによる発見,および将来の開発の方向性を概説する。
脳内デュアルレイヤー情報処理機構とその破綻による脳病態機序
著者: 松井広
ページ範囲:P.769 - P.779
脳内には,神経回路とグリア回路のデュアルレイヤーの情報処理回路が存在し,両者は緩やかに相互作用をする超回路を形成する。神経細胞の活動に応答し,グリア細胞はグルタミン酸を放出することが示された。まったく同じ経験をしても,記憶されるときとされないときとがあるが,グリア細胞の機能を操作することで効果的な学習が成立する可能性がある。てんかんを含む脳機能疾患は,この超回路機構の破綻が1つの原因となると考えられる。
グリアアセンブリと脳疾患
著者: 小泉修一
ページ範囲:P.781 - P.786
グリア細胞は集合体「アセンブリ」として機能する。このグリアアセンブリは,脳機能制御におけるグリア細胞の役割,特に各種脳疾患におけるグリア細胞の役割の理解に必須である。非侵襲的な軽度脳卒中を経験すると,その後の侵襲的な脳卒中に対する抵抗性が獲得される「虚血耐性」が誘導される。実行細胞としてアストロサイトが中心的な役割を果たすが,これにはミクログリアを含めたグリアアセンブリとしての機能が必須である。
精神疾患の新たな展望—グリア破綻から見る病態
著者: 有岡祐子 , 加藤大輔 , 和氣弘明 , 尾崎紀夫
ページ範囲:P.787 - P.794
精神疾患の病態はいまだ不明であり,病態に基づく診断・治療法開発は進んでいない。この現状を打破するには,精神症状に依拠した現在の診断分類や既存の病態仮説にとらわれない新しい視点が求められる。近年,グリアが正常な脳機能や回路形成に積極的に関与すること,その破綻が精神疾患の病態につながり得ることを示す知見が報告されている。本論では,グリア病態から見た精神疾患について,われわれの取組みとともに紹介する。
ストレスを介したミクログリア活性化と精神疾患—双方向性研究アプローチ
著者: 榎本真悟 , 加藤隆弘
ページ範囲:P.795 - P.802
ストレスはうつ病や心的外傷後ストレス障害(PTSD)の誘因であり,それらの疾患の病態にミクログリアの過剰活性化や機能不全が関与していることを示唆する知見が現在集まってきている。本論では,PTSDに特徴的な恐怖記憶制御不全を示す動物モデルでのミクログリアの機能変化と,ミクログリアに焦点を絞ったヒトを対象とするうつ病およびPTSD研究の知見を紹介する。ヒトとモデル動物での双方向性研究が,病態解明と治療法開発のために必要である。
脊髄後角での痛覚信号プロセシングとグリア細胞
著者: 津田誠
ページ範囲:P.803 - P.810
皮膚などからの痛覚信号は,一次求心性神経を介して脊髄後角へ伝達され,同部位で適切にプロセシングされた後,脳へ送られる。神経障害性疼痛は,神経系の障害により起こる構造および機能的変化が原因と考えられている。その変化の鍵となるのがグリア細胞であり,神経障害性疼痛の発症維持に重要な役割を担う。本論では,グリア細胞によるメカニズムと鎮痛薬開発への可能性を概説する。
総説
成体海馬の新生ニューロンが睡眠中に記憶を固定化する
著者: 菅谷佑樹 , 坂口昌徳
ページ範囲:P.813 - P.817
霊長類の脳の海馬では,性成熟が完了した後でも例外的にニューロンが新生する。これらの新生ニューロンがどのように既存のニューロンと機能的な神経回路をつくるかは明らかでない。筆者らは世界で初めてこれらの新生ニューロンがレム睡眠中の記憶固定化に必須の役割を果たすことを明らかにした。このメカニズムを解明し新生ニューロンが機能的な回路を形成する過程を明らかにすることで,中枢神経の再生医療の発展に貢献したい。
CIDP治療の歩み—症状改善を目的とした治療から維持療法へ〜SCIgを中心に〜
著者: 神田隆 , 飯島正博 , 祖父江元
ページ範囲:P.819 - P.828
慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー(CIDP)の治療に関する臨床研究は,2000年代前半までの初発・再発時における症状改善のための治療,2000年代後半以降の病勢進行の抑制を目的とする維持療法,さらに近年では個々の治療法の最適化へとコンセプトが移ってきた。 本総説ではCIDP治療に関わる過去の臨床研究を振り返り,これまでの変遷を概観する。そのうえでそれぞれの治療法の位置付けを明らかにし,課題と今後の治療開発の方向性について述べる。
パーキンソン病の病態と神経伝達物質の関わり
著者: 武田篤 , 冨山誠彦 , 花島律子
ページ範囲:P.829 - P.837
パーキンソン病(PD)は,運動症状を中核症状とする進行性の難病で,その中心病態はドパミン(DA)作動性神経の変性・脱落によるDA欠乏である。しかし認知機能障害,気分障害,疼痛,睡眠障害などの非運動症状や運動症状の一部については必ずしもDA補充療法に反応しないことからDA以外の神経伝達物質の関与も示唆される。今回,DAに加えてさまざまな神経伝達物質にも着目し,PDの病態について概説を試みたい。
連載 臨床神経学プロムナード—60余年を顧みて・5
小川鼎三先生の寸言に学ぶ—学生時代,東大「脳研」にて
著者: 平山惠造
ページ範囲:P.838 - P.839
筆者らの年代は,日本が太平洋戦争(第二次世界大戦)の敗戦によって,学校制度が新制度へと切り替る旧制度最後の高等学校・大学制度で教育を受けた学年である。従って,大学医学部(4年制)に入学すると,1学年から解剖学の講義と並行して人体解剖実習,次いで組織学の顕微鏡実習など医学の基本となる解剖学で1年が過ぎた。2学年の新学期から生理学,生化学,細菌学,薬理学などの基礎医学の講義が始まった。神経生理学を担当された時実利彦先生(のちに教授)は早口で「○○sensationは脊髄後根から入って,○○を通り,tractus○○を上行してnucleus○○でニューロンを代え,……してthalamusに達する。また××sensationは……」と講義される。protopathicもdyscriminativeもよくわからない中,極く大まかな見取り図が書かれ,線が下から上へと引かれるだけで,解剖名が書かれるでもない。毎回このようにして講義が進められて行った。思い出してみると,旧制度の高等学校では,教師は講義をするが,解らなかったら自分で勉強しろ,という気風であった。大学もその延長であったのであろう。それでも高校では開講前に教科書が指定されていたが,大学では入学時に医学部事務室で尋ねても「教科書はない」と怪訝そうに言われた。実際に各学科の開講時に,いくつかの本が参考書として紹介されるに過ぎず,買う,買わぬ,選択も学生次第であった。
本論に戻って,2学年の1学期が終わった時,神経生理がわからなかった,というよりは,脳,脊髄の組織構造が全くわからなかったので,それを知ろうと思い,解剖学教室の小川鼎三教授室に伺って,夏休みに勉強させて欲しいと申し出た。当時,医学部附属施設の「脳研研究室」(のちの研究所)の室長を先生が兼任しておられたからである。快諾を得て,その日から脳脊髄の染色された連続標本(プレパラート)で勉強することになった。かくして夏休みの朝から夕までを毎日ここで過ごすことになった。しかし,ここで述べるのはその話ではない。
書評
「大人のトラウマを診るということ—こころの病の背景にある傷みに気づく」—青木省三,村上伸治,鷲田健二【編】 フリーアクセス
著者: 伊藤絵美
ページ範囲:P.811 - P.811
ICD-11が改訂され,「複雑性PTSD」という診断が新たに加わったことにより,トラウマやPTSDに関する議論が活発化している。評者は認知行動療法とスキーマ療法を専門とする心理職だが,この数年,学会やシンポジウムで「複雑性PTSDに対するスキーマ療法」についての発表を依頼されることが激増している。とは言え,スキーマ療法はトラウマ処理を目的とするのではなく,安定した治療関係を少しずつ形成したり,成育歴をゆっくりと振り返ったりする中で,自らのスキーマやそれに伴う感情に気づきを向け,その結果として他者と安全につながったり,セルフケアが上手にできるようになったりするという,非常に地味で地道なセラピーである。
ところでそのような複雑性PTSDのシンポジウムでは,スキーマ療法以外は,トラウマ処理を目的とするさまざまな技法が紹介されることがほとんどである。それは例えば,EMDR,PE,STAIR/NST,CPT,ホログラフィトーク,USPT,BSP,BCTといったものである(ググってください!)。同じ壇上でプレゼンしながら,これらの技法に筆者は圧倒されてしまう。なぜなら技法の内容も紹介される事例も実に華々しいからである。評者が提示するスキーマ療法の事例はだいたい年単位(3年や5年は当たり前)であるのに比べ,他の華々しい技法はわずか数セッションでトラウマ処理がなされ,クライアントが回復する。スキーマ療法だけ地味で地道で時間がかかり,なんだか評者は自分が詐欺師であるように感じてしまうのだ。とは言え一方で,どう振り返っても,トラウマを持つ人とのセラピーは,どうしたって時間がかかるし(そもそもトラウマを扱えるようになるまでに時間がかかる),安心安全な関わりや場の中で薄皮を1枚ずつ剝ぐように少しずつ進めていくしかない,という実感しかない。なのできっと華々しい技法や事例を提示する方々も,トラウマを扱うために,地味で地道な何かをしているに違いないのだ,と考えるようになり,むしろその「地味で地道な何か」を知りたい,と思うようになった。
「連合野ハンドブック 完全版—神経科学×神経心理学で理解する大脳機能局在」—河村 満【編】 フリーアクセス
著者: 北澤茂
ページ範囲:P.812 - P.812
私は生理学の教師をしているのだが,「連合野」には苦手意識があることを告白する。「感覚野」や「運動野」に比べて「連合野」のなんと教えにくいことか。『医学大辞典』(医学書院)によれば大脳連合野とは「第一次感覚野と第一次運動野を除く大脳皮質領域」であるという。つまり「教えやすい領域を除いた残り」が連合野なのだ。しかし,本書のおかげで,「連合野」が私の得意分野に生まれ変わるかもしれない。
まず,序章が素晴らしい。「連合」という言葉に込められた思想の歴史が,19世紀後半のマイネルト(マイネルト基底核のマイネルト!)にさかのぼって活写されている。序章を読んで目を見張ったのは,マイネルト,フレクシッヒ,デジュリン,ゲシュヴィンドという連合野の巨人たちが皆「線維」に注目していた,という事実である。マイネルトの自著の表紙に掲げられた大脳内側面には剖出された連合線維が描かれていた。フレクシッヒは線維の髄鞘形成の順序に着目して脳地図をつくった。デジュリンは自身の脳解剖アトラスに白質内の神経路を精緻に描き込んだ。ゲシュヴィンドはフレクシッヒの「連合」概念を引用して連合線維の切断によって生じる臨床症候を「離断症候群」として理論化した。
--------------------
欧文目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.752 - P.752
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.751 - P.751
バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.844 - P.844
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.845 - P.845
あとがき フリーアクセス
著者: 三村將
ページ範囲:P.846 - P.846
2021年6月8日に米国食品医薬品局(FDA)がバイオジェン・エーザイのaducanumabを限定付きではあるが,アルツハイマー病の治療薬として迅速承認したというニュースが世界中を駆け巡った。それまでの諮問委員会の意見などから承認は厳しいだろうという大方の予想を覆しての結果は,日本でもマスコミが大きく取り上げた。間違いなく今年の医療界のトップテンに入る出来事だろう。これまでに承認されているアルツハイマー病治療薬はいずれも中核症状の進行を遅らせるという対症療法であり,とにもかくにも疾患修飾薬と言い得る薬剤が世界で初めて承認されたことは,世界の認知症研究者や臨床家,製薬企業にとっても弾みとなるイベントであり,何よりもアルツハイマー病の当事者や家族にとっては大きな福音であろう。
ただ,この承認を手放しで喜ぶわけにはいかない。国際老年精神医学会(IPA)のWilliam Reichman理事長は早々に“Aducanumab and Alzheimer's Disease: IPA's position on controversial FDA approval”と題したコメントを発信し,aducanumabの科学的妥当性や臨床的意義はともかく,この承認の持つ社会的インパクトについて警鐘を鳴らしている。アミロイドβをターゲットとした製剤であるaducanumabの使用にはいまのところアミロイドPETが必須であるが,この検査を受けることのできる患者はごく限られている。また,最大の有害事象であるアミロイド関連画像異常(ARIA)をモニターするには頻回のMRI検査も必要となる。医療費の高騰を心配する声も大きい。確かにaducanumabは現在の認知症の臨床における「医療格差」をさらに押し広げる結果になってしまう可能性もある。また,今回の承認はあくまでも限定付きであり,もししかるべき臨床効果が確認できなければ,むしろ後続の疾患修飾薬のブレーキになりかねない事態も懸念される。
基本情報
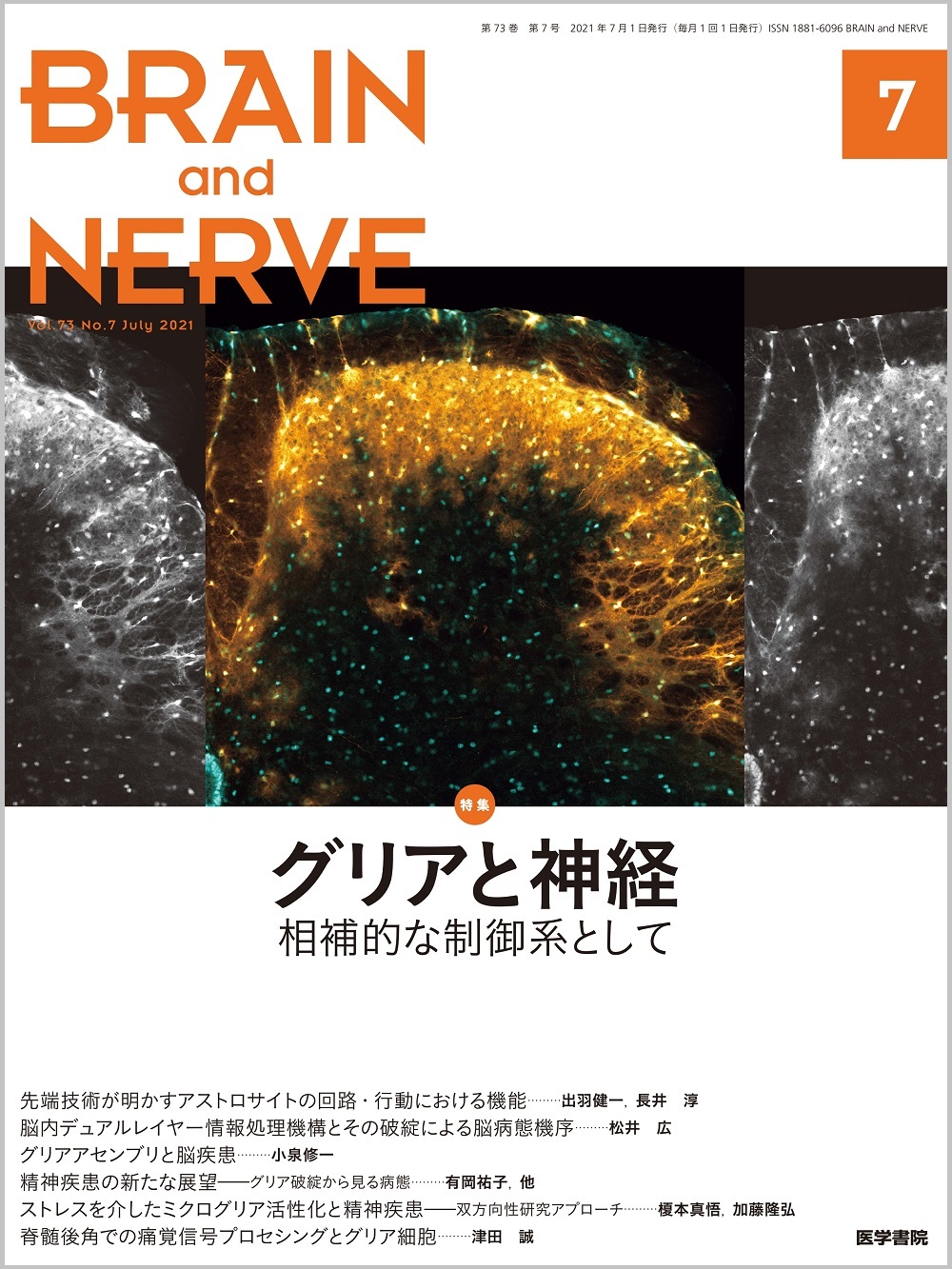
バックナンバー
76巻12号(2024年12月発行)
特集 芸術家と神経学Ⅱ
76巻11号(2024年11月発行)
特集 ALS 2024
76巻10号(2024年10月発行)
特集 どうして効くんだろう
76巻9号(2024年9月発行)
特集 治療可能な認知症としてのアルツハイマー病
76巻8号(2024年8月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である—revisited
76巻7号(2024年7月発行)
特集 ニューロ・バイオイメージング—技術と応用
76巻6号(2024年6月発行)
特集 注意と注意障害
76巻5号(2024年5月発行)
増大特集 末梢神経・筋肉の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
76巻4号(2024年4月発行)
特集 神経病理最前線
76巻3号(2024年3月発行)
特集 きちんと説明ができますか?
76巻2号(2024年2月発行)
特集 特発性正常圧水頭症の現在
76巻1号(2024年1月発行)
特集 新時代の重症筋無力症と関連疾患の診療
75巻12号(2023年12月発行)
特集 アガサ・クリスティーと神経毒
75巻11号(2023年11月発行)
特集 アロスタシス—ホメオスタシスを超えて
75巻10号(2023年10月発行)
特集 メタバースへの招待
75巻9号(2023年9月発行)
特集 妊娠と神経疾患
75巻8号(2023年8月発行)
特集 アルツハイマー病は本当に早期発見できるのか
75巻7号(2023年7月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part2 末梢編
75巻6号(2023年6月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part1 中枢編
75巻5号(2023年5月発行)
増大特集 神経・精神領域の薬剤ハンドブック
75巻4号(2023年4月発行)
特集 All About Epilepsy
75巻3号(2023年3月発行)
特集 慢性疼痛
75巻2号(2023年2月発行)
特集 多系統萎縮症の新診断基準とこれからの診療
75巻1号(2023年1月発行)
特集 よく出会う不随意運動を知る
74巻12号(2022年12月発行)
特集 映画を観て精神・神経疾患を知る
74巻11号(2022年11月発行)
特集 RFC1遺伝子関連スペクトラム障害
74巻10号(2022年10月発行)
特集 ウイルス性脳炎・脳症2022
74巻9号(2022年9月発行)
特集 動的環境への適応系としての歩行
74巻8号(2022年8月発行)
特集 迷走神経の不思議
74巻7号(2022年7月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識2022
74巻6号(2022年6月発行)
特集 脳神経内科医に求められる移行医療
74巻5号(2022年5月発行)
増大特集 次の一手—神経筋疾患難治例をどのように治療するか
74巻4号(2022年4月発行)
特集 脳科学リテラシーを高めるために
74巻3号(2022年3月発行)
特集 中枢性自律神経障害update
74巻2号(2022年2月発行)
特集 温度を感じる脳と身体の科学
74巻1号(2022年1月発行)
特集 脳神経内科医のキャリアパスとリーダーシップ
73巻12号(2021年12月発行)
特集 芸術家と神経学
73巻11号(2021年11月発行)
特集 「目」の神経学
73巻10号(2021年10月発行)
特集 中枢神経・末梢神経の悪性リンパ腫
73巻9号(2021年9月発行)
特集 脳卒中治療に必要な基礎知識
73巻8号(2021年8月発行)
特集 脳腸相関—脳-身体の双方向性制御
73巻7号(2021年7月発行)
特集 グリアと神経—相補的な制御系として
73巻6号(2021年6月発行)
特集 Lower Spine Neurology
73巻5号(2021年5月発行)
増大特集 中枢神経の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
73巻4号(2021年4月発行)
特集 片頭痛・群発頭痛治療の新たな夜明け
73巻3号(2021年3月発行)
特集 マルチリンガルブレイン
73巻2号(2021年2月発行)
特集 筋炎と壊死性筋症
73巻1号(2021年1月発行)
特集 Neuro-Oncology
72巻12号(2020年12月発行)
特集 超高齢期の精神神経疾患を診る
72巻11号(2020年11月発行)
増大特集 脳の発振現象—基礎から臨床へ
72巻10号(2020年10月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識
72巻9号(2020年9月発行)
特集 皮質性小脳萎縮症へのアプローチ
72巻8号(2020年8月発行)
特集 サルコイドーシス
72巻7号(2020年7月発行)
増大特集 神経倫理ハンドブック
72巻6号(2020年6月発行)
特集 前頭側頭葉変性症の今日的理解
72巻5号(2020年5月発行)
特集 多発性硬化症の現在と未来
72巻4号(2020年4月発行)
増大特集 神経疾患の診断における落とし穴—誤診を避けるために
72巻3号(2020年3月発行)
特集 でこぼこの脳の中でおしくらまんじゅうする脳機能
72巻2号(2020年2月発行)
特集 αシヌクレイノパチーの新たな展開
72巻1号(2020年1月発行)
特集 神経難病をクスリで治す—薬物開発の現況と近未来への展望
71巻12号(2019年12月発行)
特集 小脳と大脳—Masao Itoのレガシー
71巻11号(2019年11月発行)
増大特集 ALS2019
71巻10号(2019年10月発行)
特集 認知症と遺伝
71巻9号(2019年9月発行)
特集 神経疾患のドラッグ・リポジショニング—新時代へ
71巻8号(2019年8月発行)
特集 パーキンソン病診療の現在地—200年の変遷と新規治療
71巻7号(2019年7月発行)
増大特集 人工知能と神経科学
71巻6号(2019年6月発行)
特集 補体標的治療の現状と展望
71巻5号(2019年5月発行)
特集 NPSLE
71巻4号(2019年4月発行)
増大特集 神経学のための皮膚アトラス
71巻3号(2019年3月発行)
特集 Spine Neurology
71巻2号(2019年2月発行)
特集 “スポーツ”を生み出す脳
71巻1号(2019年1月発行)
特集 人工知能の医療応用Update
70巻12号(2018年12月発行)
特集 主訴に沿う—俯瞰し収束する画像診断の目
70巻11号(2018年11月発行)
増大特集 脳科学で解き明かす精神神経症候
70巻10号(2018年10月発行)
特集 「左脳と右脳」の現在
70巻9号(2018年9月発行)
特集 脳神経内科診療に役立つ精神科の知識
70巻8号(2018年8月発行)
特集 レヴィ小体型認知症の新知見
70巻7号(2018年7月発行)
増大特集 記憶と忘却に関わる脳のしくみ—分子機構から健忘の症候まで
70巻6号(2018年6月発行)
特集 芸術を生み出す脳
70巻5号(2018年5月発行)
特集 非アルツハイマー型認知症の病理学
70巻4号(2018年4月発行)
増大特集 Antibody Update 2018
70巻3号(2018年3月発行)
特集 『認知症疾患診療ガイドライン2017』を読み解く
70巻2号(2018年2月発行)
特集 知っておきたい神経感染症
70巻1号(2018年1月発行)
特集 筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群の今
69巻12号(2017年12月発行)
特集 運動異常症をみる—Web動画付録つき
69巻11号(2017年11月発行)
増大特集 こころの時間学の未来
69巻10号(2017年10月発行)
特集 成人てんかん—知っておきたい6つのトピック
69巻9号(2017年9月発行)
特集 ミクログリアと精神・神経疾患
69巻8号(2017年8月発行)
特集 遺伝性脊髄小脳失調症の病態と治療展望
69巻7号(2017年7月発行)
増大特集 あしたのアルツハイマー病治療
69巻6号(2017年6月発行)
特集 局在病変の神経心理学
69巻5号(2017年5月発行)
特集 Voxel-Based Morphometry—体積からわかること
69巻4号(2017年4月発行)
増大特集 ブロードマン領野の現在地
69巻3号(2017年3月発行)
特集 磁気刺激の新たな展開
69巻2号(2017年2月発行)
特集 Stroke-Like Diseases—鑑別時に注意を要する5病態
69巻1号(2017年1月発行)
特集 近年注目されている白質脳症
68巻12号(2016年12月発行)
特集 炎症性神経・筋疾患の新たな展開
68巻11号(2016年11月発行)
増大特集 連合野ハンドブック
68巻10号(2016年10月発行)
特集 アディクション—行動の嗜癖
68巻9号(2016年9月発行)
特集 自己免疫性脳炎・脳症
68巻8号(2016年8月発行)
特集 こころと汗
68巻7号(2016年7月発行)
増大特集 認知症の危険因子と防御因子
68巻6号(2016年6月発行)
特集 脳とフローラ
68巻5号(2016年5月発行)
特集 手の症候学—生理学・解剖学からみた新知見
68巻4号(2016年4月発行)
増大特集 治せる認知症
68巻3号(2016年3月発行)
特集 末梢神経の血管炎
68巻2号(2016年2月発行)
特集 筋疾患の認知機能障害
68巻1号(2016年1月発行)
特集 シャルコー・マリー・トゥース病
67巻12号(2015年12月発行)
特集 視床と高次脳機能
67巻11号(2015年11月発行)
増大特集 ギラン・バレー症候群のすべて—100年の軌跡
67巻10号(2015年10月発行)
特集 非・日常生活の脳科学
67巻9号(2015年9月発行)
特集 酵素補充療法
67巻8号(2015年8月発行)
特集 神経難病の終末期医療
67巻7号(2015年7月発行)
増大特集 神経疾患と感染症update
67巻6号(2015年6月発行)
特集 脳と「質感」
67巻5号(2015年5月発行)
特集 NCSE(非痙攣性てんかん重積状態)
67巻4号(2015年4月発行)
増大特集 大脳皮質vs.大脳白質
67巻3号(2015年3月発行)
特集 中枢神経の血管炎
67巻2号(2015年2月発行)
特集 「食べる」を考える
67巻1号(2015年1月発行)
特集 ニューロトキシコロジー
66巻12号(2014年12月発行)
特集 Orthopaedic Neurology—神経内科と整形外科の狭間で
66巻11号(2014年11月発行)
増大特集 神経症候学は神経学の“魂”である
66巻10号(2014年10月発行)
特集 分子を撃つ 神経疾患治療の新しい水平線
66巻9号(2014年9月発行)
特集 痙縮の臨床神経学
66巻8号(2014年8月発行)
特集 神経系の悪性リンパ腫update
66巻7号(2014年7月発行)
増大特集 アミロイド関連神経疾患のすべて―封入体筋炎からアルツハイマー病まで
66巻6号(2014年6月発行)
特集 ミラーニューロン
66巻5号(2014年5月発行)
特集 アセチルコリンと神経疾患―100年目の現在地
66巻4号(2014年4月発行)
増大特集 タッチ・ビジョン・アクション
66巻3号(2014年3月発行)
特集 神経筋疾患の超音波診断
66巻2号(2014年2月発行)
特集 糖尿病の神経学revisited
66巻1号(2014年1月発行)
特集 日常生活の脳科学
65巻12号(2013年12月発行)
特集 プロテイノパチーの神経病理学
65巻11号(2013年11月発行)
増大特集 Close Encounters―臨床神経学と臨床免疫学の遭遇と未来
65巻10号(2013年10月発行)
特集 神経系の発達メカニズム―最近の話題
65巻9号(2013年9月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である―現状と展望
65巻8号(2013年8月発行)
特集 こころの時間学―現在・過去・未来の起源を求めて
65巻7号(2013年7月発行)
増大特集 あしたの脳梗塞
65巻6号(2013年6月発行)
特集 見せる・仕分ける―脳機能解析の新手法
65巻5号(2013年5月発行)
特集 てんかん―新しいパースペクティブ
65巻4号(2013年4月発行)
増大特集 Antibody Update
65巻3号(2013年3月発行)
特集 次世代シーケンサーによる神経変性疾患の解析と展望
65巻2号(2013年2月発行)
特集 血液脳関門研究の進歩
65巻1号(2013年1月発行)
特集 Corticobasal Syndrome
64巻12号(2012年12月発行)
特集 The Border-Land of Dementia
64巻11号(2012年11月発行)
増大特集 痛みの神経学―末梢神経から脳まで
64巻10号(2012年10月発行)
特集 辺縁系をめぐって
64巻9号(2012年9月発行)
特集 高次脳機能イメージングの脳科学への新展開
64巻8号(2012年8月発行)
特集 線条体の基礎と臨床
64巻7号(2012年7月発行)
増大特集 顔認知の脳内機構
64巻6号(2012年6月発行)
特集 睡眠と覚醒の脳内機構
64巻5号(2012年5月発行)
特集 神経疾患のバイオマーカー
64巻4号(2012年4月発行)
増大特集 パーキンソン病の新しい側面
64巻3号(2012年3月発行)
特集 アカデミアから新規治療の実現へ―トランスレーショナルリサーチの現状
64巻2号(2012年2月発行)
特集 生物学的精神医学の進歩
64巻1号(2012年1月発行)
特集 iPS細胞と神経疾患
63巻12号(2011年12月発行)
特集 神経心理学と画像解析の融合
63巻11号(2011年11月発行)
増大特集 筋疾患update
63巻10号(2011年10月発行)
特集 緩徐進行性高次脳機能障害の病態
63巻9号(2011年9月発行)
特集 脳卒中の最新画像診断
63巻8号(2011年8月発行)
特集 日本人の発見した神経症候
63巻7号(2011年7月発行)
増大特集 神経筋接合部―基礎から臨床まで
63巻6号(2011年6月発行)
特集 ニューロパチー
63巻5号(2011年5月発行)
特集 神経系と血管内リンパ腫
63巻4号(2011年4月発行)
増大特集 てんかんの新しい治療
63巻3号(2011年3月発行)
特集 サイバーナイフ治療
63巻2号(2011年2月発行)
特集 続・日本人の発見した神経疾患
63巻1号(2011年1月発行)
特集 血管腫
62巻12号(2010年12月発行)
特集 頸部頸動脈狭窄症の診断と治療
62巻11号(2010年11月発行)
増大特集 歩行とその異常
62巻10号(2010年10月発行)
特集 ブレインバンク
62巻9号(2010年9月発行)
特集 視神経脊髄炎(NMO)update
62巻8号(2010年8月発行)
特集 辺縁系脳炎
62巻7号(2010年7月発行)
増大特集 アルツハイマー病―研究と診療の進歩
62巻6号(2010年6月発行)
特集 改正臓器移植法の問題点とその対応
62巻5号(2010年5月発行)
特集 神経画像のピットフォール―見落としと読み過ぎ
62巻4号(2010年4月発行)
特集 傍腫瘍性神経筋疾患update
62巻3号(2010年3月発行)
特集 神経回路解析法の最近の進歩
62巻2号(2010年2月発行)
特集 ニューロリハビリテーションの最前線
62巻1号(2010年1月発行)
特集 神経救急
61巻12号(2009年12月発行)
特集 Somatotopy再考
61巻11号(2009年11月発行)
特集 前頭側頭葉変性症
61巻10号(2009年10月発行)
特集 片頭痛の予防療法
61巻9号(2009年9月発行)
特集 脳血管障害治療の進歩
61巻8号(2009年8月発行)
特集 神経・筋疾患の分子標的治療
61巻7号(2009年7月発行)
特集 脳腫瘍研究の最前線―遺伝子解析から治療まで
61巻6号(2009年6月発行)
特集 脊椎・脊髄外科の最近の進歩
61巻5号(2009年5月発行)
特集 Restless legs syndrome
61巻4号(2009年4月発行)
特集 大脳基底核―分子基盤から臨床まで
61巻3号(2009年3月発行)
特集 Microneurography(微小神経電図法)の臨床応用
61巻2号(2009年2月発行)
特集 神経系の再興感染症と輸入感染症
61巻1号(2009年1月発行)
特集 脳神経倫理
60巻12号(2008年12月発行)
特集 痙縮
60巻11号(2008年11月発行)
特集 脳卒中と遺伝子
60巻10号(2008年10月発行)
特集 若年者の脳卒中
60巻9号(2008年9月発行)
特集 知・情・意の神経学
60巻8号(2008年8月発行)
特集 脳硬膜動静脈瘻
60巻7号(2008年7月発行)
増大特集 学習と記憶――基礎と臨床
60巻6号(2008年6月発行)
特集 Crow-深瀬症候群(POEMS症候群)
60巻5号(2008年5月発行)
特集 「痛み」の研究と治療の最前線
60巻4号(2008年4月発行)
増大特集 神経系の発生とその異常
60巻3号(2008年3月発行)
特集 特発性正常圧水頭症(iNPH)―最近の話題
60巻2号(2008年2月発行)
特集 がん治療と神経障害
60巻1号(2008年1月発行)
特集 日本人の発見した神経疾患
59巻12号(2007年12月発行)
特集 損傷神経の再生―温存的治療法の開発
59巻11号(2007年11月発行)
特集 手根管症候群をめぐって
59巻10号(2007年10月発行)
増大特集 ALS―研究と診療の進歩
59巻9号(2007年9月発行)
特集 パーキンソン病の認知機能障害
59巻8号(2007年8月発行)
特集 パーキンソン病の分子遺伝学―最近の知見
59巻7号(2007年7月発行)
増大特集 情報伝達処理におけるグリアの機能と異常
59巻6号(2007年6月発行)
特集 職業性神経障害の新しい展開
59巻5号(2007年5月発行)
特集 脳画像最前線
59巻4号(2007年4月発行)
増大特集 最近注目される脳神経疾患治療の研究
59巻3号(2007年3月発行)
特集 分子イメージング
59巻2号(2007年2月発行)
特集 進行性多巣性白質脳症の新しい展開―PMLが治る時代へ向けて
59巻1号(2007年1月発行)
特集 高次視覚研究の最近の進歩
