脳神経内科をめぐる状況は大きく変化している。新専門医制度や基本領域化・サブスペシャルティの問題,バーンアウト,働き方改革,そして新型コロナウイルス感染症による影響など,さまざまな要因を挙げることができる。こうした状況下では,自身のキャリアに迷い,悩むことも多いのではないだろうか。本特集では,若手〜中堅医師が自分自身に合った道を見つける一助となるよう,多くの先輩医師から多様なキャリアパスを示していただいた。一方,リーダーシップは,生まれながらにして備わっているものではなく,学問として学び身に付けるべき能力であるとして,海外学会は既にその教育に重点を置いている。年代や立場を問わずさまざまな人に,各キャリアのリーダー像を考える機会としていただきたい。
雑誌目次
BRAIN and NERVE-神経研究の進歩74巻1号
2022年01月発行
雑誌目次
特集 脳神経内科医のキャリアパスとリーダーシップ
脳神経内科医のキャリアパスとリーダーシップ
著者: 下畑享良
ページ範囲:P.5 - P.6
「脳神経内科(学)」は,若い研修医,医学生に自信を持ってお勧めすることができる診療科,学問です。理由としては,神経症候学や臨床神経学は非常に奥深く,一生をかけて行うに値する学問であること,神経救急から慢性の神経疾患の診療に至るまで間口が広く,自分の取り組みたい領域を必ず見つけることができること,患者さんに寄り添うことができ,1人の人間としても成長できること,ワークライフバランスを意識した働き方が可能であること,体力を要求される場面や技術・手技の習得が少なく,女性医師や高齢医師にも適した診療科であること,抗体医薬や核酸医薬などの臨床応用が目覚ましく,これから治療研究が著しく発展する領域であることなど,枚挙にいとまがありません。
ただいずれも真実ではあるものの,自分の経験を振り返ると,必ずしも簡単なキャリアパスではなく,ずっと無我夢中であったように思います。少し自身の履歴を書きたいと思います。学生時代に憧れた教授のもとで学ぼうと腎臓内科を志望しました。卒後2年目に脳神経内科医不在の病院で研修した際,筋萎縮性側索硬化症の女性患者さんを担当し,自分の無力さを痛感するとともに神経難病に取り組んでみたいと考えるようになり,進路を変更しました。入局後は神経症候学を身に付けるために,これと決めた教科書を繰り返し読み,論文を毎朝,誰もいない医局で音読していました。また優れた脳神経内科医とはどういう医師なのか,多くの先輩医師に質問をして回りました。症例報告にも積極的に取り組みましたが,決して1人で書けるようになったわけではなく,指導医に真っ赤になるまで書き込みをしてもらった原稿を何回もやりとりして学びました。いま振り返ると臨床神経学の基礎を身に付けるこの時期にどれだけ頑張れるかが,脳神経内科医としての成長に非常に重要であると思います。
臨床力とは何か?—どのように身につけるか?
著者: 福武敏夫
ページ範囲:P.7 - P.9
臨床力とは,臨床場面で患者に向き合うときに診断や治療に役立つ何かを発見しようとする気概である。そのためには,人間への強い興味,注意深い観察力,そして推理力が必要である。臨床力を身につけるためには,理屈や理論を先にせず,患者にみられる多様な現象をありのままに観察する態度が最も重要である。参考のために,チャールズ・ミラー・フィッシャーの至言と筆者の小さな経験を紹介する。
文献の探し方,読み方,まとめ方
著者: 渡辺宏久
ページ範囲:P.10 - P.13
論文を読むことは,日常臨床における疑問を解決するうえで,また,研究を準備し推進するうえで極めて重要である。ここでは文献の検索サービスを紹介し,最も広く使用されているPubMedの使い方を整理する。次に,文献の構造を概説し,パラグラフリーディングや時制など,英語論文を読むうえで基本となるポイントも紹介する。最後に,論文の整理の仕方,特に論文執筆におけるガイドラインを紹介し,日常臨床へ活かすうえでの留意点や,批判的吟味の重要性について述べる。
症例報告の書き方
著者: 阿部康二
ページ範囲:P.14 - P.16
日本の近代医学の祖と言われる緒方洪庵は,ベルツ医師の高祖師であるフーフェラント(ベルリン大学教授)の有名な遺訓「後の世の闇のためにも焚き残せ云々」(扶氏医戒之略第5条)を座右の銘にしていたという。その趣旨は,医師たるものは昼間の診療が一段落して夜になったら,その日に診た患者のまとめをして記録を残し,自分の貴重な経験を広く世間に,また後世にも伝えるべきであるということであろう。本論ではその方法の一端を,主として岡山大学脳神経内科での実経験をもとに紹介した。
科学的なプレゼンテーションと発表の仕方
著者: 松島理明 , 矢部一郎
ページ範囲:P.17 - P.21
効果的でわかりやすい発表を行うために,スライド,ポスターともに聴衆の印象に残るような見映えを意識して作成することが重要である。1枚のスライドに示す情報量は多くせず,見やすく作成することが望ましい。また,発表の最初に全体の構成を示し,短い言葉や文で内容を組み立てることが推奨される。さらに,聴衆が理解しやすい発表をするために,事前練習を十分に行い,自分自身で発表内容をしっかりと咀嚼しておく必要がある。
脳神経内科後期研修医が習得すべきノンテクニカルスキル
著者: 安藤哲朗 , 福武敏夫
ページ範囲:P.22 - P.24
社会で役立つ脳神経内科医になるために必要な,レジリエンス,コミュニケーション能力,マネジメント力,情報リテラシー,教育能力などの「ノンテクニカルスキル」を簡単に解説した。これらの能力は専門家としての「テクニカルスキル」を生かすために必要であり,後期研修医(専攻医)の時期に身に付けるようにするべきである。
大学院で何をどう学ぶか
著者: 勝野雅央
ページ範囲:P.25 - P.28
学位を取得することだけが大学院で学ぶ目的ではない。大学院で学ぶべきことの1つは,研究を通じて物事を科学的に考えるということである。すなわち,現状の科学に疑問を持ち,疑問に関する情報を収集,分析し,解決のために行う研究を立案,実施し,その結果を考察して発表,共有することである。さらに,大学院では専門分野以外の教育を受けることができ,学内外の研究者とのコラボレーション,国際連携,産学連携など,さまざまな活動からも学ぶことは多い。
海外留学で学ぶべきこと
著者: 関島良樹
ページ範囲:P.29 - P.32
近年,日本からの海外留学者数は減少傾向にあるが,グローバル化が進む医療・科学の分野における海外留学の重要性は決して低下していない。海外留学は「世界の多様性と普遍性」を身をもって経験できるまたとない機会である。また,海外留学により国際的な人脈の構築,最先端の研究手法や臨床技術の習得,英語力の向上なども期待できる。
コロナ禍での臨床留学
著者: 原田陽平
ページ範囲:P.33 - P.35
新型コロナウイルス感染症の拡大は,米国での脳神経内科研修の体制を大きく変えるものとなった。未曽有の感染拡大の中で,患者と医療従事者の感染リスクを最小限に抑えながら,いかにレジデントの研修の質を確保するかが大きな挑戦であった。迅速かつダイナミックな変革が求められたパンデミック開始の時期を,チーフレジデントとしてどのように過ごしたのか,そしてそこで見たリーダーシップの在り方について報告する。
コロナ禍における基礎研究留学
著者: 西山修平
ページ範囲:P.36 - P.39
新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより基礎研究留学へのハードルは上がったが,コロナ禍に対応したシステム変更が進み新しい生活様式でも基礎研究を行うことのできる土台が構築されてきている。コロナ禍以前の研究留学とは異なることも多いが,コロナ禍によって自身の夢をあきらめず,ぜひ門戸をたたきチャレンジすることをお勧めする。
女性医師のキャリアパスとリーダーシップ—市中病院
著者: 饗場郁子
ページ範囲:P.40 - P.44
自分自身の市中病院でのキャリアパスは,ライフイベントの時期を経て,臨床病理学的研究,そして現場で困っていることをテーマに臨床研究を進め,多施設共同研究へと発展させてきた。ライフイベントの時期に一時的に仕事が遅れても,大切だと思うことを継続すれば十分挽回でき,不安に思う必要はない。女性医師がバーンアウトせずに仕事を継続できるよう,リーダーシップ教育をはじめ多様なアプローチが不可欠である。
女性医師のキャリアパスとリーダーシップ—大学病院
著者: 三澤園子
ページ範囲:P.45 - P.47
大学病院の教員に占める女性割合は低いのがわが国の現状である。特に講師以上の上位ポストでその傾向は顕著になる。さまざまなライフイベントを経て,大学病院での勤務を継続するのは,女性にとっては大変なこともまだ少なくない。しかし,状況は確実に変化しつつある。大学病院ならではのやりがいのある仕事も多くあり,多くの女性医師に大学でのキャリアも選択肢の1つとして考えていただきたい。
脳神経内科で開業するためのキャリアパスは存在するか—ロールモデルとしての医師会での活動
著者: 目々澤肇
ページ範囲:P.48 - P.50
脳神経内科として開業するためのキャリアパスに一定のものはなく,医師個人ごとに異なると思われる。内科開業医として自立するためには「かかりつけ医」となる自覚が必要であり,家庭医や総合医としての最低限の素養が必要で,そのうえに「脳神経内科としての専門性」を主張するため,医療機関同士のネットワーク形成を考え,医師会活動に励むこととなった。
キュアからケアへ—在宅診療医へのキャリアパス
著者: 渡辺良
ページ範囲:P.51 - P.54
在宅診療は,通院が困難な患者がその暮らしの場で治療やケアを受けることのできる医療の形である。脳卒中,パーキンソン病,筋萎縮性側索硬化症など神経疾患を生活の場で診ることにより,患者のニーズに沿う医療やケアが可能となる。在宅診療医に期待されるのは疾患の診断治療能力のみならず患者や家族の訴えを共感的に聴く力,そして最期まで在宅で患者を支えることである。そのために多職種と連携しリーダーシップをとる必要がある。
臨床研究・治験PIのキャリアパス
著者: 桑原聡
ページ範囲:P.55 - P.58
臨床医が行う研究の最終目標は新規治療開発〜疾患克服であり,それを実現するためには新規治療薬の候補(シーズ)を開発し,臨床試験(治験)を経て国の承認(薬機法承認)を得,より有効性・安全性の高い治療を全国(あるいは全世界)の患者に届けるというプロセスが必要である。治験のPIとしてのキャリアパスを進むには,新規治療を開発しようとする意思と,シーズの発案から治験実施,承認まで一貫した長期ビジョンを持つことが最も重要である。本論ではシーズ開発の方法から特定臨床研究・治験の実施を効率的に実践するための道筋を,自身の医師主導治験の経験を含めて概説する。
臨床をベースとする基礎研究者のキャリアパスとリーダーシップ
著者: 岡澤均
ページ範囲:P.59 - P.62
若い研究者あるいは臨床医のために私のキャリアをケーススタディとして紹介した。キャリアパスには多くの可能性があると思われるが,重要な点は研究における独創性と創造性であり,新たな道を切り開くための情熱であろう。
脳神経内科医にとっての医系技官のキャリア
著者: 桑原宏哉
ページ範囲:P.63 - P.66
医系技官は,医師全体の約0.1%と少ないが,保健医療の専門的な知識や経験を持って厚生労働行政に携わる重要な職種である。本論では,脳神経内科医が人事交流で厚生労働省に出向し,医系技官として勤務する実態について,筆者自身の経験を踏まえて概説し,そのメリットとデメリットについての私見も述べる。脳神経内科医にとって,医系技官のキャリアの意義を考える一助になれば幸いである。
製薬企業で働く医師としてのキャリアパス
著者: 藤本陽子
ページ範囲:P.67 - P.70
医療において医薬品は中心的な役割を果たしており,医薬品の研究開発やエビデンスの構築,適正使用のための情報提供を担う製薬企業に勤務することは,医師として果たすべき役割の延長線上にある。幅広く医療や公衆衛生,社会に貢献したいという志を持つ医師にとって,製薬企業に勤務することは自己実現と目標達成のための1つの選択肢である。
大学発ベンチャーの現状と設立のためのキャリア
著者: 山本卓 , 横田隆徳
ページ範囲:P.71 - P.75
日本における大学発ベンチャーは,2020年度時点で2,905社に達し,そのうち907社がバイオ,ヘルスケア,医療機器に関連したベンチャー企業である。ここ数年は毎年200社を超える高い水準で大学発ベンチャーが設立されるなど,活況を呈している。本論では,創薬を目的とした大学発ベンチャーを主眼に,現状,意義,大学での発明の扱い,ベンチャー設立プロセス,知的財産マネジメント,利益相反マネジメント,エグジットについて概説する。
対談
Aducanumab—アルツハイマー病診療にもたらすインパクト
著者: 粟田主一 , 岩坪威
ページ範囲:P.79 - P.84
【2021年6月7日,米国食品医薬品局がアルツハイマー病の疾患修飾薬を迅速承認】
—この大きなニュースが世界を駆けめぐった。アルツハイマー病(AD)の原因に直接作用する治療薬(疾患修飾薬)が承認されるのは世界初であり,罹患数の多い本疾患に対する新薬の登場は,医療者のみならず多くの人々に衝撃をもたらした。その一方で,臨床試験データの解釈や諮問委員の辞任など,さまざまな懸念の声も聞かれる。今後,aducanumabは多くの患者・家族の希望の光となるのか,また,どういった形で普及していくのか。本誌ではこのたび,日本認知症学会理事長でADの病態や治療法研究のエキスパートである岩坪威先生と,副理事長で長年認知症診療の第一線でご活躍されている粟田主一先生を迎え,aducanumabの現状と課題について徹底的に議論していただいた。
総説
小分子のリピートRNA毒性に対する動物モデルでの効果
著者: 中谷和彦
ページ範囲:P.85 - P.91
リピート配列RNAは,RNA結合蛋白質を捕捉することにより機能発現を阻害する「RNA毒性」を示す。われわれの研究で創製されたミスマッチ結合分子は,リピートDNAやRNA配列が形成するスリップアウト構造に高い親和性と特異性で結合し,ハンチントン病,脊髄小脳失調症31型,筋強直性ジストロフィー1型の動物モデルにおいて,リピートDNA長の短縮,複眼変性ならびにスプライシング異常の緩和効果を示した。
原著
痙性斜頸患者に対するB型ボツリヌス毒素製剤の安全性および有効性
著者: 梶龍兒 , 遠藤亮 , 石井美佳
ページ範囲:P.93 - P.104
B型ボツリヌス毒素製剤(ナーブロック®筋注2500単位)の痙性斜頸患者に対する安全性および有効性について,国外も含めこれまでにない症例数での検討を行った。約80%でなんらかの改善が認められたことなど,本剤は臨床において有用な薬剤と考えられた。また,副作用は嚥下障害に次いで口内乾燥および口渇の発現割合が高く,本剤の自律神経への作用が示唆され,流涎など他疾患への応用の可能性が考えられた。
連載 脳神経内科領域における医学教育の展望—Post/withコロナ時代を見据えて・5
基礎医学における神経解剖学/神経科学教育の現状と今後の課題
著者: 山口瞬
ページ範囲:P.106 - P.109
はじめに
医学部の基礎医学で行う神経解剖学/神経科学の講義・実習は,教えるべき内容が複雑で量が多いという問題だけでなく,実施スケジュールや,臨床系科目との関係性,学生に関心を持たせるための方策など,多くの課題を抱えている。
本稿では,まずわが国の医学部における神経解剖学/神経科学の講義・実習の現状について分析する。そしてその後,学生に必要な知識を身に付けさせ,さらに神経科学の基礎・臨床研究や臨床科目に対する関心を持たせるにはどうすればよいか,筆者の12年間の神経解剖学/神経科学教育の経験を踏まえて論じてみたい。
臨床神経学プロムナード—60余年を顧みて・11
CT・MRI検査の出現。その光と蔭—(1)『MRI脳部位診断』:図譜からの脱却 (2)「若年性一側上肢筋萎縮症(平山病)」病因・病態機序の解明へ
著者: 平山惠造
ページ範囲:P.110 - P.113
プロローグ:筆者が千葉大学に赴任して(1978),その数年後にCTが,次いで間もなくMRIが神経放射線学的検査法として採用され,全国でも広まった。1980年代は学会発表,雑誌掲載論文などで,これらの画像が賑やかであった。画像図譜もいろいろな形式のものが相次いで出版された。まさに新検査法の出現による神経学的診断が活気づいた時代であった。反面,臨床・症候学的アプローチが軽んじられて行った。それは今日も尾を引いている蔭の部分である。
書評
「基礎から学ぶ楽しい学会発表・論文執筆 第2版」—中村好一【著】 フリーアクセス
著者: 佐伯圭吾
ページ範囲:P.76 - P.76
本書は主に,保健活動に従事するコメディカルスタッフや学生を含む初学者が,日本語での学会・論文発表を目指す際の指南書として書かれたもので,疫学書では最も人気がある中村好一氏による『基礎から学ぶ 楽しい疫学』の姉妹書である。
これから研究を始める人が,最初に読む本としてお薦めしたい。「なぜ研究を行うか」「研究指導者をどのように求めるか」から始まって,研究の実施,分析,学会発表,論文執筆,投稿,査読の過程に区分され,それぞれのステップをどのように考え,どのように進めていくかが,ありありと目に浮かぶように書かれている。読者は,各ステップを思い浮かべて読み進めていくうちに,研究プロセスを俯瞰することができ,高く感じていたハードルが,いつの間にか取り組むべき具体的な課題に変わっていることに気づくのではないだろうか。
「緩和ケア・コミュニケーションのエビデンス—ああいうとこういうはなぜ違うのか?」—森田達也【著】 森 雅紀【執筆協力】 フリーアクセス
著者: 頭木弘樹
ページ範囲:P.78 - P.78
病院に行くとき,録音機を持って行こうかと迷う。説明を覚えきれないからだ。いい加減に聞いているわけではない。その逆で,1つ1つの医師の発言に集中し,ちゃんと理解しようとしている。それだけにそしゃくに時間がかかり,次々に繰り出される言葉を飲み込みきれなくなる。
しかし,いまだに持って行ったことはない。医師のショッキングな発言が録音されると嫌だからだ。消せばよいだけなのだが,録音されたらと思うだけで,もう胸が苦しくなり,やめてしまう。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.1 - P.1
欧文目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.2 - P.2
バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.118 - P.118
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.119 - P.119
あとがき フリーアクセス
著者: 三村將
ページ範囲:P.120 - P.120
この間,『教養としてのギリシャ・ローマ—名門コロンビア大学で学んだリベラルアーツの真髄』(東洋経済新報社)という本を読んだ。「読む」と言っても,私の場合は通勤の車の中で「聴いた」ということだが,著者は中村聡一氏(甲南大学マネジメント創造学部)である。欧米の名門大学では,ギリシャ・ローマ時代の「自由7科」(文法,修辞,弁証,算術,幾何,天文,音楽)に起源を置く古典的教養(リベラルアーツ)の教育・習得が重視されている。
最近では,GAFA(Google,Apple,Facebook,Amazon)でもこのようなリベラルアーツに注目が集まっているらしい。米国ではMedical Schoolで医学の専門教育を受ける前に一般教養課程の修了が必要であり,その中核にリベラルアーツがある。医師を目指す現代の学生がいまさらプラトンやアリストテレスの思想・哲学を学ぶ意味はどこにあるのか。中村氏の本には明快な答えがある。日本の多くの大学では真のリベラルアーツが教えられていないという話はよく耳にする。私の所属する大学でも,医学部で学ぶべき専門教育の内容が加速度的に膨らんでいくにつれ,一般教養課程はどんどん縮小されてきている。私はむしろ医学部の専門教育の前に,人間性に関するリベラルアーツを学ぶ期間が十分にあるべきだと考えている。極端に言えば,医学部入学の前に別な学部で教育を受けてもよいのではないか。実際に,最近の精神科医は,他学部を中退ないし卒業した後に医学部に入り直した人が増えている印象がある。そして,これは精神科に限ったことではなく,多様なバックグラウンドを有する人は医学部を卒業して医師免許を取得したとしても,起業したり,官公庁に就職したりするなど,卒後も多様なキャリアに進んでいくことが多い。
基本情報
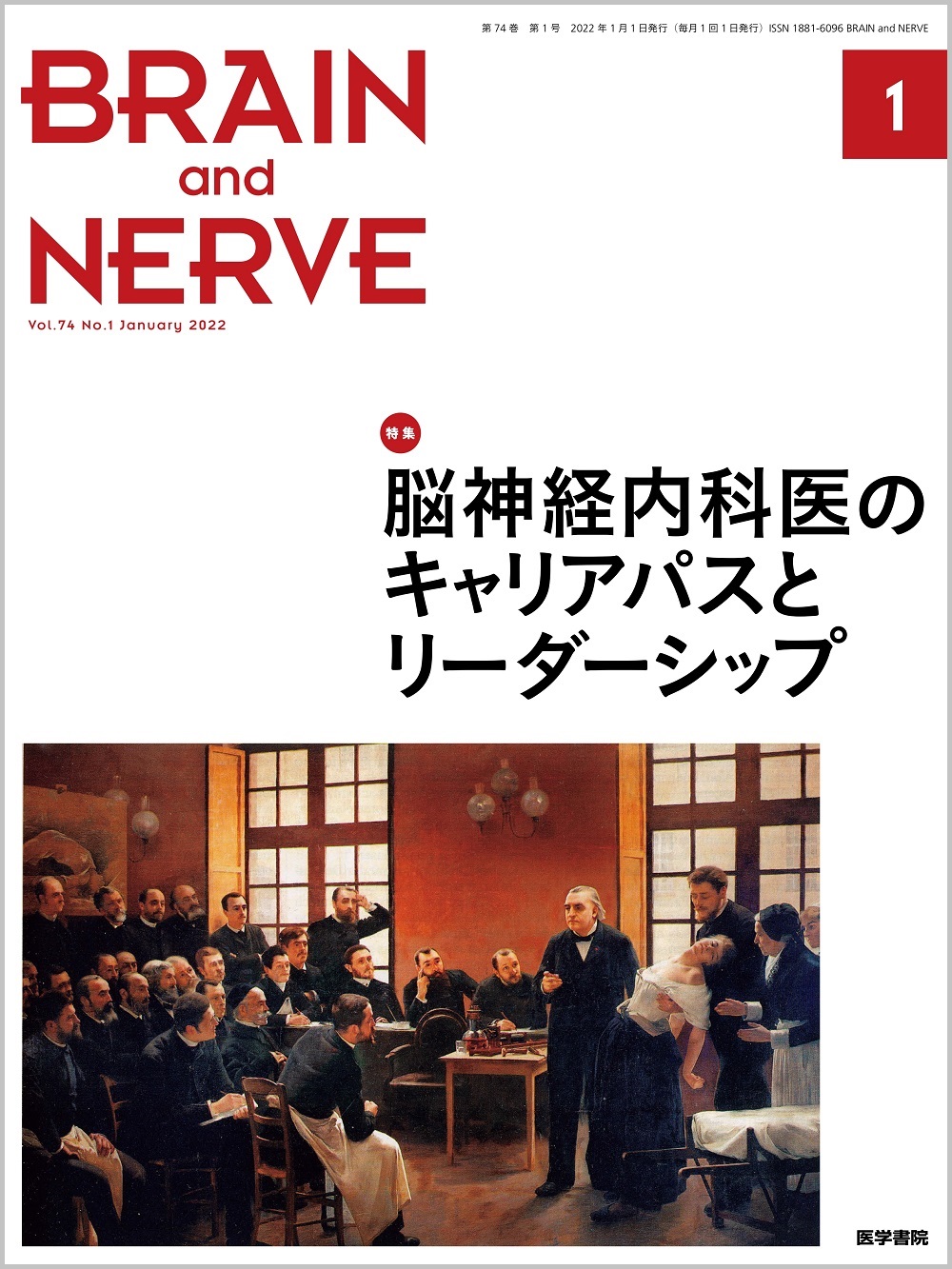
バックナンバー
76巻12号(2024年12月発行)
特集 芸術家と神経学Ⅱ
76巻11号(2024年11月発行)
特集 ALS 2024
76巻10号(2024年10月発行)
特集 どうして効くんだろう
76巻9号(2024年9月発行)
特集 治療可能な認知症としてのアルツハイマー病
76巻8号(2024年8月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である—revisited
76巻7号(2024年7月発行)
特集 ニューロ・バイオイメージング—技術と応用
76巻6号(2024年6月発行)
特集 注意と注意障害
76巻5号(2024年5月発行)
増大特集 末梢神経・筋肉の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
76巻4号(2024年4月発行)
特集 神経病理最前線
76巻3号(2024年3月発行)
特集 きちんと説明ができますか?
76巻2号(2024年2月発行)
特集 特発性正常圧水頭症の現在
76巻1号(2024年1月発行)
特集 新時代の重症筋無力症と関連疾患の診療
75巻12号(2023年12月発行)
特集 アガサ・クリスティーと神経毒
75巻11号(2023年11月発行)
特集 アロスタシス—ホメオスタシスを超えて
75巻10号(2023年10月発行)
特集 メタバースへの招待
75巻9号(2023年9月発行)
特集 妊娠と神経疾患
75巻8号(2023年8月発行)
特集 アルツハイマー病は本当に早期発見できるのか
75巻7号(2023年7月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part2 末梢編
75巻6号(2023年6月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part1 中枢編
75巻5号(2023年5月発行)
増大特集 神経・精神領域の薬剤ハンドブック
75巻4号(2023年4月発行)
特集 All About Epilepsy
75巻3号(2023年3月発行)
特集 慢性疼痛
75巻2号(2023年2月発行)
特集 多系統萎縮症の新診断基準とこれからの診療
75巻1号(2023年1月発行)
特集 よく出会う不随意運動を知る
74巻12号(2022年12月発行)
特集 映画を観て精神・神経疾患を知る
74巻11号(2022年11月発行)
特集 RFC1遺伝子関連スペクトラム障害
74巻10号(2022年10月発行)
特集 ウイルス性脳炎・脳症2022
74巻9号(2022年9月発行)
特集 動的環境への適応系としての歩行
74巻8号(2022年8月発行)
特集 迷走神経の不思議
74巻7号(2022年7月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識2022
74巻6号(2022年6月発行)
特集 脳神経内科医に求められる移行医療
74巻5号(2022年5月発行)
増大特集 次の一手—神経筋疾患難治例をどのように治療するか
74巻4号(2022年4月発行)
特集 脳科学リテラシーを高めるために
74巻3号(2022年3月発行)
特集 中枢性自律神経障害update
74巻2号(2022年2月発行)
特集 温度を感じる脳と身体の科学
74巻1号(2022年1月発行)
特集 脳神経内科医のキャリアパスとリーダーシップ
73巻12号(2021年12月発行)
特集 芸術家と神経学
73巻11号(2021年11月発行)
特集 「目」の神経学
73巻10号(2021年10月発行)
特集 中枢神経・末梢神経の悪性リンパ腫
73巻9号(2021年9月発行)
特集 脳卒中治療に必要な基礎知識
73巻8号(2021年8月発行)
特集 脳腸相関—脳-身体の双方向性制御
73巻7号(2021年7月発行)
特集 グリアと神経—相補的な制御系として
73巻6号(2021年6月発行)
特集 Lower Spine Neurology
73巻5号(2021年5月発行)
増大特集 中枢神経の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
73巻4号(2021年4月発行)
特集 片頭痛・群発頭痛治療の新たな夜明け
73巻3号(2021年3月発行)
特集 マルチリンガルブレイン
73巻2号(2021年2月発行)
特集 筋炎と壊死性筋症
73巻1号(2021年1月発行)
特集 Neuro-Oncology
72巻12号(2020年12月発行)
特集 超高齢期の精神神経疾患を診る
72巻11号(2020年11月発行)
増大特集 脳の発振現象—基礎から臨床へ
72巻10号(2020年10月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識
72巻9号(2020年9月発行)
特集 皮質性小脳萎縮症へのアプローチ
72巻8号(2020年8月発行)
特集 サルコイドーシス
72巻7号(2020年7月発行)
増大特集 神経倫理ハンドブック
72巻6号(2020年6月発行)
特集 前頭側頭葉変性症の今日的理解
72巻5号(2020年5月発行)
特集 多発性硬化症の現在と未来
72巻4号(2020年4月発行)
増大特集 神経疾患の診断における落とし穴—誤診を避けるために
72巻3号(2020年3月発行)
特集 でこぼこの脳の中でおしくらまんじゅうする脳機能
72巻2号(2020年2月発行)
特集 αシヌクレイノパチーの新たな展開
72巻1号(2020年1月発行)
特集 神経難病をクスリで治す—薬物開発の現況と近未来への展望
71巻12号(2019年12月発行)
特集 小脳と大脳—Masao Itoのレガシー
71巻11号(2019年11月発行)
増大特集 ALS2019
71巻10号(2019年10月発行)
特集 認知症と遺伝
71巻9号(2019年9月発行)
特集 神経疾患のドラッグ・リポジショニング—新時代へ
71巻8号(2019年8月発行)
特集 パーキンソン病診療の現在地—200年の変遷と新規治療
71巻7号(2019年7月発行)
増大特集 人工知能と神経科学
71巻6号(2019年6月発行)
特集 補体標的治療の現状と展望
71巻5号(2019年5月発行)
特集 NPSLE
71巻4号(2019年4月発行)
増大特集 神経学のための皮膚アトラス
71巻3号(2019年3月発行)
特集 Spine Neurology
71巻2号(2019年2月発行)
特集 “スポーツ”を生み出す脳
71巻1号(2019年1月発行)
特集 人工知能の医療応用Update
70巻12号(2018年12月発行)
特集 主訴に沿う—俯瞰し収束する画像診断の目
70巻11号(2018年11月発行)
増大特集 脳科学で解き明かす精神神経症候
70巻10号(2018年10月発行)
特集 「左脳と右脳」の現在
70巻9号(2018年9月発行)
特集 脳神経内科診療に役立つ精神科の知識
70巻8号(2018年8月発行)
特集 レヴィ小体型認知症の新知見
70巻7号(2018年7月発行)
増大特集 記憶と忘却に関わる脳のしくみ—分子機構から健忘の症候まで
70巻6号(2018年6月発行)
特集 芸術を生み出す脳
70巻5号(2018年5月発行)
特集 非アルツハイマー型認知症の病理学
70巻4号(2018年4月発行)
増大特集 Antibody Update 2018
70巻3号(2018年3月発行)
特集 『認知症疾患診療ガイドライン2017』を読み解く
70巻2号(2018年2月発行)
特集 知っておきたい神経感染症
70巻1号(2018年1月発行)
特集 筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群の今
69巻12号(2017年12月発行)
特集 運動異常症をみる—Web動画付録つき
69巻11号(2017年11月発行)
増大特集 こころの時間学の未来
69巻10号(2017年10月発行)
特集 成人てんかん—知っておきたい6つのトピック
69巻9号(2017年9月発行)
特集 ミクログリアと精神・神経疾患
69巻8号(2017年8月発行)
特集 遺伝性脊髄小脳失調症の病態と治療展望
69巻7号(2017年7月発行)
増大特集 あしたのアルツハイマー病治療
69巻6号(2017年6月発行)
特集 局在病変の神経心理学
69巻5号(2017年5月発行)
特集 Voxel-Based Morphometry—体積からわかること
69巻4号(2017年4月発行)
増大特集 ブロードマン領野の現在地
69巻3号(2017年3月発行)
特集 磁気刺激の新たな展開
69巻2号(2017年2月発行)
特集 Stroke-Like Diseases—鑑別時に注意を要する5病態
69巻1号(2017年1月発行)
特集 近年注目されている白質脳症
68巻12号(2016年12月発行)
特集 炎症性神経・筋疾患の新たな展開
68巻11号(2016年11月発行)
増大特集 連合野ハンドブック
68巻10号(2016年10月発行)
特集 アディクション—行動の嗜癖
68巻9号(2016年9月発行)
特集 自己免疫性脳炎・脳症
68巻8号(2016年8月発行)
特集 こころと汗
68巻7号(2016年7月発行)
増大特集 認知症の危険因子と防御因子
68巻6号(2016年6月発行)
特集 脳とフローラ
68巻5号(2016年5月発行)
特集 手の症候学—生理学・解剖学からみた新知見
68巻4号(2016年4月発行)
増大特集 治せる認知症
68巻3号(2016年3月発行)
特集 末梢神経の血管炎
68巻2号(2016年2月発行)
特集 筋疾患の認知機能障害
68巻1号(2016年1月発行)
特集 シャルコー・マリー・トゥース病
67巻12号(2015年12月発行)
特集 視床と高次脳機能
67巻11号(2015年11月発行)
増大特集 ギラン・バレー症候群のすべて—100年の軌跡
67巻10号(2015年10月発行)
特集 非・日常生活の脳科学
67巻9号(2015年9月発行)
特集 酵素補充療法
67巻8号(2015年8月発行)
特集 神経難病の終末期医療
67巻7号(2015年7月発行)
増大特集 神経疾患と感染症update
67巻6号(2015年6月発行)
特集 脳と「質感」
67巻5号(2015年5月発行)
特集 NCSE(非痙攣性てんかん重積状態)
67巻4号(2015年4月発行)
増大特集 大脳皮質vs.大脳白質
67巻3号(2015年3月発行)
特集 中枢神経の血管炎
67巻2号(2015年2月発行)
特集 「食べる」を考える
67巻1号(2015年1月発行)
特集 ニューロトキシコロジー
66巻12号(2014年12月発行)
特集 Orthopaedic Neurology—神経内科と整形外科の狭間で
66巻11号(2014年11月発行)
増大特集 神経症候学は神経学の“魂”である
66巻10号(2014年10月発行)
特集 分子を撃つ 神経疾患治療の新しい水平線
66巻9号(2014年9月発行)
特集 痙縮の臨床神経学
66巻8号(2014年8月発行)
特集 神経系の悪性リンパ腫update
66巻7号(2014年7月発行)
増大特集 アミロイド関連神経疾患のすべて―封入体筋炎からアルツハイマー病まで
66巻6号(2014年6月発行)
特集 ミラーニューロン
66巻5号(2014年5月発行)
特集 アセチルコリンと神経疾患―100年目の現在地
66巻4号(2014年4月発行)
増大特集 タッチ・ビジョン・アクション
66巻3号(2014年3月発行)
特集 神経筋疾患の超音波診断
66巻2号(2014年2月発行)
特集 糖尿病の神経学revisited
66巻1号(2014年1月発行)
特集 日常生活の脳科学
65巻12号(2013年12月発行)
特集 プロテイノパチーの神経病理学
65巻11号(2013年11月発行)
増大特集 Close Encounters―臨床神経学と臨床免疫学の遭遇と未来
65巻10号(2013年10月発行)
特集 神経系の発達メカニズム―最近の話題
65巻9号(2013年9月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である―現状と展望
65巻8号(2013年8月発行)
特集 こころの時間学―現在・過去・未来の起源を求めて
65巻7号(2013年7月発行)
増大特集 あしたの脳梗塞
65巻6号(2013年6月発行)
特集 見せる・仕分ける―脳機能解析の新手法
65巻5号(2013年5月発行)
特集 てんかん―新しいパースペクティブ
65巻4号(2013年4月発行)
増大特集 Antibody Update
65巻3号(2013年3月発行)
特集 次世代シーケンサーによる神経変性疾患の解析と展望
65巻2号(2013年2月発行)
特集 血液脳関門研究の進歩
65巻1号(2013年1月発行)
特集 Corticobasal Syndrome
64巻12号(2012年12月発行)
特集 The Border-Land of Dementia
64巻11号(2012年11月発行)
増大特集 痛みの神経学―末梢神経から脳まで
64巻10号(2012年10月発行)
特集 辺縁系をめぐって
64巻9号(2012年9月発行)
特集 高次脳機能イメージングの脳科学への新展開
64巻8号(2012年8月発行)
特集 線条体の基礎と臨床
64巻7号(2012年7月発行)
増大特集 顔認知の脳内機構
64巻6号(2012年6月発行)
特集 睡眠と覚醒の脳内機構
64巻5号(2012年5月発行)
特集 神経疾患のバイオマーカー
64巻4号(2012年4月発行)
増大特集 パーキンソン病の新しい側面
64巻3号(2012年3月発行)
特集 アカデミアから新規治療の実現へ―トランスレーショナルリサーチの現状
64巻2号(2012年2月発行)
特集 生物学的精神医学の進歩
64巻1号(2012年1月発行)
特集 iPS細胞と神経疾患
63巻12号(2011年12月発行)
特集 神経心理学と画像解析の融合
63巻11号(2011年11月発行)
増大特集 筋疾患update
63巻10号(2011年10月発行)
特集 緩徐進行性高次脳機能障害の病態
63巻9号(2011年9月発行)
特集 脳卒中の最新画像診断
63巻8号(2011年8月発行)
特集 日本人の発見した神経症候
63巻7号(2011年7月発行)
増大特集 神経筋接合部―基礎から臨床まで
63巻6号(2011年6月発行)
特集 ニューロパチー
63巻5号(2011年5月発行)
特集 神経系と血管内リンパ腫
63巻4号(2011年4月発行)
増大特集 てんかんの新しい治療
63巻3号(2011年3月発行)
特集 サイバーナイフ治療
63巻2号(2011年2月発行)
特集 続・日本人の発見した神経疾患
63巻1号(2011年1月発行)
特集 血管腫
62巻12号(2010年12月発行)
特集 頸部頸動脈狭窄症の診断と治療
62巻11号(2010年11月発行)
増大特集 歩行とその異常
62巻10号(2010年10月発行)
特集 ブレインバンク
62巻9号(2010年9月発行)
特集 視神経脊髄炎(NMO)update
62巻8号(2010年8月発行)
特集 辺縁系脳炎
62巻7号(2010年7月発行)
増大特集 アルツハイマー病―研究と診療の進歩
62巻6号(2010年6月発行)
特集 改正臓器移植法の問題点とその対応
62巻5号(2010年5月発行)
特集 神経画像のピットフォール―見落としと読み過ぎ
62巻4号(2010年4月発行)
特集 傍腫瘍性神経筋疾患update
62巻3号(2010年3月発行)
特集 神経回路解析法の最近の進歩
62巻2号(2010年2月発行)
特集 ニューロリハビリテーションの最前線
62巻1号(2010年1月発行)
特集 神経救急
61巻12号(2009年12月発行)
特集 Somatotopy再考
61巻11号(2009年11月発行)
特集 前頭側頭葉変性症
61巻10号(2009年10月発行)
特集 片頭痛の予防療法
61巻9号(2009年9月発行)
特集 脳血管障害治療の進歩
61巻8号(2009年8月発行)
特集 神経・筋疾患の分子標的治療
61巻7号(2009年7月発行)
特集 脳腫瘍研究の最前線―遺伝子解析から治療まで
61巻6号(2009年6月発行)
特集 脊椎・脊髄外科の最近の進歩
61巻5号(2009年5月発行)
特集 Restless legs syndrome
61巻4号(2009年4月発行)
特集 大脳基底核―分子基盤から臨床まで
61巻3号(2009年3月発行)
特集 Microneurography(微小神経電図法)の臨床応用
61巻2号(2009年2月発行)
特集 神経系の再興感染症と輸入感染症
61巻1号(2009年1月発行)
特集 脳神経倫理
60巻12号(2008年12月発行)
特集 痙縮
60巻11号(2008年11月発行)
特集 脳卒中と遺伝子
60巻10号(2008年10月発行)
特集 若年者の脳卒中
60巻9号(2008年9月発行)
特集 知・情・意の神経学
60巻8号(2008年8月発行)
特集 脳硬膜動静脈瘻
60巻7号(2008年7月発行)
増大特集 学習と記憶――基礎と臨床
60巻6号(2008年6月発行)
特集 Crow-深瀬症候群(POEMS症候群)
60巻5号(2008年5月発行)
特集 「痛み」の研究と治療の最前線
60巻4号(2008年4月発行)
増大特集 神経系の発生とその異常
60巻3号(2008年3月発行)
特集 特発性正常圧水頭症(iNPH)―最近の話題
60巻2号(2008年2月発行)
特集 がん治療と神経障害
60巻1号(2008年1月発行)
特集 日本人の発見した神経疾患
59巻12号(2007年12月発行)
特集 損傷神経の再生―温存的治療法の開発
59巻11号(2007年11月発行)
特集 手根管症候群をめぐって
59巻10号(2007年10月発行)
増大特集 ALS―研究と診療の進歩
59巻9号(2007年9月発行)
特集 パーキンソン病の認知機能障害
59巻8号(2007年8月発行)
特集 パーキンソン病の分子遺伝学―最近の知見
59巻7号(2007年7月発行)
増大特集 情報伝達処理におけるグリアの機能と異常
59巻6号(2007年6月発行)
特集 職業性神経障害の新しい展開
59巻5号(2007年5月発行)
特集 脳画像最前線
59巻4号(2007年4月発行)
増大特集 最近注目される脳神経疾患治療の研究
59巻3号(2007年3月発行)
特集 分子イメージング
59巻2号(2007年2月発行)
特集 進行性多巣性白質脳症の新しい展開―PMLが治る時代へ向けて
59巻1号(2007年1月発行)
特集 高次視覚研究の最近の進歩
