昨年12月号『芸術家と神経学』に引き続き,クリスマス特集を企画しました。精神・神経疾患が描かれた映画を題材として,その疾患がどのように扱われていたのか歴史を紐解くとともに,病態の解明や治療法の進歩,社会状況の変化を踏まえ現代の視座から何が考えられるのかを解説しています。映画館に行くことも大変になった世の中で,自宅で映画鑑賞でもしながら,あらためてさまざまな精神・神経疾患への理解を深め,楽しい年の瀬のひと時をお過ごしください。
雑誌目次
BRAIN and NERVE-神経研究の進歩74巻12号
2022年12月発行
雑誌目次
特集 映画を観て精神・神経疾患を知る
嗜眠性脳炎—『レナードの朝』
著者: 神田隆
ページ範囲:P.1327 - P.1330
1917〜1928年の間に全世界を席巻した嗜眠性脳炎は,脳炎後パーキンソニズムの代表的な原因疾患である。オリヴァー・サックス氏は,自身のマウント・カーメル病院での臨床経験を基にこの映画の原作であるAwakeningsを著し,映画はロビン・ウィリアムスとロバート・デ・ニーロを主役として1990年に公開された。レボドパ黎明期の脳炎後パーキンソニズム患者への効果,副作用,そして同治療の結末が時間を追って描かれており,長期にわたって治療法がなかった患者が「帰ってきた」ことの喜びの共有こそが,私たち脳神経内科医の原動力であることを思い起こさせる。そして何より,ロバート・デ・ニーロの迫真的な演技がこの映画の白眉である。
『アリスのままで』にみる遺伝子診断の重さ
著者: 安東由喜雄
ページ範囲:P.1331 - P.1334
映画『アリスのままで』に登場するアリスは,若年性アルツハイマー病を患っている。本症の多くは孤発例で,通常65歳以降に発症するが,遺伝性の場合,多くはプレセニリン1,2やアミロイドβ蛋白質などの遺伝子異常で起こり,アリスのように発症年齢は50代が多い。彼女はプレセニリン遺伝子変異を持つことがわかるが,本映画では,3人の子供たちの遺伝子診断に対するアリスの葛藤も描かれている。
映画にみる認知症
著者: 三村將
ページ範囲:P.1335 - P.1345
映画は人の生きざまを描き出すための映像芸術の一手法である。人生は記憶に裏打ちされており,記憶喪失をはじめ,記憶障害をテーマとした映画は古今東西,枚挙にいとまがない。その中で認知症を扱った映画も多い。本稿では若年性レビー小体型認知症の人とその家族を描いた『妻の病 レビー小体型認知症』と,若年性アルツハイマー病の人とその家族を描いた『アリスのままで』という2作品を取り上げ,精神医学的観点から考察を試みた。前者の作品では幻覚妄想状態と視覚認知障害,また認知症の介護に焦点を当てた。後者の作品では認知症の語健忘,自己鏡像認知障害,自殺,そして告知の問題について私見を述べた。
抗NMDA受容体脳炎—『エクソシスト』,『8年越しの花嫁 奇跡の実話』,『彼女が目覚めるその日まで』
著者: 亀井聡
ページ範囲:P.1346 - P.1349
抗NMDA(N-methyl-D-aspartate)受容体脳炎は,若年成人女性に好発する自己免疫性脳炎であり,亜急性に精神症状で始まり,痙攣・不随意運動・意識障害・呼吸抑制を呈する。この経過から昔は悪魔による仕業と考えられ,悪魔祓いされたこともあった。映画『エクソシスト』の原作モデルの患者は,本症であったとの指摘がなされている。また本症は免疫治療で軽快するが,回復まで年余を要する場合もあり,その体験談が映画化され,本邦では『8年越しの花嫁 奇跡の実話』,米国では『彼女が目覚めるその日まで』が製作されている。このように本症は一般の方にも知られるようになっている。
...First Do No Harm—薬剤抵抗性てんかん
著者: 甲田一馬 , 松本理器
ページ範囲:P.1350 - P.1353
てんかんは大脳の神経細胞が過剰に興奮する疾患であるが,歴史上では悪魔や精霊によるものと考えられていた。治療には抗てんかん薬が用いられるが,抵抗性の場合は手術療法が検討される。本作中の1990年代以降から,脳機能マッピングや,術中モニタリングの進歩により,外科手術の安全性は向上した。手術の適応がない場合は,ケトン食療法が施行される。本作はケトン食療法の周知に寄与し,2016年から本邦でも保険適用となっている。
副腎白質ジストロフィー—『ロレンツォのオイル/命の詩』
著者: 山脇健盛
ページ範囲:P.1354 - P.1357
『ロレンツォのオイル/命の詩』は,1992年に公開された映画である。5歳のロレンツォに奇行が目立ち始め,徐々に運動機能,言語機能が障害されていった。両親は,医学知識がないにもかかわらず,独学でこの疾患の勉強を始め,ついに治療法を見つけていくという事実に基づいた過程を描いた感動作である。本作の配役は,ほとんど実名が出ており,1992年の公開後もいろいろな意味で話題を提供してきた。
慢性外傷性脳症—『コンカッション』
著者: 下畑享良
ページ範囲:P.1358 - P.1361
実話に基づいて2015年に米国で製作された映画『コンカッション』を紹介する。この映画は慢性外傷性脳症(chronic traumatic encephalopathy:CTE)が米国においてどのように社会問題として取り上げられるようになったかを理解するのに有用なだけでなく,科学者が真実に向き合う姿勢について考えさせられる。CTE研究の歴史と現状についても合わせて提示する。
『ビューティフル・マインド』の異教的鑑賞ガイド
著者: 村松太郎
ページ範囲:P.1362 - P.1365
統合失調症の当事者であり,かつノーベル賞受賞者であるジョン・ナッシュの半生を描いたアカデミー賞受賞作品『ビューティフル・マインド』は,感動的なラブストーリーであるとともに,統合失調症の優れた教科書にもなっている。ただしもちろん美化されている部分も含まれている。真実を知るためには,ナッシュについても統合失調症についても,光だけでなく影の部分を見なければならない。
映画『ジキル&ハイド』と解離性同一性障害—自己分裂の不安に立ち戻る
著者: 林直樹
ページ範囲:P.1366 - P.1370
『ジキル博士とハイド氏』は,英国で1886年に刊行された小説であり,解離性同一性障害の代名詞として語られてきた。それは繰り返し映画化されてきたのだが,それはそこに描かれている自己分裂の不安が現代人に広く見られるものだからであろう。原小説のサイドストーリーを映画化した1996年の『ジキル&ハイド』は,住み込みのメイドとジキル,ハイドそれぞれとの交流が描かれており,そこに現代人の自己分裂を癒す治療的示唆を見出すことができる。
親友『レインマン』
著者: 酒井邦嘉
ページ範囲:P.1371 - P.1374
映画『レインマン』の主人公は自閉症サヴァンであり,利己的な弟との絆が描かれる。印象的なのは彼らの道中であり,互いへの共感と思いやりが乏しかった兄弟が,時を共にして学び,関係を深めていく。本稿では,高機能の自閉症サヴァンに見られる視覚的および数学的な把握力について例を挙げる。神経科学から自閉スペクトラム症のメカニズムについて仮説をいくつか紹介し,それらの意義と研究の方向性についても議論する。
吃音—『英国王のスピーチ』にみる発話機能の理解
著者: 虫明元
ページ範囲:P.1375 - P.1378
『英国王のスピーチ』は2010年の映画で,吃音に悩まされた英国王ジョージ6世と,その治療にあたったオーストラリア出身の平民である言語聴覚士ライオネル・ローグの友情を史実を基に描いた作品である。映画のシーンを振り返りながら,一見奇妙に思えるローグの治療法や行動の背景になる発話とその障害としての吃音に関して神経科学的に考察する。
『カッコーの巣の上で』にみる精神・神経疾患
著者: 髙尾昌樹
ページ範囲:P.1379 - P.1383
映画『カッコーの巣の上で』のワンシーンとして出てくる電気痙攣療法とロボトミーに関してまとめた。電気痙攣療法は,紆余曲折を経ながらも有効な治療法としての地位を築いた。ロボトミーは施行されることはなくなった。医学者には,未来を見据えた,確かなる治療法の確立を目指す責務が課せられている。
ALSと映像作品
著者: 荻野美恵子
ページ範囲:P.1384 - P.1387
ALSは進行性の身体障害をきたし,気管切開人工呼吸器を選択しなければ3〜5年で死亡する病気であるため,頻度の低い病気ながら多くの人に知られる。不自由な体ながら生きることを選ぶのか逝くのかを自ら選択することになり,どのような状態を「生きる」と考えるのかという課題を突き付けられる。このようなテーマを取り上げた映像作品を見ることで,この問いをさらに深く捉えることができる。
『震える舌』 破傷風—50年前の医療現場と家族の心情描写
著者: 吉沢和朗
ページ範囲:P.1388 - P.1391
映画『震える舌』は50年前の医療現場を忠実に再現している。5歳の主役は破傷風の症状を正確に表現し,当時の医療環境,医療機器,医薬品を駆使した懸命の治療にもかかわらず,症状が悪化し,それに伴い両親の不安や恐怖が増していく過程が詳細に映像化される。現在との比較,破傷風の歴史,疫学,広域災害時の発生,日常生活の中での発症,医療裁判などに触れ,最終的には個人がワクチン接種で防御すべき疾患であると確認した。
ハンセン病—『砂の器』
著者: 松原四郎
ページ範囲:P.1392 - P.1394
ハンセン病は主に末梢神経と皮膚に症状を表すらい菌による慢性感染症である。戦後有効な治療薬ができ日本では克服された。戦前は早期発見と隔離が唯一の有効な対策であったことから強制隔離などの施策がとられ,病気への強い恐怖感を国民に与える結果となった。その施策が戦後も長期に維持された原因の1つとして,疾患に対する正しい知識が社会に普及するのに年月を要したことが挙げられる。この間同病を扱った2本の映画を中心に述べる。
『ほんとうのジャクリーヌ・デュ・プレ』—天才チェリストと多発性硬化症
著者: 王子聡
ページ範囲:P.1395 - P.1398
映画『ほんとうのジャクリーヌ・デュ・プレ』は,天才チェリストであるジャクリーヌ・デュ・プレが,多発性硬化症(multiple sclerosis:MS)を発症したことをきっかけに,一人の音楽家として,そして一人の人間としての自身の意義について思い悩む姿を描いた作品である。本稿では,ジャクリーヌのMSとしての臨床像,そしてジャクリーヌにとって最善であると考えられるMS治療について,当時のMS診療と最新のMS治療戦略を比較しながら考察する。
『潜水服は蝶の夢を見る』から患者の気持ちを考える
著者: 鈴木健太郎
ページ範囲:P.1399 - P.1401
『潜水服は蝶の夢を見る』は脳梗塞により閉じ込め症候群(locked-in syndrome)を呈した元編集局長 ジャン=ドミニク・ボビー(Jean-Dominique Bauby:1952-1997)が,眼球運動による意思疎通で本を執筆するという実話を基に製作された映画である。日常診療で医療者側としては経験することのない,患者目線での感情がリアルに描かれており,年末や仕事の区切りで自らを振り返る際に,ぜひお勧めしたい作品です。本稿では,locked-in syndromeの臨床についても解説し,最後に映画について触れることとする。
脊髄小脳変性症—『1リットルの涙』
著者: 佐々木秀直
ページ範囲:P.1402 - P.1404
この作品は脊髄小脳変性症と診断された少女の闘病日記を映画化したものである。13歳で起立・歩行のふらつきで発症し,高校に入学するが,2年生で養護学校に転校した。在宅療養を経て入院療養生活に至る。病の進行が人生の夢を次々と奪っていく。しかし家族,友人,医療関係者の支援のもとに自らの人生を精一杯生きる様が描かれている。難治性進行性疾患における医師と患者の関わり方について考えさせる作品である。
筋ジストロフィー—『こんな夜更けにバナナかよ』
著者: 尾方克久
ページ範囲:P.1405 - P.1408
本邦では1964年から国立療養所に筋萎縮症病棟が整備され,医療,訓練,教育の機会が提供され療育が図られた。1990年代以降,心肺治療の進歩により筋ジストロフィーの生命予後は伸び,社会資本整備も進んだが,障害者の社会生活に対する支援体制整備にはなお時間を要した。『こんな夜更けにバナナかよ』は,自立生活を営んだ筋ジストロフィー患者とボランティアを描いた書籍であり,同書を原案に製作された映画作品である。
ポンペ病—『小さな命が呼ぶとき』
著者: 大矢寧
ページ範囲:P.1409 - P.1413
やや軽症の乳児型ポンペ病(糖原病Ⅱ型)の患児2人を抱えた両親,特に父親が糖生物学研究者とともに治療薬の開発に携わる話の映画化である。ポンペ病は呼吸筋罹患が目立つ筋疾患で,ライソゾーム病でもある。乳児型は心筋症や肝腫大も伴う。酵素補充療法が米国で2006年に承認されるまでの経過のノンフィクションを,映画では少し脚色している。難病患者を抱える家族の葛藤,患者会の力や,希少疾患をめぐる製薬企業の事情も描かれている。
連載 脳神経内科領域における医学教育の展望—Post/withコロナ時代を見据えて・16【最終回】
Post/withコロナ時代で見えてくる海外の動向とわが国の方向性—医学教育のレヴューと連載のまとめ
著者: 西城卓也 , 今福輪太郎 , 下畑享良
ページ範囲:P.1417 - P.1422
はじめに
2020年初旬からのCOVID-19感染症拡大は,わが国の医学教育の大きな転換期になったと言えます。これまで当たり前であった人々との対話や交流を主体とした対面での教育が,「新しい生活様式」のもと密閉・密集・密接を避けた教育への転換を余儀なくされました。特に,学習機会の確保のために,短期間でオンライン教育を導入することが求められました。あれから2年近くが経ち,現行の教育の代替として導入されてきたオンライン教育は,同期型と非同期型双方のメリット・デメリットを踏まえつつ,学習目標や評価方法に応じてどのように選択もしくは組み合わせながら教育を設計していくのかといった意識へと変わってきたように思います1)。本稿では,COVID-19のパンデミックの影響を受けた2020年から22年にかけての医学教育の国際的な動向を概観したあと,脳神経内科領域の教育の取り組みをご紹介し,Post/withコロナ時代を見据えたわが国の脳神経内科教育の方向性について考察したいと思います。
臨床神経学プロムナード—60余年を顧みて・22【最終回】
人名語eponymeさまざま,それは何故使われるか—それぞれに歴史や背景がある。
著者: 平山惠造
ページ範囲:P.1423 - P.1426
人名語は古くから使われて来た。病名や病態などを簡潔に表現するのに有用な場合があるからである。それぞれの人名語にはそれが造られるに至った背景がある。また確定するのに年月を要したものもあれば,批判・疑義が訴えられたものもある。それぞれの人名語が生まれた背景や歴史を散策すると意外な大切なものが見えてくる。ここでは良く知られている幾つかを散策してみよう。
書評
「—臨床で使える—半側空間無視への実践的アプローチ」—前田眞治【監修】菅原光晴,原麻理子,山本 潤【編】 フリーアクセス
著者: 石合純夫
ページ範囲:P.1415 - P.1415
脳卒中を中心とする脳疾患でみられる高次脳機能障害は多彩であるが,移動能力を含む生活機能全般のリハビリテーションに大きな影響を及ぼし,治療を難渋させるものは「半側空間無視」である。半側空間無視は,主に右半球損傷後に起こり,簡単に言えば,身体から見た左側の空間や注目した物の左側とうまく付き合えなくなる症状である。視野障害と違って,頭部や視線を動かして良い状況で起こるため,日常生活のあらゆる場面に困難をもたらす。半側空間無視は,空間性注意の方向性の偏りに,その臨床的表現を顕在化するいくつかの要因が加わって起こると考えられ,そのリハビリテーションには,行動面の多角的な分析と多職種によるアプローチが不可欠である。
本書は,タイトルに「臨床に使える」・「実践的アプローチ」とあるように,まさにリハビリテーションの現場で日々利用できる内容で,5つの章から構成されている。
「問題解決型救急初期診療 第3版」—田中和豊【著】 フリーアクセス
著者: 増井伸高
ページ範囲:P.1416 - P.1416
◆何を指標に選ぶか?
2020年代以降は救急のマニュアル本が非常に充実しています。研修医は数十冊以上の中から何を買うか迷ってしまうでしょう。上級医だってオススメ本を知る必要があります。数あるマニュアル本から皆さんは何を指標に選んでいますか?
「先輩研修医に聞く」「書店で読み比べる」「Amazonの★の数」いずれも悪くありません。しかし,私のオススメは「増刷数の多いものを選ぶ」という戦略です。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.1323 - P.1323
欧文目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.1324 - P.1324
バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.1432 - P.1432
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.1433 - P.1433
あとがき フリーアクセス
著者: 酒井邦嘉
ページ範囲:P.1434 - P.1434
今年はグレン・グールド(Glenn Gould, 1932-1982)というピアニストの生誕90年・没後40年である。さまざまな特別企画の中でも圧巻なのは,グールドが1981年に再録音したJ.S.バッハ作曲《ゴルトベルク変奏曲》(「ゴールドベルク」ではなく,ドイツ語の発音に近い表記とする)について,レコーディングセッションの全テイクが初めて公開されたことだろう(ソニー・ミュージックレーベルズより発売)。実は5年前にも同様の企画があり,そちらはグールドのデビュー盤となった同曲の録音セッション(1955年)が対象だった。映画やテレビドラマの撮影では複数のテイクを編集するのが常識だが,音楽録音に本格的な編集作業を導入したのはグールドが最初である。変奏曲のテーマとして冒頭と末尾を飾る「アリア」だけでも,テイクの数は1955年盤で18回,1981年盤は20回(インサートを含む)に及ぶ。「アリアのリメイク,テイク297」と冗談を飛ばす録音技師とグールドのやり取りも克明に収録されている。それぞれのテイクが万華鏡のように美しく変容していく様は,グールドの飽くなき探究心と創作過程を浮き彫りにする。
演奏の「いいとこ取り」を批判する人々に対して,「まず第一に,演奏家のいわゆる『一貫した構想』から生じる美点と想定されるものの多くは,本質的に音楽と何の関わりもないということだ。〔中略〕第二に,だれがやっても演奏の様式まで編集することはけっしてできないという現実がある」とグールドは反論した[ティム・ペイジ(編),野水瑞穂(訳) グレン・グールド著作集2—パフォーマンスとメディア.みすず書房,pp.148-149]。この「演奏」を「演技」と見なせば,映画にも同じ議論が成り立つだろう。
「BRAIN and NERVE」第74巻 総目次 フリーアクセス
ページ範囲:P. - P.
基本情報
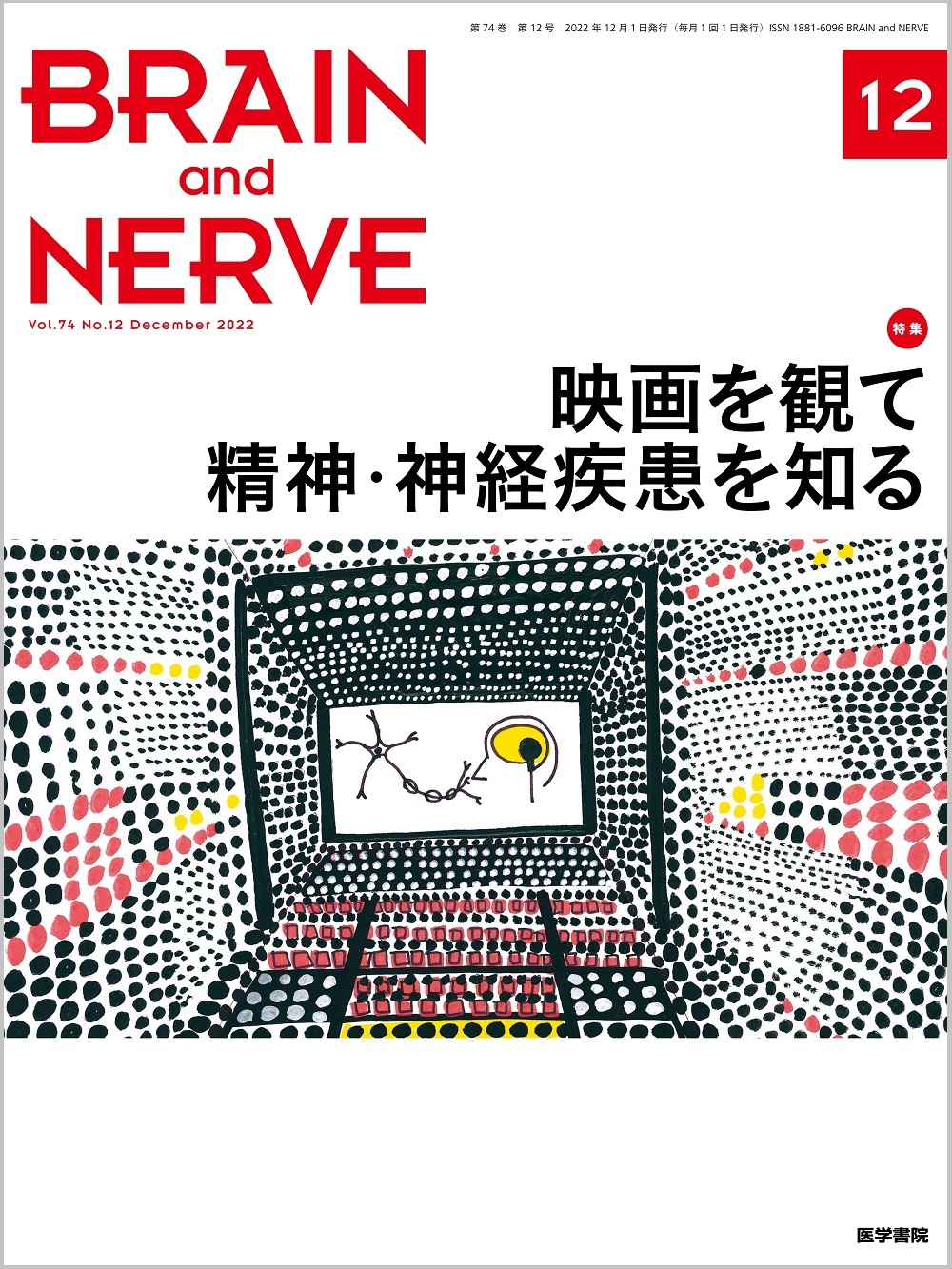
バックナンバー
76巻12号(2024年12月発行)
特集 芸術家と神経学Ⅱ
76巻11号(2024年11月発行)
特集 ALS 2024
76巻10号(2024年10月発行)
特集 どうして効くんだろう
76巻9号(2024年9月発行)
特集 治療可能な認知症としてのアルツハイマー病
76巻8号(2024年8月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である—revisited
76巻7号(2024年7月発行)
特集 ニューロ・バイオイメージング—技術と応用
76巻6号(2024年6月発行)
特集 注意と注意障害
76巻5号(2024年5月発行)
増大特集 末梢神経・筋肉の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
76巻4号(2024年4月発行)
特集 神経病理最前線
76巻3号(2024年3月発行)
特集 きちんと説明ができますか?
76巻2号(2024年2月発行)
特集 特発性正常圧水頭症の現在
76巻1号(2024年1月発行)
特集 新時代の重症筋無力症と関連疾患の診療
75巻12号(2023年12月発行)
特集 アガサ・クリスティーと神経毒
75巻11号(2023年11月発行)
特集 アロスタシス—ホメオスタシスを超えて
75巻10号(2023年10月発行)
特集 メタバースへの招待
75巻9号(2023年9月発行)
特集 妊娠と神経疾患
75巻8号(2023年8月発行)
特集 アルツハイマー病は本当に早期発見できるのか
75巻7号(2023年7月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part2 末梢編
75巻6号(2023年6月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part1 中枢編
75巻5号(2023年5月発行)
増大特集 神経・精神領域の薬剤ハンドブック
75巻4号(2023年4月発行)
特集 All About Epilepsy
75巻3号(2023年3月発行)
特集 慢性疼痛
75巻2号(2023年2月発行)
特集 多系統萎縮症の新診断基準とこれからの診療
75巻1号(2023年1月発行)
特集 よく出会う不随意運動を知る
74巻12号(2022年12月発行)
特集 映画を観て精神・神経疾患を知る
74巻11号(2022年11月発行)
特集 RFC1遺伝子関連スペクトラム障害
74巻10号(2022年10月発行)
特集 ウイルス性脳炎・脳症2022
74巻9号(2022年9月発行)
特集 動的環境への適応系としての歩行
74巻8号(2022年8月発行)
特集 迷走神経の不思議
74巻7号(2022年7月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識2022
74巻6号(2022年6月発行)
特集 脳神経内科医に求められる移行医療
74巻5号(2022年5月発行)
増大特集 次の一手—神経筋疾患難治例をどのように治療するか
74巻4号(2022年4月発行)
特集 脳科学リテラシーを高めるために
74巻3号(2022年3月発行)
特集 中枢性自律神経障害update
74巻2号(2022年2月発行)
特集 温度を感じる脳と身体の科学
74巻1号(2022年1月発行)
特集 脳神経内科医のキャリアパスとリーダーシップ
73巻12号(2021年12月発行)
特集 芸術家と神経学
73巻11号(2021年11月発行)
特集 「目」の神経学
73巻10号(2021年10月発行)
特集 中枢神経・末梢神経の悪性リンパ腫
73巻9号(2021年9月発行)
特集 脳卒中治療に必要な基礎知識
73巻8号(2021年8月発行)
特集 脳腸相関—脳-身体の双方向性制御
73巻7号(2021年7月発行)
特集 グリアと神経—相補的な制御系として
73巻6号(2021年6月発行)
特集 Lower Spine Neurology
73巻5号(2021年5月発行)
増大特集 中枢神経の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
73巻4号(2021年4月発行)
特集 片頭痛・群発頭痛治療の新たな夜明け
73巻3号(2021年3月発行)
特集 マルチリンガルブレイン
73巻2号(2021年2月発行)
特集 筋炎と壊死性筋症
73巻1号(2021年1月発行)
特集 Neuro-Oncology
72巻12号(2020年12月発行)
特集 超高齢期の精神神経疾患を診る
72巻11号(2020年11月発行)
増大特集 脳の発振現象—基礎から臨床へ
72巻10号(2020年10月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識
72巻9号(2020年9月発行)
特集 皮質性小脳萎縮症へのアプローチ
72巻8号(2020年8月発行)
特集 サルコイドーシス
72巻7号(2020年7月発行)
増大特集 神経倫理ハンドブック
72巻6号(2020年6月発行)
特集 前頭側頭葉変性症の今日的理解
72巻5号(2020年5月発行)
特集 多発性硬化症の現在と未来
72巻4号(2020年4月発行)
増大特集 神経疾患の診断における落とし穴—誤診を避けるために
72巻3号(2020年3月発行)
特集 でこぼこの脳の中でおしくらまんじゅうする脳機能
72巻2号(2020年2月発行)
特集 αシヌクレイノパチーの新たな展開
72巻1号(2020年1月発行)
特集 神経難病をクスリで治す—薬物開発の現況と近未来への展望
71巻12号(2019年12月発行)
特集 小脳と大脳—Masao Itoのレガシー
71巻11号(2019年11月発行)
増大特集 ALS2019
71巻10号(2019年10月発行)
特集 認知症と遺伝
71巻9号(2019年9月発行)
特集 神経疾患のドラッグ・リポジショニング—新時代へ
71巻8号(2019年8月発行)
特集 パーキンソン病診療の現在地—200年の変遷と新規治療
71巻7号(2019年7月発行)
増大特集 人工知能と神経科学
71巻6号(2019年6月発行)
特集 補体標的治療の現状と展望
71巻5号(2019年5月発行)
特集 NPSLE
71巻4号(2019年4月発行)
増大特集 神経学のための皮膚アトラス
71巻3号(2019年3月発行)
特集 Spine Neurology
71巻2号(2019年2月発行)
特集 “スポーツ”を生み出す脳
71巻1号(2019年1月発行)
特集 人工知能の医療応用Update
70巻12号(2018年12月発行)
特集 主訴に沿う—俯瞰し収束する画像診断の目
70巻11号(2018年11月発行)
増大特集 脳科学で解き明かす精神神経症候
70巻10号(2018年10月発行)
特集 「左脳と右脳」の現在
70巻9号(2018年9月発行)
特集 脳神経内科診療に役立つ精神科の知識
70巻8号(2018年8月発行)
特集 レヴィ小体型認知症の新知見
70巻7号(2018年7月発行)
増大特集 記憶と忘却に関わる脳のしくみ—分子機構から健忘の症候まで
70巻6号(2018年6月発行)
特集 芸術を生み出す脳
70巻5号(2018年5月発行)
特集 非アルツハイマー型認知症の病理学
70巻4号(2018年4月発行)
増大特集 Antibody Update 2018
70巻3号(2018年3月発行)
特集 『認知症疾患診療ガイドライン2017』を読み解く
70巻2号(2018年2月発行)
特集 知っておきたい神経感染症
70巻1号(2018年1月発行)
特集 筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群の今
69巻12号(2017年12月発行)
特集 運動異常症をみる—Web動画付録つき
69巻11号(2017年11月発行)
増大特集 こころの時間学の未来
69巻10号(2017年10月発行)
特集 成人てんかん—知っておきたい6つのトピック
69巻9号(2017年9月発行)
特集 ミクログリアと精神・神経疾患
69巻8号(2017年8月発行)
特集 遺伝性脊髄小脳失調症の病態と治療展望
69巻7号(2017年7月発行)
増大特集 あしたのアルツハイマー病治療
69巻6号(2017年6月発行)
特集 局在病変の神経心理学
69巻5号(2017年5月発行)
特集 Voxel-Based Morphometry—体積からわかること
69巻4号(2017年4月発行)
増大特集 ブロードマン領野の現在地
69巻3号(2017年3月発行)
特集 磁気刺激の新たな展開
69巻2号(2017年2月発行)
特集 Stroke-Like Diseases—鑑別時に注意を要する5病態
69巻1号(2017年1月発行)
特集 近年注目されている白質脳症
68巻12号(2016年12月発行)
特集 炎症性神経・筋疾患の新たな展開
68巻11号(2016年11月発行)
増大特集 連合野ハンドブック
68巻10号(2016年10月発行)
特集 アディクション—行動の嗜癖
68巻9号(2016年9月発行)
特集 自己免疫性脳炎・脳症
68巻8号(2016年8月発行)
特集 こころと汗
68巻7号(2016年7月発行)
増大特集 認知症の危険因子と防御因子
68巻6号(2016年6月発行)
特集 脳とフローラ
68巻5号(2016年5月発行)
特集 手の症候学—生理学・解剖学からみた新知見
68巻4号(2016年4月発行)
増大特集 治せる認知症
68巻3号(2016年3月発行)
特集 末梢神経の血管炎
68巻2号(2016年2月発行)
特集 筋疾患の認知機能障害
68巻1号(2016年1月発行)
特集 シャルコー・マリー・トゥース病
67巻12号(2015年12月発行)
特集 視床と高次脳機能
67巻11号(2015年11月発行)
増大特集 ギラン・バレー症候群のすべて—100年の軌跡
67巻10号(2015年10月発行)
特集 非・日常生活の脳科学
67巻9号(2015年9月発行)
特集 酵素補充療法
67巻8号(2015年8月発行)
特集 神経難病の終末期医療
67巻7号(2015年7月発行)
増大特集 神経疾患と感染症update
67巻6号(2015年6月発行)
特集 脳と「質感」
67巻5号(2015年5月発行)
特集 NCSE(非痙攣性てんかん重積状態)
67巻4号(2015年4月発行)
増大特集 大脳皮質vs.大脳白質
67巻3号(2015年3月発行)
特集 中枢神経の血管炎
67巻2号(2015年2月発行)
特集 「食べる」を考える
67巻1号(2015年1月発行)
特集 ニューロトキシコロジー
66巻12号(2014年12月発行)
特集 Orthopaedic Neurology—神経内科と整形外科の狭間で
66巻11号(2014年11月発行)
増大特集 神経症候学は神経学の“魂”である
66巻10号(2014年10月発行)
特集 分子を撃つ 神経疾患治療の新しい水平線
66巻9号(2014年9月発行)
特集 痙縮の臨床神経学
66巻8号(2014年8月発行)
特集 神経系の悪性リンパ腫update
66巻7号(2014年7月発行)
増大特集 アミロイド関連神経疾患のすべて―封入体筋炎からアルツハイマー病まで
66巻6号(2014年6月発行)
特集 ミラーニューロン
66巻5号(2014年5月発行)
特集 アセチルコリンと神経疾患―100年目の現在地
66巻4号(2014年4月発行)
増大特集 タッチ・ビジョン・アクション
66巻3号(2014年3月発行)
特集 神経筋疾患の超音波診断
66巻2号(2014年2月発行)
特集 糖尿病の神経学revisited
66巻1号(2014年1月発行)
特集 日常生活の脳科学
65巻12号(2013年12月発行)
特集 プロテイノパチーの神経病理学
65巻11号(2013年11月発行)
増大特集 Close Encounters―臨床神経学と臨床免疫学の遭遇と未来
65巻10号(2013年10月発行)
特集 神経系の発達メカニズム―最近の話題
65巻9号(2013年9月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である―現状と展望
65巻8号(2013年8月発行)
特集 こころの時間学―現在・過去・未来の起源を求めて
65巻7号(2013年7月発行)
増大特集 あしたの脳梗塞
65巻6号(2013年6月発行)
特集 見せる・仕分ける―脳機能解析の新手法
65巻5号(2013年5月発行)
特集 てんかん―新しいパースペクティブ
65巻4号(2013年4月発行)
増大特集 Antibody Update
65巻3号(2013年3月発行)
特集 次世代シーケンサーによる神経変性疾患の解析と展望
65巻2号(2013年2月発行)
特集 血液脳関門研究の進歩
65巻1号(2013年1月発行)
特集 Corticobasal Syndrome
64巻12号(2012年12月発行)
特集 The Border-Land of Dementia
64巻11号(2012年11月発行)
増大特集 痛みの神経学―末梢神経から脳まで
64巻10号(2012年10月発行)
特集 辺縁系をめぐって
64巻9号(2012年9月発行)
特集 高次脳機能イメージングの脳科学への新展開
64巻8号(2012年8月発行)
特集 線条体の基礎と臨床
64巻7号(2012年7月発行)
増大特集 顔認知の脳内機構
64巻6号(2012年6月発行)
特集 睡眠と覚醒の脳内機構
64巻5号(2012年5月発行)
特集 神経疾患のバイオマーカー
64巻4号(2012年4月発行)
増大特集 パーキンソン病の新しい側面
64巻3号(2012年3月発行)
特集 アカデミアから新規治療の実現へ―トランスレーショナルリサーチの現状
64巻2号(2012年2月発行)
特集 生物学的精神医学の進歩
64巻1号(2012年1月発行)
特集 iPS細胞と神経疾患
63巻12号(2011年12月発行)
特集 神経心理学と画像解析の融合
63巻11号(2011年11月発行)
増大特集 筋疾患update
63巻10号(2011年10月発行)
特集 緩徐進行性高次脳機能障害の病態
63巻9号(2011年9月発行)
特集 脳卒中の最新画像診断
63巻8号(2011年8月発行)
特集 日本人の発見した神経症候
63巻7号(2011年7月発行)
増大特集 神経筋接合部―基礎から臨床まで
63巻6号(2011年6月発行)
特集 ニューロパチー
63巻5号(2011年5月発行)
特集 神経系と血管内リンパ腫
63巻4号(2011年4月発行)
増大特集 てんかんの新しい治療
63巻3号(2011年3月発行)
特集 サイバーナイフ治療
63巻2号(2011年2月発行)
特集 続・日本人の発見した神経疾患
63巻1号(2011年1月発行)
特集 血管腫
62巻12号(2010年12月発行)
特集 頸部頸動脈狭窄症の診断と治療
62巻11号(2010年11月発行)
増大特集 歩行とその異常
62巻10号(2010年10月発行)
特集 ブレインバンク
62巻9号(2010年9月発行)
特集 視神経脊髄炎(NMO)update
62巻8号(2010年8月発行)
特集 辺縁系脳炎
62巻7号(2010年7月発行)
増大特集 アルツハイマー病―研究と診療の進歩
62巻6号(2010年6月発行)
特集 改正臓器移植法の問題点とその対応
62巻5号(2010年5月発行)
特集 神経画像のピットフォール―見落としと読み過ぎ
62巻4号(2010年4月発行)
特集 傍腫瘍性神経筋疾患update
62巻3号(2010年3月発行)
特集 神経回路解析法の最近の進歩
62巻2号(2010年2月発行)
特集 ニューロリハビリテーションの最前線
62巻1号(2010年1月発行)
特集 神経救急
61巻12号(2009年12月発行)
特集 Somatotopy再考
61巻11号(2009年11月発行)
特集 前頭側頭葉変性症
61巻10号(2009年10月発行)
特集 片頭痛の予防療法
61巻9号(2009年9月発行)
特集 脳血管障害治療の進歩
61巻8号(2009年8月発行)
特集 神経・筋疾患の分子標的治療
61巻7号(2009年7月発行)
特集 脳腫瘍研究の最前線―遺伝子解析から治療まで
61巻6号(2009年6月発行)
特集 脊椎・脊髄外科の最近の進歩
61巻5号(2009年5月発行)
特集 Restless legs syndrome
61巻4号(2009年4月発行)
特集 大脳基底核―分子基盤から臨床まで
61巻3号(2009年3月発行)
特集 Microneurography(微小神経電図法)の臨床応用
61巻2号(2009年2月発行)
特集 神経系の再興感染症と輸入感染症
61巻1号(2009年1月発行)
特集 脳神経倫理
60巻12号(2008年12月発行)
特集 痙縮
60巻11号(2008年11月発行)
特集 脳卒中と遺伝子
60巻10号(2008年10月発行)
特集 若年者の脳卒中
60巻9号(2008年9月発行)
特集 知・情・意の神経学
60巻8号(2008年8月発行)
特集 脳硬膜動静脈瘻
60巻7号(2008年7月発行)
増大特集 学習と記憶――基礎と臨床
60巻6号(2008年6月発行)
特集 Crow-深瀬症候群(POEMS症候群)
60巻5号(2008年5月発行)
特集 「痛み」の研究と治療の最前線
60巻4号(2008年4月発行)
増大特集 神経系の発生とその異常
60巻3号(2008年3月発行)
特集 特発性正常圧水頭症(iNPH)―最近の話題
60巻2号(2008年2月発行)
特集 がん治療と神経障害
60巻1号(2008年1月発行)
特集 日本人の発見した神経疾患
59巻12号(2007年12月発行)
特集 損傷神経の再生―温存的治療法の開発
59巻11号(2007年11月発行)
特集 手根管症候群をめぐって
59巻10号(2007年10月発行)
増大特集 ALS―研究と診療の進歩
59巻9号(2007年9月発行)
特集 パーキンソン病の認知機能障害
59巻8号(2007年8月発行)
特集 パーキンソン病の分子遺伝学―最近の知見
59巻7号(2007年7月発行)
増大特集 情報伝達処理におけるグリアの機能と異常
59巻6号(2007年6月発行)
特集 職業性神経障害の新しい展開
59巻5号(2007年5月発行)
特集 脳画像最前線
59巻4号(2007年4月発行)
増大特集 最近注目される脳神経疾患治療の研究
59巻3号(2007年3月発行)
特集 分子イメージング
59巻2号(2007年2月発行)
特集 進行性多巣性白質脳症の新しい展開―PMLが治る時代へ向けて
59巻1号(2007年1月発行)
特集 高次視覚研究の最近の進歩
