迷走神経は延髄から出る第Ⅹ脳神経であり,「迷走」の名前からもわかるように,多数に枝分れして複雑な経路を示し,胸腔内から腹腔内にまで及ぶ脳神経中最大の分布領域を有している。中枢と末梢,身体とをつなぐ自律神経機能,心身連関の根幹をなし,その失調は失神やてんかんといった意識障害とも関連する。迷走神経刺激は薬剤抵抗性てんかんに対する治療として行われているが,海外ではうつ病に対しても用いられ,また他疾患への応用も研究されている。脳腸相関の観点からは,パーキンソン病の発症・進展との関連や,食品成分を通じた認知機能の改善に関する報告がみられる。このように,迷走神経は人体の機能や疾患と多様な関わりをもつ。その奥深い世界をお楽しみいただきたい。
雑誌目次
BRAIN and NERVE-神経研究の進歩74巻8号
2022年08月発行
雑誌目次
特集 迷走神経の不思議
迷走神経の生理学—基礎研究の歴史から現在への展開
著者: 鈴木郁子
ページ範囲:P.955 - P.958
第Ⅹ脳神経にあたる迷走神経は,胸腔・腹腔などの器官に広く分布する。メインは副交感神経であり,生体の内部環境が安定に保たれるように働く(ホメオスタシス)。本論では副交感神経としての迷走神経に焦点を絞る。迷走神経遠心路は心筋,平滑筋,腺などの働きを調節する。求心路は内臓の情報を中枢に伝える。迷走神経は腸管神経系・腸内細菌叢・中枢神経系との相互連絡や免疫にも重要な役割を果たす。
マウス迷走神経活動の電気生理学的測定方法
著者: 谷田守
ページ範囲:P.959 - P.964
交感神経と副交感神経(迷走神経)から構成される自律神経は,全身の臓器の働きに関わっている。末梢臓器から脳への情報伝達を担う迷走神経求心路の役割と仕組みが近年,クローズアップされており,栄養,循環,炎症などの重要なシグナル経路として提唱されている。本論では,マウスでの迷走神経活動計測法に関するin vivo電気生理学測定法を中心に紹介して,迷走神経の特徴やホメオスタシス維持に寄与する仕組みなどについて解説する。
血管迷走神経性失神
著者: 古川俊行
ページ範囲:P.965 - P.969
脳灌流の低下による意識消失が失神である。自律神経反射が関与する失神は反射性失神(神経調節性失神)と総称され,その中に血管迷走神経性失神が含まれる。多くの患者が発症し臨床現場では頻繫に遭遇する。この血管迷走神経性失神の機序から治療まで周辺の疾患に触れながら説明していく。危険性の低い失神ではあるが,診断方法や治療法は単純でない。侵襲的な治療が必要になることもあり,ガイドラインを参考に経験も踏まえ血管迷走神経性失神の診療について紹介する。
迷走神経と腸脳相関—迷走神経反射による制御性T細胞誘導機構を中心に
著者: 金井隆典 , 寺谷俊昭
ページ範囲:P.971 - P.977
迷走神経は腸と脳を双方向性につなぐ腸脳相関における情報連絡の要と考えられている。特に,迷走神経は,腸管のさまざまな情報を受信し脳へ伝達する。われわれのグループは,最近,腸管の末梢性制御性T細胞(peripheral regulatory T cell:pTreg)による免疫寛容機構が,腸内細菌の直接的な司令だけでなく,腸内細菌情報→腸管→肝臓→脳→腸管による迷走神経反射によって制御されていることを見出した。腸管pTreg細胞は腸管の免疫寛容を担う重要な細胞である。腸管pTreg細胞誘導機構における迷走神経反射の関与の発見は,脳を介した精巧な腸脳相関を調整する神経刺激治療のヒントになるかもしれない。本論では,これ以外にも,最近次々と発見されている迷走神経と腸脳相関の発見もまとめて概説する。
パーキンソン病におけるαシヌクレイン異常凝集体は迷走神経を介して上行する
著者: 大野欽司 , 平山正昭
ページ範囲:P.979 - P.984
パーキンソン病(Parkinson's disease:PD)の中脳黒質神経細胞に蓄積するαシヌクレイン異常凝集体(レビー小体)はプリオンの性質を有する。αシヌクレイン異常蓄積は,PDの腸管神経叢に高率に認められ,剖検脳の検討では延髄から中脳黒質に上行する。事実,迷走神経全切除術はPD発症率を半減する。加えてPDでは短鎖脂肪酸(SCFA)産生菌が低下する。SCFAによる迷走神経刺激がPDにおいて低下することもPD病態の進行を促進する可能性が示唆される。
薬剤抵抗性てんかんに対する迷走神経刺激治療
著者: 杉山一郎 , 福村麻里子 , 小杉健三 , 戸田正博
ページ範囲:P.985 - P.990
薬剤抵抗性てんかんに対する迷走神経刺激治療は,本邦では2010年に薬事承認された比較的新しい緩和的外科治療法である。なぜ迷走神経刺激がてんかんに有効であるのか,その明確な理由についてはいまだ解明されていない。最近では,迷走神経刺激のてんかん以外の疾患に対する有効性についても研究が進められている。本論では,薬剤抵抗性てんかんに対する迷走神経刺激治療の適応・有効性について解説する。
経皮的耳介迷走神経刺激の臨床応用
著者: 山本貴道
ページ範囲:P.991 - P.995
経皮的耳介迷走神経刺激(transcutaneous auricular vagus nerve stimulation:taVNS)はいまだ本邦において医療機器としては未承認であるが,左側の耳甲介に分布する迷走神経耳介枝を皮膚の上から刺激する手法である。植込み型VNSと同様にてんかんをはじめとするさまざまな疾患に対して研究が行われている。主たる副作用は刺激部位のしびれ感である。臨床現場に導入された場合は24時間連続で刺激を行うよりも,1日に一定の時間を決めて毎日実施することが治療の基本となるだろう。
うつ病に対する迷走神経刺激
著者: 吉野敦雄 , 岡本泰昌 , 山脇成人
ページ範囲:P.997 - P.1001
迷走神経刺激(vagus nerve stimulation:VNS)は,欧米では難治性のてんかんだけでなくうつ病に対して行われている治療法である。本邦では難治性てんかんに対して保険適用があるが,うつ病に関しての臨床応用はほとんど進められていない。そこで本論では,これまでのVNSの歴史を振り返り,海外のうつ病に対する先行研究について紹介する。そして最後にうつ病と関連したVNSの治療効果メカニズム仮説について取り上げる。
ホップ由来苦味酸による脳腸相関活性化—食成分を通じた迷走神経刺激
著者: 阿野泰久
ページ範囲:P.1003 - P.1009
超高齢社会や社会環境変化により認知機能や気分状態の維持改善が重要な社会課題となっている。ビールの苦味成分としても知られるホップ由来苦味酸が,腸の苦味受容体に作用し,迷走神経を刺激することで脳腸相関の活性化により認知機能および抑うつ状態を改善することが非臨床試験で確認され,健常中高齢者対象の臨床試験でも有効性が確認されている。食を通じた迷走神経刺激は日常的に続けやすく,新たな予防方法の開発が期待される。
ポリヴェーガル理論—その概要と臨床的可能性
著者: 花澤寿
ページ範囲:P.1011 - P.1016
ポリヴェーガル理論は,系統発生的に異なる2つの迷走神経系の存在を前提とし,腹側迷走神経が他の脳神経群と形成する腹側迷走神経複合体による社会的関与,交感神経系による可動反応,背側迷走神経系による不動反応という3つの階層的適応反応を提唱している。この理論は,トラウマをはじめとするさまざまな病態に新しい理解をもたらすとともに,安全な関わりが前提となる精神療法等対人援助全般の基本理論となる可能性を持つ。
総説
「人工知能(AI)による筋病理判読アルゴリズム」の開発
著者: 大久保真理子 , 壁谷佳典 , 西野一三
ページ範囲:P.1019 - P.1024
筋疾患の診断には生検筋に対する筋病理診断が重要であり,特に筋炎は治療法が確立されていることから,正確な診断が求められている。今回われわれは深層学習を用い,筋病理画像から筋炎であるか否かを判別するモデルの構築を試みた。1,400検体のヘマトキシリン・エオジン染色標本の顕微鏡画像を用い,AIを用いたモデルの訓練と評価を行った。その結果,われわれの筋炎判別モデルは専門医に匹敵する判別精度を有することが明らかとなった。
症例報告
新型コロナワクチン(BNT162b2)接種後にギラン・バレー症候群を生じた71歳女性例
著者: 押部奈美子 , 本田真也 , 古賀道明 , 佐藤亮太 , 大石真莉子 , 神田隆
ページ範囲:P.1025 - P.1030
71歳,女性。新型コロナワクチン接種の1週間後から両大腿内側のビリビリ感と下痢,2週間後に排尿障害と歩行障害が出現し,4週間後に歩行障害はピークとなり,無治療で改善傾向となった。急性単相性の経過や脳脊髄液蛋白細胞解離の顕在化などからギラン・バレー症候群と診断した。先行感染は確認されずワクチンに関連したものと考えた。筋力低下が下肢近位筋や体幹筋優位であり,典型的なギラン・バレー症候群とは異なっていた。
連載 脳神経内科領域における医学教育の展望—Post/withコロナ時代を見据えて・12
オンライン多職種連携教育
著者: 河内泉
ページ範囲:P.1031 - P.1036
はじめに
世界保健機関(World Health Organization:WHO)は,2006年,世界で推定430万人の医療人の不足を指摘し,医療分野の人材育成は喫緊の課題であると表明している1)。この解消のため,多職種連携教育(interprofessional education:IPE)とその実践(interprofessional work:IPW)を推進することは革新的戦略と位置付けた2)。
歴史を振り返れば,英国で1987年にIPE推進センター(The Centre for the Advancement of Interprofessional Education:CAIPE)が設立され,IPE/IPWの推進が開始された2,3)。2010年にWHOがIPE/IPW実施のためのフレームワークを公表し2),2015年に米国Institute of Medicine(IOM)がIPE/IPWに関するエビデンス創出の重要性を指摘した4)。以降,欧米ではIPE/IPWは社会政策立案に関連した重要課題と考えられている5)。
本邦においても1980年代から,堀川らによる神経難病[筋萎縮性側索硬化症(amyotrophic lateral sclerosis:ALS)]を持つ患者と家族に向けたIPWの取り組みが開始され,日本のIPWの礎になっている6)。1990年,全国で初めて,地方公共団体による事業(新潟県特定疾患在宅患者医療機器購入補助事業:特定疾患を持つ患者に向けた貸し出し用人工呼吸管理と周辺機器の購入費用等の補助)が行われたことを皮切りに,新潟市難病対策連絡会とその下部組織の新潟市難病ケース検討会(事務局:新潟市役所保健衛生課)が毎月1回,定期開催されるようになった。神経難病に関わる多施設,多職種の医療人が匿名の問題症例を持ち寄り,患者に関わる医療や社会的な問題に対して対策を討議し,その場でケアプランを立て,包括的・継続的にケアをコーデイネートする6)。そこで生まれた課題は,新潟市難病対策連絡会(1〜2回/年)に挙げられ,難病対策の政策提言が行われた。課題覚知から政策提言まで迅速にボトムアップ可能なシステムであったこと,検討会自体がIPE教育の場になっていたこと(複数の領域の専門職が,連携およびケアの質を改善するために,同じ場所でともに学び,お互いから学び合うこと)が特徴である。この一連の活動は日本を代表するIPE/IPWのベスト・プラクティスであり,「新潟モデル」と称された。ここに培われてきたマインドセットが2000年施行の介護保険法の枠組みへとつながり,IPE/IPWを両輪とした地域包括ケアシステムへと発展している。
日本を含め世界では,高齢化を含めた人口構造の変化,働き方を含めた社会構造の変化,医療技術に支えられた疾患構造の変化,人々の価値観やイデオロギーの変化をどのように医療政策に反映させるかが求められている。ニーズが多様化する中,限られた資源で複雑化した医療サービスを提供することで,すべての人の健康寿命の延伸と豊かな社会の形成を目的に,さまざまな多分野の関係者が,共通の言語を使用し,同じ土俵に立って,地域の文脈を活かしながら,健康と健康政策を議論し,実践するしくみがIPWである7)。今,IPWを担う多職種を育成するIPEの重要性と必要性は高まるばかりである。
このような中,2019年末に中国湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルス感染症(coronavirus disease 2019:COVID-19)がいまだに(2022年5月執筆時点)世界で猛威を振るい続けている8)。パンデミックを機に,世界のいずれの国の医学教育においても,カリキュラム改訂とICT(information and communication technology)を活用したオンライン教育の導入が推進された9)。本論ではIPE/IPWに関する理論を述べたうえで,post/withコロナ時代を見据えたオンラインIPEの可能性について提起したい。
臨床神経学プロムナード—60余年を顧みて・18
Guillain-Barré症候群(GBS)の知られざる歴史的展開—(1)注目されなかった半世紀 (2)誤解と共に広がる (3)「syndrome」とは
著者: 平山惠造
ページ範囲:P.1037 - P.1039
本誌の前身である『神経研究の進歩』誌の「古典のページ」欄に「Guillain-Barré症候群(1916)」1)と題して,原著(1916)2)の全文の和訳を解説と共に収載して(1966)から半世紀余になる。それより数年前,第3回日本臨床神経学会総会(1962)でSymposium「Myeloradiculoneuritis」の中の一部でGBSが討論された。加瀬正夫先生らの意見はGuillainらの原著に則り「一疾患」との見解であったが,他にはGuillain-Barré「症候群」と「病」とを使い分けるべきだ等の発言もあり,当時の日本におけるGBSの認識はまちまちであった。その背景には日本では,Guillainらの原著(1916)の後に,彼らの追加発表(1936)3,4)が伝わらず,理解されない情況が続いたためと思われる。これは当時の時代的背景を物語る一面でもあろう(日本は大正時代でフランスの情勢に詳しい三浦謹之助が既に東京帝國大学教授を退官した後であった)。
LETTERS
レンブラント絵画の中の「脳と神経」
著者: 森望
ページ範囲:P.1040 - P.1041
昨年末の編集委員からのクリスマスプレゼントと銘打たれた『芸術家と神経学』(2021年12月号)は,コロナ禍の重苦しい空気の中で,思いがけずふらっと過去の歴史と欧州への小旅行をさせていただいた,そんな気のするありがたい特集だった。今回取り上げられた芸術家以外にも,ピカソ,ムンク,ダリ,あるいは有名なエリック・カンデルによる『神経科学』の「知覚」の章の扉絵にある相貌失認を患ったチャック・クロスの自画像1)や,自閉症と言われるスティーブン・ウィルシャーが一瞬にして描き上げる大都市の精密な鳥瞰図2)などを思い起こせば,いつかまたこんな特集の続編に出会えることを期待したくもなる。
表紙にあったゴッホの《夜のカフェテラス》の店先のチェアにそっと腰掛けて夜空を見上げれば,一見,綿帽子のようにも見える大きな星が輝いている。歴史上あまたいる科学者や芸術家の中で,この星のように輝く巨星はそう多くはない。そんな中でも,17世紀オランダのレンブラント・ファン・レイン(Rembrandt van Rijn,1606〜1669)がそんな巨星の1つであることを疑う人はないだろう。ここでは,この『芸術家と神経学』の特集にからめて,レンブラント絵画に見られる「BRAIN and NERVE」について言及しておきたい。
書評
「医学英語論文 手トリ足トリ—いまさら聞けない論文の書きかた」—千葉一裕【監修】 堀内圭輔【著】 フリーアクセス
著者: 岡田保典
ページ範囲:P.1017 - P.1017
「医学英語論文」を書くことは,医師であれば誰もがごく普通に考えることではあるが,実際には必ずしも多くの医師が英語論文を書いているわけではない。そもそも医師が英語論文を書く理由は何なのか。本書では,「Ⅰ論文を書く前に」において,このような根本的な疑問に答えることからスタートして,「医学英語論文」を書くことの意義や考え方について述べ,「Ⅱ 英語論文の『作法』」と「Ⅲ 英語論文の基本構造とその対策」において論文の書き方に関する基本的かつ実際的な注意点が丁寧に(まさに手トリ足トリ)解説されている。
本書は,優れた研究実績を有する整形外科専門医である防衛医大整形外科学講座の堀内圭輔准教授が執筆した著書であり,同講座千葉一裕教授の監修のもとに発刊されている。この手の本でよく見られる便利な英文表現や英文法の解説書ではなく,(1)英語論文作成の作法・決まり事の理解,(2)指導医,共同研究者,編集者,査読者,読者などの論文作成にかかわる人々とのコミュニケーションの重要性,(3)英語論文として発表することによる視野の拡大と充実した医師・研究者生活指向の必要性を若手医師・研究者に伝えることを主眼としている。
「緩和ケアレジデントマニュアル 第2版」—森田達也,木澤義之【監修】 西 智弘,松本禎久,森 雅紀,山口 崇【編】 フリーアクセス
著者: 柏木秀行
ページ範囲:P.1018 - P.1018
レジデントマニュアルシリーズと聞けば,「片手で持てて,ポケットに入るけど,ちょっと厚めのマニュアルね」と多くの人がイメージする。そのくらい,各領域に抜群の信頼性を備えた診療マニュアルとして位置付けられ,定番中の定番だろう。そんなレジデントマニュアルに,緩和ケアが仲間入りしたのが2016年であった。初版も緩和ケアにかかわる幅広い論点を網羅していたが,さらに充実したというのが第2版を手にとっての感想である。
緩和ケアもここ数年で大きく変化した。心不全をはじめとした非がん疾患をも対象とし,今後の症状緩和のアプローチが変わっていくような薬剤も出てきた。こういったアップデートをふんだんに盛り込んだのが第2版である。緩和ケアに関するマニュアルも増えてきたが,網羅性という点において間違いなく最強であろう。そう考えると分厚さも,「これだけのことを網羅しておいて,よくこの厚さに抑えたものだ」と感じられる。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.951 - P.951
欧文目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.952 - P.952
バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.1046 - P.1046
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.1047 - P.1047
あとがき フリーアクセス
著者: 髙尾昌樹
ページ範囲:P.1048 - P.1048
今年は,6月下旬から一気に暑くなりました。皆様,お元気でお過ごしでしょうか。暑い夏に,「熱い8月号」を皆様のお手元にお届けいたします。
今月の特集は迷走神経です。普段,私が行っている脳神経内科の診察では,迷走神経を中心に診るということはあまり意識していませんでした。しかし,診察手技は別としても,迷走神経に対する気持ちを大きく変えようと思いました。名前をvagusというくらい,迷走しているだけの神経のようですが,一部にしか分布しない運動神経よりもものすごく奥が深いです。脳だけでなく全身に関わる迷走神経が,人類が生まれてからどれだけ人体を支え,そして多くの役割を果たしているのかがわかる,すばらしい論文ばかりです。ぜひ,お読みいただければ幸いです。
基本情報
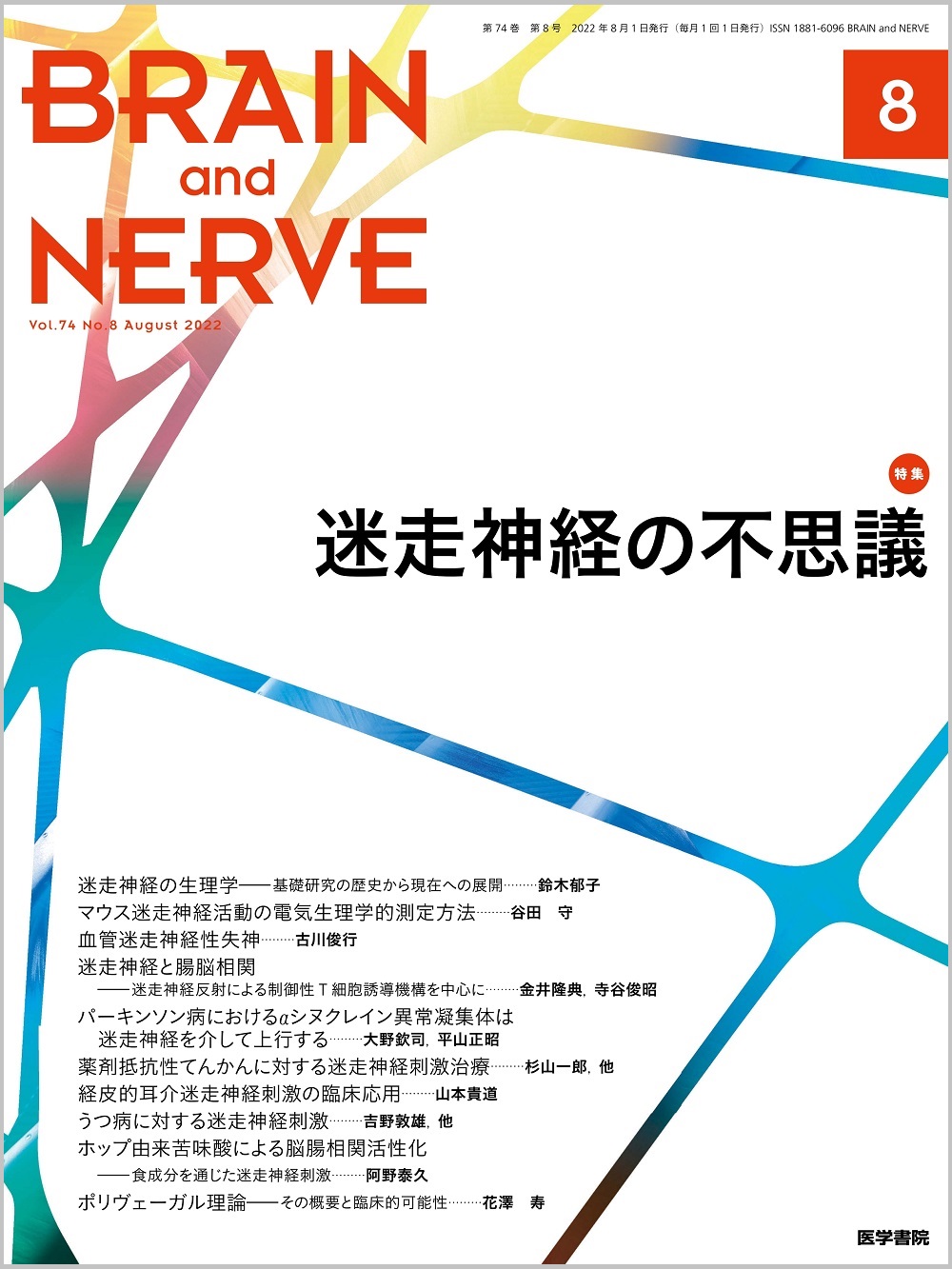
バックナンバー
76巻12号(2024年12月発行)
特集 芸術家と神経学Ⅱ
76巻11号(2024年11月発行)
特集 ALS 2024
76巻10号(2024年10月発行)
特集 どうして効くんだろう
76巻9号(2024年9月発行)
特集 治療可能な認知症としてのアルツハイマー病
76巻8号(2024年8月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である—revisited
76巻7号(2024年7月発行)
特集 ニューロ・バイオイメージング—技術と応用
76巻6号(2024年6月発行)
特集 注意と注意障害
76巻5号(2024年5月発行)
増大特集 末梢神経・筋肉の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
76巻4号(2024年4月発行)
特集 神経病理最前線
76巻3号(2024年3月発行)
特集 きちんと説明ができますか?
76巻2号(2024年2月発行)
特集 特発性正常圧水頭症の現在
76巻1号(2024年1月発行)
特集 新時代の重症筋無力症と関連疾患の診療
75巻12号(2023年12月発行)
特集 アガサ・クリスティーと神経毒
75巻11号(2023年11月発行)
特集 アロスタシス—ホメオスタシスを超えて
75巻10号(2023年10月発行)
特集 メタバースへの招待
75巻9号(2023年9月発行)
特集 妊娠と神経疾患
75巻8号(2023年8月発行)
特集 アルツハイマー病は本当に早期発見できるのか
75巻7号(2023年7月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part2 末梢編
75巻6号(2023年6月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part1 中枢編
75巻5号(2023年5月発行)
増大特集 神経・精神領域の薬剤ハンドブック
75巻4号(2023年4月発行)
特集 All About Epilepsy
75巻3号(2023年3月発行)
特集 慢性疼痛
75巻2号(2023年2月発行)
特集 多系統萎縮症の新診断基準とこれからの診療
75巻1号(2023年1月発行)
特集 よく出会う不随意運動を知る
74巻12号(2022年12月発行)
特集 映画を観て精神・神経疾患を知る
74巻11号(2022年11月発行)
特集 RFC1遺伝子関連スペクトラム障害
74巻10号(2022年10月発行)
特集 ウイルス性脳炎・脳症2022
74巻9号(2022年9月発行)
特集 動的環境への適応系としての歩行
74巻8号(2022年8月発行)
特集 迷走神経の不思議
74巻7号(2022年7月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識2022
74巻6号(2022年6月発行)
特集 脳神経内科医に求められる移行医療
74巻5号(2022年5月発行)
増大特集 次の一手—神経筋疾患難治例をどのように治療するか
74巻4号(2022年4月発行)
特集 脳科学リテラシーを高めるために
74巻3号(2022年3月発行)
特集 中枢性自律神経障害update
74巻2号(2022年2月発行)
特集 温度を感じる脳と身体の科学
74巻1号(2022年1月発行)
特集 脳神経内科医のキャリアパスとリーダーシップ
73巻12号(2021年12月発行)
特集 芸術家と神経学
73巻11号(2021年11月発行)
特集 「目」の神経学
73巻10号(2021年10月発行)
特集 中枢神経・末梢神経の悪性リンパ腫
73巻9号(2021年9月発行)
特集 脳卒中治療に必要な基礎知識
73巻8号(2021年8月発行)
特集 脳腸相関—脳-身体の双方向性制御
73巻7号(2021年7月発行)
特集 グリアと神経—相補的な制御系として
73巻6号(2021年6月発行)
特集 Lower Spine Neurology
73巻5号(2021年5月発行)
増大特集 中枢神経の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
73巻4号(2021年4月発行)
特集 片頭痛・群発頭痛治療の新たな夜明け
73巻3号(2021年3月発行)
特集 マルチリンガルブレイン
73巻2号(2021年2月発行)
特集 筋炎と壊死性筋症
73巻1号(2021年1月発行)
特集 Neuro-Oncology
72巻12号(2020年12月発行)
特集 超高齢期の精神神経疾患を診る
72巻11号(2020年11月発行)
増大特集 脳の発振現象—基礎から臨床へ
72巻10号(2020年10月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識
72巻9号(2020年9月発行)
特集 皮質性小脳萎縮症へのアプローチ
72巻8号(2020年8月発行)
特集 サルコイドーシス
72巻7号(2020年7月発行)
増大特集 神経倫理ハンドブック
72巻6号(2020年6月発行)
特集 前頭側頭葉変性症の今日的理解
72巻5号(2020年5月発行)
特集 多発性硬化症の現在と未来
72巻4号(2020年4月発行)
増大特集 神経疾患の診断における落とし穴—誤診を避けるために
72巻3号(2020年3月発行)
特集 でこぼこの脳の中でおしくらまんじゅうする脳機能
72巻2号(2020年2月発行)
特集 αシヌクレイノパチーの新たな展開
72巻1号(2020年1月発行)
特集 神経難病をクスリで治す—薬物開発の現況と近未来への展望
71巻12号(2019年12月発行)
特集 小脳と大脳—Masao Itoのレガシー
71巻11号(2019年11月発行)
増大特集 ALS2019
71巻10号(2019年10月発行)
特集 認知症と遺伝
71巻9号(2019年9月発行)
特集 神経疾患のドラッグ・リポジショニング—新時代へ
71巻8号(2019年8月発行)
特集 パーキンソン病診療の現在地—200年の変遷と新規治療
71巻7号(2019年7月発行)
増大特集 人工知能と神経科学
71巻6号(2019年6月発行)
特集 補体標的治療の現状と展望
71巻5号(2019年5月発行)
特集 NPSLE
71巻4号(2019年4月発行)
増大特集 神経学のための皮膚アトラス
71巻3号(2019年3月発行)
特集 Spine Neurology
71巻2号(2019年2月発行)
特集 “スポーツ”を生み出す脳
71巻1号(2019年1月発行)
特集 人工知能の医療応用Update
70巻12号(2018年12月発行)
特集 主訴に沿う—俯瞰し収束する画像診断の目
70巻11号(2018年11月発行)
増大特集 脳科学で解き明かす精神神経症候
70巻10号(2018年10月発行)
特集 「左脳と右脳」の現在
70巻9号(2018年9月発行)
特集 脳神経内科診療に役立つ精神科の知識
70巻8号(2018年8月発行)
特集 レヴィ小体型認知症の新知見
70巻7号(2018年7月発行)
増大特集 記憶と忘却に関わる脳のしくみ—分子機構から健忘の症候まで
70巻6号(2018年6月発行)
特集 芸術を生み出す脳
70巻5号(2018年5月発行)
特集 非アルツハイマー型認知症の病理学
70巻4号(2018年4月発行)
増大特集 Antibody Update 2018
70巻3号(2018年3月発行)
特集 『認知症疾患診療ガイドライン2017』を読み解く
70巻2号(2018年2月発行)
特集 知っておきたい神経感染症
70巻1号(2018年1月発行)
特集 筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群の今
69巻12号(2017年12月発行)
特集 運動異常症をみる—Web動画付録つき
69巻11号(2017年11月発行)
増大特集 こころの時間学の未来
69巻10号(2017年10月発行)
特集 成人てんかん—知っておきたい6つのトピック
69巻9号(2017年9月発行)
特集 ミクログリアと精神・神経疾患
69巻8号(2017年8月発行)
特集 遺伝性脊髄小脳失調症の病態と治療展望
69巻7号(2017年7月発行)
増大特集 あしたのアルツハイマー病治療
69巻6号(2017年6月発行)
特集 局在病変の神経心理学
69巻5号(2017年5月発行)
特集 Voxel-Based Morphometry—体積からわかること
69巻4号(2017年4月発行)
増大特集 ブロードマン領野の現在地
69巻3号(2017年3月発行)
特集 磁気刺激の新たな展開
69巻2号(2017年2月発行)
特集 Stroke-Like Diseases—鑑別時に注意を要する5病態
69巻1号(2017年1月発行)
特集 近年注目されている白質脳症
68巻12号(2016年12月発行)
特集 炎症性神経・筋疾患の新たな展開
68巻11号(2016年11月発行)
増大特集 連合野ハンドブック
68巻10号(2016年10月発行)
特集 アディクション—行動の嗜癖
68巻9号(2016年9月発行)
特集 自己免疫性脳炎・脳症
68巻8号(2016年8月発行)
特集 こころと汗
68巻7号(2016年7月発行)
増大特集 認知症の危険因子と防御因子
68巻6号(2016年6月発行)
特集 脳とフローラ
68巻5号(2016年5月発行)
特集 手の症候学—生理学・解剖学からみた新知見
68巻4号(2016年4月発行)
増大特集 治せる認知症
68巻3号(2016年3月発行)
特集 末梢神経の血管炎
68巻2号(2016年2月発行)
特集 筋疾患の認知機能障害
68巻1号(2016年1月発行)
特集 シャルコー・マリー・トゥース病
67巻12号(2015年12月発行)
特集 視床と高次脳機能
67巻11号(2015年11月発行)
増大特集 ギラン・バレー症候群のすべて—100年の軌跡
67巻10号(2015年10月発行)
特集 非・日常生活の脳科学
67巻9号(2015年9月発行)
特集 酵素補充療法
67巻8号(2015年8月発行)
特集 神経難病の終末期医療
67巻7号(2015年7月発行)
増大特集 神経疾患と感染症update
67巻6号(2015年6月発行)
特集 脳と「質感」
67巻5号(2015年5月発行)
特集 NCSE(非痙攣性てんかん重積状態)
67巻4号(2015年4月発行)
増大特集 大脳皮質vs.大脳白質
67巻3号(2015年3月発行)
特集 中枢神経の血管炎
67巻2号(2015年2月発行)
特集 「食べる」を考える
67巻1号(2015年1月発行)
特集 ニューロトキシコロジー
66巻12号(2014年12月発行)
特集 Orthopaedic Neurology—神経内科と整形外科の狭間で
66巻11号(2014年11月発行)
増大特集 神経症候学は神経学の“魂”である
66巻10号(2014年10月発行)
特集 分子を撃つ 神経疾患治療の新しい水平線
66巻9号(2014年9月発行)
特集 痙縮の臨床神経学
66巻8号(2014年8月発行)
特集 神経系の悪性リンパ腫update
66巻7号(2014年7月発行)
増大特集 アミロイド関連神経疾患のすべて―封入体筋炎からアルツハイマー病まで
66巻6号(2014年6月発行)
特集 ミラーニューロン
66巻5号(2014年5月発行)
特集 アセチルコリンと神経疾患―100年目の現在地
66巻4号(2014年4月発行)
増大特集 タッチ・ビジョン・アクション
66巻3号(2014年3月発行)
特集 神経筋疾患の超音波診断
66巻2号(2014年2月発行)
特集 糖尿病の神経学revisited
66巻1号(2014年1月発行)
特集 日常生活の脳科学
65巻12号(2013年12月発行)
特集 プロテイノパチーの神経病理学
65巻11号(2013年11月発行)
増大特集 Close Encounters―臨床神経学と臨床免疫学の遭遇と未来
65巻10号(2013年10月発行)
特集 神経系の発達メカニズム―最近の話題
65巻9号(2013年9月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である―現状と展望
65巻8号(2013年8月発行)
特集 こころの時間学―現在・過去・未来の起源を求めて
65巻7号(2013年7月発行)
増大特集 あしたの脳梗塞
65巻6号(2013年6月発行)
特集 見せる・仕分ける―脳機能解析の新手法
65巻5号(2013年5月発行)
特集 てんかん―新しいパースペクティブ
65巻4号(2013年4月発行)
増大特集 Antibody Update
65巻3号(2013年3月発行)
特集 次世代シーケンサーによる神経変性疾患の解析と展望
65巻2号(2013年2月発行)
特集 血液脳関門研究の進歩
65巻1号(2013年1月発行)
特集 Corticobasal Syndrome
64巻12号(2012年12月発行)
特集 The Border-Land of Dementia
64巻11号(2012年11月発行)
増大特集 痛みの神経学―末梢神経から脳まで
64巻10号(2012年10月発行)
特集 辺縁系をめぐって
64巻9号(2012年9月発行)
特集 高次脳機能イメージングの脳科学への新展開
64巻8号(2012年8月発行)
特集 線条体の基礎と臨床
64巻7号(2012年7月発行)
増大特集 顔認知の脳内機構
64巻6号(2012年6月発行)
特集 睡眠と覚醒の脳内機構
64巻5号(2012年5月発行)
特集 神経疾患のバイオマーカー
64巻4号(2012年4月発行)
増大特集 パーキンソン病の新しい側面
64巻3号(2012年3月発行)
特集 アカデミアから新規治療の実現へ―トランスレーショナルリサーチの現状
64巻2号(2012年2月発行)
特集 生物学的精神医学の進歩
64巻1号(2012年1月発行)
特集 iPS細胞と神経疾患
63巻12号(2011年12月発行)
特集 神経心理学と画像解析の融合
63巻11号(2011年11月発行)
増大特集 筋疾患update
63巻10号(2011年10月発行)
特集 緩徐進行性高次脳機能障害の病態
63巻9号(2011年9月発行)
特集 脳卒中の最新画像診断
63巻8号(2011年8月発行)
特集 日本人の発見した神経症候
63巻7号(2011年7月発行)
増大特集 神経筋接合部―基礎から臨床まで
63巻6号(2011年6月発行)
特集 ニューロパチー
63巻5号(2011年5月発行)
特集 神経系と血管内リンパ腫
63巻4号(2011年4月発行)
増大特集 てんかんの新しい治療
63巻3号(2011年3月発行)
特集 サイバーナイフ治療
63巻2号(2011年2月発行)
特集 続・日本人の発見した神経疾患
63巻1号(2011年1月発行)
特集 血管腫
62巻12号(2010年12月発行)
特集 頸部頸動脈狭窄症の診断と治療
62巻11号(2010年11月発行)
増大特集 歩行とその異常
62巻10号(2010年10月発行)
特集 ブレインバンク
62巻9号(2010年9月発行)
特集 視神経脊髄炎(NMO)update
62巻8号(2010年8月発行)
特集 辺縁系脳炎
62巻7号(2010年7月発行)
増大特集 アルツハイマー病―研究と診療の進歩
62巻6号(2010年6月発行)
特集 改正臓器移植法の問題点とその対応
62巻5号(2010年5月発行)
特集 神経画像のピットフォール―見落としと読み過ぎ
62巻4号(2010年4月発行)
特集 傍腫瘍性神経筋疾患update
62巻3号(2010年3月発行)
特集 神経回路解析法の最近の進歩
62巻2号(2010年2月発行)
特集 ニューロリハビリテーションの最前線
62巻1号(2010年1月発行)
特集 神経救急
61巻12号(2009年12月発行)
特集 Somatotopy再考
61巻11号(2009年11月発行)
特集 前頭側頭葉変性症
61巻10号(2009年10月発行)
特集 片頭痛の予防療法
61巻9号(2009年9月発行)
特集 脳血管障害治療の進歩
61巻8号(2009年8月発行)
特集 神経・筋疾患の分子標的治療
61巻7号(2009年7月発行)
特集 脳腫瘍研究の最前線―遺伝子解析から治療まで
61巻6号(2009年6月発行)
特集 脊椎・脊髄外科の最近の進歩
61巻5号(2009年5月発行)
特集 Restless legs syndrome
61巻4号(2009年4月発行)
特集 大脳基底核―分子基盤から臨床まで
61巻3号(2009年3月発行)
特集 Microneurography(微小神経電図法)の臨床応用
61巻2号(2009年2月発行)
特集 神経系の再興感染症と輸入感染症
61巻1号(2009年1月発行)
特集 脳神経倫理
60巻12号(2008年12月発行)
特集 痙縮
60巻11号(2008年11月発行)
特集 脳卒中と遺伝子
60巻10号(2008年10月発行)
特集 若年者の脳卒中
60巻9号(2008年9月発行)
特集 知・情・意の神経学
60巻8号(2008年8月発行)
特集 脳硬膜動静脈瘻
60巻7号(2008年7月発行)
増大特集 学習と記憶――基礎と臨床
60巻6号(2008年6月発行)
特集 Crow-深瀬症候群(POEMS症候群)
60巻5号(2008年5月発行)
特集 「痛み」の研究と治療の最前線
60巻4号(2008年4月発行)
増大特集 神経系の発生とその異常
60巻3号(2008年3月発行)
特集 特発性正常圧水頭症(iNPH)―最近の話題
60巻2号(2008年2月発行)
特集 がん治療と神経障害
60巻1号(2008年1月発行)
特集 日本人の発見した神経疾患
59巻12号(2007年12月発行)
特集 損傷神経の再生―温存的治療法の開発
59巻11号(2007年11月発行)
特集 手根管症候群をめぐって
59巻10号(2007年10月発行)
増大特集 ALS―研究と診療の進歩
59巻9号(2007年9月発行)
特集 パーキンソン病の認知機能障害
59巻8号(2007年8月発行)
特集 パーキンソン病の分子遺伝学―最近の知見
59巻7号(2007年7月発行)
増大特集 情報伝達処理におけるグリアの機能と異常
59巻6号(2007年6月発行)
特集 職業性神経障害の新しい展開
59巻5号(2007年5月発行)
特集 脳画像最前線
59巻4号(2007年4月発行)
増大特集 最近注目される脳神経疾患治療の研究
59巻3号(2007年3月発行)
特集 分子イメージング
59巻2号(2007年2月発行)
特集 進行性多巣性白質脳症の新しい展開―PMLが治る時代へ向けて
59巻1号(2007年1月発行)
特集 高次視覚研究の最近の進歩
