2021年にFacebookがMeta Platformsに社名を変更し,昨年には東京大学にメタバース工学部が設立された。メタバースは一過性のブームではなく,医療や教育をはじめ,さまざまな場面での応用に大きな期待が寄せられている。しかし,その実態について十分理解されているとは言いがたい。本特集では,メタバースの活用に向けたガバナンス上の課題を整理するとともに,メタバースを用いた教育やアバターを利用した精神科クリニック,カンファレンスや手術支援における活用などの実践例を取り上げた。このようにメタバースの有する可能性は計り知れないが,仮想の世界に居続けることによる心身への影響も懸念されている。メタバースは何をもたらすのか,そしてどのように向き合うべきかを考える契機としたい。
雑誌目次
BRAIN and NERVE-神経研究の進歩75巻10号
2023年10月発行
雑誌目次
特集 メタバースへの招待
【対談】メタバースが変える神経科学の未来
著者: 岡嶋裕史 , 三村將
ページ範囲:P.1093 - P.1097
三村:2021年にFacebookが社名を“Meta Platforms”に変更したことは,社運をかけてメタバースに取り組むという同社の強い意志の表れと思います。昨年にはメタバース推進協議会という一般社団法人が設立され,養老孟司氏や隈研吾氏など,一見メタバースとは縁遠いと思われる方々が役員に名を連ねていることも興味深いです。この技術は神経科学あるいは医療において今後さらに応用が進むことでしょう。本日は昨年話題となった書籍『メタバースとは何か—ネット上の「もう一つの世界」』1)の著者としても知られる岡嶋裕史先生にお話を伺いたいと思います。
メタバース×医療の可能性とそのガバナンス
著者: 藤田卓仙
ページ範囲:P.1099 - P.1106
メタバースが注目を集める中,医療でのメタバースの活用も進みつつある。サービス利用者が誰であるか,メタバース上でのサービスや行為が法律上どのような位置付けになるかを明確化したうえで,各ユーザーの権利保護ができるようにしなければならない。さらに,公共性や公平性といった観点も重要である。これらの観点を含めて,国内外の適切な機関において具体的なユースケースをベースにしたガイドラインなどの策定が求められる。
メタバースによる新しい教育
著者: 雨宮智浩
ページ範囲:P.1107 - P.1113
メタバースは,バーチャルリアリティ(virtual reality:VR)技術を基礎とし,オンラインで社会的活動が実現できる場として注目され,さまざまな応用の中でも教育訓練への活用が期待されている。メタバースを活用する教育応用は,物理世界の代替ではなく,「VRでしか実現できないこと」や「メタバースで初めて実現できること」で真価を発揮する。メタバースによる新しい教育訓練の取組みを通じて,メタバースの可能性とあるべき姿について解説する。
メディカル・メタバースを活用したニューヘルスケアへの挑戦
著者: 牧野裕一 , 小林智久 , 今野大成 , 佐々木栄二 , 太田進 , 先崎心智
ページ範囲:P.1115 - P.1120
IBMは,メタバース技術を用いて深刻化する医療課題の解決に取り組んでいる。具体的には,メタバースの特徴である新しいコミュニケーションや体験,業務効率化・高質化など価値を活かしながら,リアル・デジタル連携を強化することで,患者の満足度向上や医療現場の働き方改革を目指している。本論では,IBMが順天堂大学と取り組む「メディカル・メタバース共同研究講座」により実現を目指すサービスの具体例や将来展望を紹介する。
アバターコミュニケーションの精神科医療応用—生物・心理・社会モデルから見た考察
著者: 吉岡鉱平
ページ範囲:P.1121 - P.1127
本論では,アバターコミュニケーションの精神科医療への応用について,生物・心理・社会モデルの観点から筆者らの取組みやその他の事例を交えながら考察する。アバターコミュニケーションの応用は,オンラインでの利便性のみならず,人間を現実の制約から解放し,身体拡張技術を応用した認知への介入,そして,生物学的要素への介入すらももたらし得る,可能性を秘めた領域である。
脳神経外科領域のメタバースとExtended Realityの臨床活用—空間画像解析・遠隔手術支援・追体験型修練
著者: 末吉巧弥 , 杉本真樹
ページ範囲:P.1129 - P.1134
メタバース・XR(extended reality)は医療分野で急速に普及し,手術支援としても活用されている。高速情報通信と先進的なXRデバイスを活用し,医用画像や手術の手順などの情報が,メタバースを利用し,立体空間的に表示され,医師間で共有されている。さらに,熟練医師の技術を若手医師が時間を超えて追体験する試みも実施され,医師を含めた医療全体の質と業務効率の改善が期待されている。
超高齢社会におけるVirtual Realityの活用
著者: 登嶋健太
ページ範囲:P.1135 - P.1140
一般に65歳以上の人口の割合が総人口の21%以上になると超高齢社会と呼ばれる。日本はその比率が2022年に29%を突破し,これまでの政府の手厚い補助を永続的に行うことは困難である。加齢により自分,身体,社会との関係が変遷する中でコミュニティとの接点を持ち続けることは心身の健康維持の観点からも重要視されている。高齢者の健康と社会的活力を助ける道具としてバーチャルリアリティはその1つになるかもしれない。
総説
設計可能な抗アミロイド化合物を用いた,がん,2型糖尿病,神経変性疾患に対する疾患横断的な戦略
著者: 高松芳樹 , 橋本款
ページ範囲:P.1143 - P.1148
アミロイド蛋白は神経変性疾患だけでなく,がんや2型糖尿病など,さまざまな疾患に関与する。クライオ電子顕微鏡単粒子解析法(クライオEM)の進歩により,アミロイド蛋白に共通する構造に対してその線維化を阻止する化合物を設計する,いくつかの戦略コンセプトを見出すことができる。これらは異なる種類のアミロイド蛋白に適用可能であり,疾患の垣根を超えた応用が期待される。このように広く適用可能な戦略コンセプトとして,ペプチド模倣型フォルダマー,立体ジッパー阻害ペプチド,ディフェニルピラゾール誘導体およびアミロイド線維を分解する化合物を用いた手法について紹介する。
縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチーを対象としたアセノイラミン酸の有効性
著者: 青木正志 , 井泉瑠美子 , 鈴木直輝
ページ範囲:P.1149 - P.1154
縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチーは,10代後半から発症し緩徐に進行する有効な治療法のない難病である。原因遺伝子GNEがシアル酸代謝に関わり,非臨床試験でシアル酸の有効性が示され,東北大学病院はアセノイラミン酸による医師主導第Ⅰ相試験を実施した。その後,海外第Ⅲ相試験と同様のプロトコールにてアセノイラミン酸徐放錠の有効性と安全性を検証する第Ⅱ/Ⅲ相試験を国内5施設で行い,さらにその確認試験も実施した。
症例報告
筋萎縮性側索硬化症に意味性認知症を合併した症例—言語症状と書字障害の検討
著者: 髙木早希 , 大門正太郎 , 井上桂輔 , 梅田実穂 , 小林禅
ページ範囲:P.1155 - P.1161
症例は発症時66歳,男性。高炭酸ガス血症による意識障害で救急搬送され,人工呼吸器管理となり,その後の精査にて筋萎縮性側索硬化症(amyotrophic lateral sclerosis:ALS)と診断した。頭部MRIにて右優位に両側側頭葉前方および内側面が萎縮していた。書字でのコミュニケーションでは仮名,漢字のいずれにおいても錯書が見られた。言語機能の精査を行い,単語の理解障害,呼称障害,類音的錯書を認め,意味型原発性進行性失語(semantic variant primary progressive aphasia:svPPA)と診断した。ALS患者においては,側頭葉前方の萎縮と漢字の類音的錯書が見られた場合にsvPPAを合併している可能性がある。
ペムブロリズマブの最終投与から17週後に脳炎を発症し,自然軽快した1例
著者: 島智秋 , 古田可奈子 , 山下魁理 , 立石洋平 , 辻野彰
ページ範囲:P.1163 - P.1167
症例は73歳の男性である。多発転移を伴う肺腺癌に対しペムブロリズマブを含む化学療法を施行したが,薬剤性肺障害を発症したため治療を中断した。ペムブロリズマブを最終投与した17週後に意識障害と右片麻痺を呈する脳炎を発症したが,症状は徐々に自然軽快し,発症3週間後には消失した。免疫チェックポイント阻害薬の投与後に遅発性に脳炎を発症する例は稀である。また,重篤な脳炎症状が後遺症を残すことなく自然消失した例を本例では初めて詳細に報告した。
連載 医師国家試験から語る精神・神経疾患・10
ビタミン・微量元素欠乏
著者: 山脇健盛
ページ範囲:P.1169 - P.1173
35歳の男性。ふらつきを主訴に来院した。1年前に仕事上のトラブルをきっかけに退職した。その後は自宅に閉じこもりがちになり,食事は不規則で菓子パンやおにぎりを好んで摂取していた。1週間前から歩行時のふらつきが目立つようになり四肢のしびれ感も訴えるようになったため,心配した家族に付き添われて受診した。意識は清明。脈拍72/分,整。血圧124/68mmHg。腱反射は,上肢では減弱し,膝蓋腱反射とアキレス腱反射は消失している。Babinski徴候は陰性である。四肢筋力は遠位部優位に低下している。両下肢で痛覚過敏,振動覚の低下を認める。
この患者に補充すべきなのはどれか。
a 亜鉛
b 葉酸
c ニコチン酸
d ビタミンB1
e ビタミンB12
(第112回E29)
スペシャリストが薦める読んでおくべき名著—ニューロサイエンスを志す人のために・5
脳神経外科医としての礎を築いてくれた書籍
著者: 川俣貴一
ページ範囲:P.1174 - P.1175
私は高校生のときに「脳」や「こころ」に興味を抱き医学部進学を決めた。進学後もその興味の対象が変わることはなかったが,ポリクリなどを経て脳神経に関連する診療科の中から最終的に脳神経外科を選択した。医学部卒業とともに当時の東京女子医科大学脳神経センター脳神経外科学講座へ入局し,先輩方から最初に勧められた書籍の中の1冊が本書である。言わずと知れた神経学入門書の定番である。私が本書を手にしたのは入局間もない1986年で,改訂12版第4刷である。第1版は1966年10月20日発行となっており,現在の最新版である改訂18版が2016年に出版されるまで実に50年という長い年月にわたり読み継がれてきたことになる。
改めて手元にある本書をめくってみると至る所に勉強の跡が残り,本書以外のコピーもいくつも挟まっており,自分なりにまとめた記述もいくつも見られる。学生時代のポリクリで神経所見の取りかたをある程度は学んだが,当然のことながら身についておらず,また現在の初期研修期間などはない直接専門領域への入職であり,いきなり専門的な臨床の現場に出た状態であった。私の学生時代の不勉強も相まって,患者さんと急に対面しても神経所見など取れるはずがなかった。先輩方に教わりながら本書と首っ引きで患者さんに対応していたことを思い出す。新患が入院してくると神経所見を取るための器具が並べられた金属のトレイとまっさらな紙カルテを持ってベッドサイドに行き,すべての神経所見項目を埋めていくのが研修医の仕事であった。打腱器は私物を持ち歩きいつでも神経所見が取れる状態とし,トレイには眼底鏡もあったので散瞳薬を使わずにある程度の範囲の眼底を観察した。本書には「眼底検査の要領」という項目もあり,初学者にとってはまさにかゆいところに手が届く逸品であった。
LETTERS
王子 聡 「『ほんとうのジャクリーヌ・デュ・プレ』—天才チェリストと多発性硬化症」(Brain Nerve 74: 1395-1398, 2022) への疑義
著者: 目崎高広
ページ範囲:P.1176 - P.1177
2022年12月号に掲載された王子聡先生の論文1)を興味深く拝読致しました。
王子先生は映画『ほんとうのジャクリーヌ・デュ・プレ』をすべて事実とされているようです。Hilary and Jackieを原題とするこの映画は,チェリストJacqueline du Pré(以下,Jackie)の姉弟による回想記2)(原題:A Genius in the Family,のちにHilary and Jackieに改題。邦訳『風のジャクリーヌ—ある真実の物語』)と並行して制作され,1998年に公開されました。しかし夫であったDaniel Barenboim(以下,Daniel)は制作協力を拒否したと伝えられ,Danielの住むフランスでは提訴の恐れから劇場公開されず,またJackieの友人・知人から激しく批判されました。事実の隠蔽や歪曲がいくつもあるとされます。企画の主旨が何であれ,このような問題作であることに一切触れず,内容をすべて事実として記載するなら,実在の人物(故人)であるJackieの記録の粉飾・歪曲となりかねません。また実際,伝記との照合により,情報の誤りをいくつも確認できます。
書評
「神経病理インデックス 第2版」—新井信隆【著】 フリーアクセス
著者: 小野寺理
ページ範囲:P.1141 - P.1141
ある図形から2つの物を見ることができるのに,同時には2つの物に見えない図形を,多義図形といいます。最も有名な多義図形に『妻と義母』があります。向こうを向いている若い妻にも,年老いた義母の横顔にも見える図です。皆さんも見たことがあるかと思います。不思議なことに,一度老婦人に見えると,妻が見えなくなります。また,一度多義図形であることに気付くと,気付かなかった時期の自分には戻れません。われわれの視覚は,意識に左右されます。見えるようにならないと,永遠に見えません。また一度見えると,次からは,必ず,そう見えるようになります。この現象は,われわれの認知や知覚における,固定観念や予測の働きに関連しているといわれています。
われわれは,ありのままを認知しているのではなく,過去の経験や学習から得た情報を基に,解釈し,意味を与え,認知します。『妻と義母』で起こっていることは,このような認知のプロセスによって生じるものと考えられています。この現象が面白いのは,一度認識した解釈が強くなると,逆の解釈をすることが大変難しくなることです。一度見えてしまうと,もう見えなかった自分には戻れなくなります。
「神経眼科 第4版—臨床のために」—江本博文,清澤源弘,藤野 貞【著】 フリーアクセス
著者: 若倉雅登
ページ範囲:P.1142 - P.1142
臨床神経眼科は神経科学と眼科学が統合された独立分野で,その萌芽は20世紀初頭の米国にあった。1947年Frank B Walsh(1895〜1978)の『Clinical Neuro-ophthalmology』が上梓されるに及び,神経眼科学は広く認知された。やがてこの国は,W.F.Hoyt(1926〜2019),J.Lawton Smith(1929〜2011)らその道の泰斗を輩出し,神経眼科学は黄金時代を迎えた。
この時代にマイアミ大に留学した日本人医師がいた。藤野貞(1922〜2005),本書の初版版の著者である。長崎大助教授を辞して,この新領域を学びに渡米したのである。そこでは臨床だけでなく,視交叉血管の研究にも打ち込んだ。そして,この新領域の臨床医学をひっさげて67年に帰国すると,東京,東京医科歯科,慶應義塾,北里,大分医科などの大学や都立病院で神経眼科臨床を実践し,85年には今も続く夏の勉強会を立ち上げた。日本の弱点とされる臨床実践教育のため,彼はいずれの常勤職にもならずに全国を奔走した。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.1089 - P.1089
欧文目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.1090 - P.1090
バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.1182 - P.1182
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.1183 - P.1183
あとがき フリーアクセス
著者: 神田隆
ページ範囲:P.1184 - P.1184
東京医科歯科大学と東京工業大学が統合するというニュースは,皆様もうご存じのことと思います。私も同窓会から新大学の名称案を出せとの手紙を受け取り,研究面で尖った大学を目指すだろうから「先端」「卓越」などという単語を冠した大学名をいろいろ考えましたが,誰でも思いつく名称はほとんど既に使いまわされているのですね。結局出せずじまいで決定を待っていたら,「東京科学大学」。これがまだ残っていたか,ど真ん中のストレートを呆然と見送った気分でした。都内のいくつかの国立大学が1つになるという構想はずいぶん前からあって,この2大学プラス一橋大学,東京外国語大学,東京藝術大学の5大学連合というのがスタートでした。基本的には第二東大をつくろうという発想だったと思いますが,藝大が入っているので,私自身は実にチャーミングな総合大学が出来上がるのではないかと内心期待していたことを記憶しています。残念ながらまず藝大が脱退して4大学連合になり,時を経て理系2大学の統合ということになったわけですが,この流れは,工学と結びつくことによる明日の医学を象徴しているように思います。
本号ではメタバースを特集しました。自分の意思では自由にコントロールできない肉体との葛藤が神経難病の患者さんの日常ですが,仮想空間に自分のアバターを置いて,そのアバター君が現実と寸分変わらない社会生活を営めるのであれば,肉体の制限をはるかに飛び越えることができます。BMI(brain machine interface)という言葉,どこかでお聞きになったことがあるでしょうか。脳と機械を通信させる技術,平たく言うと脳で考えたことを機械を通じて外部にアウトプットするテクノロジーです。もちろん,現時点ではまだ発展途上の技術ですが,近未来にさらに進化したこのBMIとメタバースが結合すれば,例えばALSでtotal locked-inの状態にある患者さんであっても,自分の考えたこと,しようと思った動作が煩雑なデバイスを介することもなく即アバター君に反映されるわけですね。医療者としてはこの患者さんの脳を含めた肉体の健康管理に集中すればよいということになります。
基本情報
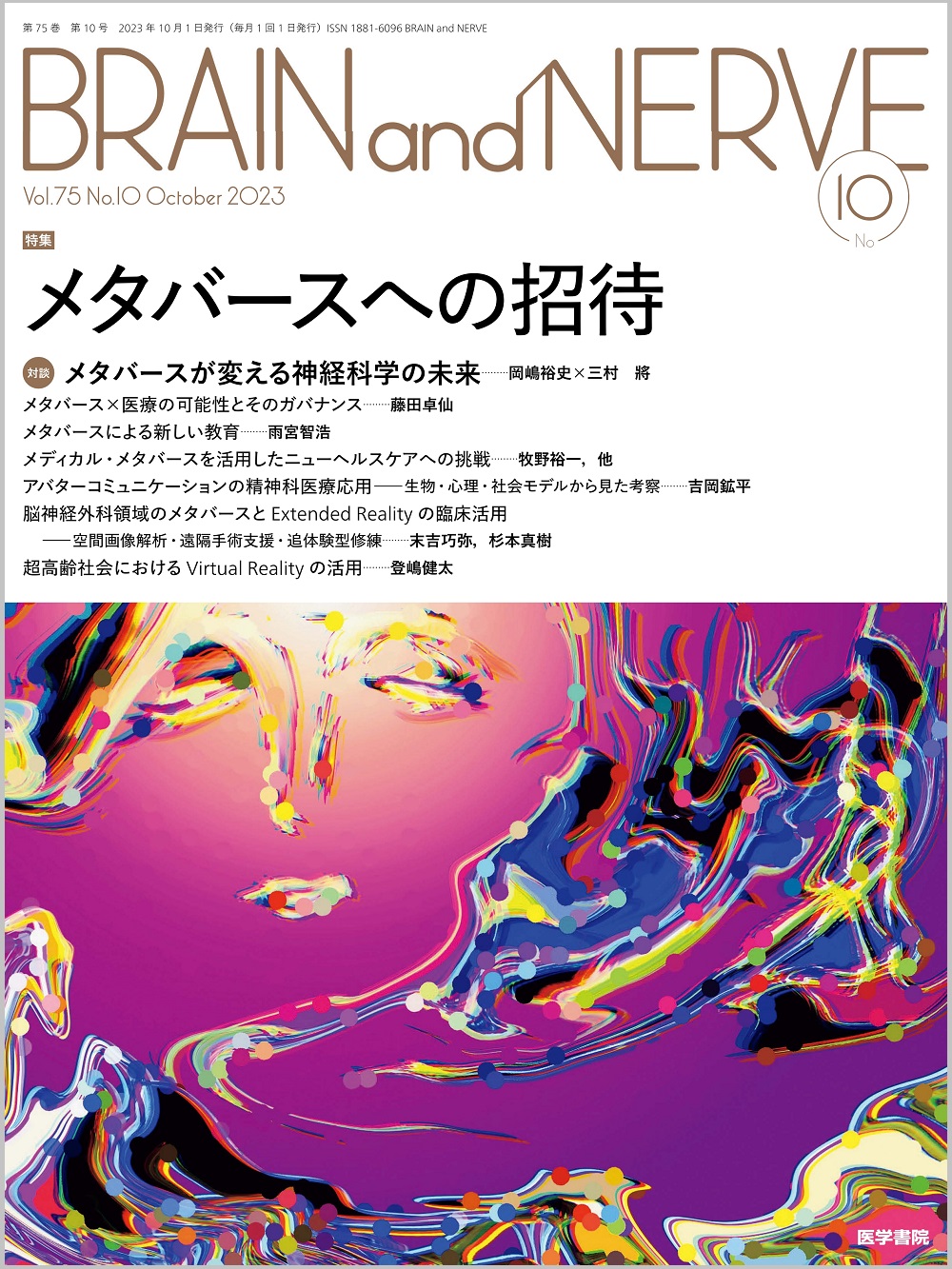
バックナンバー
76巻12号(2024年12月発行)
特集 芸術家と神経学Ⅱ
76巻11号(2024年11月発行)
特集 ALS 2024
76巻10号(2024年10月発行)
特集 どうして効くんだろう
76巻9号(2024年9月発行)
特集 治療可能な認知症としてのアルツハイマー病
76巻8号(2024年8月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である—revisited
76巻7号(2024年7月発行)
特集 ニューロ・バイオイメージング—技術と応用
76巻6号(2024年6月発行)
特集 注意と注意障害
76巻5号(2024年5月発行)
増大特集 末梢神経・筋肉の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
76巻4号(2024年4月発行)
特集 神経病理最前線
76巻3号(2024年3月発行)
特集 きちんと説明ができますか?
76巻2号(2024年2月発行)
特集 特発性正常圧水頭症の現在
76巻1号(2024年1月発行)
特集 新時代の重症筋無力症と関連疾患の診療
75巻12号(2023年12月発行)
特集 アガサ・クリスティーと神経毒
75巻11号(2023年11月発行)
特集 アロスタシス—ホメオスタシスを超えて
75巻10号(2023年10月発行)
特集 メタバースへの招待
75巻9号(2023年9月発行)
特集 妊娠と神経疾患
75巻8号(2023年8月発行)
特集 アルツハイマー病は本当に早期発見できるのか
75巻7号(2023年7月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part2 末梢編
75巻6号(2023年6月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part1 中枢編
75巻5号(2023年5月発行)
増大特集 神経・精神領域の薬剤ハンドブック
75巻4号(2023年4月発行)
特集 All About Epilepsy
75巻3号(2023年3月発行)
特集 慢性疼痛
75巻2号(2023年2月発行)
特集 多系統萎縮症の新診断基準とこれからの診療
75巻1号(2023年1月発行)
特集 よく出会う不随意運動を知る
74巻12号(2022年12月発行)
特集 映画を観て精神・神経疾患を知る
74巻11号(2022年11月発行)
特集 RFC1遺伝子関連スペクトラム障害
74巻10号(2022年10月発行)
特集 ウイルス性脳炎・脳症2022
74巻9号(2022年9月発行)
特集 動的環境への適応系としての歩行
74巻8号(2022年8月発行)
特集 迷走神経の不思議
74巻7号(2022年7月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識2022
74巻6号(2022年6月発行)
特集 脳神経内科医に求められる移行医療
74巻5号(2022年5月発行)
増大特集 次の一手—神経筋疾患難治例をどのように治療するか
74巻4号(2022年4月発行)
特集 脳科学リテラシーを高めるために
74巻3号(2022年3月発行)
特集 中枢性自律神経障害update
74巻2号(2022年2月発行)
特集 温度を感じる脳と身体の科学
74巻1号(2022年1月発行)
特集 脳神経内科医のキャリアパスとリーダーシップ
73巻12号(2021年12月発行)
特集 芸術家と神経学
73巻11号(2021年11月発行)
特集 「目」の神経学
73巻10号(2021年10月発行)
特集 中枢神経・末梢神経の悪性リンパ腫
73巻9号(2021年9月発行)
特集 脳卒中治療に必要な基礎知識
73巻8号(2021年8月発行)
特集 脳腸相関—脳-身体の双方向性制御
73巻7号(2021年7月発行)
特集 グリアと神経—相補的な制御系として
73巻6号(2021年6月発行)
特集 Lower Spine Neurology
73巻5号(2021年5月発行)
増大特集 中枢神経の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
73巻4号(2021年4月発行)
特集 片頭痛・群発頭痛治療の新たな夜明け
73巻3号(2021年3月発行)
特集 マルチリンガルブレイン
73巻2号(2021年2月発行)
特集 筋炎と壊死性筋症
73巻1号(2021年1月発行)
特集 Neuro-Oncology
72巻12号(2020年12月発行)
特集 超高齢期の精神神経疾患を診る
72巻11号(2020年11月発行)
増大特集 脳の発振現象—基礎から臨床へ
72巻10号(2020年10月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識
72巻9号(2020年9月発行)
特集 皮質性小脳萎縮症へのアプローチ
72巻8号(2020年8月発行)
特集 サルコイドーシス
72巻7号(2020年7月発行)
増大特集 神経倫理ハンドブック
72巻6号(2020年6月発行)
特集 前頭側頭葉変性症の今日的理解
72巻5号(2020年5月発行)
特集 多発性硬化症の現在と未来
72巻4号(2020年4月発行)
増大特集 神経疾患の診断における落とし穴—誤診を避けるために
72巻3号(2020年3月発行)
特集 でこぼこの脳の中でおしくらまんじゅうする脳機能
72巻2号(2020年2月発行)
特集 αシヌクレイノパチーの新たな展開
72巻1号(2020年1月発行)
特集 神経難病をクスリで治す—薬物開発の現況と近未来への展望
71巻12号(2019年12月発行)
特集 小脳と大脳—Masao Itoのレガシー
71巻11号(2019年11月発行)
増大特集 ALS2019
71巻10号(2019年10月発行)
特集 認知症と遺伝
71巻9号(2019年9月発行)
特集 神経疾患のドラッグ・リポジショニング—新時代へ
71巻8号(2019年8月発行)
特集 パーキンソン病診療の現在地—200年の変遷と新規治療
71巻7号(2019年7月発行)
増大特集 人工知能と神経科学
71巻6号(2019年6月発行)
特集 補体標的治療の現状と展望
71巻5号(2019年5月発行)
特集 NPSLE
71巻4号(2019年4月発行)
増大特集 神経学のための皮膚アトラス
71巻3号(2019年3月発行)
特集 Spine Neurology
71巻2号(2019年2月発行)
特集 “スポーツ”を生み出す脳
71巻1号(2019年1月発行)
特集 人工知能の医療応用Update
70巻12号(2018年12月発行)
特集 主訴に沿う—俯瞰し収束する画像診断の目
70巻11号(2018年11月発行)
増大特集 脳科学で解き明かす精神神経症候
70巻10号(2018年10月発行)
特集 「左脳と右脳」の現在
70巻9号(2018年9月発行)
特集 脳神経内科診療に役立つ精神科の知識
70巻8号(2018年8月発行)
特集 レヴィ小体型認知症の新知見
70巻7号(2018年7月発行)
増大特集 記憶と忘却に関わる脳のしくみ—分子機構から健忘の症候まで
70巻6号(2018年6月発行)
特集 芸術を生み出す脳
70巻5号(2018年5月発行)
特集 非アルツハイマー型認知症の病理学
70巻4号(2018年4月発行)
増大特集 Antibody Update 2018
70巻3号(2018年3月発行)
特集 『認知症疾患診療ガイドライン2017』を読み解く
70巻2号(2018年2月発行)
特集 知っておきたい神経感染症
70巻1号(2018年1月発行)
特集 筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群の今
69巻12号(2017年12月発行)
特集 運動異常症をみる—Web動画付録つき
69巻11号(2017年11月発行)
増大特集 こころの時間学の未来
69巻10号(2017年10月発行)
特集 成人てんかん—知っておきたい6つのトピック
69巻9号(2017年9月発行)
特集 ミクログリアと精神・神経疾患
69巻8号(2017年8月発行)
特集 遺伝性脊髄小脳失調症の病態と治療展望
69巻7号(2017年7月発行)
増大特集 あしたのアルツハイマー病治療
69巻6号(2017年6月発行)
特集 局在病変の神経心理学
69巻5号(2017年5月発行)
特集 Voxel-Based Morphometry—体積からわかること
69巻4号(2017年4月発行)
増大特集 ブロードマン領野の現在地
69巻3号(2017年3月発行)
特集 磁気刺激の新たな展開
69巻2号(2017年2月発行)
特集 Stroke-Like Diseases—鑑別時に注意を要する5病態
69巻1号(2017年1月発行)
特集 近年注目されている白質脳症
68巻12号(2016年12月発行)
特集 炎症性神経・筋疾患の新たな展開
68巻11号(2016年11月発行)
増大特集 連合野ハンドブック
68巻10号(2016年10月発行)
特集 アディクション—行動の嗜癖
68巻9号(2016年9月発行)
特集 自己免疫性脳炎・脳症
68巻8号(2016年8月発行)
特集 こころと汗
68巻7号(2016年7月発行)
増大特集 認知症の危険因子と防御因子
68巻6号(2016年6月発行)
特集 脳とフローラ
68巻5号(2016年5月発行)
特集 手の症候学—生理学・解剖学からみた新知見
68巻4号(2016年4月発行)
増大特集 治せる認知症
68巻3号(2016年3月発行)
特集 末梢神経の血管炎
68巻2号(2016年2月発行)
特集 筋疾患の認知機能障害
68巻1号(2016年1月発行)
特集 シャルコー・マリー・トゥース病
67巻12号(2015年12月発行)
特集 視床と高次脳機能
67巻11号(2015年11月発行)
増大特集 ギラン・バレー症候群のすべて—100年の軌跡
67巻10号(2015年10月発行)
特集 非・日常生活の脳科学
67巻9号(2015年9月発行)
特集 酵素補充療法
67巻8号(2015年8月発行)
特集 神経難病の終末期医療
67巻7号(2015年7月発行)
増大特集 神経疾患と感染症update
67巻6号(2015年6月発行)
特集 脳と「質感」
67巻5号(2015年5月発行)
特集 NCSE(非痙攣性てんかん重積状態)
67巻4号(2015年4月発行)
増大特集 大脳皮質vs.大脳白質
67巻3号(2015年3月発行)
特集 中枢神経の血管炎
67巻2号(2015年2月発行)
特集 「食べる」を考える
67巻1号(2015年1月発行)
特集 ニューロトキシコロジー
66巻12号(2014年12月発行)
特集 Orthopaedic Neurology—神経内科と整形外科の狭間で
66巻11号(2014年11月発行)
増大特集 神経症候学は神経学の“魂”である
66巻10号(2014年10月発行)
特集 分子を撃つ 神経疾患治療の新しい水平線
66巻9号(2014年9月発行)
特集 痙縮の臨床神経学
66巻8号(2014年8月発行)
特集 神経系の悪性リンパ腫update
66巻7号(2014年7月発行)
増大特集 アミロイド関連神経疾患のすべて―封入体筋炎からアルツハイマー病まで
66巻6号(2014年6月発行)
特集 ミラーニューロン
66巻5号(2014年5月発行)
特集 アセチルコリンと神経疾患―100年目の現在地
66巻4号(2014年4月発行)
増大特集 タッチ・ビジョン・アクション
66巻3号(2014年3月発行)
特集 神経筋疾患の超音波診断
66巻2号(2014年2月発行)
特集 糖尿病の神経学revisited
66巻1号(2014年1月発行)
特集 日常生活の脳科学
65巻12号(2013年12月発行)
特集 プロテイノパチーの神経病理学
65巻11号(2013年11月発行)
増大特集 Close Encounters―臨床神経学と臨床免疫学の遭遇と未来
65巻10号(2013年10月発行)
特集 神経系の発達メカニズム―最近の話題
65巻9号(2013年9月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である―現状と展望
65巻8号(2013年8月発行)
特集 こころの時間学―現在・過去・未来の起源を求めて
65巻7号(2013年7月発行)
増大特集 あしたの脳梗塞
65巻6号(2013年6月発行)
特集 見せる・仕分ける―脳機能解析の新手法
65巻5号(2013年5月発行)
特集 てんかん―新しいパースペクティブ
65巻4号(2013年4月発行)
増大特集 Antibody Update
65巻3号(2013年3月発行)
特集 次世代シーケンサーによる神経変性疾患の解析と展望
65巻2号(2013年2月発行)
特集 血液脳関門研究の進歩
65巻1号(2013年1月発行)
特集 Corticobasal Syndrome
64巻12号(2012年12月発行)
特集 The Border-Land of Dementia
64巻11号(2012年11月発行)
増大特集 痛みの神経学―末梢神経から脳まで
64巻10号(2012年10月発行)
特集 辺縁系をめぐって
64巻9号(2012年9月発行)
特集 高次脳機能イメージングの脳科学への新展開
64巻8号(2012年8月発行)
特集 線条体の基礎と臨床
64巻7号(2012年7月発行)
増大特集 顔認知の脳内機構
64巻6号(2012年6月発行)
特集 睡眠と覚醒の脳内機構
64巻5号(2012年5月発行)
特集 神経疾患のバイオマーカー
64巻4号(2012年4月発行)
増大特集 パーキンソン病の新しい側面
64巻3号(2012年3月発行)
特集 アカデミアから新規治療の実現へ―トランスレーショナルリサーチの現状
64巻2号(2012年2月発行)
特集 生物学的精神医学の進歩
64巻1号(2012年1月発行)
特集 iPS細胞と神経疾患
63巻12号(2011年12月発行)
特集 神経心理学と画像解析の融合
63巻11号(2011年11月発行)
増大特集 筋疾患update
63巻10号(2011年10月発行)
特集 緩徐進行性高次脳機能障害の病態
63巻9号(2011年9月発行)
特集 脳卒中の最新画像診断
63巻8号(2011年8月発行)
特集 日本人の発見した神経症候
63巻7号(2011年7月発行)
増大特集 神経筋接合部―基礎から臨床まで
63巻6号(2011年6月発行)
特集 ニューロパチー
63巻5号(2011年5月発行)
特集 神経系と血管内リンパ腫
63巻4号(2011年4月発行)
増大特集 てんかんの新しい治療
63巻3号(2011年3月発行)
特集 サイバーナイフ治療
63巻2号(2011年2月発行)
特集 続・日本人の発見した神経疾患
63巻1号(2011年1月発行)
特集 血管腫
62巻12号(2010年12月発行)
特集 頸部頸動脈狭窄症の診断と治療
62巻11号(2010年11月発行)
増大特集 歩行とその異常
62巻10号(2010年10月発行)
特集 ブレインバンク
62巻9号(2010年9月発行)
特集 視神経脊髄炎(NMO)update
62巻8号(2010年8月発行)
特集 辺縁系脳炎
62巻7号(2010年7月発行)
増大特集 アルツハイマー病―研究と診療の進歩
62巻6号(2010年6月発行)
特集 改正臓器移植法の問題点とその対応
62巻5号(2010年5月発行)
特集 神経画像のピットフォール―見落としと読み過ぎ
62巻4号(2010年4月発行)
特集 傍腫瘍性神経筋疾患update
62巻3号(2010年3月発行)
特集 神経回路解析法の最近の進歩
62巻2号(2010年2月発行)
特集 ニューロリハビリテーションの最前線
62巻1号(2010年1月発行)
特集 神経救急
61巻12号(2009年12月発行)
特集 Somatotopy再考
61巻11号(2009年11月発行)
特集 前頭側頭葉変性症
61巻10号(2009年10月発行)
特集 片頭痛の予防療法
61巻9号(2009年9月発行)
特集 脳血管障害治療の進歩
61巻8号(2009年8月発行)
特集 神経・筋疾患の分子標的治療
61巻7号(2009年7月発行)
特集 脳腫瘍研究の最前線―遺伝子解析から治療まで
61巻6号(2009年6月発行)
特集 脊椎・脊髄外科の最近の進歩
61巻5号(2009年5月発行)
特集 Restless legs syndrome
61巻4号(2009年4月発行)
特集 大脳基底核―分子基盤から臨床まで
61巻3号(2009年3月発行)
特集 Microneurography(微小神経電図法)の臨床応用
61巻2号(2009年2月発行)
特集 神経系の再興感染症と輸入感染症
61巻1号(2009年1月発行)
特集 脳神経倫理
60巻12号(2008年12月発行)
特集 痙縮
60巻11号(2008年11月発行)
特集 脳卒中と遺伝子
60巻10号(2008年10月発行)
特集 若年者の脳卒中
60巻9号(2008年9月発行)
特集 知・情・意の神経学
60巻8号(2008年8月発行)
特集 脳硬膜動静脈瘻
60巻7号(2008年7月発行)
増大特集 学習と記憶――基礎と臨床
60巻6号(2008年6月発行)
特集 Crow-深瀬症候群(POEMS症候群)
60巻5号(2008年5月発行)
特集 「痛み」の研究と治療の最前線
60巻4号(2008年4月発行)
増大特集 神経系の発生とその異常
60巻3号(2008年3月発行)
特集 特発性正常圧水頭症(iNPH)―最近の話題
60巻2号(2008年2月発行)
特集 がん治療と神経障害
60巻1号(2008年1月発行)
特集 日本人の発見した神経疾患
59巻12号(2007年12月発行)
特集 損傷神経の再生―温存的治療法の開発
59巻11号(2007年11月発行)
特集 手根管症候群をめぐって
59巻10号(2007年10月発行)
増大特集 ALS―研究と診療の進歩
59巻9号(2007年9月発行)
特集 パーキンソン病の認知機能障害
59巻8号(2007年8月発行)
特集 パーキンソン病の分子遺伝学―最近の知見
59巻7号(2007年7月発行)
増大特集 情報伝達処理におけるグリアの機能と異常
59巻6号(2007年6月発行)
特集 職業性神経障害の新しい展開
59巻5号(2007年5月発行)
特集 脳画像最前線
59巻4号(2007年4月発行)
増大特集 最近注目される脳神経疾患治療の研究
59巻3号(2007年3月発行)
特集 分子イメージング
59巻2号(2007年2月発行)
特集 進行性多巣性白質脳症の新しい展開―PMLが治る時代へ向けて
59巻1号(2007年1月発行)
特集 高次視覚研究の最近の進歩
