2021年(芸術家),2022年(映画)に続く,クリスマス企画の第3弾。「ミステリーの女王」として名高いアガサ・クリスティー(1890-1976)は,第一次世界大戦中にボランティアの看護師として働いただけでなく,調剤師の資格を得て薬剤師の助手を務めた経験があり,その作品の多くで毒物の作用が正確に描かれている。それは実際の毒殺事件において,病理学者が作品の記述を参考にしたほどであった。本特集では,作中で扱われた神経系症状を伴う毒物に焦点を当て,その作用機序や治療法などを,薬理作用や病理に関する現代の知見も織り交ぜながら解説している(項目は原著の発表順)。今宵は不朽のミステリー作品の世界に触れながら,人間心理や神経毒への洞察を深めたい。
雑誌目次
BRAIN and NERVE-神経研究の進歩75巻12号
2023年12月発行
雑誌目次
特集 アガサ・クリスティーと神経毒
ストリキニーネ『スタイルズ荘の怪事件』—グリシン作動性シナプス伝達の遮断
著者: 渡辺雅彦
ページ範囲:P.1285 - P.1288
ストリキニーネは古典的ミステリーでしばしば登場する毒物であるとともに,医療やさまざまな用途で用いられてきた。その作用点はグリシン受容体と明快であり,抑制性シナプス伝達を担うグリシン伝達の阻害である。その強力な興奮作用により,経口摂取後,強直性痙攣,後弓反張,痙笑などの激しく苦悶に満ちた特徴的な症状が現れる。この症状は破傷風の病態基盤とも関係し,この薬剤は神経科学から医学医療にまで及ぶ重要なトピックである。
コカイン『戦勝記念舞踏会事件』
著者: 詫間章俊
ページ範囲:P.1289 - P.1292
『戦勝記念舞踏会事件』はコカイン使用を背景とした殺人事件を描いたもので,作中にも実際にコカイン中毒の症状などが描かれている。一方でコカインは昔,麻酔薬として目や鼻などの手術に使用され,19世紀後半には米国でコカ・コーラの成分として使用されていた。日本においても薬物汚染が問題視される中,作品の内容とともにコカイン中毒の現状や危険性,医療機関と行政の連携の必要性についても触れていきたい。
ゲルセミウム『ビッグ4』
著者: 船山信次
ページ範囲:P.1293 - P.1296
アガサ・クリスティーの『ビッグ4』には,「黄色いジャスミン」の名で,猛毒アルカロイドのゲルセミンを含む有毒植物Gelsemium sempervirensが現れるが,この植物は,わが国ではカロライナジャスミンの名前で知られる。一方,その近縁の植物として,中国南部〜東南アジアに自生する猛毒植物Gelsemium elegansもあり,その根の乾燥品は「冶葛」という生薬名で,古来,奈良の正倉院に収蔵されている。
ベロナール『エッジウェア卿の死』—鎮静と依存の両刃の剣
著者: 虫明元
ページ範囲:P.1297 - P.1300
ベロナールは20世紀初頭に登場し,当時は睡眠薬として広く使われていた。アガサ・クリスティーの小説の中でも用いられている。ベロナールや同様の作用機序を持つ他の睡眠薬には,鎮静作用のほかに,中毒や過剰摂取につながる暗い側面があることが判明している。バルビツール酸の過剰摂取による死者にはマリリン・モンローも含まれている。日本では,芥川龍之介が自殺した際に服用したことで知られている。夏目漱石はこの睡眠薬に手を出したものの,結果はまったく違った。漱石は多くの弟子に囲まれており,その弟子の一人が副作用に気づき,服用をやめるように勧めた。これは,依存症がその人を取り巻く社会的関係によっていかに左右されるかを端的に示す例である。
ニコチンと殺虫剤・たばこ『三幕の殺人』
著者: 山脇健盛
ページ範囲:P.1301 - P.1304
主人公の一人が俳優であったことより,3件の殺人事件が幕に例えられている。一見関連のないように見えた3件の事件が,最後につながってくる,アガサ・クリスティーならではの醍醐味である。本書での殺人事件では3件ともニコチンが使われている。ニコチンといえばたばこが連想されるが,当時は殺虫剤の主流がニコチンであり,容易に入手可能であった。ニコチンは体内に入ると,アセチルコリン受容体に結合して,さまざまな症状を呈する。
砒素中毒『殺人は容易だ』
著者: 神田隆
ページ範囲:P.1305 - P.1308
アガサ・クリスティーの探偵小説『殺人は容易だ』は,イギリスの片田舎で起こった連続殺人事件の犯人が実は想像もできない人物であった,想像されない限り殺人は容易なのだ,というメッセージを込めた表題を有している。砒素はこの小説でも殺人の道具として用いられており,この小論は,亜ヒ酸中毒の神経学的症候について読者の知識を深めることを目的とした。今後も亜ヒ酸を用いた犯罪行為は私たちの前に現れる可能性がある。確実な診断にはここで著した基礎的知識を持つことが大前提であるが,それと同時に,常識にとらわれない柔軟な思考も要求されることをこの小説は示している。
シアン化合物『そして誰もいなくなった』,『忘られぬ死』
著者: 唐木英明
ページ範囲:P.1309 - P.1313
『そして誰もいなくなった』と『忘られぬ死』では各2人がシアン化合物で殺される。この毒は無味,無臭だが強アルカリ性で,経口摂取では消化管に強い刺激がある。胃液の塩酸と反応してシアン化水素ガスになり,吸収されてミトコンドリアの電子伝達系を阻害し,アデノシン三リン酸(adenosine triphosphate:ATP)産生を止める。そのためATP消費量が多い中枢神経系が最初に障害を受け,めまい,意識障害,昏睡,痙攣などが起こる。経口致死量は300mg程度である。
モルヒネとアポモルヒネ『杉の柩』
著者: 尾久守侑
ページ範囲:P.1315 - P.1318
アガサ・クリスティー『杉の柩』には,モルヒネとアポモルヒネを使った印象的なトリックがある。本論では,実際に自分が犯人であったらという連想をしながら本書を読み,モルヒネとアポモルヒネの作用についても考察した。
コニイン『五匹の子豚』
著者: 酒井邦嘉
ページ範囲:P.1319 - P.1323
本論では,アガサ・クリスティーによる小説『五匹の子豚』を読み解き,その作中で重要な役割を果たす神経毒「コニイン」について概観する。コニインはニコチン性アセチルコリン受容体の拮抗薬であり,末梢神経系に直接作用して遅効性の麻痺を引き起こす。この毒薬の歴史は古く,ソクラテスの刑死に使われたことが哲学書『パイドン』に描かれている。そうした背景を踏まえて,クリスティーの人間観や創造力についても議論する。
ベラドンナ(アトロピン)『ヘラクレスの冒険』
著者: 古谷博和
ページ範囲:P.1325 - P.1329
『ヘラクレスの冒険』の第7話「クレタ島の雄牛」ではアトロピンが重要な役割を果たしている。アトロピンは中枢神経系の副作用としてせん妄錯乱状態,幻視,幻覚,見当識障害,記憶障害などを容易に誘発する。この挿話では,依頼者の婚約者に自分が難治性の遺伝性神経変性疾患に罹患していると思い込ませるため,目薬から濃縮されたアトロピンによって起こされた副作用が悪用され,ポアロはその症状を見抜いて事件を解決した。
タキシン『ポケットにライ麦を』—カルシウムチャネル・ナトリウムチャネル阻害剤
著者: 古泉秀夫
ページ範囲:P.1331 - P.1333
『ポケットにライ麦を』はアガサ・クリスティーの創造したミス・マープルが活躍する長編である。殺人に使用されるタキシンはイチイの木の果肉(仮種子)以外に含まれるアルカロイド化合物で,ジテルペンが基になり,多くの骨格構造の1つに,側鎖として窒素元素が組み込まれている。タキシンはナトリウムチャネルに結合するため,筋肉の収縮が調節できず,不整脈を生じる。
トリカブト『パディントン発4時50分』—ナトリウムチャネルの持続的な活性化
著者: 小原佐衣子
ページ範囲:P.1335 - P.1338
『パディントン発4時50分』の物語で使用された毒はトリカブトであった。トリカブトは,キンポウゲ科の多年草で,世界中に約300種類が存在する。根,茎,葉,花などすべての部分にアコニチン系アルカロイドを含む。アコニチン系アルカロイドは,心筋,中枢神経,骨格筋の電位依存性ナトリウムチャネルに作用し,持続的に活性化させる。心筋細胞では自動能がトリガーされ早期興奮が誘発され,さまざまな心室性不整脈を引き起こす。
タリウム『蒼ざめた馬』—いかに診断し治療するか
著者: 下畑享良
ページ範囲:P.1339 - P.1342
『蒼ざめた馬』はアガサ・クリスティーによる推理小説で,タリウムが毒物として殺人に使用されている。タリウムは無味,無臭,かつ水溶性であるために,これまで数多くの事故や事件の原因となった。近年,タリウムの入手は困難であるが,それでもタリウムを使用した事件が発生している。しかしタリウム中毒の診断は容易ではない。本論では,いかにタリウム中毒を見抜くか,またいかに救命するか,の2点を示すことを目的としたい。
エゼリン(エセリン)『ねじれた家』,『カーテン』
著者: 髙尾昌樹
ページ範囲:P.1343 - P.1346
エゼリンはエセリンと称されることもあり,フィゾスチグミンのことでアルカロイドに分類される。コリンエステラーゼ阻害薬であり,アガサ・クリスティーの小説『ねじれた家』や『カーテン』で扱われた。臨床医学では緑内障の点眼治療薬として使用され,重症筋無力症,アルツハイマー病,遺伝性小脳失調症の治療薬としても検討された。現在は,抗コリン薬による中毒の治療薬としての役割を有している。
総説
筋萎縮性側索硬化症(ALS)のリハビリテーション医療とALSクリニック
著者: 海老原覚 , 勝又泰紀 , 朴依真
ページ範囲:P.1349 - P.1353
筋萎縮性側索硬化症(amyotrophic lateral sclerosis:ALS)の機能障害は非常に多岐にわたる。運動障害に対するリハビリテーション医療は重症度によって違い,運動療法は比較的軽症のうちに行われるべきものであり,重症度が上がるにつれて代償訓練が増えていく。HAL®(Hybrid Assistive Limb®)による運動療法は,総じてHAL®を行わない場合に比べて下肢機能は保たれるものと考えられる。その機序は廃用筋線維に対する効果であろう。ALSクリニックによる診療はALS患者の予後を改善する効果がある。
精神展開剤の過去・現在・これから
著者: 内田裕之
ページ範囲:P.1355 - P.1359
近年,精神展開剤をうつ病など複数の精神科疾患の治療に応用する動きが活発になっている。精神展開剤は1960年代に治療効果が検証されていたが,市井での乱用により1970年に麻薬に指定され,いったん臨床研究は中断した。しかし,1994年の臨床試験を皮切りに,多数の臨床試験が実施され,大きな盛り上がりを見せている。本総説では,強力な治療効果を有する精神展開剤の歴史を概観し,本分野の今後の展望を概観する。
Original Article
The Relationship between the Autistic Traits and Everyday Memory Processing in Adults with Autism Spectrum Disorder and Healthy Adults
著者: , , , ,
ページ範囲:P.1361 - P.1366
We investigated the association between everyday memory and autistic traits in adults with autism spectrum disorder (ASD, n=22) and healthy adults (n=20) by using the Rivermead Behavioral Memory Test (RBMT). A generalized linear model (GLM) was used to explore the relationships between the subjects' performance on the RBMT as the objective variable and the composite score of the Autism Spectrum Quotient (AQ) as the explanatory variable. Multiple models were created with the AQ subscales (‘Social skills,’ ‘Attention-shifting,’ ‘Attention to details,’ ‘Communication,’ ‘Imagination’), age, gender, the full-scale intelligence quotient (FSIQ), the Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9), and the General Anxiety Disorder-7 (GAD-7) scale added as the moderator variables. The GLM revealed that the AQ subscale ‘Social skills’ significantly predicted the RBMT-total scores with age, gender, and psychological measures scores as the moderator variables (Model 4: B=0.752, 95%CI: 0.191 to 1.313, p<0.01). Also, The GLM revealed that the AQ subscale ‘Communication’, in addition to ‘Social skills’, significantly predicted the RBMT- ‘Prospective memory’ (Model 4: B=0.298, 95%CI: 0.19 to 0.578, p<0.05). These results indicate an influence of social skills on everyday memory functioning, highlighting the weakness of memory processing in everyday life situations among individuals with ASD.
連載 医師国家試験から語る精神・神経疾患・12
筋萎縮性側索硬化症(ALS)
著者: 荻野美恵子
ページ範囲:P.1367 - P.1370
64歳の男性。ろれつの回りにくさと体重減少を主訴に来院した。半年前から話しにくさを自覚しており,同僚からも声が小さくて聞き取りにくいと指摘されるようになった。2か月前から食事に時間がかかるようになり,2か月間で体重が5kg減少している。1か月前からは両手指の脱力で箸が使いづらく,階段昇降も困難になってきたため受診した。意識は清明。眼球運動に制限はなく顔面の感覚には異常を認めないが,咬筋および口輪筋の筋力低下を認め,舌に萎縮と線維束性収縮を認める。四肢は遠位部優位に軽度の筋萎縮および中等度の筋力低下を認め,前胸部,左上腕および両側大腿部に線維束性収縮を認める。腱反射は全般に亢進しており,偽性の足間代を両側性に認める。Babinski徴候は両側陽性。四肢および体幹には感覚障害を認めない。血液生化学所見:総蛋白5.8g/dL,アルブミン3.5g/dL,尿素窒素11mg/dL,クレアチニン0.4mg/dL,血糖85mg/dL,HbA1c 4.5%(基準4.6〜6.2),CK 182U/L(基準30〜140)。動脈血ガス分析(room air):pH 7.38,PaCO2 45Torr,PaO2 78Torr,HCO3− 23mEq/L。呼吸機能検査:%VC 62%。末梢神経伝導検査に異常を認めない。針筋電図では僧帽筋,第1背側骨間筋および大腿四頭筋に安静時での線維自発電位と陽性鋭波,筋収縮時には高振幅電位を認める。頸椎エックス線写真および頭部単純MRIに異常を認めない。嚥下造影検査で造影剤の梨状窩への貯留と軽度の気道内流入とを認める。
この時点でまず検討すべきなのはどれか。
a 胃瘻造設
b 気管切開
c モルヒネ内服
d エダラボン静注
e リルゾール内服
(第113回A47)
書評
「病態生理と神経解剖からアプローチする—レジデントのための神経診療」—塩尻俊明【監修】,杉田陽一郎【執筆】 フリーアクセス
著者: 江原淳
ページ範囲:P.1347 - P.1347
神経診療は難しく,苦手意識のある医師は多い。
なぜ難しく苦手と感じるのか。一つに,神経領域の幅広さがあると思う。解剖学的にも,脳,脊髄,末梢神経,神経筋接合部,筋などと多彩であり,病態的にも血管障害,感染症,自己免疫,変性など幅が広く,その組み合わせで膨大な疾患が存在する。誰しもその疾患数や領域の広さに圧倒され,特に神経内科を専門領域とするもの以外にとってこれをすべて勉強しきることは無理だ,専門科に任せようという気持ちになるのもわからなくはない。
「多発性硬化症・視神経脊髄炎スペクトラム障害診療ガイドライン2023」—日本神経学会【監修】「多発性硬化症・視神経脊髄炎スペクトラム障害診療ガイドライン」作成委員会【編】 フリーアクセス
著者: 楠進
ページ範囲:P.1348 - P.1348
多発性硬化症(multiple sclerosis:MS)は中枢神経障害を引き起こす代表的な自己免疫疾患であるが,その疾患概念は21世紀に入って大きく変化した。従来はMSの1つのサブタイプと考えられていた視神経脊髄炎(neuromyelitis optica:NMO)が,NMO-IgGすなわちアクアポリン4(aquaporin 4:AQP4)抗体が見出されたことにより病態の異なる疾患と考えられるようになり,さらにAQP4抗体陽性症例の臨床像が多様であることから視神経脊髄炎スペクトラム障害(neuromyelitis optica spectrum disorders:NMOSD)という疾患概念が生まれた。また,中枢神経のミエリンを構成するミエリンオリゴデンドロサイト糖蛋白(myelin oligodendrocyte glycoprotein:MOG)に対する自己抗体の関連する疾患として,MOG抗体関連疾患(MOG antibody-associated disease:MOGAD)も類縁する疾患として確立されてきた。これらの中枢神経の炎症性疾患に対する治療も,従来のステロイド,血漿交換,免疫グロブリン製剤や免疫抑制薬に加えて各種の分子標的薬が導入されるようになっている。本書はこうしたMS,NMOSD,MOGADの最新情報を中心とし,それに加えて急性散在性脳脊髄炎(acute disseminated encephalomyelitis:ADEM)やバロー同心円硬化症(Baló concentric sclerosis:BCS)も対象として,日本神経学会が主体となって作成された診療ガイドラインであり,『多発性硬化症・視神経脊髄炎診療ガイドライン2017』の改訂版である。前の版の出版からこれまでの間に多くの進歩がみられたが,特に新規治療薬の導入は数多く,知識の整理が必要であり,今回の改訂はまさに時宜を得たものといえよう。
本書は3つの章から成り立っている。第Ⅰ章は,中枢神経系炎症性脱髄疾患診療における基本情報であり,それぞれの疾患の概要から診断,治療について詳細に記載されている。この第Ⅰ章を通読するだけで,稀少疾患であるMS,NMOSD,MOGAD,ADEM,BCSについて,要領よく理解することができるであろう。また免疫性神経疾患の治療薬について,まとまった知識を得るにも最適の教材と考えられる。第Ⅰ章の最後には,医療経済学的側面および社会資源の活用として,診療において重要な検査や治療の保険適用,法律や制度,療養や就労の支援などについて述べられていて,日常診療に役立つ内容となっている。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.1281 - P.1281
欧文目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.1282 - P.1282
投稿論文査読者 フリーアクセス
ページ範囲:P.1373 - P.1373
バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.1376 - P.1376
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.1377 - P.1377
あとがき フリーアクセス
著者: 下畑享良
ページ範囲:P.1378 - P.1378
2021年から始まった恒例のクリスマス特集号の第3弾として,「アガサ・クリスティーと神経毒」をお届けします。本企画が参考にした 『アガサ・クリスティーと14の毒薬』 (岩波書店)は,タイトルの通り,クリスティーが作品に使用した14の毒薬を取り上げ,それぞれの特徴やエピソードを紹介したものです。薬理学の講義で,ここで紹介されているような話も併せて聞かせてあげたら,学生もワクワクしながら勉強できるように思います。
さてクリスティーの作品群で特徴的なことは,何と言っても毒殺が多いことで,長編66作品のうち30人以上の犠牲者が毒殺されています。ではいつ彼女が薬理学に対して理解と知識を深めたのかというと,私の原稿 「タリウム『蒼ざめた馬』」にも書いた通り,2つの大戦中に看護師と薬剤師として働いていたときだと考えられています。
「BRAIN and NERVE」第75巻 総目次 フリーアクセス
ページ範囲:P. - P.
基本情報
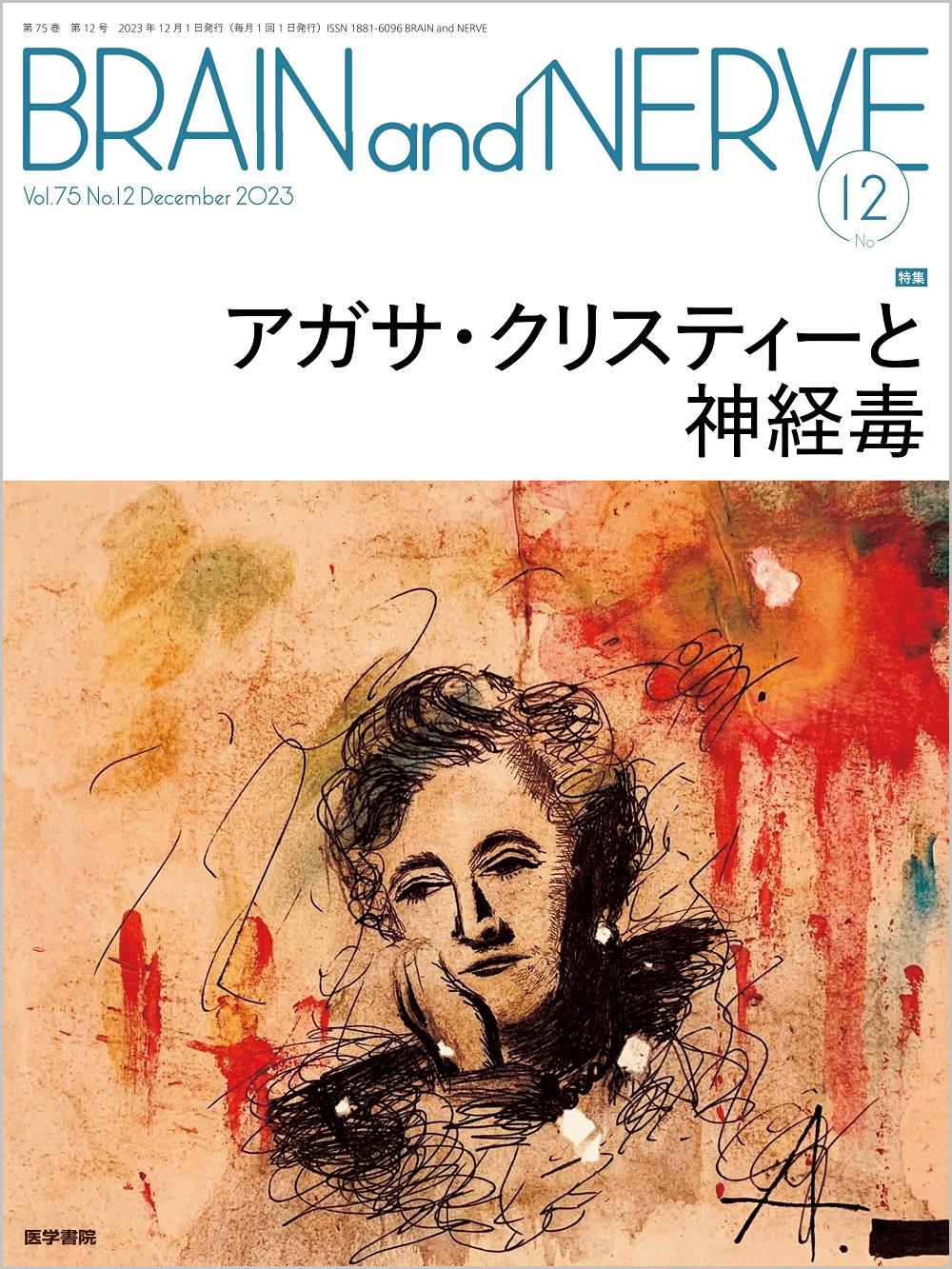
バックナンバー
76巻12号(2024年12月発行)
特集 芸術家と神経学Ⅱ
76巻11号(2024年11月発行)
特集 ALS 2024
76巻10号(2024年10月発行)
特集 どうして効くんだろう
76巻9号(2024年9月発行)
特集 治療可能な認知症としてのアルツハイマー病
76巻8号(2024年8月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である—revisited
76巻7号(2024年7月発行)
特集 ニューロ・バイオイメージング—技術と応用
76巻6号(2024年6月発行)
特集 注意と注意障害
76巻5号(2024年5月発行)
増大特集 末梢神経・筋肉の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
76巻4号(2024年4月発行)
特集 神経病理最前線
76巻3号(2024年3月発行)
特集 きちんと説明ができますか?
76巻2号(2024年2月発行)
特集 特発性正常圧水頭症の現在
76巻1号(2024年1月発行)
特集 新時代の重症筋無力症と関連疾患の診療
75巻12号(2023年12月発行)
特集 アガサ・クリスティーと神経毒
75巻11号(2023年11月発行)
特集 アロスタシス—ホメオスタシスを超えて
75巻10号(2023年10月発行)
特集 メタバースへの招待
75巻9号(2023年9月発行)
特集 妊娠と神経疾患
75巻8号(2023年8月発行)
特集 アルツハイマー病は本当に早期発見できるのか
75巻7号(2023年7月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part2 末梢編
75巻6号(2023年6月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part1 中枢編
75巻5号(2023年5月発行)
増大特集 神経・精神領域の薬剤ハンドブック
75巻4号(2023年4月発行)
特集 All About Epilepsy
75巻3号(2023年3月発行)
特集 慢性疼痛
75巻2号(2023年2月発行)
特集 多系統萎縮症の新診断基準とこれからの診療
75巻1号(2023年1月発行)
特集 よく出会う不随意運動を知る
74巻12号(2022年12月発行)
特集 映画を観て精神・神経疾患を知る
74巻11号(2022年11月発行)
特集 RFC1遺伝子関連スペクトラム障害
74巻10号(2022年10月発行)
特集 ウイルス性脳炎・脳症2022
74巻9号(2022年9月発行)
特集 動的環境への適応系としての歩行
74巻8号(2022年8月発行)
特集 迷走神経の不思議
74巻7号(2022年7月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識2022
74巻6号(2022年6月発行)
特集 脳神経内科医に求められる移行医療
74巻5号(2022年5月発行)
増大特集 次の一手—神経筋疾患難治例をどのように治療するか
74巻4号(2022年4月発行)
特集 脳科学リテラシーを高めるために
74巻3号(2022年3月発行)
特集 中枢性自律神経障害update
74巻2号(2022年2月発行)
特集 温度を感じる脳と身体の科学
74巻1号(2022年1月発行)
特集 脳神経内科医のキャリアパスとリーダーシップ
73巻12号(2021年12月発行)
特集 芸術家と神経学
73巻11号(2021年11月発行)
特集 「目」の神経学
73巻10号(2021年10月発行)
特集 中枢神経・末梢神経の悪性リンパ腫
73巻9号(2021年9月発行)
特集 脳卒中治療に必要な基礎知識
73巻8号(2021年8月発行)
特集 脳腸相関—脳-身体の双方向性制御
73巻7号(2021年7月発行)
特集 グリアと神経—相補的な制御系として
73巻6号(2021年6月発行)
特集 Lower Spine Neurology
73巻5号(2021年5月発行)
増大特集 中枢神経の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
73巻4号(2021年4月発行)
特集 片頭痛・群発頭痛治療の新たな夜明け
73巻3号(2021年3月発行)
特集 マルチリンガルブレイン
73巻2号(2021年2月発行)
特集 筋炎と壊死性筋症
73巻1号(2021年1月発行)
特集 Neuro-Oncology
72巻12号(2020年12月発行)
特集 超高齢期の精神神経疾患を診る
72巻11号(2020年11月発行)
増大特集 脳の発振現象—基礎から臨床へ
72巻10号(2020年10月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識
72巻9号(2020年9月発行)
特集 皮質性小脳萎縮症へのアプローチ
72巻8号(2020年8月発行)
特集 サルコイドーシス
72巻7号(2020年7月発行)
増大特集 神経倫理ハンドブック
72巻6号(2020年6月発行)
特集 前頭側頭葉変性症の今日的理解
72巻5号(2020年5月発行)
特集 多発性硬化症の現在と未来
72巻4号(2020年4月発行)
増大特集 神経疾患の診断における落とし穴—誤診を避けるために
72巻3号(2020年3月発行)
特集 でこぼこの脳の中でおしくらまんじゅうする脳機能
72巻2号(2020年2月発行)
特集 αシヌクレイノパチーの新たな展開
72巻1号(2020年1月発行)
特集 神経難病をクスリで治す—薬物開発の現況と近未来への展望
71巻12号(2019年12月発行)
特集 小脳と大脳—Masao Itoのレガシー
71巻11号(2019年11月発行)
増大特集 ALS2019
71巻10号(2019年10月発行)
特集 認知症と遺伝
71巻9号(2019年9月発行)
特集 神経疾患のドラッグ・リポジショニング—新時代へ
71巻8号(2019年8月発行)
特集 パーキンソン病診療の現在地—200年の変遷と新規治療
71巻7号(2019年7月発行)
増大特集 人工知能と神経科学
71巻6号(2019年6月発行)
特集 補体標的治療の現状と展望
71巻5号(2019年5月発行)
特集 NPSLE
71巻4号(2019年4月発行)
増大特集 神経学のための皮膚アトラス
71巻3号(2019年3月発行)
特集 Spine Neurology
71巻2号(2019年2月発行)
特集 “スポーツ”を生み出す脳
71巻1号(2019年1月発行)
特集 人工知能の医療応用Update
70巻12号(2018年12月発行)
特集 主訴に沿う—俯瞰し収束する画像診断の目
70巻11号(2018年11月発行)
増大特集 脳科学で解き明かす精神神経症候
70巻10号(2018年10月発行)
特集 「左脳と右脳」の現在
70巻9号(2018年9月発行)
特集 脳神経内科診療に役立つ精神科の知識
70巻8号(2018年8月発行)
特集 レヴィ小体型認知症の新知見
70巻7号(2018年7月発行)
増大特集 記憶と忘却に関わる脳のしくみ—分子機構から健忘の症候まで
70巻6号(2018年6月発行)
特集 芸術を生み出す脳
70巻5号(2018年5月発行)
特集 非アルツハイマー型認知症の病理学
70巻4号(2018年4月発行)
増大特集 Antibody Update 2018
70巻3号(2018年3月発行)
特集 『認知症疾患診療ガイドライン2017』を読み解く
70巻2号(2018年2月発行)
特集 知っておきたい神経感染症
70巻1号(2018年1月発行)
特集 筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群の今
69巻12号(2017年12月発行)
特集 運動異常症をみる—Web動画付録つき
69巻11号(2017年11月発行)
増大特集 こころの時間学の未来
69巻10号(2017年10月発行)
特集 成人てんかん—知っておきたい6つのトピック
69巻9号(2017年9月発行)
特集 ミクログリアと精神・神経疾患
69巻8号(2017年8月発行)
特集 遺伝性脊髄小脳失調症の病態と治療展望
69巻7号(2017年7月発行)
増大特集 あしたのアルツハイマー病治療
69巻6号(2017年6月発行)
特集 局在病変の神経心理学
69巻5号(2017年5月発行)
特集 Voxel-Based Morphometry—体積からわかること
69巻4号(2017年4月発行)
増大特集 ブロードマン領野の現在地
69巻3号(2017年3月発行)
特集 磁気刺激の新たな展開
69巻2号(2017年2月発行)
特集 Stroke-Like Diseases—鑑別時に注意を要する5病態
69巻1号(2017年1月発行)
特集 近年注目されている白質脳症
68巻12号(2016年12月発行)
特集 炎症性神経・筋疾患の新たな展開
68巻11号(2016年11月発行)
増大特集 連合野ハンドブック
68巻10号(2016年10月発行)
特集 アディクション—行動の嗜癖
68巻9号(2016年9月発行)
特集 自己免疫性脳炎・脳症
68巻8号(2016年8月発行)
特集 こころと汗
68巻7号(2016年7月発行)
増大特集 認知症の危険因子と防御因子
68巻6号(2016年6月発行)
特集 脳とフローラ
68巻5号(2016年5月発行)
特集 手の症候学—生理学・解剖学からみた新知見
68巻4号(2016年4月発行)
増大特集 治せる認知症
68巻3号(2016年3月発行)
特集 末梢神経の血管炎
68巻2号(2016年2月発行)
特集 筋疾患の認知機能障害
68巻1号(2016年1月発行)
特集 シャルコー・マリー・トゥース病
67巻12号(2015年12月発行)
特集 視床と高次脳機能
67巻11号(2015年11月発行)
増大特集 ギラン・バレー症候群のすべて—100年の軌跡
67巻10号(2015年10月発行)
特集 非・日常生活の脳科学
67巻9号(2015年9月発行)
特集 酵素補充療法
67巻8号(2015年8月発行)
特集 神経難病の終末期医療
67巻7号(2015年7月発行)
増大特集 神経疾患と感染症update
67巻6号(2015年6月発行)
特集 脳と「質感」
67巻5号(2015年5月発行)
特集 NCSE(非痙攣性てんかん重積状態)
67巻4号(2015年4月発行)
増大特集 大脳皮質vs.大脳白質
67巻3号(2015年3月発行)
特集 中枢神経の血管炎
67巻2号(2015年2月発行)
特集 「食べる」を考える
67巻1号(2015年1月発行)
特集 ニューロトキシコロジー
66巻12号(2014年12月発行)
特集 Orthopaedic Neurology—神経内科と整形外科の狭間で
66巻11号(2014年11月発行)
増大特集 神経症候学は神経学の“魂”である
66巻10号(2014年10月発行)
特集 分子を撃つ 神経疾患治療の新しい水平線
66巻9号(2014年9月発行)
特集 痙縮の臨床神経学
66巻8号(2014年8月発行)
特集 神経系の悪性リンパ腫update
66巻7号(2014年7月発行)
増大特集 アミロイド関連神経疾患のすべて―封入体筋炎からアルツハイマー病まで
66巻6号(2014年6月発行)
特集 ミラーニューロン
66巻5号(2014年5月発行)
特集 アセチルコリンと神経疾患―100年目の現在地
66巻4号(2014年4月発行)
増大特集 タッチ・ビジョン・アクション
66巻3号(2014年3月発行)
特集 神経筋疾患の超音波診断
66巻2号(2014年2月発行)
特集 糖尿病の神経学revisited
66巻1号(2014年1月発行)
特集 日常生活の脳科学
65巻12号(2013年12月発行)
特集 プロテイノパチーの神経病理学
65巻11号(2013年11月発行)
増大特集 Close Encounters―臨床神経学と臨床免疫学の遭遇と未来
65巻10号(2013年10月発行)
特集 神経系の発達メカニズム―最近の話題
65巻9号(2013年9月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である―現状と展望
65巻8号(2013年8月発行)
特集 こころの時間学―現在・過去・未来の起源を求めて
65巻7号(2013年7月発行)
増大特集 あしたの脳梗塞
65巻6号(2013年6月発行)
特集 見せる・仕分ける―脳機能解析の新手法
65巻5号(2013年5月発行)
特集 てんかん―新しいパースペクティブ
65巻4号(2013年4月発行)
増大特集 Antibody Update
65巻3号(2013年3月発行)
特集 次世代シーケンサーによる神経変性疾患の解析と展望
65巻2号(2013年2月発行)
特集 血液脳関門研究の進歩
65巻1号(2013年1月発行)
特集 Corticobasal Syndrome
64巻12号(2012年12月発行)
特集 The Border-Land of Dementia
64巻11号(2012年11月発行)
増大特集 痛みの神経学―末梢神経から脳まで
64巻10号(2012年10月発行)
特集 辺縁系をめぐって
64巻9号(2012年9月発行)
特集 高次脳機能イメージングの脳科学への新展開
64巻8号(2012年8月発行)
特集 線条体の基礎と臨床
64巻7号(2012年7月発行)
増大特集 顔認知の脳内機構
64巻6号(2012年6月発行)
特集 睡眠と覚醒の脳内機構
64巻5号(2012年5月発行)
特集 神経疾患のバイオマーカー
64巻4号(2012年4月発行)
増大特集 パーキンソン病の新しい側面
64巻3号(2012年3月発行)
特集 アカデミアから新規治療の実現へ―トランスレーショナルリサーチの現状
64巻2号(2012年2月発行)
特集 生物学的精神医学の進歩
64巻1号(2012年1月発行)
特集 iPS細胞と神経疾患
63巻12号(2011年12月発行)
特集 神経心理学と画像解析の融合
63巻11号(2011年11月発行)
増大特集 筋疾患update
63巻10号(2011年10月発行)
特集 緩徐進行性高次脳機能障害の病態
63巻9号(2011年9月発行)
特集 脳卒中の最新画像診断
63巻8号(2011年8月発行)
特集 日本人の発見した神経症候
63巻7号(2011年7月発行)
増大特集 神経筋接合部―基礎から臨床まで
63巻6号(2011年6月発行)
特集 ニューロパチー
63巻5号(2011年5月発行)
特集 神経系と血管内リンパ腫
63巻4号(2011年4月発行)
増大特集 てんかんの新しい治療
63巻3号(2011年3月発行)
特集 サイバーナイフ治療
63巻2号(2011年2月発行)
特集 続・日本人の発見した神経疾患
63巻1号(2011年1月発行)
特集 血管腫
62巻12号(2010年12月発行)
特集 頸部頸動脈狭窄症の診断と治療
62巻11号(2010年11月発行)
増大特集 歩行とその異常
62巻10号(2010年10月発行)
特集 ブレインバンク
62巻9号(2010年9月発行)
特集 視神経脊髄炎(NMO)update
62巻8号(2010年8月発行)
特集 辺縁系脳炎
62巻7号(2010年7月発行)
増大特集 アルツハイマー病―研究と診療の進歩
62巻6号(2010年6月発行)
特集 改正臓器移植法の問題点とその対応
62巻5号(2010年5月発行)
特集 神経画像のピットフォール―見落としと読み過ぎ
62巻4号(2010年4月発行)
特集 傍腫瘍性神経筋疾患update
62巻3号(2010年3月発行)
特集 神経回路解析法の最近の進歩
62巻2号(2010年2月発行)
特集 ニューロリハビリテーションの最前線
62巻1号(2010年1月発行)
特集 神経救急
61巻12号(2009年12月発行)
特集 Somatotopy再考
61巻11号(2009年11月発行)
特集 前頭側頭葉変性症
61巻10号(2009年10月発行)
特集 片頭痛の予防療法
61巻9号(2009年9月発行)
特集 脳血管障害治療の進歩
61巻8号(2009年8月発行)
特集 神経・筋疾患の分子標的治療
61巻7号(2009年7月発行)
特集 脳腫瘍研究の最前線―遺伝子解析から治療まで
61巻6号(2009年6月発行)
特集 脊椎・脊髄外科の最近の進歩
61巻5号(2009年5月発行)
特集 Restless legs syndrome
61巻4号(2009年4月発行)
特集 大脳基底核―分子基盤から臨床まで
61巻3号(2009年3月発行)
特集 Microneurography(微小神経電図法)の臨床応用
61巻2号(2009年2月発行)
特集 神経系の再興感染症と輸入感染症
61巻1号(2009年1月発行)
特集 脳神経倫理
60巻12号(2008年12月発行)
特集 痙縮
60巻11号(2008年11月発行)
特集 脳卒中と遺伝子
60巻10号(2008年10月発行)
特集 若年者の脳卒中
60巻9号(2008年9月発行)
特集 知・情・意の神経学
60巻8号(2008年8月発行)
特集 脳硬膜動静脈瘻
60巻7号(2008年7月発行)
増大特集 学習と記憶――基礎と臨床
60巻6号(2008年6月発行)
特集 Crow-深瀬症候群(POEMS症候群)
60巻5号(2008年5月発行)
特集 「痛み」の研究と治療の最前線
60巻4号(2008年4月発行)
増大特集 神経系の発生とその異常
60巻3号(2008年3月発行)
特集 特発性正常圧水頭症(iNPH)―最近の話題
60巻2号(2008年2月発行)
特集 がん治療と神経障害
60巻1号(2008年1月発行)
特集 日本人の発見した神経疾患
59巻12号(2007年12月発行)
特集 損傷神経の再生―温存的治療法の開発
59巻11号(2007年11月発行)
特集 手根管症候群をめぐって
59巻10号(2007年10月発行)
増大特集 ALS―研究と診療の進歩
59巻9号(2007年9月発行)
特集 パーキンソン病の認知機能障害
59巻8号(2007年8月発行)
特集 パーキンソン病の分子遺伝学―最近の知見
59巻7号(2007年7月発行)
増大特集 情報伝達処理におけるグリアの機能と異常
59巻6号(2007年6月発行)
特集 職業性神経障害の新しい展開
59巻5号(2007年5月発行)
特集 脳画像最前線
59巻4号(2007年4月発行)
増大特集 最近注目される脳神経疾患治療の研究
59巻3号(2007年3月発行)
特集 分子イメージング
59巻2号(2007年2月発行)
特集 進行性多巣性白質脳症の新しい展開―PMLが治る時代へ向けて
59巻1号(2007年1月発行)
特集 高次視覚研究の最近の進歩
