毎年数多くの新薬が上市され,既存の薬剤に関する情報も日々アップデートされています。また,高齢患者では神経・精神疾患に生活習慣病などの慢性疾患を併存することが多く,多剤服用による有害事象の防止という観点からも,薬剤の正しい知識が求められます。
本増大号特集では,脳神経内科-脳神経外科-精神科の薬剤を領域横断的に取り上げ,薬物療法によって完治を目指すのか,症状のコントロールを目的とするのかなど,治療戦略における位置づけと意義を示すとともに,症状や経過,合併症を踏まえた薬剤の選択について,処方例や注意すべき副作用と合わせて解説しました。また,非薬物療法が不十分な例では薬物療法が功を奏さない場合もあり,治療計画の全体像を把握することの重要性も論じられています。
適切なタイミング,量,期間で適切な薬剤を選択できるかが治療効果を左右することは論をまちません。臨床で活用できる薬剤の知識を網羅した本特集を傍らに置き,よきパートナーとしてお役立ていただきたいと思います。
雑誌目次
BRAIN and NERVE-神経研究の進歩75巻5号
2023年05月発行
雑誌目次
増大特集 神経・精神領域の薬剤ハンドブック
扉 フリーアクセス
ページ範囲:P.409 - P.409
〈総論〉
神経領域の薬剤の現状を俯瞰する—真のDecade of Brainの到来か
著者: 漆谷真
ページ範囲:P.411 - P.417
近年,多くの神経疾患に対して疾患修飾薬が開発された。その基盤技術は核酸医薬や抗体医薬,さらに酵素補充療法といった新規技術を用いたものから,従来薬の投与方法の工夫,さらに基礎研究によるプルーフオブコンセプト(POC)からドラッグリポジショニングを経て有効性が示されたものまで,多種多様な創薬戦略が結実している。「治る脳神経内科」に向けた最新の神経疾患治療薬を概観する。
精神領域の薬剤の現状
著者: 鈴木健文
ページ範囲:P.418 - P.420
現在のところ,ほとんどの精神疾患の病態生理は十分には解明されておらず,ゆえに薬物療法はある意味empiricと言える。そのような中でも,最近,既存の作用機序とは異なる,または既存薬の見直し(ある意味repurposing)などのアプローチにより,現状の打破が試みられている。本論ではこうした試みの一部を簡単に概説する。
神経・精神領域の薬剤相互作用
著者: 長谷達 , 古郡規雄 , 下田和孝
ページ範囲:P.421 - P.426
薬剤相互作用のうち,薬物動態学的相互作用は複数の薬剤の生体内動態が相互に影響し合うことで血中濃度変動を生じるもので,薬物代謝酵素(シトクロムP450,UDPグルクロン酸転移酵素)と薬物トランスポーター(P糖蛋白質など)が主に関与している。同時に使用する薬剤が増えるほど相互作用を生じるリスクが上がるため,可能な限り薬剤数を減らす努力とともに,相互作用のメカニズムと注意すべき薬剤を知っておくことが重要である。
脳神経内科領域における開発途上の薬剤
著者: 関島良樹
ページ範囲:P.427 - P.432
従来,脳神経内科領域の疾患,特に変性疾患に対しては,低分子医薬による対症療法が中心であった。しかし近年,疾患の発症機序の根本に働きかけ病理・病態を改善させる疾患修飾薬として,特定の蛋白質,RNA,DNAに選択的に作用する抗体医薬,核酸医薬,遺伝子治療薬の開発が進行している。神経免疫疾患や機能性疾患のみならず,蛋白質の機能喪失や異常蛋白質の蓄積による神経変性疾患も根治治療が可能になることが期待される。
脳神経外科領域における開発途上の薬剤
著者: 上羽哲也
ページ範囲:P.433 - P.436
脳神経外科領域で期待される新薬について,オープンソースを用いて記載する。脳神経外科領域で特に期待されるデリタクト®,ステミラック®と呼ばれる薬剤を紹介したい。この両剤は再生医療等製品として承認を受けているものである。デリタクト®は悪性神経膠腫を適応症としているがんウイルス療法である。本邦でのみ限定的に承認されている。ステミラック®は自己の間葉系細胞を培養した再生医療等製品で,脊髄損傷を対象に本邦でのみ限定的に承認されている。
精神科領域における開発途上の薬剤
著者: 内田裕之
ページ範囲:P.437 - P.440
近年,1つの薬剤の開発を複数の疾患に対してほぼ同時に進めることも少なくなく,その例としてpimavanserinとpsilocybinが挙げられる。一時期は,世界有数のメガファーマが中枢神経薬開発から撤退といった精神神経薬理分野にとって暗いニュースが少なくなかったが,上市前ではあるものの,上記のような新規作用機序に基づく薬剤が次々と登場している。これは臨床精神薬理分野の新たな夜明けと言えよう。
〈各論〉
パーキンソン病治療薬
著者: 齊藤勇二 , 高橋一司
ページ範囲:P.441 - P.449
パーキンソン病(Parkinson's disease:PD)はドパミン欠乏が主病態であり,ドパミン補充療法が治療の中心である。早期PDではL-ドパ,ドパミンアゴニスト(dopamine agonist:DA),モノアミン酸化酵素B(monoamine oxidase B:MAOB)阻害薬で開始する。進行期PDではウェアリングオフやジスキネジアなどの運動合併症に対し,DAやMAOB阻害薬,カテコール-O-メチル基転移酵素阻害薬,非ドパミン系治療薬を併用する。アマンタジンや抗コリン薬は特定の状況で使用されることがある。
脳卒中治療薬
著者: 永田栄一郎
ページ範囲:P.450 - P.455
脳卒中治療は,発症時(急性期)治療とその後の再発予防治療が重要である。脳梗塞急性期治療として,血栓溶解療法,局所血栓回収療法があり,再発予防は抗血栓療法を行う。脳梗塞の病型に応じて,アテローム血栓性脳梗塞,ラクナ梗塞に対しては,抗血小板療法が中心となり,また,心原性脳塞栓症に対しては,抗凝固療法が中心となる。そのほかに脳保護療法や,近年細胞再生治療なども行われるようになってきた。
抗てんかん薬
著者: 吉野相英
ページ範囲:P.456 - P.463
てんかん治療の原則は発作型に基づいて抗てんかん薬を選択することにある。発作型は焦点起始発作と全般起始発作(全般強直間代発作,全般ミオクロニー発作,欠神発作など)に分類される。併存症がある患者や妊娠可能年齢の女性患者では慎重な薬剤選択が求められる。薬剤選択と用量設定が適切な2種類以上の抗てんかん薬によっても寛解に至らなかった場合,てんかん専門医に紹介することが望ましい。
抗認知症薬(抗アルツハイマー病薬)
著者: 山田正仁
ページ範囲:P.464 - P.469
アルツハイマー病(Alzheimer's disease:AD)の主病態である認知症に対する薬物療法[抗認知症薬(抗AD薬)]は症状改善薬と疾患修飾薬(現在開発中)に分類される。本論では,現在使用可能な症状改善薬4剤[コリンエステラーゼ阻害薬(ドネぺジル,ガランタミン,リバスチグミン)およびN-メチル-D-アスパラギン酸(NMDA)受容体拮抗薬(メマンチン)]の使用の実際や使用上の注意点などについて解説した。
片頭痛治療薬
著者: 菊井祥二 , 竹島多賀夫
ページ範囲:P.470 - P.478
2000年以降,トリプタンや世界標準の片頭痛予防薬(バルプロ酸,プロプラノロール)が認可され,本邦の片頭痛治療は大きく進歩したが,アンメットニーズは存在していた。トリプタンの効果が不十分,また副作用,禁忌が見られる患者には選択的5-HT1F受容体作動薬(ラスミジタン)の,既存の片頭痛予防薬で効果不十分な患者にはカルシトニン遺伝子関連ペプチド(calcitonin gene-related peptide:CGRP)を標的にしたCGRP関連抗体薬の有効性,安全性が見られ,福音をもたらしている。
自己免疫性脳炎治療薬
著者: 亀井聡
ページ範囲:P.479 - P.484
この15年間,神経細胞表面やシナプス受容体に対する抗体を持つ自己免疫性脳炎が次々と発見され,その診断と治療のパラダイムが変化している。自己免疫性脳炎に対するfirst lineは,ステロイドパルスと免疫グロブリン大量静注療法の併用である。無反応例ではsecond lineとしてリツキシマブやシクロホスファミドが投与される。難治例に対しては明確な指針がないのが現状であるが,(1)サイトカイン製剤のトシリズマブ,(2)プロテアソーム阻害薬のボルテゾミブが提案されている。
多発性硬化症治療薬—治療戦略と疾患修飾薬
著者: 茂木晴彦 , 北川賢 , 中原仁
ページ範囲:P.485 - P.490
多発性硬化症は中枢神経を侵す原因不明の炎症性脱髄疾患である。かつて「不治の病」であったが,20世紀より多くの疾患修飾薬が登場し,本邦では8種類が処方可能である。昨今の治療戦略のアップデートは目覚ましく,“escalation strategy”から予後不良因子に基づいた“personalized approach”,さらには“early top-down strategy”へと大きく変化しつつある。
視神経脊髄炎治療薬
著者: 中島一郎
ページ範囲:P.493 - P.497
視神経脊髄炎(neuromyelitis optica:NMO)の急性期治療にはステロイドパルス治療,血漿浄化療法,免疫グロブリン大量静注療法などを用いる。再発予防には従来プレドニゾロンやアザチオプリンなどの経口免疫抑制薬が用いられていたが,近年エクリズマブ,サトラリズマブ,イネビリズマブ,リツキシマブなどの生物学的製剤の適用が承認された。
脊髄小脳変性症治療薬
著者: 松島理明 , 矢部一郎
ページ範囲:P.498 - P.502
脊髄小脳変性症や多系統萎縮症に対して,いまだに疾患修飾療法は確立しておらず,現在利用可能なものは対症療法のみである。小脳性運動失調症状に対する保険適用薬剤としては,タルチレリンとプロチレリンがあり,症状進行抑制効果が期待されている。脊髄小脳変性症に伴う痙縮には筋弛緩薬が使用され,多系統萎縮症の自律神経症状には昇圧薬や排尿障害治療薬などが用いられている。今後は新しい機序の治療薬の開発が望まれる。
筋萎縮性側索硬化症治療薬
著者: 荻野美恵子
ページ範囲:P.503 - P.506
筋萎縮性側索硬化症(amyotrophic lateral sclerosis:ALS)に対して現在保険適用になっている薬剤はリルゾールとエダラボンである。生存期間の延長または進行抑制効果が示されているが,いずれも完治させる治療ではなく,効果は実感しにくい。治験で示されたデータはすべてのALS患者に当てはまるわけではないので,リスクとベネフィットをよく説明して使用すべきである。エダラボンはこれまで静脈点滴投与であったが,2023年4月17日に経口薬が発売になった。モルヒネ塩酸塩およびモルヒネ硫酸塩はALSに対して保険審査上認められている。
脊髄性筋萎縮症治療薬
著者: 石山昭彦
ページ範囲:P.507 - P.510
脊髄性筋萎縮症はSMN1遺伝子が欠失することにより発症する。近年,遺伝子に作用する病態に沿った治療薬として3種類の薬剤が承認されてきた。SMN1遺伝子と5塩基のみ異なるSMN2遺伝子のスプライシング修飾に関わるヌシネルセン,リスジプラム,さらにSMN遺伝子をアデノ随伴ウイルスベクターを用いて遺伝子導入するオナセムノゲンアベパルボベクである。これらの新しい治療薬についての機序や特性を理解し,適応や年齢に応じ適切に薬剤選択する必要がある。
特発性炎症性筋疾患治療薬
著者: 冨滿弘之
ページ範囲:P.511 - P.516
特発性炎症性筋疾患(idiopathic inflammatory myopathy:IIM)は封入体筋炎を除き,免疫治療で治療可能な疾患である。副腎皮質ステロイド治療(高用量プレドニゾロン内服,メチルプレドニゾロンパルス追加)を軸として2週間程度で効果判定を繰り返す。効果不十分の場合,アザチオプリン,タクロリムス,メトトレキサートなどの免疫抑制薬を追加し,その効果が表れるまで免疫グロブリン大量静注療法を行う。それでも治療抵抗性を示す場合は,リツキシマブなどの生物学的製剤を導入して寛解を目指す。病勢がコントロールできたらプレドニゾロンをはじめとする治療薬を漸減していく。
遺伝性筋疾患治療薬
著者: 大矢寧
ページ範囲:P.517 - P.521
遺伝性筋疾患では,①病型や遺伝子変異によっては,ポンペ病の酵素補充療法や,デュシェンヌ型筋ジストロフィー(Duchenne muscular dystrophy:DMD)の一部の患者でのエクソンスキッピング療法のように特異的な治療法が開発されてきている。ただし,有効性には限界がある。②DMDなど一部の病型で,筋力の維持に副腎皮質ステロイドの有効性がある程度まである。DMDの小児では標準治療である。長期内服を前提とするため,副作用を避ける必要がある。特に骨粗鬆症に伴う骨折はADL/QOLを低下させる。投与量は必要最小限とし,成人では減量しやすい隔日内服も考慮する。いずれの薬物療法も,適切な評価のうえで,呼吸や心筋などに従来通りの対応がしっかりできていることが前提となる。
ミトコンドリア脳筋症治療薬
著者: 砂田芳秀
ページ範囲:P.523 - P.525
ミトコンドリア脳筋症・乳酸アシドーシス・脳卒中様発作症候群(MELAS)ではミトコンドリアロイシンtRNAのアンチコドンにおけるタウリン修飾欠損によりコドンの翻訳障害が惹起される。高用量タウリン補充療法の医師主導治験により脳卒中様発作の再発抑制効果,タウリン修飾率の改善,安全性が示され,2019年に適用追加が薬事承認された。最近,L-アルギニン塩酸塩も脳卒中様発作急性期および間欠期治療として適応外使用の保険診療が承認された。
重症筋無力症治療薬
著者: 村井弘之
ページ範囲:P.527 - P.532
重症筋無力症(myasthenia gravis:MG)の治療法としては,以前より漸増漸減による高用量の経口ステロイドが主流であったが,2010年頃より高用量のステロイドによる弊害が次第に明らかとなり,早期速効性治療戦略が提唱されるようになった。これにより患者の生活の質は改善してきたが,いまだに生活に支障のある患者は多く,また「難治性MG」も一定の割合で存在する。最近,分子標的薬が次々と開発され,現在では3剤がMGに使用可能になった。
炎症性ニューロパチー治療薬
著者: 西原秀昭 , 神田隆
ページ範囲:P.533 - P.538
炎症性ニューロパチーの多くは免疫療法で治療可能な疾患である。軸索変性による不可逆的な障害が生じる前に強力な治療を行うことが重要である。免疫療法が治療の中心だが,疾患ごとに薬剤の有効性に差があり,患者ごとに治療反応性が異なることをしばしば経験する。適切な時期に治療効果判定を行うことで,重症例を見極め,患者ごとに最適の治療を選択する必要がある。
遺伝性トランスサイレチンアミロイドーシス治療薬
著者: 植田光晴
ページ範囲:P.539 - P.541
遺伝性トランスサイレチンアミロイドーシスは,常染色体優性の代表的な遺伝性アミロイドーシスである。以前は本症に対して肝移植療法が実施されていたが,近年,本疾患に対する疾患修飾療法(薬物治療)が劇的に進歩したため,現在,本疾患に対して肝移植が実施されることはなくなった。第2世代の核酸医薬であるブトリシランが承認され,TTR gene silencing療法を継続的に受ける患者負担が大きく軽減された。
ジストニア・ミオクローヌス・コレア治療薬
著者: 長谷川一子
ページ範囲:P.542 - P.548
ジストニア,ミオクローヌス,コレアは頻度の高い運動障害である。運動障害は運動過小型と運動過多群とに分類して評価する。運動過多群の多くは不随意運動を伴い,スピードの速い順にミオクローヌス,コレア,ジストニアなどがある。運動過多群の不随意運動の発現機構は大脳皮質,白質,基底核,脳幹,小脳のいずれもが想定され,発症機構を考慮した薬物療法の選択が望ましい。ここでは運動過多運動障害群の治療法の概説を述べる。
本態性振戦治療薬
著者: 宮本勝一 , 伊東秀文
ページ範囲:P.549 - P.552
本態性振戦治療薬の第一選択は,エビデンスレベルからはβ遮断薬とプリミドンであるが,忍容性の観点からβ遮断薬から開始する。アロチノロールはわが国で開発され,本態性振戦の治療薬として承認されている唯一の薬剤である。プロプラノロールは多数の臨床試験のデータを有する。β遮断薬が使えない場合や効果不十分例ではプリミドンへの変更や併用を考慮する。また,ベンゾジアゼピン系薬剤や他の抗てんかん薬も有効である。
遅発性ジスキネジア治療薬
著者: 楠戸惠介 , 竹内啓善
ページ範囲:P.553 - P.556
遅発性ジスキネジア(tardive dyskinesia:TD)は難治性であり,生活に支障をきたし得る重大な副作用である。原因薬剤の適正化の次に,薬剤追加による治療が試みられる。本論では,最近承認された本邦初のTD治療薬であるバルベナジン,クロナゼパム,ビタミンEについて解説する。
レストレスレッグス症候群治療薬
著者: 鈴木圭輔 , 土屋智裕 , 平田幸一
ページ範囲:P.557 - P.560
レストレスレッグス症候群は不快感を伴う下肢を動かしたいという強い衝動により不眠や日中の機能障害をきたす疾患である。治療には規則的な睡眠習慣や運動などの非薬物療法のほか,血清フェリチン低値例には鉄剤の補充を行う。抗うつ薬,抗ヒスタミン薬やドパミン遮断薬は症状を惹起させるため併用している場合には投薬を減量および中止する。薬物療法ではドパミンアゴニストやα2δリガンド製剤が第一選択として用いられる。
脳腫瘍治療薬
著者: 北村洋平 , 戸田正博
ページ範囲:P.561 - P.566
脳腫瘍,特に悪性脳腫瘍は手術と放射線治療のみでのコントロールは困難なことが多く,薬物治療は非常に大きな役割を担っている。腫瘍の種類により使用する薬剤はさまざまであり,特に頻度の高い悪性神経膠腫においては長くテモゾロミドが治療の主体であるが,近年では分子標的薬やウイルス治療薬など新しい選択肢もある。また,腫瘍の種類によってはニトロソウレアや白金製剤などによる古典的な抗がん薬治療も引き続き行われている。
神経障害性疼痛治療薬
著者: 猪狩裕紀 , 牛田享宏
ページ範囲:P.567 - P.571
「神経障害性疼痛」に分類される多くの疾患は,非ステロイド性抗炎症薬やアセトアミノフェンなど一般的に頻用される鎮痛薬の効果は乏しいことが多い。第一選択薬としてカルシウムイオンチャネルα2δリガンド,セロトニン・ノルアドレナリン再取込み阻害薬,三環系抗うつ薬の中から開始する。しばらく使用しても効果が見られない場合は,ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液やトラマドール,最終的にはオピオイド鎮痛薬へとシフトしていく。
抗うつ薬
著者: 渡邊衡一郎
ページ範囲:P.573 - P.578
三環系抗うつ薬は抗コリン,抗アドレナリンα1,抗ヒスタミンH1作用,また過量服薬での危険性により患者のQOLに影響を及ぼすために,新規抗うつ薬が開発された。選択的セロトニン再取込み阻害薬はセロトニンを選択的に取り込み,非鎮静系薬で不安症にも効果を発揮する。消化器系副作用が見られ,性機能障害や出血傾向に注意する。セロトニン・ノルアドレナリン再取込み阻害薬は意欲向上が期待される非鎮静系薬である。慢性疼痛に効果的だが,消化器症状に加え,頻脈,血圧上昇に留意する。ミルタザピンは鎮静系薬で,食欲不振や不眠を呈する例に用いられる。ただ眠気,そして体重増加に留意する。ボルチオキセチンは非鎮静系薬で,不眠や性機能障害が少ないものの,胃腸症状は認められる。
抗精神病薬(統合失調症治療薬)
著者: 山田恒 , 橋本亮太
ページ範囲:P.579 - P.584
統合失調症は,幻覚や妄想,思考障害,認知機能障害などを呈する精神疾患である。統合失調症では抗精神病薬の単剤治療の有効性が示されている。近年,主に使用される抗精神病薬は,錐体外路系の副作用の出現頻度がやや低い第2世代抗精神病薬であり,これらは非定型抗精神病薬とも呼ばれる。2種類以上の抗精神病薬の単剤使用で十分な改善が認められない場合には,治療抵抗性統合失調症と診断され,クロザピンが使用される。
抗不安薬
著者: 村岡寛之 , 稲田健
ページ範囲:P.585 - P.590
抗不安薬には,主にベンゾジアゼピン受容体作動薬とセロトニン1A受容体部分作動薬がある。ベンゾジアゼピン受容体作動薬は,抗不安作用,鎮静催眠作用,筋弛緩作用,抗けいれん作用を有する。奇異反応,離脱症状,依存性が問題となるため,漫然と使用しないことが望ましい。セロトニン1A受容体部分作動薬は,発現に時間がかかるなどの問題点がある。抗不安薬の種類,それぞれの特性を理解して臨床に臨むことが重要である。
睡眠薬
著者: 加藤隆郎 , 小曽根基裕
ページ範囲:P.591 - P.598
不眠症は臨床で遭遇する頻度の高い疾患の1つであり半数程度が長期経過をたどる。このため,睡眠衛生指導など非薬物的アプローチをまず行い,慢性化を予防することが求められている。また薬物療法を行う際にも,減薬・休薬がしやすく,転倒や認知機能障害,依存・耐性形成のリスクが低いオレキシン受容体拮抗薬やメラトニン受容体作動薬等の新規睡眠薬を積極的に選択することが望ましい。
精神刺激薬(中枢神経刺激薬)
著者: 福元進太郎 , 今成英司 , 渡真利眞治 , 東琢磨 , 小坂浩隆
ページ範囲:P.599 - P.604
ナルコレプシーの治療はまず生活リズムを整えるべきだが,過眠症状にモダフィニル,短時間作用型メチルフェニデート,ぺモリンなどの中枢神経刺激薬が使用される。注意欠如・多動症(ADHD)の治療は心理社会的アプローチがメインとなるが,中等度以上には薬物治療が行われる。本邦認可の4剤のうち2剤が中枢神経刺激薬(メチルフェニデート徐放剤,リスデキサンフェタミン)であり,ADHD適正流通管理システムにて管理されている。
気分安定薬(双極性障害治療薬)
著者: 鈴木映二
ページ範囲:P.605 - P.611
双極性障害は気分,行動,意欲などに障害をきたす精神疾患である。抑うつエピソードと躁(軽躁)エピソードを繰り返し(その両方の症状が混在する混合エピソードもある),その間に寛解期がある。治療は,それぞれのエピソードに対する治療とともに,次のエピソードを予防する維持療法も必要になる。主に用いられる薬は古典的には炭酸リチウムやバルプロ酸であり,近年,ラモトリギンに加え,アリピプラゾール,クエチアピン,ルラシドンなどの非定型抗精神病薬も使用されるようになってきている。治療の原則は単剤治療であるが,実際には,いくつかの薬を組み合わせて治療を行うことも稀ではない。
アルコール依存症治療薬
著者: 松下幸生
ページ範囲:P.613 - P.622
アルコール依存の薬物療法について,アルコール離脱の薬物療法,断酒や飲酒量減少の薬物療法,断酒後に持続する不眠の薬物療法に分類して解説した。断酒を目標とする場合にはアカンプロサートが第一選択薬であり,飲酒量減少を目標とする場合にはナルメフェンを使用できるが,いずれの場合も心理社会的治療と組み合わせることによって,より効果を発揮する。
排尿障害治療薬
著者: 榊原隆次 , 澤井摂 , 尾形剛
ページ範囲:P.623 - P.629
排尿障害は過活動膀胱[OAB(overactive bladder)とも言う,トイレが近い症状]と残尿・尿閉(尿が出しにくい症状)を合わせた言葉で,一般に脳疾患はOABを,末梢神経疾患は残尿・尿閉を,多系統萎縮症や脊髄疾患はOABと残尿・尿閉を同時にきたすことが多い。このうち,OABに対して選択的β3受容体刺激薬/抗コリン薬を,残尿・尿閉に対して間欠導尿,α交感神経遮断薬,コリン作動薬を組み合わせながら投与するとよい。排尿障害の治療を積極的に行い,患者の生活の質を向上させることが望まれる。
起立性低血圧治療薬
著者: 朝比奈正人
ページ範囲:P.631 - P.636
起立性低血圧は起立に伴う血液分布の変化(下肢への貯留)に対処できずに血圧が低下する現象で自律神経不全による神経原性低血圧と非神経原性のものに分けられる。神経原性起立性低血圧は多くの神経疾患で見られる症候であり,神経疾患の日常診療において大きな問題となり,対処が求められる。本論では神経原性起立性低血圧の病態と診断について概説し,その治療戦略と治療に用いる薬の特性と使用方法について解説する。
神経領域の漢方薬
著者: 村松慎一
ページ範囲:P.637 - P.640
古典に記載された先人の経験則を考慮し品質の安定したエキス製剤を使用するとよい。片頭痛には五苓散,呉茱萸湯,当帰芍薬散,桂枝茯苓丸が頻用される。五苓散は慢性硬膜下血腫にも用いられる。認知症の行動・心理症状には抑肝散や桂枝加竜骨牡蛎湯が有用である。末梢神経障害に伴うしびれ・疼痛には附子の配合された桂枝加朮附湯,真武湯などを使用する。難治性吃逆には半夏瀉心湯を試みる。甘草による偽アルドステロン症などの副作用に注意する。
精神科領域の漢方薬
著者: 坪井貴嗣
ページ範囲:P.641 - P.644
漢方薬はさまざまな理由によりエビデンスの構築が難しく,そのため向精神薬と比較して臨床場面での使用方法は曖昧であり,治療者個人に委ねられている印象がある。本論では,漢方特有の診断手法である証の中で精神科領域において特に重要と考えられる気血水の異常を中心に,代表的な漢方薬とその処方指針について詳説した。漢方薬は当事者の望む治療手段の1つであり,例えば向精神薬治療で行き詰まった当事者の一助になればと考える。
〈特定の場面での使い方〉
周産期における向精神薬の使い方—胎児,乳児へのリスクとベネフィット
著者: 和田周平 , 小笠原一能 , 尾崎紀夫
ページ範囲:P.645 - P.651
周産期は精神疾患の発症・増悪のリスクが高まるが,胎児や乳児への影響が不安視され向精神薬による適切な治療が行われない場合がある。本論では,周産期の発症・増悪リスクが高い精神疾患を概説し,それぞれの疾患の標準的な薬物療法における胎児や乳児へのリスクとベネフィットについて解説した。また,薬物治療の際には,妊娠を見据えて患者・家族とともに事前に相談しておくことや,正しい情報を基にした共同での意思決定が重要であることを述べた。
小児神経疾患に対する薬剤の使い方
著者: 高橋孝雄 , 三橋隆行
ページ範囲:P.652 - P.657
小児は成人に比し身体が小さいのみならず薬物代謝速度が異なり,中枢神経系への作用・副作用の発現パターンも一部異なる。また疾患ごとの症例数が少ないこと,さらに倫理面で特別な配慮が必要となることなどから多くの薬剤で小児を対象とした治験がなされにくい現状がある。本論では,投薬治療が主な治療法であるてんかん,注意欠如・多動症に対する薬剤と,近年治療が可能となった脊髄性筋萎縮症に対する新規薬剤について概説する。
高齢者の薬剤の使い方
著者: 秋下雅弘
ページ範囲:P.658 - P.662
高齢者は薬物動態の加齢変化とポリファーマシーを背景として薬物有害事象が出やすい。薬物動態上の対応は少量で開始する原則と長期処方中の用量見直しであり,ポリファーマシーに対しては,「特に慎重な投与を要する薬物のリスト」などを参照しつつ,治療の優先順位を考慮した処方を心がける。高齢者では認知機能や視力,聴力の低下など服薬管理能力の低下を認める場合も多く,アドヒアランスを維持するための工夫を実践する。
薬剤と自動車運転
著者: 松尾幸治
ページ範囲:P.663 - P.669
薬剤と自動車運転との関係は,薬理学的問題にとどまらず,行政や法的問題が深く関与している。精神疾患・神経疾患患者が自動車運転で事故を起こしたときには,自動車運転死傷行為処罰法等の法律により処罰される危険性がある。また,これらの疾患の治療薬の医薬品情報(添付文書)の多くは,自動車運転の制限を科している。こうした制限を緩和させるには,学会等で声を上げることのみならず,エビデンスの蓄積も必要である。
連載 医師国家試験から語る精神・神経疾患・5
統合失調症の診断学
著者: 水谷真志 , 髙尾昌樹
ページ範囲:P.671 - P.674
統合失調症を強く示唆する患者の発言はどれか。
a 「自分には霊がとりついている」
b 「(天井のしみを指さして)虫が這っている」
c 「自分は癌にかかっているので,明日には死ぬ」
d 「自分の考えることがすべて周囲の人に伝わっている」
e 「外に出ると通行人が自分を見るので,外出できない」
(第113回B18)
お知らせ
第68回・69回 筋病理セミナー フリーアクセス
ページ範囲:P.497 - P.497
国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター主催
2023年度の筋病理セミナーを下記の要領で開催します。本セミナーでは,講義と実習を通して筋病理学の基本と代表的な筋疾患の概要を学ぶことができます。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.404 - P.405
欧文目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.406 - P.407
バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.680 - P.680
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.681 - P.681
あとがき フリーアクセス
著者: 酒井邦嘉
ページ範囲:P.682 - P.682
先日,チェスの名コーチであるアレクサンダー・チャーニン氏(Alexander Chernin, 1960-)のレクチャーを聴いた。今回の来日は,チェスの日本での普及に長年尽力されてきたジャック・ピノー氏の招きによる。両氏は将棋棋士の羽生善治九段と森内俊之九段にとって,チェスのコーチでもある。レクチャーのテーマは,prophylactic thinking(予防的思考)というチェスの高等戦術に関するものだった。
prophylaxis(予防措置)というチェスの考え方は,百年前に活躍したアロン・ニムゾヴィッチ(Aron Nimzowitsch, 1886-1935)に端を発する。My System(1925)という彼の名著には,“prophylaxis(anticipation of problems)”(問題の予期)とあり,相手の指し得る手や陣形を予期し,それを封じるような作戦を意味する。チャーニン氏のレクチャーでは,予期した手を直接抑止するような「直接予防」と,もし相手がその手を指すと不利な状況に陥るように準備する「間接予防」について,実際のゲームの局面をもとに解説がなされた。単なる攻撃や防御の手とは異なり,予防的思考には「相手の思考について考える」という奥深さがあり,人間ならではのメタ思考(思考の再帰性)の例として実に興味深い。
基本情報
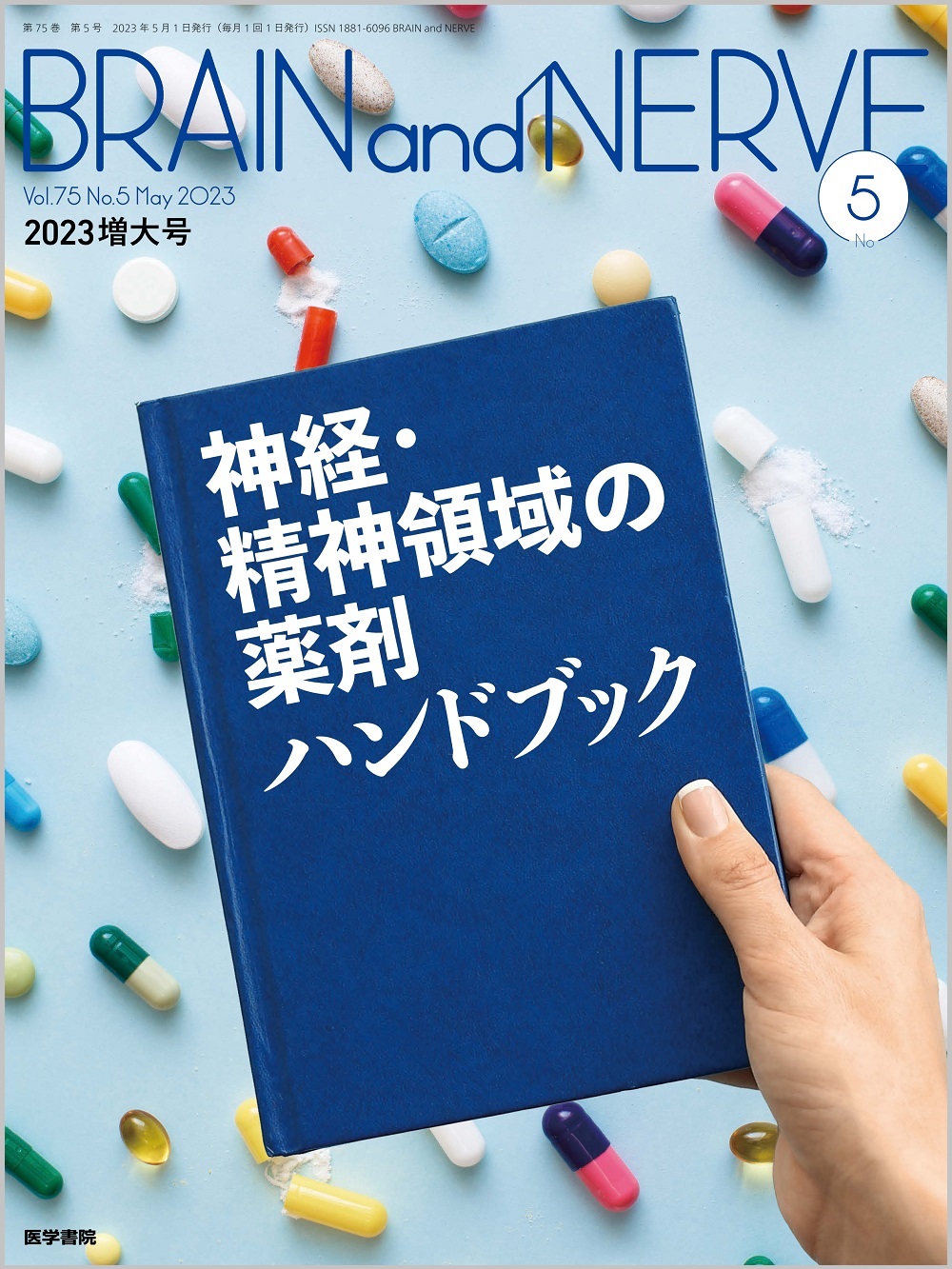
バックナンバー
76巻12号(2024年12月発行)
特集 芸術家と神経学Ⅱ
76巻11号(2024年11月発行)
特集 ALS 2024
76巻10号(2024年10月発行)
特集 どうして効くんだろう
76巻9号(2024年9月発行)
特集 治療可能な認知症としてのアルツハイマー病
76巻8号(2024年8月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である—revisited
76巻7号(2024年7月発行)
特集 ニューロ・バイオイメージング—技術と応用
76巻6号(2024年6月発行)
特集 注意と注意障害
76巻5号(2024年5月発行)
増大特集 末梢神経・筋肉の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
76巻4号(2024年4月発行)
特集 神経病理最前線
76巻3号(2024年3月発行)
特集 きちんと説明ができますか?
76巻2号(2024年2月発行)
特集 特発性正常圧水頭症の現在
76巻1号(2024年1月発行)
特集 新時代の重症筋無力症と関連疾患の診療
75巻12号(2023年12月発行)
特集 アガサ・クリスティーと神経毒
75巻11号(2023年11月発行)
特集 アロスタシス—ホメオスタシスを超えて
75巻10号(2023年10月発行)
特集 メタバースへの招待
75巻9号(2023年9月発行)
特集 妊娠と神経疾患
75巻8号(2023年8月発行)
特集 アルツハイマー病は本当に早期発見できるのか
75巻7号(2023年7月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part2 末梢編
75巻6号(2023年6月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part1 中枢編
75巻5号(2023年5月発行)
増大特集 神経・精神領域の薬剤ハンドブック
75巻4号(2023年4月発行)
特集 All About Epilepsy
75巻3号(2023年3月発行)
特集 慢性疼痛
75巻2号(2023年2月発行)
特集 多系統萎縮症の新診断基準とこれからの診療
75巻1号(2023年1月発行)
特集 よく出会う不随意運動を知る
74巻12号(2022年12月発行)
特集 映画を観て精神・神経疾患を知る
74巻11号(2022年11月発行)
特集 RFC1遺伝子関連スペクトラム障害
74巻10号(2022年10月発行)
特集 ウイルス性脳炎・脳症2022
74巻9号(2022年9月発行)
特集 動的環境への適応系としての歩行
74巻8号(2022年8月発行)
特集 迷走神経の不思議
74巻7号(2022年7月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識2022
74巻6号(2022年6月発行)
特集 脳神経内科医に求められる移行医療
74巻5号(2022年5月発行)
増大特集 次の一手—神経筋疾患難治例をどのように治療するか
74巻4号(2022年4月発行)
特集 脳科学リテラシーを高めるために
74巻3号(2022年3月発行)
特集 中枢性自律神経障害update
74巻2号(2022年2月発行)
特集 温度を感じる脳と身体の科学
74巻1号(2022年1月発行)
特集 脳神経内科医のキャリアパスとリーダーシップ
73巻12号(2021年12月発行)
特集 芸術家と神経学
73巻11号(2021年11月発行)
特集 「目」の神経学
73巻10号(2021年10月発行)
特集 中枢神経・末梢神経の悪性リンパ腫
73巻9号(2021年9月発行)
特集 脳卒中治療に必要な基礎知識
73巻8号(2021年8月発行)
特集 脳腸相関—脳-身体の双方向性制御
73巻7号(2021年7月発行)
特集 グリアと神経—相補的な制御系として
73巻6号(2021年6月発行)
特集 Lower Spine Neurology
73巻5号(2021年5月発行)
増大特集 中枢神経の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
73巻4号(2021年4月発行)
特集 片頭痛・群発頭痛治療の新たな夜明け
73巻3号(2021年3月発行)
特集 マルチリンガルブレイン
73巻2号(2021年2月発行)
特集 筋炎と壊死性筋症
73巻1号(2021年1月発行)
特集 Neuro-Oncology
72巻12号(2020年12月発行)
特集 超高齢期の精神神経疾患を診る
72巻11号(2020年11月発行)
増大特集 脳の発振現象—基礎から臨床へ
72巻10号(2020年10月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識
72巻9号(2020年9月発行)
特集 皮質性小脳萎縮症へのアプローチ
72巻8号(2020年8月発行)
特集 サルコイドーシス
72巻7号(2020年7月発行)
増大特集 神経倫理ハンドブック
72巻6号(2020年6月発行)
特集 前頭側頭葉変性症の今日的理解
72巻5号(2020年5月発行)
特集 多発性硬化症の現在と未来
72巻4号(2020年4月発行)
増大特集 神経疾患の診断における落とし穴—誤診を避けるために
72巻3号(2020年3月発行)
特集 でこぼこの脳の中でおしくらまんじゅうする脳機能
72巻2号(2020年2月発行)
特集 αシヌクレイノパチーの新たな展開
72巻1号(2020年1月発行)
特集 神経難病をクスリで治す—薬物開発の現況と近未来への展望
71巻12号(2019年12月発行)
特集 小脳と大脳—Masao Itoのレガシー
71巻11号(2019年11月発行)
増大特集 ALS2019
71巻10号(2019年10月発行)
特集 認知症と遺伝
71巻9号(2019年9月発行)
特集 神経疾患のドラッグ・リポジショニング—新時代へ
71巻8号(2019年8月発行)
特集 パーキンソン病診療の現在地—200年の変遷と新規治療
71巻7号(2019年7月発行)
増大特集 人工知能と神経科学
71巻6号(2019年6月発行)
特集 補体標的治療の現状と展望
71巻5号(2019年5月発行)
特集 NPSLE
71巻4号(2019年4月発行)
増大特集 神経学のための皮膚アトラス
71巻3号(2019年3月発行)
特集 Spine Neurology
71巻2号(2019年2月発行)
特集 “スポーツ”を生み出す脳
71巻1号(2019年1月発行)
特集 人工知能の医療応用Update
70巻12号(2018年12月発行)
特集 主訴に沿う—俯瞰し収束する画像診断の目
70巻11号(2018年11月発行)
増大特集 脳科学で解き明かす精神神経症候
70巻10号(2018年10月発行)
特集 「左脳と右脳」の現在
70巻9号(2018年9月発行)
特集 脳神経内科診療に役立つ精神科の知識
70巻8号(2018年8月発行)
特集 レヴィ小体型認知症の新知見
70巻7号(2018年7月発行)
増大特集 記憶と忘却に関わる脳のしくみ—分子機構から健忘の症候まで
70巻6号(2018年6月発行)
特集 芸術を生み出す脳
70巻5号(2018年5月発行)
特集 非アルツハイマー型認知症の病理学
70巻4号(2018年4月発行)
増大特集 Antibody Update 2018
70巻3号(2018年3月発行)
特集 『認知症疾患診療ガイドライン2017』を読み解く
70巻2号(2018年2月発行)
特集 知っておきたい神経感染症
70巻1号(2018年1月発行)
特集 筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群の今
69巻12号(2017年12月発行)
特集 運動異常症をみる—Web動画付録つき
69巻11号(2017年11月発行)
増大特集 こころの時間学の未来
69巻10号(2017年10月発行)
特集 成人てんかん—知っておきたい6つのトピック
69巻9号(2017年9月発行)
特集 ミクログリアと精神・神経疾患
69巻8号(2017年8月発行)
特集 遺伝性脊髄小脳失調症の病態と治療展望
69巻7号(2017年7月発行)
増大特集 あしたのアルツハイマー病治療
69巻6号(2017年6月発行)
特集 局在病変の神経心理学
69巻5号(2017年5月発行)
特集 Voxel-Based Morphometry—体積からわかること
69巻4号(2017年4月発行)
増大特集 ブロードマン領野の現在地
69巻3号(2017年3月発行)
特集 磁気刺激の新たな展開
69巻2号(2017年2月発行)
特集 Stroke-Like Diseases—鑑別時に注意を要する5病態
69巻1号(2017年1月発行)
特集 近年注目されている白質脳症
68巻12号(2016年12月発行)
特集 炎症性神経・筋疾患の新たな展開
68巻11号(2016年11月発行)
増大特集 連合野ハンドブック
68巻10号(2016年10月発行)
特集 アディクション—行動の嗜癖
68巻9号(2016年9月発行)
特集 自己免疫性脳炎・脳症
68巻8号(2016年8月発行)
特集 こころと汗
68巻7号(2016年7月発行)
増大特集 認知症の危険因子と防御因子
68巻6号(2016年6月発行)
特集 脳とフローラ
68巻5号(2016年5月発行)
特集 手の症候学—生理学・解剖学からみた新知見
68巻4号(2016年4月発行)
増大特集 治せる認知症
68巻3号(2016年3月発行)
特集 末梢神経の血管炎
68巻2号(2016年2月発行)
特集 筋疾患の認知機能障害
68巻1号(2016年1月発行)
特集 シャルコー・マリー・トゥース病
67巻12号(2015年12月発行)
特集 視床と高次脳機能
67巻11号(2015年11月発行)
増大特集 ギラン・バレー症候群のすべて—100年の軌跡
67巻10号(2015年10月発行)
特集 非・日常生活の脳科学
67巻9号(2015年9月発行)
特集 酵素補充療法
67巻8号(2015年8月発行)
特集 神経難病の終末期医療
67巻7号(2015年7月発行)
増大特集 神経疾患と感染症update
67巻6号(2015年6月発行)
特集 脳と「質感」
67巻5号(2015年5月発行)
特集 NCSE(非痙攣性てんかん重積状態)
67巻4号(2015年4月発行)
増大特集 大脳皮質vs.大脳白質
67巻3号(2015年3月発行)
特集 中枢神経の血管炎
67巻2号(2015年2月発行)
特集 「食べる」を考える
67巻1号(2015年1月発行)
特集 ニューロトキシコロジー
66巻12号(2014年12月発行)
特集 Orthopaedic Neurology—神経内科と整形外科の狭間で
66巻11号(2014年11月発行)
増大特集 神経症候学は神経学の“魂”である
66巻10号(2014年10月発行)
特集 分子を撃つ 神経疾患治療の新しい水平線
66巻9号(2014年9月発行)
特集 痙縮の臨床神経学
66巻8号(2014年8月発行)
特集 神経系の悪性リンパ腫update
66巻7号(2014年7月発行)
増大特集 アミロイド関連神経疾患のすべて―封入体筋炎からアルツハイマー病まで
66巻6号(2014年6月発行)
特集 ミラーニューロン
66巻5号(2014年5月発行)
特集 アセチルコリンと神経疾患―100年目の現在地
66巻4号(2014年4月発行)
増大特集 タッチ・ビジョン・アクション
66巻3号(2014年3月発行)
特集 神経筋疾患の超音波診断
66巻2号(2014年2月発行)
特集 糖尿病の神経学revisited
66巻1号(2014年1月発行)
特集 日常生活の脳科学
65巻12号(2013年12月発行)
特集 プロテイノパチーの神経病理学
65巻11号(2013年11月発行)
増大特集 Close Encounters―臨床神経学と臨床免疫学の遭遇と未来
65巻10号(2013年10月発行)
特集 神経系の発達メカニズム―最近の話題
65巻9号(2013年9月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である―現状と展望
65巻8号(2013年8月発行)
特集 こころの時間学―現在・過去・未来の起源を求めて
65巻7号(2013年7月発行)
増大特集 あしたの脳梗塞
65巻6号(2013年6月発行)
特集 見せる・仕分ける―脳機能解析の新手法
65巻5号(2013年5月発行)
特集 てんかん―新しいパースペクティブ
65巻4号(2013年4月発行)
増大特集 Antibody Update
65巻3号(2013年3月発行)
特集 次世代シーケンサーによる神経変性疾患の解析と展望
65巻2号(2013年2月発行)
特集 血液脳関門研究の進歩
65巻1号(2013年1月発行)
特集 Corticobasal Syndrome
64巻12号(2012年12月発行)
特集 The Border-Land of Dementia
64巻11号(2012年11月発行)
増大特集 痛みの神経学―末梢神経から脳まで
64巻10号(2012年10月発行)
特集 辺縁系をめぐって
64巻9号(2012年9月発行)
特集 高次脳機能イメージングの脳科学への新展開
64巻8号(2012年8月発行)
特集 線条体の基礎と臨床
64巻7号(2012年7月発行)
増大特集 顔認知の脳内機構
64巻6号(2012年6月発行)
特集 睡眠と覚醒の脳内機構
64巻5号(2012年5月発行)
特集 神経疾患のバイオマーカー
64巻4号(2012年4月発行)
増大特集 パーキンソン病の新しい側面
64巻3号(2012年3月発行)
特集 アカデミアから新規治療の実現へ―トランスレーショナルリサーチの現状
64巻2号(2012年2月発行)
特集 生物学的精神医学の進歩
64巻1号(2012年1月発行)
特集 iPS細胞と神経疾患
63巻12号(2011年12月発行)
特集 神経心理学と画像解析の融合
63巻11号(2011年11月発行)
増大特集 筋疾患update
63巻10号(2011年10月発行)
特集 緩徐進行性高次脳機能障害の病態
63巻9号(2011年9月発行)
特集 脳卒中の最新画像診断
63巻8号(2011年8月発行)
特集 日本人の発見した神経症候
63巻7号(2011年7月発行)
増大特集 神経筋接合部―基礎から臨床まで
63巻6号(2011年6月発行)
特集 ニューロパチー
63巻5号(2011年5月発行)
特集 神経系と血管内リンパ腫
63巻4号(2011年4月発行)
増大特集 てんかんの新しい治療
63巻3号(2011年3月発行)
特集 サイバーナイフ治療
63巻2号(2011年2月発行)
特集 続・日本人の発見した神経疾患
63巻1号(2011年1月発行)
特集 血管腫
62巻12号(2010年12月発行)
特集 頸部頸動脈狭窄症の診断と治療
62巻11号(2010年11月発行)
増大特集 歩行とその異常
62巻10号(2010年10月発行)
特集 ブレインバンク
62巻9号(2010年9月発行)
特集 視神経脊髄炎(NMO)update
62巻8号(2010年8月発行)
特集 辺縁系脳炎
62巻7号(2010年7月発行)
増大特集 アルツハイマー病―研究と診療の進歩
62巻6号(2010年6月発行)
特集 改正臓器移植法の問題点とその対応
62巻5号(2010年5月発行)
特集 神経画像のピットフォール―見落としと読み過ぎ
62巻4号(2010年4月発行)
特集 傍腫瘍性神経筋疾患update
62巻3号(2010年3月発行)
特集 神経回路解析法の最近の進歩
62巻2号(2010年2月発行)
特集 ニューロリハビリテーションの最前線
62巻1号(2010年1月発行)
特集 神経救急
61巻12号(2009年12月発行)
特集 Somatotopy再考
61巻11号(2009年11月発行)
特集 前頭側頭葉変性症
61巻10号(2009年10月発行)
特集 片頭痛の予防療法
61巻9号(2009年9月発行)
特集 脳血管障害治療の進歩
61巻8号(2009年8月発行)
特集 神経・筋疾患の分子標的治療
61巻7号(2009年7月発行)
特集 脳腫瘍研究の最前線―遺伝子解析から治療まで
61巻6号(2009年6月発行)
特集 脊椎・脊髄外科の最近の進歩
61巻5号(2009年5月発行)
特集 Restless legs syndrome
61巻4号(2009年4月発行)
特集 大脳基底核―分子基盤から臨床まで
61巻3号(2009年3月発行)
特集 Microneurography(微小神経電図法)の臨床応用
61巻2号(2009年2月発行)
特集 神経系の再興感染症と輸入感染症
61巻1号(2009年1月発行)
特集 脳神経倫理
60巻12号(2008年12月発行)
特集 痙縮
60巻11号(2008年11月発行)
特集 脳卒中と遺伝子
60巻10号(2008年10月発行)
特集 若年者の脳卒中
60巻9号(2008年9月発行)
特集 知・情・意の神経学
60巻8号(2008年8月発行)
特集 脳硬膜動静脈瘻
60巻7号(2008年7月発行)
増大特集 学習と記憶――基礎と臨床
60巻6号(2008年6月発行)
特集 Crow-深瀬症候群(POEMS症候群)
60巻5号(2008年5月発行)
特集 「痛み」の研究と治療の最前線
60巻4号(2008年4月発行)
増大特集 神経系の発生とその異常
60巻3号(2008年3月発行)
特集 特発性正常圧水頭症(iNPH)―最近の話題
60巻2号(2008年2月発行)
特集 がん治療と神経障害
60巻1号(2008年1月発行)
特集 日本人の発見した神経疾患
59巻12号(2007年12月発行)
特集 損傷神経の再生―温存的治療法の開発
59巻11号(2007年11月発行)
特集 手根管症候群をめぐって
59巻10号(2007年10月発行)
増大特集 ALS―研究と診療の進歩
59巻9号(2007年9月発行)
特集 パーキンソン病の認知機能障害
59巻8号(2007年8月発行)
特集 パーキンソン病の分子遺伝学―最近の知見
59巻7号(2007年7月発行)
増大特集 情報伝達処理におけるグリアの機能と異常
59巻6号(2007年6月発行)
特集 職業性神経障害の新しい展開
59巻5号(2007年5月発行)
特集 脳画像最前線
59巻4号(2007年4月発行)
増大特集 最近注目される脳神経疾患治療の研究
59巻3号(2007年3月発行)
特集 分子イメージング
59巻2号(2007年2月発行)
特集 進行性多巣性白質脳症の新しい展開―PMLが治る時代へ向けて
59巻1号(2007年1月発行)
特集 高次視覚研究の最近の進歩
