前号「Part1 中枢編」に続いて“自己抗体の今”を取り上げる。鼎談ではアクアポリン4抗体やガングリオシド抗体発見の経緯から,自己抗体測定法の進歩,測定結果を解釈するうえでの注意点まで,示唆に富む議論が交わされた。各論文では,それぞれの疾患で現在明らかになっている自己抗体や臨床的特徴,抗体の病原性,治療法などを網羅的に解説している。「中枢編」と合わせて読むことで,自己抗体に関する知見をいっそう確かなものとし,患者さんへの治療に還元してほしい。
雑誌目次
BRAIN and NERVE-神経研究の進歩75巻7号
2023年07月発行
雑誌目次
特集 Antibody Update 2023 Part2 末梢編
【鼎談】Antibody Update 10年—自己抗体は脳神経内科の臨床をどのように変えたか
著者: 藤原一男 , 海田賢一 , 神田隆
ページ範囲:P.797 - P.805
神田 自己免疫性炎症性神経疾患と自己抗体の関係についての研究は,1970年代後半から行われてきました。1982年にはコロンビア大学のNorman Latov1)がミエリン関連糖蛋白(myelin-associated glycoprotein:MAG)抗体を発見しています。私は1981年の卒業なので,疾患に直接的に結びつくMAG抗体の発見は日本でも大きな話題になっていたことを記憶しています。ただ,当時の脳神経内科診療において自己抗体はそれほど大きなウェイトを占めてはいなかったように思います。ところが最近では,中枢神経疾患,神経・筋疾患を問わず,自己免疫性炎症性神経疾患における自己抗体の重要性は不動のものになっています。
本誌では10年前に「Antibody Update」(2013年4月号)という特集を組み,その5年後に「Antibody Update 2018」(2018年4月号),そしてこの度第3弾を出すことになりました。本日は藤原先生,海田先生をお迎えして,自己抗体の発展が脳神経内科の臨床をどのように変えたのか,自己抗体の測定方法を知ることの意義,自己抗体をどのように臨床に生かすのかなどについて,お話しいただくこととしました。
ギラン・バレー症候群—日常診療での自己抗体の意義
著者: 古賀道明
ページ範囲:P.807 - P.812
自己抗体の測定は,ギラン・バレー症候群(Guillain-Barré Syndrome:GBS)やフィッシャー症候群の診療に欠かせない検査となった。しかし,実際に測定される抗体は種類が非常に多く,感度や特異度は必ずしも十分ではない。さらに検出される抗体の意義は抗体ごとに異なっている。特に脱髄型GBSでは診断マーカーとして確立した自己抗体は未同定であり,検査の限界を理解していないと,検査結果が診断をミスリードしかねないことに留意すべきである。
慢性自己免疫性脱髄性ニューロパチー
著者: 緒方英紀
ページ範囲:P.813 - P.819
過去10年でランヴィエ絞輪部,傍絞輪部に局在する膜蛋白に対する自己抗体の存在が明らかとなり,自己免疫性ノドパチーの概念が提唱された。免疫グロブリンM(immunoglobulin M:IgM)単クローン血症に伴うミエリン関連糖蛋白質抗体は難治性脱髄性ニューロパチーを引き起こす。ジシアロシル基を有するガングリオシドに対するIgM自己抗体,IgM GM1抗体,IgG LM1抗体も各種慢性自己免疫性脱髄性ニューロパチーの診断・治療方針決定に役立つ。
自己免疫性自律神経節障害—「10の課題」を解くために
著者: 中根俊成
ページ範囲:P.821 - P.829
自己免疫性自律神経節障害(autoimmune autonomic ganglionopathy:AAG)患者血清からはニコチン性自律神経節アセチルコリン受容体(ganglionic acetylcholine receptor:gAChR)に対する自己抗体が検出される。gAChR抗体は病原性を有し,自律神経節におけるシナプス伝達を障害することから自律神経障害を引き起こすことが知られている。近年,AAGの臨床像に関する報告のほか,1)新しいgAChR抗体測定法,2)免疫治療の有用性,3)新規動物モデル,4)新型コロナウイルス感染症とそのワクチン接種と自律神経障害の関連,5)がん治療における免疫チェックポイント阻害薬の免疫関連副作用として自律神経障害,などが注目されている。筆者らは以前にAAGの病態や実際の診療上の問題を理解していくための臨床と研究における「10の課題」を設定した。本論では最近5年間の研究の動向を織り込みつつ,「10の課題」の1つひとつに関する研究の現況を解説する。
重症筋無力症と自己抗体
著者: 鵜沢顕之
ページ範囲:P.831 - P.835
重症筋無力症は自己抗体が病態の中心にある代表的な自己抗体介在性免疫疾患である。重症筋無力症の病原性自己抗体としてAChR抗体,MuSK抗体,Lrp4抗体が知られているが,Lrp抗体に関しては疾患特異性などの観点から病原性自己抗体として十分確立しているとは言えない。これら自己抗体の神経筋接合部における標的,抗体陽性の意義,臨床像と治療,予後の差異などに関して概説する。
ランバート・イートン筋無力症候群—病原性自己抗体の臨床的意義
著者: 本村政勝 , 入岡隆
ページ範囲:P.837 - P.845
ランバート・イートン筋無力症候群(Lambert-Eaton myasthenic syndrome:LEMS)の約90%はP/Q型電位依存性カルシウムチャネル(P/Q-VGCCs)抗体が陽性で,小細胞肺がんなどのがんを合併する傍腫瘍性と非傍腫瘍性に分類される。本邦の診断基準では,筋力低下に加えて電気生理の異常が必須である。一方,自己抗体は病因診断に有用であり,治療方針を左右する。われわれは,重症筋無力症/ランバート・イートン筋無力症候群診療ガイドライン2022に基づいて網羅的にレビューし,さらに,P/Q-VGCCs抗体が陽性であったPCD without LEMSの1症例を提示し,自己抗体の臨床的意義を検討した。
—筋炎関連自己抗体(1)—皮膚筋炎
著者: 藤本学
ページ範囲:P.847 - P.854
皮膚筋炎は多様な疾患であり,その診療にはより均質なサブセットに分けて考えることが必要である。自己抗体は臨床所見と強く相関するため,このようなサブセットに分類するうえで有用なツールとなる。皮膚筋炎では,これまでに5つの自己抗体が特異的自己抗体としてその臨床的意義が確立している。その他にも,さまざまな自己抗体が報告されており,病因や病態を考えるうえでも興味深いものがある。
—筋炎関連自己抗体(2)—免疫介在性壊死性ミオパチー
著者: 冨滿弘之
ページ範囲:P.855 - P.861
免疫介在性壊死性ミオパチー(immune-mediated necrotizing myopathy:IMNM)は筋病理学的な根拠から2004年に多発筋炎から独立した疾患群である。典型例では亜急性に進行する近位筋優位の筋力低下と,筋線維壊死を反映した血清クレアチンキナーゼの著明な上昇を認める。さまざまな病態が原因と考えられるが,SRP抗体あるいはHMGCR抗体を伴う症例が多く,これらの抗体が病態に関与していることが証明されてきている。筋炎同様に免疫治療を行うものの,ステロイド治療抵抗性の症例も多く,集約的な治療を必要とすることが多い。
—筋炎関連自己抗体(3)—抗合成酵素症候群関連筋炎
著者: 漆葉章典
ページ範囲:P.863 - P.868
抗合成酵素症候群関連筋炎は自己免疫性筋炎の主要病型の1つで,抗アミノアシルtRNA合成酵素抗体の存在により定義される。骨格筋に加えて肺,関節,皮膚などが障害される。抗体のサブタイプにより症状の程度に違いがあり,抗OJ抗体では筋症状が重篤化しやすい。筋病理では筋束辺縁部壊死など筋束辺縁部から筋周鞘にかけての変化が目立つ。同部では形質細胞に有利な微小環境が生じており,病態理解のうえで注目される。
—筋炎関連自己抗体(4)—封入体筋炎
著者: 山下賢
ページ範囲:P.869 - P.874
封入体筋炎は,嚥下障害や手指・手関節屈筋群,大腿四頭筋の筋力低下と筋萎縮が緩徐に進行する難治性筋疾患である。診断には侵襲を伴う筋生検が不可欠である。約半数の患者血中に細胞質5'-ヌクレオチダーゼ1A抗体が検出されるが,本抗体の診断的意義については肯定的な意見がある一方,有用性には限界があるとの見解もある。病因的意義を支持する能動免疫の結果が示されているが,今後より詳細な検証が必要である。
総説
組織学的アプローチからのALS診断バイオマーカー—筋病理と筋内神経束へのリン酸化TDP-43発現
著者: 倉重毅志
ページ範囲:P.877 - P.887
TDP-43(transacting response DNA-binding protein of 43kDa)の発見以来,血液や髄液などさまざまなバイオマーカーが報告されたが疾患特異性が不十分である。剖検症例・筋生検症例の骨格筋内に含まれる筋内神経束でのリン酸化TDP-43発現が筋萎縮性側索硬化症(amyotrophic lateral sclerosis:ALS)に特異的組織所見であることを報告した。現在のALS診断基準では診断できない初期から確認可能で,ALSの生検病理診断に有用な末梢組織病理所見である可能性を示している。ALSの診断特異的バイオマーカー確立と下位運動ニューロン障害への治療ターゲット解明を目指している。
連載 医師国家試験から語る精神・神経疾患・7
双極性障害を診わける
著者: 澤田恭助
ページ範囲:P.889 - P.892
43歳の男性。自営業。すぐに機嫌を損ねて怒鳴るようになったため,妻と母親に説得されて来院した。3か月前に父親が急逝してからしばらくの間,元気がなく,家族と話さなくなった。1か月前から店で必要以上にたくさん仕入れをするようになり,従業員に対して大声で怒鳴りつけるようになった。商品陳列の場所を何度も変え,始終移動させているようになった。元来ほとんど飲酒をしなかったが,毎晩飲酒をするようになったという。多弁で,感情の動きが激しく表出され,話題が際限なく広がる。本人は受診について不満であり,精神的なストレスで悲観的な考えに陥っている家族の方に治療を受けさせたいと述べている。これまでに発達上の問題はなかった。血液検査,頭部MRI及び脳波検査に異常を認めない。
この患者にみられる症状はどれか。2つ選べ。
a 感覚失語
b 観念奔逸
c 行為心迫
d 連合弛緩
e 小動物幻視
(第114回C57)
書評
「医療者のスライドデザイン—プレゼンテーションを進化させる,デザインの教科書」—小林 啓【著】 フリーアクセス
著者: 吉橋昭夫
ページ範囲:P.875 - P.875
本書は,プレゼンテーションを効果的に行うためのデザイン手法を誰にでもわかりやすく紹介したものである。プレゼンテーションは受け手と知見を共有し新たな行動を促すものであり,そのためには適切なデザインが必要である。私は「情報デザイン」の分野で長く教育研究に携わってきたが,本書は情報デザインのエッセンスを凝縮してスライドデザインに投入したものであり,伝えたいメッセージや情報をスライドとして具体化するために必要な内容が存分に盛り込まれている。
以下は,各Chapterの概要である。
「慢性痛のサイエンス 第2版—脳からみた痛みの機序と治療戦略」—半場道子【著】 フリーアクセス
著者: 山下敏彦
ページ範囲:P.876 - P.876
本書『慢性痛のサイエンス』は,私にとって,慢性痛を考え,理解する上での「バイブル」的書籍である。このたび,内容がアップデートされ,ボリュームアップした第2版が出版されたことを大変うれしく思う。
近年,慢性痛の発生や持続には,単に組織の損傷や脊髄・末梢神経の障害だけではなく,脳の機能不全が深く関与していることが神経科学的研究により明らかにされているが,臨床家にとってそのメカニズムを理解することは決して容易ではない。しかし,本書では,中脳辺縁ドパミン系(mesolimbic dopamine system)や下行性疼痛抑制系といった複雑な神経メカニズムを,明快な図とともに,読みやすい文章で順序立てて解説されており,読み進めるうちに自然と理解が深まってくる。
お知らせ
「公益財団法人日本脳神経財団2023年度寺岡賞」募集 フリーアクセス
ページ範囲:P.812 - P.812
公益財団法人日本脳神経財団では下記の通り,寺岡賞の募集を行います。財団のHP(https://jbf.or.jp)の「各種助成申請のご案内」で要項をご確認のうえ,申請してください。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.793 - P.793
欧文目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.794 - P.794
バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.898 - P.898
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.899 - P.899
あとがき フリーアクセス
著者: 三村將
ページ範囲:P.900 - P.900
本年6月に慶應義塾大学医学部生理学教室の岡野栄之教授,神経内科の中原仁教授らの研究グループが筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者にロピニロールを投与する医師主導治験であるROPALS試験の安全性と有効性を報告し(Morimoto S, et al. Cell Stem Cell, 2023),関連したプレスリリース記事も発出された(https://www.keio.ac.jp/ja/press-releases/2023/6/2/28-138679/)。本治験の特筆すべきところは,参加患者さんからiPS細胞を作製し,ロピニロールを患者分化細胞に投与することで,薬剤の効果予測を行うことができる点である。さらに,ロピニロールが神経細胞内のコレステロール合成を制御することによって抗ALS作用を発揮していることもわかってきた。今回の研究からはiPS細胞創薬の有用性が示され,有効な治療法に乏しいALSという神経難病への新たな治療選択肢の可能性が開かれた。
さて,本号ではALSの診断バイオマーカーとしての組織学的アプローチに関する優れた総説が掲載されている。また,特集は「Antibody Update 2023 Part2 末梢編」である。疾患特異的自己抗体の発見は神経系疾患の臨床を大きく変えてきており,本誌で最初にこのテーマを取り上げた2013年から,5年後の2018年,そして今回の2023年と,5年ごとに次々と新知見が登場してきて,日進月歩の感がある。これらの免疫学的発見やバイオマーカー,神経画像の進歩はさまざまなトランスレーショナル研究やリバーストランスレーショナル研究を推し進め,治験の仕組み自体にも大きな変革をもたらしてきている。
基本情報
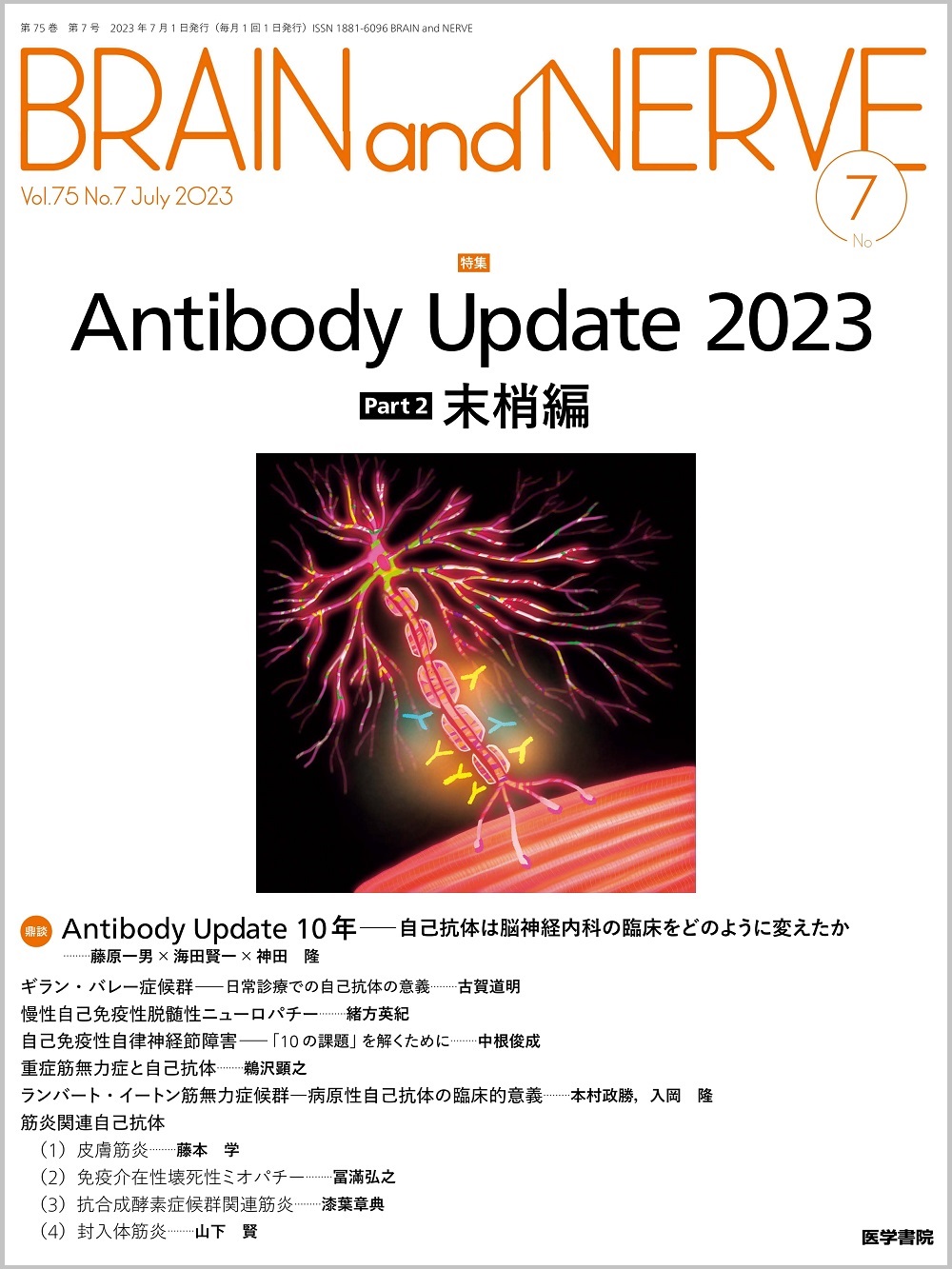
バックナンバー
76巻12号(2024年12月発行)
特集 芸術家と神経学Ⅱ
76巻11号(2024年11月発行)
特集 ALS 2024
76巻10号(2024年10月発行)
特集 どうして効くんだろう
76巻9号(2024年9月発行)
特集 治療可能な認知症としてのアルツハイマー病
76巻8号(2024年8月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である—revisited
76巻7号(2024年7月発行)
特集 ニューロ・バイオイメージング—技術と応用
76巻6号(2024年6月発行)
特集 注意と注意障害
76巻5号(2024年5月発行)
増大特集 末梢神経・筋肉の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
76巻4号(2024年4月発行)
特集 神経病理最前線
76巻3号(2024年3月発行)
特集 きちんと説明ができますか?
76巻2号(2024年2月発行)
特集 特発性正常圧水頭症の現在
76巻1号(2024年1月発行)
特集 新時代の重症筋無力症と関連疾患の診療
75巻12号(2023年12月発行)
特集 アガサ・クリスティーと神経毒
75巻11号(2023年11月発行)
特集 アロスタシス—ホメオスタシスを超えて
75巻10号(2023年10月発行)
特集 メタバースへの招待
75巻9号(2023年9月発行)
特集 妊娠と神経疾患
75巻8号(2023年8月発行)
特集 アルツハイマー病は本当に早期発見できるのか
75巻7号(2023年7月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part2 末梢編
75巻6号(2023年6月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part1 中枢編
75巻5号(2023年5月発行)
増大特集 神経・精神領域の薬剤ハンドブック
75巻4号(2023年4月発行)
特集 All About Epilepsy
75巻3号(2023年3月発行)
特集 慢性疼痛
75巻2号(2023年2月発行)
特集 多系統萎縮症の新診断基準とこれからの診療
75巻1号(2023年1月発行)
特集 よく出会う不随意運動を知る
74巻12号(2022年12月発行)
特集 映画を観て精神・神経疾患を知る
74巻11号(2022年11月発行)
特集 RFC1遺伝子関連スペクトラム障害
74巻10号(2022年10月発行)
特集 ウイルス性脳炎・脳症2022
74巻9号(2022年9月発行)
特集 動的環境への適応系としての歩行
74巻8号(2022年8月発行)
特集 迷走神経の不思議
74巻7号(2022年7月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識2022
74巻6号(2022年6月発行)
特集 脳神経内科医に求められる移行医療
74巻5号(2022年5月発行)
増大特集 次の一手—神経筋疾患難治例をどのように治療するか
74巻4号(2022年4月発行)
特集 脳科学リテラシーを高めるために
74巻3号(2022年3月発行)
特集 中枢性自律神経障害update
74巻2号(2022年2月発行)
特集 温度を感じる脳と身体の科学
74巻1号(2022年1月発行)
特集 脳神経内科医のキャリアパスとリーダーシップ
73巻12号(2021年12月発行)
特集 芸術家と神経学
73巻11号(2021年11月発行)
特集 「目」の神経学
73巻10号(2021年10月発行)
特集 中枢神経・末梢神経の悪性リンパ腫
73巻9号(2021年9月発行)
特集 脳卒中治療に必要な基礎知識
73巻8号(2021年8月発行)
特集 脳腸相関—脳-身体の双方向性制御
73巻7号(2021年7月発行)
特集 グリアと神経—相補的な制御系として
73巻6号(2021年6月発行)
特集 Lower Spine Neurology
73巻5号(2021年5月発行)
増大特集 中枢神経の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
73巻4号(2021年4月発行)
特集 片頭痛・群発頭痛治療の新たな夜明け
73巻3号(2021年3月発行)
特集 マルチリンガルブレイン
73巻2号(2021年2月発行)
特集 筋炎と壊死性筋症
73巻1号(2021年1月発行)
特集 Neuro-Oncology
72巻12号(2020年12月発行)
特集 超高齢期の精神神経疾患を診る
72巻11号(2020年11月発行)
増大特集 脳の発振現象—基礎から臨床へ
72巻10号(2020年10月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識
72巻9号(2020年9月発行)
特集 皮質性小脳萎縮症へのアプローチ
72巻8号(2020年8月発行)
特集 サルコイドーシス
72巻7号(2020年7月発行)
増大特集 神経倫理ハンドブック
72巻6号(2020年6月発行)
特集 前頭側頭葉変性症の今日的理解
72巻5号(2020年5月発行)
特集 多発性硬化症の現在と未来
72巻4号(2020年4月発行)
増大特集 神経疾患の診断における落とし穴—誤診を避けるために
72巻3号(2020年3月発行)
特集 でこぼこの脳の中でおしくらまんじゅうする脳機能
72巻2号(2020年2月発行)
特集 αシヌクレイノパチーの新たな展開
72巻1号(2020年1月発行)
特集 神経難病をクスリで治す—薬物開発の現況と近未来への展望
71巻12号(2019年12月発行)
特集 小脳と大脳—Masao Itoのレガシー
71巻11号(2019年11月発行)
増大特集 ALS2019
71巻10号(2019年10月発行)
特集 認知症と遺伝
71巻9号(2019年9月発行)
特集 神経疾患のドラッグ・リポジショニング—新時代へ
71巻8号(2019年8月発行)
特集 パーキンソン病診療の現在地—200年の変遷と新規治療
71巻7号(2019年7月発行)
増大特集 人工知能と神経科学
71巻6号(2019年6月発行)
特集 補体標的治療の現状と展望
71巻5号(2019年5月発行)
特集 NPSLE
71巻4号(2019年4月発行)
増大特集 神経学のための皮膚アトラス
71巻3号(2019年3月発行)
特集 Spine Neurology
71巻2号(2019年2月発行)
特集 “スポーツ”を生み出す脳
71巻1号(2019年1月発行)
特集 人工知能の医療応用Update
70巻12号(2018年12月発行)
特集 主訴に沿う—俯瞰し収束する画像診断の目
70巻11号(2018年11月発行)
増大特集 脳科学で解き明かす精神神経症候
70巻10号(2018年10月発行)
特集 「左脳と右脳」の現在
70巻9号(2018年9月発行)
特集 脳神経内科診療に役立つ精神科の知識
70巻8号(2018年8月発行)
特集 レヴィ小体型認知症の新知見
70巻7号(2018年7月発行)
増大特集 記憶と忘却に関わる脳のしくみ—分子機構から健忘の症候まで
70巻6号(2018年6月発行)
特集 芸術を生み出す脳
70巻5号(2018年5月発行)
特集 非アルツハイマー型認知症の病理学
70巻4号(2018年4月発行)
増大特集 Antibody Update 2018
70巻3号(2018年3月発行)
特集 『認知症疾患診療ガイドライン2017』を読み解く
70巻2号(2018年2月発行)
特集 知っておきたい神経感染症
70巻1号(2018年1月発行)
特集 筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群の今
69巻12号(2017年12月発行)
特集 運動異常症をみる—Web動画付録つき
69巻11号(2017年11月発行)
増大特集 こころの時間学の未来
69巻10号(2017年10月発行)
特集 成人てんかん—知っておきたい6つのトピック
69巻9号(2017年9月発行)
特集 ミクログリアと精神・神経疾患
69巻8号(2017年8月発行)
特集 遺伝性脊髄小脳失調症の病態と治療展望
69巻7号(2017年7月発行)
増大特集 あしたのアルツハイマー病治療
69巻6号(2017年6月発行)
特集 局在病変の神経心理学
69巻5号(2017年5月発行)
特集 Voxel-Based Morphometry—体積からわかること
69巻4号(2017年4月発行)
増大特集 ブロードマン領野の現在地
69巻3号(2017年3月発行)
特集 磁気刺激の新たな展開
69巻2号(2017年2月発行)
特集 Stroke-Like Diseases—鑑別時に注意を要する5病態
69巻1号(2017年1月発行)
特集 近年注目されている白質脳症
68巻12号(2016年12月発行)
特集 炎症性神経・筋疾患の新たな展開
68巻11号(2016年11月発行)
増大特集 連合野ハンドブック
68巻10号(2016年10月発行)
特集 アディクション—行動の嗜癖
68巻9号(2016年9月発行)
特集 自己免疫性脳炎・脳症
68巻8号(2016年8月発行)
特集 こころと汗
68巻7号(2016年7月発行)
増大特集 認知症の危険因子と防御因子
68巻6号(2016年6月発行)
特集 脳とフローラ
68巻5号(2016年5月発行)
特集 手の症候学—生理学・解剖学からみた新知見
68巻4号(2016年4月発行)
増大特集 治せる認知症
68巻3号(2016年3月発行)
特集 末梢神経の血管炎
68巻2号(2016年2月発行)
特集 筋疾患の認知機能障害
68巻1号(2016年1月発行)
特集 シャルコー・マリー・トゥース病
67巻12号(2015年12月発行)
特集 視床と高次脳機能
67巻11号(2015年11月発行)
増大特集 ギラン・バレー症候群のすべて—100年の軌跡
67巻10号(2015年10月発行)
特集 非・日常生活の脳科学
67巻9号(2015年9月発行)
特集 酵素補充療法
67巻8号(2015年8月発行)
特集 神経難病の終末期医療
67巻7号(2015年7月発行)
増大特集 神経疾患と感染症update
67巻6号(2015年6月発行)
特集 脳と「質感」
67巻5号(2015年5月発行)
特集 NCSE(非痙攣性てんかん重積状態)
67巻4号(2015年4月発行)
増大特集 大脳皮質vs.大脳白質
67巻3号(2015年3月発行)
特集 中枢神経の血管炎
67巻2号(2015年2月発行)
特集 「食べる」を考える
67巻1号(2015年1月発行)
特集 ニューロトキシコロジー
66巻12号(2014年12月発行)
特集 Orthopaedic Neurology—神経内科と整形外科の狭間で
66巻11号(2014年11月発行)
増大特集 神経症候学は神経学の“魂”である
66巻10号(2014年10月発行)
特集 分子を撃つ 神経疾患治療の新しい水平線
66巻9号(2014年9月発行)
特集 痙縮の臨床神経学
66巻8号(2014年8月発行)
特集 神経系の悪性リンパ腫update
66巻7号(2014年7月発行)
増大特集 アミロイド関連神経疾患のすべて―封入体筋炎からアルツハイマー病まで
66巻6号(2014年6月発行)
特集 ミラーニューロン
66巻5号(2014年5月発行)
特集 アセチルコリンと神経疾患―100年目の現在地
66巻4号(2014年4月発行)
増大特集 タッチ・ビジョン・アクション
66巻3号(2014年3月発行)
特集 神経筋疾患の超音波診断
66巻2号(2014年2月発行)
特集 糖尿病の神経学revisited
66巻1号(2014年1月発行)
特集 日常生活の脳科学
65巻12号(2013年12月発行)
特集 プロテイノパチーの神経病理学
65巻11号(2013年11月発行)
増大特集 Close Encounters―臨床神経学と臨床免疫学の遭遇と未来
65巻10号(2013年10月発行)
特集 神経系の発達メカニズム―最近の話題
65巻9号(2013年9月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である―現状と展望
65巻8号(2013年8月発行)
特集 こころの時間学―現在・過去・未来の起源を求めて
65巻7号(2013年7月発行)
増大特集 あしたの脳梗塞
65巻6号(2013年6月発行)
特集 見せる・仕分ける―脳機能解析の新手法
65巻5号(2013年5月発行)
特集 てんかん―新しいパースペクティブ
65巻4号(2013年4月発行)
増大特集 Antibody Update
65巻3号(2013年3月発行)
特集 次世代シーケンサーによる神経変性疾患の解析と展望
65巻2号(2013年2月発行)
特集 血液脳関門研究の進歩
65巻1号(2013年1月発行)
特集 Corticobasal Syndrome
64巻12号(2012年12月発行)
特集 The Border-Land of Dementia
64巻11号(2012年11月発行)
増大特集 痛みの神経学―末梢神経から脳まで
64巻10号(2012年10月発行)
特集 辺縁系をめぐって
64巻9号(2012年9月発行)
特集 高次脳機能イメージングの脳科学への新展開
64巻8号(2012年8月発行)
特集 線条体の基礎と臨床
64巻7号(2012年7月発行)
増大特集 顔認知の脳内機構
64巻6号(2012年6月発行)
特集 睡眠と覚醒の脳内機構
64巻5号(2012年5月発行)
特集 神経疾患のバイオマーカー
64巻4号(2012年4月発行)
増大特集 パーキンソン病の新しい側面
64巻3号(2012年3月発行)
特集 アカデミアから新規治療の実現へ―トランスレーショナルリサーチの現状
64巻2号(2012年2月発行)
特集 生物学的精神医学の進歩
64巻1号(2012年1月発行)
特集 iPS細胞と神経疾患
63巻12号(2011年12月発行)
特集 神経心理学と画像解析の融合
63巻11号(2011年11月発行)
増大特集 筋疾患update
63巻10号(2011年10月発行)
特集 緩徐進行性高次脳機能障害の病態
63巻9号(2011年9月発行)
特集 脳卒中の最新画像診断
63巻8号(2011年8月発行)
特集 日本人の発見した神経症候
63巻7号(2011年7月発行)
増大特集 神経筋接合部―基礎から臨床まで
63巻6号(2011年6月発行)
特集 ニューロパチー
63巻5号(2011年5月発行)
特集 神経系と血管内リンパ腫
63巻4号(2011年4月発行)
増大特集 てんかんの新しい治療
63巻3号(2011年3月発行)
特集 サイバーナイフ治療
63巻2号(2011年2月発行)
特集 続・日本人の発見した神経疾患
63巻1号(2011年1月発行)
特集 血管腫
62巻12号(2010年12月発行)
特集 頸部頸動脈狭窄症の診断と治療
62巻11号(2010年11月発行)
増大特集 歩行とその異常
62巻10号(2010年10月発行)
特集 ブレインバンク
62巻9号(2010年9月発行)
特集 視神経脊髄炎(NMO)update
62巻8号(2010年8月発行)
特集 辺縁系脳炎
62巻7号(2010年7月発行)
増大特集 アルツハイマー病―研究と診療の進歩
62巻6号(2010年6月発行)
特集 改正臓器移植法の問題点とその対応
62巻5号(2010年5月発行)
特集 神経画像のピットフォール―見落としと読み過ぎ
62巻4号(2010年4月発行)
特集 傍腫瘍性神経筋疾患update
62巻3号(2010年3月発行)
特集 神経回路解析法の最近の進歩
62巻2号(2010年2月発行)
特集 ニューロリハビリテーションの最前線
62巻1号(2010年1月発行)
特集 神経救急
61巻12号(2009年12月発行)
特集 Somatotopy再考
61巻11号(2009年11月発行)
特集 前頭側頭葉変性症
61巻10号(2009年10月発行)
特集 片頭痛の予防療法
61巻9号(2009年9月発行)
特集 脳血管障害治療の進歩
61巻8号(2009年8月発行)
特集 神経・筋疾患の分子標的治療
61巻7号(2009年7月発行)
特集 脳腫瘍研究の最前線―遺伝子解析から治療まで
61巻6号(2009年6月発行)
特集 脊椎・脊髄外科の最近の進歩
61巻5号(2009年5月発行)
特集 Restless legs syndrome
61巻4号(2009年4月発行)
特集 大脳基底核―分子基盤から臨床まで
61巻3号(2009年3月発行)
特集 Microneurography(微小神経電図法)の臨床応用
61巻2号(2009年2月発行)
特集 神経系の再興感染症と輸入感染症
61巻1号(2009年1月発行)
特集 脳神経倫理
60巻12号(2008年12月発行)
特集 痙縮
60巻11号(2008年11月発行)
特集 脳卒中と遺伝子
60巻10号(2008年10月発行)
特集 若年者の脳卒中
60巻9号(2008年9月発行)
特集 知・情・意の神経学
60巻8号(2008年8月発行)
特集 脳硬膜動静脈瘻
60巻7号(2008年7月発行)
増大特集 学習と記憶――基礎と臨床
60巻6号(2008年6月発行)
特集 Crow-深瀬症候群(POEMS症候群)
60巻5号(2008年5月発行)
特集 「痛み」の研究と治療の最前線
60巻4号(2008年4月発行)
増大特集 神経系の発生とその異常
60巻3号(2008年3月発行)
特集 特発性正常圧水頭症(iNPH)―最近の話題
60巻2号(2008年2月発行)
特集 がん治療と神経障害
60巻1号(2008年1月発行)
特集 日本人の発見した神経疾患
59巻12号(2007年12月発行)
特集 損傷神経の再生―温存的治療法の開発
59巻11号(2007年11月発行)
特集 手根管症候群をめぐって
59巻10号(2007年10月発行)
増大特集 ALS―研究と診療の進歩
59巻9号(2007年9月発行)
特集 パーキンソン病の認知機能障害
59巻8号(2007年8月発行)
特集 パーキンソン病の分子遺伝学―最近の知見
59巻7号(2007年7月発行)
増大特集 情報伝達処理におけるグリアの機能と異常
59巻6号(2007年6月発行)
特集 職業性神経障害の新しい展開
59巻5号(2007年5月発行)
特集 脳画像最前線
59巻4号(2007年4月発行)
増大特集 最近注目される脳神経疾患治療の研究
59巻3号(2007年3月発行)
特集 分子イメージング
59巻2号(2007年2月発行)
特集 進行性多巣性白質脳症の新しい展開―PMLが治る時代へ向けて
59巻1号(2007年1月発行)
特集 高次視覚研究の最近の進歩
