脳神経内科が扱う疾患は非常に多いが,長年臨床医として経験を積めば,中枢性疾患から末梢性疾患までおおむねを理解し,治療や患者さんへの説明をすることができるようになろう。しかし,インターネットをはじめとする情報があふれる今,さらにAIが回答をしてくれるかもしれない今,医療のプロフェッショナルでなくても,正確な(時に間違った)情報を簡単に手に入れることができるようになった。ただし,情報を手に入れても,きちんと理解できることは難しい。そのときこそ医師の役割は大きい。とはいえ,神経疾患のなかでもやや周辺とも言える疾患や病態に触れたとき,自信を持って治療し患者さんに説明できるだろうか。本特集では,脳神経内科の専門をやや外れるものの,患者さんからよく聞かれる疾患や合併症にテーマを絞り,その病態・治療の知識を確実なものとすることを目指したい。
雑誌目次
BRAIN and NERVE-神経研究の進歩76巻3号
2024年03月発行
雑誌目次
特集 きちんと説明ができますか?
ホルモン異常と神経疾患
著者: 木塚祐太 , 伊澤良兼
ページ範囲:P.213 - P.220
内分泌機能異常は神経系に大きな影響を及ぼし,頭痛,筋力低下,不随意運動,意識障害など多様で非特異的な神経症状を合併し得る。その非特異性ゆえに神経症状の背景にある内分泌異常に気がつかず,診断に苦慮する可能性がある。ホルモン補充療法など適切な治療をすみやかに行うことにより,全身状態および神経症状の改善が期待されることから,神経症状から内分泌疾患を鑑別に挙げ,見逃さないようにすることが肝要である。
血液疾患と神経疾患
著者: 大森直樹 , 長井篤
ページ範囲:P.221 - P.229
多くの血液疾患は経過中に神経症状を合併し得る。脳卒中やニューロパチーの背景に血液疾患が関与している例もあり,神経内科医は各種血液疾患に対する知識を携えておくことが望ましい。また近年では免疫チェックポイント阻害薬,キメラ抗原受容体-T細胞療法などの新規抗がん治療に伴う神経副作用の報告が増えており,今後も血液・神経領域の関わりがより密接になっていくと考えられる。
腎疾患に伴う神経合併症
著者: 秋山久尚
ページ範囲:P.231 - P.238
腎臓は,血液を濾過することで老廃物や余分な塩分を尿として体外へ排出する一方,体に必要なものを再吸収し,体内に留める働きをしている。このため腎臓の機能が悪化すると尿が出なくなり,電解質,酸塩基の恒常性も維持できなくなる。その結果,老廃物などが体に蓄積し尿毒症となり透析療法や腎移植などが必要となる。本論では腎疾患およびその治療に伴い出現する神経合併症について概説する。
神経筋疾患における呼吸不全の病態
著者: 井上貴美子
ページ範囲:P.239 - P.247
Krohnによる最新のレビューを基に,呼吸中枢とその調節機構を概説した。呼吸リズムの形成には延髄と橋の呼吸中枢が働くが,呼吸の維持と調節には末梢の化学受容器や迷走神経および中枢性化学受容器を介した複雑なネットワークが関わっている。呼吸ネットワークの解剖に基づき神経筋疾患の呼吸障害の病態を考察し,評価と対処法について述べる。
循環器疾患と神経疾患—心疾患・大動脈疾患に由来する脳梗塞
著者: 岩本創哉 , 古賀政利
ページ範囲:P.249 - P.259
脳梗塞は神経疾患の中でも極めてcommonな国民病である。脳梗塞の原因となる病態は多岐にわたり,正しく鑑別することは容易ではない。特に循環器疾患と称される心疾患や大動脈疾患の一部は脳梗塞と密接な関連を持つが,疑って検査をしなければ気づけない病態も多く,見逃されやすいものと考える。本論では,脳梗塞を併発し得る循環器疾患を挙げ,病態,検査,治療に関してエビデンスを交えながら概説する。
排尿障害と神経疾患—神経因性膀胱の見方
著者: 榊原隆次 , 内山智之 , 山本達也 , 神田武政 , 服部孝道
ページ範囲:P.261 - P.271
排尿障害と神経疾患について述べた。脳病変は過活動膀胱を,末梢神経・腰部の病変は残尿を,脊髄の病変は過活動膀胱と残尿を同時にきたす。多系統萎縮症は,脊髄の病変とそっくりの病状を呈すると言える。逆に,原因不明の神経因性膀胱患者をみた場合,そのパターンから,脳,末梢神経,脊髄/多系統萎縮症を疑い,精査を進めるとよいと思われる。高齢者で重要なものとして,夜間多尿がある。患者の生活の質を向上させるために,脳神経内科医師と泌尿器科医師の,さらなるコラボレーションが望まれる。
総説
学習と神経活動—局在を超えて
著者: 櫻井芳雄
ページ範囲:P.273 - P.281
学習には2種類あるが,単純な反射を変える古典的条件づけの神経回路は,複雑な随意反応を変えるオペラント条件づけには適用できない。オペラント条件づけによる学習が進行する際,脳の広範な部位で,神経細胞の発火頻度や同期発火が多様に変化することがわかっている。また多くの部位の神経細胞の活動を,学習により自ら変化させることも可能である。複雑な随意反応を変える学習は,極めて広範な神経活動の動的変化かもしれない。
症例報告
著明な高クレアチンキナーゼ(CK)血症と無言症を呈した抗N-メチル-D-アスパラギン酸受容体抗体脳炎(抗NMDAR抗体脳炎)の1例
著者: 田島和江 , 福武敏夫
ページ範囲:P.283 - P.287
抗N-メチル-D-アスパラギン酸受容体(抗NMDAR)抗体脳炎では痙攣や不随意運動が見られ,免疫療法以外に抗てんかん薬や抗精神病薬を要することがある。本症例は抗精神病薬の使用で,悪性症候群や横紋筋融解をきたし,ショック状態や著明な高クレアチンキナーゼ血症が生じた。リツキシマブ投与を含めた免疫療法を行い不随意運動期を脱したが,約7カ月後に独歩で退院した後も無言症は長期に後遺した。この脳炎に無言症が出現することはあるが,一時的である。本例で遷延したのは蘇生時に生じた小脳梗塞が関与しているかもしれないが,原因は明らかでない。
視覚性運動失調を呈し,微小な硬膜下膿瘍と軟膜炎の局在診断につながった細菌性髄膜炎の1例
著者: 邉見光 , 森友紀子 , 黒田岳志 , 柿沼佑樹 , 石代優美香 , 加藤悠太 , 久保田怜美 , 河村満 , 村上秀友
ページ範囲:P.289 - P.294
細菌性髄膜炎の経過中に左周辺視野で生じた両手の視覚性運動失調を認めたことから,神経症候学的な局在診断を行い,右頭頂葉の微小な硬膜下膿瘍と軟膜炎の病巣を早期に造影MRIで同定し,抗菌薬による保存的治療によって良好な転帰が得られた69歳の男性例を経験した。細菌性髄膜炎の経過中に原因不明の高次脳機能障害を認めた際にはその局在診断が微小な硬膜下膿瘍の同定に有用である。
Case Report
Adult-onset COVID-19-associated Fulminant Acute Encephalopathy with Elevated Cerebrospinal Fluid Interleukin-8: A Case Report
著者: , , ,
ページ範囲:P.295 - P.300
Abstract: A 26-year-old woman receiving immunosuppressive therapy for polymyositis was infected with COVID-19 (an omicron mutant strain) and presented with fever. On the second day after the onset, she was admitted to our hospital and developed status epilepticus. Brain magnetic resonance imaging on admission revealed abnormal symmetric hyperintensities in the bilateral putamen and around the dorsal horns of the lateral ventricle. Three days after admission, brain computed tomography revealed marked cerebral edema and herniation. The cerebrospinal fluid (CSF) cell count was normal, and the reverse transcription polymerase chain reaction for severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 was negative. Interleukin (IL)-2, 6, and 10 levels were within the normal range in both serum and CSF, whereas IL-8 levels in the CSF were markedly higher compared to serum levels. She had fulminant acute encephalopathy, suspected to be in the early stages of acute necrotizing encephalopathy (ANE). Steroid pulse therapy and intravenous infusions of remdesivir were ineffective, and the patient died of sepsis on the 26th day after admission. We demonstrated that ANE may occur even in patients infected with Omicron strains and speculated that the pathogenesis in this case might be associated with intrathecal IL-8 production by microglial activation.
連載 スーパー臨床神経病理カンファレンス・2
転倒ののち,歩行困難となり意識障害が出現した85歳女性例
著者: 足立正 , 鈴木有紀 , 田尻佑喜
ページ範囲:P.301 - P.308
〔現病歴〕既往歴に特記事項なし。もともとADL自立し,認知機能も問題なく過ごしていた。X年Y月Z日自宅で転倒しコルセットを付けて過ごしていた。当初は歩行可能であったが,徐々に起立困難となった。Z+12日整形外科病院を受診し,Th11圧迫骨折の診断のもと入院となった。Z+16日手術目的に当院へ転院。転院後,意識障害が出現したため当科へコンサルトされた。
体温35.9℃,血圧111/39mmHg,脈拍127回/分,整,SpO2 95%(室内気),胸部にラ音を聴取せず。神経学的にはJapan Coma Scale 10の意識障害,腱反射は両下肢で消失し,両下肢は近位から弛緩性麻痺と感覚鈍麻を認め,両側バビンスキー徴候を認めた。頭部単純MRIでは,拡散強調画像にて右前頭葉,左小脳に急性期脳梗塞を認めた(Fig. 1)。胸部単純CTにて,両側肺野全体に多発する粒状陰影を認めた(Fig. 2)。全脊椎単純MRIでは,Th11圧迫骨折以外,下肢麻痺をきたす髄内病変は認めなかった。
原著・過去の論文から学ぶ・1【新連載】
進行性核上性麻痺に関する2つの論文とJohn Steele先生の思い出
著者: 下畑享良
ページ範囲:P.309 - P.312
原著との出会い
Steele JC, Richardon JC, Olszewski J: Progressive supranuclear palsy: a heterogenous degeneration involving the brain stem, basal ganglia and cerebellum with vertical gaze and pseudobulbar palsy, nuchal dystonia and dementia. Arch Neurol 10: 333-359, 1964
研修医であったころ,とても印象に残った疾患があった。少し重心が後方にずれると,無抵抗に倒れる進行性核上性麻痺(progressive supranuclear palsy:PSP)である。指導医より「原著をぜひ読むように」との助言をいただいた。図書室に赴き,製本された雑誌の原著1)のページを捲ると,手垢のせいかその論文の部分が変色し,剝がれかけた箇所をテープで丁寧に留めてあることに気がついた(Fig. 1)。その論文が,多くの先輩方によって繰り返し読まれてきたことがすぐにわかった。この論文を読み,先輩方から引き継ぐべき神経学の歴史を実感するとともに,重厚な内容に圧倒され,「原著」に立ち戻ることの大切さを初めて理解した。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.209 - P.209
欧文目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.210 - P.210
バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.318 - P.318
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.319 - P.319
あとがき フリーアクセス
著者: 髙尾昌樹
ページ範囲:P.320 - P.320
今月も『BRAIN and NERVE』をお読みいただいている皆様へ,編集委員の一人として御礼申し上げます。お若い先生の中は,本誌が長い歴史のあった医学雑誌『脳と神経』と『神経研究の進歩』が2007年に統合され,改題されたことをご存知ない方もいらっしゃるかもしれません。『脳と神経』は比較的臨床重視の内容で私もよく読んでいました。一方,『神経研究の進歩』は基礎的な内容も多く,自分では読んで理解できるものではありませんでした。医学雑誌を取り巻く環境はきっといろいろ厳しいものもあると思いますが,基礎から臨床までを広くカバーできる本誌の価値がいつまでも続くことを願っています。
本号はそういった意味では臨床神経学寄りの内容になりました。少し変わったタイトルの特集になりましたが,私自身にはまさに目が覚めるような内容です。言うまでもなく神経組織は全身に広がっています。中枢から指先の末梢に至るまでさまざまな変化が起こり,多くの症状に関わるはずです。そして,神経系以外の臓器と神経疾患が合併する疾患や病態も少なくありません。自分の目の前にいる患者さんの神経疾患と一般臓器の問題との重大な関連に気付いていないこともあるかもしれません。私自身は診療をしているときに,いつもそういったことが気になり,勉強不足を再認識させられる毎日です。
基本情報
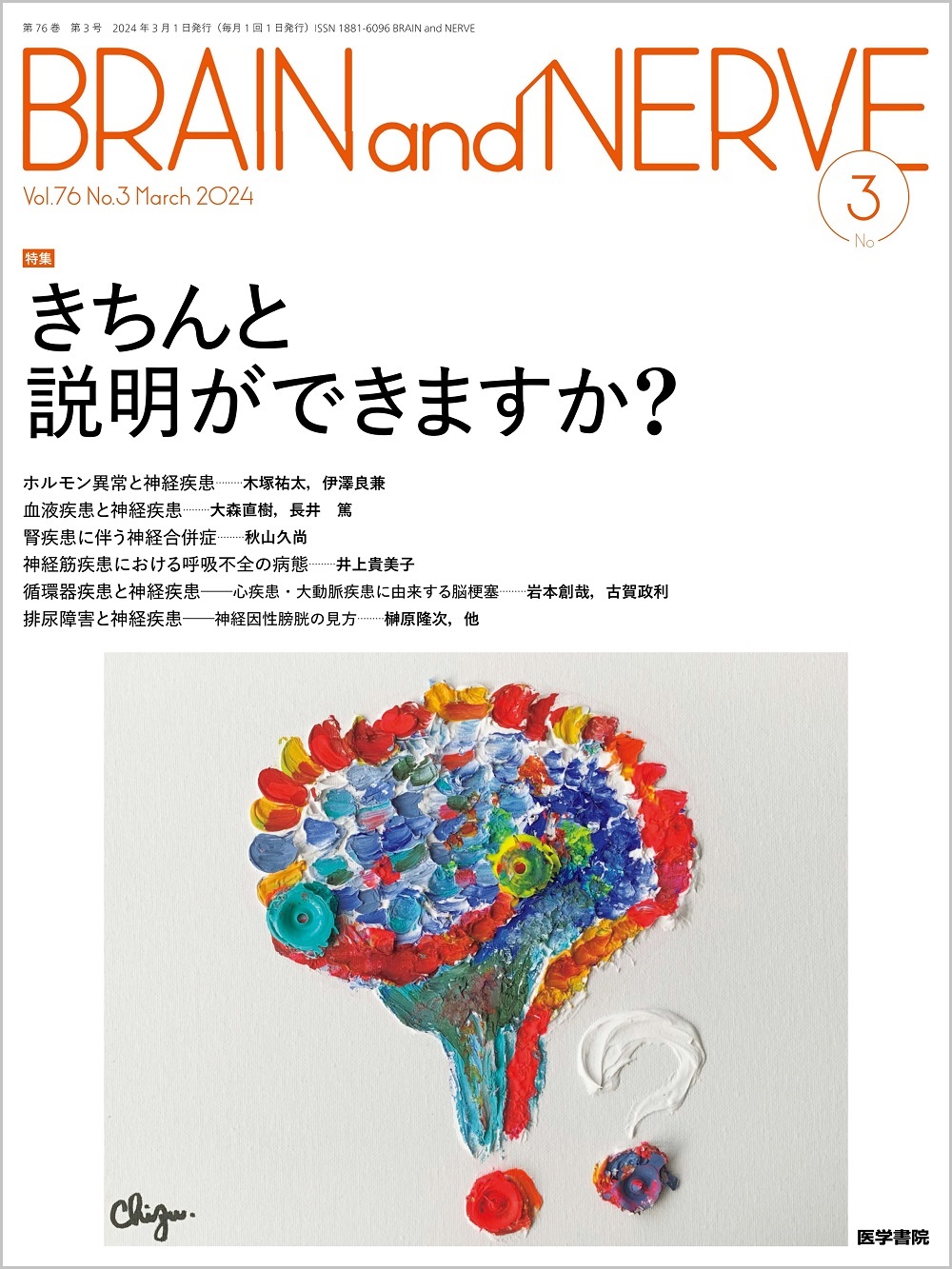
バックナンバー
76巻12号(2024年12月発行)
特集 芸術家と神経学Ⅱ
76巻11号(2024年11月発行)
特集 ALS 2024
76巻10号(2024年10月発行)
特集 どうして効くんだろう
76巻9号(2024年9月発行)
特集 治療可能な認知症としてのアルツハイマー病
76巻8号(2024年8月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である—revisited
76巻7号(2024年7月発行)
特集 ニューロ・バイオイメージング—技術と応用
76巻6号(2024年6月発行)
特集 注意と注意障害
76巻5号(2024年5月発行)
増大特集 末梢神経・筋肉の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
76巻4号(2024年4月発行)
特集 神経病理最前線
76巻3号(2024年3月発行)
特集 きちんと説明ができますか?
76巻2号(2024年2月発行)
特集 特発性正常圧水頭症の現在
76巻1号(2024年1月発行)
特集 新時代の重症筋無力症と関連疾患の診療
75巻12号(2023年12月発行)
特集 アガサ・クリスティーと神経毒
75巻11号(2023年11月発行)
特集 アロスタシス—ホメオスタシスを超えて
75巻10号(2023年10月発行)
特集 メタバースへの招待
75巻9号(2023年9月発行)
特集 妊娠と神経疾患
75巻8号(2023年8月発行)
特集 アルツハイマー病は本当に早期発見できるのか
75巻7号(2023年7月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part2 末梢編
75巻6号(2023年6月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part1 中枢編
75巻5号(2023年5月発行)
増大特集 神経・精神領域の薬剤ハンドブック
75巻4号(2023年4月発行)
特集 All About Epilepsy
75巻3号(2023年3月発行)
特集 慢性疼痛
75巻2号(2023年2月発行)
特集 多系統萎縮症の新診断基準とこれからの診療
75巻1号(2023年1月発行)
特集 よく出会う不随意運動を知る
74巻12号(2022年12月発行)
特集 映画を観て精神・神経疾患を知る
74巻11号(2022年11月発行)
特集 RFC1遺伝子関連スペクトラム障害
74巻10号(2022年10月発行)
特集 ウイルス性脳炎・脳症2022
74巻9号(2022年9月発行)
特集 動的環境への適応系としての歩行
74巻8号(2022年8月発行)
特集 迷走神経の不思議
74巻7号(2022年7月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識2022
74巻6号(2022年6月発行)
特集 脳神経内科医に求められる移行医療
74巻5号(2022年5月発行)
増大特集 次の一手—神経筋疾患難治例をどのように治療するか
74巻4号(2022年4月発行)
特集 脳科学リテラシーを高めるために
74巻3号(2022年3月発行)
特集 中枢性自律神経障害update
74巻2号(2022年2月発行)
特集 温度を感じる脳と身体の科学
74巻1号(2022年1月発行)
特集 脳神経内科医のキャリアパスとリーダーシップ
73巻12号(2021年12月発行)
特集 芸術家と神経学
73巻11号(2021年11月発行)
特集 「目」の神経学
73巻10号(2021年10月発行)
特集 中枢神経・末梢神経の悪性リンパ腫
73巻9号(2021年9月発行)
特集 脳卒中治療に必要な基礎知識
73巻8号(2021年8月発行)
特集 脳腸相関—脳-身体の双方向性制御
73巻7号(2021年7月発行)
特集 グリアと神経—相補的な制御系として
73巻6号(2021年6月発行)
特集 Lower Spine Neurology
73巻5号(2021年5月発行)
増大特集 中枢神経の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
73巻4号(2021年4月発行)
特集 片頭痛・群発頭痛治療の新たな夜明け
73巻3号(2021年3月発行)
特集 マルチリンガルブレイン
73巻2号(2021年2月発行)
特集 筋炎と壊死性筋症
73巻1号(2021年1月発行)
特集 Neuro-Oncology
72巻12号(2020年12月発行)
特集 超高齢期の精神神経疾患を診る
72巻11号(2020年11月発行)
増大特集 脳の発振現象—基礎から臨床へ
72巻10号(2020年10月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識
72巻9号(2020年9月発行)
特集 皮質性小脳萎縮症へのアプローチ
72巻8号(2020年8月発行)
特集 サルコイドーシス
72巻7号(2020年7月発行)
増大特集 神経倫理ハンドブック
72巻6号(2020年6月発行)
特集 前頭側頭葉変性症の今日的理解
72巻5号(2020年5月発行)
特集 多発性硬化症の現在と未来
72巻4号(2020年4月発行)
増大特集 神経疾患の診断における落とし穴—誤診を避けるために
72巻3号(2020年3月発行)
特集 でこぼこの脳の中でおしくらまんじゅうする脳機能
72巻2号(2020年2月発行)
特集 αシヌクレイノパチーの新たな展開
72巻1号(2020年1月発行)
特集 神経難病をクスリで治す—薬物開発の現況と近未来への展望
71巻12号(2019年12月発行)
特集 小脳と大脳—Masao Itoのレガシー
71巻11号(2019年11月発行)
増大特集 ALS2019
71巻10号(2019年10月発行)
特集 認知症と遺伝
71巻9号(2019年9月発行)
特集 神経疾患のドラッグ・リポジショニング—新時代へ
71巻8号(2019年8月発行)
特集 パーキンソン病診療の現在地—200年の変遷と新規治療
71巻7号(2019年7月発行)
増大特集 人工知能と神経科学
71巻6号(2019年6月発行)
特集 補体標的治療の現状と展望
71巻5号(2019年5月発行)
特集 NPSLE
71巻4号(2019年4月発行)
増大特集 神経学のための皮膚アトラス
71巻3号(2019年3月発行)
特集 Spine Neurology
71巻2号(2019年2月発行)
特集 “スポーツ”を生み出す脳
71巻1号(2019年1月発行)
特集 人工知能の医療応用Update
70巻12号(2018年12月発行)
特集 主訴に沿う—俯瞰し収束する画像診断の目
70巻11号(2018年11月発行)
増大特集 脳科学で解き明かす精神神経症候
70巻10号(2018年10月発行)
特集 「左脳と右脳」の現在
70巻9号(2018年9月発行)
特集 脳神経内科診療に役立つ精神科の知識
70巻8号(2018年8月発行)
特集 レヴィ小体型認知症の新知見
70巻7号(2018年7月発行)
増大特集 記憶と忘却に関わる脳のしくみ—分子機構から健忘の症候まで
70巻6号(2018年6月発行)
特集 芸術を生み出す脳
70巻5号(2018年5月発行)
特集 非アルツハイマー型認知症の病理学
70巻4号(2018年4月発行)
増大特集 Antibody Update 2018
70巻3号(2018年3月発行)
特集 『認知症疾患診療ガイドライン2017』を読み解く
70巻2号(2018年2月発行)
特集 知っておきたい神経感染症
70巻1号(2018年1月発行)
特集 筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群の今
69巻12号(2017年12月発行)
特集 運動異常症をみる—Web動画付録つき
69巻11号(2017年11月発行)
増大特集 こころの時間学の未来
69巻10号(2017年10月発行)
特集 成人てんかん—知っておきたい6つのトピック
69巻9号(2017年9月発行)
特集 ミクログリアと精神・神経疾患
69巻8号(2017年8月発行)
特集 遺伝性脊髄小脳失調症の病態と治療展望
69巻7号(2017年7月発行)
増大特集 あしたのアルツハイマー病治療
69巻6号(2017年6月発行)
特集 局在病変の神経心理学
69巻5号(2017年5月発行)
特集 Voxel-Based Morphometry—体積からわかること
69巻4号(2017年4月発行)
増大特集 ブロードマン領野の現在地
69巻3号(2017年3月発行)
特集 磁気刺激の新たな展開
69巻2号(2017年2月発行)
特集 Stroke-Like Diseases—鑑別時に注意を要する5病態
69巻1号(2017年1月発行)
特集 近年注目されている白質脳症
68巻12号(2016年12月発行)
特集 炎症性神経・筋疾患の新たな展開
68巻11号(2016年11月発行)
増大特集 連合野ハンドブック
68巻10号(2016年10月発行)
特集 アディクション—行動の嗜癖
68巻9号(2016年9月発行)
特集 自己免疫性脳炎・脳症
68巻8号(2016年8月発行)
特集 こころと汗
68巻7号(2016年7月発行)
増大特集 認知症の危険因子と防御因子
68巻6号(2016年6月発行)
特集 脳とフローラ
68巻5号(2016年5月発行)
特集 手の症候学—生理学・解剖学からみた新知見
68巻4号(2016年4月発行)
増大特集 治せる認知症
68巻3号(2016年3月発行)
特集 末梢神経の血管炎
68巻2号(2016年2月発行)
特集 筋疾患の認知機能障害
68巻1号(2016年1月発行)
特集 シャルコー・マリー・トゥース病
67巻12号(2015年12月発行)
特集 視床と高次脳機能
67巻11号(2015年11月発行)
増大特集 ギラン・バレー症候群のすべて—100年の軌跡
67巻10号(2015年10月発行)
特集 非・日常生活の脳科学
67巻9号(2015年9月発行)
特集 酵素補充療法
67巻8号(2015年8月発行)
特集 神経難病の終末期医療
67巻7号(2015年7月発行)
増大特集 神経疾患と感染症update
67巻6号(2015年6月発行)
特集 脳と「質感」
67巻5号(2015年5月発行)
特集 NCSE(非痙攣性てんかん重積状態)
67巻4号(2015年4月発行)
増大特集 大脳皮質vs.大脳白質
67巻3号(2015年3月発行)
特集 中枢神経の血管炎
67巻2号(2015年2月発行)
特集 「食べる」を考える
67巻1号(2015年1月発行)
特集 ニューロトキシコロジー
66巻12号(2014年12月発行)
特集 Orthopaedic Neurology—神経内科と整形外科の狭間で
66巻11号(2014年11月発行)
増大特集 神経症候学は神経学の“魂”である
66巻10号(2014年10月発行)
特集 分子を撃つ 神経疾患治療の新しい水平線
66巻9号(2014年9月発行)
特集 痙縮の臨床神経学
66巻8号(2014年8月発行)
特集 神経系の悪性リンパ腫update
66巻7号(2014年7月発行)
増大特集 アミロイド関連神経疾患のすべて―封入体筋炎からアルツハイマー病まで
66巻6号(2014年6月発行)
特集 ミラーニューロン
66巻5号(2014年5月発行)
特集 アセチルコリンと神経疾患―100年目の現在地
66巻4号(2014年4月発行)
増大特集 タッチ・ビジョン・アクション
66巻3号(2014年3月発行)
特集 神経筋疾患の超音波診断
66巻2号(2014年2月発行)
特集 糖尿病の神経学revisited
66巻1号(2014年1月発行)
特集 日常生活の脳科学
65巻12号(2013年12月発行)
特集 プロテイノパチーの神経病理学
65巻11号(2013年11月発行)
増大特集 Close Encounters―臨床神経学と臨床免疫学の遭遇と未来
65巻10号(2013年10月発行)
特集 神経系の発達メカニズム―最近の話題
65巻9号(2013年9月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である―現状と展望
65巻8号(2013年8月発行)
特集 こころの時間学―現在・過去・未来の起源を求めて
65巻7号(2013年7月発行)
増大特集 あしたの脳梗塞
65巻6号(2013年6月発行)
特集 見せる・仕分ける―脳機能解析の新手法
65巻5号(2013年5月発行)
特集 てんかん―新しいパースペクティブ
65巻4号(2013年4月発行)
増大特集 Antibody Update
65巻3号(2013年3月発行)
特集 次世代シーケンサーによる神経変性疾患の解析と展望
65巻2号(2013年2月発行)
特集 血液脳関門研究の進歩
65巻1号(2013年1月発行)
特集 Corticobasal Syndrome
64巻12号(2012年12月発行)
特集 The Border-Land of Dementia
64巻11号(2012年11月発行)
増大特集 痛みの神経学―末梢神経から脳まで
64巻10号(2012年10月発行)
特集 辺縁系をめぐって
64巻9号(2012年9月発行)
特集 高次脳機能イメージングの脳科学への新展開
64巻8号(2012年8月発行)
特集 線条体の基礎と臨床
64巻7号(2012年7月発行)
増大特集 顔認知の脳内機構
64巻6号(2012年6月発行)
特集 睡眠と覚醒の脳内機構
64巻5号(2012年5月発行)
特集 神経疾患のバイオマーカー
64巻4号(2012年4月発行)
増大特集 パーキンソン病の新しい側面
64巻3号(2012年3月発行)
特集 アカデミアから新規治療の実現へ―トランスレーショナルリサーチの現状
64巻2号(2012年2月発行)
特集 生物学的精神医学の進歩
64巻1号(2012年1月発行)
特集 iPS細胞と神経疾患
63巻12号(2011年12月発行)
特集 神経心理学と画像解析の融合
63巻11号(2011年11月発行)
増大特集 筋疾患update
63巻10号(2011年10月発行)
特集 緩徐進行性高次脳機能障害の病態
63巻9号(2011年9月発行)
特集 脳卒中の最新画像診断
63巻8号(2011年8月発行)
特集 日本人の発見した神経症候
63巻7号(2011年7月発行)
増大特集 神経筋接合部―基礎から臨床まで
63巻6号(2011年6月発行)
特集 ニューロパチー
63巻5号(2011年5月発行)
特集 神経系と血管内リンパ腫
63巻4号(2011年4月発行)
増大特集 てんかんの新しい治療
63巻3号(2011年3月発行)
特集 サイバーナイフ治療
63巻2号(2011年2月発行)
特集 続・日本人の発見した神経疾患
63巻1号(2011年1月発行)
特集 血管腫
62巻12号(2010年12月発行)
特集 頸部頸動脈狭窄症の診断と治療
62巻11号(2010年11月発行)
増大特集 歩行とその異常
62巻10号(2010年10月発行)
特集 ブレインバンク
62巻9号(2010年9月発行)
特集 視神経脊髄炎(NMO)update
62巻8号(2010年8月発行)
特集 辺縁系脳炎
62巻7号(2010年7月発行)
増大特集 アルツハイマー病―研究と診療の進歩
62巻6号(2010年6月発行)
特集 改正臓器移植法の問題点とその対応
62巻5号(2010年5月発行)
特集 神経画像のピットフォール―見落としと読み過ぎ
62巻4号(2010年4月発行)
特集 傍腫瘍性神経筋疾患update
62巻3号(2010年3月発行)
特集 神経回路解析法の最近の進歩
62巻2号(2010年2月発行)
特集 ニューロリハビリテーションの最前線
62巻1号(2010年1月発行)
特集 神経救急
61巻12号(2009年12月発行)
特集 Somatotopy再考
61巻11号(2009年11月発行)
特集 前頭側頭葉変性症
61巻10号(2009年10月発行)
特集 片頭痛の予防療法
61巻9号(2009年9月発行)
特集 脳血管障害治療の進歩
61巻8号(2009年8月発行)
特集 神経・筋疾患の分子標的治療
61巻7号(2009年7月発行)
特集 脳腫瘍研究の最前線―遺伝子解析から治療まで
61巻6号(2009年6月発行)
特集 脊椎・脊髄外科の最近の進歩
61巻5号(2009年5月発行)
特集 Restless legs syndrome
61巻4号(2009年4月発行)
特集 大脳基底核―分子基盤から臨床まで
61巻3号(2009年3月発行)
特集 Microneurography(微小神経電図法)の臨床応用
61巻2号(2009年2月発行)
特集 神経系の再興感染症と輸入感染症
61巻1号(2009年1月発行)
特集 脳神経倫理
60巻12号(2008年12月発行)
特集 痙縮
60巻11号(2008年11月発行)
特集 脳卒中と遺伝子
60巻10号(2008年10月発行)
特集 若年者の脳卒中
60巻9号(2008年9月発行)
特集 知・情・意の神経学
60巻8号(2008年8月発行)
特集 脳硬膜動静脈瘻
60巻7号(2008年7月発行)
増大特集 学習と記憶――基礎と臨床
60巻6号(2008年6月発行)
特集 Crow-深瀬症候群(POEMS症候群)
60巻5号(2008年5月発行)
特集 「痛み」の研究と治療の最前線
60巻4号(2008年4月発行)
増大特集 神経系の発生とその異常
60巻3号(2008年3月発行)
特集 特発性正常圧水頭症(iNPH)―最近の話題
60巻2号(2008年2月発行)
特集 がん治療と神経障害
60巻1号(2008年1月発行)
特集 日本人の発見した神経疾患
59巻12号(2007年12月発行)
特集 損傷神経の再生―温存的治療法の開発
59巻11号(2007年11月発行)
特集 手根管症候群をめぐって
59巻10号(2007年10月発行)
増大特集 ALS―研究と診療の進歩
59巻9号(2007年9月発行)
特集 パーキンソン病の認知機能障害
59巻8号(2007年8月発行)
特集 パーキンソン病の分子遺伝学―最近の知見
59巻7号(2007年7月発行)
増大特集 情報伝達処理におけるグリアの機能と異常
59巻6号(2007年6月発行)
特集 職業性神経障害の新しい展開
59巻5号(2007年5月発行)
特集 脳画像最前線
59巻4号(2007年4月発行)
増大特集 最近注目される脳神経疾患治療の研究
59巻3号(2007年3月発行)
特集 分子イメージング
59巻2号(2007年2月発行)
特集 進行性多巣性白質脳症の新しい展開―PMLが治る時代へ向けて
59巻1号(2007年1月発行)
特集 高次視覚研究の最近の進歩
