好評を博した2021年5月号増大号「中枢神経の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック」の続編です。中枢神経のそれと同じく,末梢神経・筋肉の自己免疫性・炎症性疾患は決してcommon diseaseというわけではありません。しかし,神経学の臨床に携わる者にとっては必ず遭遇する疾患群であり,common diseaseではないがゆえに指導層の経験や知識もまちまちで,臨床家として最新の知識にキャッチアップしておかなければならない領域です。何よりも,“治せる”,個々の医師の力量が大きく問われる疾患群です。
「第1章 検査法概論」では,各検査の進め方や所見の特徴,解釈における留意点などを示しました。「第2章 疾患各論」では,「疾患概念」,「診断には何が有用か」,「鑑別診断のポイント」,「治療と予後」を軸として,診療の全体像を著者の私見を交えながら解説しています。
種々の検査法から多数の疾患の病態・治療までを網羅した本特集は,末梢神経・筋肉の自己免疫性・炎症性疾患に関する現在までの到達点とも言えます。本特集を道標として強固な知識の基盤を築き上げることで,病気に苦しむ患者さんに希望の灯をともすことができるはずです。
雑誌目次
BRAIN and NERVE-神経研究の進歩76巻5号
2024年05月発行
雑誌目次
増大特集 末梢神経・筋肉の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
扉 フリーアクセス
ページ範囲:P.439 - P.439
第1章 検査法概論
抗体検査をどのように行うか
著者: 古賀道明
ページ範囲:P.443 - P.448
自己抗体の測定は,多くの末梢神経・筋疾患の診療に欠かせない検査となった。その臨床的意義は抗体ごとに異なり,検査精度や検出されるアイソタイプ・サブクラス,疾患活動性との関連など,臨床医が理解しておくべきことは多い。また,保険診療として実施できない自己抗体検査も多く,限られた医療資源の中で,検査結果を誤解なく日常診療に生かすために,臨床医は常に最新情報をアップデートしておくことが求められる。
電気生理検査をどのように行うか
著者: 幸原伸夫
ページ範囲:P.449 - P.462
末梢神経や筋,神経筋接合部疾患において,電気生理検査は診断や治療方針を決めるにあたって必須の検査であり,末梢神経の脱髄,軸索変性,神経筋接合部や筋の障害をリアルタイムで評価することができる。脱髄があれば伝導遅延,波形の時間的分散などが出現するし,軸索障害であれば振幅が低下する。経時的変化に加え,針筋電図を併用すれば病態が急性か慢性か,障害の程度がどの程度か,予後はどうかの情報を得ることができる。
—病理学的検査をどのように行うか—(1)筋生検
著者: 清水潤
ページ範囲:P.463 - P.471
炎症性筋疾患における筋生検では,炎症部分の筋組織を直接観察できるが,あくまでも全身の筋の中で選択し生検された一部の筋の情報を診ているにすぎない。そのため,得られた筋病理像が患者の臨床像と合致しているかどうかは,患者の臨床情報を基に筋病理所見の意義を解釈する必要がある。本論では,筋生検を効果的に行うために注意すべき点に関しての筆者の考えを述べ,筋炎の病理所見の解釈の仕方に関しても簡単に概説する。
—病理学的検査をどのように行うか—(2)末梢神経生検
著者: 佐藤亮太
ページ範囲:P.473 - P.479
自己免疫性・炎症性末梢神経疾患の中で,神経生検で確定診断を行う症例は少ないため,後遺障害を伴う侵襲的な神経生検の適応は慎重に判断されるべきである。神経生検を施行した場合は,疾患特異的な病理所見を検索することに加えて,鑑別診断に有用な所見を探すことが神経生検を臨床に活かすために重要である。本論では,自己免疫性・炎症性末梢神経疾患の鑑別診断に有用な神経病理所見について概説する。
—画像検査をどのように行うか—(1)MRI
著者: 横田元
ページ範囲:P.481 - P.486
MR neurographyは,撮像部位,想定される疾患で撮像法を変える必要がある。腕神経叢,腰仙骨神経叢を評価する場合は,3D-STIRなどの3D spin echo法が使われることが多い。あらかじめ,撮像法を準備し,正常像を把握しておくとよい。当院での撮像条件を提示するので,参考にしてほしい。神経肥厚,信号上昇,左右差,口径不整に注目して読影する。定性評価の標準化,技術革新による定量化が試みられている。
—画像検査をどのように行うか—(2)超音波検査
著者: 能登祐一
ページ範囲:P.487 - P.496
神経筋超音波検査は,現在では,脳神経内科領域の神経筋疾患の評価における必須検査となりつつある。神経超音波検査での神経腫大の有無の判定,筋超音波検査での選択的な筋変性の同定,fasciculationの有無,その分布の判断などが,自己免疫性・炎症性神経筋疾患と,それらと鑑別を要する神経・筋変性疾患,遺伝性疾患の診断において,大きな助けとなる。
第2章 疾患各論
ギラン・バレー症候群
著者: 海田賢一
ページ範囲:P.499 - P.507
ギラン・バレー症候群は感染をはじめとする免疫学的刺激を契機に発症する急性免疫介在性ニューロパチーであり,補体介在性神経障害が主な病態である。約60%に糖脂質抗体を認める。近年では細胞性免疫の関与も示唆されている。経静脈的免疫グロブリン療法と血漿交換療法が確立された免疫治療である。本論では病態,診断,治療,予後と予後予測に関して,最新の知見を基に解説する。
フィッシャー症候群
著者: 鈴木千恵子
ページ範囲:P.508 - P.514
フィッシャー症候群は,ギラン・バレー症候群の亜型である。急性に発症し,予後は良好である。眼球運動障害,失調,腱反射消失が三徴である。多くの症例で先行感染が確認される。ガングリオシド抗体のうち,GQ1b抗体が高率に陽性となる。本症には,三徴のうち一部の症状しか示さない不全型,意識障害や錐体路徴候が加わるビッカースタッフ脳幹脳炎,経過中四肢脱力などが加わるギラン・バレー症候群とのオーバーラップ型がある。
典型的CIDP
著者: 桑原聡
ページ範囲:P.515 - P.519
慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー(chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy:CIDP)は慢性免疫介在性脱髄性ニューロパチーの総称であり,その中心的病型が典型的CIDPである。1970年代に「近位筋と遠位筋が同時に障害される」という極めて特徴的な症状と免疫学的治療への反応性をもって定義された古典的CIDPが現在の分類では典型的CIDPと称されている。典型的CIDPにおいては標的抗原は同定されていないが,電気生理学・神経画像により病変の主体が血液神経関門の欠如する神経根と遠位部神経終末にあること,免疫グロブリン療法・血漿交換が有効であることから,抗体介在性機序が推定されている。CIDP全体の60〜70%は典型的CIDPであることから,これまでの治験のエビデンスはほぼ典型的CIDPに対する治療を示したものである。2021年にEAN(欧州神経学会)/PNS(国際末梢神経学会)CIDPガイドラインが公表され,2024年には日本神経学会による診療ガイドラインが公表予定である。本論では典型的CIDPに焦点を当ててその病態・診断・治療について概説する。
CIDPバリアント
著者: 国分則人
ページ範囲:P.520 - P.525
慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチー(chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy:CIDP)は,慢性脱髄性ニューロパチーを基礎としてさまざまな臨床症候や経過,治療反応性を示すheterogeneousな症候群である。典型的CIDPのほか,多巣性CIDP,遠位型CIDPは,CIDPの三大病型で,その臨床的・電気生理学的・病理学的な検討から,それぞれが異なる病態生理を持つ疾患単位である可能性が示唆されている。
多巣性運動ニューロパチー
著者: 神田創 , 神田隆
ページ範囲:P.526 - P.533
多巣性運動ニューロパチーは,感覚障害を伴わない,左右非対称性の上肢遠位筋優位の筋力低下と筋萎縮を主徴とする後天性の慢性脱髄性末梢神経疾患である。筋萎縮性側索硬化症との鑑別がしばしば問題になる。電気生理学的に多巣性の伝導ブロックが認められる。男性に多く,IgM型GM1抗体が半数弱の患者で陽性になる。慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチーと異なり副腎皮質ステロイド薬は無効で,免疫グロブリン大量静注療法が有効かつ唯一の確立された治療法である。
自己免疫性ノドパチー
著者: 緒方英紀
ページ範囲:P.534 - P.539
自己免疫性ノドパチー(autoimmune nodopathy)はランヴィエ絞輪部および傍絞輪部に局在する膜蛋白(neurofascin 186,neurofascin 155,contactin-1,contactin-associated protein 1)に対する自己抗体が陽性となる免疫介在性ニューロパチーである。同疾患は免疫グロブリン療法の効果が乏しくリツキシマブが奏効するため,関連する自己抗体を測定することは,診断のみならず治療方針を決定するうえで重要な役割を果たす。
MAGニューロパチー
著者: 桑原基
ページ範囲:P.540 - P.546
MAGニューロパチーはMGUSなどのIgM型M蛋白血症を背景に発症する脱髄性ニューロパチーである。緩徐進行性の感覚障害または感覚運動障害と運動失調を呈する。診断はM蛋白とMAG抗体の検出によってなされるが,神経伝導検査では遠位潜時が延長し,腓腹神経病理では電子顕微鏡でwidely spaced myelinが見られる。一般的に免疫療法への反応性は不良であるが,リツキシマブが約半数で有効であり,今後の治療開発が期待される。
POEMS症候群
著者: 水地智基 , 三澤園子
ページ範囲:P.547 - P.554
POEMS症候群は単クローン性の形質細胞増殖と血管内皮増殖因子の過剰産生を基盤とした全身性疾患である。サリドマイドをはじめとした骨髄腫治療の応用により,本疾患は治療可能な疾患となりつつあるため,早期診断し適切な治療を行うことの重要性が高まっている。早期診断を実現するには,本疾患の特徴的な全身症候や検査異常を理解しておくことが必要である。また,適切な治療を提供するためには,血液内科との連携が不可欠となる。
傍腫瘍性末梢神経障害
著者: 木村暁夫 , 大野陽哉 , 下畑享良
ページ範囲:P.555 - P.561
傍腫瘍性末梢神経障害は,腫瘍に対する自己免疫学的機序を背景として発症する末梢神経障害である。いくつかの臨床病型が知られているが,代表的な臨床病型は後根神経節細胞障害による感覚性ニューロパチーである。末梢神経障害は,腫瘍の発見に先行することが多い。患者の血清・脳脊髄液中に抗神経抗体が検出されることがある。合併腫瘍として小細胞肺癌が多い。早期の腫瘍切除と免疫療法により,症状の改善や安定化が得られる。
自己免疫性自律神経節障害・急性自律性感覚性ニューロパチー
著者: 中根俊成
ページ範囲:P.562 - P.568
自己免疫性自律神経節障害(autoimmune autonomic ganglionopathy:AAG)と急性自律性感覚性ニューロパチー(acute autonomic and sensory neuropathy:AASN)は免疫機序を基盤に発症する自律神経節あるいは後根神経節の障害を病態とする疾患である。AAG患者血清からはニコチン性自律神経節アセチルコリン受容体(ganglionic acetylcholine receptor:gAChR)に対する自己抗体が検出され,AAGの病原性自己抗体とされている。gAChR抗体はAASN患者血清では認めないとされる。AAGとAASNは現段階では臨床症状や各検査の所見からスペクトラム概念ではないと考えられる。しかし,自律神経外症状である脳症状(精神症状,性格変化を含む),内分泌障害は両者に共通して見られなんらかの病態基盤が共通する可能性を残している。
EGPAによる血管炎性ニューロパチー
著者: 竹下幸男
ページ範囲:P.569 - P.574
好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(eosinophilic granulomatosis with polyangiitis:EGPA)は,難治性の気管支喘息が先行し,末梢血の好酸球増多を伴いながら全身の小-中動脈の血管炎症状を主病態とする疾患であり,9割以上の患者でニューロパチーを発症する。EGPAニューロパチーを発症してしまうと,それまで慢性疾患の側面が強かったEGPAは,末梢神経における代表的な救急疾患に早変わりし,病態に対応した治療法選択と迅速な治療介入が必要とされる。
EGPA以外の血管炎性ニューロパチー
著者: 川頭祐一
ページ範囲:P.575 - P.582
血管炎性ニューロパチーはしばしば全身性血管炎に関連し,神経栄養血管の虚血から軸索変性をきたす疾患である。感覚優位の多発性単ニューロパチーを呈することが多く,罹患部位に疼痛の頻度は高い。さまざまな全身疾患に起因するが,ANCA関連血管炎や膠原病による二次性全身性血管炎,非全身性血管炎性ニューロパチーが重要である。血管炎性ニューロパチーの包括的理解は早期診断に必須であり,ひいては予後改善につながる。
ALアミロイドーシス
著者: 植田光晴
ページ範囲:P.583 - P.587
ALアミロイドーシスはアミロイドーシスの中で頻度の高い病型である。免疫グロブリン軽鎖由来のアミロイドが全身諸臓器に沈着し機能障害を生じる。末梢神経障害の頻度は10〜40%で認められる。確定診断には組織生検を行う必要がある。比較的非侵襲的である腹壁脂肪,皮膚,消化管の生検が実施されることが多い。近年,本疾患に対する治療法は発展しており生命予後は改善傾向にある。
シェーグレン症候群の末梢神経・筋障害
著者: 桑原宏哉 , 横田隆徳
ページ範囲:P.588 - P.597
シェーグレン症候群はしばしば多彩な神経系合併症を伴い,その中でも末梢神経障害の頻度は高い。末梢神経障害の病型は,軸索障害型多発ニューロパチーや感覚失調性ニューロパチーなどさまざまであり,おのおのの病型の病態や鑑別診断について概説する。副腎皮質ステロイドや免疫グロブリン大量静注療法といった免疫治療は,病型ごとに治療反応性が異なる傾向にある。シェーグレン症候群に合併することのある筋炎についても紹介する。
末梢神経・筋サルコイドーシス
著者: 藤澤美和子
ページ範囲:P.598 - P.604
末梢神経,筋サルコイドーシスは非乾酪性類上皮細胞肉芽腫が脳神経と脊髄神経,骨格筋に出現する疾患である。画像検査を含め,全身検索と他疾患の除外が重要で,確定診断には非乾酪性類上皮細胞肉芽腫の証明が必須である。いずれも治療はステロイド薬が第一選択ではあるが,複数の免疫抑制薬,TNF-α阻害薬を併用しながら長期の治療を要することが多い。治療薬のランダム化比較試験に乏しく,治療法の確立が望まれる。
irAEとしての末梢神経・筋障害
著者: 鈴木重明
ページ範囲:P.605 - P.611
免疫チェックポイント阻害薬による免疫関連有害事象として発症する神経・筋疾患は中枢神経疾患に比べると高頻度である。末梢神経障害には多彩な病型が報告されているが,多発神経根炎は運動麻痺を呈し最も重篤な病型である。また自律神経障害が出現することも報告されている。神経・筋接合部として重症筋無力症とランバート・イートン筋無力症候群があり,前者は筋炎と後者は傍腫瘍神経症候群と共通の免疫学的機序を有している。
AChR抗体陽性重症筋無力症
著者: 村井弘之
ページ範囲:P.613 - P.620
アセチルコリン受容体(acetylcholine receptor:AChR)抗体陽性重症筋無力症の病態,診断,治療についてまとめた。その発症機序の上流部分には,AChRに感作されたT細胞依存性にB細胞から自己抗体が産生されるという過程がある。下流部分では,産生されたAChR抗体が補体系を活性化させ,運動終板を破壊する。治療の目標は患者の生活の質を担保することである。新しく登場してきた分子標的薬についても紹介する。
MuSK抗体陽性重症筋無力症
著者: 本村政勝 , 北之園寛子 , 吉村俊祐 , 白石裕一
ページ範囲:P.623 - P.629
本邦のMuSK抗体陽性重症筋無力症(myasthenia gravis:MG)患者は,MG患者全体の約3%と報告されている。その臨床像をAChR抗体陽性MG患者と比較すると,若年発症,女性優位,眼筋型の頻度が5.9%と非常に少なく,さらに,嚥下障害を主症状とする重症例が多い。これらの臨床症状と電気生理検査で両者を鑑別することは困難で,その診断には,MuSK抗体測定が必須である。胸腺摘除術と補体阻害薬は治療の適応とはならない。それ以外のアセチルコリンエステラーゼ阻害薬,ステロイド,免疫抑制薬,血漿浄化療法,免疫グロブリン静注療法,および,胎児性Fc受容体阻害薬が活用されている。
ランバート・イートン筋無力症候群
著者: 松尾秀徳
ページ範囲:P.630 - P.634
ランバート・イートン筋無力症候群は,近位筋力低下,腱反射の低下,および自律神経障害を呈する神経筋接合部疾患で,50〜60%に小細胞肺癌を合併する。P/Q型電位依存性カルシウムチャネルに対する自己抗体が病態に関与している。重症筋無力症/ランバート・イートン筋無力症候群診療ガイドライン2022では,臨床症状,特徴的な電気生理学的所見および病原性自己抗体による診断基準および治療アルゴリズムが示されている。
皮膚筋炎
著者: 杉江和馬
ページ範囲:P.635 - P.645
皮膚筋炎(dermatomyositis:DM)は,筋症状とともに,特徴的な皮疹と筋病理学的所見から,他の特発性炎症性筋疾患と区別される。DMでは5つの筋炎特異的自己抗体が同定され,各抗体と臨床像との相関が明らかになっている。また筋病理解析により,DMが骨格筋のⅠ型インターフェロノパチーと捉えられている。治療を行ううえで,丹念な四肢・体幹の筋力評価,全身炎症所見や筋病理所見,骨格筋画像に加えて,悪性腫瘍や間質性肺疾患などの合併症を勘案して,治療計画を立てる必要がある。ステロイド治療が第一選択で,免疫抑制薬や大量免疫グロブリンが適宜使用される。少数例ながらこれらの治療への抵抗性を示す。現状では,難治例に対する治療戦略は十分確立しておらず,今後治療法の開発が求められる。
免疫介在性壊死性ミオパチー
著者: 漆葉章典
ページ範囲:P.646 - P.654
免疫介在性壊死性ミオパチーは自己免疫性筋炎の一型で,筋病理学的に壊死・再生を主要所見とする。特異自己抗体としてSRP抗体とHMGCR抗体が同定されている。高度の筋線維壊死を反映し,血清クレアチンキナーゼ値は著しく上昇する。筋力低下は高度であることが多い。特に長期経過例で筋ジストロフィーとの鑑別が課題となることがある。治療にはステロイドに加え,免疫抑制薬や免疫グロブリンなどが組み合わせられる。
ARS抗体症候群
著者: 笹井(中嶋)蘭
ページ範囲:P.655 - P.659
アミノアシルtRNA合成酵素(ARS)抗体は特発性炎症性筋疾患で最も高頻度な自己抗体で,合成酵素抗体症候群(ASyS)と呼ばれる臨床特徴(関節痛,筋炎,間質性肺疾患,発熱,レイノー減少,機械工の手)を呈しやすい。治療はステロイドに反応しやすいが,減量とともに再燃しやすく,慢性進行型の経過をたどる。治療にはステロイドを中心に,早期から免疫抑制薬を併用し継続する重要性が示唆されている。
封入体筋炎
著者: 青木正志 , 井泉瑠美子 , 鈴木直輝
ページ範囲:P.660 - P.670
封入体筋炎は中高年に発症する特発性の筋疾患である。左右非対称の筋力低下と筋萎縮が大腿四頭筋や手指・手首屈筋に見られる。骨格筋には縁取り空胞と呼ばれる特徴的な組織変化を生じ炎症細胞浸潤を伴う。炎症性筋疾患に分類されるが,筋の「変性疾患」としての側面を持つ。ステロイドなどの免疫学的治療に反応せず,かえって増悪することもある。厚生労働省研究班による全国調査によるとわが国でも患者数が増加している。
総説
糖尿病性神経障害の発症メカニズム
著者: 三五一憲 , 八子英司 , 高久静香 , 新見直子
ページ範囲:P.671 - P.680
糖尿病性神経障害は末梢神経疾患の中で最も患者数が多く,また糖尿病の慢性合併症の中で最も早期かつ高頻度に出現する。末梢神経を構成するニューロン,シュワン細胞,血管内皮細胞などの代謝異常が本症の発症・増悪に深く関与することが報告されてきたが,いまだに不明な点も多く疾患修飾薬の開発は遅れている。本論では筆者らの研究を含め,神経障害の発症メカニズム解明および治療戦略に関する最近の知見を紹介する。
連載 スーパー臨床神経病理カンファレンス・4
小児期より足の疼痛と発汗低下,49歳時洞機能不全症候群・左室肥大を呈し,その後,腎機能低下と聴力障害が進行し,67歳で死亡した男性例
著者: 福田隆浩 , 深澤寧
ページ範囲:P.681 - P.689
〔現病歴〕8歳頃より,足の疼痛を自覚。また,突然の発熱が年に5〜6回あった。汗をかいた記憶もほとんどなかった。25歳頃より,足の疼痛がやや軽減してきた。48歳時,心電図にてnegative Tを指摘され肥大型心筋症や心筋虚血が疑われていた。49歳時,失神発作にて病院を受診し,洞機能不全症候群・左室肥大を認め,DDIペースメーカー挿入と心筋生検を実施した。白血球酵素測定を行ったところα-ガラクトシダーゼAの低下が確認された。
61歳時より酵素補充療法を開始したが,慢性腎不全の状態は改善されず(BUN 27mg/dL,Cr 2.0mg/dL),66歳時BUN 78mg/dL,Cr 6.33mg/dL,Ccr 12mL/min,蛋白尿 1.92g/日,胸部X線にて心胸比拡大と胸水貯留,呼吸苦があり,血液透析が開始となった。67歳時自宅で倒れているところを発見され,死亡確認。病理解剖となった(Fig. 1〜5)。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.434 - P.435
欧文目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.436 - P.437
バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.694 - P.694
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.695 - P.695
あとがき フリーアクセス
著者: 下畑享良
ページ範囲:P.696 - P.696
増大号特集「末梢神経・筋肉の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック」をお届けします。各執筆者の熱のこもった筆致で綴られた本特集は,非常に充実した内容になりました。日々の臨床に間違いなく役に立つ1冊になると思います。
この号を拝読し,私が印象深く思ったのは,これらの疾患の免疫療法が大きく変貌しつつあることを実感したことです。今後,さらに目指すべき治療戦略は,疾患の根底にある病態機序を明らかにし,最適な治療標的分子を同定し,それに可能な限り特異的な治療薬を用い,副作用を最低限に抑えることではないかと思いました。つまり現在の広範な免疫抑制ないし非選択的抗体除去から,より標的を絞った治療へとシフトしていく過程に現在はあるように感じました。そしてその大きな変革の中心を担うのは抗体医薬であり,そしてもう1つ,CAR-T細胞ではないかと考えています。
基本情報
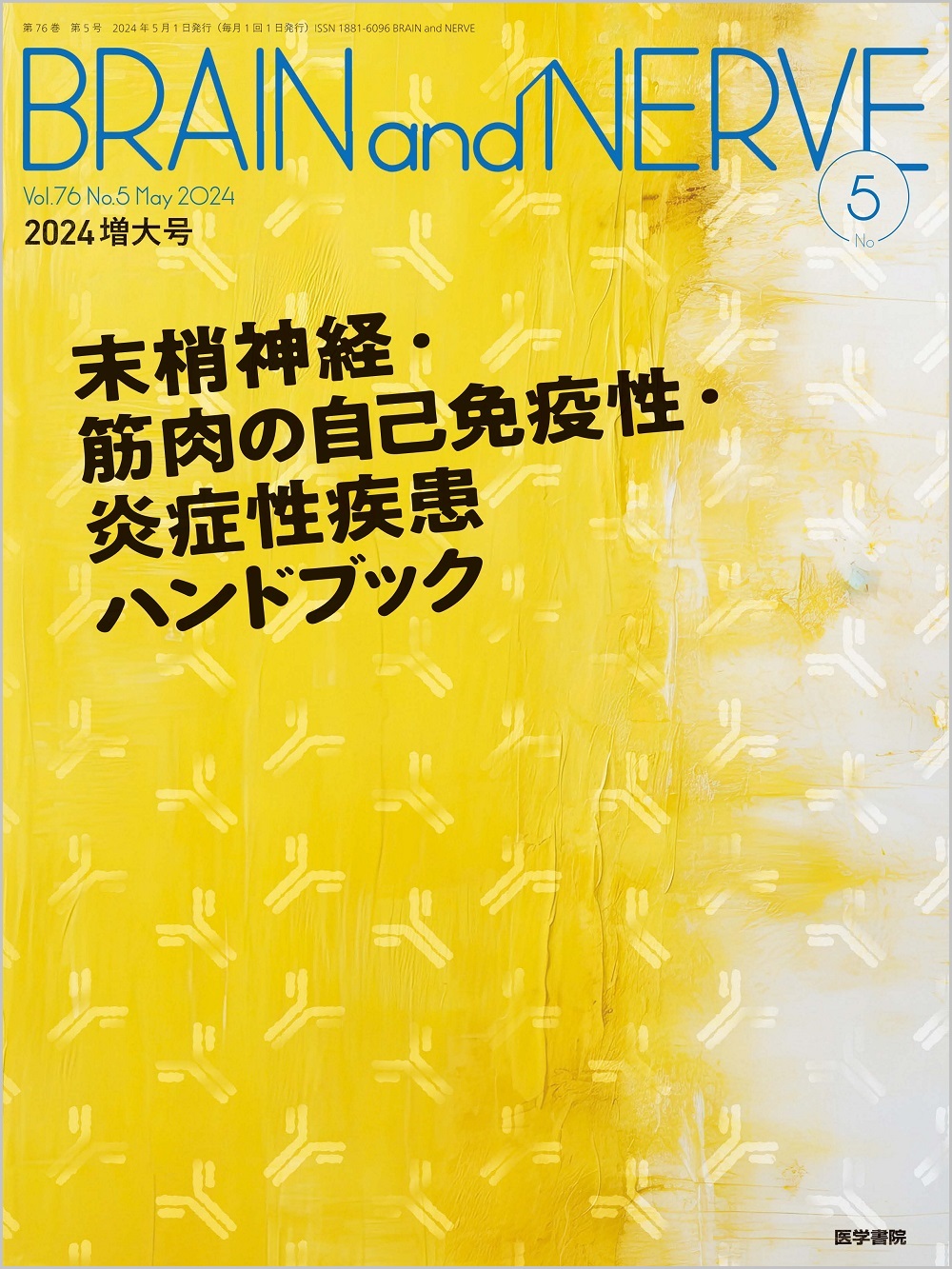
バックナンバー
76巻12号(2024年12月発行)
特集 芸術家と神経学Ⅱ
76巻11号(2024年11月発行)
特集 ALS 2024
76巻10号(2024年10月発行)
特集 どうして効くんだろう
76巻9号(2024年9月発行)
特集 治療可能な認知症としてのアルツハイマー病
76巻8号(2024年8月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である—revisited
76巻7号(2024年7月発行)
特集 ニューロ・バイオイメージング—技術と応用
76巻6号(2024年6月発行)
特集 注意と注意障害
76巻5号(2024年5月発行)
増大特集 末梢神経・筋肉の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
76巻4号(2024年4月発行)
特集 神経病理最前線
76巻3号(2024年3月発行)
特集 きちんと説明ができますか?
76巻2号(2024年2月発行)
特集 特発性正常圧水頭症の現在
76巻1号(2024年1月発行)
特集 新時代の重症筋無力症と関連疾患の診療
75巻12号(2023年12月発行)
特集 アガサ・クリスティーと神経毒
75巻11号(2023年11月発行)
特集 アロスタシス—ホメオスタシスを超えて
75巻10号(2023年10月発行)
特集 メタバースへの招待
75巻9号(2023年9月発行)
特集 妊娠と神経疾患
75巻8号(2023年8月発行)
特集 アルツハイマー病は本当に早期発見できるのか
75巻7号(2023年7月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part2 末梢編
75巻6号(2023年6月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part1 中枢編
75巻5号(2023年5月発行)
増大特集 神経・精神領域の薬剤ハンドブック
75巻4号(2023年4月発行)
特集 All About Epilepsy
75巻3号(2023年3月発行)
特集 慢性疼痛
75巻2号(2023年2月発行)
特集 多系統萎縮症の新診断基準とこれからの診療
75巻1号(2023年1月発行)
特集 よく出会う不随意運動を知る
74巻12号(2022年12月発行)
特集 映画を観て精神・神経疾患を知る
74巻11号(2022年11月発行)
特集 RFC1遺伝子関連スペクトラム障害
74巻10号(2022年10月発行)
特集 ウイルス性脳炎・脳症2022
74巻9号(2022年9月発行)
特集 動的環境への適応系としての歩行
74巻8号(2022年8月発行)
特集 迷走神経の不思議
74巻7号(2022年7月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識2022
74巻6号(2022年6月発行)
特集 脳神経内科医に求められる移行医療
74巻5号(2022年5月発行)
増大特集 次の一手—神経筋疾患難治例をどのように治療するか
74巻4号(2022年4月発行)
特集 脳科学リテラシーを高めるために
74巻3号(2022年3月発行)
特集 中枢性自律神経障害update
74巻2号(2022年2月発行)
特集 温度を感じる脳と身体の科学
74巻1号(2022年1月発行)
特集 脳神経内科医のキャリアパスとリーダーシップ
73巻12号(2021年12月発行)
特集 芸術家と神経学
73巻11号(2021年11月発行)
特集 「目」の神経学
73巻10号(2021年10月発行)
特集 中枢神経・末梢神経の悪性リンパ腫
73巻9号(2021年9月発行)
特集 脳卒中治療に必要な基礎知識
73巻8号(2021年8月発行)
特集 脳腸相関—脳-身体の双方向性制御
73巻7号(2021年7月発行)
特集 グリアと神経—相補的な制御系として
73巻6号(2021年6月発行)
特集 Lower Spine Neurology
73巻5号(2021年5月発行)
増大特集 中枢神経の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
73巻4号(2021年4月発行)
特集 片頭痛・群発頭痛治療の新たな夜明け
73巻3号(2021年3月発行)
特集 マルチリンガルブレイン
73巻2号(2021年2月発行)
特集 筋炎と壊死性筋症
73巻1号(2021年1月発行)
特集 Neuro-Oncology
72巻12号(2020年12月発行)
特集 超高齢期の精神神経疾患を診る
72巻11号(2020年11月発行)
増大特集 脳の発振現象—基礎から臨床へ
72巻10号(2020年10月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識
72巻9号(2020年9月発行)
特集 皮質性小脳萎縮症へのアプローチ
72巻8号(2020年8月発行)
特集 サルコイドーシス
72巻7号(2020年7月発行)
増大特集 神経倫理ハンドブック
72巻6号(2020年6月発行)
特集 前頭側頭葉変性症の今日的理解
72巻5号(2020年5月発行)
特集 多発性硬化症の現在と未来
72巻4号(2020年4月発行)
増大特集 神経疾患の診断における落とし穴—誤診を避けるために
72巻3号(2020年3月発行)
特集 でこぼこの脳の中でおしくらまんじゅうする脳機能
72巻2号(2020年2月発行)
特集 αシヌクレイノパチーの新たな展開
72巻1号(2020年1月発行)
特集 神経難病をクスリで治す—薬物開発の現況と近未来への展望
71巻12号(2019年12月発行)
特集 小脳と大脳—Masao Itoのレガシー
71巻11号(2019年11月発行)
増大特集 ALS2019
71巻10号(2019年10月発行)
特集 認知症と遺伝
71巻9号(2019年9月発行)
特集 神経疾患のドラッグ・リポジショニング—新時代へ
71巻8号(2019年8月発行)
特集 パーキンソン病診療の現在地—200年の変遷と新規治療
71巻7号(2019年7月発行)
増大特集 人工知能と神経科学
71巻6号(2019年6月発行)
特集 補体標的治療の現状と展望
71巻5号(2019年5月発行)
特集 NPSLE
71巻4号(2019年4月発行)
増大特集 神経学のための皮膚アトラス
71巻3号(2019年3月発行)
特集 Spine Neurology
71巻2号(2019年2月発行)
特集 “スポーツ”を生み出す脳
71巻1号(2019年1月発行)
特集 人工知能の医療応用Update
70巻12号(2018年12月発行)
特集 主訴に沿う—俯瞰し収束する画像診断の目
70巻11号(2018年11月発行)
増大特集 脳科学で解き明かす精神神経症候
70巻10号(2018年10月発行)
特集 「左脳と右脳」の現在
70巻9号(2018年9月発行)
特集 脳神経内科診療に役立つ精神科の知識
70巻8号(2018年8月発行)
特集 レヴィ小体型認知症の新知見
70巻7号(2018年7月発行)
増大特集 記憶と忘却に関わる脳のしくみ—分子機構から健忘の症候まで
70巻6号(2018年6月発行)
特集 芸術を生み出す脳
70巻5号(2018年5月発行)
特集 非アルツハイマー型認知症の病理学
70巻4号(2018年4月発行)
増大特集 Antibody Update 2018
70巻3号(2018年3月発行)
特集 『認知症疾患診療ガイドライン2017』を読み解く
70巻2号(2018年2月発行)
特集 知っておきたい神経感染症
70巻1号(2018年1月発行)
特集 筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群の今
69巻12号(2017年12月発行)
特集 運動異常症をみる—Web動画付録つき
69巻11号(2017年11月発行)
増大特集 こころの時間学の未来
69巻10号(2017年10月発行)
特集 成人てんかん—知っておきたい6つのトピック
69巻9号(2017年9月発行)
特集 ミクログリアと精神・神経疾患
69巻8号(2017年8月発行)
特集 遺伝性脊髄小脳失調症の病態と治療展望
69巻7号(2017年7月発行)
増大特集 あしたのアルツハイマー病治療
69巻6号(2017年6月発行)
特集 局在病変の神経心理学
69巻5号(2017年5月発行)
特集 Voxel-Based Morphometry—体積からわかること
69巻4号(2017年4月発行)
増大特集 ブロードマン領野の現在地
69巻3号(2017年3月発行)
特集 磁気刺激の新たな展開
69巻2号(2017年2月発行)
特集 Stroke-Like Diseases—鑑別時に注意を要する5病態
69巻1号(2017年1月発行)
特集 近年注目されている白質脳症
68巻12号(2016年12月発行)
特集 炎症性神経・筋疾患の新たな展開
68巻11号(2016年11月発行)
増大特集 連合野ハンドブック
68巻10号(2016年10月発行)
特集 アディクション—行動の嗜癖
68巻9号(2016年9月発行)
特集 自己免疫性脳炎・脳症
68巻8号(2016年8月発行)
特集 こころと汗
68巻7号(2016年7月発行)
増大特集 認知症の危険因子と防御因子
68巻6号(2016年6月発行)
特集 脳とフローラ
68巻5号(2016年5月発行)
特集 手の症候学—生理学・解剖学からみた新知見
68巻4号(2016年4月発行)
増大特集 治せる認知症
68巻3号(2016年3月発行)
特集 末梢神経の血管炎
68巻2号(2016年2月発行)
特集 筋疾患の認知機能障害
68巻1号(2016年1月発行)
特集 シャルコー・マリー・トゥース病
67巻12号(2015年12月発行)
特集 視床と高次脳機能
67巻11号(2015年11月発行)
増大特集 ギラン・バレー症候群のすべて—100年の軌跡
67巻10号(2015年10月発行)
特集 非・日常生活の脳科学
67巻9号(2015年9月発行)
特集 酵素補充療法
67巻8号(2015年8月発行)
特集 神経難病の終末期医療
67巻7号(2015年7月発行)
増大特集 神経疾患と感染症update
67巻6号(2015年6月発行)
特集 脳と「質感」
67巻5号(2015年5月発行)
特集 NCSE(非痙攣性てんかん重積状態)
67巻4号(2015年4月発行)
増大特集 大脳皮質vs.大脳白質
67巻3号(2015年3月発行)
特集 中枢神経の血管炎
67巻2号(2015年2月発行)
特集 「食べる」を考える
67巻1号(2015年1月発行)
特集 ニューロトキシコロジー
66巻12号(2014年12月発行)
特集 Orthopaedic Neurology—神経内科と整形外科の狭間で
66巻11号(2014年11月発行)
増大特集 神経症候学は神経学の“魂”である
66巻10号(2014年10月発行)
特集 分子を撃つ 神経疾患治療の新しい水平線
66巻9号(2014年9月発行)
特集 痙縮の臨床神経学
66巻8号(2014年8月発行)
特集 神経系の悪性リンパ腫update
66巻7号(2014年7月発行)
増大特集 アミロイド関連神経疾患のすべて―封入体筋炎からアルツハイマー病まで
66巻6号(2014年6月発行)
特集 ミラーニューロン
66巻5号(2014年5月発行)
特集 アセチルコリンと神経疾患―100年目の現在地
66巻4号(2014年4月発行)
増大特集 タッチ・ビジョン・アクション
66巻3号(2014年3月発行)
特集 神経筋疾患の超音波診断
66巻2号(2014年2月発行)
特集 糖尿病の神経学revisited
66巻1号(2014年1月発行)
特集 日常生活の脳科学
65巻12号(2013年12月発行)
特集 プロテイノパチーの神経病理学
65巻11号(2013年11月発行)
増大特集 Close Encounters―臨床神経学と臨床免疫学の遭遇と未来
65巻10号(2013年10月発行)
特集 神経系の発達メカニズム―最近の話題
65巻9号(2013年9月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である―現状と展望
65巻8号(2013年8月発行)
特集 こころの時間学―現在・過去・未来の起源を求めて
65巻7号(2013年7月発行)
増大特集 あしたの脳梗塞
65巻6号(2013年6月発行)
特集 見せる・仕分ける―脳機能解析の新手法
65巻5号(2013年5月発行)
特集 てんかん―新しいパースペクティブ
65巻4号(2013年4月発行)
増大特集 Antibody Update
65巻3号(2013年3月発行)
特集 次世代シーケンサーによる神経変性疾患の解析と展望
65巻2号(2013年2月発行)
特集 血液脳関門研究の進歩
65巻1号(2013年1月発行)
特集 Corticobasal Syndrome
64巻12号(2012年12月発行)
特集 The Border-Land of Dementia
64巻11号(2012年11月発行)
増大特集 痛みの神経学―末梢神経から脳まで
64巻10号(2012年10月発行)
特集 辺縁系をめぐって
64巻9号(2012年9月発行)
特集 高次脳機能イメージングの脳科学への新展開
64巻8号(2012年8月発行)
特集 線条体の基礎と臨床
64巻7号(2012年7月発行)
増大特集 顔認知の脳内機構
64巻6号(2012年6月発行)
特集 睡眠と覚醒の脳内機構
64巻5号(2012年5月発行)
特集 神経疾患のバイオマーカー
64巻4号(2012年4月発行)
増大特集 パーキンソン病の新しい側面
64巻3号(2012年3月発行)
特集 アカデミアから新規治療の実現へ―トランスレーショナルリサーチの現状
64巻2号(2012年2月発行)
特集 生物学的精神医学の進歩
64巻1号(2012年1月発行)
特集 iPS細胞と神経疾患
63巻12号(2011年12月発行)
特集 神経心理学と画像解析の融合
63巻11号(2011年11月発行)
増大特集 筋疾患update
63巻10号(2011年10月発行)
特集 緩徐進行性高次脳機能障害の病態
63巻9号(2011年9月発行)
特集 脳卒中の最新画像診断
63巻8号(2011年8月発行)
特集 日本人の発見した神経症候
63巻7号(2011年7月発行)
増大特集 神経筋接合部―基礎から臨床まで
63巻6号(2011年6月発行)
特集 ニューロパチー
63巻5号(2011年5月発行)
特集 神経系と血管内リンパ腫
63巻4号(2011年4月発行)
増大特集 てんかんの新しい治療
63巻3号(2011年3月発行)
特集 サイバーナイフ治療
63巻2号(2011年2月発行)
特集 続・日本人の発見した神経疾患
63巻1号(2011年1月発行)
特集 血管腫
62巻12号(2010年12月発行)
特集 頸部頸動脈狭窄症の診断と治療
62巻11号(2010年11月発行)
増大特集 歩行とその異常
62巻10号(2010年10月発行)
特集 ブレインバンク
62巻9号(2010年9月発行)
特集 視神経脊髄炎(NMO)update
62巻8号(2010年8月発行)
特集 辺縁系脳炎
62巻7号(2010年7月発行)
増大特集 アルツハイマー病―研究と診療の進歩
62巻6号(2010年6月発行)
特集 改正臓器移植法の問題点とその対応
62巻5号(2010年5月発行)
特集 神経画像のピットフォール―見落としと読み過ぎ
62巻4号(2010年4月発行)
特集 傍腫瘍性神経筋疾患update
62巻3号(2010年3月発行)
特集 神経回路解析法の最近の進歩
62巻2号(2010年2月発行)
特集 ニューロリハビリテーションの最前線
62巻1号(2010年1月発行)
特集 神経救急
61巻12号(2009年12月発行)
特集 Somatotopy再考
61巻11号(2009年11月発行)
特集 前頭側頭葉変性症
61巻10号(2009年10月発行)
特集 片頭痛の予防療法
61巻9号(2009年9月発行)
特集 脳血管障害治療の進歩
61巻8号(2009年8月発行)
特集 神経・筋疾患の分子標的治療
61巻7号(2009年7月発行)
特集 脳腫瘍研究の最前線―遺伝子解析から治療まで
61巻6号(2009年6月発行)
特集 脊椎・脊髄外科の最近の進歩
61巻5号(2009年5月発行)
特集 Restless legs syndrome
61巻4号(2009年4月発行)
特集 大脳基底核―分子基盤から臨床まで
61巻3号(2009年3月発行)
特集 Microneurography(微小神経電図法)の臨床応用
61巻2号(2009年2月発行)
特集 神経系の再興感染症と輸入感染症
61巻1号(2009年1月発行)
特集 脳神経倫理
60巻12号(2008年12月発行)
特集 痙縮
60巻11号(2008年11月発行)
特集 脳卒中と遺伝子
60巻10号(2008年10月発行)
特集 若年者の脳卒中
60巻9号(2008年9月発行)
特集 知・情・意の神経学
60巻8号(2008年8月発行)
特集 脳硬膜動静脈瘻
60巻7号(2008年7月発行)
増大特集 学習と記憶――基礎と臨床
60巻6号(2008年6月発行)
特集 Crow-深瀬症候群(POEMS症候群)
60巻5号(2008年5月発行)
特集 「痛み」の研究と治療の最前線
60巻4号(2008年4月発行)
増大特集 神経系の発生とその異常
60巻3号(2008年3月発行)
特集 特発性正常圧水頭症(iNPH)―最近の話題
60巻2号(2008年2月発行)
特集 がん治療と神経障害
60巻1号(2008年1月発行)
特集 日本人の発見した神経疾患
59巻12号(2007年12月発行)
特集 損傷神経の再生―温存的治療法の開発
59巻11号(2007年11月発行)
特集 手根管症候群をめぐって
59巻10号(2007年10月発行)
増大特集 ALS―研究と診療の進歩
59巻9号(2007年9月発行)
特集 パーキンソン病の認知機能障害
59巻8号(2007年8月発行)
特集 パーキンソン病の分子遺伝学―最近の知見
59巻7号(2007年7月発行)
増大特集 情報伝達処理におけるグリアの機能と異常
59巻6号(2007年6月発行)
特集 職業性神経障害の新しい展開
59巻5号(2007年5月発行)
特集 脳画像最前線
59巻4号(2007年4月発行)
増大特集 最近注目される脳神経疾患治療の研究
59巻3号(2007年3月発行)
特集 分子イメージング
59巻2号(2007年2月発行)
特集 進行性多巣性白質脳症の新しい展開―PMLが治る時代へ向けて
59巻1号(2007年1月発行)
特集 高次視覚研究の最近の進歩
