「注意」は言語,行為,知覚,記憶,遂行機能などと並んで,ヒトの重要な高次脳機能領域である。また,他の認知機能領域の背景にあるとも言え,「意識」とも密接に関係している。本特集では,注意の神経機構やワーキングメモリとの関連など基礎分野の話題から,各種検査法,半側空間無視や注意欠如多動症の病態,そしてリハビリテーションの進め方など臨床的なトピックまで包括的に取り上げた。注意障害の背景にあるメカニズムを探り,患者の病態の的確な把握,そして効果的な治療につなげてほしい。
雑誌目次
BRAIN and NERVE-神経研究の進歩76巻6号
2024年06月発行
雑誌目次
特集 注意と注意障害
注意の神経機構
著者: 木田哲夫
ページ範囲:P.701 - P.707
注意の神経機構について古くは感覚入力に対するニューロン応答や脳反応が注意により増大することが示され,情報処理モデルや計算モデルが提唱された。その後,注意障害研究と脳画像研究の発展により注意の神経機構は脳機能局在および大規模な脳ネットワークの観点からも理解されるようになった。本総説では,注意の神経機構について古典から最近の進歩まで概説する。
視覚探索における注意と記憶
著者: 澤頭亮 , 田中真樹
ページ範囲:P.709 - P.714
視覚探索の効率を上げるためには,一度見たものを記憶し,再び注意が向かないようにする必要がある。多数の物体の中から標的を探し出す採餌課題中の二度見行動に着目し,短期記憶の容量,忘却率,利用率を定量化する方法を考案した。サルの採餌行動の成績はケタミン投与で低下し,ニコチン投与で向上したが,いずれも短期記憶の利用率の変化を伴っていた。複雑な教示を必要としない本課題を用いれば,さまざまな被験者で作業記憶を定量化できる。
前頭葉と注意のトップダウン制御
著者: 小林俊輔
ページ範囲:P.715 - P.720
注意には,感覚刺激の顕著性に基づくbottom-upの注意と,強さ,割当て,選択性,持続時間などが随意的に制御されるtop-downの注意の二方向性がある。Top-downの注意は主として前頭葉がon-goingの情報処理をモニターすることにより介入が必要な状況を検出し,遂行機能の一部として下位システムの情報処理を操作することで実現されると考えられる。
注意の分類と検査法
著者: 船山道隆
ページ範囲:P.721 - P.725
注意機能の下位分類にはさまざまな分類方法がある。本論では神経心理に適応しやすい下位分類,すなわち,選択性注意,持続性注意,空間性注意,抑制性注意,配分性注意,転換性注意を挙げた。ただ,この分類同士にもオーバーラップが認められる。さらにはワーキングメモリや遂行機能などと重複する機能も多い。われわれの認知活動は注意機能と絡んで行われるため,純粋に特定の注意機能を抽出するのは困難である。
ワーキングメモリ—注意がコントロールする記憶
著者: 坪見博之
ページ範囲:P.727 - P.731
高次認知機能の基盤を担う短期記憶は,容量が厳しく制約されている。そのため,注意をコントロールし,現在の目標に必要な情報のみを選択的に記憶することが必要である。注意のコントロールを内包した短期記憶は,ワーキングメモリと呼ばれている。本論では,ワーキングメモリの心理学的モデルと測定課題を概観し,「適切に」「安定的に」記憶するために,注意のコントロールがいかに重要であるかを論じた。
注意障害に対するリハビリテーション
著者: 豊倉穣
ページ範囲:P.733 - P.741
脳損傷後の注意障害に対する認知リハビリテーションにはエビデンスに基づくガイドラインがいくつか提唱されている。本稿では『脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2023〕』と “INCOG 2.0 Guideline for Cognitive Rehabilitation Following Traumatic Brain Injury, PartII: Attention and Information Processing Speed” を紹介した。疾患により見解の相違はあるが,Attention Process Trainingシリーズ,メタ認知訓練,タイムプレッシャーマネジメント,二重課題訓練などの効果が報告されている。種々の環境調整によっても注意障害の影響を軽減させることができる。
注意障害からみた認知症
著者: 山口晴保 , 山口智晴
ページ範囲:P.743 - P.748
注意はすべての認知機能の基盤となる。特に同時並行処理のような複雑な課題処理に必要な複雑性注意は,認知症の早期から障害され,アルツハイマー型・レヴィ小体型・血管性認知症の諸症状や生活障害,コミュニケーション障害に密接に結びついている。にもかかわらず,「認知症と注意障害」の研究は乏しく,今後は注意障害に着目した研究を進める必要がある。本論では,注意障害に伴う生活障害へのケアについても解説した。
半側空間無視の臨床と神経基盤
著者: 石合純夫
ページ範囲:P.749 - P.754
半側空間無視とは,大脳半球病巣と反対側の刺激に対して,発見して,報告したり,反応したり,その方向を向いたりすることが障害される病態であり,右半球の脳血管疾患後に生じる「左」無視がほとんどである。同名性半盲とは異なり,視線を固定せずに起こる症状であり,多くの日常生活活動で困難を生じる。半側空間無視は,空間性注意の方向性の偏りと,その臨床的表現を顕在化するいくつかの要因が加わって起こると考えられる。
半側空間無視のリハビリテーション
著者: 水野勝広
ページ範囲:P.755 - P.759
脳卒中などでみられる視覚注意障害である半側空間無視は,近年では広範な視覚注意ネットワークの障害と考えられており,その発症には視覚注意ネットワークの半球間バランスの破綻が関わっていると考えられている。一方,その回復には非損傷半球を含めたネットワークによる代償作用が重要であることも明らかになりつつある。このような仮説に基づき,無視の病態理解とリハビリテーション治療の最新の知見について概説した。
注意欠如多動症(ADHD)の症候と病態
著者: 太田晴久
ページ範囲:P.761 - P.765
本邦では成人期になり注意欠如多動症(attention deficit hyperactivity disorder:ADHD)と診断される方が急増している。ADHDの特性は健常発達者との連続性があり,そのときの環境や成長過程によって変動しやすい。特に成人例においては,精神疾患を併存しやすいため,ADHD特性に影響を与えている。ADHDは多様な臨床症状,ヘテロな生物学的な背景を持つ。病態,病因の解明に向けて,RDoC(Research Domain Criteria)的なアプローチに加えて,生物学的に比較的均一なサブカテゴリーに分類する試みが期待される。
総説
α-シヌクレイノパチー患者血液由来α-シヌクレインシードの伝播凝集メカニズム
著者: 奥住文美 , 波田野琢 , 服部信孝
ページ範囲:P.767 - P.772
パーキンソン病(PD)の原因蛋白質であるα-シヌクレイン(α-syn)凝集体は,末梢自律神経から大脳皮質まで広範囲に認められる。α-synは神経回路に沿って伝播すると考えられているが,近年神経回路以外の伝播経路の存在が示唆されている。本論では,神経経路だけでなく,血液などの体液を介した多焦点的なα-synシードの伝播の可能性について概説する。
連載 スーパー臨床神経病理カンファレンス・5
5カ月前から発熱や腎機能の悪化を認め,脳出血をきたした70代女性
著者: 種井善一 , 小野寺康博 , 田中伸哉
ページ範囲:P.773 - P.783
〔主訴〕発熱,腎機能の悪化
〔現病歴〕高血圧症や気管支喘息,糖尿病で内科に通院していた。死亡5カ月前に外科で盲腸癌の手術を受けた。退院2週後より38℃台の発熱を認め,外科を受診した際にCRP 20mg/dLと上昇を指摘された。両耳の疼痛や鼻閉を訴え,同日に耳鼻咽喉科を受診。両側外耳道炎と診断され,ステロイド軟膏を処方されて帰宅した。数日後に,甲状腺乳頭癌術後で定期受診したA病院でもCRP高値を指摘され,精査加療目的に当院内科に入院となった。
原著・過去の論文から学ぶ・3
すぐれたコホート研究のアルゴリズムにふれる
著者: 森啓
ページ範囲:P.785 - P.787
原著との出会い
Bateman RJ, Xiong C, Benzinger TL, Fagan AM, Goate A, et al; Dominantly Inherited Alzheimer Network: clinical and biomarker changes in dominantly inherited Alzheimer's disease. N Engl J Med 367: 795-804, 2012
午前診療を終えた嶋田裕之大阪市立大学老年科・神経内科准教授(当時)がご自身の学舎研究室に戻ることなく,私の研究室に直接立ち寄られた。外来で得られた血液サンプルの分析依頼だと思いお迎えしたが,その日は,New England Journal of Medicine論文1)のコピーを手に熱く語られたことを覚えている。当該のNEJM論文で私にどうこうしろという話ではなかったが,研究情報を先に把握された悔しさもあったのか,即座に理解できなかったためか,「読んでおきますね」との言葉で,お別れした。その夜に,私も嶋田先生と同じ興奮に出会えたのは言うまでもない。
書評
「感染対策60のQ&A」—坂本史衣【著】 フリーアクセス
著者: 山田和範
ページ範囲:P.784 - P.784
コロナ禍を経て,全ての医療従事者は以前にも増して,正しい知識に基づいた感染対策を実践することを求められるようになった。得てして,施設の感染対策では現場と管理側スタッフの行動が乖離していることがある。真面目な管理スタッフほど,無意識に正論を振りかざし,現場スタッフは「感染は現場で起きているんだ!」と言いたい気持ちをこらえ,独自のルールを運用してささやかな抵抗をしていたりする。両者がめざすゴールは同じで「感染から患者さんと医療スタッフを守りたい」はずなのだが……。そしてこの小さな綻びを突いて,感染症やアウトブイレクが発生したりする。このような「現場と管理側スタッフとの行動の乖離」は,突き詰めれば両者の視点がズレていることが原因である。このズレを解消する糸口の1つとなるのが本書である。
一般的にHow to本の記載は,最新で充実した施設が前提となっていることが多く,そうではない(経年が目立ち設備面でも恵まれていない)施設では,「そこまでできないなぁ」と諦めがちである。しかし,本書は,充実した環境での対応のみならず,現在のセッティングでできることにも言及しており,どんな施設・環境であっても感染対策に取り組む上での羅針盤になる。そして,押さえるべきポイントはしっかりと押さえられており,妥協がない部分は小気味よい。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.697 - P.697
欧文目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.698 - P.698
バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.792 - P.792
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.793 - P.793
あとがき フリーアクセス
著者: 虫明元
ページ範囲:P.794 - P.794
注意に関する特集号で,さまざまな注意の神経機構や病態が議論されています。しかし,私は逆に,注意の反対,つまりぼんやりした状態について書いてみたいと思います。本特集の中でも少し触れられていますが,脳は休んでいるように見えるときでも,実際には活発に働いていることがわかっています。このような安静時にも活発に活動している領域は,デフォルト・モード・ネットワークと呼ばれ,計算などの認知作業時には休んでいる一方,休憩しているときに活発になることが特徴です。例えば,試験中など外部の刺激に注意を向けているときには,このネットワークの活動が低下します。しかし,外部の課題から解放されると,このネットワークは再び活発になります。つまり,このネットワークは,活動する領域と休む領域が交互に切り替わるような働きをします。
しかし,このぼんやりとした状態でも,その内容は重要です。ぼんやりとした状態は英語で“マインドワンダリング”と呼ばれ,心がさまざまな方向に飛び回る状態を指します。しかし,心の中のさまざまな考えや感情はコントロールが難しいことがあります。実際,マインドワンダリングの発生頻度や持続時間をモニタリングし,そのときの気持ちも調査した研究があります。その結果,マインドワンダリングが多い人ほど,不安や不満などのネガティブな感情と関連していることが示されました。
基本情報
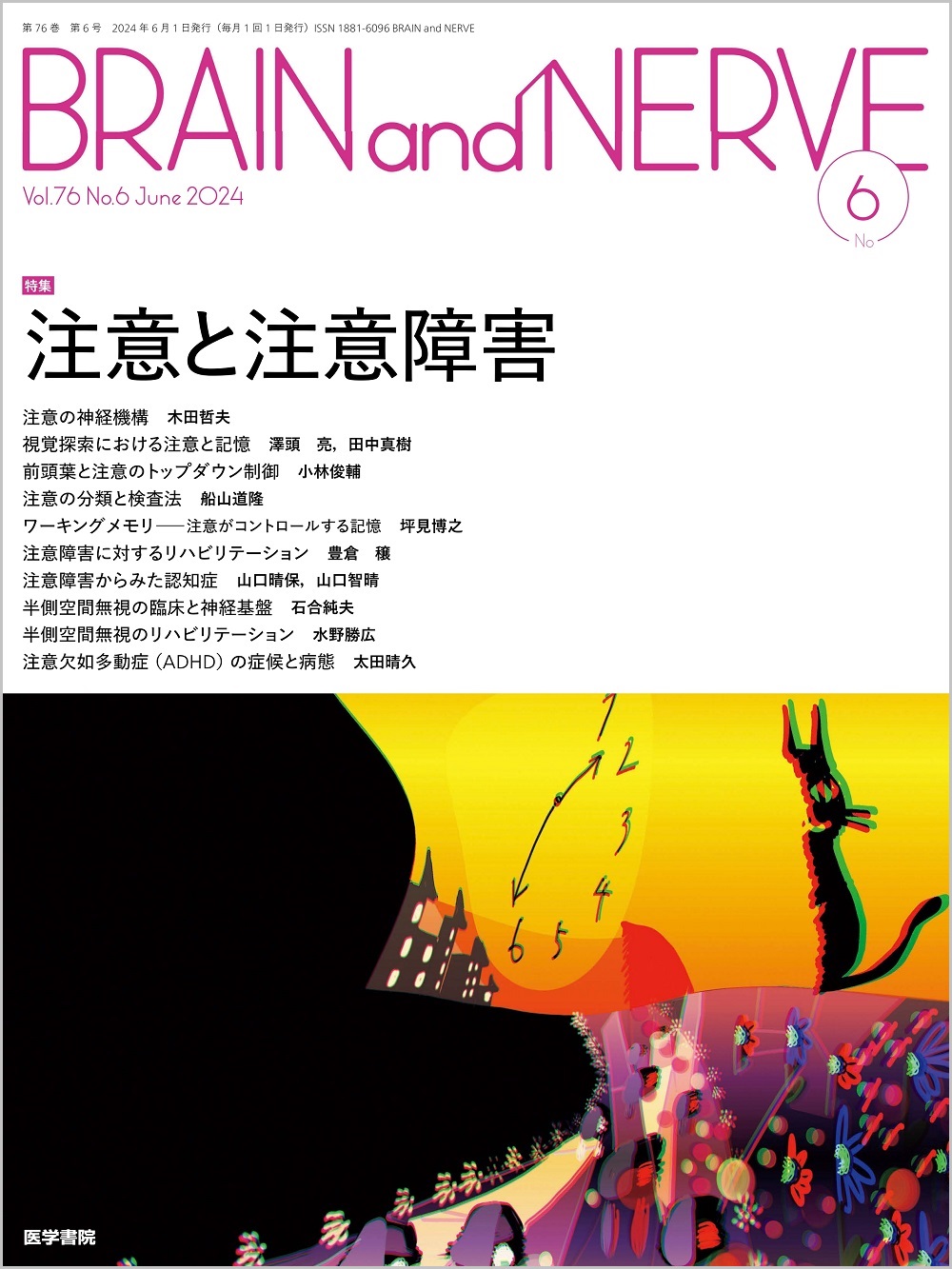
バックナンバー
76巻12号(2024年12月発行)
特集 芸術家と神経学Ⅱ
76巻11号(2024年11月発行)
特集 ALS 2024
76巻10号(2024年10月発行)
特集 どうして効くんだろう
76巻9号(2024年9月発行)
特集 治療可能な認知症としてのアルツハイマー病
76巻8号(2024年8月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である—revisited
76巻7号(2024年7月発行)
特集 ニューロ・バイオイメージング—技術と応用
76巻6号(2024年6月発行)
特集 注意と注意障害
76巻5号(2024年5月発行)
増大特集 末梢神経・筋肉の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
76巻4号(2024年4月発行)
特集 神経病理最前線
76巻3号(2024年3月発行)
特集 きちんと説明ができますか?
76巻2号(2024年2月発行)
特集 特発性正常圧水頭症の現在
76巻1号(2024年1月発行)
特集 新時代の重症筋無力症と関連疾患の診療
75巻12号(2023年12月発行)
特集 アガサ・クリスティーと神経毒
75巻11号(2023年11月発行)
特集 アロスタシス—ホメオスタシスを超えて
75巻10号(2023年10月発行)
特集 メタバースへの招待
75巻9号(2023年9月発行)
特集 妊娠と神経疾患
75巻8号(2023年8月発行)
特集 アルツハイマー病は本当に早期発見できるのか
75巻7号(2023年7月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part2 末梢編
75巻6号(2023年6月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part1 中枢編
75巻5号(2023年5月発行)
増大特集 神経・精神領域の薬剤ハンドブック
75巻4号(2023年4月発行)
特集 All About Epilepsy
75巻3号(2023年3月発行)
特集 慢性疼痛
75巻2号(2023年2月発行)
特集 多系統萎縮症の新診断基準とこれからの診療
75巻1号(2023年1月発行)
特集 よく出会う不随意運動を知る
74巻12号(2022年12月発行)
特集 映画を観て精神・神経疾患を知る
74巻11号(2022年11月発行)
特集 RFC1遺伝子関連スペクトラム障害
74巻10号(2022年10月発行)
特集 ウイルス性脳炎・脳症2022
74巻9号(2022年9月発行)
特集 動的環境への適応系としての歩行
74巻8号(2022年8月発行)
特集 迷走神経の不思議
74巻7号(2022年7月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識2022
74巻6号(2022年6月発行)
特集 脳神経内科医に求められる移行医療
74巻5号(2022年5月発行)
増大特集 次の一手—神経筋疾患難治例をどのように治療するか
74巻4号(2022年4月発行)
特集 脳科学リテラシーを高めるために
74巻3号(2022年3月発行)
特集 中枢性自律神経障害update
74巻2号(2022年2月発行)
特集 温度を感じる脳と身体の科学
74巻1号(2022年1月発行)
特集 脳神経内科医のキャリアパスとリーダーシップ
73巻12号(2021年12月発行)
特集 芸術家と神経学
73巻11号(2021年11月発行)
特集 「目」の神経学
73巻10号(2021年10月発行)
特集 中枢神経・末梢神経の悪性リンパ腫
73巻9号(2021年9月発行)
特集 脳卒中治療に必要な基礎知識
73巻8号(2021年8月発行)
特集 脳腸相関—脳-身体の双方向性制御
73巻7号(2021年7月発行)
特集 グリアと神経—相補的な制御系として
73巻6号(2021年6月発行)
特集 Lower Spine Neurology
73巻5号(2021年5月発行)
増大特集 中枢神経の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
73巻4号(2021年4月発行)
特集 片頭痛・群発頭痛治療の新たな夜明け
73巻3号(2021年3月発行)
特集 マルチリンガルブレイン
73巻2号(2021年2月発行)
特集 筋炎と壊死性筋症
73巻1号(2021年1月発行)
特集 Neuro-Oncology
72巻12号(2020年12月発行)
特集 超高齢期の精神神経疾患を診る
72巻11号(2020年11月発行)
増大特集 脳の発振現象—基礎から臨床へ
72巻10号(2020年10月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識
72巻9号(2020年9月発行)
特集 皮質性小脳萎縮症へのアプローチ
72巻8号(2020年8月発行)
特集 サルコイドーシス
72巻7号(2020年7月発行)
増大特集 神経倫理ハンドブック
72巻6号(2020年6月発行)
特集 前頭側頭葉変性症の今日的理解
72巻5号(2020年5月発行)
特集 多発性硬化症の現在と未来
72巻4号(2020年4月発行)
増大特集 神経疾患の診断における落とし穴—誤診を避けるために
72巻3号(2020年3月発行)
特集 でこぼこの脳の中でおしくらまんじゅうする脳機能
72巻2号(2020年2月発行)
特集 αシヌクレイノパチーの新たな展開
72巻1号(2020年1月発行)
特集 神経難病をクスリで治す—薬物開発の現況と近未来への展望
71巻12号(2019年12月発行)
特集 小脳と大脳—Masao Itoのレガシー
71巻11号(2019年11月発行)
増大特集 ALS2019
71巻10号(2019年10月発行)
特集 認知症と遺伝
71巻9号(2019年9月発行)
特集 神経疾患のドラッグ・リポジショニング—新時代へ
71巻8号(2019年8月発行)
特集 パーキンソン病診療の現在地—200年の変遷と新規治療
71巻7号(2019年7月発行)
増大特集 人工知能と神経科学
71巻6号(2019年6月発行)
特集 補体標的治療の現状と展望
71巻5号(2019年5月発行)
特集 NPSLE
71巻4号(2019年4月発行)
増大特集 神経学のための皮膚アトラス
71巻3号(2019年3月発行)
特集 Spine Neurology
71巻2号(2019年2月発行)
特集 “スポーツ”を生み出す脳
71巻1号(2019年1月発行)
特集 人工知能の医療応用Update
70巻12号(2018年12月発行)
特集 主訴に沿う—俯瞰し収束する画像診断の目
70巻11号(2018年11月発行)
増大特集 脳科学で解き明かす精神神経症候
70巻10号(2018年10月発行)
特集 「左脳と右脳」の現在
70巻9号(2018年9月発行)
特集 脳神経内科診療に役立つ精神科の知識
70巻8号(2018年8月発行)
特集 レヴィ小体型認知症の新知見
70巻7号(2018年7月発行)
増大特集 記憶と忘却に関わる脳のしくみ—分子機構から健忘の症候まで
70巻6号(2018年6月発行)
特集 芸術を生み出す脳
70巻5号(2018年5月発行)
特集 非アルツハイマー型認知症の病理学
70巻4号(2018年4月発行)
増大特集 Antibody Update 2018
70巻3号(2018年3月発行)
特集 『認知症疾患診療ガイドライン2017』を読み解く
70巻2号(2018年2月発行)
特集 知っておきたい神経感染症
70巻1号(2018年1月発行)
特集 筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群の今
69巻12号(2017年12月発行)
特集 運動異常症をみる—Web動画付録つき
69巻11号(2017年11月発行)
増大特集 こころの時間学の未来
69巻10号(2017年10月発行)
特集 成人てんかん—知っておきたい6つのトピック
69巻9号(2017年9月発行)
特集 ミクログリアと精神・神経疾患
69巻8号(2017年8月発行)
特集 遺伝性脊髄小脳失調症の病態と治療展望
69巻7号(2017年7月発行)
増大特集 あしたのアルツハイマー病治療
69巻6号(2017年6月発行)
特集 局在病変の神経心理学
69巻5号(2017年5月発行)
特集 Voxel-Based Morphometry—体積からわかること
69巻4号(2017年4月発行)
増大特集 ブロードマン領野の現在地
69巻3号(2017年3月発行)
特集 磁気刺激の新たな展開
69巻2号(2017年2月発行)
特集 Stroke-Like Diseases—鑑別時に注意を要する5病態
69巻1号(2017年1月発行)
特集 近年注目されている白質脳症
68巻12号(2016年12月発行)
特集 炎症性神経・筋疾患の新たな展開
68巻11号(2016年11月発行)
増大特集 連合野ハンドブック
68巻10号(2016年10月発行)
特集 アディクション—行動の嗜癖
68巻9号(2016年9月発行)
特集 自己免疫性脳炎・脳症
68巻8号(2016年8月発行)
特集 こころと汗
68巻7号(2016年7月発行)
増大特集 認知症の危険因子と防御因子
68巻6号(2016年6月発行)
特集 脳とフローラ
68巻5号(2016年5月発行)
特集 手の症候学—生理学・解剖学からみた新知見
68巻4号(2016年4月発行)
増大特集 治せる認知症
68巻3号(2016年3月発行)
特集 末梢神経の血管炎
68巻2号(2016年2月発行)
特集 筋疾患の認知機能障害
68巻1号(2016年1月発行)
特集 シャルコー・マリー・トゥース病
67巻12号(2015年12月発行)
特集 視床と高次脳機能
67巻11号(2015年11月発行)
増大特集 ギラン・バレー症候群のすべて—100年の軌跡
67巻10号(2015年10月発行)
特集 非・日常生活の脳科学
67巻9号(2015年9月発行)
特集 酵素補充療法
67巻8号(2015年8月発行)
特集 神経難病の終末期医療
67巻7号(2015年7月発行)
増大特集 神経疾患と感染症update
67巻6号(2015年6月発行)
特集 脳と「質感」
67巻5号(2015年5月発行)
特集 NCSE(非痙攣性てんかん重積状態)
67巻4号(2015年4月発行)
増大特集 大脳皮質vs.大脳白質
67巻3号(2015年3月発行)
特集 中枢神経の血管炎
67巻2号(2015年2月発行)
特集 「食べる」を考える
67巻1号(2015年1月発行)
特集 ニューロトキシコロジー
66巻12号(2014年12月発行)
特集 Orthopaedic Neurology—神経内科と整形外科の狭間で
66巻11号(2014年11月発行)
増大特集 神経症候学は神経学の“魂”である
66巻10号(2014年10月発行)
特集 分子を撃つ 神経疾患治療の新しい水平線
66巻9号(2014年9月発行)
特集 痙縮の臨床神経学
66巻8号(2014年8月発行)
特集 神経系の悪性リンパ腫update
66巻7号(2014年7月発行)
増大特集 アミロイド関連神経疾患のすべて―封入体筋炎からアルツハイマー病まで
66巻6号(2014年6月発行)
特集 ミラーニューロン
66巻5号(2014年5月発行)
特集 アセチルコリンと神経疾患―100年目の現在地
66巻4号(2014年4月発行)
増大特集 タッチ・ビジョン・アクション
66巻3号(2014年3月発行)
特集 神経筋疾患の超音波診断
66巻2号(2014年2月発行)
特集 糖尿病の神経学revisited
66巻1号(2014年1月発行)
特集 日常生活の脳科学
65巻12号(2013年12月発行)
特集 プロテイノパチーの神経病理学
65巻11号(2013年11月発行)
増大特集 Close Encounters―臨床神経学と臨床免疫学の遭遇と未来
65巻10号(2013年10月発行)
特集 神経系の発達メカニズム―最近の話題
65巻9号(2013年9月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である―現状と展望
65巻8号(2013年8月発行)
特集 こころの時間学―現在・過去・未来の起源を求めて
65巻7号(2013年7月発行)
増大特集 あしたの脳梗塞
65巻6号(2013年6月発行)
特集 見せる・仕分ける―脳機能解析の新手法
65巻5号(2013年5月発行)
特集 てんかん―新しいパースペクティブ
65巻4号(2013年4月発行)
増大特集 Antibody Update
65巻3号(2013年3月発行)
特集 次世代シーケンサーによる神経変性疾患の解析と展望
65巻2号(2013年2月発行)
特集 血液脳関門研究の進歩
65巻1号(2013年1月発行)
特集 Corticobasal Syndrome
64巻12号(2012年12月発行)
特集 The Border-Land of Dementia
64巻11号(2012年11月発行)
増大特集 痛みの神経学―末梢神経から脳まで
64巻10号(2012年10月発行)
特集 辺縁系をめぐって
64巻9号(2012年9月発行)
特集 高次脳機能イメージングの脳科学への新展開
64巻8号(2012年8月発行)
特集 線条体の基礎と臨床
64巻7号(2012年7月発行)
増大特集 顔認知の脳内機構
64巻6号(2012年6月発行)
特集 睡眠と覚醒の脳内機構
64巻5号(2012年5月発行)
特集 神経疾患のバイオマーカー
64巻4号(2012年4月発行)
増大特集 パーキンソン病の新しい側面
64巻3号(2012年3月発行)
特集 アカデミアから新規治療の実現へ―トランスレーショナルリサーチの現状
64巻2号(2012年2月発行)
特集 生物学的精神医学の進歩
64巻1号(2012年1月発行)
特集 iPS細胞と神経疾患
63巻12号(2011年12月発行)
特集 神経心理学と画像解析の融合
63巻11号(2011年11月発行)
増大特集 筋疾患update
63巻10号(2011年10月発行)
特集 緩徐進行性高次脳機能障害の病態
63巻9号(2011年9月発行)
特集 脳卒中の最新画像診断
63巻8号(2011年8月発行)
特集 日本人の発見した神経症候
63巻7号(2011年7月発行)
増大特集 神経筋接合部―基礎から臨床まで
63巻6号(2011年6月発行)
特集 ニューロパチー
63巻5号(2011年5月発行)
特集 神経系と血管内リンパ腫
63巻4号(2011年4月発行)
増大特集 てんかんの新しい治療
63巻3号(2011年3月発行)
特集 サイバーナイフ治療
63巻2号(2011年2月発行)
特集 続・日本人の発見した神経疾患
63巻1号(2011年1月発行)
特集 血管腫
62巻12号(2010年12月発行)
特集 頸部頸動脈狭窄症の診断と治療
62巻11号(2010年11月発行)
増大特集 歩行とその異常
62巻10号(2010年10月発行)
特集 ブレインバンク
62巻9号(2010年9月発行)
特集 視神経脊髄炎(NMO)update
62巻8号(2010年8月発行)
特集 辺縁系脳炎
62巻7号(2010年7月発行)
増大特集 アルツハイマー病―研究と診療の進歩
62巻6号(2010年6月発行)
特集 改正臓器移植法の問題点とその対応
62巻5号(2010年5月発行)
特集 神経画像のピットフォール―見落としと読み過ぎ
62巻4号(2010年4月発行)
特集 傍腫瘍性神経筋疾患update
62巻3号(2010年3月発行)
特集 神経回路解析法の最近の進歩
62巻2号(2010年2月発行)
特集 ニューロリハビリテーションの最前線
62巻1号(2010年1月発行)
特集 神経救急
61巻12号(2009年12月発行)
特集 Somatotopy再考
61巻11号(2009年11月発行)
特集 前頭側頭葉変性症
61巻10号(2009年10月発行)
特集 片頭痛の予防療法
61巻9号(2009年9月発行)
特集 脳血管障害治療の進歩
61巻8号(2009年8月発行)
特集 神経・筋疾患の分子標的治療
61巻7号(2009年7月発行)
特集 脳腫瘍研究の最前線―遺伝子解析から治療まで
61巻6号(2009年6月発行)
特集 脊椎・脊髄外科の最近の進歩
61巻5号(2009年5月発行)
特集 Restless legs syndrome
61巻4号(2009年4月発行)
特集 大脳基底核―分子基盤から臨床まで
61巻3号(2009年3月発行)
特集 Microneurography(微小神経電図法)の臨床応用
61巻2号(2009年2月発行)
特集 神経系の再興感染症と輸入感染症
61巻1号(2009年1月発行)
特集 脳神経倫理
60巻12号(2008年12月発行)
特集 痙縮
60巻11号(2008年11月発行)
特集 脳卒中と遺伝子
60巻10号(2008年10月発行)
特集 若年者の脳卒中
60巻9号(2008年9月発行)
特集 知・情・意の神経学
60巻8号(2008年8月発行)
特集 脳硬膜動静脈瘻
60巻7号(2008年7月発行)
増大特集 学習と記憶――基礎と臨床
60巻6号(2008年6月発行)
特集 Crow-深瀬症候群(POEMS症候群)
60巻5号(2008年5月発行)
特集 「痛み」の研究と治療の最前線
60巻4号(2008年4月発行)
増大特集 神経系の発生とその異常
60巻3号(2008年3月発行)
特集 特発性正常圧水頭症(iNPH)―最近の話題
60巻2号(2008年2月発行)
特集 がん治療と神経障害
60巻1号(2008年1月発行)
特集 日本人の発見した神経疾患
59巻12号(2007年12月発行)
特集 損傷神経の再生―温存的治療法の開発
59巻11号(2007年11月発行)
特集 手根管症候群をめぐって
59巻10号(2007年10月発行)
増大特集 ALS―研究と診療の進歩
59巻9号(2007年9月発行)
特集 パーキンソン病の認知機能障害
59巻8号(2007年8月発行)
特集 パーキンソン病の分子遺伝学―最近の知見
59巻7号(2007年7月発行)
増大特集 情報伝達処理におけるグリアの機能と異常
59巻6号(2007年6月発行)
特集 職業性神経障害の新しい展開
59巻5号(2007年5月発行)
特集 脳画像最前線
59巻4号(2007年4月発行)
増大特集 最近注目される脳神経疾患治療の研究
59巻3号(2007年3月発行)
特集 分子イメージング
59巻2号(2007年2月発行)
特集 進行性多巣性白質脳症の新しい展開―PMLが治る時代へ向けて
59巻1号(2007年1月発行)
特集 高次視覚研究の最近の進歩
