近年,バイオイメージング分野では,生体をそのままの状態で計測できる技術の発展がめざましく,これまで観察することのできなかった生体内の微細な構造や機能を可視化することで,新たな可能性を切り拓いている。しかしその高度な専門性ゆえに,技術面と応用面の双方を理解するのは容易ではない。そこで本特集では,超解像度の顕微鏡技術,PET,MRI,分子プローブの開発による最近の技術動向と,それらが脳神経系へどのように応用されているかについて,各分野を牽引する研究者にわかりやすく解説していただいた。脳科学,医学とバイオイメージング技術の接点を探究しながら,バイオイメージングの進歩がもたらす未来をともに考える機会としたい。
雑誌目次
BRAIN and NERVE-神経研究の進歩76巻7号
2024年07月発行
雑誌目次
特集 ニューロ・バイオイメージング—技術と応用
2光子顕微鏡による神経活動の多重スケールイメージング
著者: 喜多村和郎
ページ範囲:P.799 - P.805
2光子カルシウムイメージングは,動物の脳における神経活動観察法の1つとして広く用いられている。近年,2光子顕微鏡やカルシウム指示分子の改良などにより高感度化や高速化,広視野化が進み,動物個体脳内に3次元的に存在する神経細胞の活動をマイクロメートルからミリメートルのスケールで大規模に観察することが可能になっている。本論では,これらの新しい2光子観察法とその神経科学へのアプリケーションを紹介する。
2光子超解像顕微鏡法の開発
著者: 堤元佐 , 石井宏和 , 根本知己
ページ範囲:P.807 - P.812
生体組織の深部イメージングを可能にする2光子励起顕微鏡技術は,神経科学の分野を中心にさまざまな医学・生命科学分野の研究への応用が広がっている。一方で,神経細胞の微細形態の観察には従来の2光子励起顕微鏡法では空間分解能が不足しており,研究の足かせになっていた。本論では,近年の筆者らの研究グループにおける成果を示しながら,2つの異なるアプローチによる2光子励起超解像顕微鏡法の開発について紹介する。
PETイメージングによる生体機能の解析
著者: 崔翼龍
ページ範囲:P.813 - P.819
PETイメージングは,非侵襲的に体外から標的分子の時空間的な動態変化を高い感度で定量評価できるイメージング技術である。本論では,PETイメージングの基本原理,高い感度や定量性について解説し,PETイメージングを基軸とした統合的な方法論を用いた精神神経活動の神経生物学的基盤の解明,さらには薬物動態解析やセラノスティックスなど新規医薬品開発への展開について概説した。
MRIによる非侵襲的な神経回路活動イメージング技術
著者: 尾上浩隆
ページ範囲:P.821 - P.826
脳は複雑なネットワークであり,特殊な機能を持つ解剖学的に異なる脳領域が互いに協力し合い,さまざまな認知プロセスを支えている。したがって,ネットワークの観点から脳を理解することは非常に重要である。機能的磁気共鳴画像法(functional MRI:fMRI)は,脳の機能に関する豊富な情報を提供する技術として急速に普及,発展している。特に安静時(resting-state)fMRI(rsfMRI)は,タスクがないときの脳活動をマッピングするfMRIの中核技術の1つである。rsfMRIは,データ収集が容易で,非侵襲的であり,自発的な神経活動から洞察に満ちた信号を得られることから,さまざまなヒトの疾患に応用されている。機能的に相関のある領域を包含する脳機能ネットワークは,通常,機能的結合性(FC)として示される。rsfMRIデータのFC解析によって,いくつかの内在的な安静時ネットワーク(RSN)や,精神疾患の患者の異常なネットワーク構造の証拠など多くの情報と知識が明らかになっている。ネットワーク情報は脳についての理解を深めるだけでなく,精神疾患,神経変性疾患がもたらすネットワーク変異の評価に有用である。
定量的活動依存性マンガン造影MRIの原理とその応用
著者: 小山内実
ページ範囲:P.827 - P.834
脳機能発現メカニズムを解明するためには,機能発現に伴って活動が変化する領域を同定する必要がある。このための非侵襲全脳神経活動履歴イメージング法が,定量的活動依存性マンガン造影MRI(qAIM-MRI)である。qAIM-MRIはMn2+をCa2+の代理マーカーとして利用する擬似Ca2+イメージング法である。本論ではqAIM-MRIの原理とその応用例およびこの手法の限界を解説する。
光で細胞の活動を操作する「ロドプシンの選び方」
著者: 細島頌子 , 神取秀樹
ページ範囲:P.835 - P.842
光で細胞の活動を操作し,さらに光で計測する時代が到来した。オプトジェネティクス(光遺伝学)は,細胞の活動を光で操作する技術である。代表的な光遺伝学ツールとして藻類などが持つ微生物ロドプシンが挙げられる。近年,新たな機能を持った微生物ロドプシンの発見が相次ぎ,多様性は爆発的に拡がった。ここでは光遺伝学ツールとして使われている微生物ロドプシンの特徴や,最新の研究について紹介する。
Hyperscanning fMRIによる社会能力神経基盤へのアプローチ
著者: 定藤規弘
ページ範囲:P.843 - P.850
Hyperscanning fMRIは社会能力の神経基盤探求を動機として開発された。複数被験者の脳活動を同時に撮像することにより,リアルタイムの相互作用やコミュニケーションの神経基盤を解析することが可能となった。個体に還元できない現象としての個体間同期を始めとして,社会的な相互作用の神経基盤を明らかにする方法であり,私たちの生活の大部分を占める社会的相互作用を支える神経メカニズムの研究を可能にしつつある。従前の個体と環境の間の相互作用としての「一人称」の脳科学から,個人間の関係性を脳科学的手法で研究するという意味での「二人称」の脳科学へと展開するうえで,重要な方法論の1つとなり得る。開発の背景,現状と将来展望について概説する。
超高磁場MRIの中枢神経系への応用
著者: 吉岡芳親
ページ範囲:P.851 - P.861
MRI装置の高性能化を目指した開発において,最も重要であるのは基盤となる静磁場の超高磁場化である。超高磁場化には,ハード的にも,ソフト的にも,予算的にも難しい点があるが,超高磁場においてようやく得られると思われる情報もある。本論では,超高磁場化でもたらされる効果を概説し,超高磁場での利点を生かして得られた画像やスペクトルについて解説する。
総説
ベンチャーサイエンティストのすすめ
著者: 藤井直敬
ページ範囲:P.863 - P.868
日本の基礎研究者はこれまで経済的な実益を求めず,科学への奉仕に専念することが美徳だとされてきた。しかし,研究者がベンチャーマインドを持ち,研究成果を社会実装へつなげ,事業を通じ社会貢献することは現代社会の要請である。本論を通じて,社会と研究者の間にある 「死の谷」を超え,科学とビジネスの接点を創出し,研究成果を社会に還元し,新しい産業を生み出すベンチャーサイエンティストとしての生き方と挑戦を推奨する。
連載 スーパー臨床神経病理カンファレンス・6
認知機能障害に加えて歩行障害を呈するパーキンソニズムを認めた89歳男性
著者: 木村朴 , 河上緒 , 池田研二 , 永倉暁人 , 加藤忠史 , 大島健一
ページ範囲:P.869 - P.874
〔現病歴〕86歳頃,認知症の妻と老老介護で二人暮らしの生活をしていた時点より,生活機能低下が疑われていた。88歳時,妻,本人の脱水状態による入院を契機に妻は高齢者施設入所となり,本人は独居となった。その後,介護拒否や暴言が強まり88歳時に認知症専門の診療所を受診し,認知症の診断のもと,BPSD(behavioral and psychological symptoms of dementia)に対してブレクスピプラゾール1mgが開始された。
89歳時には脱水状態と転倒を繰り返しており前医へ入院となった。これまでの処方に替わり,リスペリドン4mgが開始された。前医脳神経内科にて神経学的所見「中等度の動作緩慢,両側上肢の筋強剛,体幹失調」と評価された。Mini-Mental State Examination 16/30点であったが遅延再生は保たれていた。
原著・過去の論文から学ぶ・4
知覚対側転位症候の原著を探る
著者: 河村満
ページ範囲:P.875 - P.880
Lapidous R: De L'allochirie: Thèse pour le doctorat en medicine. Jouve et Boyer, Paris, 1899(Fig. 1)
知覚対側転位/知覚転位(allochiria)
知覚対側転位/知覚転位(以下知覚対側転位)は,体の片側に与えた感覚刺激を刺激の反対側の同部位に感じるという実に奇妙な現象である(Fig. 2)1,2)。この症候を初めて診たのは1981(昭和56)年であった。千葉大学神経内科の病棟が開設されたのが1978(昭和53)年10月で,その創設と同時に入局した筆者はまず大学病院で2年間病棟受け持ち医としていろいろな神経疾患を経験し,その後やはり開設して間もない千葉県救急医療センターに1年後輩の同僚と一緒に赴任した。
この病院は脳疾患と循環器疾患にほぼ特化した3次救急病院であり,脳神経内科医の赴任は初めてであったが,脳神経外科医は既に4人いた。病院にⅩ線CTはあったが,MRIはまだなかった。救急車で運ばれてくる患者の多くが脳出血であり,知覚対側転位は脳出血123例中20例にみられ,その多くが右被殻出血であった。東京都と千葉県を結ぶ湾岸道路ができた頃でもあり,交通外傷特に頭部外傷が多く非常に多忙であったが,大学ではまったく経験することのなかったさまざまな神経疾患症例を次々に経験することができ毎日の診療が楽しく,充実感でいっぱいであった。その後,この病院での臨床経験をいくつも論文にすることになるのだが,振り返ればそれはひとえに恩師平山惠造先生をはじめとした多くの医局メンバーの指導やサポートのおかげであり,いま改めて感謝の念を強くしている。
LETTERS
ALSの分子病理最前線—TDP-43とStathmin2のクロストーク
著者: 森望
ページ範囲:P.881 - P.883
本誌2024年4月号の特集は「神経病理最前線」,3月号は「きちんと説明ができますか?」であった。私事ながら,長年「老化脳」研究をしつつも定年を迎えると,さすがに客観的な老化研究だけでなく自身の「老化脳」にも関心が向く。これまでは「生理的な」老化に関心があったが,「病理的な」老化も気になり出した。アルツハイマー病(Alzheimer's disease:AD)やパーキンソン病に他の認知症など,その背景にある神経病変をきちんと説明できるか,これら特集号の啓発に刺激されながら,加齢依存性の神経変性病理を説明してみようと,自らの研究史(の一端)1)を振り返りながら考えてみた。
進行性の重篤な神経変性疾患である筋萎縮性側索硬化症(amyotrophic lateral sclerosis:ALS)の神経病理ではRNA結合蛋白質であるTDP-43の病理像が知られて久しい2)。TDP-43は本来神経細胞の核内で機能するものだが,ALS患者の組織では運動神経細胞の細胞質に封入体を形成して隔離され,核内機能が損なわれる。
お知らせ
「公益財団法人日本脳神経財団2024年度寺岡賞」募集 フリーアクセス
ページ範囲:P.880 - P.880
公益財団法人日本脳神経財団では下記の通り,寺岡賞の募集を行います。財団のHP(https://jbf.or.jp)の「各種助成申請のご案内」で要項をご確認のうえ,申請してください。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.795 - P.795
欧文目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.796 - P.796
バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.888 - P.888
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.889 - P.889
あとがき フリーアクセス
著者: 三村將
ページ範囲:P.890 - P.890
1980年代の終わりに精神科病院に勤務していた頃,不思議な認知症の患者さんを担当した。家事がうまくこなせず,テレビのニュースにも関心を示さなくなり,前医でアルツハイマー病と診断されていた。しかし,発話が極端に減少し,さらに構語障害や嚥下障害も認めるようになり,普通のアルツハイマー病とは思えなかった。両上肢の筋力が低下し,舌や母指球にも萎縮を認め,両腕をだらんと下げて背中を丸めながら病棟をすたすたと歩く姿は特徴的であった。認知症に運動ニューロン病を合併しているのだろうかと思って悩んでいたら,神経病理をご指導いただいていた故・加藤雄司先生から宮崎の三山吉夫先生の論文を教えていただき,目からうろこが落ちたような思いをした(Mitsuyama Y and Takamiya S. Arch Neurol, 1979)。いわゆる三山型の「運動ニューロン病を伴う初老期痴呆」である。今でこそALS/FTLDとしてよく知られた概念であるが,当時はそのような例を経験した人はまわりにいなかった。三山先生がnew entity?とされていたことが印象深く,やはりアルツハイマー病ではないのだと納得した次第であった。こういう症例は続くときは続くもので,故・小阪憲司先生にもご指導いただきながら,だいぶ遅れたが,合わせて3例の臨床病理経過を報告させていただいた(Mimura M, et al. Neuropathology, 1998)。
基本情報
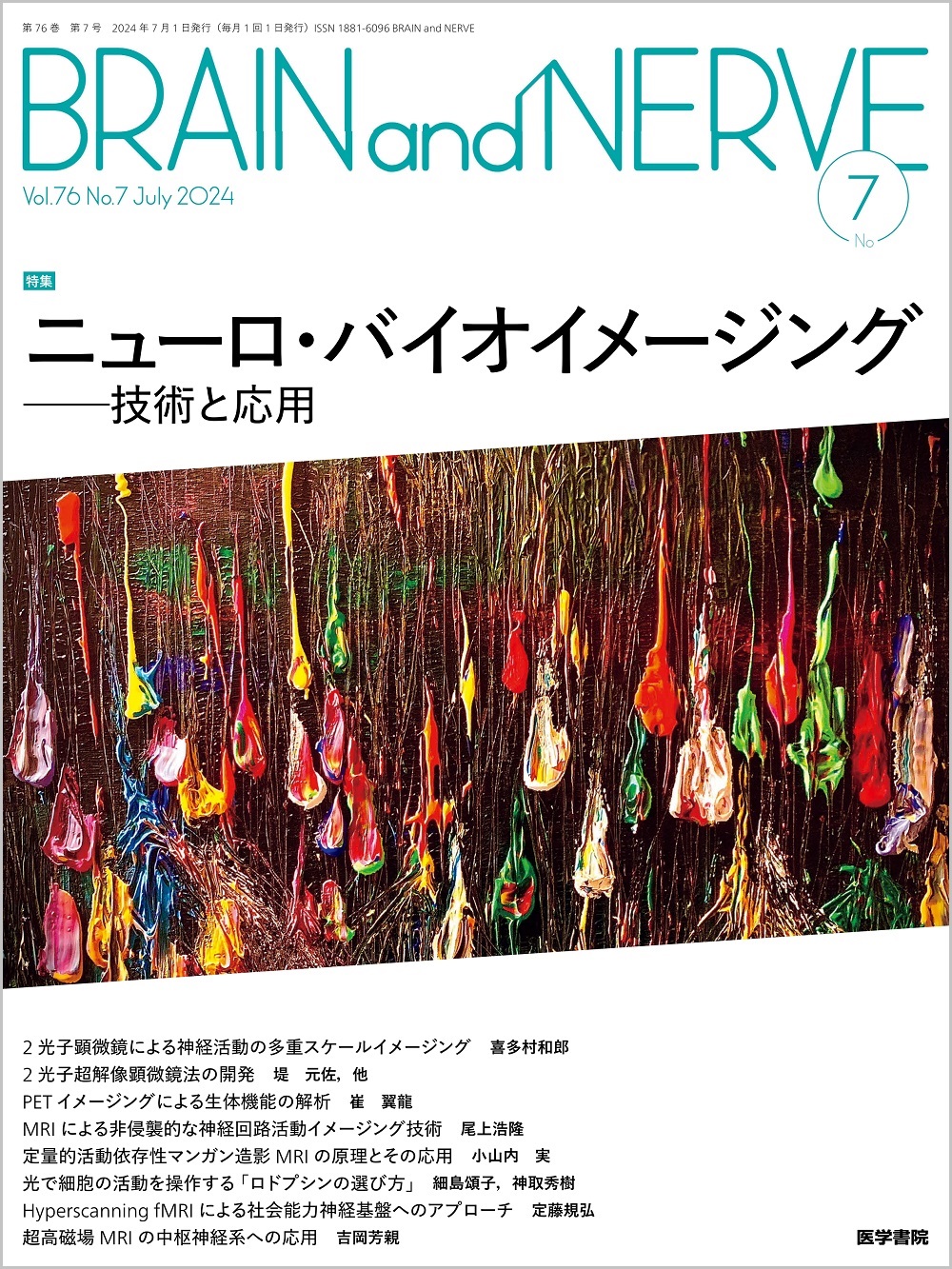
バックナンバー
76巻12号(2024年12月発行)
特集 芸術家と神経学Ⅱ
76巻11号(2024年11月発行)
特集 ALS 2024
76巻10号(2024年10月発行)
特集 どうして効くんだろう
76巻9号(2024年9月発行)
特集 治療可能な認知症としてのアルツハイマー病
76巻8号(2024年8月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である—revisited
76巻7号(2024年7月発行)
特集 ニューロ・バイオイメージング—技術と応用
76巻6号(2024年6月発行)
特集 注意と注意障害
76巻5号(2024年5月発行)
増大特集 末梢神経・筋肉の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
76巻4号(2024年4月発行)
特集 神経病理最前線
76巻3号(2024年3月発行)
特集 きちんと説明ができますか?
76巻2号(2024年2月発行)
特集 特発性正常圧水頭症の現在
76巻1号(2024年1月発行)
特集 新時代の重症筋無力症と関連疾患の診療
75巻12号(2023年12月発行)
特集 アガサ・クリスティーと神経毒
75巻11号(2023年11月発行)
特集 アロスタシス—ホメオスタシスを超えて
75巻10号(2023年10月発行)
特集 メタバースへの招待
75巻9号(2023年9月発行)
特集 妊娠と神経疾患
75巻8号(2023年8月発行)
特集 アルツハイマー病は本当に早期発見できるのか
75巻7号(2023年7月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part2 末梢編
75巻6号(2023年6月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part1 中枢編
75巻5号(2023年5月発行)
増大特集 神経・精神領域の薬剤ハンドブック
75巻4号(2023年4月発行)
特集 All About Epilepsy
75巻3号(2023年3月発行)
特集 慢性疼痛
75巻2号(2023年2月発行)
特集 多系統萎縮症の新診断基準とこれからの診療
75巻1号(2023年1月発行)
特集 よく出会う不随意運動を知る
74巻12号(2022年12月発行)
特集 映画を観て精神・神経疾患を知る
74巻11号(2022年11月発行)
特集 RFC1遺伝子関連スペクトラム障害
74巻10号(2022年10月発行)
特集 ウイルス性脳炎・脳症2022
74巻9号(2022年9月発行)
特集 動的環境への適応系としての歩行
74巻8号(2022年8月発行)
特集 迷走神経の不思議
74巻7号(2022年7月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識2022
74巻6号(2022年6月発行)
特集 脳神経内科医に求められる移行医療
74巻5号(2022年5月発行)
増大特集 次の一手—神経筋疾患難治例をどのように治療するか
74巻4号(2022年4月発行)
特集 脳科学リテラシーを高めるために
74巻3号(2022年3月発行)
特集 中枢性自律神経障害update
74巻2号(2022年2月発行)
特集 温度を感じる脳と身体の科学
74巻1号(2022年1月発行)
特集 脳神経内科医のキャリアパスとリーダーシップ
73巻12号(2021年12月発行)
特集 芸術家と神経学
73巻11号(2021年11月発行)
特集 「目」の神経学
73巻10号(2021年10月発行)
特集 中枢神経・末梢神経の悪性リンパ腫
73巻9号(2021年9月発行)
特集 脳卒中治療に必要な基礎知識
73巻8号(2021年8月発行)
特集 脳腸相関—脳-身体の双方向性制御
73巻7号(2021年7月発行)
特集 グリアと神経—相補的な制御系として
73巻6号(2021年6月発行)
特集 Lower Spine Neurology
73巻5号(2021年5月発行)
増大特集 中枢神経の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
73巻4号(2021年4月発行)
特集 片頭痛・群発頭痛治療の新たな夜明け
73巻3号(2021年3月発行)
特集 マルチリンガルブレイン
73巻2号(2021年2月発行)
特集 筋炎と壊死性筋症
73巻1号(2021年1月発行)
特集 Neuro-Oncology
72巻12号(2020年12月発行)
特集 超高齢期の精神神経疾患を診る
72巻11号(2020年11月発行)
増大特集 脳の発振現象—基礎から臨床へ
72巻10号(2020年10月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識
72巻9号(2020年9月発行)
特集 皮質性小脳萎縮症へのアプローチ
72巻8号(2020年8月発行)
特集 サルコイドーシス
72巻7号(2020年7月発行)
増大特集 神経倫理ハンドブック
72巻6号(2020年6月発行)
特集 前頭側頭葉変性症の今日的理解
72巻5号(2020年5月発行)
特集 多発性硬化症の現在と未来
72巻4号(2020年4月発行)
増大特集 神経疾患の診断における落とし穴—誤診を避けるために
72巻3号(2020年3月発行)
特集 でこぼこの脳の中でおしくらまんじゅうする脳機能
72巻2号(2020年2月発行)
特集 αシヌクレイノパチーの新たな展開
72巻1号(2020年1月発行)
特集 神経難病をクスリで治す—薬物開発の現況と近未来への展望
71巻12号(2019年12月発行)
特集 小脳と大脳—Masao Itoのレガシー
71巻11号(2019年11月発行)
増大特集 ALS2019
71巻10号(2019年10月発行)
特集 認知症と遺伝
71巻9号(2019年9月発行)
特集 神経疾患のドラッグ・リポジショニング—新時代へ
71巻8号(2019年8月発行)
特集 パーキンソン病診療の現在地—200年の変遷と新規治療
71巻7号(2019年7月発行)
増大特集 人工知能と神経科学
71巻6号(2019年6月発行)
特集 補体標的治療の現状と展望
71巻5号(2019年5月発行)
特集 NPSLE
71巻4号(2019年4月発行)
増大特集 神経学のための皮膚アトラス
71巻3号(2019年3月発行)
特集 Spine Neurology
71巻2号(2019年2月発行)
特集 “スポーツ”を生み出す脳
71巻1号(2019年1月発行)
特集 人工知能の医療応用Update
70巻12号(2018年12月発行)
特集 主訴に沿う—俯瞰し収束する画像診断の目
70巻11号(2018年11月発行)
増大特集 脳科学で解き明かす精神神経症候
70巻10号(2018年10月発行)
特集 「左脳と右脳」の現在
70巻9号(2018年9月発行)
特集 脳神経内科診療に役立つ精神科の知識
70巻8号(2018年8月発行)
特集 レヴィ小体型認知症の新知見
70巻7号(2018年7月発行)
増大特集 記憶と忘却に関わる脳のしくみ—分子機構から健忘の症候まで
70巻6号(2018年6月発行)
特集 芸術を生み出す脳
70巻5号(2018年5月発行)
特集 非アルツハイマー型認知症の病理学
70巻4号(2018年4月発行)
増大特集 Antibody Update 2018
70巻3号(2018年3月発行)
特集 『認知症疾患診療ガイドライン2017』を読み解く
70巻2号(2018年2月発行)
特集 知っておきたい神経感染症
70巻1号(2018年1月発行)
特集 筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群の今
69巻12号(2017年12月発行)
特集 運動異常症をみる—Web動画付録つき
69巻11号(2017年11月発行)
増大特集 こころの時間学の未来
69巻10号(2017年10月発行)
特集 成人てんかん—知っておきたい6つのトピック
69巻9号(2017年9月発行)
特集 ミクログリアと精神・神経疾患
69巻8号(2017年8月発行)
特集 遺伝性脊髄小脳失調症の病態と治療展望
69巻7号(2017年7月発行)
増大特集 あしたのアルツハイマー病治療
69巻6号(2017年6月発行)
特集 局在病変の神経心理学
69巻5号(2017年5月発行)
特集 Voxel-Based Morphometry—体積からわかること
69巻4号(2017年4月発行)
増大特集 ブロードマン領野の現在地
69巻3号(2017年3月発行)
特集 磁気刺激の新たな展開
69巻2号(2017年2月発行)
特集 Stroke-Like Diseases—鑑別時に注意を要する5病態
69巻1号(2017年1月発行)
特集 近年注目されている白質脳症
68巻12号(2016年12月発行)
特集 炎症性神経・筋疾患の新たな展開
68巻11号(2016年11月発行)
増大特集 連合野ハンドブック
68巻10号(2016年10月発行)
特集 アディクション—行動の嗜癖
68巻9号(2016年9月発行)
特集 自己免疫性脳炎・脳症
68巻8号(2016年8月発行)
特集 こころと汗
68巻7号(2016年7月発行)
増大特集 認知症の危険因子と防御因子
68巻6号(2016年6月発行)
特集 脳とフローラ
68巻5号(2016年5月発行)
特集 手の症候学—生理学・解剖学からみた新知見
68巻4号(2016年4月発行)
増大特集 治せる認知症
68巻3号(2016年3月発行)
特集 末梢神経の血管炎
68巻2号(2016年2月発行)
特集 筋疾患の認知機能障害
68巻1号(2016年1月発行)
特集 シャルコー・マリー・トゥース病
67巻12号(2015年12月発行)
特集 視床と高次脳機能
67巻11号(2015年11月発行)
増大特集 ギラン・バレー症候群のすべて—100年の軌跡
67巻10号(2015年10月発行)
特集 非・日常生活の脳科学
67巻9号(2015年9月発行)
特集 酵素補充療法
67巻8号(2015年8月発行)
特集 神経難病の終末期医療
67巻7号(2015年7月発行)
増大特集 神経疾患と感染症update
67巻6号(2015年6月発行)
特集 脳と「質感」
67巻5号(2015年5月発行)
特集 NCSE(非痙攣性てんかん重積状態)
67巻4号(2015年4月発行)
増大特集 大脳皮質vs.大脳白質
67巻3号(2015年3月発行)
特集 中枢神経の血管炎
67巻2号(2015年2月発行)
特集 「食べる」を考える
67巻1号(2015年1月発行)
特集 ニューロトキシコロジー
66巻12号(2014年12月発行)
特集 Orthopaedic Neurology—神経内科と整形外科の狭間で
66巻11号(2014年11月発行)
増大特集 神経症候学は神経学の“魂”である
66巻10号(2014年10月発行)
特集 分子を撃つ 神経疾患治療の新しい水平線
66巻9号(2014年9月発行)
特集 痙縮の臨床神経学
66巻8号(2014年8月発行)
特集 神経系の悪性リンパ腫update
66巻7号(2014年7月発行)
増大特集 アミロイド関連神経疾患のすべて―封入体筋炎からアルツハイマー病まで
66巻6号(2014年6月発行)
特集 ミラーニューロン
66巻5号(2014年5月発行)
特集 アセチルコリンと神経疾患―100年目の現在地
66巻4号(2014年4月発行)
増大特集 タッチ・ビジョン・アクション
66巻3号(2014年3月発行)
特集 神経筋疾患の超音波診断
66巻2号(2014年2月発行)
特集 糖尿病の神経学revisited
66巻1号(2014年1月発行)
特集 日常生活の脳科学
65巻12号(2013年12月発行)
特集 プロテイノパチーの神経病理学
65巻11号(2013年11月発行)
増大特集 Close Encounters―臨床神経学と臨床免疫学の遭遇と未来
65巻10号(2013年10月発行)
特集 神経系の発達メカニズム―最近の話題
65巻9号(2013年9月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である―現状と展望
65巻8号(2013年8月発行)
特集 こころの時間学―現在・過去・未来の起源を求めて
65巻7号(2013年7月発行)
増大特集 あしたの脳梗塞
65巻6号(2013年6月発行)
特集 見せる・仕分ける―脳機能解析の新手法
65巻5号(2013年5月発行)
特集 てんかん―新しいパースペクティブ
65巻4号(2013年4月発行)
増大特集 Antibody Update
65巻3号(2013年3月発行)
特集 次世代シーケンサーによる神経変性疾患の解析と展望
65巻2号(2013年2月発行)
特集 血液脳関門研究の進歩
65巻1号(2013年1月発行)
特集 Corticobasal Syndrome
64巻12号(2012年12月発行)
特集 The Border-Land of Dementia
64巻11号(2012年11月発行)
増大特集 痛みの神経学―末梢神経から脳まで
64巻10号(2012年10月発行)
特集 辺縁系をめぐって
64巻9号(2012年9月発行)
特集 高次脳機能イメージングの脳科学への新展開
64巻8号(2012年8月発行)
特集 線条体の基礎と臨床
64巻7号(2012年7月発行)
増大特集 顔認知の脳内機構
64巻6号(2012年6月発行)
特集 睡眠と覚醒の脳内機構
64巻5号(2012年5月発行)
特集 神経疾患のバイオマーカー
64巻4号(2012年4月発行)
増大特集 パーキンソン病の新しい側面
64巻3号(2012年3月発行)
特集 アカデミアから新規治療の実現へ―トランスレーショナルリサーチの現状
64巻2号(2012年2月発行)
特集 生物学的精神医学の進歩
64巻1号(2012年1月発行)
特集 iPS細胞と神経疾患
63巻12号(2011年12月発行)
特集 神経心理学と画像解析の融合
63巻11号(2011年11月発行)
増大特集 筋疾患update
63巻10号(2011年10月発行)
特集 緩徐進行性高次脳機能障害の病態
63巻9号(2011年9月発行)
特集 脳卒中の最新画像診断
63巻8号(2011年8月発行)
特集 日本人の発見した神経症候
63巻7号(2011年7月発行)
増大特集 神経筋接合部―基礎から臨床まで
63巻6号(2011年6月発行)
特集 ニューロパチー
63巻5号(2011年5月発行)
特集 神経系と血管内リンパ腫
63巻4号(2011年4月発行)
増大特集 てんかんの新しい治療
63巻3号(2011年3月発行)
特集 サイバーナイフ治療
63巻2号(2011年2月発行)
特集 続・日本人の発見した神経疾患
63巻1号(2011年1月発行)
特集 血管腫
62巻12号(2010年12月発行)
特集 頸部頸動脈狭窄症の診断と治療
62巻11号(2010年11月発行)
増大特集 歩行とその異常
62巻10号(2010年10月発行)
特集 ブレインバンク
62巻9号(2010年9月発行)
特集 視神経脊髄炎(NMO)update
62巻8号(2010年8月発行)
特集 辺縁系脳炎
62巻7号(2010年7月発行)
増大特集 アルツハイマー病―研究と診療の進歩
62巻6号(2010年6月発行)
特集 改正臓器移植法の問題点とその対応
62巻5号(2010年5月発行)
特集 神経画像のピットフォール―見落としと読み過ぎ
62巻4号(2010年4月発行)
特集 傍腫瘍性神経筋疾患update
62巻3号(2010年3月発行)
特集 神経回路解析法の最近の進歩
62巻2号(2010年2月発行)
特集 ニューロリハビリテーションの最前線
62巻1号(2010年1月発行)
特集 神経救急
61巻12号(2009年12月発行)
特集 Somatotopy再考
61巻11号(2009年11月発行)
特集 前頭側頭葉変性症
61巻10号(2009年10月発行)
特集 片頭痛の予防療法
61巻9号(2009年9月発行)
特集 脳血管障害治療の進歩
61巻8号(2009年8月発行)
特集 神経・筋疾患の分子標的治療
61巻7号(2009年7月発行)
特集 脳腫瘍研究の最前線―遺伝子解析から治療まで
61巻6号(2009年6月発行)
特集 脊椎・脊髄外科の最近の進歩
61巻5号(2009年5月発行)
特集 Restless legs syndrome
61巻4号(2009年4月発行)
特集 大脳基底核―分子基盤から臨床まで
61巻3号(2009年3月発行)
特集 Microneurography(微小神経電図法)の臨床応用
61巻2号(2009年2月発行)
特集 神経系の再興感染症と輸入感染症
61巻1号(2009年1月発行)
特集 脳神経倫理
60巻12号(2008年12月発行)
特集 痙縮
60巻11号(2008年11月発行)
特集 脳卒中と遺伝子
60巻10号(2008年10月発行)
特集 若年者の脳卒中
60巻9号(2008年9月発行)
特集 知・情・意の神経学
60巻8号(2008年8月発行)
特集 脳硬膜動静脈瘻
60巻7号(2008年7月発行)
増大特集 学習と記憶――基礎と臨床
60巻6号(2008年6月発行)
特集 Crow-深瀬症候群(POEMS症候群)
60巻5号(2008年5月発行)
特集 「痛み」の研究と治療の最前線
60巻4号(2008年4月発行)
増大特集 神経系の発生とその異常
60巻3号(2008年3月発行)
特集 特発性正常圧水頭症(iNPH)―最近の話題
60巻2号(2008年2月発行)
特集 がん治療と神経障害
60巻1号(2008年1月発行)
特集 日本人の発見した神経疾患
59巻12号(2007年12月発行)
特集 損傷神経の再生―温存的治療法の開発
59巻11号(2007年11月発行)
特集 手根管症候群をめぐって
59巻10号(2007年10月発行)
増大特集 ALS―研究と診療の進歩
59巻9号(2007年9月発行)
特集 パーキンソン病の認知機能障害
59巻8号(2007年8月発行)
特集 パーキンソン病の分子遺伝学―最近の知見
59巻7号(2007年7月発行)
増大特集 情報伝達処理におけるグリアの機能と異常
59巻6号(2007年6月発行)
特集 職業性神経障害の新しい展開
59巻5号(2007年5月発行)
特集 脳画像最前線
59巻4号(2007年4月発行)
増大特集 最近注目される脳神経疾患治療の研究
59巻3号(2007年3月発行)
特集 分子イメージング
59巻2号(2007年2月発行)
特集 進行性多巣性白質脳症の新しい展開―PMLが治る時代へ向けて
59巻1号(2007年1月発行)
特集 高次視覚研究の最近の進歩
