アルツハイマー病治療は新たな夜明けを迎えている。2023年9月に国内で初めてアルツハイマー病疾患修飾薬であるレカネマブが承認され,2024年7月の時点ですでに2,800例以上の人に投与が始められている。2024年7月にはdonanemabが米国で承認され,本邦でも今後の承認が見込まれており,これら新規薬剤への期待は大きい。レカネマブの投与には早期診断が必要であることから,患者は早期から病名告知を受けることになり,適切な支援が不可欠である。また,アミロイド関連画像異常(ARIA)など副作用への対策が求められ,APOE遺伝子検査をめぐる臨床倫理上の課題もある。新時代に対応した診療のストラテジーを構築したい。
雑誌目次
BRAIN and NERVE-神経研究の進歩76巻9号
2024年09月発行
雑誌目次
特集 治療可能な認知症としてのアルツハイマー病
アルツハイマー病疾患修飾薬の現状
著者: 佐藤謙一郎 , 岩坪威
ページ範囲:P.991 - P.995
超高齢社会にあって,アルツハイマー病に対する疾患修飾療法の開発が急務とされてきたが,2023年になってようやく,抗アミロイド抗体薬が正式に医薬品として承認されるようになってきた。本論では,抗アミロイド抗体薬のうち特にaducanumab,レカネマブ,donanemab,remternetug,trontinemabについてこれまでの開発・臨床実用の状況,課題や今後の展望などについて概説する。
レカネマブの光と影—早期受診者への診断後支援
著者: 津野田尚子 , 橋本衛
ページ範囲:P.997 - P.1003
レカネマブの登場は患者や家族のみならず社会全体の希望の光である。しかしレカネマブの効果には限界があり,さらに治療対象者への告知が必要となるため,早期診断,早期絶望がこれまで以上に強調され,患者の人生に影を落とすことが懸念される。このような状況において,レカネマブ治療によって延長する “認知症患者として生きる時間” を,可能な限り有意義なものにするための診断後支援が重要視されている。本論では,早期受診者への診断後支援として筆者が取り組んでいる「軽度認知症患者,家族へのピアサポート活動」を紹介する。
アルツハイマー病疾患修飾薬の適応と効果判定
著者: 岩田淳
ページ範囲:P.1005 - P.1009
抗アミロイドβ抗体薬レカネマブが上市され,新しいアルツハイマー病治療が始まった。いままでの認知症医療とは異なり診断方法,評価方法,そして副作用,どれも新しい概念での投与が必要な薬剤である。特に,進行を止める薬剤でない以上その薬効の評価は極めて重要な課題となる。厚生労働省発出の最適使用推進ガイドラインを紹介しながら私見も交えて今後の課題を議論していきたい。
アルツハイマー病疾患修飾薬によるアミロイド関連画像異常(ARIA)の病態と対策
著者: 冨本秀和
ページ範囲:P.1011 - P.1017
抗アミロイドβ抗体薬レカネマブの副作用として,アミロイド関連画像異常(amyloid-related imaging abnormalities:ARIA)がある。治療対象の患者の約2割で認められ,大部分は無症候であるが一部の患者で重篤化する場合があり,その管理・対策が課題として残る。本論では,ARIAの関連病態や発生機序について考察しその対策について概説する。
アミロイドPETの臨床実装—アルツハイマー病の診断と治療における最新知見と実践的アプローチ
著者: 木村篤史 , 島田斉
ページ範囲:P.1019 - P.1027
アミロイドPETは,アルツハイマー病の早期診断と疾患修飾薬の適応判断において重要な役割を果たす。高感度・特異度,低侵襲性,空間的評価能力といった利点をもち,認知症医療の最適化に貢献するが,限界を理解したうえでの適切な使用と結果の解釈が不可欠である。無症候者への適応には慎重な判断が必要だが,前臨床期における先制医療や個人の高精度リスク推定が確立すれば,臨床的意義がさらに拡大する可能性がある。
抗アミロイドβ療法時代のAPOE遺伝子検査の意義と対応
著者: 下畑享良
ページ範囲:P.1029 - P.1034
アルツハイマー病の日常診療において,APOE遺伝子検査はこれまで推奨されるものではなかったが,抗アミロイドβ療法の安全性に関する情報を提供することから重要な意義を持つようになった。このため米国のレカネマブの適正使用ガイドラインでは,APOE遺伝子検査を施行すべきと明記してある。しかしその施行に伴い,臨床倫理的,法的,経済的問題が生じ得る。本邦でもこれらの問題にどのように対応するか包括的議論を開始すべきである。
タウPET—各種疾患における応用
著者: 高畑圭輔 , 久保田学 , 黒瀬心 , 樋口真人
ページ範囲:P.1035 - P.1044
タウPETは,タウ凝集体に対して選択的に結合するトレーサーを用いて脳内タウ沈着を可視化する病態イメージング法である。2010年代初期に最初のタウPET薬が撮像されて以降,さまざまな改良が重ねられている。タウPETはアルツハイマー病およびその他のタウオパチーの診断や予後予測に有用である。しかし,タウPET薬の結合プロファイルは疾患によって大きく異なるため,タウPET所見の解釈に際しては疾患ごとの特性を理解しておく必要がある。
血液バイオマーカーの現状と展望
著者: 池内健
ページ範囲:P.1045 - P.1052
次世代の認知症診断ツールとして血液バイオマーカーの臨床実装が期待されている。血漿アミロイドβ比率とリン酸化タウは,アルツハイマー病で生じる脳内病理を反映する血液バイオマーカーである。また神経変性,神経炎症を反映する血液バイオマーカーの開発が進んでいる。血液バイオマーカーの課題として,検査の頑強性や交絡因子の存在がある。汎用性がある血液バイオマーカーは,認知症診療の中で適正に活用される必要がある。
アルツハイマー病に対する新たな治療戦略
著者: 富田泰輔
ページ範囲:P.1053 - P.1058
アルツハイマー病(Alzheimer's disease:AD)患者脳の病理学的特徴である老人斑および神経原線維変化の生化学的解析を嚆矢とした分子病態の理解と,家族性ADの解析に始まる遺伝学的解析が相まって,アミロイドβ(Aβ)の凝集および蓄積がAD発症機構における重要なプロセスの1つであることを示した。凝集Aβに対するレカネマブの成功はその結実とも言える。一方,ADおよび各種タウオパチーの原因分子としてのタウに対する創薬研究が徐々に進みつつある。さらに遺伝学的解析から示唆されたグリア細胞の炎症応答がAD病態の修飾因子であることが明確となり,炎症制御という新たな治療戦略も考えられるようになった。本論においてはこれらADに対する新たな治療戦略について最新の知見をまとめる。
アルツハイマー病以外の認知症に対する疾患修飾薬
著者: 宮崎峻弘 , 東晋二 , 新井哲明
ページ範囲:P.1059 - P.1064
認知症の原因の多くを占める神経変性疾患では,蛋白質の凝集が病理機序の上流にあり,疾患修飾薬の開発における治療標的となっている。アルツハイマー病以外の神経変性疾患では,特にα-シヌクレインとTDP-43が原因凝集蛋白質としての頻度が高い。α-シヌクレインではいくつかの免疫療法の臨床治験が第Ⅱ相まで進んでおり,他にも低分子療法の開発も行われている。一方でTDP-43では凝集蛋白質を標的とする免疫はまだ研究段階であるが,関連原因遺伝子を対象にした治療薬開発がいくつか行われている。どちらの疾患修飾薬も,効果判定のためのバイオマーカー検査の開発が必要であり,まだ多くの課題を残しているが,両蛋白ともに多くの認知症性神経変性疾患例の脳内に凝集蓄積することからその治療的意義は高く,今後の研究開発の進展が期待される。
総説
神経疾患の画像サイン
著者: 百島祐貴
ページ範囲:P.1067 - P.1077
神経放射線診断領域でも,さまざまな疾患に特徴的な画像サインが数多く知られているが,その臨床的有用性はさまざま,千差万別である。その中から,特にCT,MRIに的を絞って,しばしば目にするもの,あるいは稀な疾患であっても疾患特異性が高く,実際の診断に役立つサインを選んで,その背景を含めて紹介する。
連載 スーパー臨床神経病理カンファレンス・8
15年にわたる緩徐進行性の認知症を伴う小脳性運動失調を認めた55歳女性例
著者: 鈴木幹也 , 尾方克久 , 髙田真利子 , 髙尾昌樹
ページ範囲:P.1079 - P.1085
〔現病歴〕40歳時,失調性歩行が生じ,A大学病院神経内科で臨床症状より脊髄小脳変性症3型(spinocerebellar ataxia type 3:SCA3,マシャド・ジョセフ病)と診断されたが,遺伝学的検査は本人・家族が希望されず未実施だった。その後近医に通院していたが,徐々に失調性歩行が進行して独歩不能になり,また認知症が生じた。
44歳時,当科を紹介され初診した。つかまり歩きは可能だが主に車椅子移動,スプーンで食事ができるがむせがあり,オムツ着用,神経学的に四肢運動失調,構音障害,眼振,認知症があった。母方のいとこが34歳時に失調性歩行でSCAと診断され,35歳で認知症,36歳で肺炎のため死亡していた。
原著・過去の論文から学ぶ・6
疾患概念の確立は症例報告から始まる—筋萎縮性側索硬化症と前頭側頭葉変性症—湯浅・三山病
著者: 吉田眞理
ページ範囲:P.1087 - P.1089
はじめに
卒後研修を終えて2年目に脳神経内科医として赴任した病院で遭遇した症例を紹介する。数年前からうつ病として精神科に通院していた初老期男性が,嚥下障害をきたし脳神経内科に入院し,球麻痺型筋萎縮性側索硬化症(amyotrophic lateral sclerosis:ALS)と診断された。全身のびまん性の筋萎縮を呈し,高度なⅡ型呼吸不全の状態でありながら,病棟内を徘徊し,頭部CTでは前頭葉萎縮を認めた。筆者は主治医ではなかったが,ALSに認知障害を伴う症例があることに強い衝撃を受けた。後日先輩の医師から,この症例は湯浅・三山病1-4)といわれる疾患ではないかと示唆され,原著をたどるとまさに同じ疾患と考えられた。湯浅・三山病は,筆者が神経病理学を学ぶ原点となった疾患である。本論では湯浅・三山病に関する本邦と欧米の原著をたどりたい。
書評
「ジェネラリストのための内科診断リファレンス 第2版」—酒見英太【監修】 上田剛士【著】 フリーアクセス
著者: 徳田安春
ページ範囲:P.1065 - P.1065
10年前にも本書の書評を書いた。本書を読んだ感想をまとめると,本書はシステム2的な分析的推論を行うための当時最強のツールであり,EBM実践のためのクイックなデータブックである,であった。臨床疫学の各論必携本と呼んでもよい。
あれから10年,われわれジェネラリストが待っていた第2版がついに出た。待ちこがれていた理由は,医学は日進月歩で変化し発展するからだ。新たな疾患概念や病歴,身体所見,そして診断検査のデータを供給する論文が無数に出版されている。3万もの論文の中から新しくかつ重要な情報を追加してくれている。
「医学研究のための 因果推論レクチャー」—井上浩輔,杉山雄大,後藤 温【著】 フリーアクセス
著者: 中山健夫
ページ範囲:P.1066 - P.1066
本書の執筆者である井上浩輔先生,杉山雄大先生,後藤温先生の3先生は,人間・人間集団・社会を対象とするパブリックヘルス,ヘルスサービス,疫学の分野において,最も目覚ましい活躍をされている気鋭の医学研究者です。本書は,先生方自身の高いレベルでの研究成果に基づき,近年世界的に関心が高まっている因果推論の最前線の知見を入門から専門レベルまで解説された充実の一冊です。
医学における因果推論は,古典的には単一病因説に始まり,多要因病因論から,1964年に米国公衆衛生総監(Surgeon General)によって取りまとめられた「喫煙と健康」報告書の5基準(一致性,強固性,特異性,時間性,整合性),1965年に英国の統計学者Bradford Hillsによる9視点(関連の強さ,一貫性,特異性,時間的先行性,生物学的勾配,可能性,合理性,実験験的証拠,類推)が示され,その後,米国の疫学者Kenneth J. Rothmanがパイモデルを提案しました。近年では,利用可能な大規模データベースの充実と,ランダム化比較試験が困難な状況での観察研究の意義が見直される流れの中で,解析手法の高度化とともに,因果推論の方法論が大きく発展しました。
お知らせ
「公益財団法人日本脳神経財団2024年度一般研究助成」募集 フリーアクセス
ページ範囲:P.1052 - P.1052
公益財団法人日本脳神経財団では下記の通り,一般研究助成の募集を行います。財団のHP(https://jbf.or.jp)の「各種助成申請のご案内」で要項をご確認の上,申請してください。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.987 - P.987
欧文目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.988 - P.988
バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.1094 - P.1094
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.1095 - P.1095
あとがき フリーアクセス
著者: 神田隆
ページ範囲:P.1096 - P.1096
徳田虎雄氏(1938-2024)が逝去されたことは皆様ご存じのことと思います。もう40年以上前のことになりますが,私は医学部6年生のときに一度だけ,徳洲会への勧誘に来られた徳田氏の話を間近で聞いたことがあります。UCSFの教授を階段教室の傍らに座らせて,徳洲会病院に米国型のERを作るのだ,お前たち一緒にやらないか,と熱弁をふるっておられたのを今でもよく思い出します。当時彼は40歳前後だったでしょうか。脂の乗り切った,全身エネルギーの塊のような人物で,当時から毀誉褒貶さまざまな声の聞こえる人でしたが,実弟の死から医師を志し,徳之島に病院を作るのだというお話を伺い,医師となるmotivationとしてこれ以上のものはないなと感服して聴き入っていました。
後日彼がALSに罹患したというニュースに接して,志半ばでこれから自分がやれることに大きな制限がかかり,さぞかし無念であろうと感じたのと同時に,ああいうエネルギッシュな人,ずば抜けた行動力,運動能力を誇る人はやはりALSのリスクなのかなと思ったのを今でもよく覚えています。一流のアスリートにALS罹患者が多いことを読者の皆様は重々承知と思います。ルー・ゲーリック,キャットフィッシュ・ハンター……どんどん出てきますね。イタリアのプロサッカーチームの選手やNFL選手でのALS罹患率の高さが話題になったのも記憶に新しいところです。卓越した運動機能を持つ選ばれし人が動けないALSになる,神様も何と残酷なことをなさるのだろうと思ってしまいますが,TDP-43やFUSなどの分子異常と運動との間には,私たちのまだ知らないリンクがあるのでしょうか。
基本情報
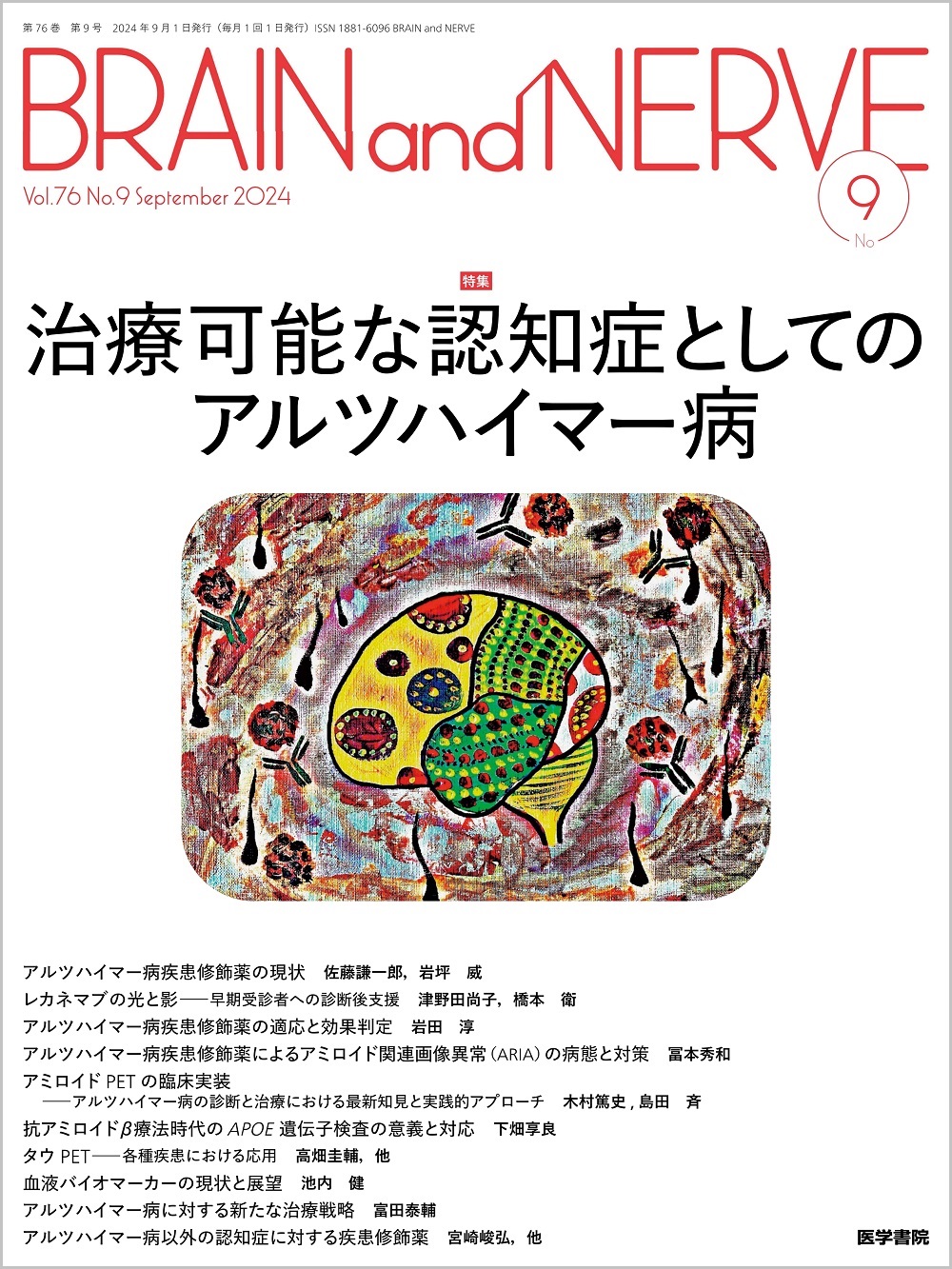
バックナンバー
76巻12号(2024年12月発行)
特集 芸術家と神経学Ⅱ
76巻11号(2024年11月発行)
特集 ALS 2024
76巻10号(2024年10月発行)
特集 どうして効くんだろう
76巻9号(2024年9月発行)
特集 治療可能な認知症としてのアルツハイマー病
76巻8号(2024年8月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である—revisited
76巻7号(2024年7月発行)
特集 ニューロ・バイオイメージング—技術と応用
76巻6号(2024年6月発行)
特集 注意と注意障害
76巻5号(2024年5月発行)
増大特集 末梢神経・筋肉の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
76巻4号(2024年4月発行)
特集 神経病理最前線
76巻3号(2024年3月発行)
特集 きちんと説明ができますか?
76巻2号(2024年2月発行)
特集 特発性正常圧水頭症の現在
76巻1号(2024年1月発行)
特集 新時代の重症筋無力症と関連疾患の診療
75巻12号(2023年12月発行)
特集 アガサ・クリスティーと神経毒
75巻11号(2023年11月発行)
特集 アロスタシス—ホメオスタシスを超えて
75巻10号(2023年10月発行)
特集 メタバースへの招待
75巻9号(2023年9月発行)
特集 妊娠と神経疾患
75巻8号(2023年8月発行)
特集 アルツハイマー病は本当に早期発見できるのか
75巻7号(2023年7月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part2 末梢編
75巻6号(2023年6月発行)
特集 Antibody Update 2023 Part1 中枢編
75巻5号(2023年5月発行)
増大特集 神経・精神領域の薬剤ハンドブック
75巻4号(2023年4月発行)
特集 All About Epilepsy
75巻3号(2023年3月発行)
特集 慢性疼痛
75巻2号(2023年2月発行)
特集 多系統萎縮症の新診断基準とこれからの診療
75巻1号(2023年1月発行)
特集 よく出会う不随意運動を知る
74巻12号(2022年12月発行)
特集 映画を観て精神・神経疾患を知る
74巻11号(2022年11月発行)
特集 RFC1遺伝子関連スペクトラム障害
74巻10号(2022年10月発行)
特集 ウイルス性脳炎・脳症2022
74巻9号(2022年9月発行)
特集 動的環境への適応系としての歩行
74巻8号(2022年8月発行)
特集 迷走神経の不思議
74巻7号(2022年7月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識2022
74巻6号(2022年6月発行)
特集 脳神経内科医に求められる移行医療
74巻5号(2022年5月発行)
増大特集 次の一手—神経筋疾患難治例をどのように治療するか
74巻4号(2022年4月発行)
特集 脳科学リテラシーを高めるために
74巻3号(2022年3月発行)
特集 中枢性自律神経障害update
74巻2号(2022年2月発行)
特集 温度を感じる脳と身体の科学
74巻1号(2022年1月発行)
特集 脳神経内科医のキャリアパスとリーダーシップ
73巻12号(2021年12月発行)
特集 芸術家と神経学
73巻11号(2021年11月発行)
特集 「目」の神経学
73巻10号(2021年10月発行)
特集 中枢神経・末梢神経の悪性リンパ腫
73巻9号(2021年9月発行)
特集 脳卒中治療に必要な基礎知識
73巻8号(2021年8月発行)
特集 脳腸相関—脳-身体の双方向性制御
73巻7号(2021年7月発行)
特集 グリアと神経—相補的な制御系として
73巻6号(2021年6月発行)
特集 Lower Spine Neurology
73巻5号(2021年5月発行)
増大特集 中枢神経の自己免疫性・炎症性疾患ハンドブック
73巻4号(2021年4月発行)
特集 片頭痛・群発頭痛治療の新たな夜明け
73巻3号(2021年3月発行)
特集 マルチリンガルブレイン
73巻2号(2021年2月発行)
特集 筋炎と壊死性筋症
73巻1号(2021年1月発行)
特集 Neuro-Oncology
72巻12号(2020年12月発行)
特集 超高齢期の精神神経疾患を診る
72巻11号(2020年11月発行)
増大特集 脳の発振現象—基礎から臨床へ
72巻10号(2020年10月発行)
特集 COVID-19—脳神経内科医が診るための最新知識
72巻9号(2020年9月発行)
特集 皮質性小脳萎縮症へのアプローチ
72巻8号(2020年8月発行)
特集 サルコイドーシス
72巻7号(2020年7月発行)
増大特集 神経倫理ハンドブック
72巻6号(2020年6月発行)
特集 前頭側頭葉変性症の今日的理解
72巻5号(2020年5月発行)
特集 多発性硬化症の現在と未来
72巻4号(2020年4月発行)
増大特集 神経疾患の診断における落とし穴—誤診を避けるために
72巻3号(2020年3月発行)
特集 でこぼこの脳の中でおしくらまんじゅうする脳機能
72巻2号(2020年2月発行)
特集 αシヌクレイノパチーの新たな展開
72巻1号(2020年1月発行)
特集 神経難病をクスリで治す—薬物開発の現況と近未来への展望
71巻12号(2019年12月発行)
特集 小脳と大脳—Masao Itoのレガシー
71巻11号(2019年11月発行)
増大特集 ALS2019
71巻10号(2019年10月発行)
特集 認知症と遺伝
71巻9号(2019年9月発行)
特集 神経疾患のドラッグ・リポジショニング—新時代へ
71巻8号(2019年8月発行)
特集 パーキンソン病診療の現在地—200年の変遷と新規治療
71巻7号(2019年7月発行)
増大特集 人工知能と神経科学
71巻6号(2019年6月発行)
特集 補体標的治療の現状と展望
71巻5号(2019年5月発行)
特集 NPSLE
71巻4号(2019年4月発行)
増大特集 神経学のための皮膚アトラス
71巻3号(2019年3月発行)
特集 Spine Neurology
71巻2号(2019年2月発行)
特集 “スポーツ”を生み出す脳
71巻1号(2019年1月発行)
特集 人工知能の医療応用Update
70巻12号(2018年12月発行)
特集 主訴に沿う—俯瞰し収束する画像診断の目
70巻11号(2018年11月発行)
増大特集 脳科学で解き明かす精神神経症候
70巻10号(2018年10月発行)
特集 「左脳と右脳」の現在
70巻9号(2018年9月発行)
特集 脳神経内科診療に役立つ精神科の知識
70巻8号(2018年8月発行)
特集 レヴィ小体型認知症の新知見
70巻7号(2018年7月発行)
増大特集 記憶と忘却に関わる脳のしくみ—分子機構から健忘の症候まで
70巻6号(2018年6月発行)
特集 芸術を生み出す脳
70巻5号(2018年5月発行)
特集 非アルツハイマー型認知症の病理学
70巻4号(2018年4月発行)
増大特集 Antibody Update 2018
70巻3号(2018年3月発行)
特集 『認知症疾患診療ガイドライン2017』を読み解く
70巻2号(2018年2月発行)
特集 知っておきたい神経感染症
70巻1号(2018年1月発行)
特集 筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群の今
69巻12号(2017年12月発行)
特集 運動異常症をみる—Web動画付録つき
69巻11号(2017年11月発行)
増大特集 こころの時間学の未来
69巻10号(2017年10月発行)
特集 成人てんかん—知っておきたい6つのトピック
69巻9号(2017年9月発行)
特集 ミクログリアと精神・神経疾患
69巻8号(2017年8月発行)
特集 遺伝性脊髄小脳失調症の病態と治療展望
69巻7号(2017年7月発行)
増大特集 あしたのアルツハイマー病治療
69巻6号(2017年6月発行)
特集 局在病変の神経心理学
69巻5号(2017年5月発行)
特集 Voxel-Based Morphometry—体積からわかること
69巻4号(2017年4月発行)
増大特集 ブロードマン領野の現在地
69巻3号(2017年3月発行)
特集 磁気刺激の新たな展開
69巻2号(2017年2月発行)
特集 Stroke-Like Diseases—鑑別時に注意を要する5病態
69巻1号(2017年1月発行)
特集 近年注目されている白質脳症
68巻12号(2016年12月発行)
特集 炎症性神経・筋疾患の新たな展開
68巻11号(2016年11月発行)
増大特集 連合野ハンドブック
68巻10号(2016年10月発行)
特集 アディクション—行動の嗜癖
68巻9号(2016年9月発行)
特集 自己免疫性脳炎・脳症
68巻8号(2016年8月発行)
特集 こころと汗
68巻7号(2016年7月発行)
増大特集 認知症の危険因子と防御因子
68巻6号(2016年6月発行)
特集 脳とフローラ
68巻5号(2016年5月発行)
特集 手の症候学—生理学・解剖学からみた新知見
68巻4号(2016年4月発行)
増大特集 治せる認知症
68巻3号(2016年3月発行)
特集 末梢神経の血管炎
68巻2号(2016年2月発行)
特集 筋疾患の認知機能障害
68巻1号(2016年1月発行)
特集 シャルコー・マリー・トゥース病
67巻12号(2015年12月発行)
特集 視床と高次脳機能
67巻11号(2015年11月発行)
増大特集 ギラン・バレー症候群のすべて—100年の軌跡
67巻10号(2015年10月発行)
特集 非・日常生活の脳科学
67巻9号(2015年9月発行)
特集 酵素補充療法
67巻8号(2015年8月発行)
特集 神経難病の終末期医療
67巻7号(2015年7月発行)
増大特集 神経疾患と感染症update
67巻6号(2015年6月発行)
特集 脳と「質感」
67巻5号(2015年5月発行)
特集 NCSE(非痙攣性てんかん重積状態)
67巻4号(2015年4月発行)
増大特集 大脳皮質vs.大脳白質
67巻3号(2015年3月発行)
特集 中枢神経の血管炎
67巻2号(2015年2月発行)
特集 「食べる」を考える
67巻1号(2015年1月発行)
特集 ニューロトキシコロジー
66巻12号(2014年12月発行)
特集 Orthopaedic Neurology—神経内科と整形外科の狭間で
66巻11号(2014年11月発行)
増大特集 神経症候学は神経学の“魂”である
66巻10号(2014年10月発行)
特集 分子を撃つ 神経疾患治療の新しい水平線
66巻9号(2014年9月発行)
特集 痙縮の臨床神経学
66巻8号(2014年8月発行)
特集 神経系の悪性リンパ腫update
66巻7号(2014年7月発行)
増大特集 アミロイド関連神経疾患のすべて―封入体筋炎からアルツハイマー病まで
66巻6号(2014年6月発行)
特集 ミラーニューロン
66巻5号(2014年5月発行)
特集 アセチルコリンと神経疾患―100年目の現在地
66巻4号(2014年4月発行)
増大特集 タッチ・ビジョン・アクション
66巻3号(2014年3月発行)
特集 神経筋疾患の超音波診断
66巻2号(2014年2月発行)
特集 糖尿病の神経学revisited
66巻1号(2014年1月発行)
特集 日常生活の脳科学
65巻12号(2013年12月発行)
特集 プロテイノパチーの神経病理学
65巻11号(2013年11月発行)
増大特集 Close Encounters―臨床神経学と臨床免疫学の遭遇と未来
65巻10号(2013年10月発行)
特集 神経系の発達メカニズム―最近の話題
65巻9号(2013年9月発行)
特集 Common diseaseは神経学の主戦場である―現状と展望
65巻8号(2013年8月発行)
特集 こころの時間学―現在・過去・未来の起源を求めて
65巻7号(2013年7月発行)
増大特集 あしたの脳梗塞
65巻6号(2013年6月発行)
特集 見せる・仕分ける―脳機能解析の新手法
65巻5号(2013年5月発行)
特集 てんかん―新しいパースペクティブ
65巻4号(2013年4月発行)
増大特集 Antibody Update
65巻3号(2013年3月発行)
特集 次世代シーケンサーによる神経変性疾患の解析と展望
65巻2号(2013年2月発行)
特集 血液脳関門研究の進歩
65巻1号(2013年1月発行)
特集 Corticobasal Syndrome
64巻12号(2012年12月発行)
特集 The Border-Land of Dementia
64巻11号(2012年11月発行)
増大特集 痛みの神経学―末梢神経から脳まで
64巻10号(2012年10月発行)
特集 辺縁系をめぐって
64巻9号(2012年9月発行)
特集 高次脳機能イメージングの脳科学への新展開
64巻8号(2012年8月発行)
特集 線条体の基礎と臨床
64巻7号(2012年7月発行)
増大特集 顔認知の脳内機構
64巻6号(2012年6月発行)
特集 睡眠と覚醒の脳内機構
64巻5号(2012年5月発行)
特集 神経疾患のバイオマーカー
64巻4号(2012年4月発行)
増大特集 パーキンソン病の新しい側面
64巻3号(2012年3月発行)
特集 アカデミアから新規治療の実現へ―トランスレーショナルリサーチの現状
64巻2号(2012年2月発行)
特集 生物学的精神医学の進歩
64巻1号(2012年1月発行)
特集 iPS細胞と神経疾患
63巻12号(2011年12月発行)
特集 神経心理学と画像解析の融合
63巻11号(2011年11月発行)
増大特集 筋疾患update
63巻10号(2011年10月発行)
特集 緩徐進行性高次脳機能障害の病態
63巻9号(2011年9月発行)
特集 脳卒中の最新画像診断
63巻8号(2011年8月発行)
特集 日本人の発見した神経症候
63巻7号(2011年7月発行)
増大特集 神経筋接合部―基礎から臨床まで
63巻6号(2011年6月発行)
特集 ニューロパチー
63巻5号(2011年5月発行)
特集 神経系と血管内リンパ腫
63巻4号(2011年4月発行)
増大特集 てんかんの新しい治療
63巻3号(2011年3月発行)
特集 サイバーナイフ治療
63巻2号(2011年2月発行)
特集 続・日本人の発見した神経疾患
63巻1号(2011年1月発行)
特集 血管腫
62巻12号(2010年12月発行)
特集 頸部頸動脈狭窄症の診断と治療
62巻11号(2010年11月発行)
増大特集 歩行とその異常
62巻10号(2010年10月発行)
特集 ブレインバンク
62巻9号(2010年9月発行)
特集 視神経脊髄炎(NMO)update
62巻8号(2010年8月発行)
特集 辺縁系脳炎
62巻7号(2010年7月発行)
増大特集 アルツハイマー病―研究と診療の進歩
62巻6号(2010年6月発行)
特集 改正臓器移植法の問題点とその対応
62巻5号(2010年5月発行)
特集 神経画像のピットフォール―見落としと読み過ぎ
62巻4号(2010年4月発行)
特集 傍腫瘍性神経筋疾患update
62巻3号(2010年3月発行)
特集 神経回路解析法の最近の進歩
62巻2号(2010年2月発行)
特集 ニューロリハビリテーションの最前線
62巻1号(2010年1月発行)
特集 神経救急
61巻12号(2009年12月発行)
特集 Somatotopy再考
61巻11号(2009年11月発行)
特集 前頭側頭葉変性症
61巻10号(2009年10月発行)
特集 片頭痛の予防療法
61巻9号(2009年9月発行)
特集 脳血管障害治療の進歩
61巻8号(2009年8月発行)
特集 神経・筋疾患の分子標的治療
61巻7号(2009年7月発行)
特集 脳腫瘍研究の最前線―遺伝子解析から治療まで
61巻6号(2009年6月発行)
特集 脊椎・脊髄外科の最近の進歩
61巻5号(2009年5月発行)
特集 Restless legs syndrome
61巻4号(2009年4月発行)
特集 大脳基底核―分子基盤から臨床まで
61巻3号(2009年3月発行)
特集 Microneurography(微小神経電図法)の臨床応用
61巻2号(2009年2月発行)
特集 神経系の再興感染症と輸入感染症
61巻1号(2009年1月発行)
特集 脳神経倫理
60巻12号(2008年12月発行)
特集 痙縮
60巻11号(2008年11月発行)
特集 脳卒中と遺伝子
60巻10号(2008年10月発行)
特集 若年者の脳卒中
60巻9号(2008年9月発行)
特集 知・情・意の神経学
60巻8号(2008年8月発行)
特集 脳硬膜動静脈瘻
60巻7号(2008年7月発行)
増大特集 学習と記憶――基礎と臨床
60巻6号(2008年6月発行)
特集 Crow-深瀬症候群(POEMS症候群)
60巻5号(2008年5月発行)
特集 「痛み」の研究と治療の最前線
60巻4号(2008年4月発行)
増大特集 神経系の発生とその異常
60巻3号(2008年3月発行)
特集 特発性正常圧水頭症(iNPH)―最近の話題
60巻2号(2008年2月発行)
特集 がん治療と神経障害
60巻1号(2008年1月発行)
特集 日本人の発見した神経疾患
59巻12号(2007年12月発行)
特集 損傷神経の再生―温存的治療法の開発
59巻11号(2007年11月発行)
特集 手根管症候群をめぐって
59巻10号(2007年10月発行)
増大特集 ALS―研究と診療の進歩
59巻9号(2007年9月発行)
特集 パーキンソン病の認知機能障害
59巻8号(2007年8月発行)
特集 パーキンソン病の分子遺伝学―最近の知見
59巻7号(2007年7月発行)
増大特集 情報伝達処理におけるグリアの機能と異常
59巻6号(2007年6月発行)
特集 職業性神経障害の新しい展開
59巻5号(2007年5月発行)
特集 脳画像最前線
59巻4号(2007年4月発行)
増大特集 最近注目される脳神経疾患治療の研究
59巻3号(2007年3月発行)
特集 分子イメージング
59巻2号(2007年2月発行)
特集 進行性多巣性白質脳症の新しい展開―PMLが治る時代へ向けて
59巻1号(2007年1月発行)
特集 高次視覚研究の最近の進歩
