本問題集は、今月の特集のご執筆者に、執筆テーマに関連して「総合診療専門医なら知っておいてほしい!」「自分ならこんな試験問題をつくりたい!」という内容を自由に作成していただいたものです。力試し問題に、チャレンジしてみてください。
雑誌目次
総合診療28巻7号
2018年07月発行
雑誌目次
特集 この薬だけは押さえておきたい! 総合診療医のためのSpecialist Drug 40
知っておきたいエビデンス一覧 フリーアクセス
ページ範囲:P.959 - P.965
【総論】
プライマリ・ケアのための臨床薬理“再”入門—薬物治療のスキルとリテラシーの基礎
著者: 植田真一郎
ページ範囲:P.888 - P.899
実践的な薬物治療学=「臨床薬理学」のススメ
「臨床薬理学」の講座はほとんどの医学部には存在しないので、たいていの医師や医学生にとっては“薬理のようなもの”かもしれない。実はぜんぜん違っていて、薬物治療全般に関して、処方する医師が知っておくべき理論であり感覚であり、きわめて実践的な「治療学」である。
臨床薬理学という名称は比較的新しいが、欧州では「Materia Medica」の名で数百年前から存在した。筆者は、もともと大学病院の内科で学んだが、診断や治療は横断的に学ばないと役に立たないと感じ、さらに研修医の時、薬剤の理論的な選択や用量設定について、当時は参考となる文献も少なく困っていた際、臨床薬理の教科書に出会い勉強を始めた。
「Specialist Drug 40」選定メモ
著者: 藤沼康樹
ページ範囲:P.900 - P.903
総合診療医の“自家薬籠”1)には入っていない、専門医が使いこなしている薬剤を「Specialist Drug」と呼ぶことにしています。主として、次の2つのタイプの薬剤です。
❶専門科とのshared careにおいて処方されている薬剤(専門医から「日常的なフォローアップをお願いします」となりやすい疾患群の薬)
❷専門科からの逆紹介で目にしたり、自分で継続処方する薬剤(専門医から「落ち着いたので、そちら〔外来・在宅〕で診てください」となりやすい疾患群の薬)
専門医から「日常的なフォローアップをお願いします」となりやすい疾患群の薬
1)乳がん|ノルバデックス®(タモキシフェン)
著者: 金子しおり
ページ範囲:P.904 - P.904
ホルモン受容体陽性乳がんに使用される内分泌(ホルモン)療法薬の一種。閉経状態にかかわらず使用できる薬剤で、SERM(選択的エストロゲン受容体モジュレーター)に分類される。術後補助療法および転移・再発乳がんに使用される。
2)乳がん|アリミデックス®(アナストロゾール)
著者: 金子しおり
ページ範囲:P.905 - P.905
ホルモン受容体陽性乳がんに使用される内分泌(ホルモン)療法薬の一種。アロマターゼ阻害薬であり、閉経後患者の術後補助療法・転移もしくは再発時に使用される。LH-RH(黄体形成ホルモン放出ホルモン)アゴニストと併用して、閉経前転移・再発患者に使用することもある。
3)前立腺がん|リュープリン®(リュープロレリン)
著者: 小路直
ページ範囲:P.906 - P.906
LH-RH(高活性の黄体形成ホルモン放出ホルモン)誘導体であるリュープロレリン酢酸塩の注射用徐放性マイクロカプセルのキット製剤である。LH-RHと比較して、LH-RHレセプターに対する親和性が高い徐放性製剤であるため、精巣の反応性低下をもたらし、下垂体-性腺機能抑制作用を示す。
4)胃がん|ティーエスワン®(テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム)
著者: サントススレスタ
ページ範囲:P.907 - P.907
5-FU(フルオロウラシル)のプロドラッグの「テガフール」に、5-FUの分解阻害薬「ギメラシル」とリン酸化阻害薬「オテラシルカリウム」を配合したフッ化ピリミジン系の経口抗がん剤。
5)肺がん|オプジーボ®(ニボルマブ(遺伝子組換え))
著者: 大山優
ページ範囲:P.908 - P.909
2014年に承認された、わが国初のがん免疫療法薬。「免疫療法はがんに効かない」という常識に風穴を開けたブレイクスルー薬。腫瘍(PD-L1)とTリンパ球(PD-1)が反応すると、T細胞の免疫反応が抑制される機構をブロックすることで作用を発揮する「免疫チェックポイント阻害薬」の1つ(本剤は抗PD-1抗体)。免疫関連副作用(irAE)に注意を要する。適応疾患は新たな試験結果にて順次拡大中。
6)膵がん|ジェムザール®(ゲムシタビン)
著者: 大山優
ページ範囲:P.910 - P.910
核酸合成を阻害することで作用を発揮する、「殺細胞薬」といわれる通常の抗がん剤の一種。膵がんのみならず、幅広い適応疾患をもつ。主な副作用は「骨髄抑制」「間質性肺炎」「肝障害」だが、他にどのような副作用が出現してもおかしくない。「脱毛」が少ないことが特徴。
7)腎がん|スーテント®(スニチニブ)
著者: 大山優
ページ範囲:P.911 - P.911
「VEGF(血管内皮増殖因子)」という血管新生に関わる受容体のチロシンキナーゼを阻害する分子標的薬(チロシンキナーゼ阻害薬)。根治切除不能または転移性の腎がんの第一選択薬。VEGF阻害薬には「VEGF class effect」と呼ばれる一連の副作用があり、迅速な対応が必要。
8)慢性骨髄性白血病|グリベック®(イマチニブ)
著者: 奈良健司
ページ範囲:P.912 - P.912
造血幹細胞移植以外では長期生存できなかった慢性骨髄性白血病(CML)を、内服のみで長期生存可能としたCMLの第一選択薬で、チロシンキナーゼ阻害薬(TKI)[O'Brien SG, et al:N Engl J Med, 2003]1)。効果があるかぎり終生服用し続ける薬剤であることから、内服状況と副作用の確認がプライマリ・ケアの役割となる。
9)小児夜尿症|ミニリンメルト®(デスモプレシン)
著者: 高村昭輝
ページ範囲:P.913 - P.913
内服型デスモプレシン酢酸塩水和物。バソプレシンV2受容体に選択的に結合し、水の再吸収を促進し、尿産生を抑制する。プライマリ・ケア領域では就寝前投与により、尿浸透圧低下型(いわゆる多尿型)夜尿症に使用する。口腔内崩壊錠で、従来の経鼻スプレーに比べて投与しやすく、鼻粘膜の状況の影響を受けにくい。
10)関節リウマチ|リウマトレックス®(メトトレキサート)
著者: 服部周平 , 萩野昇
ページ範囲:P.914 - P.914
関節リウマチ診療において最も頻用されるアンカードラッグである。耐用性が良く、生物学的製剤との併用で使用される場合も多い。一方、週1〜3回という用法、副作用予防の葉酸内服などはユニークな点であり、頻度は低いが間質性肺炎、骨髄抑制などの副作用もあるため、特殊性を熟知したうえで処方する必要がある。
11)関節リウマチ|シンポニー®(ゴリムマブ(遺伝子組換え))
著者: 服部周平 , 萩野昇
ページ範囲:P.915 - P.915
関節リウマチの治療に用いられるTNF(腫瘍壊死因子)阻害薬の一種。ヒト型IgG1モノクローナル抗体製剤であり、4週間に1回投与で奏効する。診断早期の寛解導入には効果の立ち上がりが遅くやや不向きだが、免疫原性が低く二次無効が起こりにくい利点がある。2018年4月より「自己注射」が解禁となった。
12)統合失調症|エビリファイ®(アリピプラゾール)
著者: 今村弥生
ページ範囲:P.916 - P.916
主に統合失調症の治療薬で、主にドパミン受容体に作用する非定型(第二世代)抗精神病薬である。ドパミン受容体を適度に(60〜80%)遮断する他の非定型抗精神病薬と違い、ドパミン受容体を部分的に刺激する、特徴的な作用機序をもつ。
13)双極性障害|リーマス®(炭酸リチウム)
著者: 今村弥生
ページ範囲:P.917 - P.917
双極性障害の治療においては、抗うつ・抗躁のどちらの相でも、治療効果のエビデンスは最多。古くからあるシンプルな構造ながら、再評価されている薬剤である。反面、要注意な副作用も最多。
14)てんかん|エクセグラン®(ゾニサミド)
著者: 佐野正彦
ページ範囲:P.918 - P.918
てんかんの発作型スペクトラムは広いが、主に「部分発作」に使用する薬剤。効果はかなり高いが、他の抗てんかん薬と異なる副作用があり注意を要する。「抗Parkinson病薬」としての役割もある。
15)Parkinson病|ニュープロ®パッチ(ロチゴチン)
著者: 大田健太郎 , 後藤正志 , 中島孝
ページ範囲:P.919 - P.919
持続的ドパミン受容体刺激理論(CDS)に基づき、レボドパやドパミンアゴニストを脳内で一定になるように投与することがドパミン補充療法の基本で、これにより長期経過後に出現する運動合併症の予防と精神症状などの非運動症状を最少化できる。経皮投与はCDSに最適であり、本剤はその唯一の貼付剤。
16)HIV感染症|テビケイ®(ドルテグラビル)
著者: 千葉大
ページ範囲:P.920 - P.920
抗HIV療法(ART)のキードラッグとして使われるインテグラーゼ阻害薬(INSTI)のうち、最も頻用される薬剤の1つ。早期に診断されARTによりウイルス量が抑制されているHIV感染者は生命予後良好で、「早期診断」と「安定期の併存疾患管理」が総合診療医の最も重要な役割である。
17)HIV感染症|デシコビ®(エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミド)
著者: 千葉大
ページ範囲:P.921 - P.921
多剤併用を原則とする抗HIV療法(ART)のバックボーンを構成する2成分として、最も頻用される組み合わせの合剤である。B型肝炎ウイルス(HBV)抑制効果もあるため、「HIV/HBV重複感染症例」における第一選択である。この場合、デシコビ®の中断によるHBV再燃に注意を要する。
18)乾癬|ネオーラル®(シクロスポリン)
著者: 荻堂優子
ページ範囲:P.922 - P.922
同成分のサンディミュン®の吸収性を改良した、T細胞性機能を広範囲に抑える免疫抑制剤(カルシニューリン阻害薬)。皮膚科領域では、中等症以上あるいは難治性の乾癬と、難治性のアトピー性皮膚炎に保険適応がある。使用期間と併用薬に注意する。
19)緑内障|ダイアモックス®(アセタゾラミド)
著者: 山城博子
ページ範囲:P.923 - P.923
急性閉塞隅角緑内障発作などの緊急時や、末期緑内障の手術待機時など、限られた場合にのみ眼圧下降目的で使用する。緑内障は「点眼薬」による治療が主体であり、アセタゾラミドを長期に内服することは稀である(長期投与服用による副作用リスクが高い)。
20)C型肝炎|ダクルインザ®(ダクラタスビル)
著者: 池内和彦 , 奥新和也 , 四柳宏
ページ範囲:P.924 - P.924
C型肝炎ウイルス(HCV)のNS5A複製複合体の形成を阻害する、直接型抗ウイルス薬(direct acting antivirals : DAAs)の1つ。従来のC型肝炎治療はインターフェロン(IFN)の併用が必須で副作用が多く入院を要したが、2014年に「ダクラタスビル・アスナプレビル併用療法」が国内初のIFNフリー療法として認可された。
21)C型肝炎|スンベプラ®(アスナプレビル)
著者: 池内和彦 , 奥新和也 , 四柳宏
ページ範囲:P.925 - P.925
抗HCV作用をもつDAASで、NS3/4A領域をターゲットとしたプロテアーゼ阻害薬である。ダクラタスビルとの併用療法は2014年に国内初のIFNフリー療法として「ゲノタイプ1」を対象に認可されたが、中等度〜高度の「肝障害」が時にみられ、非治癒例で「アミノ酸耐性変異」が出現することから、近年は新規プロテアーゼ阻害薬が使用されるようになってきている。
22)C型肝炎|ソバルディ®(ソホスブビル)
著者: 池内和彦 , 奥新和也 , 四柳宏
ページ範囲:P.926 - P.926
C型肝炎の治療に用いられる直接型抗ウイルス薬(direct acting antivirals : DAAs)の1つで、核酸型NS5Bポリメラーゼ阻害薬に分類される。レジパスビルと併用すること(ハーボニー®配合錠)で、「ゲノタイプ1」に対しては耐性遺伝子変異によらず高い有効性を示し、12週間で治療を完遂できる。2018年には、「ゲノタイプ2」に対してもハーボニー®配合錠の適応が確定された。
23)B型肝炎|バラクルード®(エンテカビル)
著者: 池内和彦 , 奥新和也 , 四柳宏
ページ範囲:P.927 - P.927
B型肝炎ウイルス(HBV)感染に用いられる最も代表的な核酸アナログ製剤で、肝炎の活動性と線維化進展を抑制し、肝硬変・肝細胞がんの発生を減らすことができる。一方で、HBVは感染が一度成立すると肝細胞の核内に鋳型となるcccDNA(covalently closed circular DNA)として存在し、感染が持続するにつれその量が増大するため、核酸アナログ製剤の投与で完全に駆除されることはなく、「投与中止」による再燃が問題となる。
24)更年期障害|プレマリン®(結合型エストロゲン)
著者: 池田裕美枝
ページ範囲:P.928 - P.928
ホルモン補充療法に用いる代表的な経口エストロゲン製剤。ホットフラッシュをはじめとする更年期障害の治療、または無月経の女性や閉経後女性のヘルスメンテナンス(主に骨塩量維持)の目的で用いる。
25)特発性肺線維症|ピレスパ®(ピルフェニドン)
著者: 田中淳一
ページ範囲:P.929 - P.929
2008年に発売開始された抗線維化薬で、特発性肺線維症の肺活量低下を抑制する効果がある。2015年に改訂された特発性肺線維症の治療ガイドライン1)では、「条件に応じて推奨する」治療として位置づけられている。プライマリ・ケアにおいては、病状進行を抑えるための日常生活管理が重要である。
専門医から「落ち着いたので、そちら(外来・在宅)で診てください」となりやすい疾患群の薬
26)PCI後・DES留置後|エフィエント®(プラスグレル)
著者: 小田倉弘典
ページ範囲:P.930 - P.930
P2Y12受容体阻害薬として、主に虚血性心疾患の二次予防および冠動脈ステント血栓予防に用いられる。従来のクロピドグレルより効果発現が早く、日本では出血が多くないとのエビデンスから、安定冠動脈疾患患者において、DES(薬剤溶出性ステント)留置を含むPCI(経皮的冠動脈形成術)後にも用いられてきている。
27)心房細動|エリキュース®(アピキサバン)
著者: 小田倉弘典
ページ範囲:P.931 - P.931
Xa因子を選択的に阻害するNOAC(非ビタミン拮抗経口抗凝固薬)。高齢者/腎機能低下者でワルファリンより出血が少ないことから、高リスク例によく使われる。とはいえ、出血リスクが大きいことに変わりはなく、また他のNOAC同様に高価であり、適応決定と管理には十分な注意が必要である。
28)心不全|サムスカ®(トルバプタン)
著者: 若林禎正
ページ範囲:P.932 - P.932
アルギニンバソプレシンV2受容体を阻害する経口利尿薬。2017年改訂の日本循環器学会・日本心不全学会合同『急性・慢性心不全診療ガイドライン』1)に初めて記載された。他の利尿薬に抵抗性の心不全症例に使用される。難治性心不全、特に低ナトリウム性心不全患者がよい対象と考えられている。
29)心不全|アンカロン®(アミオダロン)
著者: 若林禎正
ページ範囲:P.933 - P.933
重篤な心室頻拍(VT)・心室細動(VF)・心不全または肥大型心筋症に伴う心房細動(AF)に使用する抗不整脈薬。多彩な分子標的(Naチャネル、Caチャネル、Kチャネル、Na/K-ATPアーゼ、β受容体など)をもつ。代謝産物(デスエチルアミオダロン)も同様に作用する。副作用として、重篤な肺毒性がある。
30)糖尿病|ジャディアンス®(エンパグリフロジン)
著者: 大西由希子
ページ範囲:P.934 - P.934
尿糖排泄を促すことで血糖を下げ、「体重減少」も期待できるSGLT2阻害薬。尿糖増加による浸透圧利尿で「脱水」になりやすいので注意。本剤およびカナグリフロジンで、心血管リスクの高い2型糖尿病患者において、心血管イベント・腎症発症進展抑制効果があることが報告された1, 2)。
31)糖尿病|ビクトーザ®(リラグルチド(遺伝子組換え))
著者: 大西由希子
ページ範囲:P.935 - P.935
経口のDPP-4阻害薬と同様、インクレチン効果による血糖降下作用のあるGLP-1受容体作動薬。GLP-1アナログを1日1回自己注射することにより、薬理的濃度のGLP-1作用(インスリン分泌促進、グルカゴン分泌抑制、食欲抑制効果)をもたらす。低血糖や体重増加なく、DPP-4阻害薬以上の血糖低下作用および体重減少を期待できる。
32)肺結核|リファジン®(リファンピシン)
著者: 金子惇
ページ範囲:P.936 - P.936
「結核」「非結核性抗酸菌症」治療のキードラッグ。プライマリ・ケアセッティングで処方を開始するより、結核/非結核性抗酸菌症を疑って救急や呼吸器内科に紹介し「診断を受けたあとの処方を継続する」というシチュエーションが多い。長期の処方になるため、「内服状況」と「副作用」の確認がプライマリ・ケアの役割となる。
33)肺結核|イスコチン® ヒドラ(イソニアジド)
著者: 金子惇
ページ範囲:P.937 - P.937
結核の標準治療薬の1つであり、「潜在性結核感染症(LTBI)」に対しても第一選択として用いられることが多い。プライマリ・ケアにおいては、他の抗結核薬と同様に「診断を受けたあとの処方を継続する」というシチュエーションが多い。
34)肺結核|ピラマイド®(ピラジナミド)
著者: 金子惇
ページ範囲:P.938 - P.938
結核の標準治療薬の1つであり、日本においてはリファンピシン、イソニアジド、エタンブトール(もしくはストレプトマイシン)の3剤とともに「4剤」で2カ月間治療し、その後リファンピシンとイソニアジドの2剤で4カ月継続する治療が第一選択とされることが多い。プライマリ・ケアにおいては、他の抗結核薬と同様に「診断を受けたあとの処方を継続する」というシチュエーションが多い。
35)肺結核|エサンブトール® エブトール®(エタンブトール)
著者: 金子惇
ページ範囲:P.939 - P.939
結核の標準治療薬の1つであり、日本においてはリファンピシン、イソニアジド、ピラジナミドの3剤に、本剤(もしくはストレプトマイシン)を加えた「4剤」を2カ月間使用し、その後リファンピシンとイソニアジドを4カ月間使用する方法が第一選択となっている。プライマリ・ケアにおいては、他の抗結核薬と同様に「診断を受けたあとの処方を継続する」というシチュエーションが多い。
36)骨粗鬆症|フォルテオ®(テリパラチド(遺伝子組換え))
著者: 服部周平 , 萩野昇
ページ範囲:P.940 - P.940
副甲状腺ホルモンのアミノ酸配列の一部を製剤化したもの。ビスホスホネート製剤が使用できない場合や効果に乏しい場合の切り札として使われる。また、ステロイド骨粗鬆症で椎体骨折を起こした場合も良い適応である。1日1回の自己注射剤(最大2年間まで)。
37)腎性貧血|ミルセラ®(エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え))
著者: 鈴木創
ページ範囲:P.941 - P.941
エリスロポエチン製剤を総称して赤血球造血刺激因子製剤(ESA)と呼ぶが、慢性腎臓病(CKD)の診療のうえでは使い慣れてほしい薬剤である。緩徐に進行する貧血は症状が乏しく放置されやすいが、腎予後改善効果が示されており積極的に介入したい。本剤は、ESAのなかで作用時間が一番長く、月1回投与で安定して使用が可能。
38)勃起不全|バイアグラ®(シルデナフィル)
著者: 小路直
ページ範囲:P.942 - P.942
ヒト陰茎海綿体のcGMP(環状グアノシン一リン酸)分解酵素であるPDE5の活性を、選択的かつ競合的に阻害し、陰茎海綿体内のcGMP量を増大させる。増大したcGMPは、海綿体平滑筋を弛緩、海綿体洞を拡張させ、血液を陰茎に流入、伸展した陰茎白膜により流入静脈が圧迫されることで勃起を維持させる。
39)中心静脈栄養|エルネオパ®NF(糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液)
著者: 田直子
ページ範囲:P.943 - P.943
世界で初めて5種類の微量元素を配合した高カロリー輸液。「ブドウ糖」「電解質」「アミノ酸」「ビタミン」「微量元素」が一剤化されているため、ビタミンや微量元素の投与忘れ、混合調製時の細菌汚染などのリスクを軽減できる。簡易なキット製剤のため、入院治療だけでなく「在宅中心静脈栄養」にも適している。
40)多系統萎縮症|セレジスト®(タルチレリン)
著者: 下畑享良
ページ範囲:P.944 - P.944
脊髄小脳変性症における「運動失調」の改善に使用する。甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン誘導体であり、アセチルコリン、ドパミン、ノルアドレナリンおよびセロトニン神経系を活性化させるとともに、脊髄反射増強作用、神経栄養因子様作用、局所グルコース代謝促進作用により、運動失調を改善するとされる。
【トピックス】
総合診療医のための「分子標的薬」
著者: 植田真一郎
ページ範囲:P.946 - P.950
総合診療医や家庭医にとって今後の重要な課題の1つは、分子標的治療をはじめとしたがん治療の進歩で、長期生存が可能になったがん患者のケアであろう。これは、術後合併症や、放射線や従来の抗がん剤の長期的な毒性への対応、分子標的治療を受けている患者のshared care、あるいは治療終了後のreferred careにおける毒性発現の診断、心血管イベント予防、がんサバイバーシップへの関与と多岐にわたる。本稿では、「分子標的薬」に関連する副作用に焦点を当てた。
「オーファンドラッグ」とは—希少疾病用医薬品の光と影
著者: 水八寿裕
ページ範囲:P.951 - P.953
日本では、オーファンドラッグ(orphan drug)は「希少疾病用医薬品」と呼ばれている。筆者は、10年前にこの臨床研究の一部をお手伝いした経験があり、また日常でも薬剤師としてその調剤・服薬支援に関わった経験から、私見ではあるが書きつづってみたい。
「処方カスケード」とその対応
著者: 青島周一
ページ範囲:P.954 - P.958
処方カスケードとは
薬物有害反応によりもたらされた身体症状が「新たな医学的プロブレム」と誤認されてしまい、その治療のために他の薬剤が追加で処方されることがあります1)。
たとえば、アムロジピンの薬物有害反応として下肢浮腫があげられますが、この浮腫がアムロジピンによるものと認識されずに、利尿薬が追加投与されてしまう、というような状況です。また、追加投与された利尿薬が頻尿症状をもたらし、さらに抗コリン薬の追加投与につながってしまうこともあるでしょう。
Editorial
家庭医的外来ケース・カンファレンスの方法 フリーアクセス
著者: 藤沼康樹
ページ範囲:P.877 - P.877
さまざまなタイプの総合診療系の教育イベントに呼ばれる機会があります。かつては、講演あるいはレクチャーといったやり方を期待されていました。最近は、むしろ具体的なケースを提示してもらって、議論の促しとコメントをつける、というようなやり方が好きです。それは、準備をほとんどせずに済むということと、当日ケースを提示してくれる医師をはじめとした医療者の語りのニュアンスや雰囲気から、本当のニーズがわかるということが多く、アドリブ的にそのニーズに合わせたコメントをするのが実はとても大事だな、という思いがあるからです。
それでも僕なりの一定のやり方があって、今回はそれを紹介します。
What's your diagnosis?[187]
吾輩も曖昧なZである!
著者: 吉田常恭 , 酒見英太
ページ範囲:P.880 - P.884
病歴
患者:狭心症や陳旧性脳梗塞の既往があるものの、IADL(instrumental activities of daily living)まで自立した、70歳の非喫煙・非飲酒男性。
主訴:嗄声。
現病歴:来院約1カ月前に発熱と咽頭痛があり、近医で風邪として対処(詳細不明)されて4日程でそれらは改善した。来院14日前から嗄声が出現し、軽度のむせ込みや右耳痛も加わったため、近医耳鼻科を受診して喉頭ファイバーを受けたところ、「右声帯の動きが悪い」と言われ、メチルコバラミンが処方された。しかし2週間経過しても嗄声とむせ込みは改善しなかったため、精査目的で当科に紹介となった。発熱、盗汗、食思不振、体重減少、咳・痰、呼吸苦、頭痛、複視、構音障害、めまい・難聴、味覚障害、筋力低下、感覚障害はない。
既往歴:陳旧性脳梗塞(67歳、後遺症なし)、狭心症(67歳、PCI[経皮的冠動脈形成術]後)、高血圧症、脂質異常症、慢性便秘症。薬物・食物アレルギーはない。
薬剤歴:アスピリン、ランソプラゾール、アムロジピン、エナラプリル、アトルバスタチン、モサプリド、酸化マグネシウム、センノシド、メチルコバラミン。
もやもや処方の処方箋・4
薬は死ぬまで飲み続けるのか!?
著者: 青島周一 , 矢吹拓 , 山本祐 , 武井大
ページ範囲:P.968 - P.975
今月の処方箋
•ヘルベッサー®Rカプセル(ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル)200mg
1回1カプセル 1日1回 朝食後
•プラビックス®(クロピドグレル)75mg
1回1錠 1日1回 朝食後
•クレストール®(ロスバスタチン)2.5mg
1回1錠 1日1回 朝食後
•タケプロン®OD(ランソプラゾール腸溶錠)15mg
1回1錠 1日1回 朝食後
•ハーフジゴキシン®KY(ジゴキシン)0.125mg
1回1錠 1日1回 朝食後
•エクア®(ビルダグリプチン)50mg
1回1錠 1日2回 朝夕食後
•ペルサンチン®(ジピリダモール)25mg
1回1錠 1日2回 朝夕食後
•アイトロール®(硝酸イソソルビド)20mg
1回1錠 1日2回 朝夕食後
•アマリール®(グリメピリド)1mg
1回1錠 1日2回 朝夕食後
•ビオフェルミン®(ビフィズス菌製剤)
1回1錠 1日3回 毎食後
•マーズレン®S配合顆粒(アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン)
1回0.67g 1日3回 毎食後
ジェネラリスト漢方Basics|東西2つの視点でアプローチ・7
「私、ふりけを病むんです!」—水毒;水分代謝の異常
著者: 岡部竜吾
ページ範囲:P.976 - P.978
漢方薬を活用するにあたっては、❶漢方の効きやすい適応疾患を選択すること、❷副反応や使用上の留意点を学ぶこと、❸病名や症状に対応した処方のレパートリーを増やすこと1)、❹漢方医学的視点を勉強して応用能力を高めること、の順で進めるのがよいと思う。今回から、❹の漢方医学的視点を深めていきたい。
前回は「気・血・水がバランス良く混ざり合って、全身を上から下へ、中枢から末梢へ穏やかに回っている状態が、健康状態である」ことをお伝えした。今回からは気・血・水それぞれの異常を詳細にみていきたい。今月は、機能しない水が停滞して生じるとされる「水毒」について考える。
ところで皆さん、「ふりけを病む」という言葉をご存知ですか?
診察で使える!|急性期Point-of-Care超音波ベーシックス・16
心原性肺水腫を疑った時
著者: 亀田徹
ページ範囲:P.979 - P.983
はじめに
Bラインというアーチファクト
今回は、胸膜ラインから深部に伸びる線状アーチファクト「Bライン」を用いた心原性肺水腫の超音波診断について取り上げます。Bラインの臨床応用は、主にPoint-of-Care超音波を扱う救急・集中治療領域で進められてきました。
心原性肺水腫は、病歴と身体所見で診断可能なことが多いですが、時に他の疾患との鑑別に難渋することがあります。X線はルーチンで施行されますが、約20%は受診時のX線で肺胞性浮腫像、肺血管のうっ血像、間質性浮腫像を認めず1)、胸部X線の各所見の感度は低いとされています。一方、Bラインによる心原性肺水腫の評価は習得が容易で2〜5)、診察の一環としての活用が期待されています。
心原性肺水腫では、肺胞周囲の狭義間質、気管支血管周囲や臓側胸膜に連続する小葉間隔壁を含む広義間質に液体が貯留し、病態が進行すると肺胞内に液体が貯留します6, 7)。心原性肺水腫においてBライン発生のメカニズムは解明されていませんが、小葉間隔壁と肺胞内に液体が貯留することで顕在化すると推測されています8, 9)。
*本論文中、[▶動画]マークにつきましては、関連する動画を見ることができます(公開期間:2020年6月30日まで)。
I LOVE Urinalysis|シンプルだけどディープな尿検査の世界・16
尿中ナトリウム
著者: 上田剛士
ページ範囲:P.984 - P.987
Case
患者:71歳、女性。
病歴:食欲低下で受診。既往に高血圧、心不全があり、利尿薬を服用している。
血圧142/86mmHg、脈拍数88回/分。
身体所見上は体液量に過不足はない。
BUN 26mg/dL
Cr 1.1mg/dL
尿酸 5.8mEq/L
Na 128mEq/L
K 3.1mEq/L
血清浸透圧 271mOsm/kg
尿比重 1.012
尿Cr 39mg/dL
尿Na 50mEq/L
尿尿酸 18.1mg/dL
オール沖縄!カンファレンス|レジデントの対応と指導医の考えVer.2.0・19
「目の奥が刺されているように痛い!」「ものが二重に見える!」を主訴に救急室を受診した50代男性
著者: 齋藤隆弘 , 永田恵蔵 , 平辻知也 , 徳田安春
ページ範囲:P.988 - P.992
CASE
患者:57歳、男性。
主訴:頭痛。
現病歴:入院する5日前から、左眼と左眼奥の部位の頭痛を自覚している。頭痛は徐々に出現しており、突発発症ではない。頭痛の性状は鈍痛であり、拍動性ではなかった。頭痛の程度は「人生で一番痛い」ほどではないが、これまでとは異なる痛みだった。症状の経過は徐々に増悪傾向であった。随伴症状として、嘔気と複視を伴った。光過敏や音過敏は認めなかった。入院3日前に近医を受診し、頭部CTを撮影し、頭蓋内疾患は指摘されなかったが、症状の軽快をみないため、当院を受診した。経過中の発熱や鼻汁、意識障害、顎跛行は認めなかった。
既往歴:片頭痛、左視床出血、心筋梗塞。アレルギーはない。
内服薬:ピタバスタチン4mg、アスピリン100mg、ボノプラザン10mg、カンデサルタン2mg、プラスグレル3.75mg、エドキサバン60mg、カルベジロール1.25mg。
家族歴:父親が高血圧。
生活歴:ADL(activities of daily living)は自立。
嗜好歴:喫煙は6年前まで、10本/日×28年間。飲酒なし。
来院時身体所見:血圧 151/101mmHg、脈拍数54回/分、呼吸数18回/分、体温35.6℃、SpO2 97%(室内気)。
全身状態:疼痛強く活気低下。GCS(Glasgow Coma Scale)はE4V5M6。左眼球結膜に充血あり。黄疸なし。咽頭発赤はなく、口腔内衛生環境は保たれている。髄膜刺激症状はなし。
胸部:心音は整・心雑音なし。呼吸音は清・左右差なし。
腹部:平坦で軟、腸蠕動音は正常、圧痛なし。下腿浮腫なし。
神経所見:視野異常はなし、左眼瞼下垂あり。瞳孔径は右2mm、左3mm。左眼の散瞳を認め、対光反射は緩慢だった。左眼の内転、外転障害を認める(図1)。
脳神経所見:異常は認めず。
四肢:体幹の筋力低下を認めず。四肢腱反射も正常で、病的反射は陰性であった。
来院時検査所見:
●血算:WBC 6,100/μL、RBC 416×104/μL、Hb 13.5g/dL、 Hct 39.8%、Plt 18.1×104/μL。
●生化学: Na 140mEq/L、K 4.3mEq/L、BUN 18mg/dL、Cr 0.82mg/dL、AST 18IU/L、ALT 19IU/L、LDH 228IU/L、RF 2.6IU/L、C3 108mg/dL、C4 18mg/dL、CRP 0.02mg/dL、ESR 2mm/hr。
●頭部CT:明らかな異常所見なし。
みるトレ Special・19
お疲れのあなたもご注意!
著者: 佐田竜一
ページ範囲:P.993 - P.996
患者:39歳、男性。医師。妻・子ども2人と4人暮らし。
主訴:右上眼瞼の違和感。
既往歴:特記すべきことなし。
薬剤歴:サプリメント・漢方・健康食品含めてなし。
現病歴:3日前は当直で忙しかった。1日前から右眼の違和感を自覚した。当日、右眼の開けづらさとじんわりした疼痛を自覚したため、隣の机の医師に相談した。自覚できる視野異常や羞明、霧視などは認めない。
身体所見:血圧126/78mmHg、脈拍数64回/分、体温36.3℃、呼吸数10回/分、SpO2 98%(室内気)。右上眼瞼に発赤・腫脹があるが(図1)、自覚的にも他覚的にも明らかな視野異常なし。その他、頭頸部・胸腹部・四肢に明らかな異常所見なし。
検査所見:擦過グラム染色所見(図2)。
国試にたずねよ・19
狐の手袋
著者: 山中克郎
ページ範囲:P.1010 - P.1014
社会を震撼させた「和歌山カレー事件」が起こったのは、今からちょうど20年前の7月であった。医師であり作家の帚木蓬生が書いた『悲素』1)に事件の背景が詳細に語られている。ヒ素による毒殺には、長い歴史があることを知った。知識や経験がない疾患の診断は難しい。
薬物の「効用」と「中毒」の境界は必ずしも明確ではない。朝起きてすぐにコーヒー豆を挽き、コーヒーをいれるのが日課になっている。コーヒーは1日5杯くらい飲むことが多いので、“カフェイン中毒”になっているのかもしれない。しかし、香りよいコーヒーを飲むとスッキリ目が覚め、勉強モードに切り替わる。
総合診療専門医セルフトレーニング問題・16
55歳からの家庭医療|明日から地域で働く技術とエビデンス・19
家庭医の臨床的方法—まとめ—EXPERT GENERALIST PRACTICE
著者: 藤沼康樹
ページ範囲:P.1018 - P.1020
前回まで、家庭医療における「臨床的方法」に関して考察を続けてきました。そして、その目指すところは、家庭医が地域基盤型プライマリ・ケア担当ジェネラリストだとした時に、ジェネラリストならではの「卓越性(expertise)」を明らかにすることにありました。
こんなときオスラー|超訳『平静の心』・19
“科学の探究”という予防接種—「科学のパン種」の章より
著者: 平島修
ページ範囲:P.1021 - P.1025
◦“パン種”とは?
“パン種”とはパン生地を膨らませるもので、通常イースト(酵母)が使われる。変化をもたらすもの、活性化するもの、影響を与えるもののたとえとして、オスラー先生は新約聖書から好んで引用していた。マタイの福音書には、「天国はパン種のようなものである」「あなたがたは、少しのパン種が粉のかたまり全体を膨らませることを、知らないのか」とある。
#総合診療
#今月の特集関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.945 - P.945
#今月の特集関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.950 - P.950
#今月の特集関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.965 - P.965
#今月の特集関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.997 - P.1003
#今月の連載関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.983 - P.983
#今月の連載関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.1025 - P.1025
#医学書院の新刊 フリーアクセス
ページ範囲:P.1005 - P.1005
#書評:HEATAPP!—たった5日で臨床の“質問力”が飛躍的に向上する、すごいレクチャー フリーアクセス
著者: 國松淳和
ページ範囲:P.1007 - P.1007
まず、本書を読む前の評者の気持ちを吐露しよう。1つは、私は大学教員の経験がなく学生に臨床を教えたことがないため、それを岩田先生がどのように実践されているのか知ることができるという“期待と喜び”である。他大学・他機関の講義がそのまま聴けるというのは、本当においしい。2つ目は、評者自身が「グループ学習」が非常に苦手であり、正直に言えば“いぶかしい気持ち”である。「さあ、隣の人と考えてみましょう!」という、声高でキラキラした笑顔のリーダーの呼びかけが本当に嫌いだからだ。最後に、4月の中頃に手にした本書、正直言うと多忙であり「(書評のためとはいえ)せっかく読むのだから、役に立つといいな」という“浅ましい気持ち”。以上、3つの気持ちである。
そして読了後、これらの3つの気持ちはすべて裏切られた。書評の途中で恐縮だが、こういう書籍こそ読むべきである。何の裏切りもない本や、期待どおりの本などは、読む必要がない。
#書評:—臨床検査専門医が教える—異常値の読み方が身につく本 フリーアクセス
著者: 高木康
ページ範囲:P.1009 - P.1009
本書の著者の村上純子先生は、「臨床検査値のウラとオモテ」を理解する数少ない“真の臨床検査専門医”の1人であり、検査値のもつ深い意味を読み解くことのできる専門医です。
RCPC(Reversed Clinico-Pathological Conference)は、1965年に日本臨床病理学会(現・日本臨床検査医学会)関東支部例会で初めて企画され、その時の演者のお1人である河合忠先生(元・日本臨床病理学会会長)が1967年から日本大学医学部臨床病理学教室(現・臨床検査医学)での卒前教育に導入されたのが先駆けです。村上先生はその教室に在籍し、RCPCのノウハウを修得するとともに、この素晴らしい教育技法を全国に普及させたお1人です。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.878 - P.879
『総合診療』編集方針 フリーアクセス
ページ範囲:P.885 - P.885
1991年に創刊した弊誌は、2015年に『JIM』より『総合診療』に誌名を変更いたしました。その後も高齢化はさらに進み、社会構造や価値観、さらなる科学技術の進歩など、日本の医療を取り巻く状況は刻々と変化し続けています。地域医療の真価が問われ、ジェネラルに診ることがいっそう求められる時代となり、ますます「総合診療」への期待が高まってきました。これまで以上に多岐にわたる知識・技術、そして思想・価値観の共有が必要とされています。そこで弊誌は、さらなる誌面の充実を図るべく、2017年にリニューアルをいたしました。本誌は、今後も下記の「編集方針」のもと、既存の価値にとらわれることなく、また診療現場からの要請に応え、読者ならびに執筆者のみなさまとともに、日本の総合診療の新たな未来を切り拓いていく所存です。
2018年1月 『総合診療』編集委員会
読者アンケート
ページ範囲:P.1027 - P.1027
『総合診療』バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.1028 - P.1029
お得な年間購読のご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.1029 - P.1030
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.1031 - P.1032
基本情報
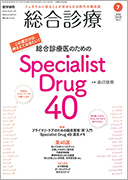
バックナンバー
34巻12号(2024年12月発行)
特集 妊婦・褥婦が外来に来たらUpdate—症状対応からワクチン・プラネタリーヘルスまで
34巻11号(2024年11月発行)
特集 電子カルテとベッドサイドの壁を打ち破る!—患者情報の「言語化」への挑戦
34巻10号(2024年10月発行)
特集 化かしが得意なカメレオンな疾患を捕まえろ!—よくある騙され方のゲシュタルト
34巻9号(2024年9月発行)
特集 今伝えたいクリニカル・パール—つくり方、使い方、活かし方
34巻8号(2024年8月発行)
特集 ストーン・ウォーズ 果てしなき“石”と医師との闘い
34巻7号(2024年7月発行)
特集 どうする!? 健診異常—これってホントに異常なの? どう説明する?
34巻6号(2024年6月発行)
特集 医師のウェルビーイング
34巻5号(2024年5月発行)
特集 —優柔不断にサヨウナラ!—あなたの「臨床判断」を高めるケーススタディ11選
34巻4号(2024年4月発行)
特集 困ったときの漢方—この症状に役立ちます!
34巻3号(2024年3月発行)
特集 —え、ウソ!実は◯◯だった!?—“コモンディジーズ”の診断ピットフォール
34巻2号(2024年2月発行)
特集 日常診療で出合う筋骨格疾患—脳神経内科と整形外科からのアプローチ
34巻1号(2024年1月発行)
特集 —“体験型”臨床クイズで習得する!—フィジカル診断エクセレンス
33巻12号(2023年12月発行)
特集 海の外へ渡る航行者を診る—アウトバウンドにまつわるetc.
33巻11号(2023年11月発行)
特集 —続・総合診療外来に“実装”したい—最新エビデンスMy Best 3
33巻10号(2023年10月発行)
特集 ○×クイズ110問!日常診療アップグレード—Choosing WiselyとHigh Value Careを学ぼう
33巻9号(2023年9月発行)
特集 ジェネラリストのための「発達障害(神経発達症)」入門
33巻8号(2023年8月発行)
特集 都市のプライマリ・ケア—「見えにくい」を「見えやすく」
33巻7号(2023年7月発行)
特集 “消去法”で考え直す「抗菌薬選択」のセオリー—広域に考え、狭域に始める
33巻6号(2023年6月発行)
特集 知っておくべき!モノクロな薬たち(注:モノクローナル抗体の話ですよ〜)
33巻5号(2023年5月発行)
特集 —疾患別“イルネススクリプト”で学ぶ—「腹痛診療」を磨き上げる22症例
33巻4号(2023年4月発行)
特集 救急対応ドリル—外来から在宅までの60問!
33巻3号(2023年3月発行)
特集 —自信がもてるようになる!—エビデンスに基づく「糖尿病診療」大全—新薬からトピックスまで
33巻2号(2023年2月発行)
特集 しびれQ&A—ビビッとシビれるクリニカルパール付き!
33巻1号(2023年1月発行)
特集 COVID-19パンデミック 振り返りと将来への備え
32巻12号(2022年12月発行)
特集 レクチャーの達人—とっておきの生ライブ付き!
32巻11号(2022年11月発行)
特集 不定愁訴にしない“MUS”診療—病態からマネジメントまで
32巻10号(2022年10月発行)
特集 日常診療に潜む「処方カスケード」—その症状、薬のせいではないですか?
32巻9号(2022年9月発行)
特集 総合診療・地域医療スキルアップドリル—こっそり学べる“特講ビデオ”つき!
32巻8号(2022年8月発行)
特集 こんなところも!“ちょいあて”エコー—POCUSお役立ちTips!
32巻7号(2022年7月発行)
特集 —どうせやせない!? やせなきゃいけない??苦手克服!—「肥満」との向き合い方講座
32巻6号(2022年6月発行)
特集 総合診療外来に“実装”したい最新エビデンス—My Best 3
32巻5号(2022年5月発行)
特集 「診断エラー」を科学する!—セッティング別 陥りやすい疾患・状況
32巻4号(2022年4月発行)
特集 えっ、これも!? 知っておきたい! 意外なアレルギー疾患
32巻3号(2022年3月発行)
特集 AI時代の医師のクリニカル・スキル—君は生き延びることができるか?
32巻2号(2022年2月発行)
特集 —withコロナ—かぜ診療の心得アップデート
32巻1号(2022年1月発行)
特集 実地医家が楽しく学ぶ 「熱」「炎症」、そして「免疫」—街場の免疫学・炎症学
31巻12号(2021年12月発行)
特集 “血が出た!”ときのリアル・アプローチ—そんな判断しちゃダメよ!
31巻11号(2021年11月発行)
特集 Q&Aで深める「むくみ診断」—正攻法も!一発診断も!外来も!病棟も!
31巻10号(2021年10月発行)
特集 医師の働き方改革—システムとマインドセットを変えよう!
31巻9号(2021年9月発行)
特集 「検査」のニューノーマル2021—この検査はもう古い? あの新検査はやるべき?
31巻8号(2021年8月発行)
特集 メンタルヘルス時代の総合診療外来—精神科医にぶっちゃけ相談してみました。
31巻7号(2021年7月発行)
特集 新時代の「在宅医療」—先進的プラクティスと最新テクノロジー
31巻6号(2021年6月発行)
特集 この診断で決まり!High Yieldな症候たち—見逃すな!キラリと光るその病歴&所見
31巻5号(2021年5月発行)
特集 臨床医のための 進化するアウトプット—学術論文からオンライン勉強会、SNSまで
31巻4号(2021年4月発行)
特集 消化器診療“虎の巻”—あなたの切実なギモンにズバリ答えます!
31巻3号(2021年3月発行)
特集 ライフステージでみる女性診療at a glance!—よくあるプロブレムを網羅しピンポイントで答えます。
31巻2号(2021年2月発行)
特集 肺炎診療のピットフォール—COVID-19から肺炎ミミックまで
31巻1号(2021年1月発行)
特別増大特集 新型コロナウイルス・パンデミック—今こそ知っておきたいこと、そして考えるべき未来
30巻12号(2020年12月発行)
特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き) Part 2
30巻11号(2020年11月発行)
特集 診断に役立つ! 教育で使える! フィジカル・エポニム!—身体所見に名を残すレジェンドたちの技と思考
30巻10号(2020年10月発行)
特集 —ポリファーマシーを回避する—エビデンスに基づく非薬物療法のススメ
30巻9号(2020年9月発行)
特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【感染症・内分泌・整形外科 編】
30巻8号(2020年8月発行)
特集 マイナーエマージェンシー門外放出—知っておくと役立つ! テクニック集
30巻7号(2020年7月発行)
特集 その倦怠感、単なる「疲れ」じゃないですよ!—筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群とミミック
30巻6号(2020年6月発行)
特集 下降期慢性疾患患者の“具合”をよくする—ジェネラリストだからできること!
30巻5号(2020年5月発行)
特集 誌上Journal Club—私を変えた激アツ論文
30巻4号(2020年4月発行)
特集 大便強ドリル—便秘・下痢・腹痛・消化器疾患に強くなる41問!
30巻3号(2020年3月発行)
特集 これではアカンで!こどもの診療—ハマりがちな11のピットフォール
30巻2号(2020年2月発行)
特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【循環器・消化器・神経疾患編】
30巻1号(2020年1月発行)
特集 総合診療医の“若手ロールモデル”を紹介します!—私たちはどう生きるか
29巻12号(2019年12月発行)
特集 困っている“あなた”に届く 認知症診療
29巻11号(2019年11月発行)
特集 臨床写真図鑑 レアな疾患編—見逃したくない疾患のコモンな所見
29巻10号(2019年10月発行)
特集 教えて!医師のためのビジネス・スキル
29巻9号(2019年9月発行)
特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き)
29巻8号(2019年8月発行)
特集 —ノーモア見逃し—日常の検査と画像に潜むピットフォール
29巻7号(2019年7月発行)
特集 リウマチ・膠原病ミミック症例帖—“膠原病っぽくみえてしまう疾患たち”にだまされない!
29巻6号(2019年6月発行)
特集 皮膚科診療エクササイズ—1枚の写真から
29巻5号(2019年5月発行)
特集 一般外来で診断できたら「えっへん!」な疾患38
29巻4号(2019年4月発行)
特集 “ナゾ”の痛み診療ストラテジー|OPQRSTで読み解く
29巻3号(2019年3月発行)
特集 —あなたのギモンに答えます!—循環器診療のハードルを下げるQ&A31
29巻2号(2019年2月発行)
特集 意外な中毒、思わぬ依存、知っておきたい副作用—一般外来で!OTCも処方薬も!
29巻1号(2019年1月発行)
特集 教えて検索!—膨大な医学情報を吟味・整理するスキル
28巻12号(2018年12月発行)
特集 こんなときこそ漢方を!
28巻11号(2018年11月発行)
特集 日本一マジメな「おしっこドリル」—今これだけは押さえておきたい腎・泌尿器のモンダイ
28巻10号(2018年10月発行)
特集 クリニカル・パールPremium!—憧れのカリスマ医師はかく語りき
28巻9号(2018年9月発行)
特集 オンコ・ジェネラリスト—「がん」に強い総合診療医をめざして
28巻8号(2018年8月発行)
特集 80歳からの診療スタンダードUp to Date—Silver Standard
28巻7号(2018年7月発行)
特集 この薬だけは押さえておきたい! 総合診療医のためのSpecialist Drug 40
28巻6号(2018年6月発行)
特集 聴診・触診×エコーで診断推論!—Point-of-Care超音波(POCUS)の底力
28巻5号(2018年5月発行)
特集 “一発診断”トレーニング問題集—懸賞論文「GM Clinical Pictures」大賞発表!
28巻4号(2018年4月発行)
特集 感染症外来診療「賢医の選択」—検査・経口薬・ワクチンをどう使えばいいんですか?
28巻3号(2018年3月発行)
特集 糖尿病のリアル—現場の「困った!」にとことん答えます。
28巻2号(2018年2月発行)
特集 頭痛患者で頭が痛いんです!
28巻1号(2018年1月発行)
特集 シン・フィジカル改革宣言!—私の“神技”伝授します。
27巻12号(2017年12月発行)
特集 小児診療“苦手”克服!!—劇的Before & After
27巻11号(2017年11月発行)
特集 今そこにある、ファミリー・バイオレンス|Violence and Health
27巻10号(2017年10月発行)
特集 めまいがするんです!─特別付録Web動画付
27巻9号(2017年9月発行)
特集 うつより多い「不安」の診かた—患者も医師も安らぎたい
27巻8号(2017年8月発行)
特集 見逃しやすい内分泌疾患─このキーワード、この所見で診断する!
27巻7号(2017年7月発行)
特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 3 カリスマ編
27巻6号(2017年6月発行)
特集 「地域を診る医者」最強の養成法!
27巻5号(2017年5月発行)
特集 コミュニケーションを処方する—ユマニチュードもオープンダイアローグも入ってます!
27巻4号(2017年4月発行)
特集 病歴と診察で診断できない発熱!—その謎の賢い解き方を伝授します。
27巻3号(2017年3月発行)
特集 これがホントに必要な薬40—総合診療医の外来自家薬籠
27巻2号(2017年2月発行)
特集 The総合診療ベーシックス—白熱!「総合診療フェスin OKINAWA」ライブ・レクチャー! 一挙公開 フィジカル動画付!
27巻1号(2017年1月発行)
特集 総合診療の“夜明け”—キーマンが語り尽くした「来し方、行く末」
26巻12号(2016年12月発行)
特集 これでパッチリ! 眼の健康問題
26巻11号(2016年11月発行)
特集 続・しびれるんです!
26巻10号(2016年10月発行)
特集 内科診療を劇的に変える“まとめ”の達人
26巻9号(2016年9月発行)
特集 症状・症候別 エコーを使った診断推論─Point-of-Care超音波
26巻8号(2016年8月発行)
特集 The 初診外来
26巻7号(2016年7月発行)
特集 感染症ケアバンドル・チェックリスト
26巻6号(2016年6月発行)
特集 “賢い処方”と“ナゾ処方”
26巻5号(2016年5月発行)
特集 しびれるんです!─知っておくべきシビレル疾患
26巻4号(2016年4月発行)
特集 ケースとクイズで総ざらい! 街場の2型糖尿病治療
26巻3号(2016年3月発行)
特集 こんな時は漢方でしょう!
26巻2号(2016年2月発行)
特集 フィジカル改革宣言! ──診断からフォローアップまで
26巻1号(2016年1月発行)
特集 妊婦・褥婦が一般外来に来たら─エマージェンシー&コモンプロブレム
25巻12号(2015年12月発行)
特集 外来で「複数の疾患」をもつ患者を診る─マルチモビディティの時代のプライマリ・ケア
25巻11号(2015年11月発行)
特集 レアだけど重要な「痛み」の原因─システム1診断学
25巻10号(2015年10月発行)
特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 2
25巻9号(2015年9月発行)
特集 診断ピットフォール10選─こんな疾患,見逃していませんか?
25巻8号(2015年8月発行)
特集 健診データで困ったら─こんな検査結果を持ってこられたら
25巻7号(2015年7月発行)
特集 ここを知りたい!頭部外傷初期対応・慢性期ケア
25巻6号(2015年6月発行)
特集 高齢者救急の落とし穴─紹介する時,される時
25巻5号(2015年5月発行)
特集 咳を聴きとり,咳を止める
25巻4号(2015年4月発行)
特集 関節が痛いんです!─コモンからレアものまでの診断と治療
25巻3号(2015年3月発行)
特集 神経難病ケアのコペルニクス的転回
25巻2号(2015年2月発行)
特集 総合医のためのスポーツ医学ベーシックス
25巻1号(2015年1月発行)
特集 動悸・息切れ─ヤバい病気の見つけ方 そして見つからなかった時の対処法
