2024年から働き方改革の医師への導入が予定されているが、現場ではどの程度、現実感を持って受け止められているだろうか?「そもそも働き方改革は必要ない」という意見や、「無理である」という意見も現場では多かったのではないだろうか?
2020年から医療現場はコロナ禍の状況となったが、国の方向性は働き方改革に向けて舵を切られており、もはや前に進むしかない状況となっている。おそらく医療界に大きな変化をもたらすであろう「医師の働き方改革」をどう見るか? そして現場で、どうシステムとマインドセットを変えていくか?
本特集ではさまざまな観点から医師の働き方改革を概観し、来るべき時代にどう対応していくか、読者と共に考えたい。
雑誌目次
総合診療31巻10号
2021年10月発行
雑誌目次
特集 医師の働き方改革—システムとマインドセットを変えよう!
扉 フリーアクセス
著者: 片岡仁美
ページ範囲:P.1212 - P.1213
【総論】
❶なぜシステムとマインドセットを変えるのか?
著者: 片岡仁美
ページ範囲:P.1215 - P.1215
働き方改革が社会全体で進められているが、医師は働き方の特殊性と著しい長時間労働の実態があることから、医師の働き方改革に関する検討会が設けられた1)。[総論❷]の渋谷健司先生(p.1216〜)が副座長を務められた同検討会において、私も構成員として2年余りの議論に参加した。自身も多くを学び考えるなかで、働き方改革を受け身ではなく、自ら考えて取り組む必要性を実感した。検討会の詳細については渋谷論文を参照されたいが、本稿では自身の経験からマインドセットとシステムについて考察したい。
卒業後、研修病院で上司に言われたことは、「医師はどれだけ自分のプライベートの時間を患者さんに捧げられるかで価値が決まる」ということだった。労働時間が著しく長いだけでなく、プライベートがほとんどない生活は、「普通の」生活をしていた私の価値観を塗り替えるのに十分過ぎた。当直による寝不足、慣れない仕事の緊張感と感情的にもすり減っていくことが重なり、私はたやすく「自分の時間をすべて捧げるのが医師として当然」という価値観に染まり、それについて考えることもなくなった。
❷「医師の働き方改革」で伝えたいこと
著者: 渋谷健司
ページ範囲:P.1216 - P.1220
読者にとって「医師の働き方改革」はどのような印象を受けるだろうか? ある人にとっては勤務時間が管理され、今までのような超過勤務が減るのではないか、と好意的に考えるかもしれない。逆に、大学病院などで働いている若手にとっては、当直やアルバイトの時間が減って、どうやって生活を維持できるのか不安になるかもしれない。コメディカルの方は、タスクシフトやその負担が気になるかもしれない。サービスを管理する側の視点からは、医師不足がますます顕在化して医療供給体制が維持できなくなってしまう、と考える方もいるかもしれない。多様な意見があると思われるが、共通する印象は、「よくわからないけれども、自分の身がどうなるか不安だ」ということではないだろうか。そのため、医師の働き方改革とは何を目指したのか、そしてその先にある医療のあり方を、できるだけ多くの医療関係者と共有する必要があるだろう。
本稿では、この2点に関して、医師の働き方改革の前提となる医療のあり方のビジョン、そして、医師の働き方改革そのものに関する2つの政府の検討会に関わった者として、私見を述べたいと思う。
❸一目でわかる「医師の働き方改革」
著者: 安里賀奈子
ページ範囲:P.1222 - P.1223
医師の働き方改革はなぜ必要か?
▶より良い医療の提供へ——医者の不養生からの卒業!
◦休息を確保し、健康を維持しながら働ける環境が必要!
◦自分の時間を確保して、各医師がそれを、研究/自己研鑽/リフレッシュする時間などに自己投資することで、より質の高い医療の提供につながる!
【360度 働き方改革】働き方改革をもっと詳しく!
❶【インタビュー】なぜ働き方改革が必要か?—人口減少社会への対策として
著者: 白河桃子 , 片岡仁美
ページ範囲:P.1224 - P.1228
人口減少社会を支えるために、働き方改革は必須と考えられる。
「なぜ働き方改革が必要なのか?」。本特集を企画した片岡仁美氏が、他業界の働き方改革の成功と失敗を熟知する白河桃子氏に、その本質について聞いた。
❷医師の働き方改革の進め方—病院経営の観点から
著者: 裵英洙
ページ範囲:P.1229 - P.1232
高齢化社会の進展とともに複合疾患を有する高齢患者や難症例患者が増えてきており、医療現場の負担は増大傾向にある。また、医療の質の向上と患者の要求の高まりが相まって、医師をはじめ、医療者が習得すべき医学知識や技術は日に日に増えてきている。さらに、医師不足、医師偏在のなか、自己犠牲や自己献身の姿勢で、心身ともに疲弊状態で臨床現場に立ち続ける医師は少なくない。
そのような状況のなかで、医師の働き方改革はいよいよカウントダウンに入ってきた。2024年4月に医師の時間外労働時間の上限規制がスタートする。ようやく、「働き過ぎ」といわれて久しい医師の世界に、大きな改革がやってくるのだ。ただ実際には、医療機関内で働き方改革を進める際に、「効率的な進め方がわからない」「すべきことが多過ぎて、何から手を付けるべきかわからない」「大きな問題過ぎて対処できない」などの経営・マネジメント側の困惑の声も聞こえてくる。
❸医師会は「働き方改革」をこう見る
著者: 今村聡
ページ範囲:P.1233 - P.1236
2017年3月に閣議決定された働き方改革実行計画において、医師の働き方については「別途協議の場を設ける」とされた。その後、2020年12月までの間に2つの検討会の議論を経て、2021年5月末に医師の働き方を規定した医療法等の改正法が成立した。議論を始めてから法律制定に至るまでに約4年を要した大きな制度改革である。
日本医師会は、2008年に勤務医の健康を守るプロジェクト委員会を設置し、勤務医の健康を守る病院7か条、医師が元気に働くための7か条の作成、病院管理者を対象とした勤務医の健康支援ワークショップの開催など、働き方改革が議論になる前から、勤務医の健康支援に長年地道に取り組んできた。小職は厚生労働省の「医師の働き方改革の推進に関する検討会」に参画し、日本医師会の10年以上にわたる取り組みの知見をもとに意見を述べてきた。以下、現時点で決まっている制度概要を述べるが、具体的な制度設計はこれからである。より良い制度になるよう、引き続き力を尽くしていきたい。
【360度 働き方改革】働き方改革と法
❹応招義務の考え方
著者: 三谷和歌子
ページ範囲:P.1237 - P.1240
働き方改革と応招義務
医師の働き方改革を進めるにあたり、医師の特殊性として応招義務の存在が挙げられた。
応招義務は、医師法第19条第1項において、「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」として規定されている。
❺宿日直、自己研鑽の考え方
著者: 安里賀奈子
ページ範囲:P.1241 - P.1244
宿日直や自己研鑽については、医師の働き方改革に関する検討会において、
❶ 宿日直の待機時間は、労働時間から除外してもよいのではないか?
❷ 論文作成や学会発表準備のために院内に残り、電子カルテの操作等を行うことや、自ら経験を積みたいと業務終了後に自主的に残って診療の機会を待つ場合もある。在院時間がすべて労働時間とは限らないのではないか?
といった要望が医療界より寄せられ、労働法学者も交えて議論され1)、これを契機に、令和元(2019)年7月に宿日直許可基準および研鑽に係る労働時間に関する考え方について、よりわかりやすく示した通達が発出されるに至っています2〜4)。また❶については、実際の許可事例を含めた制度の説明資料を作成しています5)。
本稿では、宿日直許可制度および研鑽の労働時間該当性について、そのエッセンスをご紹介します。
【360度 働き方改革】緊急に取り組むべき項目—どう対応する?
❻タスクシェア・タスクシフトは実際にどこまでできる?
著者: 江原淳
ページ範囲:P.1245 - P.1248
医師の「働き方改革」において、タスクシェア・タスクシフトの推進はきわめて重要である。患者ケアにまつわる実務はそう簡単には減らせないので、そのなかで他の職種に移行できるものを他職種に移行する、もしくは他職種が共同で実施することで質を落とさず医師の労働を削減する、という狙いである1)。
本稿では、当院でのタスクシェア・タスクシフトの実例を挙げ、実施するための要点について解説する。前半は診療看護師(NP)について、後半はそれ以外の例について紹介する。
❼女性医師の働き方
著者: 片岡仁美
ページ範囲:P.1249 - P.1252
女性医師の現状
女性医師数は、平成30(2018)年で7万1,758人(21.9%)であり、近年の新規医師免許取得者の3割は女性である1)。女性医師の人数は増加し続けているが、女性医師の年齢構成は男性医師と異なり、全体のうち20〜30代が47%を占めている1)。このことには、近年急速に女性医師の人数が増えてきた、という要素と、女性医師の就労率が低下する年代がある、という要素の両方が関与しているだろう。
【360度 働き方改革】働き方改革とエビデンス
❽米国研修医の週80時間ルールを検証する
著者: 野木真将
ページ範囲:P.1253 - P.1256
1890年代の米国研修医は、病院に寝泊まりして研修に従事するのが一般的で、常に病院に「住んでいる」ことから「Resident(居住者)」という用語がついたのではないかと言われています。
それから時代は変わり、現在の米国レジデントは労働時間を厳しく管理されるようになりました。各地の研修プログラムは、責任を持って全レジデントの労働時間が制約内であることをACGME(Accreditation Council for Graduate Medical Education:米国卒後医学教育認可機構)に報告しています。
❾睡眠に関するエビデンス
著者: 高橋正也
ページ範囲:P.1257 - P.1259
ケガや病気は時刻に関係なく発生する。治療を担う医師は、長時間にわたって手術を施したり、深夜・早朝に処置を行ったりせざるをえない。このような働き方は睡眠を奪うことになる。睡眠研究が飛躍的に進んでいる現状では、医師の労働生活を向上させるのに役立つ成果が増えている。
本稿では、その主な知見を解説する。
❿初期臨床研修医の労働時間に関するエビデンス
著者: 西﨑祐史
ページ範囲:P.1260 - P.1263
背景
研修医の時間外労働を決定するにあたり、研修時間の確保(能力開発)と、研修医の健康が考慮されたが、教育効果に関する妥当な労働時間はエビデンスが十分でないとされ、B水準(p.1222左下参照)に習い、月155時間に決定された経緯がある。研修医の長時間労働と、燃え尽き症候群、うつ病、過度のストレス等との関連性が報告されている。研修医のメンタルヘルスを守りながら、能力を最大限開発すべく、至適労働時間の決定や研修プログラムの最適化が望まれている。
そこでわれわれは、初期臨床研修医の至適労働時間を決定していくうえで、基本的臨床能力評価試験(GM-ITE : General Medicine In-Training Examination)のデータを活用し、労働時間と基本的臨床能力の関連性を評価した1,2)。
【360度 働き方改革】私の職場の働き方改革
⓫働き方改革に取り組んだ実績と見えてきたこと
著者: 本田宜久
ページ範囲:P.1264 - P.1266
当院(頴田病院)は、2018年に労働基準監督署より突然の臨検があり、医師の就労への是正勧告を受けました。真摯に受け止め、多くの方々の協力で無事に是正することができましたが、本稿における働き方改革論においては、実は是正勧告が変革の主軸ではありません。やはり経営ビジョンや戦略に基づいた就労制度、働き方改革が重要であると感じます。
⓬クリニックでの働き方改革
著者: 雨森正記 , 中村琢弥
ページ範囲:P.1267 - P.1269
医師の働き方改革について議論は進んできている1)。しかし、診療所での医師の働き方改革は進んでいるのだろうか?
わが国の診療所は、ほとんどが医師1名のソロ開業医である。個人事業主であることから長時間勤務に関する規定は適用されないが、ほとんどは長時間勤務をされているのではないだろうか?また最近では高齢社会になり、入院から在宅へのシフトが叫ばれ、在宅医療の充実が期待されているが、複数の医師を抱える在宅専門診療所ではない個人の開業医では、24時間365日の対応をすることは困難で、社会の期待に応えにくくなっている。医師の働き方改革を進めながら、24時間365日という社会のニーズに応える方策として、グループ診療が注目されている2)。
【360度 働き方改革】医師の視点から見る働き方改革
⓭総合診療医から見る働き方改革
著者: 大野毎子
ページ範囲:P.1270 - P.1272
1993年に医学部を卒業して、家庭医寄りの総合診療医として歩んで27年になる。その経験と現在公立小病院の病院長という視点で、医師の働き方改革について私見を述べたい。
働き方改革の目指すものは以下のとおりである。
⓮産婦人科医から見る働き方改革
著者: 鈴木幸雄
ページ範囲:P.1273 - P.1276
産婦人科は働き方改革を実質的に進めていくうえで、医療提供体制の再構築という大きな課題を抱えている。われわれは生命の誕生を支えるインフラの役割を担っており、24時間体制の産婦人科診療を支えるために、若手、中堅、ベテランを問わず、限界を超えて働いているのが現状である。医師の過剰な労働量によって調整されてきてしまった提供体制を、今後は他の方法で守っていかなければならない。
医師の働き方改革の本質は「患者のwell-being」であり、それを実現するためには「医師のwell-being」1)が前提となるが、この認識はまだまだ不十分だ。現状の働き方では、客観的には過剰労働となっていても、個人や施設の使命感で何とか乗り切っている状況であり、長時間労働をしていても、「自分は何とかなっている」と主観的に判断してしまう医師も少なくない。私も以前まではその1人であったと自認している。
【コラム】
❶医療者も患者も幸せになれる、真の働き方改革とは?—医師のみ過労死ラインの2倍を容認する現実を踏まえて
著者: 中原のり子
ページ範囲:P.1277 - P.1279
◦1999年、突然の別れ
夫・中原利郎は、都内の民間病院に勤務する小児科医師でした。部長代行になって半年後、勤務先の屋上から真新しい白衣を着て投身自殺しました。享年44歳でした。執務机には「少子化と経営効率のはざまで」という文書が残されていました。医療費抑制政策、診療報酬の問題、長時間労働による医療ミスや女性医師支援の問題を訴えていました。元来明るく快活な人物で、「小児科医は天職」と公言する夫が、亡くなる前には「馬車馬のように働かされている」「病院に搾取されている」「小児科医師なんて誰にも感謝されない職業だ」と自棄的な発言を繰り返し、遺書には「不眠・不整脈・視力の衰え…精神的にも、身体的にも、限界を超えてしまいました」と綴られていました。
❷そもそも日本人の働き方って?
著者: 大室正志
ページ範囲:P.1280 - P.1281
現在、働き方をめぐる議論が活発化しています。2017年に内閣官房に設置された働き方改革推進会議では、労働生産性向上、長時間労働の是正、柔軟な働き方の環境整備、多様な人材の活躍など9つの項目に言及した働き方改革実行計画がまとめられ、2019年からは働き方改革関連法案が順次施行されています。
❸医師紹介の現状とそこから見えてくるもの
著者: 小野勝広
ページ範囲:P.1283 - P.1285
読者の皆様は、医師の転職エージェント(紹介会社)にどのような印象をお持ちでしょうか? また担当するキャリアコンサルタントに対してはいかがでしょうか? 「全く知らない」「接したことがない」という方も多いでしょうが、おそらくエージェントの宣伝広告は、WEB上で散見することと思います。しかもその大半が、たとえば高条件の求人で医師の関心を得ようとしていたり、豊富な求人数を誇ったりしているものの、残念ながら健全とは言えない印象があるのではないでしょうか。
私自身も医師の転職支援、そしてクリニックの開業支援を行っている1人ではありますが、今まで関わってきた多くの医師、また知人医師から、さらにSNSでの医師の発言なども含めて、医師の転職エージェント(紹介会社)については、正直あまりポジティブな見解を伺うことはありません。それはなぜなのでしょうか?
❹メンタルヘルスとバーンアウト
著者: 前野哲博
ページ範囲:P.1286 - P.1287
◦医療職のバーンアウト
働き方改革が進めば、近い将来、医師の労働時間は確実に減る方向に進むだろう。しかしながら、ただ時間さえ減らせば医師のメンタルヘルスが改善する、という単純な問題ではない。時々刻々と変化する環境のなかで、高い専門性とコミュニケーション能力を要求される医療職は、非常にストレスの多い職種である。そのうえ最近では深刻化する人手不足、要求される医療サービス水準の向上など、医療職を取り巻く事情は年々厳しくなってきている。
医療職のストレス反応として代表的なものがバーンアウトであり、以下の3つの下位尺度それぞれにおける程度の問題として説明されている。すなわち、❶情緒的消耗感(emotional exhaustion:仕事を通して気配りや思いやりといった情緒的なエネルギーを注ぎ続けることで、自分が消耗した状態になり、強い疲弊感を感じる)、❷脱人格化(depersonalization:自分のさらなる情緒的エネルギーの消耗を防ぐために、相手の人格を無視した、思いやりの感じられない割り切った態度などの防衛反応をとる)、❸職務効力感(personal accomplishmentの低下:自らが消耗し、他人に優しくできなくなった結果、仕事にやりがいを感じられなくなったり自信を失ったりしてしまう)である。バーンアウトの頻度は高く、医師の約半数がバーンアウトしていたとする報告もある。また医療職のバーンアウトは、医療職自身の生産性や退職率などに影響を与えるだけでなく、医療の質やエラーとも関連することが明らかになっており、ヘルスケアシステム全体に関わる大きな問題である。
❺ポスト働き方改革時代に生き抜く医師を育てる—自分自身で主体的・自律的なキャリアプランニングを
著者: 蓮沼直子
ページ範囲:P.1288 - P.1289
キャリア教育、キャリア支援とは、医師としてのキャリアのみならず、最終的にはよりよい人生を送るためのものと考えている。働き方の選択も、価値観の投影とも言える。勿論状況により選択の範囲はそれぞれ異なるが、その中から主体的に選び取り、積み重ねていってほしい。もちろん自分勝手ということではなく、主体的に社会のニーズを知り、周囲とコミュニケーションをとることは重要である。
現代の若手や女性医師を見ていると、働き方が多様化して選択肢が広がってきている分、自分の価値観を見失いがちになり、悩みが深まっているようにも思われる。自身の強みを理解してそれを伸ばしていくこと、またこれからの社会に求められる医師像や組織に求められる役割などを理解したうえで、どのような能力を獲得していくのか(したいのか)、という戦略的視点が必要である。それはたとえば、子育てなど時間的制約のある働き方や経験の中で何が得られるか、中長期的な展望のもとに何を学ぶかなど、よりよい自身の働き方を考えるヒントになるのではないか。
Editorial
未来への道しるべに フリーアクセス
著者: 片岡仁美
ページ範囲:P.1201 - P.1201
コロナ禍による医療の逼迫という報道を見ない日はなく、先が見えない閉塞感のなかで、現場の医師、医療スタッフは目の前の患者さんに向き合っている。本特集が出版される時に状況が少しでも改善されていることを願っている。
「働き方改革どころではない」という方も多くいらっしゃると思う。しかし、コロナ禍における医療の逼迫と働き方改革は、実は密接に関係している。渋谷論文(p.1216〜)で指摘されているように、わが国の医療提供体制の問題点が、急激な医療需要を生み出したコロナ禍によって、一気に顕在化したと言えよう。また、白河論文(p.1224〜)での指摘にもあるように、これまで医療従事者の長時間労働によって何とか支えられていた現場には、人的にも時間的にも余裕がなく、危機が起こった時には対応が難しくなる。
What's your diagnosis?[226]
真昼の釈迦牟尼
著者: 榎本悠里 , 河村裕美 , 杉本雪乃 , 大矢亮 , 藤本卓司
ページ範囲:P.1204 - P.1209
病歴
患者:18歳、男性
主訴:歩行障害、足のしびれ
現病歴:機械工場に就職1年目。入院2日前から現場実習が始まり、しゃがんだ姿勢で1時間ホースをひたすら結束バンドで巻く仕事をした。作業終了後、右足首より末梢がしびれていることに気づいたが、運動機能に問題はなかった。翌日、職場で習慣となっている縄跳びをした後、休憩の1時間以外、計6時間同様の作業をした。その後、右足は前日と同様の範囲にしびれが持続し、背屈ができなくなった。左足も右足と同範囲にしびれが出現したが、歩行はできた。入院当日、症状が持続し、歩くとすぐ転げて縄跳びも跳べなくなったため、近医を受診し、精査目的で当院紹介となった。
ROS陰性:腰痛、臀部痛、尿閉、尿失禁、便秘、インポテンツ、先行感染、外傷
既往歴:アトピー性皮膚炎、右膝内側側副靱帯損傷・左分裂膝蓋骨(3年前、保存的)
常用薬:アンテベート®、保湿剤塗布
生活歴:10歳から現在までバドミントンクラブに所属し熱心に活動
【エッセイ】アスクレピオスの杖—想い出の診療録・18
“WHY”を大切に
著者: 坂本壮
ページ範囲:P.1211 - P.1211
本連載は、毎月替わる著者が、これまでの診療で心に残る患者さんとの出会いや、人生を変えた出来事を、エッセイにまとめてお届けします。
55歳からの家庭医療 Season 2|明日から地域で働く技術とエビデンス・40【最終回】
55歳からの家庭医療—Fifty Five Way to Family Medicine
著者: 藤沼康樹
ページ範囲:P.1290 - P.1294
医師は、いったい何歳まで働けるのか? 仕事をリタイアするのは、どんな時なのか? 記憶力や判断力が低下した時? 体力の低下を自覚した時? それとも、仕事自体に飽きてしまった時?
単純に年齢で区切ってしまうことに関しては、歴史的には比較的最近発明された「定年」という制度がある。しかし医師の場合、たとえ勤務医であっても、定年という概念は案外曖昧である。少なくとも、ある年齢で仕事を辞めるというコンセプトは、「エイジズム(agism)」とみなされるようになっており、もはや非現実的である。
『19番目のカルテ』を読んで答える! あなたの“ドクターG度”検定&深読み解説・7
最善の選択—(『19番目のカルテ—徳重晃の問診』第7話より)
著者: 山中克郎
ページ範囲:P.1295 - P.1297
本連載は総合診療ビギナーの皆さんに、総合診療の楽しさと奥深さを解説することが目的です。漫画『19番目のカルテ』のエピソードを深読みすることにより、総合診療医がどのような根拠に基づいて診断しているのかを理解していただければ幸いです。本連載は『総合診療』×『19番目のカルテ』のコラボ企画で、本誌編集委員の山中克郎先生・徳田安春先生が隔月で作問&解説します!
患者さんには言えない!? 医者のコッソリ養生法・5
不養生の医者、「肩こり」の“集学的治療”を学ぶ
著者: 須田万勢
ページ範囲:P.1298 - P.1302
突然現れた医神・アスクレピオス(自称ピオちゃん)に、このまま不養生が続くと未来が危ないと半強制的に弟子入りさせられた貝原先生は、前回「肩こり」に対する西洋医学的アプローチを学んだ。そして今回は、伝統医学を含む“集学的治療”のレクチャーが始まる。
Dr.上田剛士のエビデンス実践レクチャー!医学と日常の狭間で|患者さんからの素朴な質問にどう答える?・19
この薬、空腹時に飲んではダメですか?
著者: 上田剛士
ページ範囲:P.1303 - P.1308
患者さんからのふとした質問に答えられないことはないでしょうか? 素朴な疑問ほど回答が難しいものはありませんが、新たな気づきをもたらす良問も多いのではないでしょうか? 本連載では素朴な疑問に、文献的根拠を提示しながらお答えします!
“コミュ力”増強!「医療文書」書きカタログ・16
—相手が“不慣れ”でも大丈夫!—手術入院中の内科管理を一時的に委託する紹介状
著者: 天野雅之
ページ範囲:P.1314 - P.1318
今月の文書
診療情報提供書
セッティング:病院→病院への紹介
患者:70歳、男性。血管炎で外来治療中の患者が、頸椎症性脊髄症を発症した。脊椎専門医のいる東部病院への手術入院が必要となった。整形外科医の仲介で内科に、血管炎の一時的管理を依頼することになり、紹介状を作成した。
【登場人物】
桜井:総合診療科1年目専攻医。南部医療センターで研修中。
生駒:総合診療科4年目専攻医。病棟診療チームのリーダー。
飛鳥:桜井の指導医。総合診療専門研修プログラムの責任者。
古津:整形外科医。外勤先の東部病院で手術の助手を務める予定。
名井:東部病院の内科医。古津は部活の先輩。血管炎の治療経験はない。
オール沖縄!カンファレンス|レジデントの対応と指導医の考えVer.2.0・58
来院時間も大事な病歴
著者: 堀内朱音 , 林耕次 , 徳田安春
ページ範囲:P.1319 - P.1322
CASE
患者:70代、女性。 主訴:下腿浮腫。
現病歴:受診1カ月前より全身倦怠感、労作時の息切れが出現。元来活動的であったが、臥床しがちになっていた。受診約1週間前より節々の痛みを自覚。肩は疼痛のため、挙上困難であった。受診4日前に変形性膝関節症で通院中の整形外科を受診。膝に関節内注射を行い、ジクロフェナクが処方された。受診2日前に両側の下腿浮腫を自覚。浮腫の増悪傾向に不安を感じ、救急外来を受診された。
既往歴:糖尿病、高血圧症、両側変形性膝関節症。
嗜好歴:飲酒なし、喫煙なし。
内服薬:エンパグリフロジン10mg 1日1錠、メトホルミン500mg 1日2錠、メトホルミン250mg 1日2錠、エナラプリル5mg 1日1錠、ヒドロクロロチアジド12.5mg 1日1錠、アトルバスタチン5mg 1日0.5錠、ファモチジン10mg 1日2錠、アムロジピン5mg 1日1錠、メチルコバラミン500μg 1日3錠、ジクロフェナク37.5mg 1日2錠。
アレルギー歴:特記事項なし。
家族歴:特記事項なし。
生活歴:長女と2人暮らし、無職。
研修医Issy&指導医Hiro&Dr.Sudoのとびだせフィジカル! 聴診音付・10
【臨床小説】後悔しない医者|あの日できなかった決断・第19話
人にないものをもっている医者
著者: 國松淳和
ページ範囲:P.1328 - P.1333
前回までのあらすじ 今月のナゾ
「本当に要るのかって、看護師さんの価値観でそんなのわかるんですか!?」。前回、初期研修1年目の五明が、看護師たちと一触即発の事態を演じた。問題の患者は80歳・女性、卵巣がんの末期で腹膜播種を伴い、アルコール性肝硬変や種々の合併症で入退院を繰り返している。今回の入院契機は蜂窩織炎だが、腹水を抜くべく腹腔穿刺の準備を依頼したところ、看護師は患者がDNARを希望していることから懸念を表明したのだ。その直前、五明は自ら採血を行い、血液培養検査も提出していた。初期研修2年目の宮川は「蜂窩織炎の血培の陽性率は高くない」と異を唱えたが、その結果は…。
内科と言えば「臨床推論」だ。卓越した臨床医のそれは、時に“名探偵”にも例えられる。進路も定まらぬ時期の初期研修医にとって、指導医の推論の理路はブラックボックスのように思えるかもしれない。黒野は、指導医たちは、悩める研修医をいかに導いていくのか?
#総合診療
#今月の特集関連本❶ フリーアクセス
ページ範囲:P.1232 - P.1232
#今月の特集関連本❷ フリーアクセス
ページ範囲:P.1248 - P.1248
#今月の連載関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.1308 - P.1308
#医学書院の新刊 フリーアクセス
ページ範囲:P.1310 - P.1311
#書評:総合内科マニュアル 第2版 フリーアクセス
著者: 青木眞
ページ範囲:P.1313 - P.1313
「時間がないので長文になりました」とは、ある賢人の言葉…。文章表現は、その贅肉を「そぎ落とす」ことが本質ということなのだろうか? 評者も「できる」研修医には10秒で症例をプレゼンさせることがある。面白いことに、10秒を強いられた瞬間に、その研修医に症例の本質が見えてくるから不思議なものである。本書も余分なものが徹底的に削られた、それゆえに極めて中身の濃いマニュアルとなっている。「(総合内科の)大多数のコモンな問題に世界標準の質で診療ができるようにまとめた」という本書の一部を、本文を引用しながらご紹介しようと思う。
第1章「患者ケアの目標設定」:「目標設定はきわめて重要(中略)。目標を設定し、そこから逆算して手段が導き出される。(中略)手段を目的化してはならない。(中略)最大の目標は『患者のニーズ』に応えることである。(中略)隠れたニーズも(中略)プロとして積極的にこれを掘り起こす必要がある(例:閉経後女性の骨密度測定、肺炎球菌ワクチン)」(本書p.1)。「アセスメントと行動の一貫性を保つ」(p.2)。「入院初日に退院までの流れを想定する」(p.3)。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.1202 - P.1203
読者アンケート
ページ範囲:P.1312 - P.1312
『総合診療』バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.1334 - P.1335
お得な年間購読のご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.1335 - P.1336
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.1337 - P.1338
基本情報
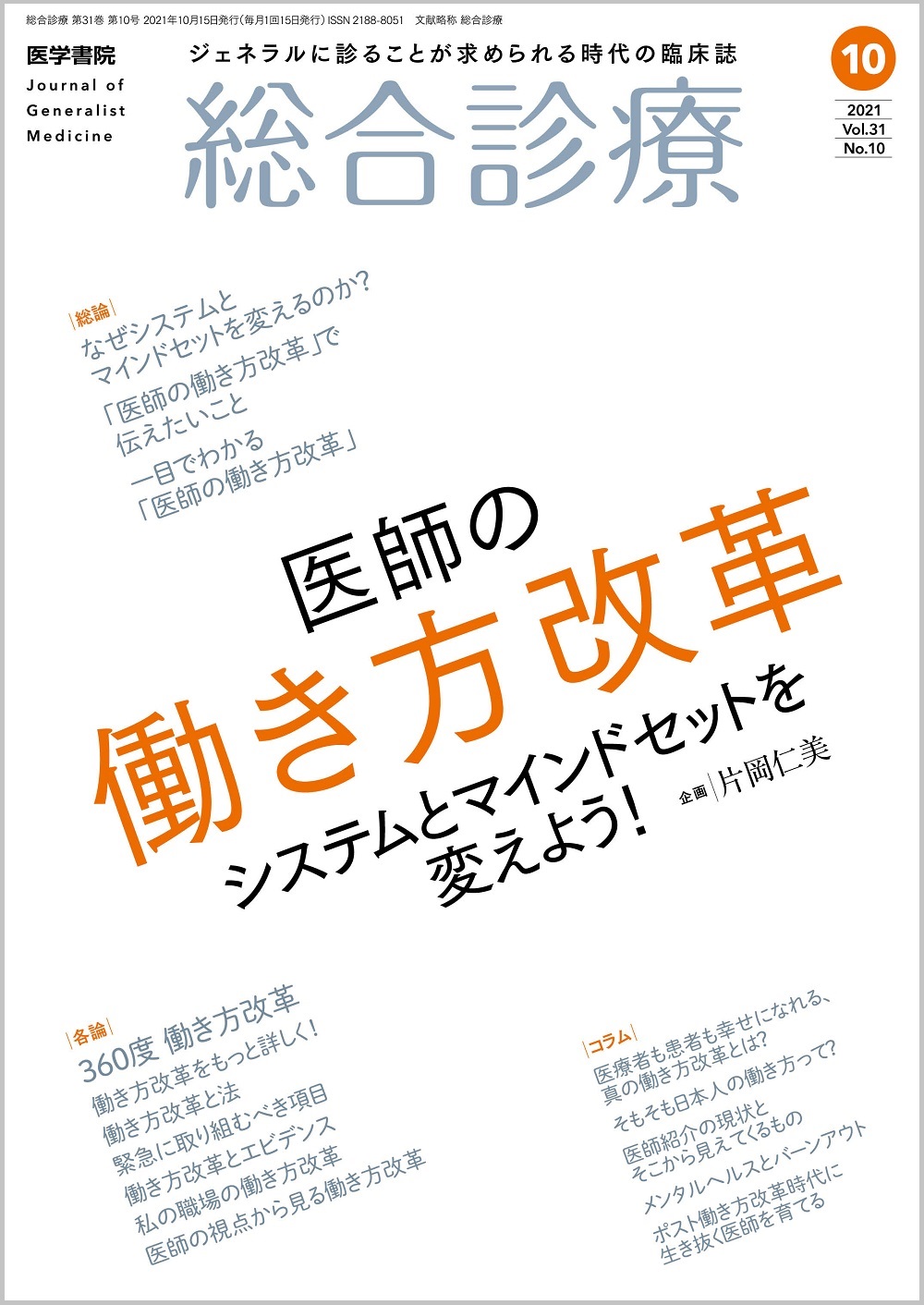
バックナンバー
34巻12号(2024年12月発行)
特集 妊婦・褥婦が外来に来たらUpdate—症状対応からワクチン・プラネタリーヘルスまで
34巻11号(2024年11月発行)
特集 電子カルテとベッドサイドの壁を打ち破る!—患者情報の「言語化」への挑戦
34巻10号(2024年10月発行)
特集 化かしが得意なカメレオンな疾患を捕まえろ!—よくある騙され方のゲシュタルト
34巻9号(2024年9月発行)
特集 今伝えたいクリニカル・パール—つくり方、使い方、活かし方
34巻8号(2024年8月発行)
特集 ストーン・ウォーズ 果てしなき“石”と医師との闘い
34巻7号(2024年7月発行)
特集 どうする!? 健診異常—これってホントに異常なの? どう説明する?
34巻6号(2024年6月発行)
特集 医師のウェルビーイング
34巻5号(2024年5月発行)
特集 —優柔不断にサヨウナラ!—あなたの「臨床判断」を高めるケーススタディ11選
34巻4号(2024年4月発行)
特集 困ったときの漢方—この症状に役立ちます!
34巻3号(2024年3月発行)
特集 —え、ウソ!実は◯◯だった!?—“コモンディジーズ”の診断ピットフォール
34巻2号(2024年2月発行)
特集 日常診療で出合う筋骨格疾患—脳神経内科と整形外科からのアプローチ
34巻1号(2024年1月発行)
特集 —“体験型”臨床クイズで習得する!—フィジカル診断エクセレンス
33巻12号(2023年12月発行)
特集 海の外へ渡る航行者を診る—アウトバウンドにまつわるetc.
33巻11号(2023年11月発行)
特集 —続・総合診療外来に“実装”したい—最新エビデンスMy Best 3
33巻10号(2023年10月発行)
特集 ○×クイズ110問!日常診療アップグレード—Choosing WiselyとHigh Value Careを学ぼう
33巻9号(2023年9月発行)
特集 ジェネラリストのための「発達障害(神経発達症)」入門
33巻8号(2023年8月発行)
特集 都市のプライマリ・ケア—「見えにくい」を「見えやすく」
33巻7号(2023年7月発行)
特集 “消去法”で考え直す「抗菌薬選択」のセオリー—広域に考え、狭域に始める
33巻6号(2023年6月発行)
特集 知っておくべき!モノクロな薬たち(注:モノクローナル抗体の話ですよ〜)
33巻5号(2023年5月発行)
特集 —疾患別“イルネススクリプト”で学ぶ—「腹痛診療」を磨き上げる22症例
33巻4号(2023年4月発行)
特集 救急対応ドリル—外来から在宅までの60問!
33巻3号(2023年3月発行)
特集 —自信がもてるようになる!—エビデンスに基づく「糖尿病診療」大全—新薬からトピックスまで
33巻2号(2023年2月発行)
特集 しびれQ&A—ビビッとシビれるクリニカルパール付き!
33巻1号(2023年1月発行)
特集 COVID-19パンデミック 振り返りと将来への備え
32巻12号(2022年12月発行)
特集 レクチャーの達人—とっておきの生ライブ付き!
32巻11号(2022年11月発行)
特集 不定愁訴にしない“MUS”診療—病態からマネジメントまで
32巻10号(2022年10月発行)
特集 日常診療に潜む「処方カスケード」—その症状、薬のせいではないですか?
32巻9号(2022年9月発行)
特集 総合診療・地域医療スキルアップドリル—こっそり学べる“特講ビデオ”つき!
32巻8号(2022年8月発行)
特集 こんなところも!“ちょいあて”エコー—POCUSお役立ちTips!
32巻7号(2022年7月発行)
特集 —どうせやせない!? やせなきゃいけない??苦手克服!—「肥満」との向き合い方講座
32巻6号(2022年6月発行)
特集 総合診療外来に“実装”したい最新エビデンス—My Best 3
32巻5号(2022年5月発行)
特集 「診断エラー」を科学する!—セッティング別 陥りやすい疾患・状況
32巻4号(2022年4月発行)
特集 えっ、これも!? 知っておきたい! 意外なアレルギー疾患
32巻3号(2022年3月発行)
特集 AI時代の医師のクリニカル・スキル—君は生き延びることができるか?
32巻2号(2022年2月発行)
特集 —withコロナ—かぜ診療の心得アップデート
32巻1号(2022年1月発行)
特集 実地医家が楽しく学ぶ 「熱」「炎症」、そして「免疫」—街場の免疫学・炎症学
31巻12号(2021年12月発行)
特集 “血が出た!”ときのリアル・アプローチ—そんな判断しちゃダメよ!
31巻11号(2021年11月発行)
特集 Q&Aで深める「むくみ診断」—正攻法も!一発診断も!外来も!病棟も!
31巻10号(2021年10月発行)
特集 医師の働き方改革—システムとマインドセットを変えよう!
31巻9号(2021年9月発行)
特集 「検査」のニューノーマル2021—この検査はもう古い? あの新検査はやるべき?
31巻8号(2021年8月発行)
特集 メンタルヘルス時代の総合診療外来—精神科医にぶっちゃけ相談してみました。
31巻7号(2021年7月発行)
特集 新時代の「在宅医療」—先進的プラクティスと最新テクノロジー
31巻6号(2021年6月発行)
特集 この診断で決まり!High Yieldな症候たち—見逃すな!キラリと光るその病歴&所見
31巻5号(2021年5月発行)
特集 臨床医のための 進化するアウトプット—学術論文からオンライン勉強会、SNSまで
31巻4号(2021年4月発行)
特集 消化器診療“虎の巻”—あなたの切実なギモンにズバリ答えます!
31巻3号(2021年3月発行)
特集 ライフステージでみる女性診療at a glance!—よくあるプロブレムを網羅しピンポイントで答えます。
31巻2号(2021年2月発行)
特集 肺炎診療のピットフォール—COVID-19から肺炎ミミックまで
31巻1号(2021年1月発行)
特別増大特集 新型コロナウイルス・パンデミック—今こそ知っておきたいこと、そして考えるべき未来
30巻12号(2020年12月発行)
特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き) Part 2
30巻11号(2020年11月発行)
特集 診断に役立つ! 教育で使える! フィジカル・エポニム!—身体所見に名を残すレジェンドたちの技と思考
30巻10号(2020年10月発行)
特集 —ポリファーマシーを回避する—エビデンスに基づく非薬物療法のススメ
30巻9号(2020年9月発行)
特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【感染症・内分泌・整形外科 編】
30巻8号(2020年8月発行)
特集 マイナーエマージェンシー門外放出—知っておくと役立つ! テクニック集
30巻7号(2020年7月発行)
特集 その倦怠感、単なる「疲れ」じゃないですよ!—筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群とミミック
30巻6号(2020年6月発行)
特集 下降期慢性疾患患者の“具合”をよくする—ジェネラリストだからできること!
30巻5号(2020年5月発行)
特集 誌上Journal Club—私を変えた激アツ論文
30巻4号(2020年4月発行)
特集 大便強ドリル—便秘・下痢・腹痛・消化器疾患に強くなる41問!
30巻3号(2020年3月発行)
特集 これではアカンで!こどもの診療—ハマりがちな11のピットフォール
30巻2号(2020年2月発行)
特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【循環器・消化器・神経疾患編】
30巻1号(2020年1月発行)
特集 総合診療医の“若手ロールモデル”を紹介します!—私たちはどう生きるか
29巻12号(2019年12月発行)
特集 困っている“あなた”に届く 認知症診療
29巻11号(2019年11月発行)
特集 臨床写真図鑑 レアな疾患編—見逃したくない疾患のコモンな所見
29巻10号(2019年10月発行)
特集 教えて!医師のためのビジネス・スキル
29巻9号(2019年9月発行)
特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き)
29巻8号(2019年8月発行)
特集 —ノーモア見逃し—日常の検査と画像に潜むピットフォール
29巻7号(2019年7月発行)
特集 リウマチ・膠原病ミミック症例帖—“膠原病っぽくみえてしまう疾患たち”にだまされない!
29巻6号(2019年6月発行)
特集 皮膚科診療エクササイズ—1枚の写真から
29巻5号(2019年5月発行)
特集 一般外来で診断できたら「えっへん!」な疾患38
29巻4号(2019年4月発行)
特集 “ナゾ”の痛み診療ストラテジー|OPQRSTで読み解く
29巻3号(2019年3月発行)
特集 —あなたのギモンに答えます!—循環器診療のハードルを下げるQ&A31
29巻2号(2019年2月発行)
特集 意外な中毒、思わぬ依存、知っておきたい副作用—一般外来で!OTCも処方薬も!
29巻1号(2019年1月発行)
特集 教えて検索!—膨大な医学情報を吟味・整理するスキル
28巻12号(2018年12月発行)
特集 こんなときこそ漢方を!
28巻11号(2018年11月発行)
特集 日本一マジメな「おしっこドリル」—今これだけは押さえておきたい腎・泌尿器のモンダイ
28巻10号(2018年10月発行)
特集 クリニカル・パールPremium!—憧れのカリスマ医師はかく語りき
28巻9号(2018年9月発行)
特集 オンコ・ジェネラリスト—「がん」に強い総合診療医をめざして
28巻8号(2018年8月発行)
特集 80歳からの診療スタンダードUp to Date—Silver Standard
28巻7号(2018年7月発行)
特集 この薬だけは押さえておきたい! 総合診療医のためのSpecialist Drug 40
28巻6号(2018年6月発行)
特集 聴診・触診×エコーで診断推論!—Point-of-Care超音波(POCUS)の底力
28巻5号(2018年5月発行)
特集 “一発診断”トレーニング問題集—懸賞論文「GM Clinical Pictures」大賞発表!
28巻4号(2018年4月発行)
特集 感染症外来診療「賢医の選択」—検査・経口薬・ワクチンをどう使えばいいんですか?
28巻3号(2018年3月発行)
特集 糖尿病のリアル—現場の「困った!」にとことん答えます。
28巻2号(2018年2月発行)
特集 頭痛患者で頭が痛いんです!
28巻1号(2018年1月発行)
特集 シン・フィジカル改革宣言!—私の“神技”伝授します。
27巻12号(2017年12月発行)
特集 小児診療“苦手”克服!!—劇的Before & After
27巻11号(2017年11月発行)
特集 今そこにある、ファミリー・バイオレンス|Violence and Health
27巻10号(2017年10月発行)
特集 めまいがするんです!─特別付録Web動画付
27巻9号(2017年9月発行)
特集 うつより多い「不安」の診かた—患者も医師も安らぎたい
27巻8号(2017年8月発行)
特集 見逃しやすい内分泌疾患─このキーワード、この所見で診断する!
27巻7号(2017年7月発行)
特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 3 カリスマ編
27巻6号(2017年6月発行)
特集 「地域を診る医者」最強の養成法!
27巻5号(2017年5月発行)
特集 コミュニケーションを処方する—ユマニチュードもオープンダイアローグも入ってます!
27巻4号(2017年4月発行)
特集 病歴と診察で診断できない発熱!—その謎の賢い解き方を伝授します。
27巻3号(2017年3月発行)
特集 これがホントに必要な薬40—総合診療医の外来自家薬籠
27巻2号(2017年2月発行)
特集 The総合診療ベーシックス—白熱!「総合診療フェスin OKINAWA」ライブ・レクチャー! 一挙公開 フィジカル動画付!
27巻1号(2017年1月発行)
特集 総合診療の“夜明け”—キーマンが語り尽くした「来し方、行く末」
26巻12号(2016年12月発行)
特集 これでパッチリ! 眼の健康問題
26巻11号(2016年11月発行)
特集 続・しびれるんです!
26巻10号(2016年10月発行)
特集 内科診療を劇的に変える“まとめ”の達人
26巻9号(2016年9月発行)
特集 症状・症候別 エコーを使った診断推論─Point-of-Care超音波
26巻8号(2016年8月発行)
特集 The 初診外来
26巻7号(2016年7月発行)
特集 感染症ケアバンドル・チェックリスト
26巻6号(2016年6月発行)
特集 “賢い処方”と“ナゾ処方”
26巻5号(2016年5月発行)
特集 しびれるんです!─知っておくべきシビレル疾患
26巻4号(2016年4月発行)
特集 ケースとクイズで総ざらい! 街場の2型糖尿病治療
26巻3号(2016年3月発行)
特集 こんな時は漢方でしょう!
26巻2号(2016年2月発行)
特集 フィジカル改革宣言! ──診断からフォローアップまで
26巻1号(2016年1月発行)
特集 妊婦・褥婦が一般外来に来たら─エマージェンシー&コモンプロブレム
25巻12号(2015年12月発行)
特集 外来で「複数の疾患」をもつ患者を診る─マルチモビディティの時代のプライマリ・ケア
25巻11号(2015年11月発行)
特集 レアだけど重要な「痛み」の原因─システム1診断学
25巻10号(2015年10月発行)
特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 2
25巻9号(2015年9月発行)
特集 診断ピットフォール10選─こんな疾患,見逃していませんか?
25巻8号(2015年8月発行)
特集 健診データで困ったら─こんな検査結果を持ってこられたら
25巻7号(2015年7月発行)
特集 ここを知りたい!頭部外傷初期対応・慢性期ケア
25巻6号(2015年6月発行)
特集 高齢者救急の落とし穴─紹介する時,される時
25巻5号(2015年5月発行)
特集 咳を聴きとり,咳を止める
25巻4号(2015年4月発行)
特集 関節が痛いんです!─コモンからレアものまでの診断と治療
25巻3号(2015年3月発行)
特集 神経難病ケアのコペルニクス的転回
25巻2号(2015年2月発行)
特集 総合医のためのスポーツ医学ベーシックス
25巻1号(2015年1月発行)
特集 動悸・息切れ─ヤバい病気の見つけ方 そして見つからなかった時の対処法
