本特集はプライマリ・ケアの消化器診療の現場で誰しもが悩みそうな、かゆいところに手が届く珠玉のQuestionを26題選びました。実はこの26のQ、日々の救急や内科外来のまさにフロントラインで患者さんと向き合う、若手総合内科医から寄せてもらいました。そして26のQにご回答いただくのは、ジェネラルな視点をお持ちの消化器内科医・薬剤師の先生方で、“かゆいところに手が届きながらも”、“Evidence-basedな内容で”、近年クローズアップされている“ポリファーマシー”や“Choosing Wisely®”にも触れていただきながら、実臨床で湧き上がるリアルなQにお答えいただきました。読者の皆様におかれましては、本特集を通じて日常の消化器診療をブラッシュアップしていただき、診療の一助としていただければ幸いです。
雑誌目次
総合診療31巻4号
2021年04月発行
雑誌目次
特集 消化器診療“虎の巻”—あなたの切実なギモンにズバリ答えます!
【消化管】
Q1 逆流性食道炎に対するPPIはどの時点で中止してよいの?
著者: 青島周一
ページ範囲:P.418 - P.420
逆流性食道炎に対するプロトンポンプ阻害薬(proton pump inhibitor:PPI)は、「中止」「継続」という二分法ではなく、患者個別の状況に応じて多面的な視点で評価を行いたい。
Q2 抗血小板薬内服中のPPIはいつまで継続すればよい?
著者: 志波慶樹 , 西野徳之
ページ範囲:P.421 - P.423
アスピリンやチエノピリジン系薬剤に代表される抗血小板薬が処方されている場合には、酸分泌抑制薬、特にプロトンポンプ阻害薬(proton pump inhibitor:PPI)の処方が望ましく、可能であれば継続すべきである。しかしポリファーマシーの側面から、処方や継続については検討することも重要である。
Q3 漫然としたPPI投与は御法度? 本当にCDIのリスクは上がる?
著者: 宮垣亜紀
ページ範囲:P.424 - P.425
プロトンポンプ阻害薬(proton pump inhibitor:PPI)の長期投与によるさまざまな有害事象が報告されている。クロストリジウム・ディフィシル感染症(Clostridium difficile infection:CDI)もその1つである。すべて観察研究であり、RCT(randomized controlled trial)で示されたものはないが、今後の動向に注目が必要な領域である。もちろん漫然としたPPI長期投与は御法度である。
Q4 肺炎や尿路感染症で入院した高齢者。お薬手帳に内服理由不明のPPIが入っていた。消化性潰瘍の既往がなければ「off」してよい?
著者: 青島周一
ページ範囲:P.426 - P.428
プロトンポンプ阻害薬(proton pump inhibitor:PPI)は肺炎など、感染症のリスク増加と関連していることが報告されている。したがって肺炎を発症した症例において、内服理由不明のPPIがあれば、その因果関係を少なからず意識することもあるかもしれない。しかし、必ずしもPPIだけが感染症の原因となっているわけではないことに留意したい。そもそも内服の理由が不明なことは、薬のリスク/ベネフィットに対する不確実性が高いことを意味しており、安易な「off」は推奨できない。
Q5 Helicobacter pyloriはどう診断するの? 感染経路は井戸水だけ?
著者: 遠藤明志 , 田中由佳里
ページ範囲:P.430 - P.431
pylori菌検査に際し、まず内視鏡検査が必須である。それに加え、尿素呼気試験(UBT)、血液や尿からの抗体測定・糞便中の抗原測定、胃の粘膜生検による迅速ウレアーゼ試験や鏡検法、培養法などがあり、それぞれ一長一短がある。pylori菌の感染経路は経口感染が主であるとされる。古くは人の糞便が堆肥溜めから地下水に浸透し、井戸水からの感染とされていたが、現在の主な感染経路は、幼少期に近親者からの口移しなどによるとされている。ただ、成人の初感染も少ないがゼロではないため、油断はできない。
Q6 Helicobacter pylori除菌後の定期的な内視鏡フォローはいつまで行うの?
著者: 宮垣亜紀
ページ範囲:P.432 - P.434
Helicobacter pylori(以下、pylori菌)感染症は胃癌のリスクを高める。除菌を行うと発癌リスクは下がるが、ゼロにはならず、定期的な内視鏡フォローが必要である。どのくらいの間隔で検査を行うべきか、今のところガイドライン等で定められたものはないが、一般的に1〜2年間隔での内視鏡検査が勧められている。また、年齢の上限や、いつまで行うかなども決まったものはないため、患者さんの基礎疾患や年齢、検査の負担などを総合的に判断して、いつまでフォローをするのか決めればよい。
Q7 心窩部痛で汎用される“痛み止め=胃薬”は本当に必要?
著者: 永橋尭之 , 西野徳之
ページ範囲:P.436 - P.437
初診時に処方してもよいが、大切なことはその原因を鑑別し確定診断を得ること。心筋梗塞の下壁梗塞を「胃が痛い」と訴える患者もおり、その原因疾患により痛みの性質、対処法が違ってくる。効果が得られない場合は適切な検査と診断の見直しを行い、治療を変更していく必要がある。
Q8 漫然と処方される“胃粘膜保護薬(防御因子増強薬)の数々”、本当に必要?
著者: 小林健二
ページ範囲:P.438 - P.439
防御因子増強薬の有効性を示すデータは限定的であり、消化性潰瘍(peptic ulcer disease : PUD)や機能性ディスペプシア(functional dyspepsia : FD)の治療では補助的な使用にとどめる。
Q9 胃アニサキス症は内視鏡検査で摘出がマスト? 抗アレルギー薬の点滴のみで経過を見れないか?
著者: 西野徳之 , 濱田晃市
ページ範囲:P.440 - P.441
「経過を見る」ならYesかも。しかし「完治を目指す」ならNo! 胃アニサキス症の診断は上部内視鏡検査が必須である。内視鏡医にとっては、内視鏡で虫体を確認した際それを除去せず看過する選択肢はない。すぐに内視鏡検査ができない状況下で「アニサキス症疑い」の場合、検査までの橋渡しのため副腎皮質ホルモン、抗アレルギー薬、胃局所麻酔薬、鎮痙薬、正露丸®などの投与は考慮してよいかもしれないが、治療目標は症状の緩和ではなく、病態の把握と虫体の除去である1)。
Q10 感染性腸炎に抗菌薬は本当に必要?
著者: 宮垣亜紀
ページ範囲:P.442 - P.444
抗菌薬が必要な感染性腸炎は限られ、ルーチンで必要なものではない。感染性腸炎と一括りにしても、原因は細菌性・ウイルス性・寄生虫によるものに大別される。抗菌薬が必要なのは、細菌性腸炎の一部と寄生虫である。患者背景(既往歴や渡航歴など)や環境要因(市中感染か院内感染か)によっても、抗菌薬が必要か否かが変わってくる。
Q11 CDIのリスクとなる抗菌薬はいつまでさかのぼるの?
著者: 青島周一
ページ範囲:P.445 - P.447
クロストリジウム・ディフィシル感染症(clostridioides difficile infection:CDI)の主要な危険因子は、❶高齢、❷長期入院、❸抗菌薬もしくは制酸薬の使用であり、抗菌薬においては、特にセファロスポリン、フルオロキノロン、クリンダマイシンでリスクが高い。抗菌薬はその投与中のみならず、投与終了後もCDIの危険因子となりうるが、そのリスク期間は2週間前後、時に1〜3カ月まで持続することもある。少なくとも1カ月、ハイリスク患者では3カ月までさかのぼって確認できるとよい。
Q12 大腸ポリープ摘除後に大腸内視鏡をフォローするタイミングは?
著者: 西野徳之 , 堀川宜範
ページ範囲:P.448 - P.450
急性期のポリープ切除(polypectomy)後の出血は速やかに検査を行い、止血処置をすべきである。2〜3日後に遅発性に出血することがあり、切除後は過度の運動や飲酒は避けるように指導する。通常、大腸内視鏡(CS:colonoscopy)フォローアップの目的は、局所再発、異時性多発ポリープ、癌の合併を確認すること。CSを施行する時期は、切除したポリープの大きさや数、組織学的悪性度によって異なる。日本では各種ガイドラインから概ね次のように考える。❶早期大腸癌あるいは高リスクのポリープでは治療後最初は6カ月後、その後は1年毎、❷腫瘍性ポリープを切除した場合は1〜3年以内、❸ポリープをすべて取り切った場合(clean colon)や非腫瘍性ポリープの場合は3年以上のフォローアップを目安とする1〜3)。日本の治療の時期の考え方は欧米のガイドラインとは少々異なる。
Q13 高齢の便秘患者。すでに3つ以上の便秘薬を処方中だが、患者がさらにほしいと言って困っている。腸に優しい便秘薬の適切な処方は?
著者: 田中由佳里
ページ範囲:P.452 - P.453
本人の「便秘」と考える排便回数、便性状などの症状と、「便秘」の定義のズレがあるか確認しよう。刺激性下剤や高用量の酸化マグネシウム製剤の連用を控え、上皮機能変容薬、浸透圧性下剤を軸に、便秘薬を組み立てよう。
Q14 1カ月以上下痢が続いている患者。どうアプローチしたらよい?
著者: 小林健二
ページ範囲:P.454 - P.455
まず医原性下痢を除外。医原性下痢が除外され、便に血液、白血球を認める、または便中カルプロテクチン陽性、もしくは血液検査で炎症反応があれば、まず大腸内視鏡検査(CS)を行う。
【肝胆膵】
Q16 健診で指摘された肝障害。どう対応したらよい?
著者: 重福隆太
ページ範囲:P.459 - P.461
肝臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれ、健診で初めて異常を指摘される機会も多く、初診時に肝硬変や肝細胞癌の診断に至る場合もある。日常診療で遭遇する肝障害の多くは、脂肪性肝疾患(アルコール性、非アルコール性)および薬剤性肝障害である。一方、健診で初めて診断されるウイルス性肝炎や自己免疫性肝疾患も存在する。肝障害をみた場合には、生活習慣病としてフォローするのか、専門医へ紹介するのかを判断する必要がある。
Q17 ウルソ®(肝庇護薬)はどんな状況で処方したらよいの? 漫然と処方していない?
著者: 中野弘康
ページ範囲:P.462 - P.463
ウルソ®が第一選択となるのは、PBC(primary biliary cholangitis : 原発性胆汁性胆管炎)である。ウルソ®を内服している患者を診たら、内服理由を明らかにしたい。ポリファーマシー対策にも有効だ。
Q18 IPMNの経過観察はどこまで必要?
著者: 白水将憲 , 野々垣浩二
ページ範囲:P.464 - P.465
IPMN(intraductal papillary mucinous neoplasm:膵管内乳頭粘液性腫瘍)の経過観察は、囊胞径、主膵管径、囊胞内結節の有無により、間隔を症例に応じて決定する。
Q19 アルコール性脂肪肝でフォロー中、経過観察で肝障害持続。断酒進まず。よい方法は?
著者: 重福隆太
ページ範囲:P.466 - P.467
アルコール依存症のスクリーニングを行い、依存症と診断した場合は、早期に専門施設へ紹介し、断酒および飲酒量低減のための治療介入を行う必要がある。
Q20 急性胆囊炎。外科と内科、どちらにコンサルトする?
著者: 中原一有
ページ範囲:P.468 - P.470
急性胆囊炎治療の大原則は、早期の腹腔鏡下胆囊摘出術(laparoscopic cholecystectomy : Lap-C)であり、ガイドライン(Tokyo Guidelines 2018 : TG18)1)では、耐術可能と判断した場合は発症からの時間にかかわらず、早期(可能であれば72時間以内、遅くとも1週間以内)のLap-Cが推奨されている。よって急性胆囊炎と診断した際には、明らかな耐術不能例や一部の例外を除き、基本的には速やかに外科へコンサルトすべきである。しかし一部の症例では、胆囊ドレナージ術が優先される場合があり、その適応を見極めることが内科医にとって重要となる。
Q22 NASHが疑われる患者。専門医に紹介するタイミングは?
著者: 桐野桜 , 黒崎雅之
ページ範囲:P.474 - P.475
NAFLD(非アルコール性脂肪性肝疾患)症例の一部は炎症を伴うNASH(非アルコール性脂肪肝炎)に進展する。肝線維化が疑われる症例は肝発癌や肝硬変への進展のリスクが高く専門医に紹介しよう。
Q23 たまたま採血したらHBs抗原陽性。どのタイミングで肝臓専門医に紹介したらよい?
著者: 奥瀬千晃
ページ範囲:P.476 - P.478
HBs抗原はB型肝炎ウイルス(hepatitis B virus:HBV)粒子の表面を覆う蛋白質であり、通常ではHBs抗原が陽性ということは、HBVに感染しているということを意味する。HBV感染は多彩な病態を呈するので、HBs抗原が陽性と判明した時点で専門医に紹介してよいが、折角の機会なので少々踏み込んだ病態精査をしてから診療を依頼できるように整理してみよう。
※p. 477 「表2|HBV持続感染者における治療対象(文献1より)」については,2次利用の許諾を得ておりませんので冊子体のみの掲載となります.
Q24 C型肝炎の薬はどこまで進歩したの?どの患者まで適応が拡大している?
著者: 前屋舖千明 , 黒崎雅之
ページ範囲:P.480 - P.481
数多くのC型肝炎ウイルス(HCV)治療薬が開発され、慢性肝炎と代償性肝硬変で100%近いウイルス排除が可能な時代となった。また2019年以降は非代償性肝硬変の患者まで適応が拡大。
Q25 健診で胆囊結石を指摘された。手術の適応とタイミングは?
著者: 中原一有
ページ範囲:P.482 - P.483
健診などで偶発的に発見された無症状の胆囊結石には治療適応はないが、充満結石などで胆囊壁の評価が困難な場合や癌の疑いがある胆囊壁肥厚を認める場合には、無症状であっても手術を考慮すべきである1)。また、胆囊結石に伴う症状(胆石発作)を頻回に認める場合や急性胆囊炎合併例は、手術適応となる。手術のタイミングは、急性胆囊炎合併例は耐術可能であれば早期(可能であれば72時間以内、遅くとも1週間以内)の腹腔鏡下胆囊摘出術(laparoscopic cholecystectomy : Lap-C)が推奨されているが2)、胆石発作と考えられる症例では、症状の原因となりうるその他の疾患を除外した後に、待機的手術を考慮する。
Q26 他院で臨床症状のみで慢性膵炎と診断された患者を診る時に、何に注意したらよい?
著者: 白水将憲 , 野々垣浩二
ページ範囲:P.484 - P.485
他疾患を否定したうえで、早期慢性膵炎と診断する場合には、画像検査が必須である。
Editorial
消化器診療で誰もが悩む26のギモンと回答がズラリ! フリーアクセス
著者: 中野弘康
ページ範囲:P.407 - P.407
施設入所中の高齢患者が発熱で救急搬送されてきました。診断は肺炎。さて、お薬手帳を確認したところ、10種類以上の内服薬がありました!
よく見てみると、消化器病関連薬の多いこと。マグミット®、センノシド®、ネキシウム®、ムコスタ®……。肺炎の治療はもちろん大切ですが、それ以上に、内服理由が不明な薬剤が多く、入院を契機にポリファーマシーの介入をしたいところです。でも、これらの薬、どのように減薬・調整したらよいか悩んでしまうのが実情ではないでしょうか?
『19番目のカルテ』を読んで答える! あなたの“ドクターG度”検定&深読み解説・1【新連載】
なんでも治せるお医者さん—(『19番目のカルテ』第1話より)
著者: 山中克郎
ページ範囲:P.491 - P.493
本連載は総合診療ビギナーの皆さんに、総合診療の楽しさと奥深さを解説することが目的です。漫画『19番目のカルテ』のエピソードを深読みすることにより、総合診療医がどのような根拠に基づいて診断しているのかを理解していただければ幸いです。本連載は『総合診療』×『19番目のカルテ』のコラボ企画で、本誌編集委員の山中克郎先生・徳田安春先生が隔月で作問&解説します!
What's your diagnosis?[220]
あったらいいが、なくてもいい
著者: 西久保雅司 , 金森真紀
ページ範囲:P.410 - P.414
病歴
患者:71歳、男性
主訴:発熱、皮疹、関節痛
現病歴:2カ月前から発熱、両手・膝・足関節の腫脹と両側下腿の痛みが出現した。2週間前から頸部〜前胸部に皮疹が出現し(図1)、精査目的で入院となった。
ROS陽性:体重減少(-10kg/7カ月)
ROS陰性:悪寒戦慄、盗汗、腰痛、手指の硬化・腫脹、筋力低下
曝露歴:海外渡航・ハイリスクな性交渉・小児との接触歴なし、新規薬剤なし
既往歴:7カ月前:肺癌術後(低分化腺癌、扁平上皮癌)、2カ月前:早期食道癌ESD(内視鏡的粘膜下層剝離術)切除、肺結核(20歳頃)、心房細動
内服薬:エドキサバン30mg、エソメプラゾール10mg、市販の医薬品・サプリメントなし
生活歴:喫煙は1年前まで20本/日×50年、飲酒は1年前まで日本酒2〜4合/日
【エッセイ】アスクレピオスの杖—想い出の診療録・12
1粒のアメ
著者: 矢島つかさ
ページ範囲:P.487 - P.487
本連載は、毎月替わる著者が、これまでの診療で心に残る患者さんとの出会いや、人生を変えた出来事を、エッセイにまとめてお届けします。
Dr.上田剛士のエビデンス実践レクチャー!医学と日常の狭間で|患者さんからの素朴な質問にどう答える?・13
お餅をのどに詰まらせた
著者: 上田剛士
ページ範囲:P.494 - P.498
患者さんからのふとした質問に答えられないことはないでしょうか? 素朴な疑問ほど回答が難しいものはないですが、新たな気づきをもたらす良問も多いのではないでしょうか? 本連載では素朴な疑問に、文献的根拠を提示しながらお答えします!
オール沖縄!カンファレンス|レジデントの対応と指導医の考えVer.2.0・52
専門医でも難しかった「しびれ」の診断
著者: 渡口侑樹 , 本村和久 , 徳田安春
ページ範囲:P.499 - P.503
CASE
患者:47歳、女性。
主訴:四肢のしびれ、糖尿病コントロール不良のため紹介で来院。
現病歴:X-2月、徐々に右肩のしびれと疼痛を自覚して近医整形外科受診となった。神経痛との診断で鎮痛薬が処方されたが、効果に乏しかった。この頃から疼痛のため運動量が減ったこともあり、糖尿病コントロールが悪化した。X-1月上旬から両手の指先のしびれと氷水に浸かっているような冷たく感じる感覚を自覚するようになった。X-1月中旬から階段昇降時に脱力と両側腓腹部の疼痛が出現した。症状は増悪傾向で当院救急外来に2回受診したが、いずれも糖尿病性神経症とのことで帰宅となった。X月、症状増悪し歩行困難となり、かかりつけ医ではプレガバリンとロキソプロフェンが処方されたが改善はなかった。さらに症状が進行、屋内での生活も困難となったため、かかりつけ医より当院整形外科(四肢のしびれに関して)と総合内科(糖尿病コントロールに関して)に紹介となった。
既往歴:気管支喘息、高血圧症、糖尿病、睡眠障害、統合失調症、左手手根管症候群手術後。
社会歴:機会飲酒、喫煙20本/日×25年間、独居、無職。
内服薬:メトホルミン500mg 1回1錠・1日3回、カナグリフロジン100mg 1日1錠、テルミサルタン20mg 1日1錠、バイアスピリン100mg 1日1錠、デュラグルチド(持続性GLP-1受容体作動薬)皮下注0.75mg週1回、ロキソプロフェン60mg 1回1錠・1日3回、プレガバリン75mg 1回1錠・1日2回、ケトプロフェンテープ。
家族歴:特記事項なし。
アレルギー歴:特記事項なし。
“コミュ力”増強!「医療文書」書きカタログ・10
—短時間で仕上げる「病診連携」の礎—かかりつけ患者の“準緊急時”の紹介状
著者: 天野雅之
ページ範囲:P.504 - P.508
今月の文書
診療情報提供書
セッティング:診療所→総合病院の整形外科へ紹介(翌日受診)
患者:84歳、女性。糖尿病・陳旧性心筋梗塞で定期通院中。転倒後の疼痛のため夕方に受診し、「橈骨遠位端骨折」の診断で翌日紹介とした。
【登場人物】
桜井:総合診療科1年目専攻医。現在は地域の診療所で研修中。
古津:総合病院に勤務する整形外科医。当日の外来担当。
飛鳥:桜井の指導医。プログラム責任者として定期的に面談している。
研修医Issy & 指導医Hiro & Dr.Sudoのとびだせフィジカル! 聴診音付・4
胸痛のフィジカル
著者: 石井大太 , 中野弘康 , 須藤博
ページ範囲:P.509 - P.513
ここは、とある病院の初診外来。研修医Issyは今日もフィジカルマスターのDr. Sudo、そして指導医Hiroと共に、外来研修に打ち込むのであった。
“JOY”of the World!|ロールモデル百花繚乱・15
自分にとって最適なワークライフバランスを実現するには
著者: 黒木愛
ページ範囲:P.514 - P.518
私は現在、週2日手術を行いながら、小学1年生になる息子の子育てに取り組んでいる脳神経外科医だ(表1)。今回、光栄にも執筆のお話をいただいたが、家庭と仕事を両立させている女性医師も多いなか、私でいいのだろうかという思いもあった。しかし、尊敬する加藤庸子先生(2020年6月号で本欄に執筆)からのご推薦ということで、ご縁に感謝しつつ、徒然に書きつづっていきたいと思う。これから育児と仕事を両立させていく女性外科医やその周囲の方々に、1つのワークライフバランスとして参考になれば幸いである。
「総合診療」達人伝|7つのコアコンピテンシーとその向こう側・4
人間中心の医療・ケア
著者: 紅谷浩之 , 奥知久
ページ範囲:P.519 - P.526
令和2年12月。軽井沢の抜けるような青空は、徐々に第3波が迫り来るCOVID-19の巨大な波を一瞬忘れさせてくれるようだった。今回筆者が訪ねたのは2020年4月にオープンしたばかりの「ほっちのロッヂ(一口メモ1)」。そこに今回の達人、紅谷浩之先生がいる。紅谷先生は国の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスガイドライン1)」策定委員として、advance care planning(ACP)の日本における愛称が「人生会議」となった過程で大きな役割を果たされた。人の生老病死のプロセスやドラマを深く見つめてこられた紅谷達人の「ほっちのロッヂ」から、今回のテーマ「人間中心の医療・ケア」を考察してみよう。
55歳からの家庭医療 Season 2|明日から地域で働く技術とエビデンス・38
—“家庭医脳”の育て方—Family Medicine and Difficult Teaching Issues
著者: 藤沼康樹
ページ範囲:P.527 - P.531
プライマリ・ケア外来診療の教育に関するワークショップを、2021年初頭にリモートで行う機会がありました。今回は、そのワークショップのコンセプトを提示しようと思います。
現在、僕が関心をもっているのは、疾患の診断や治療に関する指導ではなく、これまであまり言語化されてこなかった領域に関する指導です。以下に、僕の(指導に関する)問題意識を反映したCaseをあげていきましょう。実際のワークショップでは、これらのCaseをめぐって、参加指導医に「どう指導するか?」をディスカッションしてもらいました。
【臨床小説】後悔しない医者|あの日できなかった決断・第13話
空を見させた医者
著者: 國松淳和
ページ範囲:P.532 - P.538
前回までのあらすじ 今月のナゾ
専門医試験を控え症例サマリーを作成しにきた田山陽輔と再会し、3年前の症例を回想する筧。全身性エリテマトーデス(SLE)の患者・湯川伶子は来院時は18歳、高校3年生だった。精神症状がひどい時は「創くん…」と彼氏をうわ言のように呼ぶこともあったが、治療が効を奏し順調に回復しているようにみえた。しかし、ステロイドを減量し始めたところで精神症状が増悪、「ステロイド精神病」だと考えた田山と筧が、さらにステロイドを減らすと…。本当は、ステロイドを減量したせいで、「精神・神経ループス」が再燃していたのだ。それを黒野は見抜いた。そして、伶子は19歳の誕生日を迎えようとしていたが…。
前回は、ステロイドを減らすか増やすか、その分岐点が問われた。「ステロイド精神病」は、特にSLE患者に起こりやすい。しかしSLEに起こりやすい合併症は、それだけではない。退院後の伶子に、今度は何が起こるのか?
#総合診療
#今月の特集関連本❶ フリーアクセス
ページ範囲:P.429 - P.429
#今月の特集関連本❷ フリーアクセス
ページ範囲:P.435 - P.435
#今月の特集関連本❸ フリーアクセス
ページ範囲:P.451 - P.451
#今月の特集関連本❹ フリーアクセス
ページ範囲:P.471 - P.471
#今月の特集関連本❺ フリーアクセス
ページ範囲:P.473 - P.473
#今月の連載関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.533 - P.533
#医学書院の新刊 フリーアクセス
ページ範囲:P.488 - P.489
#書評:—別冊『呼吸器ジャーナル』—COVID-19の病態・診断・治療—現場の知恵とこれからの羅針盤 フリーアクセス
著者: 藤田次郎
ページ範囲:P.486 - P.486
別冊『呼吸器ジャーナル』として、『COVID-19の病態・診断・治療——現場の知恵とこれからの羅針盤』が出版された。多くの臨床医の興味を引きつけるテーマである。私自身、『呼吸器ジャーナル』の編集・執筆に携わったことがあるものの、これまでとは異なるスタイルの企画であると感じた。
Ⅰ章ではCOVID-19(新型コロナウイルス感染症)に関する総論を、Ⅱ章ではCOVID-19を理解するために必要な基礎知識を、Ⅲ章では各論として疫学・診断・治療を示しており、COVID-19診療の基本を学ぶことができる。なかなか見ることができない「病理像」まで紹介されている点には感心した。また、臨床医の関心の高い「ワクチン」の開発状況も参考になった。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.408 - P.409
『総合診療』編集方針 フリーアクセス
ページ範囲:P.415 - P.415
1991年に創刊した弊誌は、2015年に『JIM』より『総合診療』に誌名を変更いたしました。その後も高齢化はさらに進み、社会構造や価値観、さらなる科学技術の進歩など、日本の医療を取り巻く状況は刻々と変化し続けています。地域医療の真価が問われ、ジェネラルに診ることがいっそう求められる時代となり、ますます「総合診療」への期待が高まってきました。これまで以上に多岐にわたる知識・技術、そして思想・価値観の共有が必要とされています。そこで弊誌は、さらなる誌面の充実を図るべく、2017年にリニューアルをいたしました。本誌は、今後も下記の「編集方針」のもと、既存の価値にとらわれることなく、また診療現場からの要請に応え、読者ならびに執筆者のみなさまとともに、日本の総合診療の新たな未来を切り拓いていく所存です。
2018年1月 『総合診療』編集委員会
読者アンケート
ページ範囲:P.490 - P.490
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.539 - P.542
『総合診療』バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.540 - P.541
お得な年間購読のご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.541 - P.541
基本情報
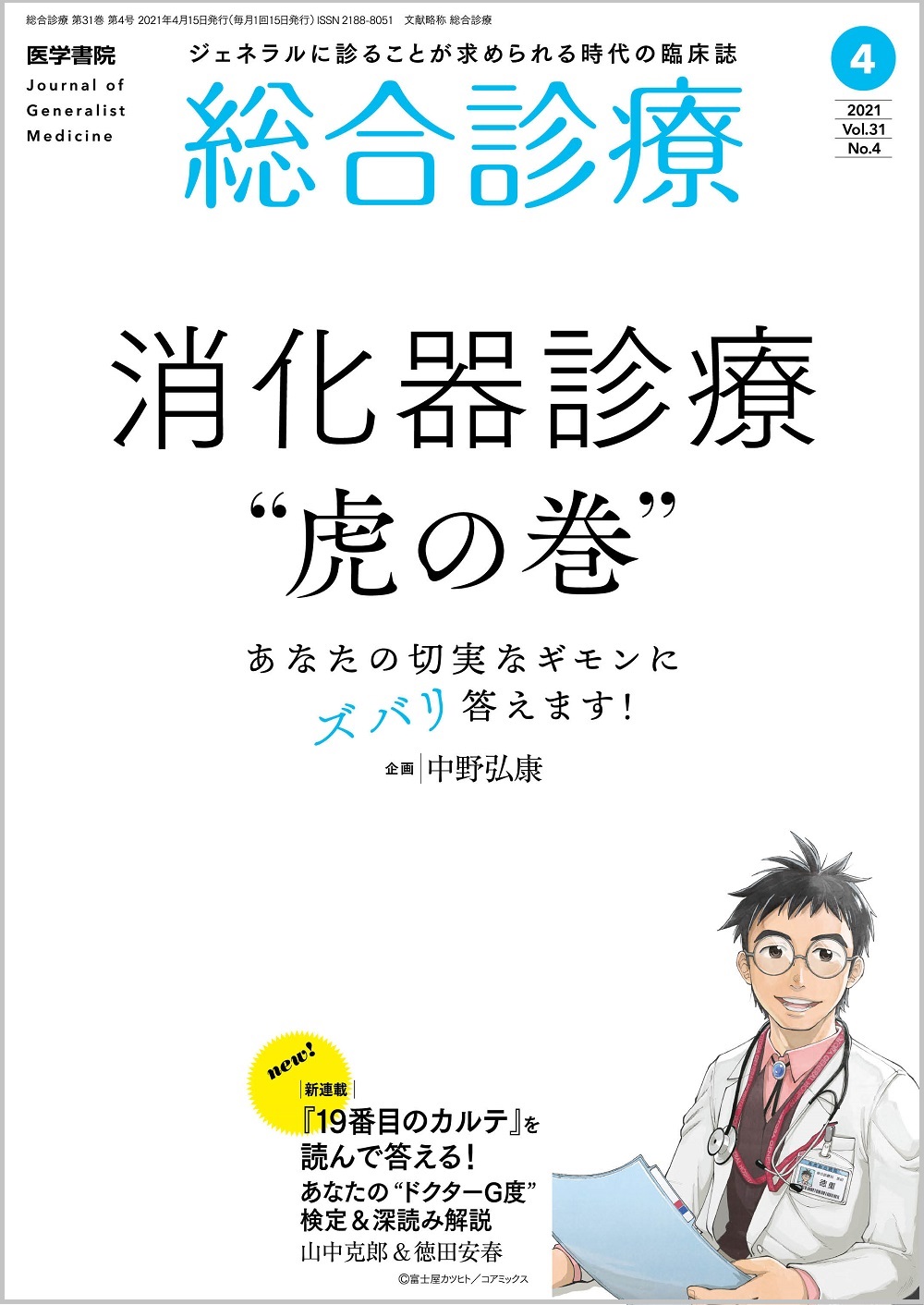
バックナンバー
34巻12号(2024年12月発行)
特集 妊婦・褥婦が外来に来たらUpdate—症状対応からワクチン・プラネタリーヘルスまで
34巻11号(2024年11月発行)
特集 電子カルテとベッドサイドの壁を打ち破る!—患者情報の「言語化」への挑戦
34巻10号(2024年10月発行)
特集 化かしが得意なカメレオンな疾患を捕まえろ!—よくある騙され方のゲシュタルト
34巻9号(2024年9月発行)
特集 今伝えたいクリニカル・パール—つくり方、使い方、活かし方
34巻8号(2024年8月発行)
特集 ストーン・ウォーズ 果てしなき“石”と医師との闘い
34巻7号(2024年7月発行)
特集 どうする!? 健診異常—これってホントに異常なの? どう説明する?
34巻6号(2024年6月発行)
特集 医師のウェルビーイング
34巻5号(2024年5月発行)
特集 —優柔不断にサヨウナラ!—あなたの「臨床判断」を高めるケーススタディ11選
34巻4号(2024年4月発行)
特集 困ったときの漢方—この症状に役立ちます!
34巻3号(2024年3月発行)
特集 —え、ウソ!実は◯◯だった!?—“コモンディジーズ”の診断ピットフォール
34巻2号(2024年2月発行)
特集 日常診療で出合う筋骨格疾患—脳神経内科と整形外科からのアプローチ
34巻1号(2024年1月発行)
特集 —“体験型”臨床クイズで習得する!—フィジカル診断エクセレンス
33巻12号(2023年12月発行)
特集 海の外へ渡る航行者を診る—アウトバウンドにまつわるetc.
33巻11号(2023年11月発行)
特集 —続・総合診療外来に“実装”したい—最新エビデンスMy Best 3
33巻10号(2023年10月発行)
特集 ○×クイズ110問!日常診療アップグレード—Choosing WiselyとHigh Value Careを学ぼう
33巻9号(2023年9月発行)
特集 ジェネラリストのための「発達障害(神経発達症)」入門
33巻8号(2023年8月発行)
特集 都市のプライマリ・ケア—「見えにくい」を「見えやすく」
33巻7号(2023年7月発行)
特集 “消去法”で考え直す「抗菌薬選択」のセオリー—広域に考え、狭域に始める
33巻6号(2023年6月発行)
特集 知っておくべき!モノクロな薬たち(注:モノクローナル抗体の話ですよ〜)
33巻5号(2023年5月発行)
特集 —疾患別“イルネススクリプト”で学ぶ—「腹痛診療」を磨き上げる22症例
33巻4号(2023年4月発行)
特集 救急対応ドリル—外来から在宅までの60問!
33巻3号(2023年3月発行)
特集 —自信がもてるようになる!—エビデンスに基づく「糖尿病診療」大全—新薬からトピックスまで
33巻2号(2023年2月発行)
特集 しびれQ&A—ビビッとシビれるクリニカルパール付き!
33巻1号(2023年1月発行)
特集 COVID-19パンデミック 振り返りと将来への備え
32巻12号(2022年12月発行)
特集 レクチャーの達人—とっておきの生ライブ付き!
32巻11号(2022年11月発行)
特集 不定愁訴にしない“MUS”診療—病態からマネジメントまで
32巻10号(2022年10月発行)
特集 日常診療に潜む「処方カスケード」—その症状、薬のせいではないですか?
32巻9号(2022年9月発行)
特集 総合診療・地域医療スキルアップドリル—こっそり学べる“特講ビデオ”つき!
32巻8号(2022年8月発行)
特集 こんなところも!“ちょいあて”エコー—POCUSお役立ちTips!
32巻7号(2022年7月発行)
特集 —どうせやせない!? やせなきゃいけない??苦手克服!—「肥満」との向き合い方講座
32巻6号(2022年6月発行)
特集 総合診療外来に“実装”したい最新エビデンス—My Best 3
32巻5号(2022年5月発行)
特集 「診断エラー」を科学する!—セッティング別 陥りやすい疾患・状況
32巻4号(2022年4月発行)
特集 えっ、これも!? 知っておきたい! 意外なアレルギー疾患
32巻3号(2022年3月発行)
特集 AI時代の医師のクリニカル・スキル—君は生き延びることができるか?
32巻2号(2022年2月発行)
特集 —withコロナ—かぜ診療の心得アップデート
32巻1号(2022年1月発行)
特集 実地医家が楽しく学ぶ 「熱」「炎症」、そして「免疫」—街場の免疫学・炎症学
31巻12号(2021年12月発行)
特集 “血が出た!”ときのリアル・アプローチ—そんな判断しちゃダメよ!
31巻11号(2021年11月発行)
特集 Q&Aで深める「むくみ診断」—正攻法も!一発診断も!外来も!病棟も!
31巻10号(2021年10月発行)
特集 医師の働き方改革—システムとマインドセットを変えよう!
31巻9号(2021年9月発行)
特集 「検査」のニューノーマル2021—この検査はもう古い? あの新検査はやるべき?
31巻8号(2021年8月発行)
特集 メンタルヘルス時代の総合診療外来—精神科医にぶっちゃけ相談してみました。
31巻7号(2021年7月発行)
特集 新時代の「在宅医療」—先進的プラクティスと最新テクノロジー
31巻6号(2021年6月発行)
特集 この診断で決まり!High Yieldな症候たち—見逃すな!キラリと光るその病歴&所見
31巻5号(2021年5月発行)
特集 臨床医のための 進化するアウトプット—学術論文からオンライン勉強会、SNSまで
31巻4号(2021年4月発行)
特集 消化器診療“虎の巻”—あなたの切実なギモンにズバリ答えます!
31巻3号(2021年3月発行)
特集 ライフステージでみる女性診療at a glance!—よくあるプロブレムを網羅しピンポイントで答えます。
31巻2号(2021年2月発行)
特集 肺炎診療のピットフォール—COVID-19から肺炎ミミックまで
31巻1号(2021年1月発行)
特別増大特集 新型コロナウイルス・パンデミック—今こそ知っておきたいこと、そして考えるべき未来
30巻12号(2020年12月発行)
特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き) Part 2
30巻11号(2020年11月発行)
特集 診断に役立つ! 教育で使える! フィジカル・エポニム!—身体所見に名を残すレジェンドたちの技と思考
30巻10号(2020年10月発行)
特集 —ポリファーマシーを回避する—エビデンスに基づく非薬物療法のススメ
30巻9号(2020年9月発行)
特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【感染症・内分泌・整形外科 編】
30巻8号(2020年8月発行)
特集 マイナーエマージェンシー門外放出—知っておくと役立つ! テクニック集
30巻7号(2020年7月発行)
特集 その倦怠感、単なる「疲れ」じゃないですよ!—筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群とミミック
30巻6号(2020年6月発行)
特集 下降期慢性疾患患者の“具合”をよくする—ジェネラリストだからできること!
30巻5号(2020年5月発行)
特集 誌上Journal Club—私を変えた激アツ論文
30巻4号(2020年4月発行)
特集 大便強ドリル—便秘・下痢・腹痛・消化器疾患に強くなる41問!
30巻3号(2020年3月発行)
特集 これではアカンで!こどもの診療—ハマりがちな11のピットフォール
30巻2号(2020年2月発行)
特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【循環器・消化器・神経疾患編】
30巻1号(2020年1月発行)
特集 総合診療医の“若手ロールモデル”を紹介します!—私たちはどう生きるか
29巻12号(2019年12月発行)
特集 困っている“あなた”に届く 認知症診療
29巻11号(2019年11月発行)
特集 臨床写真図鑑 レアな疾患編—見逃したくない疾患のコモンな所見
29巻10号(2019年10月発行)
特集 教えて!医師のためのビジネス・スキル
29巻9号(2019年9月発行)
特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き)
29巻8号(2019年8月発行)
特集 —ノーモア見逃し—日常の検査と画像に潜むピットフォール
29巻7号(2019年7月発行)
特集 リウマチ・膠原病ミミック症例帖—“膠原病っぽくみえてしまう疾患たち”にだまされない!
29巻6号(2019年6月発行)
特集 皮膚科診療エクササイズ—1枚の写真から
29巻5号(2019年5月発行)
特集 一般外来で診断できたら「えっへん!」な疾患38
29巻4号(2019年4月発行)
特集 “ナゾ”の痛み診療ストラテジー|OPQRSTで読み解く
29巻3号(2019年3月発行)
特集 —あなたのギモンに答えます!—循環器診療のハードルを下げるQ&A31
29巻2号(2019年2月発行)
特集 意外な中毒、思わぬ依存、知っておきたい副作用—一般外来で!OTCも処方薬も!
29巻1号(2019年1月発行)
特集 教えて検索!—膨大な医学情報を吟味・整理するスキル
28巻12号(2018年12月発行)
特集 こんなときこそ漢方を!
28巻11号(2018年11月発行)
特集 日本一マジメな「おしっこドリル」—今これだけは押さえておきたい腎・泌尿器のモンダイ
28巻10号(2018年10月発行)
特集 クリニカル・パールPremium!—憧れのカリスマ医師はかく語りき
28巻9号(2018年9月発行)
特集 オンコ・ジェネラリスト—「がん」に強い総合診療医をめざして
28巻8号(2018年8月発行)
特集 80歳からの診療スタンダードUp to Date—Silver Standard
28巻7号(2018年7月発行)
特集 この薬だけは押さえておきたい! 総合診療医のためのSpecialist Drug 40
28巻6号(2018年6月発行)
特集 聴診・触診×エコーで診断推論!—Point-of-Care超音波(POCUS)の底力
28巻5号(2018年5月発行)
特集 “一発診断”トレーニング問題集—懸賞論文「GM Clinical Pictures」大賞発表!
28巻4号(2018年4月発行)
特集 感染症外来診療「賢医の選択」—検査・経口薬・ワクチンをどう使えばいいんですか?
28巻3号(2018年3月発行)
特集 糖尿病のリアル—現場の「困った!」にとことん答えます。
28巻2号(2018年2月発行)
特集 頭痛患者で頭が痛いんです!
28巻1号(2018年1月発行)
特集 シン・フィジカル改革宣言!—私の“神技”伝授します。
27巻12号(2017年12月発行)
特集 小児診療“苦手”克服!!—劇的Before & After
27巻11号(2017年11月発行)
特集 今そこにある、ファミリー・バイオレンス|Violence and Health
27巻10号(2017年10月発行)
特集 めまいがするんです!─特別付録Web動画付
27巻9号(2017年9月発行)
特集 うつより多い「不安」の診かた—患者も医師も安らぎたい
27巻8号(2017年8月発行)
特集 見逃しやすい内分泌疾患─このキーワード、この所見で診断する!
27巻7号(2017年7月発行)
特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 3 カリスマ編
27巻6号(2017年6月発行)
特集 「地域を診る医者」最強の養成法!
27巻5号(2017年5月発行)
特集 コミュニケーションを処方する—ユマニチュードもオープンダイアローグも入ってます!
27巻4号(2017年4月発行)
特集 病歴と診察で診断できない発熱!—その謎の賢い解き方を伝授します。
27巻3号(2017年3月発行)
特集 これがホントに必要な薬40—総合診療医の外来自家薬籠
27巻2号(2017年2月発行)
特集 The総合診療ベーシックス—白熱!「総合診療フェスin OKINAWA」ライブ・レクチャー! 一挙公開 フィジカル動画付!
27巻1号(2017年1月発行)
特集 総合診療の“夜明け”—キーマンが語り尽くした「来し方、行く末」
26巻12号(2016年12月発行)
特集 これでパッチリ! 眼の健康問題
26巻11号(2016年11月発行)
特集 続・しびれるんです!
26巻10号(2016年10月発行)
特集 内科診療を劇的に変える“まとめ”の達人
26巻9号(2016年9月発行)
特集 症状・症候別 エコーを使った診断推論─Point-of-Care超音波
26巻8号(2016年8月発行)
特集 The 初診外来
26巻7号(2016年7月発行)
特集 感染症ケアバンドル・チェックリスト
26巻6号(2016年6月発行)
特集 “賢い処方”と“ナゾ処方”
26巻5号(2016年5月発行)
特集 しびれるんです!─知っておくべきシビレル疾患
26巻4号(2016年4月発行)
特集 ケースとクイズで総ざらい! 街場の2型糖尿病治療
26巻3号(2016年3月発行)
特集 こんな時は漢方でしょう!
26巻2号(2016年2月発行)
特集 フィジカル改革宣言! ──診断からフォローアップまで
26巻1号(2016年1月発行)
特集 妊婦・褥婦が一般外来に来たら─エマージェンシー&コモンプロブレム
25巻12号(2015年12月発行)
特集 外来で「複数の疾患」をもつ患者を診る─マルチモビディティの時代のプライマリ・ケア
25巻11号(2015年11月発行)
特集 レアだけど重要な「痛み」の原因─システム1診断学
25巻10号(2015年10月発行)
特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 2
25巻9号(2015年9月発行)
特集 診断ピットフォール10選─こんな疾患,見逃していませんか?
25巻8号(2015年8月発行)
特集 健診データで困ったら─こんな検査結果を持ってこられたら
25巻7号(2015年7月発行)
特集 ここを知りたい!頭部外傷初期対応・慢性期ケア
25巻6号(2015年6月発行)
特集 高齢者救急の落とし穴─紹介する時,される時
25巻5号(2015年5月発行)
特集 咳を聴きとり,咳を止める
25巻4号(2015年4月発行)
特集 関節が痛いんです!─コモンからレアものまでの診断と治療
25巻3号(2015年3月発行)
特集 神経難病ケアのコペルニクス的転回
25巻2号(2015年2月発行)
特集 総合医のためのスポーツ医学ベーシックス
25巻1号(2015年1月発行)
特集 動悸・息切れ─ヤバい病気の見つけ方 そして見つからなかった時の対処法
