地方に行くほど、「高齢化問題」は深刻だ。高齢化率が50%を超え、社会的共同生活が困難になった限界集落も多く存在する。医療の重要性が増す一方で、そうした地域では医師不足や医療へのアクセス性が問題になっている。積雪が多い山間部などでは、高齢者が自ら車を運転し1時間かけて町の病院を受診する負担は大きい。昨冬は、「気候変動」の影響もあってか、豪雪に見舞われた地域もあった。「新型コロナウイルス感染症」の流行による受診控えや面会制限などで、患者・家族とも病院へ行きづらい状況もある。今こそ、“新時代”の「在宅医療」が求められている。
もとより、医療や介護が必要な状態になっても、自宅で自立した暮らしを続け、住み慣れた地域で家族・友人と生活を楽しむことは、QOLや患者満足度を高める。そのためには、疾患の早期発見・早期治療や重症化の予防などを実現する、病院・診療所そして在宅医療の連携と地域ネットワークが必要だ。都市部に先んじて高齢化が進む地方では、すでにその試行錯誤が進んでいる。そこで本特集では、まず「地方」での在宅医療に着目した。東日本大震災から10年を迎えた「福島」の地域医療の今に光を当て、また各地の先進的な取り組みを紹介する。
雑誌目次
総合診療31巻7号
2021年07月発行
雑誌目次
特集 新時代の「在宅医療」—先進的プラクティスと最新テクノロジー
扉 フリーアクセス
著者: 山中克郎
ページ範囲:P.822 - P.823
今月の「めざせ! 総合診療専門医!」問題
ページ範囲:P.885 - P.885
本問題集は、今月の特集のご執筆者に、執筆テーマに関連して「総合診療専門医なら知っておいてほしい!」「自分ならこんな試験問題をつくりたい!」という内容を自由に作成していただいたものです。力試し問題に、チャレンジしてみてください。
【総論】座談会
“新時代”の在宅医療が目指すべきもの—「都市部/地方」の違いからみた課題と可能性
著者: 奥知久 , 藤沼康樹 , 山中克郎
ページ範囲:P.824 - P.831
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行により、「在宅医療」のニーズが全国的に高まっている。感染対策としての受診控えや面会制限などのため、病院へのアクセスも悪くなっている。しかし在宅医療のリソース不足は、都市部/地方それぞれに、特に山間へき地では深刻だ。今後ますます高齢化、都市化・過疎化が進むなかで、いかに在宅ニーズに応えていくのか? その時、在宅医療を行う医師に求められるスキルは? 本座談会では、それぞれの現場で地域医療を実践してきた三氏が、「都市部/地方」を対比して語ることで、“新時代”の在宅医療の方向性を示した。
【各論Ⅰ】東日本大震災から10年—「福島」における地域医療の今
「復興地域」の医療の現状と課題—原発事故の影響と医療ニーズの拡大・多様化
著者: 谷川攻一
ページ範囲:P.832 - P.836
原発事故による「住民」の避難と帰還
筆者が院長を務める「福島県ふたば医療センター附属病院」が所在する福島県双葉郡は、2011年3月11日の東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所(以下、福島第一原発)事故により、最も大きな被害を受けた地域である。
「福島市」の在宅医療の現状と課題—仮設住宅での看取りに学んだ「住まい」の意味
著者: 橋本孝太郎
ページ範囲:P.837 - P.840
Case(仮想症例)
患者:80代、男性。直腸がん末期、転移性肝腫瘍。福島第一原発がある福島県双葉郡(p.832)からの避難者で、福島市内の「仮設住宅」に在住。同居家族は妻のみだが、同一敷地内の仮設住宅群の別棟に娘夫婦・孫がいた。もともと住んでいた地域の住民もこの仮設住宅群に多くいたが、県外に避難した者も多かった。もとのかかりつけ医も被災しており、主治医変更も余儀なくされた。
現病歴:東日本大震災後に化学療法が長期間中止され、その間に全身状態も悪化したため、「在宅緩和ケア」を目的に当院紹介となった。介入当初はPS(performance status)3程度で、なんとか室内歩行は可能であった。
訪問看護・訪問介護・訪問薬剤管理サービスを利用し、娘家族・地域住民も積極的に介入してくれたおかげで、仮設住宅においても通常と同等の医療・ケアを提供でき、その場で最期を迎えることができた。しかし、本人・家族らのパーソナルスペースを確保しプライバシーを保つこと、双葉郡の自宅への想い、コミュニティを失った寂しさを埋めることは難しく、仮設住宅での療養環境は決して良いものではなかった。
「奥会津」における在宅医療の挑戦—Think globally, act locally!
著者: 鎌田一宏
ページ範囲:P.841 - P.845
2020年7月1月、「奥会津在宅医療センター」(福島県大沼郡三島町)が設立された。筆者は、総合内科と感染症診療を軸に、この3年半は海外を主戦場としてきた。この間、日本へ帰国する機会が時折あったが、都市部と地方の「医療格差」を改めて感じ、それを心のどこかで憂い釈然としないまま、また海外へおもむいていた。そんななか、山中克郎先生(福島県立医科大学 会津医療センター)にお声かけいただき、医師不足・医療過疎が深刻な奥会津で「在宅医療」を展開することになった。本稿では、そのなかで見えてきた高齢化・過疎化が進む「地方」の医療の課題と可能性、日本全国、そして世界の医療の課題を概観してみたい。
【各論Ⅱ】各地の先進的実践事例集
「誤嚥性肺炎・摂食嚥下障害」の多職種連携
著者: 大浦誠
ページ範囲:P.846 - P.850
Case
患者:80歳、男性
既存歴:Parkinson病
現病歴:ADLは杖歩行レベルで、同程度のADLの妻と2人暮らし。食事は、普段からたまにむせることがあったが、とろみをつけずに食べていた。たまに一過性に発熱することはあったが活気もあり、食事を1食スキップすると解熱し、今までどおり食べているようであった。入院するほどでもなく、外来治療が必要というほどでもないが、今後もっと悪くなることを心配している。近所の方から南砺市民病院に「外来嚥下評価パス」があることを教えてもらったと相談があった。
「ポータブルエコー」でここまでわかる!
著者: 亀田徹
ページ範囲:P.851 - P.855
Case
転倒して右胸部をぶつけた一例
患者:78歳、男性
既往歴:脳梗塞による右不全麻痺・運動性失語
現病歴:要介護2で、週1回の訪問看護を受けている。この半年で認知機能の低下が進んできた。
昼食摂取中に椅子から転倒したところを、家族に発見された。なんとか起き上がらせてベッドまで軽介助で連れていったが、体動時に顔をしかめていた。連絡を受けた看護師が訪問すると、ベッドで臥していた。顔色は良く、頻呼吸はなかった。血圧は安定、SpO2 93%(普段は94〜96%程度)、呼吸音は右が少し弱いように感じた。右側胸部に限局性の圧痛があり、皮下気腫ははっきりしなかった。
看護師が往診を依頼したところ、医師の所見も看護師のアセスメントと同様で、「右肋骨骨折」の可能性があり、「血胸」と「気胸」の除外が必要と考えられた。往診時に携帯しているポケットサイズのポータブルエコー(ポケットエコー)で評価したところ、仰臥位では左右胸腔に胸水貯留はなく、右前胸部の胸膜ライン上でlung slidingは消失(図1ⓐ)、左前胸部のlung slidingは認めた。また、右側胸部の圧痛部位に一致して肋骨表面の不連続性(ズレ)を確認した(図1ⓑ)。
エコー以外の「ポイントオブケア検査」—発熱時の感染症診療の原則
著者: 小野正博
ページ範囲:P.856 - P.859
Case
急性の発熱をきたした超高齢者の一例
患者:91歳、女性
現病歴:3年前、多発性骨髄腫と診断されたが、化学療法は行わない方針となっていた。1カ月前、高カルシウム血症による意識障害のため入院。点滴後意識状態は改善したが、貧血・腎障害は悪化した。自宅で看取る方針となり、1週間前に自宅退院、訪問診療・訪問看護を導入した。
3日前より38℃台の発熱出現。バイタルサインは、意識レベルJCS(Japan Coma Scale)3〜10、呼吸数20回/分、脈拍数96回/分、血圧112/60mmHg、SpO2 95%(室内気)、体温38.0℃。身体所見は、結膜;貧血あり、頸部;異常所見なし、胸部;心雑音なし、肺音;清、腹部;腸雑音正常、平坦・軟、自発痛・圧痛なさそう、浮腫・皮疹;なし。新型コロナウイルス鼻咽頭抗原検査は、接触歴がないため行わなかった。尿が混濁しているとの報告があり、尿路感染を疑って「尿グラム染色」を行ったところ、グラム陰性桿菌を認めた。尿培養検体を採取後、セフトリアキソンを点滴し、解熱したためセファレキシンの内服に変更した。
本年3月末、東京から会津に移住した。福島県立宮下病院(大沼郡)に常勤医として週3日、福島県立医科大学会津医療センター(会津若松市)に非常勤医として週2日勤務している。本稿では、宮下病院に入院後、奥会津在宅医療センター(大沼郡、p.841)の訪問診療・訪問看護を導入したCaseをもとに、在宅診療における「発熱時」の検査を中心に述べる(本Caseは、実際には退院3日前の発熱であり、在宅診療時の発熱ならこうなったであろうという架空症例である)。
「在宅リハビリテーション」と「栄養指導」
著者: 若林秀隆
ページ範囲:P.860 - P.863
Case
栄養改善で外出自立・復職した一例
患者:50歳、男性。身長178cm、体重49kg(健常時体重58kg)、BMI 15.5。
現病歴:右前頭葉〜側頭葉の脳腫瘍に対して開頭腫瘍除去術、その後に放射線療法と化学療法が施行された。食欲不振・味覚障害・高次脳機能障害・軽度左片麻痺を認める。基本的ADL(日常生活活動)は自立していたが、低栄養と体力低下のため外出困難・閉じこもりとなった。GLIM(Global Leadership Initiative on Malnutrition)基準で「低栄養」、AWGS(Asian Working Group for Sarcopenia)2019基準で「サルコペニア」と診断し、在宅リハビリテーション(以下、リハ)で介入した。
「3カ月後に1kgの体重増加と10分間の屋外歩行可能」「1年後に9kgの体重増加と復職」をゴールとして、多職種でリハ栄養を実施した。1年後に8kg体重増加し(57kg、BMI 18.5)、復職した。低栄養・サルコペニアも改善した。
在宅医療における「ナース・プラクティショナー(診療看護師)」の可能性と課題
著者: 福添恵寿
ページ範囲:P.864 - P.867
NP(診療看護師)って?
2008年から本邦でも、米国(p.882)のナース・プラクティショナー(nurse practitioner:NP)教育を参考に、「NP(診療看護師)教育課程」(大学院)が設置された。そこでは、病態生理学・臨床薬理学などとともに、対象者の身体状況を的確に把握し、診断や治療を提案するプロセスを講義・実習を通して学んでいる。修了者は、日本NP大学院協議会による認定試験を経て、医療現場でその知識や判断力を活かし、患者・利用者(家族やパートナー、ケアマネジャーほか地域の関係者を含む)に的確に対応しており、さまざまなアウトカムに貢献している。
しかし、本邦ではNPは制度化されておらず、法的には「看護師特定行為研修修了者」(特定看護師)と位置づけられている。そのため、米国などのNPとは異なり、単独での診療行為は認められていないのが現状である。
「コミュニティ」を巻き込む
著者: 大曽根衛
ページ範囲:P.868 - P.870
コミュニティに働きかける動きに落としどころや正解を求めたり、他地域の真似をしたりしても、うまくいかないのは想像に難くない。では、「個人や町にとっての健康に関する“好循環”をどのように創り出すか」という問いに、どう向き合っていけばよいのか?
その答えに正解はないが、「コミュニティ」にアプローチするうえで意識するとよいツボのようなものはある。筆者は、一般社団法人「地域包括ケア研究所」(鎌田實所長)のカタリスト(触媒役)として、各地のまちづくり・地域包括ケアの文化づくりに携わってきた。本稿では、当研究所が提供するバリューである「まちづくり循環モデル(地域包括ケア研究所が提供するバリュー)」(図1)を、福島県西会津町での取り組みを例に紹介する。
【スペシャル・アーティクル】ICT(情報通信技術)を使い倒す
病院と在宅・診療所を結ぶ「遠隔医療」「オンライン診療」
著者: 本村和久
ページ範囲:P.871 - P.874
Case1
離島診療所での遠隔コンサルテーション
沖縄県には16の県立離島診療所があり、そこに単独赴任する医師は卒後9年目以下の若手医師で最も経験年数の少ない医師は総合診療専門研修3年次(最短で卒後5年目)である。診療の場は、診療所のみならず、在宅や施設など幅広い。
皮膚科に関する相談窓口は、研修プログラムをもつ沖縄県立中部病院の皮膚科医が関わっている。スマートフォンで撮った皮膚所見を皮膚科医に送ってコメントを得るコンサルテーションを行っている。整形外科領域でも、X線写真での骨折診断やその後のギブス固定の方法などを、スマートフォンの写真をもとに指導している現状がある。
「スマートシティ」の概念と医療・介護
著者: 藤井靖史
ページ範囲:P.875 - P.878
変化し続ける「スマートシティ」の定義・概念
私たちがスマートシティを語る時、「そもそもスマートシティとは何か?」という基本の議論を、しっかり共有しておかねばならないだろう。なぜなら、この言葉は時とともに、また技術やプロジェクトの進行によっても、定義そのものが変化していくため、もしかしたら私とあなたでは別のスマートシティを想定しているかもしれないからである。
【コラム】
総合診療医センター構想
著者: 山中克郎
ページ範囲:P.879 - P.881
2020年、厚生労働省は「総合診療医センター」構想を発表、これを実施する団体を公募した。その目的は表11)のとおりである。2021年度には、全国で7つの大学(秋田大学、福島県立医科大学、新潟大学、福井大学、三重大学、島根大学、大分大学)の案が採択され、それぞれが特色ある総合診療医養成のためのアイデアを練って実現に移そうとしている。本稿では、福島医大での取り組みを紹介する。
米国の在宅医療—ナース・プラクティショナー(NP)の視点から
著者: 毛受契輔
ページ範囲:P.882 - P.884
病院→在宅への回帰
米国では、「プライマリ・ケア」への回帰が起こっており、病院から在宅での治療への移行を望む患者・家族が増えている。新型コロナウイルス感染症流行により、その傾向は顕著である。
筆者は、2018年に米・カリフォルニア州立大学NP(nurse practitoner)大学院を修了後、2019年よりナース・プラクティショナー(NP)として、カリフォルニア州で在宅医療に携わっている。本稿では、その経験から、米国の在宅医療の現状について紹介する。
Editorial
最先端の技術で“昔ながらの医療”を フリーアクセス
著者: 山中克郎
ページ範囲:P.815 - P.815
在宅医療を展開している山間部の奥会津(p.841)に車を走らせながら、こう考えた。AI(人工知能)の発達とともに、近未来の医療はどうなっていくのだろう? 生活の快適さを求め、大都市への人口集中が世界中で急速に進んでいる(p.844)。地域で最期まで家族と一緒に幸せに暮らすことはできるのだろうか?
エリック・トポル著『Deep Medicine』1)には、AIのディープラーニングを用いた医療の変革が描かれている。パターン認識力の向上により、AIは専門医と同等の水準で、CT/MRI画像の読影や病理診断、皮膚科診断を行うことができる。眼底写真読影による早期の糖尿病網膜症の発見、検診で撮影された胸部X線写真上の小さな肺がんの検出、自殺を精神科医以上の能力で予測することはAIを用いれば可能となる。専門医の仕事は楽になり、へき地においても医療水準を大きく引き上げるであろう。
What's your diagnosis?[223]
免疫で節節が…
著者: 小田垣孝雄
ページ範囲:P.818 - P.821
病歴
患者:70代、女性
主訴:発熱、心窩部痛
現病歴:X年5月下旬、37℃台の発熱と起床時に動けなくなるほどの四肢関節周囲の痛みを自覚するようになった。その頃より食欲が低下し、水分以外は十分に摂取できず、体重が1カ月で6kg減少した。
6月末に前医を受診し、体重減少に対して食道胃十二指腸内視鏡検査、大腸内視鏡検査を施行されたが異常は指摘されず、血液検査にて抗核抗体1,280倍、抗CCP抗体>500U/mLであったことから当院膠原病・リウマチ内科を紹介受診予定であった。7月初旬にタクシーを下車し歩いている間に前兆なく眼前暗黒感が出現し、膝をつくように転倒した。数分休んでいると回復し、起き上がることができるようになったが心配になり、翌日に当院救急外来を受診した。
既往歴・薬剤歴:高血圧症(以前はアムロジピン5mgを内服していたが、数カ月前から休薬)、尿路感染症
生活歴:生活状況:喫茶店で働いていたが、体調悪化のため退職。飲酒歴:なし、喫煙歴:なし、アレルギー:特記事項なし
【エッセイ】アスクレピオスの杖—想い出の診療録・15
“JOY”of the World!|ロールモデル百花繚乱・18
流水不腐—腐らず、よどまず
著者: 中山明子
ページ範囲:P.888 - P.892
総合診療医として医師16年目となった。女性医師のロールモデルとなるようなキャリア・働き方についての連載とのことだが、残念ながら私のキャリア(表1)は胸を張ってお見せできるようなものではない(特に私生活)。本連載の執筆者は素敵な女性医師ばかりだが、こんな女医もいるという一例としてご笑覧いただければ幸いである。
『19番目のカルテ』を読んで答える! あなたの“ドクターG度”検定&深読み解説・4
治療の主役—(『19番目のカルテ—徳重晃の問診』第4話より)
著者: 徳田安春
ページ範囲:P.893 - P.895
本連載は総合診療ビギナーの皆さんに、総合診療の楽しさと奥深さを解説することが目的です。漫画『19番目のカルテ』のエピソードを深読みすることにより、総合診療医がどのような根拠に基づいて診断しているのかを理解していただければ幸いです。本連載は『総合診療』×『19番目のカルテ』のコラボ企画で、本誌編集委員の徳田安春先生・山中克郎先生が隔月で作問&解説します!
研修医Issy&指導医Hiro&Dr.Sudoのとびだせフィジカル! 聴診音付・7
心臓のフィジカル Part3
著者: 石井大太 , 須藤博
ページ範囲:P.897 - P.900
ここは、とある病院。研修医IssyはフィジカルマスターDr. Sudoとともに、入院患者さんのベッドサイドへ回診に赴くのであった。
オール沖縄!カンファレンス|レジデントの対応と指導医の考えVer.2.0・55
多彩な症状に、どうアプローチする?
著者: 山形未来 , 知花なおみ , 徳田安春
ページ範囲:P.911 - P.915
CASE
患者:70代、女性。
主訴:微熱、食欲不振、下肢のしびれ。
現病歴:COVID-19感染拡大に伴い自宅待機していたが、X月1日に2カ月ぶりに出勤。帰宅後から左膝下〜左足趾と右足趾にしびれが出現。食欲不振も感じるようになった。X月3日に37℃台の微熱があり、かかりつけの呼吸器内科を受診。血液検査で白血球数上昇(14,000/μL)を認めたが、経過観察の方針となった。下肢のしびれで整形外科へ紹介され、変形性腰痛症の診断を受けた。X月9日、食欲不振で食事が摂れず、微熱・下肢のしびれも改善しないため、当院夜間救急外来を受診。
ROS(+):倦怠感、喘鳴(普段から喘鳴あり。悪化していない)。
ROS(-):腹痛・嘔気、便秘・下痢、咳・痰、呼吸困難感、嚥下困難、関節痛。
既往歴:気管支喘息(50歳で発症。怠薬はないが60歳で入院歴あり、時々ステロイドの点滴を受けている)、右滲出性中耳炎(2年前)、インフルエンザ桿菌肺炎(2年前)、高血圧、アレルギー性鼻炎、脂質異常症。
薬剤歴:レルベア® 200μg 1吸入/日、スピリーバ® 2.5μg 2吸入/日、テオドール® 400mg/日、アムロジピン® 5mg/日、メチコバール® 1,500mg/日、MS温湿布® 1日1枚。
アレルギー歴:なし。
生活歴:喫煙・飲酒なし。
職業:結婚式場のフロア係(機材の運搬や掃除でよく体を動かす)。
“コミュ力”増強!「医療文書」書きカタログ・13
—総合診療医の腕の見せどころ!—下降期慢性疾患“リセット入院”の依頼状
著者: 天野雅之
ページ範囲:P.916 - P.920
今月の文書
診療情報提供書
セッティング:診療所→総合病院への診療依頼
患者:82歳、男性。慢性心不全、認知症。1カ月前より、大学病院から診療所外来で診療を引き継いだ。訪問診療導入も検討したが、「浮腫増悪」と「労作時呼吸苦」があり、各種調整目的に入院加療を計画した。
【登場人物】
桜井:総合診療科1年目専攻医。現在は地域の診療所で研修中。
生駒:総合診療科4年目専攻医。桜井の先輩。病棟診療のチームリーダー。
飛鳥:桜井の指導医。専門研修プログラム責任者として、定期的に面談している。
Dr.上田剛士のエビデンス実践レクチャー!医学と日常の狭間で|患者さんからの素朴な質問にどう答える?・16
つわりが強ければ女の子!?
著者: 上田剛士
ページ範囲:P.922 - P.925
患者さんからのふとした質問に答えられないことはないでしょうか? 素朴な疑問ほど回答が難しいものはありませんが、新たな気づきをもたらす良問も多いのではないでしょうか? 本連載では素朴な疑問に、文献的根拠を提示しながらお答えします!
患者さんには言えない!? 医者のコッソリ養生法・2
不養生の医者、東洋医学で不摂生を見破られる
著者: 須田万勢
ページ範囲:P.926 - P.930
前回、医者なのに風邪をひきやすく、ひいても治せない貝原先生の前に、状況を見かねた古代ギリシャの医療の神・アスクレピオス(自称ピオちゃん)が現れた。古今東西の医療を知り尽くすピオちゃんの言うとおりにしてみると、するりと風邪を経過させることができた貝原先生だったが、ピオちゃんはそれだけでは許してくれない。風邪を引いた“原因”を考え、風邪を“予防”する方法について、「東洋医学」の病因論と「西洋医学」のエビデンスの双方から、医神による怒涛のレクチャーが今日も展開される。
【臨床小説】後悔しない医者|あの日できなかった決断・第16話
運命を受け入れられない医者
著者: 國松淳和
ページ範囲:P.931 - P.936
前回までのあらすじ 今月のナゾ
患者は83歳・男性、教育部長・吉田の父である。昨年末から手足が効かなくなったり、むせやすくなり、整形外科・脳外科・神経内科で診察を受けたが、特に診断はついていない。パーキンソン病は否定されており、「高齢だから」というのが神経内科の診立てだった。そこで吉田が黒野に相談に来たのだ。実際に診察した筧に、黒野は「加齢か病気か」と問うて…。
「診断エラー」とは、どの時点でそれをエラーというのだろうか? 初療時に診断がつかないことはままあるし、その後、当初の診立てが異なっていたと徐々にわかってくることもある。時に、それが取り返しのつかない結果を招くこともあるだろう。今回のタイトルは「運命を受け入れられない医者」だが、果たして運命とは? そして今回、運命を受け入れられなかったのは?
投稿 GM Clinical Pictures
肺炎入院中のバイタルチャートに異変が…
著者: 若林崇雄 , 渡邉智之 , 田口遼 , 石立尚路 , 須藤大智 , スフィ・ノルハニ
ページ範囲:P.901 - P.902
CASE
患者:特記すべき既往のない81歳、女性。
主訴:1週間持続する嘔気。
バイタルサイン:意識清明。血圧111/61mmHg、脈拍数92回/分・整、体温39.0℃(腋窩温)、呼吸数20回/分。
身体所見:右下肺野にholo coarse crackleを聴取した。
血液検査:炎症反応(WBC 9,570/μL、Neut 95%、CRP 14.59mg/dL)とともに軽度の肝障害(AST 53IU/L、ALT 38IU/L、LDH 301IU/L)と電解質異常(Na 131mEq/L、Cl 96mEq/L、K 3.5mEq/L)を認めた。
胸部単純X線:同部位に一致して浸潤影を認めた(図1)。
経過:市中肺炎と診断し、抗菌薬アンピシリン/スルバクタム 1回3g、1日4回を開始したが、改善に乏しかった。入院後の経過表を図2に示す。
#総合診療
#今月の特集関連本❶ フリーアクセス
ページ範囲:P.850 - P.850
#今月の特集関連本❷ フリーアクセス
ページ範囲:P.867 - P.867
#今月の特集関連本❸ フリーアクセス
ページ範囲:P.870 - P.870
#今月の特集関連本❹ フリーアクセス
ページ範囲:P.881 - P.881
#今月の特集関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.903 - P.905
#今月の連載関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.819 - P.819
#今月の連載関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.907 - P.907
#今月の連載関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.930 - P.930
#医学書院の新刊 フリーアクセス
ページ範囲:P.906 - P.907
#書評:内科医の私と患者さんの物語—血液診療のサイエンスとアート フリーアクセス
著者: 山中克郎
ページ範囲:P.909 - P.909
最近注目されている能力の1に「ソフトスキル」がある。常識として必要であることがわかっているが、点数化することが難しいスキルのことである。コミュニケーション力やチームワーク、失敗から立ち直る力、批判的な思考、ユーモアのセンスが含まれる。経済が目まぐるしく変化する現代において、よい仕事をするためには必須のスキルと言われている。医療従事者にも必要なこれらのスキルを、どう磨けばよいか? それを本書から学ぶことができる。長く豊富な臨床経験があり、真摯に患者さん1人ひとりと向き合ってきた岡田定先生にしか書けない、患者さんと紡いだ心温まる物語集だ。
本書のサブタイトルは「血液診療のサイエンスとアート」である。世界中の多くの医師に敬愛されている、カナダ生まれの内科医ウィリアム・オスラー(1849-1919)は、「医療はサイエンスに基づいたアートである」という言葉を残した。医学は真理を追求する「科学(サイエンス)」であるが、それだけでは不十分なのだ。発熱した子どもを優しく見守る母親のような「慈しみ(アート)」が必要である。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.816 - P.817
読者アンケート
ページ範囲:P.910 - P.910
『総合診療』編集方針 フリーアクセス
ページ範囲:P.937 - P.937
1991年に創刊した弊誌は、2015年に『JIM』より『総合診療』に誌名を変更いたしました。その後も高齢化はさらに進み、社会構造や価値観、さらなる科学技術の進歩など、日本の医療を取り巻く状況は刻々と変化し続けています。地域医療の真価が問われ、ジェネラルに診ることがいっそう求められる時代となり、ますます「総合診療」への期待が高まってきました。これまで以上に多岐にわたる知識・技術、そして思想・価値観の共有が必要とされています。そこで弊誌は、さらなる誌面の充実を図るべく、2017年にリニューアルをいたしました。本誌は、今後も下記の「編集方針」のもと、既存の価値にとらわれることなく、また診療現場からの要請に応え、読者ならびに執筆者のみなさまとともに、日本の総合診療の新たな未来を切り拓いていく所存です。
2018年1月 『総合診療』編集委員会
『総合診療』バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.938 - P.939
お得な年間購読のご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.939 - P.940
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.941 - P.942
基本情報
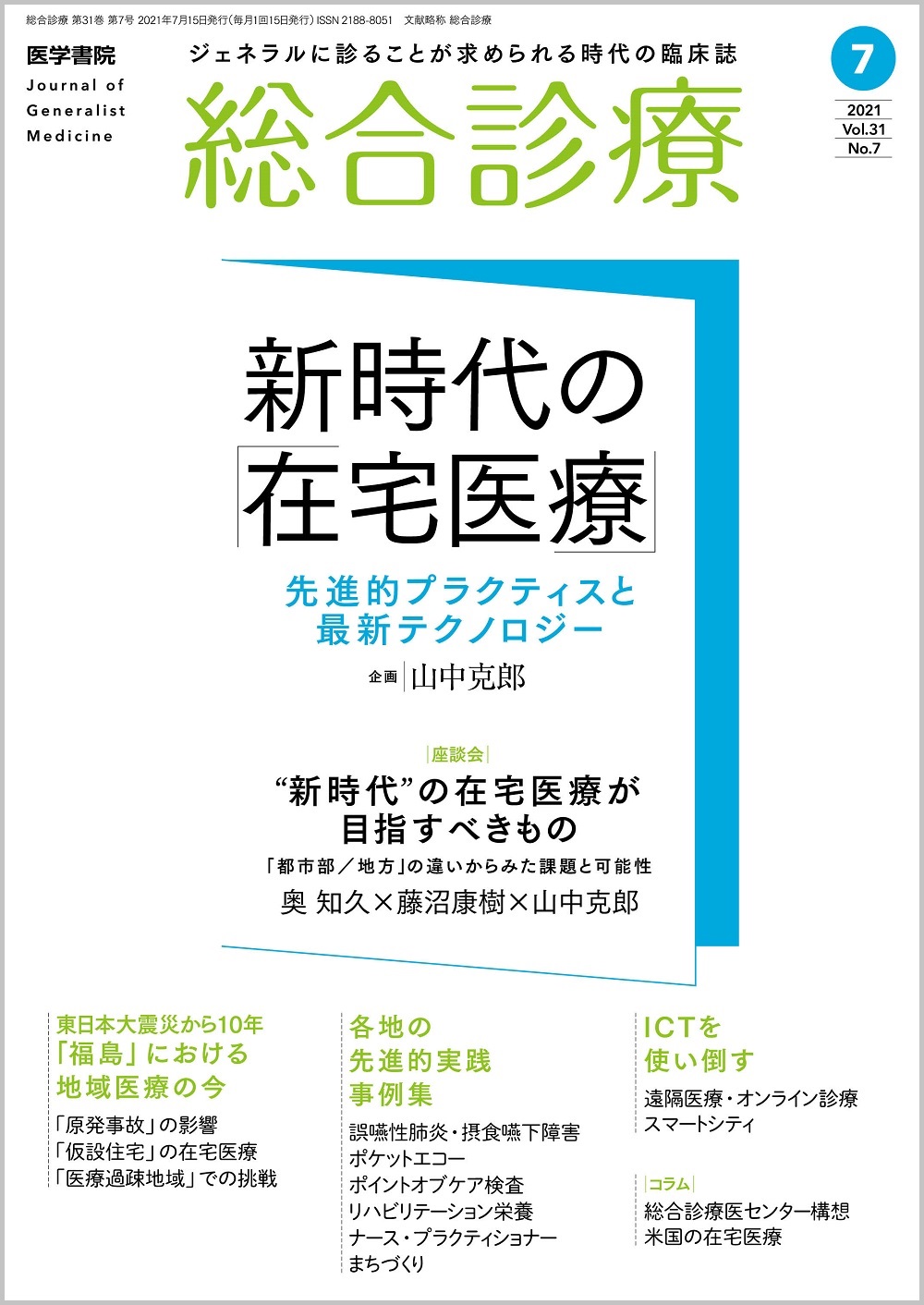
バックナンバー
34巻12号(2024年12月発行)
特集 妊婦・褥婦が外来に来たらUpdate—症状対応からワクチン・プラネタリーヘルスまで
34巻11号(2024年11月発行)
特集 電子カルテとベッドサイドの壁を打ち破る!—患者情報の「言語化」への挑戦
34巻10号(2024年10月発行)
特集 化かしが得意なカメレオンな疾患を捕まえろ!—よくある騙され方のゲシュタルト
34巻9号(2024年9月発行)
特集 今伝えたいクリニカル・パール—つくり方、使い方、活かし方
34巻8号(2024年8月発行)
特集 ストーン・ウォーズ 果てしなき“石”と医師との闘い
34巻7号(2024年7月発行)
特集 どうする!? 健診異常—これってホントに異常なの? どう説明する?
34巻6号(2024年6月発行)
特集 医師のウェルビーイング
34巻5号(2024年5月発行)
特集 —優柔不断にサヨウナラ!—あなたの「臨床判断」を高めるケーススタディ11選
34巻4号(2024年4月発行)
特集 困ったときの漢方—この症状に役立ちます!
34巻3号(2024年3月発行)
特集 —え、ウソ!実は◯◯だった!?—“コモンディジーズ”の診断ピットフォール
34巻2号(2024年2月発行)
特集 日常診療で出合う筋骨格疾患—脳神経内科と整形外科からのアプローチ
34巻1号(2024年1月発行)
特集 —“体験型”臨床クイズで習得する!—フィジカル診断エクセレンス
33巻12号(2023年12月発行)
特集 海の外へ渡る航行者を診る—アウトバウンドにまつわるetc.
33巻11号(2023年11月発行)
特集 —続・総合診療外来に“実装”したい—最新エビデンスMy Best 3
33巻10号(2023年10月発行)
特集 ○×クイズ110問!日常診療アップグレード—Choosing WiselyとHigh Value Careを学ぼう
33巻9号(2023年9月発行)
特集 ジェネラリストのための「発達障害(神経発達症)」入門
33巻8号(2023年8月発行)
特集 都市のプライマリ・ケア—「見えにくい」を「見えやすく」
33巻7号(2023年7月発行)
特集 “消去法”で考え直す「抗菌薬選択」のセオリー—広域に考え、狭域に始める
33巻6号(2023年6月発行)
特集 知っておくべき!モノクロな薬たち(注:モノクローナル抗体の話ですよ〜)
33巻5号(2023年5月発行)
特集 —疾患別“イルネススクリプト”で学ぶ—「腹痛診療」を磨き上げる22症例
33巻4号(2023年4月発行)
特集 救急対応ドリル—外来から在宅までの60問!
33巻3号(2023年3月発行)
特集 —自信がもてるようになる!—エビデンスに基づく「糖尿病診療」大全—新薬からトピックスまで
33巻2号(2023年2月発行)
特集 しびれQ&A—ビビッとシビれるクリニカルパール付き!
33巻1号(2023年1月発行)
特集 COVID-19パンデミック 振り返りと将来への備え
32巻12号(2022年12月発行)
特集 レクチャーの達人—とっておきの生ライブ付き!
32巻11号(2022年11月発行)
特集 不定愁訴にしない“MUS”診療—病態からマネジメントまで
32巻10号(2022年10月発行)
特集 日常診療に潜む「処方カスケード」—その症状、薬のせいではないですか?
32巻9号(2022年9月発行)
特集 総合診療・地域医療スキルアップドリル—こっそり学べる“特講ビデオ”つき!
32巻8号(2022年8月発行)
特集 こんなところも!“ちょいあて”エコー—POCUSお役立ちTips!
32巻7号(2022年7月発行)
特集 —どうせやせない!? やせなきゃいけない??苦手克服!—「肥満」との向き合い方講座
32巻6号(2022年6月発行)
特集 総合診療外来に“実装”したい最新エビデンス—My Best 3
32巻5号(2022年5月発行)
特集 「診断エラー」を科学する!—セッティング別 陥りやすい疾患・状況
32巻4号(2022年4月発行)
特集 えっ、これも!? 知っておきたい! 意外なアレルギー疾患
32巻3号(2022年3月発行)
特集 AI時代の医師のクリニカル・スキル—君は生き延びることができるか?
32巻2号(2022年2月発行)
特集 —withコロナ—かぜ診療の心得アップデート
32巻1号(2022年1月発行)
特集 実地医家が楽しく学ぶ 「熱」「炎症」、そして「免疫」—街場の免疫学・炎症学
31巻12号(2021年12月発行)
特集 “血が出た!”ときのリアル・アプローチ—そんな判断しちゃダメよ!
31巻11号(2021年11月発行)
特集 Q&Aで深める「むくみ診断」—正攻法も!一発診断も!外来も!病棟も!
31巻10号(2021年10月発行)
特集 医師の働き方改革—システムとマインドセットを変えよう!
31巻9号(2021年9月発行)
特集 「検査」のニューノーマル2021—この検査はもう古い? あの新検査はやるべき?
31巻8号(2021年8月発行)
特集 メンタルヘルス時代の総合診療外来—精神科医にぶっちゃけ相談してみました。
31巻7号(2021年7月発行)
特集 新時代の「在宅医療」—先進的プラクティスと最新テクノロジー
31巻6号(2021年6月発行)
特集 この診断で決まり!High Yieldな症候たち—見逃すな!キラリと光るその病歴&所見
31巻5号(2021年5月発行)
特集 臨床医のための 進化するアウトプット—学術論文からオンライン勉強会、SNSまで
31巻4号(2021年4月発行)
特集 消化器診療“虎の巻”—あなたの切実なギモンにズバリ答えます!
31巻3号(2021年3月発行)
特集 ライフステージでみる女性診療at a glance!—よくあるプロブレムを網羅しピンポイントで答えます。
31巻2号(2021年2月発行)
特集 肺炎診療のピットフォール—COVID-19から肺炎ミミックまで
31巻1号(2021年1月発行)
特別増大特集 新型コロナウイルス・パンデミック—今こそ知っておきたいこと、そして考えるべき未来
30巻12号(2020年12月発行)
特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き) Part 2
30巻11号(2020年11月発行)
特集 診断に役立つ! 教育で使える! フィジカル・エポニム!—身体所見に名を残すレジェンドたちの技と思考
30巻10号(2020年10月発行)
特集 —ポリファーマシーを回避する—エビデンスに基づく非薬物療法のススメ
30巻9号(2020年9月発行)
特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【感染症・内分泌・整形外科 編】
30巻8号(2020年8月発行)
特集 マイナーエマージェンシー門外放出—知っておくと役立つ! テクニック集
30巻7号(2020年7月発行)
特集 その倦怠感、単なる「疲れ」じゃないですよ!—筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群とミミック
30巻6号(2020年6月発行)
特集 下降期慢性疾患患者の“具合”をよくする—ジェネラリストだからできること!
30巻5号(2020年5月発行)
特集 誌上Journal Club—私を変えた激アツ論文
30巻4号(2020年4月発行)
特集 大便強ドリル—便秘・下痢・腹痛・消化器疾患に強くなる41問!
30巻3号(2020年3月発行)
特集 これではアカンで!こどもの診療—ハマりがちな11のピットフォール
30巻2号(2020年2月発行)
特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【循環器・消化器・神経疾患編】
30巻1号(2020年1月発行)
特集 総合診療医の“若手ロールモデル”を紹介します!—私たちはどう生きるか
29巻12号(2019年12月発行)
特集 困っている“あなた”に届く 認知症診療
29巻11号(2019年11月発行)
特集 臨床写真図鑑 レアな疾患編—見逃したくない疾患のコモンな所見
29巻10号(2019年10月発行)
特集 教えて!医師のためのビジネス・スキル
29巻9号(2019年9月発行)
特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き)
29巻8号(2019年8月発行)
特集 —ノーモア見逃し—日常の検査と画像に潜むピットフォール
29巻7号(2019年7月発行)
特集 リウマチ・膠原病ミミック症例帖—“膠原病っぽくみえてしまう疾患たち”にだまされない!
29巻6号(2019年6月発行)
特集 皮膚科診療エクササイズ—1枚の写真から
29巻5号(2019年5月発行)
特集 一般外来で診断できたら「えっへん!」な疾患38
29巻4号(2019年4月発行)
特集 “ナゾ”の痛み診療ストラテジー|OPQRSTで読み解く
29巻3号(2019年3月発行)
特集 —あなたのギモンに答えます!—循環器診療のハードルを下げるQ&A31
29巻2号(2019年2月発行)
特集 意外な中毒、思わぬ依存、知っておきたい副作用—一般外来で!OTCも処方薬も!
29巻1号(2019年1月発行)
特集 教えて検索!—膨大な医学情報を吟味・整理するスキル
28巻12号(2018年12月発行)
特集 こんなときこそ漢方を!
28巻11号(2018年11月発行)
特集 日本一マジメな「おしっこドリル」—今これだけは押さえておきたい腎・泌尿器のモンダイ
28巻10号(2018年10月発行)
特集 クリニカル・パールPremium!—憧れのカリスマ医師はかく語りき
28巻9号(2018年9月発行)
特集 オンコ・ジェネラリスト—「がん」に強い総合診療医をめざして
28巻8号(2018年8月発行)
特集 80歳からの診療スタンダードUp to Date—Silver Standard
28巻7号(2018年7月発行)
特集 この薬だけは押さえておきたい! 総合診療医のためのSpecialist Drug 40
28巻6号(2018年6月発行)
特集 聴診・触診×エコーで診断推論!—Point-of-Care超音波(POCUS)の底力
28巻5号(2018年5月発行)
特集 “一発診断”トレーニング問題集—懸賞論文「GM Clinical Pictures」大賞発表!
28巻4号(2018年4月発行)
特集 感染症外来診療「賢医の選択」—検査・経口薬・ワクチンをどう使えばいいんですか?
28巻3号(2018年3月発行)
特集 糖尿病のリアル—現場の「困った!」にとことん答えます。
28巻2号(2018年2月発行)
特集 頭痛患者で頭が痛いんです!
28巻1号(2018年1月発行)
特集 シン・フィジカル改革宣言!—私の“神技”伝授します。
27巻12号(2017年12月発行)
特集 小児診療“苦手”克服!!—劇的Before & After
27巻11号(2017年11月発行)
特集 今そこにある、ファミリー・バイオレンス|Violence and Health
27巻10号(2017年10月発行)
特集 めまいがするんです!─特別付録Web動画付
27巻9号(2017年9月発行)
特集 うつより多い「不安」の診かた—患者も医師も安らぎたい
27巻8号(2017年8月発行)
特集 見逃しやすい内分泌疾患─このキーワード、この所見で診断する!
27巻7号(2017年7月発行)
特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 3 カリスマ編
27巻6号(2017年6月発行)
特集 「地域を診る医者」最強の養成法!
27巻5号(2017年5月発行)
特集 コミュニケーションを処方する—ユマニチュードもオープンダイアローグも入ってます!
27巻4号(2017年4月発行)
特集 病歴と診察で診断できない発熱!—その謎の賢い解き方を伝授します。
27巻3号(2017年3月発行)
特集 これがホントに必要な薬40—総合診療医の外来自家薬籠
27巻2号(2017年2月発行)
特集 The総合診療ベーシックス—白熱!「総合診療フェスin OKINAWA」ライブ・レクチャー! 一挙公開 フィジカル動画付!
27巻1号(2017年1月発行)
特集 総合診療の“夜明け”—キーマンが語り尽くした「来し方、行く末」
26巻12号(2016年12月発行)
特集 これでパッチリ! 眼の健康問題
26巻11号(2016年11月発行)
特集 続・しびれるんです!
26巻10号(2016年10月発行)
特集 内科診療を劇的に変える“まとめ”の達人
26巻9号(2016年9月発行)
特集 症状・症候別 エコーを使った診断推論─Point-of-Care超音波
26巻8号(2016年8月発行)
特集 The 初診外来
26巻7号(2016年7月発行)
特集 感染症ケアバンドル・チェックリスト
26巻6号(2016年6月発行)
特集 “賢い処方”と“ナゾ処方”
26巻5号(2016年5月発行)
特集 しびれるんです!─知っておくべきシビレル疾患
26巻4号(2016年4月発行)
特集 ケースとクイズで総ざらい! 街場の2型糖尿病治療
26巻3号(2016年3月発行)
特集 こんな時は漢方でしょう!
26巻2号(2016年2月発行)
特集 フィジカル改革宣言! ──診断からフォローアップまで
26巻1号(2016年1月発行)
特集 妊婦・褥婦が一般外来に来たら─エマージェンシー&コモンプロブレム
25巻12号(2015年12月発行)
特集 外来で「複数の疾患」をもつ患者を診る─マルチモビディティの時代のプライマリ・ケア
25巻11号(2015年11月発行)
特集 レアだけど重要な「痛み」の原因─システム1診断学
25巻10号(2015年10月発行)
特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 2
25巻9号(2015年9月発行)
特集 診断ピットフォール10選─こんな疾患,見逃していませんか?
25巻8号(2015年8月発行)
特集 健診データで困ったら─こんな検査結果を持ってこられたら
25巻7号(2015年7月発行)
特集 ここを知りたい!頭部外傷初期対応・慢性期ケア
25巻6号(2015年6月発行)
特集 高齢者救急の落とし穴─紹介する時,される時
25巻5号(2015年5月発行)
特集 咳を聴きとり,咳を止める
25巻4号(2015年4月発行)
特集 関節が痛いんです!─コモンからレアものまでの診断と治療
25巻3号(2015年3月発行)
特集 神経難病ケアのコペルニクス的転回
25巻2号(2015年2月発行)
特集 総合医のためのスポーツ医学ベーシックス
25巻1号(2015年1月発行)
特集 動悸・息切れ─ヤバい病気の見つけ方 そして見つからなかった時の対処法
