現代はメンタルヘルスの時代といわれています。それは、現代において、精神障害の予防や治療だけでなく、今まさに進行中のパンデミック下の社会不安、社会的分断等を背景にした増大するストレスや、さまざまな精神的な負荷により生じる幅広い心の問題が注目されているということです。
総合診療外来の場においては、精神疾患を含む多疾患併存や、心理・社会・経済的な複雑困難事例に対応する場面は頻度が多いものです。また、外来で出合う未分化な健康問題は精神疾患がキーと考えられることもあります。漠然とした心の問題に対応する診療も多く、さらに最近は発達障害やパーソナリティ障害と困難事例の関連が指摘されることも多くなっています。
また、精神科以外の診療科においては、健康問題の医学的診断がつけば、治療あるいは対処可能であるという暗黙の前提があり、しばしば診断基準に基づいて「◯項目満たすから、うつ病である」といったDSM等に代表される操作的診断の発想が根深くあるようです。しかし、実際の精神科医療における診断は、それほど単純なものではありません。紹介やshared careの場面で、認識の齟齬が問題になるケースの多くが、そうした診断や治療の基本的な考え方の違いに由来しているという認識が経験上あります。
上記の問題意識から、総合診療外来で出合うメンタルヘルスをめぐる問題に関して、従来「真正面から」は語りにくかった領域について、掘り下げる特集を企画しました。
雑誌目次
総合診療31巻8号
2021年08月発行
雑誌目次
特集 メンタルヘルス時代の総合診療外来—精神科医にぶっちゃけ相談してみました。
扉 フリーアクセス
著者: 藤沼康樹 , 塚原美穂子
ページ範囲:P.952 - P.953
【総論1】
現代社会において、なぜ心の健康(メンタルヘルス)が注目されているのか?
著者: 森屋淳子
ページ範囲:P.954 - P.957
「これからは心の時代だ」と言われるようになってから、何十年も経ちました。内閣府の「国民生活に関する世論調査」1)でも、昭和54(1979)年以降は「物の豊かさ」よりも「心の豊かさ」を求める割合が多くなっています。日本は世界的に見ると、経済的に恵まれ、衛生・医療環境が整っているにもかかわらず、自ら死を選ぶ人が非常に多い国です。若者の自殺率の高さは非常に深刻で、15〜34歳の若い世代で死因の第1位が自殺となっているのは、先進国(G7)では日本のみです。精神疾患による患者数も大幅に増えており、「うつ病」は30年前に50万人程度だった患者数が、現在では120万人を超えています。また、最近では「発達障害」と診断される子どもも増えてきました。
本稿では、心療内科医/総合診療医としてプライマリ・ケアの現場でメンタルヘルスに携わっていた立場から、現代社会においてメンタルヘルスで着目したい事柄について、簡単にご紹介したいと思います。
【総論2】
精神科の診断を再考する—精神疾患の「力動的モデル」とは?
著者: 西依康
ページ範囲:P.958 - P.963
“素人診断(lay diagnosis)”の問題
我々は日常生活のなかで、“素人診断”することがある。それは隣人や同僚、あるいは新聞に載るような社会的人物に対してであったりする。専門家としてであっても、談話室や議事録が残らない検討会のような場所で、——人格障碍注1)、発達障碍などといった——ある種の素人診断をしていないだろうか? 診断名の体裁をとってはいても、直接の診察や厳密な臨床推論を経ていないという意味では、精神科医による素人診断もありうる注2)。
こうした素人診断はほとんどの場合、診断される当人に伝えられることはない。おそらくそれは、診断される当人よりも、診断する我々のための診断なのだ。診断するということは、それがなければ露わになるであろう不安を覆い隠し、それに対処する勇気を我々に引き起こす。そしてこの不安を覆い隠すという点にこそ、診断の最初の役目は求められるに違いない。だから現代精神医学体系の祖であるクレペリン(1856-1926)もまた、現代のような診断がなかった時代に、精神病院で最初に感じた不安を書き残している。体系づけられた学問と、それに裏打ちされた診断がなければ、混沌とした病理現象を前にして、医師は途方に暮れるだろう。
【各論1】
精神科で対応するのが困難な各科からの精神科紹介事例集
著者: 塚原美穂子
ページ範囲:P.964 - P.972
はじめに
筆者は精神科医であるが、精神科、総合診療科、東洋医学科の診療、また企業での精神保健相談、障害者施設での相談・就労支援などに携わってきており、立ち位置としては浅く広く、今いる場所でできることを何とか考えて行う、というものである。そのため、筆者の視点が一般的な精神科医のものと言えるか定かでないが、逆に「どのような人が来ても何とかする」、という点では、総合診療の先生方と通じるかもしれない。
以下は、筆者のやや古い経験からであるが、精神科と他科のより良い連携のために、普段あまり書かれないような視点から、精神科で対応するのが困難な5つの紹介事例について書いてみた。なお、各事例はプライバシー保護のため、いくつかのケースを混合したり細部を改変している。
【各論2】総合診療医から精神科医への“ぶっちゃけ”相談集
Q1 なんとなく精神疾患かな? でも、どこがどういうふうに違和感があるのか、うまく表現できないです。正常と異常の区別がよくわからないです。「なんとなく違和感がある」をどう表現し、どうアプローチしたらよいでしょうか?
著者: 今村弥生
ページ範囲:P.974 - P.977
正常と異常の境界、つまり、診察室で患者から伝わってくる「違和感」が、精神疾患か否かの判断は、われわれ精神科医にとっても悩ましい臨床課題である。われわれの手元にはDSM(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders、現在は第5版。詳細は他稿を参照)などの、精神科領域に広く伝播した診断基準があり、精神疾患の診断と、主に研究上の議論のうえでの共通言語としては大変有用であるものの、臨床場面で「ある人」にDSM-5を使用するとなると、まずここに書かれている症候学から、それはどういう症状か具体的なイメージを持って、かつ目の前の人が訴える、あるいは醸し出す所見はその症候と合致するのかどうかを、頭のなかで照合しなくてはならない。これは精神障碍当事者と、ある程度の回数を治療者として対面していないと、患者のほうを診断基準に当てはめてしまい、患者の困難さと診断がずれていたり、症状しか見ていない、つまりは重要な問題が隠れたままの診断につながりかねない。千差万別の当事者の症状、その元にある苦悩のなかには、DSMでは測りきれないものもあり、かつ、精神疾患と非精神疾患の間にはまり込んだ微妙な境界を判断するのは困難であるが、その境界を含めて見ることは、相手を全人的に診ることになるとも考える。
本稿では自験例を交え、精神疾患かもしれない“なんとなくの違和感”の表現と、そのアプローチについての回答を求めてみたい。
Q2 すでに精神科に通院中の患者さんを総合診療科で診察する時に留意すべきことを教えてください。特に、統合失調症の患者さんの併存疾患(糖尿病や心不全など)へのケアがあまりうまくいきません。療養指導や生活指導が難しいです…。
著者: 田村修
ページ範囲:P.978 - P.981
精神疾患患者、とりわけ統合失調症患者は、他科受診することを嫌うことも少なくありません。まずは総合診療科で継続的に診ていただけるだけでも、大変意味のあることです。
精神疾患患者の身体合併症は、ⓐ偶発的に併存した身体疾患、ⓑ精神疾患の病態(精神症状や行動)に由来する身体疾患、ⓒ向精神薬の影響や副作用に由来する身体疾患、ⓓ身体疾患に起因する精神症状、ⓔその他、精神疾患に付随するさまざまな身体的問題、の5つに類別されます。慢性疾患の多くはⓐ+ⓑ+ⓒと複合的な成因ですので、まずはその全体像の把握が重要です1,2)。
Q3 アルコール依存症だと思うのですが、本人にその自覚がありません。家族は困っているようです。どうしたらよいでしょうか?
著者: 小松知己
ページ範囲:P.982 - P.986
Case1
アルコール性肝障害、高血圧症と、家族トラブルが徐々に進行した例
患者:43歳、男性。
家族歴:父も大酒家(詳細不明)。
現病歴:職場の健診で毎年肝機能障害を指摘されており、今回はγ-GTPが300IU/L台に上昇して高血圧も悪化したため、産業保健室からの強い促しで精査のため当院受診。腹部超音波検査と血液検査で肝障害はアルコール性と確定、二次性高血圧も除外された。精査中に妻から外来窓口に相談があり、「実は、この数年は二日酔いで欠勤することが月に1〜3回ある。また休日に子どもたちと出かける約束を守れない。それを諫めて『酒量を減らすように』と言うと、怒って大声を出してモノを投げる」とのこと。暴力の危険度を詳しく聴取したうえで、スタッフから妻へ、本人受診時に同伴してもらうよう依頼。三者面談を行い、そのなかで「アルコール依存症だとは全く思わないが、高血圧の薬を増やしたくないし、月曜出勤時に身体がだるくて辛いのは何とかしたい。少しは酒が絡んではいると思う」という本人の発言を引き出して、アプローチを開始した。
Q4 いわゆるゴミ屋敷に住んでいる患者さんの訪問診療をすることになりました。介護スタッフの話によると、「こだわりの強い」利用者さんとのことです。どのようにアプローチしたらよいでしょうか?
著者: 岡﨑公彦
ページ範囲:P.987 - P.990
Case
認知機能低下からセルフネグレクトに陥った、いわゆるゴミ屋敷事例
患者:75歳、男性。単身生活。
現病歴:数年前、認知症疾患医療センターにてAlzheimer型認知症との診断を受け、投薬が開始された。1年前より生活上の混乱、無頓着さ、物忘れの増悪、物盗られ妄想が出現し、薬物調整等が行われたが、治療中断となっていた。
近隣からの連絡で、関わっていた民生委員から地域包括支援センターに連絡が入り、認知症初期集中支援チームが介入を開始した。当初は拒絶的で、特定のチーム員が物盗られ妄想の対象となったが、民生委員の仲介で徐々にチーム員を受け入れるようになり、介入から1カ月後、チーム医(筆者)も訪問した。
室内は尿臭が漂いコバエが舞い、窓にはヒビが入り、ゴミが山積みになり玄関からあふれていた。本人はやせが目立ち困惑した表情で「もうゲームオーバーだよ」「死んじゃうのが一番なんだ」と繰り返していた。日中は外で過ごして夜間は自宅に帰る生活で、パチンコで生活費の大半を浪費し、食費はほぼ残っていない状況であった。現状の変更を望まず、自宅での生活を希望し、受診や施設入所の提案に対しては強い口調で拒絶した。
治療を中断し、医療・介護サービスにつながっていない認知症の方のセルフネグレクト状態と判断し、❶生活保護の医療扶助を受けられるように整え、❷筆者が訪問診療を開始し、❸介護保険申請も行い、❹定期的に弁当が配達されるよう宅配弁当の契約を行った。❺ケアマネジャーを決めて、ヘルパーやデイサービスを導入し、❻本人と相談しながら徐々に部屋の片付けを行った。
その後も訪問診療を継続し、生活への不安は強いものの、デイサービスでは趣味の麻雀やカラオケを楽しんでいる。
Q5 職場の人間関係のストレスで、食欲が低下し、やる気がなくなってしまったとのことで、一応適応障害と診断して傾聴と対症療法を続けて、だいぶよくなったのですが、こういう方の職場復帰は、どういう時期に行ったらよいのでしょうか?
著者: 塚原美穂子
ページ範囲:P.991 - P.994
筆者は、主治医として患者の休職・復職を支援する立場と、企業での精神保健相談と休職・業務復帰の相談の両方を行ってきたが、主治医側と企業の産業医的な立場では取る立ち位置がやや異なる。本テーマは主治医側の対応についてであるが、本稿では筆者の経験を踏まえ、産業保健からの観点も織り交ぜて書いた。
Q6 外来の初診で「メンタルがやられて眠れないので薬が欲しい」という30代の男性がやってきました。どう考えたらよいでしょうか?
著者: 塚原美穂子
ページ範囲:P.995 - P.998
昨今は「メンタルの問題」「メンタルが病んだ」など、「メンタル」というワードが気軽に使われることが多く、精神科医としては精神・心理面に焦点が当たることは喜ばしいことと考えてはいるが、「メンタル」の意味するところはさまざまであり、当事者がどのような意味で使用しているかを今一度、考えてみる必要がある。
本タイトルの訴えには、「メンタルがやられている」「眠れない」「薬が欲しい」の3つの要素があり、互いに関連があるようでいて、実はそれぞれ独立した内容である。「メンタルがやられた→(そのため)眠れない→(だから)薬が欲しい」という困りごとに対し、患者自身のアセスメントが行われている。どれも主訴であるが、どれが困りごとの核心なのかについて医療者がアセスメントを行うには、その内訳を知る必要がある。
Q7 いわゆる困った人で、クレーマーっぽくて多弁で、診療に非常に時間がかかって困っています。どうしたらよいでしょうか?
著者: 田村修
ページ範囲:P.999 - P.1001
来るたびに難癖のような発言を一方的に聞かされる、言質を取られないよう腫れ物に触るような対応で神経が磨り減る、診療時間がありえないくらい長くなり他の患者への迷惑にもなる、うんざりしているのに他所へ行ってくれない…等々、どれも目に浮かぶような診療の光景です。いくつかの調査報告によれば、プライマリ・ケア診療場面の約15%は「困難な状況」に該当するとのことです。困難に立ち向かっている読者の皆さんに、まずは敬意を表します。
このような、医師にとって対応困難な状況(difficult clinical encounter)は、患者要因(patient characteristics)、医師要因(physician characteristics)、状況要因(situational issues)の3要素で構成されます1)。それぞれの代表的な内容を表1に示します。
Q8 他院精神科に通院している方で、外来にかぜ症状で来られたのですが、「今、精神科にかかっているけど、話をあまり聞いてくれず薬だけ出して終わりで、これではかかっていても意味がないと思う。こちらで薬を出してくれないか」とのことでした。精神科の処方薬も非常に多いことがあり、その場合対応が難しく、どうしたらよいのでしょうか?
著者: 西依康
ページ範囲:P.1002 - P.1006
他者を理解する
精神医学の仕事とは一般に、他者の内面について理解したり、それに共感したりすることに関わると思われがちである。しかし筆者としては、そうしたことは話半分に聞くのがちょうどいいと考えている。
Q9 なかなかよくならないメンタル症状の方を診るのはつらいです。つらいから精神科に紹介、というのもつらいです。メンタル症状の方を診る時の自分自身のコントロールの仕方を教えてください。
著者: 塚原美穂子
ページ範囲:P.1007 - P.1011
本テーマは、かかりつけ医、プライマリ・ケア医、非専門医がさまざまな理由で、「なかなかよくならないメンタル症状の人」の診療を続けざるをえない状況を想定して書いた。都市部から遠く医療資源が乏しい地などで、専門医へのアクセスに物理的距離があったり、本人が精神科受診に抵抗がある場合など、時にかかりつけ医や家庭医が診療を続けなければならない状況があると推察する。
しかし、専門医にとってもなかなかよくならない人の診療は、同じくつらいものである。米国での4,000名弱の大うつ病患者の治療と予後の関係を調査した2006年のSequenced Treatment Alternatives to Relieve Depression(STAR*D)報告によると1)、数種類の薬物療法や認知療法などを1年以上の期間をかけて行っても、大うつ病患者の1/3が標準的な治療に対して難治であった。なかなかよくならない人、一筋縄でいかない人は、多くの標準的な治療者にとっても同様に難しいものである。
【スペシャル・アーティクル】
ルフィのレジリエンスマンガから精神病理学を学ぶ
著者: 今村弥生
ページ範囲:P.1012 - P.1015
精神科医、漫画に出合う
上記のQ & Aの質問者は筆者である。当時、社会人大学院生だった筆者が受講した「臨床医学教室からの最新の話題について」の講義で、際立って私たち受講生にインパクトを残したのは、今村明先生(長崎大学病院地域連携児童思春期精神医学講座)による「最近話題の発達障害(注:当時の呼称)について」の講義だった。
「週刊少年ジャンプで連載中の大変人気が高い『ONE PIECE』という作品には、発達障碍の特性を持った登場人物が多く登場する。なかでも主人公のルフィ君は、ADHD(attention-deficit hyperactivity disorder:注意欠如・多動性障碍)の診断基準を満たすと考えます」
Editorial
メンタルヘルスの時代と「リアルワールド」 フリーアクセス
著者: 藤沼康樹 , 塚原美穂子
ページ範囲:P.943 - P.943
2019年の米国のシンガーソングライターであるビリー・アイリッシュの大ブレイクが引き金となって、若者のメンタルヘルスの問題が大きくクローズアップされた。彼女のメッセージは、つらいときは「つらい」と声を出して助けを求めよう、助けを求めることはあなたが弱いことを意味するわけでない、ということだった。また、英国の批評家マーク・フィッシャーは、その著書『資本主義リアリズム』1)で強調しているように、資本主義や新自由主義のオルタナティブが構想できない中で、自己実現や成長を強いられ、結果は自己責任とされてしまうことが、西欧諸国で若者の精神疾患の罹患率の増加に結びついているはずと主張した。そして、若者のメンタルヘルスの悪化こそ、これ以上に完成されたシステムはないとされる資本主義が実は穴だらけの、不完全な構造物であることの証明であると記し、話題となった。メンタルヘルスの問題は、わたしたちが生きているこの現代社会の現在と未来に、重要な議論を投げかけている。
本特集を組むにあたって、普段カルチャー、音楽、文学などについていつも新鮮な刺激をいただいている、精神科医・塚原先生の全面的な協力を得ることができた。総合診療や家庭医療におけるメンタルヘルス問題に造詣が深い共同編集(企画)者を得たことで、読み応えのあるよい特集になったと思う。
What's your diagnosis?[224]
真相は靄の中
著者: 中神太志
ページ範囲:P.946 - P.950
病歴
患者:36歳、女性
主訴:間欠的な発熱と咳嗽
現病歴:7週間前(11月下旬)、鼻汁が出たが数日で自然軽快した。5週間前、夕方より悪寒(戦慄はなし)と乾性咳嗽を伴って38℃台の発熱、倦怠感が出現したが、無治療で翌朝の起床時にはいずれも消失した。4週間前、3週間前、2週間前にも全く同様のエピソードがあり、4回も繰り返したために、発熱した翌日に近医を受診。LVFX(レボフロキサシン)1日500mg×4日を内服したところ、症状は再発しなくなったが、原因精査目的で紹介受診。食欲低下、体重減少、頭痛、眼・耳症状、喘鳴、呼吸困難、消化器症状、泌尿生殖器症状、皮疹、関節痛はない
既往歴:特記すべきものなし。薬物、食物へのアレルギー歴なし
薬剤歴:サプリメントを含め、常用薬なし
社会歴:3年前より築10年程の中古マンションに夫と小学生の子ども2人と同居。ペットは飼っていない。専業主婦であったが、2カ月前からバイク通勤で額縁梱包のパートを始めた
【エッセイ】アスクレピオスの杖—想い出の診療録・16
医師として、かけがえのない財産
著者: 佐野良仁
ページ範囲:P.951 - P.951
本連載は、毎月替わる著者が、これまでの診療で心に残る患者さんとの出会いや、人生を変えた出来事を、エッセイにまとめてお届けします。
『19番目のカルテ』を読んで答える! あなたの“ドクターG度”検定&深読み解説・5
自分だけのワザ—(『19番目のカルテ—徳重晃の問診』第5話より)
著者: 山中克郎
ページ範囲:P.1017 - P.1019
本連載は総合診療ビギナーの皆さんに、総合診療の楽しさと奥深さを解説することが目的です。漫画『19番目のカルテ』のエピソードを深読みすることにより、総合診療医がどのような根拠に基づいて診断しているのかを理解していただければ幸いです。本連載は『総合診療』×『19番目のカルテ』のコラボ企画で、本誌編集委員の徳田安春先生・山中克郎先生が隔月で作問&解説します!
患者さんには言えない!? 医者のコッソリ養生法・3
不養生の医者、風邪予防のヒケツを伝授される
著者: 須田万勢
ページ範囲:P.1020 - P.1025
前回、医神アスクレピオスの導きで養生を駆使し、すんでのところで風邪をひかずに乗り切った貝原先生。ここぞとばかりに東洋医学的な風邪の原因を説かれ、生活の不摂生を正された。それだけでは許してもらえず、医神による「エビデンスのある風邪予防」のレクチャーが始まった。
研修医Issy&指導医Hiro&Dr.Sudoのとびだせフィジカル! 聴診音付・8
心臓のフィジカル Part4
著者: 石井大太 , 中野弘康 , 須藤博
ページ範囲:P.1030 - P.1034
ここは、とある病院。研修医Issyは指導医Hiroのもと、今日も忙しい日々の病棟業務に追われているのであった。
“コミュ力”増強!「医療文書」書きカタログ・14
—まるく収まる伝え方!—他院の処方で生じた「薬剤有害反応」の情報共有
著者: 天野雅之
ページ範囲:P.1038 - P.1042
今月の文書
診療情報提供書
セッティング:診療所→診療所への診療依頼
患者:86歳、男性。以前から当院(慢性心不全、陳旧性心筋梗塞)と他院(糖尿病、脂質異常症)の両方に定期通院している。6週間前の他院受診時に、血圧高値のためアムロジピンが追加された。下腿浮腫が出現したため、2週間前に他院を再診し、利尿薬が追加された。1週間前に当院の定期受診があり、「薬剤性浮腫」が疑われたため精査した。
【登場人物】
桜井:総合診療科1年目専攻医。現在は地域の診療所で研修中。
飛鳥:桜井の指導医。総合診療専門研修プログラムの責任者として、定期的に面談している。
名井:東部診療所の非常勤医師。卒後8年目の内科医。
オール沖縄!カンファレンス|レジデントの対応と指導医の考えVer.2.0・56
その肺炎、COVID-19ですか?—診断の早期閉鎖を回避せよ!
著者: 酒井達也 , 徳田安春
ページ範囲:P.1044 - P.1047
CASE
患者:78歳、女性。
主訴:発熱、呼吸困難感。
現病歴:来院2週間前にCOVID-19流行地域に滞在する孫と接触があった。来院4日前より発熱および家事などの労作で、軽度呼吸困難感を自覚した。来院2日前に近医を受診し、感冒と診断され対症療法となった。しかしその後も症状が遷延し、呼吸困難感が継続するため、来院当日再度近医を受診した。胸部単純CTで両側のすりガラス陰影を認めたため、COVID-19が疑われ、同日当院に紹介となった。
ROS:倦怠感あり、味覚障害・嗅覚障害なし、筋肉痛・関節痛なし、起坐呼吸なし、夜間呼吸困難感なし、血痰なし。
既往歴:高血圧症、脂質異常症、甲状腺摘出後。喫煙歴なし、飲酒歴なし。
社会歴:夫、息子と3人暮らし。無職。
内服歴:レボチロキシン100μg 1日1回、アムロジピン5mg 1日1回、プラバスタチン5mg 1日1回、エチゾラム0.5mg 1日1回。
Dr.上田剛士のエビデンス実践レクチャー!医学と日常の狭間で|患者さんからの素朴な質問にどう答える?・17
飲酒すると翌朝むくみます
著者: 上田剛士
ページ範囲:P.1048 - P.1051
患者さんからのふとした質問に答えられないことはないでしょうか? 素朴な疑問ほど回答が難しいものはありませんが、新たな気づきをもたらす良問も多いのではないでしょうか? 本連載では素朴な疑問に、文献的根拠を提示しながらお答えします!
“JOY”of the World!|ロールモデル百花繚乱・19
出会いに導かれ「性差医療」から「研究開発」まで
著者: 片井みゆき
ページ範囲:P.1052 - P.1056
私は現在、内分泌代謝内科医として「性差医学・医療」の臨床研究に携わっています。医学生の頃から臨床と研究の両立、海外留学、国際医療の夢を思い描いてきましたが、医師になり6年目には育児と仕事の両立の壁に突き当たりました。しかし、それが原点となり、数々の貴重な出会いに導かれ、その後の「留学」「翻訳出版」「性差医療」「国際医療」「大型臨床研究」へとつながってきました(表1)。登山でも、険しい崖の直登は困難でも、樹林帯や尾根づたいの登頂ルートもあります。女性医師のキャリアも同様、希望をもち一歩一歩進めば、夢に辿り着けるのではないかと思います。
55歳からの家庭医療 Season 2|明日から地域で働く技術とエビデンス・39
—医師像の変容と総合診療—Transforming into an Alternative Doctor
著者: 藤沼康樹
ページ範囲:P.1058 - P.1061
海外では通じない日本の英語表記
「総合診療」。この英語表記を、私は「Generalist Medicine」が適切であると考えている。日本では「General Medicine」や「General Practice」と表現されているが、海外では前者は「総合内科」あるいは「内科」、後者は「診療所基盤型家庭医療」を意味する。この2つの英語がどちらも「総合診療」と呼ばれることは、日本以外の国では理解されない。むしろ、コンテキストの誤解に基づくコミュニケーション不全が生まれる可能性があり、要注意である。
「Generalist Medicine」という表記を部門名として正式に採用している場所はないようだが、何人かの海外の家庭医の友人の反応をみると、語感は十分に伝わると思う。「Generalist Medicine」は、病院の総合診療科、プライマリ・ケア診療所など、診療の場の多様性を特徴とする“日本の総合診療”を、なんとか表現するための造語である。
【臨床小説】後悔しない医者|あの日できなかった決断・第17話
将来を悩む医者
著者: 國松淳和
ページ範囲:P.1063 - P.1069
前回までのあらすじ 今月のナゾ
新緑輝く初夏が過ぎ、季節は夏に移り変わる頃、黒野のチームにも新たなローテーターがやってくる。対照的なキャラクターの2人の初期研修医だ。その1人の教育係を担当することになった後期研修医・栗塚は、自分の初期研修医時代とはあまりに違う彼女の反応にとまどうことになる。一方、自分のキャリアパスに悩む初期研修医・西畑も思うところがあって…。
医師のあり方にはさまざまある。「臨床医」ばかりが、その進路ではない。どんな医師になるか。「初期研修」は将来の方向性を左右する重要な期間だ。2004年からの「臨床研修制度」に加え、最近では「働き方改革」なども、臨床教育の現場に影響を与えている。いかにして臨床医になるか? いかにして臨床医を育てるか?
投稿 GM Clinical Pictures
巨峰の窒息解除後の呼吸障害
著者: 金井宏明 , 西山秀 , 佐藤広樹 , 武井義親
ページ範囲:P.1035 - P.1036
CASE
患者:5歳、男児。
現病歴:巨峰を喉に詰まらせ、自分で取り出そうとしたが排出できず、母も試みたが不可能だった。その後、顔色不良になり暴れ出して転倒し、再度自分で口に手を入れ取り出すことができたが、数秒間の意識消失を認めた。回復後、血性痰あり、頻回の咳嗽と呼吸苦が出現したため救急搬送された。
身体所見:GCS(Glasgow Coma Scale)E4V5M6、体温37.9℃、脈拍数120回/分、呼吸数36回/分、SpO2 88〜91%(室内気)、両肺エア入り不良、crackles聴取、陥没呼吸あり。
検査所見:WBC 8,940/μL、CRP 0.17mg/dL、静脈血液ガス分析:PH 7.337、PCO2 41.7mmHg、HCO3 21.8mmol/L
画像所見:胸部単純X線:両肺野に気管支透亮像を伴うびまん性浸潤影(図1)、胸部単純CT:両側肺門部を中心としたすりガラス陰影(図2)。
#総合診療
#今月の特集関連本❶ フリーアクセス
ページ範囲:P.963 - P.963
#今月の特集関連本❷ フリーアクセス
ページ範囲:P.973 - P.973
#今月の特集関連本❸ フリーアクセス
ページ範囲:P.990 - P.990
#今月の特集関連本❹ フリーアクセス
ページ範囲:P.1006 - P.1006
#今月の特集関連本❺ フリーアクセス
ページ範囲:P.1011 - P.1011
#今月の特集関連本❻ フリーアクセス
ページ範囲:P.1015 - P.1015
#今月の連載関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.1064 - P.1064
#医学書院の新刊 フリーアクセス
ページ範囲:P.1027 - P.1027
#書評:大人のトラウマを診るということ—こころの病の背景にある傷みに気づく フリーアクセス
著者: 福田正人
ページ範囲:P.1026 - P.1026
「200頁以上の症例集部分は退屈するのでは」、そうした予想はすぐに裏切られた。「あぁ、やはりこう考えていいんだ」、読みながら繰り返しそう思い、「どのくらいの精神科医が同じように考えるだろうか」、読み終えた今そう考えている——。
こう書いたのは、6年前の『大人の発達障害を診るということ』(医学書院、2015)の書評であった。今、同じことを、トラウマについて感じている。「トラウマをそこまで拾い上げて診るのだ」と感じた箇所がいくつもあった。それは、「日々の臨床は、発達障害やトラウマを考えずには行えないのではないかというのが実感である」という、編者らの思いに基づいている。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.944 - P.945
読者アンケート
ページ範囲:P.1028 - P.1028
『総合診療』編集方針 フリーアクセス
ページ範囲:P.1070 - P.1070
1991年に創刊した弊誌は、2015年に『JIM』より『総合診療』に誌名を変更いたしました。その後も高齢化はさらに進み、社会構造や価値観、さらなる科学技術の進歩など、日本の医療を取り巻く状況は刻々と変化し続けています。地域医療の真価が問われ、ジェネラルに診ることがいっそう求められる時代となり、ますます「総合診療」への期待が高まってきました。これまで以上に多岐にわたる知識・技術、そして思想・価値観の共有が必要とされています。そこで弊誌は、さらなる誌面の充実を図るべく、2017年にリニューアルをいたしました。本誌は、今後も下記の「編集方針」のもと、既存の価値にとらわれることなく、また診療現場からの要請に応え、読者ならびに執筆者のみなさまとともに、日本の総合診療の新たな未来を切り拓いていく所存です。
2018年1月 『総合診療』編集委員会
『総合診療』バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.1072 - P.1073
お得な年間購読のご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.1073 - P.1074
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.1075 - P.1076
基本情報
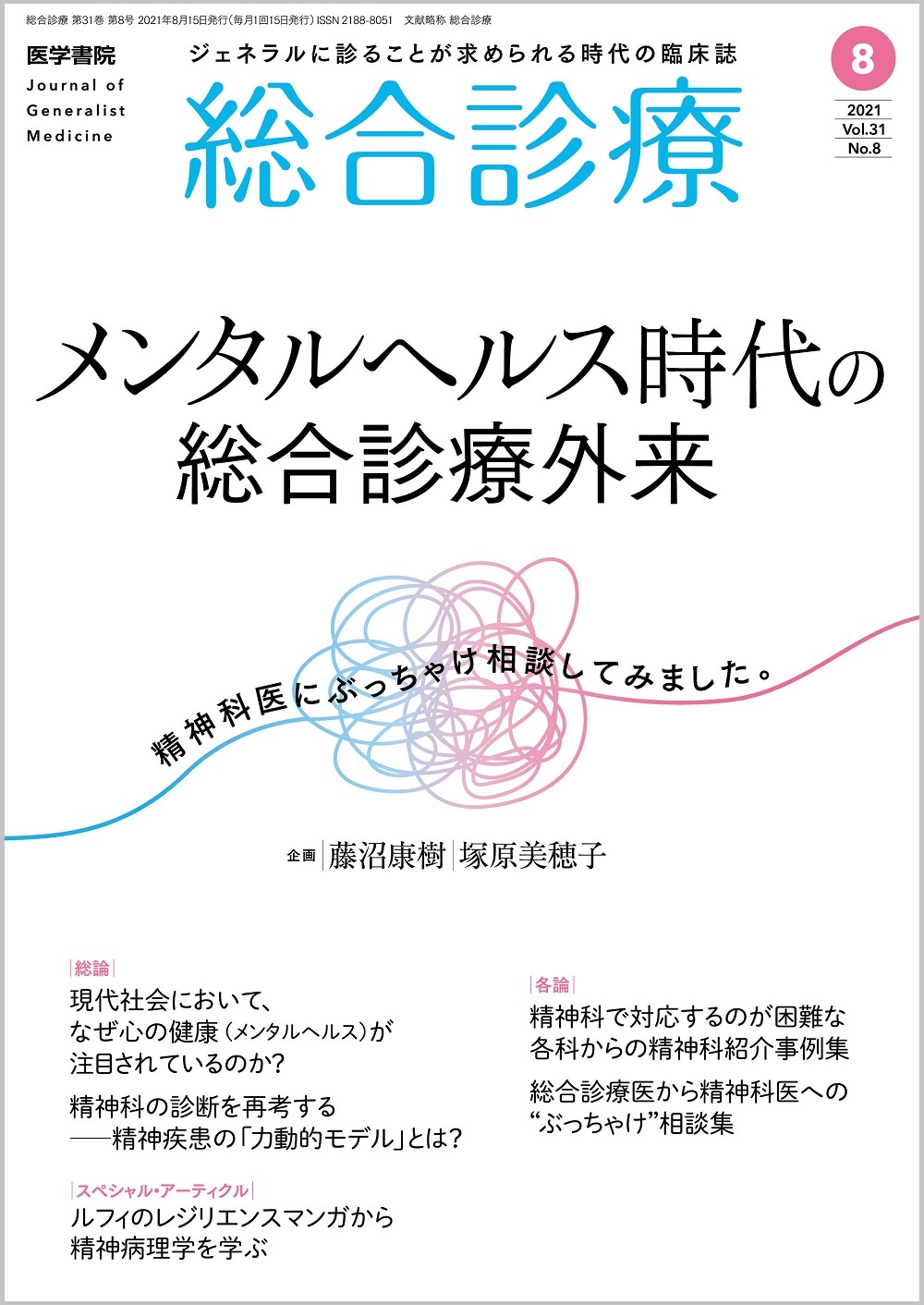
バックナンバー
34巻12号(2024年12月発行)
特集 妊婦・褥婦が外来に来たらUpdate—症状対応からワクチン・プラネタリーヘルスまで
34巻11号(2024年11月発行)
特集 電子カルテとベッドサイドの壁を打ち破る!—患者情報の「言語化」への挑戦
34巻10号(2024年10月発行)
特集 化かしが得意なカメレオンな疾患を捕まえろ!—よくある騙され方のゲシュタルト
34巻9号(2024年9月発行)
特集 今伝えたいクリニカル・パール—つくり方、使い方、活かし方
34巻8号(2024年8月発行)
特集 ストーン・ウォーズ 果てしなき“石”と医師との闘い
34巻7号(2024年7月発行)
特集 どうする!? 健診異常—これってホントに異常なの? どう説明する?
34巻6号(2024年6月発行)
特集 医師のウェルビーイング
34巻5号(2024年5月発行)
特集 —優柔不断にサヨウナラ!—あなたの「臨床判断」を高めるケーススタディ11選
34巻4号(2024年4月発行)
特集 困ったときの漢方—この症状に役立ちます!
34巻3号(2024年3月発行)
特集 —え、ウソ!実は◯◯だった!?—“コモンディジーズ”の診断ピットフォール
34巻2号(2024年2月発行)
特集 日常診療で出合う筋骨格疾患—脳神経内科と整形外科からのアプローチ
34巻1号(2024年1月発行)
特集 —“体験型”臨床クイズで習得する!—フィジカル診断エクセレンス
33巻12号(2023年12月発行)
特集 海の外へ渡る航行者を診る—アウトバウンドにまつわるetc.
33巻11号(2023年11月発行)
特集 —続・総合診療外来に“実装”したい—最新エビデンスMy Best 3
33巻10号(2023年10月発行)
特集 ○×クイズ110問!日常診療アップグレード—Choosing WiselyとHigh Value Careを学ぼう
33巻9号(2023年9月発行)
特集 ジェネラリストのための「発達障害(神経発達症)」入門
33巻8号(2023年8月発行)
特集 都市のプライマリ・ケア—「見えにくい」を「見えやすく」
33巻7号(2023年7月発行)
特集 “消去法”で考え直す「抗菌薬選択」のセオリー—広域に考え、狭域に始める
33巻6号(2023年6月発行)
特集 知っておくべき!モノクロな薬たち(注:モノクローナル抗体の話ですよ〜)
33巻5号(2023年5月発行)
特集 —疾患別“イルネススクリプト”で学ぶ—「腹痛診療」を磨き上げる22症例
33巻4号(2023年4月発行)
特集 救急対応ドリル—外来から在宅までの60問!
33巻3号(2023年3月発行)
特集 —自信がもてるようになる!—エビデンスに基づく「糖尿病診療」大全—新薬からトピックスまで
33巻2号(2023年2月発行)
特集 しびれQ&A—ビビッとシビれるクリニカルパール付き!
33巻1号(2023年1月発行)
特集 COVID-19パンデミック 振り返りと将来への備え
32巻12号(2022年12月発行)
特集 レクチャーの達人—とっておきの生ライブ付き!
32巻11号(2022年11月発行)
特集 不定愁訴にしない“MUS”診療—病態からマネジメントまで
32巻10号(2022年10月発行)
特集 日常診療に潜む「処方カスケード」—その症状、薬のせいではないですか?
32巻9号(2022年9月発行)
特集 総合診療・地域医療スキルアップドリル—こっそり学べる“特講ビデオ”つき!
32巻8号(2022年8月発行)
特集 こんなところも!“ちょいあて”エコー—POCUSお役立ちTips!
32巻7号(2022年7月発行)
特集 —どうせやせない!? やせなきゃいけない??苦手克服!—「肥満」との向き合い方講座
32巻6号(2022年6月発行)
特集 総合診療外来に“実装”したい最新エビデンス—My Best 3
32巻5号(2022年5月発行)
特集 「診断エラー」を科学する!—セッティング別 陥りやすい疾患・状況
32巻4号(2022年4月発行)
特集 えっ、これも!? 知っておきたい! 意外なアレルギー疾患
32巻3号(2022年3月発行)
特集 AI時代の医師のクリニカル・スキル—君は生き延びることができるか?
32巻2号(2022年2月発行)
特集 —withコロナ—かぜ診療の心得アップデート
32巻1号(2022年1月発行)
特集 実地医家が楽しく学ぶ 「熱」「炎症」、そして「免疫」—街場の免疫学・炎症学
31巻12号(2021年12月発行)
特集 “血が出た!”ときのリアル・アプローチ—そんな判断しちゃダメよ!
31巻11号(2021年11月発行)
特集 Q&Aで深める「むくみ診断」—正攻法も!一発診断も!外来も!病棟も!
31巻10号(2021年10月発行)
特集 医師の働き方改革—システムとマインドセットを変えよう!
31巻9号(2021年9月発行)
特集 「検査」のニューノーマル2021—この検査はもう古い? あの新検査はやるべき?
31巻8号(2021年8月発行)
特集 メンタルヘルス時代の総合診療外来—精神科医にぶっちゃけ相談してみました。
31巻7号(2021年7月発行)
特集 新時代の「在宅医療」—先進的プラクティスと最新テクノロジー
31巻6号(2021年6月発行)
特集 この診断で決まり!High Yieldな症候たち—見逃すな!キラリと光るその病歴&所見
31巻5号(2021年5月発行)
特集 臨床医のための 進化するアウトプット—学術論文からオンライン勉強会、SNSまで
31巻4号(2021年4月発行)
特集 消化器診療“虎の巻”—あなたの切実なギモンにズバリ答えます!
31巻3号(2021年3月発行)
特集 ライフステージでみる女性診療at a glance!—よくあるプロブレムを網羅しピンポイントで答えます。
31巻2号(2021年2月発行)
特集 肺炎診療のピットフォール—COVID-19から肺炎ミミックまで
31巻1号(2021年1月発行)
特別増大特集 新型コロナウイルス・パンデミック—今こそ知っておきたいこと、そして考えるべき未来
30巻12号(2020年12月発行)
特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き) Part 2
30巻11号(2020年11月発行)
特集 診断に役立つ! 教育で使える! フィジカル・エポニム!—身体所見に名を残すレジェンドたちの技と思考
30巻10号(2020年10月発行)
特集 —ポリファーマシーを回避する—エビデンスに基づく非薬物療法のススメ
30巻9号(2020年9月発行)
特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【感染症・内分泌・整形外科 編】
30巻8号(2020年8月発行)
特集 マイナーエマージェンシー門外放出—知っておくと役立つ! テクニック集
30巻7号(2020年7月発行)
特集 その倦怠感、単なる「疲れ」じゃないですよ!—筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群とミミック
30巻6号(2020年6月発行)
特集 下降期慢性疾患患者の“具合”をよくする—ジェネラリストだからできること!
30巻5号(2020年5月発行)
特集 誌上Journal Club—私を変えた激アツ論文
30巻4号(2020年4月発行)
特集 大便強ドリル—便秘・下痢・腹痛・消化器疾患に強くなる41問!
30巻3号(2020年3月発行)
特集 これではアカンで!こどもの診療—ハマりがちな11のピットフォール
30巻2号(2020年2月発行)
特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【循環器・消化器・神経疾患編】
30巻1号(2020年1月発行)
特集 総合診療医の“若手ロールモデル”を紹介します!—私たちはどう生きるか
29巻12号(2019年12月発行)
特集 困っている“あなた”に届く 認知症診療
29巻11号(2019年11月発行)
特集 臨床写真図鑑 レアな疾患編—見逃したくない疾患のコモンな所見
29巻10号(2019年10月発行)
特集 教えて!医師のためのビジネス・スキル
29巻9号(2019年9月発行)
特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き)
29巻8号(2019年8月発行)
特集 —ノーモア見逃し—日常の検査と画像に潜むピットフォール
29巻7号(2019年7月発行)
特集 リウマチ・膠原病ミミック症例帖—“膠原病っぽくみえてしまう疾患たち”にだまされない!
29巻6号(2019年6月発行)
特集 皮膚科診療エクササイズ—1枚の写真から
29巻5号(2019年5月発行)
特集 一般外来で診断できたら「えっへん!」な疾患38
29巻4号(2019年4月発行)
特集 “ナゾ”の痛み診療ストラテジー|OPQRSTで読み解く
29巻3号(2019年3月発行)
特集 —あなたのギモンに答えます!—循環器診療のハードルを下げるQ&A31
29巻2号(2019年2月発行)
特集 意外な中毒、思わぬ依存、知っておきたい副作用—一般外来で!OTCも処方薬も!
29巻1号(2019年1月発行)
特集 教えて検索!—膨大な医学情報を吟味・整理するスキル
28巻12号(2018年12月発行)
特集 こんなときこそ漢方を!
28巻11号(2018年11月発行)
特集 日本一マジメな「おしっこドリル」—今これだけは押さえておきたい腎・泌尿器のモンダイ
28巻10号(2018年10月発行)
特集 クリニカル・パールPremium!—憧れのカリスマ医師はかく語りき
28巻9号(2018年9月発行)
特集 オンコ・ジェネラリスト—「がん」に強い総合診療医をめざして
28巻8号(2018年8月発行)
特集 80歳からの診療スタンダードUp to Date—Silver Standard
28巻7号(2018年7月発行)
特集 この薬だけは押さえておきたい! 総合診療医のためのSpecialist Drug 40
28巻6号(2018年6月発行)
特集 聴診・触診×エコーで診断推論!—Point-of-Care超音波(POCUS)の底力
28巻5号(2018年5月発行)
特集 “一発診断”トレーニング問題集—懸賞論文「GM Clinical Pictures」大賞発表!
28巻4号(2018年4月発行)
特集 感染症外来診療「賢医の選択」—検査・経口薬・ワクチンをどう使えばいいんですか?
28巻3号(2018年3月発行)
特集 糖尿病のリアル—現場の「困った!」にとことん答えます。
28巻2号(2018年2月発行)
特集 頭痛患者で頭が痛いんです!
28巻1号(2018年1月発行)
特集 シン・フィジカル改革宣言!—私の“神技”伝授します。
27巻12号(2017年12月発行)
特集 小児診療“苦手”克服!!—劇的Before & After
27巻11号(2017年11月発行)
特集 今そこにある、ファミリー・バイオレンス|Violence and Health
27巻10号(2017年10月発行)
特集 めまいがするんです!─特別付録Web動画付
27巻9号(2017年9月発行)
特集 うつより多い「不安」の診かた—患者も医師も安らぎたい
27巻8号(2017年8月発行)
特集 見逃しやすい内分泌疾患─このキーワード、この所見で診断する!
27巻7号(2017年7月発行)
特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 3 カリスマ編
27巻6号(2017年6月発行)
特集 「地域を診る医者」最強の養成法!
27巻5号(2017年5月発行)
特集 コミュニケーションを処方する—ユマニチュードもオープンダイアローグも入ってます!
27巻4号(2017年4月発行)
特集 病歴と診察で診断できない発熱!—その謎の賢い解き方を伝授します。
27巻3号(2017年3月発行)
特集 これがホントに必要な薬40—総合診療医の外来自家薬籠
27巻2号(2017年2月発行)
特集 The総合診療ベーシックス—白熱!「総合診療フェスin OKINAWA」ライブ・レクチャー! 一挙公開 フィジカル動画付!
27巻1号(2017年1月発行)
特集 総合診療の“夜明け”—キーマンが語り尽くした「来し方、行く末」
26巻12号(2016年12月発行)
特集 これでパッチリ! 眼の健康問題
26巻11号(2016年11月発行)
特集 続・しびれるんです!
26巻10号(2016年10月発行)
特集 内科診療を劇的に変える“まとめ”の達人
26巻9号(2016年9月発行)
特集 症状・症候別 エコーを使った診断推論─Point-of-Care超音波
26巻8号(2016年8月発行)
特集 The 初診外来
26巻7号(2016年7月発行)
特集 感染症ケアバンドル・チェックリスト
26巻6号(2016年6月発行)
特集 “賢い処方”と“ナゾ処方”
26巻5号(2016年5月発行)
特集 しびれるんです!─知っておくべきシビレル疾患
26巻4号(2016年4月発行)
特集 ケースとクイズで総ざらい! 街場の2型糖尿病治療
26巻3号(2016年3月発行)
特集 こんな時は漢方でしょう!
26巻2号(2016年2月発行)
特集 フィジカル改革宣言! ──診断からフォローアップまで
26巻1号(2016年1月発行)
特集 妊婦・褥婦が一般外来に来たら─エマージェンシー&コモンプロブレム
25巻12号(2015年12月発行)
特集 外来で「複数の疾患」をもつ患者を診る─マルチモビディティの時代のプライマリ・ケア
25巻11号(2015年11月発行)
特集 レアだけど重要な「痛み」の原因─システム1診断学
25巻10号(2015年10月発行)
特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 2
25巻9号(2015年9月発行)
特集 診断ピットフォール10選─こんな疾患,見逃していませんか?
25巻8号(2015年8月発行)
特集 健診データで困ったら─こんな検査結果を持ってこられたら
25巻7号(2015年7月発行)
特集 ここを知りたい!頭部外傷初期対応・慢性期ケア
25巻6号(2015年6月発行)
特集 高齢者救急の落とし穴─紹介する時,される時
25巻5号(2015年5月発行)
特集 咳を聴きとり,咳を止める
25巻4号(2015年4月発行)
特集 関節が痛いんです!─コモンからレアものまでの診断と治療
25巻3号(2015年3月発行)
特集 神経難病ケアのコペルニクス的転回
25巻2号(2015年2月発行)
特集 総合医のためのスポーツ医学ベーシックス
25巻1号(2015年1月発行)
特集 動悸・息切れ─ヤバい病気の見つけ方 そして見つからなかった時の対処法
