ポリファーマシーが問題になっている昨今、単に多疾患併存のために処方薬が多くなっているわけではなく、薬剤による副作用を、新たに生じた医学的問題と誤解して、この症状に対してさらなる処方がなされるという「処方カスケード(カスケード:雪崩現象)」が問題になっています(下図)。処方カスケードによって生じる健康影響としては、副作用に対して新たに開始された薬(処方薬や市販薬)がさらなる副作用を引き起こしたり、副作用と診断できていれば避けられる不要な検査・医療デバイスが導入される可能性があります。これに伴い医療費の負担も増え、その他にも患者経験としてQOLの低下も生じます。多疾患併存の患者で処方薬が増えることは、相互作用による薬剤の効果の増強や減弱、あるいは転倒やせん妄、認知機能低下といった問題を悪化させる可能性もあり、非常に重要な問題です。
本特集では、日常診療でよくみられる「処方カスケード」のパターンを紹介し、これを認識することによって読者の皆さんが「処方カスケード」に気づくきっかけとなり、薬剤副作用の回避のために薬剤の中止・減量や変更、その後のモニタリングといった対応ができるようになることを期待しています。
雑誌目次
総合診療32巻10号
2022年10月発行
雑誌目次
特集 日常診療に潜む「処方カスケード」—その症状、薬のせいではないですか?
扉 フリーアクセス
著者: 鈴木智晴 , 徳田安春
ページ範囲:P.1186 - P.1187
今月の「めざせ! 総合診療専門医!」問題
ページ範囲:P.1247 - P.1247
本問題集は、今月の特集のご執筆者に、執筆テーマに関連して「総合診療専門医なら知っておいてほしい!」「自分ならこんな試験問題をつくりたい!」という内容を自由に作成していただいたものです。力試し問題に、チャレンジしてみてください。
【総論】
「処方カスケード」とは?
著者: 鈴木智晴
ページ範囲:P.1188 - P.1191
処方カスケードとは、「ポリファーマシーの一形態で、薬剤有害事象が新たな症状や疾患と誤解され、この有害事象を打ち消すために新たな処方が開始されること」とされ1)、現在は新たな処方だけではなく、検査や治療、処方薬に加えて市販薬の開始につながったものを広義の「処方カスケード」と呼ぶ2,3)。さらに処方カスケードの新たな定義・形式として、「適切な処方カスケード」「不適切な処方カスケード」という考え方もあり4)、いわば副作用を認識しながら、その副作用の契機になった薬剤のベネフィットが副作用およびそれを打ち消すための薬剤の処方に勝る場合に、「適切な処方カスケード」という概念も生まれている。しかし、「適切か、不適切か」と断ずるのではなく、減量によって1)、あるいは同効薬への変更によって、この二項対立に陥らずに対処することが望ましい5)。減薬を行えば、ある程度の有効性を担保しつつも、副作用を低減し、この副作用を打ち消すための処方を減らすということはできるかもしれない。あるいは同効薬で、副作用のない/少ない薬剤への変更ができないかを検討することはできる。もちろん、やむをえない、あるいは明らかなベネフィットのある「適切な」処方カスケードも存在する。処方カスケードを発見する確固たる方法はないが、処方カスケードを発見することによって、不要な薬剤、不要な検査、不要なコンサルテーション、不要な入院6)、不要な害を防ぐことができるのである。
【各論】
❶抑うつ—抗うつ薬を使う前に、こちらの薬をチェックせよ!
著者: 松田能宣
ページ範囲:P.1192 - P.1195
わが国におけるうつ病の頻度は高く、厚生労働省の患者調査では2008年には704,000人の患者がいるとされている1)。ただし、うつ病患者の受診率は低いことから、実際はより多くの患者がいることが予想される。また、うつ病では身体症状を伴うことも多く、最初は精神科や心療内科を受診するのではなく、身体科を受診することが多い2)。そのため、どの科においてもうつ病患者を診る機会があると考えられる。ただし、抑うつの原因はすべてうつ病とは限らず、そのうつ病以外の原因に対処することよって、患者の抑うつが改善するかもしれない。そのため、抑うつをきたす、もしくは抑うつと類似した症状の原因となりうる身体疾患および薬剤について知っておくことは非常に重要である。
❷不眠—眠れない理由に薬も
著者: 今村弥生
ページ範囲:P.1196 - P.1198
現代社会の3人に2人の成人が睡眠について何らかの問題を抱えていると言われており1)、「不眠」の訴えはプライマリ・ケア診療のなかでも高頻度に遭遇し、その治療のためベンゾジアゼピン受容体作動薬(BZ系薬剤)を含む、何らかの向精神薬を処方する機会は少なくない。しかし、鑑別なき不眠への治療戦略による、不要な薬物投与から次々と副作用が発生する“処方カスケード”に留意する必要がある。
❸認知機能低下—認知症=Alzheimer病とは限らない、薬も考えよ!
著者: 関岡叙衣 , 天野雅之
ページ範囲:P.1199 - P.1202
「認知機能低下」と「認知症」とは明確に区別する必要がある。「認知機能低下」は症候であり、さまざまな病態により引き起こされる。認知機能低下と言われた患者のうち10%は医薬品によるものであったという報告もあり1)、薬剤歴の確認は特に重要だ。一方で、「認知症」は脳疾患から成る症候群である。ほとんどの例は臨床的に診断され、Alzheimer型認知症、脳血管性認知症、Lewy小体型認知症、前頭側頭型認知症などの病名がつけられる。抗認知症薬の効果は限定的であるから2,3)、できるだけ丁寧に診断して病型を捉えたうえで、抗認知症薬を使用する場合は、他の薬剤と同様に、慎重な経過観察と効果判定を要する。
❹味覚障害—味覚障害はコロナとは限らない
著者: 笹木晋
ページ範囲:P.1203 - P.1204
COVID-19の大きな流行を経験しているが、そのなかで注目された症状が味覚障害である。COVID-19では、鼻閉がないのに味覚障害が起こることが特徴とされる。COVID-19の味覚障害の場合、何かを食べた、または飲んだ時に味覚が変わったことに気づくといった具合に、急性発症で、咽頭痛や咳などの呼吸器症状を伴うので、あまり他疾患との鑑別に悩む場面は少ないと思われる。しかし、COVID-19で味覚障害が起こることが医療関係者以外にも広く知れ渡るようになったため、COVID-19以外の病態で味覚障害が起こった患者が「COVID-19ではないか」と不安になり、外来を受診するようになった。本稿では、味覚障害の原因として重要な鑑別である薬剤について述べる。
❺咳嗽—ACE阻害薬だけではない、薬剤性咳嗽の原因
著者: 倉原優
ページ範囲:P.1205 - P.1208
慢性咳嗽を診療する際、プライマリ・ケアでは咳喘息やアトピー咳嗽などが鑑別疾患に挙がることが多いが、通常の検査で診断がつかないものを難治性慢性咳嗽と呼び、ベースラインにあるcough hypersensitivity syndrome(CHS)が関与しているという見解が主流である。CHSというのは、あらゆる刺激において咳嗽に対して過敏になる病態のことで、疼痛に対するアロディニアと類似する概念である。難治性慢性咳嗽の原因のなかには回避可能なものがあり、その代表的なものが薬剤である。本稿では、咳嗽の原因となる薬剤について述べたい。
❻不整脈—命にかかわる薬とは?
著者: 大石悠太
ページ範囲:P.1209 - P.1212
突然死を引き起こす可能性のあるものの1つに「QT延長症候群」がある。QT延長症候群とは、心電図にQT延長を認め、torsade de pointes(TdP)と呼ばれる特徴的な心室頻拍(ventricular tachycardia : VT)や、心室細動(ventricular fibrillation : VF)等の致死的不整脈を生じて、突然死を引き起こす。発症原因によって先天性と2次性(薬剤、電解質異常など)に分類されるが、本稿では主に2次性(特に薬剤性)について言及する。
2次性QT延長症候群の最大のポイントは後述するが、原因となる薬剤が非常に多岐にわたるという点である。抗不整脈薬、抗うつ薬、抗がん薬などのように専門医が主に処方する薬剤から、抗菌薬、抗アレルギー薬、制吐薬など、多くの医師が処方するものまで実に幅広い1)。抗不整脈薬服用によるTdPの発生率は2.0〜8.8%とされ、抗不整脈薬以外の非循環器系薬物である向精神薬、抗菌薬、抗真菌薬、抗アレルギー薬、消化器用薬などによるQT延長の発生率は、年間1人/1万人〜1人/10万人と見積もられている2)。薬剤によるQT延長症候群、TdPは、要因となっている薬剤の減量や変更により回避できる可能性が高く、QT間隔を延長させる薬剤を把握しておくことは非常に重要である。
❼浮腫—見逃しが多い薬剤性浮腫
著者: 松山拓 , 矢吹拓
ページ範囲:P.1213 - P.1215
浮腫は間質液量の増加により生じる腫脹のことである。外来受診患者において、頻度の高い症状の1つであり、生命予後には直結しないかもしれないが、QOLを低下させる要因となりうる。浮腫の代表的な原因として、局所の炎症による血管透過性亢進や、心臓・腎臓・肝臓・甲状腺疾患などによるものと共に、薬剤性浮腫も考慮する。多くの薬剤がさまざまな機序で浮腫を引き起こすことが知られているが、実際には薬剤性浮腫と気づかれず、安易に対症療法的な利尿薬処方がなされ、処方カスケードの一因となることも知られている。たとえばカナダの人口ベースのコホート研究1)においても、カルシウムチャネル拮抗薬を新規に処方された患者が浮腫を引き起こし、ループ利尿薬が処方される頻度は、他の降圧薬と比べて60%以上高くなったと報告されている。
薬剤の減量、変更、または中止により、浮腫の改善が見込まれる可能性もあるため、浮腫の原因として薬剤性浮腫の可能性を検討し、適切に評価することが重要である。
❽食欲不振—痩せ薬リスト?
著者: 濱田治
ページ範囲:P.1216 - P.1218
すべての薬剤に副作用を起こす可能性があり、外来で処方された薬剤の3〜5%に副作用が出現すると報告されている1)。皮疹など特異的な副作用もあれば、食欲不振のように非特異的なものもある。特に高齢者は複数の基礎疾患があり、多数の薬剤を併用していることが多く、副作用を生じやすい。食欲不振の診療において、薬剤性を鑑別の1つに挙げることは非常に重要である。
❾嘔気—吐き気はクスリのリスク
著者: 中川龍太郎 , 北和也
ページ範囲:P.1219 - P.1221
嘔気(nausea)とは、胃の内容物を口から吐き出したいという切迫した不快な感覚を咽頭部や心窩部に感じる状態である。原因としては薬剤の副作用が最も多く、通常は使用開始後早期に生じる1)。このため、嘔気・嘔吐を呈する患者を診察する際は、内服薬の聴取が重要であることは当然ながら、どの薬剤が嘔気の原因となりうるのかを知っておく必要がある。薬剤性に限らないが、嘔吐反射に伝達する経路があるため嘔気・嘔吐が出現しており、この経路を同定したうえで、適切なアプローチ(原因薬剤の中止・制吐薬の選択)が求められる。
❿GERD、胸焼け—内視鏡検査の前にチェックしておくべき薬
著者: 原田拓
ページ範囲:P.1222 - P.1224
胃食道逆流症(gastroesophageal reflux disease:GERD)は非常に頻度の高い疾患である。プロトンポンプ阻害薬(proton pump inhibitor:PPI)を出せばよい、というような疾患ではない。というのも、非心原性の胸痛の原因として最も頻度が高い疾患であること1)、長期のPPI投与は骨粗鬆症、骨折、低Mg血症、慢性腎臓病、間質性腎炎、C.difficile感染症などの有害事象のリスクになるため2)、漫然と制酸薬を処方することなく、期間を決めた内服と非薬物療法の併用が鍵になる疾患だからである。そしてGERDの増悪因子に一部の薬剤が関連していることは、GERDの適切な管理において重要な知識となる。本稿ではそのあたりを中心に述べたい。
⓫頻尿—トイレが近いのはこの薬を飲んでからでは?
著者: 児玉泰介
ページ範囲:P.1225 - P.1227
「最近トイレが近いんです」。そのような訴えの患者が受診したら、内科医の皆さんはどう考えますか?「水分の摂り過ぎでは?」と多飲の背景も考慮せず安易に答えを求めたり、「それだけ尿が出るということは、多尿をきたす疾患が背景にあるに違いない!!」といきなり膨大な量の検査をオーダーしたりするかもしれません。頻尿はすぐに命に関わる主訴ではないため、診療する医師のモチベーションによって対応はさまざまでしょう。しかし、「トイレが近い」ことに困って外来を受診した患者の悩みを何とか解決したいと考えるのは、皆さん同じではないでしょうか? ましてや「よかれ」と思って処方していた“あの薬”が頻尿の原因だった、なんてことにならないようにしたいものです。
⓬下痢—下痢の原因にARBも!
著者: 中野弘康
ページ範囲:P.1228 - P.1231
日常診療において下痢はcommonである。“下痢を扱わない診療科は存在しない”と言うといささか大げさに聞こえるが、下痢を経験したことのない読者諸氏はいないであろう。下痢は医学的に便重量の増加>200〜250gと定義されるが、実際には軟便・便の液状化や排便回数の増多(>3行/日)をもって下痢と捉えることが多い。患者の訴える下痢を切り取るための1st stepは、下痢の発症がいつからか(つまりはonset)を明らかにすることである。すなわち発症後2週以内の下痢は“急性下痢”と分類され、その多くはself-limitingに軽快する感染性腸炎が該当するため、日常診療で鑑別に困ることは少ない。一方で、4週以上続く下痢は“慢性下痢”と分類し、非感染性病態がほとんどで、鑑別疾患も多い。具体的には、過敏性腸症候群(IBS)、炎症性腸疾患、吸収不良症候群などを想起するが、実臨床では医原性下痢も少なからず経験する。慢性下痢の患者を診たら、まずは患者が内服している薬剤をすべて洗い出し、下痢をきたす薬剤の整理から始めるとよい。教科書的には、NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)、PPI(プロトンポンプ阻害薬)が下痢をきたす悪名高き薬剤として知られているが、実は高血圧の治療薬としてわが国で頻用されるARB(アンジオテンシン受容体拮抗薬)も下痢をきたしてしまう。よかれと思って処方した薬で、患者が苦しむのは避けたいところである。ぜひ、この機会に薬剤性下痢に関して整理してみたい。
⓭痙攣—痛み止めでも痙攣することあり
著者: 林祐一 , 西田承平 , 鈴木昭夫
ページ範囲:P.1232 - P.1234
痙攣は、発作的な筋の不随意な収縮を指す言葉で、その起源は、大脳、脊髄、末梢神経、筋などさまざまであるが、本稿では、大脳由来のもののみに焦点を当てて薬剤性の痙攣について概説する。
⓮振戦、パーキンソニズム—抗精神病薬だけではない薬剤性振戦
著者: 辻浩史
ページ範囲:P.1235 - P.1238
振戦は、身体の一部がリズミカルに振動する不随意運動の一種である1)。患者は「手足がふるえる」、「振るえて字が書けない」、「コップの水をこぼしてしまう」などと訴え、日常生活に支障をきたすこともある。振戦をきたす疾患と言えば「Parkinson病」をまず考えるかもしれないが、甲状腺疾患など鑑別疾患は多岐にわたる(表1)。もちろん本テーマである薬剤性振戦も鑑別に挙げる必要がある(表2)。一方で、現在の国際的なParkinson病の診断基準では、運動緩慢が必須の症状であり、さらに筋強剛もしくは静止時振戦のどちらか1つが見られることがパーキンソニズムと定義されている2)。この定義に従うと、パーキンソニズムでは、必ずしも振戦が出現するとは限らないことにも注意する必要がある。振戦を診療する時は、背景病理を正しく診断・理解し、適切な治療を行うことが重要である。
⓯転倒—転倒リスクを高める薬剤は鎮静薬だけではない〜薬剤の種類と予防、中止のタイミング
著者: 藤井達也
ページ範囲:P.1239 - P.1241
2025年には国民の4人に1人が75歳以上の“超高齢社会”になると予想されている1)。加齢に伴い、脳血管疾患2)、認知症3)、フレイル、サルコペニア4)の罹患が増加することが見込まれ、なかでも転倒は、健康寿命に大きな影響を与えるイベントである。転倒で骨折すれば、入院や手術、それに伴う内科的合併症治療、骨粗鬆症の評価治療、リハビリテーションといったカスケードとなり、膨大な医療資源が必要となる。そのため、転倒予防を目的としたさまざまな介入が必要だと、複数のガイドラインで述べられている5)。しかしながら、介入をするうえで最も考えるべきは、なぜ転倒したのか、その「理由」である。本稿では転倒の原因とリスク、なかでも薬剤に注目して解説する。
⓰高尿酸血症・痛風発作—その痛風発作、薬のせいではないですか?
著者: 鈴木智晴
ページ範囲:P.1242 - P.1244
高尿酸血症の頻度は高く、わが国の全人口の男性では20%、女性では5%にみられる。痛風発作は高尿酸血症のある30代以上の男性の1%で発症している。高尿酸血症のある人口の80%に高血圧や脂質異常症、糖尿病や肥満などが併存すると言われており、食事や飲酒、ソフトドリンクの摂取などが高尿酸血症のリスクになることからも“生活習慣病”という側面があり1)、薬剤による高尿酸血症は意識されにくい。しかし、利尿薬を使用している患者の3%で痛風発作がみられ2)、実際には稀な病態ではない。薬剤による高尿酸血症は要因となっている薬剤の減量や変更により回避できる可能性もあり、高尿酸血症および痛風の診療において、薬剤性の原因を鑑別しておくことは非常に重要である。
⓱ビタミンB12欠乏—制酸薬でビタミン欠乏?
著者: 金昇赫 , 綿貫聡
ページ範囲:P.1245 - P.1246
貧血の定義を男性はヘモグロビン13g/dL未満、女性は12g/dL未満とした場合、高齢者における貧血の有病率は17%であり、高齢者にとってはコモンな状態であると言える。高齢者の貧血の原因には、悪性腫瘍や慢性炎症、感染症などの重篤な疾患が背景にあることがある一方で、複数の薬剤を内服している場合には、薬剤に起因する造血障害も鑑別となる。特に一般外来で日常的に用いられる薬剤でも、貧血の原因になりうることには注意が必要である。
Editorial
「処方カスケード」のクリニカルパールズ フリーアクセス
著者: 鈴木智晴 , 徳田安春
ページ範囲:P.1185 - P.1185
本特集はポリファーマシーの一形態である「処方カスケード」について特集しました。処方カスケードに着目したのは、院内の「ポリファーマシーカンファレンス」という、薬剤師と医師が集まり、患者さんの薬剤を最適化するために相談する定例会議がきっかけでした。カンファレンスでは処方カスケードが見つかることが多く、常に問題意識を持っていました。同時に、介入を行う意義も大きいと考え、今回処方カスケードを取り上げた次第です。
本特集では錚々たる著者の先生方にご寄稿を依頼しました。ご執筆の先生方のお原稿に共通していたことは、プロブレムに対する鑑別診断を列挙するという、診療のエッセンスを大切にすることと、処方した薬に責任を持ち、自分の処方を含め厳しく見直すメタ認知の重要性でした。
ゲストライブ〜Improvisation〜・19
なぜ僕らは現場で「教育」するのか?—“どうする!?サロン”始めます。
著者: 佐田竜一 , 木村武司 , 長野広之
ページ範囲:P.1167 - P.1175
臨床医なら誰しも、多かれ少なかれ日々「教育」を行っているのではないか。教育研修機関の医師や研修病院の指導医であれば、なおさらだ。一方で、臨床医が教育について体系的に学ぶ機会はあまりない。もとより臨床教育の悩みは尽きないが、働き方改革やハラスメントの問題、コロナ禍による制限もあり、いっそう教育の提供が難しくなってきている。そうしたなか、どう教えるか? 何のために教えるのか? それぞれの立場で“現場教育”に悪戦苦闘してきた3人の指導医が、原点に立ち戻って語り合った。(編集室)
What's your diagnosis?[238]
膝カックン!—“押されたんじゃなくて引っ張られたの”
著者: 酒見英太 , 岩下靖史
ページ範囲:P.1180 - P.1184
病歴
患者:16歳、女性
主訴:易転倒性
現病歴:生来健康な高校1年生。偏頭痛でたまにロキソニン®を頓服するが常用薬はなく、アレルギーもない。吹奏楽部でクラリネットを吹いている。京都出身の両親と弟との4人暮らし。ペットは飼っていない。月経は順調で、最終正常月経は4日前。経血に凝血塊なし。偏食はしていない。
当科受診の7カ月前に駅の階段で2度転んだことはあるが、特に外傷も負わないですみ、以後同様なエピソードはなかった。4カ月前の学校検診で脊柱側弯を指摘されたため、脊椎外科受診を勧められた。8週間前にヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンを接種されたが、特に問題はなかった。5週間前に当院脊椎外科を受診。側弯は軽度であり介入不要とされたが、上肢<下肢のDTR(深部腱反射)亢進が認められたため、全脊椎MRIが撮影され、脊椎管が全般に拡大しているように思われたが、脊髄自体に異常は認められなかった。
約1カ月前より転倒しやすくなり、17日前からは歩行中に頻回に膝折れがして前方に転び、膝をすりむくことが多くなったため、再度脊椎外科外来を再診したところ救急外来に回され、血液、脳および頸胸髄MRIの検査を受け、そこから精査を求めて3日後に内科を紹介受診した。母親はHPVワクチンの副作用を心配している。
ROS(review of systems):易転倒性はあるが、どこも痛くなく、体調が悪いとも感じていない。悪寒・発熱・寝汗、頭重、口腔咽頭症状、上下気道症状、呼吸困難、消化器・泌尿生殖器症状、皮膚・関節症状、複視、めまい・聴覚症状、構音・嚥下障害、嗅覚・味覚障害、四肢の異常感覚・感覚鈍麻、立ちくらみ、膀胱・直腸障害はない。
【エッセイ】アスクレピオスの杖—想い出の診療録・30
田舎で医師が定着するには?
著者: 仲田和正
ページ範囲:P.1249 - P.1249
本連載は、毎月替わる著者が、これまでの診療で心に残る患者さんとの出会いや、人生を変えた出来事を、エッセイにまとめてお届けします。
高齢者診療スピードアップ塾|効率も質も高める超・時短術・10
「腎機能障害」でのCT、単純か? 造影か?
著者: 増井伸高
ページ範囲:P.1256 - P.1258
腎機能障害がある高齢者では、「単純CT」と「造影CT」の選択に迷うことは多いです。単純CT後に「やっぱり造影が必要!」となり、再検査すれば「20分」ほど余計に時間がかかります。一方、全例で造影CT検査とするのも、検査時間が「10分」ほど長くなり、造影剤腎症のリスクも増え、得策とは言えません。適切な造影CTの選択こそ、時短診療のカギとなります。今回は、その取捨選択について考えてみましょう。
オール沖縄!カンファレンス|レジデントの対応と指導医の考えVer.2.0・69
左手が使えない!
著者: 照屋翔二郎 , 杉田周一 , 本永英治 , 徳田安春
ページ範囲:P.1259 - P.1263
CASE
患者:16歳、女性(高校生)。
主訴:左上肢の異常感覚と動かしづらさ。
現病歴:来院1年前から左手第5指の違和感を自覚し、来院9カ月前からは左手第5指が動かしづらくなり、楽器が上手く吹けなくなった。来院7カ月前からは左手の第4指や第3指まで症状が広がった。A病院を受診してビタミンB12製剤の服用が開始されたが、症状は改善しなかった。来院2カ月前に旅行先でB病院を受診して「尺骨神経麻痺の疑い」と判断され、地元での精査を勧められた。来院1カ月前から左頸部の「ジンジンするような」感覚が出てきたためA病院を再診し、精査目的に当院整形外科を受診した。整形外科で精査を継続する予定であったが、内科的疾患の可能性も考慮され、当科へ紹介となった。
既往歴:特記事項なし。
アレルギー:指摘なし。 家族歴:特記事項なし。
生活歴:楽器を演奏している。小児期に成長発達の遅れを指摘されたことはない。学校の体育の成績も大きな問題はない。
患者さんには言えない!? 医者のコッソリ養生法・14
翌日に疲れを残さない、ぐっすり「睡眠」の養生❹—日中にすべきこと編
著者: 須田万勢
ページ範囲:P.1265 - P.1269
“プチ不健康”を放置してきたツケで弱っていた貝原先生。突然現れた医神アスクレピオス(自称ピオちゃん)に半ば強制的に弟子入りさせられ、養生で健康を取り戻す方法をしぶしぶ学ぶうち、身体も心も少しずつ変わってきた。「風邪」「肩こり」「肥満」「お酒」に続き、ちゃんと疲れがとれる「睡眠」の方法を伝授されることに。前回は「夜寝る前にすべきこと」を教わるうち、寝落ちしてしまった貝原先生だったが…。
Dr.上田剛士のエビデンス実践レクチャー!医学と日常の狭間で|患者さんからの素朴な質問にどう答える?・31
眼に良いブルー、眼に悪いブルー
著者: 上田剛士
ページ範囲:P.1270 - P.1272
患者さんからのふとした質問に答えられないことはないでしょうか? 素朴な疑問ほど回答が難しいものはありませんが、新たな気づきをもたらす良問も多いのではないでしょうか? 本連載では素朴な疑問に、文献的根拠を提示しながらお答えします!
【臨床小説—第二部】後悔しない医者|今と未来をつなぐもの・第30話
自分を信じる医者
著者: 國松淳和
ページ範囲:P.1276 - P.1282
前回までのあらすじ 今月のナゾ
ある日の金曜、向後チーム定例のカンファレンスで、左座から気になる外来症例が共有された。患者は16歳・男性で高校1年生。頭ケ島白浜病院がある五島の出身だが、この春、長崎市内の県下有数の進学校に入学した。しかし4月下旬から、体がだるくて朝起きられず、頭痛もあり、今は学校に行けなくなっている。中学時代は、3年時には登校前の腹痛や下痢こそ時折あったが、文武両道で活動的なリーダー的存在だった。複数の医療機関を受診するも改善せず、数カ月にわたるつかみどころのない症状を前に、左座の診療も手探り状態になっている。右井は起立性調整障害の可能性を指摘したが…。
不登校。この問題は一筋縄では解決しない。身体症状を伴うことも多く、総合診療外来や一般内科を受診することも少なくない。思春期は小児科診療との間にあり、身体も心も激変していく時だ。小児科医あるいは精神科医ではなく「内科医」として、思春期の不登校にどうアプローチすることができるだろう?
投稿 GM Report
専攻医から見た新専門医制度における総合診療専攻医の育成
著者: 大塚勇輝 , 小比賀美香子 , 大塚文男
ページ範囲:P.1274 - P.1275
日本専門医機構が2014年に発足し、19番目の基本領域専門医として「総合診療」を掲げ1)、2018年より専攻医育成に取り組み始めて4年が経過した。その第1期生が対象となる専門医試験が開催され、新制度下での名実共に新しい専門医が誕生したところである。
総合診療専門医制度が発足した当初は、当事者である専攻医や興味を持つ若手医師から、専門医機構の体制不備や専門医制度そのものの未熟さへの批判的意見も多かったが、この数年間で多くの改革がなされてきたように我々は思う。専攻医向けの説明会が定期的に開催されるようになり、専門医機構と専攻医の橋渡しをする形で、研修医・専攻医支援部会が設置された。それまでブラックボックスに近かった専門医機構内部の議論についても、議事録がインターネット上で公開され、透明性がある程度担保されるようになり、当然のことではあるが研修修了や専門医認定などに関する各種要件や、通称J-GOALと呼ばれるオンライン研修手帳などの研修に必要な細部についても調整がなされた。これまで諸専攻医・指導医の不満と不安の種となっていた“事務局と全く連絡が取れない”という問題についても、現在は概ね解消されたと我々は考えている。専門医機構のウェブサイトとは別に、総合診療専門医検討委員会専用ページも開設され2)、「Q&A」などを通じた専攻医への情報提供も、以前よりは充実してきたと、専攻医である筆頭著者自身も感じている。
#総合診療
#今月の特集関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.1195 - P.1195
#今月の特集関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.1202 - P.1202
#今月の特集関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.1212 - P.1212
#今月の特集関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.1218 - P.1218
#今月の特集関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.1241 - P.1241
#今月の特集関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.1252 - P.1252
#今月の連載関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.1176 - P.1176
#今月の連載関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.1253 - P.1253
#今月の連載関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.1258 - P.1258
#今月の連載関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.1277 - P.1277
#医学書院の新刊 フリーアクセス
ページ範囲:P.1253 - P.1253
#書評:—チーフレジデント直伝!—デキる指導医になる70の方法—研修医教育・マネジメント・リーダーシップ・評価法の極意 フリーアクセス
著者: 小杉俊介
ページ範囲:P.1254 - P.1254
「指導医」と聞くと、「自分なんかまだ指導医とは言えないし」と思われる若手医師も多いと思います。しかし、研修医1年目であっても学生が実習に来ることもあるし、研修医2年目は1年目から気軽に相談を受けることは日常茶飯事だと思います。このように若手医師も、いろいろなシチュエーションで実は「指導(教育)」をしています。
#書評:—ジェネラリストための—内科診断キーフレーズ フリーアクセス
著者: 佐田竜一
ページ範囲:P.1255 - P.1255
臨床現場では、患者さんの問題を整理することが難しいことがしばしばある。特に昨今は、超高齢社会の急激な深化に伴い、「他疾患併存」が当たり前の世の中である。このような状況下における「診断の複雑性」を解決するために、臨床推論に関するさまざまな良書が生まれている。本書も、その1つに並ぶであろう、診断方略のエッセンスを凝縮した書籍である。
本書では、患者がもつ臨床問題のうち最も疾患特異性の高い問題点を「キーフレーズ」という言葉で表現し、そこから鑑別疾患を発想・整理することを目的としている。われわれは臨床推論を進める際、しばしば表11,2)のようなキーワードのタイプから整理を進めることが多い。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.1178 - P.1179
『総合診療』編集方針 フリーアクセス
ページ範囲:P.1250 - P.1250
1991年に創刊した弊誌は、2015年に『JIM』より『総合診療』に誌名を変更いたしました。その後も高齢化はさらに進み、社会構造や価値観、さらなる科学技術の進歩など、日本の医療を取り巻く状況は刻々と変化し続けています。地域医療の真価が問われ、ジェネラルに診ることがいっそう求められる時代となり、ますます「総合診療」への期待が高まってきました。これまで以上に多岐にわたる知識・技術、そして思想・価値観の共有が必要とされています。そこで弊誌は、さらなる誌面の充実を図るべく、2017年にリニューアルをいたしました。本誌は、今後も下記の「編集方針」のもと、既存の価値にとらわれることなく、また診療現場からの要請に応え、読者ならびに執筆者のみなさまとともに、日本の総合診療の新たな未来を切り拓いていく所存です。
2018年1月 『総合診療』編集委員会
読者アンケート
ページ範囲:P.1251 - P.1251
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.1283 - P.1284
『総合診療』バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.1284 - P.1285
お得な年間購読のご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.1285 - P.1285
基本情報
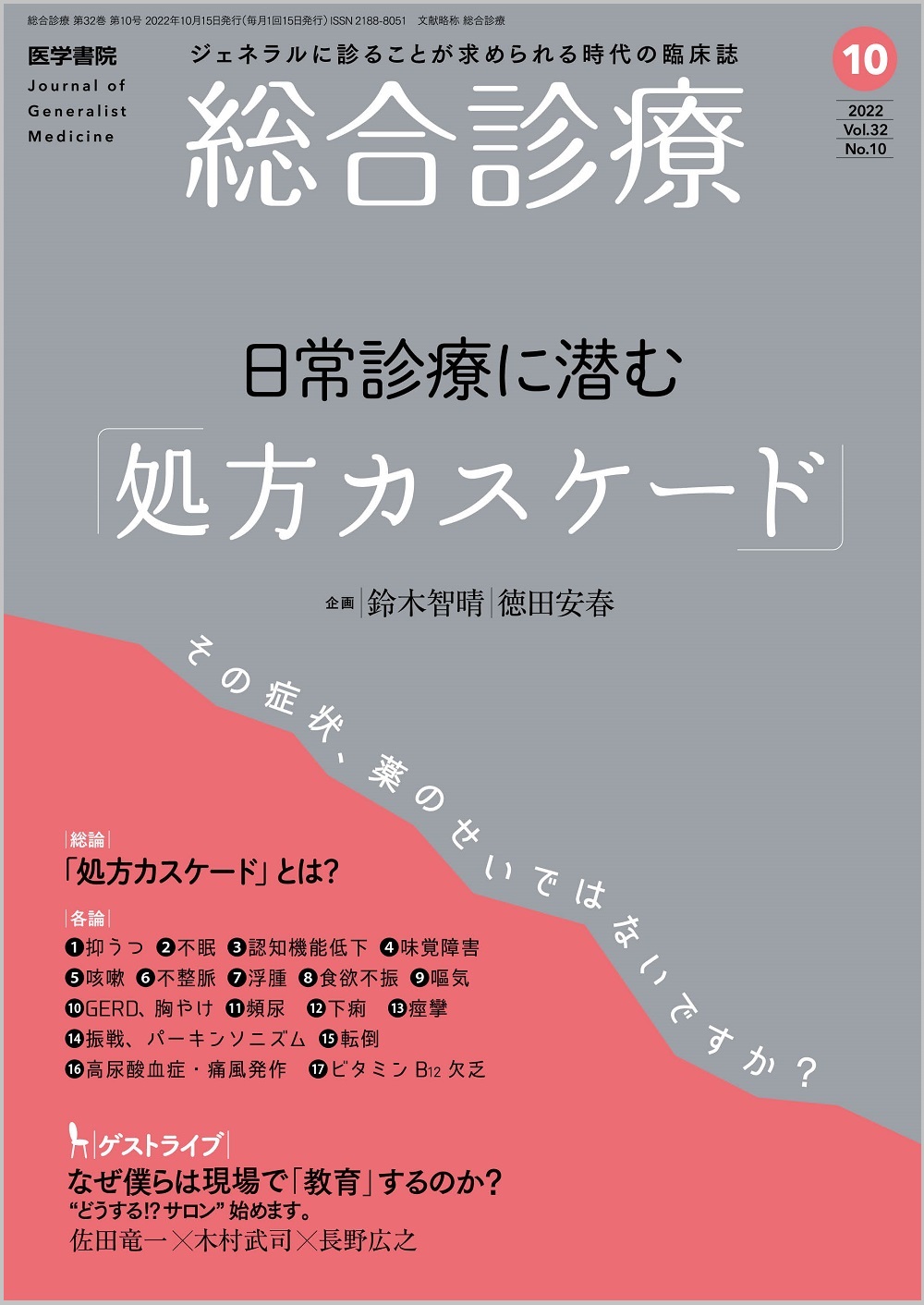
バックナンバー
34巻12号(2024年12月発行)
特集 妊婦・褥婦が外来に来たらUpdate—症状対応からワクチン・プラネタリーヘルスまで
34巻11号(2024年11月発行)
特集 電子カルテとベッドサイドの壁を打ち破る!—患者情報の「言語化」への挑戦
34巻10号(2024年10月発行)
特集 化かしが得意なカメレオンな疾患を捕まえろ!—よくある騙され方のゲシュタルト
34巻9号(2024年9月発行)
特集 今伝えたいクリニカル・パール—つくり方、使い方、活かし方
34巻8号(2024年8月発行)
特集 ストーン・ウォーズ 果てしなき“石”と医師との闘い
34巻7号(2024年7月発行)
特集 どうする!? 健診異常—これってホントに異常なの? どう説明する?
34巻6号(2024年6月発行)
特集 医師のウェルビーイング
34巻5号(2024年5月発行)
特集 —優柔不断にサヨウナラ!—あなたの「臨床判断」を高めるケーススタディ11選
34巻4号(2024年4月発行)
特集 困ったときの漢方—この症状に役立ちます!
34巻3号(2024年3月発行)
特集 —え、ウソ!実は◯◯だった!?—“コモンディジーズ”の診断ピットフォール
34巻2号(2024年2月発行)
特集 日常診療で出合う筋骨格疾患—脳神経内科と整形外科からのアプローチ
34巻1号(2024年1月発行)
特集 —“体験型”臨床クイズで習得する!—フィジカル診断エクセレンス
33巻12号(2023年12月発行)
特集 海の外へ渡る航行者を診る—アウトバウンドにまつわるetc.
33巻11号(2023年11月発行)
特集 —続・総合診療外来に“実装”したい—最新エビデンスMy Best 3
33巻10号(2023年10月発行)
特集 ○×クイズ110問!日常診療アップグレード—Choosing WiselyとHigh Value Careを学ぼう
33巻9号(2023年9月発行)
特集 ジェネラリストのための「発達障害(神経発達症)」入門
33巻8号(2023年8月発行)
特集 都市のプライマリ・ケア—「見えにくい」を「見えやすく」
33巻7号(2023年7月発行)
特集 “消去法”で考え直す「抗菌薬選択」のセオリー—広域に考え、狭域に始める
33巻6号(2023年6月発行)
特集 知っておくべき!モノクロな薬たち(注:モノクローナル抗体の話ですよ〜)
33巻5号(2023年5月発行)
特集 —疾患別“イルネススクリプト”で学ぶ—「腹痛診療」を磨き上げる22症例
33巻4号(2023年4月発行)
特集 救急対応ドリル—外来から在宅までの60問!
33巻3号(2023年3月発行)
特集 —自信がもてるようになる!—エビデンスに基づく「糖尿病診療」大全—新薬からトピックスまで
33巻2号(2023年2月発行)
特集 しびれQ&A—ビビッとシビれるクリニカルパール付き!
33巻1号(2023年1月発行)
特集 COVID-19パンデミック 振り返りと将来への備え
32巻12号(2022年12月発行)
特集 レクチャーの達人—とっておきの生ライブ付き!
32巻11号(2022年11月発行)
特集 不定愁訴にしない“MUS”診療—病態からマネジメントまで
32巻10号(2022年10月発行)
特集 日常診療に潜む「処方カスケード」—その症状、薬のせいではないですか?
32巻9号(2022年9月発行)
特集 総合診療・地域医療スキルアップドリル—こっそり学べる“特講ビデオ”つき!
32巻8号(2022年8月発行)
特集 こんなところも!“ちょいあて”エコー—POCUSお役立ちTips!
32巻7号(2022年7月発行)
特集 —どうせやせない!? やせなきゃいけない??苦手克服!—「肥満」との向き合い方講座
32巻6号(2022年6月発行)
特集 総合診療外来に“実装”したい最新エビデンス—My Best 3
32巻5号(2022年5月発行)
特集 「診断エラー」を科学する!—セッティング別 陥りやすい疾患・状況
32巻4号(2022年4月発行)
特集 えっ、これも!? 知っておきたい! 意外なアレルギー疾患
32巻3号(2022年3月発行)
特集 AI時代の医師のクリニカル・スキル—君は生き延びることができるか?
32巻2号(2022年2月発行)
特集 —withコロナ—かぜ診療の心得アップデート
32巻1号(2022年1月発行)
特集 実地医家が楽しく学ぶ 「熱」「炎症」、そして「免疫」—街場の免疫学・炎症学
31巻12号(2021年12月発行)
特集 “血が出た!”ときのリアル・アプローチ—そんな判断しちゃダメよ!
31巻11号(2021年11月発行)
特集 Q&Aで深める「むくみ診断」—正攻法も!一発診断も!外来も!病棟も!
31巻10号(2021年10月発行)
特集 医師の働き方改革—システムとマインドセットを変えよう!
31巻9号(2021年9月発行)
特集 「検査」のニューノーマル2021—この検査はもう古い? あの新検査はやるべき?
31巻8号(2021年8月発行)
特集 メンタルヘルス時代の総合診療外来—精神科医にぶっちゃけ相談してみました。
31巻7号(2021年7月発行)
特集 新時代の「在宅医療」—先進的プラクティスと最新テクノロジー
31巻6号(2021年6月発行)
特集 この診断で決まり!High Yieldな症候たち—見逃すな!キラリと光るその病歴&所見
31巻5号(2021年5月発行)
特集 臨床医のための 進化するアウトプット—学術論文からオンライン勉強会、SNSまで
31巻4号(2021年4月発行)
特集 消化器診療“虎の巻”—あなたの切実なギモンにズバリ答えます!
31巻3号(2021年3月発行)
特集 ライフステージでみる女性診療at a glance!—よくあるプロブレムを網羅しピンポイントで答えます。
31巻2号(2021年2月発行)
特集 肺炎診療のピットフォール—COVID-19から肺炎ミミックまで
31巻1号(2021年1月発行)
特別増大特集 新型コロナウイルス・パンデミック—今こそ知っておきたいこと、そして考えるべき未来
30巻12号(2020年12月発行)
特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き) Part 2
30巻11号(2020年11月発行)
特集 診断に役立つ! 教育で使える! フィジカル・エポニム!—身体所見に名を残すレジェンドたちの技と思考
30巻10号(2020年10月発行)
特集 —ポリファーマシーを回避する—エビデンスに基づく非薬物療法のススメ
30巻9号(2020年9月発行)
特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【感染症・内分泌・整形外科 編】
30巻8号(2020年8月発行)
特集 マイナーエマージェンシー門外放出—知っておくと役立つ! テクニック集
30巻7号(2020年7月発行)
特集 その倦怠感、単なる「疲れ」じゃないですよ!—筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群とミミック
30巻6号(2020年6月発行)
特集 下降期慢性疾患患者の“具合”をよくする—ジェネラリストだからできること!
30巻5号(2020年5月発行)
特集 誌上Journal Club—私を変えた激アツ論文
30巻4号(2020年4月発行)
特集 大便強ドリル—便秘・下痢・腹痛・消化器疾患に強くなる41問!
30巻3号(2020年3月発行)
特集 これではアカンで!こどもの診療—ハマりがちな11のピットフォール
30巻2号(2020年2月発行)
特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【循環器・消化器・神経疾患編】
30巻1号(2020年1月発行)
特集 総合診療医の“若手ロールモデル”を紹介します!—私たちはどう生きるか
29巻12号(2019年12月発行)
特集 困っている“あなた”に届く 認知症診療
29巻11号(2019年11月発行)
特集 臨床写真図鑑 レアな疾患編—見逃したくない疾患のコモンな所見
29巻10号(2019年10月発行)
特集 教えて!医師のためのビジネス・スキル
29巻9号(2019年9月発行)
特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き)
29巻8号(2019年8月発行)
特集 —ノーモア見逃し—日常の検査と画像に潜むピットフォール
29巻7号(2019年7月発行)
特集 リウマチ・膠原病ミミック症例帖—“膠原病っぽくみえてしまう疾患たち”にだまされない!
29巻6号(2019年6月発行)
特集 皮膚科診療エクササイズ—1枚の写真から
29巻5号(2019年5月発行)
特集 一般外来で診断できたら「えっへん!」な疾患38
29巻4号(2019年4月発行)
特集 “ナゾ”の痛み診療ストラテジー|OPQRSTで読み解く
29巻3号(2019年3月発行)
特集 —あなたのギモンに答えます!—循環器診療のハードルを下げるQ&A31
29巻2号(2019年2月発行)
特集 意外な中毒、思わぬ依存、知っておきたい副作用—一般外来で!OTCも処方薬も!
29巻1号(2019年1月発行)
特集 教えて検索!—膨大な医学情報を吟味・整理するスキル
28巻12号(2018年12月発行)
特集 こんなときこそ漢方を!
28巻11号(2018年11月発行)
特集 日本一マジメな「おしっこドリル」—今これだけは押さえておきたい腎・泌尿器のモンダイ
28巻10号(2018年10月発行)
特集 クリニカル・パールPremium!—憧れのカリスマ医師はかく語りき
28巻9号(2018年9月発行)
特集 オンコ・ジェネラリスト—「がん」に強い総合診療医をめざして
28巻8号(2018年8月発行)
特集 80歳からの診療スタンダードUp to Date—Silver Standard
28巻7号(2018年7月発行)
特集 この薬だけは押さえておきたい! 総合診療医のためのSpecialist Drug 40
28巻6号(2018年6月発行)
特集 聴診・触診×エコーで診断推論!—Point-of-Care超音波(POCUS)の底力
28巻5号(2018年5月発行)
特集 “一発診断”トレーニング問題集—懸賞論文「GM Clinical Pictures」大賞発表!
28巻4号(2018年4月発行)
特集 感染症外来診療「賢医の選択」—検査・経口薬・ワクチンをどう使えばいいんですか?
28巻3号(2018年3月発行)
特集 糖尿病のリアル—現場の「困った!」にとことん答えます。
28巻2号(2018年2月発行)
特集 頭痛患者で頭が痛いんです!
28巻1号(2018年1月発行)
特集 シン・フィジカル改革宣言!—私の“神技”伝授します。
27巻12号(2017年12月発行)
特集 小児診療“苦手”克服!!—劇的Before & After
27巻11号(2017年11月発行)
特集 今そこにある、ファミリー・バイオレンス|Violence and Health
27巻10号(2017年10月発行)
特集 めまいがするんです!─特別付録Web動画付
27巻9号(2017年9月発行)
特集 うつより多い「不安」の診かた—患者も医師も安らぎたい
27巻8号(2017年8月発行)
特集 見逃しやすい内分泌疾患─このキーワード、この所見で診断する!
27巻7号(2017年7月発行)
特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 3 カリスマ編
27巻6号(2017年6月発行)
特集 「地域を診る医者」最強の養成法!
27巻5号(2017年5月発行)
特集 コミュニケーションを処方する—ユマニチュードもオープンダイアローグも入ってます!
27巻4号(2017年4月発行)
特集 病歴と診察で診断できない発熱!—その謎の賢い解き方を伝授します。
27巻3号(2017年3月発行)
特集 これがホントに必要な薬40—総合診療医の外来自家薬籠
27巻2号(2017年2月発行)
特集 The総合診療ベーシックス—白熱!「総合診療フェスin OKINAWA」ライブ・レクチャー! 一挙公開 フィジカル動画付!
27巻1号(2017年1月発行)
特集 総合診療の“夜明け”—キーマンが語り尽くした「来し方、行く末」
26巻12号(2016年12月発行)
特集 これでパッチリ! 眼の健康問題
26巻11号(2016年11月発行)
特集 続・しびれるんです!
26巻10号(2016年10月発行)
特集 内科診療を劇的に変える“まとめ”の達人
26巻9号(2016年9月発行)
特集 症状・症候別 エコーを使った診断推論─Point-of-Care超音波
26巻8号(2016年8月発行)
特集 The 初診外来
26巻7号(2016年7月発行)
特集 感染症ケアバンドル・チェックリスト
26巻6号(2016年6月発行)
特集 “賢い処方”と“ナゾ処方”
26巻5号(2016年5月発行)
特集 しびれるんです!─知っておくべきシビレル疾患
26巻4号(2016年4月発行)
特集 ケースとクイズで総ざらい! 街場の2型糖尿病治療
26巻3号(2016年3月発行)
特集 こんな時は漢方でしょう!
26巻2号(2016年2月発行)
特集 フィジカル改革宣言! ──診断からフォローアップまで
26巻1号(2016年1月発行)
特集 妊婦・褥婦が一般外来に来たら─エマージェンシー&コモンプロブレム
25巻12号(2015年12月発行)
特集 外来で「複数の疾患」をもつ患者を診る─マルチモビディティの時代のプライマリ・ケア
25巻11号(2015年11月発行)
特集 レアだけど重要な「痛み」の原因─システム1診断学
25巻10号(2015年10月発行)
特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 2
25巻9号(2015年9月発行)
特集 診断ピットフォール10選─こんな疾患,見逃していませんか?
25巻8号(2015年8月発行)
特集 健診データで困ったら─こんな検査結果を持ってこられたら
25巻7号(2015年7月発行)
特集 ここを知りたい!頭部外傷初期対応・慢性期ケア
25巻6号(2015年6月発行)
特集 高齢者救急の落とし穴─紹介する時,される時
25巻5号(2015年5月発行)
特集 咳を聴きとり,咳を止める
25巻4号(2015年4月発行)
特集 関節が痛いんです!─コモンからレアものまでの診断と治療
25巻3号(2015年3月発行)
特集 神経難病ケアのコペルニクス的転回
25巻2号(2015年2月発行)
特集 総合医のためのスポーツ医学ベーシックス
25巻1号(2015年1月発行)
特集 動悸・息切れ─ヤバい病気の見つけ方 そして見つからなかった時の対処法
