プライマリ・ケアセッティングの患者さんの20%を占めるとも言われる「MUS(medically unexplained symptoms)」。
総合診療医が対応する機会が多いであろう課題です。
なかには、MUSでないものが“不定愁訴”として扱われてしまっている場合もあります。
MUSは「機能性身体症候群(FSS)」が占める割合が大きく、従来MUSとされてきたもののなかに疾患概念が確立しつつある疾患もあります。
そこで本特集では、「症状」「FSS」「身体症状症」の3つの切り口から、最新の知見を含めて整理しました。
雑誌目次
総合診療32巻11号
2022年11月発行
雑誌目次
特集 不定愁訴にしない“MUS”診療—病態からマネジメントまで
扉 フリーアクセス
著者: 片岡仁美
ページ範囲:P.1296 - P.1297
今月の「めざせ! 総合診療専門医!」問題
ページ範囲:P.1367 - P.1368
本問題集は、今月の特集のご執筆者に、執筆テーマに関連して「総合診療専門医なら知っておいてほしい!」「自分ならこんな試験問題をつくりたい!」という内容を自由に作成していただいたものです。力試し問題に、チャレンジしてみてください。
【総論】
❶ひと目でわかるMUS
著者: 片岡仁美
ページ範囲:P.1298 - P.1299
医学的に説明のつかない症状や愁訴は、わが国では「不定愁訴」と呼ばれてきた。疾患としての診断基準を満たさない症状や機能障害のうち、前者は「MUS」、後者は「機能性身体症候群(FSS)」(p.1331)と表現される。全体像がつかみにくいMUSを少しでも可視化できたらと考えていた時、岡田宏基先生(宇多津病院 心療内科、p.1328)による概念図1)に出会った。これを、岡田先生にも監修いただき、「ひと目でわかるMUS」として改変して作成したのが右図である(岡田先生の原図はp.1302)。
MUSは、「FSS」と「身体症状症(SSD)」を中心とした多要素を含む概念であるが、重要なのは1人1人の患者さんがどのカテゴリーに属するかを検証していくことであろう。また、MUSには「未診断の器質的疾患」も含まれている。医師側の問題として未診断である場合もあるし、現時点の限界としてまだ診断できない疾患概念もあるだろう。そのことにも、われわれは謙虚である必要があるかもしれない。
❷MUSの概念—それは本当にMUSなのか?
著者: 西山順滋
ページ範囲:P.1300 - P.1303
Case
「“原因不明”の症状を治してください」
患者:54歳、男性
既往歴:特記事項なし
家族歴:兄;大腸がん(55歳時に死去)
現病歴:X年4月頃より、嘔気・腹痛・便秘を認めるようになる。他院消化器内科を受診し、血液検査や上下部消化管内視鏡・腹部超音波・腹部造影CTなどの検査を実施されるも、異常はなかった。「機能性ディスペプシア(functional dyspepsia:FD)」「過敏性腸症候群(irritable bowel syndrome:IBS)」の診断で、ガイドラインに則った薬物治療を実施されたが、不定期に症状を認める状況が続いた。その後、呼吸苦や手足のしびれも認めるようになり、複数の医療機関を受診し、心電図・胸部X線・呼吸機能検査などを実施されるも改善しなかった。同年9月に紹介受診した。
☞みなさんなら、どのように対応されますか?
❸MUSの診方—診断・治療から「患者のwell-being」へ
著者: 加藤光樹
ページ範囲:P.1304 - P.1306
Case
全身の疼痛を訴える女性
患者:70歳、女性
現病歴:全身の疼痛、下肢のしびれ、腹部の灼熱感、背部の重みが続いている。「線維筋痛症」(p.1339)と考え、さまざまな薬物療法(鎮痛薬、SNRI〔セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬〕、三環系抗うつ薬、弱オピオイドなど)を試すも、不応であるか、副作用のため中止となることを繰り返していた。大学病院のペインクリニックで精査を受けるも、症状を説明できるような異常は指摘できず、改善に至らなかった。何か特別な対応があるわけではないものの、痛みがひどい時は近医を受診し、医師と会話をして帰っていく。
❹MUSと器質的疾患—“自分との戦い”:自分を制御する技法
著者: 國松淳和
ページ範囲:P.1307 - P.1310
Case
かなり多忙で時間的に追い詰められた外来。受付終了時刻は近づいているが、まだ患者は列をなしている。そんななか、この4カ月ずっと体中が痛いという初診患者が新たにやってきた。「4カ月も前からで、なんで今!?」という怒りが担当医にわいたが、外来における“時間圧”のなかスプリッティングを起こさせ、「こんなことで怒っているオレ」と「この状況で『こういう患者こそ危ないんだよね〜』みたいなことをさらっと言える、臨床の神のように理想化した医師」に自らを二分した結果、正直なところ菌血症など疑いもしなかったが、とりあえず実施してみた血液培養が翌日陽性となり、「菌血症」と診断され治療につながった。
【各論Ⅰ】「症状」から診るMUS Q&A
❶—倦怠感—鑑別のポイントは? 病的な倦怠感とは?
著者: 片岡仁美
ページ範囲:P.1311 - P.1313
倦怠感を鑑別するには、「病因」と「時間軸」に分けて考えることが必要である。「検査異常を伴うもの」と「検査異常を伴わないもの」へのアプローチの違いも重要である。また、休んでも回復しない、あるいは労働強度に見合わない疲労は、「病的な倦怠感」と考えられる。症状が「1カ月以上」続いている場合には、過労が含まれてくる可能性は少ない。
❷—慢性疼痛—どんな評価で鑑別するか? 専門家へのコンサルが必要なのは?
著者: 鉄永倫子 , 鉄永智紀
ページ範囲:P.1314 - P.1315
慢性疼痛は、生物・心理・社会的な要因が複雑に関わっている場合がある。そのため、器質的な疾患の精査に加えて、心理社会的な要因がないかを「痛みの悪循環モデル(fear-avoidanceモデル)」に基づき多角的に評価する。専門家へのコンサルテーションは、「慢性疼痛に関わる因子が多因子で、一診療科だけでアプローチするのが難しいと考えられる場合」「オピオイドに依存している場合」「運動療法に乗らない場合」などには、集学的な痛みセンターへの紹介を考慮する。ただし、患者さんに“主体的”に参加する意思がある場合に紹介する。
❸—めまい・ふらつき—慢性めまいは心因性? 見落としてはならない疾患は?
著者: 鋪野紀好
ページ範囲:P.1316 - P.1318
慢性めまいの高頻度疾患として、「持続性知覚性姿勢誘発めまい(PPPD)」がある。PPPDは、適切な診断を行うことで、治療介入できる可能性がある。
❹—胃腸症状—内視鏡や画像検査で診断できない疾患群は? その鑑別のポイントは?
著者: 笹平百世 , 三澤拓 , 塩谷昭子
ページ範囲:P.1319 - P.1321
「機能性消化管障害」があり、主なものとして、「機能性胸やけ」「逆流過敏症」「機能性ディスペプシア」「過敏性腸症候群」などがある。器質的疾患を除外できれば、主に「症状」により鑑別する。
❺—頭痛—一次性頭痛の鑑別のポイントは? 稀な一次性頭痛は?
著者: 伊藤康男 , 荒木信夫
ページ範囲:P.1322 - P.1323
一次性頭痛は、国際頭痛分類第3版(ICHD-3)で、❶片頭痛、❷緊張型頭痛、❸三叉神経・自律神経性頭痛(TACs)、❹その他の一次性頭痛疾患の4つに分類される(表1)1)。そのうち稀な一次性頭痛は❹に含まれるが、「睡眠時頭痛」や「貨幣状頭痛」など診断分類は多岐にわたる。
❻—動悸・胸痛—診断の進め方のポイントは?
著者: 樗木晶子
ページ範囲:P.1324 - P.1327
動悸・胸痛は、それぞれが独立した症状の時もあれば、両者が混在する場合もある。その原因となる疾患のうち、迅速な対応が必要なものを見落とさないために「系統的問診」が大切である。
❼—息切れ—診断・鑑別のポイントは?
著者: 岡田宏基
ページ範囲:P.1328 - P.1330
息切れ(shortness of breath)の鑑別は、呼吸器疾患・循環器疾患などの「器質的疾患」によるものと、不安や抑うつなどの「非器質的疾患」によるものとに大別される。この両者は「SpO2」を測定することで大まかに区別が可能である。
【各論Ⅱ】「FSS」の病態とマネジメントCaseつき
❶機能性身体症候群(FSS)とは
著者: 村上正人
ページ範囲:P.1331 - P.1334
Case
患者:45歳、女性。主婦。
現病歴:5年前の冬頃から肩・首・四肢の痛みや朝のこわばりが徐々に増悪し、4年前には全身の痛みに拡大した。関節リウマチや膠原病などが疑われ諸検査を受けたが、臨床検査・画像検査などでは異常が認められず、疲労やストレスによるものとされ治療には至らなかった。しかし、頭痛、顎関節痛、胸腹部痛、下痢や便秘の繰り返し、胃もたれ感、月経痛、頻尿、不眠、強度の疲労・倦怠感など、多彩な症状を伴うようになり、多数の科を受診するようになった。
発症の時期に、高齢の姑の介護、転居、転倒による腰部打撲などが重なり、心身の疲労が極限に達していた。
❷筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)
著者: 佐藤元紀 , 伴信太郎
ページ範囲:P.1335 - P.1338
◦正しく診断することが重要:診断基準を満たす患者でも、半数以上でME/CFS以外の診断となる。
◦特異的な薬物治療はない:抗うつ薬・睡眠導入薬などの対症療法や、漢方薬による治療が有効なケースもある。
◦生活指導・社会的サポートが重要:さまざまな診療科・職種が関与した包括的な治療が必要である。
❸線維筋痛症
著者: 松本美富士
ページ範囲:P.1339 - P.1342
◦慢性疼痛以外に多彩な随伴症状があるため、過剰な検査の繰り返し、ポリファーマシーは避ける。
◦治療・ケアのゴールは痛みの消退でなく、痛みの緩和と日常生活動作の改善による発病前の生活への復帰である。
◦慢性疼痛から破局的思考に陥ることがあり、リエゾン的な心療内科・精神科と積極的に連携することが必要である。
❹過敏性腸症候群(IBS)/機能性ディスペプシア(FD)
著者: 三澤拓 , 笹平百世 , 塩谷昭子
ページ範囲:P.1343 - P.1344
IBSとFDは、「機能性消化管障害(FGID)」の代表疾患であり、器質的疾患を除外したうえで、それぞれの疾患の特徴を捉え、症状に対し必要に応じて生活習慣の改善や適切な薬物療法を行う。
❺筋・筋膜性疼痛症候群
著者: 鉄永倫子 , 鉄永智紀
ページ範囲:P.1345 - P.1347
筋・筋膜性疼痛症候群は慢性疼痛性障害で、筋肉が繰り返し収縮したあとに発生することが多く、治療としては「理学療法」と「トリガーポイント注射」に加え、「消炎鎮痛薬」や「リラクゼーション」が有効である。
❻レストレスレッグス症候群/周期性四肢運動障害
著者: 中村真樹
ページ範囲:P.1348 - P.1351
レストレスレッグス症候群(RLS)と、これに合併しやすい周期性四肢運動障害は、この不快感・不随意運動のため、「入眠困難」や「中途覚醒」「熟眠感欠如」の原因となる。夜間の下肢不快感という主観的症状が特徴で、客観的評価が難しく、不眠症状に対して安易に「睡眠薬」のみを処方すると、逆に不快感を強めることがあり、注意が必要である。
❼PTSD
著者: 加茂登志子
ページ範囲:P.1352 - P.1354
PTSDは稀ではないが、日常臨床のなかでは発見されにくい。持続性・難治性の「自律神経失調症状」を訴える患者が多く、トラウマ体験は積極的に語られることは少ない。安全が確保され、生活環境が整い、あるいは薬物療法に効果が認められた場合には、心理療法導入以前に寛解する事例もある。
❽化学物質過敏症
著者: 坂部貢
ページ範囲:P.1355 - P.1357
化学物質過敏症(CS)は、1つの疾患として捉えるのではなく、化学物質過敏を主訴とする多くの疾患カテゴリーの集まりと考えることが、臨床的には重要である。初診患者においては、問診票「QEESI」を用いた詳細な問診が鍵となる。CSの診断は、問診に始まり問診に終わると言っても過言ではない。「症状出現」と「生活環境要因」を1つの線で結びつけることが重要である。
【各論Ⅲ】「身体症状症」を見定める
❶身体症状症の診断・治療—原因不明の身体症状に“伴走”する
著者: 太田大介
ページ範囲:P.1358 - P.1360
Case
動悸のために眠れなくなった女性
患者:50代、女性。会社員。
主訴:動悸、息苦しさ、不眠
現病歴:2カ月前から、息苦しさを自覚するようになった。症状が改善せず不眠もきたすようになったため、当科を紹介受診した。脈拍数90回/分・整、血圧120/70mmHg。胸部単純X線や心電図などに問題はみられなかった。
患者は、動悸・息切れは1日中あり、動悸がすると手足の血の気がなくなっていく感じがすると述べた。疲れた日の夜には症状が悪化し、一方、症状が改善する状況としては、休日のショッピングなどでは動悸を自覚していない時間もあるという。この数カ月間は、職場のスタッフが減り多忙であったことも明らかとなった。担当医は、長期間の疲労で自律神経の働きが緊張状態に傾き、動悸・息切れ・不眠などの各種症状につながることがよくあること、そのため意識的に体を休め気分転換をしていく必要があることを患者に伝え、頓用薬としてクロチアゼパム5mgを処方した。2週間後の診察では、頓用薬は用いず諸症状は改善していた。
❷原因不明の身体症状について精神科医が総合診療医に伝えたいこと
著者: 宮岡等
ページ範囲:P.1361 - P.1362
“自覚的身体症状”の精神医学
本特集のタイトルは「不定愁訴にしないMUS診療」である。「MUS(medically unexplained symptoms)」は、さまざまな自覚症状があり、十分な診察や検査を行っても、原因を医学的に説明できない状態であると考えられる。過去の身体医学は、このような状態に対して「自律神経失調症」「不定愁訴症候群」、さらには専門学会の定義を軽視して「心身症」などと呼んできた。このような状態の多くは、自覚症状を主とする診断の曖昧さや期待される治療効果にばらつきはあるものの、精神医学からみれば「心気症」「身体化障害」「身体症状症(p.1298・1302・1333・1358)」など何らかの診断がつけられてきた。しかし、精神科診断基準の改訂に伴い診断名が頻回に変わる、精神科医が身体症状を診察したがらない、精神医学への偏見などが影響して、“自覚的な身体症状を主とする精神疾患”の精神医学は十分に議論されず、あるいは軽視され、身体医学の側から独自に診断名がつくられてきたとも言える。最近の「MUS」や「機能性身体症候群(functional somatic syndrome:FSS)」(p.1331〜)にも同様の傾向がある。
【コラム】
❶COVID-19罹患後症状とMUS
著者: 大塚勇輝 , 徳増一樹 , 大塚文男
ページ範囲:P.1363 - P.1364
Case
患者:30代、男性。会社員。
現病歴:発熱や咽頭痛でCOVID-19(新型コロナウイルス感染症)を発症。2〜3日のみで軽快し、10日間の自宅療養をもって隔離解除となったが、その頃から労作に伴って増悪する倦怠感と呼吸困難感が目立つようになった。症状の遷延により、罹患前同様の勤務が不能な状態が1カ月以上持続したため、当院を紹介受診した。
炎症・自己免疫系や内分泌・代謝系も含めた血液検査、胸部CTや呼吸機能検査では、特に症状の原因を説明できるものはなかった。呼吸リハビリテーションの必要性とともに、無理せず休養をとることが症状を増悪・遷延させないうえで重要であることを伝え、勤務先に提出する診断書を作成した。補剤を中心とした漢方薬治療も行うことで、数カ月かけて症状は改善傾向にある。
❷マインドフルネス
著者: 佐渡充洋
ページ範囲:P.1365 - P.1365
「マインドフルネス」という概念がある。近年、ある種のブームにもなっており、聞き覚えのある方もいるかもしれない。具体的には、「瞑想」を実践することである。こうした取り組みを通して、今この瞬間に起きているさまざまな体験(身体の痛みや違和感なども含まれる)に優しい好奇心を向けながら、これと一緒にいられる力を身につけていくものだ。
❸総合診療医のMUS診療トレーニングプログラム
著者: 太田大介
ページ範囲:P.1366 - P.1366
本稿では、MUS(medically unexplained symptoms)に特化した総合診療医(あるいは家庭医)向けのトレーニングプログラムの1つとして、デンマークで行われている「TERM(the extended reattribution and management)モデル」を紹介し、その日本への導入にも触れたい。
ヨーロッパ諸国では、広く家庭医制度が採用されている。住民はそれぞれ特定の家庭医に登録されており、すべての医療はそのかかりつけ医を通して提供されるシステムとなっている1)。MUSを有する患者についても、総合診療医が窓口となって対応する必要がある。そのため、総合診療医にとって、MUS患者への対応を習得することは喫緊の課題になっている。
Editorial
本当にmedically unexplained? フリーアクセス
著者: 片岡仁美
ページ範囲:P.1287 - P.1287
「不定愁訴」という言葉が好きではなかった。「いろいろと訴えが多い(…大変だ)」といったニュアンスが、どことなく含まれている気がするからである。「不定愁訴」というラベルを貼った時点で、実は隠れているかもしれない器質的疾患を明らかにする可能性を自ら閉じてしまうような気がして、私自身は不定愁訴という言葉は使ってこなかった。自分への戒め、といった気持ちであった。そのことは、多くの診断がつかない患者さんが「どこへ行っても異常がないと言われた」「気のせい、年のせいと言われた」「でも本当に症状があるんです。つらいんです」と時には泣きながら訴えられるのを、大学病院で何度も目にしてきたことも影響していると思われる。
最近では「MUS(medically unexplained symptoms)」という概念も浸透してきたが、これについても明確な診断基準はなく、他の病態との重なりもある概念である。なかでも「機能性身体症候群(functional somatic syndromes:FSS)」は、特に重要な概念である。本特集を企画している時にちょうど発表された西山順滋先生の論文1)は、まさに自分が言語化したかったことが綿密なデータで示されたもので、膝を打つ思いで今回の総論(p.1300)をご執筆いただいた次第である。FSSを明確に診断することによって、混沌として見えるMUSの中に、一連の共通性をもった疾患群が浮かび上がるように思われる。FSSの疾患群は互いに合併することも多く、「中枢性感作症候群(central sensitization syndromes:CSS)」の概念とも重なることから、共通のメカニズムを有している可能性があるのではないかと感じる。MUSを少しでも可視化できたらという思いで、岡田宏基先生(宇多津病院 心療内科、p.1328)が提唱された概念図を、岡田先生とともにアップデートして掲載させていただいた(p.1298)。
What's your diagnosis?[239]
秋のマナー
著者: 猪飼浩樹 , 岩崎慶太 , 山本真理 , 渡邉剛史 , 村井由香里 , 滝澤直歩 , 国領和佳 , 藤田芳郎
ページ範囲:P.1290 - P.1294
病歴
患者:60代、男性
主訴:腰背部痛
現病歴:10年前に肩痛および手指痛が出現し関節リウマチ(RA)と診断される。その後、メトトレキサート(MTX)を含む抗リウマチ薬で加療された経過あり。朝のこわばりはあるが、疼痛は現在おおむね自制内で推移している。
5年前に化膿性椎体炎・椎間板炎で入院加療された。5年前の時点でのRA治療はMTX 8mg/週、および非ステロイド性消炎鎮痛薬(NSAIDs)頓服であった。MRI画像で「化膿性脊椎炎」を疑い椎間板生検も実施されたが、起炎菌は不明であった。ST合剤で加療されたが、肝障害でミノサイクリン(MINO)内服へ変更されて軽快した(図1)。
受診半年前にテニスで腰を痛め、その後、背部痛が断続的に持続している。痛みは労作で増悪する。受診1カ月から腰痛の程度が増悪した。
既往歴(既出のもの以外に):高血圧症
内服薬:ブシラミン100mg 1回1錠・1日2回、ナプロキセン100mg 1回2錠・1日3回、フェキソフェナジン塩酸塩60mg 1回1錠・1日2回、カンデサルタン4mg 1回1錠・1日1回
家族歴:母と祖母がRA
ROS(review of systems)陰性:体重減少、寝汗、食思不振、倦怠感、皮疹の自覚、頭痛、めまい、難聴の自覚、鼻出血、咽頭痛、ドライアイ、ドライマウス、咳嗽、呼吸困難、喀痰の増加、血痰、動悸、浮腫の自覚、悪心、嘔吐、腹痛、下痢、軟便、血便、頻尿、排尿困難感、尿失禁、多尿、血尿、複視、しびれの自覚
【エッセイ】アスクレピオスの杖—想い出の診療録・31
君といつまでも
著者: 松村真司
ページ範囲:P.1295 - P.1295
本連載は、毎月替わる著者が、これまでの診療で心に残る患者さんとの出会いや、人生を変えた出来事を、エッセイにまとめてお届けします。
オール沖縄!カンファレンス|レジデントの対応と指導医の考えVer.2.0・70
見逃していませんか、その貧血
著者: 長嶺さつき , 上間貴仁 , 知花なおみ , 徳田安春
ページ範囲:P.1371 - P.1375
CASE
患者:90歳、男性。職業は元教師。
主訴:食思不振、貧血。
現病歴:X年7月からの食思不振、倦怠感、2カ月で4〜5kgの体重減少を主訴に、同年10月に近医を受診し、血液検査で大球性貧血(Hb 8.6g/dL、MCV 111.7fL)と腎機能低下(Cr 1.28mg/dL、eGFR 40.7mL/分/1.73m2)を指摘され、当院紹介受診となった。もともとゴルフができる程度の自立した生活をしていたが、X年7月からは徐々に倦怠感が強くなり、1日のほとんどをベッド上で過ごすようになっていた。当院来院時、食思不振は改善傾向であったが、体重減少を認めていた。嘔吐・下痢や腹痛、下血などの消化器症状はなく、発熱や上気道症状も認めなかった。検査を行った結果、腎性貧血を考え、ダルベポエチン アルファ30μgを投与し、かかりつけ医で治療継続する方針となった。
その後、同年12月にトイレから立ち上がろうとした際にふらつき、背後に転倒した。腰痛があり、体動困難であったため、当院救急搬送となった。救急搬送される3週間前から再度食思不振と倦怠感があり、普段行っていた庭作業も息切れが起こるようになっていたとのこと。
既往歴:慢性腎臓病、脂質異常症、前立腺肥大症、大動脈弁狭窄症、胆囊摘出術後、慢性便秘症。
鉄欠乏なし、葉酸欠乏なし。上部消化管内視鏡検査にて悪性所見・潰瘍なし。
薬剤歴:メコバラミン0.5mg 1回1錠・1日3回(毎食後)、葉酸5mg 1回1錠・1日3回(毎食後)、フェノフィブラート80mg 1回1錠・1日1回(朝食後)、タムスロシン0.2mg 1回1錠・1日1回(朝食後)、ルビプロストン12μg 1回1cp・1日2回(朝・夕食後)、クエン酸第一鉄ナトリウム50mg 1回1錠・1日1回(朝食後)、ベンフォチアミン・B6・B12配合剤カプセル1回1cp・1日3回(毎食後)。
アレルギー:薬なし、食物なし。
生活歴:喫煙:13本/日(20歳〜)、飲酒:X年10月から禁酒。ADLは独歩可能、X年7月まではゴルフをしていた。
Dr.上田剛士のエビデンス実践レクチャー!医学と日常の狭間で|患者さんからの素朴な質問にどう答える?・32
発酵食品は身体に良いですか?
著者: 上田剛士
ページ範囲:P.1377 - P.1379
患者さんからのふとした質問に答えられないことはないでしょうか? 素朴な疑問ほど回答が難しいものはありませんが、新たな気づきをもたらす良問も多いのではないでしょうか? 本連載では素朴な疑問に、文献的根拠を提示しながらお答えします!
フィジカル・ラウンド・オンライン・6【最終回】
嵐の前の静けさ
著者: 河野勲 , 矢吹拓 , 平島修
ページ範囲:P.1380 - P.1385
平島:今年最後のPRO(Physical Round Online)ですね〜。
矢吹:結局コロナはなかなかいなくなりませんね。オンライン回診の需要があるのは、よいような、よくないような…。
高齢者診療スピードアップ塾|効率も質も高める超・時短術・11
その業務、「タスク・シフト」で30分時短せよ!
著者: 増井伸高
ページ範囲:P.1398 - P.1400
2024年4月から、医師の働き方改革が開始されます。「タスク・シフト」は、その目玉の1つです。医師でなくても実施可能な仕事を他職種に移行することで、医師は本来の仕事に専念できます。タスク・シフトにより医師の総勤務時間は7%減ると予測され1)、高齢者診療の時短にも寄与することでしょう。そこで今回は、具体的なタスク・シフトの方法について確認していきます。
【臨床小説—第二部】後悔しない医者|今と未来をつなぐもの・第31話
よくならない患者を診る医者
著者: 國松淳和
ページ範囲:P.1401 - P.1406
前回までのあらすじ 今月のナゾ
向後チーム定例のカンファでは、左座が気になっている外来症例のプレゼンが続いていた。患者は16歳・男性、頭ケ島白浜病院がある五島の出身だ。この春、長崎市内の県下有数の進学校に入学し、下宿生活を送っていた。強豪のバスケ部にも入ったが、体育会系の雰囲気には馴染めずにいた。そして4月下旬から、体がだるくて朝起きられなくなった。頭痛もひどく、下宿の大家である「おばあちゃん」に見守られながらも、学校に行けなくなってしまった。市内の総合病院で精査を行ったが異常は認められず、左座の診療も行き詰まりつつあった。
いくら検査をしても異常がない。心因性ではないか——。「不定愁訴」あるいは「MUS(medically unexplained symptoms)」を訴える患者がいる。患者にとって症状は確かにあるのだが、器質的疾患がないか精査し、機能性の病態も疑ったうえで、その症状に説明ができない場合、他になすすべはないのだろうか? 左座は、そして向後は、この患者にどう向き合っていくのだろう?
投稿 GM Clinical Pictures
考えど考えど診断は浮かび難し。じっと手を見る。
著者: 若林崇雄 , スフィ・ノルハニ , 石立尚路 , 須藤大智 , 渡邉智之
ページ範囲:P.1387 - P.1388
CASE
患者:43歳、男性。
主訴:手掌痛。
現病歴:読書中、特別な誘因なく、突然左手手掌に疼痛を自覚した(「ぶちっという痛み」と表現)。
左手手掌を見ると、暗紫色斑が数分かけて広がった(図1)。患者は同様のエピソードを過去に経験している。手掌の疼痛以外に自覚症状はない。
受診時のバイタルサイン:意識清明。血圧126/80mmHg、脈拍数56回/分 整、体温36.6℃(腋窩温)、呼吸数16回/分、SpO2 98%(室内気)。
既往歴:特記すべき既往なし。
生活歴:飲酒歴:週に数回程度、喫煙歴:なし。
体重減少:なし。
身体所見:現病歴に記載した所見以外に、特記すべき所見はない。
検査所見:検査不要と考え、実施していない。
頭を捻っても答えは出ない
著者: 若林崇雄 , 石立尚路 , 須藤大智 , 渡邉智之 , スフィ・ノルハニ
ページ範囲:P.1389 - P.1390
CASE
患者:88歳、女性。
主訴:2日前から断続的に持続する腹痛。
現病歴:来院2日前、ときどき生じる腹痛を自覚していた。腹痛は間欠的で、消失することもあった。来院当日、起床時から腹痛と頻脈を自覚。嘔気を自覚するも吐物はない。昼過ぎに訪問看護師に促されて救急搬送された。
既往歴:虫垂炎、心房細動、結核、心不全(原因疾患は不詳)。
内服薬:エルデカルシトール、アトルバスタチン、アスピリン・ランソプラゾール、エドキサバン、ビソプロロール、フロセミド。
生活歴:ADL(日常生活動作):要介護1。生活周辺動作はほぼ自立していた。飲酒歴なし、喫煙歴なし。最終排便は起床時に少量で、普通便であった。
受診時のバイタルサイン:意識清明。血圧163/98mmHg、脈拍数108回/分 整、体温36.6℃(腋窩温)、呼吸数18回/分、SpO2 98%(室内気)。
外観:急性疾患。
身体所見:心窩部は膨隆しているものの、下腹部の膨隆は著明ではない。腹部は平坦で柔らかく腫瘤を蝕知しない。腸蠕動音はやや低下していた。
圧痛や腹膜刺激徴候は認めなかった。「腹痛」と訴えるものの、心窩部に近い痛みである。
血液検査:特記すべき異常を認めなかった。
画像所見:何らかの腸閉塞もしくはイレウスを疑って撮像した造影CTを示す(図1、2)。
#総合診療
#今月の特集関連本❶ フリーアクセス
ページ範囲:P.1303 - P.1303
#今月の特集関連本❷ フリーアクセス
ページ範囲:P.1310 - P.1310
#今月の特集関連本❸ フリーアクセス
ページ範囲:P.1313 - P.1313
#今月の特集関連本❹ フリーアクセス
ページ範囲:P.1318 - P.1318
#今月の特集関連本❺ フリーアクセス
ページ範囲:P.1321 - P.1321
#今月の特集関連本❻ フリーアクセス
ページ範囲:P.1334 - P.1334
#今月の特集関連本❼ フリーアクセス
ページ範囲:P.1347 - P.1347
#今月の特集関連本❽ フリーアクセス
ページ範囲:P.1351 - P.1351
#今月の特集関連本❾ フリーアクセス
ページ範囲:P.1354 - P.1354
#今月の特集関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.1391 - P.1391
#今月の特集関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.1393 - P.1393
#今月の特集関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.1395 - P.1395
#今月の連載関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.1400 - P.1400
#医学書院の新刊 フリーアクセス
ページ範囲:P.1364 - P.1364
#医学書院の新刊 フリーアクセス
ページ範囲:P.1396 - P.1396
#書評:—こころとからだにチームでのぞむ—慢性疼痛ケースブック フリーアクセス
著者: 矢吹省司
ページ範囲:P.1397 - P.1397
本書は、慢性疼痛患者を診療する医療者が参考にできる事例集が中心となっている。8章から成っており、1章「慢性痛を知る」、2章「慢性痛をどう評価するか」、3章「慢性痛の臨床—エビデンスの治療と原則」、そして4〜8章「ケースブック」という構成である。
まず、慢性痛を理解し、どのように評価し、そしてどのような治療があるのかを1〜3章で知ることができる。これらの章の各項目には「Point」があり、その項目のまとめが記載されている。そこを読んでいくだけでも、内容をある程度理解できるようになっている。そして4章「ICD-11分類に基づく慢性痛」、5章「精神疾患と併発する慢性痛」、6章「ライフステージと慢性痛」、7章「臨床で気を付けたい慢性痛」および8章「慢性痛診療のアプローチ」で、具体的に事例をあげて病態の評価の結果と、それをもとにどのような治療方針を立てるかについて記載されている。共通していることは、❶一医師だけでの評価や治療では限界がある、❷多くの専門家がそれぞれの視点で評価し、それをカンファレンスでディスカッションすることで的確な治療方針が見えてくる、そして❸多面的に治療することで複雑な慢性痛であっても改善(痛みの程度そのものに変化がなくてもADLやQOLは改善)できる可能性がある、ということである。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.1288 - P.1289
『総合診療』編集方針 フリーアクセス
ページ範囲:P.1369 - P.1369
1991年に創刊した弊誌は、2015年に『JIM』より『総合診療』に誌名を変更いたしました。その後も高齢化はさらに進み、社会構造や価値観、さらなる科学技術の進歩など、日本の医療を取り巻く状況は刻々と変化し続けています。地域医療の真価が問われ、ジェネラルに診ることがいっそう求められる時代となり、ますます「総合診療」への期待が高まってきました。これまで以上に多岐にわたる知識・技術、そして思想・価値観の共有が必要とされています。そこで弊誌は、さらなる誌面の充実を図るべく、2017年にリニューアルをいたしました。本誌は、今後も下記の「編集方針」のもと、既存の価値にとらわれることなく、また診療現場からの要請に応え、読者ならびに執筆者のみなさまとともに、日本の総合診療の新たな未来を切り拓いていく所存です。
2018年1月 『総合診療』編集委員会
読者アンケート
ページ範囲:P.1407 - P.1407
『総合診療』バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.1408 - P.1409
お得な年間購読のご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.1409 - P.1410
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.1411 - P.1412
基本情報
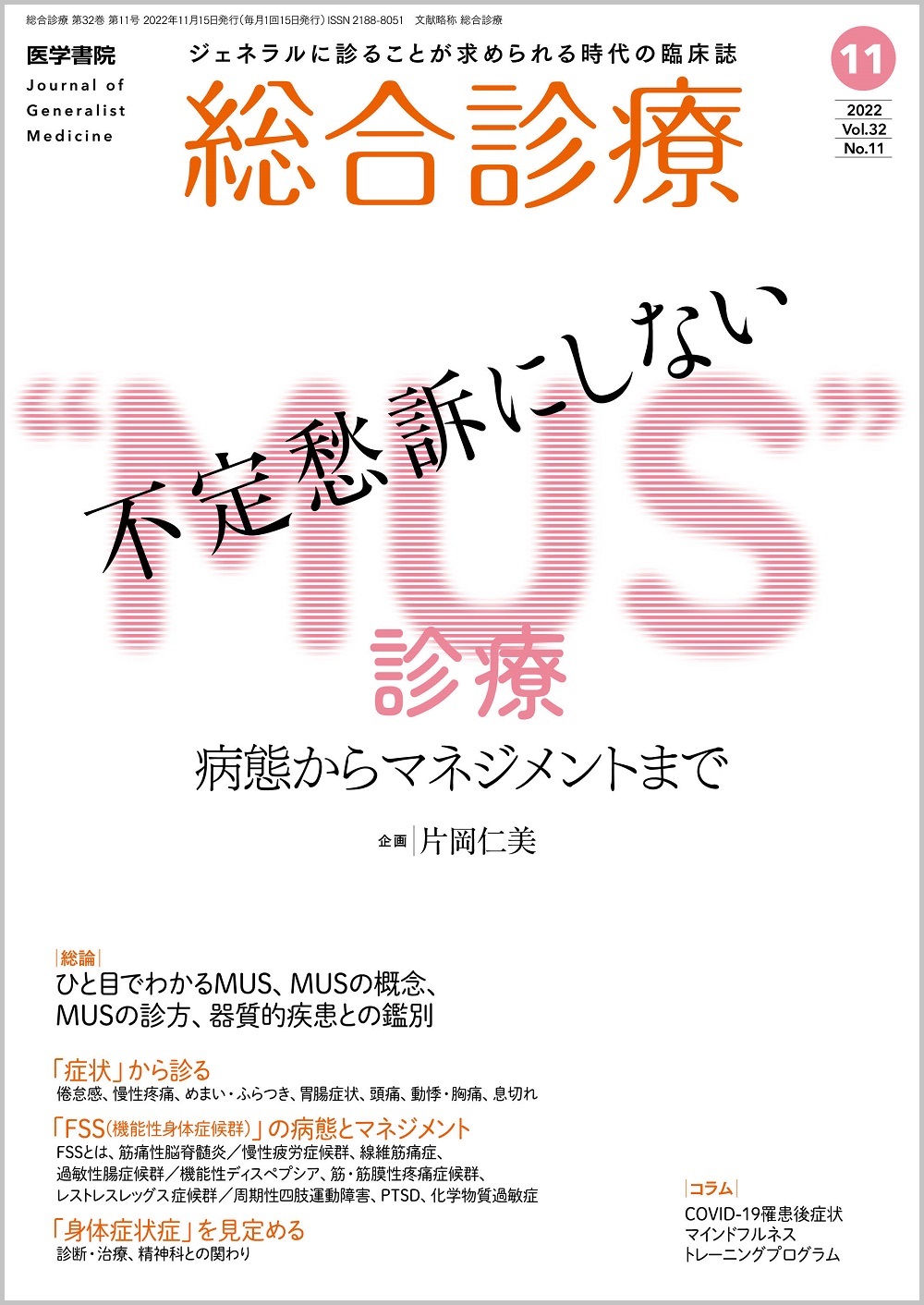
バックナンバー
34巻12号(2024年12月発行)
特集 妊婦・褥婦が外来に来たらUpdate—症状対応からワクチン・プラネタリーヘルスまで
34巻11号(2024年11月発行)
特集 電子カルテとベッドサイドの壁を打ち破る!—患者情報の「言語化」への挑戦
34巻10号(2024年10月発行)
特集 化かしが得意なカメレオンな疾患を捕まえろ!—よくある騙され方のゲシュタルト
34巻9号(2024年9月発行)
特集 今伝えたいクリニカル・パール—つくり方、使い方、活かし方
34巻8号(2024年8月発行)
特集 ストーン・ウォーズ 果てしなき“石”と医師との闘い
34巻7号(2024年7月発行)
特集 どうする!? 健診異常—これってホントに異常なの? どう説明する?
34巻6号(2024年6月発行)
特集 医師のウェルビーイング
34巻5号(2024年5月発行)
特集 —優柔不断にサヨウナラ!—あなたの「臨床判断」を高めるケーススタディ11選
34巻4号(2024年4月発行)
特集 困ったときの漢方—この症状に役立ちます!
34巻3号(2024年3月発行)
特集 —え、ウソ!実は◯◯だった!?—“コモンディジーズ”の診断ピットフォール
34巻2号(2024年2月発行)
特集 日常診療で出合う筋骨格疾患—脳神経内科と整形外科からのアプローチ
34巻1号(2024年1月発行)
特集 —“体験型”臨床クイズで習得する!—フィジカル診断エクセレンス
33巻12号(2023年12月発行)
特集 海の外へ渡る航行者を診る—アウトバウンドにまつわるetc.
33巻11号(2023年11月発行)
特集 —続・総合診療外来に“実装”したい—最新エビデンスMy Best 3
33巻10号(2023年10月発行)
特集 ○×クイズ110問!日常診療アップグレード—Choosing WiselyとHigh Value Careを学ぼう
33巻9号(2023年9月発行)
特集 ジェネラリストのための「発達障害(神経発達症)」入門
33巻8号(2023年8月発行)
特集 都市のプライマリ・ケア—「見えにくい」を「見えやすく」
33巻7号(2023年7月発行)
特集 “消去法”で考え直す「抗菌薬選択」のセオリー—広域に考え、狭域に始める
33巻6号(2023年6月発行)
特集 知っておくべき!モノクロな薬たち(注:モノクローナル抗体の話ですよ〜)
33巻5号(2023年5月発行)
特集 —疾患別“イルネススクリプト”で学ぶ—「腹痛診療」を磨き上げる22症例
33巻4号(2023年4月発行)
特集 救急対応ドリル—外来から在宅までの60問!
33巻3号(2023年3月発行)
特集 —自信がもてるようになる!—エビデンスに基づく「糖尿病診療」大全—新薬からトピックスまで
33巻2号(2023年2月発行)
特集 しびれQ&A—ビビッとシビれるクリニカルパール付き!
33巻1号(2023年1月発行)
特集 COVID-19パンデミック 振り返りと将来への備え
32巻12号(2022年12月発行)
特集 レクチャーの達人—とっておきの生ライブ付き!
32巻11号(2022年11月発行)
特集 不定愁訴にしない“MUS”診療—病態からマネジメントまで
32巻10号(2022年10月発行)
特集 日常診療に潜む「処方カスケード」—その症状、薬のせいではないですか?
32巻9号(2022年9月発行)
特集 総合診療・地域医療スキルアップドリル—こっそり学べる“特講ビデオ”つき!
32巻8号(2022年8月発行)
特集 こんなところも!“ちょいあて”エコー—POCUSお役立ちTips!
32巻7号(2022年7月発行)
特集 —どうせやせない!? やせなきゃいけない??苦手克服!—「肥満」との向き合い方講座
32巻6号(2022年6月発行)
特集 総合診療外来に“実装”したい最新エビデンス—My Best 3
32巻5号(2022年5月発行)
特集 「診断エラー」を科学する!—セッティング別 陥りやすい疾患・状況
32巻4号(2022年4月発行)
特集 えっ、これも!? 知っておきたい! 意外なアレルギー疾患
32巻3号(2022年3月発行)
特集 AI時代の医師のクリニカル・スキル—君は生き延びることができるか?
32巻2号(2022年2月発行)
特集 —withコロナ—かぜ診療の心得アップデート
32巻1号(2022年1月発行)
特集 実地医家が楽しく学ぶ 「熱」「炎症」、そして「免疫」—街場の免疫学・炎症学
31巻12号(2021年12月発行)
特集 “血が出た!”ときのリアル・アプローチ—そんな判断しちゃダメよ!
31巻11号(2021年11月発行)
特集 Q&Aで深める「むくみ診断」—正攻法も!一発診断も!外来も!病棟も!
31巻10号(2021年10月発行)
特集 医師の働き方改革—システムとマインドセットを変えよう!
31巻9号(2021年9月発行)
特集 「検査」のニューノーマル2021—この検査はもう古い? あの新検査はやるべき?
31巻8号(2021年8月発行)
特集 メンタルヘルス時代の総合診療外来—精神科医にぶっちゃけ相談してみました。
31巻7号(2021年7月発行)
特集 新時代の「在宅医療」—先進的プラクティスと最新テクノロジー
31巻6号(2021年6月発行)
特集 この診断で決まり!High Yieldな症候たち—見逃すな!キラリと光るその病歴&所見
31巻5号(2021年5月発行)
特集 臨床医のための 進化するアウトプット—学術論文からオンライン勉強会、SNSまで
31巻4号(2021年4月発行)
特集 消化器診療“虎の巻”—あなたの切実なギモンにズバリ答えます!
31巻3号(2021年3月発行)
特集 ライフステージでみる女性診療at a glance!—よくあるプロブレムを網羅しピンポイントで答えます。
31巻2号(2021年2月発行)
特集 肺炎診療のピットフォール—COVID-19から肺炎ミミックまで
31巻1号(2021年1月発行)
特別増大特集 新型コロナウイルス・パンデミック—今こそ知っておきたいこと、そして考えるべき未来
30巻12号(2020年12月発行)
特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き) Part 2
30巻11号(2020年11月発行)
特集 診断に役立つ! 教育で使える! フィジカル・エポニム!—身体所見に名を残すレジェンドたちの技と思考
30巻10号(2020年10月発行)
特集 —ポリファーマシーを回避する—エビデンスに基づく非薬物療法のススメ
30巻9号(2020年9月発行)
特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【感染症・内分泌・整形外科 編】
30巻8号(2020年8月発行)
特集 マイナーエマージェンシー門外放出—知っておくと役立つ! テクニック集
30巻7号(2020年7月発行)
特集 その倦怠感、単なる「疲れ」じゃないですよ!—筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群とミミック
30巻6号(2020年6月発行)
特集 下降期慢性疾患患者の“具合”をよくする—ジェネラリストだからできること!
30巻5号(2020年5月発行)
特集 誌上Journal Club—私を変えた激アツ論文
30巻4号(2020年4月発行)
特集 大便強ドリル—便秘・下痢・腹痛・消化器疾患に強くなる41問!
30巻3号(2020年3月発行)
特集 これではアカンで!こどもの診療—ハマりがちな11のピットフォール
30巻2号(2020年2月発行)
特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【循環器・消化器・神経疾患編】
30巻1号(2020年1月発行)
特集 総合診療医の“若手ロールモデル”を紹介します!—私たちはどう生きるか
29巻12号(2019年12月発行)
特集 困っている“あなた”に届く 認知症診療
29巻11号(2019年11月発行)
特集 臨床写真図鑑 レアな疾患編—見逃したくない疾患のコモンな所見
29巻10号(2019年10月発行)
特集 教えて!医師のためのビジネス・スキル
29巻9号(2019年9月発行)
特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き)
29巻8号(2019年8月発行)
特集 —ノーモア見逃し—日常の検査と画像に潜むピットフォール
29巻7号(2019年7月発行)
特集 リウマチ・膠原病ミミック症例帖—“膠原病っぽくみえてしまう疾患たち”にだまされない!
29巻6号(2019年6月発行)
特集 皮膚科診療エクササイズ—1枚の写真から
29巻5号(2019年5月発行)
特集 一般外来で診断できたら「えっへん!」な疾患38
29巻4号(2019年4月発行)
特集 “ナゾ”の痛み診療ストラテジー|OPQRSTで読み解く
29巻3号(2019年3月発行)
特集 —あなたのギモンに答えます!—循環器診療のハードルを下げるQ&A31
29巻2号(2019年2月発行)
特集 意外な中毒、思わぬ依存、知っておきたい副作用—一般外来で!OTCも処方薬も!
29巻1号(2019年1月発行)
特集 教えて検索!—膨大な医学情報を吟味・整理するスキル
28巻12号(2018年12月発行)
特集 こんなときこそ漢方を!
28巻11号(2018年11月発行)
特集 日本一マジメな「おしっこドリル」—今これだけは押さえておきたい腎・泌尿器のモンダイ
28巻10号(2018年10月発行)
特集 クリニカル・パールPremium!—憧れのカリスマ医師はかく語りき
28巻9号(2018年9月発行)
特集 オンコ・ジェネラリスト—「がん」に強い総合診療医をめざして
28巻8号(2018年8月発行)
特集 80歳からの診療スタンダードUp to Date—Silver Standard
28巻7号(2018年7月発行)
特集 この薬だけは押さえておきたい! 総合診療医のためのSpecialist Drug 40
28巻6号(2018年6月発行)
特集 聴診・触診×エコーで診断推論!—Point-of-Care超音波(POCUS)の底力
28巻5号(2018年5月発行)
特集 “一発診断”トレーニング問題集—懸賞論文「GM Clinical Pictures」大賞発表!
28巻4号(2018年4月発行)
特集 感染症外来診療「賢医の選択」—検査・経口薬・ワクチンをどう使えばいいんですか?
28巻3号(2018年3月発行)
特集 糖尿病のリアル—現場の「困った!」にとことん答えます。
28巻2号(2018年2月発行)
特集 頭痛患者で頭が痛いんです!
28巻1号(2018年1月発行)
特集 シン・フィジカル改革宣言!—私の“神技”伝授します。
27巻12号(2017年12月発行)
特集 小児診療“苦手”克服!!—劇的Before & After
27巻11号(2017年11月発行)
特集 今そこにある、ファミリー・バイオレンス|Violence and Health
27巻10号(2017年10月発行)
特集 めまいがするんです!─特別付録Web動画付
27巻9号(2017年9月発行)
特集 うつより多い「不安」の診かた—患者も医師も安らぎたい
27巻8号(2017年8月発行)
特集 見逃しやすい内分泌疾患─このキーワード、この所見で診断する!
27巻7号(2017年7月発行)
特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 3 カリスマ編
27巻6号(2017年6月発行)
特集 「地域を診る医者」最強の養成法!
27巻5号(2017年5月発行)
特集 コミュニケーションを処方する—ユマニチュードもオープンダイアローグも入ってます!
27巻4号(2017年4月発行)
特集 病歴と診察で診断できない発熱!—その謎の賢い解き方を伝授します。
27巻3号(2017年3月発行)
特集 これがホントに必要な薬40—総合診療医の外来自家薬籠
27巻2号(2017年2月発行)
特集 The総合診療ベーシックス—白熱!「総合診療フェスin OKINAWA」ライブ・レクチャー! 一挙公開 フィジカル動画付!
27巻1号(2017年1月発行)
特集 総合診療の“夜明け”—キーマンが語り尽くした「来し方、行く末」
26巻12号(2016年12月発行)
特集 これでパッチリ! 眼の健康問題
26巻11号(2016年11月発行)
特集 続・しびれるんです!
26巻10号(2016年10月発行)
特集 内科診療を劇的に変える“まとめ”の達人
26巻9号(2016年9月発行)
特集 症状・症候別 エコーを使った診断推論─Point-of-Care超音波
26巻8号(2016年8月発行)
特集 The 初診外来
26巻7号(2016年7月発行)
特集 感染症ケアバンドル・チェックリスト
26巻6号(2016年6月発行)
特集 “賢い処方”と“ナゾ処方”
26巻5号(2016年5月発行)
特集 しびれるんです!─知っておくべきシビレル疾患
26巻4号(2016年4月発行)
特集 ケースとクイズで総ざらい! 街場の2型糖尿病治療
26巻3号(2016年3月発行)
特集 こんな時は漢方でしょう!
26巻2号(2016年2月発行)
特集 フィジカル改革宣言! ──診断からフォローアップまで
26巻1号(2016年1月発行)
特集 妊婦・褥婦が一般外来に来たら─エマージェンシー&コモンプロブレム
25巻12号(2015年12月発行)
特集 外来で「複数の疾患」をもつ患者を診る─マルチモビディティの時代のプライマリ・ケア
25巻11号(2015年11月発行)
特集 レアだけど重要な「痛み」の原因─システム1診断学
25巻10号(2015年10月発行)
特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 2
25巻9号(2015年9月発行)
特集 診断ピットフォール10選─こんな疾患,見逃していませんか?
25巻8号(2015年8月発行)
特集 健診データで困ったら─こんな検査結果を持ってこられたら
25巻7号(2015年7月発行)
特集 ここを知りたい!頭部外傷初期対応・慢性期ケア
25巻6号(2015年6月発行)
特集 高齢者救急の落とし穴─紹介する時,される時
25巻5号(2015年5月発行)
特集 咳を聴きとり,咳を止める
25巻4号(2015年4月発行)
特集 関節が痛いんです!─コモンからレアものまでの診断と治療
25巻3号(2015年3月発行)
特集 神経難病ケアのコペルニクス的転回
25巻2号(2015年2月発行)
特集 総合医のためのスポーツ医学ベーシックス
25巻1号(2015年1月発行)
特集 動悸・息切れ─ヤバい病気の見つけ方 そして見つからなかった時の対処法
