第Ⅰ章「カリスマ達のレクチャーの極意」
▼まずは「医師編」として、3人のスーパードクター、林寛之先生・山中克郎先生・藤沼康樹先生に、誰が聞いても惹き込まれるレクチャーのコツを披露してもらいました。また(ご自身の過去の反省点や失敗談などを踏まえ)レクチャーをする際に「これだけは必ず意識していること!」もご教授いただきます。〉〉〉pp.1438〜1445
▼さらに「非医療者編」として、ミュージカル俳優、落語家、ソプラノ歌手、コミュニティデザイナーといった様々な職種の方々から、自身の思いを相手に届けて、心に響かせる術を伝授いただきました。〉〉〉pp.1446〜1455
雑誌目次
総合診療32巻12号
2022年12月発行
雑誌目次
特集 レクチャーの達人—とっておきの生ライブ付き!
扉 フリーアクセス
著者: 坂本壮 , 髙橋宏端 , 鎌田一宏
ページ範囲:P.1436 - P.1437
【第Ⅰ章:カリスマ達のレクチャーの極意 医師編】
❶プレゼンはエンタメだぁ!
著者: 林寛之
ページ範囲:P.1438 - P.1440
プレゼンテーションは誰のため?
「スティーブ・ジョブスのようなプレゼンができるようになりたい!」「ガー・レイノルズのような美しいスライドを背景に話してみたい!」などなど、“プレゼンテーションの神”はとても格好いい。しかし、格好いいプレゼンテーションに憧れるのは理解できるが、本来プレゼンテーションは誰のためにあるのだろうか?
はい、それはもちろん聴講者のため。…わかりきったことだけど、わかっていない…(笑)。
❷ちょっと「変」なレクチャーを楽しむ
著者: 藤沼康樹
ページ範囲:P.1442 - P.1443
多領域への越境
筆者は基本的にフルタイムの家庭医であり、地域医療現場の臨床家であり、家庭医療に関する指導医でもある。そして、医師、医学生、その他の医療介護系職種の方たちからレクチャーを求められる機会が多い。求められるテーマとしては、個別疾患の診断や治療に関するものは少なく、むしろ総論的な内容、領域横断的な問題に関するものがほとんどである。たとえば、「総合診療・家庭医療とは何か?」「地域基盤型医学教育とは何か?」「これからの日本の医療の行く末は?」といった医療論、教育論、政策論に関するものがある。またこの数年、「多疾患併存」「未分化健康問題」「複雑困難事例」「下降期慢性疾患」といった健康問題の構造的特徴に関するレクチャーも求められる機会が増えている。しかし、「高血圧症治療の最近の動向」「めまいの診かた」「うつ病の認知行動療法」といったタイプのテーマに関する依頼については、筆者はお断りしている。したがって、明日からの診療にすぐ活用できる知識やスキルを提供するといったレクチャーはしていない。
❸レクチャーの極意
著者: 山中克郎
ページ範囲:P.1444 - P.1445
事前準備はしっかりと
◦まず講義対象がどのような人々なのかを確認しよう。たとえば医学生を対象とした講義で稀な疾患のことを詳細に話すと、医学生は混乱して誰も講義に関心を持たなくなってしまう。しかし簡単なことばかりの繰り返しでは聴衆を飽きさせてしまう。「今回の講義はどのような人が対象か、聴衆は何に興味を持っているのか」の見極めが重要である。
◦よくある間違いは、自分の持つすべての知識を与えようとすることである。「この講義で強調したいことは何なのか」のポイントをはっきりさせる。講義時間が50分なら、50枚のスライドを作ることを原則としている。私はゆっくりとしか話せないので、それ以上作ると全部のスライドを説明できなくなってしまう。時間がなくなり説明をほとんどしないままスライドを先送りすることはできるだけ避けたい。急いでたくさんのことを話すと講師は満足するが、聞いている人の記憶にはほとんど残らない。
【第Ⅰ章:カリスマ達のレクチャーの極意 非医療者編】
❹今この瞬間を生きる
著者: 今井美範
ページ範囲:P.1446 - P.1447
ミュージカルとの出合い
私がミュージカルの世界に踏み込んだのは2002年のことだった。まだ19歳だった私は右も左もわからず、稽古について行くのに必死だったことを思い出す。私にとっては、劇団四季が初めての仕事場で、『マンマミーア』という演目が初めての作品だった。稽古初日に主役の方が台本をほぼ見ずに“本読み”(出演者が脚本を読み合わせること)に参加している姿を見て、驚いたと同時に、プロの世界の厳しさを垣間見た気がした。その時、私は事前に台本を読んでもいなければ、楽譜にも目を通していなかったのだ。
プロの世界の厳しさをまざまざと実感したのは、これだけではない。よく生前、浅利慶太先生が「慣れだれ崩れ=去れ」と口になさっていた。劇団四季ではミュージカル『ライオンキング』を含め、たくさんの作品がロングラン公演されていて、役者たちは何十回、何百回と同じ役を演じることがある。これは、契約が1年だったり、契約が伸びて2、3年同じ作品に関わることになるためだが、そうすると、毎回新鮮な気持ちで行うのが難しくなっていく。その役に慣れることはとても大事なことで、いい意味で作品に慣れて、慣れることでその役をもっと深めることができるのだが、その慣れが“こなす”慣れになると、だんだんとだれて、崩れていくことになる。そうならないために、ロングラン公演に関わっていた時は、かなり気を遣ったものだ。
❺笑ってもらえることの喜びを求めて
著者: 三遊亭とむ
ページ範囲:P.1448 - P.1450
私は、「笑点」のピンクの着物でおなじみの三遊亭好楽の6番弟子で、三遊亭とむと申します。ひらがなで“とむ”と書きます。お笑い芸人から落語家に転身しました。落語界には見習い、前座、二つ目、真打という位がありまして、私は今は二つ目です。“不祥事がなければ”という条件つきで、来年真打になることが内定しています。
❻自身の想いを歌に乗せ、聴く人の心に美しく届ける術
著者: 平井富司子
ページ範囲:P.1451 - P.1453
歌の人生の始まり
そもそも父がピアノを買ってくれたことが、私の音楽の世界の始まりでした。幼い頃の私は、走ったら転ぶ、勉強したらビリと、まさに劣等生。そんな時、音楽は常に私を孤独から守ってくれる存在でした。高校卒業間近、「音楽大学であれば大学進学の可能性がある」と言われ、ピアノで大学受験に挑みました。他のクラスメイトよりは得意な分野でしたが、ここでも失敗。翌年の入学を目指した浪人時代に、予備校で「歌がいいのではないか? ピアノだけでなく、歌もできれば可能性がさらに広がる」と言われ、そこから私の歌の人生が始まったのです。
❼“私”がレクチャーする時に意識していること
著者: 山崎亮
ページ範囲:P.1454 - P.1455
前提について
レクチャーについて考える時、前提として意識しているのは「話し手と聞き手には、それぞれいろんなタイプがいる」ということです。
まずは話し手について。あなたと私では、年齢も性別も専門分野も言葉遣い(方言)も違います。髪型も服装も体格も態度も違うでしょう。だから、私のやり方があなたにも当てはまるとは言い切れません。自分は聞き手から「どう見られているのか」を自覚することが、自分なりのレクチャーを見つける助けになるでしょう。
【第Ⅱ章:My Best レクチャー講義録「7人の“My Bestレクチャー”15分1本勝負!」総論】
レクチャー概論
著者: 坂本壮 , 髙橋宏端 , 鎌田一宏
ページ範囲:P.1456 - P.1461
Introduction
レクチャーの方法を習ったことがあるでしょうか? コロナ禍となりオンラインでのレクチャーを聴く機会が増え、うまいレクチャー、いまいちなレクチャーをたくさん目にしていることでしょう。私自身レクチャーを行う機会は多いのですが、なかなか満足のいくものが実践できずに、日々頭を悩ませています。もちろん臨床現場がメインではありますが、日々の診療に役立つ情報を伝えたり、診療のレベルアップにもつながるレクチャーをやるからには、質を高めたいですよね。
本稿では、誰もが実践できるレクチャーのポイントを整理します。絶対的なものではないものもありますが、“まずはここから”的な内容を記載していますので、ぜひ意識してみてください。
【第Ⅱ章:My Best レクチャー講義録「7人の“My Bestレクチャー”15分1本勝負!」】
❻臨床の中の病理—臨床画像・病理対比
著者: 市原真
ページ範囲:P.1486 - P.1489
【対象】
❶ 医学生。❷ 15年前に元・国立がん研究センター(以下、国がん)中央病院病理部にてチーフレジデント(以下、チーレジ)として研修をされていた皆さん。
❼みんなに知っておいてほしい介護保険の話
著者: 橋本忠幸
ページ範囲:P.1490 - P.1493
【対象】
初期研修医。聴衆は、研修医1年目がメイン。必須のレクチャーのためモチベーションはバラバラ。
Editorial
“他者に伝える”スキルと秘訣と醍醐味と フリーアクセス
著者: 坂本壮 , 髙橋宏端 , 鎌田一宏
ページ範囲:P.1435 - P.1435
今年10月、帝国劇場ではミュージカル“エリザベート”が開幕した。ミュージカルは多少のアドリブはあるものの、基本的には台詞や歌詞は決まっている。何度観たって大きな変化はない。しかし、“エリザベート”は何度も観てしまう。
2017年、私は髙橋先生・鎌田先生と共通の知人を通じて出会い、意気投合。その後、青木眞先生(p.1414)宅で手作りカレーをいただきながら、「一緒に活動(“三銃士”と命名)すると、面白いのではないか」と青木先生から後押しされ、私たちは動き始めた。この“三銃士”の活動の1つにレクチャーシリーズがある。15分のレクチャーを6〜8名でつないで行うというものだ。他者のレクチャーから得られるものは非常に多い。内容はもちろん、伝え方やスキルなども。そう、今回の特集“レクチャーの達人”になるための珠玉の16のTips(p.1461)が、ここでまとめられた。
ゲストライブ〜Improvisation〜・20
カリスマティーチャーズ・インタビュー三連弾!—❶“感染症診療の原則”を話し続けて/❷レクチャースタイル確立までの道のり/❸自身の専門分野を非専門医(職)へ伝える
著者: 青木眞 , 髙橋宏瑞 , 徳田安春 , 鎌田一宏 , 仲田和正 , 坂本壮
ページ範囲:P.1413 - P.1426
長年、レクチャーを通じて多くの人々に影響を与えてきた青木先生、徳田先生、仲田先生。
その熱意はどこからくるのか? 人を動かすレクチャーの秘訣とは?
本特集企画者の髙橋宏端先生、鎌田一宏先生、坂本壮先生がそれぞれ聞き手となり、教育に関わり続けながら自身も成長していくための術などに迫ります。
カリスマティーチャーたちの豪華インタビュー三連弾をお楽しみください!(編集室)
What's your diagnosis?[240]
統制がとれません!
著者: 古川智偉 , 杉本雪乃 , 大矢亮 , 藤本卓司
ページ範囲:P.1430 - P.1434
病歴
患者:アルコール依存症・肝硬変で訪問看護を利用している48歳、女性
主訴:右腕が暴れる
現病歴:入院9日前から、右前腕が自分の意思とは無関係に動くようになった。腕は肘から先が小さく揺れるように動き、時折つったようになった。頻度は1時間に1回で、1回あたり10秒ほど持続。8日前に近医で低Na血症を指摘され、毎日ビタミン入りの点滴を施行。その後も右前腕の動きは徐々に悪化。6日前には右前腕は“より大きくブンブン暴れるような”動きになり、頻度も1時間に2〜3回に増加、1回あたり20秒ほど持続。3日前より寝ている時以外、右前腕が暴れている状態になった。1日前に右上腕を自分で動かせなくなったため、当院に紹介となった。
ROS(-):発熱、寝汗、頭痛、複視、嚥下困難、構音障害、歩行障害、失神、嘔気・嘔吐、下痢
既往歴:2型糖尿病(インスリンを使用していたが、食事量低下で2カ月前より中止)、アルコール性肝硬変・アルコール依存症(2年前から)、肝性脳症・食道静脈瘤破裂(4カ月前)
内服薬:プレガバリン50mg、ラベプラゾール10mg、ナルフラフィン2.5μg、ロキソプロフェン120mg、ジクロフェナク25mg
アレルギー:レボフロキサシン、蟹、牡蠣
嗜好歴:喫煙10〜20本/日×28年。飲酒4カ月前から禁酒(過去は浴びるほど)
高齢者診療スピードアップ塾|効率も質も高める超・時短術・12【最終回】
3つの「実践術」+2つの「根源力」=60分の時短診療に
著者: 増井伸高
ページ範囲:P.1494 - P.1496
本連載もいよいよ最終回! 最後に、これまでに解説した各論的テクニックを総括し、総論的に「時短診療」を解説します。今回の技術を習得すれば、「スピードアップ塾」は卒業です。免許皆伝となれば、平均「60分」の時短診療も可能です。そのノウハウをチェックしてみましょう。
オール沖縄!カンファレンス|レジデントの対応と指導医の考えVer.2.0・71
無酸素運動後の腰痛には“腰”注意!?
著者: 板垣健介 , 酒井達也 , 徳田安春
ページ範囲:P.1498 - P.1501
CASE
患者:40歳、男性。
主訴:左腰部痛。
現病歴:X-4日より左腰部痛を認めた。X-1日に左腰部痛が改善しないため前医を受診し、急性腎盂腎炎の疑いで当院へ精査加療目的に紹介受診となった。
既往歴:高尿酸血症。
家族歴:特記事項なし。
内服歴:アロプリノール200mg 3錠/毎食後。
アレルギー歴:特記事項なし。
生活歴:喫煙は10本/日のcurrent smoker。飲酒はハイボールをコップ4〜5杯/日。仕事は工場の備品整備業。
Dr.上田剛士のエビデンス実践レクチャー!医学と日常の狭間で|患者さんからの素朴な質問にどう答える?・33
お風呂で指に皺ができるのはなぜですか?
著者: 上田剛士
ページ範囲:P.1502 - P.1504
患者さんからのふとした質問に答えられないことはないでしょうか? 素朴な疑問ほど回答が難しいものはありませんが、新たな気づきをもたらす良問も多いのではないでしょうか? 本連載では素朴な疑問に、文献的根拠を提示しながらお答えします!
【エッセイ】アスクレピオスの杖—想い出の診療録・32
一期一会
著者: 志水太郎
ページ範囲:P.1506 - P.1507
本連載は、毎月替わる著者が、これまでの診療で心に残る患者さんとの出会いや、人生を変えた出来事を、エッセイにまとめてお届けします。
【臨床小説—第二部】後悔しない医者|今と未来をつなぐもの・第32話
許しを得た医者
著者: 國松淳和
ページ範囲:P.1520 - P.1526
前回までのあらすじ 今月のナゾ
患者は16歳・男性。この春、長崎市の進学校に入学したが、4月下旬から体がだるくて朝起きられず、頭痛もあって「不登校」になってしまった。親戚の「おばあちゃん」が大家をしている市内の下宿屋から、療養のため7月に帰島して以来、左座の外来を定期受診している。検査に異常は認められず、一時診療は行き詰まったが、少量のルラシドンと苓桂朮甘湯を処方すると徐々に回復。しかし頭痛が残り、2学期になっても登校できずにいた。すると向後から、「体を動かすのに慣れるため、外来の掃除をしにきてもらおう」と異例の提案があり、ある日、患者と向後が外来で偶然顔を合わせることになって…。
前回、向後は「思春期診療」ならではのクリニカルな技法を、2つ提示した。1つは、次回予約の受診時刻をあえて定めないこと。もう1つは、思春期の子どもの性質を「循環気質」とみたて、躁うつ病への治療を希釈して対症療法的に試みることであった。そして今回、患者は思わぬ形で回復する。彼らは、いかにして癒されるのか?
#総合診療
#今月の特集関連本❶ フリーアクセス
ページ範囲:P.1441 - P.1441
#今月の特集関連本❷ フリーアクセス
ページ範囲:P.1467 - P.1467
#今月の特集関連本❸ フリーアクセス
ページ範囲:P.1473 - P.1473
#今月の連載関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.1496 - P.1496
#今月の連載関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.1521 - P.1521
#医学書院の新刊 フリーアクセス
ページ範囲:P.1510 - P.1512
#参加者募集 フリーアクセス
ページ範囲:P.1513 - P.1513
#書評:救急外来、ここだけの話 フリーアクセス
著者: 杉田学
ページ範囲:P.1515 - P.1515
2021年8月。われわれ東京で働く救急医にとって、普段の救急医療に加えて新型コロナウイルス感染症の対応、東京2020オリンピック・パラリンピックの医療救護体制への参加が加わり、前年から一貫してとても忙しい毎日であった。医療従事者のワクチン接種はおおむね完了したが、自由に外出できる状況ではなく、日々ストレスを感じていた。私は救急医であり、また感染対策室長も務めているため、毎日新たな感染症関連のエビデンスを収集し発信していた。そんななか、坂本壮先生から、田中竜馬先生と編集にかかわったという本書を紹介され手に取った。
『救急外来、ここだけの話』。その題名に釣られてエッセイを読むようにページをめくってみたら、なんと中身は“超硬派”であった。そうか「ここだけの話」とは、スキャンダルでもオモシロ経験談でもなく、専門医がもっている「得意分野のピカイチネタ」なのかと納得した。特筆すべきはその読みやすさで、エビデンスが確立していることだけでなくcontroversialな話題にも触れ、「救急外来での最初の数時間をどう過ごすか」に焦点を当てている。「忙しい」「忙しい」という毎日ではあるが、勤務時間には終わりがくる。飲みにも行けず家で過ごす間に読破できてしまった。面白かったし、パクって研修医に話してやろう、というネタも増えた。
#書評:—チーフレジデント直伝!—デキる指導医になる70の方法—研修医教育・マネジメント・リーダーシップ・評価法の極意 フリーアクセス
著者: 西澤俊紀
ページ範囲:P.1516 - P.1516
本書は発売直後から話題になり、また私がお世話になった先生方が執筆された書籍のため、ぜひ購入して読もうと思っていたところに、書評の依頼をいただきました。
著者の松尾貴公先生や岡本武士先生は、聖路加国際病院で内科チーフレジデントを経験されたあと、ご自身の専門の道(感染症科と消化器内科)にそれぞれ進まれましたが、専門分野の知識のみならず幅広い内科的知識を教えてくださり、また院内の教育や医療安全、システムをよりよくしようというカリスマ性に溢れ、私たち聖路加国際病院の研修医にとってロールモデルでした。そのような偉大な先生方が経験された「内科チーフレジデント」は、憧れのキャリアでした。
#書評:—外来・病棟・地域をつなぐ—ケア移行実践ガイド フリーアクセス
著者: 小西竜太
ページ範囲:P.1517 - P.1517
本書のケア移行をすべての医療・介護従事者が心がけたら、この国の健康寿命、患者さんのQOLや幸福度、そして医療・介護従事者のやりがい、すべてが向上するに違いない。
本書には医療・介護現場におけるケア移行という観点で、望ましい情報コミュニケーションの実践知が詰め込まれている。特に素晴らしいのは、相手を思いやる精神論や顔の見える関係づくり、コミュニケーションテクニックを披露するものではなく、あくまでも「ケア移行に必要な情報整理」に絞って解説している点である。さらには、多様な現場やケアプロセスにおけるアセスメントツールも紹介されており、情報の精度をさらに高めることができるだろう。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.1428 - P.1429
『総合診療』編集方針 フリーアクセス
ページ範囲:P.1427 - P.1427
1991年に創刊した弊誌は、2015年に『JIM』より『総合診療』に誌名を変更いたしました。その後も高齢化はさらに進み、社会構造や価値観、さらなる科学技術の進歩など、日本の医療を取り巻く状況は刻々と変化し続けています。地域医療の真価が問われ、ジェネラルに診ることがいっそう求められる時代となり、ますます「総合診療」への期待が高まってきました。これまで以上に多岐にわたる知識・技術、そして思想・価値観の共有が必要とされています。そこで弊誌は、さらなる誌面の充実を図るべく、2017年にリニューアルをいたしました。本誌は、今後も下記の「編集方針」のもと、既存の価値にとらわれることなく、また診療現場からの要請に応え、読者ならびに執筆者のみなさまとともに、日本の総合診療の新たな未来を切り拓いていく所存です。
2018年1月 『総合診療』編集委員会
読者アンケート
ページ範囲:P.1509 - P.1509
『総合診療』バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.1528 - P.1529
お得な年間購読のご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.1529 - P.1530
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.1531 - P.1532
「総合診療」 第32巻 総目次 フリーアクセス
ページ範囲:P. - P.
基本情報
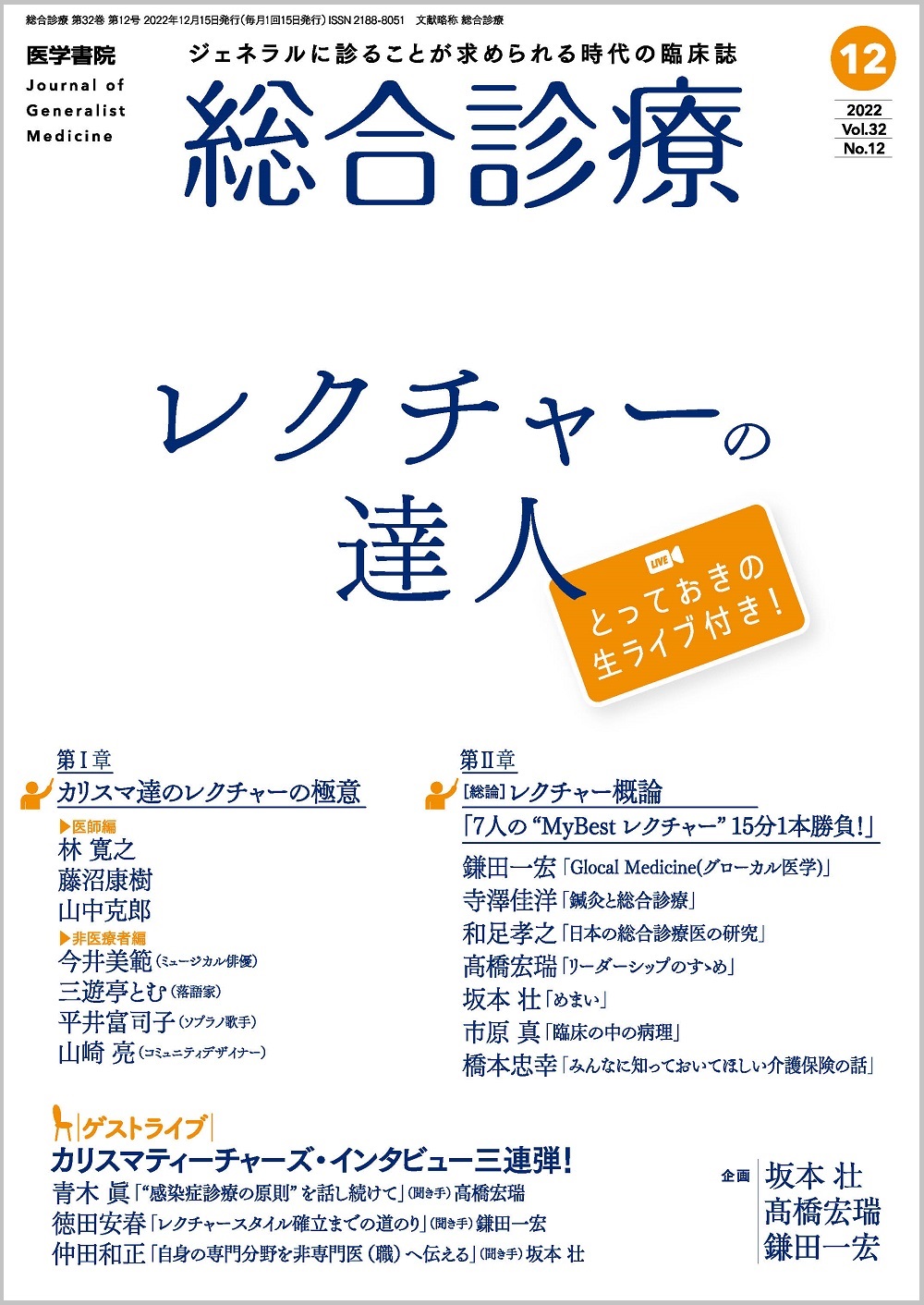
バックナンバー
34巻12号(2024年12月発行)
特集 妊婦・褥婦が外来に来たらUpdate—症状対応からワクチン・プラネタリーヘルスまで
34巻11号(2024年11月発行)
特集 電子カルテとベッドサイドの壁を打ち破る!—患者情報の「言語化」への挑戦
34巻10号(2024年10月発行)
特集 化かしが得意なカメレオンな疾患を捕まえろ!—よくある騙され方のゲシュタルト
34巻9号(2024年9月発行)
特集 今伝えたいクリニカル・パール—つくり方、使い方、活かし方
34巻8号(2024年8月発行)
特集 ストーン・ウォーズ 果てしなき“石”と医師との闘い
34巻7号(2024年7月発行)
特集 どうする!? 健診異常—これってホントに異常なの? どう説明する?
34巻6号(2024年6月発行)
特集 医師のウェルビーイング
34巻5号(2024年5月発行)
特集 —優柔不断にサヨウナラ!—あなたの「臨床判断」を高めるケーススタディ11選
34巻4号(2024年4月発行)
特集 困ったときの漢方—この症状に役立ちます!
34巻3号(2024年3月発行)
特集 —え、ウソ!実は◯◯だった!?—“コモンディジーズ”の診断ピットフォール
34巻2号(2024年2月発行)
特集 日常診療で出合う筋骨格疾患—脳神経内科と整形外科からのアプローチ
34巻1号(2024年1月発行)
特集 —“体験型”臨床クイズで習得する!—フィジカル診断エクセレンス
33巻12号(2023年12月発行)
特集 海の外へ渡る航行者を診る—アウトバウンドにまつわるetc.
33巻11号(2023年11月発行)
特集 —続・総合診療外来に“実装”したい—最新エビデンスMy Best 3
33巻10号(2023年10月発行)
特集 ○×クイズ110問!日常診療アップグレード—Choosing WiselyとHigh Value Careを学ぼう
33巻9号(2023年9月発行)
特集 ジェネラリストのための「発達障害(神経発達症)」入門
33巻8号(2023年8月発行)
特集 都市のプライマリ・ケア—「見えにくい」を「見えやすく」
33巻7号(2023年7月発行)
特集 “消去法”で考え直す「抗菌薬選択」のセオリー—広域に考え、狭域に始める
33巻6号(2023年6月発行)
特集 知っておくべき!モノクロな薬たち(注:モノクローナル抗体の話ですよ〜)
33巻5号(2023年5月発行)
特集 —疾患別“イルネススクリプト”で学ぶ—「腹痛診療」を磨き上げる22症例
33巻4号(2023年4月発行)
特集 救急対応ドリル—外来から在宅までの60問!
33巻3号(2023年3月発行)
特集 —自信がもてるようになる!—エビデンスに基づく「糖尿病診療」大全—新薬からトピックスまで
33巻2号(2023年2月発行)
特集 しびれQ&A—ビビッとシビれるクリニカルパール付き!
33巻1号(2023年1月発行)
特集 COVID-19パンデミック 振り返りと将来への備え
32巻12号(2022年12月発行)
特集 レクチャーの達人—とっておきの生ライブ付き!
32巻11号(2022年11月発行)
特集 不定愁訴にしない“MUS”診療—病態からマネジメントまで
32巻10号(2022年10月発行)
特集 日常診療に潜む「処方カスケード」—その症状、薬のせいではないですか?
32巻9号(2022年9月発行)
特集 総合診療・地域医療スキルアップドリル—こっそり学べる“特講ビデオ”つき!
32巻8号(2022年8月発行)
特集 こんなところも!“ちょいあて”エコー—POCUSお役立ちTips!
32巻7号(2022年7月発行)
特集 —どうせやせない!? やせなきゃいけない??苦手克服!—「肥満」との向き合い方講座
32巻6号(2022年6月発行)
特集 総合診療外来に“実装”したい最新エビデンス—My Best 3
32巻5号(2022年5月発行)
特集 「診断エラー」を科学する!—セッティング別 陥りやすい疾患・状況
32巻4号(2022年4月発行)
特集 えっ、これも!? 知っておきたい! 意外なアレルギー疾患
32巻3号(2022年3月発行)
特集 AI時代の医師のクリニカル・スキル—君は生き延びることができるか?
32巻2号(2022年2月発行)
特集 —withコロナ—かぜ診療の心得アップデート
32巻1号(2022年1月発行)
特集 実地医家が楽しく学ぶ 「熱」「炎症」、そして「免疫」—街場の免疫学・炎症学
31巻12号(2021年12月発行)
特集 “血が出た!”ときのリアル・アプローチ—そんな判断しちゃダメよ!
31巻11号(2021年11月発行)
特集 Q&Aで深める「むくみ診断」—正攻法も!一発診断も!外来も!病棟も!
31巻10号(2021年10月発行)
特集 医師の働き方改革—システムとマインドセットを変えよう!
31巻9号(2021年9月発行)
特集 「検査」のニューノーマル2021—この検査はもう古い? あの新検査はやるべき?
31巻8号(2021年8月発行)
特集 メンタルヘルス時代の総合診療外来—精神科医にぶっちゃけ相談してみました。
31巻7号(2021年7月発行)
特集 新時代の「在宅医療」—先進的プラクティスと最新テクノロジー
31巻6号(2021年6月発行)
特集 この診断で決まり!High Yieldな症候たち—見逃すな!キラリと光るその病歴&所見
31巻5号(2021年5月発行)
特集 臨床医のための 進化するアウトプット—学術論文からオンライン勉強会、SNSまで
31巻4号(2021年4月発行)
特集 消化器診療“虎の巻”—あなたの切実なギモンにズバリ答えます!
31巻3号(2021年3月発行)
特集 ライフステージでみる女性診療at a glance!—よくあるプロブレムを網羅しピンポイントで答えます。
31巻2号(2021年2月発行)
特集 肺炎診療のピットフォール—COVID-19から肺炎ミミックまで
31巻1号(2021年1月発行)
特別増大特集 新型コロナウイルス・パンデミック—今こそ知っておきたいこと、そして考えるべき未来
30巻12号(2020年12月発行)
特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き) Part 2
30巻11号(2020年11月発行)
特集 診断に役立つ! 教育で使える! フィジカル・エポニム!—身体所見に名を残すレジェンドたちの技と思考
30巻10号(2020年10月発行)
特集 —ポリファーマシーを回避する—エビデンスに基づく非薬物療法のススメ
30巻9号(2020年9月発行)
特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【感染症・内分泌・整形外科 編】
30巻8号(2020年8月発行)
特集 マイナーエマージェンシー門外放出—知っておくと役立つ! テクニック集
30巻7号(2020年7月発行)
特集 その倦怠感、単なる「疲れ」じゃないですよ!—筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群とミミック
30巻6号(2020年6月発行)
特集 下降期慢性疾患患者の“具合”をよくする—ジェネラリストだからできること!
30巻5号(2020年5月発行)
特集 誌上Journal Club—私を変えた激アツ論文
30巻4号(2020年4月発行)
特集 大便強ドリル—便秘・下痢・腹痛・消化器疾患に強くなる41問!
30巻3号(2020年3月発行)
特集 これではアカンで!こどもの診療—ハマりがちな11のピットフォール
30巻2号(2020年2月発行)
特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【循環器・消化器・神経疾患編】
30巻1号(2020年1月発行)
特集 総合診療医の“若手ロールモデル”を紹介します!—私たちはどう生きるか
29巻12号(2019年12月発行)
特集 困っている“あなた”に届く 認知症診療
29巻11号(2019年11月発行)
特集 臨床写真図鑑 レアな疾患編—見逃したくない疾患のコモンな所見
29巻10号(2019年10月発行)
特集 教えて!医師のためのビジネス・スキル
29巻9号(2019年9月発行)
特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き)
29巻8号(2019年8月発行)
特集 —ノーモア見逃し—日常の検査と画像に潜むピットフォール
29巻7号(2019年7月発行)
特集 リウマチ・膠原病ミミック症例帖—“膠原病っぽくみえてしまう疾患たち”にだまされない!
29巻6号(2019年6月発行)
特集 皮膚科診療エクササイズ—1枚の写真から
29巻5号(2019年5月発行)
特集 一般外来で診断できたら「えっへん!」な疾患38
29巻4号(2019年4月発行)
特集 “ナゾ”の痛み診療ストラテジー|OPQRSTで読み解く
29巻3号(2019年3月発行)
特集 —あなたのギモンに答えます!—循環器診療のハードルを下げるQ&A31
29巻2号(2019年2月発行)
特集 意外な中毒、思わぬ依存、知っておきたい副作用—一般外来で!OTCも処方薬も!
29巻1号(2019年1月発行)
特集 教えて検索!—膨大な医学情報を吟味・整理するスキル
28巻12号(2018年12月発行)
特集 こんなときこそ漢方を!
28巻11号(2018年11月発行)
特集 日本一マジメな「おしっこドリル」—今これだけは押さえておきたい腎・泌尿器のモンダイ
28巻10号(2018年10月発行)
特集 クリニカル・パールPremium!—憧れのカリスマ医師はかく語りき
28巻9号(2018年9月発行)
特集 オンコ・ジェネラリスト—「がん」に強い総合診療医をめざして
28巻8号(2018年8月発行)
特集 80歳からの診療スタンダードUp to Date—Silver Standard
28巻7号(2018年7月発行)
特集 この薬だけは押さえておきたい! 総合診療医のためのSpecialist Drug 40
28巻6号(2018年6月発行)
特集 聴診・触診×エコーで診断推論!—Point-of-Care超音波(POCUS)の底力
28巻5号(2018年5月発行)
特集 “一発診断”トレーニング問題集—懸賞論文「GM Clinical Pictures」大賞発表!
28巻4号(2018年4月発行)
特集 感染症外来診療「賢医の選択」—検査・経口薬・ワクチンをどう使えばいいんですか?
28巻3号(2018年3月発行)
特集 糖尿病のリアル—現場の「困った!」にとことん答えます。
28巻2号(2018年2月発行)
特集 頭痛患者で頭が痛いんです!
28巻1号(2018年1月発行)
特集 シン・フィジカル改革宣言!—私の“神技”伝授します。
27巻12号(2017年12月発行)
特集 小児診療“苦手”克服!!—劇的Before & After
27巻11号(2017年11月発行)
特集 今そこにある、ファミリー・バイオレンス|Violence and Health
27巻10号(2017年10月発行)
特集 めまいがするんです!─特別付録Web動画付
27巻9号(2017年9月発行)
特集 うつより多い「不安」の診かた—患者も医師も安らぎたい
27巻8号(2017年8月発行)
特集 見逃しやすい内分泌疾患─このキーワード、この所見で診断する!
27巻7号(2017年7月発行)
特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 3 カリスマ編
27巻6号(2017年6月発行)
特集 「地域を診る医者」最強の養成法!
27巻5号(2017年5月発行)
特集 コミュニケーションを処方する—ユマニチュードもオープンダイアローグも入ってます!
27巻4号(2017年4月発行)
特集 病歴と診察で診断できない発熱!—その謎の賢い解き方を伝授します。
27巻3号(2017年3月発行)
特集 これがホントに必要な薬40—総合診療医の外来自家薬籠
27巻2号(2017年2月発行)
特集 The総合診療ベーシックス—白熱!「総合診療フェスin OKINAWA」ライブ・レクチャー! 一挙公開 フィジカル動画付!
27巻1号(2017年1月発行)
特集 総合診療の“夜明け”—キーマンが語り尽くした「来し方、行く末」
26巻12号(2016年12月発行)
特集 これでパッチリ! 眼の健康問題
26巻11号(2016年11月発行)
特集 続・しびれるんです!
26巻10号(2016年10月発行)
特集 内科診療を劇的に変える“まとめ”の達人
26巻9号(2016年9月発行)
特集 症状・症候別 エコーを使った診断推論─Point-of-Care超音波
26巻8号(2016年8月発行)
特集 The 初診外来
26巻7号(2016年7月発行)
特集 感染症ケアバンドル・チェックリスト
26巻6号(2016年6月発行)
特集 “賢い処方”と“ナゾ処方”
26巻5号(2016年5月発行)
特集 しびれるんです!─知っておくべきシビレル疾患
26巻4号(2016年4月発行)
特集 ケースとクイズで総ざらい! 街場の2型糖尿病治療
26巻3号(2016年3月発行)
特集 こんな時は漢方でしょう!
26巻2号(2016年2月発行)
特集 フィジカル改革宣言! ──診断からフォローアップまで
26巻1号(2016年1月発行)
特集 妊婦・褥婦が一般外来に来たら─エマージェンシー&コモンプロブレム
25巻12号(2015年12月発行)
特集 外来で「複数の疾患」をもつ患者を診る─マルチモビディティの時代のプライマリ・ケア
25巻11号(2015年11月発行)
特集 レアだけど重要な「痛み」の原因─システム1診断学
25巻10号(2015年10月発行)
特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 2
25巻9号(2015年9月発行)
特集 診断ピットフォール10選─こんな疾患,見逃していませんか?
25巻8号(2015年8月発行)
特集 健診データで困ったら─こんな検査結果を持ってこられたら
25巻7号(2015年7月発行)
特集 ここを知りたい!頭部外傷初期対応・慢性期ケア
25巻6号(2015年6月発行)
特集 高齢者救急の落とし穴─紹介する時,される時
25巻5号(2015年5月発行)
特集 咳を聴きとり,咳を止める
25巻4号(2015年4月発行)
特集 関節が痛いんです!─コモンからレアものまでの診断と治療
25巻3号(2015年3月発行)
特集 神経難病ケアのコペルニクス的転回
25巻2号(2015年2月発行)
特集 総合医のためのスポーツ医学ベーシックス
25巻1号(2015年1月発行)
特集 動悸・息切れ─ヤバい病気の見つけ方 そして見つからなかった時の対処法
