「診断エラー」に陥りやすい状況には特性やパターンがあることが、科学的に明らかになってきています。
それを予めわかっていさえすれば、防げるエラーもあるはずです。
そこで本特集では、診断エラー学における最近のトピックスである「situativity(状況性)」の視点から、「救急外来」「入院診療」「一般外来」「在宅診療」のセッティング別に、特にエラーを生じやすい疾患や医療関連合併症などについて、診断エラーに陥りやすい理由、早期診断・発見のための対策を各領域のエキスパートにご解説いただきました。
かつては「誤診=医者のミス・能力不足」とされ、語りづらい雰囲気もあった診断エラーを、科学的に解きほぐします。
雑誌目次
総合診療32巻5号
2022年05月発行
雑誌目次
特集 「診断エラー」を科学する!—セッティング別 陥りやすい疾患・状況
扉 フリーアクセス
著者: 綿貫聡
ページ範囲:P.544 - P.545
今月の「めざせ! 総合診療専門医!」問題
ページ範囲:P.617 - P.617
本問題集は、今月の特集のご執筆者に、執筆テーマに関連して「総合診療専門医なら知っておいてほしい!」「自分ならこんな試験問題をつくりたい!」という内容を自由に作成していただいたものです。力試し問題に、チャレンジしてみてください。
【総論】
「誤診」から「診断エラー」へ
著者: 和足孝之
ページ範囲:P.546 - P.551
Case
インフルエンザが大流行しており、救急外来は発熱患者で大混雑し、待ち時間が長く患者もスタッフもイライラしている。また、先ほど救急搬送の収容依頼が2件同時にきてしまった。あなたは、その隙間時間に外来診療もこなさなければならない。
患者:35歳、女性。生来健康。
現病歴:1日前からの発熱を主訴に、23時に救急外来を受診した。一緒に来院した2人の女児(6歳と2歳)は、どちらも1週間前にインフルエンザA型の診断を受けていた。当日の午前中に最寄りのクリニックを受診し、迅速検査では陰性であったが、病歴からおそらくインフルエンザだろうとの診断を受け、アセトアミノフェンを処方された。しかし、半日経っても解熱しないため受診したという。
体温38.5℃、呼吸数22回/分、脈拍数100回/分。インフルエンザ迅速検査を実施し、陰性を再度確認した。身体所見上はこれといった異常がないことを確認し、「クリニックの先生がおっしゃるように、検査は今回も陰性ですが、病歴からインフルエンザでよいと思います。そこまで心配せず、水分をとって、よく寝ましょう」と説明した。患者からは「そうですか。でも、なんか少し変で、点滴をしてくれませんか?」との訴えがあったが、食事がとれていればインフルエンザには点滴は不要であることを告げ、帰宅となった。
その患者は2日後に自施設へ救急搬送となり、急性前骨髄性白血病による播種性血管内凝固の病態で「脳出血」の診断を受けた。
【セッティングⅠ】救急外来
—オーバービュー—「救急外来」における診断エラー
著者: 國友耕太郎 , 原田拓
ページ範囲:P.552 - P.556
Case
大腿骨転子部骨折の背後に隠れていた消化管出血
患者:87歳、女性。施設入所中。
現病歴:転倒後に右股関節痛を訴え、体動困難となったため救急搬送された。救急外来は指導医1人・研修医2人で担当していたが、次々と患者が搬送され混雑していた。
転倒は目撃されておらず、本人は認知機能低下があり、転倒の原因ははっきりしなかった。血圧102/78mmHg、心拍数100回/分、体温36.8℃、呼吸数18回/分。血液検査はHb 10.6g/dL、MCV 93fL、BUN 26.5mg/dL、Cr 0.8mg/dL。軽度の貧血が認められたが、骨折で少し出血したのだろうと考え、次の急患対応に移った。
画像検査結果が出て「大腿骨転子部骨折」の所見が認められたため、整形外科にコンサルトし入院手続きが進んでいた。入院病棟にあがろうとしていた時に吐血しショックバイタルとなり、緊急の上部消化管内視鏡検査により「消化管出血」と診断された。過去の血液検査データを確認すると、1カ月前はHb 12.2g/dLだった。痛みの原因は大腿骨転子部骨折だと早期閉鎖してしまい、転倒の原因検索や軽度の貧血や頻脈について検討していなかった。
❶急性冠症候群/大動脈解離
著者: 川上将司
ページ範囲:P.557 - P.561
Case
患者:60歳、男性
既往歴:高血圧症、糖尿病、脂質異常症
現病歴:3日前に労作時胸痛が出現、10分で改善した。6時間前、勤務中に同様の労作時胸痛が出現し、15分で改善した。帰宅後に家族に勧められて救急外来を受診。受診時は胸痛なく、心電図でST変化も認めず、心臓超音波検査でも壁運動異常を認めなかった。心筋トロポニン値も正常範囲内であった。狭心症の可能性があるため、ニトログリセリンを処方し翌日の循環器科受診を指示した。帰宅後、安静時胸痛が出現、ニトログリセリンを使用したが改善なく、救急搬送された。心電図では前胸部誘導でST上昇が認められ、primary PCI(直接的経皮的冠動脈インターベンション)の方針となった。
❷くも膜下出血/脳梗塞
著者: 角替麻里絵 , 上田雅之
ページ範囲:P.562 - P.566
Case1
持続性頭痛のため独歩受診し、頭部CT陰性だったくも膜下出血の授乳中女性の一例
患者:34歳、女性。出産後4週。
既往歴:偏頭痛(スマトリプタン内服中)
現病歴:X日の夕食後、突然頭全体を殴られたような強い頭痛を自覚した。頭痛は若干の改善を認めるもその後も持続し、睡眠が十分とれなかった。X+2日に、スマトリプタンを内服しても改善しないため夫と救急外来を独歩で受診。救急外来担当医が頭部CTを撮影したが、明らかな頭蓋内出血は指摘できなかった。
「普段の偏頭痛発作とは頭痛の経過・性状・部位が異なる(突然発症、片側性や拍動性ではない、トリプタンが効かない)」という患者の訴えから、頭部MRIを撮影すると、FLAIR (fluid attenuated inversion recovery)で左頭頂葉の脳溝に沿った高信号を認めた。MRAでは明らかな動脈瘤を指摘できず、髄液検査でも細胞数・蛋白は正常であったが、赤血球上昇とキサントクロミーが認められた。経過から可逆性脳血管攣縮症候群による「くも膜下出血」を疑い、同日脳神経外科入院・脳神経内科併診とし、カルシウム拮抗薬静注/内服による加療を行いながら経過観察とした。X+14日、経過フォローの目的で撮影した頭部MRAで頭蓋内血管の広範な攣縮を認めた。頭痛・脳血管攣縮所見の改善と、SAHが消退傾向であることを確認し、X+46日に自宅退院となった。
【セッティングⅡ】入院診療
—オーバービュー—「入院診療」における診断エラー
著者: 栗原健
ページ範囲:P.567 - P.570
Case
患者:62歳、男性
現病歴:前日夜間に、腹痛のため救急外来を受診した。明らかな閉塞起点はなかったが、腸管拡張しているようにみえたため、暫定的に「麻痺性イレウス」として診断し入院加療となった。
翌日、入院診療チームが担当を引き継ぎ、救急外来での診断に則り、麻痺性イレウスとして治療を継続した。一方で、患者の腹痛は徐々に増悪した。最終的に入院2日目に急変し死亡した。死亡後の剖検で「上腸間膜動脈解離」が明らかになった。
❶院内発症静脈血栓塞栓症
著者: 中西俊就 , 小坂鎮太郎
ページ範囲:P.571 - P.574
Case
憩室出血で入院加療中に急性発症の呼吸困難を訴えた一例
患者:84歳、女性。入院前ADLは屋内自立、普通食でたまにむせこむ。BMI 28.2。
既往歴:慢性心不全、高血圧症
現病歴:憩室出血に対して保存的加療目的に入院中。年齢以外はリスクに乏しく、抗凝固薬や間欠的空気圧迫法などによる静脈血栓塞栓症の予防は行っていない。動くと苦しく、本人は離床を拒否して臥床傾向であった。
血便が消失したため、第3病日より低残渣食を再開した。第5病日、急性発症の呼吸困難と乾性咳嗽を認めた。体温37.8℃、脈拍数106回/分・整、血圧152/98mmHg、呼吸数24回/分、SpO2 92%(室内気)。身体所見は、入院時から認める左優位の下腿浮腫を認めるのみで、頸静脈怒張や心音など特に異常を認めず。胸部X線でも心拡大や浸潤影なし。担当医は、暫定診断として「誤嚥性肺炎」による軽度の心不全増悪の疑いとして、痰培養を提出して抗菌薬と利尿薬の投与を開始した。担当看護師より、痰の喀出もなく痰培養採取が困難と報告があったが、当直明けで疲れていた当直医は、違和感を感じず誤嚥性肺炎だと考えて痰培養採取も省略してよいと判断した。翌朝、血圧低下と酸素化低下の増悪を認め、造影CTを撮影したところ、左膝下静脈と肺動脈に血栓を認め、「急性肺血栓塞栓症」と診断した。
❷医療関連感染症
著者: 濵田洋平 , 青木洋介
ページ範囲:P.575 - P.578
Case1
肺炎やCOVID-19が疑われたが「カテーテル関連血流感染症」の診断に至った一例
患者:74歳、男性
既往歴:脳梗塞
病歴:咽頭がんの手術目的で入院となったが、術前に39℃台の発熱がみられた。脳梗塞と咽頭がんによる嚥下障害があったことと入院後まもないことから、「肺炎」もしくは「COVID-19(新型コロナウイルス感染症)」の可能性が考えられ、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)PCR検査の施行とスルバクタム・アンピシリンの投与が開始された。PCR検査は陰性であったが、血液培養2セットからメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(methicillin-resistant Staphylococcus aureus : MRSA)が分離され、「カテーテル関連血流感染症」の診断となり、バンコマイシンの投与で改善した。
❸画像診断レポートの確認不足
著者: 飯田茂晴
ページ範囲:P.579 - P.583
Case
腰背部痛を主訴に救急を受診した一例
患者:50代、男性
現病歴:血尿と腰背部痛を主訴に救急外来を受診。依頼した単純CTにて右尿管に結石を認めた(図1)。「右尿管結石症」と診断し、薬剤処方のうえ経過観察とした。しかし、依頼医が読まなかった画像診断レポートに「左腎がんの疑い」と記載されていた。
【セッティングⅢ】一般外来
—オーバービュー—「一般外来」における診断エラー
著者: 鋪野紀好
ページ範囲:P.584 - P.587
Case
感冒様症状・下痢で受診した一例
患者:19歳、男性
既往歴・家族歴:特記事項なし
現病歴:前日からの感冒様症状ならびに下痢のため、大病院(800床)の内科外来を受診した。下痢は昨日から水様便が1回のみで、腹痛の訴えはなかった。また、同様の患者とのシックコンタクトはない。
受診時バイタルサインは体温38.1℃、血圧102/56mmHg、脈拍数106回/分、呼吸数14回/分、SpO2 97%(室内気)。暫定的に「急性胃腸炎」と診断し帰宅指示としたが、その際の説明で「帰宅後に、息苦しさが出現したり、だるさが悪化してしまう場合は、他の原因の可能性も考えられるため、速やかに病院に電話をしてください」と伝えた。帰宅後の夜間に呼吸苦が出現。指示どおり救急外来を受診し、「急性心筋炎」の診断となった。
❶がん(悪性腫瘍)
著者: 下井辰徳
ページ範囲:P.588 - P.592
Case
患者:19歳、女性。生来健康。
現病歴:1カ月続く左大腿部の腫脹を自覚したため、近くの診療所を受診したが、「異常なし」と言われ様子をみた。さらに2週間で明らかな増大を自覚し、近医整形外科を受診したが、「なんでもない」と言われた。しかし、1週間後に疼痛と運動への支障が出現したため、再度整形外科を受診したところ、画像検査で大腿部に腫瘤を認め、大学病院の受診を推奨された。
大学病院の整形外科では左大腿の「悪性軟部腫瘍」の診断となり、「下肢切断以外の方法がない」と言われて当院へ紹介となった。当院の病理再評価によって「横紋筋肉腫」の診断となり、VAC療法(ビンクリスチン、アクチノマイシンD、シクロホスファミド)を開始し、腫瘍縮小ののちに患肢温存のうえ切除と放射線治療を行った。術後5年経過し、再発を認めない。
❷感染性心内膜炎
著者: 西口翔
ページ範囲:P.593 - P.596
Case
診療所を繰り返し受診した「不明熱」の一例
患者:40歳、女性
現病歴:入院6週間前に発熱を自覚し、近隣診療所を受診した。クラリスロマイシンと鎮咳薬を処方され、解熱した。4週間前に再度発熱を認めたため再診し、ガレノキサシン® 200mgを処方された。そして2週間前、再度37℃台の発熱を認め、当院紹介となった。悪寒戦慄および全身倦怠感あり。う歯の自覚や歯科治療歴は認めなかった。
既往歴:先天性心疾患あり(詳細不明)
身体所見:体温38.3℃。眼瞼結膜出血斑なし。心尖部に収縮期の逆流性雑音を聴取した。
検査所見:血液;WBC 8,100/μL(Neut 87.1%)、CRP 9.8mg/dL。経胸壁心臓超音波;僧帽弁に1cm程度の疣贅を認め、Ⅳ度の僧帽弁逆流を認めた。頭部MRI;塞栓や動脈瘤の所見なし。
経過:入院時の血液培養からα-Streptococcusが検出された。「感染性心内膜炎」の診断で抗菌薬点滴治療を継続した。入院4日目に経食道心臓超音波検査を施行し、僧帽弁前尖に付着物あり、左房後方に逆流所見を認めた。疣贅のサイズは1cmあったが、血行動態は安定しており塞栓所見を認めなかったため、待機的に手術予定となった。その後、合併症なく経過し、入院23日目に疣贅ドレナージと僧帽弁逆流に対する治療を目的として、僧帽弁置換術を施行した。
❸結核
著者: 大藤貴
ページ範囲:P.597 - P.600
Case
「繰り返す気管支炎」と考えられていた肺結核の一例
患者:55歳、男性
既往歴:高血圧症、高尿酸血症
生活歴:喫煙;1日20本を35年
現病歴:普段から喀痰が多いことを自覚していた。2カ月前から微熱と咳嗽、喀痰量の増加を自覚し受診した。バイタルサインは体温37.5℃、SpO2 97%、呼吸数15回/分と安定していた。「気管支炎」と考え、ガレノキサシンが処方された。
その後いったん症状は軽快したが、1カ月後に同様の症状があり、ガレノキサシンが再び処方された。「副鼻腔気管支症候群」の可能性があり、耳鼻科の受診を指示したが、忙しくて受診できなかった。
再び同様の症状があり、3回目の受診となった。バイタルサインは安定していた。初めて撮影した胸部X線では、両肺野に粒状影(図1)がみられた。胸部CT(図2)で抗酸菌感染症が疑われた。喀痰抗酸菌検査で抗酸菌塗抹++、拡散増幅法で結核菌が陽性、「肺結核」の診断となった。
❹HIV感染症
著者: 滝澤あゆみ , 福島一彰
ページ範囲:P.601 - P.605
Case
長引く発熱のため受診した一例
患者:36歳、男性
現病歴:来院2カ月前に抜歯したが、傷の治りが悪かった。また、口腔内に白苔を認め、歯科で「口腔カンジダ症」と診断された。3週間前より38℃台の発熱と乾性咳嗽があった。近医を受診し、「感冒」の診断で対症療法を行った。その後も発熱が続き、抗菌薬を処方されたが改善しなかったため、当院を紹介された。
当院初診時、口腔カンジダ症の既往と同性間性交渉歴があることを聴取した。身体診察で複数の頸部リンパ節腫大があり、胸部CTで両側にすりガラス影、血液検査でβ-Dグルカン上昇を認めた。「ニューモシスチス肺炎」と判明し、HIVスクリーニング検査を行うと陽性であった。HIV確定検査も陽性となり、「HIV感染症」と診断した。
❺リウマチ膠原病
著者: 吉田常恭
ページ範囲:P.606 - P.610
Case
患者:43歳、男性。重喫煙者。
現病歴:2カ月続く手指関節痛のため、内科外来を受診した。身体診察では、両手関節に加えてMCP(中手指節間)・PIP(近位指節間)・DIP(遠位指節間)の各関節が非対称性に腫脹。血液検査で抗CCP(抗シトルリン化ペプチド)抗体陰性だが、RF(リウマトイド因子)25IU/mLと上昇していた。2010年のACR/EULAR(米国リウマチ学会/欧州リウマチ学会)の分類基準に則り「関節リウマチ」と診断し、メトトレキサート(MTX)による治療を開始した。
ところが、MTX16mgまで増量しても改善がなかった。TNF(腫瘍壊死因子)阻害薬を追加したが効果不十分で、IL(インターロイキン)-6阻害薬やアバタセプトに変更しても、効果は部分的であった。リウマチ膠原病内科に相談したところ、後頸部の髪の生え際に落屑を伴う紅斑を指摘され、生検で乾癬が判明した。「乾癬性関節炎」が疑われ、IL-17阻害薬を開始したところ、皮疹・関節炎ともに消退した。本人談では、長年の腰痛も消退したという。
【セッティングⅣ】在宅診療
—オーバービュー—「在宅診療」における診断エラー
著者: 木島庸貴
ページ範囲:P.611 - P.615
Case
患者:62歳、男性。2年前に脳梗塞を発症し、右片麻痺、失語症あり。1年前から自宅療養中で、当院より訪問診療を行っている。主介護者の妻と2人暮らし。
現病歴:「朝から調子が悪そう」と妻から連絡があり、正午頃に臨時往診となった。妻より「横になると苦しそう」とのこと、ベッドのリクライニングを起こして様子をみていた。失語のため、本人からの情報収集は困難。臥位にて、体温37.2℃、血圧130/80mmHg、脈拍数95回/分、SpO2 93%(室内気)、呼吸数24回/分、表情は苦悶様。身体診察では、頸静脈怒張は認めず、胸部聴診に異常なし、腹部圧痛は認めない。臥位で苦悶症状あるが、起きると少し軽減する。心電図に異常所見なし。なお、診療所は30分ほど離れた場所にあり、検査はCBC(血算)・CRP(C反応性蛋白)・血糖・尿検査は可能、その他は外部に委託、ポータブルエコーはなし。
以上より起坐呼吸と考え、「心不全」疑いにて救急外来に紹介したところ、血液検査・胸腹部CT検査の結果、「急性上気道炎」疑いにて抗菌薬を処方されて帰宅となった。しかし3日後、全身状態が悪化し再度臨時往診。救急外来で実施された腹部CTで胆のう腫大の指摘もあり、「急性胆のう炎」疑いにて外科紹介とし、同診断にて同日緊急手術が行われた。
Editorial
「診断エラー」の未来を予測する フリーアクセス
著者: 綿貫聡
ページ範囲:P.535 - P.535
診断エラー(diagnostic error)は近年、患者安全領域において話題となっており、日本でも幅広い啓蒙活動が行われるようになった。本特集は、診断エラーの最近のトピックスの1つである「situativity(状況性)」を意識して企画した。
われわれの知識・思考・学習は経験の中に位置づけられると主張する理論的枠組みを「状況性理論(situativity theory)」1)という。この理論では、「文脈(コンテクスト)」が最も重要であるとされ、知識・思考・学習は文脈から分離できない(文脈に依存する)と主張されている。
What's your diagnosis?[233]
高くついた代返
著者: 横江正道 , 吉見祐輔 , 末松篤樹 , 久田敦史 , 宮川慶 , 田口雄一郎 , 小林奈津希 , 竹内元規
ページ範囲:P.538 - P.541
病歴
患者:73歳、男性
主訴:発熱、紅斑、酸素化不良
現病歴:
●3カ月前にCOVID-19中等症Ⅱにて当院入院。ステロイドパルスとレムデシビルにて治療
●2カ月前に発熱と呼吸苦にて当院ERを受診。COVID-19肺炎後の間質性肺炎として入院し、ステロイドパルスで治療。後療法としてプレドニゾロン40mgを開始し、ダイフェン®配合錠(スルファメトキサゾール・トリメトプリム錠)併用とともにプレドニゾロン30mgに漸減したタイミングで退院。その後、外来にてステロイドを20mgまで漸減していた。
●202X年4月1日、発熱にて受診。熱源はっきりせず、アモキシシリン/クラブラン酸にて加療開始となった。
●4月3日、発熱とSpO2値低下にてER受診。肺炎を合併したと判断され、呼吸器内科にて入院治療となった。入院後はタゾバクタム/ピペラシリンにて治療開始となった。
●4月5日、顔面、頭部の紅斑と眼球充血が出現。同日造影胸部腹部骨盤部CT撮影をするも、明らかな熱源を示唆する所見は得られず。
●4月6日、熱源精査目的に当科へ相談となった。
生活習慣:機会飲酒、喫煙なし。ADL(日常生活動作)は維持されている。
既往歴:65歳:自家感作性皮膚炎(皮膚科にてもともとプレドニゾロン5mgでフォローアップされていた)。71歳:潜在性結核(TSPOT陽性が判明、イソニアジド・ピドキサール処方)
内服薬:プレドニゾロン20mg/日、ランソプラゾール15mg/日、ダイフェン®配合錠4錠/日、イソニアジド300mg/日、ピリドキサール10mg/日、ボナロン® 35mg/週
review of systems(+):発熱、体重減少(COVID-19罹患後3カ月で5kgの減少)
review of systems(-):咳嗽、喀痰、咽頭痛、鼻汁、嘔気・嘔吐、腹痛、下痢、関節痛、背部痛、頻尿、残尿感、眼痛、羞明
【エッセイ】アスクレピオスの杖—想い出の診療録・25
医局での立ち聞き
著者: 板金広
ページ範囲:P.543 - P.543
本連載は、毎月替わる著者が、これまでの診療で心に残る患者さんとの出会いや、人生を変えた出来事を、エッセイにまとめてお届けします。
オール沖縄!カンファレンス|レジデントの対応と指導医の考えVer.2.0・64
新型コロナ流行期の呼吸不全は、やっぱり呼吸器疾患!?
著者: 上原裕子 , 仲里信彦 , 徳田安春
ページ範囲:P.618 - P.623
CASE
患者:85歳、女性。
主訴:活気低下。
現病歴:不安障害で近医通院中。発症時期は不明だが眼瞼下垂があり、来院3週間前に眼科で両側眼瞼挙上術が施行された。その頃から歩行時に背中が曲がる(前傾歩行)、転倒が目立つなどの症状に加え、患者の声が聞き取りづらいことに家族が気づいた。食事も途中でやめたり、活気の低下も見られていたため、それに対してかかりつけ医より漢方薬が処方された。しかし、その2週間経過後も症状は改善せず、再受診した際に発熱、低酸素血症があり、胸部CTでCOVID-19を含めた肺炎を疑われて当院紹介となった。嚥下困難、著明な咳嗽などは明らかでなかった。
既往歴:胆石性胆囊炎(約10年前に胆囊摘出)、白内障(1年前に両側手術)、不安障害(5年ほど前から通院)、眼瞼下垂(両側眼瞼挙上術、3週間前)。
常用薬:ニトラゼパム10mg、ロラゼパム1.5mg、香蘇散3包。
生活歴:夫と同居。basic ADL(基本的日常生活動作)は保たれていた。喫煙・飲酒歴なし。
Dr.上田剛士のエビデンス実践レクチャー!医学と日常の狭間で|患者さんからの素朴な質問にどう答える?・26
食べると眠くなります
著者: 上田剛士
ページ範囲:P.624 - P.627
患者さんからのふとした質問に答えられないことはないでしょうか? 素朴な疑問ほど回答が難しいものはありませんが、新たな気づきをもたらす良問も多いのではないでしょうか? 本連載では素朴な疑問に、文献的根拠を提示しながらお答えします!
フィジカル・ラウンド・オンライン・3
麻痺はないのに歩けない!—冷たい手足と小声の関係
著者: 平島修 , 矢吹拓 , 吉原さつき
ページ範囲:P.628 - P.634
平島:みなさん、こんにちは! 今月もやってきましたPROの時間です〜。
矢吹:相変わらず元気っすね。PROって聞いてまだわからない人もいる気がするので、もう一度確認しますが、「Physical Round Online」の略ですよ。皆さん、ぜひお見知りおきください!
高齢者診療スピードアップ塾|効率も質も高める超・時短術・5
「転倒」の原因はどこまでどう評価する?
著者: 増井伸高
ページ範囲:P.649 - P.651
転倒で来院する高齢者、その表面的な外傷の影に潜む「内科疾患」が致死的な場合も珍しくありません。それを見抜くためには、「外傷に至ったエピソード」を聞き出すことが極めて重要です。しかし認知症の高齢者では、病歴聴取が困難な場合もあります。だからといって、全例で採血・心エコー・造影CTと検査を“絨毯爆撃”するのは過剰医療となります。今回は、どうすれば「転倒の原因」をスマート&スピーディに評価できるか、学んでいきましょう。
【臨床小説―第二部】後悔しない医者|今と未来をつなぐもの・第25話
未来が見える医者
著者: 國松淳和
ページ範囲:P.652 - P.657
前回までのあらすじ 今月のナゾ
進路に悩む西畑は、地域実習を行った山梨県鰍沢の白川診療所を再び訪れ、思いがけず黒野にまつわるある逸話を聞いた。白川鐘春の知己であった故人の甥っ子・向後翠が黒野の双子の兄弟かもしれないこと、さらに翠には未来を見通すような不思議な力があったことを…。しかも翠は現在医師をしていることもわかり、翠(と黒野)への関心が後期研修先に迷う西畑の背中を不意に押した。西畑は、向後翠のいる病院に行くことを決意したのだ。
3月号で【第一部】を終えた。今月からスタートする【第二部】では、東京から長崎は新上五島町、いわゆる五島列島の離島に舞台を変える。今回、内科医となった向後翠の不思議な能力は、「病理診断」「画像診断」にまつわる形で語られる。臨床解説では「検査の限界」が問われる。果たして、向後医師は何を見ているのか?
投稿 GM Clinical Pictures
血便の原因は?
著者: 梶原祐策
ページ範囲:P.635 - P.637
CASE
患者:92歳、女性。
現病歴:高度のAlzheimer型認知症があり施設に入所していたところ、1カ月ほど前から時折血便が見られるようになり、精査加療目的で当科を受診した。なお、抗血栓薬は内服していない。
既往歴:89歳:うっ血性心不全、90歳:Alzheimer型認知症。
社会生活歴・家族歴:特記すべきことなし。
身体所見:身長146.0cm、体重42.4kg(この1年間の体重変化なし)、体温36.6℃、血圧144/86mmHg、脈拍数76回/分、腹部は平坦・軟で圧痛なし。直腸診では肛門縁を越えてすぐの12時方向に、3cm超の弾性軟の腫瘤が触知された。
検査所見:Hb値11.9g/dL(基準:11.5〜15.0)で貧血はなく、肝機能や腎機能、凝固・線溶系も正常であった。
画像所見:下部消化管内視鏡検査の所見を示す(図1)。
小児だけじゃない腹部の疝痛
著者: 鈴木哲 , 大井利起 , 木佐健悟
ページ範囲:P.639 - P.641
CASE
患者:45歳、女性。主訴:腹痛。
現病歴:来院当日の朝から腹痛と10回程度の嘔吐あり。食事摂取不良のため、同日夕方に休日夜間救急外来を受診、当直医による対症療法で帰宅した。
翌日朝、腹痛・嘔吐と下痢もあり、再度休日救急外来を受診した。家族を含めて周囲に同様の症状の人なし。妊娠の可能性はなし。既往歴:帝王切開術後(3回)。片頭痛。
内服薬:リザトリプタン、レバミピド、クエン酸第一鉄ナトリウム。
アレルギー歴:既知のものなし。
バイタルサイン:意識清明。血圧108/76mmHg、脈拍数69回/分、SpO2 97%、呼吸数16回/分、体温37.0℃。
身体所見:腹部平坦・軟、心窩部と右下腹部に圧痛あり、反跳痛なし。
採血所見:肝胆道系酵素の上昇なし、WBC 3,800/μL、CRP 1.70mg/dL。
画像所見:腹部CT画像を示す(図1)。
#総合診療
#今月の特集関連本❶ フリーアクセス
ページ範囲:P.561 - P.561
#今月の特集関連本❷ フリーアクセス
ページ範囲:P.600 - P.600
#今月の特集関連本❸ フリーアクセス
ページ範囲:P.605 - P.605
#今月の特集関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.643 - P.645
#今月の連載関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.647 - P.647
#今月の連載関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.651 - P.651
#医学書院の新刊 フリーアクセス
ページ範囲:P.646 - P.647
#書評:誰も教えてくれなかった皮疹の診かた・考えかた[Web動画付] フリーアクセス
著者: 國松淳和
ページ範囲:P.648 - P.648
さて、書評である。
この本の書評は難しい。なぜなら、とても良い本だからだ。
良い本。買ったほうがいい。本来これで終了である。
この本は、ちゃんとした医学書である。
その点が非常に重要である。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.536 - P.537
読者アンケート
ページ範囲:P.642 - P.642
『総合診療』バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.658 - P.659
お得な年間購読のご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.659 - P.660
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.661 - P.662
基本情報
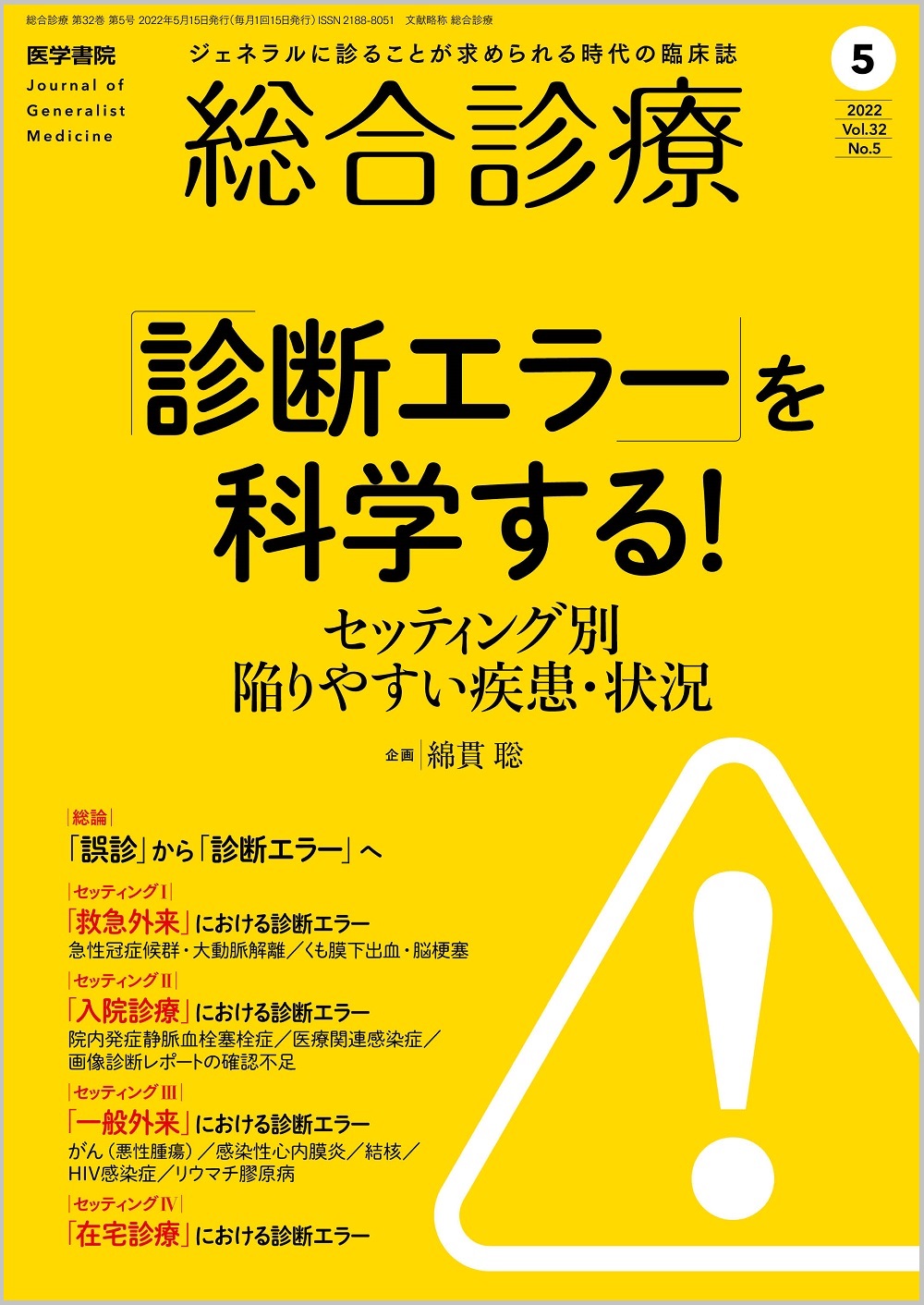
バックナンバー
34巻12号(2024年12月発行)
特集 妊婦・褥婦が外来に来たらUpdate—症状対応からワクチン・プラネタリーヘルスまで
34巻11号(2024年11月発行)
特集 電子カルテとベッドサイドの壁を打ち破る!—患者情報の「言語化」への挑戦
34巻10号(2024年10月発行)
特集 化かしが得意なカメレオンな疾患を捕まえろ!—よくある騙され方のゲシュタルト
34巻9号(2024年9月発行)
特集 今伝えたいクリニカル・パール—つくり方、使い方、活かし方
34巻8号(2024年8月発行)
特集 ストーン・ウォーズ 果てしなき“石”と医師との闘い
34巻7号(2024年7月発行)
特集 どうする!? 健診異常—これってホントに異常なの? どう説明する?
34巻6号(2024年6月発行)
特集 医師のウェルビーイング
34巻5号(2024年5月発行)
特集 —優柔不断にサヨウナラ!—あなたの「臨床判断」を高めるケーススタディ11選
34巻4号(2024年4月発行)
特集 困ったときの漢方—この症状に役立ちます!
34巻3号(2024年3月発行)
特集 —え、ウソ!実は◯◯だった!?—“コモンディジーズ”の診断ピットフォール
34巻2号(2024年2月発行)
特集 日常診療で出合う筋骨格疾患—脳神経内科と整形外科からのアプローチ
34巻1号(2024年1月発行)
特集 —“体験型”臨床クイズで習得する!—フィジカル診断エクセレンス
33巻12号(2023年12月発行)
特集 海の外へ渡る航行者を診る—アウトバウンドにまつわるetc.
33巻11号(2023年11月発行)
特集 —続・総合診療外来に“実装”したい—最新エビデンスMy Best 3
33巻10号(2023年10月発行)
特集 ○×クイズ110問!日常診療アップグレード—Choosing WiselyとHigh Value Careを学ぼう
33巻9号(2023年9月発行)
特集 ジェネラリストのための「発達障害(神経発達症)」入門
33巻8号(2023年8月発行)
特集 都市のプライマリ・ケア—「見えにくい」を「見えやすく」
33巻7号(2023年7月発行)
特集 “消去法”で考え直す「抗菌薬選択」のセオリー—広域に考え、狭域に始める
33巻6号(2023年6月発行)
特集 知っておくべき!モノクロな薬たち(注:モノクローナル抗体の話ですよ〜)
33巻5号(2023年5月発行)
特集 —疾患別“イルネススクリプト”で学ぶ—「腹痛診療」を磨き上げる22症例
33巻4号(2023年4月発行)
特集 救急対応ドリル—外来から在宅までの60問!
33巻3号(2023年3月発行)
特集 —自信がもてるようになる!—エビデンスに基づく「糖尿病診療」大全—新薬からトピックスまで
33巻2号(2023年2月発行)
特集 しびれQ&A—ビビッとシビれるクリニカルパール付き!
33巻1号(2023年1月発行)
特集 COVID-19パンデミック 振り返りと将来への備え
32巻12号(2022年12月発行)
特集 レクチャーの達人—とっておきの生ライブ付き!
32巻11号(2022年11月発行)
特集 不定愁訴にしない“MUS”診療—病態からマネジメントまで
32巻10号(2022年10月発行)
特集 日常診療に潜む「処方カスケード」—その症状、薬のせいではないですか?
32巻9号(2022年9月発行)
特集 総合診療・地域医療スキルアップドリル—こっそり学べる“特講ビデオ”つき!
32巻8号(2022年8月発行)
特集 こんなところも!“ちょいあて”エコー—POCUSお役立ちTips!
32巻7号(2022年7月発行)
特集 —どうせやせない!? やせなきゃいけない??苦手克服!—「肥満」との向き合い方講座
32巻6号(2022年6月発行)
特集 総合診療外来に“実装”したい最新エビデンス—My Best 3
32巻5号(2022年5月発行)
特集 「診断エラー」を科学する!—セッティング別 陥りやすい疾患・状況
32巻4号(2022年4月発行)
特集 えっ、これも!? 知っておきたい! 意外なアレルギー疾患
32巻3号(2022年3月発行)
特集 AI時代の医師のクリニカル・スキル—君は生き延びることができるか?
32巻2号(2022年2月発行)
特集 —withコロナ—かぜ診療の心得アップデート
32巻1号(2022年1月発行)
特集 実地医家が楽しく学ぶ 「熱」「炎症」、そして「免疫」—街場の免疫学・炎症学
31巻12号(2021年12月発行)
特集 “血が出た!”ときのリアル・アプローチ—そんな判断しちゃダメよ!
31巻11号(2021年11月発行)
特集 Q&Aで深める「むくみ診断」—正攻法も!一発診断も!外来も!病棟も!
31巻10号(2021年10月発行)
特集 医師の働き方改革—システムとマインドセットを変えよう!
31巻9号(2021年9月発行)
特集 「検査」のニューノーマル2021—この検査はもう古い? あの新検査はやるべき?
31巻8号(2021年8月発行)
特集 メンタルヘルス時代の総合診療外来—精神科医にぶっちゃけ相談してみました。
31巻7号(2021年7月発行)
特集 新時代の「在宅医療」—先進的プラクティスと最新テクノロジー
31巻6号(2021年6月発行)
特集 この診断で決まり!High Yieldな症候たち—見逃すな!キラリと光るその病歴&所見
31巻5号(2021年5月発行)
特集 臨床医のための 進化するアウトプット—学術論文からオンライン勉強会、SNSまで
31巻4号(2021年4月発行)
特集 消化器診療“虎の巻”—あなたの切実なギモンにズバリ答えます!
31巻3号(2021年3月発行)
特集 ライフステージでみる女性診療at a glance!—よくあるプロブレムを網羅しピンポイントで答えます。
31巻2号(2021年2月発行)
特集 肺炎診療のピットフォール—COVID-19から肺炎ミミックまで
31巻1号(2021年1月発行)
特別増大特集 新型コロナウイルス・パンデミック—今こそ知っておきたいこと、そして考えるべき未来
30巻12号(2020年12月発行)
特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き) Part 2
30巻11号(2020年11月発行)
特集 診断に役立つ! 教育で使える! フィジカル・エポニム!—身体所見に名を残すレジェンドたちの技と思考
30巻10号(2020年10月発行)
特集 —ポリファーマシーを回避する—エビデンスに基づく非薬物療法のススメ
30巻9号(2020年9月発行)
特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【感染症・内分泌・整形外科 編】
30巻8号(2020年8月発行)
特集 マイナーエマージェンシー門外放出—知っておくと役立つ! テクニック集
30巻7号(2020年7月発行)
特集 その倦怠感、単なる「疲れ」じゃないですよ!—筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群とミミック
30巻6号(2020年6月発行)
特集 下降期慢性疾患患者の“具合”をよくする—ジェネラリストだからできること!
30巻5号(2020年5月発行)
特集 誌上Journal Club—私を変えた激アツ論文
30巻4号(2020年4月発行)
特集 大便強ドリル—便秘・下痢・腹痛・消化器疾患に強くなる41問!
30巻3号(2020年3月発行)
特集 これではアカンで!こどもの診療—ハマりがちな11のピットフォール
30巻2号(2020年2月発行)
特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【循環器・消化器・神経疾患編】
30巻1号(2020年1月発行)
特集 総合診療医の“若手ロールモデル”を紹介します!—私たちはどう生きるか
29巻12号(2019年12月発行)
特集 困っている“あなた”に届く 認知症診療
29巻11号(2019年11月発行)
特集 臨床写真図鑑 レアな疾患編—見逃したくない疾患のコモンな所見
29巻10号(2019年10月発行)
特集 教えて!医師のためのビジネス・スキル
29巻9号(2019年9月発行)
特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き)
29巻8号(2019年8月発行)
特集 —ノーモア見逃し—日常の検査と画像に潜むピットフォール
29巻7号(2019年7月発行)
特集 リウマチ・膠原病ミミック症例帖—“膠原病っぽくみえてしまう疾患たち”にだまされない!
29巻6号(2019年6月発行)
特集 皮膚科診療エクササイズ—1枚の写真から
29巻5号(2019年5月発行)
特集 一般外来で診断できたら「えっへん!」な疾患38
29巻4号(2019年4月発行)
特集 “ナゾ”の痛み診療ストラテジー|OPQRSTで読み解く
29巻3号(2019年3月発行)
特集 —あなたのギモンに答えます!—循環器診療のハードルを下げるQ&A31
29巻2号(2019年2月発行)
特集 意外な中毒、思わぬ依存、知っておきたい副作用—一般外来で!OTCも処方薬も!
29巻1号(2019年1月発行)
特集 教えて検索!—膨大な医学情報を吟味・整理するスキル
28巻12号(2018年12月発行)
特集 こんなときこそ漢方を!
28巻11号(2018年11月発行)
特集 日本一マジメな「おしっこドリル」—今これだけは押さえておきたい腎・泌尿器のモンダイ
28巻10号(2018年10月発行)
特集 クリニカル・パールPremium!—憧れのカリスマ医師はかく語りき
28巻9号(2018年9月発行)
特集 オンコ・ジェネラリスト—「がん」に強い総合診療医をめざして
28巻8号(2018年8月発行)
特集 80歳からの診療スタンダードUp to Date—Silver Standard
28巻7号(2018年7月発行)
特集 この薬だけは押さえておきたい! 総合診療医のためのSpecialist Drug 40
28巻6号(2018年6月発行)
特集 聴診・触診×エコーで診断推論!—Point-of-Care超音波(POCUS)の底力
28巻5号(2018年5月発行)
特集 “一発診断”トレーニング問題集—懸賞論文「GM Clinical Pictures」大賞発表!
28巻4号(2018年4月発行)
特集 感染症外来診療「賢医の選択」—検査・経口薬・ワクチンをどう使えばいいんですか?
28巻3号(2018年3月発行)
特集 糖尿病のリアル—現場の「困った!」にとことん答えます。
28巻2号(2018年2月発行)
特集 頭痛患者で頭が痛いんです!
28巻1号(2018年1月発行)
特集 シン・フィジカル改革宣言!—私の“神技”伝授します。
27巻12号(2017年12月発行)
特集 小児診療“苦手”克服!!—劇的Before & After
27巻11号(2017年11月発行)
特集 今そこにある、ファミリー・バイオレンス|Violence and Health
27巻10号(2017年10月発行)
特集 めまいがするんです!─特別付録Web動画付
27巻9号(2017年9月発行)
特集 うつより多い「不安」の診かた—患者も医師も安らぎたい
27巻8号(2017年8月発行)
特集 見逃しやすい内分泌疾患─このキーワード、この所見で診断する!
27巻7号(2017年7月発行)
特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 3 カリスマ編
27巻6号(2017年6月発行)
特集 「地域を診る医者」最強の養成法!
27巻5号(2017年5月発行)
特集 コミュニケーションを処方する—ユマニチュードもオープンダイアローグも入ってます!
27巻4号(2017年4月発行)
特集 病歴と診察で診断できない発熱!—その謎の賢い解き方を伝授します。
27巻3号(2017年3月発行)
特集 これがホントに必要な薬40—総合診療医の外来自家薬籠
27巻2号(2017年2月発行)
特集 The総合診療ベーシックス—白熱!「総合診療フェスin OKINAWA」ライブ・レクチャー! 一挙公開 フィジカル動画付!
27巻1号(2017年1月発行)
特集 総合診療の“夜明け”—キーマンが語り尽くした「来し方、行く末」
26巻12号(2016年12月発行)
特集 これでパッチリ! 眼の健康問題
26巻11号(2016年11月発行)
特集 続・しびれるんです!
26巻10号(2016年10月発行)
特集 内科診療を劇的に変える“まとめ”の達人
26巻9号(2016年9月発行)
特集 症状・症候別 エコーを使った診断推論─Point-of-Care超音波
26巻8号(2016年8月発行)
特集 The 初診外来
26巻7号(2016年7月発行)
特集 感染症ケアバンドル・チェックリスト
26巻6号(2016年6月発行)
特集 “賢い処方”と“ナゾ処方”
26巻5号(2016年5月発行)
特集 しびれるんです!─知っておくべきシビレル疾患
26巻4号(2016年4月発行)
特集 ケースとクイズで総ざらい! 街場の2型糖尿病治療
26巻3号(2016年3月発行)
特集 こんな時は漢方でしょう!
26巻2号(2016年2月発行)
特集 フィジカル改革宣言! ──診断からフォローアップまで
26巻1号(2016年1月発行)
特集 妊婦・褥婦が一般外来に来たら─エマージェンシー&コモンプロブレム
25巻12号(2015年12月発行)
特集 外来で「複数の疾患」をもつ患者を診る─マルチモビディティの時代のプライマリ・ケア
25巻11号(2015年11月発行)
特集 レアだけど重要な「痛み」の原因─システム1診断学
25巻10号(2015年10月発行)
特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 2
25巻9号(2015年9月発行)
特集 診断ピットフォール10選─こんな疾患,見逃していませんか?
25巻8号(2015年8月発行)
特集 健診データで困ったら─こんな検査結果を持ってこられたら
25巻7号(2015年7月発行)
特集 ここを知りたい!頭部外傷初期対応・慢性期ケア
25巻6号(2015年6月発行)
特集 高齢者救急の落とし穴─紹介する時,される時
25巻5号(2015年5月発行)
特集 咳を聴きとり,咳を止める
25巻4号(2015年4月発行)
特集 関節が痛いんです!─コモンからレアものまでの診断と治療
25巻3号(2015年3月発行)
特集 神経難病ケアのコペルニクス的転回
25巻2号(2015年2月発行)
特集 総合医のためのスポーツ医学ベーシックス
25巻1号(2015年1月発行)
特集 動悸・息切れ─ヤバい病気の見つけ方 そして見つからなかった時の対処法
