総合診療医は、常に幅広い知識を最新のものにアップデートすることが求められますが、なかなか独力では困難な側面が多くあります。
そこで本特集では、近年の主要な疾患や健康問題に関する“知っておくべきエビデンス”を各領域の専門家にご紹介いただき、プライマリ・ケアや総合診療の現場へ“実装”する支援に資する内容をめざしました。
総論では「実装科学」について、初学者にもわかりやすく、実装科学の対象や方法、最近の成果などを紹介していただきました。
そして20項目ある各論では、執筆者自身が、「プライマリ・ケアに従事する医師にぜひ知っておいてほしい!」と考える診断、治療、予後や疫学等に関する近年の「3つのエビデンス」と「その背景となる論文」(原著論文あるいはメタアナリシス)を取り上げ、そのポイントを解説してもらい、さらにプライマリ・ケア現場への“実装”についても言及してもらいました。
雑誌目次
総合診療32巻6号
2022年06月発行
雑誌目次
特集 総合診療外来に“実装”したい最新エビデンス—My Best 3
扉 フリーアクセス
著者: 藤沼康樹
ページ範囲:P.684 - P.685
今月の「めざせ! 総合診療専門医!」問題
ページ範囲:P.754 - P.755
本問題集は、今月の特集のご執筆者に、執筆テーマに関連して「総合診療専門医なら知っておいてほしい!」「自分ならこんな試験問題をつくりたい!」という内容を自由に作成していただいたものです。力試し問題に、チャレンジしてみてください。
【総論】
エビデンスを実地診療に実装するには—実装科学(Implementation Science)入門
著者: 梶有貴
ページ範囲:P.686 - P.690
EBMの“次の一手”「実装科学」
1990年代に「エビデンスに基づく医療(evidence-based medicine:EBM)」の概念が導入され、さまざまな臨床研究が実施され、そこで得られた多くの知見が臨床現場で応用されるようになりました。本稿を手に取っていただいている皆さんも、日常業務のなかで当然のごとく、エビデンスを駆使して診療されていることと思います。しかし、それほどにエビデンスが当たり前のように浸透してきた現在であっても、エビデンスレベルや推奨レベルが高いプラクティスがあるにもかかわらず実際の現場では十分に活用されていない、あるいはエビデンスがないプラクティスであるにもかかわらず実際の現場でよく実施されている、という状況も見受けられ、もどかしい思いをした経験があるかもしれません。これをエビデンスと診療現場の間に大きな隔たり(ギャップ)が存在するという意味で、「エビデンス・プラクティスギャップ(evidence-practice gap)」と呼びます。
なぜこのようなギャップが生まれてしまうのでしょうか?
【知っておきたい!Common Disease最新エビデンスMy Best 3】
❶高血圧—厳しすぎる血圧治療と薬物治療偏重、フレイルの低血圧の危険
著者: 名郷直樹
ページ範囲:P.691 - P.693
My BestエビデンスNo.1
降圧治療はどこまで厳しくなるのか?
収縮期血圧110mmHgを目指す厳格治療は、130〜150mmHgの標準治療と比べて、心血管イベントが26%少ないというランダム化比較試験の結果が報告された。これは、公衆衛生の視点で脳卒中予防効果が明らかなことを示しているが、個々の患者に対しては、収縮期血圧が130mmHgでも高いという不安を引き起こすだけかもしれない。
❷慢性腎臓病
著者: 杉本俊郎
ページ範囲:P.694 - P.696
My BestエビデンスNo.1
慢性腎臓病(CKD)の進展予防にSGLT2阻害薬が有効である
尿蛋白を有する、もしくは、Grade 3b(eGFR<45mL/分/1.73m2)以上に進展した慢性腎臓病(CKD)に対しては、2型糖尿病の有無にかかわらず、腎機能の悪化(GFRの減少)を予防するために、SGLT2阻害薬投与を行うべきである。
❸糖尿病
著者: 岩岡秀明
ページ範囲:P.697 - P.699
My BestエビデンスNo.1
2型糖尿病は5つのリスク因子をきちんとコントロールすれば、生命予後は一般人とほとんど変わらない
2型糖尿病において、HbA1c、LDLコレステロール、血圧、尿中アルブミン、喫煙という5つのリスク因子を目標範囲内に保てば、全死亡、急性心筋梗塞、脳卒中のリスクは、一般人とほとんど変わらない時代になった。
❹多疾患併存
著者: 大浦誠
ページ範囲:P.700 - P.702
My BestエビデンスNo.1
多疾患併存をシステムとしてとらえよう
多疾患併存を個別性の高い生物・心理・社会的な相互作用のネットワーク障害と捉え、目に見える病気だけに関わるのではなく、複雑適応系のバランスを取ることに焦点を当てるべきである。
❺脂質異常症
著者: 大西由希子
ページ範囲:P.703 - P.705
My BestエビデンスNo.1
スタチン服用による心血管イベント予防のメリットは、その副作用リスクを上回る
脂質異常症のスタチンによる治療は、その副作用リスクを上回る心血管イベントの一次予防効果がある。スタチンの副作用などは少なく、スタチンの種類や用量による副作用の差もほとんどないが、肝機能モニタリングはすべきである。イベント既往のない脂質異常症の患者が、薬の副作用を気にして服薬開始を拒む時に、服用開始の意義についての説明の根拠になる。
❻骨粗鬆症
著者: 山本昌弘
ページ範囲:P.706 - P.708
My BestエビデンスNo.1
骨粗鬆症治療は大腿骨近位部骨折後の生命予後を改善する
骨粗鬆症骨折患者は直後から死亡率が増加するが、骨粗鬆症治療薬、特にビスホスホネート治療により死亡率を改善することが可能である。加齢に伴い大腿骨近位部の骨折リスクが増加するため、高齢者ほど骨粗鬆症治療薬の処方を受けているはずだが、実態はどうだろうか?
❼痛風
著者: 浜田紀宏 , 谷口尚平 , 大塚裕眞 , 中井翼
ページ範囲:P.709 - P.711
My BestエビデンスNo.1
痛風関節炎の確定が難しいときは関節エコーを
痛風関節炎を確定診断に近づけるために、関節エコーは有用である。
❽COPD
著者: 吉松由貴
ページ範囲:P.712 - P.715
My BestエビデンスNo.1
重症COPDでは3剤合剤による吸入療法を積極的に試そう
重症COPD(慢性閉塞性肺疾患)では、積極的な薬物治療により増悪や進行を予防したい。重症例では、特に末梢血好酸球数が高い場合には、LAMA/LABA/ICSによる3剤治療を検討する。アドヒアランスを改善して治療効果を高めるためには、3剤合剤による吸入療法(single inhaler triple therapy : SITT)を使いこなそう。
❾喘息
著者: 倉原優
ページ範囲:P.716 - P.719
My BestエビデンスNo.1
軽症喘息に対するブデソニド/ホルモテロールの1剤管理
軽症喘息では、ブデソニド/ホルモテロールだけで管理する手法が、国際的に推奨されている。
❿急性冠症候群
著者: 太田洋
ページ範囲:P.720 - P.722
My BestエビデンスNo.1
胸痛とST上昇
●冠危険因子のある患者の胸痛は、バイタルサインと心電図12誘導、ST上昇があればすぐに心臓カテーテル検査・治療が可能な病院へ!
●ST上昇心筋梗塞はSTBT(症状から治療までの時間:symptom-to-balloon time)が重要!
●高齢女性のSTEMI(ST上昇心筋梗塞)は予後不良であり、早めの治療介入が必要!
⓫進行期・終末期心不全
著者: 大森崇史
ページ範囲:P.723 - P.726
My BestエビデンスNo.1
LVEFの低下した心不全の薬の最適な組み合わせはどれ?
心不全の薬物治療の進歩は目覚ましい。1980年代、LVEF(左室駆出率)の低下した心不全(heart failure with reduced ejection fraction : HFrEF)の治療薬は、ジゴキシンと利尿薬のみであった。1990年頃からACEI(アンジオテンシン変換酵素阻害薬)、βB(β遮断薬)、MRA(ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬)、ARB(アンジオテンシン受容体拮抗薬)が加わった。それからしばらくは、薬剤に関する大きなアップデートはなかったが、2010年代に入り、ARNI(アンジオテンシン受容体-ネプリライシン阻害薬)が登場した。これだけある薬剤をすべて投与するのはあまり現実的ではないし、ポリファーマシーの観点からも問題となる。それらの薬剤をどのように組み合わせればよいか、30年にわたるエビデンスを集約したネットワークメタアナリシスを紹介する。その結果、「ARNI+βB+MRA」による治療が最も死亡率が低いことが報告された。コストパフォーマンスで言えば、ジェネリック医薬品が揃っている「ACEI+βB+MRA」または「ACEI+βB」がよさそうだ。
⓬心房細動
著者: 小田倉弘典
ページ範囲:P.727 - P.729
My BestエビデンスNo.1
抗凝固薬と抗血小板薬の併用はいつまで?
心房細動を合併する安定冠動脈疾患の慢性期(1年以降)では、抗凝固薬単独投与が推奨される。
⓭ポリファーマシー
著者: 青島周一
ページ範囲:P.730 - P.732
My BestエビデンスNo.1
関心を向けるべきは薬そのものというよりはむしろ、薬以外の要因かもしれない
ポリファーマシーは、薬による潜在的な有害事象リスクの問題というよりはむしろ、医療化された人の生活の一側面である。そのことを示唆したエビデンスの1つを取り上げたい。
⓮逆流性食道炎
著者: 久野裕司 , 京兼和宏 , 松浦俊博
ページ範囲:P.733 - P.735
My BestエビデンスNo.1
PPIとP-CABはどのように使い分ければよいか?
逆流性食道炎の治療薬には第一選択薬としてPPI(proton pump inhibitor)が使われてきたが、より強力で安定した酸分泌抑制作用を有するP-CAB(potassium-competitive acid blocker)が登場した。これらの薬剤をどのような症例に使い分ければよいのだろうか?
⓯COVID-19
著者: 古谷賢人 , 伊東直哉
ページ範囲:P.736 - P.738
My BestエビデンスNo.1
重症化リスクを有する軽症・中等症ⅠのCOVID-19患者に中和抗体薬もしくは抗ウイルス薬を使用し重症化を防ごう
・重症化リスク因子のある軽症・中等症ⅠのCOVID-19症例では、中和抗体薬もしくは抗ウイルス薬の使用を検討する。
・酸素投与が必要でないCOVID-19患者へのステロイドの使用は、予後を悪化させる可能性があるため使用を控える。
⓰関節リウマチ
著者: 山室亮介 , 萩野昇
ページ範囲:P.739 - P.741
My BestエビデンスNo.1
関節リウマチに対するステロイド投与は、低用量でも可能な限り避ける
関節リウマチ患者へのステロイド投与は、たとえ低用量であっても重篤な感染症の発生リスクを増加させるために、可能な限り減量・中止が望ましい。
⓱統合失調症
著者: 宇野晃人 , 田宗秀隆
ページ範囲:P.742 - P.745
My BestエビデンスNo.1
統合失調症に対する抗精神病薬は、安易に中断できるものではない
統合失調症の精神症状が安定しているとしても、抗精神病薬は再発予防のために継続されるべきである。身体疾患に抗精神病薬が悪影響を及ぼしていたり、ポリファーマシーの是正に着手したりする場合、できる限り精神科主治医と連携して、薬剤の減量や置換などの策を講じることが望ましい。
⓲うつ病—生物心理社会的に読む、うつ病論文My Best3
著者: 今村弥生
ページ範囲:P.746 - P.747
My BestエビデンスNo.1
最も有用な抗うつ薬とは?
うつ症状への効果と安全性の観点から、21種類の抗うつ薬を網羅的に比較検討したネットワークメタアナリシスが報告された。すべての抗うつ薬はプラセボより優れていたものの、各抗うつ薬の間で差は小さく、特定の薬剤が他に比べて優越性を持つものでもないという解釈がなされる。
⓳健康の社会的決定要因
著者: 水本潤希
ページ範囲:P.748 - P.750
My BestエビデンスNo.1
プライマリ・ケア医は社会経済的に困窮した状態にいる患者の診療をおざなりにする傾向がある
本稿では、プライマリ・ケア従事者が健康の社会的決定要因の考え方を日常診療に組み入れる際に押さえておくべき知見を解説する。まず、現状の認識として、プライマリ・ケア医は困難を抱えた患者に決して優しくない、むしろ冷たくあしらっているのではないか、という「不都合な事実」を紹介する。
⓴小児期発症疾患成人移行例
著者: 窪田満
ページ範囲:P.751 - P.753
My BestエビデンスNo.1
大事なのはフォローアップが中断されないこと
小児期発症疾患の成人移行において、それが成功しているかどうかは、小児科と成人診療科の連携が担保され、転科後にも良質な医療が継続されているかどうかで評価されるべきである。
Editorial
「総合診療」の本来の姿を求めて フリーアクセス
著者: 藤沼康樹
ページ範囲:P.683 - P.683
今号の特集は「総合診療」領域の、特に外来診療において、現在重要と思われる分野をセレクションし、私が個人的に信頼しているご執筆者の皆さんの視点から「これは知っておいてほしい!」というリサーチ・エビデンスを3つ紹介していただく内容となっています。
こうした、“○○のアップデート”といった特集は、“○○=(イコール)疾患”になっていることが多いですが、今回は疾患や病態だけでなく、多疾患併存に代表される健康問題の構造的特徴についても取り上げています。これは、「総合診療」という仕事の対象の特徴が、疾患や病態、あるいは検査・治療法などの排他的独自性ではなく、健康問題の構造自体(例えば未分化健康問題や下降期慢性疾患等)にあるからです。
ゲストライブ〜Improvisation〜・18
磨け!問診力 診断に迫る“+α”のテクニック—11のQuestionsにタロウとタケシがお答えします!
著者: 上田剛士 , 志水太郎
ページ範囲:P.663 - P.672
日常診療において欠かせない「問診」「病歴聴取」であるが、日々ルーチンで終わっていないだろうか?
『medicina』2021年11月号「外来で役立つAha! クエスチョン—この症状で、次は何を聞く?」と『総合診療』2021年6月号「この診断で決まり! High Yieldな症候たち—見逃すな! キラリと光るその病歴&所見」の特集を企画した診断のエキスパート・志水太郎先生と上田剛士先生。今年1月8日にお2人を講師にお迎えして、問診力を磨くためのオンラインセミナーが開催された。当日、視聴者から直接寄せられた問診にまつわる11のQuestionsについて、タロウ先生とタケシ先生が直接回答、診断につながる問診のチカラとコツについてもわかりやすく解説くださった。
ここではその収録内容を一挙公開! さあ、診断に迫る“+α”の問診技術を身につけて、問診力に磨きをかけよう!(編集室)
【エッセイ】アスクレピオスの杖—想い出の診療録・26
傾聴の偉大な力
著者: 小宮ひろみ
ページ範囲:P.677 - P.677
本連載は、毎月替わる著者が、これまでの診療で心に残る患者さんとの出会いや、人生を変えた出来事を、エッセイにまとめてお届けします。
What's your diagnosis?[234]
泣けなしの金と赤いお尻
著者: 池田宜央 , 酒見英太
ページ範囲:P.678 - P.682
病歴
患者:73歳、女性
主訴:繰り返す発熱、咳嗽
現病歴:少なくとも20年来、関節リウマチを治療中の元看護師。約1年前より、夜間に増悪する乾性咳嗽とともに38℃を超える高熱が間欠的に出現するようになった。1回のエピソードは1〜3週間持続し、その度に他院外来で肺炎として毎回抗菌薬投与を受けて改善していた。無熱期には咳は出ない。同様のエピソードをこの1年間で季節に関係なく10回繰り返したため、精査目的に当院に紹介された。
既往歴:関節リウマチ、帯状疱疹
常用薬:プレドニゾロン1mg/日、サラゾスルファピリジン1,000mg/日、セレコキシブ200mg/日、エソメプラゾール20mg/日。なおメトトレキサート(MTX)は4カ月前まで服用していた(4〜6mg/週)が、服用をやめると発熱、咳が若干改善したため、本人の希望で中止された。しかしその後も主訴は繰り返している。
生活歴:夫・娘と3人暮らし。ペットは飼っていない。飲酒歴・喫煙歴はない。
陰性所見:悪寒・戦慄、盗汗、体重減少、食思不振、頭痛、複視・霧視、結膜充血・眼脂、難聴・耳鳴、耳痛・耳漏、鼻汁・鼻閉、口内痛、歯痛、咽頭痛・嚥下時痛、平熱期の咳、胸痛、血痰、呼吸困難、頸部痛・背部痛・腰痛、腹痛・腹部膨満、便秘・下痢、血便・黒色便、頻尿・残尿感、排尿困難、筋肉痛・関節痛、皮疹、浮腫、脱力、感覚障害、ふらつき
高齢者診療スピードアップ塾|効率も質も高める超・時短術・6
「院内コンサルト」は8割の情報でいい!
著者: 増井伸高
ページ範囲:P.760 - P.762
専門医への「院内コンサルト」のタイミングは難しいです。検査情報などがすべてそろってからでは遅すぎます。かといって、情報不足だとコンサルトに応じてもらえないこともあるでしょう。患者診療が最もスピーディになる、院内コンサルトのベストタイミングについて、今回は確認していきます。
オール沖縄!カンファレンス|レジデントの対応と指導医の考えVer.2.0・65
発熱、頭痛ときたら…
著者: 宇佐美福人 , 鈴木智晴 , 徳田安春
ページ範囲:P.763 - P.767
CASE
患者:46歳、女性。
主訴:発熱、頭痛。
現病歴:繰り返す尿路感染症と細菌性髄膜炎の既往あり。1週間前から頻尿と排尿時痛があったが、一時的な症状であり、その後は一旦軽快していた。5日前に発熱、頭痛、関節痛を主訴に当院の救急外来を受診したところ、急性上気道炎の診断でアセトアミノフェンを処方されて帰宅した。その後も38〜39℃台の発熱が続き、頭痛が増強してきたため、救急外来を再受診した。
既往歴:細菌性髄膜炎(24歳)、急性腎盂腎炎、繰り返す膀胱炎。
内服歴:特記事項なし。
家族歴:特記事項なし。
アレルギー:なし。
患者さんには言えない!? 医者のコッソリ養生法・12
翌日に疲れを残さない、ぐっすり「睡眠」の養生❷
著者: 須田万勢
ページ範囲:P.768 - P.771
“プチ不健康”を放置してきたツケで弱っていた貝原先生。突然現れた医神アスクレピオス(自称ピオちゃん)に半ば強制的に弟子入りさせられ、養生で健康を取り戻す方法をしぶしぶ学ぶうち、身体も心も少しずつ変わってきた。「風邪」「肩こり」「肥満」「お酒」に続き、ちゃんと疲れがとれる「睡眠」の方法を伝授されることに…。
Dr.上田剛士のエビデンス実践レクチャー!医学と日常の狭間で|患者さんからの素朴な質問にどう答える?・27
夫婦が似るならペットも似る
著者: 上田剛士
ページ範囲:P.772 - P.775
患者さんからのふとした質問に答えられないことはないでしょうか? 素朴な疑問ほど回答が難しいものはありませんが、新たな気づきをもたらす良問も多いのではないでしょうか? 本連載では素朴な疑問に、文献的根拠を提示しながらお答えします!
【臨床小説—第二部】後悔しない医者|今と未来をつなぐもの・第26話
感じとろうとする医者
著者: 國松淳和
ページ範囲:P.778 - P.783
前回までのあらすじ 今月のナゾ
「この患者さん、今日の夕方、足が動かなくなる」。異常所見を認めなかったはずの腹部骨盤造影CT像を一瞥した向後がそう“予言”すると、右井と左座は慌てて駆け出した。患者は、1カ月続く微熱と倦怠感、体重減少のため入院中の83歳・男性で、一向に病状が改善しないことから退院を逸っていた。
舞台は長崎、五島列島の小さな離島の頭ケ島白浜病院である。内科と外科しかないこの病院の内科医・向後のもとで後期研修を受けるため、西畑がここを訪れる直前の出来事だった。
黒野の双子の兄弟と目される向後翠の不思議な力は、どうやら「見ること」と関係するようだ。たとえば画像診断をする時、どのように画像を見て、どのように思考を展開していくだろう? 予め見るべきものを意識化し、見落としがないようリストアップして順に確認していくだろうか。しかし、向後のやり方は違う。どう違うのか? 画像診断医から内科医に転向した右井が、その言語化を試みる。
#総合診療
#今月の特集関連本❶ フリーアクセス
ページ範囲:P.699 - P.699
#今月の特集関連本❷ フリーアクセス
ページ範囲:P.705 - P.705
#今月の特集関連本❸ フリーアクセス
ページ範囲:P.719 - P.719
#今月の特集関連本❹ フリーアクセス
ページ範囲:P.729 - P.729
#医学書院の新刊 フリーアクセス
ページ範囲:P.756 - P.757
#今月の連載関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.762 - P.762
#今月の連載関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.779 - P.779
#書評:—トップジャーナルに学ぶ—センスのいい科学英語論文の書き方 フリーアクセス
著者: 倉本秋
ページ範囲:P.758 - P.758
本書の著者であるジャンさんとの出会いは、1980年代後半までさかのぼる。当時、私が勤務していた東大病院分院の助教授から、ジャンさんを紹介された。知り合って10年間は、2週間に1回程度おしゃべりの機会をもち、論文ができたら校閲してもらっていた。その後、私の職場は高知大、そして高知医療再生機構へと変わったが、投稿論文はすべてジャンさんの手を経ており、今では機構が販売する学内委員会Web審査システムの英文マニュアルまで校正をお願いしている。
今回、本書を読み進めながら、30年以上前にレトロな東大分院の建物で教えてもらっていたことは、ステップⅠの「英語のマインドをつくる」に述べられている内容であったと気づいた。たしかに、科学論文を書こうとする日本人は皆、英作文はできる。しかし残念なことに、「(日本の)学校英文法」とは似て非なる、「英文」を構成する法則やコンセプトの理解は欠落している。native speaker(以下、native)が学ぶようなparagraph writingの概念を教える授業は、日本にはないからである。そこをすっ飛ばして中学から大学まで英語を学んだ若い研究者たちは、卒前あるいは卒後しばらくして初めての論文を完成させる。「事実は現在形で」とか、「受動態は少なめがよい」とかいう先輩の指示だけを道標に…。“paragraph”を日本語の「段落」に置き換えただけの頭では、「ミニエッセイ風」などの構成は思いも至らない。このような前提を知らないと、nativeのproofreadを受け取った時、その朱字を許容しがたい場合がある。nativeも、日本人の文の順序や改行を怪訝に思いながら、校正と格闘する羽目になる。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.674 - P.675
『総合診療』編集方針 フリーアクセス
ページ範囲:P.676 - P.676
1991年に創刊した弊誌は、2015年に『JIM』より『総合診療』に誌名を変更いたしました。その後も高齢化はさらに進み、社会構造や価値観、さらなる科学技術の進歩など、日本の医療を取り巻く状況は刻々と変化し続けています。地域医療の真価が問われ、ジェネラルに診ることがいっそう求められる時代となり、ますます「総合診療」への期待が高まってきました。これまで以上に多岐にわたる知識・技術、そして思想・価値観の共有が必要とされています。そこで弊誌は、さらなる誌面の充実を図るべく、2017年にリニューアルをいたしました。本誌は、今後も下記の「編集方針」のもと、既存の価値にとらわれることなく、また診療現場からの要請に応え、読者ならびに執筆者のみなさまとともに、日本の総合診療の新たな未来を切り拓いていく所存です。
2018年1月 『総合診療』編集委員会
読者アンケート
ページ範囲:P.785 - P.785
『総合診療』バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.786 - P.787
お得な年間購読のご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.787 - P.788
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.789 - P.790
基本情報
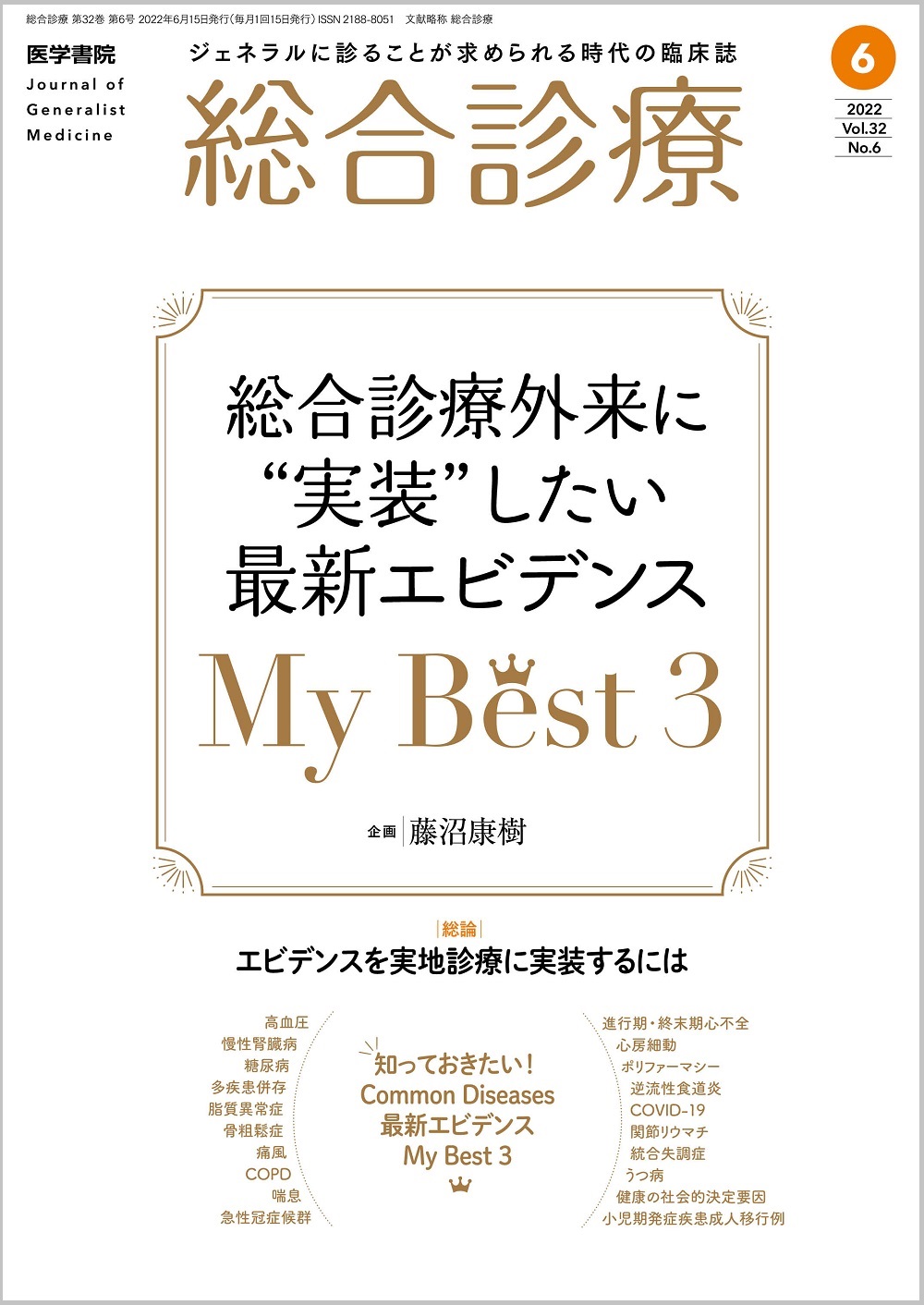
バックナンバー
34巻12号(2024年12月発行)
特集 妊婦・褥婦が外来に来たらUpdate—症状対応からワクチン・プラネタリーヘルスまで
34巻11号(2024年11月発行)
特集 電子カルテとベッドサイドの壁を打ち破る!—患者情報の「言語化」への挑戦
34巻10号(2024年10月発行)
特集 化かしが得意なカメレオンな疾患を捕まえろ!—よくある騙され方のゲシュタルト
34巻9号(2024年9月発行)
特集 今伝えたいクリニカル・パール—つくり方、使い方、活かし方
34巻8号(2024年8月発行)
特集 ストーン・ウォーズ 果てしなき“石”と医師との闘い
34巻7号(2024年7月発行)
特集 どうする!? 健診異常—これってホントに異常なの? どう説明する?
34巻6号(2024年6月発行)
特集 医師のウェルビーイング
34巻5号(2024年5月発行)
特集 —優柔不断にサヨウナラ!—あなたの「臨床判断」を高めるケーススタディ11選
34巻4号(2024年4月発行)
特集 困ったときの漢方—この症状に役立ちます!
34巻3号(2024年3月発行)
特集 —え、ウソ!実は◯◯だった!?—“コモンディジーズ”の診断ピットフォール
34巻2号(2024年2月発行)
特集 日常診療で出合う筋骨格疾患—脳神経内科と整形外科からのアプローチ
34巻1号(2024年1月発行)
特集 —“体験型”臨床クイズで習得する!—フィジカル診断エクセレンス
33巻12号(2023年12月発行)
特集 海の外へ渡る航行者を診る—アウトバウンドにまつわるetc.
33巻11号(2023年11月発行)
特集 —続・総合診療外来に“実装”したい—最新エビデンスMy Best 3
33巻10号(2023年10月発行)
特集 ○×クイズ110問!日常診療アップグレード—Choosing WiselyとHigh Value Careを学ぼう
33巻9号(2023年9月発行)
特集 ジェネラリストのための「発達障害(神経発達症)」入門
33巻8号(2023年8月発行)
特集 都市のプライマリ・ケア—「見えにくい」を「見えやすく」
33巻7号(2023年7月発行)
特集 “消去法”で考え直す「抗菌薬選択」のセオリー—広域に考え、狭域に始める
33巻6号(2023年6月発行)
特集 知っておくべき!モノクロな薬たち(注:モノクローナル抗体の話ですよ〜)
33巻5号(2023年5月発行)
特集 —疾患別“イルネススクリプト”で学ぶ—「腹痛診療」を磨き上げる22症例
33巻4号(2023年4月発行)
特集 救急対応ドリル—外来から在宅までの60問!
33巻3号(2023年3月発行)
特集 —自信がもてるようになる!—エビデンスに基づく「糖尿病診療」大全—新薬からトピックスまで
33巻2号(2023年2月発行)
特集 しびれQ&A—ビビッとシビれるクリニカルパール付き!
33巻1号(2023年1月発行)
特集 COVID-19パンデミック 振り返りと将来への備え
32巻12号(2022年12月発行)
特集 レクチャーの達人—とっておきの生ライブ付き!
32巻11号(2022年11月発行)
特集 不定愁訴にしない“MUS”診療—病態からマネジメントまで
32巻10号(2022年10月発行)
特集 日常診療に潜む「処方カスケード」—その症状、薬のせいではないですか?
32巻9号(2022年9月発行)
特集 総合診療・地域医療スキルアップドリル—こっそり学べる“特講ビデオ”つき!
32巻8号(2022年8月発行)
特集 こんなところも!“ちょいあて”エコー—POCUSお役立ちTips!
32巻7号(2022年7月発行)
特集 —どうせやせない!? やせなきゃいけない??苦手克服!—「肥満」との向き合い方講座
32巻6号(2022年6月発行)
特集 総合診療外来に“実装”したい最新エビデンス—My Best 3
32巻5号(2022年5月発行)
特集 「診断エラー」を科学する!—セッティング別 陥りやすい疾患・状況
32巻4号(2022年4月発行)
特集 えっ、これも!? 知っておきたい! 意外なアレルギー疾患
32巻3号(2022年3月発行)
特集 AI時代の医師のクリニカル・スキル—君は生き延びることができるか?
32巻2号(2022年2月発行)
特集 —withコロナ—かぜ診療の心得アップデート
32巻1号(2022年1月発行)
特集 実地医家が楽しく学ぶ 「熱」「炎症」、そして「免疫」—街場の免疫学・炎症学
31巻12号(2021年12月発行)
特集 “血が出た!”ときのリアル・アプローチ—そんな判断しちゃダメよ!
31巻11号(2021年11月発行)
特集 Q&Aで深める「むくみ診断」—正攻法も!一発診断も!外来も!病棟も!
31巻10号(2021年10月発行)
特集 医師の働き方改革—システムとマインドセットを変えよう!
31巻9号(2021年9月発行)
特集 「検査」のニューノーマル2021—この検査はもう古い? あの新検査はやるべき?
31巻8号(2021年8月発行)
特集 メンタルヘルス時代の総合診療外来—精神科医にぶっちゃけ相談してみました。
31巻7号(2021年7月発行)
特集 新時代の「在宅医療」—先進的プラクティスと最新テクノロジー
31巻6号(2021年6月発行)
特集 この診断で決まり!High Yieldな症候たち—見逃すな!キラリと光るその病歴&所見
31巻5号(2021年5月発行)
特集 臨床医のための 進化するアウトプット—学術論文からオンライン勉強会、SNSまで
31巻4号(2021年4月発行)
特集 消化器診療“虎の巻”—あなたの切実なギモンにズバリ答えます!
31巻3号(2021年3月発行)
特集 ライフステージでみる女性診療at a glance!—よくあるプロブレムを網羅しピンポイントで答えます。
31巻2号(2021年2月発行)
特集 肺炎診療のピットフォール—COVID-19から肺炎ミミックまで
31巻1号(2021年1月発行)
特別増大特集 新型コロナウイルス・パンデミック—今こそ知っておきたいこと、そして考えるべき未来
30巻12号(2020年12月発行)
特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き) Part 2
30巻11号(2020年11月発行)
特集 診断に役立つ! 教育で使える! フィジカル・エポニム!—身体所見に名を残すレジェンドたちの技と思考
30巻10号(2020年10月発行)
特集 —ポリファーマシーを回避する—エビデンスに基づく非薬物療法のススメ
30巻9号(2020年9月発行)
特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【感染症・内分泌・整形外科 編】
30巻8号(2020年8月発行)
特集 マイナーエマージェンシー門外放出—知っておくと役立つ! テクニック集
30巻7号(2020年7月発行)
特集 その倦怠感、単なる「疲れ」じゃないですよ!—筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群とミミック
30巻6号(2020年6月発行)
特集 下降期慢性疾患患者の“具合”をよくする—ジェネラリストだからできること!
30巻5号(2020年5月発行)
特集 誌上Journal Club—私を変えた激アツ論文
30巻4号(2020年4月発行)
特集 大便強ドリル—便秘・下痢・腹痛・消化器疾患に強くなる41問!
30巻3号(2020年3月発行)
特集 これではアカンで!こどもの診療—ハマりがちな11のピットフォール
30巻2号(2020年2月発行)
特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【循環器・消化器・神経疾患編】
30巻1号(2020年1月発行)
特集 総合診療医の“若手ロールモデル”を紹介します!—私たちはどう生きるか
29巻12号(2019年12月発行)
特集 困っている“あなた”に届く 認知症診療
29巻11号(2019年11月発行)
特集 臨床写真図鑑 レアな疾患編—見逃したくない疾患のコモンな所見
29巻10号(2019年10月発行)
特集 教えて!医師のためのビジネス・スキル
29巻9号(2019年9月発行)
特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き)
29巻8号(2019年8月発行)
特集 —ノーモア見逃し—日常の検査と画像に潜むピットフォール
29巻7号(2019年7月発行)
特集 リウマチ・膠原病ミミック症例帖—“膠原病っぽくみえてしまう疾患たち”にだまされない!
29巻6号(2019年6月発行)
特集 皮膚科診療エクササイズ—1枚の写真から
29巻5号(2019年5月発行)
特集 一般外来で診断できたら「えっへん!」な疾患38
29巻4号(2019年4月発行)
特集 “ナゾ”の痛み診療ストラテジー|OPQRSTで読み解く
29巻3号(2019年3月発行)
特集 —あなたのギモンに答えます!—循環器診療のハードルを下げるQ&A31
29巻2号(2019年2月発行)
特集 意外な中毒、思わぬ依存、知っておきたい副作用—一般外来で!OTCも処方薬も!
29巻1号(2019年1月発行)
特集 教えて検索!—膨大な医学情報を吟味・整理するスキル
28巻12号(2018年12月発行)
特集 こんなときこそ漢方を!
28巻11号(2018年11月発行)
特集 日本一マジメな「おしっこドリル」—今これだけは押さえておきたい腎・泌尿器のモンダイ
28巻10号(2018年10月発行)
特集 クリニカル・パールPremium!—憧れのカリスマ医師はかく語りき
28巻9号(2018年9月発行)
特集 オンコ・ジェネラリスト—「がん」に強い総合診療医をめざして
28巻8号(2018年8月発行)
特集 80歳からの診療スタンダードUp to Date—Silver Standard
28巻7号(2018年7月発行)
特集 この薬だけは押さえておきたい! 総合診療医のためのSpecialist Drug 40
28巻6号(2018年6月発行)
特集 聴診・触診×エコーで診断推論!—Point-of-Care超音波(POCUS)の底力
28巻5号(2018年5月発行)
特集 “一発診断”トレーニング問題集—懸賞論文「GM Clinical Pictures」大賞発表!
28巻4号(2018年4月発行)
特集 感染症外来診療「賢医の選択」—検査・経口薬・ワクチンをどう使えばいいんですか?
28巻3号(2018年3月発行)
特集 糖尿病のリアル—現場の「困った!」にとことん答えます。
28巻2号(2018年2月発行)
特集 頭痛患者で頭が痛いんです!
28巻1号(2018年1月発行)
特集 シン・フィジカル改革宣言!—私の“神技”伝授します。
27巻12号(2017年12月発行)
特集 小児診療“苦手”克服!!—劇的Before & After
27巻11号(2017年11月発行)
特集 今そこにある、ファミリー・バイオレンス|Violence and Health
27巻10号(2017年10月発行)
特集 めまいがするんです!─特別付録Web動画付
27巻9号(2017年9月発行)
特集 うつより多い「不安」の診かた—患者も医師も安らぎたい
27巻8号(2017年8月発行)
特集 見逃しやすい内分泌疾患─このキーワード、この所見で診断する!
27巻7号(2017年7月発行)
特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 3 カリスマ編
27巻6号(2017年6月発行)
特集 「地域を診る医者」最強の養成法!
27巻5号(2017年5月発行)
特集 コミュニケーションを処方する—ユマニチュードもオープンダイアローグも入ってます!
27巻4号(2017年4月発行)
特集 病歴と診察で診断できない発熱!—その謎の賢い解き方を伝授します。
27巻3号(2017年3月発行)
特集 これがホントに必要な薬40—総合診療医の外来自家薬籠
27巻2号(2017年2月発行)
特集 The総合診療ベーシックス—白熱!「総合診療フェスin OKINAWA」ライブ・レクチャー! 一挙公開 フィジカル動画付!
27巻1号(2017年1月発行)
特集 総合診療の“夜明け”—キーマンが語り尽くした「来し方、行く末」
26巻12号(2016年12月発行)
特集 これでパッチリ! 眼の健康問題
26巻11号(2016年11月発行)
特集 続・しびれるんです!
26巻10号(2016年10月発行)
特集 内科診療を劇的に変える“まとめ”の達人
26巻9号(2016年9月発行)
特集 症状・症候別 エコーを使った診断推論─Point-of-Care超音波
26巻8号(2016年8月発行)
特集 The 初診外来
26巻7号(2016年7月発行)
特集 感染症ケアバンドル・チェックリスト
26巻6号(2016年6月発行)
特集 “賢い処方”と“ナゾ処方”
26巻5号(2016年5月発行)
特集 しびれるんです!─知っておくべきシビレル疾患
26巻4号(2016年4月発行)
特集 ケースとクイズで総ざらい! 街場の2型糖尿病治療
26巻3号(2016年3月発行)
特集 こんな時は漢方でしょう!
26巻2号(2016年2月発行)
特集 フィジカル改革宣言! ──診断からフォローアップまで
26巻1号(2016年1月発行)
特集 妊婦・褥婦が一般外来に来たら─エマージェンシー&コモンプロブレム
25巻12号(2015年12月発行)
特集 外来で「複数の疾患」をもつ患者を診る─マルチモビディティの時代のプライマリ・ケア
25巻11号(2015年11月発行)
特集 レアだけど重要な「痛み」の原因─システム1診断学
25巻10号(2015年10月発行)
特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 2
25巻9号(2015年9月発行)
特集 診断ピットフォール10選─こんな疾患,見逃していませんか?
25巻8号(2015年8月発行)
特集 健診データで困ったら─こんな検査結果を持ってこられたら
25巻7号(2015年7月発行)
特集 ここを知りたい!頭部外傷初期対応・慢性期ケア
25巻6号(2015年6月発行)
特集 高齢者救急の落とし穴─紹介する時,される時
25巻5号(2015年5月発行)
特集 咳を聴きとり,咳を止める
25巻4号(2015年4月発行)
特集 関節が痛いんです!─コモンからレアものまでの診断と治療
25巻3号(2015年3月発行)
特集 神経難病ケアのコペルニクス的転回
25巻2号(2015年2月発行)
特集 総合医のためのスポーツ医学ベーシックス
25巻1号(2015年1月発行)
特集 動悸・息切れ─ヤバい病気の見つけ方 そして見つからなかった時の対処法
