PubMed収載誌に掲載されたPOCUS(point-of-care ultrasound)関連論文は年々右肩上がりで増え続けており、2021年10月には『New England Journal of Medicine』誌に10年ぶりにPOCUSの総説が掲載されました(N Engl J Med 2021;385(17):1593-1602. PMID: 34670045)。国際的に非常に注目されているPOCUSですが、日本でもPOCUSに対する認知度は年々向上しており、書籍も多く出版されるようになりました。POCUSのスキル修得のための国際標準コースも、2017年7月に国内で第1回が開催され(JHospitalist Network主催)、2020年にはPOCUSの第一人者で同コースディレクターでもあるNilam J. Soni先生のバイブル本である『Point-of-Care Ultrasound』第2版の翻訳本(丸善出版)も出版されています。
今回、こうした流れの中で、本誌『総合診療』では4年ぶりにPOCUSについての特集を企画します。とはいえ、心臓・腹部・肺・下肢静脈などのエコーは、もはや「おなじみの部位」のエコーになってきており、類書も多く存在します。
本特集では、ルーチンに近いエコー評価は敢えて“あまり”取り上げず、徐々に浸透しつつある領域や、比較的新しい領域、急ぐ必要のある病態でのエコーの活用「POCUSお役立ちTips!」の企画を皆様にお届けします。
雑誌目次
総合診療32巻8号
2022年08月発行
雑誌目次
特集 こんなところも!“ちょいあて”エコー—POCUSお役立ちTips!
扉 フリーアクセス
著者: 佐藤直行
ページ範囲:P.920 - P.921
今月の「めざせ! 総合診療専門医!」問題
ページ範囲:P.998 - P.999
本問題集は、今月の特集のご執筆者に、執筆テーマに関連して「総合診療専門医なら知っておいてほしい!」「自分ならこんな試験問題をつくりたい!」という内容を自由に作成していただいたものです。力試し問題に、チャレンジしてみてください。
【@外来】
❶関節、腱、神経など骨軟部組織の撮像ポイント
著者: 森達男 , 花岡成典
ページ範囲:P.922 - P.925
エコー検査は対象物の運動の様子をリアルタイムに見ることができるため、関節、筋、腱、滑液包といった筋骨格系の評価に適性が高く、整形外科やリウマチ科で近年広く診療に取り入れられている。国内外の団体が、筋骨格エコー技術を拡充するために研修会などを行っている。欧州リウマチ学会(EULAR)では、オンラインでも学習コースや実地での研修を開催し1)、充実した資料を提供している2)。日本リウマチ学会は、2014年から学会認定ソノグラファーの制度を始め、関節超音波の講習会を各地で開催して、エコー技術の標準化に力を入れている。
しかし総合診療領域においては、筋骨格エコーはまだ馴染みが薄い分野だろう。総合診療において筋骨格系の愁訴を相談される場面は多々あり、筋骨格エコーの技術は役立つはずである。
❷関節×エコー—痛風、偽痛風
著者: 安本有佑
ページ範囲:P.926 - P.929
結晶性関節炎
結晶性関節炎とは、関節内や関節周囲の腱付着部、滑液包などに沈着した結晶に関連した炎症である。その代表例として、尿酸ナトリウム(monosodium urate: MSU)による痛風関節炎、ピロリン酸カルシウム(calcium pyrophosphate: CPP)による偽痛風が挙げられ、本稿ではこれら2つについて取り扱う。いずれも緊急度の高い疾患ではないが、鑑別が必要な化膿性関節炎などは迅速な診断および治療が望ましいため、適切な診断が必要である。
原則として、それぞれ診断の確定には関節液の顕微鏡検査が必要である。しかし、たとえ結晶が鏡検で見えたとしても、約5%で化膿性関節炎が合併することも報告されており、病歴、身体所見、その他の検査を含めた総合的な判断が必要である1)。忙しい外来のなかで診断を確定させることは難しいかもしれないが、エコーを“ちょいあて”することで、その後のスムースなマネジメントにつなげたい。
❸正中神経×エコー—手根管症候群
著者: 石塚光太郎
ページ範囲:P.930 - P.933
手根管症候群(CTS)
手根管とは、手根骨と横手根靭帯とから成るトンネル(図1)であり1)、このなかには正中神経と長母指屈筋腱、示指から小指の深・浅指屈筋腱が通過している。手根管症候群(carpal tunnel syndrome : CTS)はこの部位に起こる、さまざまな原因によって生じる正中神経障害の総称である。
手根管症候群との鑑別が必要な疾患は、頸椎神経根症状(頸椎症性神経根症や頸椎椎間板ヘルニアなど)や頸椎症・脊髄症のような整形外科疾患から、糖尿病や甲状腺疾患、多発神経炎などの内科疾患も考えられる。また関節リウマチや透析の既往、妊娠期や更年期にも関連すると言われているため、問診は鑑別をしていくうえで重要である。
❹側頭動脈×エコー—巨細胞性動脈炎
著者: 板金正記 , 金城光代
ページ範囲:P.935 - P.937
巨細胞性動脈炎(GCA)
巨細胞性動脈炎(giant cell arteritis:GCA)は、通常50歳以上に発症し、大動脈とその分枝に至る大血管および中血管の血管炎を特徴とする。なかでも側頭動脈は、頭蓋内で最もGCAによる血管炎を起こしやすい動脈である。頻度の高い症状として、発熱、食思不振、体重減少などの全身症状、新規発症の頭痛を押さえておく。その他、頭皮の感覚異常(髪を櫛でとかす時の知覚過敏)や顎跛行(咀嚼時に徐々に顎が重だるくなる)は、約半数の患者にみられる。患者の40〜50%にリウマチ性多発筋痛症(polymyalgia rheumatica:PMR)を合併することが知られており、PMR様の症状(朝のこわばり、両肩挙上困難、寝返りが打てない)も聴取する。失明はGCAの緊急症で、前駆症状として複視や一過性黒内障が10%でみられ、その半数が失明に至るため注意が必要である1)。高齢者では全身症状が主体で、不明熱として紹介されてくることもある。GCAを疑う患者では、浅側頭動脈の前頭、もしくは頭頂枝に圧痛、肥厚、結節、発赤がないか、また触診にて脈の減弱・消失がないかを確認する。他に聴診では鎖骨上窩や頸動脈分岐部、大動脈弁領域の血管雑音がないか、眼底検査では虚血性病変がないかを確認する1)。
❺ヘルスメンテナンス×エコー—動脈硬化性疾患スクリーニング
著者: 河田祥吾
ページ範囲:P.938 - P.941
スクリーニングとは?
ヘルスメンテナンスの1つであるスクリーニングは、無症状の病気や病態、または病気のリスクを発見して、何らかの介入を行うもので、がん検診だけでなく、うつ病やアルコール依存症など健康問題を調べることも含まれる1)。日本においては一部のがん検診を除き、合意されたエビデンスに基づくスクリーニングに関する推奨がなされていないため、米国予防医学専門委員会(United States Preventive Services Task Force:USPSTF)の推奨を用いて実践することが多い。USPSTFにおいて、エコーを用いたスクリーニングで推奨されているのは、腹部大動脈瘤(abdominal aortic aneurysm:AAA)のみである(2022年3月4日時点)。
本稿では、まずAAAスクリーニングについて解説し、次いで動脈硬化性疾患関連として頸動脈狭窄(carotid artery stenting : CAS)についても解説する。
【@救急】
❻骨折×エコー
著者: 神野敦
ページ範囲:P.942 - P.945
骨折と超音波検査
骨折は、救急患者において頻度の高い疾患の1つで、その診断はX線写真、CT、MRIなどの画像検査を基に行うのが一般的である。近年、超音波装置の小型化、低価格化により、さまざまな領域においてベッドサイド超音波検査が実施されるようになり、骨折診療においても超音波検査、特にPOCUS(point-of-care ultrasound)が有用であることが明らかになってきた。外傷診療において“超音波”と聞くと、FAST(focused assessment with sonography for trauma)の印象が強く、超音波検査はprimary surveyに用いると認識されている場合も多いが、『外傷初期診療ガイドラインJATEC改定第6版』1)において、骨折の評価に対する超音波検査の活用が取り上げられており、診療における超音波検査の活用はさらなる広がりを見せることが期待されている。
現在では、さまざまな種類の骨折においてPOCUSの診断性能が報告され、POCUSの有効性が示されている。たとえば、上肢および下肢の骨折における診断性能を検討したChampagneらのsystematic reviewでは、超音波検査の診断能は上肢骨折で感度93%・特異度92%、下肢骨折で感度83%・特異度93%であったと報告されている2)。POCUSの特性である、簡便、迅速、低侵襲の要素に加え、高い診断能もPOCUSを活用する理由の1つである。
❼卵巣×エコー
著者: 柴田綾子
ページ範囲:P.946 - P.950
子宮と卵巣の経腹エコー
経腹エコーで子宮や卵巣を見る際は、膀胱に尿が溜まっているほうが見やすくなる(子宮の前に腸管がなくなり、膀胱と子宮の境界がわかりやすくなるため)(表1)。逆に、経腟エコーをする場合は、排尿後のほうが検査しやすい。妊娠可能女性の腹痛では、尿中のヒト絨毛性ゴナドトロピン(human chorionic gonadotropin:hCG)を調べる妊娠反応検査を施行することが多いため、経腹エコー検査との順番に注意する。
子宮は膀胱と直腸の間に見える(図1)。非妊娠時の子宮は長径約7〜8cm、正常卵巣は3〜4cmほどで、閉経後は子宮も卵巣も萎縮する。子宮自体が大きい場合は、子宮腺筋症、子宮筋腫、子宮留膿症などを鑑別に挙げる。卵巣の位置は個人差があり、子宮後面の卵巣窩(総腸骨動静脈が内・外腸骨動静脈に分岐する三角部)にあることが多い。日本人を対象とした経腹エコー検査では、約38.9%(16〜45歳の女性の66.2%、45歳以上の女性の5.7%)の正常卵巣が検出可能だったという報告があるが1)、実際には肥満や腸管ガスなどで正常卵巣が見えないことも多い。
❽皮膚軟部感染症×エコー—蜂窩織炎と膿瘍、壊死性筋膜炎
著者: 官澤洋平
ページ範囲:P.951 - P.954
皮膚軟部感染症
皮膚軟部感染症は、単純な蜂窩織炎から壊死性筋膜炎に及ぶさまざまな疾患の集まりである。蜂窩織炎の30%は誤診であるという報告もあり1)、皮膚軟部感染症の診断は一筋縄にはいかない。診断エラーは、不必要な抗菌薬投与などの医療曝露や、介入が必要な病変や重篤な疾患の見逃しによる致死的な経過となってしまうこともある。
皮膚軟部感染症を考えるうえで、皮膚軟部組織の解剖についての理解が、疾患の臨床像やエコーを含めた画像診断のために重要である(図1)2)。頻度が高い蜂窩織炎は、皮下脂肪を主座とする感染症である。一般的には非侵襲的な治療(抗菌薬・安静・アイシング)で治癒するが、切開排膿やドレナージが必要となる皮下膿瘍を見逃さないことが大切である。
❾気腫性尿路感染症×エコー
著者: 佐藤直行
ページ範囲:P.955 - P.958
気腫性尿路感染症
気腫性尿路感染症(emphysematous urinary tract infection)とは、ガス産生を伴った上部あるいは下部尿路感染症である。尿路感染症のなかでは稀であるが、主に気腫性膀胱炎と気腫性腎盂炎・腎盂腎炎(本稿では「気腫性腎盂腎炎」とまとめる)があり、尿路感染症の所見に加え、画像でガス産生の所見があれば診断できる。表11)に気腫性尿路感染症の特徴を示したが、臨床症状のみで通常の(気腫を伴わない)尿路感染症と鑑別することは難しいうえに、本症は重症度が高く、治療としても抗菌薬投与以外の介入を要することがあるため、「疑って、早く気づく」ことが重要である。
ガス像は単純X線写真でも確認できることがあるが、特に腎臓付近では腸管ガスとの区別が難しいことが多く、CT画像のほうが感度が高い。しかし、一般的に尿路感染症を疑った段階で全例にCT撮影することはなく、そもそも診療所などではCTにアクセスできない状況もある。腎盂腎炎で初療時に画像検査を行うタイミングは、敗血症を疑う時やショック合併時、あるいは、❶腎結石の既往、❷尿pH≧7.0、❸新規eGFR≦40mL/分/1.73m2の3つのうちいずれか1つがある場合であり、尿路の閉塞機転の確認が主目的となる2)。その際にエコー検査が有用であるが、ここで気腫性尿路感染症も疑うことができるかどうかが本稿のポイントになる。
【@病棟・手技】
❿動・静脈留置カテーテル挿入×エコー
著者: 片桐欧 , 吉野俊平
ページ範囲:P.959 - P.963
エコー下動脈留置カテーテル挿入
従来、動脈留置カテーテル挿入は触診法(ランドマーク法)で行われてきたが、近年は超音波ガイド下で行う動脈留置カテーテル挿入が普及してきている。ベッドサイドエコー(POCUS)はすべての分野において広まっており、動脈留置カテーテル挿入に関しても同様に、Society of Hospital Medicine(SHM)などでも推奨されている1)。
⓫腰椎穿刺×エコー
著者: 本田優希
ページ範囲:P.964 - P.967
腰椎穿刺でのエコーの使いどころ
患者の肥満や脊椎の変形・弯曲などのため、腰椎穿刺の手技が難しいことがあります。触診で棘突起がわかりにくい、脊椎が弯曲して正中線が同定できない、棘間が狭くて穿刺できない、針が骨に当たってしまい正しい穿刺方向がわからない等々…。そんな時、エコーを使うことで手技の成功率を高めることができるかもしれません。
2019年に米国のHospitalistの学会であるSociety of Hospital Medicineから、成人の腰椎穿刺でエコーガイドによる穿刺部位の同定を推奨するposition statementが出るなど1)、その有用性が認識されてきています。
⓬挿管×エコー
著者: 糟谷智史 , 坂本壮
ページ範囲:P.968 - P.970
心肺停止状態や気道緊急、呼吸不全、ショック、意識障害など重症患者を診療する際に、気管挿管は非常に重要な手技であるが、患者の状態や手技を行う環境によって難易度は大きく異なるため、経験豊富な救急医といえども容易でないことがしばしば見受けられる。ましてや普段慣れていない医師にとっては、気管挿管は非常に難しく、プレッシャーのかかる手技である。
一般的に挿管が成功したように思えて失敗している時には、食道挿管をしていることが多い。これに気づかず放置すると、低酸素脳症や心肺停止など不幸な結果を招いてしまうため、気管内に挿管できていることを手技の直後に確認することは非常に重要である。確認方法としては、呼吸音やチューブの曇り、胸郭の動きなどの身体所見に加えて、可能なら波形表示のある呼気中CO2モニターを用いることが推奨されているが、使用できない場所では波形表示のないCO2モニターや、比色式CO2検出機、食道挿管検出機、あるいは気管超音波検査で代用するようにと『JRC蘇生ガイドライン2020』で推奨されている1)。
⓭抜管×エコー—横隔膜エコー
著者: 鍋島正慶
ページ範囲:P.971 - P.975
人工呼吸器の適応となった状態が安定したら、毎日の人工呼吸器からの離脱を検討する。離脱ができるかどうかを判断するためには、PEEP 5cmH2O、サポート圧5〜8cmH2Oなどの最小限の設定の自発呼吸モードや、Tピースによる自発呼吸トライアル(spontaneous breathing trial:SBT)を30〜120分行う。ガス交換能、循環動態、呼吸状態が落ち着いている場合、SBTは成功と判断し、人工呼吸器からの離脱、すなわち多くの場合は抜管を行う1)。
しかし必ずしもSBTに成功した患者が抜管に成功するわけではない。抜管が失敗する原因には、呼吸状態の悪化、循環動態の悪化、喀痰排泄の問題、意識障害による気道維持の問題、上気道閉塞が含まれる2)。
【@在宅・緩和・教育】
⓮ポケットエコー活用事例
著者: 近藤敬太
ページ範囲:P.976 - P.980
ここまで、外来、救急、病棟・手技でのPOCUS(point-of-care ultrasound)の重要性について解説していただきました。大型のエコー装置だけでなく、近年、ポケットエコーの使い勝手も非常に良くなっています。ポケットエコーの普及に伴い、在宅医療の現場でのPOCUSも急激に広まってきており、私も毎日のように在宅医療の現場で活用しています。
私たちのプログラムでは、専攻医に少しでもエコーに慣れ親しんでほしいという想いから、2021年度に富士フイルムとの共同研究として総合診療プログラムの専攻医に1人1台ポケットエコーを導入しました。
⓯褥瘡×エコー
著者: 大浦誠
ページ範囲:P.981 - P.985
褥瘡は、寝たきりの患者に最もよく見られる症状の1つである。皮膚が圧迫されて発赤となり、損傷があっても真皮内にとどまっているのが「1度褥瘡」と呼ばれる軽度の褥瘡で、圧迫を解除すれば短時間で改善する。一方で、圧迫が持続すると不可逆な虚血性変化から潰瘍を形成して、いわゆる褥瘡と言われるものになる。端的に言えば、自然に治癒する発赤なのか、褥瘡に移行する可能性のある深部組織の損傷なのかの見分けがつかないことが問題なのである。診断が曖昧だと、標準的なケアをしているにもかかわらず、きちんと除圧できているどうかのモニタリングを行うことも困難である。褥瘡になると医療費の拡大にも影響するため、早期診断が望ましいのは言うまでもない。
褥瘡の国際ガイドラインでも、国内のガイドラインでも、深部組織損傷(deep tissue injury:DTI)という用語が使われている。これは「初期の段階では表皮から判断すると一見軽症の褥瘡に見えるが、時間の経過とともに深い褥瘡へと変化するもの」と定義されている。実際には圧力やずれなどの負荷で虚血や代謝障害が起こり、深部組織に壊死が起こっている状態である。褥瘡の評価スケールも2020年に改定されて「DESIGN-R®2020」となり、深さを評価する項目に「DTI疑い」という項目が追加されている1)。
⓰緩和ケア×エコー
著者: 石上雄一郎
ページ範囲:P.986 - P.989
なぜ、緩和ケア領域にも超音波が必要なのか?
昨今、緩和ケアは早期から行われるようになり、さまざまな非がんの領域(救急集中治療・心不全など)と統合している。実際の現場では、慢性期、急性期、そして終末期は連続していることが多く、急性期治療と緩和ケアを分けることは不可能である。
緩和ケアとは、一言で言うと、「苦痛を緩和することで、患者と家族のQOLを上げること」であり、このマインドセットは、緩和ケアの専門家に限らず、すべての医療者に必要である。緩和ケアを必要とする患者の定量化は難しいが、急性期の医師のキャリアのなかでは“開胸”することよりも、緩和ケアの状況に遭遇することのほうが間違いなく多い。
⓱医学教育×エコー
著者: 小杉俊介
ページ範囲:P.990 - P.993
昨今、POCUS(point-of-care ultrasound)は日常的に行われている身体診察の一部とも捉えられるほどに普及してきており、超音波機器は聴診器と同じように、日常的に使用できるツールとなりつつある1)。そのため、北米を中心とした海外では、その教育が医学部卒前教育の段階で必要であると判断され、POCUSカリキュラムが導入されるようになってきている2,3)。
2014年の段階で、すでに全米の医学部の60%以上がPOCUSをカリキュラムに組み込んでいることが確認されており4)、2022年現在では、さらに多くの医学部がPOCUS教育に取り組んでいることが推定される。海外はもとより、日本でもエコー教育が注目されており、日本内科学会・日本救急医学会などを中心にPOCUSの普及が行われている。
【コラム】
❶POCUSのセミナーと書籍などの紹介—コロナ禍でもPOCUSを学ぶために
著者: 佐藤直行
ページ範囲:P.994 - P.994
昨今、新型コロナウイルス感染症の影響により、エコー技能の修得には欠かせないハンズオンセミナーの開催が難しくなっています。しかしこういった状況でも、各団体でオンライン開催を行うなど、工夫を凝らしながらPOCUS(point-of-care ultrasound)の普及への努力が続けられています。
本稿では、ハンズオンセミナーができない状況でも、座学の第一歩として有用なPOCUS教材をいくつか紹介します。みなさまの生涯学習のお役に立てていただけましたら幸いです。
❷ポケットエコー機の紹介
著者: 上松東宏
ページ範囲:P.995 - P.997
近年、エコーの小型化および性能向上の流れは加速しており、スマホやタブレットに接続して簡単に持ち運びながら検査を行えるようになった。いよいよ“1人1台”の時代の訪れに期待が高まるが、現場ではまだエコーを個人持ちしているのは少数派である。次々と市場に姿を現すポケットエコーを、なかなか選びきれないプライマリ・ケア医もいるのではないだろうか?
本稿では、エコー選びのポイントと主な機種について紹介する。
Editorial
エコーで“見える”これからの診療の可能性 フリーアクセス
著者: 佐藤直行
ページ範囲:P.911 - P.911
近年、エコー機器の性能は飛躍的に進歩し、エコー所見の知見も数多く蓄積され、「人体の組織でエコー評価ができないもののほうが少ないのでは」と思えるほどになってきました。また、身体診察のようにベッドサイドで行うエコー検査であるPOCUS(point-of-care ultrasound)は、世界的にも非常に注目されてきており、活用の場面が著しく広がっています。特に浅い部位にある構造物の描出性能の向上は目を見張るものがあり、以前は“画像に映り込んでいるだけ”と思っていた構造(皮膚や筋肉、筋膜、腱、関節、神経、肺、横隔膜など)も、POCUSの主要な対象になってきました。さらに、ひと昔前は他の画像検査で評価することが多かった病態もPOCUSで評価できますし、熟練の技で実施されていた各種の穿刺手技や(中心静脈路以外の)血管確保などの処置も、エコーガイド下で安全かつ成功率高く施行できるようになってきています。POCUSのお陰で格段に診療がしやすくなる場面が増えており、活用できる状況を知っておくだけで、診療の幅が広がることは間違いありません。
そこで今回の特集では、「エコーを使って診療する時の思考の幅を広げること」を目的に、今後のスタンダードにもなりうるような比較的新しいPOCUSの活用について、現場の最前線でPOCUSを活用している先生方にご解説いただきました。新しい視点に焦点を当てるため、エコーの入門書でよく取り上げられる部位や病態の解説はあえてあまり取り上げず、正常像の解説についても、見慣れない方が多いと思われる筋骨格系エコーのみとしています。加えて、ポケットエコー機も増えていますので、在宅診療での活用事例も取り上げました(導入に興味のある方はポケットエコー機の紹介コラムp.995もご覧ください)。緩和ケアや教育、救急、病棟・集中治療などの場面に応じた活用も広がっており、本特集から、POCUSが場所を選ばずに医療の質と患者安全の改善に役立っていることを実感していただけることと存じます。
What's your diagnosis?[236]
SESA症候群—飲んだらシーサー
著者: 三谷和可 , 風間亮 , 妻鹿旭 , 北村大 , 浅川麻里 , 浜田禅
ページ範囲:P.915 - P.919
病歴
患者:56歳、男性
主訴:意識障害
現病歴(救急外来にて訪問看護師より聴取):糖尿病、アルコール依存症で他院に通院している。16歳から飲酒を始め、X-4年前にアルコール依存症と診断された。アルコール専門病院で計5回の断酒治療を受けた。身内はおらず独居。週1回訪問看護を受けながら、作業所に通所していた。X年、入院2カ月前から飲酒を再開した。正確な飲酒量は不明であったが、焼酎一升が2日でなくなるほどだった。入院前日は作業所に行ったが、入院当日は朝から無断欠勤をしていた。不審に思った訪問看護師が自宅を訪問すると、患者が全裸で床に座り込み、尿・便失禁しているのを発見した。受け答えができず、立ち上がれない状態であったため、訪問看護師が救急要請した。
喫煙歴:15本/日×40年
飲酒歴:16歳〜。最近は焼酎1升が2日間でなくなる
内服薬:ウルソデオキシコール酸150mg、シダクリプチン50mg、メトホルミン1,000mg、ピオグリタゾン15mg、インスリンアスパルト6単位
アレルギー:なし
【エッセイ】アスクレピオスの杖—想い出の診療録・28
米国Kentucky大学への臨床留学記—思い出の診療録(1984〜85年)より
著者: 青木眞
ページ範囲:P.1000 - P.1001
本連載は、毎月替わる著者が、これまでの診療で心に残る患者さんとの出会いや、人生を変えた出来事を、エッセイにまとめてお届けします。
オール沖縄!カンファレンス|レジデントの対応と指導医の考えVer.2.0・67
“ねこばば”が問題となった1例—頸部リンパ節腫脹を訴える30代女性
著者: 高江洲真 , 永田恵蔵 , 徳田安春
ページ範囲:P.1017 - P.1021
CASE
患者:31歳、女性。
主訴:頸部リンパ節腫脹・疼痛。
現病歴:1カ月前に悪寒戦慄を伴わない発熱・多関節痛あり。発熱はそれ以降なし。
同時期に、頸部が腫れていることに気づいた。頸部の腫瘤は痛みを伴っており、徐々に腫大してきた。来院前日に顎下にも同様に痛みを伴う腫瘤があるのに気づいたため来院。体重減少・寝汗なし。食事は摂取できている。下痢はよくある。紫外線に当たると肌荒れする。口渇感やドライアイはない。3週間前に温泉旅行に行った。子どもとの接触歴はない。不特定多数との性交渉なし。
既往歴:虫垂炎、手掌多汗症。
内服歴:市販のビタミン剤を内服している。その他、薬剤なし。
家族歴:奇形腫(姉)、肺癌(祖父)、子宮頸癌(祖母)。膠原病・血液疾患・結核の家族歴なし。
生活歴:ADL(activities of daily living)は自立。ペットの飼育歴はない。
嗜好歴:喫煙5本/日、機会飲酒。
高齢者診療スピードアップ塾|効率も質も高める超・時短術・8
「意識障害」は“一発診断”で90分時短する!
著者: 増井伸高
ページ範囲:P.1022 - P.1024
「意識障害」で来院する高齢者は多いです。初学者が困る症例は、「検査はすべて正常」な一部の高齢者意識障害です。マネジメントに困り、時間だけが過ぎてゆくようではいけません。この場合は、鑑別診断で「薬剤性意識障害」をあげられるかがスピードアップにつながります。どのような薬剤を、どう診断するか? 今回は、そのコツを解説します。
患者さんには言えない!? 医者のコッソリ養生法・13
翌日に疲れを残さない、ぐっすり「睡眠」の養生❸—夜寝る前にすべきこと編
著者: 須田万勢
ページ範囲:P.1026 - P.1030
“プチ不健康”を放置してきたツケで弱っていた貝原先生。突然現れた医神アスクレピオス(自称ピオちゃん)に半ば強制的に弟子入りさせられ、養生で健康を取り戻す方法をしぶしぶ学ぶうち、身体も心も少しずつ変わってきた。「風邪」「肩こり」「肥満」「お酒」に続き、ちゃんと疲れがとれる「睡眠」の方法を伝授されることに…。
Dr.上田剛士のエビデンス実践レクチャー!医学と日常の狭間で|患者さんからの素朴な質問にどう答える?・29
右利きの人が多いのはなぜですか?
著者: 上田剛士
ページ範囲:P.1032 - P.1035
患者さんからのふとした質問に答えられないことはないでしょうか? 素朴な疑問ほど回答が難しいものはありませんが、新たな気づきをもたらす良問も多いのではないでしょうか? 本連載では素朴な疑問に、文献的根拠を提示しながらお答えします!
【臨床小説—第二部】後悔しない医者|今と未来をつなぐもの・第28話
聴こえてしまった医者
著者: 國松淳和
ページ範囲:P.1036 - P.1041
前回までのあらすじ 今月のナゾ
西畑は、頭ケ島白浜病院での後期研修をそつなくこなしていた。ある日、念願だった向後の外来に陪席し、なんとなく気になる患者に出くわした。その患者は75歳・女性、新型コロナワクチン接種後に下痢が始まり、副反応の熱が下がったあともなかなか治らないと何度も受診していた。血液検査はすべて陰性、CRPも正常。1週間前に人参湯から半夏瀉心湯に処方を変更し様子をみていたが、体温37.2℃と微熱が出始めたため臨時受診した。患者は「なんだか体がおかしい」と訴えてはいるが元気そうに見え、下部消化管内視鏡検査を予定どおり受けることを促すと、納得して帰っていった。しかし西畑は違和感を覚えていた。なんとなく変…。
器質的な異常を認めないのに、非特異的な症状が続くことはままある。機能性の病態、あるいは時に心因性と高を括って、原因追究を棚上げすることもあるだろう。しかし不調をきたしている以上、ロジックは必ずあるはずだ。それを読み解けば、解決の糸口がつかめるかもしれない。果たして、今回の患者の不調の原因は何なのか?
投稿 総合診療外来
孤発性クロイツフェルト・ヤコブ病
著者: 飯田智哉 , 吉崎秀夫 , 江尻知美 , 岸本利一郎
ページ範囲:P.1006 - P.1007
症例
患者:68歳、男性。
自宅で妻と生活していたが、物忘れの症状が目立ち始め、慣れた道路で迷うようになった。頭部MRIのFLAIR像では軽度の脳萎縮を認めるのみであったが(図1Ⓐ)、急速に認知症が進行、発症から2カ月後には左半側空間無視、寡動、小脳失調、ミオクローヌス、ジストニアなどの神経症状も見られるようになった。脳波では周期性同期性放電(PSD)が見られ、頭部MRIの拡散強調像では大脳皮質、左視床内側、両側線条体などに高信号が認められ(図1Ⓑ)、髄液検査では細胞数正常、蛋白軽度上昇、総タウ蛋白および14-3-3蛋白の高値が確認され、孤発性クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)と診断された。
GM Clinical Pictures
多発する皮下結節の原因は?
著者: 桑原健輔 , 矢部正浩 , 中村杏奈 , 富山勝博
ページ範囲:P.1009 - P.1011
CASE
患者:80代、女性。主訴は左臀部〜左下肢痛、右膝痛。
現病歴:入院3カ月前から右膝関節痛を自覚し、入院2カ月前から右臀部から左下肢に疼痛やしびれを自覚した。症状の改善なく、当院へ紹介され受診した。食欲低下あり、体重減少あり。
既往歴:第5腰椎分離症(20代)、子宮体癌術後(不明)、1カ月前から皮下結節が多発。
生活歴:喫煙歴なし。
家族歴:特記事項なし。
身体所見:全身状態は悪くないが、左下肢痛もあり、臥床している。
1cm大のリンパ節を右後頸部に1個、両腋窩に各数個、両鼠径リンパ節に各数個認めた。体幹・上肢・臀部に1〜5cm大の境界明瞭で可動性のない、弾性〜石様硬の無痛性皮下結節が多発、発赤を伴うものも見られた(図1)。
右側胸部5cm大の皮下結節は一部潰瘍化していた(図2)。
その他、頭頸部、心肺、腹部、四肢に異常なし。
#総合診療
#今月の特集関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.934 - P.934
#今月の特集関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.1012 - P.1013
#今月の連載関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.1024 - P.1024
#医学書院の新刊 フリーアクセス
ページ範囲:P.1014 - P.1015
#編集室に届いた執筆者関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.1015 - P.1015
#書評:—内科救急で使える!—Point-of-Care超音波ベーシックス—【Web動画付】 フリーアクセス
著者: 谷口信行
ページ範囲:P.1003 - P.1003
本書は、カラーなうえに図や写真が多くてわかりやすく、読んでいてワクワクする超音波検査の本である。その疾患の超音波検査を試みたことのある方であれば、臨床の状況と必要な検査を想定できる記述となっている。動画が豊富についているのもいい。超音波検査を扱った書籍は静止画のみで構成されたものが多いが、本書はQRコードにより手元のスマートフォンやタブレットですぐに動画を見ることができる。
タイトルになっている「Point-of-Care超音波(POCUS)」は、研修医だけでなく、内科・外科をはじめとする多くの臨床医にとって、診療に役立つものである。研修医であれば、現場でPOCUSを行うことで、のちに自分で行わなければならない検査のハードルをだいぶ下げることができるだろう。研修医が修得すべき手技は数多くあるが、なかでもPOCUSはその場で検査を行うことができ、安心して次の診療ステップに進むことができる。ちなみに、POCUSにおいて最近注目を集めているのは肺エコーであり、これは救急や在宅の場面で、肺炎などの肺疾患に加え、左心不全の診断に役立つものである。
#書評:—国循・天理よろづ印—心エコー読影ドリル—【Web動画付】 フリーアクセス
著者: 渡辺弘之
ページ範囲:P.1005 - P.1005
心エコーには「読影」が必要だ。私は、この書籍がハートチームに必須の1冊になると確信している。超高齢社会において心疾患は増え続けており、特に心不全症例の増加は顕著である。そのような社会的背景のなかで、心エコー図検査の需要は今後も増え続ける。それは、心エコーの特性が、ベッドサイドでいつでもリアルタイムに心疾患や血行動態を評価することができるからである。在宅医療でもクリニック診療でも病院の救急室でも病棟でも、あらゆる医療の現場に心エコー図検査は拡散していくだろう。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.912 - P.913
『総合診療』編集方針 フリーアクセス
ページ範囲:P.914 - P.914
1991年に創刊した弊誌は、2015年に『JIM』より『総合診療』に誌名を変更いたしました。その後も高齢化はさらに進み、社会構造や価値観、さらなる科学技術の進歩など、日本の医療を取り巻く状況は刻々と変化し続けています。地域医療の真価が問われ、ジェネラルに診ることがいっそう求められる時代となり、ますます「総合診療」への期待が高まってきました。これまで以上に多岐にわたる知識・技術、そして思想・価値観の共有が必要とされています。そこで弊誌は、さらなる誌面の充実を図るべく、2017年にリニューアルをいたしました。本誌は、今後も下記の「編集方針」のもと、既存の価値にとらわれることなく、また診療現場からの要請に応え、読者ならびに執筆者のみなさまとともに、日本の総合診療の新たな未来を切り拓いていく所存です。
2018年1月 『総合診療』編集委員会
読者アンケート
ページ範囲:P.1016 - P.1016
『総合診療』バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.1042 - P.1043
お得な年間購読のご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.1043 - P.1044
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.1045 - P.1046
基本情報
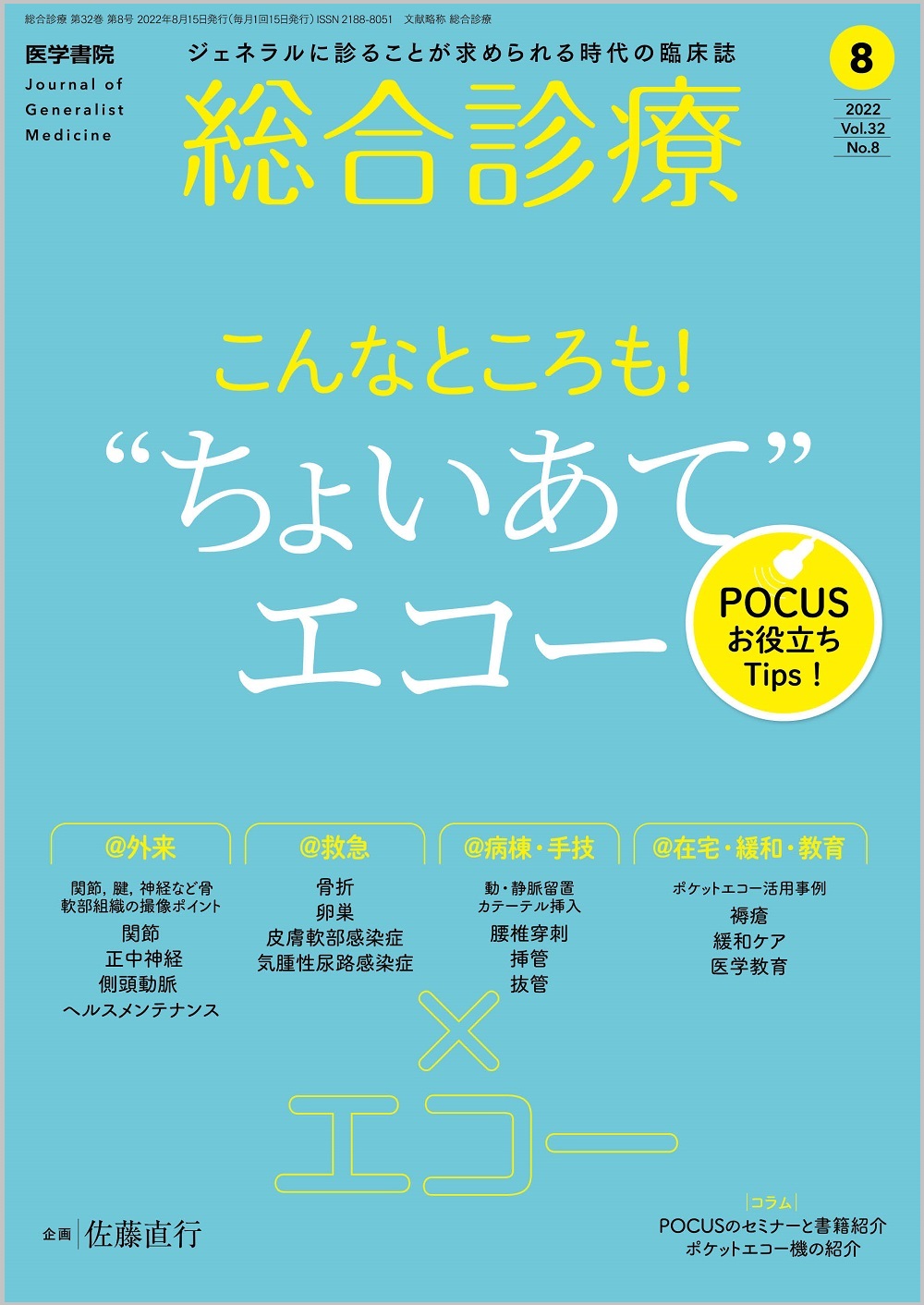
バックナンバー
34巻12号(2024年12月発行)
特集 妊婦・褥婦が外来に来たらUpdate—症状対応からワクチン・プラネタリーヘルスまで
34巻11号(2024年11月発行)
特集 電子カルテとベッドサイドの壁を打ち破る!—患者情報の「言語化」への挑戦
34巻10号(2024年10月発行)
特集 化かしが得意なカメレオンな疾患を捕まえろ!—よくある騙され方のゲシュタルト
34巻9号(2024年9月発行)
特集 今伝えたいクリニカル・パール—つくり方、使い方、活かし方
34巻8号(2024年8月発行)
特集 ストーン・ウォーズ 果てしなき“石”と医師との闘い
34巻7号(2024年7月発行)
特集 どうする!? 健診異常—これってホントに異常なの? どう説明する?
34巻6号(2024年6月発行)
特集 医師のウェルビーイング
34巻5号(2024年5月発行)
特集 —優柔不断にサヨウナラ!—あなたの「臨床判断」を高めるケーススタディ11選
34巻4号(2024年4月発行)
特集 困ったときの漢方—この症状に役立ちます!
34巻3号(2024年3月発行)
特集 —え、ウソ!実は◯◯だった!?—“コモンディジーズ”の診断ピットフォール
34巻2号(2024年2月発行)
特集 日常診療で出合う筋骨格疾患—脳神経内科と整形外科からのアプローチ
34巻1号(2024年1月発行)
特集 —“体験型”臨床クイズで習得する!—フィジカル診断エクセレンス
33巻12号(2023年12月発行)
特集 海の外へ渡る航行者を診る—アウトバウンドにまつわるetc.
33巻11号(2023年11月発行)
特集 —続・総合診療外来に“実装”したい—最新エビデンスMy Best 3
33巻10号(2023年10月発行)
特集 ○×クイズ110問!日常診療アップグレード—Choosing WiselyとHigh Value Careを学ぼう
33巻9号(2023年9月発行)
特集 ジェネラリストのための「発達障害(神経発達症)」入門
33巻8号(2023年8月発行)
特集 都市のプライマリ・ケア—「見えにくい」を「見えやすく」
33巻7号(2023年7月発行)
特集 “消去法”で考え直す「抗菌薬選択」のセオリー—広域に考え、狭域に始める
33巻6号(2023年6月発行)
特集 知っておくべき!モノクロな薬たち(注:モノクローナル抗体の話ですよ〜)
33巻5号(2023年5月発行)
特集 —疾患別“イルネススクリプト”で学ぶ—「腹痛診療」を磨き上げる22症例
33巻4号(2023年4月発行)
特集 救急対応ドリル—外来から在宅までの60問!
33巻3号(2023年3月発行)
特集 —自信がもてるようになる!—エビデンスに基づく「糖尿病診療」大全—新薬からトピックスまで
33巻2号(2023年2月発行)
特集 しびれQ&A—ビビッとシビれるクリニカルパール付き!
33巻1号(2023年1月発行)
特集 COVID-19パンデミック 振り返りと将来への備え
32巻12号(2022年12月発行)
特集 レクチャーの達人—とっておきの生ライブ付き!
32巻11号(2022年11月発行)
特集 不定愁訴にしない“MUS”診療—病態からマネジメントまで
32巻10号(2022年10月発行)
特集 日常診療に潜む「処方カスケード」—その症状、薬のせいではないですか?
32巻9号(2022年9月発行)
特集 総合診療・地域医療スキルアップドリル—こっそり学べる“特講ビデオ”つき!
32巻8号(2022年8月発行)
特集 こんなところも!“ちょいあて”エコー—POCUSお役立ちTips!
32巻7号(2022年7月発行)
特集 —どうせやせない!? やせなきゃいけない??苦手克服!—「肥満」との向き合い方講座
32巻6号(2022年6月発行)
特集 総合診療外来に“実装”したい最新エビデンス—My Best 3
32巻5号(2022年5月発行)
特集 「診断エラー」を科学する!—セッティング別 陥りやすい疾患・状況
32巻4号(2022年4月発行)
特集 えっ、これも!? 知っておきたい! 意外なアレルギー疾患
32巻3号(2022年3月発行)
特集 AI時代の医師のクリニカル・スキル—君は生き延びることができるか?
32巻2号(2022年2月発行)
特集 —withコロナ—かぜ診療の心得アップデート
32巻1号(2022年1月発行)
特集 実地医家が楽しく学ぶ 「熱」「炎症」、そして「免疫」—街場の免疫学・炎症学
31巻12号(2021年12月発行)
特集 “血が出た!”ときのリアル・アプローチ—そんな判断しちゃダメよ!
31巻11号(2021年11月発行)
特集 Q&Aで深める「むくみ診断」—正攻法も!一発診断も!外来も!病棟も!
31巻10号(2021年10月発行)
特集 医師の働き方改革—システムとマインドセットを変えよう!
31巻9号(2021年9月発行)
特集 「検査」のニューノーマル2021—この検査はもう古い? あの新検査はやるべき?
31巻8号(2021年8月発行)
特集 メンタルヘルス時代の総合診療外来—精神科医にぶっちゃけ相談してみました。
31巻7号(2021年7月発行)
特集 新時代の「在宅医療」—先進的プラクティスと最新テクノロジー
31巻6号(2021年6月発行)
特集 この診断で決まり!High Yieldな症候たち—見逃すな!キラリと光るその病歴&所見
31巻5号(2021年5月発行)
特集 臨床医のための 進化するアウトプット—学術論文からオンライン勉強会、SNSまで
31巻4号(2021年4月発行)
特集 消化器診療“虎の巻”—あなたの切実なギモンにズバリ答えます!
31巻3号(2021年3月発行)
特集 ライフステージでみる女性診療at a glance!—よくあるプロブレムを網羅しピンポイントで答えます。
31巻2号(2021年2月発行)
特集 肺炎診療のピットフォール—COVID-19から肺炎ミミックまで
31巻1号(2021年1月発行)
特別増大特集 新型コロナウイルス・パンデミック—今こそ知っておきたいこと、そして考えるべき未来
30巻12号(2020年12月発行)
特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き) Part 2
30巻11号(2020年11月発行)
特集 診断に役立つ! 教育で使える! フィジカル・エポニム!—身体所見に名を残すレジェンドたちの技と思考
30巻10号(2020年10月発行)
特集 —ポリファーマシーを回避する—エビデンスに基づく非薬物療法のススメ
30巻9号(2020年9月発行)
特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【感染症・内分泌・整形外科 編】
30巻8号(2020年8月発行)
特集 マイナーエマージェンシー門外放出—知っておくと役立つ! テクニック集
30巻7号(2020年7月発行)
特集 その倦怠感、単なる「疲れ」じゃないですよ!—筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群とミミック
30巻6号(2020年6月発行)
特集 下降期慢性疾患患者の“具合”をよくする—ジェネラリストだからできること!
30巻5号(2020年5月発行)
特集 誌上Journal Club—私を変えた激アツ論文
30巻4号(2020年4月発行)
特集 大便強ドリル—便秘・下痢・腹痛・消化器疾患に強くなる41問!
30巻3号(2020年3月発行)
特集 これではアカンで!こどもの診療—ハマりがちな11のピットフォール
30巻2号(2020年2月発行)
特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【循環器・消化器・神経疾患編】
30巻1号(2020年1月発行)
特集 総合診療医の“若手ロールモデル”を紹介します!—私たちはどう生きるか
29巻12号(2019年12月発行)
特集 困っている“あなた”に届く 認知症診療
29巻11号(2019年11月発行)
特集 臨床写真図鑑 レアな疾患編—見逃したくない疾患のコモンな所見
29巻10号(2019年10月発行)
特集 教えて!医師のためのビジネス・スキル
29巻9号(2019年9月発行)
特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き)
29巻8号(2019年8月発行)
特集 —ノーモア見逃し—日常の検査と画像に潜むピットフォール
29巻7号(2019年7月発行)
特集 リウマチ・膠原病ミミック症例帖—“膠原病っぽくみえてしまう疾患たち”にだまされない!
29巻6号(2019年6月発行)
特集 皮膚科診療エクササイズ—1枚の写真から
29巻5号(2019年5月発行)
特集 一般外来で診断できたら「えっへん!」な疾患38
29巻4号(2019年4月発行)
特集 “ナゾ”の痛み診療ストラテジー|OPQRSTで読み解く
29巻3号(2019年3月発行)
特集 —あなたのギモンに答えます!—循環器診療のハードルを下げるQ&A31
29巻2号(2019年2月発行)
特集 意外な中毒、思わぬ依存、知っておきたい副作用—一般外来で!OTCも処方薬も!
29巻1号(2019年1月発行)
特集 教えて検索!—膨大な医学情報を吟味・整理するスキル
28巻12号(2018年12月発行)
特集 こんなときこそ漢方を!
28巻11号(2018年11月発行)
特集 日本一マジメな「おしっこドリル」—今これだけは押さえておきたい腎・泌尿器のモンダイ
28巻10号(2018年10月発行)
特集 クリニカル・パールPremium!—憧れのカリスマ医師はかく語りき
28巻9号(2018年9月発行)
特集 オンコ・ジェネラリスト—「がん」に強い総合診療医をめざして
28巻8号(2018年8月発行)
特集 80歳からの診療スタンダードUp to Date—Silver Standard
28巻7号(2018年7月発行)
特集 この薬だけは押さえておきたい! 総合診療医のためのSpecialist Drug 40
28巻6号(2018年6月発行)
特集 聴診・触診×エコーで診断推論!—Point-of-Care超音波(POCUS)の底力
28巻5号(2018年5月発行)
特集 “一発診断”トレーニング問題集—懸賞論文「GM Clinical Pictures」大賞発表!
28巻4号(2018年4月発行)
特集 感染症外来診療「賢医の選択」—検査・経口薬・ワクチンをどう使えばいいんですか?
28巻3号(2018年3月発行)
特集 糖尿病のリアル—現場の「困った!」にとことん答えます。
28巻2号(2018年2月発行)
特集 頭痛患者で頭が痛いんです!
28巻1号(2018年1月発行)
特集 シン・フィジカル改革宣言!—私の“神技”伝授します。
27巻12号(2017年12月発行)
特集 小児診療“苦手”克服!!—劇的Before & After
27巻11号(2017年11月発行)
特集 今そこにある、ファミリー・バイオレンス|Violence and Health
27巻10号(2017年10月発行)
特集 めまいがするんです!─特別付録Web動画付
27巻9号(2017年9月発行)
特集 うつより多い「不安」の診かた—患者も医師も安らぎたい
27巻8号(2017年8月発行)
特集 見逃しやすい内分泌疾患─このキーワード、この所見で診断する!
27巻7号(2017年7月発行)
特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 3 カリスマ編
27巻6号(2017年6月発行)
特集 「地域を診る医者」最強の養成法!
27巻5号(2017年5月発行)
特集 コミュニケーションを処方する—ユマニチュードもオープンダイアローグも入ってます!
27巻4号(2017年4月発行)
特集 病歴と診察で診断できない発熱!—その謎の賢い解き方を伝授します。
27巻3号(2017年3月発行)
特集 これがホントに必要な薬40—総合診療医の外来自家薬籠
27巻2号(2017年2月発行)
特集 The総合診療ベーシックス—白熱!「総合診療フェスin OKINAWA」ライブ・レクチャー! 一挙公開 フィジカル動画付!
27巻1号(2017年1月発行)
特集 総合診療の“夜明け”—キーマンが語り尽くした「来し方、行く末」
26巻12号(2016年12月発行)
特集 これでパッチリ! 眼の健康問題
26巻11号(2016年11月発行)
特集 続・しびれるんです!
26巻10号(2016年10月発行)
特集 内科診療を劇的に変える“まとめ”の達人
26巻9号(2016年9月発行)
特集 症状・症候別 エコーを使った診断推論─Point-of-Care超音波
26巻8号(2016年8月発行)
特集 The 初診外来
26巻7号(2016年7月発行)
特集 感染症ケアバンドル・チェックリスト
26巻6号(2016年6月発行)
特集 “賢い処方”と“ナゾ処方”
26巻5号(2016年5月発行)
特集 しびれるんです!─知っておくべきシビレル疾患
26巻4号(2016年4月発行)
特集 ケースとクイズで総ざらい! 街場の2型糖尿病治療
26巻3号(2016年3月発行)
特集 こんな時は漢方でしょう!
26巻2号(2016年2月発行)
特集 フィジカル改革宣言! ──診断からフォローアップまで
26巻1号(2016年1月発行)
特集 妊婦・褥婦が一般外来に来たら─エマージェンシー&コモンプロブレム
25巻12号(2015年12月発行)
特集 外来で「複数の疾患」をもつ患者を診る─マルチモビディティの時代のプライマリ・ケア
25巻11号(2015年11月発行)
特集 レアだけど重要な「痛み」の原因─システム1診断学
25巻10号(2015年10月発行)
特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 2
25巻9号(2015年9月発行)
特集 診断ピットフォール10選─こんな疾患,見逃していませんか?
25巻8号(2015年8月発行)
特集 健診データで困ったら─こんな検査結果を持ってこられたら
25巻7号(2015年7月発行)
特集 ここを知りたい!頭部外傷初期対応・慢性期ケア
25巻6号(2015年6月発行)
特集 高齢者救急の落とし穴─紹介する時,される時
25巻5号(2015年5月発行)
特集 咳を聴きとり,咳を止める
25巻4号(2015年4月発行)
特集 関節が痛いんです!─コモンからレアものまでの診断と治療
25巻3号(2015年3月発行)
特集 神経難病ケアのコペルニクス的転回
25巻2号(2015年2月発行)
特集 総合医のためのスポーツ医学ベーシックス
25巻1号(2015年1月発行)
特集 動悸・息切れ─ヤバい病気の見つけ方 そして見つからなかった時の対処法
