総合診療医には、幅広い領域の最新知識を継続的にアップデートすることが求められます。
しかし独力では、なかなか実践困難なことも多くあります。
本特集は、予想以上の好評を得た本誌2022年6月号の続編です。
今回は、プライマリ・ケアにおいて重要な臨床テーマを新たに21項目取り上げ、現場へのエビデンスの実装支援を目指します。
およそ過去5年間に発表された論文を中心に、主要な疾患や健康問題に関する“知っておくべきエビデンス”を各領域の専門家にご紹介いただきました。
各執筆者が「プライマリ・ケア医にぜひ知っておいてほしい」と考える、診断・治療・予後や疫学などに関する近年の「3つのエビデンス」を、主には原著論文やメタ解析から取り上げ、その背景となる論文も交えてポイントを解説し、プライマリ・ケア現場への実装にも言及していただきました。
雑誌目次
総合診療33巻11号
2023年11月発行
雑誌目次
特集 —続・総合診療外来に“実装”したい—最新エビデンスMy Best 3
扉 フリーアクセス
著者: 藤沼康樹
ページ範囲:P.1276 - P.1277
今月の「めざせ! 総合診療専門医!」問題
ページ範囲:P.1347 - P.1349
本問題集は、今月の特集のご執筆者に、執筆テーマに関連して「総合診療専門医なら知っておいてほしい!」「自分ならこんな試験問題をつくりたい!」という内容を自由に作成していただいたものです。力試し問題に、チャレンジしてみてください。
【総論】
EBMの最近の進歩
著者: 安原千晴 , 岡田悟
ページ範囲:P.1278 - P.1282
プロローグ
「私にはEBMなんてできない…」
「こんにちは、総合診療科の高原祐希です。よろしくお願いします」
私は総合診療医を目指す卒後3年目の専攻医だ。市中病院の総合診療科で働いている。今日は、午後の予約外来の担当だ。
【各論】
❶認知症
著者: 佐治直樹
ページ範囲:P.1283 - P.1285
中高年の難聴者は、「補聴器」を装用しなかった場合、認知症発症リスクが1.42倍と上昇する。一方、装用した場合はリスクは上昇せず(1.04倍)、難聴のない中高年と同程度に軽減された。
❷Parkinson病
著者: 関守信
ページ範囲:P.1286 - P.1288
2015年に発表された「Movement Disorder Society Parkinson's Disease臨床診断基準」の診断精度は、病理診断をゴールドスタンダードとして、運動障害専門医97.2%、非専門医90.3%であった。発症早期のPD患者においても高い正診率が示された。
❸慢性腰痛症
著者: 長谷川優 , 南郷栄秀
ページ範囲:P.1289 - P.1291
慢性腰痛症に対して、アセトアミノフェンは疼痛の軽減に寄与しないが、「NSAIDs」「ベンゾジアゼピン」「オピオイド」は有害事象に注意しながら使用すると、わずかに効果がある可能性がある。
❹difficult patient encounters(対応困難な状況)
著者: 鋪野紀好
ページ範囲:P.1292 - P.1294
日本の総合診療外来におけるdifficult patient encountersの頻度は「市中病院」で15.0%と、諸外国のプライマリ・ケア外来と同等の結果であった。一方、紹介患者が中心の「大学病院」においては39.8%と、市中病院より有意に高い結果であった(p<0.001)。
❺発達障害
著者: 今村弥生
ページ範囲:P.1295 - P.1297
児童思春期(13〜18歳)の注意欠如多動症(ADHD)患者に対し、中枢神経刺激薬などの「薬物療法」はすべて症状改善に効果があるとRCT(ランダム化比較試験)によって示され、使用を検討すべきである。一方、大人のADHDの多くは他に合併する精神疾患があり、RCTに参加できる被験者は実臨床の患者と同様とは言えない点を考慮し、「心理・社会的アプローチ」も考慮したい。
❻サルコペニア
著者: 若林秀隆
ページ範囲:P.1298 - P.1300
サルコペニアの高齢者のQOLを改善させる最も効果的な治療は、「筋力トレーニング±栄養」もしくは「筋力トレーニング+バランス運動+有酸素運動」の併用であり、運動と栄養の複合介入が第一選択である。
❼不眠症
著者: 高野裕太 , 井上雄一
ページ範囲:P.1301 - P.1303
不眠症の発症・持続・寛解の割合を5年間追跡した疫学研究の結果、5年後にも59.1%に不眠症が「持続」していた。さらに、自然経過で一時的に症状が軽減したとしても、翌年には「悪化」に転じる割合が高かった。
❽甲状腺機能低下症
著者: 高瀬了輔 , 大塚文男
ページ範囲:P.1304 - P.1306
甲状腺刺激ホルモン(TSH)濃度は基準値内でも、正常上限や下限では、高齢者の「サルコペニア」と相関がある。甲状腺機能や筋肉量・歩行速度・活動性などを定期的に評価し、運動・栄養指導に加え、適切な治療介入の検討が重要である。
❾非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)
著者: 上村顕也
ページ範囲:P.1307 - P.1309
NAFLD/NASHの診療では、その予後規定因子である「肝線維化」の評価が重要である。ガイドラインでゴールドスタンダードとされる「肝生検」は、全患者には施行困難な侵襲的検査で、経時的評価が難しい。そこで、プライマリ・ケアの現場で病態を把握できる「FIB-4 index」や「超音波検査」による非侵襲的評価法が検証されている。
❿下肢閉塞性動脈硬化症
著者: 山本洋平 , 工藤敏文
ページ範囲:P.1310 - P.1312
下肢閉塞性動脈硬化症による間欠性跛行の改善に明確なエビデンスを有する薬物は「シロスタゾール」である。
⓫肺塞栓症
著者: 近藤真未
ページ範囲:P.1313 - P.1315
呼吸器症状が悪化して入院した「COPD(慢性閉塞性肺疾患)」患者のなかには肺塞栓症(PE)を合併している場合がある。治療経過がCOPDの急性増悪と合わない時は、PEも鑑別にあげて注意深く観察する必要がある。
⓬前立腺肥大症
著者: 小路直
ページ範囲:P.1316 - P.1318
尿閉をきたした患者には、まず「導尿」あるいは「尿道カテーテル留置」を行う。前立腺肥大症による尿閉の場合、「α1遮断薬」がカテーテル離脱に有用である。
⓭HIV感染症
著者: 田島靖久
ページ範囲:P.1319 - P.1321
HIV陽性のパートナーが抗レトロウイルス療法(ART)を受け、ウイルス量が「200コピー/mL以下」の場合、コンドームを使用しない性交渉によるHIV感染のリスクは事実上ゼロとなる。
⓮過敏性腸症候群(IBS)
著者: 田中由佳里
ページ範囲:P.1322 - P.1324
感染性腸炎後の腸内細菌叢は、多様性が低下し、組成も変化していた。この変化には「食事」が関連しており、食物繊維摂取による「プレバイオティクス」の効果が、感染性腸炎後IBSを抑制する可能性が示唆された。
⓯高齢者の便秘
著者: 田中由佳里
ページ範囲:P.1325 - P.1327
高齢者の大腸神経筋機能について、特に上行結腸で「コリン作動性」の筋収縮が低下していることがわかった。反応性が低下した大腸に抗コリン薬が付加されると、便秘症を悪化させる可能性が考えられ、「処方薬に抗コリン作用をもつ薬がどの程度含まれているか」に注意する必要性が示唆される。
⓰小児の起立性調節障害
著者: 柳夲嘉時
ページ範囲:P.1328 - P.1330
起立性調節障害(OD)の重要な非薬物療法の1つは、水分・塩分の摂取である。1日に「水分2L以上」「塩分10〜12g」を摂取することがOD治療の第一歩であり、水分摂取が不十分だと他の治療効果も不十分になる。
⓱女性の更年期障害
著者: 吉持盾信 , 森田修平 , 小林駿介 , 鳴本敬一郎
ページ範囲:P.1331 - P.1333
「エクオール」は、腸内細菌によりイソフラボンから産生される植物性エストロゲンであり、食品として販売されているため誰でも摂取可能である。閉経期におけるエクオールの摂取は「ホットフラッシュ」を統計学的に有意に減少させるが、その臨床的意義は限定的である。
⓲LGBTQと医療
著者: 吉田絵理子
ページ範囲:P.1334 - P.1336
トランスジェンダーのヘルスケアに関する国際的ガイドラインが、10年ぶりに改訂された。疑問が生じたら、まずこのガイドラインに目を通すとよい。
⓳複雑な健康問題のケア
著者: 青木拓也
ページ範囲:P.1337 - P.1339
新たな複雑性指標は、より多くのリソースを必要とする“複雑性の高い患者”を診療情報に基づきあらかじめ特定することで、時間的・人的資源の効率的な配分に寄与する可能性がある。
⓴がんサバイバーシップ
著者: 高橋都
ページ範囲:P.1340 - P.1342
「がんサバイバーシップケア」は、がん患者の身体・心理・社会的ケアに加えて、がん以外の疾患管理や健康増進も含む。サバイバーシップケアによって、患者の健康関連QOLの改善、不要なヘルスケア利用の減少、ケアのコスト削減、死亡率の低下が期待される。
(21)外来における医学生教育
著者: 高村昭輝
ページ範囲:P.1343 - P.1346
総合診療外来における長期間の臨床実習は、大病院の臓器専門外来や病棟で伝統的な短期ブロックローテーションをした学生に比べて臨床経験機会が多く、「臨床能力修得」において利点があるだけでなく、「学業成績」も同等かそれ以上である。
Editorial
プライマリ・ケアの“3つのルール”と“創発特性” フリーアクセス
著者: 藤沼康樹
ページ範囲:P.1265 - P.1265
複雑性科学の最も魅力的な原理の1つは、複雑なシステムの動作が単純なルールで説明できる場合があるということだ。たとえば、鳥の驚異的に複雑な群れ行動は、以下の3つの単純なルールによって生み出されると言われている。
●整列:近くの鳥たちときちんと並ぶ。
●密着:周囲の鳥たちの中に出現する中心集団に向かって進む。
●別々:衝突しないように隣の鳥と等距離になるようにする。
What's your diagnosis?[251]
たるんどるよ! 簡単じゃないか!
著者: 吉田常恭 , 酒見英太
ページ範囲:P.1268 - P.1273
病歴
患者:78歳、女性
主訴:右下腹部痛
現病歴:中等度の認知症をもつ78歳女性。夫によると、来院7日前から右肩痛を訴えていたが、鎮痛薬は使用せず消退した。来院1日前から腹部の違和感(本人は「調子が悪い」と表現)を訴えていた。来院当日、朝食の準備中より臍周囲の腹痛を訴え始めた。徐々に右下腹部の間欠痛となり、しゃがみこんで動けなくなったため救急搬送された。救急車中では茶色吐物の嘔吐が1回あった。悪寒・発熱、便通変化、血便・黒色便、腰背部痛、性器出血・帯下はない。
生もの・鶏肉・焼肉食はなかったが、来院2日前にしめ鯖を含む刺身を食べたという。周囲に腹痛や下痢を訴える者はいない。
既往歴:髄膜腫術後症候性痙攣、甲状腺機能低下症、骨粗鬆症
薬剤歴:カルバマゼピン200mg×2/日、レボチロキシン25μg/日、エルデカルシトール0.75μg/日、ミノドロン酸50mg/月
生活歴:京都出身で京都在住。旅行は長年しておらず、飲酒・喫煙はしない
【エッセイ】アスクレピオスの杖—想い出の診療録・43
医療によるトラウマ
著者: 池田裕美枝
ページ範囲:P.1274 - P.1275
本連載は、毎月替わる著者が、これまでの診療で心に残る患者さんとの出会いや、人生を変えた出来事を、エッセイにまとめてお届けします。
対談|医のアートを求めて・5
医療×ナラティブ—ノンフィクション作家が見た命の現場 ハッピー・エンド・オブ・ライフとは何か?
著者: 佐々涼子 , 平島修
ページ範囲:P.1351 - P.1357
この40年間で年間死亡者数は2倍となり、現在、年間約140万人を超えているが、果たして「死」は40年前と比べ、身近な出来事になったのだろうか?
私たちの社会は今、都会への一極集中、核家族化が進む中で、高齢者世帯は増加している。国は在宅医療を推進する一方で、介護者不在により人生の最期を病院で過ごす人が増え、「死」は私たちの日常からなくなってしまった。
そのような中、佐々涼子氏は在宅医療を中心に行う京都の渡辺西賀茂診療所への取材を通して、「死とは何か?」を探していた。そしてたどり着いた答えは…?
本対談は、書籍『エンド・オブ・ライフ』(集英社2020)の内容をもとに進めていった。
読者の皆さんにも、それぞれのエンド・オブ・ライフを考えてもらえたら幸いである。(平島修)
オール沖縄!カンファレンス|レジデントの対応と指導医の考えVer.2.0・82
帯状疱疹で入院した高齢患者の意識レベルが良くなりません…
著者: 山田衛 , 與那覇忠博 , 新里敬 , 徳田安春 , 仲里信彦 , 鈴木智晴 , 佐藤直行
ページ範囲:P.1359 - P.1363
CASE
患者:80代、女性。
主訴:嘔気、体動困難、微熱。
現病歴:受診3日前に背部・前胸部の水疱を伴う皮疹が出現、近医で帯状疱疹と診断されアメナメビルの処方を受けた。その後も皮疹は持続し、嘔気とそれによる経口摂取困難、歩行困難、微熱を伴ってきたため、当院へ救急搬送となった。
併存症:高血圧症、脂質異常症、骨粗鬆症、気管支喘息、皮膚瘙痒症、白内障、原発閉塞隅角症。
既往歴:冠動脈バイパス術後。腰椎圧迫骨折(1年前に転倒し、近医整形外科で診断)。
内服薬:クロピドグレル、バルサルタン、アトルバスタチン、アルファカルシドール、オロパタジン、フルチカゾン・サルメテロール合剤(吸入)、ケトチフェン点眼液。3日前よりアメナメビル、ミロガバリン、ボノプラザン、ビダラビン軟膏、フェルビナク軟膏。
嗜好歴:喫煙・飲酒ともになし。
ADL:自立、移動時歩行器利用。自宅で夫と娘と3人暮らし。
アレルギー歴:なし。
ワクチン接種歴:SARS-CoV-2ワクチン3回済、帯状疱疹ワクチンなし(水痘罹患歴あり)。
Review of systems:腰椎圧迫骨折後より腰痛が持続。その他の症状なし。
Dr.上田剛士のエビデンス実践レクチャー!医学と日常の狭間で|患者さんからの素朴な質問にどう答える?・44
乗り物酔いを克服する
著者: 上田剛士
ページ範囲:P.1372 - P.1377
患者さんからのふとした質問に答えられないことはないでしょうか? 素朴な疑問ほど回答が難しいものはありませんが、新たな気づきをもたらす良問も多いのではないでしょうか? 本連載では素朴な疑問に、文献的根拠を提示しながらお答えします!
臨床教育お悩み相談室|どうする!?サロン・10
本当にベンキョーになる「勉強会」の話
著者: 佐田竜一 , 木村武司 , 長野広之
ページ範囲:P.1378 - P.1382
今月のお悩み
卒後11年目の指導医です。研修医から「勉強会を開催してほしい」と依頼されました。勉強会と一口に言っても、「レクチャー」から「ケースカンファレンス」まで、さまざまあると思います。レクチャーは準備しやすいけど、昨今はオンラインのコンテンツも充実しているし…、一方向性になるとせっかく「対面」で集まる旨みが活かせない気もします。研修医の隠れたニーズも拾い上げられれば最適とは思いますが、どのような形式の勉強会を行うとよいのでしょうか?
[ペンネーム:Jimmy]
臨床医のためのライフハック│限りある時間を有効に使う仕事術・8
—ウェブ発信❷—「リクルート」や「人脈形成」に活かすウェブ発信術
著者: 中島啓
ページ範囲:P.1383 - P.1386
時間がない! 臨床医の仕事は診療だけにあらず、事務、教育、自己学習、研究、学会発表、情報発信、所属組織の運営などなど、尽きることはありません。もちろんプライベートの生活もあり、「時間不足」は臨床医の永遠の課題です。では、一度きりの“医師人生”の限られた時間を、どう有効に使うのか? 筆者が培ってきた「ライフハック(仕事術)」のすべてを、余すところなく開陳します。
ジェネラリストに必要な ご遺体の診断学・8
「死後硬直」と「四肢」を診る
著者: 森田沙斗武
ページ範囲:P.1387 - P.1391
Case
患者:40歳、男性。妻と子ども2人と4人暮らし。
既往歴:抑うつ気分。コロナ禍でリストラされ就職活動を行っていたが、その頃から不眠・倦怠感を自覚し当院を受診。諸検査にて異常を認めず、抑うつ状態からの身体症状を疑い、精神科または心療内科を受診するように指導していた。
現病歴:某日20時頃に家族と夕食をとったあと、22時頃に自室に入った。翌朝7時に妻が起こしに行くと、部屋のクローゼットにベルトをかけて縊頸しているのを発見。7時10分に救急通報、18分に救急隊到着。救急隊はわずかに死後硬直があると感じたが、取り乱した家族におされ、当院に搬送した。
救急隊から申し訳なさそうに「死後硬直があると思いましたが…」と申し送りを受けたが、救急救命処置を継続した。当然反応せず、20分後に家族の受け入れとともに死亡確認となった。家族に「搬送時にすでに死後硬直を認め、救命は難しかった」と説明すると、「では何時頃に首を吊ったのですか?」と聞かれた。とりあえず「数時間前と思います」と答えたが、よくわからなかった。
異状死のため警察に届出を行い、捜査協力をしたが、「搬送時に硬直があったそうですが、どの程度でしたか?」と聞かれた。明らかなご遺体への医療行為は保険診療にならないことを思い出し、とっさに「ハッキリしませんでしたので、救急救命処置を行いました」と答えた。死後硬直についていろいろ聞かれたが、実際には死後硬直を評価しておらず、ポイントもよくわからなかった。
投稿 GM Clinical Pictures
進行大腸癌で下痢が生じた理由は?
著者: 梶原祐策
ページ範囲:P.1365 - P.1366
CASE
患者:72歳、男性。
現病歴:3カ月前から続く下痢と、本日になって便に血が混じるようになったことから当科を受診した。下部消化管内視鏡検査でS状結腸に全周性の3型腫瘍(図1Ⓐ)が明らかとなり、潰瘍性腫瘍による狭窄(図1Ⓑ)で内視鏡を通過させることができなかった。既往歴:なし。
社会生活歴・家族歴:特記すべきことなし。
身体所見:身長165.2cm、体重53.9kg(3カ月前は60.5kg)、体温37.0℃、血圧159/70mmHg、脈拍数98回/分、腹部は平坦・軟で、圧痛なし。
画像所見:水溶性消化管造影剤(ガストログラフィン®)を用いたX線透視検査(図2Ⓐ・Ⓑ)とガストログラフィン®注入後の腹部〜骨盤部単純CT検査(図2Ⓒ)。
総合診療病棟
減量チームによる集学的介入が喘息コントロールの改善につながった肥満喘息の1例
著者: 井上拓弥 , 住谷充弘 , 北浜誠一 , 竹嶋好 , 中島進介
ページ範囲:P.1392 - P.1395
高用量の吸入ステロイドや気管支拡張薬を使用するも、7〜10%の患者において治療効果が乏しい喘息病態(難治気管支喘息)が存在し、難治病態因子の1つにBMI 25kg/m2以上の肥満病態が報告されている1)。肥満喘息患者では体重の減少が喘息コントロールに効果があり、10%の体重減量が喘息のコントロールを改善した報告を認める2)。しかし、高度肥満者の体重減少は困難な例も多く、一概に体重減少と言っても一筋縄でいかないことも多い。
今回、当院減量チームの集学的介入により減量・代謝改善手術につながり、結果的に体重減少を契機に喘息コントロールの改善につながった1例を経験したので本稿にて報告する。
#総合診療
#今月の特集関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.1294 - P.1294
#今月の特集関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.1300 - P.1300
#今月の特集関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.1303 - P.1303
#今月の特集関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.1349 - P.1349
#今月の特集関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.1357 - P.1357
#今月の特集関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.1367 - P.1367
#今月の特集関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.1391 - P.1391
#今月の連載関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.1273 - P.1273
#医学書院の新刊 フリーアクセス
ページ範囲:P.1368 - P.1368
#編集部に届いた執筆者関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.1369 - P.1369
#参加者募集 フリーアクセス
ページ範囲:P.1369 - P.1369
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.1266 - P.1267
読者アンケート
ページ範囲:P.1371 - P.1371
『総合診療』バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.1396 - P.1397
お得な年間購読のご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.1397 - P.1398
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.1399 - P.1400
基本情報
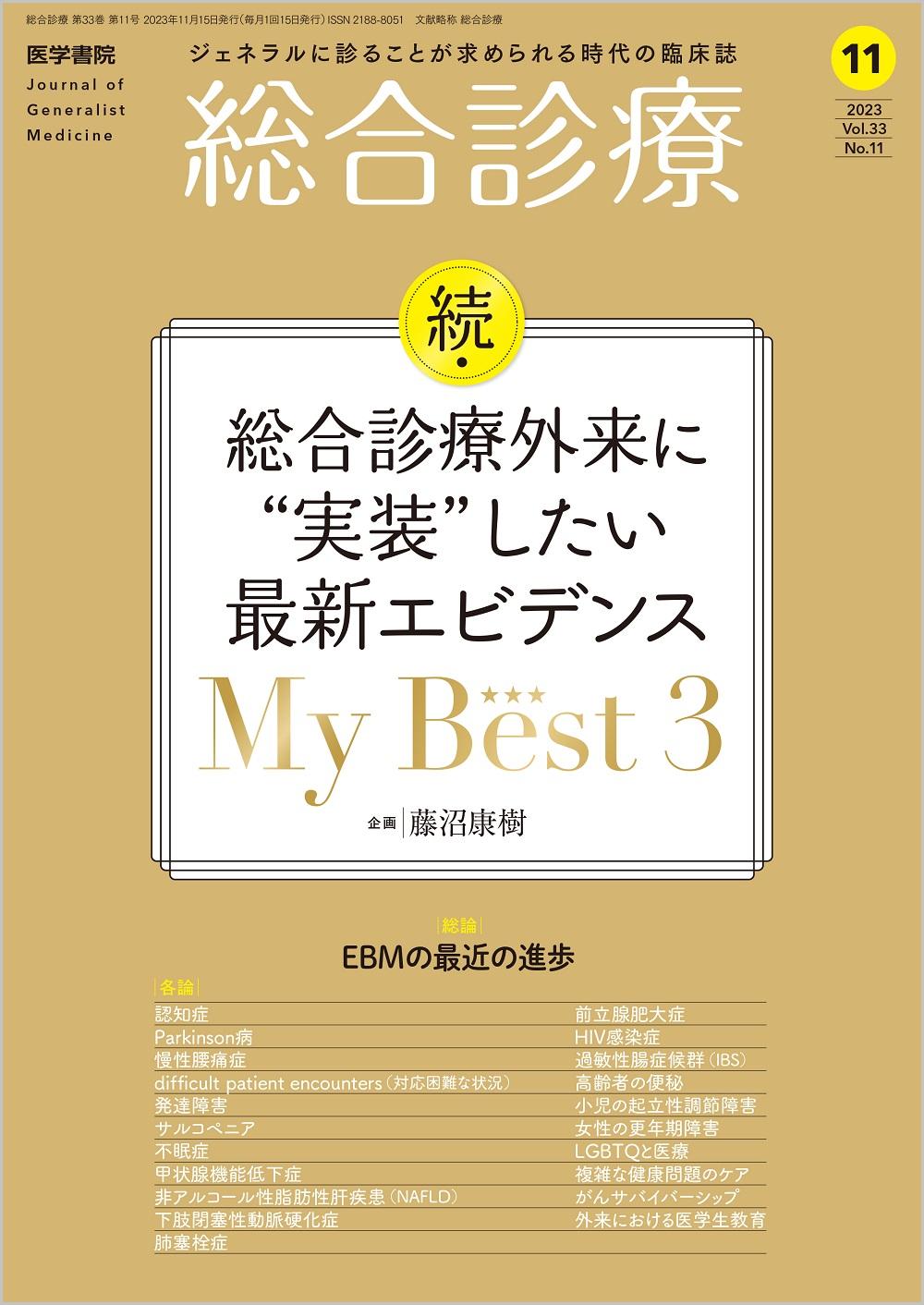
バックナンバー
34巻12号(2024年12月発行)
特集 妊婦・褥婦が外来に来たらUpdate—症状対応からワクチン・プラネタリーヘルスまで
34巻11号(2024年11月発行)
特集 電子カルテとベッドサイドの壁を打ち破る!—患者情報の「言語化」への挑戦
34巻10号(2024年10月発行)
特集 化かしが得意なカメレオンな疾患を捕まえろ!—よくある騙され方のゲシュタルト
34巻9号(2024年9月発行)
特集 今伝えたいクリニカル・パール—つくり方、使い方、活かし方
34巻8号(2024年8月発行)
特集 ストーン・ウォーズ 果てしなき“石”と医師との闘い
34巻7号(2024年7月発行)
特集 どうする!? 健診異常—これってホントに異常なの? どう説明する?
34巻6号(2024年6月発行)
特集 医師のウェルビーイング
34巻5号(2024年5月発行)
特集 —優柔不断にサヨウナラ!—あなたの「臨床判断」を高めるケーススタディ11選
34巻4号(2024年4月発行)
特集 困ったときの漢方—この症状に役立ちます!
34巻3号(2024年3月発行)
特集 —え、ウソ!実は◯◯だった!?—“コモンディジーズ”の診断ピットフォール
34巻2号(2024年2月発行)
特集 日常診療で出合う筋骨格疾患—脳神経内科と整形外科からのアプローチ
34巻1号(2024年1月発行)
特集 —“体験型”臨床クイズで習得する!—フィジカル診断エクセレンス
33巻12号(2023年12月発行)
特集 海の外へ渡る航行者を診る—アウトバウンドにまつわるetc.
33巻11号(2023年11月発行)
特集 —続・総合診療外来に“実装”したい—最新エビデンスMy Best 3
33巻10号(2023年10月発行)
特集 ○×クイズ110問!日常診療アップグレード—Choosing WiselyとHigh Value Careを学ぼう
33巻9号(2023年9月発行)
特集 ジェネラリストのための「発達障害(神経発達症)」入門
33巻8号(2023年8月発行)
特集 都市のプライマリ・ケア—「見えにくい」を「見えやすく」
33巻7号(2023年7月発行)
特集 “消去法”で考え直す「抗菌薬選択」のセオリー—広域に考え、狭域に始める
33巻6号(2023年6月発行)
特集 知っておくべき!モノクロな薬たち(注:モノクローナル抗体の話ですよ〜)
33巻5号(2023年5月発行)
特集 —疾患別“イルネススクリプト”で学ぶ—「腹痛診療」を磨き上げる22症例
33巻4号(2023年4月発行)
特集 救急対応ドリル—外来から在宅までの60問!
33巻3号(2023年3月発行)
特集 —自信がもてるようになる!—エビデンスに基づく「糖尿病診療」大全—新薬からトピックスまで
33巻2号(2023年2月発行)
特集 しびれQ&A—ビビッとシビれるクリニカルパール付き!
33巻1号(2023年1月発行)
特集 COVID-19パンデミック 振り返りと将来への備え
32巻12号(2022年12月発行)
特集 レクチャーの達人—とっておきの生ライブ付き!
32巻11号(2022年11月発行)
特集 不定愁訴にしない“MUS”診療—病態からマネジメントまで
32巻10号(2022年10月発行)
特集 日常診療に潜む「処方カスケード」—その症状、薬のせいではないですか?
32巻9号(2022年9月発行)
特集 総合診療・地域医療スキルアップドリル—こっそり学べる“特講ビデオ”つき!
32巻8号(2022年8月発行)
特集 こんなところも!“ちょいあて”エコー—POCUSお役立ちTips!
32巻7号(2022年7月発行)
特集 —どうせやせない!? やせなきゃいけない??苦手克服!—「肥満」との向き合い方講座
32巻6号(2022年6月発行)
特集 総合診療外来に“実装”したい最新エビデンス—My Best 3
32巻5号(2022年5月発行)
特集 「診断エラー」を科学する!—セッティング別 陥りやすい疾患・状況
32巻4号(2022年4月発行)
特集 えっ、これも!? 知っておきたい! 意外なアレルギー疾患
32巻3号(2022年3月発行)
特集 AI時代の医師のクリニカル・スキル—君は生き延びることができるか?
32巻2号(2022年2月発行)
特集 —withコロナ—かぜ診療の心得アップデート
32巻1号(2022年1月発行)
特集 実地医家が楽しく学ぶ 「熱」「炎症」、そして「免疫」—街場の免疫学・炎症学
31巻12号(2021年12月発行)
特集 “血が出た!”ときのリアル・アプローチ—そんな判断しちゃダメよ!
31巻11号(2021年11月発行)
特集 Q&Aで深める「むくみ診断」—正攻法も!一発診断も!外来も!病棟も!
31巻10号(2021年10月発行)
特集 医師の働き方改革—システムとマインドセットを変えよう!
31巻9号(2021年9月発行)
特集 「検査」のニューノーマル2021—この検査はもう古い? あの新検査はやるべき?
31巻8号(2021年8月発行)
特集 メンタルヘルス時代の総合診療外来—精神科医にぶっちゃけ相談してみました。
31巻7号(2021年7月発行)
特集 新時代の「在宅医療」—先進的プラクティスと最新テクノロジー
31巻6号(2021年6月発行)
特集 この診断で決まり!High Yieldな症候たち—見逃すな!キラリと光るその病歴&所見
31巻5号(2021年5月発行)
特集 臨床医のための 進化するアウトプット—学術論文からオンライン勉強会、SNSまで
31巻4号(2021年4月発行)
特集 消化器診療“虎の巻”—あなたの切実なギモンにズバリ答えます!
31巻3号(2021年3月発行)
特集 ライフステージでみる女性診療at a glance!—よくあるプロブレムを網羅しピンポイントで答えます。
31巻2号(2021年2月発行)
特集 肺炎診療のピットフォール—COVID-19から肺炎ミミックまで
31巻1号(2021年1月発行)
特別増大特集 新型コロナウイルス・パンデミック—今こそ知っておきたいこと、そして考えるべき未来
30巻12号(2020年12月発行)
特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き) Part 2
30巻11号(2020年11月発行)
特集 診断に役立つ! 教育で使える! フィジカル・エポニム!—身体所見に名を残すレジェンドたちの技と思考
30巻10号(2020年10月発行)
特集 —ポリファーマシーを回避する—エビデンスに基づく非薬物療法のススメ
30巻9号(2020年9月発行)
特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【感染症・内分泌・整形外科 編】
30巻8号(2020年8月発行)
特集 マイナーエマージェンシー門外放出—知っておくと役立つ! テクニック集
30巻7号(2020年7月発行)
特集 その倦怠感、単なる「疲れ」じゃないですよ!—筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群とミミック
30巻6号(2020年6月発行)
特集 下降期慢性疾患患者の“具合”をよくする—ジェネラリストだからできること!
30巻5号(2020年5月発行)
特集 誌上Journal Club—私を変えた激アツ論文
30巻4号(2020年4月発行)
特集 大便強ドリル—便秘・下痢・腹痛・消化器疾患に強くなる41問!
30巻3号(2020年3月発行)
特集 これではアカンで!こどもの診療—ハマりがちな11のピットフォール
30巻2号(2020年2月発行)
特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【循環器・消化器・神経疾患編】
30巻1号(2020年1月発行)
特集 総合診療医の“若手ロールモデル”を紹介します!—私たちはどう生きるか
29巻12号(2019年12月発行)
特集 困っている“あなた”に届く 認知症診療
29巻11号(2019年11月発行)
特集 臨床写真図鑑 レアな疾患編—見逃したくない疾患のコモンな所見
29巻10号(2019年10月発行)
特集 教えて!医師のためのビジネス・スキル
29巻9号(2019年9月発行)
特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き)
29巻8号(2019年8月発行)
特集 —ノーモア見逃し—日常の検査と画像に潜むピットフォール
29巻7号(2019年7月発行)
特集 リウマチ・膠原病ミミック症例帖—“膠原病っぽくみえてしまう疾患たち”にだまされない!
29巻6号(2019年6月発行)
特集 皮膚科診療エクササイズ—1枚の写真から
29巻5号(2019年5月発行)
特集 一般外来で診断できたら「えっへん!」な疾患38
29巻4号(2019年4月発行)
特集 “ナゾ”の痛み診療ストラテジー|OPQRSTで読み解く
29巻3号(2019年3月発行)
特集 —あなたのギモンに答えます!—循環器診療のハードルを下げるQ&A31
29巻2号(2019年2月発行)
特集 意外な中毒、思わぬ依存、知っておきたい副作用—一般外来で!OTCも処方薬も!
29巻1号(2019年1月発行)
特集 教えて検索!—膨大な医学情報を吟味・整理するスキル
28巻12号(2018年12月発行)
特集 こんなときこそ漢方を!
28巻11号(2018年11月発行)
特集 日本一マジメな「おしっこドリル」—今これだけは押さえておきたい腎・泌尿器のモンダイ
28巻10号(2018年10月発行)
特集 クリニカル・パールPremium!—憧れのカリスマ医師はかく語りき
28巻9号(2018年9月発行)
特集 オンコ・ジェネラリスト—「がん」に強い総合診療医をめざして
28巻8号(2018年8月発行)
特集 80歳からの診療スタンダードUp to Date—Silver Standard
28巻7号(2018年7月発行)
特集 この薬だけは押さえておきたい! 総合診療医のためのSpecialist Drug 40
28巻6号(2018年6月発行)
特集 聴診・触診×エコーで診断推論!—Point-of-Care超音波(POCUS)の底力
28巻5号(2018年5月発行)
特集 “一発診断”トレーニング問題集—懸賞論文「GM Clinical Pictures」大賞発表!
28巻4号(2018年4月発行)
特集 感染症外来診療「賢医の選択」—検査・経口薬・ワクチンをどう使えばいいんですか?
28巻3号(2018年3月発行)
特集 糖尿病のリアル—現場の「困った!」にとことん答えます。
28巻2号(2018年2月発行)
特集 頭痛患者で頭が痛いんです!
28巻1号(2018年1月発行)
特集 シン・フィジカル改革宣言!—私の“神技”伝授します。
27巻12号(2017年12月発行)
特集 小児診療“苦手”克服!!—劇的Before & After
27巻11号(2017年11月発行)
特集 今そこにある、ファミリー・バイオレンス|Violence and Health
27巻10号(2017年10月発行)
特集 めまいがするんです!─特別付録Web動画付
27巻9号(2017年9月発行)
特集 うつより多い「不安」の診かた—患者も医師も安らぎたい
27巻8号(2017年8月発行)
特集 見逃しやすい内分泌疾患─このキーワード、この所見で診断する!
27巻7号(2017年7月発行)
特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 3 カリスマ編
27巻6号(2017年6月発行)
特集 「地域を診る医者」最強の養成法!
27巻5号(2017年5月発行)
特集 コミュニケーションを処方する—ユマニチュードもオープンダイアローグも入ってます!
27巻4号(2017年4月発行)
特集 病歴と診察で診断できない発熱!—その謎の賢い解き方を伝授します。
27巻3号(2017年3月発行)
特集 これがホントに必要な薬40—総合診療医の外来自家薬籠
27巻2号(2017年2月発行)
特集 The総合診療ベーシックス—白熱!「総合診療フェスin OKINAWA」ライブ・レクチャー! 一挙公開 フィジカル動画付!
27巻1号(2017年1月発行)
特集 総合診療の“夜明け”—キーマンが語り尽くした「来し方、行く末」
26巻12号(2016年12月発行)
特集 これでパッチリ! 眼の健康問題
26巻11号(2016年11月発行)
特集 続・しびれるんです!
26巻10号(2016年10月発行)
特集 内科診療を劇的に変える“まとめ”の達人
26巻9号(2016年9月発行)
特集 症状・症候別 エコーを使った診断推論─Point-of-Care超音波
26巻8号(2016年8月発行)
特集 The 初診外来
26巻7号(2016年7月発行)
特集 感染症ケアバンドル・チェックリスト
26巻6号(2016年6月発行)
特集 “賢い処方”と“ナゾ処方”
26巻5号(2016年5月発行)
特集 しびれるんです!─知っておくべきシビレル疾患
26巻4号(2016年4月発行)
特集 ケースとクイズで総ざらい! 街場の2型糖尿病治療
26巻3号(2016年3月発行)
特集 こんな時は漢方でしょう!
26巻2号(2016年2月発行)
特集 フィジカル改革宣言! ──診断からフォローアップまで
26巻1号(2016年1月発行)
特集 妊婦・褥婦が一般外来に来たら─エマージェンシー&コモンプロブレム
25巻12号(2015年12月発行)
特集 外来で「複数の疾患」をもつ患者を診る─マルチモビディティの時代のプライマリ・ケア
25巻11号(2015年11月発行)
特集 レアだけど重要な「痛み」の原因─システム1診断学
25巻10号(2015年10月発行)
特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 2
25巻9号(2015年9月発行)
特集 診断ピットフォール10選─こんな疾患,見逃していませんか?
25巻8号(2015年8月発行)
特集 健診データで困ったら─こんな検査結果を持ってこられたら
25巻7号(2015年7月発行)
特集 ここを知りたい!頭部外傷初期対応・慢性期ケア
25巻6号(2015年6月発行)
特集 高齢者救急の落とし穴─紹介する時,される時
25巻5号(2015年5月発行)
特集 咳を聴きとり,咳を止める
25巻4号(2015年4月発行)
特集 関節が痛いんです!─コモンからレアものまでの診断と治療
25巻3号(2015年3月発行)
特集 神経難病ケアのコペルニクス的転回
25巻2号(2015年2月発行)
特集 総合医のためのスポーツ医学ベーシックス
25巻1号(2015年1月発行)
特集 動悸・息切れ─ヤバい病気の見つけ方 そして見つからなかった時の対処法
