たかが血糖、されど血糖。
血糖コントロールは何のためにするの?
血糖コントロールをしないと何が起きる?
その答えは、患者さんごとに異なるはずです。
これほど多種類の薬があるのに、それでもやっぱり血糖コントロールが難しい患者さんもいらっしゃいます。
専門医でなくても、かなりのところまで糖尿病診療はできるようになりました。
しかしその内容は、新薬にとどまらず、日々新たな治療法や考え方へと刷新されています。
また、古典的とも言えそうな基本的な治療や薬物にも新しい知見が多くあります。
そこで、糖尿病治療の“新スタンダード”から、基本の“おさらい”、知っておきたい“トピックス”まで、全部を本特集に集約しました。
ぜひこの1冊で糖尿病診療に自信をもっていただき、適切なタイミングで専門医にコンサルトしていただけましたら幸いです。
雑誌目次
総合診療33巻3号
2023年03月発行
雑誌目次
特集 —自信がもてるようになる!—エビデンスに基づく「糖尿病診療」大全—新薬からトピックスまで
扉 フリーアクセス
著者: 大西由希子
ページ範囲:P.260 - P.261
今月の「めざせ! 総合診療専門医!」問題
ページ範囲:P.339 - P.340
本問題集は、今月の特集のご執筆者に、執筆テーマに関連して「総合診療専門医なら知っておいてほしい!」「自分ならこんな試験問題をつくりたい!」という内容を自由に作成していただいたものです。力試し問題に、チャレンジしてみてください。
【Ⅰ章】「薬物療法」の新スタンダード
❶2型糖尿病の薬物療法の「考え方」
著者: 能登洋
ページ範囲:P.262 - P.267
糖尿病診療の目的は、血糖コントロールを良好にすることだけではなく、リスク因子のコントロールと合併症の抑制をし、最終的には糖尿病のない人と変わらない寿命とQOLを確保することである1)。現在、糖尿病治療薬は百花繚乱の状態であるため、病態や合併症・併発症、臨床的アウトカムのエビデンスなどをもとに薬物を選択することが重要である。本稿では、「アウトカム」と「実用性」を重視した日本糖尿病・生活習慣病ヒューマンデータ学会『糖尿病標準診療マニュアル2022』2)に沿って解説する。
❷糖尿病に合併した「高血圧症」「脂質異常症」の薬剤選択
著者: 横溝久 , 川浪大治
ページ範囲:P.268 - P.272
糖尿病患者では、「動脈硬化性疾患発症リスク因子」を複数有することが多く、早期から血糖値だけでなく脂質・血圧などの厳格な管理を包括的に行う重要性が、Steno-2研究1)やJ-DOIT32)で示されている。本稿では、糖尿病患者が合併しやすい「高血圧症」および「脂質異常症」に対する薬剤選択について述べる。
❸メトホルミンとイメグリミン
著者: 藤嶋伶 , 宮塚健
ページ範囲:P.274 - P.275
1961年にメトホルミンが本邦で臨床の場に登場してから、60年以上が経過した。最も古くから使用されている経口血糖降下薬であり、その薬効や副作用、作用機序に関する数々の知見が報告されている。一方で、今でも新たな知見が続々と発表される、謎の多い薬でもある。
2021年に発売されたイメグリミンは、ミトコンドリアの機能を改善する特長をもつ、新規の糖尿病治療薬である。メトホルミンに類似した構造をもつものの、その薬効や副作用に関しては“メトホルミンとは似て非なるもの”と考えられる。
❹DPP-4阻害薬とGLP-1受容体作動薬
著者: 酒井麻有 , 加藤丈博 , 矢部大介
ページ範囲:P.276 - P.278
経口摂取した栄養素に応答して消化管から分泌され、インスリン分泌を促進する消化管ホルモンは「インクレチン」と総称され、今日までにGIP(glucose-dependent insulinotropic polypeptide)とGLP-1(glucagon-like peptide-1)が同定されている。GIPとGLP-1は、膵β細胞に発現する受容体に結合することで血糖依存的にインスリン分泌を促進し、血糖降下作用を発揮する。GLP-1は、グルカゴン分泌を抑制し、胃運動を抑制することでも食後の血糖上昇を抑制する。さらに中枢に作用して食欲を抑制し、体重減量効果を発揮する。
GIPとGLP-1は、消化管から分泌されると、直ちに蛋白分解酵素DPP-4(dipeptidyl peptidase-4)により不活化される。今日までに、DPP-4の働きを阻害し、内因性インクレチンの活性を生理学的レベルで高める「DPP-4阻害薬」、DPP-4により分解されにくいGLP-1アナログを薬理学的レベルで補充する「GLP-1受容体作動薬」が開発され、2型糖尿病治療薬として広く使用されている。特にGLP-1受容体作動薬は、体重減量効果に加え、心血管イベントや腎イベントのリスク軽減も示され、動脈硬化性疾患リスク(p.268)の高い「肥満2型糖尿病」に対する使用が増えている。さらに近年、1つのペプチドでありながらGIP受容体とGLP-1受容体を同時に活性化し、顕著な血糖改善効果と体重減量効果を発揮しうる「GIP/GLP-1共受容体作動薬」が製造承認を受け、肥満2型糖尿病に対する新たな治療薬として注目を集めている。
❺SGLT2阻害薬
著者: 田中健一 , 岡田洋右
ページ範囲:P.280 - P.281
Case
心血管イベント再発抑制目的でSGLT2阻害薬へ変更した2型糖尿病の一例
患者:74歳、男性
既往歴:S状結腸がん(53歳時に手術)
現病歴:65歳時に2型糖尿病と診断。細小血管合併症は認めないが、eGFR(推算糸球体濾過量) 50mL/分/1.73m2と腎機能低下を認め、DPP-4阻害薬が開始された。HbA1c 6%台で経過していたが、74歳時に急性心筋梗塞を発症し冠動脈ステントが留置された。心血管イベント再発抑制のためDPP-4阻害薬から経口GLP-1受容体作動薬へ変更されたが、消化器症状のため治療を継続できなかった。認知症はなく、BMI 26kg/m2と肥満もあり、SGLT2阻害薬に変更したところ、血糖値や腎機能の悪化は認めず、有害事象なく経過している。
❻SU薬とグリニド薬
著者: 中西修平
ページ範囲:P.282 - P.284
Case
高齢2型糖尿病患者にSU薬を使用した一例
患者:82歳、男性
現病歴:2型糖尿病で、グリベンクラミド2.5mgを内服中。BMIは22.6kg/m2。長期にわたり内服薬の変更はなく、HbA1c<7%を維持できている。定期受診にて、体調はよく、低血糖症状の自覚はないらしい。
「まあ、今日も同じ薬でいくか…」
❼インスリンとさまざまな配合注射剤—比較的新しい注射剤と総合診療医が活用する注射剤
著者: 岩田葉子 , 弘世貴久
ページ範囲:P.285 - P.287
Case
放置していた糖尿病が悪化し職場健診で指摘された一例
患者:59歳、男性。身長172cm、体重86kg(BMI 29.0kg/m2)。
家族歴:父が糖尿病
現病歴:5年前に糖尿病と診断され内服開始となるも、血糖値が改善したため数カ月で通院中断した。職場健診は毎年受診し、3年前から血糖高値を指摘されたが、多忙で放置していた。前年
の健診でHbA1c 8.6%、本年はHbA1c 10.4%、空腹時血糖値202mg/dLとなり、産業医に指示され来院した。在宅勤務が増え活動量が減るとともに、食事量が増え間食も習慣化し、体重はこの1年で6kg増加した。今回の健診で脂質異常症も指摘されたが、他は異常なし。夜間頻尿・倦怠感などの自覚症状はない。どのような処方で治療開始するか?
【Ⅱ章】基本が大事!ちゃんとできてる?“おさらい”糖尿病診療
❶2型糖尿病の病態
著者: 山田悟
ページ範囲:P.288 - P.292
Case
「清涼飲料水多飲」に伴って2型糖尿病を発症した一例
患者:32歳、男性。独身、独居。
家族歴:父が2型糖尿病。他に特記事項なし。
現病歴:2年前の30歳時健診の血液検査では、血糖値の異常を指摘されていなかった。1年半前に転職し、給与は上がったものの、仕事上の責任が重くなり、また周囲に相談できる人はいなかったという。その頃から、お茶に代えてエネルギードリンクやスポーツ飲料を多飲するようになっていた。3カ月前から口喝・多尿となり、1日1L以上とますますスポーツ飲料を飲んでいる。全身倦怠感が徐々に増してきたため、近医を受診。血糖386mg/dL、HbA1c 12.8%で、糖尿病と診断された。精査・加療を目的に同日、緊急に当院を紹介初診された。
身体所見:身長173cm、体重82kg、BMI 27.4kg/m2。20歳時体重68kg、人生最大体重82kg(現在)。血圧128/82mmHg、心拍数84回/分・整。胸腹部に異常所見なし、アキレス腱反射正常、足背動脈触知良好、胼胝や鶏眼なし。白癬あり。
検査所見:末梢血異常なし、血沈正常。AST 38IU/mL 、ALT 62IU/mL、γ-GTP 70IU/mL、
LDL-C 136mg/dL、TG 380mg/dL、HDL-C 38mg/dL、随時血糖 386mg/dL、HbA1c 12.8%、IRI 12.4μU/mL。尿ケトン体(3+)。
❷糖尿病患者が定期的に行ったほうがよい検査
著者: 及川洋一 , 島田朗
ページ範囲:P.293 - P.295
Case
尿中アルブミン排泄量の定期測定によって早期に糖尿病性腎症第2期と診断し、治療介入により腎症の寛解がみられた一例
患者:47歳、男性
現病歴:39歳の時、健診を契機に2型糖尿病と診断された。著明な肥満があり、高血圧症も認めたため、ビグアナイド薬とカルシウム拮抗薬が開始されたが、近年はHbA1c 8%前後、血圧150/100mmHg程度と、血糖・血圧ともにコントロール不良であった。
半年に1回の頻度で定期的に尿アルブミン排泄量を測定していたところ、46歳の時に2回続けて100mg/gCr台となり(eGFRは60mL/分/1.73m2程度)、糖尿病性腎症第2期と診断した。ただちにSGLT2阻害薬を開始した結果、肥満の是正とともにHbA1cは6%台にまで改善し、塩分制限(1日6g)とARB(アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬)の追加投与によって、血圧は120/80mmHg程度で推移した。1年後には腎症第1期への寛解がみられた。
❸血糖自己測定(SMBG)と持続グルコース測定(CGM)
著者: 安藤精貴 , 西村理明
ページ範囲:P.296 - P.297
Case
糖尿病治療を数年行っているが血糖コントロールの改善が乏しい一例
患者:51歳、男性。BMI 25kg/m2。
家族歴:母親が糖尿病。
現病歴:39歳時に、健康診断で高血糖を指摘され、総合病院を受診し2型糖尿病と診断された。経口血糖降下薬が開始され、徐々に内服薬が追加されたが、3剤内服(メトホルミン1,500mg、テネリグリプチン20mg、ダパグリフロジン10mg)しても血糖コントロールが改善せず、当院へ紹介された。少量の基礎インスリン導入時に、持続グルコース測定(continuous glucose monitoring:CGM)も開始した。その結果、食後高血糖の是正が不十分であることが判明したため、GLP-1受容体作動薬を追加して良好な血糖コントロールを達成した。
❹—2型糖尿病の合併症—眼
著者: 池田恒彦
ページ範囲:P.298 - P.300
Case
患者:55歳、男性
現病歴:10年以上前に近医で2型糖尿病を指摘されていたが、眼科受診は途絶えがちであった。最近、左眼の視力低下と右眼の飛蚊症を自覚し、近医眼科を受診。両眼の増殖糖尿病網膜症(PDR)を指摘され、経過中、右眼に著明な視力低下をきたした。眼底検査にて、右眼は「硝子体出血」(図1ⓐ)、左眼は視神経乳頭から鼻側にかけて「線維血管増殖膜」を認めた(図1ⓑ)。矯正視力は右眼0.1・左眼0.5であった。
右眼に対して硝子体手術(pars plana vitrectomy : PPV)を施行し、矯正視力は1.0に改善した(図2)。左眼は現在、汎網膜光凝固術(panretinal photocoagulation:PRPC)を開始し、時期をみてPPVを予定している。
❺—2型糖尿病の合併症—腎臓
著者: 和田健彦
ページ範囲:P.301 - P.303
「糖尿病性腎臓病(DKD)」とは
糖尿病性腎症または糖尿病腎症(diabetic nephropathy:DN)は、網膜症(p.298)・神経障害(p.304)と並んで、2型糖尿病の「3大細小血管合併症」として重要な疾患である。
DNは、長期の糖尿病罹患を背景に、臨床的には「微量アルブミン尿」の出現に始まり、「顕性蛋白尿」への進展と比較的速い腎機能低下を認め、最終的に末期腎不全へと至るという特徴を有する。1998年以降、新規維持透析導入患者の基礎疾患として最多の位置を占め続け、腎臓領域でも最も頻度が高く重要な疾患である。
❻—2型糖尿病の合併症—神経
著者: 水地智基 , 三澤園子
ページ範囲:P.304 - P.306
糖尿病は多彩な神経障害を起こしうるが、主要な病型は「糖尿病性多発神経障害(diabetic polyneuropathy:DPN)」である。細小血管合併症の1つであるDPNは、糖尿病患者の30〜40%にみられ1)、左右対称性かつ長さ依存性に生じ、「遠位対称性感覚運動性多発神経障害」と「自律神経障害」を呈する。発症早期には両足趾・足底の「しびれ感」「疼痛」「異常感覚」が出現し、緩徐に症状が上行する。進行すると「感覚鈍麻」、足内在筋の「萎縮」や「筋力低下」が左右対称性に出現する。自律神経障害としては、「起立性低血圧」「便秘・下痢」「神経因性膀胱」「発汗異常」など、多彩な症候を呈する。
❼—2型糖尿病の合併症—冠動脈疾患と脳血管障害
著者: 堀内優 , 田邉健吾
ページ範囲:P.307 - P.309
糖尿病は、冠動脈疾患や脳血管障害のリスク因子である。血糖コントロールの悪化にしたがって心筋梗塞や脳梗塞などの「動脈硬化性疾患」(p.268)のリスクが上昇することが知られており、これらは糖尿病患者の死因となりうる重大なイベントである。早期発見・早期治療のため、患者リスクに応じた適切なスクリーニングが求められる。
❽糖尿病の足病変とフットケア
著者: 富田益臣
ページ範囲:P.310 - P.311
Case
患者:76歳、男性
現病歴:40歳時に2型糖尿病を指摘され、インスリン治療中である。右第5趾外側に胼胝下潰瘍が形成され(図1)、近医皮膚科にて治療し軽快したが、その後も胼胝による痛みがあり、フットケア外来を受診した。
❾—2型糖尿病の治療—食事療法
著者: 上野慎士 , 清野祐介 , 鈴木敦詞
ページ範囲:P.312 - P.313
糖尿病における食事療法は、目標体重と日常生活の労作状況から総エネルギー摂取量を適正化し、良好な血糖コントロールを目指すことを目標とする。特に「肥満」を有する糖尿病患者では、食事療法により体重が減少し、インスリン感受性が亢進することが期待できる。
❿—2型糖尿病の治療—運動療法
著者: 田村好史
ページ範囲:P.314 - P.315
◦血糖コントロールがよければ運動療法は勧めなくてもよいのか?
2型糖尿病治療において、食事・運動療法は重要な役割を担っている。近年では、糖尿病に対する経口薬が普及し、運動療法を行わなくても血糖値を低下させることが可能となってきた。しかしながら、もし血糖コントロールが良好であることを理由に、患者に運動療法を勧めず、患者が運動不足となれば、どうなるであろうか?
運動不足はさまざまな疾患のリスクを増加させることが知られており、運動療法は、糖尿病のコントロールの良し悪しにかかわらず、禁忌でなければ全員にお勧めすべき治療法なのである。もう少し広く言えば、糖尿病患者であるかどうかにかかわらず、本稿を読んでいるあなた自身も含め、基本的にはどのような人でも運動療法(正確には身体活動量を増やすこと)が勧められる。
⓫いろいろな世代の糖尿病
著者: 荒田尚子
ページ範囲:P.316 - P.318
Case
就職して転居し紹介となった2型糖尿病をもった20代女性の一例
患者:22歳、女性
家族歴:両親ともに糖尿病あり
現病歴:14歳の学校検診で尿糖陽性を認め、小児内分泌代謝専門医のもと、肥満の改善とメトホルミン内服でHbA1c 6.5%前後にコントロールされていた。就職を機に転居し、内科へ紹介となった。
月経周期は35〜45日。喫煙歴・飲酒歴なし。彼氏はいない。
現症:身長154cm、58kg。血圧100/56mmHg。
対応:生活習慣の改善とメトホルミンを中心に、メタボリック症候群に留意しつつ肥満の改善を目指して治療を継続する。挙児可能年齢であり、月経に伴う体重や食欲の変動、プレコンセプションケア(後述)を行いつつ、治療中断がないように対応することが重要である。
⓬どうする? 高齢糖尿病患者の「マルチモビディティ」と「ポリファーマシー」
著者: 大浦誠
ページ範囲:P.320 - P.323
Case
患者:78歳、男性。妻と2人暮らし。遠方に長男夫婦が住んでいる。
現病歴:50歳で「高血圧症」「2型糖尿病」「脂質異常症」「慢性腎臓病」「高尿酸血症」を指摘され、58歳で「急性心筋梗塞」を発症し、循環器内科に「非弁膜症性心房細動」「慢性心不全」「肺気腫」で通院していた。また、泌尿器科に「前立腺肥大症」のため通院していたが受診しなくなり、整形外科には「変形性膝関節症」と「腰部脊柱管狭窄症」で通院していた。
ADLは杖歩行で、食事・更衣・排泄は自立している。要介護1で、デイサービスを週2回利用している。嗜好歴は58歳まで喫煙、日本酒1合/日であった。定期受診日に、内服薬が大量に余っていることが発覚。また高齢者総合機能評価で、軽度の認知機能障害と抑うつ傾向を認めていた。
処方薬:ヒドロクロロチアジド、トラセミド、エナラプリル、ビソプロロール、リバーロキサバン、クロピドグレル、シタグリプチン、ロスバスタチン。整形外科でセレコキシブ、プレガバリン。
⓭「1型糖尿病」の患者が受診した際の注意点
著者: 高池浩子
ページ範囲:P.324 - P.325
Case
SGLT2阻害薬内服中に急性胃腸炎を契機として「正常血糖ケトアシドーシス」を発症した一例
患者:38歳、女性。16歳時に1型糖尿病と診断され、インスリン強化療法中。
現病歴:X-1年に、SGLT2阻害薬が開始された。2日前より嘔気・下痢のため食事摂取量が低下し、近医で「急性胃腸炎」と診断された。その後、腹痛・全身倦怠感が出現・増悪したため、救急外来を受診した。
身体所見 :身長155cm、体重53kg。血圧104/
66mmHg、脈拍数96回/分・整、呼吸数17回/分。その他、明らかな異常は認めない。
検査所見:随時血糖245mg/dL、HbA1c 7.8%。尿ケトン(3+)。pH 7.159、HCO3- 8.1mmol/L。血中総ケトン17,016μmol/L、CPR<0.03 ng/mL。
⓮「耐糖能異常」の段階で行うべき指導と治療
著者: 大塚雄一郎 , 中神朋子
ページ範囲:P.326 - P.328
耐糖能異常とは、正常よりも血糖値が高いが糖尿病ではない状態で、「境界型糖尿病」あるいは「糖尿病予備群」とも呼ばれている。耐糖能異常者の25%は3〜5年以内に糖尿病を発症し、生涯発症率は約70%であり1)、正常耐糖能に比べて大血管障害のリスクや死亡率も高いため、耐糖能異常の段階で積極的な介入が必要である2)。
【Ⅲ章】知っておきたい! NEWトピックス
❶2型糖尿病と「スティグマ」
著者: 加藤明日香
ページ範囲:P.329 - P.331
米国の社会学者Goffman1)は、スティグマとは「属性・特性・障がいなどが“通常”の人々とは区別され、容認しがたい存在として特徴づけられること」(1963)と定義した。ここで言う属性・特性・障がいは疾患に限定されず、性別・年齢・人種・宗教・学歴といったさまざまな属性も含まれる1)。疾患がスティグマの対象とされやすいかどうかは、それがどの程度可視的かによる1)。さらに、本人の責任が問われるような疾患、すなわち個人が予防・管理可能であると一般に考えられている疾患は、よりスティグマの対象とされやすい2)。
しばしばスティグマと混同して使用される用語として「偏見」と「差別」があるが、これらは、「ステレオタイプ」とともに、スティグマ化のプロセスの構成要素となる3)。スティグマの対象となる人々について社会に広く行きわたっている固定されたネガティブな見方(ステレオタイプ)が、多くの人々に負の感情反応(偏見)を生み、それが行動的な反応(差別)へとつながっていく3)。
❷「コロナ禍」における糖尿病診療
著者: 大杉満
ページ範囲:P.332 - P.333
新型コロナウイルス感染拡大の初期から、「糖尿病」や「肥満」がCOVID-19の重症化リスクであることが指摘されている。多数の国でのさまざまな検討から、なかでも「血糖コントロールの悪い糖尿病」と「肥満」が重症化のリスク因子であることが確定している1,2)。可能なら「減量」や「血糖コントロール」を良好に保つことが勧められるが、加えて日頃から「身体活動量」を保つこと(週150分以上の軽く息があがる以上の運動)でもCOVID-19が重症化したり、それを原因とする死亡が減少することが知られている3)。
❸糖尿病患者の「災害」への備え
著者: 石垣泰
ページ範囲:P.334 - P.334
平時には管理良好な糖尿病患者でも、災害時には血糖コントロールが不安定になる。その理由として、「炭水化物中心の食事」「活動量の大きな変化」「ストレス」「糖尿病治療薬の不足・不適合から血糖値が上昇しやすい」「食料不足や夜間に絶食が長時間に及ぶための低血糖リスク増加」などがあげられる。高血糖の持続やインスリン治療の不足は、「感染症」や「高血糖緊急症」による救急搬送につながる。
❹糖尿病と「認知症」
著者: 荒木厚
ページ範囲:P.335 - P.338
Case
インスリン治療の単純化を行った一例
患者:82歳、女性。娘夫婦と同居。
現病歴:50歳の時に2型糖尿病を指摘され、62歳から強化インスリン療法で治療し、HbA1c 8.0%前後で経過していた。81歳から物忘れがあり、6カ月前から買い物ができなくなった。インスリン注射を忘れることも多くなり、HbA1c 8.5%となった。DASC-8(認知・生活機能質問票)は16点でカテゴリーⅡ、MMSE(ミニメンタルステート検査)は22点で軽度認知症と診断し、血糖コントロール目標はHbA1c<8.0%、目標下限値7.0%とした。血糖コントロール目的で2週間入院し、インスリン分泌は保たれているため、週1回のGLP-1受容体作動薬の注射とグリクラジド20mg、メトホルミン500mgの併用に変更し、治療の単純化を行った。要介護1となり、週2回のデイケアを開始し、週1回の訪問看護師による注射と服薬確認を行い、家族へ服薬サポートを依頼した。
Editorial
一病息災:糖尿病とともに生きる フリーアクセス
著者: 大西由希子
ページ範囲:P.251 - P.251
告白しなければならない。研修医時代、私は糖尿病診療が苦手だった。「雨が多かったので、ウォーキングできませんでした」「外食が多かったので、インスリンを打てない時が多かったのです」と、患者さんは血糖管理がうまくできない理由を外来でおっしゃる。私自身は日々の忙しさを言い訳に、食生活は乱れ、運動らしい運動もせずに仕事ばかりしていたにもかかわらず、自分のことは棚に上げて「糖尿病患者さんの言い訳ばかり聞きたくないなぁ」と思うことさえあり、患者さんたちに全く寄り添えていなかった。
糖尿病を専門として志した理由は、大学院で糖尿病研究室の先輩方と一緒に研究させていただきたいと思ったからで、糖尿病診療を熱望していたわけではなかったかもしれない。そんな大学院生の頃、患者さんに「先生だって、おいしいものをおなかいっぱい食べたいでしょう?」と聞かれ、はたと気づいた。振り返ると、この1カ月に飲み会が何回あって、雨の日が何回あって、栄養バランスに気をつけた食事を何回できたか、自分は即答できるだろうか。「糖尿病患者さんは、食事・運動療法をいつも気にしながら生活しているなんて、えらいなぁ」と、患者さんに敬意をもって診療するようになった。
What's your diagnosis?[243]
お酢を足せば少ないはずなのに…
著者: 浜田禅 , 風間亮 , 牧隆太郎 , 北村大 , 浅川麻里
ページ範囲:P.254 - P.258
病歴
患者:67歳、男性
主訴:粘液便
現病歴:もともと便秘でセンナエキスを服用していた。1カ月前に便秘が増悪したため下剤を増量した頃から、卵の白身のような粘液便が出現した。下剤を中止して整腸薬(近医処方)を服用したが改善せず、赤い粘液便が出現するようになった。3時間に1回程の排便回数であり、食事に関係なく夜間も認めた。食欲はやや低下し、今回で約5kg体重が減少した。近医より精査目的に当院の外来に紹介受診となった。腹痛、嘔気・嘔吐、しぶり腹、腹部膨満感、頻尿・排尿時痛、咳・痰、熱・寒気・盗汗などはなかった。
併存症:Parkinson病、変形性頸椎症、うつ病
既往歴:脳梗塞(後遺症なし)
内服薬:レボドパ、ドンペリドン、クロピドグレル、エスシタロプラム、ミルタザピン、ブロチゾラム、サナクターゼ、ビフィズス菌製剤、その他漢方・サプリメントの使用なし
アレルギー:なし
嗜好歴:喫煙20本/日(20〜38歳)、飲酒 なし
海外渡航:なし
性交歴:機会は全くなし
【エッセイ】アスクレピオスの杖—想い出の診療録・35
「先生は、何もわかっていない」
著者: 浜田久之
ページ範囲:P.259 - P.259
本連載は、毎月替わる著者が、これまでの診療で心に残る患者さんとの出会いや、人生を変えた出来事を、エッセイにまとめてお届けします。
対談|医のアートを求めて・2
医療×映画—社会の枠組みからはみ出した「声にならない声」を表現する—映画『MOTHER マザー』より
著者: 大森立嗣 , 平島修
ページ範囲:P.343 - P.348
対談は大森立嗣監督の映画『MOTHERマザー(2020)』をもとに進めていった。この映画に描かれていたのは、貧困・虐待・犯罪といった社会の闇が最初から最後まで貫かれていた物語であった。親から暴力を受け続けた子どもが成長し、やがて思春期になり、他の子ども・社会と交わる中で、自分が受けている暴力が当たり前のことではないと知った時、いったい子どもはどのような声を上げるのか? 大森監督は映画人生を通して、こうした「声にならない声」を表現したいとおっしゃる。
社会に存在する全ての人を対象とする医師は、最新のエビデンスや医学知識と同等に、患者の背景を知る必要があり、それには芸術や文化、社会情勢といったところに目を向けることが大切である。そのことを、本対談を通して感じていただけたら幸いである。
(平島 修)
Dr.上田剛士のエビデンス実践レクチャー!医学と日常の狭間で|患者さんからの素朴な質問にどう答える?・36
タマゴは1日1個までしかダメですか?
著者: 上田剛士
ページ範囲:P.349 - P.353
患者さんからのふとした質問に答えられないことはないでしょうか? 素朴な疑問ほど回答が難しいものはありませんが、新たな気づきをもたらす良問も多いのではないでしょうか? 本連載では素朴な疑問に、文献的根拠を提示しながらお答えします!
臨床教育お悩み相談室|どうする!?サロン・3
“Residents are alright!”—研修医の「心理的安全性」を守るには?
著者: 佐田竜一 , 木村武司 , 長野広之
ページ範囲:P.362 - P.365
今月のお悩み
卒後10年目の指導医です。レジデントの外来指導担当に最近なりました。指導経験も少なく、悩みながらやっているのですが、最近あるレジデント(初期研修2年目)が、外来指導で気になる点を注意したあと、目を合わせてくれません。指導がキツすぎたのでしょうか?
[ペンネーム:りー5世]
オール沖縄!カンファレンス|レジデントの対応と指導医の考えVer.2.0・74
“Hi-Phy-Image”で乗り越えよう!
著者: 比嘉真凡 , 佐藤直行 , 徳田安春
ページ範囲:P.366 - P.370
CASE
患者:52歳、女性。
主訴:心窩部痛、発熱、右腰痛。
現病歴:当院入院前日の午前3時頃に心窩部から下腹部中央にかけての腹痛が出現し、目が覚めた。腹痛は絞られるような波のある痛みで、嘔気・嘔吐はない。のたうちまわるほど痛みが強くて冷や汗も出た。我慢していたら少し眠れたが、再度目を覚ました時にも腹痛があったため、同日朝にかかりつけの近医を受診した。診察では当初、腹部全体に圧痛があったが、反跳痛はなく、検査などが終わる頃には圧痛は心窩部に限局していた。採血では白血球11,100/μL以外に肝腎機能に異常はなく、血清アミラーゼやCRPの上昇はなかった。エソメプラゾール20mgが処方され、翌日に当院を受診するよう紹介状を渡され帰宅となった。帰宅後に悪寒と38.5℃の発熱があり、アセトアミノフェンを内服した。食事は摂らずに飲水のみで我慢していたが、飲水しても腹痛の増悪はなかった。右の腰痛もいつの間にか出現しており、発熱も腹痛も持続するため、当院消化器内科を紹介受診した。
頭痛や呼吸器症状、下痢、黒色便、関節痛、排尿時痛、頻尿、残尿感、めまい、しびれ、脱力はない。消化器内科で評価後、造影CTで尿路感染症が疑われ、同日当科に入院依頼となった。
既往歴・内服薬:本態性高血圧症、不安神経症で近医通院中。定期内服はアムロジピン2.5mg/日のみ。毎年健診を受けている。2カ月前に下部消化管内視鏡検査、1カ月前に上部消化管内視鏡検査も受けており、十二指腸下降部の憩室の指摘のみだった。手術歴なし。市販薬やサプリメントなどの内服なし。
家族歴:悪性腫瘍や心血管系疾患を含め、特記事項なし。
社会歴:飲酒歴:ビール350mLを2本/日。喫煙歴:10本/日を30年間。アレルギー:薬剤・食物共になし。
【臨床小説—第二部】後悔しない医者|今と未来をつなぐもの・第35話【最終回】
未来へ向かう医者
著者: 國松淳和
ページ範囲:P.371 - P.379
前回までのあらすじ 今月のナゾ
オンラインカンファレンスにて、ついに東京の黒野鈴と五島の向後翠が、場を隔てて再会した。向後の育ての父・向後英の旧知であった山梨の白川も参加しており、2人の再会を画面越しに見届けた。その再会は実にあっさりしたものだった。五島の右井の相談症例(69歳・男性、全身浮腫に加え顕著な血小板減少)を、東京の栗塚が鮮やかに「TAFRO症候群」と診立てると、黒野は「たこつぼ心筋症」の合併を言い当てた。なぜ黒野は、それを見抜くことができたのか? その疑問は解消しないまま向後チームは治療を急ぎ、カンファレンスは呆気なく幕切れたのだが…。
ついに最終回を迎えた。黒野と向後は、実は双子の兄弟で幼い頃に生き別れるも、示し合わせたように2人とも医者になっていた。1人は聴覚に、1人は視覚に長け、臨床医として超能力をもっている。その力は荒唐無稽なものなのだろうか? 臨床医の「能力」とは?
投稿 Update'23
末期腎不全期の糖尿病治療では、DPP-4阻害薬よりGLP-1受容体作動薬を選ぶべきか?—最新研究より
著者: 大城譲
ページ範囲:P.341 - P.342
DPP-4(ジペプチジルペプチダーゼ-4)阻害薬は、単剤では低血糖が起こりにくいことなどから、初期の糖尿病薬物療法での投与が急速に拡大した。しかし、そうした傾向のなかで、注意すべき研究が報告されたので紹介する。
DPP-4阻害薬と、GLP-1(グルカゴン様ペプチド-1)受容体作動薬は、主要な作用機序は共通とされている糖尿病治療薬である。この両薬剤を、末期腎不全患者で比べた場合、予後に大きな差が生じることが報告された(台湾での後ろ向きコホート研究である)1)。
#総合診療
#今月の特集関連本❶ フリーアクセス
ページ範囲:P.284 - P.284
#今月の特集関連本❷ フリーアクセス
ページ範囲:P.300 - P.300
#今月の特集関連本❸ フリーアクセス
ページ範囲:P.306 - P.306
#今月の特集関連本❹ フリーアクセス
ページ範囲:P.318 - P.318
#今月の特集関連本❺ フリーアクセス
ページ範囲:P.331 - P.331
#今月の特集関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.357 - P.357
#医学書院の新刊 フリーアクセス
ページ範囲:P.359 - P.360
#書評:フローチャート 糖尿病漢方薬—漢方でインスリンは出ません! フリーアクセス
著者: 古川慎哉
ページ範囲:P.355 - P.355
漢方を糖尿病診療に上手に取り入れるための実践本
田村朋子先生と新見正則先生との共著で、フローチャートシリーズに「糖尿病漢方薬」が登場しました。糖尿病の治療は、食事や運動をはじめとした生活習慣の見直しが基本となります。生活習慣を変えようとしている患者さんを診ていると、私たちもどうにか後押ししたいという気持ちにしばしばなります。そんな患者さんを支えることは、臨床家の力の見せ所でもありますし、糖尿病診療の面白さの1つだと思います。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.252 - P.253
読者アンケート
ページ範囲:P.361 - P.361
『総合診療』編集方針 フリーアクセス
ページ範囲:P.381 - P.381
1991年に創刊した弊誌は、2015年に『JIM』より『総合診療』に誌名を変更いたしました。その後も高齢化はさらに進み、社会構造や価値観、さらなる科学技術の進歩など、日本の医療を取り巻く状況は刻々と変化し続けています。地域医療の真価が問われ、ジェネラルに診ることがいっそう求められる時代となり、ますます「総合診療」への期待が高まってきました。これまで以上に多岐にわたる知識・技術、そして思想・価値観の共有が必要とされています。そこで弊誌は、さらなる誌面の充実を図るべく、2017年にリニューアルをいたしました。本誌は、今後も下記の「編集方針」のもと、既存の価値にとらわれることなく、また診療現場からの要請に応え、読者ならびに執筆者のみなさまとともに、日本の総合診療の新たな未来を切り拓いていく所存です。
2018年1月 『総合診療』編集委員会
『総合診療』バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.382 - P.383
お得な年間購読のご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.383 - P.384
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.385 - P.386
基本情報
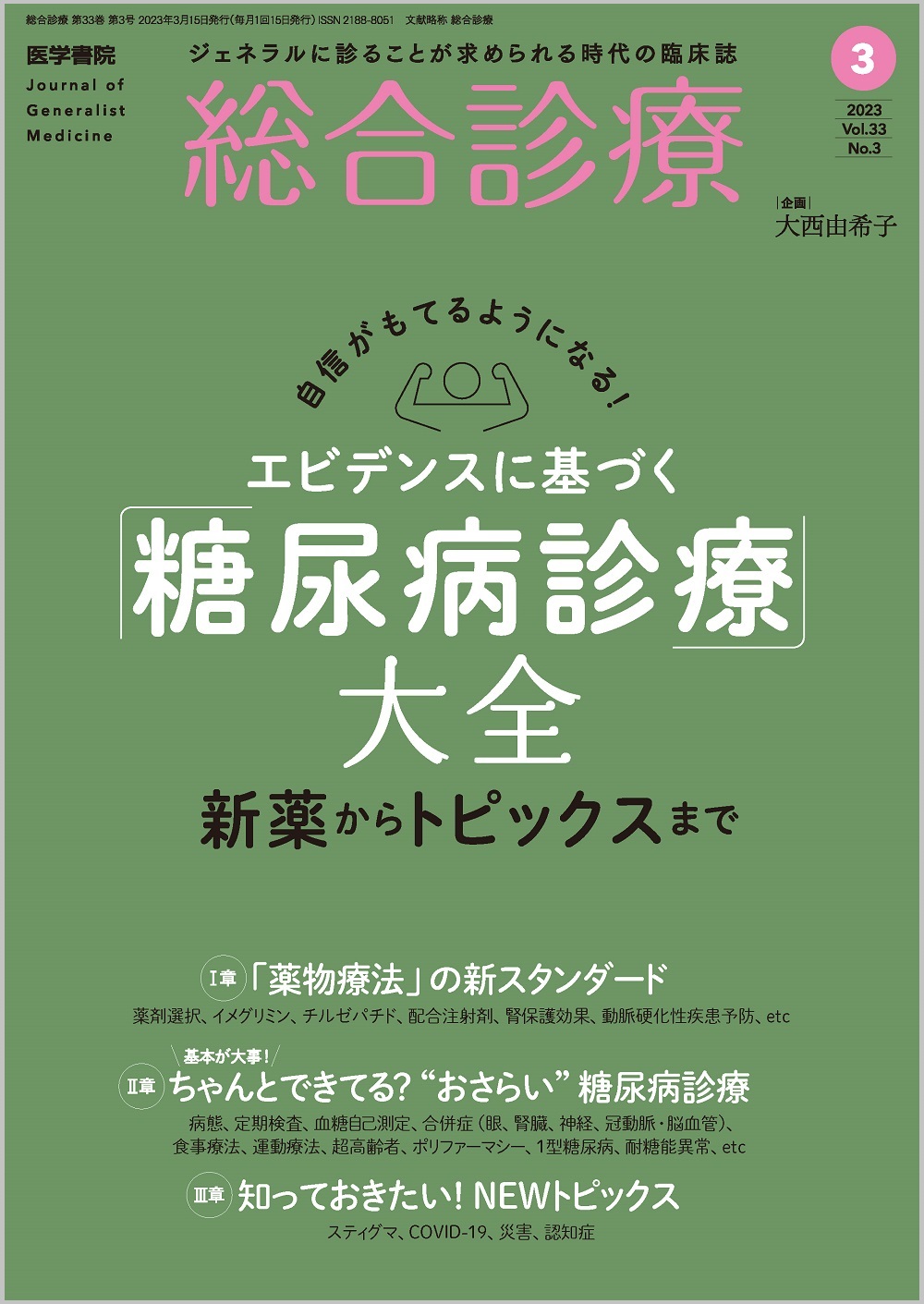
バックナンバー
34巻12号(2024年12月発行)
特集 妊婦・褥婦が外来に来たらUpdate—症状対応からワクチン・プラネタリーヘルスまで
34巻11号(2024年11月発行)
特集 電子カルテとベッドサイドの壁を打ち破る!—患者情報の「言語化」への挑戦
34巻10号(2024年10月発行)
特集 化かしが得意なカメレオンな疾患を捕まえろ!—よくある騙され方のゲシュタルト
34巻9号(2024年9月発行)
特集 今伝えたいクリニカル・パール—つくり方、使い方、活かし方
34巻8号(2024年8月発行)
特集 ストーン・ウォーズ 果てしなき“石”と医師との闘い
34巻7号(2024年7月発行)
特集 どうする!? 健診異常—これってホントに異常なの? どう説明する?
34巻6号(2024年6月発行)
特集 医師のウェルビーイング
34巻5号(2024年5月発行)
特集 —優柔不断にサヨウナラ!—あなたの「臨床判断」を高めるケーススタディ11選
34巻4号(2024年4月発行)
特集 困ったときの漢方—この症状に役立ちます!
34巻3号(2024年3月発行)
特集 —え、ウソ!実は◯◯だった!?—“コモンディジーズ”の診断ピットフォール
34巻2号(2024年2月発行)
特集 日常診療で出合う筋骨格疾患—脳神経内科と整形外科からのアプローチ
34巻1号(2024年1月発行)
特集 —“体験型”臨床クイズで習得する!—フィジカル診断エクセレンス
33巻12号(2023年12月発行)
特集 海の外へ渡る航行者を診る—アウトバウンドにまつわるetc.
33巻11号(2023年11月発行)
特集 —続・総合診療外来に“実装”したい—最新エビデンスMy Best 3
33巻10号(2023年10月発行)
特集 ○×クイズ110問!日常診療アップグレード—Choosing WiselyとHigh Value Careを学ぼう
33巻9号(2023年9月発行)
特集 ジェネラリストのための「発達障害(神経発達症)」入門
33巻8号(2023年8月発行)
特集 都市のプライマリ・ケア—「見えにくい」を「見えやすく」
33巻7号(2023年7月発行)
特集 “消去法”で考え直す「抗菌薬選択」のセオリー—広域に考え、狭域に始める
33巻6号(2023年6月発行)
特集 知っておくべき!モノクロな薬たち(注:モノクローナル抗体の話ですよ〜)
33巻5号(2023年5月発行)
特集 —疾患別“イルネススクリプト”で学ぶ—「腹痛診療」を磨き上げる22症例
33巻4号(2023年4月発行)
特集 救急対応ドリル—外来から在宅までの60問!
33巻3号(2023年3月発行)
特集 —自信がもてるようになる!—エビデンスに基づく「糖尿病診療」大全—新薬からトピックスまで
33巻2号(2023年2月発行)
特集 しびれQ&A—ビビッとシビれるクリニカルパール付き!
33巻1号(2023年1月発行)
特集 COVID-19パンデミック 振り返りと将来への備え
32巻12号(2022年12月発行)
特集 レクチャーの達人—とっておきの生ライブ付き!
32巻11号(2022年11月発行)
特集 不定愁訴にしない“MUS”診療—病態からマネジメントまで
32巻10号(2022年10月発行)
特集 日常診療に潜む「処方カスケード」—その症状、薬のせいではないですか?
32巻9号(2022年9月発行)
特集 総合診療・地域医療スキルアップドリル—こっそり学べる“特講ビデオ”つき!
32巻8号(2022年8月発行)
特集 こんなところも!“ちょいあて”エコー—POCUSお役立ちTips!
32巻7号(2022年7月発行)
特集 —どうせやせない!? やせなきゃいけない??苦手克服!—「肥満」との向き合い方講座
32巻6号(2022年6月発行)
特集 総合診療外来に“実装”したい最新エビデンス—My Best 3
32巻5号(2022年5月発行)
特集 「診断エラー」を科学する!—セッティング別 陥りやすい疾患・状況
32巻4号(2022年4月発行)
特集 えっ、これも!? 知っておきたい! 意外なアレルギー疾患
32巻3号(2022年3月発行)
特集 AI時代の医師のクリニカル・スキル—君は生き延びることができるか?
32巻2号(2022年2月発行)
特集 —withコロナ—かぜ診療の心得アップデート
32巻1号(2022年1月発行)
特集 実地医家が楽しく学ぶ 「熱」「炎症」、そして「免疫」—街場の免疫学・炎症学
31巻12号(2021年12月発行)
特集 “血が出た!”ときのリアル・アプローチ—そんな判断しちゃダメよ!
31巻11号(2021年11月発行)
特集 Q&Aで深める「むくみ診断」—正攻法も!一発診断も!外来も!病棟も!
31巻10号(2021年10月発行)
特集 医師の働き方改革—システムとマインドセットを変えよう!
31巻9号(2021年9月発行)
特集 「検査」のニューノーマル2021—この検査はもう古い? あの新検査はやるべき?
31巻8号(2021年8月発行)
特集 メンタルヘルス時代の総合診療外来—精神科医にぶっちゃけ相談してみました。
31巻7号(2021年7月発行)
特集 新時代の「在宅医療」—先進的プラクティスと最新テクノロジー
31巻6号(2021年6月発行)
特集 この診断で決まり!High Yieldな症候たち—見逃すな!キラリと光るその病歴&所見
31巻5号(2021年5月発行)
特集 臨床医のための 進化するアウトプット—学術論文からオンライン勉強会、SNSまで
31巻4号(2021年4月発行)
特集 消化器診療“虎の巻”—あなたの切実なギモンにズバリ答えます!
31巻3号(2021年3月発行)
特集 ライフステージでみる女性診療at a glance!—よくあるプロブレムを網羅しピンポイントで答えます。
31巻2号(2021年2月発行)
特集 肺炎診療のピットフォール—COVID-19から肺炎ミミックまで
31巻1号(2021年1月発行)
特別増大特集 新型コロナウイルス・パンデミック—今こそ知っておきたいこと、そして考えるべき未来
30巻12号(2020年12月発行)
特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き) Part 2
30巻11号(2020年11月発行)
特集 診断に役立つ! 教育で使える! フィジカル・エポニム!—身体所見に名を残すレジェンドたちの技と思考
30巻10号(2020年10月発行)
特集 —ポリファーマシーを回避する—エビデンスに基づく非薬物療法のススメ
30巻9号(2020年9月発行)
特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【感染症・内分泌・整形外科 編】
30巻8号(2020年8月発行)
特集 マイナーエマージェンシー門外放出—知っておくと役立つ! テクニック集
30巻7号(2020年7月発行)
特集 その倦怠感、単なる「疲れ」じゃないですよ!—筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群とミミック
30巻6号(2020年6月発行)
特集 下降期慢性疾患患者の“具合”をよくする—ジェネラリストだからできること!
30巻5号(2020年5月発行)
特集 誌上Journal Club—私を変えた激アツ論文
30巻4号(2020年4月発行)
特集 大便強ドリル—便秘・下痢・腹痛・消化器疾患に強くなる41問!
30巻3号(2020年3月発行)
特集 これではアカンで!こどもの診療—ハマりがちな11のピットフォール
30巻2号(2020年2月発行)
特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【循環器・消化器・神経疾患編】
30巻1号(2020年1月発行)
特集 総合診療医の“若手ロールモデル”を紹介します!—私たちはどう生きるか
29巻12号(2019年12月発行)
特集 困っている“あなた”に届く 認知症診療
29巻11号(2019年11月発行)
特集 臨床写真図鑑 レアな疾患編—見逃したくない疾患のコモンな所見
29巻10号(2019年10月発行)
特集 教えて!医師のためのビジネス・スキル
29巻9号(2019年9月発行)
特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き)
29巻8号(2019年8月発行)
特集 —ノーモア見逃し—日常の検査と画像に潜むピットフォール
29巻7号(2019年7月発行)
特集 リウマチ・膠原病ミミック症例帖—“膠原病っぽくみえてしまう疾患たち”にだまされない!
29巻6号(2019年6月発行)
特集 皮膚科診療エクササイズ—1枚の写真から
29巻5号(2019年5月発行)
特集 一般外来で診断できたら「えっへん!」な疾患38
29巻4号(2019年4月発行)
特集 “ナゾ”の痛み診療ストラテジー|OPQRSTで読み解く
29巻3号(2019年3月発行)
特集 —あなたのギモンに答えます!—循環器診療のハードルを下げるQ&A31
29巻2号(2019年2月発行)
特集 意外な中毒、思わぬ依存、知っておきたい副作用—一般外来で!OTCも処方薬も!
29巻1号(2019年1月発行)
特集 教えて検索!—膨大な医学情報を吟味・整理するスキル
28巻12号(2018年12月発行)
特集 こんなときこそ漢方を!
28巻11号(2018年11月発行)
特集 日本一マジメな「おしっこドリル」—今これだけは押さえておきたい腎・泌尿器のモンダイ
28巻10号(2018年10月発行)
特集 クリニカル・パールPremium!—憧れのカリスマ医師はかく語りき
28巻9号(2018年9月発行)
特集 オンコ・ジェネラリスト—「がん」に強い総合診療医をめざして
28巻8号(2018年8月発行)
特集 80歳からの診療スタンダードUp to Date—Silver Standard
28巻7号(2018年7月発行)
特集 この薬だけは押さえておきたい! 総合診療医のためのSpecialist Drug 40
28巻6号(2018年6月発行)
特集 聴診・触診×エコーで診断推論!—Point-of-Care超音波(POCUS)の底力
28巻5号(2018年5月発行)
特集 “一発診断”トレーニング問題集—懸賞論文「GM Clinical Pictures」大賞発表!
28巻4号(2018年4月発行)
特集 感染症外来診療「賢医の選択」—検査・経口薬・ワクチンをどう使えばいいんですか?
28巻3号(2018年3月発行)
特集 糖尿病のリアル—現場の「困った!」にとことん答えます。
28巻2号(2018年2月発行)
特集 頭痛患者で頭が痛いんです!
28巻1号(2018年1月発行)
特集 シン・フィジカル改革宣言!—私の“神技”伝授します。
27巻12号(2017年12月発行)
特集 小児診療“苦手”克服!!—劇的Before & After
27巻11号(2017年11月発行)
特集 今そこにある、ファミリー・バイオレンス|Violence and Health
27巻10号(2017年10月発行)
特集 めまいがするんです!─特別付録Web動画付
27巻9号(2017年9月発行)
特集 うつより多い「不安」の診かた—患者も医師も安らぎたい
27巻8号(2017年8月発行)
特集 見逃しやすい内分泌疾患─このキーワード、この所見で診断する!
27巻7号(2017年7月発行)
特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 3 カリスマ編
27巻6号(2017年6月発行)
特集 「地域を診る医者」最強の養成法!
27巻5号(2017年5月発行)
特集 コミュニケーションを処方する—ユマニチュードもオープンダイアローグも入ってます!
27巻4号(2017年4月発行)
特集 病歴と診察で診断できない発熱!—その謎の賢い解き方を伝授します。
27巻3号(2017年3月発行)
特集 これがホントに必要な薬40—総合診療医の外来自家薬籠
27巻2号(2017年2月発行)
特集 The総合診療ベーシックス—白熱!「総合診療フェスin OKINAWA」ライブ・レクチャー! 一挙公開 フィジカル動画付!
27巻1号(2017年1月発行)
特集 総合診療の“夜明け”—キーマンが語り尽くした「来し方、行く末」
26巻12号(2016年12月発行)
特集 これでパッチリ! 眼の健康問題
26巻11号(2016年11月発行)
特集 続・しびれるんです!
26巻10号(2016年10月発行)
特集 内科診療を劇的に変える“まとめ”の達人
26巻9号(2016年9月発行)
特集 症状・症候別 エコーを使った診断推論─Point-of-Care超音波
26巻8号(2016年8月発行)
特集 The 初診外来
26巻7号(2016年7月発行)
特集 感染症ケアバンドル・チェックリスト
26巻6号(2016年6月発行)
特集 “賢い処方”と“ナゾ処方”
26巻5号(2016年5月発行)
特集 しびれるんです!─知っておくべきシビレル疾患
26巻4号(2016年4月発行)
特集 ケースとクイズで総ざらい! 街場の2型糖尿病治療
26巻3号(2016年3月発行)
特集 こんな時は漢方でしょう!
26巻2号(2016年2月発行)
特集 フィジカル改革宣言! ──診断からフォローアップまで
26巻1号(2016年1月発行)
特集 妊婦・褥婦が一般外来に来たら─エマージェンシー&コモンプロブレム
25巻12号(2015年12月発行)
特集 外来で「複数の疾患」をもつ患者を診る─マルチモビディティの時代のプライマリ・ケア
25巻11号(2015年11月発行)
特集 レアだけど重要な「痛み」の原因─システム1診断学
25巻10号(2015年10月発行)
特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 2
25巻9号(2015年9月発行)
特集 診断ピットフォール10選─こんな疾患,見逃していませんか?
25巻8号(2015年8月発行)
特集 健診データで困ったら─こんな検査結果を持ってこられたら
25巻7号(2015年7月発行)
特集 ここを知りたい!頭部外傷初期対応・慢性期ケア
25巻6号(2015年6月発行)
特集 高齢者救急の落とし穴─紹介する時,される時
25巻5号(2015年5月発行)
特集 咳を聴きとり,咳を止める
25巻4号(2015年4月発行)
特集 関節が痛いんです!─コモンからレアものまでの診断と治療
25巻3号(2015年3月発行)
特集 神経難病ケアのコペルニクス的転回
25巻2号(2015年2月発行)
特集 総合医のためのスポーツ医学ベーシックス
25巻1号(2015年1月発行)
特集 動悸・息切れ─ヤバい病気の見つけ方 そして見つからなかった時の対処法
