抗菌薬適正使用の実践には「適切な薬剤の選択」が重要です。
しかし、「適切な」薬剤の判断は医師ごとに異なる場合もあり、また1つの薬剤だけが正解という状況も多くはありません。
たとえば、身体に「良い」食物をあげることは難しいですが、「良くない」食物は連想できます。
(とても脂っこい、あるいは塩辛い、甘すぎる、熱すぎる食べ物でしょうか)
これらを避けることが、身体により良い物を食すことにつながるように、抗菌薬選択でも「不適切な」薬剤を避けることが、「より適切な」薬剤の使用につながります。
通常の試験問題では「正しいのはどれか?」という形式が推奨されます。
しかし実際の臨床では、“正解”がよくわからない場面もあります。
このような場合、「“不正解”あるいは“不要と判断するもの”以外から選択する」という、“消去法”のアプローチは一考の価値があります。
「ピンポイントな正解かどうかはわからないが、間違いではない」という判断を積み上げるほうが、「最適な抗菌薬を1つ選ばなければならない」と考えるより安心であり、周囲も受け入れやすいのではないでしょうか。
本特集では、初期治療薬として「必要性が低い抗菌薬はどれか?」という視点をもつことで、広域に考えつつ、より狭域で適正な抗菌薬選択を行うことを企図しました。
雑誌目次
総合診療33巻7号
2023年07月発行
雑誌目次
特集 “消去法”で考え直す「抗菌薬選択」のセオリー—広域に考え、狭域に始める
扉 フリーアクセス
著者: 青木洋介
ページ範囲:P.770 - P.771
今月の「めざせ! 総合診療専門医!」問題
ページ範囲:P.832 - P.833
本問題集は、今月の特集のご執筆者に、執筆テーマに関連して「総合診療専門医なら知っておいてほしい!」「自分ならこんな試験問題をつくりたい!」という内容を自由に作成していただいたものです。力試し問題に、チャレンジしてみてください。
【総論】
抗菌薬適正使用の実践に必要な「基本」—理論と行動科学
著者: 青木洋介
ページ範囲:P.772 - P.774
「基本」となる診療能力のレベルや範囲については多様な考え方があるが、筆者は「診療の骨子をなす理論と、その実践を正しく、あるいは誤りなく方向づけるための判断(judgment)と、意思決定(decision making)を行うことができる認知・思考機能の最小単位」を、すべての診療に共通する基本と考える。この能力を獲得するには、各論的知識の修得に加え、自身の判断や意思決定に影響を及ぼす「行動科学的特性」についても認識しておくほうがよい。本稿では、このような視点から、「抗菌薬適正使用(prudent antimicrobial use:PAUSE)」のための基本的論理について述べる。
【抗菌薬選択クイズⅠ】“消去法”で絞り込む抗菌薬選択
❶頭頸部感染症(鼻副鼻腔炎、中耳炎、咽頭炎)
著者: 伊藤渉 , 笠原敬
ページ範囲:P.775 - P.779
1|「診断」を検証して狭める!
鼻副鼻腔炎
顔面の疼痛や腫脹を伴う鼻汁・鼻閉などの症状で、鼻副鼻腔炎を疑う。咽頭痛や咳嗽など、複数の領域(咽頭や下気道)に症状が随伴する場合は、「感冒(ウイルス性急性気道感染症)」と診断し、抗菌薬は投与しない(p.781・809)。
症状が鼻・副鼻腔に限局し鼻副鼻腔炎と診断すれば、次はウイルス性か細菌性かを鑑別する。「細菌性鼻副鼻腔炎」の特徴は、罹病期間が長いこと(7〜10日以上)、一度軽快した症状が再増悪する二峰性の病歴を示すことなどとされる1,2)。「ウイルス性鼻副鼻腔炎」を疑えば、もちろん抗菌薬は投与しないが、細菌性鼻副鼻腔炎を疑ったとしても、その全例に抗菌薬が必要というわけではない(詳細は後述)。
❷肺炎(気道感染症)
著者: 青木洋介
ページ範囲:P.780 - P.784
呼吸器感染症の適正な治療には、診断の確認(検証)と、原因となる菌種および感受性を想定した抗菌薬の選択が必要である。本稿では「肺炎」を主として、初期治療薬をいかに適正に選択するか、その考え方を述べる。
❸胆道感染症
著者: 畑啓昭 , 末永尚浩
ページ範囲:P.785 - P.789
胆道感染症は「胆囊炎」と「胆管炎」に分けられる。病態悪化のスピードや治療方針、抗菌薬の投与期間などが異なるため、両者を区別して正しく診断することが重要である。また、胆管炎では、ステントや腫瘍など、原因菌が複雑化する因子がないかを確認して抗菌薬を考えることも重要である。
胆道感染症に関しては、日本発のガイドライン1,2)が世界で使用されており参考になるが、治療については多くの抗菌薬が併記されており、選択肢を狭めるステップが必要であろう。
❹尿路感染症
著者: 髙橋聡
ページ範囲:P.790 - P.793
尿路感染症の適正な治療は、「複雑性尿路感染症」と「単純性尿路感染症」で異なる。原因となる菌種は主として「大腸菌」であることは共通だが、単純性尿路感染症では比較的抗菌薬感受性が良好であり、複雑性尿路感染症では「耐性菌」を想定しなくてはならない。単純性尿路感染症では、万が一、初期治療薬が原因菌の感受性試験で耐性菌であったとしても、治療不成功とならなかったり、適切な抗菌薬への変更により対応可能である。しかし複雑性尿路感染症、特に重症化した「有熱性尿路感染症」では、初期治療薬の選択によっては全く無効であったり難治化する場合がある。
❺皮膚・軟部組織感染症
著者: 石田景子 , 荒岡秀樹
ページ範囲:P.794 - P.798
1|「診断」を検証して狭める!
皮膚・軟部組織感染症(skin and soft tissue infection:SSTI)は、病変の部位・深さ、および病因によって特徴づけられるため、診察の際には皮膚の解剖を想起するとよい。「膿痂疹」は表在にとどまる痂皮性・水疱性の病変であり、水疱性膿痂疹は「とびひ」とも呼ばれる。「丹毒」は真皮の浅い部分の病変であるため境界が明瞭で、隆起する鮮やかな紅斑を生じる。一方、「蜂窩織炎」は丹毒よりも深く、真皮から皮下組織の病変であるため境界が不明瞭で、境界の隆起しない紅斑と腫脹を生じる。「壊死性筋膜炎」は、皮下組織と筋膜に壊死を起こす病態であり、通常急性の経過をとる。身体のどの部位にも起きうるが、四肢に多く3分の2が下肢に起こる1)。
❻腸管感染症
著者: 中村(内山)ふくみ
ページ範囲:P.799 - P.803
腸管感染症に対する抗菌薬は、想定される原因菌と患者背景によって投与するか否かを判断する。本稿では、腸管感染症のなかでも「急性下痢症(発症から14日間以内で、軟便または水様便が普段の排便回数よりも1日3回以上増加している状態)」への対応について考え方を整理する。
❼眼科感染症
著者: 佐々木香る
ページ範囲:P.804 - P.807
眼科感染症における抗菌薬適正使用として、主として「点眼剤」の使い方を取り上げる。点眼剤の種類は少なく、本邦では極端にフルオロキノロン系薬の使用に偏っている。そのため結膜囊常在菌は、すでに高度に「フルオロキノロン耐性」を獲得している。
本稿では、「結膜充血」にプライマリ・ケア医としてどのように対応すべきか、初期治療における抗菌薬の要否をどのように考えるか、そして何を選択するか、またどのような場合に眼科受診を検討するかについて述べる。
❽小児感染症
著者: 石和田稔彦
ページ範囲:P.808 - P.811
小児感染症の適切な治療は、年齢と病歴、微生物検査に基づく原因微生物の推定と、その種類および薬剤感受性を想定した治療薬の選択が基本となる。本稿では、小児感染症として頻度の高い呼吸器感染症である「咽頭炎」「中耳炎」「気管支炎」「肺炎」を取り上げ、いかに初期治療薬を適正に選択するか、その考え方を述べる。
【抗菌薬選択クイズⅡ】緊急を要する感染症の初期抗菌薬選択
❶「中枢神経感染症」を疑う患者
著者: 加藤英明
ページ範囲:P.812 - P.815
中枢神経感染症は、「髄膜炎」「脳炎」「脳膿瘍」などを総称したものである。深部臓器であるため、症状には発熱・頭痛・精神変容・異常行動など幅がある。髄膜刺激症状としてKernig徴候やBrudzinski徴候がよく知られるが、これらがみられるのは細菌性髄膜炎の10%程度と低く、髄膜に炎症が及ばない脳炎や脳膿瘍では、必ずしも髄膜刺激症状がみられるとは限らない。
しかしながら、いずれも迅速な診断と治療を要する病態であり、画像・髄液検査などの診断を進めるのと並行して、典型的な病原微生物を想定した初期治療の開始が必要である。また、髄液は抗菌薬が移行しにくい臓器の1つであり、「髄液移行性」を考慮した抗菌薬選択と投与量の調整が必要である。
❷「敗血症・敗血症性ショック」の初期治療
著者: 石井潤貴 , 志馬伸朗
ページ範囲:P.816 - P.821
敗血症性ショックの初期治療では、経験的治療における抗菌薬選択が広域となりがちで、時に過剰な広域・多剤が使用されることもある。しかし広域抗菌薬の使用は、死亡を含む不良転帰との関連を示唆する報告が増え、重症であることだけでは正当化されない(p.830)。
致死率を下げずに、より狭域の経験的治療薬選択を目指す意義があり、その1つの考え方を「targeted empirical therapy(TET)」(図1)と筆者は呼んでいる。本稿では、市中発症の「敗血症」および「敗血症性ショック」の患者を想定したTETの考え方について述べる。
【抗菌薬選択クイズⅢ】スキルアップ! 抗菌薬の要否と選択
❶「一次検査所見」を抗菌薬要否の判断に役立てる
著者: 濵田洋平
ページ範囲:P.822 - P.826
プライマリ・ケアの現場で初期に検査される項目を「一次検査」と呼ぶ。尿検査やCBC、血液生化学検査などは、外来診療や入院時スクリーニングとして多くの患者に施行される。一次検査は、診断につながる多くの情報を臨床医に与えるものであり、本稿では「発熱診療」における有用性について概説する。
❷「フォーカス不明」の感染症の抗菌薬の要否と選択
著者: 的野多加志
ページ範囲:P.827 - P.831
1|感染症診療における「臨床推論」
「医学は不確実性のサイエンスであり、確率のアートである」。このWilliam Oslerの言葉のように、医師は、ある“疾患らしさ”の確率を上げ下げしつつ診断を行っている。その手法は「臨床推論」と呼ばれ、「病歴聴取」「身体診察」「診断的検査」「コンサルテーション」から得られた情報を統合することで診断を導き出している。
確定診断にたどり着かない場合には、これらの必要な情報の何かが欠けているはずであり、なかでも「病歴」から得られる情報が最も重要だと考えられている(図1)1)。要するに、診断に重要なプロセスとは、患者と向かい合って詳細な病歴聴取と身体診察を行うことと、検査前確率を意識した適切な検査を行うことなのだ。決して、検査の乱れ打ちや、「発熱=COVID-19(新型コロナウイルス感染症)」「発熱+CRP上昇=細菌感染症」といった短絡的な思考ではない。これらは、臨床推論の原則から大きく逸脱するものであり、診断エラーを起こしかねない。そもそも感染症は、悪性腫瘍や心血管系疾患と並び、「診断エラー(診断の見逃し、間違い、遅れ)」が多い疾患である2)。
Editorial
広すぎる「安全ネット」を安全に狭めるための“消去法” フリーアクセス
著者: 青木洋介
ページ範囲:P.759 - P.759
1981年、208名の判事を被験者として16件の仮想犯罪事例それぞれに量刑を下す研究が、米国で行われました1)。すると、たとえば、全判事の平均刑期「8.5年」の事例の最長刑期は「終身刑」、あるいは同「1.1年」の最長刑期は「15年」と、かなりのバラつき—ノイズ—があることが判明し、特定の犯罪に固有の量刑の範囲が定められることになりました。このようなことを背景に生まれたのが「ガイドライン」です。
「診療ガイドライン」も、医師間の診療方針のバラつきをなくし、医療の焦点をゆるやかに絞ることを目的とした診療支援ツールです。しかし、“唯一の真実”というわけではありません。一定方向に偏移すると、ノイズが低減される代わりに「バイアス(≒偏重)」が生じます。
What's your diagnosis?[247]
理由に口無し
著者: 松島弘季 , 明保洋之 , 佐田竜一
ページ範囲:P.764 - P.768
病歴
患者:53歳、女性
主訴:腹痛、嘔吐
現病歴:来院5日前と1日前に、突発性の鋭い腹痛、嘔吐を主訴に救急外来を受診した。便秘・腸蠕動運動に起因する腹痛として、緩下薬・制吐薬・鎮痛薬を処方のうえ帰宅とし、有事再診となっていた。帰宅後も嘔吐があり、腹痛が再燃したため救急外来を再受診した。
ROS(+):腹痛、嘔吐(腹痛の後)、腹部膨満感、便秘
ROS(-):発熱、悪寒戦慄、体重減少、頭痛、脱力、構音障害、難聴、耳鳴り、めまい、血便、黒色便、排尿時痛
既往歴:Ménière病、両側乳腺腫瘍
常備薬:なし
アレルギー歴:なし
嗜好歴:飲酒・喫煙なし
【エッセイ】アスクレピオスの杖—想い出の診療録・39
ジェネラリストに必要な ご遺体の診断学・4
「異状死の届出」と「死因の種類」の関係
著者: 森田沙斗武
ページ範囲:P.834 - P.838
Case
患者:82歳、男性。息子と2人暮らし。
既往歴:認知症、脳梗塞、高血圧
病歴:5年前に脳梗塞を発症したあと、軽度の認知症を認めていたが、身の回りのことはできていた。1年ほど前から肺炎を繰り返すようになり、当院内科にたびたび通院および入院をしていた。嚥下造影検査にて誤嚥を認め、嚥下障害・誤嚥性肺炎と診断。入院中は、抗菌薬治療のあと、嚥下食などを用い、口腔ケアに努めることで、再発を予防できていた。しかし自宅でのケアが難しく、退院後1カ月程度で肺炎を再発。主治医が施設入所や胃ろう造設を提案するも、いずれも希望されず自宅療養を続けていた。
第1病日、発熱を主訴に受診され、誤嚥性肺炎と診断するも、同行の息子が入院に拒否的で、経口抗菌薬を処方して帰宅。第10病日、自宅のベッド上で心肺停止で発見され、当院に救急搬送。救急救命処置を行うも蘇生せず、死亡確認となった。四肢に軽度の皮下出血を認めたが、致命的な損傷を認めなかった。息子は「長らくお世話になりました」と当院および主治医に感謝を述べ、トラブルになる様子もなかったが、担当した救急医が「自宅で死亡した事例なので、警察に届け出る必要がある。死亡診断書は書くべきではない」と主張。息子と主治医は納得していなかったが、病院から警察に届出を行い、ご遺体は警察に引き取られた。
オール沖縄!カンファレンス|レジデントの対応と指導医の考えVer.2.0・78
突然の上気道閉塞! 正しい対応は?
著者: 安次嶺裕 , 清水徹郎 , 徳田安春
ページ範囲:P.839 - P.843
CASE
患者:79歳、女性。
主訴:意識障害。
現病歴:X年1月17日、患者自宅敷地内の駐車場を借りている人が、4日前より患者の家の電気が点いていないことから、患者宅を訪問。室内で倒れていた患者を発見し、救急要請した。16:35搬入。妹が最後に目撃したのはX-1年12月31日で、この時、患者は自宅の草むしりを行っていたとのこと。
患者背景:自宅独居。結婚歴なし。ADL自立。姉が1人、妹が2人いるが、もともと頑固な性格で、訪問すると怒るため、家族は1カ月に一度連絡を取る程度。妹の話では、認知症に加えて、ここ数カ月で足腰が弱ってきたため在宅介護サービスを調整したが、他人が家に上がることを嫌い頓挫した。
既往歴:X-5年に左大腿骨転子部骨折、骨接合術。心不全で入院歴があるとのことだが、詳細は不明。
薬剤歴:内服中の薬剤なし。
喫煙・飲酒歴:なし。
アレルギー歴:なし。
対談|医のアートを求めて・3
医療×育児・教育—不安定な大激動時代を生き抜くための教育とは?
著者: 高濱正伸 , 平島修
ページ範囲:P.855 - P.861
今日の常識が、明日の非常識。われわれはまさに、今このような時代に生きている。
ChatGPTというAIが昨年末に一般リリースされ、一気に世界が変わっていく予感を抱いている人も多いのではないだろうか。医師の仕事の大半がAIに取って代わるのも時間の問題かもしれないと感じており、教育の第一線で活躍される方と話してみたいと思った。
不安定な大激動時代を生き抜くために、いったいわれわれにとって何が重要なのか?
本対談がそのことを考えるきっかけとなれば幸いである。 (平島修)
臨床教育お悩み相談室|どうする!?サロン・7
The 細かすぎて伝わらない指導医
著者: 佐田竜一 , 木村武司 , 長野広之
ページ範囲:P.862 - P.866
今月のお悩み
2年目研修医です。指導医の指導に悩んでいます。私がとった身体所見をとり直すし、日中に出した検査オーダーは夕方出し直されてるし、「アレが足りない。コレが出てない」といちいち細かいんです! 自分の診療が患者さんへ悪い影響を与えているとも思えず…。信頼されてないんですかね? 指導医であるサロンのみなさんは、どう思いますか?
[ペンネーム:スルメ]
Dr.上田剛士のエビデンス実践レクチャー!医学と日常の狭間で|患者さんからの素朴な質問にどう答える?・40
鼻をかむことの弊害
著者: 上田剛士
ページ範囲:P.867 - P.869
患者さんからのふとした質問に答えられないことはないでしょうか? 素朴な疑問ほど回答が難しいものはありませんが、新たな気づきをもたらす良問も多いのではないでしょうか? 本連載では素朴な疑問に、文献的根拠を提示しながらお答えします!
臨床医のためのライフハック│限りある時間を有効に使う仕事術・4
—勉強法—自分の価値を高める「アウトプット主体」の勉強法
著者: 中島啓
ページ範囲:P.870 - P.873
時間がない! 臨床医の仕事は診療だけにあらず、事務、教育、自己学習、研究、学会発表、情報発信、所属組織の運営などなど、尽きることはありません。もちろんプライベートの生活もあり、「時間不足」は臨床医の永遠の課題です。では、一度きりの“医師人生”の限られた時間を、どう有効に使うのか? 筆者が培ってきた「ライフハック(仕事術)」のすべてを、余すところなく開陳します。
#総合診療
#今月の特集関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.845 - P.845
#今月の特集関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.847 - P.847
#今月の特集関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.849 - P.849
#今月の連載関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.873 - P.873
#医学書院の新刊 フリーアクセス
ページ範囲:P.851 - P.851
#書評:—トップジャーナルへの掲載を叶える—ケースレポート執筆法 フリーアクセス
著者: 皿谷健
ページ範囲:P.853 - P.853
向川原充、金城光代両先生の執筆による本書は、タイトルのとおりトップジャーナルへの掲載を叶えるケースレポート執筆法を述べた書籍である。究極的には、「論文を書くこと」を通じて「臨床能力をさらに高めるための本」だと言える。向川原先生が研修を受け、金城先生は現在も診療を行う沖縄県立中部病院には、今に語り継がれる数々のクリニカル・パール(教訓)がある。その多くは、common diseaseのuncommon presentationを1症例ずつ大切に語り継ぐ土壌があって残っているのだろう。本書でも、教訓をストーリーに即して提示する意義が強調されているのは、同院のそうした風土を基に執筆されているからではないか。大学院で「英文でのCase reportの書き方—How much is enough?」と題した講義を毎年行っている評者も、本書の随所に感じられる両先生の症例報告執筆に対する信念に深い共感を抱いた。
そもそも臨床医が症例報告を書きたい、形に残したいと思うのはなぜか? その理由は、圧倒的な熱量を注いで診療した患者には、患者自身あるいは患者-医師間のストーリーがあり、それを残したいと思うからだ。臨床経過上の困難を教訓として残し、次にその症例に出合った時に遅滞なく解決するためでもある。ストーリーに臨場感のある症例報告は、他施設で同様の困難に直面している医師のプラクティスを変えることに必ずや貢献するだろう。
#書評:—これでわかる!—抗菌薬選択トレーニング—感受性検査を読み解けば処方が変わる フリーアクセス
著者: 青木眞
ページ範囲:P.854 - P.854
2016年5月に開催された先進国首脳会議、通称「伊勢志摩サミット」で薬剤耐性(AMR)の問題が取り上げられ、当時の塩崎恭久厚生労働大臣のイニシアチブのもと、さまざまな企画が立ち上げられた。国立国際医療研究センターにある国際感染症センターの活動も周知のとおりである。
にもかかわらず、広域抗菌薬の代表とも言えるカルバペネム系抗菌薬の消費が、日本だけで世界の7割を占めるという状況から、(一部の意識の高い施設を除いて)大きく変わった印象が現場に少ない。もちろん、最大の原因は「感染症診療の原則とその文化」の広がりが均一でないことによる。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.760 - P.761
『総合診療』編集方針 フリーアクセス
ページ範囲:P.762 - P.762
1991年に創刊した弊誌は、2015年に『JIM』より『総合診療』に誌名を変更いたしました。その後も高齢化はさらに進み、社会構造や価値観、さらなる科学技術の進歩など、日本の医療を取り巻く状況は刻々と変化し続けています。地域医療の真価が問われ、ジェネラルに診ることがいっそう求められる時代となり、ますます「総合診療」への期待が高まってきました。これまで以上に多岐にわたる知識・技術、そして思想・価値観の共有が必要とされています。そこで弊誌は、さらなる誌面の充実を図るべく、2017年にリニューアルをいたしました。本誌は、今後も下記の「編集方針」のもと、既存の価値にとらわれることなく、また診療現場からの要請に応え、読者ならびに執筆者のみなさまとともに、日本の総合診療の新たな未来を切り拓いていく所存です。
2018年1月 『総合診療』編集委員会
『総合診療』バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.874 - P.875
お得な年間購読のご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.875 - P.876
読者アンケート
ページ範囲:P.876 - P.876
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.877 - P.878
基本情報
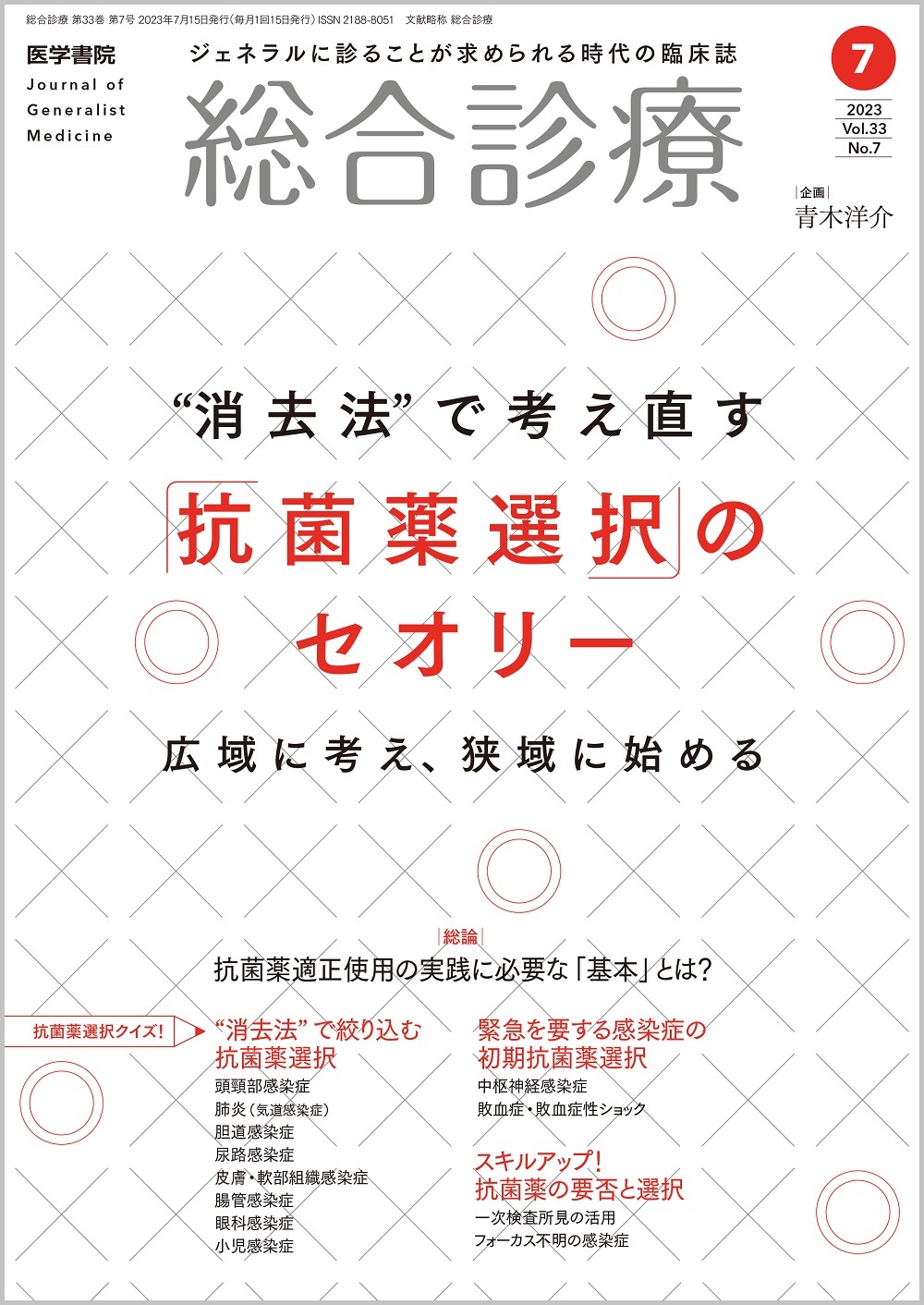
バックナンバー
34巻12号(2024年12月発行)
特集 妊婦・褥婦が外来に来たらUpdate—症状対応からワクチン・プラネタリーヘルスまで
34巻11号(2024年11月発行)
特集 電子カルテとベッドサイドの壁を打ち破る!—患者情報の「言語化」への挑戦
34巻10号(2024年10月発行)
特集 化かしが得意なカメレオンな疾患を捕まえろ!—よくある騙され方のゲシュタルト
34巻9号(2024年9月発行)
特集 今伝えたいクリニカル・パール—つくり方、使い方、活かし方
34巻8号(2024年8月発行)
特集 ストーン・ウォーズ 果てしなき“石”と医師との闘い
34巻7号(2024年7月発行)
特集 どうする!? 健診異常—これってホントに異常なの? どう説明する?
34巻6号(2024年6月発行)
特集 医師のウェルビーイング
34巻5号(2024年5月発行)
特集 —優柔不断にサヨウナラ!—あなたの「臨床判断」を高めるケーススタディ11選
34巻4号(2024年4月発行)
特集 困ったときの漢方—この症状に役立ちます!
34巻3号(2024年3月発行)
特集 —え、ウソ!実は◯◯だった!?—“コモンディジーズ”の診断ピットフォール
34巻2号(2024年2月発行)
特集 日常診療で出合う筋骨格疾患—脳神経内科と整形外科からのアプローチ
34巻1号(2024年1月発行)
特集 —“体験型”臨床クイズで習得する!—フィジカル診断エクセレンス
33巻12号(2023年12月発行)
特集 海の外へ渡る航行者を診る—アウトバウンドにまつわるetc.
33巻11号(2023年11月発行)
特集 —続・総合診療外来に“実装”したい—最新エビデンスMy Best 3
33巻10号(2023年10月発行)
特集 ○×クイズ110問!日常診療アップグレード—Choosing WiselyとHigh Value Careを学ぼう
33巻9号(2023年9月発行)
特集 ジェネラリストのための「発達障害(神経発達症)」入門
33巻8号(2023年8月発行)
特集 都市のプライマリ・ケア—「見えにくい」を「見えやすく」
33巻7号(2023年7月発行)
特集 “消去法”で考え直す「抗菌薬選択」のセオリー—広域に考え、狭域に始める
33巻6号(2023年6月発行)
特集 知っておくべき!モノクロな薬たち(注:モノクローナル抗体の話ですよ〜)
33巻5号(2023年5月発行)
特集 —疾患別“イルネススクリプト”で学ぶ—「腹痛診療」を磨き上げる22症例
33巻4号(2023年4月発行)
特集 救急対応ドリル—外来から在宅までの60問!
33巻3号(2023年3月発行)
特集 —自信がもてるようになる!—エビデンスに基づく「糖尿病診療」大全—新薬からトピックスまで
33巻2号(2023年2月発行)
特集 しびれQ&A—ビビッとシビれるクリニカルパール付き!
33巻1号(2023年1月発行)
特集 COVID-19パンデミック 振り返りと将来への備え
32巻12号(2022年12月発行)
特集 レクチャーの達人—とっておきの生ライブ付き!
32巻11号(2022年11月発行)
特集 不定愁訴にしない“MUS”診療—病態からマネジメントまで
32巻10号(2022年10月発行)
特集 日常診療に潜む「処方カスケード」—その症状、薬のせいではないですか?
32巻9号(2022年9月発行)
特集 総合診療・地域医療スキルアップドリル—こっそり学べる“特講ビデオ”つき!
32巻8号(2022年8月発行)
特集 こんなところも!“ちょいあて”エコー—POCUSお役立ちTips!
32巻7号(2022年7月発行)
特集 —どうせやせない!? やせなきゃいけない??苦手克服!—「肥満」との向き合い方講座
32巻6号(2022年6月発行)
特集 総合診療外来に“実装”したい最新エビデンス—My Best 3
32巻5号(2022年5月発行)
特集 「診断エラー」を科学する!—セッティング別 陥りやすい疾患・状況
32巻4号(2022年4月発行)
特集 えっ、これも!? 知っておきたい! 意外なアレルギー疾患
32巻3号(2022年3月発行)
特集 AI時代の医師のクリニカル・スキル—君は生き延びることができるか?
32巻2号(2022年2月発行)
特集 —withコロナ—かぜ診療の心得アップデート
32巻1号(2022年1月発行)
特集 実地医家が楽しく学ぶ 「熱」「炎症」、そして「免疫」—街場の免疫学・炎症学
31巻12号(2021年12月発行)
特集 “血が出た!”ときのリアル・アプローチ—そんな判断しちゃダメよ!
31巻11号(2021年11月発行)
特集 Q&Aで深める「むくみ診断」—正攻法も!一発診断も!外来も!病棟も!
31巻10号(2021年10月発行)
特集 医師の働き方改革—システムとマインドセットを変えよう!
31巻9号(2021年9月発行)
特集 「検査」のニューノーマル2021—この検査はもう古い? あの新検査はやるべき?
31巻8号(2021年8月発行)
特集 メンタルヘルス時代の総合診療外来—精神科医にぶっちゃけ相談してみました。
31巻7号(2021年7月発行)
特集 新時代の「在宅医療」—先進的プラクティスと最新テクノロジー
31巻6号(2021年6月発行)
特集 この診断で決まり!High Yieldな症候たち—見逃すな!キラリと光るその病歴&所見
31巻5号(2021年5月発行)
特集 臨床医のための 進化するアウトプット—学術論文からオンライン勉強会、SNSまで
31巻4号(2021年4月発行)
特集 消化器診療“虎の巻”—あなたの切実なギモンにズバリ答えます!
31巻3号(2021年3月発行)
特集 ライフステージでみる女性診療at a glance!—よくあるプロブレムを網羅しピンポイントで答えます。
31巻2号(2021年2月発行)
特集 肺炎診療のピットフォール—COVID-19から肺炎ミミックまで
31巻1号(2021年1月発行)
特別増大特集 新型コロナウイルス・パンデミック—今こそ知っておきたいこと、そして考えるべき未来
30巻12号(2020年12月発行)
特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き) Part 2
30巻11号(2020年11月発行)
特集 診断に役立つ! 教育で使える! フィジカル・エポニム!—身体所見に名を残すレジェンドたちの技と思考
30巻10号(2020年10月発行)
特集 —ポリファーマシーを回避する—エビデンスに基づく非薬物療法のススメ
30巻9号(2020年9月発行)
特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【感染症・内分泌・整形外科 編】
30巻8号(2020年8月発行)
特集 マイナーエマージェンシー門外放出—知っておくと役立つ! テクニック集
30巻7号(2020年7月発行)
特集 その倦怠感、単なる「疲れ」じゃないですよ!—筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群とミミック
30巻6号(2020年6月発行)
特集 下降期慢性疾患患者の“具合”をよくする—ジェネラリストだからできること!
30巻5号(2020年5月発行)
特集 誌上Journal Club—私を変えた激アツ論文
30巻4号(2020年4月発行)
特集 大便強ドリル—便秘・下痢・腹痛・消化器疾患に強くなる41問!
30巻3号(2020年3月発行)
特集 これではアカンで!こどもの診療—ハマりがちな11のピットフォール
30巻2号(2020年2月発行)
特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【循環器・消化器・神経疾患編】
30巻1号(2020年1月発行)
特集 総合診療医の“若手ロールモデル”を紹介します!—私たちはどう生きるか
29巻12号(2019年12月発行)
特集 困っている“あなた”に届く 認知症診療
29巻11号(2019年11月発行)
特集 臨床写真図鑑 レアな疾患編—見逃したくない疾患のコモンな所見
29巻10号(2019年10月発行)
特集 教えて!医師のためのビジネス・スキル
29巻9号(2019年9月発行)
特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き)
29巻8号(2019年8月発行)
特集 —ノーモア見逃し—日常の検査と画像に潜むピットフォール
29巻7号(2019年7月発行)
特集 リウマチ・膠原病ミミック症例帖—“膠原病っぽくみえてしまう疾患たち”にだまされない!
29巻6号(2019年6月発行)
特集 皮膚科診療エクササイズ—1枚の写真から
29巻5号(2019年5月発行)
特集 一般外来で診断できたら「えっへん!」な疾患38
29巻4号(2019年4月発行)
特集 “ナゾ”の痛み診療ストラテジー|OPQRSTで読み解く
29巻3号(2019年3月発行)
特集 —あなたのギモンに答えます!—循環器診療のハードルを下げるQ&A31
29巻2号(2019年2月発行)
特集 意外な中毒、思わぬ依存、知っておきたい副作用—一般外来で!OTCも処方薬も!
29巻1号(2019年1月発行)
特集 教えて検索!—膨大な医学情報を吟味・整理するスキル
28巻12号(2018年12月発行)
特集 こんなときこそ漢方を!
28巻11号(2018年11月発行)
特集 日本一マジメな「おしっこドリル」—今これだけは押さえておきたい腎・泌尿器のモンダイ
28巻10号(2018年10月発行)
特集 クリニカル・パールPremium!—憧れのカリスマ医師はかく語りき
28巻9号(2018年9月発行)
特集 オンコ・ジェネラリスト—「がん」に強い総合診療医をめざして
28巻8号(2018年8月発行)
特集 80歳からの診療スタンダードUp to Date—Silver Standard
28巻7号(2018年7月発行)
特集 この薬だけは押さえておきたい! 総合診療医のためのSpecialist Drug 40
28巻6号(2018年6月発行)
特集 聴診・触診×エコーで診断推論!—Point-of-Care超音波(POCUS)の底力
28巻5号(2018年5月発行)
特集 “一発診断”トレーニング問題集—懸賞論文「GM Clinical Pictures」大賞発表!
28巻4号(2018年4月発行)
特集 感染症外来診療「賢医の選択」—検査・経口薬・ワクチンをどう使えばいいんですか?
28巻3号(2018年3月発行)
特集 糖尿病のリアル—現場の「困った!」にとことん答えます。
28巻2号(2018年2月発行)
特集 頭痛患者で頭が痛いんです!
28巻1号(2018年1月発行)
特集 シン・フィジカル改革宣言!—私の“神技”伝授します。
27巻12号(2017年12月発行)
特集 小児診療“苦手”克服!!—劇的Before & After
27巻11号(2017年11月発行)
特集 今そこにある、ファミリー・バイオレンス|Violence and Health
27巻10号(2017年10月発行)
特集 めまいがするんです!─特別付録Web動画付
27巻9号(2017年9月発行)
特集 うつより多い「不安」の診かた—患者も医師も安らぎたい
27巻8号(2017年8月発行)
特集 見逃しやすい内分泌疾患─このキーワード、この所見で診断する!
27巻7号(2017年7月発行)
特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 3 カリスマ編
27巻6号(2017年6月発行)
特集 「地域を診る医者」最強の養成法!
27巻5号(2017年5月発行)
特集 コミュニケーションを処方する—ユマニチュードもオープンダイアローグも入ってます!
27巻4号(2017年4月発行)
特集 病歴と診察で診断できない発熱!—その謎の賢い解き方を伝授します。
27巻3号(2017年3月発行)
特集 これがホントに必要な薬40—総合診療医の外来自家薬籠
27巻2号(2017年2月発行)
特集 The総合診療ベーシックス—白熱!「総合診療フェスin OKINAWA」ライブ・レクチャー! 一挙公開 フィジカル動画付!
27巻1号(2017年1月発行)
特集 総合診療の“夜明け”—キーマンが語り尽くした「来し方、行く末」
26巻12号(2016年12月発行)
特集 これでパッチリ! 眼の健康問題
26巻11号(2016年11月発行)
特集 続・しびれるんです!
26巻10号(2016年10月発行)
特集 内科診療を劇的に変える“まとめ”の達人
26巻9号(2016年9月発行)
特集 症状・症候別 エコーを使った診断推論─Point-of-Care超音波
26巻8号(2016年8月発行)
特集 The 初診外来
26巻7号(2016年7月発行)
特集 感染症ケアバンドル・チェックリスト
26巻6号(2016年6月発行)
特集 “賢い処方”と“ナゾ処方”
26巻5号(2016年5月発行)
特集 しびれるんです!─知っておくべきシビレル疾患
26巻4号(2016年4月発行)
特集 ケースとクイズで総ざらい! 街場の2型糖尿病治療
26巻3号(2016年3月発行)
特集 こんな時は漢方でしょう!
26巻2号(2016年2月発行)
特集 フィジカル改革宣言! ──診断からフォローアップまで
26巻1号(2016年1月発行)
特集 妊婦・褥婦が一般外来に来たら─エマージェンシー&コモンプロブレム
25巻12号(2015年12月発行)
特集 外来で「複数の疾患」をもつ患者を診る─マルチモビディティの時代のプライマリ・ケア
25巻11号(2015年11月発行)
特集 レアだけど重要な「痛み」の原因─システム1診断学
25巻10号(2015年10月発行)
特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 2
25巻9号(2015年9月発行)
特集 診断ピットフォール10選─こんな疾患,見逃していませんか?
25巻8号(2015年8月発行)
特集 健診データで困ったら─こんな検査結果を持ってこられたら
25巻7号(2015年7月発行)
特集 ここを知りたい!頭部外傷初期対応・慢性期ケア
25巻6号(2015年6月発行)
特集 高齢者救急の落とし穴─紹介する時,される時
25巻5号(2015年5月発行)
特集 咳を聴きとり,咳を止める
25巻4号(2015年4月発行)
特集 関節が痛いんです!─コモンからレアものまでの診断と治療
25巻3号(2015年3月発行)
特集 神経難病ケアのコペルニクス的転回
25巻2号(2015年2月発行)
特集 総合医のためのスポーツ医学ベーシックス
25巻1号(2015年1月発行)
特集 動悸・息切れ─ヤバい病気の見つけ方 そして見つからなかった時の対処法
