「都市のプライマリ・ケアは見えにくい」、ここが本特集のスタートです。
「都会に地域医療なんてあるの?」「医療資源が多いから、ちゃんと診なくても都市は何とかなっているんでしょ?」と、私は離島の1人診療所で働いている時そう思っていました。
しかし実際に都市に出て診療してみると、人口は集中し、multimorbidityの高齢者、経済的に困窮している人、海外にルーツを持つ人など、プライマリ・ケアが必要なのにそのケアが届きにくい人の数は都市部で増えており、プライマリ・ケアの果たすべき役割はたくさんあります。それにもかかわらず、都市のプライマリ・ケアはいったい何をしているのか、とにかく「見えにくい」のです。私はその見えにくさから、いったん都市を離れましたが、今また再び都市の診療に関わっています。続けられている理由は、その「見かた」をさまざまな人から教えてもらい、都市のプライマリ・ケアの面白さに気づいたからです。
「都市初心者」の筆者が、日本プライマリ・ケア連合学会大都市圏医療委員会(現在は地域包括ケア委員会に統合)のこれまでの積み重ねや、第13回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会(2022年)でのシンポジウム「『見えにくい』都市のプライマリ・ケアを『見えやすく』」を共に開催してくれたメンバーなど、多くの先達に教えてもらったこれまでの「都市の見かた」を元に、本特集でそれらを共有し、都市のプライマリ・ケアの役割と魅力についてさまざまな角度から語り尽くしてもらいました。
「都市に地域医療なんてない」と思っているあなた。「都市のプライマリ・ケアの面白さに半分気づいているけど、上手く言葉にできない」あなた。そして「都市でも地域に出ていろいろやりたい」というあなたも。本特集を手に持って、一緒に街へ出ましょう!
雑誌目次
総合診療33巻8号
2023年08月発行
雑誌目次
特集 都市のプライマリ・ケア—「見えにくい」を「見えやすく」
扉 フリーアクセス
著者: 金子惇
ページ範囲:P.890 - P.891
今月の「めざせ! 総合診療専門医!」問題
ページ範囲:P.967 - P.967
本問題集は、今月の特集のご執筆者に、執筆テーマに関連して「総合診療専門医なら知っておいてほしい!」「自分ならこんな試験問題をつくりたい!」という内容を自由に作成していただいたものです。力試し問題に、チャレンジしてみてください。
【セクション1】座談会
都市とは何か? 都市の健康問題とは何か?
著者: 藤沼康樹 , 南後由和 , 近藤尚己 , 金子惇
ページ範囲:P.892 - P.900
都市とは何か? 都市部の特徴である人口集中や高齢化、COVID-19、気候変動などの都市の健康問題とはいったい何か? 本座談会では「都市ってどういうものなのか、どういう視点で見ればよいかよくわからない」という“まちのお医者さん”を想定オーディエンスとして、本特集を企画された金子惇先生を司会に、総合診療医(家庭医)の藤沼康樹先生と、社会学や都市・建築に詳しい南後由和先生、そして健康の社会決定要因と健康格差の疫学研究を進めている近藤尚己先生がどのような視点で「都市」を見ているか、多角的にアツく語り合っていただきました。(編集室)
【セクション2】実践! 都市のプライマリ・ケア—4つの現場から @臨床
❶社会から周縁化された複雑なケースを診る—marginalized populationのケア
著者: 吉田絵理子
ページ範囲:P.901 - P.904
社会から周縁化された人々、たとえばホームレス状態の人、精神疾患を有する人、経済的に困難のある人、障害がある人、移民や難民、LGBTQ(lesbian,gay,bisexual,transgender,queer,questioning)などの人々は、さまざまな場面において社会から疎外され、健康格差にさらされたり、医療アクセスが制限されることがある。筆者の働く川崎協同病院(以下、当院)のある川崎市南部の地域は、生活保護受給率が5%を超え、また外国籍の人が4%を超えており、多様性が豊かであるのと同時に、経済的に厳しい状況に置かれている人が多い。社会から孤立して暮らしている人を診療する機会が多く、病院の救急外来への受診を契機に福祉・介護につながるケースもあり、医療機関は社会的なリソースの窓口としての役割があると感じている。
しかし、周縁化され複雑な背景を持つ患者に、適切な医療やサービスを提供することは時に容易ではない。水本らは、プライマリ・ケア医はSDHへの取り組みを期待されることに誇りを持つ一方で、サポートが不足している環境ではSDHに取り組むよう勧告されることを理不尽で煩わしいと感じていると報告している1)。
❷大都市の外国人診療—multicultureな中でのケア
著者: 弓野綾 , 沢田貴志
ページ範囲:P.905 - P.908
ある在日ベトナム人女性のCASE
神奈川県にある私たちの総合内科の外来を、ある日、言葉少なくうつむいている女性が受診した。健康保険証は持っていなかった。
片言の日本語から聞き取れたのは技能実習生として日本に来たベトナム人で、下腹部が痛いとのこと。体温は36.5℃。「下痢しているの?」「吐き気はないの?」と聞いても怪訝な顔。やむをえず腹部触診の後、超音波検査でざっと診てしまう。特定の圧痛点もなく、虫垂炎や憩室炎も否定的であった。痛みのあるところには水様便があることがわかり、卵巣囊腫もなさそう、と一安心したのもつかの間。おや? 子宮内に胎児が…。うーん、この大きさはすでに妊娠10週を超えているかも…。
❸ケアの分断とプライマリ・ケア
著者: 八百壮大
ページ範囲:P.909 - P.912
Case
患者:大川五郎さん(仮名)、80代、男性。
生活保護受給。
15年来の脳梗塞後遺症で左不全麻痺と症候性てんかんがあり、A大学病院神経内科に通院するほか、気管支喘息とCOPD(慢性閉塞性肺疾患)にてA大学病院呼吸器内科に通院、心房細動と高血圧症を背景とした慢性心不全でB診療所に通院、石綿肺症にてC病院呼吸器内科に通院、大腸がん術後の慢性疼痛と逆流性食道炎にてD病院消化器内科に通院、皮脂欠乏性湿疹と爪白癬にてD病院皮膚科に通院、前立腺肥大症にてE泌尿器科クリニックに通院しており、内服薬は21種類、外用薬は7種類が処方されていた。
主介護者の12歳年下の妻、洋子さん(仮名)はLewy小体型認知症でF精神病院に通院、頸動脈硬化症でG脳外科クリニックに通院、網膜剝離後と白内障・緑内障による視力低下がありD病院眼科に通院、喘息でB診療所に通院、脊柱管狭窄症でD病院整形外科に通院中であった。
同居で40代独身の長女、秀子さん(仮名)は、統合失調症でF精神病院に通院、気管支喘息でB診療所に通院しており、3人暮らしである。
五郎さんは杖を使用し、夫婦で外出は可能で、バスやタクシーで通院ができる。
❹事例で読み解く都市のプライマリ・ケア—住環境編(団地)
著者: 佐野康太
ページ範囲:P.913 - P.916
Case
よくある単身高齢女性の圧迫骨折
患者:仲野良子さん(仮名)。80代、女性。
現病歴:2型糖尿病で糖尿病クリニック、高血圧症で内科医院、変形性膝関節症と骨粗鬆症で整形外科医院に通院している。左眼は加齢黄斑変性で手動弁レベルだったが、最近になって右眼の網膜静脈閉塞症により下方視野欠損が生じ、大学病院眼科にも通院するようになった。
築50年近くになる団地で1人暮らしをしており、介護サービスを利用することなく近所の人々と仲良く暮らしていた。夫はすでに他界し、長女は遠方に在住。理容師の長男は隣県で開業しており、多忙のため月1回ほど顔を出す程度の付き合いとなっていた。
ある日、自宅で転倒し腰痛で動けなくなりA病院へ救急搬送されて、腰椎圧迫骨折の診断で入院となり、コルセットを作成しつつ2週間の床上安静となった。歩行練習を開始したものの転倒リスクが高いため、リハビリ継続を目的として当院へ転院した。
@研究
❺都市のプライマリ・ケア医のコンピテンシー
著者: 密山要用
ページ範囲:P.917 - P.920
なぜ都市のプライマリ・ケアが重要か?
近年、世界的に都市化(urbanization)が進み1)、都市人口が増加し、それに伴い都市部に特有のさまざまな健康問題が指摘されるようになりました2)。そのため都市に特徴的な健康問題を理解し、都市の人々の健康を向上させる役割が、都市部のプライマリ・ケア医に期待されています。
特に日本は、世界最大の人口規模である関東大都市圏(約3,700万人)を有し、他国に先駆けて高齢化と人口減少が起きているという特徴があります。高齢者のほうが医療の必要度が増す傾向にあるため、日本の都市においては高齢者数の爆発的増加と、それに伴って起こる種々の問題への対処が課題になると言えます。
❻都市のプライマリ・ケアに関する研究
著者: 金子惇
ページ範囲:P.921 - P.923
本稿では都市のプライマリ・ケアに関する研究について概説する。ここでは大きく3つのパートに分けて、この課題について論じることとする。1つ目は「都市とは何か?」である。本特集全体では特に「都市」というものを定義しておらず、個々の執筆者に委ねているが、研究として都市のプライマリ・ケアを扱う場合には何らかの定義や条件が必要となる。2つ目は「都市のプライマリ・ケアの特徴」である。国や地域によって「都市」で提供される医療はさまざまであるが、これまで挙げられてきた都市のプライマリ・ケアのある程度共通した特徴について述べる。最後は「都市のプライマリ・ケアに関する研究の実際」とする。大枠を提示したうえで、実際にどのような研究があるかを例示する。
@教育
❼都市での卒前教育の実践
著者: 安藤崇之
ページ範囲:P.924 - P.926
慶應におけるカリキュラム
慶應義塾大学医学部(以下、当大学)では、2013年から総合診療教育センターが設置され、2020年から総合診療科の臨床実習が必修化されました。また、臨床実習前にも段階的にプライマリ・ケアや総合診療に触れられるようなカリキュラムになっています(表1)。1年生で総合診療という学問を知り、高齢者や看取りに総合的に関わる必要性を学びます。基礎医学を学んだ後に3年生の早期体験型実習(early exposure program:EEP)Ⅱで地域に行って、基礎・臨床という「医師アタマ」をリセットする機会を提供しています。その後、臨床科目で細分化された医学のなかでの総合診療の位置づけを確認し、臨床実習でそのリアルを感じてもらい、興味がある学生にはさらに多様な地域を体験するカリキュラムを展開しています。
❽都市での卒後教育の実践と海外プログラムの紹介
著者: 八百壮大
ページ範囲:P.927 - P.931
大都市のプライマリ・ケア教育の必要性
国際的なトレンドとして、人口の集中する大都市は、少子高齢化、グローバル化、健康格差という大きな社会課題に直面しています。徒歩30分圏内に約6,000人の人口が密集する当診療地区にも、第二次世界大戦後の経済成長期に移住してきた人々、国立大学の学生や教職員、留学生などの外国籍の人々らをはじめとしたさまざまなpopulationが混在して生活しています。それぞれ高齢化した核家族や新たな1人暮らし世帯などの文脈により、世帯同居人数は緩やかに最小単位に向かっています(図1)。地域のつながりは疎であるように見えながらも、その歴史に触れ、共通の特性や目的を持った個々人が網の目のようにつながっている現象を発見する日々の臨床は面白く、これらは大都市の地域医療の醍醐味です。
医学部の卒前教育においては、2022年の「医学教育モデル・コア・カリキュラム」の改訂に伴い、病気が人々の生活に及ぼす影響、人の言動と生活史・社会関係、経済的側面や制度的側面をふまえた医療現場の実践など、行動医学や健康の社会的決定要因に関する内容がより重視されるようになりました。同様に卒後教育でも、初期研修医や総合診療専攻医、家庭医療専門研修生に対し、地域医療活動を通して多様な人々の健康について考える機会を提供する必要があります。
@地域ケア
❾都市での地域ケアの実践—経験則からの“3つのポイント”
著者: 密山要用
ページ範囲:P.932 - P.935
なぜ都市で地域ケアが重要なのか?
プライマリ・ケアの専門家として地域を診る地域志向性アプローチ(ここでは「地域ケア」と呼ぶ)は、都市においても重要な役割であり、専門性の1つである。近年の健康の社会的決定要因(social determinants of health : SDH)に関する知見の蓄積によって、私たちを取り巻く周辺環境や社会構造が健康に影響を与えることが明らかになってきた。特に都市においては都市環境を形成する要因が複雑であり、その把握はより困難である1)。
一方で、都市には多くの医療専門職がいるが、多くは身体そのものへのアプローチを専門としており、それゆえ専ら医療機関の中で働いている。しかしプライマリ・ケア医療者は地域志向性アプローチを専門の1つに持つため、病院から地域へと飛び出して、多職種・多業種とつながり、地域の課題に取り組む貴重な医療資源としての役割が期待される。
【セクション3】都市のプライマリ・ケアの役割—3つの視点から @ミクロ
❶医者と屋台と医師焼き芋—「東京都国分寺市」での“街に出る!”地域活動の実践
著者: 岩浪悟 , 平沼仁実
ページ範囲:P.936 - P.938
その1 医者が屋台を引こう!(岩浪 悟)
◦「診療室の中」でのモヤモヤ
本稿は、東京の都市部で「家庭医療/総合診療」の後期研修をしている医師7年目の専攻医の事例である。
3次医療機関で各診療所からの紹介外来、地域の診療所で各科に振られないマルチプロブレムの患者さんを診る中で、「なぜこんなに複雑に絡まってから受診することになるのだろう?」と、日々モヤモヤすることが多かった。まさにSDH(social determinants of health)の下流を実感するような感覚で、実際こうした経験をしている医師は多くおられることと思う。
❷銭湯という社会的居場所—日常の動線上にケアを接続すること
著者: 平松佑介
ページ範囲:P.939 - P.942
小杉湯は、1933(昭和8)年創業、東京の高円寺で90年続く銭湯です。2021年には登録有形文化財に指定され、50年、100年先も変わらずに小杉湯を続けていくことを目的に、日々営業しています。
❸食材の量り売りのお店を協同労働で立ち上げました!—“人間らしい暮らし”を求めて
著者: 岡田光
ページ範囲:P.943 - P.945
近年の気候危機・環境問題への意識の高まりや、大量消費社会への反省から、必要なものを必要な分だけ購入する“量り売り”という小売スタイルに再び注目が集まっている。また、そうした事業が小規模ながらも地域市民の手によって立ち上げられる“協同労働”という新たな働き方も、地域における自助と公助の限界の打開策として着目されている。
本稿では、筆者が立ち上げ人の1人として参加している食材の量り売りのお店である「量り売りとまちの台所 野の」の取り組み事例をもとに、健康的な都市への転換に向けて、“量り売り”という販売形態や、“協同労働”という働き方がいかなる可能性を持ちうるかについて探ってみたい。
❹大学生が取り組む農業×地域づくり—Agridge Projectの目指す地域モデル
著者: 清水翼
ページ範囲:P.946 - P.948
Agridge Project発足の経緯について
筆者が通う横浜国立大学には、主専攻以外の分野を系統的に学習する副専攻プログラムがある。それはグローバルな視野を持って地域課題を解決する、先端的かつ複合的な実践能力を身につける内容となっている。Agridge Project(アグリッジプロジェクト;以下、アグリッジ)はこのプログラムの中の「地域課題実習」という枠組みで活動している。
アグリッジは、2017年に横浜国立大学経済学部生によって発足したプロジェクトである。地域活性化を図るうえで活路を見出したのが「農業」だった。アグリッジは「農業による地域活性化」を理念として掲げ、教育・経済・経営・理工・都市科学部の5つの学部の学生が、それぞれの専門性を活かし、さまざまな切り口から農業にアプローチしている。
@メゾ
❺行政が都市のプライマリ・ケアに求めるもの
著者: 工藤恵子 , 新堀大吾
ページ範囲:P.949 - P.951
横浜市寿地区に見るプライマリ・ケアの必要性(工藤恵子)
まずは、「都市のプライマリ・ケアの役割」を考える1つの手がかりとして、横浜市寿地区での取り組みをご紹介します。
❻都市のプライマリ・ケアの連携—GPs at the Deep End 川崎/横浜
著者: 金子惇
ページ範囲:P.952 - P.954
本特集の他稿(p.901〜の吉田論文など)にも見られるように、都市のプライマリ・ケアの役割として、生活困窮の状況にある患者およびそのような方が多く住んでいる地域へのケアが挙げられる。しかし、そういった地域ではmultimorbidityを抱えた複雑性が高い患者が多く、医療者への負担が大きいため、医療者側のバーンアウトが起きやすい1,2)。また、他地域に比べて1人の患者を診察するのに時間がかかる場合も多く、医療機関の経営維持も課題となる1)。
本稿では、そのような状況に立ち向かうために、英国で始まった「GPs at the Deep End」(以下、Deep End)というプロジェクトと、その日本での広がりについて紹介する。
@マクロ
❼気候変動とプライマリ・ケア
著者: 佐野康太
ページ範囲:P.955 - P.959
プライマリ・ケアにおける気候変動の緊急性、重大性
気候変動は、21世紀における唯一最大のグローバルな健康脅威であると言われています1)。気候変動は、図12)のような疾患リスクを高めると言われています。これに対して世界中の医学誌が、緊急の行動を起こす必要性を訴えています3)。
【エッセイ】
❶都市部と郡部のプライマリ・ケアの違いと教育への活用
著者: 中川貴史 , 勝俣元都
ページ範囲:P.960 - P.961
筆者らは指導医や専攻医として、200万都市である札幌市の無床診療所(栄町ファミリークリニック)と、人口約2,800人の寿都町の有床診療所(寿都町立寿都診療所)での診療を経験してきた。
本稿ではそこで感じた都市部と郡部のプライマリ・ケアの違いと、教育への活用について考察する。
❷都市の地域包括ケア—訪問看護を基盤に持つ相談支援の立場から—Compassionate citiesの再構築を夢見て
著者: 秋山正子
ページ範囲:P.962 - P.966
筆者は訪問看護が制度化される前の1991年から、医療法人春峰会 白十字診療所で在宅ケアに取り組んできた。主だった活動場所が都市部でのスタートだった。
1992年4月からは老人保健法の改正による老人訪問看護ステーション制度が開始され、先駆的に訪問看護に取り組んでいた当診療所は、その新たな事業として白十字訪問看護ステーションの申請をし、その年11月に認可を受け、12月から新たなスタートを切った。
Editorial
「都市のプライマリ・ケア」とは何なのか? フリーアクセス
著者: 金子惇
ページ範囲:P.880 - P.881
今月の特集は「都市のプライマリ・ケア」です。「“都市の”プライマリ・ケアとは何なんだ!」「プライマリ・ケアはプライマリ・ケアだろう、これ以上分断するな!」というお叱りの声もあるかと思います。筆者としても、いたずらに分断を増やしたいわけではありません。むしろ、これまで光が当たりにくかった「都市のプライマリ・ケア」の魅力を発信して、プライマリ・ケアの幅広さ、面白さをさらに感じていただければと思っています。
What's your diagnosis?[248]
在るべきものが無い
著者: 山下恵実 , 上田剛士
ページ範囲:P.884 - P.888
病歴
患者:60歳、男性
主訴:腹痛
現病歴:受診3日前から、臍周囲に持続性の鈍痛と嘔気が出現した。2日前に近医を受診し、ドンペリドン、イブプロフェンを処方されたが、受診当日まで腹痛が改善せず、徐々に増悪傾向のため救急要請した。
ROS陰性:嘔吐、下痢、黒色便、血便、発熱
既往歴:高血圧症、2型糖尿病、脂質異常症、Ménière病
内服歴:アムロジピン5 mg、シタグリプチン50 mg、ロスバスタチン2.5 mg、ファモチジン20 mg、トフィソパム50 mg、ベタヒスチン12 mg、レバミピド100 mg
アレルギー歴:なし
喫煙歴:20年前まで10本/日
飲酒歴:なし
【エッセイ】アスクレピオスの杖—想い出の診療録・40
“陽性感情”に向き合うその先に
著者: 鋪野紀好
ページ範囲:P.889 - P.889
本連載は、毎月替わる著者が、これまでの診療で心に残る患者さんとの出会いや、人生を変えた出来事を、エッセイにまとめてお届けします。
臨床教育お悩み相談室|どうする!?サロン・8
新入りでも教えていいんですか!?—Here comes a new challenger!
著者: 佐田竜一 , 木村武司 , 長野広之
ページ範囲:P.968 - P.972
今月のお悩み
卒後10年目の医師です。この春から勤務先が変わり、教育に力を入れていこうと思っています。ただ、病院ごとの文化や意識の違いがあるため、なかなか今までのやり方は通じず悩んでいます。新しい組織の文化に、どう溶け込んでいけばいいでしょうか? 自分なりに組織を変えていきたいとも思っているのですが、コツや注意点はありますか?
[ペンネーム:のんびりやっていきた医]
臨床医のためのライフハック│限りある時間を有効に使う仕事術・5
—事務作業—「診断書」「紹介状」などを効率的に作成するには?
著者: 中島啓
ページ範囲:P.973 - P.975
時間がない! 臨床医の仕事は診療だけにあらず、事務、教育、自己学習、研究、学会発表、情報発信、所属組織の運営などなど、尽きることはありません。もちろんプライベートの生活もあり、「時間不足」は臨床医の永遠の課題です。では、一度きりの“医師人生”の限られた時間を、どう有効に使うのか? 筆者が培ってきた「ライフハック(仕事術)」のすべてを、余すところなく開陳します。
ジェネラリストに必要な ご遺体の診断学・5
ご遺体への問診
著者: 森田沙斗武
ページ範囲:P.986 - P.989
Case
患者:72歳、男性。妻と2人暮らし。
既往歴:2型糖尿病、高血圧症、狭心症
病歴:1年前に、当院にて狭心症に対するカテーテル治療を施行後、フォロー目的で3カ月に1回ほど通院していた。また自宅近くのかかりつけ医に、2型糖尿病と高血圧症で定期受診されていた。比較的アドヒアランスはよく、血圧140/90 mmHg程度、HbA1c 6.8%程度を推移していた。
某日の朝、別室で眠っていた妻は7時頃に起床。夫が8時になっても起きてこないことを不審に思い寝室を見にいくと、ベッド脇にうつ伏せで倒れていた。8時10分に救急および警察覚知、19分には救急隊が現場に到着したが心肺停止状態。救急救命処置を行いながら搬送し、8時42分に当院到着。救急救命処置を継続するも、蘇生しなかった。午前9時32分、当院にて死亡確認された。
10時30分、警察に異状死の届出を行ったが、すでに警察による現場検証が完了し、事件性はないと判断したとのこと。そのため、「可能なら、かかりつけ医と相談して死体検案書を書いてほしい」と依頼された。担当した救急医は、「病院外で亡くなったのに、そんなもの書けるわけがない!」と立腹。当院から連絡を受けたかかりつけ医は「それなら仕方ありませんね」と言いながら、13時頃来院し「死因:虚血性心疾患」と記載した死亡診断書を作成した。病院主治医としては、一連の対応がこれでよかったのかどうか、釈然としなかった。
オール沖縄!カンファレンス|レジデントの対応と指導医の考えVer.2.0・79
発熱および左下腿発赤にて来院し、左膝腫脹を生じた高齢女性
著者: 宮城孝雅 , 仲里信彦 , 徳田安春
ページ範囲:P.991 - P.995
CASE
患者:85歳、女性。
主訴:発熱、左下腿発赤。
現病歴:ADL一部介助が必要な、施設入所中の高度認知症患者。10年前に右大腿骨頸部骨折で骨頭全置換術、左人工膝関節置換術(total knee replacement : TKR)後である。受診前日に発熱、左下腿の熱感および発赤を認め、かかりつけ医を受診した。蜂窩織炎疑いにて第3世代セフェム系抗菌薬を処方され、外来経過観察となった。しかし左下腿の発赤腫脹の悪化を認め、当院救急室を受診した。悪寒戦慄は明らかではなかった。最近の下肢の外傷歴はない。
既往歴:認知症、妄想性障害、肝硬変(Child-Pugh B)・食道静脈瘤あり、大腸憩室出血、右大腿骨頸部骨折および骨頭全置換術(10年前)、左TKR後(10年前)、腎盂腎炎、右下腿蜂窩織炎(2年前と8カ月前の2度発症し、2回とも血液培養からStreptococcus dysgalactiae subsp. equisimilisが検出)。
内服歴:カルベジロール(1.25 mg)1回1錠 1日1回朝、ランソプラゾール(15 mg)1回1錠 1日1回朝、ベタネコール(20 mg)1回1包 1日2回朝夕、酸化マグネシウム(500 mg)1回1錠 1日1回昼、センノシド(12 mg)1回2錠 1日1回夕、ラクツロースシロップ65% 1回20 mL 1日2回朝夕、抑肝散(2.5 g)1回1包 1日2回夕食前と寝る前。
生活歴:飲酒歴なし、喫煙歴なし。
Dr.上田剛士のエビデンス実践レクチャー!医学と日常の狭間で|患者さんからの素朴な質問にどう答える?・41
意外に知らない「くしゃみ」の秘密
著者: 上田剛士
ページ範囲:P.996 - P.999
患者さんからのふとした質問に答えられないことはないでしょうか? 素朴な疑問ほど回答が難しいものはありませんが、新たな気づきをもたらす良問も多いのではないでしょうか? 本連載では素朴な疑問に、文献的根拠を提示しながらお答えします!
患者さんには言えない!? 医者のコッソリ養生法・18
「やる気」と「集中力」を最大に引き出す生活とは!?❹
著者: 須田万勢
ページ範囲:P.1001 - P.1007
“プチ不健康”を放置してきたツケで弱っていた貝原先生。突然現れた医神アスクレピオス(自称ピオちゃん)に半ば強制的に弟子入りさせられ、養生で健康を取り戻す方法をしぶしぶ学ぶうち、身体も心も少しずつ変わってきた。「風邪」「肩こり」「肥満」「お酒」「睡眠」に続き、これまた苦手な「集中力」をアップする方法を伝授されることに…。「集中とはどんな状態か(2月号)」「4つの“集中モード”とそれらの切り替え方法(4月号)」に続き、前回(6月号)から「具体的な集中方法」を学ぶ!
#総合診療
#今月の特集関連本❶ フリーアクセス
ページ範囲:P.881 - P.881
#今月の特集関連本❷ フリーアクセス
ページ範囲:P.904 - P.904
#今月の特集関連本❸ フリーアクセス
ページ範囲:P.916 - P.916
#今月の特集関連本❹ フリーアクセス
ページ範囲:P.926 - P.926
#今月の特集関連本❺ フリーアクセス
ページ範囲:P.931 - P.931
#今月の特集関連本❻ フリーアクセス
ページ範囲:P.966 - P.966
#今月の特集関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.976 - P.978
#医学書院の新刊 フリーアクセス
ページ範囲:P.979 - P.980
#参加者募集 フリーアクセス
ページ範囲:P.980 - P.980
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.882 - P.883
『総合診療』編集方針 フリーアクセス
ページ範囲:P.879 - P.879
1991年に創刊した弊誌は、2015年に『JIM』より『総合診療』に誌名を変更いたしました。その後も高齢化はさらに進み、社会構造や価値観、さらなる科学技術の進歩など、日本の医療を取り巻く状況は刻々と変化し続けています。地域医療の真価が問われ、ジェネラルに診ることがいっそう求められる時代となり、ますます「総合診療」への期待が高まってきました。これまで以上に多岐にわたる知識・技術、そして思想・価値観の共有が必要とされています。そこで弊誌は、さらなる誌面の充実を図るべく、2017年にリニューアルをいたしました。本誌は、今後も下記の「編集方針」のもと、既存の価値にとらわれることなく、また診療現場からの要請に応え、読者ならびに執筆者のみなさまとともに、日本の総合診療の新たな未来を切り拓いていく所存です。
2018年1月 『総合診療』編集委員会
読者アンケート
ページ範囲:P.1009 - P.1009
『総合診療』バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.1010 - P.1011
お得な年間購読のご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.1011 - P.1011
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.1013 - P.1014
基本情報
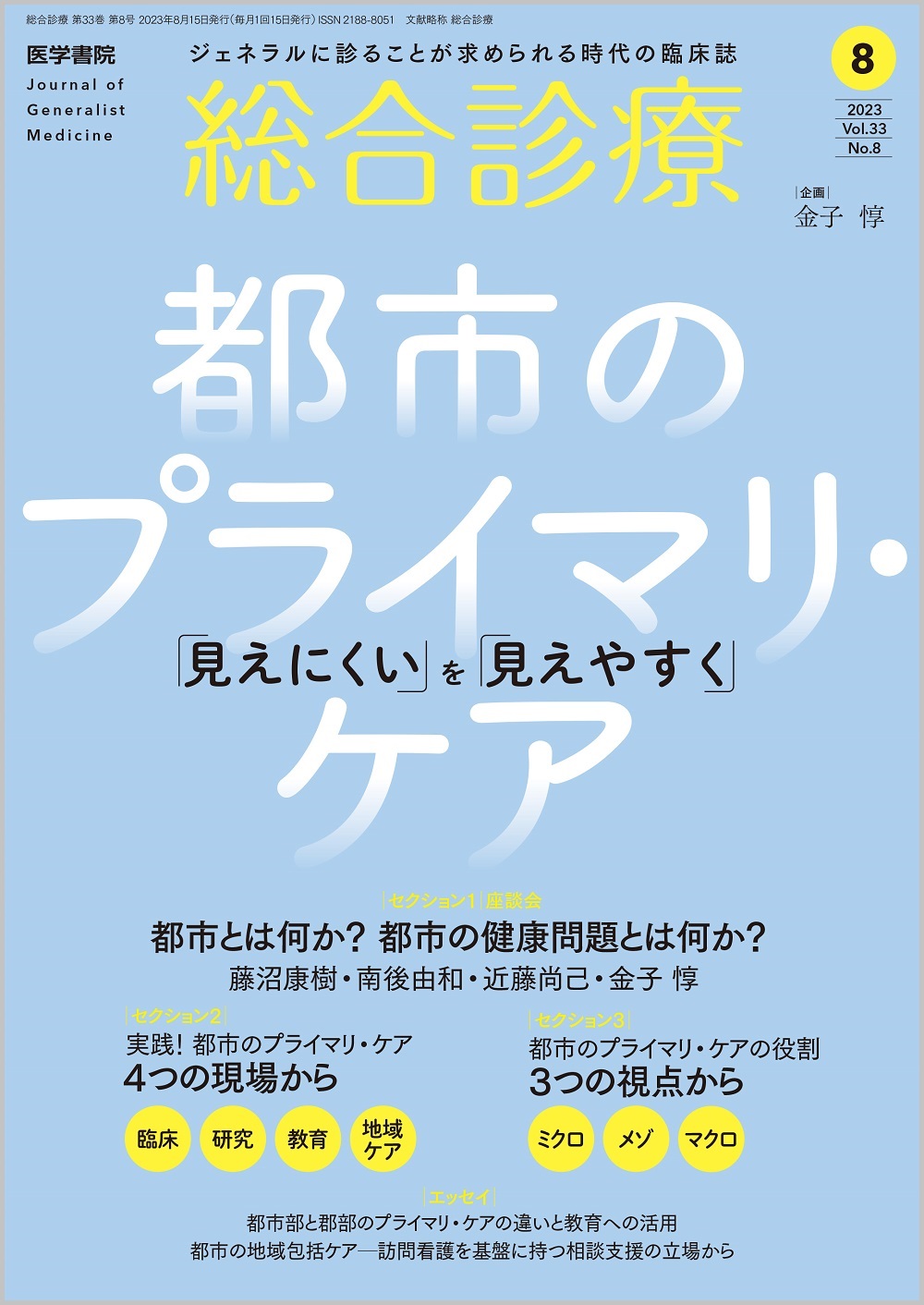
バックナンバー
34巻12号(2024年12月発行)
特集 妊婦・褥婦が外来に来たらUpdate—症状対応からワクチン・プラネタリーヘルスまで
34巻11号(2024年11月発行)
特集 電子カルテとベッドサイドの壁を打ち破る!—患者情報の「言語化」への挑戦
34巻10号(2024年10月発行)
特集 化かしが得意なカメレオンな疾患を捕まえろ!—よくある騙され方のゲシュタルト
34巻9号(2024年9月発行)
特集 今伝えたいクリニカル・パール—つくり方、使い方、活かし方
34巻8号(2024年8月発行)
特集 ストーン・ウォーズ 果てしなき“石”と医師との闘い
34巻7号(2024年7月発行)
特集 どうする!? 健診異常—これってホントに異常なの? どう説明する?
34巻6号(2024年6月発行)
特集 医師のウェルビーイング
34巻5号(2024年5月発行)
特集 —優柔不断にサヨウナラ!—あなたの「臨床判断」を高めるケーススタディ11選
34巻4号(2024年4月発行)
特集 困ったときの漢方—この症状に役立ちます!
34巻3号(2024年3月発行)
特集 —え、ウソ!実は◯◯だった!?—“コモンディジーズ”の診断ピットフォール
34巻2号(2024年2月発行)
特集 日常診療で出合う筋骨格疾患—脳神経内科と整形外科からのアプローチ
34巻1号(2024年1月発行)
特集 —“体験型”臨床クイズで習得する!—フィジカル診断エクセレンス
33巻12号(2023年12月発行)
特集 海の外へ渡る航行者を診る—アウトバウンドにまつわるetc.
33巻11号(2023年11月発行)
特集 —続・総合診療外来に“実装”したい—最新エビデンスMy Best 3
33巻10号(2023年10月発行)
特集 ○×クイズ110問!日常診療アップグレード—Choosing WiselyとHigh Value Careを学ぼう
33巻9号(2023年9月発行)
特集 ジェネラリストのための「発達障害(神経発達症)」入門
33巻8号(2023年8月発行)
特集 都市のプライマリ・ケア—「見えにくい」を「見えやすく」
33巻7号(2023年7月発行)
特集 “消去法”で考え直す「抗菌薬選択」のセオリー—広域に考え、狭域に始める
33巻6号(2023年6月発行)
特集 知っておくべき!モノクロな薬たち(注:モノクローナル抗体の話ですよ〜)
33巻5号(2023年5月発行)
特集 —疾患別“イルネススクリプト”で学ぶ—「腹痛診療」を磨き上げる22症例
33巻4号(2023年4月発行)
特集 救急対応ドリル—外来から在宅までの60問!
33巻3号(2023年3月発行)
特集 —自信がもてるようになる!—エビデンスに基づく「糖尿病診療」大全—新薬からトピックスまで
33巻2号(2023年2月発行)
特集 しびれQ&A—ビビッとシビれるクリニカルパール付き!
33巻1号(2023年1月発行)
特集 COVID-19パンデミック 振り返りと将来への備え
32巻12号(2022年12月発行)
特集 レクチャーの達人—とっておきの生ライブ付き!
32巻11号(2022年11月発行)
特集 不定愁訴にしない“MUS”診療—病態からマネジメントまで
32巻10号(2022年10月発行)
特集 日常診療に潜む「処方カスケード」—その症状、薬のせいではないですか?
32巻9号(2022年9月発行)
特集 総合診療・地域医療スキルアップドリル—こっそり学べる“特講ビデオ”つき!
32巻8号(2022年8月発行)
特集 こんなところも!“ちょいあて”エコー—POCUSお役立ちTips!
32巻7号(2022年7月発行)
特集 —どうせやせない!? やせなきゃいけない??苦手克服!—「肥満」との向き合い方講座
32巻6号(2022年6月発行)
特集 総合診療外来に“実装”したい最新エビデンス—My Best 3
32巻5号(2022年5月発行)
特集 「診断エラー」を科学する!—セッティング別 陥りやすい疾患・状況
32巻4号(2022年4月発行)
特集 えっ、これも!? 知っておきたい! 意外なアレルギー疾患
32巻3号(2022年3月発行)
特集 AI時代の医師のクリニカル・スキル—君は生き延びることができるか?
32巻2号(2022年2月発行)
特集 —withコロナ—かぜ診療の心得アップデート
32巻1号(2022年1月発行)
特集 実地医家が楽しく学ぶ 「熱」「炎症」、そして「免疫」—街場の免疫学・炎症学
31巻12号(2021年12月発行)
特集 “血が出た!”ときのリアル・アプローチ—そんな判断しちゃダメよ!
31巻11号(2021年11月発行)
特集 Q&Aで深める「むくみ診断」—正攻法も!一発診断も!外来も!病棟も!
31巻10号(2021年10月発行)
特集 医師の働き方改革—システムとマインドセットを変えよう!
31巻9号(2021年9月発行)
特集 「検査」のニューノーマル2021—この検査はもう古い? あの新検査はやるべき?
31巻8号(2021年8月発行)
特集 メンタルヘルス時代の総合診療外来—精神科医にぶっちゃけ相談してみました。
31巻7号(2021年7月発行)
特集 新時代の「在宅医療」—先進的プラクティスと最新テクノロジー
31巻6号(2021年6月発行)
特集 この診断で決まり!High Yieldな症候たち—見逃すな!キラリと光るその病歴&所見
31巻5号(2021年5月発行)
特集 臨床医のための 進化するアウトプット—学術論文からオンライン勉強会、SNSまで
31巻4号(2021年4月発行)
特集 消化器診療“虎の巻”—あなたの切実なギモンにズバリ答えます!
31巻3号(2021年3月発行)
特集 ライフステージでみる女性診療at a glance!—よくあるプロブレムを網羅しピンポイントで答えます。
31巻2号(2021年2月発行)
特集 肺炎診療のピットフォール—COVID-19から肺炎ミミックまで
31巻1号(2021年1月発行)
特別増大特集 新型コロナウイルス・パンデミック—今こそ知っておきたいこと、そして考えるべき未来
30巻12号(2020年12月発行)
特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き) Part 2
30巻11号(2020年11月発行)
特集 診断に役立つ! 教育で使える! フィジカル・エポニム!—身体所見に名を残すレジェンドたちの技と思考
30巻10号(2020年10月発行)
特集 —ポリファーマシーを回避する—エビデンスに基づく非薬物療法のススメ
30巻9号(2020年9月発行)
特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【感染症・内分泌・整形外科 編】
30巻8号(2020年8月発行)
特集 マイナーエマージェンシー門外放出—知っておくと役立つ! テクニック集
30巻7号(2020年7月発行)
特集 その倦怠感、単なる「疲れ」じゃないですよ!—筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群とミミック
30巻6号(2020年6月発行)
特集 下降期慢性疾患患者の“具合”をよくする—ジェネラリストだからできること!
30巻5号(2020年5月発行)
特集 誌上Journal Club—私を変えた激アツ論文
30巻4号(2020年4月発行)
特集 大便強ドリル—便秘・下痢・腹痛・消化器疾患に強くなる41問!
30巻3号(2020年3月発行)
特集 これではアカンで!こどもの診療—ハマりがちな11のピットフォール
30巻2号(2020年2月発行)
特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【循環器・消化器・神経疾患編】
30巻1号(2020年1月発行)
特集 総合診療医の“若手ロールモデル”を紹介します!—私たちはどう生きるか
29巻12号(2019年12月発行)
特集 困っている“あなた”に届く 認知症診療
29巻11号(2019年11月発行)
特集 臨床写真図鑑 レアな疾患編—見逃したくない疾患のコモンな所見
29巻10号(2019年10月発行)
特集 教えて!医師のためのビジネス・スキル
29巻9号(2019年9月発行)
特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き)
29巻8号(2019年8月発行)
特集 —ノーモア見逃し—日常の検査と画像に潜むピットフォール
29巻7号(2019年7月発行)
特集 リウマチ・膠原病ミミック症例帖—“膠原病っぽくみえてしまう疾患たち”にだまされない!
29巻6号(2019年6月発行)
特集 皮膚科診療エクササイズ—1枚の写真から
29巻5号(2019年5月発行)
特集 一般外来で診断できたら「えっへん!」な疾患38
29巻4号(2019年4月発行)
特集 “ナゾ”の痛み診療ストラテジー|OPQRSTで読み解く
29巻3号(2019年3月発行)
特集 —あなたのギモンに答えます!—循環器診療のハードルを下げるQ&A31
29巻2号(2019年2月発行)
特集 意外な中毒、思わぬ依存、知っておきたい副作用—一般外来で!OTCも処方薬も!
29巻1号(2019年1月発行)
特集 教えて検索!—膨大な医学情報を吟味・整理するスキル
28巻12号(2018年12月発行)
特集 こんなときこそ漢方を!
28巻11号(2018年11月発行)
特集 日本一マジメな「おしっこドリル」—今これだけは押さえておきたい腎・泌尿器のモンダイ
28巻10号(2018年10月発行)
特集 クリニカル・パールPremium!—憧れのカリスマ医師はかく語りき
28巻9号(2018年9月発行)
特集 オンコ・ジェネラリスト—「がん」に強い総合診療医をめざして
28巻8号(2018年8月発行)
特集 80歳からの診療スタンダードUp to Date—Silver Standard
28巻7号(2018年7月発行)
特集 この薬だけは押さえておきたい! 総合診療医のためのSpecialist Drug 40
28巻6号(2018年6月発行)
特集 聴診・触診×エコーで診断推論!—Point-of-Care超音波(POCUS)の底力
28巻5号(2018年5月発行)
特集 “一発診断”トレーニング問題集—懸賞論文「GM Clinical Pictures」大賞発表!
28巻4号(2018年4月発行)
特集 感染症外来診療「賢医の選択」—検査・経口薬・ワクチンをどう使えばいいんですか?
28巻3号(2018年3月発行)
特集 糖尿病のリアル—現場の「困った!」にとことん答えます。
28巻2号(2018年2月発行)
特集 頭痛患者で頭が痛いんです!
28巻1号(2018年1月発行)
特集 シン・フィジカル改革宣言!—私の“神技”伝授します。
27巻12号(2017年12月発行)
特集 小児診療“苦手”克服!!—劇的Before & After
27巻11号(2017年11月発行)
特集 今そこにある、ファミリー・バイオレンス|Violence and Health
27巻10号(2017年10月発行)
特集 めまいがするんです!─特別付録Web動画付
27巻9号(2017年9月発行)
特集 うつより多い「不安」の診かた—患者も医師も安らぎたい
27巻8号(2017年8月発行)
特集 見逃しやすい内分泌疾患─このキーワード、この所見で診断する!
27巻7号(2017年7月発行)
特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 3 カリスマ編
27巻6号(2017年6月発行)
特集 「地域を診る医者」最強の養成法!
27巻5号(2017年5月発行)
特集 コミュニケーションを処方する—ユマニチュードもオープンダイアローグも入ってます!
27巻4号(2017年4月発行)
特集 病歴と診察で診断できない発熱!—その謎の賢い解き方を伝授します。
27巻3号(2017年3月発行)
特集 これがホントに必要な薬40—総合診療医の外来自家薬籠
27巻2号(2017年2月発行)
特集 The総合診療ベーシックス—白熱!「総合診療フェスin OKINAWA」ライブ・レクチャー! 一挙公開 フィジカル動画付!
27巻1号(2017年1月発行)
特集 総合診療の“夜明け”—キーマンが語り尽くした「来し方、行く末」
26巻12号(2016年12月発行)
特集 これでパッチリ! 眼の健康問題
26巻11号(2016年11月発行)
特集 続・しびれるんです!
26巻10号(2016年10月発行)
特集 内科診療を劇的に変える“まとめ”の達人
26巻9号(2016年9月発行)
特集 症状・症候別 エコーを使った診断推論─Point-of-Care超音波
26巻8号(2016年8月発行)
特集 The 初診外来
26巻7号(2016年7月発行)
特集 感染症ケアバンドル・チェックリスト
26巻6号(2016年6月発行)
特集 “賢い処方”と“ナゾ処方”
26巻5号(2016年5月発行)
特集 しびれるんです!─知っておくべきシビレル疾患
26巻4号(2016年4月発行)
特集 ケースとクイズで総ざらい! 街場の2型糖尿病治療
26巻3号(2016年3月発行)
特集 こんな時は漢方でしょう!
26巻2号(2016年2月発行)
特集 フィジカル改革宣言! ──診断からフォローアップまで
26巻1号(2016年1月発行)
特集 妊婦・褥婦が一般外来に来たら─エマージェンシー&コモンプロブレム
25巻12号(2015年12月発行)
特集 外来で「複数の疾患」をもつ患者を診る─マルチモビディティの時代のプライマリ・ケア
25巻11号(2015年11月発行)
特集 レアだけど重要な「痛み」の原因─システム1診断学
25巻10号(2015年10月発行)
特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 2
25巻9号(2015年9月発行)
特集 診断ピットフォール10選─こんな疾患,見逃していませんか?
25巻8号(2015年8月発行)
特集 健診データで困ったら─こんな検査結果を持ってこられたら
25巻7号(2015年7月発行)
特集 ここを知りたい!頭部外傷初期対応・慢性期ケア
25巻6号(2015年6月発行)
特集 高齢者救急の落とし穴─紹介する時,される時
25巻5号(2015年5月発行)
特集 咳を聴きとり,咳を止める
25巻4号(2015年4月発行)
特集 関節が痛いんです!─コモンからレアものまでの診断と治療
25巻3号(2015年3月発行)
特集 神経難病ケアのコペルニクス的転回
25巻2号(2015年2月発行)
特集 総合医のためのスポーツ医学ベーシックス
25巻1号(2015年1月発行)
特集 動悸・息切れ─ヤバい病気の見つけ方 そして見つからなかった時の対処法
