臨床推論領域において「ミミッカー」「○○ミミック」という用語がよく使われるようになってきたのは2000年代で、特に2010年以降に論文数が増えています。最近では国内の医学書・医学雑誌でも使用されており、認知度が高くなっています。一方、「ミミック」に対して「カメレオン」という用語もありますが、こちらはまだあまり認知されていない概念です。「ミミック」が“looks like one, but isn't.”という概念であるのに対して、「カメレオン」は“doesn't look like one, but is.” という概念になります(図1)。両者はそれぞれ「○○に化ける」「○○が化ける」という“臨床医が騙される”概念は共通ですが、どちらの疾患から見たかの“視点”が違うものになります(図2)。「カメレオン」は“一見その疾患らしく見えない非典型的症状”と言え、「ミミック」同様に教訓的なものであり、学術誌でも例えば『BMJ journals』の『Practical Neurology』では、2012年以降「(疾患名):mimics and chameleons」という論文を複数掲載しています。UpToDate®では疾患の解説において「differential diagnosis」の項が記載されていることもあり、これもその疾患がどの疾患と類似した臨床像を呈するかを知る材料になります。
どの疾患も何かしら他の疾患に“化ける”ことがありますが、本特集ではその中でもコモンかつ「いろいろな疾患に化ける」=「非典型的な臨床像が多い/さまざまな病態で潜んでいる」疾患を“カメレオンな疾患”として取り上げることにしました。難解なケースカンファレンスで頻繁に鑑別に挙がる疾患が呈するさまざまな症状から、コモンな疾患の非典型的症状まで、“カメレオンな疾患”に気づくためのポイント(こういった時にはこの疾患が隠れていることがある!)を読者の皆さんに知っていただければ幸いです。典型像だけでは捕まえきれない疾患の非典型像のゲシュタルト(全体像)を捉えましょう!
雑誌目次
総合診療34巻10号
2024年10月発行
雑誌目次
特集 化かしが得意なカメレオンな疾患を捕まえろ!—よくある騙され方のゲシュタルト
扉 フリーアクセス
著者: 佐藤直行
ページ範囲:P.1114 - P.1115
今月の「めざせ! 総合診療専門医!」問題
ページ範囲:P.1170 - P.1172
本問題集は、今月の特集のご執筆者に、執筆テーマに関連して「総合診療専門医なら知っておいてほしい!」「自分ならこんな試験問題をつくりたい!」という内容を自由に作成していただいたものです。力試し問題に、チャレンジしてみてください。
【化かしが得意なカメレオンな疾患たち】
❶成人急性ヒトパルボウイルスB19感染症
著者: 佐藤直行
ページ範囲:P.1116 - P.1119
Point
◦成人の急性感染症は、小児の伝染性紅斑とは臨床像が異なり、非典型例も多い。
◦SLEを疑ったらパルボウイルス感染症も疑おう。
◦流行期には接触歴がはっきりしないことがあるため、流行状況をチェックしよう。
◦ヒトパルボウイルスB19感染症では多様な自己抗体が陽性になることがある。
◦ヒトパルボウイルスB19感染症では腎炎や肝炎、肺炎、心筋炎などの臓器障害も起こしうる。
❷結核
著者: 山口裕崇
ページ範囲:P.1120 - P.1123
Point
◦結核患者の半分以上を70歳以上の高齢者が占める。
◦粟粒結核や肺外結核(結核性リンパ節炎、腸結核、結核性心外膜炎、脊椎カリエス、結核性ぶどう膜炎、結核性髄膜炎、性器結核、腎結核)が、不明熱の病像となりやすい。
◦粟粒結核が疑われ、喀痰や胃液から結核菌が検出されない場合は、肝生検や骨髄生検を行うことを検討する。特に肝生検では粟粒結核の80〜90%において肉芽腫の所見がみられる。
❸梅毒
著者: 岩田健太郎
ページ範囲:P.1124 - P.1127
Point
◦ほぼどんな皮疹でも、二期梅毒の可能性がある。
◦ほぼどのような症状であっても、梅毒の可能性がある。
◦事前確率が低い患者の梅毒反応陽性は、梅毒でないことが多い。
❹感染性心内膜炎
著者: 官澤洋平
ページ範囲:P.1128 - P.1130
Point
◦感染性心内膜炎(IE)のカメレオンケースをパターン化してストックする。
◦初療で鑑別疾患に挙がらず血液培養が採取されなければ診断の遅れをきたすため、血液培養を採取するというアクションをとれるかが、診断の鍵となる。
◦病態の上流が何なのか、追究する姿勢を忘れないようにする。
◦不適切な抗菌薬投与は診断を遅らせる可能性があることを肝に銘じる。
❺悪性リンパ腫
著者: 林寧 , 上原孝紀
ページ範囲:P.1131 - P.1135
Point
◦悪性リンパ腫(ML)の特徴は、塊(主にリンパ節)の形成と、B症状(発熱、盗汗、体重減少)。
◦リンパ節外の塊や、塊をつくらないMLもある。
◦化かされやすいのは、リンパ節外の他臓器に塊をつくった場合と、塊自体をつくらない場合。
◦不明熱、血球減少、高LDH血症に加えて、呼吸困難、神経脱落症状➡血管内リンパ腫を考慮する。
❻偽痛風
著者: 山本恭資 , 金城光代
ページ範囲:P.1137 - P.1141
Point
◦CPPD症は、偽痛風(急性CPP結晶関節炎)だけでなく、多彩な臨床像を呈する。
◦髄膜炎や化膿性椎体炎など感染症を十分に考えながら、経過が合わない時はCPPD症も考える。
◦関節リウマチやリウマチ性多発筋痛症を疑う時は、CPPD症の可能性も考慮する。
❼甲状腺機能低下症
著者: 又吉貴也 , 佐藤直行
ページ範囲:P.1142 - P.1145
Point
◦甲状腺機能低下症は、幅広い年齢層に幅広い症状が出現するため、さまざまな疾患に化ける。
◦スクリーニングを行う際は、まずは甲状腺刺激ホルモン(TSH)のみ測定しよう。
◦甲状腺機能低下症と関節リウマチは密接に関連しており、疾患活動性にも関わっている。
◦なかには見逃すと生命予後に関わる疾患が隠れていることもある。
❽脳梗塞
著者: 山本大介
ページ範囲:P.1146 - P.1150
Point
◦脳梗塞の典型的症候(片麻痺、構音障害、失語、
半盲)を理解する。
◦脳梗塞の非典型的症候(めまい感、意識障害、頭痛、てんかん発作、不随意運動、MRI偽陰性)を理解する。
◦脳梗塞診断を肯定するヒント:❶突発発症/急性経過であるor ❷血圧上昇があるor ❸血管障害リスクがあるor ❹心疾患の併存症がある。
◦MRI偽陰性の場合のアクション:時間的・部位的偽陰性を克服するための「2回目の拡散強調画像(DWI)による2方向撮像」を活用する。
❾急性大動脈解離
著者: 神野敦
ページ範囲:P.1151 - P.1154
Point
◦急性大動脈解離は一般的に病歴から疑い、画像検査で確定診断を行う。
◦急性大動脈解離は「突然」「裂けるような」「胸部・背部痛」の典型的症状から、失神、片麻痺、下肢の対麻痺、腹痛、四肢の疼痛、呼吸困難、発熱など、さまざまな主訴に化けてわれわれの目の前に現れる。
◦急性大動脈解離のカメレオン疾患も緊急性が高いものが多く含まれるため、現場でのマネジメントは困難を伴う。臨床医はさまざまなパターンを認識し、急性大動脈解離の診断力を向上させることが求められる。
❿アナフィラキシー
著者: 坂本壮
ページ範囲:P.1155 - P.1158
Point
◦急性発症の消化器症状は、アナフィラキシーも考えよう!
◦ショックを診たら、アナフィラキシーか否か、パッと判断しよう!
◦「遅発性アナフィラキシー」という病態を知ろう!
⓫尿路結石
著者: 鈴木智晴
ページ範囲:P.1160 - P.1162
Point
◦腎・尿管を支配する神経の範囲はT10〜L2で、迷走神経も含むため多彩な症状をきたす。
◦尿潜血が陰性ということが、尿路結石を除外するとは限らない。
◦肋骨脊柱角(CVA)叩打痛(costovertebral angle tenderness)が陰性ということが、尿路結石を診断・除外するとは限らない。
◦結石性腎盂腎炎・敗血症性ショックは、泌尿器科的な緊急対応を要するカメレオンである。
◦腎盂腎炎や急性胃腸炎は、診断の決め手が存在しない症候群であり、診断は慎重に行う。
⓬ビタミンB1欠乏症
著者: 冨山嘉月 , 本田優希
ページ範囲:P.1163 - P.1166
Point
◦ビタミンB1欠乏症は現代日本においても稀な疾患ではなく、明らかな欠乏リスクがなくても基礎疾患や生活習慣に起因した欠乏が起こりうる。
◦ビタミンB1欠乏症は心不全やWernicke脳症以外にも多彩な症状を呈する。原因不明の代謝性アシドーシスや消化器症状、神経症状を認める場合は、ビタミンB1欠乏症を鑑別に挙げて補充を検討する。
◦全血総ビタミンB1濃度測定は検査精度が低いことや、結果が出るまでに時間がかかるなどの問題点があるため、ビタミンB1欠乏症を疑った場合は結果を待たずに治療を開始する。
【コラム】
脊椎・脊髄病変からの胸痛や腹痛
著者: 石塚晃介
ページ範囲:P.1168 - P.1169
圧迫骨折や椎間板ヘルニアでは胸痛や腹痛をきたすこともあるが、その場合、急性冠症候群や胆石発作などの内臓疾患としばしば誤診される1)。原因不明の腹痛では前皮神経絞扼症候群(anterior ctaneous nerve entrapment syndrome:ACNES)が注目されているが、圧迫骨折や椎間板ヘルニアなどの脊椎病変が原因不明の腹痛の原因であることは、実はあまり知られていないかもしれない2)。また、頸椎・頸髄病変からの胸痛はcervical anginaとして知られている3)。
本コラムでは、これらの脊椎・脊髄病変からの胸痛や腹痛の特徴について、症例を提示しながら解説する。
Editorial
騙されないための経験知をインプットしよう! フリーアクセス
著者: 佐藤直行
ページ範囲:P.1113 - P.1113
医学の中で、私が“ゲシュタルト”という言葉に初めて出合ったのは、2013年に発刊された『診断のゲシュタルトとデギュスタシオン』1)(金芳堂)を手に取った時でした。当時、わりと厳しい病院の研修医だった私は、コモンな疾患ですら診断するのに難渋する日々を過ごしており、「医学の中に数多ある疾患をうまく診断できるようになる日など来るのだろうか…」と途方に暮れていました。忙しい臨床現場でも自分で経験できる疾患には限りがあり、その少ない経験だけではうまく疾患を見抜く眼はなかなか養われません。研修医であれば尚更で、未熟者だった私は、さまざまな非典型的な臨床像に簡単に騙されていました。「この症状からこの疾患を想起するのか…」と悔しい思いをしていた頃に出合ったその名著には、great physicianである高名な先生方の豊富な経験知が詰め込まれていました。great physicianがどのように疾患を見抜いているのか、経験を通してしか身に付けられないはずの「疾患の全体像(ゲシュタルト)を捉えるための見識」が散りばめられた内容に、私は強い衝撃を受けたものです。まさに「巨人の肩の上に乗る矮人*」の感覚でした。
とはいえその後も、臨床をやればやるほど、疾患の取りうる臨床像の幅の広さに驚かされると共に、未だに臨床の奥深さを実感し続ける日々です。以前よりも騙されにくくなったとは感じていますが、その要因の1つとして、疾患が騙してくる時の“化け方”にはゲシュタルトがあり、経験知としてのストックが増えてきたことが挙げられます。その“化け方”とは、最近で言うところの「カメレオン」にあたるのでした。診断学の領域で「ミミック」という言葉がよく使われるようになりましたが、「カメレオン」という概念は、ある疾患がとりうる臨床像の幅を認識することにも役立ちます。ミミックもカメレオンも、偉大な先人たちの叡智の結晶であり、騙されないための大切な教訓を含んでいますが、カメレオンのほうはまだあまり認知されていません。
ゲストライブ〜Improvisation〜・28 『「卓越したジェネラリスト診療」入門』出版記念座談会
医師人生は長い! じっくり登ろう「卓越」の山—「卓ジェネ」や「家庭医療」はハードルが高いか?
著者: 松村真司 , 藤沼康樹 , 志水太郎
ページ範囲:P.1097 - P.1108
本年6月、本誌編集委員である藤沼康樹氏が、初の単著『「卓越したジェネラリスト診療」入門—複雑困難な時代を生き抜く臨床医のメソッド』1)を上梓した。出版するや、またたく間に話題となり、『卓ジェネ』として親しまれ、すでに3刷を重ねている。今なぜ「卓越したジェネラリスト診療」(以下「卓ジェネ」)が注目されるのか? 日本の「家庭医療(学)」を牽引してきた藤沼氏と、それぞれのフィールドにおいて各々の方法で「卓ジェネ」への道を歩んできた松村真司氏・志水太郎氏が、複雑困難化あるいはマンネリ化する日々の診療に求められる「卓越性」をめぐり、本音で語り合った。(編集室)
※以下、本文中の参照頁数は、「本誌」と断ったもの以外、『「卓越したジェネラリスト診療」入門』のページ番号です。
撮影:安部俊太郎|構成:編集室
【エッセイ】アスクレピオスの杖—想い出の診療録・54
医師としての使命
著者: 斎田瑞恵
ページ範囲:P.1173 - P.1173
本連載は、毎月替わる著者が、これまでの診療で心に残る患者さんとの出会いや、人生を変えた出来事を、エッセイにまとめてお届けします。
What's your diagnosis?[262]
あんまんだけじゃない
著者: 河田薫 , 陣内牧子 , 小山弘
ページ範囲:P.1180 - P.1183
病歴
患者:40代、女性
主訴:腰痛
現病歴:当院受診の2カ月ほど前、特に誘因なく突然右腰部の疼痛が出現した。4日後、症状が改善しないため近医整形外科を受診し(図1)、坐骨神経痛と診断されて鎮痛薬を処方されたが、無効であった。
当院受診の20日前から症状が増悪し前医を受診した。CTで第2腰椎(L2)椎体右側に軟部陰影、MRIでL2右側に骨融解像があり、L2転移性骨腫瘍を疑われて当院整形外科に紹介された。整形外科より転移性腫瘍の疑いについて当科に紹介され、入院となった。
陰性症状:最近の体重変化、発熱、悪寒戦慄、盗汗、食欲不振、全身倦怠感、朝のこわばり、咳嗽、悪心・嘔吐、膀胱直腸障害、脱力
既往歴・家族歴:特記事項なし
薬剤歴:トラマドール・アセトアミノフェン、プレガバリン、ジクロフェナクナトリウム坐薬
飲酒:ビール350mL×3本(毎日)
喫煙:10本×30年(14歳〜)
職業:介護職
最終月経:3年前
オール沖縄!カンファレンス|レジデントの対応と指導医の考えVer.2.0・93
ただの酒飲みの誤嚥性肺炎じゃない?—うまくいかない時は立ち止まって考えよう!
著者: 大谷哲平 , 今村恵 , 徳田安春 , 仲里信彦 , 鈴木智晴 , 佐藤直行
ページ範囲:P.1185 - P.1189
CASE
患者:65歳、男性。
主訴:酩酊状態、頭部打撲。
現病歴:来院前日の夕方から飲酒しており、居酒屋の駐車場で転倒した。朝方まで、倒れたままでいたところを通行人が発見して救急要請され、当院に搬送となった。
患者背景:ADLは自立。子どもは4名で、数十年前に離婚し、それ以降独居。土木・配管工事に従事しており、収入は十分ある。500mL缶のビールを毎日5〜6本程度飲酒し、その習慣が30年程度あり、飲酒すると人格が変化してしまう。喫煙は10代より1日3箱程度。
既往歴:かかりつけの病院は特にない。橈骨遠位端骨折に対して観血的骨折整復術。
内服歴:常用薬やサプリメントの服用はない。
〈来院時身体所見〉
general appearance:sick。
バイタルサイン:体温36.7℃。血圧146/68 mmHg、脈拍数61回/分、呼吸数36回/分、SpO2 94%(酸素2 L/分)。
神経:GCS(Glasgow Coma Scale)E3V3M5。意思疎通は曖昧な状態。明らかな麻痺はなし。瞳孔は両側5mmで、対光反射は両側あり。
頭頸部:左前頭部に2cmの裂創あり。左後頭部に12cmの皮下出血。
気管変位なし、頸静脈怒張なし、皮下気腫なし、後頸部圧痛なし。
胸部:胸郭の動きの左右差なし。呼吸音の左右差もないが、深呼吸の従命困難で副雑音の評価困難。
腹部:平坦、軟、圧痛なし。
四肢:両側肘関節・膝関節に擦過創あり、四肢の変形はなし。
皮膚:黄疸なし。発赤・腫脹はなし。
〈検査結果〉
血液検査結果:表1。
画像所見:図1。
臨床教育お悩み相談室|どうする!?サロン・18
「クイズ・ちょうどえぇ」“距離感”とは何か? を考える
著者: 佐田竜一 , 木村武司 , 長野広之
ページ範囲:P.1190 - P.1195
今月のお悩み
「教育者と学習者の距離感について、どう考えますか?」
[ペンネーム:二丁拳銃(医師11年目)]
臨床医のためのライフハック│限りある時間を有効に使う仕事術・19
—会議—効率的に会議を行うには?
著者: 中島啓
ページ範囲:P.1196 - P.1199
時間がない! 臨床医の仕事は診療だけにあらず。事務、教育、自己学習、研究、学会発表、情報発信、所属組織の運営などなど、尽きることはありません。もちろんプライベートの生活もあり、「時間不足」は臨床医の永遠の課題です。では、一度きりの“医師人生”の限られた時間を、どう有効に使うのか? 筆者が培ってきた「ライフハック(仕事術)」のすべてを、余すところなく開陳します。
ジェネラリストに必要な ご遺体の診断学・19
腐敗したご遺体と孤独死
著者: 森田沙斗武
ページ範囲:P.1200 - P.1202
Case
患者:63歳、男性
既往歴:アルコール性肝障害
病歴:生活保護を受けながら独居生活をしている。半年ほど前に衰弱状態で倒れて救急搬送され、脱水と肝障害を指摘され入院を勧められたが、拒否し帰宅した病歴がある。近隣住民の話では、以前は泥酔した状態で歩いている姿を見かけたが、最近は姿を見かけなかったという。
某日、いつもは生活保護の支払日に家賃が振り込まれるが、それがないため、管理会社が訪問するも応答なし。そこで、督促状を自宅の郵便受けに入れた。その後、1週間経っても連絡がないため再度訪問したところ、郵便物がそのままの状態であったため、安否確認のために警察官立ち会いのもと合鍵で侵入したところ、布団上で高度腐敗したご遺体を発見した。念のため救急要請するも、腐敗のために搬送されなかった。鍵が施錠された状態であり金銭の動きに不審な点もなく、警察は事件性なしと判断し、警察医が検案することとなったが、本来の警察医は夏休み中で、当クリニックが担当することとなった。
ご遺体は全身緑褐色で全体に膨れ上がり、蛆虫が多数付着しており、異臭も強く正視に堪えない状態であった。正義感をもって診察を行ったが、硬直もなく死斑もわからず、死因に検討もつかなかった。現場の警察官に「心臓でしょうか?」と尋ねられ、「こんな状態で死因なんてわかるわけがない」と内心思ったが、何か死因をつけなくてはならないと思い直し、「そうですね、心臓かもしれませんね」と答えた。最終的に「虚血性心疾患」を死因とした死体検案書を発行したが、自分自身の対応がこれでよかったとは思えなかった。
#総合診療
#今月の特集関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.1136 - P.1136
#今月の特集関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.1159 - P.1159
#今月の特集関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.1167 - P.1167
#今月の連載関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.1099 - P.1099
#今月の連載関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.1109 - P.1109
#今月の連載関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.1199 - P.1199
#医学書院の新刊 フリーアクセス
ページ範囲:P.1174 - P.1176
#書評:「卓越したジェネラリスト診療」入門—複雑困難な時代を生き抜く臨床医のメソッド フリーアクセス
著者: 志水太郎
ページ範囲:P.1177 - P.1177
日本の多くの若手総合診療医に“oyabun”と慕われ,私自身も敬愛してやまない藤沼康樹先生(医療福祉生協連 家庭医療学開発センター長)の初の単著を拝読しました。読了後に浮かんだのは,米国の医師フランシス・ピーボディ(1881〜1927)の格言「患者ケアの秘訣は患者をケアすることにある」(JAMA 88(12):877-882, 1927)でした。「臨床医の重要な資質の1つは人間性への関心である」とするこの格言が,本書の箴言の数々と共鳴し,胸を撃ち抜かれたような衝撃を何度も感じました。それが,この本の通読1回目の感想でした。
本書の第Ⅰ章1節の最初のページに明記されているように,医療は「不確実性」が高いものです。現代の医学教育では,多くは説明可能でクリアカットな部分が好まれ,不確実な「灰色」な部分(グレーゾーン)は全体からすれば補集合の扱いに甘んじ,時に無視されてきたのではないかと思います。しかし,この不確実な領域への関心と探索がなければ,全体をつかむことはできないでしょう。コントロール可能な壁の中の世界にだけ生きていたのでは,エルディア人は自分たちの始祖のことを決して知り得なかったのではないでしょうか(『進撃の巨人』)。本書にはその不確実性をも可能な限り言語化して構造化する試みが随所にあり,本邦で現在これに比肩する類書は存在しないとみます。
#書評:ジェネラリストのための内科診断リファレンス 第2版 フリーアクセス
著者: 徳田安春
ページ範囲:P.1179 - P.1179
10年前にも本書の書評を書いた。その際の感想をまとめると、本書はシステム2的な分析的推論を行うための当時最強のツールであり、EBM実践のためのクイックなデータブックである、であった。臨床疫学の各論必携本と呼んでもよい。
あれから10年、われわれジェネラリストが待っていた第2版がついに出た。待ちこがれていた理由は、医学は日進月歩で変化し発展するからだ。新たな疾患概念や病歴、身体所見、そして診断検査のデータを供給する論文が無数に出版されている。第2版では3万もの論文のなかから、新しくかつ重要な情報を追加してくれている。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.1110 - P.1111
『総合診療』編集方針 フリーアクセス
ページ範囲:P.1203 - P.1203
1991年に創刊した弊誌は、2015年に『JIM』より『総合診療』に誌名を変更いたしました。その後も高齢化はさらに進み、社会構造や価値観、さらなる科学技術の進歩など、日本の医療を取り巻く状況は刻々と変化し続けています。地域医療の真価が問われ、ジェネラルに診ることがいっそう求められる時代となり、ますます「総合診療」への期待が高まってきました。これまで以上に多岐にわたる知識・技術、そして思想・価値観の共有が必要とされています。そこで弊誌は、さらなる誌面の充実を図るべく、2017年にリニューアルをいたしました。本誌は、今後も下記の「編集方針」のもと、既存の価値にとらわれることなく、また診療現場からの要請に応え、読者ならびに執筆者のみなさまとともに、日本の総合診療の新たな未来を切り拓いていく所存です。
2018年1月 『総合診療』編集委員会
読者アンケート
ページ範囲:P.1205 - P.1205
『総合診療』バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.1206 - P.1207
お得な年間購読のご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.1207 - P.1208
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.1209 - P.1210
基本情報
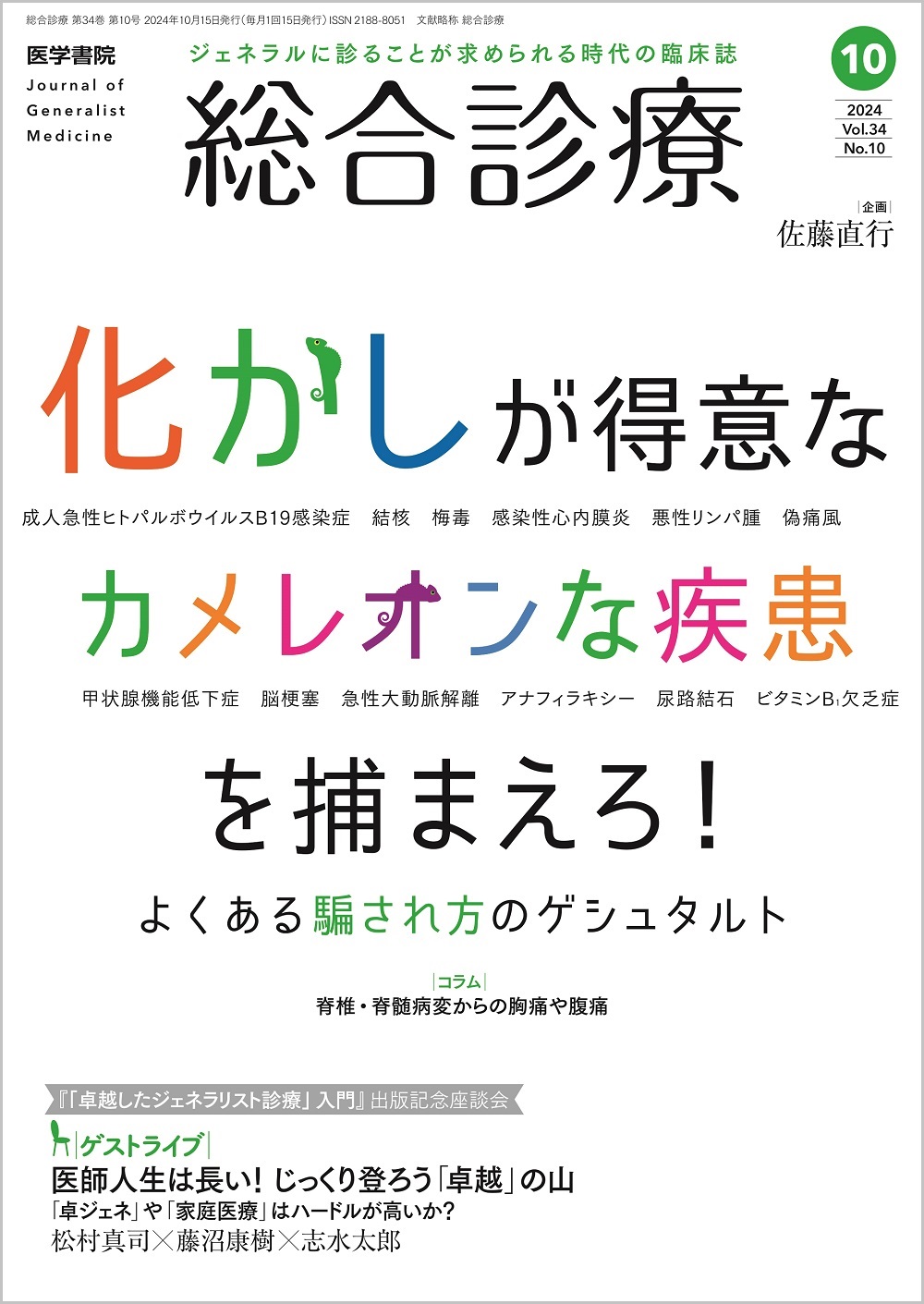
バックナンバー
34巻12号(2024年12月発行)
特集 妊婦・褥婦が外来に来たらUpdate—症状対応からワクチン・プラネタリーヘルスまで
34巻11号(2024年11月発行)
特集 電子カルテとベッドサイドの壁を打ち破る!—患者情報の「言語化」への挑戦
34巻10号(2024年10月発行)
特集 化かしが得意なカメレオンな疾患を捕まえろ!—よくある騙され方のゲシュタルト
34巻9号(2024年9月発行)
特集 今伝えたいクリニカル・パール—つくり方、使い方、活かし方
34巻8号(2024年8月発行)
特集 ストーン・ウォーズ 果てしなき“石”と医師との闘い
34巻7号(2024年7月発行)
特集 どうする!? 健診異常—これってホントに異常なの? どう説明する?
34巻6号(2024年6月発行)
特集 医師のウェルビーイング
34巻5号(2024年5月発行)
特集 —優柔不断にサヨウナラ!—あなたの「臨床判断」を高めるケーススタディ11選
34巻4号(2024年4月発行)
特集 困ったときの漢方—この症状に役立ちます!
34巻3号(2024年3月発行)
特集 —え、ウソ!実は◯◯だった!?—“コモンディジーズ”の診断ピットフォール
34巻2号(2024年2月発行)
特集 日常診療で出合う筋骨格疾患—脳神経内科と整形外科からのアプローチ
34巻1号(2024年1月発行)
特集 —“体験型”臨床クイズで習得する!—フィジカル診断エクセレンス
33巻12号(2023年12月発行)
特集 海の外へ渡る航行者を診る—アウトバウンドにまつわるetc.
33巻11号(2023年11月発行)
特集 —続・総合診療外来に“実装”したい—最新エビデンスMy Best 3
33巻10号(2023年10月発行)
特集 ○×クイズ110問!日常診療アップグレード—Choosing WiselyとHigh Value Careを学ぼう
33巻9号(2023年9月発行)
特集 ジェネラリストのための「発達障害(神経発達症)」入門
33巻8号(2023年8月発行)
特集 都市のプライマリ・ケア—「見えにくい」を「見えやすく」
33巻7号(2023年7月発行)
特集 “消去法”で考え直す「抗菌薬選択」のセオリー—広域に考え、狭域に始める
33巻6号(2023年6月発行)
特集 知っておくべき!モノクロな薬たち(注:モノクローナル抗体の話ですよ〜)
33巻5号(2023年5月発行)
特集 —疾患別“イルネススクリプト”で学ぶ—「腹痛診療」を磨き上げる22症例
33巻4号(2023年4月発行)
特集 救急対応ドリル—外来から在宅までの60問!
33巻3号(2023年3月発行)
特集 —自信がもてるようになる!—エビデンスに基づく「糖尿病診療」大全—新薬からトピックスまで
33巻2号(2023年2月発行)
特集 しびれQ&A—ビビッとシビれるクリニカルパール付き!
33巻1号(2023年1月発行)
特集 COVID-19パンデミック 振り返りと将来への備え
32巻12号(2022年12月発行)
特集 レクチャーの達人—とっておきの生ライブ付き!
32巻11号(2022年11月発行)
特集 不定愁訴にしない“MUS”診療—病態からマネジメントまで
32巻10号(2022年10月発行)
特集 日常診療に潜む「処方カスケード」—その症状、薬のせいではないですか?
32巻9号(2022年9月発行)
特集 総合診療・地域医療スキルアップドリル—こっそり学べる“特講ビデオ”つき!
32巻8号(2022年8月発行)
特集 こんなところも!“ちょいあて”エコー—POCUSお役立ちTips!
32巻7号(2022年7月発行)
特集 —どうせやせない!? やせなきゃいけない??苦手克服!—「肥満」との向き合い方講座
32巻6号(2022年6月発行)
特集 総合診療外来に“実装”したい最新エビデンス—My Best 3
32巻5号(2022年5月発行)
特集 「診断エラー」を科学する!—セッティング別 陥りやすい疾患・状況
32巻4号(2022年4月発行)
特集 えっ、これも!? 知っておきたい! 意外なアレルギー疾患
32巻3号(2022年3月発行)
特集 AI時代の医師のクリニカル・スキル—君は生き延びることができるか?
32巻2号(2022年2月発行)
特集 —withコロナ—かぜ診療の心得アップデート
32巻1号(2022年1月発行)
特集 実地医家が楽しく学ぶ 「熱」「炎症」、そして「免疫」—街場の免疫学・炎症学
31巻12号(2021年12月発行)
特集 “血が出た!”ときのリアル・アプローチ—そんな判断しちゃダメよ!
31巻11号(2021年11月発行)
特集 Q&Aで深める「むくみ診断」—正攻法も!一発診断も!外来も!病棟も!
31巻10号(2021年10月発行)
特集 医師の働き方改革—システムとマインドセットを変えよう!
31巻9号(2021年9月発行)
特集 「検査」のニューノーマル2021—この検査はもう古い? あの新検査はやるべき?
31巻8号(2021年8月発行)
特集 メンタルヘルス時代の総合診療外来—精神科医にぶっちゃけ相談してみました。
31巻7号(2021年7月発行)
特集 新時代の「在宅医療」—先進的プラクティスと最新テクノロジー
31巻6号(2021年6月発行)
特集 この診断で決まり!High Yieldな症候たち—見逃すな!キラリと光るその病歴&所見
31巻5号(2021年5月発行)
特集 臨床医のための 進化するアウトプット—学術論文からオンライン勉強会、SNSまで
31巻4号(2021年4月発行)
特集 消化器診療“虎の巻”—あなたの切実なギモンにズバリ答えます!
31巻3号(2021年3月発行)
特集 ライフステージでみる女性診療at a glance!—よくあるプロブレムを網羅しピンポイントで答えます。
31巻2号(2021年2月発行)
特集 肺炎診療のピットフォール—COVID-19から肺炎ミミックまで
31巻1号(2021年1月発行)
特別増大特集 新型コロナウイルス・パンデミック—今こそ知っておきたいこと、そして考えるべき未来
30巻12号(2020年12月発行)
特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き) Part 2
30巻11号(2020年11月発行)
特集 診断に役立つ! 教育で使える! フィジカル・エポニム!—身体所見に名を残すレジェンドたちの技と思考
30巻10号(2020年10月発行)
特集 —ポリファーマシーを回避する—エビデンスに基づく非薬物療法のススメ
30巻9号(2020年9月発行)
特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【感染症・内分泌・整形外科 編】
30巻8号(2020年8月発行)
特集 マイナーエマージェンシー門外放出—知っておくと役立つ! テクニック集
30巻7号(2020年7月発行)
特集 その倦怠感、単なる「疲れ」じゃないですよ!—筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群とミミック
30巻6号(2020年6月発行)
特集 下降期慢性疾患患者の“具合”をよくする—ジェネラリストだからできること!
30巻5号(2020年5月発行)
特集 誌上Journal Club—私を変えた激アツ論文
30巻4号(2020年4月発行)
特集 大便強ドリル—便秘・下痢・腹痛・消化器疾患に強くなる41問!
30巻3号(2020年3月発行)
特集 これではアカンで!こどもの診療—ハマりがちな11のピットフォール
30巻2号(2020年2月発行)
特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【循環器・消化器・神経疾患編】
30巻1号(2020年1月発行)
特集 総合診療医の“若手ロールモデル”を紹介します!—私たちはどう生きるか
29巻12号(2019年12月発行)
特集 困っている“あなた”に届く 認知症診療
29巻11号(2019年11月発行)
特集 臨床写真図鑑 レアな疾患編—見逃したくない疾患のコモンな所見
29巻10号(2019年10月発行)
特集 教えて!医師のためのビジネス・スキル
29巻9号(2019年9月発行)
特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き)
29巻8号(2019年8月発行)
特集 —ノーモア見逃し—日常の検査と画像に潜むピットフォール
29巻7号(2019年7月発行)
特集 リウマチ・膠原病ミミック症例帖—“膠原病っぽくみえてしまう疾患たち”にだまされない!
29巻6号(2019年6月発行)
特集 皮膚科診療エクササイズ—1枚の写真から
29巻5号(2019年5月発行)
特集 一般外来で診断できたら「えっへん!」な疾患38
29巻4号(2019年4月発行)
特集 “ナゾ”の痛み診療ストラテジー|OPQRSTで読み解く
29巻3号(2019年3月発行)
特集 —あなたのギモンに答えます!—循環器診療のハードルを下げるQ&A31
29巻2号(2019年2月発行)
特集 意外な中毒、思わぬ依存、知っておきたい副作用—一般外来で!OTCも処方薬も!
29巻1号(2019年1月発行)
特集 教えて検索!—膨大な医学情報を吟味・整理するスキル
28巻12号(2018年12月発行)
特集 こんなときこそ漢方を!
28巻11号(2018年11月発行)
特集 日本一マジメな「おしっこドリル」—今これだけは押さえておきたい腎・泌尿器のモンダイ
28巻10号(2018年10月発行)
特集 クリニカル・パールPremium!—憧れのカリスマ医師はかく語りき
28巻9号(2018年9月発行)
特集 オンコ・ジェネラリスト—「がん」に強い総合診療医をめざして
28巻8号(2018年8月発行)
特集 80歳からの診療スタンダードUp to Date—Silver Standard
28巻7号(2018年7月発行)
特集 この薬だけは押さえておきたい! 総合診療医のためのSpecialist Drug 40
28巻6号(2018年6月発行)
特集 聴診・触診×エコーで診断推論!—Point-of-Care超音波(POCUS)の底力
28巻5号(2018年5月発行)
特集 “一発診断”トレーニング問題集—懸賞論文「GM Clinical Pictures」大賞発表!
28巻4号(2018年4月発行)
特集 感染症外来診療「賢医の選択」—検査・経口薬・ワクチンをどう使えばいいんですか?
28巻3号(2018年3月発行)
特集 糖尿病のリアル—現場の「困った!」にとことん答えます。
28巻2号(2018年2月発行)
特集 頭痛患者で頭が痛いんです!
28巻1号(2018年1月発行)
特集 シン・フィジカル改革宣言!—私の“神技”伝授します。
27巻12号(2017年12月発行)
特集 小児診療“苦手”克服!!—劇的Before & After
27巻11号(2017年11月発行)
特集 今そこにある、ファミリー・バイオレンス|Violence and Health
27巻10号(2017年10月発行)
特集 めまいがするんです!─特別付録Web動画付
27巻9号(2017年9月発行)
特集 うつより多い「不安」の診かた—患者も医師も安らぎたい
27巻8号(2017年8月発行)
特集 見逃しやすい内分泌疾患─このキーワード、この所見で診断する!
27巻7号(2017年7月発行)
特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 3 カリスマ編
27巻6号(2017年6月発行)
特集 「地域を診る医者」最強の養成法!
27巻5号(2017年5月発行)
特集 コミュニケーションを処方する—ユマニチュードもオープンダイアローグも入ってます!
27巻4号(2017年4月発行)
特集 病歴と診察で診断できない発熱!—その謎の賢い解き方を伝授します。
27巻3号(2017年3月発行)
特集 これがホントに必要な薬40—総合診療医の外来自家薬籠
27巻2号(2017年2月発行)
特集 The総合診療ベーシックス—白熱!「総合診療フェスin OKINAWA」ライブ・レクチャー! 一挙公開 フィジカル動画付!
27巻1号(2017年1月発行)
特集 総合診療の“夜明け”—キーマンが語り尽くした「来し方、行く末」
26巻12号(2016年12月発行)
特集 これでパッチリ! 眼の健康問題
26巻11号(2016年11月発行)
特集 続・しびれるんです!
26巻10号(2016年10月発行)
特集 内科診療を劇的に変える“まとめ”の達人
26巻9号(2016年9月発行)
特集 症状・症候別 エコーを使った診断推論─Point-of-Care超音波
26巻8号(2016年8月発行)
特集 The 初診外来
26巻7号(2016年7月発行)
特集 感染症ケアバンドル・チェックリスト
26巻6号(2016年6月発行)
特集 “賢い処方”と“ナゾ処方”
26巻5号(2016年5月発行)
特集 しびれるんです!─知っておくべきシビレル疾患
26巻4号(2016年4月発行)
特集 ケースとクイズで総ざらい! 街場の2型糖尿病治療
26巻3号(2016年3月発行)
特集 こんな時は漢方でしょう!
26巻2号(2016年2月発行)
特集 フィジカル改革宣言! ──診断からフォローアップまで
26巻1号(2016年1月発行)
特集 妊婦・褥婦が一般外来に来たら─エマージェンシー&コモンプロブレム
25巻12号(2015年12月発行)
特集 外来で「複数の疾患」をもつ患者を診る─マルチモビディティの時代のプライマリ・ケア
25巻11号(2015年11月発行)
特集 レアだけど重要な「痛み」の原因─システム1診断学
25巻10号(2015年10月発行)
特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 2
25巻9号(2015年9月発行)
特集 診断ピットフォール10選─こんな疾患,見逃していませんか?
25巻8号(2015年8月発行)
特集 健診データで困ったら─こんな検査結果を持ってこられたら
25巻7号(2015年7月発行)
特集 ここを知りたい!頭部外傷初期対応・慢性期ケア
25巻6号(2015年6月発行)
特集 高齢者救急の落とし穴─紹介する時,される時
25巻5号(2015年5月発行)
特集 咳を聴きとり,咳を止める
25巻4号(2015年4月発行)
特集 関節が痛いんです!─コモンからレアものまでの診断と治療
25巻3号(2015年3月発行)
特集 神経難病ケアのコペルニクス的転回
25巻2号(2015年2月発行)
特集 総合医のためのスポーツ医学ベーシックス
25巻1号(2015年1月発行)
特集 動悸・息切れ─ヤバい病気の見つけ方 そして見つからなかった時の対処法
