前回の本誌特集「妊婦・褥婦が一般外来に来たら」が発刊されたのは2016年1月(松村真司先生企画)でした。それ以降、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミック、気候変動、戦争など、人々の生活、社会、環境に大きな変化がもたらされ、医療においても診療の在り方やケアの視点、臨床推論が見直されてきました。
そこで2024年12月発行の本特集では、この間に経験したCOVID-19や新型コロナワクチン、今注目されている健康の社会的決定要因(Social Determinants of Health:SDH)、プラネタリーヘルスをキーワードとして取り入れた内容を考えました。また、妊婦・褥婦のケアにおいて、プライマリ・ケア医として理解しておきたい病態・疾患についても、産婦人科医やその他の専門職と連携する際に必要となるミニマムエッセンスを組み入れて、「妊婦・褥婦が外来に来たら」現代版としてUpdateしました。
本特集が皆様のお役に立てば幸いです。
雑誌目次
総合診療34巻12号
2024年12月発行
雑誌目次
特集 妊婦・褥婦が外来に来たらUpdate—症状対応からワクチン・プラネタリーヘルスまで
扉 フリーアクセス
著者: 鳴本敬一郎
ページ範囲:P.1352 - P.1353
一目でわかる! 本特集の重要ポイント
著者: 鳴本敬一郎
ページ範囲:P.1354 - P.1355
❶プライマリ・ケア医が妊婦・褥婦をケアする意義
近年の急速な社会変化に伴い妊娠に関わる生物医学的・心理的・社会的リスクが増加し、プライマリ・ケア医は妊娠前から産後の様々なフェーズで新たなライフサイクルに移行する“家族”全体を診ると同時に、多様な健康ニーズを把握し適切に対応することが期待される。
今月の「めざせ! 総合診療専門医!」問題
ページ範囲:P.1431 - P.1431
本問題集は、今月の特集のご執筆者に、執筆テーマに関連して「総合診療専門医なら知っておいてほしい!」「自分ならこんな試験問題をつくりたい!」という内容を自由に作成していただいたものです。力試し問題に、チャレンジしてみてください。
【総論】
❶ プライマリ・ケア医が妊婦・褥婦をケアする意義
著者: 井上真智子
ページ範囲:P.1356 - P.1359
少子高齢社会における妊婦・褥婦診療
妊娠・出産に関する状況はこの数十年で大きく変化した。分娩件数は2023年には73万件となり、過去最低を更新した。1970年代頃に毎年200万人以上が生まれていたことからすると、約1/3である。一方で、出産年齢は上昇し、第1子の平均出産年齢は30歳を超え、「高齢出産」と言われる35歳以上の出産が全体の30%を占める。それに伴い、妊産婦が内科などの合併症をもつケースが3割以上と増加している。さらに、ハイリスク妊産婦の割合も増加し、社会的ハイリスク妊産婦は5〜20%と報告されている。「社会的ハイリスク妊娠」とは、定まった定義はないものの、平成30(2018)〜令和2(2020)年度厚生労働科学研究班(研究代表者 光田信明)では、「さまざまな要因により、今後の子育てが困難であろうと思われる妊娠」としており、児の虐待や妊産婦自殺を防ぐことを目的にリスクアセスメントを行っている。なお、児童福祉法の「特定妊婦」とは「出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦」と定義されており、要保護・要支援児童をより早期に発見して適切に支援するため、望まない妊娠や妊婦健診未受診などのケースは、要保護児童対策地域協議会などで情報共有が行われている。「社会的ハイリスク妊産婦」は、特定妊婦を包含し、フォローすべき妊産婦をより広く捉えた概念である。たとえば、若年(10代)、高齢、身体・精神疾患の既往、虐待・被虐待の既往、児の合併症、さらに妊娠出産の受け止め方や経済状況、家庭環境などの要因も含む。若年の在留外国人が増えていることから、外国人妊婦の出産は全体の約3.1%と増えているが、言語の問題や在留資格、経済状況、社会的孤立など医療アクセスに障壁がある場合、社会的ハイリスクとして認識する必要がある。
晩婚化、非婚化により出産を経験しない女性が27%(2020年、50歳時点)と増えている一方で、妊娠を望んで不妊治療を受ける人の数も増加傾向である。2022年度から不妊治療の一部が公的医療保険の対象となったことで、体外受精の治療件数は年間約54万件へと増加した。2022年に体外受精で生まれた子どもは7.7万人であり、全出生のうち10人に1人となる(日本産科婦人科学会調査、2024年8月30日公表)。「子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)」のデータを用いた研究では、生殖補助医療により生まれた子どもは自然妊娠と比べて神経発達の遅れが有意に多くみられたが、医療技術そのものに起因するとは言えず、主に親の年齢など不妊に関わる要因と多胎妊娠、およびそれによって生じる妊娠合併症(糖尿病・妊娠糖尿病、妊娠高血圧症候群)や、胎児の発育不全に起因する可能性が示されている1)。
❷ 外来患者に対して「えっ、妊娠してる!」と気づいた時の対応
著者: 岩田智子 , 平野零
ページ範囲:P.1360 - P.1364
妊娠を疑う病歴について
外来患者に妊娠の疑いがある時に、ヒト絨毛性ゴナドトロピン(hCG)定性検査による「妊娠反応検査」を行うことはゴールドスタンダードである。一方で、患者自身が妊娠の可能性を認識していないことや、医療者が患者の妊娠の可能性を見落としてしまうことは、診療において度々経験される。患者自身が認識していない妊娠は、救急外来を受診した妊娠可能女性の2〜19%に認められたという報告もある1,2)。以下に、妊娠の可能性がある人を適切に疑い、妊娠反応検査につなげるための病歴聴取における3つのポイントを説明する。
❸ 妊婦・授乳婦への投薬
著者: 髙畠育 , 水谷佳敬
ページ範囲:P.1365 - P.1369
CASE1
患者:31歳、女性。妊娠30週、2経妊1経産。前日夜からの発熱、鼻汁、咳嗽を主訴に受診した。同居する5歳の長女が2日前に発熱し、迅速検査でインフルエンザA型と診断されており、症状・診察所見から臨床的にインフルエンザと診断した。
❹ 妊婦・授乳婦の画像検査
著者: 上松東宏
ページ範囲:P.1370 - P.1373
プライマリ・ケアの現場で、体調の悪い妊婦や授乳婦の診療にあたることは珍しくない。その際、適切な診断や治療のために、画像検査が必要になることがある。特に妊婦において、放射線を用いる画像検査がもたらす胎児への影響は、患者本人だけでなく、家族や依頼する医師本人にとって気がかりとなる。本稿では、妊婦や授乳中の患者における画像検査の基本的な知識をまとめ、患者説明のポイントについて述べる。
❺ 妊婦・授乳婦へのワクチン接種
著者: 守屋章成
ページ範囲:P.1374 - P.1377
妊婦・授乳婦で検討するワクチン
2024年現在、国内で流通しているワクチンのうち、妊婦・授乳婦に対する接種可否は表1、2のように分類できる。
【各論】
❶ 妊婦・褥婦(授乳婦)の発熱
著者: 小幡健太 , 城向賢
ページ範囲:P.1378 - P.1383
CASE 授乳中女性の発熱
患者:32歳、帰省分娩による産後8週、授乳中の女性。
現病歴:2日前からの37℃台の発熱を主訴に外来受診。気道症状はなく、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)とインフルエンザウイルスの抗原検査は共に陰性であった。再度身体所見を確認したところ、右乳房に圧痛を伴う発赤と硬結を認め、うっ滞性乳腺炎と診断した。乳腺炎ケアのフローチャートに基づき治療を開始し、右乳房の冷却とロキソプロフェンの処方を行った。出産した医療機関が県外にあるため、市内の助産所へ連絡し、乳房ケアを依頼。2日後には解熱し、乳腺炎が軽快していることを確認した。
❷ 妊婦・褥婦の腹痛
著者: 柴田綾子
ページ範囲:P.1384 - P.1388
CASE
患者:32歳、妊娠12週の妊婦。
現病歴:下腹部痛を主訴に夜間の救急外来を受診。緩徐発症の間欠的な腹痛で、左下腹部が強いとのこと。悪阻のため、飲水・食事は十分にとれていなかったが、2日前の妊婦健診では明らかな異常は指摘されなかったという。
陰性症状:発熱、性器出血。
問診にて最終排便が1週間前であることが判明した。便秘薬を服用してもらい、悪阻に対して補液をして経過観察したところ、補液後に排便があり、疼痛が消失した。
産婦人科医が不在の施設のため、経腟超音波検査は施行しなかった。翌日に、かかりつけ産婦人科にも電話で報告するよう説明し、帰宅となった。
❸ 妊婦・褥婦の頭痛
著者: 伊藤雄二
ページ範囲:P.1389 - P.1393
CASE 1 妊娠高血圧を見逃した1例
患者:33歳、妊娠32週、初産婦。健診は近医で受けている。
現病歴:微熱と咳嗽、軽度の頭痛で近医を受診したが、血圧が155/100mmHgであったことに気づかず、尿検査も未施行で、アセトアミノフェンの頓用処方のみで帰宅させられていた。後日、近医での健診時に血圧170/110mmHg、尿蛋白3+であり、当院へ緊急母体搬送となった。搬送後、胎児機能不全のため緊急帝王切開を施行した。新生児は呼吸障害が強く、厳重な呼吸管理が必要であった。
❹ 妊婦・褥婦の高血圧
著者: 杉村基 , 平井久也
ページ範囲:P.1394 - P.1397
CASE
妊娠初期に発症したBasedow病合併妊娠の1例
患者:26歳、女性。妊娠13週。
既往歴、家族歴:特記すべきことなし。
現病歴:妊婦診察のための産婦人科外来受診時に、2週間前から動悸、頭痛があるとの訴えがあった。超音波断層検査上、胎児心拍を認め、異常は認めなかった。甲状腺軽度腫大、血圧145/92mmHg、脈拍数130回/分、体温37.3℃のため、内科紹介受診となった。胸部X線検査は異常なし、心電図で上室性頻脈、TSH(甲状腺刺激ホルモン)低下、FT3・FT4増加、抗TSHレセプター抗体(TRAb)陽性のため、Basedow病と診断された。一時的にβ遮断薬により降圧ならびにレートコントロールを図りながら、チアマゾール投与を開始した。速やかに頻脈の改善を認め、降圧が得られた。
❺ 妊婦・褥婦の糖尿病
著者: 中西篤史 , 三澤美和
ページ範囲:P.1398 - P.1404
CASE
プレコンセプションケアがスムーズな妊娠・分娩経過に寄与した1例
患者:40歳、1妊0産。身長165cm、妊娠前体重64kg。
既往歴:糖尿病、家族性高コレステロール血症(ヘテロ接合体)。
家族歴:母・母方祖父:脂質異常症、父:糖尿病。
現病歴:妊娠2年前、健診を契機に糖尿病と診断され、SGLT2阻害薬で加療開始。妊娠1年前、挙児希望のためSGLT2阻害薬を中止したところ体重増加があり、HbA1c 7.5%まで悪化した。網膜症はなし。栄養指導と減量でHbA1c 6.6%まで改善した。インスリン デテミルを開始したところ、HbA1c 6.2%まで改善し、妊娠を許可したところ翌月に排卵誘発+人工授精で妊娠が成立した。インスリン デテミルは継続し、1,600kcal分割食を開始した。児の発育に問題はなく、明らかな形態異常を認めず、妊娠高血圧症候群の発症もなかった。妊娠37週4日に分娩誘発を行い、2,921gの男児を経腟分娩した。
本稿では妊娠前、妊娠中、出産後の3つのステージに分けて考えていく。
❻ 妊婦・褥婦によくみられる症状・徴候
著者: 伊達岡要
ページ範囲:P.1405 - P.1408
CASE
産褥期に多発肺転移で判明した子宮体がん
患者:20代、女性。
月経歴:初経12歳。月経周期30日。
現病歴:第1子出産後、産褥3カ月より下痢、持続する微熱と咳を主訴に内科を受診。胸部X線上、両肺野に多発小結節陰影を認め(図1)、当初は粟粒結核が疑われて高次医療機関の内科で精査された。胸腹部CT検査で多発肺転移腫瘍と子宮腫大を認めて産婦人科へ紹介となり、精査の結果、低分化型類内膜腺癌stage Ⅳb(T2NXM1)と診断された(図2)。外来化学療法を9コース受けて、いったんは肺転移像は縮小したものの、その後脳転移をきたし永眠された。
本CASEは若年であることに加え、産婦人科領域内で「産褥3カ月以内に子宮体がんはない」が定説とされていたことを覆す、極めて稀な症例であった。内科受診時に伝えられていなかったこととして、産後2カ月経過の時点で不正出血が持続していたことが挙げられる。悪露は通常、産後1カ月で終了する。
❼ 妊婦・褥婦のメンタルヘルス
著者: 森屋淳子
ページ範囲:P.1409 - P.1413
CASE
患者:40歳、女性。
現病歴:元来、責任感が強い性格。第一子出産後2カ月頃から、授乳後に子どもが泣き止まず、不眠や不安感、イライラが強まるようになった。夫が仕事に出た後、子どもと2人きりになることへの恐怖が生じ、夫の勧めで受診。産後うつ病と診断し、選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)を少量から開始した。実家に里帰りするも症状は改善せず、希死念慮も出現したため、子どもを乳児院に預け、精神科への紹介で入院加療を行った。退院後は当院での外来治療を継続し、子どもの成長に伴い、本人の不安感や抑うつ症状も徐々に改善。抗うつ薬を漸減中止し、その後も不定期で通院加療を継続している。
❽ 妊婦・褥婦のSDH
著者: 飯塚玄明 , 向原千夏
ページ範囲:P.1414 - P.1419
CASE
産後に抑うつ状態をきたした1例
患者:24歳、女性。産後6カ月。
背景:夫の仕事の関係で3カ月前に転居。
現病歴:「花粉症の薬がほしい」との主訴で、近所のクリニックである当院を受診した。花粉症についての診療を終えたが、疲れた表情であったため、さらに問診していくと、「最近、夜眠れない」と打ち明けられた。育児が思うようにいかず、気持ちが落ち込み、自分を責めてしまうとのこと。抑うつ状態が疑われた。夫は仕事で帰りが遅く、夫婦の両親や家族は県外在住であり、引っ越したばかりで地域に知り合いもおらず、孤立しているようだった。当院で不眠症や抑うつ状態に対する診療を行うと共に、本人に了承を得て役場の母子保健担当者に連絡し、情報共有した。保健師の勧めで定期的に産後ケア事業が利用できるようになり、また助産師や臨床心理士などの専門職も介入したことで、患者の心身は少しずつ安定していった。
❾ 妊娠にまつわる予防医療—プレコンセプションケアを中心に
著者: 宮崎景
ページ範囲:P.1420 - P.1424
女性にとって妊娠・出産は、身体的、精神的に大きな変化を経験するイベントである。これに対応するためには、適切な予防医療が不可欠である。総合診療医は妊娠前から妊娠期、そして産後に至るまで、女性の健康を包括的に支援することが求められる。そのなかでも妊娠期、産後のケアは、日本では産婦人科医を中心に、ルーチンケアが確立している。一方で妊娠前のケア、すなわちプレコンセプションケアは、その重要性にもかかわらず、十分に注目され、確立したケアが提供されているとは言いがたい。本稿では、プレコンセプションケアを中心に解説していく。
【スペシャル・アーティクル】
妊婦・褥婦のケアを通したプラネタリーヘルスの実践
著者: 山村倫啓 , 王謙之 , 豊田喜弘 , 梶有貴
ページ範囲:P.1425 - P.1430
プラネタリーヘルスとは?
今年の夏は暑かった! いや、「今年の夏も暑かった!」と言うべきだろう。外来で「先生、これは熱中症ですか?」と尋ねられるのも、1日に1回や2回どころではなかった。実際、図11)からは世界の平均気温が急激に上昇していることが一目瞭然であり、2023年は世界の平均気温が有史以来最も高い1年になった1)。そして気温の上昇に伴って、豪雨、台風、干ばつ、山火事などの自然災害も増加し、激甚化している。われわれが肌身で感じるレベルで、地球の気候変動が起きているのだ。この気候変動は、工業化による化石燃料の使用が増加して、二酸化炭素・メタン・亜酸化窒素といった温室効果ガスの排出が増えたこと、つまりわれわれ人間の活動が主な原因なのである。
実は地球環境への影響は気候変動だけではない。ここで“プラネタリー・バウンダリーズ”という概念を紹介したい(図2)2)。これは、人々が地球で安全に活動できる範囲を科学的に定義し、地球システムが安定した状態を保つために守るべき限界点を表したものである。いわば、地球の健康診断の結果、といったところだろうか。「気候変動」「生物圏の一体性」「土地利用の変化」「淡水変化」「窒素・リンの生物地球化学的循環」「海洋の酸性化」「大気エアロゾルによる負荷」「成層圏オゾン層の破壊」「新規化学物質」という9つの領域があるが、実は2023年の調査では、実に6つの領域で不可逆的な状態に達していたのである2)。つまり、地球は糖尿病、高血圧症、脂質異常症、変形性膝関節症、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、うつ病…といった高齢者の多疾患併存のような状態であり、しかも急速に進行して人類の生活に支障が出ているフェーズにあるのだ。
Editorial
「妊婦・褥婦」の健康の基本知識や診療アプローチを現代版にアップデートしよう フリーアクセス
著者: 鳴本敬一郎
ページ範囲:P.1351 - P.1351
前回の特集「妊婦・褥婦が一般外来に来たら」の発刊(2016年1月号,松村真司先生企画)から8年が経過しました。この間、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミックや気候変動、東欧・中東アジアでの戦争などの影響で、人々の生活や社会に大きな変化がもたらされました。
特に女性の健康に関しては、生理(または女性)の貧困や女性への暴力、リプロダクティブ・ヘルス、ジェンダーイシューなどの課題が浮き彫りになりました。これに伴い、プライマリ・ケアの医療現場でも、臨床推論を含む診療の在り方やケアの視点が大きく変化してきました。
【エッセイ】アスクレピオスの杖—想い出の診療録・56
なんかうるっときた「西村眞紀さん江」
著者: 西村真紀
ページ範囲:P.1437 - P.1437
本連載は、毎月替わる著者が、これまでの診療で心に残る患者さんとの出会いや、人生を変えた出来事を、エッセイにまとめてお届けします。
「総合診療」達人伝|7つのコアコンピテンシーとその向こう側・7
連携重視のマネジメント
著者: 松下明 , 奥知久
ページ範囲:P.1438 - P.1445
岡山県の真ん中にある津山市。そこからバスでコトコト1時間。家庭医のパワースポット・奈義町に到着。奈義町と言えば、合計特殊出生率2.95(2019年)という驚異的な数字を記録したこともある“子育ての町”として知られている(注:解釈には諸説あり)。筆者がここを訪ねた所以は、この町に言わずと知れた家庭医のカリスマ! 家族志向ケアの達人・松下 明先生(一口メモ1)がおられるからである。いったい達人はどんな振る舞いで、この町の家族や多職種と共にケアの形を構築しているのか? そこにはどんなワザが隠れているのか? 今回のテーマ「連携重視のマネジメント」の観点から考察してみよう。
What's your diagnosis?[264]
トラの優勝だ!
著者: 渡部亮太郎 , 河村勇志 , 山口諒也 , 藤本卓司 , 大矢亮
ページ範囲:P.1446 - P.1450
病歴
患者:87歳、男性。身の回りのことは自立
主訴:右膝の痛み
現病歴:受診3カ月前に右足背、受診1カ月前に右下肢全体の浮腫を認めた。受診3週間前に近医を受診し、変形性膝関節症に伴う浮腫を疑われ、右膝にヒアルロン酸注射を施行された。その後、右膝の内側に淡いピンク色で数cm程度の紅斑が出現。1週間程度で皮疹は拡大し、右膝の圧痛、運動時痛や可動域制限も出現した。受診11日前に近医にて蜂窩織炎や化膿性関節炎を疑われ、セフトリアキソン(CTRX)点滴投与を3日間とアモキシシリン(AMPC)の内服を7日間継続した。その後も皮疹は徐々に拡大して色調は赤褐色に変化、痛みも増強し、右足を引きずるようになった(図1)。受診2日前から歩行困難となり、当院救急搬送となった。
ROS陰性:発熱、悪寒戦慄、感覚障害
既往歴:慢性心不全、心房細動、高血圧、両側膝関節症、深部静脈血栓症。結核なし
内服薬:エドキサバン15mg/日、サクビトリルバルサルタン100mg/日、ラベプラゾール10mg/日、アルファカルシドール0.25μg/日、メコバラミン500μg/日、猪苓湯7.5g/日
アレルギー:なし
嗜好歴:喫煙歴:20本/日×60年間、飲酒歴:日本酒200mL/日×60年間
ジェネラリストに必要な ご遺体の診断学・21
実践基本編①:心臓突然死
著者: 森田沙斗武
ページ範囲:P.1452 - P.1455
Case 1
患者:52歳、男性。妻と子の三人暮らし。
既往歴:特になし。
現病歴:職場の健診で高血圧とLDLコレステロール高値を指摘されていたが、忙しいからと医療機関を受診していなかった。仕事は建設現場の作業員で、喫煙20本/日の習慣があった。
某日午後5時頃に帰宅。午後から背中が急に痛くなったため仕事を早退したという。妻が病院に行くように勧めるも、「痛み止めで様子をみるから大丈夫。明日も痛かったら仕事を休んで病院に行くわ」と、夕食も摂らずに自室で横になっていた。午後9時頃、居間に現れ「少し痛みがマシになってきたから、明日は仕事に行けそう」と話し、入浴。午後10時頃に自室で就寝した。
翌日午前6時から鳴り始めた目覚まし時計がいつまで経っても止まらないことを不審に思った妻が、ベッド上で死亡している患者を発見。午前6時11分に救急要請、20分に救急隊が到着するも全身の硬直を認め、不搬送決定となった。
臨床教育お悩み相談室|どうする!?サロン・20
「ハラスメント、ダメ、ゼッタイ」
著者: 佐田竜一 , 木村武司 , 長野広之
ページ範囲:P.1456 - P.1461
今月のお悩み
10年目の研修管理業務に携わる医師です。研修医が上級医からのハラスメントで悩み、研修を中断してしまいました。自分の職場でこんなことがあるなんてショックです。教育現場でのハラスメントってよくあるのでしょうか? 今後どのように加害者、被害者に接したらよいのか、どうハラスメントを防止していけばいいのかなど悩んでいます。
[ペンネーム:DR-METALさん]
臨床医のためのライフハック│限りある時間を有効に使う仕事術・21
—組織マネジメント②—働きやすく、やりがいのある組織を創るにはどうすればよいか?
著者: 中島啓
ページ範囲:P.1462 - P.1464
時間がない! 臨床医の仕事は診療だけにあらず。事務、教育、自己学習、研究、学会発表、情報発信、所属組織の運営などなど、尽きることはありません。もちろんプライベートの生活もあり、「時間不足」は臨床医の永遠の課題です。では、一度きりの“医師人生”の限られた時間を、どう有効に使うのか? 筆者が培ってきた「ライフハック(仕事術)」のすべてを、余すところなく開陳します。
オール沖縄!カンファレンス|レジデントの対応と指導医の考えVer.2.0・95
A Hidden Diagnosis Underneath the Red Herrings
著者: 櫻井俊彰 , 鈴木智晴 , 徳田安春 , 仲里信彦 , 鈴木智晴 , 佐藤直行
ページ範囲:P.1465 - P.1469
CASE
患者:80代、男性。
主訴:発熱、体動困難。
現病歴:入院5日前までは食事も全量摂取しており、会話も普段通りできていた。入院4日前より倦怠感が、3日前から食欲低下があったが、様子をみていた。しかし入院前日から発熱も出現、翌日には体動困難となったため救急搬送された。SARS-CoV-2抗原検査が陽性で、中等症の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)と診断し、レムデシビルにより入院治療されていた。しかし日中の傾眠傾向と食事摂取不良が悪化傾向であり、入院第14病日で当科へ紹介された。
その他の病歴:座位になる際に「立ちくらみ」あり。また理学療法士や看護師より、「トイレに行くと、一点を見つめて動作が止まってしまう」「眼球の上転や、けいれんのような手足の動きもあった」という追加の情報を得た。
併存症:Lewy小体型認知症、Parkinson病、下垂体性副腎不全、慢性腎臓病(ステージ3)、神経因性膀胱、側頭葉てんかん。
既往歴:心筋梗塞(経皮的冠動脈形成術後)、右放線冠ラクナ梗塞(明らかな後遺症なし)。
内服薬:ヒドロコルチゾン10 mg錠(4.5錠)毎食後/日、レベチラセタム500 mg錠(1.5錠)毎食後/日、ドロキシドパOD 100 mg錠(1錠)1回/日、ビソプロロール2.5 mg錠(1錠)1回/日、アトルバスタチン10 mg錠(1錠)1回/日、バイアスピリン100 mg錠(1錠)1回/日、ランソプラゾール15 mg錠(1錠)1回/日
入院前のADL:ほぼ自立。
アレルギー:薬剤、食物共になし。
〈紹介時の検査所見〉
意識レベル:Glasgow Coma Scale:E3V4M6(13点)
バイタルサイン:血圧140/82 mm Hg、心拍数80回/分・整、呼吸数12回/分、SpO2 97%(室内気)、体温37.3℃。
頭頸部:眼球結膜黄染なし。眼瞼結膜蒼白なし。甲状腺腫大なし・圧痛なし。項部硬直なし。
口腔内:う蝕なし。舌側面に咬傷なし。
胸部:心音に不整なし。過剰心音なし。心雑音を聴取せず。肺音 清。副雑音なし。
腹部:平坦・軟、圧痛なし。蠕動音の亢進・減弱なし。明らかな圧痛なし。
四肢:浮腫なし。関節の熱感や腫脹なし。
皮膚:Turgorの低下なし。
神経:四肢麻痺なし。
〈検査所見(早朝空腹時採血)〉
血算:WBC 9,200/μL、Hb 13.4 g/dL、MCV 94 fL、Plt 45×104/μL。
生化学:BUN 21.2 mg/dL、Cre 1.49 mg/dL、Na 138 mEq/L、K 4.1 mEq/L、Cl 98 mEq/L、AST 12 U/L、ALT 15 U/L、LDH 110 U/L、CK 80 U/L、血糖90 mg/dL、HbA1c 6.6%、CRP 0.50 mg/dL、Ca 9.2 mg/dL、Mg 2.0 mg/dL。
尿ケトン 陰性、SARS-CoV-2抗原検査 陰性、ビタミンB1 40 ng/mL(基準範囲>28 ng/mL)。
動脈血液ガス分析:pH 7.43、pCO2 40 Torr、pO2 260 Torr、HCO3- 26 mmol/L。
内分泌:コルチゾール11.7μg/dL、TSH 1.58 μU/mL(基準範囲0.2〜4.5μU/mL)、FT4 1.54 ng/dL(基準範囲0.7〜1.48 ng/dL)。
心電図:陳旧性の虚血性変化あり。
髄液所見:初圧13 cm H2O、無色透明で日光微塵なし。細胞数3個/μL、好中球:リンパ球=1:2、キサントクロミーなし。髄液中総蛋白40 mg/dL(基準範囲10〜52.6 mg/dL)、髄液糖定性58 mg/dL、LD髄液<25 U/L、CK髄液<4 U/L、髄液ADA<2.0 U/L、墨汁染色 陰性、髄液マルチプレックスPCR検査 陰性、髄液結核菌PCR 陰性。
脳波検査:明らかなてんかん波なし。
頭部MRI検査:特記すべき所見なし。
投稿 Correspondence
不確実性の扱い方
著者: 若林崇雄 , 天野雅之 , 杉田陽一郎
ページ範囲:P.1470 - P.1472
『総合診療』誌34巻5号(2024年5月号)を拝読し、一見すると方向性が真逆な論考が同時掲載されており、興味深く感じた。
1つはその号の特集企画者である天野雅之先生による「『不確実性』が極めて高い状況での意思決定戦略」の記事1)である。不確実性は総合診療分野で頻繁に遭遇し2)、医師の離職やバーンアウトの原因となる3)、やっかいな存在だ。天野先生の論考では、経営学を用いた無理のない意思決定プロセスや、エフェクチュエーションなどを利用した合理的に決定を促す手法などが紹介されていた。これらの考察は総合診療医にとって、明日にでも応用可能な話題であり、特に指導医には“研修医への指導”という観点からも有益であろう。
GM Clinical Pictures
敗血症性ショック、AKI.このCT所見は?
著者: 柴田健継 , 佐藤信宏 , 廣瀬保夫 , 若松拓也 , 中村元
ページ範囲:P.1473 - P.1475
CASE
患者:50代、女性。
主訴:腹痛。
現病歴:来院前日に腹痛が出現し、近医を受診して尿路感染症を疑われ、セフトリアキソンの静脈内投与、シタフロキサシンとアセトアミノフェンの処方を受けた。その後も腹痛は改善せず、当院に救急搬送された。
既往歴・内服歴:特記事項なし。
身体所見:体温36.2℃、血圧65/52mmHg、脈拍数115回/分。呼吸数16回/分、SpO2 98%(酸素3L/分)、意識清明。末梢冷感あり、腹部全体に圧痛があるが、反跳痛や筋性防御は認めなかった。
血液検査:AST 43 U/L、ALT 25 U/L、BUN 33.4 mg/dL、Cr 2.21 mg/dL、CRP 16.64 mg/dL、Lac 3.99 mmol/L、WBC 6,500/μL(Neut 89.4%)、RBC 416×104/μL、Hb 11.3 g/dL、Hct 35.5 %、Plt 5.7×104/μL、APTT 54.6秒、PT-INR 2.04。
尿検査:混濁(3+)、白血球(2+)、亜硝酸塩(-)。
画像所見:腹部造影CT(図1)。
#総合診療
#今月の特集関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.1419 - P.1419
#今月の特集関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.1424 - P.1424
#今月の特集関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.1432 - P.1432
#医学書院の新刊 フリーアクセス
ページ範囲:P.1433 - P.1436
#参加者募集 フリーアクセス
ページ範囲:P.1432 - P.1432
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.1348 - P.1349
『総合診療』編集方針 フリーアクセス
ページ範囲:P.1347 - P.1347
1991年に創刊した弊誌は、2015年に『JIM』より『総合診療』に誌名を変更いたしました。その後も高齢化はさらに進み、社会構造や価値観、さらなる科学技術の進歩など、日本の医療を取り巻く状況は刻々と変化し続けています。地域医療の真価が問われ、ジェネラルに診ることがいっそう求められる時代となり、ますます「総合診療」への期待が高まってきました。これまで以上に多岐にわたる知識・技術、そして思想・価値観の共有が必要とされています。そこで弊誌は、さらなる誌面の充実を図るべく、2017年にリニューアルをいたしました。本誌は、今後も下記の「編集方針」のもと、既存の価値にとらわれることなく、また診療現場からの要請に応え、読者ならびに執筆者のみなさまとともに、日本の総合診療の新たな未来を切り拓いていく所存です。
2018年1月 『総合診療』編集委員会
読者アンケート
ページ範囲:P.1477 - P.1477
『総合診療』バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.1478 - P.1479
お得な年間購読のご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.1479 - P.1480
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.1481 - P.1482
「総合診療」 第34巻 総目次 フリーアクセス
ページ範囲:P. - P.
基本情報
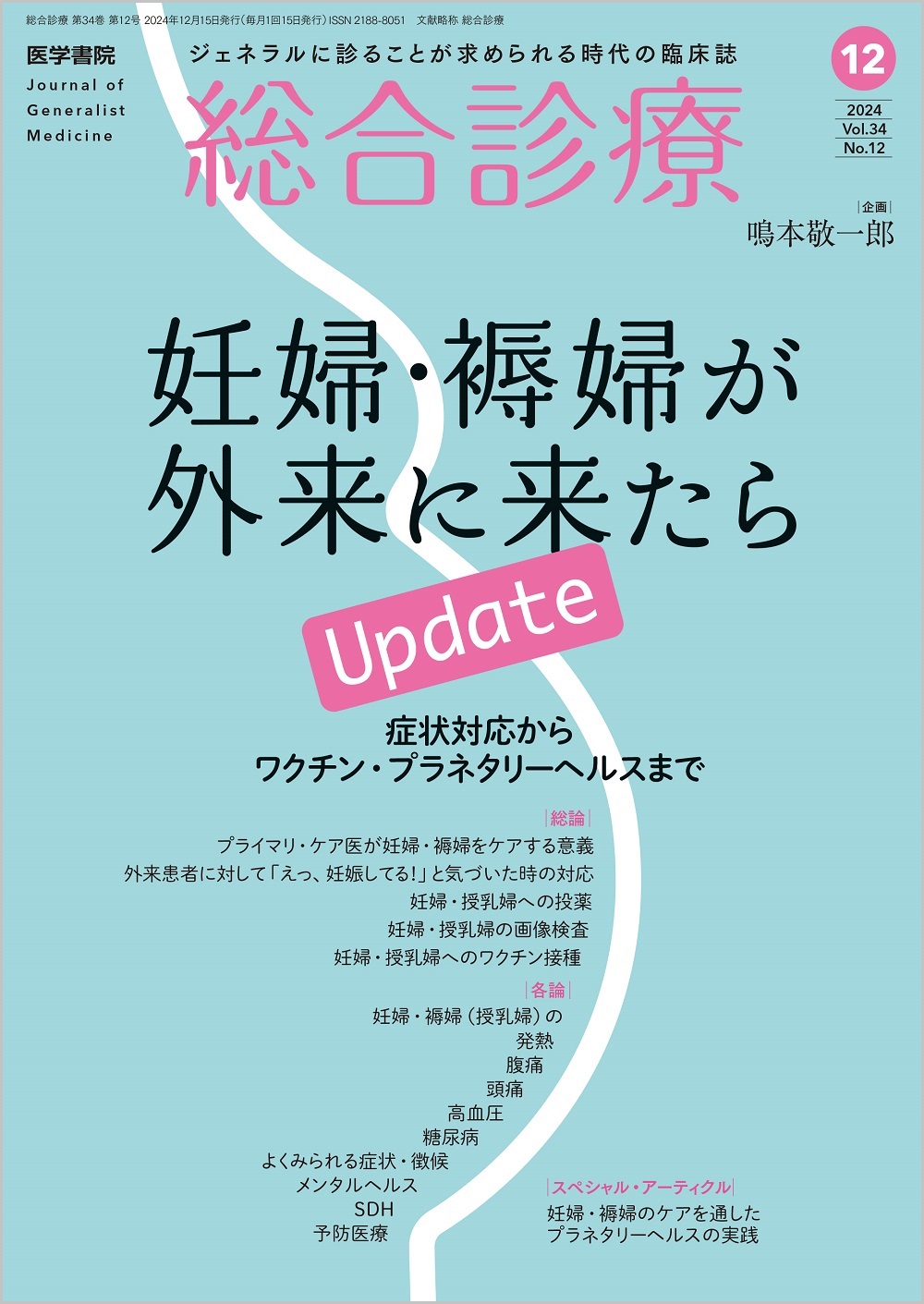
バックナンバー
34巻12号(2024年12月発行)
特集 妊婦・褥婦が外来に来たらUpdate—症状対応からワクチン・プラネタリーヘルスまで
34巻11号(2024年11月発行)
特集 電子カルテとベッドサイドの壁を打ち破る!—患者情報の「言語化」への挑戦
34巻10号(2024年10月発行)
特集 化かしが得意なカメレオンな疾患を捕まえろ!—よくある騙され方のゲシュタルト
34巻9号(2024年9月発行)
特集 今伝えたいクリニカル・パール—つくり方、使い方、活かし方
34巻8号(2024年8月発行)
特集 ストーン・ウォーズ 果てしなき“石”と医師との闘い
34巻7号(2024年7月発行)
特集 どうする!? 健診異常—これってホントに異常なの? どう説明する?
34巻6号(2024年6月発行)
特集 医師のウェルビーイング
34巻5号(2024年5月発行)
特集 —優柔不断にサヨウナラ!—あなたの「臨床判断」を高めるケーススタディ11選
34巻4号(2024年4月発行)
特集 困ったときの漢方—この症状に役立ちます!
34巻3号(2024年3月発行)
特集 —え、ウソ!実は◯◯だった!?—“コモンディジーズ”の診断ピットフォール
34巻2号(2024年2月発行)
特集 日常診療で出合う筋骨格疾患—脳神経内科と整形外科からのアプローチ
34巻1号(2024年1月発行)
特集 —“体験型”臨床クイズで習得する!—フィジカル診断エクセレンス
33巻12号(2023年12月発行)
特集 海の外へ渡る航行者を診る—アウトバウンドにまつわるetc.
33巻11号(2023年11月発行)
特集 —続・総合診療外来に“実装”したい—最新エビデンスMy Best 3
33巻10号(2023年10月発行)
特集 ○×クイズ110問!日常診療アップグレード—Choosing WiselyとHigh Value Careを学ぼう
33巻9号(2023年9月発行)
特集 ジェネラリストのための「発達障害(神経発達症)」入門
33巻8号(2023年8月発行)
特集 都市のプライマリ・ケア—「見えにくい」を「見えやすく」
33巻7号(2023年7月発行)
特集 “消去法”で考え直す「抗菌薬選択」のセオリー—広域に考え、狭域に始める
33巻6号(2023年6月発行)
特集 知っておくべき!モノクロな薬たち(注:モノクローナル抗体の話ですよ〜)
33巻5号(2023年5月発行)
特集 —疾患別“イルネススクリプト”で学ぶ—「腹痛診療」を磨き上げる22症例
33巻4号(2023年4月発行)
特集 救急対応ドリル—外来から在宅までの60問!
33巻3号(2023年3月発行)
特集 —自信がもてるようになる!—エビデンスに基づく「糖尿病診療」大全—新薬からトピックスまで
33巻2号(2023年2月発行)
特集 しびれQ&A—ビビッとシビれるクリニカルパール付き!
33巻1号(2023年1月発行)
特集 COVID-19パンデミック 振り返りと将来への備え
32巻12号(2022年12月発行)
特集 レクチャーの達人—とっておきの生ライブ付き!
32巻11号(2022年11月発行)
特集 不定愁訴にしない“MUS”診療—病態からマネジメントまで
32巻10号(2022年10月発行)
特集 日常診療に潜む「処方カスケード」—その症状、薬のせいではないですか?
32巻9号(2022年9月発行)
特集 総合診療・地域医療スキルアップドリル—こっそり学べる“特講ビデオ”つき!
32巻8号(2022年8月発行)
特集 こんなところも!“ちょいあて”エコー—POCUSお役立ちTips!
32巻7号(2022年7月発行)
特集 —どうせやせない!? やせなきゃいけない??苦手克服!—「肥満」との向き合い方講座
32巻6号(2022年6月発行)
特集 総合診療外来に“実装”したい最新エビデンス—My Best 3
32巻5号(2022年5月発行)
特集 「診断エラー」を科学する!—セッティング別 陥りやすい疾患・状況
32巻4号(2022年4月発行)
特集 えっ、これも!? 知っておきたい! 意外なアレルギー疾患
32巻3号(2022年3月発行)
特集 AI時代の医師のクリニカル・スキル—君は生き延びることができるか?
32巻2号(2022年2月発行)
特集 —withコロナ—かぜ診療の心得アップデート
32巻1号(2022年1月発行)
特集 実地医家が楽しく学ぶ 「熱」「炎症」、そして「免疫」—街場の免疫学・炎症学
31巻12号(2021年12月発行)
特集 “血が出た!”ときのリアル・アプローチ—そんな判断しちゃダメよ!
31巻11号(2021年11月発行)
特集 Q&Aで深める「むくみ診断」—正攻法も!一発診断も!外来も!病棟も!
31巻10号(2021年10月発行)
特集 医師の働き方改革—システムとマインドセットを変えよう!
31巻9号(2021年9月発行)
特集 「検査」のニューノーマル2021—この検査はもう古い? あの新検査はやるべき?
31巻8号(2021年8月発行)
特集 メンタルヘルス時代の総合診療外来—精神科医にぶっちゃけ相談してみました。
31巻7号(2021年7月発行)
特集 新時代の「在宅医療」—先進的プラクティスと最新テクノロジー
31巻6号(2021年6月発行)
特集 この診断で決まり!High Yieldな症候たち—見逃すな!キラリと光るその病歴&所見
31巻5号(2021年5月発行)
特集 臨床医のための 進化するアウトプット—学術論文からオンライン勉強会、SNSまで
31巻4号(2021年4月発行)
特集 消化器診療“虎の巻”—あなたの切実なギモンにズバリ答えます!
31巻3号(2021年3月発行)
特集 ライフステージでみる女性診療at a glance!—よくあるプロブレムを網羅しピンポイントで答えます。
31巻2号(2021年2月発行)
特集 肺炎診療のピットフォール—COVID-19から肺炎ミミックまで
31巻1号(2021年1月発行)
特別増大特集 新型コロナウイルス・パンデミック—今こそ知っておきたいこと、そして考えるべき未来
30巻12号(2020年12月発行)
特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き) Part 2
30巻11号(2020年11月発行)
特集 診断に役立つ! 教育で使える! フィジカル・エポニム!—身体所見に名を残すレジェンドたちの技と思考
30巻10号(2020年10月発行)
特集 —ポリファーマシーを回避する—エビデンスに基づく非薬物療法のススメ
30巻9号(2020年9月発行)
特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【感染症・内分泌・整形外科 編】
30巻8号(2020年8月発行)
特集 マイナーエマージェンシー門外放出—知っておくと役立つ! テクニック集
30巻7号(2020年7月発行)
特集 その倦怠感、単なる「疲れ」じゃないですよ!—筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群とミミック
30巻6号(2020年6月発行)
特集 下降期慢性疾患患者の“具合”をよくする—ジェネラリストだからできること!
30巻5号(2020年5月発行)
特集 誌上Journal Club—私を変えた激アツ論文
30巻4号(2020年4月発行)
特集 大便強ドリル—便秘・下痢・腹痛・消化器疾患に強くなる41問!
30巻3号(2020年3月発行)
特集 これではアカンで!こどもの診療—ハマりがちな11のピットフォール
30巻2号(2020年2月発行)
特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【循環器・消化器・神経疾患編】
30巻1号(2020年1月発行)
特集 総合診療医の“若手ロールモデル”を紹介します!—私たちはどう生きるか
29巻12号(2019年12月発行)
特集 困っている“あなた”に届く 認知症診療
29巻11号(2019年11月発行)
特集 臨床写真図鑑 レアな疾患編—見逃したくない疾患のコモンな所見
29巻10号(2019年10月発行)
特集 教えて!医師のためのビジネス・スキル
29巻9号(2019年9月発行)
特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き)
29巻8号(2019年8月発行)
特集 —ノーモア見逃し—日常の検査と画像に潜むピットフォール
29巻7号(2019年7月発行)
特集 リウマチ・膠原病ミミック症例帖—“膠原病っぽくみえてしまう疾患たち”にだまされない!
29巻6号(2019年6月発行)
特集 皮膚科診療エクササイズ—1枚の写真から
29巻5号(2019年5月発行)
特集 一般外来で診断できたら「えっへん!」な疾患38
29巻4号(2019年4月発行)
特集 “ナゾ”の痛み診療ストラテジー|OPQRSTで読み解く
29巻3号(2019年3月発行)
特集 —あなたのギモンに答えます!—循環器診療のハードルを下げるQ&A31
29巻2号(2019年2月発行)
特集 意外な中毒、思わぬ依存、知っておきたい副作用—一般外来で!OTCも処方薬も!
29巻1号(2019年1月発行)
特集 教えて検索!—膨大な医学情報を吟味・整理するスキル
28巻12号(2018年12月発行)
特集 こんなときこそ漢方を!
28巻11号(2018年11月発行)
特集 日本一マジメな「おしっこドリル」—今これだけは押さえておきたい腎・泌尿器のモンダイ
28巻10号(2018年10月発行)
特集 クリニカル・パールPremium!—憧れのカリスマ医師はかく語りき
28巻9号(2018年9月発行)
特集 オンコ・ジェネラリスト—「がん」に強い総合診療医をめざして
28巻8号(2018年8月発行)
特集 80歳からの診療スタンダードUp to Date—Silver Standard
28巻7号(2018年7月発行)
特集 この薬だけは押さえておきたい! 総合診療医のためのSpecialist Drug 40
28巻6号(2018年6月発行)
特集 聴診・触診×エコーで診断推論!—Point-of-Care超音波(POCUS)の底力
28巻5号(2018年5月発行)
特集 “一発診断”トレーニング問題集—懸賞論文「GM Clinical Pictures」大賞発表!
28巻4号(2018年4月発行)
特集 感染症外来診療「賢医の選択」—検査・経口薬・ワクチンをどう使えばいいんですか?
28巻3号(2018年3月発行)
特集 糖尿病のリアル—現場の「困った!」にとことん答えます。
28巻2号(2018年2月発行)
特集 頭痛患者で頭が痛いんです!
28巻1号(2018年1月発行)
特集 シン・フィジカル改革宣言!—私の“神技”伝授します。
27巻12号(2017年12月発行)
特集 小児診療“苦手”克服!!—劇的Before & After
27巻11号(2017年11月発行)
特集 今そこにある、ファミリー・バイオレンス|Violence and Health
27巻10号(2017年10月発行)
特集 めまいがするんです!─特別付録Web動画付
27巻9号(2017年9月発行)
特集 うつより多い「不安」の診かた—患者も医師も安らぎたい
27巻8号(2017年8月発行)
特集 見逃しやすい内分泌疾患─このキーワード、この所見で診断する!
27巻7号(2017年7月発行)
特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 3 カリスマ編
27巻6号(2017年6月発行)
特集 「地域を診る医者」最強の養成法!
27巻5号(2017年5月発行)
特集 コミュニケーションを処方する—ユマニチュードもオープンダイアローグも入ってます!
27巻4号(2017年4月発行)
特集 病歴と診察で診断できない発熱!—その謎の賢い解き方を伝授します。
27巻3号(2017年3月発行)
特集 これがホントに必要な薬40—総合診療医の外来自家薬籠
27巻2号(2017年2月発行)
特集 The総合診療ベーシックス—白熱!「総合診療フェスin OKINAWA」ライブ・レクチャー! 一挙公開 フィジカル動画付!
27巻1号(2017年1月発行)
特集 総合診療の“夜明け”—キーマンが語り尽くした「来し方、行く末」
26巻12号(2016年12月発行)
特集 これでパッチリ! 眼の健康問題
26巻11号(2016年11月発行)
特集 続・しびれるんです!
26巻10号(2016年10月発行)
特集 内科診療を劇的に変える“まとめ”の達人
26巻9号(2016年9月発行)
特集 症状・症候別 エコーを使った診断推論─Point-of-Care超音波
26巻8号(2016年8月発行)
特集 The 初診外来
26巻7号(2016年7月発行)
特集 感染症ケアバンドル・チェックリスト
26巻6号(2016年6月発行)
特集 “賢い処方”と“ナゾ処方”
26巻5号(2016年5月発行)
特集 しびれるんです!─知っておくべきシビレル疾患
26巻4号(2016年4月発行)
特集 ケースとクイズで総ざらい! 街場の2型糖尿病治療
26巻3号(2016年3月発行)
特集 こんな時は漢方でしょう!
26巻2号(2016年2月発行)
特集 フィジカル改革宣言! ──診断からフォローアップまで
26巻1号(2016年1月発行)
特集 妊婦・褥婦が一般外来に来たら─エマージェンシー&コモンプロブレム
25巻12号(2015年12月発行)
特集 外来で「複数の疾患」をもつ患者を診る─マルチモビディティの時代のプライマリ・ケア
25巻11号(2015年11月発行)
特集 レアだけど重要な「痛み」の原因─システム1診断学
25巻10号(2015年10月発行)
特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 2
25巻9号(2015年9月発行)
特集 診断ピットフォール10選─こんな疾患,見逃していませんか?
25巻8号(2015年8月発行)
特集 健診データで困ったら─こんな検査結果を持ってこられたら
25巻7号(2015年7月発行)
特集 ここを知りたい!頭部外傷初期対応・慢性期ケア
25巻6号(2015年6月発行)
特集 高齢者救急の落とし穴─紹介する時,される時
25巻5号(2015年5月発行)
特集 咳を聴きとり,咳を止める
25巻4号(2015年4月発行)
特集 関節が痛いんです!─コモンからレアものまでの診断と治療
25巻3号(2015年3月発行)
特集 神経難病ケアのコペルニクス的転回
25巻2号(2015年2月発行)
特集 総合医のためのスポーツ医学ベーシックス
25巻1号(2015年1月発行)
特集 動悸・息切れ─ヤバい病気の見つけ方 そして見つからなかった時の対処法
