「風が吹けば桶屋が儲かる」「Time is money」といった格言は、われわれ人類が大切にしてきた教訓である。こうした語り継がれる言葉は極めて具体的なことを表現しているように見えながら、実は「深い」抽象的なメッセージを有していることが多い。身近な生活の知恵のみならず、アカデミックな知も同様であり、臨床では「クリニカル・パール」と呼ばれる。
各分野の第一線で活躍されている臨床医は、何を大事にし、何を後輩に伝えているのだろうか? 「各施設の中で共有するだけではもったいない。全国に伝えたい」という願いで本特集は誕生した。令和の時代に生きる私たちも、いつかはこの世からいなくなる。では、パールはどうだろう? 私たちがいなくなっても、パールは口伝や文章として受け継がれていく。そして、私たち自身がそうであるように、新たな時代の医師がそのパールを用いて、未来の患者さんを救うことになるであろう。時代を超えて普遍的かつ俯瞰的であり、落とし穴にはまりそうなところを防いでくれる。まるで北極星のように輝き続け、迷える臨床医の助けになる。本特集ではそんな珠玉のパールを集結させた。あなたが後輩に伝えたいパールはどんなパールだろうか?
雑誌目次
総合診療34巻9号
2024年09月発行
雑誌目次
特集 今伝えたいクリニカル・パール—つくり方、使い方、活かし方
扉 フリーアクセス
著者: 玉井道裕
ページ範囲:P.990 - P.991
今月の「めざせ! 総合診療専門医!」問題
ページ範囲:P.1053 - P.1054
本問題集は、今月の特集のご執筆者に、執筆テーマに関連して「総合診療専門医なら知っておいてほしい!」「自分ならこんな試験問題をつくりたい!」という内容を自由に作成していただいたものです。力試し問題に、チャレンジしてみてください。
【総論】
❶「クリニカル・パール」とは何か? その臨床活用における注意点は?
著者: 春田淳志
ページ範囲:P.992 - P.995
「クリニカル・パール」は2012年の『JIM』(本誌の前身雑誌)で、筆者が大学院生時に初めて商業誌へ寄稿した際のテーマであった。今回は12年前を振り返り、文献を見直して、新たに情報社会やAI(artificial intelligence)などのトピックを盛り込んだ内容に書き直した。定義や基準などは一部再掲となることはご容赦いただきたい。
❷クリニカル・パールの生まれ方
著者: 玉井道裕
ページ範囲:P.996 - P.999
なぜか私はパールに心惹かれる。それは臨床に役立つという単純な理由からではない。
パールの表面的な言葉の意味に惹かれるのではなく、そのパールが生まれた経緯や物語に興味がある。いかにして、パールは生まれるのであろうか。今回はクリニカル・パールがどのように生まれるかを考察し、私見を述べさせていただく。
—スペシャル・アーティクル—アンチクリニカル・パール委員会提言〜Trust nobody!?〜
著者: 佐田竜一
ページ範囲:P.1000 - P.1003
アンチクリニカル・パール委員会の検証
クリニカル・パールは、
❶効率的な知識伝達:短く要点を絞るため、忙しい医療現場で効率的に知識伝達が可能となる
【“あの先生”のクリニカル・パールMy Best 3】
❶研修医教育で生まれたクリニカル・パール
著者: 上田剛士
ページ範囲:P.1004 - P.1006
世の中にはよいクリニカル・パールがたくさんあります。何を取り上げるべきか悩んだため、後輩たちの記憶に残っていた筆者の言葉を、クリニカル・パール代わりに紹介させていただきます。
❷大切にしているパール
著者: 植西憲達
ページ範囲:P.1008 - P.1011
My Bestクリニカル・パール❶その対症療法に向けた情熱を病歴にそそげ
筆者は集中治療医(兼総合内科医)としてICUで勤務しています。ICUでは人工呼吸器、体外循環、血液透析(浄化)に代表されるような“積極的な”治療がいろいろと行われます。そして、こういった治療を適切かつ安全に行うには相当のトレーニングを必要としますし、ICUで医師たちは多くの時間をこういった治療に使います。
ICUでは当然ながら疾患の重症度や緊急性が高く、さまざまなことを同時に行う必要があり、患者入室時などは非常にバタバタとします。いろいろな処置の準備や施行、患者や家族からの同意書の取得や説明、各部門への連絡、必要な科への相談、場合によっては緊急手術や処置の準備、いろいろな薬剤のオーダーなど、あっという間に時間が経過します。ところが注意しないと、この多忙な業務の中でついつい病歴の確認が後回しになってしまうことがあり、それで診断が遅れてしまうということが起こりえます。ICUで行われる治療は、生命を維持するためにとても重要な治療です。しかし、忘れてはいけないことはこれらの治療の多くは全身管理という名の対症療法です。この対症療法は生命維持のために重要なのですが、同じくらい原因疾患を診断してその根治治療を行うことが重要なのは言うまでもありません。「適切な診断と治療」。これがないと、患者の多くは助かりません。ICUでは全身管理と診断(と診断に基づいた根治治療)の両輪を回すことが重要なのです。
❸2024年Dr. Kiyotaの3つのクリニカル・パールズ
著者: 清田雅智
ページ範囲:P.1012 - P.1015
My Bestクリニカル・パール❶RPRは思慮なくオーダーされるが、解釈には深い思慮が必要
梅毒は2021年頃から世界的流行下にあり、国内でも同様に増加を認め、1999年の全例把握開始以来の最多数を更新している1)。2023年になってから、当院の総合診療科でも外来で梅毒を診断して治療するという事例が多くなり、週に2人も治療したことがあった(内科の外来ですよ!)。個人的に経験した院内の梅毒は、2009年に珍しい鎖骨骨炎で顕在化した2期梅毒と、神経梅毒のコンサルト症例を合わせて3例程度であった。実際には「術前検査でRPR(rapid plasma reagin)陽性になり、その判断がわからない」という相談を受けたものの、高齢者の無症状な生物学的偽陽性(biologically false positive : BPF)であったというのが大半である。2005年にMayo Clinicに留学した時に、そもそもBPFと真の感染を分けるのにRPR 16倍のカットオフを設定した由来に興味をもった。しかし、文献や教科書を読んでも、その起源を当時見つけることができなかった。とある本に、「梅毒感染の早期には抗カルジオリピン抗体が他の疾患と比べて極端に高くなることが経験的に知られていたので、診断の基準とした」という記述を確認したにすぎなかった。
しかし、Mayo Clinicでの衝撃は、いわゆる“術前感染症検査”というのが全くされていないことだった。現地の医師に尋ねると、「そもそも何で手術をする前に、梅毒やB型肝炎やC型肝炎を確認するの? その結果によって手術の方針は変わるの?」と問われ、逆にハッとさせられた。何も考えていなかったという、ルーチンワークの怖さである。当時の日本では、術中の針刺しによる血液経由の感染を心配して術前検査をしていた印象である。陽性者の場合、布の術衣を使い捨てに変えたりしていた。しかし、今や術衣はすべてディスポーザブルであるし、針刺し時には、発生後に患者へ説明して検査をするのが妥当なので、そもそも術前に検査する理由などないのである。術前の検査結果によって針刺し自体は防げないし、通常は術前に調べないHIV(ヒト免疫不全ウイルス)は、針刺しを考えるのであれば無視するのは問題でもある。RPRは本来なら梅毒の診断時にしかオーダーする必要はないので、術前検査なら全く無思慮だと思っていた。
❹想起すること、解像度を上げること、タイミングを見極めること
著者: 具芳明
ページ範囲:P.1016 - P.1018
My Bestクリニカル・パール❶誰かが結核かもと言ったら、否定できるまでは結核である
結核は過去の病気ではない。肺結核は感染対策の観点からも重要である。排菌している肺結核であれば、空気予防策をとらなくてはならないからである。
筆者は感染症を専門とし、さまざまな医療機関で感染症診療に関わってきたが、結核を100%適切に診断できる自信はない。誰にでも感染しうる感染症であることや、さまざまな病態をとったり非典型的な画像所見を示したりするなど、しばしば臨床医の裏をかくような振る舞いをするからである。当然のことながら、「T-SPOT®. TB検査が陰性だから結核を除外できた」とは口が裂けても言えない。
❺ラベンダーサイン
著者: 國松淳和
ページ範囲:P.1019 - P.1021
My Bestクリニカル・パール❶ラベンダーサイン
当院のとある外来診察ブースでは、放射線画像を表示するパソコンディスプレイの壁紙(デスクトップの背景画像、デスクトップピクチャ)が、一面に広がるラベンダー畑の写真になっている。画像検査や血液検査の結果を患者に見せる時には、このディスプレイに表示させ説明に用いる。しかし、検査結果説明以外の場面では、そのパソコン画面は使わないのでデスクトップピクチャの画像のままとなっており、すなわち綺麗なラベンダー畑の風景写真が表示されたままになっている。
普通の患者は、そこは診察室であり医師と患者が診療中であるという状況である以上、よほど打ち解けていない限りその画像を話題にすることはない。しかしある患者群は、そのラベンダー画像に反応する。結論から言うと、軽度認知障害〔いわゆるmild cognitive impairment(MCI)〕であろう人たちがそうである。とりわけAlzheimer型の場合に多い。
❻Taroの診断型クリニカル・パール集より
著者: 志水太郎
ページ範囲:P.1022 - P.1024
クリニカル・パール(以下、パール)を上手につくるヒントは、その情報(現象、技術、症候、疾患など)の特異的な部分に着目して言語化を図り、それが実用性をもつことを確認し、そのうえで覚えやすく語感のよい“刺さる”言葉で、できる限り短文にまとめることだと思う。自身のコア・インタレストがdiagnostic medicine(診断医学)であるため、本稿では診断に関連したパールをご紹介したい。
❼プロフェッショナリズムとは「目的に対する単純強固な意思、日々の愚直な継続」—福島県立医科大学元学長 故・菊地臣一先生のクリニカル・パール
著者: 仲田和正
ページ範囲:P.1026 - P.1029
以前『外科手術に上達くなる法—トップナイフたちの鍛錬法』(シービーアール、2009年)という本を上梓しました。外科系のトップナイフの先生方と対談しその方々の哲学や、実際にどのように手術の鍛錬をしてきたかをお聞きし、経験を科学にしたいという思いの企画です。
その際、福島県立医科大学学長(当時)の菊地臣一先生と対談するという、私にとっては願ってもない機会を得ました。その菊地先生のクリニカル・パールが上記の3つであり、深く感動しました。私の娘(ピアニスト)にもこの3つを教えたところ、涙を流していました。
❽私のクリニカル・パール
著者: 藤沼康樹
ページ範囲:P.1030 - P.1032
My Bestクリニカル・パール❶「既往歴」は存在しない
よく医師による症例プレゼンテーションでは、主訴、現病歴、既往歴、生活歴、家族歴などと患者情報が分散して述べられる。これが整理されたプレゼンテーションの枠組みとされ、あたりまえのように卒前医学教育からくりかえし使われている。この枠組みでは、当該の主訴に関する診断と治療に資するための情報として既往歴や生活歴、家族歴が集められ、それらは「背景情報」と言われる。プライマリ・ケアの現場では、患者の相談内容の主たるテーマが職業由来のケースも少なくないことはほぼ同意が得られるだろう。では、既往歴はどうだろうか? たとえば「10年前に胃癌で胃切除」は終わった問題なのか? 家族歴で、「子どもは息子が3人いるが、長女は4歳時に他界した」と患者から得た情報は「あ〜そうなんですね」となんとなく答えてよい問題なのだろうか? もしかしたら「また癌になるのではないか?」「入院や手術は二度と経験したくない」「死んだ娘に謝りたいことがある」などの気持ちがあったら、それは現在の医療やケアに深く関係する問題となっている可能性があるのではないだろうか。
トラウマインフォームドケア(TIC)とは、支援に携わる人たちがトラウマについての知識や対応を身に付け、支援の対象となる人たちに「トラウマがあるかもしれない」という視点をもって関わる支援の枠組みのことと言えるが1)、患者は上述した既往歴を大なり小なりトラウマとして捉え、心に傷を負う経験と考えるというのが筆者の臨床上のパールである。
【継承された“とっておきパール”】
❶「結核らしい影」というものはあるが、「結核らしくない影」というものはない
著者: 九鬼隆家
ページ範囲:P.1034 - P.1035
「結核らしい影」というのは、肺の上葉(下葉なら上方の区域)に多く、小葉中心性の粒状影や散布影、“tree in bud lesion”などと称され、空洞病変を伴えばさらに典型的である。
「結核らしくない影」というのは、通常の肺炎や心不全で見られるようなベタっとした浸潤影や、間質性肺炎で見られるようなすりガラス影、肺癌で見られるような腫瘤影など、その他のさまざまな陰影のことであり、「これがあったら結核は否定的」と言えるような所見はない。
❷内科に急変なし! 入院中の患者に悪いことが起こったら自分の手を見ろ!
著者: 佐々木陽典
ページ範囲:P.1036 - P.1037
このパールは入院患者の急変や発熱などのイベントに備える内科医の心構えを示した2つのパールを組み合わせた合成パールである。
❸高齢×男性×喫煙者。臍から下の急な症状はAAAカメレオンを除外せよ!
著者: 柴﨑俊一
ページ範囲:P.1038 - P.1038
中規模病院でホスピタリストとして働いているさなか、自院他院問わず、診断エラーが目に付くようになった。患者はもちろん、医師たちを診断エラーで訴訟にならないよう守る必要があると感じた。トラブルになりやすい疾患はだいたい決まっており、くも膜下出血、急性心筋梗塞、大動脈解離、肺塞栓症、腹部大動脈瘤、虫垂炎、絞扼性腸閉塞、急性喉頭蓋炎、化膿性脊椎炎などらしい1,2)。これらのピットフォールにハマらないようあれこれ模索するなかで、このクリニカル・パールが生まれた。
❹付き添いや家族との関係性や呼び名を決めつけるべからず
著者: 柴田綾子
ページ範囲:P.1040 - P.1041
外来や入院中に患者に付き添ってくる人は多い。患者との関係性(夫・妻・母親・父親)を医療者の思い込みで進めてしまったり、呼び名(彼氏・彼女)を決めつけることでLGBTQsの方を排除してしまう可能性がある。
日本におけるLGBTQsは約3〜10%で1,2)、左利きの人と同じくらいの割合だと報告されている。一方LGBTQsの66%が医療機関受診時に困難を経験しており、20%が医療者から「LGBTQsでないこと」を前提とした質問や発言があったと報告している(n=961、LGBTQ医療福祉調査2023)3)。
❺患者の人生を診よう
著者: 陶山恭博
ページ範囲:P.1043 - P.1043
人生を診るのがrheumatologistです。膠原病関連疾患の多くは、高血圧症や気管支喘息のように一生お付き合いする疾患になります。外来でお会いする時間は長期になり、たとえば、若い女性の患者さんであれば結婚、妊娠・出産、職場復帰などのライフイベントを共に経験することになります。昭和の過去のカルテを見直していると、「膠原病だから結婚できない、出産してはいけないと言われた」という悲しい記録を目にすることもあります。しかし、時代は平成も越えて令和です。早期診断・早期加療が可能となり、治療薬の選択肢も増えています。「rheumatologistは患者さんを治療して半人前、寛解した患者さんが出産したら一人前」ということばを耳にするようになるほど、膠原病と診断されても“普通の人生”を送ることができるようになっています。そのため、rheumatologistの診療は“do処方”(前回と同じ処方)を続けるのではなく、疾患活動性、患者さんの環境やライフステージ、経済状況などに合わせて治療方針を調節していくのが実際です。
治療方針に迷った時は、“どういう方向に進むと患者さんは一番幸せか”を意識すると答えは見えてきます。バイタルサインが崩れた状況に追い込まれたとしても、“患者さんご本人・ご家族・ご友人のことを想う”と、もう少しだけ踏ん張ってベッドサイドにいることや知恵を絞ることが可能になります。クリニカル・パールとしては「膠原病を疑った時は血液培養をとる時」「諦めなければループスは改善する」「リウマチ性多発筋痛症(polymyalgia rheumatica:PMR)でふくらはぎの痛みがあれば血管炎を疑う」など診断に関するtipsはいくつかありますが、臨床の現場では治療も大切です。そこで、今回は筆者が先人から受け継いだ治療のことば、“患者さんの人生を診よう”を伝えたいと思います。
❻prepared mind
著者: 瀧宮龍一
ページ範囲:P.1044 - P.1045
◦心房細動患者の臓器塞栓症を見たら、フルで神経診察せよ
研修医時分のことである。かかりつけのない50代女性が、左腰痛で早朝に救急搬送された。尿管結石を疑ったが、モニターを付けると心房細動である。“これは”と思い造影CTを撮ると、予想どおり左腎梗塞が見つかり、入院でヘパリンを開始した。しかしその夜、病棟で看護師が本人確認すると、自分の名前が言えなかったのである。すぐに頭部MRIを撮ると、左脳梗塞で運動性失語をきたしていた。わずかに出血も合併しており、ヘパリンが中止になった。振り返ってみると、初診時から、麻痺はないが自分の住所を話しづらそうにしている様子があった(が、気にも留めていなかった)。
心房細動患者の臓器塞栓症をみたら、ほかにも塞栓症を合併しているはずと思って、注意深く診察し直す必要がある。それが脳梗塞、特に皮質動脈の塞栓であれば、高次脳機能のみ障害され、麻痺や呂律不良など典型的な脳梗塞症状を欠くこともある。このような症例には普段評価しない失語・失行・失認といった高次脳機能まで神経診察する必要がある。出血性梗塞にヘパリンを開始してしまった痛恨の1例だが、上記パールが深く刻まれた。
❼治り方のディテールは、経験でしか学べない
著者: 武田孝一
ページ範囲:P.1046 - P.1046
「蜂窩織炎に対して抗菌薬を開始した後」「帯状疱疹に対してバラシクロビルを投与した後」「抗菌薬による薬疹を発症し、被疑薬を中止した後」、1〜2日経っても皮疹が改善したとは言えない時、しばしば医師や患者は不安になる。しかし、事前に皆が「明日〜明後日までは皮疹が拡大しうるが、普通は3日以内にピークを越え、1週間ほどかけてかなりよくなっていく」という流れを共有すれば、その不安は大きく軽減されるだろう。
術後の腹腔内感染症を念頭に抗菌薬を開始後、(5〜)7日経過してもC反応性蛋白(CRP)が下がっていない時、「CRPは参考にするべきではない」という考えに固執していると、「ドレナージを要する膿瘍の存在を念頭に、造影CTを撮像する」というアクションの遅れにつながりうる。ほかにも、「炎症性筋炎に対してグルココルチコイドを開始後、筋力はどのくらいのペースで改善していくのか」「バンコマイシンによる高度の腎毒性が顕在化した際に、薬剤中止後、いつ頃から腎機能は回復し始めるのか」「グルココルチコイドによるムーンフェイスは、減量とともにいつ頃から消退するのか」…など、枚挙にいとまがない。これらすべてにおいて、医療者がいつ頃から、どのようなペースで各治療指標が改善していくのか、つまり「病態が治療していく一般的な過程」を熟知しているか否かが、患者への説明内容や、日々の意思決定の精度に多大なる影響を及ぼすことは、臨床医なら容易に想像がつくであろう。
❽Do small things with great Love
著者: 鍋島志穂
ページ範囲:P.1047 - P.1047
今から20年ほど前、医学部の学生だった私は、春休みにインド・コルカタにあるマザー・テレサの施設「カリガート(死を待つ人の家)」でのボランティア活動に参加した。毎朝、カリガートに行く前に、マザーハウス(マザーの立ち上げたMissionaries of Charityの本部であり、マザーやシスターたちの家)で聖書の一節を音読し、聖歌を歌う。その建物の一室にマザー・テレサが眠る棺があり、誰でもそこを訪れることができる。その棺の上に、オレンジ色の花びらを使ってマザーの言葉が書かれていた。その時にそこで出合った言葉が“Do small things with great Love”であった。「小さなことに大きな愛を込めて行いなさい」というこの言葉を、それからの人生で何度も心のなかで繰り返しながら生きてきた。
私たちの生きる毎日は、当たり前に思っているけれどそうではない、たくさんの小さな幸せと奇跡の連続である。毎朝目が覚めること、ベッドから自分で起き上がり、自分の足でトイレに行き用が足せること、階段を降りてリビングで家族と「おはよう」と言い合えること、美味しくご飯が食べられること…何ともないこのような日常は、本当はかけがえのない幸せな一瞬一瞬でできているのだと思う。このことは、21歳で交通事故に遭い、意識がなく体の中にありとあらゆる管を入れられて生死をさまよった2カ月間、その後命は助かったものの、自分で寝返りさえうてず、座ることも立つことも、食べることも全くできないということをこの身を以て経験した時に衝撃にも似た感覚でわかったことなのだ。
❾嘔吐がなく増悪傾向のない正中部の腹痛は重篤なことが少ない
著者: 原田拓
ページ範囲:P.1049 - P.1049
上記は、過去の職場の上司から教わったものです。正中部の痛みに波がある腹痛で、腹膜刺激徴候や増悪傾向や嘔吐がなく、鎮痛も成功しているならば、経験上、重篤な疾患の頻度は少ないというパールでした。
急性腹痛の診療において、重篤な疾患を見逃さないことは大前提で、それを否定するつもりはありません。しかし、「重篤な疾患が否定できないから」という理由ですべての急性腹痛患者にCT撮像をするわけにもいきません。したがって、CTの検査前確率が低い、あるいはCT検査を行わずにフォローアップをする患者さんをどのように判断するかというのは臨床的に重要な課題と言えます。
❿目の前で起きた血小板減少は、専門家不要!
著者: 藤野貴久
ページ範囲:P.1050 - P.1051
さまざまな血小板減少のコンサルテーションを受けるなかで、上司がぼそっとつぶやく言葉から学ぶことも多い。上記はそのなかから生まれたパールである。科学的根拠があるわけでもなく、調べても類書に書かれている有名な経験則でもない。しかし、これほどにシンプルで的を射たパールを他に知らない、そんなとっておきのパールである。
セッティングは病棟でも外来でもよいが、若手医師の皆さんは病棟で血小板減少と出合うことが多いだろう。このパールは特に血小板減少がない患者に、血小板減少が急性に起こった場合に威力を発揮する。目の前で血小板減少が起こった患者の、50%以上は薬剤性か、ヘパリン起因性血小板減少症(heparin-induced thrombocytopenia:HIT)、つまり非血液腫瘍である。よって、まずはこれらの病態かどうかを評価する必要がある(血小板減少を見た場合に、まず行うべきは「重症度/緊急度の評価」と「輸血必要性」だが、本稿では割愛する)。
⓫外傷に至った原因を突き止めることは重要である。しかしながら、その原因を突き止めた後、外傷そのものに対する再評価をすることはさらに重要である
著者: 山里一志
ページ範囲:P.1052 - P.1052
頻回の転倒の原因としてラクナ梗塞が同定されるも、入院後に急激な心肺停止に至った事例
患者:80歳、男性
主訴・搬送理由:転倒、歩行困難。
病歴と入院後の経過:高血圧症以外には特記すべき既往はなく、身体機能に問題なく日常生活を送っていた。搬送当日の朝より自宅内で頻回に転倒し、歩行が困難であることから搬送当日の夕に家人により救急要請されて搬送となった。搬送時、左上下肢のごく軽微な片麻痺と顕著な失調を認め、頭部MRI検査で右内包後脚近傍に梗塞巣を認めた。夜間の救急対応を行った総合診療医は「ラクナ梗塞によるataxic hemiparesis1,2)によって頻回に転倒した」とのアセスメントで入院治療を開始したが、数時間後に急激な酸素飽和度低下、徐脈の先行する心肺停止に至り、蘇生を試みるも回復することなく死亡した。事後の検証で自宅内での転倒の際に頭部打撲もあり、救急搬送時には四肢のしびれ感も訴えていたことから、外傷性頸髄損傷が併存したものと推定された。
Editorial
“クリニカル・パール”から始まる物語の扉を開こう! フリーアクセス
著者: 玉井道裕
ページ範囲:P.989 - P.989
まさか、研修医時代から読み、勉強してきた雑誌『総合診療』の編集をさせてもらえるとは夢にも思わなかった。どんな特集を組もうかと考えた時、私にしかできない編集をしようと決意した。クリニカル・パール特集なら、それが可能かもしれない。どなたに原稿を依頼するかは悩んだが、自分の医師人生に大きな影響を与えてくれた先生を候補に挙げさせてもらった。執筆者の候補リストを作成すると、たくさんの医師の名前が浮かんだ。どの方にお願いするか迷った。そして、そのリストを見て、自分がこれほど多くの方々に支えられてきたことを、しみじみと実感した。読者の皆さんも、自分を育ててくれた“先生特集”を作るとしたら、誰に執筆を依頼するか考えてみてほしい。
私は恵まれた医師人生を歩んできた。多くの素晴らしい出会いと心に残る言葉をいただき、今の自分の医師像が形成されてきた。エビデンスはインターネットで調べれば出てくるが、自分が見聞きした言葉は検索したとしても出てこない。それは自分の中にしか残っていない。そして、それは一人ひとり違うはずである。各々の人生が異なるように、医師としての人生もまた異なる。あなたが医師として過ごした日々で、記憶に残っているのはどんな時だろうか。そこにはどんな言葉があったのであろうか。
ゲストライブ〜Improvisation〜・27
クリニカル・パールの原点—医学における「言葉」の効用
著者: 佐藤泰吾 , 玉井道裕 , 佐田竜一
ページ範囲:P.977 - P.984
「evidence based medicine」とは言われるが、臨床の問題はevidenceだけですべて解決するわけではない。以前は今よりevidenceが希薄な領域が多く、手探り状態で臨床の中を進んできたのではないだろうか。そんな暗闇の中を一緒に進んでくれるのが、上司や指導医の存在である。指導医の言葉が懐中電灯のような小さな光となって暗闇を照らし、私たちは歩むことができている。私に尊敬すべき指導医や上司がいるように、その指導医にもまた指導医がいたはずだ。脈々と受け継がれてきた大切な言葉は、いつしか「クリニカル・パール」となっていく。自分が聞いて心に残った言葉から、臨床教育の中でふと発した自分の言葉。その言葉が生まれた背景や要因は何か? 本座談会では、「クリニカル・パールの原点」を探す旅に出かけたい。
対談|医のアートを求めて・10
医療×テクノロジー—人類の進化はテクノロジーの進化と共にある
著者: 山海嘉之 , 平島修
ページ範囲:P.1055 - P.1062
正直、終始圧倒され続けた対談だった。世界初の装着型サイボーグ「HAL」の開発者である山海嘉之さんから、テクノロジーと医療についてのお考えを伺うつもりが、話は医療だけにとどまらず、人類の進化にまでおよび、人間がテクノロジーと共に進化する新時代にどのような価値観で生きるべきかという壮大な話へと広がっていった。そして山海さんは子ども時代に思い描いた純粋な未来予想図を、ワクワクとチャレンジしながら、1つずつ形にされていたのだった。
今回、山海さんのこれまでの活動を通して、医療とテクノロジーの未来について、読者の皆さんに何かを感じていただけたら幸いである。(平島修)
What's your diagnosis?[261]
脛に傷
著者: 猪飼浩樹 , 岩﨑慶太 , 山本真理 , 滝澤直歩 , 藤田芳郎
ページ範囲:P.1064 - P.1068
病歴
患者:40代、男性 主訴:脛が痛い
現病歴:来院1カ月前から両足首付近の疼痛あり。労作で悪化は認めず、朝より夜間のほうが痛みを強く感じた。当初は市販のNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)で自制内の疼痛の程度であった。間欠的な痛みで疼痛を自覚しない時間帯もある。来院2週間前から左前腕に疼痛が出現。夜間痛で眠れなこともあった。その後、両下腿の疼痛も出現し、痛みは経時的に増悪傾向であった。来院3日前に近医総合病院の整形外科を受診し、両下腿のX線写真を撮像された。「骨には問題ない」と言われ、「線維筋痛症の疑い」で当科への紹介状をもらった。しかし夜間の疼痛がひどく、来院当日の夜間に動けず救急外来を受診した。受診時の痛みの部位は両膝蓋骨より3cm以上以遠〜足関節より3cm近位の下腿前面であった。
陰性所見:体重減少、発熱、悪寒戦慄、発疹の自覚、頭痛、めまい、難聴、耳鳴り、鼻出血、呼吸困難、咳嗽、喀痰、血痰、胸痛、動悸、間欠性跛行、浮腫の自覚、悪心・嘔吐、腹痛、下痢、膀胱刺激症状、しびれ、頭痛、複視、皮疹の自覚
生活歴:事務業、喫煙は5本/日、飲酒は缶ビール1本/日、不特定多数との性交渉は否定
既往歴:右脛骨骨折(小児期、外傷による)
内服薬:市販薬のNSAIDs
家族歴:特記事項なし
オール沖縄!カンファレンス|レジデントの対応と指導医の考えVer.2.0・92
「首下がり」は首の病気なのか?
著者: 金沢章弘 , 安次嶺宏哉 , 嵩原安彦 , 徳田安春 , 仲里信彦 , 鈴木智晴 , 佐藤直行
ページ範囲:P.1069 - P.1073
CASE
患者:70歳、女性。
主訴:呼吸困難、食事がとれない。
現病歴:来院2カ月ほど前に転倒、その後特に問題なく経過していたが、X-14日前から首が前下がりになり持ち上げにくくなってきた。X-5日目に当院整形外科を受診。頸部のX線写真・CT画像では特に問題はないと判断され、帰宅となった。帰宅後周囲は苦しそうな印象を持っていたが、本人は自覚症状なく生活していた。X日に呼吸困難を訴え、当院救急外来を受診した。
既往歴:未破裂脳動脈瘤(ステント併用瘤内塞栓術施行後)、被殻出血、内頸動脈狭窄、高血圧症、脂質異常症。
内服薬:スピロノラクトン25mg 0.5錠1日1回(朝食後)、アロプリノール50mg 1錠1日1回(朝食後)、カプトプリル12.5mg 2錠1日2回(朝・夕食後)、ニフェジピン10mg 2錠1日2回(朝・夕食後)、アトルバスタチン5mg 0.5錠1日1回(夕食後)、ミラべグロン50mg 1錠1日1回(昼食後)。
生活歴:喫煙なし。
【エッセイ】アスクレピオスの杖—想い出の診療録・53
ソフィアとフロネシス
著者: 松村正巳
ページ範囲:P.1074 - P.1075
本連載は、毎月替わる著者が、これまでの診療で心に残る患者さんとの出会いや、人生を変えた出来事を、エッセイにまとめてお届けします。
ジェネラリストに必要な ご遺体の診断学・18
現場で役立つ医療事故調査の実際
著者: 森田沙斗武
ページ範囲:P.1076 - P.1080
Case
患者:85歳、男性
既往歴:慢性心不全、慢性腎不全
病歴:妻との2人暮らし。慢性心不全のコントロール目的に当院循環器内科に定期的に通院していた。某日発熱を主訴に予約外受診し、肺炎像を認めた。体温38.2℃、SpO2 85%(room air)、血圧162/90mmHgと低酸素血症を認め、緊急入院。酸素投与が開始されO2 3L/分吸入下でSpO2 95%、血液培養および痰培養を提出後、抗菌薬による加療が開始された。入院時、急変時の対応について家族に意向を伺ったところ「人工呼吸器装着は希望しない」ということであり、急変時蘇生措置拒否(DNAR)の方針となった。
入院第2病日も38℃以上の発熱が続き、呼吸は促迫しており、血圧は高めに推移していたため、モニター装着を指示した。
入院第3病日午前6時に看護師により抗菌薬の点滴を施行。午前7時頃、他患者に処方された抗菌薬はないが本患者の抗菌薬がナースステーションに残っていることに看護師が気づき、慌てて本患者を訪室するもバイタルに大きな変化を認めなかった。当直医師に報告し、医療安全責任者や主治医の出勤を待ってから患者説明や対応を相談することとなった。
午前8時50分、モニターアラームが鳴り訪室したところ、心肺停止の本患者を発見した。心臓マッサージを開始し、主治医に連絡した。午前8時53分、主治医が到着し急変時DNARの意向であることから、救急救命処置の中止を指示した。妻に連絡し、妻の到着を待って午前9時48分に死亡確認とした。抗菌薬の取り違いが起こったこと、基礎疾患のある高齢者の肺炎であり入院時より重篤であったことを説明したところ、妻から「これまでよくしてもらいましたし、入院時から覚悟をしていました。特に病院に不満はありません」と言われたため、死因を「細菌性肺炎」とした死亡診断書を発行した。
医療安全責任者から、医療事故調査のための解剖を勧めなくてよかったのかと尋ねられたため「遺族が納得しているものをわざわざ解剖しても、問題が大きくなるだけ」と答えたが、心中はこの対応でよかったのか不安だった。
臨床医のためのライフハック│限りある時間を有効に使う仕事術・18
—メンタルヘルスマネジメント—現代の臨床医が自分のメンタルヘルスを保つには?
著者: 中島啓
ページ範囲:P.1083 - P.1087
時間がない! 臨床医の仕事は診療だけにあらず。事務、教育、自己学習、研究、学会発表、情報発信、所属組織の運営などなど、尽きることはありません。もちろんプライベートの生活もあり、「時間不足」は臨床医の永遠の課題です。では、一度きりの“医師人生”の限られた時間を、どう有効に使うのか? 筆者が培ってきた「ライフハック(仕事術)」のすべてを、余すところなく開陳します。
#総合診療
#今月の特集関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.1015 - P.1015
#今月の特集関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.1035 - P.1035
#今月の特集関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.1037 - P.1037
#今月の特集関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.1042 - P.1042
#今月の特集関連本 フリーアクセス
ページ範囲:P.1045 - P.1045
#医学書院の新刊 フリーアクセス
ページ範囲:P.1081 - P.1082
#書評:「卓越したジェネラリスト診療」入門—複雑困難な時代を生き抜く臨床医のメソッド フリーアクセス
著者: 酒井郁子
ページ範囲:P.1033 - P.1033
本書は,家庭医としての藤沼康樹氏(医療福祉生協連家庭医療学開発センター長)が,これまでの自身のジェネラリストとしての実践知を,多様な領域の大理論や概念モデルと照らし合わせ解説し,今後の発展の方向性を論述したものである。
第Ⅰ章「プライマリ・ケア外来の一般要件」は,家庭医としての実践を始めたばかりの方へのパール集となっており,独り立ちする際に「ここは気をつけよう」と先輩としてアドバイスするような内容となっている。第Ⅱ章「卓越したジェネラリスト診療の実践」では,既存の大理論や概念モデルについて基礎知識の整理を行い,かつ“医師らしく”考えるその方法は「診断推論」だけではなく,患者を理解していくにはいろいろな見方があるということを,豊富な事例を基に解説している。特にこの章の4〜8節は,看護学領域でのパトリシア・ベナーの著書『From Novice to Expert』をほうふつとさせる内容でエキスパートになっていく(卓越していく)ときのものの見方・考え方が具体的に論述されている。第Ⅲ章「卓越性を支える『チーム』と『教育』」では,多職種連携教育の3つのメリット「チームスキルの獲得」「共同学習の方法の獲得」「省察と経験学習の方法の獲得」のうち共同学習・省察・経験学習について考察している。専門職連携教育は,チームビルディングなどのチームスキルの獲得のみに焦点が当てられがちだが,実は,チームを俯瞰し,どんなチームであってもその職種の役割を果たし,かつ他の職種の役割発揮を支援する「共同学習」「省察」「経験学習」のスキルが必要である。家庭医として,というか,臨床家として,全ての職種が長く活動するために必須のコンピテンシーであると思う。
#書評:—《ジェネラリストBOOKS》—総合内科対策本部—これってどうする!? フリーアクセス
著者: 上田剛士
ページ範囲:P.1048 - P.1048
『総合内科対策本部 これってどうする!?』は、総合内科の現場で直面する多岐にわたる難症例や珍相談に対する具体的な対応策を紹介する書籍です。総合内科の魅力や奥深さを余すところなく伝える一冊であり、総合内科医としての臨床能力を高めるのにうってつけの書籍です。
総合内科とは、多様な症状や病態を総合的に診療する専門分野であり、まさに「医療の総合力」が問われる場です。本書では「微熱が続く」「リンパ節が腫れている」「両足がむくむ」「爪が黄色い」といった症例が次々と紹介され、それに対する具体的なアプローチが述べられています。総合内科の診療現場で必要な思考過程を鍛え、ピットフォールを知るにふさわしい症例が厳選されて書かれています。
#書評:発達障害Q&A—臨床の疑問に応える104問 フリーアクセス
著者: 小平雅基
ページ範囲:P.1088 - P.1089
本書は『精神医学』誌2023年5月増大号特集『いま、知っておきたい発達障害Q&A 98』に、追加の質問を加えバージョンアップして書籍化したものである。日常診療で生じる多岐にわたる実臨床に沿った疑問に対して、発達障害の臨床の第一線で活躍する専門家たちが回答している。医療から福祉・教育領域の支援者まで幅広い読者の知りたいことにQ&A形式でわかりやすく解説しており、発達障害臨床の指針となる一冊といえるだろう。
今では「発達障害」という言葉は世間一般に広く知れわたるようになっているが、その概念は時代とともに拡大してきた経過がある。歴史をさかのぼると1963年に米国で法律用語として誕生した「発達障害」という用語だが、さまざまな変遷を経て日本でその社会的理解や支援が促進される転換期となったのは2005年「発達障害者支援法」の施行といえる。ただし非営利団体が行ったある調査によれば、「発達障害」の社会的認知度は高い一方で、当事者や家族の多くは「十分に理解されていない」と感じているというギャップが存在することも報告されている。これは社会的な認知度が高まる一方、ともすればスティグマになりかねない危うさを示しているともいえよう。同様に「グレーゾーン」「Highly Sensitive Child」などといった言葉も発達障害と絡んで臨床現場に広がってきているが、これらもまた整理が難しく、そのような用語を使用する背景には、さまざまな医師側の葛藤が見え隠れしているようにも思える。
--------------------
目次 フリーアクセス
ページ範囲:P.986 - P.987
『総合診療』編集方針 フリーアクセス
ページ範囲:P.985 - P.985
1991年に創刊した弊誌は、2015年に『JIM』より『総合診療』に誌名を変更いたしました。その後も高齢化はさらに進み、社会構造や価値観、さらなる科学技術の進歩など、日本の医療を取り巻く状況は刻々と変化し続けています。地域医療の真価が問われ、ジェネラルに診ることがいっそう求められる時代となり、ますます「総合診療」への期待が高まってきました。これまで以上に多岐にわたる知識・技術、そして思想・価値観の共有が必要とされています。そこで弊誌は、さらなる誌面の充実を図るべく、2017年にリニューアルをいたしました。本誌は、今後も下記の「編集方針」のもと、既存の価値にとらわれることなく、また診療現場からの要請に応え、読者ならびに執筆者のみなさまとともに、日本の総合診療の新たな未来を切り拓いていく所存です。
2018年1月 『総合診療』編集委員会
読者アンケート
ページ範囲:P.1091 - P.1091
『総合診療』バックナンバーのご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.1092 - P.1093
お得な年間購読のご案内 フリーアクセス
ページ範囲:P.1093 - P.1094
次号予告 フリーアクセス
ページ範囲:P.1095 - P.1096
基本情報
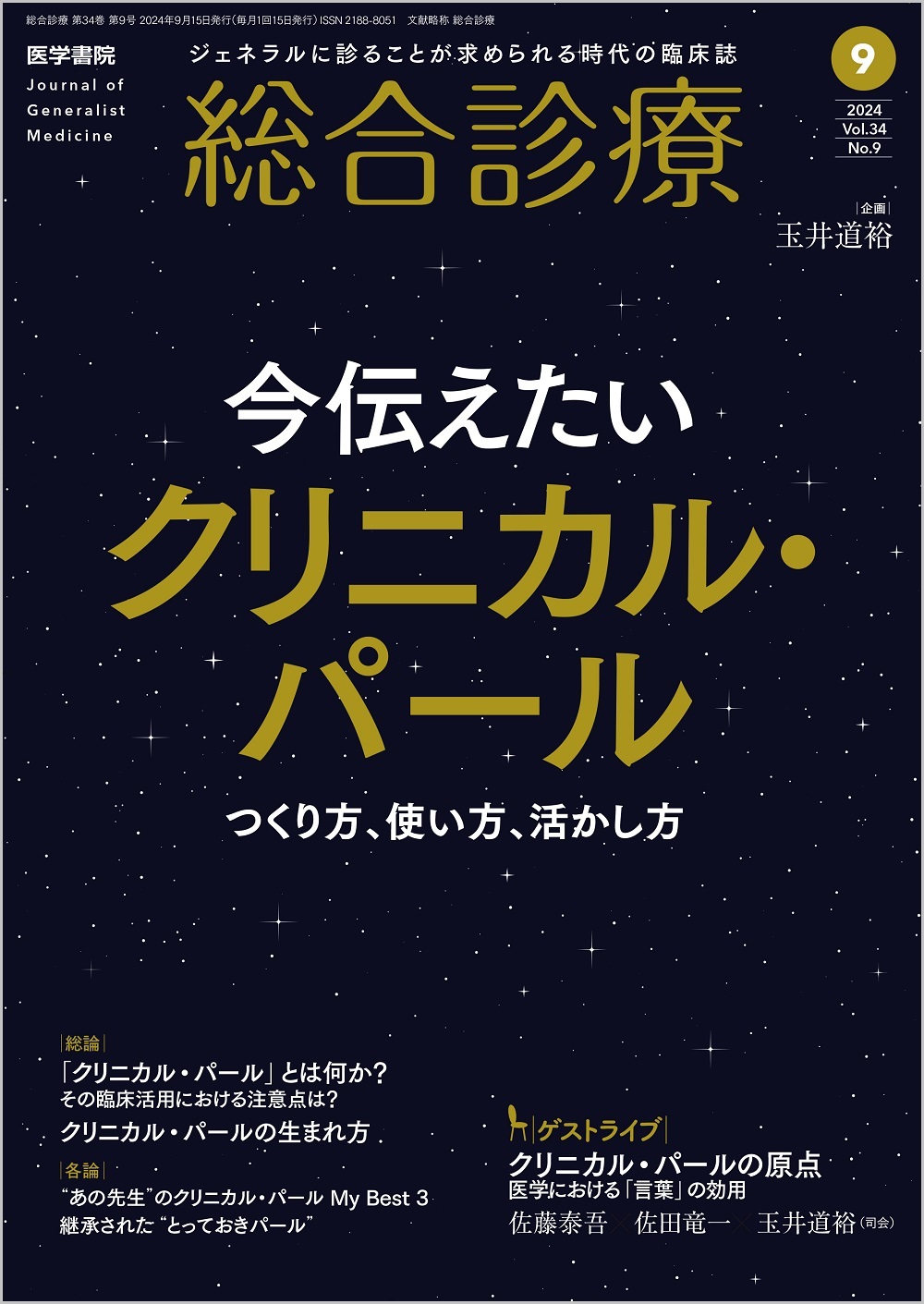
バックナンバー
34巻12号(2024年12月発行)
特集 妊婦・褥婦が外来に来たらUpdate—症状対応からワクチン・プラネタリーヘルスまで
34巻11号(2024年11月発行)
特集 電子カルテとベッドサイドの壁を打ち破る!—患者情報の「言語化」への挑戦
34巻10号(2024年10月発行)
特集 化かしが得意なカメレオンな疾患を捕まえろ!—よくある騙され方のゲシュタルト
34巻9号(2024年9月発行)
特集 今伝えたいクリニカル・パール—つくり方、使い方、活かし方
34巻8号(2024年8月発行)
特集 ストーン・ウォーズ 果てしなき“石”と医師との闘い
34巻7号(2024年7月発行)
特集 どうする!? 健診異常—これってホントに異常なの? どう説明する?
34巻6号(2024年6月発行)
特集 医師のウェルビーイング
34巻5号(2024年5月発行)
特集 —優柔不断にサヨウナラ!—あなたの「臨床判断」を高めるケーススタディ11選
34巻4号(2024年4月発行)
特集 困ったときの漢方—この症状に役立ちます!
34巻3号(2024年3月発行)
特集 —え、ウソ!実は◯◯だった!?—“コモンディジーズ”の診断ピットフォール
34巻2号(2024年2月発行)
特集 日常診療で出合う筋骨格疾患—脳神経内科と整形外科からのアプローチ
34巻1号(2024年1月発行)
特集 —“体験型”臨床クイズで習得する!—フィジカル診断エクセレンス
33巻12号(2023年12月発行)
特集 海の外へ渡る航行者を診る—アウトバウンドにまつわるetc.
33巻11号(2023年11月発行)
特集 —続・総合診療外来に“実装”したい—最新エビデンスMy Best 3
33巻10号(2023年10月発行)
特集 ○×クイズ110問!日常診療アップグレード—Choosing WiselyとHigh Value Careを学ぼう
33巻9号(2023年9月発行)
特集 ジェネラリストのための「発達障害(神経発達症)」入門
33巻8号(2023年8月発行)
特集 都市のプライマリ・ケア—「見えにくい」を「見えやすく」
33巻7号(2023年7月発行)
特集 “消去法”で考え直す「抗菌薬選択」のセオリー—広域に考え、狭域に始める
33巻6号(2023年6月発行)
特集 知っておくべき!モノクロな薬たち(注:モノクローナル抗体の話ですよ〜)
33巻5号(2023年5月発行)
特集 —疾患別“イルネススクリプト”で学ぶ—「腹痛診療」を磨き上げる22症例
33巻4号(2023年4月発行)
特集 救急対応ドリル—外来から在宅までの60問!
33巻3号(2023年3月発行)
特集 —自信がもてるようになる!—エビデンスに基づく「糖尿病診療」大全—新薬からトピックスまで
33巻2号(2023年2月発行)
特集 しびれQ&A—ビビッとシビれるクリニカルパール付き!
33巻1号(2023年1月発行)
特集 COVID-19パンデミック 振り返りと将来への備え
32巻12号(2022年12月発行)
特集 レクチャーの達人—とっておきの生ライブ付き!
32巻11号(2022年11月発行)
特集 不定愁訴にしない“MUS”診療—病態からマネジメントまで
32巻10号(2022年10月発行)
特集 日常診療に潜む「処方カスケード」—その症状、薬のせいではないですか?
32巻9号(2022年9月発行)
特集 総合診療・地域医療スキルアップドリル—こっそり学べる“特講ビデオ”つき!
32巻8号(2022年8月発行)
特集 こんなところも!“ちょいあて”エコー—POCUSお役立ちTips!
32巻7号(2022年7月発行)
特集 —どうせやせない!? やせなきゃいけない??苦手克服!—「肥満」との向き合い方講座
32巻6号(2022年6月発行)
特集 総合診療外来に“実装”したい最新エビデンス—My Best 3
32巻5号(2022年5月発行)
特集 「診断エラー」を科学する!—セッティング別 陥りやすい疾患・状況
32巻4号(2022年4月発行)
特集 えっ、これも!? 知っておきたい! 意外なアレルギー疾患
32巻3号(2022年3月発行)
特集 AI時代の医師のクリニカル・スキル—君は生き延びることができるか?
32巻2号(2022年2月発行)
特集 —withコロナ—かぜ診療の心得アップデート
32巻1号(2022年1月発行)
特集 実地医家が楽しく学ぶ 「熱」「炎症」、そして「免疫」—街場の免疫学・炎症学
31巻12号(2021年12月発行)
特集 “血が出た!”ときのリアル・アプローチ—そんな判断しちゃダメよ!
31巻11号(2021年11月発行)
特集 Q&Aで深める「むくみ診断」—正攻法も!一発診断も!外来も!病棟も!
31巻10号(2021年10月発行)
特集 医師の働き方改革—システムとマインドセットを変えよう!
31巻9号(2021年9月発行)
特集 「検査」のニューノーマル2021—この検査はもう古い? あの新検査はやるべき?
31巻8号(2021年8月発行)
特集 メンタルヘルス時代の総合診療外来—精神科医にぶっちゃけ相談してみました。
31巻7号(2021年7月発行)
特集 新時代の「在宅医療」—先進的プラクティスと最新テクノロジー
31巻6号(2021年6月発行)
特集 この診断で決まり!High Yieldな症候たち—見逃すな!キラリと光るその病歴&所見
31巻5号(2021年5月発行)
特集 臨床医のための 進化するアウトプット—学術論文からオンライン勉強会、SNSまで
31巻4号(2021年4月発行)
特集 消化器診療“虎の巻”—あなたの切実なギモンにズバリ答えます!
31巻3号(2021年3月発行)
特集 ライフステージでみる女性診療at a glance!—よくあるプロブレムを網羅しピンポイントで答えます。
31巻2号(2021年2月発行)
特集 肺炎診療のピットフォール—COVID-19から肺炎ミミックまで
31巻1号(2021年1月発行)
特別増大特集 新型コロナウイルス・パンデミック—今こそ知っておきたいこと、そして考えるべき未来
30巻12号(2020年12月発行)
特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き) Part 2
30巻11号(2020年11月発行)
特集 診断に役立つ! 教育で使える! フィジカル・エポニム!—身体所見に名を残すレジェンドたちの技と思考
30巻10号(2020年10月発行)
特集 —ポリファーマシーを回避する—エビデンスに基づく非薬物療法のススメ
30巻9号(2020年9月発行)
特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【感染症・内分泌・整形外科 編】
30巻8号(2020年8月発行)
特集 マイナーエマージェンシー門外放出—知っておくと役立つ! テクニック集
30巻7号(2020年7月発行)
特集 その倦怠感、単なる「疲れ」じゃないですよ!—筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群とミミック
30巻6号(2020年6月発行)
特集 下降期慢性疾患患者の“具合”をよくする—ジェネラリストだからできること!
30巻5号(2020年5月発行)
特集 誌上Journal Club—私を変えた激アツ論文
30巻4号(2020年4月発行)
特集 大便強ドリル—便秘・下痢・腹痛・消化器疾患に強くなる41問!
30巻3号(2020年3月発行)
特集 これではアカンで!こどもの診療—ハマりがちな11のピットフォール
30巻2号(2020年2月発行)
特集 いつ手術・インターベンションに送るの?|今でしょ! 今じゃないでしょ! 今のジョーシキ!【循環器・消化器・神経疾患編】
30巻1号(2020年1月発行)
特集 総合診療医の“若手ロールモデル”を紹介します!—私たちはどう生きるか
29巻12号(2019年12月発行)
特集 困っている“あなた”に届く 認知症診療
29巻11号(2019年11月発行)
特集 臨床写真図鑑 レアな疾患編—見逃したくない疾患のコモンな所見
29巻10号(2019年10月発行)
特集 教えて!医師のためのビジネス・スキル
29巻9号(2019年9月発行)
特集 “ヤブ化”を防ぐ!—外来診療 基本の(き)
29巻8号(2019年8月発行)
特集 —ノーモア見逃し—日常の検査と画像に潜むピットフォール
29巻7号(2019年7月発行)
特集 リウマチ・膠原病ミミック症例帖—“膠原病っぽくみえてしまう疾患たち”にだまされない!
29巻6号(2019年6月発行)
特集 皮膚科診療エクササイズ—1枚の写真から
29巻5号(2019年5月発行)
特集 一般外来で診断できたら「えっへん!」な疾患38
29巻4号(2019年4月発行)
特集 “ナゾ”の痛み診療ストラテジー|OPQRSTで読み解く
29巻3号(2019年3月発行)
特集 —あなたのギモンに答えます!—循環器診療のハードルを下げるQ&A31
29巻2号(2019年2月発行)
特集 意外な中毒、思わぬ依存、知っておきたい副作用—一般外来で!OTCも処方薬も!
29巻1号(2019年1月発行)
特集 教えて検索!—膨大な医学情報を吟味・整理するスキル
28巻12号(2018年12月発行)
特集 こんなときこそ漢方を!
28巻11号(2018年11月発行)
特集 日本一マジメな「おしっこドリル」—今これだけは押さえておきたい腎・泌尿器のモンダイ
28巻10号(2018年10月発行)
特集 クリニカル・パールPremium!—憧れのカリスマ医師はかく語りき
28巻9号(2018年9月発行)
特集 オンコ・ジェネラリスト—「がん」に強い総合診療医をめざして
28巻8号(2018年8月発行)
特集 80歳からの診療スタンダードUp to Date—Silver Standard
28巻7号(2018年7月発行)
特集 この薬だけは押さえておきたい! 総合診療医のためのSpecialist Drug 40
28巻6号(2018年6月発行)
特集 聴診・触診×エコーで診断推論!—Point-of-Care超音波(POCUS)の底力
28巻5号(2018年5月発行)
特集 “一発診断”トレーニング問題集—懸賞論文「GM Clinical Pictures」大賞発表!
28巻4号(2018年4月発行)
特集 感染症外来診療「賢医の選択」—検査・経口薬・ワクチンをどう使えばいいんですか?
28巻3号(2018年3月発行)
特集 糖尿病のリアル—現場の「困った!」にとことん答えます。
28巻2号(2018年2月発行)
特集 頭痛患者で頭が痛いんです!
28巻1号(2018年1月発行)
特集 シン・フィジカル改革宣言!—私の“神技”伝授します。
27巻12号(2017年12月発行)
特集 小児診療“苦手”克服!!—劇的Before & After
27巻11号(2017年11月発行)
特集 今そこにある、ファミリー・バイオレンス|Violence and Health
27巻10号(2017年10月発行)
特集 めまいがするんです!─特別付録Web動画付
27巻9号(2017年9月発行)
特集 うつより多い「不安」の診かた—患者も医師も安らぎたい
27巻8号(2017年8月発行)
特集 見逃しやすい内分泌疾患─このキーワード、この所見で診断する!
27巻7号(2017年7月発行)
特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 3 カリスマ編
27巻6号(2017年6月発行)
特集 「地域を診る医者」最強の養成法!
27巻5号(2017年5月発行)
特集 コミュニケーションを処方する—ユマニチュードもオープンダイアローグも入ってます!
27巻4号(2017年4月発行)
特集 病歴と診察で診断できない発熱!—その謎の賢い解き方を伝授します。
27巻3号(2017年3月発行)
特集 これがホントに必要な薬40—総合診療医の外来自家薬籠
27巻2号(2017年2月発行)
特集 The総合診療ベーシックス—白熱!「総合診療フェスin OKINAWA」ライブ・レクチャー! 一挙公開 フィジカル動画付!
27巻1号(2017年1月発行)
特集 総合診療の“夜明け”—キーマンが語り尽くした「来し方、行く末」
26巻12号(2016年12月発行)
特集 これでパッチリ! 眼の健康問題
26巻11号(2016年11月発行)
特集 続・しびれるんです!
26巻10号(2016年10月発行)
特集 内科診療を劇的に変える“まとめ”の達人
26巻9号(2016年9月発行)
特集 症状・症候別 エコーを使った診断推論─Point-of-Care超音波
26巻8号(2016年8月発行)
特集 The 初診外来
26巻7号(2016年7月発行)
特集 感染症ケアバンドル・チェックリスト
26巻6号(2016年6月発行)
特集 “賢い処方”と“ナゾ処方”
26巻5号(2016年5月発行)
特集 しびれるんです!─知っておくべきシビレル疾患
26巻4号(2016年4月発行)
特集 ケースとクイズで総ざらい! 街場の2型糖尿病治療
26巻3号(2016年3月発行)
特集 こんな時は漢方でしょう!
26巻2号(2016年2月発行)
特集 フィジカル改革宣言! ──診断からフォローアップまで
26巻1号(2016年1月発行)
特集 妊婦・褥婦が一般外来に来たら─エマージェンシー&コモンプロブレム
25巻12号(2015年12月発行)
特集 外来で「複数の疾患」をもつ患者を診る─マルチモビディティの時代のプライマリ・ケア
25巻11号(2015年11月発行)
特集 レアだけど重要な「痛み」の原因─システム1診断学
25巻10号(2015年10月発行)
特集 感染症を病歴と診察だけで診断する!Part 2
25巻9号(2015年9月発行)
特集 診断ピットフォール10選─こんな疾患,見逃していませんか?
25巻8号(2015年8月発行)
特集 健診データで困ったら─こんな検査結果を持ってこられたら
25巻7号(2015年7月発行)
特集 ここを知りたい!頭部外傷初期対応・慢性期ケア
25巻6号(2015年6月発行)
特集 高齢者救急の落とし穴─紹介する時,される時
25巻5号(2015年5月発行)
特集 咳を聴きとり,咳を止める
25巻4号(2015年4月発行)
特集 関節が痛いんです!─コモンからレアものまでの診断と治療
25巻3号(2015年3月発行)
特集 神経難病ケアのコペルニクス的転回
25巻2号(2015年2月発行)
特集 総合医のためのスポーツ医学ベーシックス
25巻1号(2015年1月発行)
特集 動悸・息切れ─ヤバい病気の見つけ方 そして見つからなかった時の対処法
