発作性夜間色素尿症とは
発作性夜間色素尿症(paroxysmal nocturnal hemoglobinuria;PNH)は,主として睡眠時に血管内溶血が起こり,翌朝の尿が赤褐色のヘモグロビン尿になる疾患である.血管内溶血の原因は,補体溶血を起こしやすいPNH赤血球が産生されることにあり,その点から後天性溶血性貧血の仲間に入る1).しかしPNHには,溶血のみでなく,骨髄での造血にも異常があり,低形成になって再生不良性貧血に似た病像を呈する症例が知られている.補体感受性は白血球,血小板にも認められ,したがって造血幹細胞レベルで異常が起こっていると考えられ,溶血性貧血とともに造血異常を含めたさまざまな病態を示すのが特徴である.PNHの診断には,赤血球の補体溶血感受性の亢進を証明するHam試験が行われる.
雑誌目次
検査と技術15巻12号
1987年11月発行
雑誌目次
病気のはなし
発作性夜間血色素尿症
著者: 藤岡成德
ページ範囲:P.1258 - P.1263
技術講座 生化学
NAGの測定法—活性測定およびアイソザイム分析
著者: 矢沢直行
ページ範囲:P.1277 - P.1282
N-acetyl-β-D-glucosaminidase(NAG,EC 3.2.1.30)は糖蛋白,糖脂質などの構成成分で,アミノ糖であるN-acetyl-β-D-glucosaminideを基質としてN-acetyl-D-glucosamineに加水分解する酵素である.本酵素は分子量が約14万で,シアル酸を含み,アイソザイムの存在が知られている.NAGの生体内での分布は各組織に認められるが,特に腎臓に多く存在する.細胞内の局在はライソゾーム分画に高濃度に存在しており,一部は細胞可溶性分画にも存在する.
このようにNAGは腎ネフロンの近位尿細管に高濃度に局在している.尿細管の傷害程度は尿中に逸脱したNAG活性に反映される.尿中NAG測定の有用性は,腎疾患の病態観察のほかに,アミノグリコシド系抗生物質の腎毒性に対する指標として,あるいは腎移植後の経過観察,集団検診による腎疾患スクリーニングなどに利用されている.NAG活性は尿中以外にも血中,髄液,羊水でも測定される.特に血中でのNAG活性は炎症性疾患,肝炎,心筋梗塞,悪性腫瘍,白血病,妊娠によって上昇することが知られている.
血液
フォン・ウィルブランド因子の測定法2—フォン・ウィルブランド因子抗原の測定
著者: 高瀬俊夫
ページ範囲:P.1283 - P.1287
フォン・ウィルブランド因子(vWF)は血管内皮や血小板で分子量270kDaのサブユニットとして合成され,血漿中では分子量0.5×103〜20×103kDaに至るマルチマー(multimer)シリーズを形成する巨大糖蛋白である1,2).vWFは出血の際に血小板の粘着に関与し,常染色体遺伝性出血性疾患であるフォン・ウィルブランド病(vWD)では量的ないし質的に異常を呈する.
vWFの測定は,生物学的活性測定として抗生剤の一種でありリストセチンの存在下で洗浄血小板の凝集能(RCof)3)で見る方法と,免疫学的測定として異種抗体を用いて量的ないし質的に測定(vWF:Ag)の方法とがある.前者については前号で述べたので,今回は後者のうち①vWF:Ag測定として免疫電気泳動法(EIA)4)および酵素抗体法(ELISA)5,6),②質的異常を検索する目的で二次元交叉免疫電気泳動法(CIE)7),③vWFマルチマー構造を解析する目的でSDSアガロース電気泳動法8,9)について述べる.
輸血
赤血球抗体解離法
著者: 佐藤千秋 , 松島弘子
ページ範囲:P.1288 - P.1292
赤血球膜に結合している抗体を解離する方法として,温度変換法,pH変動法,有機溶媒処理法が一般的に挙げられる.抗体解離法は,その目的,すなわち解離する抗体のサブクラス別,抗体解離後の赤血球の利用などにより方法が選択される.
抗体解離の利用目的を大別すると,
1)赤血球に結合している抗体の同定を必要とする場合:ⓐ血液型母子不適合新生児溶血性疾患,ⓑ自己免疫性溶血性貧血,ⓒ血液型不適合輸血
2)既知の特異抗体を赤血球に吸着させ,さらに解離することにより,赤血球抗原の存在の有無を確認する場合
3)混在する複数の赤血球抗体を既知の赤血球を用いて吸着,解離させ,抗体の型特異性を同定する場合
4)自己抗体を解離し,解離後の赤血球を用いて各種の型抗原を決定しようとする場合
などが挙げられる.
生理
小児脳波のとりかた
著者: 山磨康子 , 大田原俊輔
ページ範囲:P.1293 - P.1298
脳波は生きている脳の機能を安全かつ簡便にしかも継時的,動的に把握しうるきわめて優れた検査法であり,幼弱な小児,重篤な症例にも広く応用しうる.一般に発達障害,熱性痙攣,てんかんをはじめ出生前および周生期の脳障害に起因する中枢神経疾患は小児期に多く,小児科および小児神経科領域では脳波検査の適応が多く,日常診療上不可欠の検査法である(表1).
記録法(とりかた)は基本的には成人の場合と同じであるが,特に乳幼児および精神遅滞児では聞き分けがなく,検査を恐れたりするため協力が得にくく安静が保てないので,十分な記録を得るにはくふうと根気を要する.
病理
モノクローナル抗体を用いた免疫組織化学的染色のための脱灰法
著者: 森士朗 , 京極方久
ページ範囲:P.1299 - P.1303
1975年,KöhlerとMilstein1)が細胞融合法を免疫学に導入して以来,さまざまな種類のモノクローナル抗体が開発されてきた.これらの抗体は,形態学的に同定が困難な細胞を識別するために組織学的な分野にも応用されるようになり,例えば,従来形態学的に識別が困難であったhelper T cell,cytotoxic T cell,あるいはsuppressor T cellなどのT cellのサブセットが組織切片上でも識別できるようになってきた.しかし,以上のような検索法を硬組織に対して応用する場合,硬組織標本から切片を作製する際に必要な脱灰操作が細胞の抗原性を失活させることになり,特に抗原性が失活しやすい細胞膜表面抗原の免疫組織化学的検索は,非常に困難なものであった.
そこで,最近筆者らは,硬組織標本に含まれるリンパ球やマクロファージなどの細胞膜表面抗原の免疫組織化学的検索を光顕および電顕的に可能にする脱灰法を開発した2〜4).本稿では,この脱灰法の手技を中心に解説し,いくつかの染色例を呈示する.
検査法の基礎理論 なぜこうなるの?
輸血副作用の発現機序
著者: 川越裕也
ページ範囲:P.1265 - P.1270
輸血副作用の発生要因は表1のように,技術的な誤りと事務上または管理上の誤りに大別される.致命的な輸血の副作用の頻度は表2のように患者の取り違えがもっとも高く,次いで検査室内での輸血液,検体などの取り違えが多く,検査技術による誤りは,それらの2割以下にすぎない.その他,患者の異常体質あるいは免疫学的異常によるアナフィラキシー,多種抗体,遅発反応,呼吸不全症候群が目だっている.これらの発生要因によって生ずる輸血副作用は,表3のように多くの種類の反応として現れる2).なぜそのような症状が生ずるかについて紹介する.
喀痰検査—採取法と保存法
著者: 古田格
ページ範囲:P.1271 - P.1275
日常の細菌検査において喀痰検査の占める比率は,尿検査とともに高い.それは,細菌感染症のうちでも呼吸器感染症の頻度の高いことを物語っている.喀痰を検査材料とする場合は,下部気道感染症が対象となり,気管支炎や各種肺炎などが含まれる.
呼吸器感染症は細菌に限らず各種の病原微生物,例えばマイコプラズマ,クラミジア,ウイルス,真菌や寄生虫なども感染に関与し,それぞれでさまざまな特徴のある身体所見や検査所見が得られる.このような各種病原微生物による感染症においては,感染病巣から病原微生物を証明することで診断が可能となる.
マスターしよう基本操作
腹部超音波検査でのプローブの当てかた
著者: 丹生谷徹
ページ範囲:P.1307 - P.1314
腹部領域の超音波検査の臨床的価値の高さは,現在の医療施設の大半にこの装置が設置されていることからもよく理解できる.実際,超音波断層法,中でもリアルタイム断層装置の出現によって,胆石の診断をはじめ多くの腫瘍性病変の早期発見も可能となってきている.また患者に対し苦痛を与えることなく,短期間で,しかも容易に影像として腹腔内を描出することが可能で,また短期日の間に反復して検査が実施できるので,経過観察にはたいへん有用である.
リアルタイム断層装置の出現とその後の技術革新によって,従来の手動接触型複合走査装置に比して走査技術は容易となり,かつ分解能の高い画像がリアルタイムに得られ,解剖学的にも理解しやすくなった.しかしながら,走査技術が容易になったとはいえ,他の診断技術に比して難易度は高い.そこで腹部領域において基本的走査法を中心として,超音波の投入の妨げとなる骨や肺,腸管ガスを避けながら,いかに明瞭な画像を描出するかを解説する.
検査ファイル 項目
17-OHP
著者: 福士勝
ページ範囲:P.1316 - P.1317
1.17-OHP測定法の種類
17α-ヒドロキシプロゲステロン(17α-hydroxyprogesterone;17-OHP)は副腎,睾丸,卵巣などで産生されるステロイドホルモンの一つであり,図1に示すようにコルチゾールの生合成過程の前駆物質である.本ステロイドの血中濃度の測定は,先天性副腎皮質過形成症,不妊症,多毛症などの診断および治療の評価に不可欠なものである.
測定法としては1969年にStrottらにより特異的な抗体を用いるラジオイムノアッセイが開発されて以来,種々のイムノアッセイによる測定系が報告されており,さらにクロマトグラフィーによる測定も報告されている.
カタラーゼテスト
著者: 斎藤肇
ページ範囲:P.1318 - P.1319
カタラーゼはH2O2を特異的に分解する鉄ポルフィリン酵素であって,動植物組織や細菌に存在する.ウシ肝臓のカタラーゼが結晶として最初に分離されて以来,諸種の動物組織をはじめとして植物,細菌のカタラーゼが結晶として取り出されている1).
細菌のカタラーゼの有無は,その鑑別,同定の重要な鍵となっている.通性嫌気性菌の大部分は呼吸系をもつが,ヘム蛋白の合成能を欠く細菌(Streptococcus,Lactobacillus)では呼吸系をもたず,カタラーゼを欠く.O2が存在すると,細菌細胞内で起こる酸化反応に伴って細胞に有害なO2-,H2O2,OH,1O2ができる.したがって,O2の存在下で発育できる菌のほとんどは,H2O2を分解するカタラーゼとO2-を分解するスーパーオキサイドディスムターゼ(superoxide dismutase)をもつ.
試薬
総カルシウム測定用試薬(o-CPC法)
著者: 佐藤悦子
ページ範囲:P.1320 - P.1321
o-クレゾールフタレインコンプレキソン(o-CPC)法は血中総カルシウム測定法として,現在いちばん普及している測定法といえる.61年度日本医師会サーベイ,日臨技サーベイにおいても,その参加施設の約85%で使用されている.
o-CPC法は非常に特異性が高く,鋭敏な反応であり,また操作性も非常に簡便である.特別な装置を必要とすることなく,短時間に多検体処理が可能であり,自動分析機器への適用が容易であることなどが,その普及に貢献していると思われる.しかし,非常に特異的で簡便な方法ではあるが,なお若干の問題を抱えている.精度のよい測定値を得るためには,その試薬の特性を十分考慮したうえで使用する必要がある.
用語
骨髄巨核球
著者: 寺田秀夫
ページ範囲:P.1322 - P.1323
1.概念
止血や血栓形成にたいせつな働きをする血小板は,骨髄巨核球(megakaryocyte;Mgk)の細胞質から生成される.したがってMgkの数やその血小板生成能を見ることは,血小板減少症の鑑別診断に重要である.また,その細胞が腫瘍性に増殖したものを巨核芽球性白血病と呼び,急性骨髄線維症と密接な関係を有することが知られてきた.今日,巨核球の形態学的変化やその増減を見ることは,臨床検査の分野で非常な脚光を浴びている.
Letter from Abroad 海外で活躍する日本の検査技師
意外に少ない勉強会や交流—スイスからの手紙(6) スイス6
著者:
ページ範囲:P.1324 - P.1325
■ルツェルンの夏
ルツェルンの夏はさわやかです.湿度の低い,からりとしたよい天気が続きます.車にクーラーは不必要です.ここでは,さんさんと陽の降り注いでいる日は,猫も杓子も戸外へ飛び出し,太陽を全身に浴びます.ルツェルンは,Vierwaldstätter Seeと呼ばれる大きな湖のほとりに発展した古都で,街の中にヨットハーバーを抱いた広々としたSeepark(湖公園)があります.その公園は湖に面しており,そこで泳ぐこともできます.夏の天気のよい週末などにその公園に行くと,太陽に誘われて繰り出して来た多くの市民で,公園はパッと花が咲いたように活気づいています.湖辺で泳いでいるのは小さな子供ぐらいで,ほとんどの人は,薄物や水着をつけて,芝生の上に寝そべったり,ボール遊びに興じたりしています.ラウドスピーカーや,物売りなどがないので,あのいやな,神経を逆なでする騒々しさとは無縁です.
ここで,ルツェルンの夏に趣きを添える一つの催し物があることを,この手紙に書かないわけにはいきません.それは,Luzern Internationale Musikfestwochenという,4週間にわたる音楽祭です.この音楽祭は毎夏やって来て,古都の真夏の夜を麗美な調べで包みます.1984年には,小沢征爾が,Boston Symphony Orchestraを引き連れて来て,指揮棒を振りました.Herbert von Karajanは毎年来ます.その他,Claudio Abbado,Lorin Maazel,Anne-Sophie Mutter,そしてJames Galwayなどのそうそうたる音楽家が,洗練された調べを古都の夕べに織りなします.
ひとくち英会話 English Conversation in Your Laboratory
〔国際総会にて(4)—質疑応答〕
著者: 𠮷野二男 , 常田正
ページ範囲:P.1326 - P.1327
Q:検査室でこの方法をお使いになる場合,どのくらいの精密度を期待されますか.
A:この方法のCVは正常値で約2%,それより高いところで約5%です.これで臨床的には十分役になつと思います.
トピックス
FAB分類のその後
著者: 天木一太
ページ範囲:P.1328 - P.1329
急性白血病のFAB分類は,世界的に普及しており,症例を記載するときには必ずこの分類が付記されるようになった.この分類法は1976年の最初の提唱以来3回改訂が行われてきたが,1985年末にさらに重要な二つの改訂がなされた.一つはAML(急性骨髄性白血病)とMDS myelodysplastic syndrome(骨髄異形成症候群)についてで1),いま一つはM7骨髄巨核球性白血病についてのものである2).これらの改訂をすべて理解して鏡検することは容易ではないが,必要なことなのである.
この解説では,詳細に及ぶことはできないが,改訂の理念とどのように行われたかについて書いておく.実際の利用には別の文献3)を用いてください.なおこの分類は世界的に同じ規則が用いられているのがよいので,自分の好みで勝手に修正してはならない.この点,日本はFAB分類の優等生であることが認められている1).なお,L1,M2などと記すのは1976年のときのみで,1980年からはL1,M2などと書くようになった.
INR
著者: 安部英
ページ範囲:P.1329 - P.1330
まずINRとは何か,それはなぜ必要であるかを述べると,これはプロトロンビン(プ)時間の比較評価のために考案されたものである.実地臨床でプ時間は肝機能検査中のたいせつな項目として重視されているが,またDICをはじめ各種の血液疾患や肺,腎など種々臓器の障害診断や病状把握に重要な意味を持っている.しかし臨床上プ時間の変動がもっとも注目されるのは,経口抗凝血薬療法管理の場合である1,2).ところが,このプ時間値は,被験血漿中のプの量の多寡や質的な反応性,また血漿中に同時に存在する反応性抑制ないし促進物質によって影響される.ことに測定に用いられるトロンボプラスチン(トプ)試薬をはじめ,使用する測定器械,測定者の手技の巧拙によってその値は著しく左右されるが,中でもトプ試薬の血漿プに対する感受性はプ測定に基本的な意義を持っている.この立場から国際血液学標準化委員会と国際血栓止血学会委員会はWHOとも協同でトプ試薬に対する国際的に共通な標準試薬を定め,これを基に各トプ試薬の感度に対する共通な指標を設定することとした3,4).
現在トプ試薬には,その原料としてウサギの脳,ウサギの脳と肺,ウシの脳,ヒトの胎盤およびヒトの脳(これは標準試薬として用いる)を用いたものが市販されているが,これらの試薬はプ感度に相当な差異があり,各試薬で得られるプ時間(秒),活性(%),プ比(被検血漿のプ時間を標準正常血漿のそれで割った値;prothrombin ratio;PR)は,同じ血漿についても大きく異なる.したがって,このように異なったトプ試薬を用いて得られる各患者血漿のプ時間,その他を直接比較して,各患者のプの状況を評価することはできない.これまでは患者のプ時間測定のたびごとに,同じトプ試薬を用いて標準正常血漿のプ時間,その他を測り,それらの値を比較して間接的に各患者のプの状況を知るほかはなかったが,このINR法により初めて各患者間のプ値の比較をトプ試薬の差異にかかわらず,また異なった研究者,検査技師,研究室(国内的にも国際的にも)間のバラツキをふまえて評価することができるようになったのである3〜6).
検査技師のためのME講座 計測器・17
記録器
著者: 池田博
ページ範囲:P.1331 - P.1334
現代社会は情報化時代と呼ばれ,各種の情報が氾濫している.それらの情報も最終的には目に見える形で人間に伝えられ,さらに,その情報を保存するために紙の上に記録された波形,図形,文字の必要性に迫られている.
ME分野に用いられる記録器は,精度,画質などについて他の分野に用いられている記録器と同等であるが,生体現象を取り扱うため,若干異なる点がある.この分野における計測は対象が生体であるため現象が単発であり,繰り返しがないため,記録されたデータが非常に重要となり連続記録が必要になることが多い.また,そのデータ整理には波形の読みやすさが必要であることはもとより,データ整理に当たっては装置,測定系の安定性が必要であり,客観的に判断が可能な測定条件を測定者が記載したり,入力換算をしたりするのが容易であることが望まれている.
ザ・トレーニング
基準電極が活性化した脳波例の技術的対策
著者: 平賀旗夫
ページ範囲:P.1335 - P.1338
基準電極の活性化とは何か
Q 基準電極の活性化とは何のことですか.
A いわゆる単極導出(正しくは基準導出)で生体現象を記録するとき,基準電極(referencial electrode)はすべての生体現象に関して零電位であることが理想なのですが,脳波ではこれがなかなか難しいのです.定義としては,基準電極に生体電気活動が波及して,電位をもつことを「基準電極の活性化」(active reference electrode)といい,その結果,基準導出の各導出(素子)における記録波形,特にその部位的分布に歪みが生じてしまうことになります6〜8).例えば図1のように,診断に使おうとしている異常波についてこれが起こると,たいへん判読がしにくくなりますから,記録中に的確に見分けて対処しなければなりません,早く気づかないと,分布歪みのある基準導出モンタージュのままで,過呼吸,光刺激などの賦活をやってしまい,双極導出になってからやっと気づく,などというぶざまな記録を作ってしまうのですね.
検査を築いた人びと
喉頭鏡を臨床医学に応用した ヨハン・ツェルマーク
著者: 深瀬泰旦
ページ範囲:P.1264 - P.1264
ツェルマークとチュルク(本誌15巻10月号)は,1858年にそれぞれ独立に喉頭鏡の利用についての論文を発表した.ツェルマークは3月27日,チュルクはそれにおくれること3か月,6月26日のことであった.2人はパリに行き,そこで喉頭鏡検査の技術について公開実演と講演を行って,お互いに張り合った.2人の間の感情はますます微妙となり,ついにチュルクはウィーンの高等裁判所に出頭して,法的行動でツェルマークを脅かした.さらにこの2人の競争者は,それぞれフランス医学アカデミーのモンティオン賞候補として申請した.彼らを調査するための特別委員会が設置され,その委員会は大岡裁きよろしく,プライオリティーの問題にはふれずに,喉頭鏡を紹介したという科学への貢献に対して,この2人に賞状と賞金を授与した.
ヨハン・ツェルマークは1828年6月7日チェコスロヴァキアのプラハで生まれ,そこで医学の教育を受けた.ツェルマークの父と祖父はプラハの内科医であり,伯父はウィーンの解剖学と生理学の教授であった.ツェルマークはプラハ,ウィーン,ブレスラウなどで研究に従事したが,とくにブレスラウの生理学教授プルキンエ(本誌13巻1号)からは研究上の庇護と助言を与えられ,生涯にわたって強い影響を受けた.ツェルマークの研究の分野は,プルキンエが研究した問題をさらに発展させたものが多い(歯の構造,視覚現象,めまい,音声学など).
私たちの本棚
私の旅の常備薬—読むクスリ—上前 淳一郎 著
著者: 井田喜博
ページ範囲:P.1276 - P.1276
若いころに比べ,最近は視力が落ちたせいか本を読む機会も減ってしまった.必要にせまられて読む専門書か,乗り物に長く乗るときに読む,あまり肩が凝らず楽しく,かつ若干とも役だつような本などになっている.ここで紹介する『読むクスリ』は週刊文春に掲載したものを単行本に編集したものであり,現在までにPART Ⅰ〜Ⅶまで出版されている.この『読むクスリ』というタイトルは,いろんな意味を含んでいるようだ.読んでいてクスリと笑う部分や,我々に薬になる内容など盛りたくさんで,国の内外から取材を行い編集している.その一つ一つが日常性の出来事であったり,非日常性の事がらであったり,またビジネス情報(最先端技術の生まれる背景など)であったり,たいへんバラエティーに富んでいる.それと,個人・チーム・組織・社会・国が違えば根本的な考え方の起源が異なるため,常識といえる部分がいろいろあるものだという実例など,発想の転換にも参考になる.
ではいくつか原文を引用して,なるほどと思えるものを紹介してみよう.
けんさアラカルト
精度管理の基礎を見つめて
著者: 坂野重子
ページ範囲:P.1306 - P.1306
この春,新築の社会保険中央総合病院が完成し,そしてまた,それぞれ出身校の異なる新卒の技師5名を迎えた.技師の採用に当たっては,男女差別などをするはずもないのであるが,公正な試験の結果はいつも女性上位となり,今年も女性ばかり.男女雇用機会均等法の時代とはいえ,時に私は,「男性技師を集めない」との誹りを受けて迷惑する.
しかし,角度を変えてみれば,新陳代謝の早い若い女性集団も悪くないものである.
りんりんダイヤル
小実験動物標本の染色時の剥離
著者: 五十嵐正市郎
ページ範囲:P.1341 - P.1341
問 小実験動物(マウスやラット)の標本が染色時にはがれて困ることがしばしばあります.3μmくらいに薄く切っているのですが,何が原因なのでしょうか.その防止法もお教えください.(神奈川 N生)
ME図記号に強くなろう
39医用超音波機器図記号(5) 映像調整
著者: 小野哲章
ページ範囲:P.1282 - P.1282
画像を見やすくしたり,目的画像を強調するための様々な調整機能の記号である.それぞれのツマミに付けられる.
①ダイナミックレンジ:画像表示の最低信号強度と最高信号強度を調整するツマミに付けられる.下限より弱いものは映らないし,上限より強いものは上限と同じ濃さになる.
コーヒーブレイク
ポケットベル
著者: S.I.
ページ範囲:P.1303 - P.1303
ポケットベルを持たされて久しいが,いまだにいまいましさを感じている.病院にいる間,どこにでも追いかけてくる.ついこの前までは,電話なら「ただいま席をはずしています」と言ってもらい,急ぎの場合は,用件でも聞いてもらっておけばよかったが,ポケットベル出現以来,会議中であろうと仕事中であろうと,無念無想の境地でトイレにいる時でもおかまいなしに鳴り出す.このことを予想して携帯を辞退したのだが,緊急の場合連絡がつかないと困るとの理由で持たされた.管理者ゆえに管理される羽目となったわけだ.実際には,緊急の場合どころか,「外線がかかっています」「お客が室にみえてます」「診療側がクレームに来てます」等々,トイレを中途でがまんしてまで出るに及ばない用件ばかりである.鳴っても切って知らん顔をしていると,「ポケットベル鳴りませんでしたか」と交換嬢の詰問,「鳴ったかも知れないナー」ととぼける昨今である.
NTTが1968年7月にポケベルサービスをはじめた時は5000台であったが,現在では220万台を超えたという.会社の中は勿論,外にまで首にツナをつけられているようなものである.ツナで思い出したが,最近は犬の首輪にポケベルを付けて,鳴ったら帰ってくるように訓練し,飼主は散歩に同行する手間を省いているとか(本当かな?).とにかく,この一方的な伝達を考えた奴をにがにがしく思っていると,誰かが「電話は悪魔の発明品である」と言ったのを思い出した.が,ポケベルの方がもっと悪魔的だ.
エトランゼ
林語堂先生の教え・後日談(続)
著者: 常田正
ページ範囲:P.1327 - P.1327
最近の新聞報道によれば,半世紀前の"ニューヨーク・レストラン皿割り紳士"の直系の孫に当たるかと思われる紳士がいたらしい.その紳士は海外にも現地法人をつくっており,ビジネスのため月に10回ほどは外国に出かけるほど忙しい方で,日本航空国際線のファーストクラスの常連客である.事のおこりはやはりスープが原因であつた.機内食のスープにスプーンをつけ忘れたことを社長はひどくお怒りになって,担当のスチュワーデスの謝罪に満足せず,調理室におしかけでいってチーフパーサーやスチュワーデスらをニューヨークに着くまで延べ5時間にわたって責め続けたというのである.この間チーフパーサーの胸ぐらをつかんでボタンをひきちぎったり,腕を殴打したり,「でかい顔をするな」とか「退職届けを書け」などと暴言をあびせ続けたというのだ.事を重大視した日航は,内容証明つきの搭乗拒否通告書をこの社長さんに送りつけたという.そんなに不愉快なら二度と日航のヒコーキほ乗らないのかと思ったら,この社長さん「日航は便利だし,ほかの乗務員は皆さん親切だから塔乗拒否を撤回してもらいたい」と言っているとのこと.日本航空でなくてアメリカかイギリスのヒコーキで問題をおこしてくれたら,実験はもっと正確であったのだがと思うと,ちょっと残念な気もする.
--------------------
第33回臨床検査技師国家試験—解答速報
ページ範囲:P.1340 - P.1340
基本情報
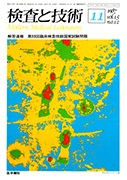
バックナンバー
52巻12号(2024年12月発行)
技術講座 生理
52巻11号(2024年11月発行)
技術講座 生理
52巻10号(2024年10月発行)
技術講座 生理
52巻9号(2024年9月発行)
増大号 臨床医に伝わりやすい 検査報告書とパニック値報告の心得
52巻8号(2024年8月発行)
技術講座 生理
52巻7号(2024年7月発行)
技術講座 生理
52巻6号(2024年6月発行)
技術講座 生理
52巻5号(2024年5月発行)
技術講座 その他
52巻4号(2024年4月発行)
技術講座 生理
52巻3号(2024年3月発行)
増大号 POCUSの決め手。 早く、正確な診断のために
52巻2号(2024年2月発行)
技術講座 生理
52巻1号(2024年1月発行)
技術講座 その他
51巻12号(2023年12月発行)
技術講座 生理
51巻11号(2023年11月発行)
技術講座 生理
51巻10号(2023年10月発行)
技術講座 その他
51巻9号(2023年9月発行)
増大号 匠から学ぶ 血栓止血検査ガイド
51巻8号(2023年8月発行)
技術講座 生理
51巻7号(2023年7月発行)
技術講座 生理
51巻6号(2023年6月発行)
技術講座 生理
51巻5号(2023年5月発行)
技術講座 生理
51巻4号(2023年4月発行)
技術講座 生理
51巻3号(2023年3月発行)
増大号 症例から学ぶ 疾患と検査値の推移
51巻2号(2023年2月発行)
技術講座 その他
51巻1号(2023年1月発行)
技術講座 生理
50巻12号(2022年12月発行)
技術講座 その他
50巻11号(2022年11月発行)
技術講座 生理
50巻10号(2022年10月発行)
技術講座 生理
50巻9号(2022年9月発行)
増大号 希少例と特殊像がわかる! エコーの撮り方完全マスター
50巻8号(2022年8月発行)
技術講座 生理
50巻7号(2022年7月発行)
技術講座 生理
50巻6号(2022年6月発行)
技術講座 生理
50巻5号(2022年5月発行)
技術講座 生理
50巻4号(2022年4月発行)
技術講座 生理
50巻3号(2022年3月発行)
増大号 見て学ぶ 一般検査学アトラス—外観検査から顕微鏡検査まで
50巻2号(2022年2月発行)
技術講座 その他
50巻1号(2022年1月発行)
技術講座 生理
49巻12号(2021年12月発行)
技術講座 生理
49巻11号(2021年11月発行)
技術講座 生理
49巻10号(2021年10月発行)
技術講座 生理
49巻9号(2021年9月発行)
増刊号 病態別 腹部エコーの観察・記録・報告書作成マスター
49巻8号(2021年8月発行)
技術講座 生理
49巻7号(2021年7月発行)
技術講座 生理
49巻6号(2021年6月発行)
技術講座 生理
49巻5号(2021年5月発行)
技術講座 生理
49巻4号(2021年4月発行)
技術講座 一般
49巻3号(2021年3月発行)
増刊号 First&Next Step 微生物検査サポートブック
49巻2号(2021年2月発行)
技術講座 微生物
49巻1号(2021年1月発行)
技術講座 病理・生理
48巻12号(2020年12月発行)
技術講座 その他
48巻11号(2020年11月発行)
技術講座 生化学
48巻10号(2020年10月発行)
技術講座 生理
48巻9号(2020年9月発行)
増刊号 学会発表・論文執筆はもう怖くない! 臨床検査技師のための研究入門
48巻8号(2020年8月発行)
技術講座 遺伝子
48巻7号(2020年7月発行)
技術講座 その他
48巻6号(2020年6月発行)
技術講座 輸血
48巻5号(2020年5月発行)
技術講座 生化学
48巻4号(2020年4月発行)
技術講座 生理
48巻3号(2020年3月発行)
増刊号 採血のすべて—手技から採血室の運用まで徹底解説
48巻2号(2020年2月発行)
技術講座 微生物
48巻1号(2020年1月発行)
技術講座 生理
47巻12号(2019年12月発行)
技術講座 病理
47巻11号(2019年11月発行)
技術講座 生理
47巻10号(2019年10月発行)
技術講座 生理
47巻9号(2019年9月発行)
増刊号 染色画像を比べて学ぶ 体腔液アトラス
47巻8号(2019年8月発行)
技術講座 病理
47巻7号(2019年7月発行)
技術講座 一般
47巻6号(2019年6月発行)
技術講座 血液
47巻5号(2019年5月発行)
技術講座 血液
47巻4号(2019年4月発行)
技術講座 血液
47巻3号(2019年3月発行)
増刊号 エキスパートが教える 心・血管エコー計測のノウハウ
47巻2号(2019年2月発行)
技術講座 病理
47巻1号(2019年1月発行)
技術講座 微生物
46巻12号(2018年12月発行)
技術講座 生理
46巻11号(2018年11月発行)
技術講座 輸血・遺伝子検査
46巻10号(2018年10月発行)
技術講座 その他
46巻9号(2018年9月発行)
増刊号 現場で“パッ”と使える 免疫染色クイックガイド
46巻8号(2018年8月発行)
技術講座 輸血・遺伝子検査
46巻7号(2018年7月発行)
技術講座 生理
46巻6号(2018年6月発行)
技術講座 管理
46巻5号(2018年5月発行)
技術講座 生化学
46巻4号(2018年4月発行)
技術講座 一般
46巻3号(2018年3月発行)
増刊号 感染症クイックリファレンス
46巻2号(2018年2月発行)
技術講座 輸血
46巻1号(2018年1月発行)
技術講座 病理
45巻12号(2017年12月発行)
技術講座 生理
45巻11号(2017年11月発行)
技術講座 一般
45巻10号(2017年10月発行)
技術講座 微生物
45巻9号(2017年9月発行)
増刊号 循環器病院の技師が教える メディカルスタッフのための心電図教室
45巻8号(2017年8月発行)
技術講座 栄養
45巻7号(2017年7月発行)
技術講座 病理
45巻6号(2017年6月発行)
技術講座 病理
45巻5号(2017年5月発行)
技術講座 細胞治療・管理
45巻4号(2017年4月発行)
技術講座 遺伝子・染色体検査
45巻3号(2017年3月発行)
45巻2号(2017年2月発行)
技術講座 細胞治療
45巻1号(2017年1月発行)
技術講座 病理
44巻13号(2016年12月発行)
技術講座 免疫
44巻12号(2016年11月発行)
技術講座 微生物
44巻11号(2016年10月発行)
技術講座 微生物
44巻10号(2016年9月発行)
増刊号 はじめて出会う 検査画像
44巻9号(2016年9月発行)
技術講座 管理・その他
44巻8号(2016年8月発行)
技術講座 微生物
44巻7号(2016年7月発行)
技術講座 生理
44巻6号(2016年6月発行)
技術講座 微生物
44巻5号(2016年5月発行)
技術講座 生理
44巻4号(2016年4月発行)
技術講座 微生物
44巻3号(2016年3月発行)
技術講座 生理
44巻2号(2016年2月発行)
技術講座 微生物
44巻1号(2016年1月発行)
技術講座 微生物
43巻13号(2015年12月発行)
技術講座 生化学
43巻12号(2015年11月発行)
技術講座 生化学
43巻11号(2015年10月発行)
技術講座 一般
43巻10号(2015年9月発行)
増刊号 血液形態アトラス
43巻9号(2015年9月発行)
技術講座 生理
43巻8号(2015年8月発行)
技術講座 生理
43巻7号(2015年7月発行)
技術講座 生理
43巻6号(2015年6月発行)
技術講座 微生物
43巻5号(2015年5月発行)
技術講座 移植医療
43巻4号(2015年4月発行)
技術講座 病理
43巻3号(2015年3月発行)
技術講座 血液
43巻2号(2015年2月発行)
技術講座 管理
43巻1号(2015年1月発行)
技術講座 病理
42巻13号(2014年12月発行)
技術講座 生化学
42巻12号(2014年11月発行)
技術講座 病理
42巻11号(2014年10月発行)
技術講座 血液
42巻10号(2014年9月発行)
増刊号 超音波×病理 対比アトラス
42巻9号(2014年9月発行)
技術講座 生理
42巻8号(2014年8月発行)
技術講座 免疫
42巻7号(2014年7月発行)
技術講座 生理
42巻6号(2014年6月発行)
技術講座 生理
42巻5号(2014年5月発行)
技術講座 病理
42巻4号(2014年4月発行)
技術講座 輸血
42巻3号(2014年3月発行)
技術講座 血液
42巻2号(2014年2月発行)
技術講座 微生物
42巻1号(2014年1月発行)
技術講座 病理
41巻13号(2013年12月発行)
技術講座 生理
41巻12号(2013年11月発行)
技術講座 生化学
41巻11号(2013年10月発行)
技術講座 生化学
41巻10号(2013年9月発行)
増刊号 解剖と正常像がわかる! エコーの撮り方完全マスター
41巻9号(2013年9月発行)
技術講座 微生物
41巻8号(2013年8月発行)
技術講座 生理
41巻7号(2013年7月発行)
技術講座 生理
41巻6号(2013年6月発行)
技術講座 微生物
41巻5号(2013年5月発行)
技術講座 一般
41巻4号(2013年4月発行)
技術講座 生化学
41巻3号(2013年3月発行)
技術講座 生理
41巻2号(2013年2月発行)
技術講座 生理
41巻1号(2013年1月発行)
技術講座 生理
40巻13号(2012年12月発行)
技術講座 血液
40巻12号(2012年11月発行)
技術講座 生理
40巻11号(2012年10月発行)
技術講座 生理
40巻10号(2012年9月発行)
増刊号 この検査データを読めますか?―検査値から病態を探る
40巻9号(2012年9月発行)
技術講座 生理
40巻8号(2012年8月発行)
技術講座 細胞診
40巻7号(2012年7月発行)
技術講座 生理
40巻6号(2012年6月発行)
技術講座 生理
40巻5号(2012年5月発行)
技術講座 生理
40巻4号(2012年4月発行)
技術講座 血液
40巻3号(2012年3月発行)
技術講座 生理
40巻2号(2012年2月発行)
技術講座 輸血
40巻1号(2012年1月発行)
技術講座 遺伝子
39巻13号(2011年12月発行)
疾患と検査値の推移
39巻12号(2011年11月発行)
疾患と検査値の推移
39巻11号(2011年10月発行)
疾患と検査値の推移
39巻10号(2011年9月発行)
増刊号 緊急報告すべき検査結果のすべて―すぐに使えるパニック値事典
39巻9号(2011年9月発行)
疾患と検査値の推移
39巻8号(2011年8月発行)
疾患と検査値の推移
39巻7号(2011年7月発行)
疾患と検査値の推移
39巻6号(2011年6月発行)
技術講座 生理
39巻5号(2011年5月発行)
技術講座 生理
39巻4号(2011年4月発行)
疾患と検査値の推移
39巻3号(2011年3月発行)
疾患と検査値の推移
39巻2号(2011年2月発行)
疾患と検査値の推移
39巻1号(2011年1月発行)
疾患と検査値の推移
38巻13号(2010年12月発行)
疾患と検査値の推移
38巻12号(2010年11月発行)
疾患と検査値の推移
38巻11号(2010年10月発行)
疾患と検査値の推移
38巻10号(2010年9月発行)
増刊号 免疫反応と臨床検査2010
38巻9号(2010年9月発行)
疾患と検査値の推移
38巻8号(2010年8月発行)
疾患と検査値の推移
38巻7号(2010年7月発行)
疾患と検査値の推移
38巻6号(2010年6月発行)
疾患と検査値の推移
38巻5号(2010年5月発行)
疾患と検査値の推移
38巻4号(2010年4月発行)
疾患と検査値の推移
38巻3号(2010年3月発行)
疾患と検査値の推移
38巻2号(2010年2月発行)
疾患と検査値の推移
38巻1号(2010年1月発行)
疾患と検査値の推移
37巻13号(2009年12月発行)
疾患と検査値の推移
37巻12号(2009年11月発行)
疾患と検査値の推移
37巻11号(2009年10月発行)
疾患と検査値の推移
37巻10号(2009年9月発行)
増刊号 顕微鏡検査のコツ―臨床に役立つ形態学
37巻9号(2009年9月発行)
疾患と検査値の推移
37巻8号(2009年8月発行)
疾患と検査値の推移
37巻7号(2009年7月発行)
疾患と検査値の推移
37巻6号(2009年6月発行)
疾患と検査値の推移
37巻5号(2009年5月発行)
疾患と検査値の推移
37巻4号(2009年4月発行)
疾患と検査値の推移
37巻3号(2009年3月発行)
疾患と検査値の推移
37巻2号(2009年2月発行)
疾患と検査値の推移
37巻1号(2009年1月発行)
疾患と検査値の推移
36巻13号(2008年12月発行)
疾患と検査値の推移
36巻12号(2008年11月発行)
疾患と検査値の推移
36巻11号(2008年10月発行)
疾患と検査値の推移
36巻10号(2008年9月発行)
増刊号 これから広がる生理検査・新たにはじまる生理検査
36巻9号(2008年9月発行)
疾患と検査値の推移
36巻8号(2008年8月発行)
疾患と検査値の推移
36巻7号(2008年7月発行)
疾患と検査値の推移
36巻6号(2008年6月発行)
疾患と検査値の推移
36巻5号(2008年5月発行)
疾患と検査値の推移
36巻4号(2008年4月発行)
疾患と検査値の推移
36巻3号(2008年3月発行)
疾患と検査値の推移
36巻2号(2008年2月発行)
疾患と検査値の推移
36巻1号(2008年1月発行)
疾患と検査値の推移
35巻13号(2007年12月発行)
疾患と検査値の推移
35巻12号(2007年11月発行)
疾患と検査値の推移
35巻11号(2007年10月発行)
増刊号 メタボリックシンドローム健診検査技術マニュアル
35巻10号(2007年10月発行)
疾患と検査値の推移
35巻9号(2007年9月発行)
疾患と検査値の推移
35巻8号(2007年8月発行)
疾患と検査値の推移
35巻7号(2007年7月発行)
疾患と検査値の推移
35巻6号(2007年6月発行)
疾患と検査値の推移
35巻5号(2007年5月発行)
疾患と検査値の推移
35巻4号(2007年4月発行)
疾患と検査値の推移
35巻3号(2007年3月発行)
疾患と検査値の推移
35巻2号(2007年2月発行)
疾患と検査値の推移
35巻1号(2007年1月発行)
疾患と検査値の推移
34巻13号(2006年12月発行)
技術講座 生理
34巻12号(2006年11月発行)
技術講座 一般
34巻11号(2006年10月発行)
増刊号 新しい臨床検査・未来の臨床検査
34巻10号(2006年10月発行)
疾患と検査値の推移
34巻9号(2006年9月発行)
疾患と検査値の推移
34巻8号(2006年8月発行)
疾患と検査値の推移
34巻7号(2006年7月発行)
疾患と検査値の推移
34巻6号(2006年6月発行)
疾患と検査値の推移
34巻5号(2006年5月発行)
疾患と検査値の推移
34巻4号(2006年4月発行)
疾患と検査値の推移
34巻3号(2006年3月発行)
疾患と検査値の推移
34巻2号(2006年2月発行)
疾患と検査値の推移
34巻1号(2006年1月発行)
疾患と検査値の推移
33巻13号(2005年12月発行)
疾患と検査値の推移
33巻12号(2005年11月発行)
疾患と検査値の推移
33巻11号(2005年10月発行)
増刊号 一線診療のための臨床検査
33巻10号(2005年10月発行)
疾患と検査値の推移
33巻9号(2005年9月発行)
疾患と検査値の推移
33巻8号(2005年8月発行)
疾患と検査値の推移
33巻7号(2005年7月発行)
疾患と検査値の推移
33巻6号(2005年6月発行)
疾患と検査値の推移
33巻5号(2005年5月発行)
疾患と検査値の推移
33巻4号(2005年4月発行)
疾患と検査値の推移
33巻3号(2005年3月発行)
疾患と検査値の推移
33巻2号(2005年2月発行)
疾患と検査値の推移
33巻1号(2005年1月発行)
疾患と検査値の推移
32巻13号(2004年12月発行)
技術講座 血液
32巻12号(2004年11月発行)
技術講座 病理
32巻11号(2004年10月発行)
技術講座 血液
32巻10号(2004年9月発行)
増刊号 細胞像の見かた―病理・血液・尿沈渣
32巻9号(2004年9月発行)
技術講座 生化学
32巻8号(2004年8月発行)
技術講座 免疫
32巻7号(2004年7月発行)
技術講座 微生物
32巻6号(2004年6月発行)
技術講座 病理
32巻5号(2004年5月発行)
技術講座 病理
32巻4号(2004年4月発行)
技術講座 病理
32巻3号(2004年3月発行)
技術講座 微生物
32巻2号(2004年2月発行)
技術講座 生化学
32巻1号(2004年1月発行)
技術講座 微生物
31巻13号(2003年12月発行)
技術講座 微生物
31巻12号(2003年11月発行)
技術講座 病理
31巻11号(2003年10月発行)
技術講座 微生物
31巻10号(2003年9月発行)
増刊号 包括医療と臨床検査
31巻9号(2003年9月発行)
技術講座 一般
31巻8号(2003年8月発行)
技術講座 微生物
31巻7号(2003年7月発行)
技術講座 病理
31巻6号(2003年6月発行)
技術講座 免疫
31巻5号(2003年5月発行)
技術講座 一般
31巻4号(2003年4月発行)
技術講座 病理
31巻3号(2003年3月発行)
技術講座 生化学
31巻2号(2003年2月発行)
技術講座 免疫
31巻1号(2003年1月発行)
技術講座 免疫
30巻13号(2002年12月発行)
技術講座 生理
30巻12号(2002年11月発行)
技術講座 生理
30巻11号(2002年10月発行)
技術講座 生化学
30巻10号(2002年9月発行)
増刊号 誰でもわかる遺伝子検査
30巻9号(2002年9月発行)
技術講座 微生物
30巻8号(2002年8月発行)
技術講座 生化学
30巻7号(2002年7月発行)
技術講座 微生物
30巻6号(2002年6月発行)
技術講座 生化学
30巻5号(2002年5月発行)
技術講座 微生物
30巻4号(2002年4月発行)
技術講座 一般
30巻3号(2002年3月発行)
技術講座 生化学
30巻2号(2002年2月発行)
技術講座 一般
30巻1号(2002年1月発行)
技術講座 免疫
29巻13号(2001年12月発行)
技術講座 病理
29巻12号(2001年11月発行)
技術講座 生理
29巻11号(2001年10月発行)
技術講座 病理
29巻10号(2001年9月発行)
技術講座 病理
29巻9号(2001年8月発行)
技術講座 病理
29巻8号(2001年7月発行)
技術講座 生理
29巻7号(2001年6月発行)
増刊号 病理組織・細胞診のための日常染色法ガイダンス
29巻6号(2001年6月発行)
技術講座 微生物
29巻5号(2001年5月発行)
技術講座 生理
29巻4号(2001年4月発行)
技術講座 病理
29巻3号(2001年3月発行)
技術講座 微生物
29巻2号(2001年2月発行)
技術講座 微生物
29巻1号(2001年1月発行)
技術講座 一般
28巻13号(2000年12月発行)
技術講座 病理
28巻12号(2000年11月発行)
技術講座 病理
28巻11号(2000年10月発行)
技術講座 免疫
28巻10号(2000年9月発行)
技術講座 微生物
28巻9号(2000年8月発行)
技術講座 微生物
28巻8号(2000年7月発行)
技術講座 生理
28巻7号(2000年6月発行)
増刊号 血液検査実践マニュアル
28巻6号(2000年6月発行)
技術講座 免疫
28巻5号(2000年5月発行)
技術講座 血液
28巻4号(2000年4月発行)
技術講座 一般
28巻3号(2000年3月発行)
技術講座 生理
28巻2号(2000年2月発行)
技術講座 生化学
28巻1号(2000年1月発行)
技術講座 一般
27巻13号(1999年12月発行)
技術講座 病理
27巻12号(1999年11月発行)
技術講座 一般
27巻11号(1999年10月発行)
技術講座 生化学
27巻10号(1999年9月発行)
技術講座 免疫
27巻9号(1999年8月発行)
技術講座 病理
27巻8号(1999年7月発行)
技術講座 病理
27巻7号(1999年6月発行)
増刊号 緊急検査実践マニュアル
27巻6号(1999年6月発行)
技術講座 生化学
27巻5号(1999年5月発行)
技術講座 血液
27巻4号(1999年4月発行)
技術講座 一般
27巻3号(1999年3月発行)
技術講座 生理
27巻2号(1999年2月発行)
技術講座 微生物
27巻1号(1999年1月発行)
技術講座 生理
26巻13号(1998年12月発行)
技術講座 一般
26巻12号(1998年11月発行)
技術講座 病理
26巻11号(1998年10月発行)
技術講座 病理
26巻10号(1998年9月発行)
技術講座 生理
26巻9号(1998年8月発行)
技術講座 生理
26巻8号(1998年7月発行)
技術講座 生理
26巻7号(1998年6月発行)
増刊号 病理組織・細胞診実践マニュアル
26巻6号(1998年6月発行)
技術講座 病理
26巻5号(1998年5月発行)
技術講座 一般
26巻4号(1998年4月発行)
技術講座 病理
26巻3号(1998年3月発行)
技術講座 一般
26巻2号(1998年2月発行)
技術講座 生理
26巻1号(1998年1月発行)
技術講座 血液
25巻13号(1997年12月発行)
技術講座 一般
25巻12号(1997年11月発行)
技術講座 一般
25巻11号(1997年10月発行)
技術講座 生理
25巻10号(1997年9月発行)
技術講座 血液
25巻9号(1997年8月発行)
技術講座 一般
25巻8号(1997年7月発行)
技術講座 一般
25巻7号(1997年6月発行)
増刊号 輸血検査実践マニュアル
25巻6号(1997年6月発行)
技術講座 免疫
25巻5号(1997年5月発行)
技術講座 生理
25巻4号(1997年4月発行)
技術講座 生理
25巻3号(1997年3月発行)
技術講座 微生物
25巻2号(1997年2月発行)
技術講座 生理
25巻1号(1997年1月発行)
技術講座 一般
24巻13号(1996年12月発行)
技術講座 生理
24巻12号(1996年11月発行)
技術講座 一般
24巻11号(1996年10月発行)
技術講座 生理
24巻10号(1996年9月発行)
技術講座 管理
24巻9号(1996年8月発行)
技術講座 生理
24巻8号(1996年7月発行)
技術講座 生理
24巻7号(1996年6月発行)
増刊号 感染症検査実践マニュアル
24巻6号(1996年6月発行)
技術講座 病理
24巻5号(1996年5月発行)
技術講座 生理
24巻4号(1996年4月発行)
技術講座 生理
24巻3号(1996年3月発行)
技術講座 生理
24巻2号(1996年2月発行)
技術講座 生理
24巻1号(1996年1月発行)
技術講座 一般
23巻13号(1995年12月発行)
技術講座 生理
23巻12号(1995年11月発行)
技術講座 病理
23巻11号(1995年10月発行)
技術講座 微生物
23巻10号(1995年9月発行)
技術講座 生理
23巻9号(1995年8月発行)
技術講座 一般
23巻8号(1995年7月発行)
技術講座 免疫
23巻7号(1995年6月発行)
技術講座 生理
23巻6号(1995年5月発行)
技術講座 一般
23巻5号(1995年4月発行)
増刊号 臨床生理検査実践マニュアル画像検査を中心として
23巻4号(1995年4月発行)
技術講座 病理
23巻3号(1995年3月発行)
技術講座 病理
23巻2号(1995年2月発行)
技術講座 一般
23巻1号(1995年1月発行)
技術講座 生理
22巻13号(1994年12月発行)
技術講座 一般
22巻12号(1994年11月発行)
技術講座 一般
22巻11号(1994年10月発行)
技術講座 一般
22巻10号(1994年9月発行)
技術講座 一般
22巻9号(1994年8月発行)
技術講座 生理
22巻8号(1994年7月発行)
技術講座 病理
22巻7号(1994年6月発行)
技術講座 一般
22巻6号(1994年5月発行)
技術講座 一般
22巻5号(1994年4月発行)
増刊号 免疫検査実践マニュアル
22巻4号(1994年4月発行)
技術講座 生理
22巻3号(1994年3月発行)
技術講座 免疫
22巻2号(1994年2月発行)
技術講座 一般
22巻1号(1994年1月発行)
技術講座 生理
21巻13号(1993年12月発行)
技術講座 一般
21巻12号(1993年11月発行)
技術講座 一般
21巻11号(1993年10月発行)
技術講座 一般
21巻10号(1993年9月発行)
技術講座 生理
21巻9号(1993年8月発行)
技術講座 一般
21巻8号(1993年7月発行)
技術講座 病理
21巻7号(1993年6月発行)
技術講座 一般
21巻6号(1993年5月発行)
技術講座 生理
21巻5号(1993年4月発行)
増刊号 臨床化学実践マニュアル
21巻4号(1993年4月発行)
技術講座 生理
21巻3号(1993年3月発行)
技術講座 病理
21巻2号(1993年2月発行)
技術講座 生理
21巻1号(1993年1月発行)
技術講座 生理
20巻13号(1992年12月発行)
技術講座 一般
20巻12号(1992年11月発行)
技術講座 一般
20巻11号(1992年10月発行)
技術講座 一般
20巻10号(1992年9月発行)
技術講座 一般
20巻9号(1992年8月発行)
技術講座 一般
20巻8号(1992年7月発行)
技術講座 血液
20巻7号(1992年6月発行)
技術講座 一般
20巻6号(1992年5月発行)
増刊号 尿検査法
20巻5号(1992年5月発行)
技術講座 生理
20巻4号(1992年4月発行)
技術講座 生理
20巻3号(1992年3月発行)
技術講座 病理
20巻2号(1992年2月発行)
技術講座 一般
20巻1号(1992年1月発行)
技術講座 生理
19巻13号(1991年12月発行)
技術講座 管理
19巻12号(1991年11月発行)
技術講座 生理
19巻11号(1991年10月発行)
技術講座 生理
19巻10号(1991年9月発行)
技術講座 一般
19巻9号(1991年8月発行)
技術講座 一般
19巻8号(1991年7月発行)
技術講座 生理
19巻7号(1991年6月発行)
増刊号 臨床血液検査
19巻6号(1991年6月発行)
技術講座 生理
19巻5号(1991年5月発行)
技術講座 生理
19巻4号(1991年4月発行)
技術講座 一般
19巻3号(1991年3月発行)
技術講座 生理
19巻2号(1991年2月発行)
技術講座 生理
19巻1号(1991年1月発行)
技術講座 一般
18巻13号(1990年12月発行)
技術講座 生理
18巻12号(1990年11月発行)
技術講座 微生物
18巻11号(1990年10月発行)
技術講座 生理
18巻10号(1990年9月発行)
技術講座 一般
18巻9号(1990年8月発行)
技術講座 一般
18巻8号(1990年7月発行)
技術講座 一般
18巻7号(1990年6月発行)
技術講座 一般
18巻6号(1990年5月発行)
増刊号 血液・尿以外の体液検査法
18巻5号(1990年5月発行)
技術講座 一般
18巻4号(1990年4月発行)
技術講座 一般
18巻3号(1990年3月発行)
技術講座 血液
18巻2号(1990年2月発行)
技術講座 生理
18巻1号(1990年1月発行)
技術講座 生理
17巻13号(1989年12月発行)
技術講座 一般
17巻12号(1989年11月発行)
技術講座 一般
17巻11号(1989年10月発行)
技術講座 一般
17巻10号(1989年9月発行)
技術講座 一般
17巻9号(1989年8月発行)
技術講座 生理
17巻8号(1989年7月発行)
技術講座 血清
17巻7号(1989年6月発行)
技術講座 一般
17巻6号(1989年5月発行)
感染症の検査法 Ⅲ 検査法各論
17巻5号(1989年5月発行)
技術講座 一般
17巻4号(1989年4月発行)
技術講座 生理
17巻3号(1989年3月発行)
技術講座 病理
17巻2号(1989年2月発行)
技術講座 一般
17巻1号(1989年1月発行)
技術講座 生理
16巻13号(1988年12月発行)
技術講座 一般
16巻12号(1988年11月発行)
技術講座 一般
16巻11号(1988年10月発行)
技術講座 一般
16巻10号(1988年9月発行)
技術講座 生理
16巻9号(1988年8月発行)
技術講座 一般
16巻8号(1988年7月発行)
技術講座 一般
16巻7号(1988年6月発行)
免疫化学検査法 資料
16巻6号(1988年6月発行)
技術講座 一般
16巻5号(1988年5月発行)
技術講座 一般
16巻4号(1988年4月発行)
技術講座 病理
16巻3号(1988年3月発行)
技術講座 生理
16巻2号(1988年2月発行)
技術講座 一般
16巻1号(1988年1月発行)
技術講座 血液
15巻13号(1987年12月発行)
技術講座 一般
15巻12号(1987年11月発行)
技術講座 病理
15巻11号(1987年10月発行)
技術講座 細胞診
15巻10号(1987年9月発行)
技術講座 一般
15巻9号(1987年8月発行)
技術講座 細胞診
15巻8号(1987年7月発行)
技術講座 病理
15巻7号(1987年6月発行)
技術講座 病理
15巻6号(1987年5月発行)
技術講座 病理
15巻5号(1987年4月発行)
臨床生理検査と技術 座談会
15巻4号(1987年4月発行)
技術講座 生理
15巻3号(1987年3月発行)
技術講座 血液
15巻2号(1987年2月発行)
技術講座 一般
15巻1号(1987年1月発行)
技術講座 病理
14巻13号(1986年12月発行)
技術講座 一般
14巻12号(1986年11月発行)
技術講座 病理
14巻11号(1986年10月発行)
技術講座 血清
14巻10号(1986年9月発行)
技術講座 血清
14巻9号(1986年8月発行)
技術講座 生理
14巻8号(1986年7月発行)
技術講座 血清
14巻7号(1986年6月発行)
技術講座 病理
14巻6号(1986年5月発行)
技術講座 生理
14巻5号(1986年4月発行)
形態学的検査と技術 血液と病理
14巻4号(1986年4月発行)
技術講座 病理
14巻3号(1986年3月発行)
技術講座 細菌
14巻2号(1986年2月発行)
技術講座 病理
14巻1号(1986年1月発行)
技術講座 細菌
13巻12号(1985年12月発行)
技術講座 病理
13巻11号(1985年11月発行)
技術講座 病理
13巻10号(1985年10月発行)
技術講座 生理
13巻9号(1985年9月発行)
技術講座 病理
13巻8号(1985年8月発行)
技術講座 病理
13巻7号(1985年7月発行)
技術講座 血液
13巻6号(1985年6月発行)
技術講座 一般
13巻5号(1985年5月発行)
技術講座 病理
13巻4号(1985年4月発行)
技術講座 一般
13巻3号(1985年3月発行)
技術講座 血液
13巻2号(1985年2月発行)
技術講座 一般
13巻1号(1985年1月発行)
技術講座 血液
12巻12号(1984年12月発行)
技術講座 血液
12巻11号(1984年11月発行)
技術講座 病理
12巻10号(1984年10月発行)
技術講座 輸血
12巻9号(1984年9月発行)
技術講座 一般
12巻8号(1984年8月発行)
技術講座 細菌
12巻7号(1984年7月発行)
技術講座 細菌
12巻6号(1984年6月発行)
技術講座 生理
12巻5号(1984年5月発行)
技術講座 一般
12巻4号(1984年4月発行)
技術講座 病理
12巻3号(1984年3月発行)
技術講座 血液
12巻2号(1984年2月発行)
技術講座 一般
12巻1号(1983年12月発行)
技術講座 血清
11巻12号(1983年12月発行)
技術講座 一般
11巻11号(1983年11月発行)
技術講座 細菌
11巻10号(1983年10月発行)
技術講座 細胞診
11巻9号(1983年9月発行)
技術講座 一般
11巻8号(1983年8月発行)
技術講座 血清
11巻7号(1983年7月発行)
技術講座 細菌
11巻6号(1983年6月発行)
技術講座 一般
11巻5号(1983年5月発行)
技術講座 病理
11巻4号(1983年4月発行)
技術講座 一般
11巻3号(1983年3月発行)
技術講座 血液
11巻2号(1983年2月発行)
技術講座 一般
11巻1号(1983年1月発行)
技術講座 血液
10巻12号(1982年12月発行)
技術講座 一般
10巻11号(1982年11月発行)
技術講座 生理
10巻10号(1982年10月発行)
技術講座 血清
10巻9号(1982年9月発行)
技術講座 細菌
10巻8号(1982年8月発行)
技術講座 一般
10巻7号(1982年7月発行)
技術講座 病理
10巻6号(1982年6月発行)
技術講座 細菌
10巻5号(1982年5月発行)
技術講座 病理
10巻4号(1982年4月発行)
技術講座 血清
10巻3号(1982年3月発行)
技術講座 生化学
10巻2号(1982年2月発行)
技術講座 病理
10巻1号(1982年1月発行)
技術講座 生化学
9巻12号(1981年12月発行)
技術講座 細菌
9巻11号(1981年11月発行)
技術講座 生理
9巻10号(1981年10月発行)
技術講座 一般
9巻9号(1981年9月発行)
技術講座 血清
9巻8号(1981年8月発行)
技術講座 血清
9巻7号(1981年7月発行)
技術講座 生理
9巻6号(1981年6月発行)
技術講座 細菌
9巻5号(1981年5月発行)
技術講座 一般
9巻4号(1981年4月発行)
技術講座 一般
9巻3号(1981年3月発行)
技術講座 血清
9巻2号(1981年2月発行)
技術講座 一般
9巻1号(1981年1月発行)
技術講座 生化学
8巻12号(1980年12月発行)
技術講座 一般
8巻11号(1980年11月発行)
技術講座 生理
8巻10号(1980年10月発行)
技術講座 検体の取り扱いと保存
8巻9号(1980年9月発行)
技術講座 病理
8巻8号(1980年8月発行)
技術講座 生化学
8巻7号(1980年7月発行)
技術講座 一般
8巻6号(1980年6月発行)
技術講座 生理
8巻5号(1980年5月発行)
技術講座 生化学
8巻4号(1980年4月発行)
技術講座 血清
8巻3号(1980年3月発行)
技術講座 病理
8巻2号(1980年2月発行)
技術講座 一般
8巻1号(1980年1月発行)
技術講座 生化学
7巻12号(1979年12月発行)
技術講座 一般
7巻11号(1979年11月発行)
技術講座 一般
7巻10号(1979年10月発行)
技術講座 細菌
7巻9号(1979年9月発行)
技術講座 生理
7巻8号(1979年8月発行)
技術講座 病理
7巻7号(1979年7月発行)
技術講座 生理
7巻6号(1979年6月発行)
技術講座 一般
7巻5号(1979年5月発行)
技術講座 血液
7巻4号(1979年4月発行)
技術講座 生理
7巻3号(1979年3月発行)
技術講座 病理
7巻2号(1979年2月発行)
技術講座 細菌
7巻1号(1979年1月発行)
技術講座 生化学
6巻12号(1978年12月発行)
技術講座 細菌
6巻11号(1978年11月発行)
技術講座 病理
6巻10号(1978年10月発行)
技術講座 血清
6巻9号(1978年9月発行)
技術講座 細菌
6巻8号(1978年8月発行)
技術講座 生化学
6巻7号(1978年7月発行)
技術講座 一般
6巻6号(1978年6月発行)
技術講座 病理
6巻5号(1978年5月発行)
技術講座 生理
6巻4号(1978年4月発行)
技術講座 一般
6巻3号(1978年3月発行)
技術講座 病理
6巻2号(1978年2月発行)
技術講座 一般
6巻1号(1978年1月発行)
技術講座 病理
5巻12号(1977年12月発行)
技術講座 生理
5巻11号(1977年11月発行)
技術講座 一般
5巻10号(1977年10月発行)
技術講座 細菌付録
5巻9号(1977年9月発行)
技術講座 一般
5巻8号(1977年8月発行)
技術講座 生理
5巻7号(1977年7月発行)
技術講座 一般
5巻6号(1977年6月発行)
技術講座 一般
5巻5号(1977年5月発行)
技術講座 一般
5巻4号(1977年4月発行)
技術講座 一般
5巻3号(1977年3月発行)
技術講座 一般
5巻2号(1977年2月発行)
技術講座 一般
5巻1号(1977年1月発行)
技術講座 一般
4巻12号(1976年12月発行)
技術講座 一般
4巻11号(1976年11月発行)
技術講座 一般
4巻10号(1976年10月発行)
技術講座 一般
4巻9号(1976年9月発行)
技術講座 一般
4巻8号(1976年8月発行)
技術講座 一般
4巻7号(1976年7月発行)
技術講座 一般
4巻6号(1976年6月発行)
技術講座 一般
4巻5号(1976年5月発行)
技術講座 一般
4巻4号(1976年4月発行)
技術講座 一般
4巻3号(1976年3月発行)
技術講座 一般
4巻2号(1976年2月発行)
技術講座 一般
4巻1号(1976年1月発行)
技術講座 一般
3巻12号(1975年12月発行)
技術講座 一般
3巻11号(1975年11月発行)
技術講座 一般
3巻10号(1975年10月発行)
技術講座 一般
3巻9号(1975年9月発行)
技術講座 一般
3巻7号(1975年8月発行)
特集 必修 日常検査の実技
3巻6号(1975年6月発行)
技術講座 生理
3巻5号(1975年5月発行)
技術講座 一般
3巻4号(1975年4月発行)
技術講座 一般
3巻3号(1975年3月発行)
技術講座 一般
3巻2号(1975年2月発行)
技術講座 一般
3巻1号(1975年1月発行)
技術講座 一般
