サマリー
骨髄増殖性疾患(MPD)は多能性造血幹細胞の異常に起因し,骨髄などにおいて原因不明の増殖を示す疾患群である.代表的なMPDとしては赤芽球系の過形成を特徴とする真性赤血球増加症,巨核球と線維芽細胞が増生する原発性骨髄線維症,骨髄球系の過形成を特徴とする慢性骨髄性白血病,および巨核球と血小板数が増加する本態性血小板血症の4疾患がある.MPDに属する疾患はしばしば相互に移行がみられ,時に急性白血病化する.治療についてはヒドロキシ尿素,インターフェロンが有望視されている.また,近年染色体レベル,分子生物学的レベルで研究が盛んであり,発病や病態,白血病化に関してさらなる解明が期待される.
雑誌目次
検査と技術19巻11号
1991年10月発行
雑誌目次
病気のはなし
骨髄増殖性疾患
著者: 川端浩 , 吉田彌太郎 , 山岸司久
ページ範囲:P.898 - P.903
検査法の基礎
Fmθの出現機序
著者: 水木泰 , 山田通夫
ページ範囲:P.905 - P.909
サマリー
精神活動と脳波活動に関する研究はHans Bergerがヒトの脳波を記録して以後,時を経ずして始められた.それらのなかで,frontal midline theta activity(Fmθ)の研究は主に日本で行われ,種々の特徴が明らかにされてきた.精神作業中に出現するFmθの一般的事項ばかりでなく,その生物学的側面についても紹介した.また波形の類似性から,精神作業時のFmθ,睡眠時のθリズム,睡眠紡錘波が同一の出現機序を有している可能性についても述べた.
血液凝固と抗凝固
著者: 鈴木宏治
ページ範囲:P.911 - P.918
サマリー
血液凝固反応は,傷害組織からの出血を阻止するための生体防御反応の一つである.凝固反応では,主に傷害組織や,そこに粘着・凝集した血小板などの細胞上に凝固因子が集合し,多分子複合体を形成してフィブリン血栓が形成され止血する.他方,血管内には,多数の抗凝固因子が存在し,過度の凝固反応は制御調節されている.出血症や血栓症は,先天性あるいは後天性の原因による両反応系の過度のアンバランスによって生ずると考えられる.
技術講座 生化学
血中ケトン体の測定法
著者: 青木芳和
ページ範囲:P.919 - P.924
サマリー
血中ケトン体は主に糖代謝が阻害されると脂質代謝が亢進し,その結果増加する.このため糖尿病治療の指標のひとつとして測定されている.また近年は肝予備能の推定に動脈血中のケトン体比(アセト酢酸/3-ヒドロキシ酪酸)が利用されている.
血中ケトン体の測定は,主としてアセト酢酸と3-ヒドロキシ酪酸との反応を触媒する3-ヒドロキシ酪酸テヒドロゲナーゼ反応が用いられている.測定法はNADHの増減を測定する紫外部測定法,アセト酢酸とアゾ化合物を作って発色させるジアゾニウム塩法,ホルマザン発色系を利用する試験紙法がある.ここではこれらの代表的測定法について説明した.
免疫
CRP定量法とその問題点
著者: 本多信治 , 吉田浩
ページ範囲:P.925 - P.930
サマリー
c-反応性蛋白(CRP)は,急性相反応物質のひとつとして,主に炎症性疾患や組織破壊をきたす疾患の診断や経過観察のマーカーとして,多くの検査室で測定されている.この測定法としては,従来から毛細管法,一元免疫拡散法(SRID)による半定量法が主流となっていたが,今日では,レーザーネフェロメトリーや免疫比濁法による自動化と定量法が普及し,数多くの検討成績が報告されている.しかし,これまでの検討から多くの問題点も指摘されている.本稿ではラテックス疑集反応を原理としたネフェロメトリーによるBNA,ラテックス免疫比濁法によるLPIA-100とLX-3000,ラテックス凝集反応による積分球濁度を用いたEL-1200,さらに蛍光偏光免疫測定法を原理としたTDXを中心に,これらの測定原理,測定法の特徴と問題点について記述した.
血液
May-Giemsa(Wright-Giemsa)染色
著者: 小宮正行 , 古沢新平
ページ範囲:P.931 - P.933
サマリー
May-Grunwald染色およびWrlght染色(ことに前者)は,顆粒の染色性は良好だが核の染色性が不良で,一方Giemsa染色は逆に核の染色性は良好だが顆粒の染色性が不十分である.そこで両者を組み合わせたMay-Giemsa染色あるいはWright-Giemsa複染色は,各単染色の欠点を補い合った理想的な普通染色法として日常的に用いられている.種々の近代的な血液学的検査法が開発されつつある今日でも,血液および骨髄塗抹普通染色標本から得られる情報の多さと重要性は変わらないが,それには本染色に関する原理と正しい技術をあらためて認識しておくことが必要である.
病理
組織内金属の染色法
著者: 田村猛 , 菊地正子 , 大宮章子 , 佐々木佳郎 , 田中祐吉
ページ範囲:P.934 - P.938
サマリー
組織内金属の対象となるものには,鉄,カルシウム,銅,水銀,亜鉛,クロム,アルミニウムなどがある.その中でも病理組織学的には,カルシウム,鉄,銅の検出を要する頻度が高い.
そこで,本稿ではこれら3つの組織内金属の染色法についてのみ述べた.また,これらの中でも種々の方法があるので,比較的手技が簡単で,感度が高く,特異性に優れた方法を選び,その技術的な解説を試みた.
生理
甲状腺の超音波検査の進めかた
著者: 高梨昇 , 南里和秀 , 小林久雄 , 久保田光博
ページ範囲:P.939 - P.944
サマリー
甲状腺癌,乳癌の発生率は年々上昇しており,これら表在性疾患の診断には超音波検査は必要不可欠な検査法として定着している.本稿では,甲状腺の超音波検査に必要な音響カプラーの使用上の注意点,画像の表示方法,解剖学など,初めて甲状腺を検査する方にもわかりやすく解説した.びまん性甲状腺疾患や甲状腺腫瘍など典型的な甲状腺疾患の超音波像についても特徴的所見を掲載した.また,診断基準や超音波用語の混同を避けるためにも,甲状腺腫瘍の分類は甲状腺癌取扱い規約を,超音波性状は日本超音波医学会の甲状腺腫瘍の診断基準案に準じ,いずれも現段階で最も新しい分類を掲載したので検査の際に参考としていただければ幸いである.
マスターしよう検査技術
プール血清の簡易的な作製法
著者: 山舘周恒 , 関口光夫
ページ範囲:P.949 - P.954
はじめに
精度管理は信頼性の高い臨床検査データを提供するために欠かすことのできない“検査室の義務”のひとつであり,現在,これに用いられる多種多様な管理血清が市販されている.市販管理血清は凍結乾燥品が主流であるが,溶解液,添加物,溶解時の手数とその精度などの問題点が指摘され,近年,凍結状態の管理血清も発売されている.このように多くの種類の管理血清が供給されるようになったことから,精度管理を目的としたプール血清を自家調整する検査室は非常に少なくなってきている.その製法に関する二,三の文献もみられるが1,2),その数は限られている.
自家製プール血清には,経済性,適応項目数の多さ,添加物の有無が明らかであるなど,多くの有用性があり,イオン選択電極に対する防腐剤や,酵素活性測定での添加酵素の由来などの影響を考慮して調整することができる.しかし,その作製には多くの手数と時間を要することから,作製意欲がしだいに薄れてきているのも事実である.筆者らの検査室では年に一度の恒例行事としてプール血清を作製しているが,長年の経験から,その作製手順を簡略化してきているのでここに紹介する.この方法ではデスクタイプの1枚のフィルターに代えて,カートリッジフィルターを使用しており,血清の濾過に費やす時間が短縮される.
検査ファイル
項目●CA72-4
著者: 小西二三男 , 小西奎子
ページ範囲:P.955 - P.957
[1]腫瘍マーカーの概要とCA72-4
腫瘍マーカーは,腫瘍細胞が産生する物質を細胞,血液,分泌液あるいは排泄液の材料で検出測定し,腫瘍の診断や経過観察に利用するものである.しかし,癌細胞だけに特異的に存在する物質の検出測定は,まだ実用段階に到達していない.現在普及している腫瘍マーカーのほとんどは癌関連物質であり,癌細胞だけに存在するものではなく,癌細胞が異常に多く産生する物質を測定し,臨床に応用している.これらの物質はホルモン,蛋白,酵素など多種類にわたり,測定法もさまざまである.免疫測定法はモノクローナル抗体の開発で測定感度が飛躍的に向上し,細胞膜結合糖蛋白を抗原として,多くの腫瘍マーカーが研究作製されてきた.
癌関連抗原(cancer associated antigen)の多くにCAシリーズの名称がつけられているが,使用した抗原や作製過程は異なり,まだエピトープの未決定のものもあるが,血液型糖鎖関連ファミリーに属するものでは,エピトープの糖鎖構造と合成経路がよく解析されている.
項目●肝細胞増殖因子(HGF)
著者: 二井谷好行
ページ範囲:P.958 - P.959
はじめに
肝細胞増殖因子(hepatocyte growth factor;HGF)は,1967年Mooltonらにより部分肝切除ラットの血液中に存在する肝再生を促進させる因子として見いだされた1).その後,劇症肝炎患者血中に同様の因子が存在することが確認され,ヒト肝細胞増殖因子(human hepatocyte growth factor;hHGF)と名づけられた2〜4).
hHGFは分子量56〜65 kDの重鎖と31.5〜34.5kDの軽鎖とから成り,その二次構造も最近解明された(図1)5).またhHGFの分子構造と性能を表に示す.hHGFは肝再生促進作用を有することから肝治療薬として期待されるばかりでなく,劇症肝炎患者血中に存在することより,致死率80%を超す予後不良の疾患である劇症肝炎の予知および予後診断に有用なマーカーとして期待されている.本稿では,このhHGFのELISAについて述べたい.
試薬●coupling medium(伝達物質)
著者: 南里和秀
ページ範囲:P.960 - P.962
はじめに
従来,乳房,甲状腺などの体表臓器の超音波検査には,機械式アークスキャンが使用されていた.しかし,水槽の脱着,脱気水作製の手間,頸部に与える水槽の圧迫感,検査時間の延長などの問題があり,現在ではリニア電子スキャンやセクタスキャン装置が普及している.電子走査型探触子は比較的大きいため,体表に直接接触させただけでは接触が悪く良好な画像が得られないことが多い.通常体表臓器の検査や体表面への密着性が悪いやせた老人,アーチファクトの影響や焦点距離の問題,あるいは解剖学的な形状の点から探触子と皮膚との問には伝達物質(coupling medium)として音響カプラーを用いることが多くなってきている(図1).
用語●カットオフ値
著者: 大倉久直
ページ範囲:P.963 - P.965
[1]カットオフ値とは
臨床検査におけるカットオフ値とは,2つのグループ(通常は正常人と特定疾患群)を識別する目的で定めた,境界値または〔しきい(=閾)値〕のことをいい,個々の検査について,診断の明らかな多数のデータを元にして決められる.
しかし,このしきい値は,分けようとする両グループの性格と,2群に分けることの背後にある「真の目的」によってさまざまに定められるので,常に正常値の境界を意味するわけではない.例えば,良性肝疾患と肝細胞癌を区別するには,AFPのカットオフ値を正常上界値の20ng/mlではなく,200ng/mlまたは400ng/mlに定めるほうが妥当とされている.しかし,カットオフ値をどのように決めても,少なからぬ例外ができるのが普通である.AFPの例では,400ng/mlを超える良性肝疾患も,またこれより低い値の肝細胞癌も多数あって,これらはそれぞれ偽陽性,偽陰性と呼ばれる.言い換えると,カットオフ値とは,ある範囲に一部重なり合って分布している2群を分別するために,最も適当と考えられる一点に恣意的に設定されるものだが,その設定目的と数理的根拠はさまざまで,絶対的なものではない.
トピックス
遺伝性発作性夜間ヘモグロビン尿症—CD59欠損による
著者: 折居忠夫 , 山階学
ページ範囲:P.978 - P.979
■発作性夜間ヘモグロビン尿症
発作性夜間ヘモグロビン尿症(paroxysmal nocturnal hemoglobinuria;PNH)は,突然変異により造血幹細胞の分化の段階で自己補体に感受性の高い異常赤血球が産生され,それが血管内で溶血する後天性の溶血性疾患と定義されている.そのため,PNH患者では夜間睡眠時などに体液が弱酸性となり,補体の活性が起こると異常赤血球が血管内溶血を起こし,貧血やヘモグロビン尿を呈することとなる.近年,このPNH赤血球の補体感受性の亢進が,血球膜上に存在する補体制御膜蛋白の欠損と密接な関連性のあることが明らかになった.
カテプシンL
著者: 唐渡孝枝 , 勝沼信彦
ページ範囲:P.979 - P.981
はじめに
高等動物に存在するリソゾームは,各種高分子化合物の細胞内での分解を担っているオルガネラである.蛋白質に関しても,細胞構成蛋白質ならびに,外来蛋白質ともに,最終的にはリソゾームで分解されるものが多い.このリソゾームには蛋白質分解酵素が各種存在しているが,その中でもシステインプロテアーゼは重要な役割をしている群であり,特にカテプシンB,H,L,J,Sは代表的なものとして知られている.
カテプシンLは筆者ら1)とKirschkeら2)が,おのおの独自に,初めてラット肝より単離精製に成功したプロテアーゼであるが,その極端な不安定性と低含量のため,他のカテプシン群に比して研究が特に遅れ,完全な構造と遺伝子構造が決定されたのは最近である.このLが特にリソゾームにおける蛋白質分解のイニシエーションに大きな役割を果たしていることが,最近明らかになりつつあり,大変重要視されている.ここでは,このLの性質,構造,機能(病態との関係)について,筆者らの得た結果を中心として紹介したい.
フルクトサミン測定法の変更
著者: 奥田清
ページ範囲:P.981 - P.982
フルクトサミン測定法開発の経緯は表1に示すように,1982年にニュージーランドのJohnson,R. N.,Baker,J. R.らがNBTの還元を用いたglycated protein(フルクトサミン;fructosamine)の測定を発表したのに始まる1).
1988年の4月には健保に収載され,日本で非常に急速な広がりをみせ,日常の臨床検査として現在すでに定着したかに思える.
ガンマナイフ
著者: 河本俊介 , 高倉公朋
ページ範囲:P.983 - P.984
高線量の放射線を,目標部位だけに選択的に照射してその組織を破壊する方法を放射線外科(radiosurgery)といい,このための装置として1968年Leksellによりスウェーデンで開発されたのがガンマナイフである.1970年代に脳動静脈奇形や聴神経腫瘍の治療経験が蓄積され良好な成績が発表されて以来,手術的に到達の困難な脳深部病変の安全な治療法としての位置づけを確立しつつある.
検査データを考える
好中球アルカリホスファターゼ
著者: 浦部晶夫
ページ範囲:P.967 - P.969
はじめに
好中球アルカリホスファターゼ(neutrophil alkaline phosphatase;NAP)は,分葉核好中球に存在する酵素である.NAPは,慢性骨髄性白血病(chronic myelogenous leukemia;CML)を鑑別するうえで有用である.ここではNAPの臨床上の意義を実例に即して述べてみたい.
生体のメカニズム・10
主要組織適合遺伝子複合体
著者: 柏木登
ページ範囲:P.972 - P.975
主要組織適合遺伝子複合体(major histocompatibility complex;MHC)は,その名の通り,同種移植の拒絶反応の原因となる主要な移植抗原を決める遺伝子の複合体として定義された.しかし,MHC産物の組織適合抗原としての機能は,人為的な同種移植が行われたために浮上したむしろ副次的なものであって,本来の機能は,個体が外来抗原に対して発揮する免疫応答の過程において中枢的な役割を果たす分子のひとつであると考えられている.その理由は次のことが明白となったからである.
体内に入った蛋白質性の抗原体は,それが単独の分子であろうと,あるいは巨大な化学構造物に組み込まれた複合体の一部であろうと,マクロファージを代表とする抗原提示細胞によって食作用された後は,細胞内でペプチドのレベルまで分解される.そのペプチドは,抗原提示細胞の作るMHC分子と複合体を形成した後,細胞表面に表現されてくる.そして,T細胞上にある抗原レセプター(T cell receptor;TcR)の結合する抗原体は,このMHC分子・ペプチド複合体だけであって,他の形態の抗原体は,蛋白質であれ,脂質であれ,糖質であれ,TcRと結合することができない.
講座 英語論文を読む・10
臍帯血中のジギタリス様物質の部分精製
著者: 弘田明成
ページ範囲:P.970 - P.971
ヒトの体液中には細胞膜のナトリウム/カリウムポンプを阻害しうる内因性の配糖体様物質が存在していることを多くの研究者が報告してきている.妊娠,新生児,血管性高血圧,肝不全および心不全などのときにはこれらの阻害物質の血中濃度が上昇することはすでに認められており,このことはこの物質がこれらの病態のときにはなんらかの役割を果たしている可能性を示唆している.これらの物質はまたいろいろな抗ジゴキシン抗体と反応する可能性がある.しかし,これらの物質の構造もその産生部位も明らかではない.さらに,これらの阻害物質が血漿中のさまざまな物質の存在を意味しているのか,また,どの程度までそれが単に測定に用いたアッセイ系の非特異的反応であるかもいまだに明らかにはなっていない.文献にこのような相反する結果がみられることを,部分的にはこれらの物質を抽出や精製するのに用いたさまざまな方法の相違によって説明することが可能かもしれない.
われわれは新生児(臍帯血)および成人の血漿中に存在している抗ジゴキシン抗体と交叉反応を示し,しかも,(赤血球による)86Rbの取り込みを阻害する物質の部分精製の方法を述べる.
明日の検査技師に望む
技術革新と検査室の対応
著者: 岡田正彦
ページ範囲:P.904 - P.904
世間では,技術革新が起こるたびに,その技術を第○世代などと呼ぶのがつい最近まで流行っていた.しかし,この頃は進歩があまりに目まぐるしく,いちいち数えていられなくなってきた.臨床検査の分野も同様である.
けんさアラカルト
医療機器のメインテナンス
著者: 小林昭
ページ範囲:P.910 - P.910
■メインテナンスの考えかた
医療機器においては,その機能面からの要求として,信頼性,安全性の確保は極めて重要な課題である.この課題の解決には機器の保守管理(メインテナンス)の考えかたが基本になる.
保守管理は適正な点検を正確かつ適切な時期に行うことであると考えられるが,この点検の内容のうち,信頼性については,機器が本来持つべき性能をその通りに発揮するように維持することであり精度管理とも呼ばれる.検査機器であればその検査データが正確であって,その誤差が許容範囲内であることが要求されるわけで,それを維持することを示している.
けんさ質問箱
Q 交差適合試験としてのブロメリン法
著者: 秋田真哉 , T.H.
ページ範囲:P.985 - P.986
交差適合試験を通常の方法にしたいのですが,ブロメリン法のみを考えています.クームス血清も用意しておくべきでしょうか.
Q 外注検査の時間的経過による検査値への影響
著者: 星野茂 , T.H.
ページ範囲:P.986 - P.987
当院はほとんどの検査を外注し,緊急検査のみ院内で行っています.外注の集配から検査センターまで約1時間かかります.ヘパプラスチンテスト,プロトロンビン時間,活性化部分トロンボプラスチン時間などの検査のための検体も採血スピッツのまま持って帰ってもらっています.検査値に影響はないでしょうか.
Q 蛋白分画中のβ-リポ蛋白
著者: 安部彰 ,
ページ範囲:P.987 - P.988
セパラックスに塗布した蛋白分画を自動分画感度調整機能(検体測定中,5分画以外の場合には機能が作動して自動的に感度を調整する)付きのデンシトメーターで測定し,β-リポ蛋白がα2分画からβ分画にかけて縞の形成ができたときに,α2分画として読み取ったり,β分画として読み取ったりしています.ところで,教科書ではβ-リポ蛋白やトランスフェリンなどはβ分画に含まれるよう書かれていますが,どちらにするべきなのでしょうか.
Q 一般サルモネラ菌に有効な薬剤
著者: 増田剛太 , T.M.
ページ範囲:P.989 - P.990
一般サルモネラ菌(保菌者も含めて)に有効な薬剤はないとの記事がありましたが,現在,最も進歩したサルモネラに対する薬剤および治療法はどのようなものでしょうか.薬剤がききにくいわけもお教えください.
今月の表紙
腹部大動脈瘤の三次元像
著者: 布川雅雄 , 畠山卓弥
ページ範囲:P.945 - P.945
腹部大動脈瘤は,閉塞性動脈硬化症とともに動脈硬化性変化の終末像とされている.この病態は壁の肥厚や内腔の狭窄といった通常の動脈硬化性変化と異なり,破裂という重篤な病態に至る可能性を秘めているため,破裂頻度や破裂に至る拡張進展様式の解明が待たれている.
近年超音波診断装置(US)やX線CTが日常の診療に取り入れられ,腹部大動脈瘤の大きさに関する術前評価が正確になってきている.これを基に瘤の最大横径と破裂との関連が報告され,現在では手術適応の基準を瘤径が5〜6cm以上の場合としている施設が多い.
基本情報
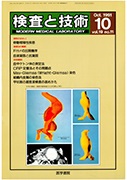
バックナンバー
52巻12号(2024年12月発行)
技術講座 生理
52巻11号(2024年11月発行)
技術講座 生理
52巻10号(2024年10月発行)
技術講座 生理
52巻9号(2024年9月発行)
増大号 臨床医に伝わりやすい 検査報告書とパニック値報告の心得
52巻8号(2024年8月発行)
技術講座 生理
52巻7号(2024年7月発行)
技術講座 生理
52巻6号(2024年6月発行)
技術講座 生理
52巻5号(2024年5月発行)
技術講座 その他
52巻4号(2024年4月発行)
技術講座 生理
52巻3号(2024年3月発行)
増大号 POCUSの決め手。 早く、正確な診断のために
52巻2号(2024年2月発行)
技術講座 生理
52巻1号(2024年1月発行)
技術講座 その他
51巻12号(2023年12月発行)
技術講座 生理
51巻11号(2023年11月発行)
技術講座 生理
51巻10号(2023年10月発行)
技術講座 その他
51巻9号(2023年9月発行)
増大号 匠から学ぶ 血栓止血検査ガイド
51巻8号(2023年8月発行)
技術講座 生理
51巻7号(2023年7月発行)
技術講座 生理
51巻6号(2023年6月発行)
技術講座 生理
51巻5号(2023年5月発行)
技術講座 生理
51巻4号(2023年4月発行)
技術講座 生理
51巻3号(2023年3月発行)
増大号 症例から学ぶ 疾患と検査値の推移
51巻2号(2023年2月発行)
技術講座 その他
51巻1号(2023年1月発行)
技術講座 生理
50巻12号(2022年12月発行)
技術講座 その他
50巻11号(2022年11月発行)
技術講座 生理
50巻10号(2022年10月発行)
技術講座 生理
50巻9号(2022年9月発行)
増大号 希少例と特殊像がわかる! エコーの撮り方完全マスター
50巻8号(2022年8月発行)
技術講座 生理
50巻7号(2022年7月発行)
技術講座 生理
50巻6号(2022年6月発行)
技術講座 生理
50巻5号(2022年5月発行)
技術講座 生理
50巻4号(2022年4月発行)
技術講座 生理
50巻3号(2022年3月発行)
増大号 見て学ぶ 一般検査学アトラス—外観検査から顕微鏡検査まで
50巻2号(2022年2月発行)
技術講座 その他
50巻1号(2022年1月発行)
技術講座 生理
49巻12号(2021年12月発行)
技術講座 生理
49巻11号(2021年11月発行)
技術講座 生理
49巻10号(2021年10月発行)
技術講座 生理
49巻9号(2021年9月発行)
増刊号 病態別 腹部エコーの観察・記録・報告書作成マスター
49巻8号(2021年8月発行)
技術講座 生理
49巻7号(2021年7月発行)
技術講座 生理
49巻6号(2021年6月発行)
技術講座 生理
49巻5号(2021年5月発行)
技術講座 生理
49巻4号(2021年4月発行)
技術講座 一般
49巻3号(2021年3月発行)
増刊号 First&Next Step 微生物検査サポートブック
49巻2号(2021年2月発行)
技術講座 微生物
49巻1号(2021年1月発行)
技術講座 病理・生理
48巻12号(2020年12月発行)
技術講座 その他
48巻11号(2020年11月発行)
技術講座 生化学
48巻10号(2020年10月発行)
技術講座 生理
48巻9号(2020年9月発行)
増刊号 学会発表・論文執筆はもう怖くない! 臨床検査技師のための研究入門
48巻8号(2020年8月発行)
技術講座 遺伝子
48巻7号(2020年7月発行)
技術講座 その他
48巻6号(2020年6月発行)
技術講座 輸血
48巻5号(2020年5月発行)
技術講座 生化学
48巻4号(2020年4月発行)
技術講座 生理
48巻3号(2020年3月発行)
増刊号 採血のすべて—手技から採血室の運用まで徹底解説
48巻2号(2020年2月発行)
技術講座 微生物
48巻1号(2020年1月発行)
技術講座 生理
47巻12号(2019年12月発行)
技術講座 病理
47巻11号(2019年11月発行)
技術講座 生理
47巻10号(2019年10月発行)
技術講座 生理
47巻9号(2019年9月発行)
増刊号 染色画像を比べて学ぶ 体腔液アトラス
47巻8号(2019年8月発行)
技術講座 病理
47巻7号(2019年7月発行)
技術講座 一般
47巻6号(2019年6月発行)
技術講座 血液
47巻5号(2019年5月発行)
技術講座 血液
47巻4号(2019年4月発行)
技術講座 血液
47巻3号(2019年3月発行)
増刊号 エキスパートが教える 心・血管エコー計測のノウハウ
47巻2号(2019年2月発行)
技術講座 病理
47巻1号(2019年1月発行)
技術講座 微生物
46巻12号(2018年12月発行)
技術講座 生理
46巻11号(2018年11月発行)
技術講座 輸血・遺伝子検査
46巻10号(2018年10月発行)
技術講座 その他
46巻9号(2018年9月発行)
増刊号 現場で“パッ”と使える 免疫染色クイックガイド
46巻8号(2018年8月発行)
技術講座 輸血・遺伝子検査
46巻7号(2018年7月発行)
技術講座 生理
46巻6号(2018年6月発行)
技術講座 管理
46巻5号(2018年5月発行)
技術講座 生化学
46巻4号(2018年4月発行)
技術講座 一般
46巻3号(2018年3月発行)
増刊号 感染症クイックリファレンス
46巻2号(2018年2月発行)
技術講座 輸血
46巻1号(2018年1月発行)
技術講座 病理
45巻12号(2017年12月発行)
技術講座 生理
45巻11号(2017年11月発行)
技術講座 一般
45巻10号(2017年10月発行)
技術講座 微生物
45巻9号(2017年9月発行)
増刊号 循環器病院の技師が教える メディカルスタッフのための心電図教室
45巻8号(2017年8月発行)
技術講座 栄養
45巻7号(2017年7月発行)
技術講座 病理
45巻6号(2017年6月発行)
技術講座 病理
45巻5号(2017年5月発行)
技術講座 細胞治療・管理
45巻4号(2017年4月発行)
技術講座 遺伝子・染色体検査
45巻3号(2017年3月発行)
45巻2号(2017年2月発行)
技術講座 細胞治療
45巻1号(2017年1月発行)
技術講座 病理
44巻13号(2016年12月発行)
技術講座 免疫
44巻12号(2016年11月発行)
技術講座 微生物
44巻11号(2016年10月発行)
技術講座 微生物
44巻10号(2016年9月発行)
増刊号 はじめて出会う 検査画像
44巻9号(2016年9月発行)
技術講座 管理・その他
44巻8号(2016年8月発行)
技術講座 微生物
44巻7号(2016年7月発行)
技術講座 生理
44巻6号(2016年6月発行)
技術講座 微生物
44巻5号(2016年5月発行)
技術講座 生理
44巻4号(2016年4月発行)
技術講座 微生物
44巻3号(2016年3月発行)
技術講座 生理
44巻2号(2016年2月発行)
技術講座 微生物
44巻1号(2016年1月発行)
技術講座 微生物
43巻13号(2015年12月発行)
技術講座 生化学
43巻12号(2015年11月発行)
技術講座 生化学
43巻11号(2015年10月発行)
技術講座 一般
43巻10号(2015年9月発行)
増刊号 血液形態アトラス
43巻9号(2015年9月発行)
技術講座 生理
43巻8号(2015年8月発行)
技術講座 生理
43巻7号(2015年7月発行)
技術講座 生理
43巻6号(2015年6月発行)
技術講座 微生物
43巻5号(2015年5月発行)
技術講座 移植医療
43巻4号(2015年4月発行)
技術講座 病理
43巻3号(2015年3月発行)
技術講座 血液
43巻2号(2015年2月発行)
技術講座 管理
43巻1号(2015年1月発行)
技術講座 病理
42巻13号(2014年12月発行)
技術講座 生化学
42巻12号(2014年11月発行)
技術講座 病理
42巻11号(2014年10月発行)
技術講座 血液
42巻10号(2014年9月発行)
増刊号 超音波×病理 対比アトラス
42巻9号(2014年9月発行)
技術講座 生理
42巻8号(2014年8月発行)
技術講座 免疫
42巻7号(2014年7月発行)
技術講座 生理
42巻6号(2014年6月発行)
技術講座 生理
42巻5号(2014年5月発行)
技術講座 病理
42巻4号(2014年4月発行)
技術講座 輸血
42巻3号(2014年3月発行)
技術講座 血液
42巻2号(2014年2月発行)
技術講座 微生物
42巻1号(2014年1月発行)
技術講座 病理
41巻13号(2013年12月発行)
技術講座 生理
41巻12号(2013年11月発行)
技術講座 生化学
41巻11号(2013年10月発行)
技術講座 生化学
41巻10号(2013年9月発行)
増刊号 解剖と正常像がわかる! エコーの撮り方完全マスター
41巻9号(2013年9月発行)
技術講座 微生物
41巻8号(2013年8月発行)
技術講座 生理
41巻7号(2013年7月発行)
技術講座 生理
41巻6号(2013年6月発行)
技術講座 微生物
41巻5号(2013年5月発行)
技術講座 一般
41巻4号(2013年4月発行)
技術講座 生化学
41巻3号(2013年3月発行)
技術講座 生理
41巻2号(2013年2月発行)
技術講座 生理
41巻1号(2013年1月発行)
技術講座 生理
40巻13号(2012年12月発行)
技術講座 血液
40巻12号(2012年11月発行)
技術講座 生理
40巻11号(2012年10月発行)
技術講座 生理
40巻10号(2012年9月発行)
増刊号 この検査データを読めますか?―検査値から病態を探る
40巻9号(2012年9月発行)
技術講座 生理
40巻8号(2012年8月発行)
技術講座 細胞診
40巻7号(2012年7月発行)
技術講座 生理
40巻6号(2012年6月発行)
技術講座 生理
40巻5号(2012年5月発行)
技術講座 生理
40巻4号(2012年4月発行)
技術講座 血液
40巻3号(2012年3月発行)
技術講座 生理
40巻2号(2012年2月発行)
技術講座 輸血
40巻1号(2012年1月発行)
技術講座 遺伝子
39巻13号(2011年12月発行)
疾患と検査値の推移
39巻12号(2011年11月発行)
疾患と検査値の推移
39巻11号(2011年10月発行)
疾患と検査値の推移
39巻10号(2011年9月発行)
増刊号 緊急報告すべき検査結果のすべて―すぐに使えるパニック値事典
39巻9号(2011年9月発行)
疾患と検査値の推移
39巻8号(2011年8月発行)
疾患と検査値の推移
39巻7号(2011年7月発行)
疾患と検査値の推移
39巻6号(2011年6月発行)
技術講座 生理
39巻5号(2011年5月発行)
技術講座 生理
39巻4号(2011年4月発行)
疾患と検査値の推移
39巻3号(2011年3月発行)
疾患と検査値の推移
39巻2号(2011年2月発行)
疾患と検査値の推移
39巻1号(2011年1月発行)
疾患と検査値の推移
38巻13号(2010年12月発行)
疾患と検査値の推移
38巻12号(2010年11月発行)
疾患と検査値の推移
38巻11号(2010年10月発行)
疾患と検査値の推移
38巻10号(2010年9月発行)
増刊号 免疫反応と臨床検査2010
38巻9号(2010年9月発行)
疾患と検査値の推移
38巻8号(2010年8月発行)
疾患と検査値の推移
38巻7号(2010年7月発行)
疾患と検査値の推移
38巻6号(2010年6月発行)
疾患と検査値の推移
38巻5号(2010年5月発行)
疾患と検査値の推移
38巻4号(2010年4月発行)
疾患と検査値の推移
38巻3号(2010年3月発行)
疾患と検査値の推移
38巻2号(2010年2月発行)
疾患と検査値の推移
38巻1号(2010年1月発行)
疾患と検査値の推移
37巻13号(2009年12月発行)
疾患と検査値の推移
37巻12号(2009年11月発行)
疾患と検査値の推移
37巻11号(2009年10月発行)
疾患と検査値の推移
37巻10号(2009年9月発行)
増刊号 顕微鏡検査のコツ―臨床に役立つ形態学
37巻9号(2009年9月発行)
疾患と検査値の推移
37巻8号(2009年8月発行)
疾患と検査値の推移
37巻7号(2009年7月発行)
疾患と検査値の推移
37巻6号(2009年6月発行)
疾患と検査値の推移
37巻5号(2009年5月発行)
疾患と検査値の推移
37巻4号(2009年4月発行)
疾患と検査値の推移
37巻3号(2009年3月発行)
疾患と検査値の推移
37巻2号(2009年2月発行)
疾患と検査値の推移
37巻1号(2009年1月発行)
疾患と検査値の推移
36巻13号(2008年12月発行)
疾患と検査値の推移
36巻12号(2008年11月発行)
疾患と検査値の推移
36巻11号(2008年10月発行)
疾患と検査値の推移
36巻10号(2008年9月発行)
増刊号 これから広がる生理検査・新たにはじまる生理検査
36巻9号(2008年9月発行)
疾患と検査値の推移
36巻8号(2008年8月発行)
疾患と検査値の推移
36巻7号(2008年7月発行)
疾患と検査値の推移
36巻6号(2008年6月発行)
疾患と検査値の推移
36巻5号(2008年5月発行)
疾患と検査値の推移
36巻4号(2008年4月発行)
疾患と検査値の推移
36巻3号(2008年3月発行)
疾患と検査値の推移
36巻2号(2008年2月発行)
疾患と検査値の推移
36巻1号(2008年1月発行)
疾患と検査値の推移
35巻13号(2007年12月発行)
疾患と検査値の推移
35巻12号(2007年11月発行)
疾患と検査値の推移
35巻11号(2007年10月発行)
増刊号 メタボリックシンドローム健診検査技術マニュアル
35巻10号(2007年10月発行)
疾患と検査値の推移
35巻9号(2007年9月発行)
疾患と検査値の推移
35巻8号(2007年8月発行)
疾患と検査値の推移
35巻7号(2007年7月発行)
疾患と検査値の推移
35巻6号(2007年6月発行)
疾患と検査値の推移
35巻5号(2007年5月発行)
疾患と検査値の推移
35巻4号(2007年4月発行)
疾患と検査値の推移
35巻3号(2007年3月発行)
疾患と検査値の推移
35巻2号(2007年2月発行)
疾患と検査値の推移
35巻1号(2007年1月発行)
疾患と検査値の推移
34巻13号(2006年12月発行)
技術講座 生理
34巻12号(2006年11月発行)
技術講座 一般
34巻11号(2006年10月発行)
増刊号 新しい臨床検査・未来の臨床検査
34巻10号(2006年10月発行)
疾患と検査値の推移
34巻9号(2006年9月発行)
疾患と検査値の推移
34巻8号(2006年8月発行)
疾患と検査値の推移
34巻7号(2006年7月発行)
疾患と検査値の推移
34巻6号(2006年6月発行)
疾患と検査値の推移
34巻5号(2006年5月発行)
疾患と検査値の推移
34巻4号(2006年4月発行)
疾患と検査値の推移
34巻3号(2006年3月発行)
疾患と検査値の推移
34巻2号(2006年2月発行)
疾患と検査値の推移
34巻1号(2006年1月発行)
疾患と検査値の推移
33巻13号(2005年12月発行)
疾患と検査値の推移
33巻12号(2005年11月発行)
疾患と検査値の推移
33巻11号(2005年10月発行)
増刊号 一線診療のための臨床検査
33巻10号(2005年10月発行)
疾患と検査値の推移
33巻9号(2005年9月発行)
疾患と検査値の推移
33巻8号(2005年8月発行)
疾患と検査値の推移
33巻7号(2005年7月発行)
疾患と検査値の推移
33巻6号(2005年6月発行)
疾患と検査値の推移
33巻5号(2005年5月発行)
疾患と検査値の推移
33巻4号(2005年4月発行)
疾患と検査値の推移
33巻3号(2005年3月発行)
疾患と検査値の推移
33巻2号(2005年2月発行)
疾患と検査値の推移
33巻1号(2005年1月発行)
疾患と検査値の推移
32巻13号(2004年12月発行)
技術講座 血液
32巻12号(2004年11月発行)
技術講座 病理
32巻11号(2004年10月発行)
技術講座 血液
32巻10号(2004年9月発行)
増刊号 細胞像の見かた―病理・血液・尿沈渣
32巻9号(2004年9月発行)
技術講座 生化学
32巻8号(2004年8月発行)
技術講座 免疫
32巻7号(2004年7月発行)
技術講座 微生物
32巻6号(2004年6月発行)
技術講座 病理
32巻5号(2004年5月発行)
技術講座 病理
32巻4号(2004年4月発行)
技術講座 病理
32巻3号(2004年3月発行)
技術講座 微生物
32巻2号(2004年2月発行)
技術講座 生化学
32巻1号(2004年1月発行)
技術講座 微生物
31巻13号(2003年12月発行)
技術講座 微生物
31巻12号(2003年11月発行)
技術講座 病理
31巻11号(2003年10月発行)
技術講座 微生物
31巻10号(2003年9月発行)
増刊号 包括医療と臨床検査
31巻9号(2003年9月発行)
技術講座 一般
31巻8号(2003年8月発行)
技術講座 微生物
31巻7号(2003年7月発行)
技術講座 病理
31巻6号(2003年6月発行)
技術講座 免疫
31巻5号(2003年5月発行)
技術講座 一般
31巻4号(2003年4月発行)
技術講座 病理
31巻3号(2003年3月発行)
技術講座 生化学
31巻2号(2003年2月発行)
技術講座 免疫
31巻1号(2003年1月発行)
技術講座 免疫
30巻13号(2002年12月発行)
技術講座 生理
30巻12号(2002年11月発行)
技術講座 生理
30巻11号(2002年10月発行)
技術講座 生化学
30巻10号(2002年9月発行)
増刊号 誰でもわかる遺伝子検査
30巻9号(2002年9月発行)
技術講座 微生物
30巻8号(2002年8月発行)
技術講座 生化学
30巻7号(2002年7月発行)
技術講座 微生物
30巻6号(2002年6月発行)
技術講座 生化学
30巻5号(2002年5月発行)
技術講座 微生物
30巻4号(2002年4月発行)
技術講座 一般
30巻3号(2002年3月発行)
技術講座 生化学
30巻2号(2002年2月発行)
技術講座 一般
30巻1号(2002年1月発行)
技術講座 免疫
29巻13号(2001年12月発行)
技術講座 病理
29巻12号(2001年11月発行)
技術講座 生理
29巻11号(2001年10月発行)
技術講座 病理
29巻10号(2001年9月発行)
技術講座 病理
29巻9号(2001年8月発行)
技術講座 病理
29巻8号(2001年7月発行)
技術講座 生理
29巻7号(2001年6月発行)
増刊号 病理組織・細胞診のための日常染色法ガイダンス
29巻6号(2001年6月発行)
技術講座 微生物
29巻5号(2001年5月発行)
技術講座 生理
29巻4号(2001年4月発行)
技術講座 病理
29巻3号(2001年3月発行)
技術講座 微生物
29巻2号(2001年2月発行)
技術講座 微生物
29巻1号(2001年1月発行)
技術講座 一般
28巻13号(2000年12月発行)
技術講座 病理
28巻12号(2000年11月発行)
技術講座 病理
28巻11号(2000年10月発行)
技術講座 免疫
28巻10号(2000年9月発行)
技術講座 微生物
28巻9号(2000年8月発行)
技術講座 微生物
28巻8号(2000年7月発行)
技術講座 生理
28巻7号(2000年6月発行)
増刊号 血液検査実践マニュアル
28巻6号(2000年6月発行)
技術講座 免疫
28巻5号(2000年5月発行)
技術講座 血液
28巻4号(2000年4月発行)
技術講座 一般
28巻3号(2000年3月発行)
技術講座 生理
28巻2号(2000年2月発行)
技術講座 生化学
28巻1号(2000年1月発行)
技術講座 一般
27巻13号(1999年12月発行)
技術講座 病理
27巻12号(1999年11月発行)
技術講座 一般
27巻11号(1999年10月発行)
技術講座 生化学
27巻10号(1999年9月発行)
技術講座 免疫
27巻9号(1999年8月発行)
技術講座 病理
27巻8号(1999年7月発行)
技術講座 病理
27巻7号(1999年6月発行)
増刊号 緊急検査実践マニュアル
27巻6号(1999年6月発行)
技術講座 生化学
27巻5号(1999年5月発行)
技術講座 血液
27巻4号(1999年4月発行)
技術講座 一般
27巻3号(1999年3月発行)
技術講座 生理
27巻2号(1999年2月発行)
技術講座 微生物
27巻1号(1999年1月発行)
技術講座 生理
26巻13号(1998年12月発行)
技術講座 一般
26巻12号(1998年11月発行)
技術講座 病理
26巻11号(1998年10月発行)
技術講座 病理
26巻10号(1998年9月発行)
技術講座 生理
26巻9号(1998年8月発行)
技術講座 生理
26巻8号(1998年7月発行)
技術講座 生理
26巻7号(1998年6月発行)
増刊号 病理組織・細胞診実践マニュアル
26巻6号(1998年6月発行)
技術講座 病理
26巻5号(1998年5月発行)
技術講座 一般
26巻4号(1998年4月発行)
技術講座 病理
26巻3号(1998年3月発行)
技術講座 一般
26巻2号(1998年2月発行)
技術講座 生理
26巻1号(1998年1月発行)
技術講座 血液
25巻13号(1997年12月発行)
技術講座 一般
25巻12号(1997年11月発行)
技術講座 一般
25巻11号(1997年10月発行)
技術講座 生理
25巻10号(1997年9月発行)
技術講座 血液
25巻9号(1997年8月発行)
技術講座 一般
25巻8号(1997年7月発行)
技術講座 一般
25巻7号(1997年6月発行)
増刊号 輸血検査実践マニュアル
25巻6号(1997年6月発行)
技術講座 免疫
25巻5号(1997年5月発行)
技術講座 生理
25巻4号(1997年4月発行)
技術講座 生理
25巻3号(1997年3月発行)
技術講座 微生物
25巻2号(1997年2月発行)
技術講座 生理
25巻1号(1997年1月発行)
技術講座 一般
24巻13号(1996年12月発行)
技術講座 生理
24巻12号(1996年11月発行)
技術講座 一般
24巻11号(1996年10月発行)
技術講座 生理
24巻10号(1996年9月発行)
技術講座 管理
24巻9号(1996年8月発行)
技術講座 生理
24巻8号(1996年7月発行)
技術講座 生理
24巻7号(1996年6月発行)
増刊号 感染症検査実践マニュアル
24巻6号(1996年6月発行)
技術講座 病理
24巻5号(1996年5月発行)
技術講座 生理
24巻4号(1996年4月発行)
技術講座 生理
24巻3号(1996年3月発行)
技術講座 生理
24巻2号(1996年2月発行)
技術講座 生理
24巻1号(1996年1月発行)
技術講座 一般
23巻13号(1995年12月発行)
技術講座 生理
23巻12号(1995年11月発行)
技術講座 病理
23巻11号(1995年10月発行)
技術講座 微生物
23巻10号(1995年9月発行)
技術講座 生理
23巻9号(1995年8月発行)
技術講座 一般
23巻8号(1995年7月発行)
技術講座 免疫
23巻7号(1995年6月発行)
技術講座 生理
23巻6号(1995年5月発行)
技術講座 一般
23巻5号(1995年4月発行)
増刊号 臨床生理検査実践マニュアル画像検査を中心として
23巻4号(1995年4月発行)
技術講座 病理
23巻3号(1995年3月発行)
技術講座 病理
23巻2号(1995年2月発行)
技術講座 一般
23巻1号(1995年1月発行)
技術講座 生理
22巻13号(1994年12月発行)
技術講座 一般
22巻12号(1994年11月発行)
技術講座 一般
22巻11号(1994年10月発行)
技術講座 一般
22巻10号(1994年9月発行)
技術講座 一般
22巻9号(1994年8月発行)
技術講座 生理
22巻8号(1994年7月発行)
技術講座 病理
22巻7号(1994年6月発行)
技術講座 一般
22巻6号(1994年5月発行)
技術講座 一般
22巻5号(1994年4月発行)
増刊号 免疫検査実践マニュアル
22巻4号(1994年4月発行)
技術講座 生理
22巻3号(1994年3月発行)
技術講座 免疫
22巻2号(1994年2月発行)
技術講座 一般
22巻1号(1994年1月発行)
技術講座 生理
21巻13号(1993年12月発行)
技術講座 一般
21巻12号(1993年11月発行)
技術講座 一般
21巻11号(1993年10月発行)
技術講座 一般
21巻10号(1993年9月発行)
技術講座 生理
21巻9号(1993年8月発行)
技術講座 一般
21巻8号(1993年7月発行)
技術講座 病理
21巻7号(1993年6月発行)
技術講座 一般
21巻6号(1993年5月発行)
技術講座 生理
21巻5号(1993年4月発行)
増刊号 臨床化学実践マニュアル
21巻4号(1993年4月発行)
技術講座 生理
21巻3号(1993年3月発行)
技術講座 病理
21巻2号(1993年2月発行)
技術講座 生理
21巻1号(1993年1月発行)
技術講座 生理
20巻13号(1992年12月発行)
技術講座 一般
20巻12号(1992年11月発行)
技術講座 一般
20巻11号(1992年10月発行)
技術講座 一般
20巻10号(1992年9月発行)
技術講座 一般
20巻9号(1992年8月発行)
技術講座 一般
20巻8号(1992年7月発行)
技術講座 血液
20巻7号(1992年6月発行)
技術講座 一般
20巻6号(1992年5月発行)
増刊号 尿検査法
20巻5号(1992年5月発行)
技術講座 生理
20巻4号(1992年4月発行)
技術講座 生理
20巻3号(1992年3月発行)
技術講座 病理
20巻2号(1992年2月発行)
技術講座 一般
20巻1号(1992年1月発行)
技術講座 生理
19巻13号(1991年12月発行)
技術講座 管理
19巻12号(1991年11月発行)
技術講座 生理
19巻11号(1991年10月発行)
技術講座 生理
19巻10号(1991年9月発行)
技術講座 一般
19巻9号(1991年8月発行)
技術講座 一般
19巻8号(1991年7月発行)
技術講座 生理
19巻7号(1991年6月発行)
増刊号 臨床血液検査
19巻6号(1991年6月発行)
技術講座 生理
19巻5号(1991年5月発行)
技術講座 生理
19巻4号(1991年4月発行)
技術講座 一般
19巻3号(1991年3月発行)
技術講座 生理
19巻2号(1991年2月発行)
技術講座 生理
19巻1号(1991年1月発行)
技術講座 一般
18巻13号(1990年12月発行)
技術講座 生理
18巻12号(1990年11月発行)
技術講座 微生物
18巻11号(1990年10月発行)
技術講座 生理
18巻10号(1990年9月発行)
技術講座 一般
18巻9号(1990年8月発行)
技術講座 一般
18巻8号(1990年7月発行)
技術講座 一般
18巻7号(1990年6月発行)
技術講座 一般
18巻6号(1990年5月発行)
増刊号 血液・尿以外の体液検査法
18巻5号(1990年5月発行)
技術講座 一般
18巻4号(1990年4月発行)
技術講座 一般
18巻3号(1990年3月発行)
技術講座 血液
18巻2号(1990年2月発行)
技術講座 生理
18巻1号(1990年1月発行)
技術講座 生理
17巻13号(1989年12月発行)
技術講座 一般
17巻12号(1989年11月発行)
技術講座 一般
17巻11号(1989年10月発行)
技術講座 一般
17巻10号(1989年9月発行)
技術講座 一般
17巻9号(1989年8月発行)
技術講座 生理
17巻8号(1989年7月発行)
技術講座 血清
17巻7号(1989年6月発行)
技術講座 一般
17巻6号(1989年5月発行)
感染症の検査法 Ⅲ 検査法各論
17巻5号(1989年5月発行)
技術講座 一般
17巻4号(1989年4月発行)
技術講座 生理
17巻3号(1989年3月発行)
技術講座 病理
17巻2号(1989年2月発行)
技術講座 一般
17巻1号(1989年1月発行)
技術講座 生理
16巻13号(1988年12月発行)
技術講座 一般
16巻12号(1988年11月発行)
技術講座 一般
16巻11号(1988年10月発行)
技術講座 一般
16巻10号(1988年9月発行)
技術講座 生理
16巻9号(1988年8月発行)
技術講座 一般
16巻8号(1988年7月発行)
技術講座 一般
16巻7号(1988年6月発行)
免疫化学検査法 資料
16巻6号(1988年6月発行)
技術講座 一般
16巻5号(1988年5月発行)
技術講座 一般
16巻4号(1988年4月発行)
技術講座 病理
16巻3号(1988年3月発行)
技術講座 生理
16巻2号(1988年2月発行)
技術講座 一般
16巻1号(1988年1月発行)
技術講座 血液
15巻13号(1987年12月発行)
技術講座 一般
15巻12号(1987年11月発行)
技術講座 病理
15巻11号(1987年10月発行)
技術講座 細胞診
15巻10号(1987年9月発行)
技術講座 一般
15巻9号(1987年8月発行)
技術講座 細胞診
15巻8号(1987年7月発行)
技術講座 病理
15巻7号(1987年6月発行)
技術講座 病理
15巻6号(1987年5月発行)
技術講座 病理
15巻5号(1987年4月発行)
臨床生理検査と技術 座談会
15巻4号(1987年4月発行)
技術講座 生理
15巻3号(1987年3月発行)
技術講座 血液
15巻2号(1987年2月発行)
技術講座 一般
15巻1号(1987年1月発行)
技術講座 病理
14巻13号(1986年12月発行)
技術講座 一般
14巻12号(1986年11月発行)
技術講座 病理
14巻11号(1986年10月発行)
技術講座 血清
14巻10号(1986年9月発行)
技術講座 血清
14巻9号(1986年8月発行)
技術講座 生理
14巻8号(1986年7月発行)
技術講座 血清
14巻7号(1986年6月発行)
技術講座 病理
14巻6号(1986年5月発行)
技術講座 生理
14巻5号(1986年4月発行)
形態学的検査と技術 血液と病理
14巻4号(1986年4月発行)
技術講座 病理
14巻3号(1986年3月発行)
技術講座 細菌
14巻2号(1986年2月発行)
技術講座 病理
14巻1号(1986年1月発行)
技術講座 細菌
13巻12号(1985年12月発行)
技術講座 病理
13巻11号(1985年11月発行)
技術講座 病理
13巻10号(1985年10月発行)
技術講座 生理
13巻9号(1985年9月発行)
技術講座 病理
13巻8号(1985年8月発行)
技術講座 病理
13巻7号(1985年7月発行)
技術講座 血液
13巻6号(1985年6月発行)
技術講座 一般
13巻5号(1985年5月発行)
技術講座 病理
13巻4号(1985年4月発行)
技術講座 一般
13巻3号(1985年3月発行)
技術講座 血液
13巻2号(1985年2月発行)
技術講座 一般
13巻1号(1985年1月発行)
技術講座 血液
12巻12号(1984年12月発行)
技術講座 血液
12巻11号(1984年11月発行)
技術講座 病理
12巻10号(1984年10月発行)
技術講座 輸血
12巻9号(1984年9月発行)
技術講座 一般
12巻8号(1984年8月発行)
技術講座 細菌
12巻7号(1984年7月発行)
技術講座 細菌
12巻6号(1984年6月発行)
技術講座 生理
12巻5号(1984年5月発行)
技術講座 一般
12巻4号(1984年4月発行)
技術講座 病理
12巻3号(1984年3月発行)
技術講座 血液
12巻2号(1984年2月発行)
技術講座 一般
12巻1号(1983年12月発行)
技術講座 血清
11巻12号(1983年12月発行)
技術講座 一般
11巻11号(1983年11月発行)
技術講座 細菌
11巻10号(1983年10月発行)
技術講座 細胞診
11巻9号(1983年9月発行)
技術講座 一般
11巻8号(1983年8月発行)
技術講座 血清
11巻7号(1983年7月発行)
技術講座 細菌
11巻6号(1983年6月発行)
技術講座 一般
11巻5号(1983年5月発行)
技術講座 病理
11巻4号(1983年4月発行)
技術講座 一般
11巻3号(1983年3月発行)
技術講座 血液
11巻2号(1983年2月発行)
技術講座 一般
11巻1号(1983年1月発行)
技術講座 血液
10巻12号(1982年12月発行)
技術講座 一般
10巻11号(1982年11月発行)
技術講座 生理
10巻10号(1982年10月発行)
技術講座 血清
10巻9号(1982年9月発行)
技術講座 細菌
10巻8号(1982年8月発行)
技術講座 一般
10巻7号(1982年7月発行)
技術講座 病理
10巻6号(1982年6月発行)
技術講座 細菌
10巻5号(1982年5月発行)
技術講座 病理
10巻4号(1982年4月発行)
技術講座 血清
10巻3号(1982年3月発行)
技術講座 生化学
10巻2号(1982年2月発行)
技術講座 病理
10巻1号(1982年1月発行)
技術講座 生化学
9巻12号(1981年12月発行)
技術講座 細菌
9巻11号(1981年11月発行)
技術講座 生理
9巻10号(1981年10月発行)
技術講座 一般
9巻9号(1981年9月発行)
技術講座 血清
9巻8号(1981年8月発行)
技術講座 血清
9巻7号(1981年7月発行)
技術講座 生理
9巻6号(1981年6月発行)
技術講座 細菌
9巻5号(1981年5月発行)
技術講座 一般
9巻4号(1981年4月発行)
技術講座 一般
9巻3号(1981年3月発行)
技術講座 血清
9巻2号(1981年2月発行)
技術講座 一般
9巻1号(1981年1月発行)
技術講座 生化学
8巻12号(1980年12月発行)
技術講座 一般
8巻11号(1980年11月発行)
技術講座 生理
8巻10号(1980年10月発行)
技術講座 検体の取り扱いと保存
8巻9号(1980年9月発行)
技術講座 病理
8巻8号(1980年8月発行)
技術講座 生化学
8巻7号(1980年7月発行)
技術講座 一般
8巻6号(1980年6月発行)
技術講座 生理
8巻5号(1980年5月発行)
技術講座 生化学
8巻4号(1980年4月発行)
技術講座 血清
8巻3号(1980年3月発行)
技術講座 病理
8巻2号(1980年2月発行)
技術講座 一般
8巻1号(1980年1月発行)
技術講座 生化学
7巻12号(1979年12月発行)
技術講座 一般
7巻11号(1979年11月発行)
技術講座 一般
7巻10号(1979年10月発行)
技術講座 細菌
7巻9号(1979年9月発行)
技術講座 生理
7巻8号(1979年8月発行)
技術講座 病理
7巻7号(1979年7月発行)
技術講座 生理
7巻6号(1979年6月発行)
技術講座 一般
7巻5号(1979年5月発行)
技術講座 血液
7巻4号(1979年4月発行)
技術講座 生理
7巻3号(1979年3月発行)
技術講座 病理
7巻2号(1979年2月発行)
技術講座 細菌
7巻1号(1979年1月発行)
技術講座 生化学
6巻12号(1978年12月発行)
技術講座 細菌
6巻11号(1978年11月発行)
技術講座 病理
6巻10号(1978年10月発行)
技術講座 血清
6巻9号(1978年9月発行)
技術講座 細菌
6巻8号(1978年8月発行)
技術講座 生化学
6巻7号(1978年7月発行)
技術講座 一般
6巻6号(1978年6月発行)
技術講座 病理
6巻5号(1978年5月発行)
技術講座 生理
6巻4号(1978年4月発行)
技術講座 一般
6巻3号(1978年3月発行)
技術講座 病理
6巻2号(1978年2月発行)
技術講座 一般
6巻1号(1978年1月発行)
技術講座 病理
5巻12号(1977年12月発行)
技術講座 生理
5巻11号(1977年11月発行)
技術講座 一般
5巻10号(1977年10月発行)
技術講座 細菌付録
5巻9号(1977年9月発行)
技術講座 一般
5巻8号(1977年8月発行)
技術講座 生理
5巻7号(1977年7月発行)
技術講座 一般
5巻6号(1977年6月発行)
技術講座 一般
5巻5号(1977年5月発行)
技術講座 一般
5巻4号(1977年4月発行)
技術講座 一般
5巻3号(1977年3月発行)
技術講座 一般
5巻2号(1977年2月発行)
技術講座 一般
5巻1号(1977年1月発行)
技術講座 一般
4巻12号(1976年12月発行)
技術講座 一般
4巻11号(1976年11月発行)
技術講座 一般
4巻10号(1976年10月発行)
技術講座 一般
4巻9号(1976年9月発行)
技術講座 一般
4巻8号(1976年8月発行)
技術講座 一般
4巻7号(1976年7月発行)
技術講座 一般
4巻6号(1976年6月発行)
技術講座 一般
4巻5号(1976年5月発行)
技術講座 一般
4巻4号(1976年4月発行)
技術講座 一般
4巻3号(1976年3月発行)
技術講座 一般
4巻2号(1976年2月発行)
技術講座 一般
4巻1号(1976年1月発行)
技術講座 一般
3巻12号(1975年12月発行)
技術講座 一般
3巻11号(1975年11月発行)
技術講座 一般
3巻10号(1975年10月発行)
技術講座 一般
3巻9号(1975年9月発行)
技術講座 一般
3巻7号(1975年8月発行)
特集 必修 日常検査の実技
3巻6号(1975年6月発行)
技術講座 生理
3巻5号(1975年5月発行)
技術講座 一般
3巻4号(1975年4月発行)
技術講座 一般
3巻3号(1975年3月発行)
技術講座 一般
3巻2号(1975年2月発行)
技術講座 一般
3巻1号(1975年1月発行)
技術講座 一般
