α1-AT=α1-antitrypsin:α1-アンチトリプシン
α2-PI=α2-plasmin inhibitor:α2-プラスミンインヒビター
雑誌目次
検査と技術28巻7号
2000年06月発行
雑誌目次
増刊号 血液検査実践マニュアル
本増刊号で用いられている略語一覧
ページ範囲:P.626 - P.633
Part 1 総論
2.血液検査の基準値
著者: 巽典之 , 日野雅之 , 津田泉 , 近藤弘
ページ範囲:P.663 - P.668
基準値とは何か
元来“正常値”とは健康な個人または母集団から求められた健康評価の基準となるべき値あるいはその範囲を指すものである.しかし“正常値”とは何か? そして,そのもとになる“正常”とは何か? との疑問が生ずる.WHOの健康の定義は「完全に身体的・精神的・社会的に良好な状態であって,ただ単に病気がないとか虚弱な状態でないというものではない」であるが,満足すべきものでなく,残念ながら統一された定義が存在しないのが現状である.健康の基準は対象として扱った健常人の集団の人種・数・年齢・性・体格・生活環境と生活習慣(食習慣を含む)などによって左右されることから,国により条件が異なってくる.さらに体格・生活環境や生活習慣は,それぞれの国において年々わずかずつ変化するし,測定法と測定精度の変化も考慮しなければならない.これらのことから,正常とは絶対的な基準でなく相対的なものであると考え,健常な状態を維持していると判断される対象群での集団正常値を基準値〔reference value;基準範囲(reference interval)〕と呼ぶ1,2).しかし,その値は絶対的かつ恒久的なものでなく,一定の期間ごとに訂正する必要がある.国際血液学標準化標議会(International Council for Standardization in Haematology;ICSH)の定義1,2)を以下に示す.
3.血液の採取方法と患者への対応
著者: 柴田綾子
ページ範囲:P.669 - P.671
はじめに
臨床検査技師は医師の具体的な指示を受け,検査を目的とした採血を行うことができる.採血部位は耳朶,指頭および足蹠の毛細血管と肘静脈や手背,足背の表在静脈に限定されている.採血の手技については,多くの教科書で説明されている.今回は現在一般的に行われている真空採血管を用いた静脈血採血について,現場での注意点をまじえて解説する.
4.血液検査におけるバイオハザード対策
著者: 内田博
ページ範囲:P.672 - P.674
はじめに
血液検査室は患者の血液を分析処理する機会が多いので,「すべての患者の血液・体液は感染性がある」として対応することが求められる.
1.血液学の基礎知識
1)血球の分化・成熟過程
著者: 長井一浩 , 栗山一孝
ページ範囲:P.636 - P.639
はじめに
生理的な状態において,体内循環血中の血液細胞はほぼ一定の量に保たれている.各系統の血球はその寿命を全うするか,なんらかの要因で消費されることによって,日々おびただしい数が壊されている.その一方で,骨髄において新たな血液細胞の増殖・分化・成熟が巧妙に調節・維持されていることによって,この恒常性が生涯にわたり保たれているのである.
本稿では,骨髄における造血機構を,造血幹細胞(hematopoietic stem cell;HSC)を頂点とする造血システムととらえる視点から概説する.
2)造血機能とその調節機構 a)赤血球系
著者: 坂田亨 , 別所正美
ページ範囲:P.640 - P.642
はじめに
赤血球は末梢血中に最も多く存在する血球で,その中に含まれているヘモグロビンによって,酸素と二酸化炭素の運搬を行っている.赤血球の寿命は約120日と有限なものであるが,血液中の赤血球数は生涯にわたってほぼ一定に維持されている.これは寿命によって失われた分に相当する赤血球が絶えず産生されているからであり,健常人の場合,毎時1010個という膨大な数がターンオーバーしているといわれる.また,生体内ではこのような定常状態における造血だけではなく,出血などのアクシデントに対する反応としての造血も必要に応じて行われる.このような赤血球産生システムが長期間にわたって秩序正しく機能し続けるには,赤血球の産生をコントロールする巧妙なメカニズムが存在しているものと考えられる.
本稿では造血幹細胞から赤血球への増殖・分化機構と,これに関連する造血因子について述べる.
2)造血機能とその調節機構 b)白血球系
著者: 奈良信雄
ページ範囲:P.643 - P.645
はじめに
白血球には,好中球,好酸球,好塩基球,リンパ球,単球がある.これらは,形態学的観察・染色性・表面抗原・機能などから見ると,それぞれが異なっている.しかし,それらは共通した祖先から派生し,さらに形態的,機能的により異なった赤血球,血小板も同じ祖先から作られてくる.すなわち,骨髄の中で,多能性幹細胞である造血幹細胞が分化し,成熟して各血球が産生され,末梢血液に流れ出てくる.
本稿では,白血球系細胞の作られるプロセスについて,血球の分化と,その調節について概説する.
2)造血機能とその調節機構 c)血小板系
著者: 米野琢哉 , 長澤俊郎
ページ範囲:P.646 - P.647
はじめに
血小板の存在が初めて記載されたのは19世紀半ばであり,当初は白血球あるいは赤血球の前駆体と考えられていた.20世紀初頭になりライト染色で有名なWright1)により,巨核球-血小板系の存在が示された.その後1980年代に入り,エリスロポエチン(EPO)などに代表される造血因子が次々にクローニングされ,これら造血因子が生体内で極めて重要な働きをすることが明らかになってきた.ところが,巨核球-血小板造血の特異的因子と想定されたトロンボポエチン(TPO)の同定は長年成功しなかった.このため,巨核球-血小板造血機構の解析は血球3系統の中で最も研究が遅れてきた.
3)凝固・線溶因子とその調節機構 a)止血機序と線溶機序
著者: 小山高敏 , 広沢信作
ページ範囲:P.648 - P.650
はじめに
健康なとき,血管内は,血液が固まらないようにする抗凝固機序が優位に働き,血液は滑らかに流れる.しかし,いったん出血すると,出血が起こっている場所で,効果的に血液が固まって出血を止めるように血栓ができる(止血栓の形成).止血の最初の反応は,血小板が傷害部位へつき(粘着),さらにお互いにつく(凝集)ことで,これを一次止血と呼ぶ.次いで血液の凝固が起こり,出血が完全に止まるようになり,これを二次止血と呼ぶ.血栓のでき過ぎを防ぎ,血栓を溶解しようとする反応をフィブリン(線維素)溶解(線溶)と呼び,生理的にも存在するが,通常は線溶を抑える因子の働きのほうが強く隠されている.
3)凝固・線溶因子とその調節機構 b)凝固・線溶因子の種類と役割
著者: 加藤久雄
ページ範囲:P.651 - P.655
はじめに
血液凝固は血小板の凝集とフィブリンの形成によって引き起こされ,血管壁の傷害による出血を阻止するために必須の反応であると同時に,血管内で凝固すると多くの循環器疾患の成因となる血栓症を引き起こすことになる.そのために,血栓の形成とその溶解に関与する反応は,わずかな刺激により増幅される仕組みと同時に,それらの反応が過剰に進行しないように制御する仕組みが極めて巧妙に作られており,それだけに,多くの因子が関与する複雑な反応系を構成している.
本稿では,フィブリンの形成とその溶解に関与する因子の種類とその働きについて記す.
3)凝固・線溶因子とその調節機構 c)凝固阻止因子
著者: 鈴木宏治
ページ範囲:P.656 - P.659
はじめに
正常時,循環血液の流動性は維持され,また血液凝固反応は傷害部位に限局化される.この理由は,傷害部位以外での凝固反応は血管内壁上で機能する凝固阻止因子によって制御されることによる.凝固阻止因子はその作用機構からプロテアーゼインヒビターとプロテアーゼに大別される.前者にはアンチトロンビンIII(antithrombin;ATIII)をはじめとするセリンプロテアーゼインヒビター(serine protease inhibitor;SERPIN)によるトロンビン,Xa因子,IXa因子などの阻害反応と,クニッツ(Kunitz)型インヒビターの組織因子(tissue factor;TF)経路インヒビター(tissue factor pathway inhibitor;TFPI)による外因系凝固の阻害反応がある.他方,後者にはプロテアーゼの活性化プロテインC(activated protein C;APC)とその関連因子による凝固補酵素蛋白(Va因子とVIIIa因子)の分解に基づくプロテインC凝固制御系がある.
3)凝固・線溶因子とその調節機構 d)血小板の機能
著者: 安藤泰彦
ページ範囲:P.660 - P.660
はじめに
血管が損傷されると,血小板は損傷箇所の内皮下組織に接着,伸展し,粘着する.粘着によって,血小板は活性化されて各種物質を放出する.放出された血小板凝集惹起物質の作用により周辺の血小板が活性化されて,血小板が互いに凝集し,血小板血栓を作り,失血を防ぐ.血小板の3大機能,粘着,放出,凝集の機能発揮には,複数の活性化因子,接着因子,それらの受容体,血小板内部の複雑なシグナル伝達機構が関与している.
3)凝固・線溶因子とその調節機構 e)血管内皮の機能
著者: 高木明 , 小嶋哲人
ページ範囲:P.661 - P.662
はじめに
血管内皮細胞は,血管内腔を覆い血漿成分の血管周囲組織への漏出を防ぐバリアと考えられていた1層の細胞である.しかし,最近では血圧の調節,血液凝固・線溶の調節,炎症反応の調節などに関与する多機能細胞であることが明らかとなってきた.本稿では,血管内皮細胞の産生するさまざまな生理活性物質(表)を通して,血管内皮細胞の役割のうち血液凝固・線溶調節機能を中心に概説する.
Part 2 血球計数検査 1.血球計数検査
1)検査の目的と意義
著者: 桑島実
ページ範囲:P.676 - P.678
はじめに
血球計数は血液疾患や血液に異常をきたす病態を診断し,治療効果を見るとき,最も基本になる必須検査である.自動血球計数器あるいは自動血液分析装置の普及と進歩に伴い,いつでも,どこでも,容易に実施できる血球計数は尿一般検査と同様,すでに診察の一部とみなされてきた.また,健康診断や日常初期診療では最もよく利用されているスクリーニング検査項目の1つでもある.しかし,検査の有効活用という観点から,ただ漫然と機械的に検査するのではなく,血球計数の目的と意義を十分知り検査する必要がある(表1).すなわち,病歴,症状,身体所見などの臨床所見から鑑別診断をいくつか想定し,血球計数値に異常があると予想される場合,あるいは血液の異常を否定する必要がある場合に検査する.また,受診者や患者が抱えている血液に関係した問題点の解決に必要な最初の検査として活用する.たとえ簡便な血球計数であっても,患者の利益につながらないと予想される場合は検査すべきではない.
2)検体の取り扱い,保存法と注意点
著者: 大竹順子
ページ範囲:P.679 - P.681
はじめに
臨床検査すべてにいえることであるが,検体採取,取り扱い,保存などが正しく行われていなければ,質のよい,正しい成績は得られない.
現場で検査に携わる者は,検査前に検体採取や検体保存が正しく行われたかどうかのチェックを日常の業務として行うべきである.
3)検査に用いる抗凝固剤の種類と使い分け
著者: 大竹順子
ページ範囲:P.682 - P.682
はじめに
血球計数は視算法,自動血球計数器で算定する方法がある.自動血球計数器の場合,その計測原理は機種により異なるが,いずれにせよ,血球の容積の違いで,赤血球,白血球,血小板を鑑別している機種が多い.したがって,血球の容積が保たれていることが,正しい成績を出す条件の1つである.このためには,適切な抗凝固剤を選択することである.
4)用手法の実際 a)赤血球数
著者: 氏家幸
ページ範囲:P.683 - P.684
はじめに
血球数算定(視算法)は,従来メランジュールを用いる方法で施行された検査であるが,感染の危険の可能性があり,メランジュールは使用せず,ピペットを用いる方法に改良された.
自動血球計数装置の普及に伴い,操作にある程度の習熟を要する本法は,日常検査ではほとんど使用されないが,基本的検査である.
4)用手法の実際 b)白血球数
著者: 氏家幸
ページ範囲:P.685 - P.685
はじめに
血球数算定(視算法)は,従来メランジュールを用いる方法で施行された検査であるが,感染の危険の可能性があり,メランジュールは使用せずピペットを用いる方法に改良された.自動血球計数装置を用いて血球計数を行う場合,EDTAによる血小板凝集(偽性血小板減少),有核赤血球(赤芽球)の存在,クリオグロブリンの混在などにより白血球数を正確に測定できない検体に遭遇する.このようなときには視算法で白血球数をカウントしなければならない.
4)用手法の実際 c)血小板数(直接法,ブレッカー・クロンカイト法)
著者: 氏家幸
ページ範囲:P.686 - P.686
はじめに
血球数算定(視算法)は,従来メランジュールを用いる方法で施行された検査であるが,感染の危険の可能性があり,メランジュールは使用せずピペットを用いる方法に改良された.現在,自動血球計数装置による測定が一般的である.しかし,赤血球の存在下で行うため,血小板と同程度の大きさの小赤血球や,通常サイズより大きい大〜巨大血小板が出現する検体では正しい計数ができない.このような場合は,直接算定板による計数が必要となる.
本法では赤血球を溶血し,血小板は光屈折性を持つ円形〜楕円形の小体として算定する.
4)用手法の実際 e)網赤血球数(ブレッカー法)
著者: 氏家幸
ページ範囲:P.688 - P.689
はじめに
網赤血球数算定は,骨髄の赤血球系の造血機能を把握するうえで重要な検査の1つである.自動網赤血球測定装置が広く普及してきたが,簡便かつ正確で,染色性のよい本法もいまだ多く用いられている.
5)自動測定法の実際 a)赤血球系
著者: 久保田浩 , 巽典之
ページ範囲:P.690 - P.693
測定原理および方法
1.赤血球数と容積の測定
血球計数で主に使われている2つの方式についての測定原理を述べる.
5)自動測定法の実際 b)白血球系
著者: 丹羽欣正
ページ範囲:P.694 - P.698
はじめに
白血球系の自動計測は白血球数(以下WBC)測定において古くより研究開発が行われてきた.WBC測定での機器開発の歴史は,赤血球の溶血操作に始まるのであるが,現在においてもなお続いている永遠の課題であろう.さらに近年,自動血球計数器の多項目化,多機能化がなされ,多項目自動血球分析装置と呼称されるに至っており,白血球系分析項目も多岐にわたって解析可能となってきている.
このように,当初WBCとしてしか計測ができなかった測定装置も,溶血技術の進歩により,白血球を3種類(リンパ球,好中球,その他)に分類することが可能となった.さらに現在では,フローサイトメトリー技術の導入に伴い,5分類(リンパ球,好中球,単球,好酸球,好塩基球)可能な機種が多数登場してきた.しかし,ここでいう白血球5分類とは正常かつ成熟白血球のみを指し,骨髄芽球など幼若白血球および反応性異型リンパ球の分析までには至っておらず,これらの異常細胞をいかに正確に検出できるかの精度向上に全力が注がれている.その一方で,有核赤血球の定量化が一部の機種で可能となったり,細胞性免疫学的手法の応用による細胞分析への試みもなされるなど,日進月歩の開発状態は今後も持続するであろう.
5)自動測定法の実際 c)血小板数
著者: 松野一彦
ページ範囲:P.699 - P.702
はじめに
血小板数の測定は血小板減少症や血小板増多症の診断に必須であり,現在血液疾患をはじめ自己免疫疾患,肝疾患など多くの臨床の場で重要な検査である.
従来,血小板数の測定はBrecher-Cronkite法やRees-Ecker法などの視算法(マニュアル法)によっていたが,測定に時間を要するため,検体数が増加した現在ではほとんどの施設が自動測定法によっている.しかし,小赤血球が多数存在したり,血小板凝集が存在している場合,自動測定法では不正確な結果を出すことがあり,このような場合には現在でも視算法によって真の値を求める必要がある.
5)自動測定法の実際 d)網赤血球数
著者: 武内恵
ページ範囲:P.703 - P.708
はじめに
網赤血球の自動測定はレーザーフローサイトメトリーの出現により,1988年,世界に先がけてわが国で初めて自動網赤血球測定装置R-1000(シスメックス社)1)が開発された.全血で迅速簡便に多数検体処理可能となり,従来の目視法では困難であった未熟網赤血球の比率も簡単に測定できるようになった.それにより未熟網赤血球測定は骨髄移植や末梢血幹細胞移植後,あるいは白血病や癌の化学療法後の赤血球造血の新たな指標として臨床的有用性が報告されている.
現在,網赤血球の自動測定には半自動測定,つまり塗抹染色標本を用いるパターン認識原理による自動測定法や,あらかじめ血液を希釈染色し,汎用型のフローサイトメーター(網赤血球測定専用機ではない)で測定する方法などもある.しかし,ここでは検体の前処理が不要な全自動網赤血球測定について解説する.
6)データの読みかたとコメントの付けかた
著者: 宮地勇人
ページ範囲:P.709 - P.715
赤血球検査
1.疾患・病態
貧血の原因は,赤血球動態に基づいて,赤血球の喪失(出血),破壊の充進(溶血),成熟赤血球の産生不良(骨髄疾患,慢性疾患)に大別される(表1)1).貧血の存在は,白血病,骨髄異形成症候群,多発性骨髄腫など骨髄疾患をはじめ,癌,慢性感染症,慢性炎症性疾患,慢性腎疾患や内分泌機能低下などの診断のきっかけとなる.
赤血球増加の原因には,赤血球数が絶対的に増加する骨髄増殖性疾患(真性多血症など),続発性多血症(心肺機能異常など)および相対的多血症(ストレス多血症など)がある(表2).
7)再検基準
著者: 宮地勇人
ページ範囲:P.716 - P.719
赤血球検査
1.緊急異常値,パニック値
輸血など臨床的処置の判断を必要とする緊急異常値および測定誤差を示唆する異常値においては,測定過程で技術的誤りがなかったかどうかを確認する(表1)1,2).緊急異常値はヘモグロビン5g/dl(幼児7g/dl)以下,18g/dl(幼児21g/dl)以上である.通常,ヘモグロビン7%以下で貧血症状が出現する.自動血球計数器による末梢血血球算定において,血液検体の異常に起因するさまざまな人為的な検査値の変化が生じる.MCHC異常値は,ヘマトクリットやヘモグロビン両者における測定誤差を反映する可能性がある.赤血球内のヘモグロビン飽和溶解度は37g/dl近くにあり,遺伝性球状赤血球症と一部のヘモグロビン異常を除きMCHCが37%以上になることはない.これ以上の場合,測定誤差要因を検討し再検する.本来,ヘマトクリットとヘモグロビンとの比は3:1になる.この比から解離した検体は再検が必要である.
8)精度管理
著者: 巽典之 , 田窪孝行 , 津田泉 , 松本英彬
ページ範囲:P.720 - P.721
はじめに
血液検査の精度管理は内部精度管理と外部精度評価に大別できる.精度管理の基本的な解説と付図は誌面の関係上割愛させていただくことと,わが国では現在ほとんどが自動機器で検査が実施されていて1),血液検査ではシスメックス社の製品が比較的よく使用されている現状に鑑み,その製品名が記載されていることに関してお許しいただきたい.
2.赤血球沈降速度
1)目的と臨床的意義,検査の実際
著者: 新井盛夫
ページ範囲:P.722 - P.723
検査の目的と臨床的意義
赤血球沈降速度(erythrocyte sedimentation rate;ESR)は通常,赤沈と呼ばれ,血漿中の赤血球が重力で沈降する速度を測る臨床検査である.赤沈は臨床検査の中でも最も古いものの1つであるが,その測定手技が簡便で測定器具も安価であることから,現在でも検査室や外来などで汎用されている.
赤沈は,血液中での赤血球と血漿成分の物理的な相互反応が,多くの要素の下で働く非特異的現象である.すなわち,測定温度,抗凝固剤の濃度や混合比,沈降管の口径,傾き,検体のヘマトクリット値,血漿蛋白濃度などの条件により,赤血球の沈降速度は影響を受ける.これらの要素を念頭に置いて,赤沈値から病態把握の補助診断としての情報を得ることができる.
2)データの読みかたとコメントの付けかた
著者: 新井盛夫
ページ範囲:P.724 - P.724
基準値
Westergren原法では1時間値と2時間値,さらに24時間値を測定するようになっているが,臨床的に最も重要なものは1時間値である.国際血液学標準化委員会(ICSH)では1時間値の測定を基本とし,基準値は各国で定めることを推奨している.わが国での基準値は男性で2〜10mm,女性で3〜15mmである.それ以上を促進,0〜2mmの場合を遅延と判断する.
3)自動赤沈測定装置の特徴と精度管理
著者: 新井盛夫
ページ範囲:P.725 - P.725
測定機器
Westergren原法の赤沈検査は特殊な器具や電力が必要ないことから,外来や検査室で簡便に行うことができる.しかし開放管を用いるため,操作時の血液汚染の問題がある.また多検体の一括測定には不向きである.
近年,ディスポーザブルな閉鎖システムを用いた自動赤沈測定機器がいくつか開発されてきた.わが国で発売されているセディシステム(ベクトン・ディッキンソン社)1)とベスマティック60(エム・シー・メディカル社)2)の特徴を半自動法のESR-6000BP(テクノメディカ)やWestergren法と比較して表に示した.全自動の前2者は,真空採血管をそのまま赤沈管として利用したクローズドシステムを採用しており,利便性に優れ,操作時の血液汚染事故の危険性が少ない.また,多検体のランダム処理に優れ,測定時間もWestergren法に比較して短縮されている.Westergren法との相関や再現性は良好であるという.しかし,赤沈測定を用手法から自動赤沈測定に移行するときは,各施設での相関データと基準値を検討する必要があろう.
Part 3 血球形態検査 1.末梢血検査
1)検査の目的と意義
著者: 亀井喜恵子
ページ範囲:P.728 - P.729
はじめに
血液像検査は血液検査の基本的な検査法の1つである.血液細胞(赤血球・白血球・血小板)は主に骨髄で造られ,分化・成熟し,成熟球が各々複雑な機能を果たしつつ体内を循環する.わずか数μlの血液をスライドグラスに塗抹・染色し,顕微鏡下で個々の血球形態を観察することによって,造血器および生体内からの種々の情報を得ることができる.血球の数に異常がある場合はもちろんのこと,数に異常がない場合でも,血液疾患を含むある種の疾患の診断や予後の判定に結びつく重要な手がかりを早期に発見できることが多い.
2)塗抹標本の作製
著者: 亀井喜恵子
ページ範囲:P.730 - P.730
はじめに
血液塗抹標本の作製要点は個々の血液細胞が観察しやすいことや均一な分布であることなど,試料中の血球形態性状が的確に反映されることである.現在広く使用されている塗抹標本の種類は約3種類ある.1つは最も多く使用されているウエッジ標本であり,もう1つは2枚のスライドグラスの間に血液を挟み左右に引き離す圧坐伸展標本(骨髄像検査によく使用される),さらに自動分析器に多く使用されている遠心法によるスピナー標本である.各々一長一短があるが,ここではウエッジ標本の作製を中心に述べていくことにする.
3)染色法 a)普通染色
著者: 亀井喜恵子
ページ範囲:P.731 - P.735
はじめに
血液細胞は塗抹標本を作製しただけでは観察不可能で,血液細胞各々の性質を利用した染色を行い初めて観察・鑑別が可能となる.現在,血液細胞全般を染色する染色法を普通染色または一般染色と呼んでいる.広く使われている普通染色はロマノフスキー(Romanowsky)染色と総称されギムザ(Giemsa)染色,ライト(Wright)染色,ライト・ギムザ(Wright-Giemsa)染色,メイ・ギムザ(May-Giemsa)染色がある.その他,緊急の場合に便利なフィールド染色などがある.各々の染色には特徴があるので,最も細胞観察がしやすい染色法を選択することも大切である.いかに細胞鑑別に自信のある技師でも染色不良の標本では鑑別に苦慮するし,時間もかかりすぎ,仕事がスムーズに進まなくなる.
3)染色法 b)特殊染色
著者: 亀井喜恵子
ページ範囲:P.736 - P.746
はじめに
細胞の観察・鑑別の基本はあくまでも普通染色所見にあることに変わりはないが,形態的に類似した未熟細胞や異常細胞の鑑別に,またそれらの同定を客観的に裏づける1つの手段として,さらに細胞機能の有無などの判定に特殊染色を実施することでよりいっそう鑑別・同定が容易になる.
特殊染色の意義は目的とする細胞の形態を保ちつつ,特異性のある細胞内の特定物質を細胞化学的に証明することである1〜7).主な細胞内の特定物質とその証明法を下記に示す.
4)血球の見かた
著者: 丹羽欣正
ページ範囲:P.747 - P.750
はじめに
血球を見るということは,血液形態学的に血球を観察することである.末梢血液で血球観察の対象となるものは白血球,赤血球,血小板であり,当然のことながら血液そのままでは目的を達成することはできない.これら血球をいかに自然に近い状態に保ち,かつその特徴を的確に把握可能とすることができるかが重要なポイントであり,血球を観察するうえでの前提条件となる.
前提条件が完全に整った状態での標本観察法について記載しなければならないのであるが,前提条件,血球観察方法のいずれにも画一的なものがなく,残念ながら絶対的といえる作業手順の紹介はできない.近年,国内外における血液形態検査の標準化への取り組みが多数見られるようになったが,すべてにおいて絶対的な状態の推奨法提唱には至っていない.前述の理由から,ここでは米国臨床検査標準協議会(NCCLS:National Committee for Clinical Laboratory Standards)におけるDocument H20-Aおよび日本臨床衛生検査技師会(以下日臨技)における血液形態検査に関する勧告法を主体にして,現時点において最も一般的といえる血球観察法について述べてみたい.
5)判定基準
著者: 丹羽欣正
ページ範囲:P.751 - P.758
はじめに
末梢血液塗抹標本を観察することは,血液の中を直接のぞき見ることであり,血液細胞の状態が正常であるか否かを,自分の目で直接判定する手段である.すなわち,検査を行う者の目および頭の中の判定基準が,そのまま検査成績に反映する検査方法であり,適切な判定基準のもとにトレーニングを積んだうえで挑まなければならない検査手段であるといえる.
最近では自動血球分析装置の機能向上により,各種血球の数値的諸情報および正常白血球の分類に関しては,機械まかせでもほぼ信頼できる成績が得られるようになった.しかしながら,ここで重要な問題となってくるのは,何が異常で,何が正常かの適切な判別能力が,分析装置を扱う者には必要であるということである.つまり,いかに自動血球分析装置の高機能化がなされても,各血球を的確な判定基準をもって行う顕微鏡観察技術の習熟が,血液検査に携わる者には必須事項であることには変わりはない.
2.骨髄穿刺検査
1)検査の目的と意義
著者: 佐藤尚武
ページ範囲:P.759 - P.760
はじめに
骨髄(bone marrow)は出生後はほとんど唯一の造血組織であり,造血の状態やそこに生じた変化を調べる場合は骨髄検査が必要となる.したがって,骨髄穿刺検査の主な対象疾患は,造血器の異常をきたす血液疾患である.なお,骨髄穿刺液を用いて行う検査には,形態検査のほかに血球抗原検索(immunophenotyping)や,染色体・遺伝子検査,コロニー形成能を調べる検査などがある.このうち,本稿では血液細胞の形態検査について述べる.他の検査に関してはPart 6〜8の関連項目を参照されたい.
2)検体の採取方法と注意点
著者: 佐藤尚武
ページ範囲:P.761 - P.761
はじめに
骨髄穿刺液からは,形態観察用に塗抹標本(wedge smear),圧挫伸展標本(squash preparation,crushed particle smear)および凝固骨髄組織切片標本(clot section)が作製される.さらに骨髄穿刺針より太い針で骨髄組織を直接採取し,作製する骨髄生検標本がある.
3)検体の処理方法,検査の実際と骨髄細胞の見かた
著者: 佐藤尚武
ページ範囲:P.762 - P.768
検体の処理方法
塗抹標本の作製に関しては,基本的に末梢血液の場合と同じである.ただし,一般に骨髄液の採取には抗凝固剤を用いないので,穿刺した骨髄液を素早く受け取り,手際よく迅速に標本を作製する必要がある.また,実施する染色の種類数などを考慮し,標本の作製必要枚数も事前に確かめておく.同時に時計皿などに骨髄液を別に採り,骨髄有核細胞数や骨髄巨核球数の算定,ミエロクリットの測定を行う.したがって理想をいえば,骨髄穿刺には複数の技師が参加することが望ましい.骨髄有核細胞数や骨髄巨核球数は,チュルク(Türk)液で希釈し,計算盤を使って算定する.なお,本稿のテーマは形態検査なので,これら算定検査に関する処理法は省略する.用手法による血球計数に準じた手技なので,Part 2の該当項目を参照されたい.
圧挫伸展標本を作製する場合は,まずピンセットなどでスライドグラスに骨髄液中の小塊を採る.次に,反対の手で別のスライドグラスを持って,骨髄液小塊の載ったスライドグラスにこれを押しつける.2枚のスライドグラス間で小塊が押しつぶされ,広がったことを確認して2枚のスライドグラスを左右に,水平を保って速やかに引き離す.
3.FAB分類
1)検査の目的と意義
著者: 阿南建一
ページ範囲:P.771 - P.772
検査の目的と意義
FAB分類とは,1976年,French-American-British(FAB)グループによってこれまで煩雑化した急性白血病分類を整理したもので,急性白血病の治療成績,予後を同じ土俵で比較するため病型に客観性を持たせようとして誕生したものである1).本グループは,JM Bennett,D Catovsky,M-T Daniel,G Flandrin,DAG Galton,HR Gralnick,C. Sultanの7人の血液学者より構成され,白血病細胞の分化と成熟度を光顕的(形態学および細胞化学的手法)所見を主体に分類を試みたものである.
本分類の最大の特徴は,①どこの施設でも実施されること,②ある程度の熟練者であれば診断が可能であること,③急性白血病との間に一線を画し,骨髄異形成症候群(myelodysplastic syndrome;MDS)を提唱したことにある.現在,5病型に分類されているMDSは,1976年の提唱時にはCMMLとRAEBの2病型のみで,dysmyelopoietic syndromes(DMPS)として設定されていた.
2)M0〜M7
著者: 阿南建一
ページ範囲:P.773 - P.777
AMLの病型と診断へのプロセス1〜4)
AMLはMDSとの鑑別が必要となるので,芽球の割合がポイントとなり,ANC(all nucleated bone marrow cells)とNEC(nonerythroid cells:bone marrow cells excluding erythroblasts)の規定が設けられた2).すなわち,ANCとは,全骨髄有核細胞から非造血細胞(リンパ球,形質細胞,肥満細胞,マクロファージ)を除外したものであり,さらに赤芽球を除外したものをNECとして扱い,最終的に芽球の算定よりAMLの診断を行う(図1).
また,“芽球”についてFABグループは,type I(クロマチン繊細,核小体明瞭,アズール顆粒やアウエル小体を認めず)とtype II(type Iに類似するが,少数のアズール顆粒,アウエル小体を認める)に分けて,それらは前骨髄球との鑑別が必要であると述べている.Bennett,Goasguenら(1991年)は,さらに“type IIIの芽球”を取り上げ,芽球に幅を持たせようとしている.FABグループでは公認されていないが,最近では文献などで記載を見るので,ここではそれを加味して述べることにする(表).
3)L1〜L3
著者: 阿南建一
ページ範囲:P.778 - P.779
ALLの病型と診断へのプロセス1,3,4)
ALLの診断は,芽球のMPO染色陰性が必要条件となるが,AML-M0,M5a,M7を否定することが要求される.形態学的にFAB分類では,L1,L2,L3の3つに分けられるが,免疫学的,細胞遺伝学的なMIC分類では,early B-precursor-ALL,common ALL,pre B-ALL,B-cell ALLの4つに分けられる.L1とL2については,客観性をもたせるためにスコアリング・システムが導入されている(表).リンパ芽球の起源を知るうえからもMIC分類2)は有効となるので参考までに紹介する.
4)MDS
著者: 須永真司
ページ範囲:P.780 - P.781
疾患概念
MDSは造血幹細胞の異常に起因する疾患で,無効造血による血球減少と血球の異形成を特徴とする,種々の疾患の集まりと考えられている.
以前から,末梢血では汎血球減少があるにもかかわらず,骨髄の細胞密度は正〜過形成を示し,数か月から数年の経過で高率に急性白血病に移行する疾患があることが知られていた.このような疾患群はhemopoietic dysplasia,dysmyelopoietic syndromeなどと呼ばれ,血球細胞に種々の形態学的変化が認められることが特徴の1つであった.1982年にFABグループはこれらの疾患をMDSとしてまとめ,5病型に分類して客観的な診断基準を提唱した1)(表1).MDSの名が広く流布したのは,このFAB分類があったからにほかならない.
5)慢性白血病とFAB分類
著者: 須永真司
ページ範囲:P.782 - P.784
慢性リンパ性白血病類縁疾患のFAB分類
末梢血中に成熟リンパ球が増加する腫瘍性疾患としては慢性リンパ性白血病(chronic lymphocytic leukemia;CLL)が代表的である.しかし,ひとくちに「リンパ球が増加し,比較的慢性に経過する白血病」とはいっても,腫瘍化したリンパ球の形態は単一ではなく,臨床像も異なっていた.1989年,FABグループは腫瘍細胞の形態と表面形質をもとにCLLの類縁疾患を表1のように整理・分類した1).これらをまとめて慢性(型)リンパ系白血病(chronic lymphoid leukemia)と称する場合もあるが,狭義の“CLL”と混同しやすく,文献を読む際には注意が必要である.
本稿ではFAB分類に沿って腫瘍細胞の形態や表面形質などを中心に概説する.
6)FAB分類のトピックス
著者: 須永真司
ページ範囲:P.785 - P.786
FAB分類の問題点
FAB分類は形態学と細胞化学染色を分類の中心にすえており,どの施設でも特殊な技術を使わずに分類が可能であったため,白血病の国際分類として最も広く使われてきた.世界的に共通の土台での議論,臨床研究を可能にしたという点でのFAB分類の功績は,非常に大きなものがある.
しかし一方で,なるべく単純な検査で分類を試みた結果,いくつかの問題点が指摘されている.それらの点を含め,FAB分類の置かれている現状について述べていきたい.
4.LE細胞検査
1)検査の目的と意義
著者: 西村敏治
ページ範囲:P.789 - P.790
はじめに
LE細胞(lupus erythematosus cell)は1948年,Hargravesら1)によって全身性エリテマトーデス(SLE)患者のヘパリン加骨髄塗抹標本の中に均一無構造な紫紅色の封入体を持つ細胞として発見された.この細胞の発見を機にその成立機序が明らかになり,種々の検出法も報告されるようになった.
LE細胞は生体内にはほとんど認められず,通常採血後,生体外で人工的に形成される細胞で,封入体(LE体)を貪食した細胞のことである.
2)検体の取り扱い,保存法,注意点と検査に用いる抗凝固剤の種類と使い分け
著者: 西村敏治
ページ範囲:P.791 - P.791
はじめに
検体(材料)としては静脈血が一般的であるが,骨髄,胸水,腹水,髄液などでも検索することができる.
LE細胞形成には白血球数(特に好中球数),補体が関係することから,これらの測定値を事前に確認しておくことも必要であろう.
3)検査の実際
著者: 西村敏治
ページ範囲:P.792 - P.793
はじめに
LE細胞検査には全血を用いる直接法と血清を用いる間接法がある.前者は抗凝固剤を用いない凝血法とヘパリン加血液を用いる方法がある.後者は操作がやや煩雑で陽性率も落ちるが,患者の血清しか得られないとき(保存も可能)や患者の好中球が著減している場合などに,患者血清と健常人血液(白血球)を混合してLE細胞を検出する方法としても用いられている.
以下,直接法の代表的方法について述べる.
4)細胞の観察と成績評価
著者: 西村敏治
ページ範囲:P.794 - P.794
はじめに
LE細胞検査ではSLE患者の75%ぐらいが陽性を呈する.SLEの活動期には陽性率は高い傾向にあり,治療により寛解に近づくと陰性化する場合もある.
5.白血球機能検査
1)検査の目的と意義,検体の取り扱い・保存法と注意点,抗凝固剤の種類と使い分け
著者: 東克巳
ページ範囲:P.795 - P.796
はじめに
ヒトの生体防御機構は病原微生物などから自己を守るために必須の機構の1つである.この機構には特異的免疫機構と非特異的免疫機構があるのは周知のとおりである.
病原微生物が生体に侵入すると,まず非特異的免疫機構が働く.ここで主役をなすのが顆粒球(ほとんどが好中球)である.好中球は微生物に近づき(遊走),取り込み(貪食),殺傷(殺菌)という一連の機能を発揮し,微生物の生体からの排除を完結するとともに自解し,炎症反応の引き金となる.しかし,ここで排除が完了しないと,リンパ球を介する特異的免疫機構が働くことになる.
2)検査の実際 a)顆粒球機能検査
著者: 東克巳
ページ範囲:P.797 - P.799
遊走能試験
遊走能試験は好中球が大量に必要なため採血量が多くなり,臨床検査としてはほとんど行われていない.貪食能試験などで代用されているのが現状であろう.遊走能試験には代表としてBoyden法とアガロース法があるが,Boyden法は特殊な器具を必要とするため,ここではアガロース法を紹介する.
2)検査の実際 b)リンパ球幼若化試験
著者: 近藤弘 , 小林恵美 , 津田泉 , 巽典之
ページ範囲:P.800 - P.802
検査の目的と意義
末梢血液中のリンパ球の大部分は細胞周期のうえでは休止期にあり,刺激を受けて幼若化し,分裂・増殖することによってエフェクター細胞となり,免疫機能を発揮する.リンパ球幼若化試験はリンパ球が刺激に対して反応し,機能細胞に移行する能力を検査するin vitro検査法である.
リンパ球幼若化試験の目的の1つは,免疫不全を伴う疾患の病態を評価したり,免疫機能に影響する薬剤の使用時などに,治療効果や副作用を判定するために,リンパ球の免疫担当細胞としての機能を総体的にとらえることにある.この際,通常は分裂刺激剤として特異性には欠けるが,再現性や簡便性の点から表1に示す各種マイトゲンを用いる.
3)成績の評価とコメントの付けかた
著者: 東克巳
ページ範囲:P.803 - P.804
顆粒球機能検査
1.遊走能試験
図1に示すように,走化性因子に向かった遊走距離をchemotaxis:A,対照側の遊走距離をspontaneous migration:Bとすると,A/Bをchemotactic index,A-Bをchemotactic differentialとして表す.
遊走能機能不全としてはなまけもの白血球症候群や高IgE血症(Job症候群)がある.前者は好中球の運動能や殺菌能は正常であるが,ランダム運動や走化能が欠如する.後者は高IgE血症と好中球走化能低下が見られる症例である.しかし,いずれの場合も病因論としては確立されたものではない.
Part 4 溶血検査
4.データの読みかたとコメントの付けかた
著者: 杉原尚
ページ範囲:P.822 - P.824
はじめに
溶血性貧血(hemolytic anemia)とは,なんらかの原因によって赤血球の崩壊が亢進した状態の総称であり,多くの疾患を包括する一種の症候群である.赤血球崩壊が亢進し,約120日ある赤血球寿命が短縮してくると,骨髄はその産生能力を高め,通常よりも多くの赤血球を産生する.赤血球の崩壊を骨髄造血が代償できる範囲内であると貧血は見られない(代償された溶血).しかし,赤血球崩壊が著しく亢進して,これに対する産生能が追いつかない場合(非代償性溶血)に初めて貧血を生ずることになる.したがって,実際には貧血を呈さない症例も多くあり,溶血性疾患と呼ぶのが妥当と考えられる.
3.検査の実際
1)赤血球抵抗試験
著者: 臼杵憲祐 , 長野美恵子 , 浦部晶夫
ページ範囲:P.811 - P.812
検査の目的
赤血球抵抗試験は赤血球の表面積/体積比を調べる検査である.表面積/体積比の低い遺伝性球状赤血球症の診断や,表面積/体積比の高いサラセミアのスクリーニングに用いられる.表面積/体積比が低いほど低浸透圧水溶液(低張液)中で溶血の程度が高くなる.これを赤血球浸透圧抵抗性の低下(浸透圧脆弱性の充進)という.
2)PNHに関する検査
著者: 臼杵憲祐 , 長野美恵子 , 浦部晶夫
ページ範囲:P.813 - P.815
はじめに
発作性夜間血色素尿症(paroxysmal nocturnal hemoglobinuria;PNH)は赤血球膜の補体感受性の亢進を特徴とする後天性溶血性貧血である.PNHではglycosyl-phosphatidyl-inositol(GPI)アンカー蛋白の生合成障害があり,GPIアンカー蛋白であるCD55やCD59が赤血球膜上で欠損している.CD55は補体C3/C5転換酵素の崩壊促進因子(decay-accelerating factor)であり,CD59は補体の膜侵襲複合体形成を制御する分子である.これらの補体制御蛋白質の赤血球膜上での欠損によって補体感受性が亢進していると考えられている.なお,最近,GPIアンカー蛋白の生合成障害の原因としてPIG-A遺伝子の異常が明らかになった.
PNHの診断にはSugar Water試験やHam試験が用いられるが,いずれもPNH赤血球の補体感受性の亢進を検出する検査である.Sugar Water試験は補体のclassical pathwayの活性化による溶血を,Ham試験は補体のalternative pathwayの活性化による溶血を利用したものである.Sugar Water試験は鋭敏であるためPNHのスクリーニングに用いられる.
3)赤血球酵素活性測定
著者: 井手口裕
ページ範囲:P.816 - P.817
赤血球酵素活性測定の意義
先天性溶血性貧血のうち遺伝性球状赤血球症などの赤血球膜異常や不安定ヘモグロビン(Hb)症が否定され,原因不明の遺伝性非球状溶血性貧血の場合には,赤血球酵素異常症が疑われるので種々の赤血球酵素活性の測定が必要となる.現在までに解糖系,五単糖リン酸回路,グルタチオン代謝・合成系,ヌクレオチド代謝に関連した十数種の酵素異常症が発見されており,なかでも特に頻度が高いのはPK(ピルビン酸キナーゼ)異常症とG-6-PD(グルコース-6-リン酸脱水素酵素)異常症である1).
4)異常ヘモグロビンの検出法
著者: 岡山直子 , 服部幸夫
ページ範囲:P.818 - P.819
はじめに
異常ヘモグロビン(Hb)は主としてグロビンのアミノ酸異常によるもので,多くは無症候性である.しかし,ときに溶血性貧血(不安定Hb症),まれにチアノーゼ(HbM症,低酸素親和性Hb),多血症(高酸素親和性Hb)などの症候性として見られる.鎌状赤血球症では多くの米国黒人が苦しんでいる.しばしば高速液体クロマトグラフィー(HPLC)でのHbA1cの測定干渉をきっかけとして発見される.サラセミアはHb分子(α2β2)の一方のグロビンの産生低下による小球性低色素性貧血で,その重症型では溶血を呈する.非鉄欠乏性の小球性貧血はほとんどがサラセミアである.日本人の700〜1,000人に1人の割合で見られる.
5)胎児ヘモグロビンの検出法
著者: 服部幸夫
ページ範囲:P.820 - P.821
はじめに
ヘモグロビン(Hb)は2分子ずつのα,非αグロビン鎖(β,γ,δ)からなる四量体である.胎児期はほとんどが胎児ヘモグロビンHbF(α2γ2)で占められるが,出生を境にHbA(α2β2)が優位となる.HbFは生後6か月間に急激に低下し,1〜2歳で成人値となる.成人ではHbA 96%,HbA2(α2δ2)3%,HbF 1%程度である.しかし,成人でもHbFの増加は多数の先天性および後天性血液疾患でしばしば見られる.
Part 5 凝固・線溶検査
1.検査の目的と意義
著者: 渡辺清明
ページ範囲:P.827 - P.829
はじめに
凝固・線溶系検査の目的および測定意義は,多くは出血傾向の診断のためにある.ただ,最近は血栓症,特に血栓性素因の診断にも一部の検査が用いられるようになった.
2.検体の取り扱い,保存法と注意点
著者: 安室洋子
ページ範囲:P.830 - P.831
はじめに
臨床検査における各種測定は,近年,精度の高い多機能の測定装置が開発され,信頼性の高い測定が可能となった.そのような環境の中で測定を行う技師は,単なるスイッチマンになっていないであろうか.特に凝固・線溶検査分野では検体試料の状態(扱いかた,保存状態)は検査手技以上に測定結果に影響を及ぼす重要な因子となることがある.本稿では多岐にわたる凝固検査項目の中で活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT),プロトロンビン時間(PT),フィブリノゲン(Fbg)など日常凝固検査として施行されている検査項目,および特殊検査として凝固因子定量およびその抑制因子,ループスアンチコアグラント(LA)検査など,検体として主に血漿を用いる検査について解説する.
3.検査に用いる抗凝固剤の種類と使い分け
著者: 松野一彦
ページ範囲:P.832 - P.833
はじめに
現在,凝固検査の多くは自動測定が可能となり,測定精度の向上には目を見はるものがある.誤差の多くは,むしろ抗凝固剤の使いかたを含めた採血から血漿分離までの測定前(preanalytical)の要因によることが多い.
本稿では,凝固・線溶・血小板機能検査に用いられる抗凝固剤の種類と特徴,具体的な使いかた,使用上の注意などについて述べる.
4.ルーチン検査
1)検査の実際 a)出血時間
著者: 田中由美子 , 権藤和美
ページ範囲:P.834 - P.838
検査の目的と意義
出血時間は,皮膚に切創を作り,湧出する血液が自然に止血するまでの時間を測定するin vivoのスクリーニング検査である.この検査は一次止血を反映し,一次止血をつかさどる血小板の量的,質的異常によって延長する.
出血時間の測定法には,Duke法,Ivy法,Template Ivy法,Simplate法などがある.
1)検査の実際 b)APTT
著者: 高宮脩
ページ範囲:P.839 - P.840
検査の目的と意義
活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)は内因系凝固のスクリーニング検査法である.高分子キニノゲン,プレカリクレイン,第XII因子,第XI因子,第IX因子,第VIII因子,第X因子,第V因子,第II因子,フィブリノゲンの量および質の低下を反映する.内因系凝固過程に関与する後天性循環抗凝固物質やヘパリンに感受性を示すが,アンチトロンビンIIIやプロテインCなどの生理的凝固制御因子の増減に影響することはない.第X因子,第V因子,第II因子,フィブリノゲンはむしろプロトロンビン時間(PT)に感受性を示す.
1)検査の実際 c)PT
著者: 馬場百合子
ページ範囲:P.841 - P.843
検査の目的と意義
PTは1935年にQuickにより発表され,外因性凝固因子と共通性凝固因子のスクリーニング検査として用いられている.原理は被検血漿に組織トロンボプラスチンとカルシウムイオンを加えて,凝固するまでの時間を測定するものである.この検査は外因性凝固因子と共通性凝固因子群の複合した反応を測定する方法であり,第II因子,第V因子,第VII因子,第X因子の活性に関する異常を検出することができる.
内因性凝固因子群と共通性凝固因子群の反応を測定するAPTTと組み合わせることにより,血液凝固異常症のスクリーニング検査に用いられるほか,ワーファリン服用患者のコントロールの指標などに使われている.
1)検査の実際 d)フィブリノゲン
著者: 岡村啓子
ページ範囲:P.844 - P.846
はじめに
フィブリノゲンは,凝固過程の最終段階にトロンビンによってフィブリンに転化する分子量34万の糖蛋白である.A(α)鎖,B(β)鎖,γ鎖の3種類のポリペプチドがS-S結合したものが対をつくっている二量体であり,トロンビンが作用すると,A(α)鎖,B(β)鎖のN末端からフィブリノペプチドA,Bが遊離し,(α,β,γ)2からなるフィブリンモノマーが生成される.このモノマーが重合してポリマーとなり,さらに活性化第XIII因子により安定化フィブリンに転化する.フィブリノゲンは,熱に不安定で,56℃,30分間で完全に変性し,pH9.5以上で凝固活性を失う.等電点はpH6.5で,電気泳動でβ-グロブリンとγ-グロブリンの間の易動度を持つ.肝実質細胞で産生され,血中(約80%)および組織液(約20%)に分布する1).血中半減期は100〜150時間である2).
1)検査の実際 e)トロンボテスト
著者: 国分まさ子 , 鈴木節子
ページ範囲:P.847 - P.850
検査の目的と意義
トロンボテスト(TT)は,第II・VII・X因子活性およびPIVKA(protein induced by vitamin K absence or antagonist)による阻害反応を特異的・総合的にとらえる検査である.TTはビタミンK欠乏状態の検出および経口抗凝血薬療法の指標のために,当時行われていたプロトロンビン時間(PT)より安定性と特異性に優れた方法として1959年にオーレンにより考案された方法である1).経口抗凝血薬療法で用いられるクマリン系抗凝血薬は,ビタミンK依存性の因子が産生される際に必須のビタミンKに分子構造が極めて類似しているために競合して取り込まれ,人工的なビタミンKの不足環境により正常な因子の産生が低下し,同時にPIVKAが産生される.PIVKAは凝固活性能がなく,むしろ正常な因子が作用する際に競合して阻害する.
1)検査の実際 f)FDP
著者: 末久悦次
ページ範囲:P.851 - P.854
検査の目的・意義
生体内での線溶現象は,フィブリンの形成(血栓)を認めない線溶現象(一次線溶)と,形成された血栓を溶解する線溶現象(二次線溶)とに区別され,線溶亢進時には,フィブリノゲンもしくはフィブリンが産生されたプラスミンにより分解を受け,分解産物として血液中に存在することになる(図1).したがって,FDPとは,フィブリノゲンとフィブリンの分解産物の総称であり,血液中のFDPを検出することは,生体内での線溶亢進を意味していることになる.
また,FDPの生成は,産生されたプラスミンにより,フィブリノゲンのAα鎖およびBβ鎖の一部が切断されX分画となり,さらにY分画とD分画に切断され最終的にE分画とD分画に分解され,一次線溶のFDP(FgDP)として産生される.一方,二次線溶では,まず凝固系活性化に伴うトロンビンの生成により,フィブリノゲンからフィブリンポリマー,さらに安定化フィブリンに転化した後,プラスミンにより分解を受けることになり,互いに異なる分子から形成されるDドメイン2分子とEドメイン1分子を最小単位とするさまざまな(D2E)nが産生されることになる(図2).したがって,FDPは単一な蛋白ではなく,フィブリノゲン由来のFgDPとフィブリン由来のFDP(Dダイマー)との種々の構成により存在していると考えられる.
2)データの読みかたと検査診断の進めかた
著者: 川合陽子
ページ範囲:P.855 - P.859
はじめに
凝固・線溶系のルーチン検査としてはAPTT・PT・フィブリノゲンの3項目が一般的である.手術前や重篤な基礎疾患を有する患者の凝血学的スクリーニング検査としては,上記3項目にFDPを加え,血小板数の検査とともに5項目が一般的である.出血時間やトロンボテスト(TT)は対象患者がやや限定され,若干異なる位置づけと思われる.凝血学的検査は出血傾向の診断のために進歩してきたが,スクリーニング検査としては,一次止血には血小板数と出血時間,二次止血にはAPTT,PT,フィブリノゲン,線溶のスクリーニング検査にはフィブリノゲンとFDPがある.臨床医が出血傾向の患者を認めたときに鑑別する疾患を図1に示した.
3)再検基準と精度管理
著者: 香川和彦
ページ範囲:P.860 - P.864
はじめに
血液凝固・線溶系因子は,わずかな条件の違いで変性しやすいため,異常値の判断や精度管理を行う際には,測定以前の条件,すなわち検体の採取,分離,保存状況などが適切かどうか(分析前段階の精度保証)を常に意識することが大切である.また血液凝固・線溶系検査の多くの項目は,十分な標準化の検討がなされていないことも念頭に置かなければならない.これらの特徴をよく理解したうえで血液凝固・線溶系検査の業務にかかわる必要がある.
5.特殊検査
1)血小板機能検査
著者: 井上克枝 , 矢冨裕 , 尾崎由基男
ページ範囲:P.865 - P.869
検査の目的と意義
コラーゲン,エピネフリン,ADPなどの血小板活性化物質は血小板上のそれぞれの受容体に結合するが,血小板内情報伝達機構1)を介して,最終的には血小板上のglycoprotein(GP)IIb/IIIaを活性化させる.活性化GPIIb/IIIaはフィブリノゲンとの結合能を持つようになる.フィブリノゲンが糊のような役割を果たし,血小板同士がGPIIb/IIIaを介して架橋され,血小板凝集が成立する.ずり応力刺激時などには,von Willebrand因子(vWF)が,血小板膜上のGPIbと結合して,GPIIb/IIIaではなくGPIbを介した血小板凝集を起こす.ただし,in vitroの血小板凝集能検査においては,リストセチンによりGPIbとvWFの結合を惹起させる.生体内では,血管の損傷部位において血小板がコラーゲンなどの血管内皮下組織,あるいはコラーゲンに接着したvWFを認識し,そこに粘着することで血栓形成が開始される.さらに血小板活性化に伴って,血小板内の顆粒より放出される血小板活性化物質がさらに周囲の血小板の活性化を引き起こすというポジティブフィードバックが生じ,速やかに血小板凝集が進行する(図1).
本稿ではこれら血小板凝集能,粘着能,放出能の異常など,血小板の質的(機能)異常に対する検査について概説する.本検査が行われるのは次のような場合である.
2)血餅退縮試験
著者: 渡辺清明
ページ範囲:P.870 - P.871
検査の目的と意義
血餅退縮試験は血小板無力症の診断のために行われる.その他の目的で検査されても臨床的意義はほとんどない.
血液凝固が起こると,血小板は血餅中に取り込まれ,血小板膜の糖蛋白GPIIb/IIIaとフィブリンが結合する.GP IIb/IIIaは血小板内の収縮蛋白と結合しているので,血小板がトロンビンで活性化されると,収縮蛋白が機能し,フィブリンは引っ張られ血餅が退縮する.これが血餅退縮である.
3)β-TG,PF4
著者: 新倉春男
ページ範囲:P.872 - P.874
検査の目的と意義
β-トロンボグロブリン(β-TG)と血小板第4因子(PF4)はいずれも血小板のα顆粒に存在する血小板に固有の蛋白であり,血小板以外の組織,細胞にはほとんど存在しないので血小板特異蛋白と呼ばれている1).コラーゲンやトロンビンなどのアゴニスト刺激により血小板から放出されるので,血漿中のβ-TGやPF 4濃度の上昇は血管内での血小板活性化の指標と考えられ,血栓症およびその準備状態の診断,血栓症の薬物治療効果判定などに有用な検査である2).
血小板増加,フィブリノゲン高値,FDP高値,アンチトロンビンIII(ATIII)低下など,止血凝固検査で血栓準備状態が疑われる場合,また糖尿病,高脂血症,虚血性心疾患,脳血管障害などが存在する場合に測定の意義がある.
4)凝固因子測定
著者: 木下幸子 , 脇山マチ子
ページ範囲:P.875 - P.878
検査の目的と意義
日常検査で凝血学的検査の異常が見られ,凝固因子に異常があると考えられる患者の確定診断を必要とする場合に凝固因子活性,凝固因子量(習慣的に抗原量ともいう)を測定する1).凝固因子欠乏症には単独因子欠乏と複合因子欠乏があり,前者は先天性欠乏症が考えられ,後者は肝臓で産生される凝固因子の肝障害による低下や,ビタミンK依存性凝固因子のビタミンK欠乏症による低下,DICによる低下,出血症状による低下などが考えられる.また,近年は,凝固因子活性,凝固因子量を測定し,蛋白欠損症や蛋白の機能異常症が考えられた場合は遺伝学的解析が行われている2).表1は日常検査の測定値から欠乏している凝固因子を推測する場合の参考に,プロトロンビン時間(PT),活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT),ヘパプラスチン(HP)の測定値と患者の出血傾向の有無により関連している凝固因子を分類した3)ものである.
5)AT III
著者: 湯浅宗一 , 辻肇
ページ範囲:P.879 - P.881
検査の目的と意義
AT III(アンチトロンビンIII)は432個のアミノ酸残基からなる分子量59,000の一本鎖の糖蛋白質である.また,血漿セリンプロテアーゼインヒビターファミリーの蛋白の1つで,ヘパリンの存在下にトロンビンや活性化第X因子などのセリンプロテアーゼ凝固因子を阻害する1).AT IIIは主として肝臓で産生されるが,この血中の濃度はその産生と消費のバランスによって保たれている.例えば肝障害ではその産生が低下し,DICにおいては消費によって血中濃度は低下する.したがって,肝障害時,DIC,あるいはヘパリン投与時のAT III製剤補充の適応の決定などにAT III活性値を測定することが必要となる.また,妊娠,手術などを契機として血栓塞栓症を発症する疾患の2〜6%に先天的AT III欠損症が報告されているが2),これらの疾患については活性値と同時に抗原量の測定,さらに遺伝子検査も必要となってくる.AT III遺伝子は第1染色体q23〜25に存在し,全長約19kbからなり,7個のエクソンと6個のイントロンから構成されている.
6)プロテインC,S
著者: 西岡淳二 , 登勉 , 鈴木宏治
ページ範囲:P.882 - P.886
はじめに
血管内壁にはプロテインC(PC)凝固制御系と呼ばれるXa因子やトロンビンの生成を阻害する血液凝固制御機構が存在する.血管内で生成された微量のトロンビンは,血管内皮細胞上のトロンボモジュリン(TM)に結合し,セリンプロテアーゼ前駆体であるPCを特異的に活性化する.血管内皮細胞上にはPCレセプター(endothelial cellprotein C receptor:EPCR)が存在し,EPCR結合PCはトロンビン・TM複合体により効率的に活性化される1).活性化されたPC(APC)は,プロテインS(PS)をコファクターとして,凝固反応の律速因子であるVa因子とVIIIa因子を分解・失活化し,凝固反応の過剰な進展を阻害する.一方,APCは内皮細胞や活性化血小板リン脂質膜上でPCインヒビター(PCI)により失活化される2).
血漿中のPSは,補体系制御因子のC4b結合蛋白質(C4BP)と乖離・会合の平衡状態にあり,PSの約60%はC4BPとの複合体型として,40%は遊離型として存在し,遊離型PSのみがAPCのコファクターとして機能する.また,PSはVa因子およびXa因子に直接結合してプロトロンビナーゼ複合体の形成を阻害し,APC非依存性に血液凝固反応を阻害する.
7)ループスアンチコアグラント
著者: 天谷初夫
ページ範囲:P.887 - P.889
検査の目的と意義
ループスアンチコアグラント(LA)は,細胞膜を構成するリン脂質などの抗リン脂質抗体のうち,凝固因子活性を抑制することなく,プロトロンビン時間(PT)や活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)などのリン脂質依存性の凝固検査において凝固時間を延長させる自己抗体である.試験管内では,凝固時間を延長するにもかかわらず,臨床的には出血症状ではなく血栓症状を示す.1980年代に,全身性エリテマトーデス(SLE)を中心とする自己免疫疾患における血栓症,臓器梗塞および習慣性流産とLA,抗カルジオリピン抗体との関係が明らかになり,これらを必須検査とする抗リン脂質抗体症候群の疾患概念が確立され1),LA測定の臨床的意義が注目されるところとなった.また,1997年のアメリカリウマチ協会のSLE分類基準の改訂において,LA陽性所見などが追加された2).さらに,1999年9月にはLAテスト「グラディポア」(LAテスト:グラディポア社)がLA検査として初めて保険収載された.
8)凝固因子インヒビター
著者: 腰原公人
ページ範囲:P.890 - P.892
はじめに
凝固因子インヒビターには,生理的に存在するアンチトロンビンやプロテインCなどの凝固阻止因子と後天的に出現する循環抗凝血素とも呼ばれるものがある.
ここでは後者のうち,単一の凝固因子(第VIII,IX因子を中心に)を標的とする免疫グロブリンの検査方法について解説する.なお,invitroでリン脂質依存性に凝固因子活性に影響を及ぼすループスアンチコアグラントについては前項を参照されたい.
9)TAT,PIC
著者: 島津千里
ページ範囲:P.893 - P.896
はじめに
凝固機構の活性化によりプロトロンビンはプロトロンビナーゼ複合体(活性化第X,V因子,リン脂質)の限定分解を受け,プロトロンビンフラグメント1+2を遊離しトロンビンが生成される.トロンビンはフィブリノゲンをフィブリンに転換し,また血小板を活性化して血栓を形成するなど止血に重要な役割を果たすが,トロンビンの過剰生成は血栓症やDICを惹起する.生理的条件下でトロンビンはAT IIIやヘパリンコファクターIIにより阻害され,過剰な凝固反応が進展しないよう制御される.AT IIIはトロンビンに対する最も強力な阻害因子であり,ヘパリンの存在下で阻害速度は促進される.N未端側のヘパリン結合ドメインと血管内皮細胞にて産生されるグリコサミノグリカンとの結合により立体構造が変化し,トロンビン阻害に必要なドメインが表面に露出される.このC末端近くのトロンビンとの反応部位(Arg-393/Ser-394)がトロンビンの結合により切断され,トロンビンとAT IIIのモル比1:1の複合体であるトロンビン-AT III複合体(thrombin-antithrombin III complex;TAT)が形成される1).
線溶機構はプラスミンが血栓の主成分フィブリンを溶解する反応である.
10)Dダイマー
著者: 片桐尚子
ページ範囲:P.897 - P.900
検査の目的と意義
Dダイマーは架橋化されたフィブリンのプラスミンによる分解産物であり,二次線溶を反映する分子マーカーの代表的検査である.
凝固過程の最終産物であるフィブリノゲンにトロンビンが作用するとフィブリンモノマーが生成され,フィブリンモノマーは重合してフィブリンポリマーとなる.フィブリンポリマーはトロンビンによって活性化された第XIII因子(F XIIIa)とカルシウムイオンの作用で強固な安定化した架橋化(cross-linked)フィブリンポリマーとなる.架橋化フィブリンにプラスミンが作用すると,高分子の中間分解産物を経て,DD/E複合体が生成され,最終的にDダイマーとE分画となる(図1).したがって,血中Dダイマーの高値は生体内にフィブリン血栓が存在し二次線溶が亢進していることを意味し,播種性血管内凝固症候群(DIC)や血栓性疾患の病態把握,血栓溶解療法の治療効果のモニタリングなど臨床的に測定意義がある.
11)可溶性フィブリン
著者: 岡嶋研二
ページ範囲:P.901 - P.903
検査の目的と意義
血栓症の臨床症状や出血傾向,また凝固時間の延長や血沈の遅延,さらに血小板数の減少などの播種性血管内凝固症候群(DIC)の存在を疑わせる所見が認められれば,微小血栓形成のマーカーである可溶性フィブリンモノマー複合体や可溶性フィブリン濃度を測定し,上記の病態診断のための重要な所見とする.
血栓症の病態では,いろいろな原因で血液凝固系が活性化され,その結果,トロンビンが生成され,血栓が形成される.フィブリノゲンにトロンビンが作用すると,フィブリノゲンのAα鎖のArg16-Gly17間の結合が切断され,アミノ末端から16個のアミノ酸からなるペプチド(フィブリノペプチドA)が放出され,desAA-fibrin(フィブリンI)が形成される.さらに,トロンビンの作用により,フィブリノゲンのBβ鎖のアミノ末端のArg14-Gly15間の結合を切断し,14個のアミノ酸からなるペプチド(フィブリノペプチドB)が放出され,desAABB-fibrin(フィブリンII)が生成される.フィブリンIIでは,AαおよびBβのアミノ末端に,それぞれ新たにAおよびB重合部位が露出され,それぞれフィブリノゲンのAαおよびBβのカルボキシ末端と結合し,フィブリノゲンと可溶性複合体を形成する.形成されたフィブリンの濃度がフィブリノゲン濃度を超えると,フィブリンが重合し,不溶性フィブリンを形成する.
12)プラスミノゲン
著者: 上嶋繁 , 松尾理
ページ範囲:P.904 - P.906
生理作用
プラスミノゲンは肝細胞で産生される糖蛋白質で,血液線溶系(血液中のフィブリノゲンまたはフィブリンの分解)に深く関与している.プラスミノゲン自体には酵素活性がなく,プラスミノゲンアクチベーター(plasminogen activator;PA)によって酵素活性を有するプラスミンに活性化1)される.活性化されたプラスミンの多くは,その活性阻害物質であるα2-プラスミンインヒビター(α2-plasmin inhibitor;α2-PI2))と複合体(PIC)を形成して失活化されるが,失活化を免れたプラスミンは血液中のフィブリノゲンや血栓の構成成分であるフィブリンを分解する(図).
PAには血管内皮細胞から分泌されるtissue-type PA(t-PA)やurokinase-type PA(u-PA)があり,その活性はPAのインヒビターであるplasminogen activator inhibitor(PAI;血液中には主にPAI-1が存在する)によって制御されている.PAにはt-PAやu-PAのほかに細菌由来のストレプトキナーゼやスタフィロキナーゼ3)などがある.
Part 6 フローサイトメトリー
1.フローサイトメトリーの原理
著者: 米山彰子
ページ範囲:P.911 - P.912
フローサイトメトリーとは
フローサイトメーターは蛍光染色した細胞などの粒子を細い流路に流し,それにレーザー光を当て,放射される散乱光や蛍光を細胞単位で測定する装置である.目的とする細胞を分取するソーティングの機能を備えた機種もある.
フローサイトメーターを用いた測定あるいは学問分野をフローサイトメトリーと呼ぶ.モノクローナル抗体や蛍光色素の開発とともに,近年,生物学や免疫学など幅広い分野で用いられ,その応用分野は細胞表面および細胞内抗原の解析,核DNA量の解析,細胞機能解析,細胞内pHや細胞内Ca2+測定,細胞内酵素測定,微生物の解析など多岐にわたる1〜3).
2.細胞表面抗原検査の実際
著者: 米山彰子
ページ範囲:P.913 - P.914
はじめに
血液細胞は浮遊液としてフローサイトメーターで解析するのに適しており,造血器悪性腫瘍細胞の抗原解析やリンパ球サブセット検査などは臨床検査として広く行われるようになった.フローサイトメーターは,大量の細胞の複数のパラメーターを短時間に,しかも個々の細胞について測定できることが最大の特徴であり,例えば前方散乱光と側方散乱光のサイトグラムで単核球にゲーティングし,多重染色した2〜3種類の細胞表面抗原について解析するというようなことが簡単に行われる.特徴をよく知ったうえで使いこなすことが大切である.また,臨床検査としては検査法や測定機器が異なっても施設間差がないことが大切であり,フローサイトメトリーの標準化が求められている.米国ではNational Committee for Clinical Laboratory Standards(NCCLS)がフローサイトメトリーの標準化のためのapproved guidelineを発刊し1),わが国においても日本臨床検査標準協議会のワーキンググループから末梢血リンパ球表面抗原検査に関するガイドラインが発表された2).フローサイトメトリーの標準化は現状ではまだ不十分であるが,これらの動きを通して今後検討が重ねられると思われる.モノクローナル抗体による細胞の染色,フローサイトメーターの調整,測定と解析までの流れを以下に解説する.
3.モノクローナル抗体のCD分類
著者: 米山彰子
ページ範囲:P.915 - P.917
CD分類とは
血液細胞の表面には抗原レセプター,細胞接着分子,サイトカインレセプター,補体レセプター,Fcレセプターなど種々の分子が存在し,機能を果たしている.これらの分子に対する非常に多くのモノクローナル抗体が作製されており,国際ワークショップ(International Workshop onHuman Leukocyte Differentiation Antigens)によってこれらをclusterとして整理分類し,統一的CD(cluster of differentiation)番号がつけられている1).1996年の第6回WorkshopでCDナンバーが166に達した.
主なCD抗原を表に示す.
4.造血細胞の分化・成熟過程における細胞表面抗原の変化
著者: 米山彰子
ページ範囲:P.918 - P.919
血液細胞はその種類により,また分化成熟の段階によって発現している抗原が異なる.細胞表面抗原を解析することにより,末梢血や骨髄,リンパ節その他の組織中の血液細胞を同定あるいは分類したり,白血病や悪性リンパ腫細胞を同定したりすることができる.そのためには各種の血液細胞の分化に伴う抗原の変化を知ることが必要である.各種造血細胞の成熟・分化に伴う細胞表面抗原の変化を図1〜3に示す.
5.リンパ球サブセット検査
著者: 米山彰子
ページ範囲:P.920 - P.920
検査の目的と意義
リンパ球サブセット検査は,主に末梢血リンパ球について通常の形態的検査ではわからない細胞表面抗原の検索からリンパ球の分類を行うものである.Tリンパ球,Bリンパ球,NK細胞の比率を求め,さらにTリンパ球のうち,CD4陽性のhelper/inducer T cell,CD8陽性のsuppressor/cytotoxic T cellの比率を求めることができる.疾患によってはサブセットの増減がさほど著明でないために個々の変動としてはとらえにくく,CD4陽性リンパ球とCD8陽性リンパ球の比として比較することも多い(CD4/CD8比,TH/TS比).この場合も比だけでなく,何が絶対数として増加あるいは減少しているのか,末梢血のリンパ球数を考慮して判断することが大切である.
6.造血器腫瘍の診断における細胞表面抗原検査の応用
著者: 米山彰子
ページ範囲:P.921 - P.923
はじめに
造血器腫瘍の診断にあたり,細胞表面抗原検査は欠くことのできないものになっている.白血病,悪性リンパ腫について細胞表面抗原検査がどのように応用されているか紹介する.
Part 7 免疫組織化学染色の実際
1.白血病
著者: 須永良 , 花田英子
ページ範囲:P.926 - P.927
はじめに
白血病は骨髄原発の自律増殖性疾患で,形態学的分類に加えて,免疫学的検索による骨髄球系,Tリンパ球系,Bリンパ球系の大別や,分化段階の推定が予後判定に関係することから,検査は両者を併用して行う必要がある.特にミエロペルオキシダーゼ陰性のANLL(FAB-M0),赤芽球系(FAB-M6),巨核球系(FAB-M7),biphenotypic leukemia,mix leukemiaなどの判定には,形態観察とともに免疫マーカー判定が可能な免疫組織化学染色が重要である.
2.悪性リンパ腫
著者: 須永良 , 花田英子
ページ範囲:P.928 - P.929
はじめに
悪性リンパ腫は自律増殖性悪性腫瘍であるリンパ増殖性疾患で,形態学的検索に加えて免疫学的検索による腫瘍細胞の帰属の決定,分化段階の推定が必要であり,免疫マーカーを形態観察とともに判定可能とする免疫組織化学染色が診断法の1つとして重要とされている.
3.多発性骨髄腫
著者: 須永良 , 花田英子
ページ範囲:P.930 - P.930
はじめに
多発性骨髄腫はBリンパ球の最終分化段階である形質細胞の1個が骨髄内で自律増殖して,単クローン性のいわゆる骨髄腫細胞を形成し,他の形質細胞を圧倒し,大部分の症例で単クローン性免疫グロブリン(M蛋白)を産生する疾患である.
M蛋白は軽鎖(light chain)の型のどちらか一方に対してのみ単クローンを形成することから,免疫組織化学染色にてκ型,λ型を証明することで腫瘍性か否かの判定が可能となる.
Part 8 遺伝子関連検査 1.染色体検査
1)染色体検査の原理・種類・目的および外部委託のしかたと注意点
著者: 田村高志
ページ範囲:P.932 - P.932
はじめに
染色体は細胞分裂中期にのみ観察することができる.そのため,染色体検査は分裂している細胞をとらえなければならない.しかし,検体として細胞を採取してそのままで染色体を観察できるのは,骨髄細胞あるいは生殖細胞のように活発に分裂・増殖している組織に限定されてしまう.検体採取が容易にでき,分裂増殖している細胞を得るためには培養液を用いてin vitroでの組織培養をする必要がある.この組織培養の技術から,TjioとLevan(1956年)は流産胎児の肺組織の培養細胞から得られた標本でヒトの染色体が46本であることを最初に報告した.これ以後,組織培養の技術向上,組織培養用培地の改良と開発,Gバンド法などの分染法による染色体解析法の導入によって,ダウン症候群を代表とするさまざまな染色体異常症が次々に報告された.
染色体と造血器腫瘍との関係が論じられるようになった契機は,染色体数が46本と報告された4年後の1960年に慢性骨髄性白血病(CML)患者に特異的に見られるPhiladelphia(Ph)染色体の発見である.Ph染色体は22番染色体の長腕が欠失した微小染色体である.後にその欠失した部分が9番染色体と相互転座していることが判明した.その後しばらくの間,造血器腫瘍に特異的な染色体異常の報告はなかった.
2)検体の採取と注意点
著者: 田村高志
ページ範囲:P.933 - P.933
はじめに
主題は造血器腫瘍の染色体検査であるが,染色体検査の基本は末梢血リンパ球から得られた標本を分析することであるので,末梢血についても解説する.
前項で述べたように,染色体検査は目的によって検査材料が異なってくる.通常の染色体検査では先天異常を対象としていることから,乳幼児からの検体採取が容易な末梢血が一般的である.
3)検査の実際 a)培養と標本作製
著者: 田村高志
ページ範囲:P.934 - P.935
はじめに
細胞培養はすべて無菌操作で行うのが原則である.使用する試薬,器具類は乾熱滅菌,高圧滅菌あるいは濾過滅菌を行う.また,培養操作は専用の培養室で行う.培養室のような専用スペースが確保できない場合はクリーンベンチでも可能である.
3)検査の実際 b)分染法による染色体同定
著者: 田村高志
ページ範囲:P.936 - P.938
はじめに
分染法の開発は染色体検査の第2期黄金時代といわれている.1970年代に入り,3)Hチミジンを利用した分染法に代わりQ,G,Rバンド法が次々と報告され,現在では分染法なしでは染色体検査の報告ができなくなっている.これらの分染法が報告されてからは,詳細な染色体解析が可能となり,新たな染色体異常症が報告されるようになった.
分染法による解析において,検査の基本は分析しやすい標本を,つまり重なりが少ない広がりのよい分裂像が多数見られる標本を作製する技術が必要である.
3)検査の実際 c)染色体分析
著者: 田村高志
ページ範囲:P.939 - P.941
はじめに
造血器腫瘍と染色体異常との最初のかかわりは1960年,慢性骨髄性白血病(chronic myelocyticleukemia;CML)の患者で見られたPh染色体の発見である.Ph染色体は当初G群染色体長腕の部分欠失と推測されていた.分染法による解析で,この染色体は22番染色体(22q-)であることが判明した.さらに9番染色体長腕と相互転座していることも併せて確認された.急性骨髄性白血病,リンパ性白血病でも特異的な染色体異常が報告された.
近年,FISH法(後述)などの分子細胞遺伝学的手法を用いることで,染色体分染法で見逃されていた微小な染色体異常についても新たに報告されてきている.最近は染色体転座の切断点に局在する癌遺伝子との関連についての病因論も明らかにされてきている(「遺伝子検査」の項を参照).ここでは染色体異常についてのみ述べる.
3)検査の実際 d)FISH法
著者: 田村高志
ページ範囲:P.942 - P.945
はじめに
蛍光in situ分子雑種(fluorescence in situ hybridization;FISH)法は,遺伝子DNAの局在部位を染色体,間期細胞核あるいは病理組織切片上に蛍光シグナルとして可視的に観察することができる分子細胞遺伝学的手法である.その原理は,スライドグラス上の染色体DNAを一本鎖に変性後,やはり一本鎖に変性した検出用プローブとの間でハイブリダイゼーションを行い,相補的な標的DNAにプローブが結合した部位を蛍光顕微鏡によりシグナルとして検出することである.このときRバンド処理をした染色体標本を使うと,分染パターンも同時に蛍光で観察できることからプローブの局在を同定でき,遺伝子マッピングとして利用されている.
4)検査結果の読みかたとコメントの付けかた
著者: 田村高志
ページ範囲:P.946 - P.946
はじめに
造血器腫瘍の場合,骨髄細胞の染色体検査は末梢血リンパ球培養法と比較して得られる分裂像の数が少ないことが多い.さらに特異的な染色体構造異常を持つ細胞の頻度が低いときは,核型解析を行っても正常核型を認めてしまうことがある.そのため,造血器腫瘍の検査においては,できる限り数多くの染色体分析を行うことが必要である.末梢血リンパ球の染色体検査は,通常,広がりのよい核板で20細胞以上について染色体総数をカウントし,数的異常,構造異常のないことを確認する.次に5細胞についてG分染法による解析を行い,2〜3細胞を写真撮影して核型に並べて報告する.
造血器腫瘍については,これまで述べてきたように染色体分裂像が少ないため,通常の検索では解析が困難なことが多い,そこで転座異常の染色体を絞り込み,その染色体ペインティングプローブを用いて解析を行う.また,M-FISH,SKY法による解析はより簡便に転座異常を起こしている染色体解析のスクリーニングが可能である.しかし,最終的な結果報告は分染法による核型記載が必要である.核型の記載方法は,ISCN(International System for Human Cytogenetic Nomenclature)に従って行う.
2.遺伝子検査
1)遺伝子検査の原理・種類と目的
著者: 北村聖
ページ範囲:P.947 - P.949
はじめに
白血病の診断は腫瘍細胞が末梢血中を流れているため,当然,末梢血や,骨髄血の形態的観察で診断可能な場合が大多数である.しかし,その病型診断,あるいは治療後の残存腫瘍細胞の検出などにおいては,いまだ少ない病型の白血病であるが,これらの染色体変化や遺伝子変化をとらえることで非常に鋭敏かつ正確な診断をすることができるようになってきた.本稿では,表に示すような白血病・リンパ腫の遺伝子診断の意義と原理,種類について概説する.
2)遺伝子検査の倫理的課題
著者: 北村聖
ページ範囲:P.950 - P.950
はじめに
遺伝子操作技術と分子生物学的な知見の集積に伴い,遺伝子診断と呼ばれる診断技術が進歩し,実用化されてきている.本稿では,遺伝子診断に関する倫理的な問題点を議論する.
3)検査の実際
著者: 横田浩充 , 北村聖
ページ範囲:P.951 - P.953
はじめに
近年,白血病の治療は化学療法や骨髄移植などの技術的進歩に伴い,従来の光学顕微鏡による診断法では検出できない微小残存白血病細胞(minimal residual disease;MRD)の検出が必要となっている.光学顕微鏡では百ないし数百に1個の確率でしか白血病細胞を検出しえないが,PCR法を用いた遺伝子検査では白血病の各病型に特徴的なキメラ遺伝子を検出することで,104〜106細胞に1個の高感度で白血病細胞を検出しうる.このように高感度にMRDをとらえることで,化学療法や骨髄移植後の治療効果確認,自己骨髄移植における腫瘍細胞混入の有無,予後の推定や再発予知に役立てるのがこの検査の目的である.
本稿では,保険適応のあるPCR法を用いた転座型白血病の遺伝子検査について,検査の実際を概説する.
4)遺伝子検査の精度管理—検体採取と検査上の留意点
著者: 横田浩充 , 北村聖
ページ範囲:P.954 - P.955
はじめに
遺伝子検査の精度管理を行ううえで,検査および検体に対する双方の手技操作上の正誤確認が必要と考えられる.特に検体,すなわちRNA採取には十分な注意が必要である.本稿ではこの点について概説する.
なお,末梢血液ならびに骨髄血の採取に関する留意点は最終項の外部委託のしかたに記載した.
5)検査結果の読みかたと留意点
著者: 横田浩充 , 北村聖
ページ範囲:P.956 - P.957
はじめに
白血病の転座遺伝子の検出の実際を前項で述べた.本稿では,筆者らが勤務する東京大学医学部附属病院での現状を紹介し,検査の読みかたに代えたいと考える.
6)外部委託のしかたと注意点
著者: 北村聖
ページ範囲:P.958 - P.958
はじめに
外注検査項目には,造血器腫瘍のみならず多くの悪性腫瘍の遺伝子診断検査がリストアップされている.前の項目と重複する点も多いが,外注検査の留意点を列挙してみる.
Part 9 臓器移植と臨床検査
3.造血幹細胞移植におけるキメリズム解析
著者: 神田善伸
ページ範囲:P.973 - P.974
はじめに
同種造血幹細胞移植は前処置と呼ばれる大量抗癌剤や全身放射線照射などの治療によって患者(宿主)の造血系を撲滅した後に,ドナー由来の造血幹細胞を移植することにより,新たな造血系を構築する治療法である.この間に骨髄や末梢血の血液細胞は宿主細胞からドナー細胞に入れ替わり,最終的にすべてがドナー由来の細胞になる(full chimerism).しかし,ときにドナー由来の細胞と宿主由来の細胞が共存した状態が持続することも観察される(mixed chimerism).特に,移植後汎血球減少が持続し,移植片不全(graft failure)が疑われる場合などには,その時点での造血がドナー由来か患者由来かによって,その後の治療が変わってくる場合がある.その他にも表に示すような場合にキメリズム(chimerism)解析が必要になる.しかし,通常の検査では血液細胞の由来を決定することは困難であり,以下に述べるような検査が行われている(参考文献は総論的なものだけにとどめた.個々の文献は総論より引用可能である).
1.HLAタイピング
1)血清学的検査
著者: 荒木延夫 , 秋田真哉
ページ範囲:P.960 - P.963
はじめに
HLA(human leukocyte antigen)抗原はヒト第6染色体短腕(6p21.3)上の約4,000kb(400万塩基対)の距離にわたって存在する主要組織適合複合体(major histocompatibility complex;MHC)遺伝子領域に支配される細胞膜抗原である.HLA抗原は表1,2)に示すように高度の多型性を有し,2つのクラスに大きく分類される.クラスI抗原(HLA-A,B,C)は,ほとんどすべての有核細胞に発現し,クラスII抗原(HLA-DR,DQ,DP)はBリンパ球,活性化Tリンパ球,単球/マクロファージなどの限られた細胞に発現している.両クラスともにHLA抗原は分子内に抗原ペプチドを挟み込み,クラスI抗原はキラーT細胞の標的分子となり,クラスII抗原はヘルパーT細胞に抗原提示をする.それゆえに,臓器移植においてはドナーとレシピエント間のHLA適合性が求められ,組織適合性検査としてのHLAタイピング検査が実施されている.HLAタイピング法は,生きたリンパ球を用いる血清学的,細胞学的検査法(HLA-D,DP抗原を検出)と,PCR(polymerase chain reaction)法を用いたDNAレベルでのアリルの検査法があるが,ここでは血清学的検査法について述べる.
2)DNAタイピング
著者: 安藤麻子 , 成瀬妙子
ページ範囲:P.964 - P.968
検査の目的
ヒトの主要組織適合遺伝子複合体(major histocompatibility complex;MHC)であるHLA(human leukocyte antigen)抗原は,自己と非白己の識別因子として働き,高度な遺伝的多型性を示す細胞膜糖蛋白質である.このHLA抗原の検査は,移植におけるドナーとレシピエントの選択に重要であるほか,法医学における個人識別や親子鑑定,疾患と特定のHLAタイプとの相関を用いた各種の疾患の診断などに広く利用されている.HLA検査法としては,前項の「血清学的検査」で述べられた抗血清を用いた血清学的方法やリンパ球混合培養反応を利用した細胞学的方法が従来行われてきたが,近年の遺伝子解析技術の進展によって,HLA遺伝子の塩基配列が明らかになり,現在,再現性が高く,簡便なPCR(Polymerase chain reaction)を用いたDNAタイピングが多くの施設で普及している.
2.造血幹細胞の同定検査
1)フローサイトメトリー
著者: 田窪孝行 , 山根孝久 , 日野雅之 , 巽典之
ページ範囲:P.969 - P.970
はじめに
造血幹細胞を解析する技術の急速な進歩により,フローサイトメトリー(flow cytometry;FCM)によるCD 34モノクローナル抗体を用いた造血幹細胞の測定が迅速性・簡便性の点で極めて優れた解析法として行われている.
2)in vitroコロニー法
著者: 海老原康博 , 辻浩一郎
ページ範囲:P.971 - P.972
はじめに
造血幹細胞は自己複製能と各種血球細胞に分化できる性質を有している.造血幹細胞の分化過程において,その子孫である各種造血前駆細胞を検出する方法としてin vitroコロニー法が確立され,未分化な造血細胞の増殖能と分化能を見極めることができるようになった.現在,in vitroコロニー法は造血前駆細胞数の評価と造血前駆細胞の造血因子への反応性の評価の最も有用な手段として用いられている.
本稿では,筆者らの研究室で行っているメチルセルロース培養法を紹介する.
Part 10 血液検査データに影響を及ぼす治療法
1.輸血
著者: 比留間潔
ページ範囲:P.977 - P.979
はじめに
輸血療法は減少した血液成分を補正するために行われるので,輸血を行えば当然のことながら血球算定検査値や血液凝固検査値が変化することになる.近年では輸血用血液の有効利用のために成分輸血の考えかたが浸透し,不足する血液成分を重点的に補充することが原則である.したがって,むしろ改善させる目的を決めて輸血する量を決定し,必要以上に輸血しないことが重要である.
一方,不測の事態により血液型不適合輸血が行われた場合は,溶血などの副作用のために血液検査値が変化することもある.本稿では輸血により補正される血液検査値の変動および輸血副作用が生じた際の血液検査値への影響について解説する.
2.造血幹細胞移植
著者: 岡本真一郎
ページ範囲:P.980 - P.983
はじめに
造血幹細胞移植(stem cell transplantation)とは,すべての血球に分化・増殖し,かつ自分自身を複製する能力を持つ造血幹細胞を移植する治療法である.現在,造血幹細胞移植は再生不良性貧血,白血病,悪性リンパ腫といった致死的造血疾患の治療としてばかりでなく,化学療法に感受性の高い固型癌の治療や,免疫不全症候群や小児の遺伝性疾患の治療として広く用いられている.
医学は進歩したが,現時点では造血幹細胞自身を純粋に分離し移植することは困難である.そこで,造血幹細胞を多量に含む細胞/細胞分画を輸注することで造血幹細胞移植は行われている.造血幹細胞源としては骨髄血が広く用いられてきたが,最近では末梢血あるいは膀帯血も用いられるようになり,各々骨髄移植(bone marrow transplantation;BMT),末梢血幹細胞移植(peripheral blood stem cell transplantation;PBSCT),膀帯血移植(cord blood transplantation;CBT)と呼ばれている.また,造血幹細胞移植は血縁者あるいは非血縁者より造血幹細胞を採取し移植する同種移植(allogeneic transplantation)と,自分自身の正常と考えられる造血幹細胞を採取・凍結保存し移植する自家移植(autologous transplantation)に分類される.
3.サイトカイン療法
1)EPO
著者: 山下卓也
ページ範囲:P.984 - P.985
赤血球系造血とEPO
エリスロポエチン(EPO)は赤血球系前駆細胞の増殖と分化を促進し,未梢血中の赤血球を調節するサイトカインである.赤血球系の造血については図のとおりであるが,EPOレセプターの発現はBFU-Eから前赤芽球にまで見られ,なかでもCFU-EのEPOに対する感受性が最も高い.
EPOの主たる産生臓器は腎臓である.腎のいずれの部位あるいは細胞でEPOが産生されているかについては結論が得られていない.全産生量の10〜15%は肝臓などの腎以外の臓器で産生されている.こうした臓器におけるEPOの産生量を調節する因子は動脈血の酸素分圧であり,血中酸素分圧の低下に伴って産生細胞におけるEPO遺伝子の転写が促進される.
2)G-CSF
著者: 山下卓也
ページ範囲:P.986 - P.988
G-CSFの作用
G-CSFの生体における作用には,前駆細胞に対しては,好中球系細胞への分化,増殖,成熟を促進し,成熟好中球に対しては,その細胞寿命を延長させ,活性酸素産生能,遊走能,貧食能,殺菌能を亢進させることなどがある.
また,G-CSFは成熟好中球を骨髄や血管内辺縁プールから末梢循環プールへ動員する働きも有する.
3)IFN
著者: 小山覚
ページ範囲:P.989 - P.991
IFNの種類と作用
インターフェロン(IFN)は,遺伝子や蛋白質の構造の違いにより,I型(IFN-α,IFN-βおよびIFN-ω)とII型(IFN-γ)に大別される.さらに現在,IFN-αには28種類の分子種のサブタイプが確認されている.
一般にIFNはサイトカインの一種として多面的生物活性(表1)を有しており,その効果は直接的作用と宿主を介した間接的作用(BRM;biological response modifiers作用)により発揮される.IFNはIFNレセプターと結合し作用を発現する.さらにIFNには,他のサイトカイン産生を誘導・促進したり,逆にIL-2など他のサイトカインにより誘導されたりするというサイトカインネットワークが存在する.
4)IL-2
著者: 小山覚
ページ範囲:P.992 - P.993
IL-2の作用(表1)
IL-2は抗原などに刺激されたTリンパ球より産生され,IL2レセプターを発現した他のTリンパ球あるいは自分自身に作用して細胞増殖を刺激する.また,抗原と反応したTリンパ球を細胞傷害活性を持つキラーTリンパ球に分化させる重要な働きがある.また,Bリンパ球を増殖させ,Bリンパ球が抗体産生細胞に分化するのを助ける.IL-2の作用によりNK細胞も増殖し,IFN-γを産生するようになる.さらに,IL-2はIFN-γと共同しNK細胞の細胞傷害性を増強する.IL-2には,腫瘍細胞を傷害する能力を持つLAK細胞を誘導することが報告され注目されてきた.
ミニ辞典
パッペンハイマー小体
著者: 荒井智子
ページ範囲:P.650 - P.650
■形態学的特徴
パッペンハイマー小体とは,赤血球や有核赤血球中に見られる封入体の一種で,普通染色では紫青色に染まる顆粒である.
鉄過剰供給状態のとき,ジデロソームが有核赤血球内の細胞質内に増加し,ミトコンドリアにも沈着する.このジデロソームや鉄を含むミトコンドリアが成熟赤血球内に移行し,細胞質の辺縁に偏って顆粒の群塊をつくる.顆粒は1個以上,しばしば2〜5個の塊として密集し,直径は0.3〜2μmである.
ゴーシェ細胞
著者: 東克巳
ページ範囲:P.662 - P.662
■普通染色所見
細胞の大きさが50〜60μmくらいの大型細胞で,N/C比が極端に小さく,一見マクロファージか網内系細胞(reticuloendothelial system;RES)を疑わせる細胞である.
核は小型で,窪みが見られたり鋸歯状を呈する.核クロマチンは明確ではないが,網状構造を呈することが多い.細胞質は明るい灰白をおびた青色様であるが,染色色素を取り込んでいないようにも見える.また,細胞質には猫が爪でひっかいたとき筋が入ったようであるとか,タマネギの皮(onion-skin)様あるいは雲状構造と表現される結晶が見られる.
神経芽細胞
著者: 武内恵
ページ範囲:P.729 - P.729
■形態学的特徴
リンパ球とほぼ同大またはやや大きな細胞で,核は円形から類円形で,クロマチンは密である.小さい核小体を見る.細胞質は乏しく,胞体の境界はやや不明瞭である.しばしば花冠(rosette)形成が見られる.これらの細胞間には細い神経線維が介在している.もし,骨髄塗抹標本上で細胞の集簇性やrosette形成が認められれば,診断はかなり確実となる.
偽ペルゲル・ヒュー核異常好中球
著者: 志村裕美
ページ範囲:P.735 - P.735
■形態学的特徴
成熟好中球および好酸球の核は桿状または2核のみで,核型は円形,亜鈴型またはピーナッツ型を示す.好中球,リンパ球および単球の核クロマチンは粗い.
骨髄では骨髄球の時期までの成熟は正常であるが,それ以後クロマチンは粗い小体となり,核の成熟障害が認められる.しかし,細胞質は正常の成熟を示す.また,成熟した好中球も少数出現する.
デーレ小体
著者: 伊井野潤子
ページ範囲:P.746 - P.746
■普通染色所見
デーレ小体は,成熟した好中球の細胞質に見られる封入体で,好塩基性に染まる不明瞭な斑点として認められる.ギムザ染色で淡青色ないし青色に染色され,類円形で,大きさは1〜2μmである.リボソームに存在するRNA(rRNA)が,塩基性色素のメチレンブルーに親和性を示すことから青色に染色される.
電顕的にはリボソームと層状配列の粗面小胞体からなり,特定の封入体というよりは,成熟好中球におけるリボソームや粗面小胞体の部分的遺残というべき変化である.
リード・ステルンベルグ細胞,ホジキン細胞
著者: 清水長子
ページ範囲:P.750 - P.750
■形態学的特徴
リード・ステルンベルグ(Reed-Sternberg;RS)細胞は大リンパ球の2〜6倍(15〜50μm)の巨細胞である.この細胞は,淡紅色の好酸性細胞質を持つ細胞で多核または過分葉の不整形な核を有し,核膜は平滑でやや肥厚,核辺縁部に特徴的なレース状のクロマチン網が存在する.核小体の大きさは赤血球ほどもあり,核小体周囲はクロマチンが分布せず明帯を形成する.RS細胞は核分裂しても細胞分裂はせず,鏡が互いに向かいあっているように左右対称性に2核が配列し,鏡像型(mirror image)を呈することがある.
ホジキン(Hodgkin)細胞は核分裂せず,単核の巨大な細胞で,RS細胞と同様な核小体,豊富な細胞質を持つ.
造血微小環境を構成する細胞
著者: 東克巳
ページ範囲:P.760 - P.760
造血に関係する細胞の中で,最も重要な細胞の1つに造血幹細胞(幹細胞)があることは疑う余地のないところである.しかし,その幹細胞を育てる環境もまた重要であることがわかってきた.特に再生不良性貧血の場合には,幹細胞が正常な機能をしているにもかかわらず,造血能に障害が見られることからも,そのことが明確になった.最近になり,特に幹細胞への造血シグナルの情報伝達に幹細胞の周囲に存在するストローマ細胞や細胞外マトリックスが重要視されている.
幹細胞の分化・増殖はよく植物の栽培に比喩され,幹細胞は植物の種に,ストローマ細胞や細胞外マトリックスは畑に,刺激因子は肥料にたとえられる.どの因子を見ても重要なことがわかる.
マクロファージ
著者: 東克巳
ページ範囲:P.770 - P.770
■形態学的特徴
マクロファージは末梢血を循環しているときは単球と呼ばれる.単球が組織に定住するとマクロファージと呼ばれる.また,マクロファージは組織球と同義語としても用いられている.骨髄では単球と区別して分類される.
細胞の大きさは20μmぐらいから大きいものは100μmぐらいまで見られる.核はほとんどが円形から類円形で,細胞質が円形様であれば偏在し,クロマチン構造は網状構造を呈する.核小体は1個から数個見られることもある.細胞質は不整形が特徴で,類円形から長い突起の見られるもの,あるいは細胞質の辺縁が不明瞭なものなどさまざまである.細胞質は基本的には広く,淡青色で透明感があるが,貧食能が旺盛なため,種々貧食したものと思われる物質が含まれていることが多い.貧食物が青色に染まり,充満しているマクロファージを特に青藍組織球(sea-blue histiocyte)という.
ATL細胞
著者: 片桐尚子
ページ範囲:P.772 - P.772
■形態学的特徴
ATL(adult T cell leukemia)細胞は,類円形を呈する異常リンパ球で,N/C比は大きく,大小不同があり多型性に富む.核網はやや密で,核は不規則な陥凹,深い切れ込みや分葉を有し,腎臓型,分葉型,クローバー型,花弁状(flower cell),くるみ殻状を呈することもある.
脂肪細胞
著者: 東克巳
ページ範囲:P.779 - P.779
■形態学的特徴
脂肪細胞は骨髄塗抹標本に見られ,骨髄巨核球に次いで大型の細胞である.直径は100μmくらいで,核は通常,中央部に円形あるいは類円形として見られ,核クロマチンは粗剛で核小体は見られない.大型な細胞で,異常にN/Cが小さいので,そのような目で探してもすぐに見つけられる細胞である.細胞質には脂肪が含まれているが,標本では染色作業中に溶け出してしまうため皺(ヒダ状)が見らられることがある.それ以外は細胞質に顆粒や封入体は見られない.
中毒性顆粒
著者: 伊井野潤子
ページ範囲:P.790 - P.790
■普通染色所見
通常,好中球の細胞質に見られる顆粒は二次顆粒であり,中性好性の特殊顆粒である.この顆粒はギムザ染色で紫紅色に染まり,微細な顆粒であまり目立たず,細胞質に均一に分布している.
これに比較し,好中球の細胞質に著しく目立つ顆粒に中毒性顆粒がある.この顆粒は,細胞質に大型で不揃いな赤紫色の顆粒として認められる.電顕によるとこの顆粒はアズール顆粒(一次顆粒)であり,アズール顆粒の融合により正常の顆粒よりも大型になっている.また,中毒性顆粒が目立つ好中球では,二次顆粒の数は脱顆粒を起こし著減しているといわれている.
有毛細胞
著者: 杉崎憲子
ページ範囲:P.802 - P.802
■形態学的特徴
有毛細胞(hairy cell)は大リンパ球様(12〜20μm)で細胞質周辺から多数の毛様突起が伸びている細胞である.核は円形から卵円形あるいは彎入し,中央または偏在している.核小体は約半数の有毛細胞で認められる.しかし,わが国では典型例はまれであり,毛様突起の確認が容易ではない非典型例が主体である.その細胞形態は単球様であり,単球とリンパ球の中間程度の形態を示す.
アウエル小体とファゴット細胞
著者: 東克巳
ページ範囲:P.808 - P.808
■普通染色所見
白血病細胞の細胞質にアズール好性で赤紫色の針状に染まる封入体が見られる.これがアウエル小体と呼ばれる.この封入体の形は長さが長いものから非常に短いもの,あるいは太さの太いものから非常に細いものまで見られ,多様性を示す.また,この封入体が1本見られる細胞と2本の束状に見られるbundleと呼ばれるものから,多数見られるファゴット細胞(faggot cell)と呼ばれるものがある.
過分節核好中球
著者: 志村裕美
ページ範囲:P.821 - P.821
■形態学的特徴
通常,好中球の分節核球は2〜5分節核で,平均3分節核であるが,平均5分節核以上の場合は過分節核とみなされる.
好中球の核の過分節は先天的異常として出現することがあり,このような例では分節核を示す以前の成熟好中球(桿状核好中球)の核は大型であるといわれる.
ドラムスティック
著者: 寺島道子
ページ範囲:P.824 - P.824
■形態学的特徴
好中球の分節核球にある小さな突起で,直径が1.2〜1.5μm,充実性の丸いテニスのラケット状ないし太鼓のばち状のもので,1本の糸で核につながっている.
低顆粒球
著者: 荒井智子
ページ範囲:P.854 - P.854
■形態学的特徴
低顆粒球とは,好中球内の二次顆粒が減少あるいは消失している細胞をいう.この場合,顆粒中に含まれているミエロペルオキシダーゼやアルカリホスファターゼなどの活性異常,もしくは低下も考えられる.
造骨細胞
著者: 東克巳
ページ範囲:P.874 - P.874
■形態学的特徴
造骨細胞は非常にまれにしか見られない細胞である.しかし,比較的大きな細胞で,1個単独で存在することは少なく,数個が近辺に見られるので,弱拡大でもわかりやすい細胞である.
細胞の大きさは20〜40μmくらいで,類円形から紡錘形を呈するが,細胞の輪郭や細胞質の辺縁は不明瞭なことが多い.核はほとんどが類円形で,核クロマチン構造は繊細網状である.核小体は1個から数個青く染まるのが見られる.核は偏在することが多く,なかには核から飛び出しているように観察される細胞もある.細胞質は好塩基性に染まるが,嫌色庭と呼ばれる細胞質の一部に染色の淡い部分が見られるのが特徴である.しかし,形質細胞の核周明庭とは明らかに異なり,核から離れて存在する.また,細胞質には微細なアズール顆粒を認める.
小巨核球/破骨細胞
著者: 荒井智子 , 東克巳
ページ範囲:P.924 - P.924
■形態学的特徴
小巨核球とは,直径が20〜30μmで正常好中球の約2倍程度まで,あるいは前骨髄球程度の大きさをいう(正常巨核球:35〜160μm).このような小巨核球はすでに成熟した巨核球であるが,核分裂が進まないので,小型のままとどまっているものと考えられている.
ハウエル・ジョリー小体
著者: 氏家幸
ページ範囲:P.935 - P.935
■形態学的特徴
赤血球または赤芽球に1個ないし数個存在する直径1〜2μmの小体.細胞分裂の際に,染色体の一部が核の本体に融合せず,細胞質に残存したもの.ライト・ギムザ染色では核濃縮の染色を示し,DNAのフォイルゲン反応陽性.ハウエル・ジョリー小体を有する赤血球は,脾臓でマクロファージに取り込まれ処理されるため,正常人では見られない.
肥満細胞
著者: 東克巳
ページ範囲:P.988 - P.988
■形態学的特徴
肥満細胞は骨髄像観察時に弱拡大でも容易に見つけることのできる細胞である.それは濃紫赤色の顆粒がぎっしり詰まった特徴ある細胞のためである.
細胞の大きさは15〜30μmで,ほとんどが円形あるいは類円形を呈するが,なかには50μmにも及ぶ紡錘形状を見ることもある.核は顆粒に被われているため形やクロマチン構造は見られないが,物理的破壊で顆粒の逸脱した細胞を見ると,核の形は類円形で分葉傾向は見られないようである.
大顆粒リンパ球
著者: 氏家幸
ページ範囲:P.993 - P.993
■形態学的特徴
大型のリンパ球で細胞質は単青色で,核/細胞質比が高い.典型的なリンパ球(10〜12μm)より大きく,ペルオキシダーゼ反応陰性のアズール顆粒を持つ.大というのは,顆粒より細胞が大きいことを意味する.
基本情報
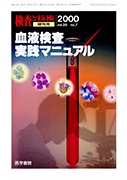
バックナンバー
52巻12号(2024年12月発行)
技術講座 生理
52巻11号(2024年11月発行)
技術講座 生理
52巻10号(2024年10月発行)
技術講座 生理
52巻9号(2024年9月発行)
増大号 臨床医に伝わりやすい 検査報告書とパニック値報告の心得
52巻8号(2024年8月発行)
技術講座 生理
52巻7号(2024年7月発行)
技術講座 生理
52巻6号(2024年6月発行)
技術講座 生理
52巻5号(2024年5月発行)
技術講座 その他
52巻4号(2024年4月発行)
技術講座 生理
52巻3号(2024年3月発行)
増大号 POCUSの決め手。 早く、正確な診断のために
52巻2号(2024年2月発行)
技術講座 生理
52巻1号(2024年1月発行)
技術講座 その他
51巻12号(2023年12月発行)
技術講座 生理
51巻11号(2023年11月発行)
技術講座 生理
51巻10号(2023年10月発行)
技術講座 その他
51巻9号(2023年9月発行)
増大号 匠から学ぶ 血栓止血検査ガイド
51巻8号(2023年8月発行)
技術講座 生理
51巻7号(2023年7月発行)
技術講座 生理
51巻6号(2023年6月発行)
技術講座 生理
51巻5号(2023年5月発行)
技術講座 生理
51巻4号(2023年4月発行)
技術講座 生理
51巻3号(2023年3月発行)
増大号 症例から学ぶ 疾患と検査値の推移
51巻2号(2023年2月発行)
技術講座 その他
51巻1号(2023年1月発行)
技術講座 生理
50巻12号(2022年12月発行)
技術講座 その他
50巻11号(2022年11月発行)
技術講座 生理
50巻10号(2022年10月発行)
技術講座 生理
50巻9号(2022年9月発行)
増大号 希少例と特殊像がわかる! エコーの撮り方完全マスター
50巻8号(2022年8月発行)
技術講座 生理
50巻7号(2022年7月発行)
技術講座 生理
50巻6号(2022年6月発行)
技術講座 生理
50巻5号(2022年5月発行)
技術講座 生理
50巻4号(2022年4月発行)
技術講座 生理
50巻3号(2022年3月発行)
増大号 見て学ぶ 一般検査学アトラス—外観検査から顕微鏡検査まで
50巻2号(2022年2月発行)
技術講座 その他
50巻1号(2022年1月発行)
技術講座 生理
49巻12号(2021年12月発行)
技術講座 生理
49巻11号(2021年11月発行)
技術講座 生理
49巻10号(2021年10月発行)
技術講座 生理
49巻9号(2021年9月発行)
増刊号 病態別 腹部エコーの観察・記録・報告書作成マスター
49巻8号(2021年8月発行)
技術講座 生理
49巻7号(2021年7月発行)
技術講座 生理
49巻6号(2021年6月発行)
技術講座 生理
49巻5号(2021年5月発行)
技術講座 生理
49巻4号(2021年4月発行)
技術講座 一般
49巻3号(2021年3月発行)
増刊号 First&Next Step 微生物検査サポートブック
49巻2号(2021年2月発行)
技術講座 微生物
49巻1号(2021年1月発行)
技術講座 病理・生理
48巻12号(2020年12月発行)
技術講座 その他
48巻11号(2020年11月発行)
技術講座 生化学
48巻10号(2020年10月発行)
技術講座 生理
48巻9号(2020年9月発行)
増刊号 学会発表・論文執筆はもう怖くない! 臨床検査技師のための研究入門
48巻8号(2020年8月発行)
技術講座 遺伝子
48巻7号(2020年7月発行)
技術講座 その他
48巻6号(2020年6月発行)
技術講座 輸血
48巻5号(2020年5月発行)
技術講座 生化学
48巻4号(2020年4月発行)
技術講座 生理
48巻3号(2020年3月発行)
増刊号 採血のすべて—手技から採血室の運用まで徹底解説
48巻2号(2020年2月発行)
技術講座 微生物
48巻1号(2020年1月発行)
技術講座 生理
47巻12号(2019年12月発行)
技術講座 病理
47巻11号(2019年11月発行)
技術講座 生理
47巻10号(2019年10月発行)
技術講座 生理
47巻9号(2019年9月発行)
増刊号 染色画像を比べて学ぶ 体腔液アトラス
47巻8号(2019年8月発行)
技術講座 病理
47巻7号(2019年7月発行)
技術講座 一般
47巻6号(2019年6月発行)
技術講座 血液
47巻5号(2019年5月発行)
技術講座 血液
47巻4号(2019年4月発行)
技術講座 血液
47巻3号(2019年3月発行)
増刊号 エキスパートが教える 心・血管エコー計測のノウハウ
47巻2号(2019年2月発行)
技術講座 病理
47巻1号(2019年1月発行)
技術講座 微生物
46巻12号(2018年12月発行)
技術講座 生理
46巻11号(2018年11月発行)
技術講座 輸血・遺伝子検査
46巻10号(2018年10月発行)
技術講座 その他
46巻9号(2018年9月発行)
増刊号 現場で“パッ”と使える 免疫染色クイックガイド
46巻8号(2018年8月発行)
技術講座 輸血・遺伝子検査
46巻7号(2018年7月発行)
技術講座 生理
46巻6号(2018年6月発行)
技術講座 管理
46巻5号(2018年5月発行)
技術講座 生化学
46巻4号(2018年4月発行)
技術講座 一般
46巻3号(2018年3月発行)
増刊号 感染症クイックリファレンス
46巻2号(2018年2月発行)
技術講座 輸血
46巻1号(2018年1月発行)
技術講座 病理
45巻12号(2017年12月発行)
技術講座 生理
45巻11号(2017年11月発行)
技術講座 一般
45巻10号(2017年10月発行)
技術講座 微生物
45巻9号(2017年9月発行)
増刊号 循環器病院の技師が教える メディカルスタッフのための心電図教室
45巻8号(2017年8月発行)
技術講座 栄養
45巻7号(2017年7月発行)
技術講座 病理
45巻6号(2017年6月発行)
技術講座 病理
45巻5号(2017年5月発行)
技術講座 細胞治療・管理
45巻4号(2017年4月発行)
技術講座 遺伝子・染色体検査
45巻3号(2017年3月発行)
45巻2号(2017年2月発行)
技術講座 細胞治療
45巻1号(2017年1月発行)
技術講座 病理
44巻13号(2016年12月発行)
技術講座 免疫
44巻12号(2016年11月発行)
技術講座 微生物
44巻11号(2016年10月発行)
技術講座 微生物
44巻10号(2016年9月発行)
増刊号 はじめて出会う 検査画像
44巻9号(2016年9月発行)
技術講座 管理・その他
44巻8号(2016年8月発行)
技術講座 微生物
44巻7号(2016年7月発行)
技術講座 生理
44巻6号(2016年6月発行)
技術講座 微生物
44巻5号(2016年5月発行)
技術講座 生理
44巻4号(2016年4月発行)
技術講座 微生物
44巻3号(2016年3月発行)
技術講座 生理
44巻2号(2016年2月発行)
技術講座 微生物
44巻1号(2016年1月発行)
技術講座 微生物
43巻13号(2015年12月発行)
技術講座 生化学
43巻12号(2015年11月発行)
技術講座 生化学
43巻11号(2015年10月発行)
技術講座 一般
43巻10号(2015年9月発行)
増刊号 血液形態アトラス
43巻9号(2015年9月発行)
技術講座 生理
43巻8号(2015年8月発行)
技術講座 生理
43巻7号(2015年7月発行)
技術講座 生理
43巻6号(2015年6月発行)
技術講座 微生物
43巻5号(2015年5月発行)
技術講座 移植医療
43巻4号(2015年4月発行)
技術講座 病理
43巻3号(2015年3月発行)
技術講座 血液
43巻2号(2015年2月発行)
技術講座 管理
43巻1号(2015年1月発行)
技術講座 病理
42巻13号(2014年12月発行)
技術講座 生化学
42巻12号(2014年11月発行)
技術講座 病理
42巻11号(2014年10月発行)
技術講座 血液
42巻10号(2014年9月発行)
増刊号 超音波×病理 対比アトラス
42巻9号(2014年9月発行)
技術講座 生理
42巻8号(2014年8月発行)
技術講座 免疫
42巻7号(2014年7月発行)
技術講座 生理
42巻6号(2014年6月発行)
技術講座 生理
42巻5号(2014年5月発行)
技術講座 病理
42巻4号(2014年4月発行)
技術講座 輸血
42巻3号(2014年3月発行)
技術講座 血液
42巻2号(2014年2月発行)
技術講座 微生物
42巻1号(2014年1月発行)
技術講座 病理
41巻13号(2013年12月発行)
技術講座 生理
41巻12号(2013年11月発行)
技術講座 生化学
41巻11号(2013年10月発行)
技術講座 生化学
41巻10号(2013年9月発行)
増刊号 解剖と正常像がわかる! エコーの撮り方完全マスター
41巻9号(2013年9月発行)
技術講座 微生物
41巻8号(2013年8月発行)
技術講座 生理
41巻7号(2013年7月発行)
技術講座 生理
41巻6号(2013年6月発行)
技術講座 微生物
41巻5号(2013年5月発行)
技術講座 一般
41巻4号(2013年4月発行)
技術講座 生化学
41巻3号(2013年3月発行)
技術講座 生理
41巻2号(2013年2月発行)
技術講座 生理
41巻1号(2013年1月発行)
技術講座 生理
40巻13号(2012年12月発行)
技術講座 血液
40巻12号(2012年11月発行)
技術講座 生理
40巻11号(2012年10月発行)
技術講座 生理
40巻10号(2012年9月発行)
増刊号 この検査データを読めますか?―検査値から病態を探る
40巻9号(2012年9月発行)
技術講座 生理
40巻8号(2012年8月発行)
技術講座 細胞診
40巻7号(2012年7月発行)
技術講座 生理
40巻6号(2012年6月発行)
技術講座 生理
40巻5号(2012年5月発行)
技術講座 生理
40巻4号(2012年4月発行)
技術講座 血液
40巻3号(2012年3月発行)
技術講座 生理
40巻2号(2012年2月発行)
技術講座 輸血
40巻1号(2012年1月発行)
技術講座 遺伝子
39巻13号(2011年12月発行)
疾患と検査値の推移
39巻12号(2011年11月発行)
疾患と検査値の推移
39巻11号(2011年10月発行)
疾患と検査値の推移
39巻10号(2011年9月発行)
増刊号 緊急報告すべき検査結果のすべて―すぐに使えるパニック値事典
39巻9号(2011年9月発行)
疾患と検査値の推移
39巻8号(2011年8月発行)
疾患と検査値の推移
39巻7号(2011年7月発行)
疾患と検査値の推移
39巻6号(2011年6月発行)
技術講座 生理
39巻5号(2011年5月発行)
技術講座 生理
39巻4号(2011年4月発行)
疾患と検査値の推移
39巻3号(2011年3月発行)
疾患と検査値の推移
39巻2号(2011年2月発行)
疾患と検査値の推移
39巻1号(2011年1月発行)
疾患と検査値の推移
38巻13号(2010年12月発行)
疾患と検査値の推移
38巻12号(2010年11月発行)
疾患と検査値の推移
38巻11号(2010年10月発行)
疾患と検査値の推移
38巻10号(2010年9月発行)
増刊号 免疫反応と臨床検査2010
38巻9号(2010年9月発行)
疾患と検査値の推移
38巻8号(2010年8月発行)
疾患と検査値の推移
38巻7号(2010年7月発行)
疾患と検査値の推移
38巻6号(2010年6月発行)
疾患と検査値の推移
38巻5号(2010年5月発行)
疾患と検査値の推移
38巻4号(2010年4月発行)
疾患と検査値の推移
38巻3号(2010年3月発行)
疾患と検査値の推移
38巻2号(2010年2月発行)
疾患と検査値の推移
38巻1号(2010年1月発行)
疾患と検査値の推移
37巻13号(2009年12月発行)
疾患と検査値の推移
37巻12号(2009年11月発行)
疾患と検査値の推移
37巻11号(2009年10月発行)
疾患と検査値の推移
37巻10号(2009年9月発行)
増刊号 顕微鏡検査のコツ―臨床に役立つ形態学
37巻9号(2009年9月発行)
疾患と検査値の推移
37巻8号(2009年8月発行)
疾患と検査値の推移
37巻7号(2009年7月発行)
疾患と検査値の推移
37巻6号(2009年6月発行)
疾患と検査値の推移
37巻5号(2009年5月発行)
疾患と検査値の推移
37巻4号(2009年4月発行)
疾患と検査値の推移
37巻3号(2009年3月発行)
疾患と検査値の推移
37巻2号(2009年2月発行)
疾患と検査値の推移
37巻1号(2009年1月発行)
疾患と検査値の推移
36巻13号(2008年12月発行)
疾患と検査値の推移
36巻12号(2008年11月発行)
疾患と検査値の推移
36巻11号(2008年10月発行)
疾患と検査値の推移
36巻10号(2008年9月発行)
増刊号 これから広がる生理検査・新たにはじまる生理検査
36巻9号(2008年9月発行)
疾患と検査値の推移
36巻8号(2008年8月発行)
疾患と検査値の推移
36巻7号(2008年7月発行)
疾患と検査値の推移
36巻6号(2008年6月発行)
疾患と検査値の推移
36巻5号(2008年5月発行)
疾患と検査値の推移
36巻4号(2008年4月発行)
疾患と検査値の推移
36巻3号(2008年3月発行)
疾患と検査値の推移
36巻2号(2008年2月発行)
疾患と検査値の推移
36巻1号(2008年1月発行)
疾患と検査値の推移
35巻13号(2007年12月発行)
疾患と検査値の推移
35巻12号(2007年11月発行)
疾患と検査値の推移
35巻11号(2007年10月発行)
増刊号 メタボリックシンドローム健診検査技術マニュアル
35巻10号(2007年10月発行)
疾患と検査値の推移
35巻9号(2007年9月発行)
疾患と検査値の推移
35巻8号(2007年8月発行)
疾患と検査値の推移
35巻7号(2007年7月発行)
疾患と検査値の推移
35巻6号(2007年6月発行)
疾患と検査値の推移
35巻5号(2007年5月発行)
疾患と検査値の推移
35巻4号(2007年4月発行)
疾患と検査値の推移
35巻3号(2007年3月発行)
疾患と検査値の推移
35巻2号(2007年2月発行)
疾患と検査値の推移
35巻1号(2007年1月発行)
疾患と検査値の推移
34巻13号(2006年12月発行)
技術講座 生理
34巻12号(2006年11月発行)
技術講座 一般
34巻11号(2006年10月発行)
増刊号 新しい臨床検査・未来の臨床検査
34巻10号(2006年10月発行)
疾患と検査値の推移
34巻9号(2006年9月発行)
疾患と検査値の推移
34巻8号(2006年8月発行)
疾患と検査値の推移
34巻7号(2006年7月発行)
疾患と検査値の推移
34巻6号(2006年6月発行)
疾患と検査値の推移
34巻5号(2006年5月発行)
疾患と検査値の推移
34巻4号(2006年4月発行)
疾患と検査値の推移
34巻3号(2006年3月発行)
疾患と検査値の推移
34巻2号(2006年2月発行)
疾患と検査値の推移
34巻1号(2006年1月発行)
疾患と検査値の推移
33巻13号(2005年12月発行)
疾患と検査値の推移
33巻12号(2005年11月発行)
疾患と検査値の推移
33巻11号(2005年10月発行)
増刊号 一線診療のための臨床検査
33巻10号(2005年10月発行)
疾患と検査値の推移
33巻9号(2005年9月発行)
疾患と検査値の推移
33巻8号(2005年8月発行)
疾患と検査値の推移
33巻7号(2005年7月発行)
疾患と検査値の推移
33巻6号(2005年6月発行)
疾患と検査値の推移
33巻5号(2005年5月発行)
疾患と検査値の推移
33巻4号(2005年4月発行)
疾患と検査値の推移
33巻3号(2005年3月発行)
疾患と検査値の推移
33巻2号(2005年2月発行)
疾患と検査値の推移
33巻1号(2005年1月発行)
疾患と検査値の推移
32巻13号(2004年12月発行)
技術講座 血液
32巻12号(2004年11月発行)
技術講座 病理
32巻11号(2004年10月発行)
技術講座 血液
32巻10号(2004年9月発行)
増刊号 細胞像の見かた―病理・血液・尿沈渣
32巻9号(2004年9月発行)
技術講座 生化学
32巻8号(2004年8月発行)
技術講座 免疫
32巻7号(2004年7月発行)
技術講座 微生物
32巻6号(2004年6月発行)
技術講座 病理
32巻5号(2004年5月発行)
技術講座 病理
32巻4号(2004年4月発行)
技術講座 病理
32巻3号(2004年3月発行)
技術講座 微生物
32巻2号(2004年2月発行)
技術講座 生化学
32巻1号(2004年1月発行)
技術講座 微生物
31巻13号(2003年12月発行)
技術講座 微生物
31巻12号(2003年11月発行)
技術講座 病理
31巻11号(2003年10月発行)
技術講座 微生物
31巻10号(2003年9月発行)
増刊号 包括医療と臨床検査
31巻9号(2003年9月発行)
技術講座 一般
31巻8号(2003年8月発行)
技術講座 微生物
31巻7号(2003年7月発行)
技術講座 病理
31巻6号(2003年6月発行)
技術講座 免疫
31巻5号(2003年5月発行)
技術講座 一般
31巻4号(2003年4月発行)
技術講座 病理
31巻3号(2003年3月発行)
技術講座 生化学
31巻2号(2003年2月発行)
技術講座 免疫
31巻1号(2003年1月発行)
技術講座 免疫
30巻13号(2002年12月発行)
技術講座 生理
30巻12号(2002年11月発行)
技術講座 生理
30巻11号(2002年10月発行)
技術講座 生化学
30巻10号(2002年9月発行)
増刊号 誰でもわかる遺伝子検査
30巻9号(2002年9月発行)
技術講座 微生物
30巻8号(2002年8月発行)
技術講座 生化学
30巻7号(2002年7月発行)
技術講座 微生物
30巻6号(2002年6月発行)
技術講座 生化学
30巻5号(2002年5月発行)
技術講座 微生物
30巻4号(2002年4月発行)
技術講座 一般
30巻3号(2002年3月発行)
技術講座 生化学
30巻2号(2002年2月発行)
技術講座 一般
30巻1号(2002年1月発行)
技術講座 免疫
29巻13号(2001年12月発行)
技術講座 病理
29巻12号(2001年11月発行)
技術講座 生理
29巻11号(2001年10月発行)
技術講座 病理
29巻10号(2001年9月発行)
技術講座 病理
29巻9号(2001年8月発行)
技術講座 病理
29巻8号(2001年7月発行)
技術講座 生理
29巻7号(2001年6月発行)
増刊号 病理組織・細胞診のための日常染色法ガイダンス
29巻6号(2001年6月発行)
技術講座 微生物
29巻5号(2001年5月発行)
技術講座 生理
29巻4号(2001年4月発行)
技術講座 病理
29巻3号(2001年3月発行)
技術講座 微生物
29巻2号(2001年2月発行)
技術講座 微生物
29巻1号(2001年1月発行)
技術講座 一般
28巻13号(2000年12月発行)
技術講座 病理
28巻12号(2000年11月発行)
技術講座 病理
28巻11号(2000年10月発行)
技術講座 免疫
28巻10号(2000年9月発行)
技術講座 微生物
28巻9号(2000年8月発行)
技術講座 微生物
28巻8号(2000年7月発行)
技術講座 生理
28巻7号(2000年6月発行)
増刊号 血液検査実践マニュアル
28巻6号(2000年6月発行)
技術講座 免疫
28巻5号(2000年5月発行)
技術講座 血液
28巻4号(2000年4月発行)
技術講座 一般
28巻3号(2000年3月発行)
技術講座 生理
28巻2号(2000年2月発行)
技術講座 生化学
28巻1号(2000年1月発行)
技術講座 一般
27巻13号(1999年12月発行)
技術講座 病理
27巻12号(1999年11月発行)
技術講座 一般
27巻11号(1999年10月発行)
技術講座 生化学
27巻10号(1999年9月発行)
技術講座 免疫
27巻9号(1999年8月発行)
技術講座 病理
27巻8号(1999年7月発行)
技術講座 病理
27巻7号(1999年6月発行)
増刊号 緊急検査実践マニュアル
27巻6号(1999年6月発行)
技術講座 生化学
27巻5号(1999年5月発行)
技術講座 血液
27巻4号(1999年4月発行)
技術講座 一般
27巻3号(1999年3月発行)
技術講座 生理
27巻2号(1999年2月発行)
技術講座 微生物
27巻1号(1999年1月発行)
技術講座 生理
26巻13号(1998年12月発行)
技術講座 一般
26巻12号(1998年11月発行)
技術講座 病理
26巻11号(1998年10月発行)
技術講座 病理
26巻10号(1998年9月発行)
技術講座 生理
26巻9号(1998年8月発行)
技術講座 生理
26巻8号(1998年7月発行)
技術講座 生理
26巻7号(1998年6月発行)
増刊号 病理組織・細胞診実践マニュアル
26巻6号(1998年6月発行)
技術講座 病理
26巻5号(1998年5月発行)
技術講座 一般
26巻4号(1998年4月発行)
技術講座 病理
26巻3号(1998年3月発行)
技術講座 一般
26巻2号(1998年2月発行)
技術講座 生理
26巻1号(1998年1月発行)
技術講座 血液
25巻13号(1997年12月発行)
技術講座 一般
25巻12号(1997年11月発行)
技術講座 一般
25巻11号(1997年10月発行)
技術講座 生理
25巻10号(1997年9月発行)
技術講座 血液
25巻9号(1997年8月発行)
技術講座 一般
25巻8号(1997年7月発行)
技術講座 一般
25巻7号(1997年6月発行)
増刊号 輸血検査実践マニュアル
25巻6号(1997年6月発行)
技術講座 免疫
25巻5号(1997年5月発行)
技術講座 生理
25巻4号(1997年4月発行)
技術講座 生理
25巻3号(1997年3月発行)
技術講座 微生物
25巻2号(1997年2月発行)
技術講座 生理
25巻1号(1997年1月発行)
技術講座 一般
24巻13号(1996年12月発行)
技術講座 生理
24巻12号(1996年11月発行)
技術講座 一般
24巻11号(1996年10月発行)
技術講座 生理
24巻10号(1996年9月発行)
技術講座 管理
24巻9号(1996年8月発行)
技術講座 生理
24巻8号(1996年7月発行)
技術講座 生理
24巻7号(1996年6月発行)
増刊号 感染症検査実践マニュアル
24巻6号(1996年6月発行)
技術講座 病理
24巻5号(1996年5月発行)
技術講座 生理
24巻4号(1996年4月発行)
技術講座 生理
24巻3号(1996年3月発行)
技術講座 生理
24巻2号(1996年2月発行)
技術講座 生理
24巻1号(1996年1月発行)
技術講座 一般
23巻13号(1995年12月発行)
技術講座 生理
23巻12号(1995年11月発行)
技術講座 病理
23巻11号(1995年10月発行)
技術講座 微生物
23巻10号(1995年9月発行)
技術講座 生理
23巻9号(1995年8月発行)
技術講座 一般
23巻8号(1995年7月発行)
技術講座 免疫
23巻7号(1995年6月発行)
技術講座 生理
23巻6号(1995年5月発行)
技術講座 一般
23巻5号(1995年4月発行)
増刊号 臨床生理検査実践マニュアル画像検査を中心として
23巻4号(1995年4月発行)
技術講座 病理
23巻3号(1995年3月発行)
技術講座 病理
23巻2号(1995年2月発行)
技術講座 一般
23巻1号(1995年1月発行)
技術講座 生理
22巻13号(1994年12月発行)
技術講座 一般
22巻12号(1994年11月発行)
技術講座 一般
22巻11号(1994年10月発行)
技術講座 一般
22巻10号(1994年9月発行)
技術講座 一般
22巻9号(1994年8月発行)
技術講座 生理
22巻8号(1994年7月発行)
技術講座 病理
22巻7号(1994年6月発行)
技術講座 一般
22巻6号(1994年5月発行)
技術講座 一般
22巻5号(1994年4月発行)
増刊号 免疫検査実践マニュアル
22巻4号(1994年4月発行)
技術講座 生理
22巻3号(1994年3月発行)
技術講座 免疫
22巻2号(1994年2月発行)
技術講座 一般
22巻1号(1994年1月発行)
技術講座 生理
21巻13号(1993年12月発行)
技術講座 一般
21巻12号(1993年11月発行)
技術講座 一般
21巻11号(1993年10月発行)
技術講座 一般
21巻10号(1993年9月発行)
技術講座 生理
21巻9号(1993年8月発行)
技術講座 一般
21巻8号(1993年7月発行)
技術講座 病理
21巻7号(1993年6月発行)
技術講座 一般
21巻6号(1993年5月発行)
技術講座 生理
21巻5号(1993年4月発行)
増刊号 臨床化学実践マニュアル
21巻4号(1993年4月発行)
技術講座 生理
21巻3号(1993年3月発行)
技術講座 病理
21巻2号(1993年2月発行)
技術講座 生理
21巻1号(1993年1月発行)
技術講座 生理
20巻13号(1992年12月発行)
技術講座 一般
20巻12号(1992年11月発行)
技術講座 一般
20巻11号(1992年10月発行)
技術講座 一般
20巻10号(1992年9月発行)
技術講座 一般
20巻9号(1992年8月発行)
技術講座 一般
20巻8号(1992年7月発行)
技術講座 血液
20巻7号(1992年6月発行)
技術講座 一般
20巻6号(1992年5月発行)
増刊号 尿検査法
20巻5号(1992年5月発行)
技術講座 生理
20巻4号(1992年4月発行)
技術講座 生理
20巻3号(1992年3月発行)
技術講座 病理
20巻2号(1992年2月発行)
技術講座 一般
20巻1号(1992年1月発行)
技術講座 生理
19巻13号(1991年12月発行)
技術講座 管理
19巻12号(1991年11月発行)
技術講座 生理
19巻11号(1991年10月発行)
技術講座 生理
19巻10号(1991年9月発行)
技術講座 一般
19巻9号(1991年8月発行)
技術講座 一般
19巻8号(1991年7月発行)
技術講座 生理
19巻7号(1991年6月発行)
増刊号 臨床血液検査
19巻6号(1991年6月発行)
技術講座 生理
19巻5号(1991年5月発行)
技術講座 生理
19巻4号(1991年4月発行)
技術講座 一般
19巻3号(1991年3月発行)
技術講座 生理
19巻2号(1991年2月発行)
技術講座 生理
19巻1号(1991年1月発行)
技術講座 一般
18巻13号(1990年12月発行)
技術講座 生理
18巻12号(1990年11月発行)
技術講座 微生物
18巻11号(1990年10月発行)
技術講座 生理
18巻10号(1990年9月発行)
技術講座 一般
18巻9号(1990年8月発行)
技術講座 一般
18巻8号(1990年7月発行)
技術講座 一般
18巻7号(1990年6月発行)
技術講座 一般
18巻6号(1990年5月発行)
増刊号 血液・尿以外の体液検査法
18巻5号(1990年5月発行)
技術講座 一般
18巻4号(1990年4月発行)
技術講座 一般
18巻3号(1990年3月発行)
技術講座 血液
18巻2号(1990年2月発行)
技術講座 生理
18巻1号(1990年1月発行)
技術講座 生理
17巻13号(1989年12月発行)
技術講座 一般
17巻12号(1989年11月発行)
技術講座 一般
17巻11号(1989年10月発行)
技術講座 一般
17巻10号(1989年9月発行)
技術講座 一般
17巻9号(1989年8月発行)
技術講座 生理
17巻8号(1989年7月発行)
技術講座 血清
17巻7号(1989年6月発行)
技術講座 一般
17巻6号(1989年5月発行)
感染症の検査法 Ⅲ 検査法各論
17巻5号(1989年5月発行)
技術講座 一般
17巻4号(1989年4月発行)
技術講座 生理
17巻3号(1989年3月発行)
技術講座 病理
17巻2号(1989年2月発行)
技術講座 一般
17巻1号(1989年1月発行)
技術講座 生理
16巻13号(1988年12月発行)
技術講座 一般
16巻12号(1988年11月発行)
技術講座 一般
16巻11号(1988年10月発行)
技術講座 一般
16巻10号(1988年9月発行)
技術講座 生理
16巻9号(1988年8月発行)
技術講座 一般
16巻8号(1988年7月発行)
技術講座 一般
16巻7号(1988年6月発行)
免疫化学検査法 資料
16巻6号(1988年6月発行)
技術講座 一般
16巻5号(1988年5月発行)
技術講座 一般
16巻4号(1988年4月発行)
技術講座 病理
16巻3号(1988年3月発行)
技術講座 生理
16巻2号(1988年2月発行)
技術講座 一般
16巻1号(1988年1月発行)
技術講座 血液
15巻13号(1987年12月発行)
技術講座 一般
15巻12号(1987年11月発行)
技術講座 病理
15巻11号(1987年10月発行)
技術講座 細胞診
15巻10号(1987年9月発行)
技術講座 一般
15巻9号(1987年8月発行)
技術講座 細胞診
15巻8号(1987年7月発行)
技術講座 病理
15巻7号(1987年6月発行)
技術講座 病理
15巻6号(1987年5月発行)
技術講座 病理
15巻5号(1987年4月発行)
臨床生理検査と技術 座談会
15巻4号(1987年4月発行)
技術講座 生理
15巻3号(1987年3月発行)
技術講座 血液
15巻2号(1987年2月発行)
技術講座 一般
15巻1号(1987年1月発行)
技術講座 病理
14巻13号(1986年12月発行)
技術講座 一般
14巻12号(1986年11月発行)
技術講座 病理
14巻11号(1986年10月発行)
技術講座 血清
14巻10号(1986年9月発行)
技術講座 血清
14巻9号(1986年8月発行)
技術講座 生理
14巻8号(1986年7月発行)
技術講座 血清
14巻7号(1986年6月発行)
技術講座 病理
14巻6号(1986年5月発行)
技術講座 生理
14巻5号(1986年4月発行)
形態学的検査と技術 血液と病理
14巻4号(1986年4月発行)
技術講座 病理
14巻3号(1986年3月発行)
技術講座 細菌
14巻2号(1986年2月発行)
技術講座 病理
14巻1号(1986年1月発行)
技術講座 細菌
13巻12号(1985年12月発行)
技術講座 病理
13巻11号(1985年11月発行)
技術講座 病理
13巻10号(1985年10月発行)
技術講座 生理
13巻9号(1985年9月発行)
技術講座 病理
13巻8号(1985年8月発行)
技術講座 病理
13巻7号(1985年7月発行)
技術講座 血液
13巻6号(1985年6月発行)
技術講座 一般
13巻5号(1985年5月発行)
技術講座 病理
13巻4号(1985年4月発行)
技術講座 一般
13巻3号(1985年3月発行)
技術講座 血液
13巻2号(1985年2月発行)
技術講座 一般
13巻1号(1985年1月発行)
技術講座 血液
12巻12号(1984年12月発行)
技術講座 血液
12巻11号(1984年11月発行)
技術講座 病理
12巻10号(1984年10月発行)
技術講座 輸血
12巻9号(1984年9月発行)
技術講座 一般
12巻8号(1984年8月発行)
技術講座 細菌
12巻7号(1984年7月発行)
技術講座 細菌
12巻6号(1984年6月発行)
技術講座 生理
12巻5号(1984年5月発行)
技術講座 一般
12巻4号(1984年4月発行)
技術講座 病理
12巻3号(1984年3月発行)
技術講座 血液
12巻2号(1984年2月発行)
技術講座 一般
12巻1号(1983年12月発行)
技術講座 血清
11巻12号(1983年12月発行)
技術講座 一般
11巻11号(1983年11月発行)
技術講座 細菌
11巻10号(1983年10月発行)
技術講座 細胞診
11巻9号(1983年9月発行)
技術講座 一般
11巻8号(1983年8月発行)
技術講座 血清
11巻7号(1983年7月発行)
技術講座 細菌
11巻6号(1983年6月発行)
技術講座 一般
11巻5号(1983年5月発行)
技術講座 病理
11巻4号(1983年4月発行)
技術講座 一般
11巻3号(1983年3月発行)
技術講座 血液
11巻2号(1983年2月発行)
技術講座 一般
11巻1号(1983年1月発行)
技術講座 血液
10巻12号(1982年12月発行)
技術講座 一般
10巻11号(1982年11月発行)
技術講座 生理
10巻10号(1982年10月発行)
技術講座 血清
10巻9号(1982年9月発行)
技術講座 細菌
10巻8号(1982年8月発行)
技術講座 一般
10巻7号(1982年7月発行)
技術講座 病理
10巻6号(1982年6月発行)
技術講座 細菌
10巻5号(1982年5月発行)
技術講座 病理
10巻4号(1982年4月発行)
技術講座 血清
10巻3号(1982年3月発行)
技術講座 生化学
10巻2号(1982年2月発行)
技術講座 病理
10巻1号(1982年1月発行)
技術講座 生化学
9巻12号(1981年12月発行)
技術講座 細菌
9巻11号(1981年11月発行)
技術講座 生理
9巻10号(1981年10月発行)
技術講座 一般
9巻9号(1981年9月発行)
技術講座 血清
9巻8号(1981年8月発行)
技術講座 血清
9巻7号(1981年7月発行)
技術講座 生理
9巻6号(1981年6月発行)
技術講座 細菌
9巻5号(1981年5月発行)
技術講座 一般
9巻4号(1981年4月発行)
技術講座 一般
9巻3号(1981年3月発行)
技術講座 血清
9巻2号(1981年2月発行)
技術講座 一般
9巻1号(1981年1月発行)
技術講座 生化学
8巻12号(1980年12月発行)
技術講座 一般
8巻11号(1980年11月発行)
技術講座 生理
8巻10号(1980年10月発行)
技術講座 検体の取り扱いと保存
8巻9号(1980年9月発行)
技術講座 病理
8巻8号(1980年8月発行)
技術講座 生化学
8巻7号(1980年7月発行)
技術講座 一般
8巻6号(1980年6月発行)
技術講座 生理
8巻5号(1980年5月発行)
技術講座 生化学
8巻4号(1980年4月発行)
技術講座 血清
8巻3号(1980年3月発行)
技術講座 病理
8巻2号(1980年2月発行)
技術講座 一般
8巻1号(1980年1月発行)
技術講座 生化学
7巻12号(1979年12月発行)
技術講座 一般
7巻11号(1979年11月発行)
技術講座 一般
7巻10号(1979年10月発行)
技術講座 細菌
7巻9号(1979年9月発行)
技術講座 生理
7巻8号(1979年8月発行)
技術講座 病理
7巻7号(1979年7月発行)
技術講座 生理
7巻6号(1979年6月発行)
技術講座 一般
7巻5号(1979年5月発行)
技術講座 血液
7巻4号(1979年4月発行)
技術講座 生理
7巻3号(1979年3月発行)
技術講座 病理
7巻2号(1979年2月発行)
技術講座 細菌
7巻1号(1979年1月発行)
技術講座 生化学
6巻12号(1978年12月発行)
技術講座 細菌
6巻11号(1978年11月発行)
技術講座 病理
6巻10号(1978年10月発行)
技術講座 血清
6巻9号(1978年9月発行)
技術講座 細菌
6巻8号(1978年8月発行)
技術講座 生化学
6巻7号(1978年7月発行)
技術講座 一般
6巻6号(1978年6月発行)
技術講座 病理
6巻5号(1978年5月発行)
技術講座 生理
6巻4号(1978年4月発行)
技術講座 一般
6巻3号(1978年3月発行)
技術講座 病理
6巻2号(1978年2月発行)
技術講座 一般
6巻1号(1978年1月発行)
技術講座 病理
5巻12号(1977年12月発行)
技術講座 生理
5巻11号(1977年11月発行)
技術講座 一般
5巻10号(1977年10月発行)
技術講座 細菌付録
5巻9号(1977年9月発行)
技術講座 一般
5巻8号(1977年8月発行)
技術講座 生理
5巻7号(1977年7月発行)
技術講座 一般
5巻6号(1977年6月発行)
技術講座 一般
5巻5号(1977年5月発行)
技術講座 一般
5巻4号(1977年4月発行)
技術講座 一般
5巻3号(1977年3月発行)
技術講座 一般
5巻2号(1977年2月発行)
技術講座 一般
5巻1号(1977年1月発行)
技術講座 一般
4巻12号(1976年12月発行)
技術講座 一般
4巻11号(1976年11月発行)
技術講座 一般
4巻10号(1976年10月発行)
技術講座 一般
4巻9号(1976年9月発行)
技術講座 一般
4巻8号(1976年8月発行)
技術講座 一般
4巻7号(1976年7月発行)
技術講座 一般
4巻6号(1976年6月発行)
技術講座 一般
4巻5号(1976年5月発行)
技術講座 一般
4巻4号(1976年4月発行)
技術講座 一般
4巻3号(1976年3月発行)
技術講座 一般
4巻2号(1976年2月発行)
技術講座 一般
4巻1号(1976年1月発行)
技術講座 一般
3巻12号(1975年12月発行)
技術講座 一般
3巻11号(1975年11月発行)
技術講座 一般
3巻10号(1975年10月発行)
技術講座 一般
3巻9号(1975年9月発行)
技術講座 一般
3巻7号(1975年8月発行)
特集 必修 日常検査の実技
3巻6号(1975年6月発行)
技術講座 生理
3巻5号(1975年5月発行)
技術講座 一般
3巻4号(1975年4月発行)
技術講座 一般
3巻3号(1975年3月発行)
技術講座 一般
3巻2号(1975年2月発行)
技術講座 一般
3巻1号(1975年1月発行)
技術講座 一般
