新しい知見
クロイツフェルト・ヤコブ病(Creutzfeldt-Jakob disease;CJD)は100万人に1人の割合で孤発性に発生し,脳組織の海綿(スポンジ)状変性を特徴とする疾患である.近年,伝達性がクローズアップされ社会的に認知された.CJDは1920年代初頭,ドイツの神経病理学者CreutzfeldtとJakobによって別々に記述された.現在ではその成因から,プリオン(prion)病,ないし病理所見から伝達性海綿状脳症(transmissible spongiform encephaolopathy;TSE)として哺乳類の神経疾患群にひとくくりにされている.
雑誌目次
検査と技術31巻5号
2003年05月発行
雑誌目次
病気のはなし
クロイツフェルト・ヤコブ病
著者: 高橋秀宗 , 佐多徹太郎
ページ範囲:P.392 - P.396
技術講座 輸血
血液製剤の取り扱い法
著者: 深井寛治 , 山本定光 , 池田久實
ページ範囲:P.397 - P.401
新しい知見
血液新法
2002年7月31日公布された平成14年法律第96号で薬事法及び採血及び供血あっせん業取締法の一部を改正する法律をいう.この法律は,医療機器に関する規制の見直しや生物由来製品の特性に着目した安全確保のための措置を講ずるとともに,医薬品,医療機器などの承認・許可制度の再構築を行い,あわせて安全な血液製剤の計画的な供給の確保などを図るために改正された.特に採血及び供血あっせん業取締法は,その名称を安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律として変更され,血液製剤の国内自給にかかわる基本理念として,血液製剤について安全性の向上,国内自給の原則および安定供給,適正使用ならびに施策に関する公正の確保および透明性の向上を規定することとして定められた.
免疫
クリオグロブリンの測定
著者: 岡崎登志夫 , 長井辰男
ページ範囲:P.403 - P.406
新しい知見
1990年代初頭,クリオグロブリン血症がC型肝炎に合併することが報告されて以来,クリオグロブリン測定が再び注目されるようになった.しかし,C型肝炎合併クリオグロブリンは少量で,従来の冷却沈殿法では見逃しやすく,同定のための精製も困難であった.冷却ゲル内拡散法は,クリオグロブリン凝集塊を寒天ゲル内に沈降リングとして捕獲できるため,視覚的にとらえやすい.また,精製も比較的容易で確実に実施でき,構成成分解析に有効である.今後,C型肝炎合併クリオグロブリンの構成成分を明らかにし,生成メカニズムを解明するために威力を発揮するものと期待される.
一般
尿沈渣に必要な不明物質の鑑別法
著者: 坂牛省二
ページ範囲:P.409 - P.415
新しい知見
無晶性塩類(リン酸塩,尿酸塩)やシュウ酸カルシウム結晶および薬物結晶を封入した塩類・結晶円柱の尿沈への出現は,尿細管腔内での結晶化や尿細管腔の閉塞が考えられ,尿細管障害の1つの指標となる.また,腎尿路の結石症との関連においても重要な沈成分である.JCCLS尿沈検査法1)(GP1-P3)ではそのほかの円柱に分類されているが判別にも特殊な方法を必要とせず積極的に報告されるべきである.塩類・結晶円柱は,時に幅の広い円柱となって尿細管腔を拡張させ,円柱の内外に線維状や円形・類円形の特殊型尿細管上皮細胞を伴うことがある.
オピニオン
臨床検査部の創造的構造改革
著者: 赤星透
ページ範囲:P.402 - P.402
急激な少子・高齢化の進行と国民医療費の高騰は,わが国の医療制度に抜本的な改革を迫り,医療を取り巻く環境は日に日に厳しさを増しています.検体検査を中心とした診療報酬の度重なる改定により,ブランチラボの院内導入や臨床検査部のFMS(facility managed system)化などによる検査のアウトソーシング化が進みつつあります.さらに,大学病院では,2003年4月から包括医療制度が導入され,卒後研修の必修化の日程も迫っており,大学病院臨床検査部にとってもまったく先を読むことができない状況です.まさに,暗夜航路を漂う船といったところです.
私どもの北里大学病院は,1971年の開院当初から院内に検査会社のラボを併設し,院内における生化学検査や免疫学検査を委託してきました.院内の臨床検査部による検査が当然であった当時としては,全国的にもユニークな病院であったと思われます.今からみれば時代を先取りしていたといえるかもしれません.この30年間,大学病院臨床検査部とブランチラボは院内で上手く棲み分けながら,検査業務を分担し,共存し合ってきました.しかし,医療環境の変化を受け,2000年には検体検査全体のブランチ化案が提示され,論議の末に私どもはブランチラボの院内取り込みという,時流とは逆の選択をしました.これは,ブランチラボの業務を院内に取り込み実施するが検査部の人員は増やさず,むしろ合理化と効率化により検体検査部門から生理検査部門に人員をシフトさせるというものでした.2002年8月には試薬リース方式の新しい検査室(免疫化学検査室)が稼動を開始し,また生理検査部門には5人の技師をシフトさせました.この改革により検体検査の迅速性が高まり,かつ生理検査の待ち時間短縮と新規検査の導入などにより臨床サイドからは高い評価を得ています.また,検査経費の削減による経済効果も予測どおりに生じています.
絵で見る免疫学 基礎編 41
血液型抗原(4)―Lewis式血液型
著者: 高木淳 , 玉井一
ページ範囲:P.426 - P.427
体液中の血液型物質
血漿,唾液,そのほかの体液中にABH式血液型物質を分泌している人と分泌していない人がいる.前者を分泌型,後者を非分泌型と呼ぶ.分泌型の人の体液中にはABO型式血液型に一致した型物質,すなわち O 型は H 物質,A 型は A と H,B型はBとH,AB型はA,BおよびH物質を分泌している.したがって,非分泌型の人の体液中の血液型物質にはABH血液型物質は存在しない.分泌型および非分泌型抗原は分泌遺伝子(Se)によって調節されている.Seは対立遺伝子seに対して優勢で,分泌型の遺伝子型はSeSeまたはSeseであり非分泌型の遺伝子型はseseである.赤血球膜上に存在するABH型物質は,血球とともに骨髄で作られて赤血球膜の一部を構成している.体液中のABH式血液型物質は各々の分泌腺で作られて体液中に分泌される.体液中のABH型物質は,胃液,唾液,胆汁,精液などに多く,汗,涙,尿,血漿中には少ない.
Lewis 抗原
Lewis抗原は,血漿中に存在する型前駆物質のN-アセチルグルコサミン(GlcNAc)の4位にフコースを添加する酵素をコードしている遺伝子(Le)によって調節されている.Leは対立遺伝子leに対して優勢である.このフコース(Fuc)は,赤血球膜状の型鎖に付加されることはない.なぜならば,GlcNAcの4位の炭素がガラクトース(Gal)によって占められているからである.赤血球膜上にLewis抗原が存在するのは,血漿中のLewis抗原が赤血球膜に吸着されたためである(図1).
ラボクイズ
尿沈渣 3
著者: 伊瀬恵子
ページ範囲:P.428 - P.428
症例:55 歳,男性.検診で尿糖を指摘され外来を受診.2型糖尿病と診断されたが予後が悪く,眼科にて糖尿病性網膜症と診断されている患者の尿沈である.表に外来受診時の検査所見を示した.
問題1 図1a,bの矢印で示した尿中成分で正しいのはどれか.
① 硝子円柱
② 上皮円柱
③ 顆粒円柱
④ 空胞円柱
⑤ 尿細管上皮細胞
4月号の解答と解説
著者: 大家辰彦 , 犀川哲典
ページ範囲:P.429 - P.429
【問題1】 解答:④ WPW症候群(Wolff-Parkinson-White syndrome)
解説:本症例の心電図はQRS波形の前にP波が先行しPQ間隔は80msecと短縮している.またデルタ波によるQRS幅の延長が認められる典型的なB型WPW症候群である.この心電図変化は洞調律時,心室が正常の房室伝導路を介する興奮と副伝導路を介する興奮による融合収縮をなすためである.副伝導路の伝導速度が速いため,これを介する心室筋の早期興奮が心電図上PQ間隔の短縮とデルタ波を形成する.脚ブロックおよび心室内伝導障害でもQRS幅は延長するが房室結節内伝導は正常であるためPQ間隔は短縮しない.心室補充調律ではQRS波形にP波が先行しない.
【問題2】 解答:(2) 発作性上室性頻拍症
解説:図2の心電図は幅が狭いQRS波でR-R間隔が整の頻脈であり,QRS波に先行するP波は認められない(↓に逆行性陰性P波が観察される).このような心電図を呈する頻脈を発作性上室性頻拍症と呼ぶ.心室頻拍はQRS幅が広く房室解離となるためP波とQRS波とが1:1対応をしない.心房細動は頻脈の場合でもR-R間隔が不規則となる.洞性頻脈はQRS波の前にP波が観察される.心房粗動の2:1伝導時はR-R間隔が整となるがF波が観察される.
私の必要な検査/要らない検査
内分泌検査 2.性腺機能検査―臨床医の立場から
著者: 久保田俊郎
ページ範囲:P.435 - P.439
はじめに
性腺は,視床下部,下垂体前葉,性腺を構成要素とした機能的なフィードバック機構の中で制御されている.この機構の中で,男性性腺は精子の産生(精子形成)と男性の性ホルモン(アンドロゲン)産生を,女性性腺は周期的な成熟卵母細胞の産生と卵巣からの周期的ホルモン産生という重要な機能を保持しているが,本稿では紙面の限りもあり女性性腺機能検査に焦点を絞った.
女性性腺に関する重要な内分泌検査として,視床下部-下垂体-卵巣系の機能検査と妊娠中の胎盤機能検査が挙げられる.それらのなかで,私が特に必要と思われる検査法を挙げてその臨床的な意義や測定値の評価を説明することにより,その重要性を明らかにしたい.また,要らないと判断される検査についても,紙面が許される限り言及したい(表).
内分泌検査 2.性腺機能検査―検査医の立場から
著者: 岩谷良則
ページ範囲:P.439 - P.442
必要な検査,要らない検査とは
要らない検査とはっきりいえるものがあるかと考えると,ないように思う.どの臨床検査項目もなんらかの独自の臨床的有用性を持っている.例えば,ある疾患の診断において,その検査項目よりも感度,特異度のかなり優れた新しい検査項目が出てきたとしても,その疾患の診断以外になんらかの臨床的有用性があったり,極めて廉価であったり,また新たな有用性が見いだされたりすることもある.また,稀にしか使用されない検査項目であっても,ある特定の疾患の診断に不可欠であれば必要な検査といわざるを得ない.おそらく,今回の必要な検査,要らない検査というのは,医療の高度化,複雑化,さらには社会の超高齢化による医療費の高騰を抑えるために必要な検査,要らない検査と考えるのが妥当であろう.
現在,医療費の高騰を抑えるために,保健医療制度の抜本的改革として医療費の包括化を推進し,診断群別包括払い方式が導入されようとしている.そのため医療効率を上げることが必須であり,最も少ない医療費で診断・治療できる方法が模索されている.その1つが,診断効率の高い検査診断法の確立であり,できるだけ余分な検査をせずに,早く的確に診断できる方法が望まれる.もちろん診断の感度・特異度を上げようとすれば,できるだけ多くの検査をするにこしたことはないが,対費用効果を考慮して決める必要がある.そこで,今回,性腺・胎盤機能関連検査(表1)のなかで,性腺機能の診断・治療に最も効率的と考えられる必要な臨床検査項目を取り上げ説明したい.
検査データを考える
CKおよび関連項目の解釈における問題点
著者: 吉藤元 , 三森経世
ページ範囲:P.443 - P.446
はじめに
クレアチンキナーゼ(creatine kinase;CK)は主要な生化学検査項目の1つであるが,関連疾患は多くなく日常検査では出番が少ないほうで,後述するように初診時スクリーニングセットとしてCKを測定するかどうかについては異論がある.しかし疾患が限られているため,論理的思考による鑑別は比較的容易といえる.以下,CKに関する基本的かつ重要な事項に絞って論述する.
復習のページ
血清分離後にフィブリン析出する検体への対処法
著者: 下広寿 , 小谷和彦 , 飯島憲司
ページ範囲:P.452 - P.453
[フィブリン析出との遭遇]
透析患者検体のように血清分離後にもフィブリンが析出する場合,前処理を十分に行わないと,フィブリンが自動分注機や自動分析装置のノズルや電極に詰まって,正確な結果を得ることができない.さらに次検体のサンプリングにまで影響を及ぼす可能性もある.このように血清を用いる検査の場合,血清分離後のフィブリン析出には注意が必要である.学生時にはフィブリンが析出するような血清を扱う実習まではなかなか行われておらず,このことへの注意は臨床現場に出て初めてわかってくる.
[フィブリン析出の真相]
血液を体外に取り出し試験管に入れておくと,暗赤色の固まりができる.これは血液中のフィブリノゲンがフィブリンに変わる現象である.つまりフィブリンの網目の中に血球成分がからまっているのだ.これを静置するとフィブリンと細胞成分の塊状物(血餅)は収縮して小さくなり淡黄色の液体が分離する.これが血液からフィブリンと細胞成分を除いた血清である(図1)1).
けんさアラカルト
心筋ミオシン軽鎖
著者: 鈴木亨 , 永井良三
ページ範囲:P.454 - P.455
心筋細胞の逸脱蛋白質を用いた心筋梗塞の診断は約半世紀前に1950年代にKarmenらによるトランスアミナーゼを用いた検討に始まり,1960年代に酵素活性の測定(creatine phosphokinase;CPK,lactate dehydrogenase;LDHなど)へと発展した.微量蛋白質の測定への関心が高まり,1970年代に心筋ミオシン軽鎖やトロポニンの研究が行われるようになった.心筋ミオシン軽鎖の測定系は筆者が所属する研究室で開発されたものであり,前教授矢崎義雄先生ならびに現教授永井良三先生らが中心となって世界に先駆けて研究開発した,日本オリジナルの産物である.亜急性期の心筋梗塞の世界初めての生化学的な診断マーカーとして,心筋ミオシン軽鎖は重要な役割を果たしてきた.現在でもコンスタントに使用されており,臨床の場において有用な検査である.
ミオシンは人体内で最も多く存在する蛋白の1つであり,特に筋組織では豊富で,アクチンとともに重合し,筋収縮機構を形成する.ミオシンは心筋には2種の重鎖と4種の軽鎖が存在する.分子量200kDaの重鎖がダイマーを形成し,頭部に20kDaの軽鎖と17kDaの軽鎖とが結合する.本系は心筋ミオシン軽鎖を検出しているが,心筋ミオシン軽鎖は心筋ミオシン軽鎖より安定であると考えられている.
陽イオン交換クロマトグラフィーによるリポ蛋白分離法
著者: 黒澤秀夫 , 堂満憲一
ページ範囲:P.456 - P.458
はじめに
動脈硬化の進展と発症にコレステロールが深くかかわっていることは論を待たない.疫学的研究(Framingum Study)の再評価により低比重リポ蛋白コレステロール(low density lipoprotein cholesterol;LDL-C)が重要であることが明らかとなり,動脈硬化学会診療基準においてLDL-Cを重要視する方向性が示されている1).近年,LDL-C,高比重リポ蛋白コレステロール(high density lipoprotein cholesterol;HDL-C)の直接法が開発され,手軽に測定可能となった2~4).一方,高中性脂肪血症患者で増加する中間型リポ蛋白(intermediate density lipoprotein;IDL),PAG(polyaerylamide gel)電気泳動のmidband,レムナント様リポ蛋白コレステロール(remnant like particles-cholesterol;RLP-C)などの構造様式の詳細は不明である.
リポ蛋白の分離は超遠心法が基準法としてあるが5),手技が煩雑で一般的に普及していない.また,PAG電気泳動法(Lipophor),ゲル濾過法6),イオン交換クロマトグラフィーなど7) が用いられてきたが,定量法としては不備な点が多くいっそうの精度向上が求められていた.
このような状況の中で,新たに開発したリポ蛋白分離法(陽イオン交換クロマトグラフィー)8,9) は,リポ蛋白コレステロール定量法として世界的に十分通用する方法と考えられる.
臨床検査フロンティア 検査技術を生かせる新しい職種
認定臨床エンブリオロジスト
著者: 縄公美
ページ範囲:P.460 - P.462
はじめに
認定臨床エンブリオロジストと聞いてもピンとこない方も多いのではないでしょうか.これは生殖医療に携わる技術者の呼称で,不妊治療をしている施設で配偶子(精子や卵子)のお世話をする技師はすべてエンブリオロジストと呼ばれています.エンブリオロジストの中で日本臨床エンブリオロジスト研究会の定める規定を満たし,認定を受けた者が認定臨床エンブリオロジストというわけです.
私は夜間学部生だったため,学生の頃からアルバイトとして検査業務に従事していました.アルバイト時代には生化学,血液,一般などといった授業や実習などでも馴染みのある検査業務だったのですが,就職した施設では普通の検査をすることはあまり求められず不妊治療のための精子の調整,卵子の培養が主な業務となりました.初めのころは学んだことのない分野に戸惑いと不安がありましたが,卵子が受精し分割するさまを見ていくことのおもしろさ,生命の誕生,その神秘性を直に感じることのできる仕事です.体外に取り出された瞬間から卵子を大事に大事に育て数日後には子宮に戻す.その胚がうまく着床すれば晴れて妊婦さんの仲間入りをされます.当院で治療した方のほとんどが転院することなく出産し,乳児健診も受診されます.妊婦健診では超音波を担当しているので自分自身で心拍や胎動を観察することができ,そしていよいよ出産というときにはお母さんを励ますことも,無事に産まれてきてくれた児を抱きともに喜ぶこともできます.かわいく元気な姿を見ることが何より楽しく,あの精子と卵子から育ったのかと喜ばずにはいられません.このやりがいこそさらに技術を向上させようと思う原動力だと思います.技術を向上させるためには,ハムスターやマウスの卵子,また研究用に使用する同意を得たうえで患者さんから提供していただいた未受精卵あるいは成長の止まってしまった胚を用いた日々の練習だけでなく勉強会などで議論することも,同じ志を持った技師同士のつながりも大切です.エンブリオロジストには検査技師だけでなく薬剤師,農学部出身者などもいますので普段なら職域の壁を感じてしまうところですが,それぞれの得意分野に応じて疑問点も解決策も違うため,異なる発想で意見交換をすることがとてもよい刺激になっています.今のところ法整備もなく,生殖医療に携わるうえで特に資格を有することは必要とされていません.将来的にも何か公的な資格制度ができる可能性は低いようです.
Laboratory Practice 血液:骨髄塗抹標本の見かた
FAB分類 [3]急性リンパ性白血病(L1~L3)
著者: 清水長子
ページ範囲:P.416 - P.419
はじめに
急性白血病は,血液細胞の腫瘍であり骨髄中で腫瘍性に増殖する疾患である.
大きく急性リンパ性白血病(acute lymphoblastic leukemia;ALL)と急性骨髄性白血病(acute myelocytic leukemia;AML)の2群に分けることができ,ALLは未熟なリンパ球系芽球の腫瘍性増殖を来す疾患である.
FAB(French American British)分類1) ではALLとAMLの区別は,芽球のペルオキシダーゼ反応で区別されペルオキシダーゼ反応陽性芽球が3%未満のものをALLとする.しかし,一部のAMLのうちでペルオキシダーゼ反応陰性の疾患もあるためALLの確定診断には,芽球の表面形質2,3) での確認が必要である.
ALLは塗抹標本の形態特徴によりL1~L3の3型に分類される.1981年に一致率の向上のためにscoring systemが加えられた4).
表1に細胞の特徴を示した.
病理:細胞像からここまでわかる
体腔液(4) 白血病・リンパ腫
著者: 堀内啓 , 牛島友則 , 松谷章司
ページ範囲:P.420 - P.424
はじめに
体腔液中に白血病あるいは悪性リンパ腫の細胞が出現することは,癌腫に比べれば頻度は低い.しかし,鑑別診断においては,常に念頭に置くべき疾患である.特に小児では,これらの疾患が原因となる体腔液貯留が成人に比べて頻度が高く,重要である.白血病やリンパ腫の体腔への浸潤は,進行した病期に発生することが多いが,時には体腔液の貯留が初発症状のこともある.悪性リンパ腫の場合,体腔以外の部位に腫瘤を形成する原発巣があり,それが体腔へ浸潤することがほとんどであるが,稀に,体腔液中にリンパ腫細胞が出現するが,ほかに腫瘤を形成する原発巣がなく,原発性体腔液リンパ腫(primary effusion lymphoma)とよばれる疾患も知られている.また,白血病・リンパ腫の細胞形態の観察には,パパニコロウ染色(Papanicolaou stain)だけではなく,ギムザ染色(Giemza stain)や免疫細胞化学も重要であり,標本作製の際に留意が必要である.
トピックス
パラフィン標本からのDNA抽出法
著者: 五十嵐久喜 , 椙村春彦
ページ範囲:P.463 - P.465
はじめに
1985年にGoelzら1) によってホルマリン固定パラフィン包埋組織からのDNA抽出法が報告されて以来,分子病理学は急速な進展をみせている.通常,病理組織からのDNA抽出は新鮮材料を用いて行われるが,生材料が採取できない状況下,あるいは過去の症例について解析する場合はホルマリン固定パラフィン切片よりDNAを抽出し行うこととなる.近年では,脱パラフィン処理や蛋白質分解処理が不要で短時間でのDNA抽出を可能にした試薬(DNA Isolator PS-Rapid Reagent:和光純薬社,TaKaRa DEXPAT:TaKaRa社)も市販されているが,本稿では従来より行われているパラフィン切片からのDNA抽出法および問題点とその対策について述べてみたい.
糖尿病治療薬の使い分け
著者: 石田均 , 鈴木清
ページ範囲:P.465 - P.467
はじめに
糖尿病の患者数は近年になり急激に増加しており,既に約700万人に達していると推定される.そのなかで糖尿病の治療はここ数年で大きく変化してきており,特に2型糖尿病に対する経口剤治療は,特徴的な作用を有する薬剤が次々と使用可能となっている.したがって,それぞれの症例の糖尿病の病態を正確に把握して,的確な薬剤を選択することが必要となってきた.
ナノテクノロジー
著者: 只野壽太郎
ページ範囲:P.467 - P.468
ノーベル物理学賞を受賞したファインマン博士は1959年“将来は原子を1つずつ組み上げて,思いどおりの物質を作れるようになるだろう”と予言した.1980年代になるとマサチューセッツ工科大学のドレクスラー博士が“空気や水や炭素から,飛行機や自動車やパンや肉が,あまりエネルギーを使わずにできる”ナノテクノロジーによる打ち出の小槌論を発表した.1981年IBM社は走査型トンネル顕微鏡を開発し,これを使ってニッケル単結晶の上に,キセノン原子36個でIBMという文字を書いた.この技術は300kmの上空からロボットアームでゴマ粒を並べるのと同じくらい高精度の技術といわれる.
これに対応し,2000年に当時のアメリカ合衆国大統領クリントンはナノテクノロジーの推進を国家戦略の1つに決め国家ナノ技術計画に約600億円を充てると発表し,わが国も2001年ナノ物質研究センターを立ち上げ,33億円の予算をつけた.
Serratia marcescensのnucleaseによるPCR産物の分解
著者: 岩城有佳 , 森田未香 , 多賀由紀子 , 野手良剛 , 吉田郁子 , 小澤哲夫 , 北島勲
ページ範囲:P.468 - P.469
はじめに
現在わが国では,臓器移植,癌治療など医療の高度化に伴ってグラム陰性菌感染症に対する第3世代セフェム系,カルバペネム系抗菌薬の使用量が増加し,メタロ-β-ラクタマーゼ産生菌出現が問題となっている.
そこで,われわれは富山県内のメタロ-β-ラクタマーゼ産生菌出現状況を把握することを目的として,2002年7月~9月までの間に県内14施設で分離された好気性グラム陰性桿菌のIMP-1型,IMP-2型メタロ-β-ラクタマーゼ遺伝子(IMP-1,IMP-2)の保有調査をPCR(polymerase chain reaction,ポリメラーゼ連鎖反応)法により行った.DNAの抽出には操作手技の簡便性からグラム陰性菌でよく行われている加熱処理法(95°C10分間)を用いた.今回はその際に経験した,Serratia marcescensのDNAサンプルを取り扱う上での注意点について述べる.
ワンポイントアドバイス
アルシアングリーン3BXを用いた尿沈渣染色液
著者: 松岡優 , 岡田茂治
ページ範囲:P.425 - P.425
尿沈鏡検において,欠かせないものの1つにステルンハイマー染色(Sternheimer stain)液1)(S染色液)が挙げられる.通常無染色標本で観察している諸氏も,沈成分の判定に苦慮したときなど迷わずS染色液で染色していることと思われる.
S染色液は青色色素に2%のアルシアンブルー水溶液(特にアルシアンブルー 8GXが色素溶解性や染色性がよいといわれている2)),赤色色素に1.5%ピロニンB水溶液が用いられている.しかし,近年,一部メーカーでアルシアンブルー 8GXの色素が販売終了となり,在庫色素の値段が高騰し,手に入りにくい状況となった.それに伴い,自施設で作製している施設は,自家調整S染色液を作製することが困難となった.また,日本国内で一番使われていると思われるメーカーが尿染色液の販売を中止する事態となった.
検査じょうほう室 微生物:ステップアップにいかす微生物の知識
アルコール系殺菌消毒剤によるウイルス不活化対策
著者: 山崎謙治
ページ範囲:P.430 - P.431
はじめに
微生物を除去したいときに思い浮かぶ言葉として,滅菌,消毒,(除菌)洗浄などがあるが,これらはどのように異なるのであろうか.滅菌とはすべての微生物を殺滅するか,完全に除去して無菌状態にすることであり,オートクレーブ(高圧蒸気滅菌器),ガンマ線,エチレンオキサイドガスおよび濾過フィルターなどが用いられる.消毒とは人体に有害な微生物(病原微生物)をなくすか,菌量を少なくすることをいい,消毒したい対象物によってその方法は異なり,煮沸,紫外線照射あるいは殺菌剤による消毒などがある.また洗浄とは洗い清めることであり,傷のない健康な皮膚に接触するような,あるいはヒトの手に接触しないような器具,器械などが対象となる.実際,水道水で流すだけでも意外に大きな微生物除去効果があるものである.
一般:一般検査のミステリー
尿中蛋白電気泳動における易動度の違いで判明した卵白混入の事例
著者: 松田徳子 , 山本慶和 , 松尾収二
ページ範囲:P.432 - P.434
日常業務に追われている日々のなかで時々何かが変だと感じることはありませんか.そんなときはふと立ち止まってじっくりデータを見ていますか.今回,私が経験した,こんなことはあるのか,こんな値はあるのか,という話をしてみたいと思います.
皆さんは年に何度か“これっておしっこ?”と疑うことはありませんか.糖尿病の患者さんが医師によく思われたくて尿の代わりに水を提出されることがありますが,今回はこれとはまったく逆で自分あるいは子どもが病気になりたくて,尿に卵白を混入させた事例を紹介したいと思います.
けんさ質問箱Q&A
尿沈渣成績の記載法
著者: 油野友二
ページ範囲:P.447 - P.448
Q 尿沈渣成績の記載法
「尿沈検査法2000」の血球・上皮細胞の記載法で,1個未満/HPF(JCCLS法)とは0個から数視野に1個という意味なのでしょうか.また,それは常に報告書に記載するべきなのでしょうか.記載し,報告するべきであるのは,どの細胞についてでしょうか.卵円形脂肪体,ウイルス感染細胞,異型細胞なども概数表記すべきなのでしょうか.(岡山県津山市 H. I. 生)
A 尿沈中に認められる成分としては,ご承知のように血球類,上皮細胞類,円柱類,微生物・寄生虫類,結晶類,その他に分類される.それらが尿中にどのようにして出現するかという視点で考えると
( 1 ) 生理的剝離
いわゆる新陳代謝による老朽化した細胞が剝離して落下してくると考えられるもの.主に尿細管上皮細胞,移行上皮細胞,扁平上皮細胞など上皮細胞類と新陳代謝による老朽化とは異なるが一定量の血球類も排出されている.
高齢化社会に対応した人間ドックでの検査項目
著者: 青木芳和
ページ範囲:P.448 - P.451
Q 高齢化社会に対応した人間ドックでの検査項目
人間ドックの検査項目は今後何を加え,何を外せばよいでしょうか.高齢化社会への対応策を教えてください.(埼玉県春日部市 K. I. 生)
A 日本が高齢化社会に突入していることは周知のとおりで,2010年には日本の人口の22.5%は65歳以上になるといわれている1).一方で次世代をになう子どもたちの出生数は1975年以来減少し続けている.このような状況では現在,一般に60歳で定年を迎え,社会の一線を退く人々も元気にもうしばらく社会を背負っていかなければならない時代になっている.また,高齢化社会に伴い老人の医療費は年々増大しており,老人医療費の抑制が国政レベルでの重要課題となっている.
今月の表紙
間質性肺炎(interstitial pneumonia;IP)
著者: 尾関貴子
ページ範囲:P.459 - P.459
【解説】 57 歳,女性.全身性硬化症に伴う間質性肺炎(interstitial pneumonia;IP)の呼吸機能検査値(図1,表)および胸部X線像(図2),CT像(図3-a,b)である.VC(vital capacity,肺活量)低下,DLCO(diffusing capacity,肺拡散能力)低下を認め,両側肺尖部における胸膜肥厚と,全肺野における胸膜直下に淡いすりガラス状陰影を伴う線状網状陰影を認め,特に両下肺野は蜂窩肺を呈している.
間質性肺炎とは
呼吸困難および乾性咳を主訴とし,呼吸機能上拘束性障害・肺拡散障害,胸部X線像上両側肺野にびまん性の陰影を呈する疾患で,組織学的には進行性の線維化を生じる疾患である.線維化が進み,蜂窩肺となったものが肺線維症である.
検査センター悲話・秘話・疲話
■最終話■最終回を迎えて
著者: ラボ検査研究会
ページ範囲:P.470 - P.470
■最終話■ 最終回を迎えて
読者の皆様に少しでも,検査センターの実情を知っていただこうとスタートしたこの悲話・秘話・疲話シリーズも最終回となりました.
検査センター側が改善しなければいけないことへの自戒や,医療機関側に対して要求,啓蒙していかなければならないことへのグチなど,11回にわたり書き綴ってきました.この間に業界初の公取委の排除勧告などもあり,現在の臨床検査の存在意義や問題点や将来について考えることの多い1年間でした.特に検体検査に関し,社会通念上の位置付けや関連法規および医療保険制度上の取り扱いと位置付けについて,整備する必要を強く感じました.
基本情報
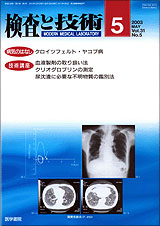
バックナンバー
52巻12号(2024年12月発行)
技術講座 生理
52巻11号(2024年11月発行)
技術講座 生理
52巻10号(2024年10月発行)
技術講座 生理
52巻9号(2024年9月発行)
増大号 臨床医に伝わりやすい 検査報告書とパニック値報告の心得
52巻8号(2024年8月発行)
技術講座 生理
52巻7号(2024年7月発行)
技術講座 生理
52巻6号(2024年6月発行)
技術講座 生理
52巻5号(2024年5月発行)
技術講座 その他
52巻4号(2024年4月発行)
技術講座 生理
52巻3号(2024年3月発行)
増大号 POCUSの決め手。 早く、正確な診断のために
52巻2号(2024年2月発行)
技術講座 生理
52巻1号(2024年1月発行)
技術講座 その他
51巻12号(2023年12月発行)
技術講座 生理
51巻11号(2023年11月発行)
技術講座 生理
51巻10号(2023年10月発行)
技術講座 その他
51巻9号(2023年9月発行)
増大号 匠から学ぶ 血栓止血検査ガイド
51巻8号(2023年8月発行)
技術講座 生理
51巻7号(2023年7月発行)
技術講座 生理
51巻6号(2023年6月発行)
技術講座 生理
51巻5号(2023年5月発行)
技術講座 生理
51巻4号(2023年4月発行)
技術講座 生理
51巻3号(2023年3月発行)
増大号 症例から学ぶ 疾患と検査値の推移
51巻2号(2023年2月発行)
技術講座 その他
51巻1号(2023年1月発行)
技術講座 生理
50巻12号(2022年12月発行)
技術講座 その他
50巻11号(2022年11月発行)
技術講座 生理
50巻10号(2022年10月発行)
技術講座 生理
50巻9号(2022年9月発行)
増大号 希少例と特殊像がわかる! エコーの撮り方完全マスター
50巻8号(2022年8月発行)
技術講座 生理
50巻7号(2022年7月発行)
技術講座 生理
50巻6号(2022年6月発行)
技術講座 生理
50巻5号(2022年5月発行)
技術講座 生理
50巻4号(2022年4月発行)
技術講座 生理
50巻3号(2022年3月発行)
増大号 見て学ぶ 一般検査学アトラス—外観検査から顕微鏡検査まで
50巻2号(2022年2月発行)
技術講座 その他
50巻1号(2022年1月発行)
技術講座 生理
49巻12号(2021年12月発行)
技術講座 生理
49巻11号(2021年11月発行)
技術講座 生理
49巻10号(2021年10月発行)
技術講座 生理
49巻9号(2021年9月発行)
増刊号 病態別 腹部エコーの観察・記録・報告書作成マスター
49巻8号(2021年8月発行)
技術講座 生理
49巻7号(2021年7月発行)
技術講座 生理
49巻6号(2021年6月発行)
技術講座 生理
49巻5号(2021年5月発行)
技術講座 生理
49巻4号(2021年4月発行)
技術講座 一般
49巻3号(2021年3月発行)
増刊号 First&Next Step 微生物検査サポートブック
49巻2号(2021年2月発行)
技術講座 微生物
49巻1号(2021年1月発行)
技術講座 病理・生理
48巻12号(2020年12月発行)
技術講座 その他
48巻11号(2020年11月発行)
技術講座 生化学
48巻10号(2020年10月発行)
技術講座 生理
48巻9号(2020年9月発行)
増刊号 学会発表・論文執筆はもう怖くない! 臨床検査技師のための研究入門
48巻8号(2020年8月発行)
技術講座 遺伝子
48巻7号(2020年7月発行)
技術講座 その他
48巻6号(2020年6月発行)
技術講座 輸血
48巻5号(2020年5月発行)
技術講座 生化学
48巻4号(2020年4月発行)
技術講座 生理
48巻3号(2020年3月発行)
増刊号 採血のすべて—手技から採血室の運用まで徹底解説
48巻2号(2020年2月発行)
技術講座 微生物
48巻1号(2020年1月発行)
技術講座 生理
47巻12号(2019年12月発行)
技術講座 病理
47巻11号(2019年11月発行)
技術講座 生理
47巻10号(2019年10月発行)
技術講座 生理
47巻9号(2019年9月発行)
増刊号 染色画像を比べて学ぶ 体腔液アトラス
47巻8号(2019年8月発行)
技術講座 病理
47巻7号(2019年7月発行)
技術講座 一般
47巻6号(2019年6月発行)
技術講座 血液
47巻5号(2019年5月発行)
技術講座 血液
47巻4号(2019年4月発行)
技術講座 血液
47巻3号(2019年3月発行)
増刊号 エキスパートが教える 心・血管エコー計測のノウハウ
47巻2号(2019年2月発行)
技術講座 病理
47巻1号(2019年1月発行)
技術講座 微生物
46巻12号(2018年12月発行)
技術講座 生理
46巻11号(2018年11月発行)
技術講座 輸血・遺伝子検査
46巻10号(2018年10月発行)
技術講座 その他
46巻9号(2018年9月発行)
増刊号 現場で“パッ”と使える 免疫染色クイックガイド
46巻8号(2018年8月発行)
技術講座 輸血・遺伝子検査
46巻7号(2018年7月発行)
技術講座 生理
46巻6号(2018年6月発行)
技術講座 管理
46巻5号(2018年5月発行)
技術講座 生化学
46巻4号(2018年4月発行)
技術講座 一般
46巻3号(2018年3月発行)
増刊号 感染症クイックリファレンス
46巻2号(2018年2月発行)
技術講座 輸血
46巻1号(2018年1月発行)
技術講座 病理
45巻12号(2017年12月発行)
技術講座 生理
45巻11号(2017年11月発行)
技術講座 一般
45巻10号(2017年10月発行)
技術講座 微生物
45巻9号(2017年9月発行)
増刊号 循環器病院の技師が教える メディカルスタッフのための心電図教室
45巻8号(2017年8月発行)
技術講座 栄養
45巻7号(2017年7月発行)
技術講座 病理
45巻6号(2017年6月発行)
技術講座 病理
45巻5号(2017年5月発行)
技術講座 細胞治療・管理
45巻4号(2017年4月発行)
技術講座 遺伝子・染色体検査
45巻3号(2017年3月発行)
45巻2号(2017年2月発行)
技術講座 細胞治療
45巻1号(2017年1月発行)
技術講座 病理
44巻13号(2016年12月発行)
技術講座 免疫
44巻12号(2016年11月発行)
技術講座 微生物
44巻11号(2016年10月発行)
技術講座 微生物
44巻10号(2016年9月発行)
増刊号 はじめて出会う 検査画像
44巻9号(2016年9月発行)
技術講座 管理・その他
44巻8号(2016年8月発行)
技術講座 微生物
44巻7号(2016年7月発行)
技術講座 生理
44巻6号(2016年6月発行)
技術講座 微生物
44巻5号(2016年5月発行)
技術講座 生理
44巻4号(2016年4月発行)
技術講座 微生物
44巻3号(2016年3月発行)
技術講座 生理
44巻2号(2016年2月発行)
技術講座 微生物
44巻1号(2016年1月発行)
技術講座 微生物
43巻13号(2015年12月発行)
技術講座 生化学
43巻12号(2015年11月発行)
技術講座 生化学
43巻11号(2015年10月発行)
技術講座 一般
43巻10号(2015年9月発行)
増刊号 血液形態アトラス
43巻9号(2015年9月発行)
技術講座 生理
43巻8号(2015年8月発行)
技術講座 生理
43巻7号(2015年7月発行)
技術講座 生理
43巻6号(2015年6月発行)
技術講座 微生物
43巻5号(2015年5月発行)
技術講座 移植医療
43巻4号(2015年4月発行)
技術講座 病理
43巻3号(2015年3月発行)
技術講座 血液
43巻2号(2015年2月発行)
技術講座 管理
43巻1号(2015年1月発行)
技術講座 病理
42巻13号(2014年12月発行)
技術講座 生化学
42巻12号(2014年11月発行)
技術講座 病理
42巻11号(2014年10月発行)
技術講座 血液
42巻10号(2014年9月発行)
増刊号 超音波×病理 対比アトラス
42巻9号(2014年9月発行)
技術講座 生理
42巻8号(2014年8月発行)
技術講座 免疫
42巻7号(2014年7月発行)
技術講座 生理
42巻6号(2014年6月発行)
技術講座 生理
42巻5号(2014年5月発行)
技術講座 病理
42巻4号(2014年4月発行)
技術講座 輸血
42巻3号(2014年3月発行)
技術講座 血液
42巻2号(2014年2月発行)
技術講座 微生物
42巻1号(2014年1月発行)
技術講座 病理
41巻13号(2013年12月発行)
技術講座 生理
41巻12号(2013年11月発行)
技術講座 生化学
41巻11号(2013年10月発行)
技術講座 生化学
41巻10号(2013年9月発行)
増刊号 解剖と正常像がわかる! エコーの撮り方完全マスター
41巻9号(2013年9月発行)
技術講座 微生物
41巻8号(2013年8月発行)
技術講座 生理
41巻7号(2013年7月発行)
技術講座 生理
41巻6号(2013年6月発行)
技術講座 微生物
41巻5号(2013年5月発行)
技術講座 一般
41巻4号(2013年4月発行)
技術講座 生化学
41巻3号(2013年3月発行)
技術講座 生理
41巻2号(2013年2月発行)
技術講座 生理
41巻1号(2013年1月発行)
技術講座 生理
40巻13号(2012年12月発行)
技術講座 血液
40巻12号(2012年11月発行)
技術講座 生理
40巻11号(2012年10月発行)
技術講座 生理
40巻10号(2012年9月発行)
増刊号 この検査データを読めますか?―検査値から病態を探る
40巻9号(2012年9月発行)
技術講座 生理
40巻8号(2012年8月発行)
技術講座 細胞診
40巻7号(2012年7月発行)
技術講座 生理
40巻6号(2012年6月発行)
技術講座 生理
40巻5号(2012年5月発行)
技術講座 生理
40巻4号(2012年4月発行)
技術講座 血液
40巻3号(2012年3月発行)
技術講座 生理
40巻2号(2012年2月発行)
技術講座 輸血
40巻1号(2012年1月発行)
技術講座 遺伝子
39巻13号(2011年12月発行)
疾患と検査値の推移
39巻12号(2011年11月発行)
疾患と検査値の推移
39巻11号(2011年10月発行)
疾患と検査値の推移
39巻10号(2011年9月発行)
増刊号 緊急報告すべき検査結果のすべて―すぐに使えるパニック値事典
39巻9号(2011年9月発行)
疾患と検査値の推移
39巻8号(2011年8月発行)
疾患と検査値の推移
39巻7号(2011年7月発行)
疾患と検査値の推移
39巻6号(2011年6月発行)
技術講座 生理
39巻5号(2011年5月発行)
技術講座 生理
39巻4号(2011年4月発行)
疾患と検査値の推移
39巻3号(2011年3月発行)
疾患と検査値の推移
39巻2号(2011年2月発行)
疾患と検査値の推移
39巻1号(2011年1月発行)
疾患と検査値の推移
38巻13号(2010年12月発行)
疾患と検査値の推移
38巻12号(2010年11月発行)
疾患と検査値の推移
38巻11号(2010年10月発行)
疾患と検査値の推移
38巻10号(2010年9月発行)
増刊号 免疫反応と臨床検査2010
38巻9号(2010年9月発行)
疾患と検査値の推移
38巻8号(2010年8月発行)
疾患と検査値の推移
38巻7号(2010年7月発行)
疾患と検査値の推移
38巻6号(2010年6月発行)
疾患と検査値の推移
38巻5号(2010年5月発行)
疾患と検査値の推移
38巻4号(2010年4月発行)
疾患と検査値の推移
38巻3号(2010年3月発行)
疾患と検査値の推移
38巻2号(2010年2月発行)
疾患と検査値の推移
38巻1号(2010年1月発行)
疾患と検査値の推移
37巻13号(2009年12月発行)
疾患と検査値の推移
37巻12号(2009年11月発行)
疾患と検査値の推移
37巻11号(2009年10月発行)
疾患と検査値の推移
37巻10号(2009年9月発行)
増刊号 顕微鏡検査のコツ―臨床に役立つ形態学
37巻9号(2009年9月発行)
疾患と検査値の推移
37巻8号(2009年8月発行)
疾患と検査値の推移
37巻7号(2009年7月発行)
疾患と検査値の推移
37巻6号(2009年6月発行)
疾患と検査値の推移
37巻5号(2009年5月発行)
疾患と検査値の推移
37巻4号(2009年4月発行)
疾患と検査値の推移
37巻3号(2009年3月発行)
疾患と検査値の推移
37巻2号(2009年2月発行)
疾患と検査値の推移
37巻1号(2009年1月発行)
疾患と検査値の推移
36巻13号(2008年12月発行)
疾患と検査値の推移
36巻12号(2008年11月発行)
疾患と検査値の推移
36巻11号(2008年10月発行)
疾患と検査値の推移
36巻10号(2008年9月発行)
増刊号 これから広がる生理検査・新たにはじまる生理検査
36巻9号(2008年9月発行)
疾患と検査値の推移
36巻8号(2008年8月発行)
疾患と検査値の推移
36巻7号(2008年7月発行)
疾患と検査値の推移
36巻6号(2008年6月発行)
疾患と検査値の推移
36巻5号(2008年5月発行)
疾患と検査値の推移
36巻4号(2008年4月発行)
疾患と検査値の推移
36巻3号(2008年3月発行)
疾患と検査値の推移
36巻2号(2008年2月発行)
疾患と検査値の推移
36巻1号(2008年1月発行)
疾患と検査値の推移
35巻13号(2007年12月発行)
疾患と検査値の推移
35巻12号(2007年11月発行)
疾患と検査値の推移
35巻11号(2007年10月発行)
増刊号 メタボリックシンドローム健診検査技術マニュアル
35巻10号(2007年10月発行)
疾患と検査値の推移
35巻9号(2007年9月発行)
疾患と検査値の推移
35巻8号(2007年8月発行)
疾患と検査値の推移
35巻7号(2007年7月発行)
疾患と検査値の推移
35巻6号(2007年6月発行)
疾患と検査値の推移
35巻5号(2007年5月発行)
疾患と検査値の推移
35巻4号(2007年4月発行)
疾患と検査値の推移
35巻3号(2007年3月発行)
疾患と検査値の推移
35巻2号(2007年2月発行)
疾患と検査値の推移
35巻1号(2007年1月発行)
疾患と検査値の推移
34巻13号(2006年12月発行)
技術講座 生理
34巻12号(2006年11月発行)
技術講座 一般
34巻11号(2006年10月発行)
増刊号 新しい臨床検査・未来の臨床検査
34巻10号(2006年10月発行)
疾患と検査値の推移
34巻9号(2006年9月発行)
疾患と検査値の推移
34巻8号(2006年8月発行)
疾患と検査値の推移
34巻7号(2006年7月発行)
疾患と検査値の推移
34巻6号(2006年6月発行)
疾患と検査値の推移
34巻5号(2006年5月発行)
疾患と検査値の推移
34巻4号(2006年4月発行)
疾患と検査値の推移
34巻3号(2006年3月発行)
疾患と検査値の推移
34巻2号(2006年2月発行)
疾患と検査値の推移
34巻1号(2006年1月発行)
疾患と検査値の推移
33巻13号(2005年12月発行)
疾患と検査値の推移
33巻12号(2005年11月発行)
疾患と検査値の推移
33巻11号(2005年10月発行)
増刊号 一線診療のための臨床検査
33巻10号(2005年10月発行)
疾患と検査値の推移
33巻9号(2005年9月発行)
疾患と検査値の推移
33巻8号(2005年8月発行)
疾患と検査値の推移
33巻7号(2005年7月発行)
疾患と検査値の推移
33巻6号(2005年6月発行)
疾患と検査値の推移
33巻5号(2005年5月発行)
疾患と検査値の推移
33巻4号(2005年4月発行)
疾患と検査値の推移
33巻3号(2005年3月発行)
疾患と検査値の推移
33巻2号(2005年2月発行)
疾患と検査値の推移
33巻1号(2005年1月発行)
疾患と検査値の推移
32巻13号(2004年12月発行)
技術講座 血液
32巻12号(2004年11月発行)
技術講座 病理
32巻11号(2004年10月発行)
技術講座 血液
32巻10号(2004年9月発行)
増刊号 細胞像の見かた―病理・血液・尿沈渣
32巻9号(2004年9月発行)
技術講座 生化学
32巻8号(2004年8月発行)
技術講座 免疫
32巻7号(2004年7月発行)
技術講座 微生物
32巻6号(2004年6月発行)
技術講座 病理
32巻5号(2004年5月発行)
技術講座 病理
32巻4号(2004年4月発行)
技術講座 病理
32巻3号(2004年3月発行)
技術講座 微生物
32巻2号(2004年2月発行)
技術講座 生化学
32巻1号(2004年1月発行)
技術講座 微生物
31巻13号(2003年12月発行)
技術講座 微生物
31巻12号(2003年11月発行)
技術講座 病理
31巻11号(2003年10月発行)
技術講座 微生物
31巻10号(2003年9月発行)
増刊号 包括医療と臨床検査
31巻9号(2003年9月発行)
技術講座 一般
31巻8号(2003年8月発行)
技術講座 微生物
31巻7号(2003年7月発行)
技術講座 病理
31巻6号(2003年6月発行)
技術講座 免疫
31巻5号(2003年5月発行)
技術講座 一般
31巻4号(2003年4月発行)
技術講座 病理
31巻3号(2003年3月発行)
技術講座 生化学
31巻2号(2003年2月発行)
技術講座 免疫
31巻1号(2003年1月発行)
技術講座 免疫
30巻13号(2002年12月発行)
技術講座 生理
30巻12号(2002年11月発行)
技術講座 生理
30巻11号(2002年10月発行)
技術講座 生化学
30巻10号(2002年9月発行)
増刊号 誰でもわかる遺伝子検査
30巻9号(2002年9月発行)
技術講座 微生物
30巻8号(2002年8月発行)
技術講座 生化学
30巻7号(2002年7月発行)
技術講座 微生物
30巻6号(2002年6月発行)
技術講座 生化学
30巻5号(2002年5月発行)
技術講座 微生物
30巻4号(2002年4月発行)
技術講座 一般
30巻3号(2002年3月発行)
技術講座 生化学
30巻2号(2002年2月発行)
技術講座 一般
30巻1号(2002年1月発行)
技術講座 免疫
29巻13号(2001年12月発行)
技術講座 病理
29巻12号(2001年11月発行)
技術講座 生理
29巻11号(2001年10月発行)
技術講座 病理
29巻10号(2001年9月発行)
技術講座 病理
29巻9号(2001年8月発行)
技術講座 病理
29巻8号(2001年7月発行)
技術講座 生理
29巻7号(2001年6月発行)
増刊号 病理組織・細胞診のための日常染色法ガイダンス
29巻6号(2001年6月発行)
技術講座 微生物
29巻5号(2001年5月発行)
技術講座 生理
29巻4号(2001年4月発行)
技術講座 病理
29巻3号(2001年3月発行)
技術講座 微生物
29巻2号(2001年2月発行)
技術講座 微生物
29巻1号(2001年1月発行)
技術講座 一般
28巻13号(2000年12月発行)
技術講座 病理
28巻12号(2000年11月発行)
技術講座 病理
28巻11号(2000年10月発行)
技術講座 免疫
28巻10号(2000年9月発行)
技術講座 微生物
28巻9号(2000年8月発行)
技術講座 微生物
28巻8号(2000年7月発行)
技術講座 生理
28巻7号(2000年6月発行)
増刊号 血液検査実践マニュアル
28巻6号(2000年6月発行)
技術講座 免疫
28巻5号(2000年5月発行)
技術講座 血液
28巻4号(2000年4月発行)
技術講座 一般
28巻3号(2000年3月発行)
技術講座 生理
28巻2号(2000年2月発行)
技術講座 生化学
28巻1号(2000年1月発行)
技術講座 一般
27巻13号(1999年12月発行)
技術講座 病理
27巻12号(1999年11月発行)
技術講座 一般
27巻11号(1999年10月発行)
技術講座 生化学
27巻10号(1999年9月発行)
技術講座 免疫
27巻9号(1999年8月発行)
技術講座 病理
27巻8号(1999年7月発行)
技術講座 病理
27巻7号(1999年6月発行)
増刊号 緊急検査実践マニュアル
27巻6号(1999年6月発行)
技術講座 生化学
27巻5号(1999年5月発行)
技術講座 血液
27巻4号(1999年4月発行)
技術講座 一般
27巻3号(1999年3月発行)
技術講座 生理
27巻2号(1999年2月発行)
技術講座 微生物
27巻1号(1999年1月発行)
技術講座 生理
26巻13号(1998年12月発行)
技術講座 一般
26巻12号(1998年11月発行)
技術講座 病理
26巻11号(1998年10月発行)
技術講座 病理
26巻10号(1998年9月発行)
技術講座 生理
26巻9号(1998年8月発行)
技術講座 生理
26巻8号(1998年7月発行)
技術講座 生理
26巻7号(1998年6月発行)
増刊号 病理組織・細胞診実践マニュアル
26巻6号(1998年6月発行)
技術講座 病理
26巻5号(1998年5月発行)
技術講座 一般
26巻4号(1998年4月発行)
技術講座 病理
26巻3号(1998年3月発行)
技術講座 一般
26巻2号(1998年2月発行)
技術講座 生理
26巻1号(1998年1月発行)
技術講座 血液
25巻13号(1997年12月発行)
技術講座 一般
25巻12号(1997年11月発行)
技術講座 一般
25巻11号(1997年10月発行)
技術講座 生理
25巻10号(1997年9月発行)
技術講座 血液
25巻9号(1997年8月発行)
技術講座 一般
25巻8号(1997年7月発行)
技術講座 一般
25巻7号(1997年6月発行)
増刊号 輸血検査実践マニュアル
25巻6号(1997年6月発行)
技術講座 免疫
25巻5号(1997年5月発行)
技術講座 生理
25巻4号(1997年4月発行)
技術講座 生理
25巻3号(1997年3月発行)
技術講座 微生物
25巻2号(1997年2月発行)
技術講座 生理
25巻1号(1997年1月発行)
技術講座 一般
24巻13号(1996年12月発行)
技術講座 生理
24巻12号(1996年11月発行)
技術講座 一般
24巻11号(1996年10月発行)
技術講座 生理
24巻10号(1996年9月発行)
技術講座 管理
24巻9号(1996年8月発行)
技術講座 生理
24巻8号(1996年7月発行)
技術講座 生理
24巻7号(1996年6月発行)
増刊号 感染症検査実践マニュアル
24巻6号(1996年6月発行)
技術講座 病理
24巻5号(1996年5月発行)
技術講座 生理
24巻4号(1996年4月発行)
技術講座 生理
24巻3号(1996年3月発行)
技術講座 生理
24巻2号(1996年2月発行)
技術講座 生理
24巻1号(1996年1月発行)
技術講座 一般
23巻13号(1995年12月発行)
技術講座 生理
23巻12号(1995年11月発行)
技術講座 病理
23巻11号(1995年10月発行)
技術講座 微生物
23巻10号(1995年9月発行)
技術講座 生理
23巻9号(1995年8月発行)
技術講座 一般
23巻8号(1995年7月発行)
技術講座 免疫
23巻7号(1995年6月発行)
技術講座 生理
23巻6号(1995年5月発行)
技術講座 一般
23巻5号(1995年4月発行)
増刊号 臨床生理検査実践マニュアル画像検査を中心として
23巻4号(1995年4月発行)
技術講座 病理
23巻3号(1995年3月発行)
技術講座 病理
23巻2号(1995年2月発行)
技術講座 一般
23巻1号(1995年1月発行)
技術講座 生理
22巻13号(1994年12月発行)
技術講座 一般
22巻12号(1994年11月発行)
技術講座 一般
22巻11号(1994年10月発行)
技術講座 一般
22巻10号(1994年9月発行)
技術講座 一般
22巻9号(1994年8月発行)
技術講座 生理
22巻8号(1994年7月発行)
技術講座 病理
22巻7号(1994年6月発行)
技術講座 一般
22巻6号(1994年5月発行)
技術講座 一般
22巻5号(1994年4月発行)
増刊号 免疫検査実践マニュアル
22巻4号(1994年4月発行)
技術講座 生理
22巻3号(1994年3月発行)
技術講座 免疫
22巻2号(1994年2月発行)
技術講座 一般
22巻1号(1994年1月発行)
技術講座 生理
21巻13号(1993年12月発行)
技術講座 一般
21巻12号(1993年11月発行)
技術講座 一般
21巻11号(1993年10月発行)
技術講座 一般
21巻10号(1993年9月発行)
技術講座 生理
21巻9号(1993年8月発行)
技術講座 一般
21巻8号(1993年7月発行)
技術講座 病理
21巻7号(1993年6月発行)
技術講座 一般
21巻6号(1993年5月発行)
技術講座 生理
21巻5号(1993年4月発行)
増刊号 臨床化学実践マニュアル
21巻4号(1993年4月発行)
技術講座 生理
21巻3号(1993年3月発行)
技術講座 病理
21巻2号(1993年2月発行)
技術講座 生理
21巻1号(1993年1月発行)
技術講座 生理
20巻13号(1992年12月発行)
技術講座 一般
20巻12号(1992年11月発行)
技術講座 一般
20巻11号(1992年10月発行)
技術講座 一般
20巻10号(1992年9月発行)
技術講座 一般
20巻9号(1992年8月発行)
技術講座 一般
20巻8号(1992年7月発行)
技術講座 血液
20巻7号(1992年6月発行)
技術講座 一般
20巻6号(1992年5月発行)
増刊号 尿検査法
20巻5号(1992年5月発行)
技術講座 生理
20巻4号(1992年4月発行)
技術講座 生理
20巻3号(1992年3月発行)
技術講座 病理
20巻2号(1992年2月発行)
技術講座 一般
20巻1号(1992年1月発行)
技術講座 生理
19巻13号(1991年12月発行)
技術講座 管理
19巻12号(1991年11月発行)
技術講座 生理
19巻11号(1991年10月発行)
技術講座 生理
19巻10号(1991年9月発行)
技術講座 一般
19巻9号(1991年8月発行)
技術講座 一般
19巻8号(1991年7月発行)
技術講座 生理
19巻7号(1991年6月発行)
増刊号 臨床血液検査
19巻6号(1991年6月発行)
技術講座 生理
19巻5号(1991年5月発行)
技術講座 生理
19巻4号(1991年4月発行)
技術講座 一般
19巻3号(1991年3月発行)
技術講座 生理
19巻2号(1991年2月発行)
技術講座 生理
19巻1号(1991年1月発行)
技術講座 一般
18巻13号(1990年12月発行)
技術講座 生理
18巻12号(1990年11月発行)
技術講座 微生物
18巻11号(1990年10月発行)
技術講座 生理
18巻10号(1990年9月発行)
技術講座 一般
18巻9号(1990年8月発行)
技術講座 一般
18巻8号(1990年7月発行)
技術講座 一般
18巻7号(1990年6月発行)
技術講座 一般
18巻6号(1990年5月発行)
増刊号 血液・尿以外の体液検査法
18巻5号(1990年5月発行)
技術講座 一般
18巻4号(1990年4月発行)
技術講座 一般
18巻3号(1990年3月発行)
技術講座 血液
18巻2号(1990年2月発行)
技術講座 生理
18巻1号(1990年1月発行)
技術講座 生理
17巻13号(1989年12月発行)
技術講座 一般
17巻12号(1989年11月発行)
技術講座 一般
17巻11号(1989年10月発行)
技術講座 一般
17巻10号(1989年9月発行)
技術講座 一般
17巻9号(1989年8月発行)
技術講座 生理
17巻8号(1989年7月発行)
技術講座 血清
17巻7号(1989年6月発行)
技術講座 一般
17巻6号(1989年5月発行)
感染症の検査法 Ⅲ 検査法各論
17巻5号(1989年5月発行)
技術講座 一般
17巻4号(1989年4月発行)
技術講座 生理
17巻3号(1989年3月発行)
技術講座 病理
17巻2号(1989年2月発行)
技術講座 一般
17巻1号(1989年1月発行)
技術講座 生理
16巻13号(1988年12月発行)
技術講座 一般
16巻12号(1988年11月発行)
技術講座 一般
16巻11号(1988年10月発行)
技術講座 一般
16巻10号(1988年9月発行)
技術講座 生理
16巻9号(1988年8月発行)
技術講座 一般
16巻8号(1988年7月発行)
技術講座 一般
16巻7号(1988年6月発行)
免疫化学検査法 資料
16巻6号(1988年6月発行)
技術講座 一般
16巻5号(1988年5月発行)
技術講座 一般
16巻4号(1988年4月発行)
技術講座 病理
16巻3号(1988年3月発行)
技術講座 生理
16巻2号(1988年2月発行)
技術講座 一般
16巻1号(1988年1月発行)
技術講座 血液
15巻13号(1987年12月発行)
技術講座 一般
15巻12号(1987年11月発行)
技術講座 病理
15巻11号(1987年10月発行)
技術講座 細胞診
15巻10号(1987年9月発行)
技術講座 一般
15巻9号(1987年8月発行)
技術講座 細胞診
15巻8号(1987年7月発行)
技術講座 病理
15巻7号(1987年6月発行)
技術講座 病理
15巻6号(1987年5月発行)
技術講座 病理
15巻5号(1987年4月発行)
臨床生理検査と技術 座談会
15巻4号(1987年4月発行)
技術講座 生理
15巻3号(1987年3月発行)
技術講座 血液
15巻2号(1987年2月発行)
技術講座 一般
15巻1号(1987年1月発行)
技術講座 病理
14巻13号(1986年12月発行)
技術講座 一般
14巻12号(1986年11月発行)
技術講座 病理
14巻11号(1986年10月発行)
技術講座 血清
14巻10号(1986年9月発行)
技術講座 血清
14巻9号(1986年8月発行)
技術講座 生理
14巻8号(1986年7月発行)
技術講座 血清
14巻7号(1986年6月発行)
技術講座 病理
14巻6号(1986年5月発行)
技術講座 生理
14巻5号(1986年4月発行)
形態学的検査と技術 血液と病理
14巻4号(1986年4月発行)
技術講座 病理
14巻3号(1986年3月発行)
技術講座 細菌
14巻2号(1986年2月発行)
技術講座 病理
14巻1号(1986年1月発行)
技術講座 細菌
13巻12号(1985年12月発行)
技術講座 病理
13巻11号(1985年11月発行)
技術講座 病理
13巻10号(1985年10月発行)
技術講座 生理
13巻9号(1985年9月発行)
技術講座 病理
13巻8号(1985年8月発行)
技術講座 病理
13巻7号(1985年7月発行)
技術講座 血液
13巻6号(1985年6月発行)
技術講座 一般
13巻5号(1985年5月発行)
技術講座 病理
13巻4号(1985年4月発行)
技術講座 一般
13巻3号(1985年3月発行)
技術講座 血液
13巻2号(1985年2月発行)
技術講座 一般
13巻1号(1985年1月発行)
技術講座 血液
12巻12号(1984年12月発行)
技術講座 血液
12巻11号(1984年11月発行)
技術講座 病理
12巻10号(1984年10月発行)
技術講座 輸血
12巻9号(1984年9月発行)
技術講座 一般
12巻8号(1984年8月発行)
技術講座 細菌
12巻7号(1984年7月発行)
技術講座 細菌
12巻6号(1984年6月発行)
技術講座 生理
12巻5号(1984年5月発行)
技術講座 一般
12巻4号(1984年4月発行)
技術講座 病理
12巻3号(1984年3月発行)
技術講座 血液
12巻2号(1984年2月発行)
技術講座 一般
12巻1号(1983年12月発行)
技術講座 血清
11巻12号(1983年12月発行)
技術講座 一般
11巻11号(1983年11月発行)
技術講座 細菌
11巻10号(1983年10月発行)
技術講座 細胞診
11巻9号(1983年9月発行)
技術講座 一般
11巻8号(1983年8月発行)
技術講座 血清
11巻7号(1983年7月発行)
技術講座 細菌
11巻6号(1983年6月発行)
技術講座 一般
11巻5号(1983年5月発行)
技術講座 病理
11巻4号(1983年4月発行)
技術講座 一般
11巻3号(1983年3月発行)
技術講座 血液
11巻2号(1983年2月発行)
技術講座 一般
11巻1号(1983年1月発行)
技術講座 血液
10巻12号(1982年12月発行)
技術講座 一般
10巻11号(1982年11月発行)
技術講座 生理
10巻10号(1982年10月発行)
技術講座 血清
10巻9号(1982年9月発行)
技術講座 細菌
10巻8号(1982年8月発行)
技術講座 一般
10巻7号(1982年7月発行)
技術講座 病理
10巻6号(1982年6月発行)
技術講座 細菌
10巻5号(1982年5月発行)
技術講座 病理
10巻4号(1982年4月発行)
技術講座 血清
10巻3号(1982年3月発行)
技術講座 生化学
10巻2号(1982年2月発行)
技術講座 病理
10巻1号(1982年1月発行)
技術講座 生化学
9巻12号(1981年12月発行)
技術講座 細菌
9巻11号(1981年11月発行)
技術講座 生理
9巻10号(1981年10月発行)
技術講座 一般
9巻9号(1981年9月発行)
技術講座 血清
9巻8号(1981年8月発行)
技術講座 血清
9巻7号(1981年7月発行)
技術講座 生理
9巻6号(1981年6月発行)
技術講座 細菌
9巻5号(1981年5月発行)
技術講座 一般
9巻4号(1981年4月発行)
技術講座 一般
9巻3号(1981年3月発行)
技術講座 血清
9巻2号(1981年2月発行)
技術講座 一般
9巻1号(1981年1月発行)
技術講座 生化学
8巻12号(1980年12月発行)
技術講座 一般
8巻11号(1980年11月発行)
技術講座 生理
8巻10号(1980年10月発行)
技術講座 検体の取り扱いと保存
8巻9号(1980年9月発行)
技術講座 病理
8巻8号(1980年8月発行)
技術講座 生化学
8巻7号(1980年7月発行)
技術講座 一般
8巻6号(1980年6月発行)
技術講座 生理
8巻5号(1980年5月発行)
技術講座 生化学
8巻4号(1980年4月発行)
技術講座 血清
8巻3号(1980年3月発行)
技術講座 病理
8巻2号(1980年2月発行)
技術講座 一般
8巻1号(1980年1月発行)
技術講座 生化学
7巻12号(1979年12月発行)
技術講座 一般
7巻11号(1979年11月発行)
技術講座 一般
7巻10号(1979年10月発行)
技術講座 細菌
7巻9号(1979年9月発行)
技術講座 生理
7巻8号(1979年8月発行)
技術講座 病理
7巻7号(1979年7月発行)
技術講座 生理
7巻6号(1979年6月発行)
技術講座 一般
7巻5号(1979年5月発行)
技術講座 血液
7巻4号(1979年4月発行)
技術講座 生理
7巻3号(1979年3月発行)
技術講座 病理
7巻2号(1979年2月発行)
技術講座 細菌
7巻1号(1979年1月発行)
技術講座 生化学
6巻12号(1978年12月発行)
技術講座 細菌
6巻11号(1978年11月発行)
技術講座 病理
6巻10号(1978年10月発行)
技術講座 血清
6巻9号(1978年9月発行)
技術講座 細菌
6巻8号(1978年8月発行)
技術講座 生化学
6巻7号(1978年7月発行)
技術講座 一般
6巻6号(1978年6月発行)
技術講座 病理
6巻5号(1978年5月発行)
技術講座 生理
6巻4号(1978年4月発行)
技術講座 一般
6巻3号(1978年3月発行)
技術講座 病理
6巻2号(1978年2月発行)
技術講座 一般
6巻1号(1978年1月発行)
技術講座 病理
5巻12号(1977年12月発行)
技術講座 生理
5巻11号(1977年11月発行)
技術講座 一般
5巻10号(1977年10月発行)
技術講座 細菌付録
5巻9号(1977年9月発行)
技術講座 一般
5巻8号(1977年8月発行)
技術講座 生理
5巻7号(1977年7月発行)
技術講座 一般
5巻6号(1977年6月発行)
技術講座 一般
5巻5号(1977年5月発行)
技術講座 一般
5巻4号(1977年4月発行)
技術講座 一般
5巻3号(1977年3月発行)
技術講座 一般
5巻2号(1977年2月発行)
技術講座 一般
5巻1号(1977年1月発行)
技術講座 一般
4巻12号(1976年12月発行)
技術講座 一般
4巻11号(1976年11月発行)
技術講座 一般
4巻10号(1976年10月発行)
技術講座 一般
4巻9号(1976年9月発行)
技術講座 一般
4巻8号(1976年8月発行)
技術講座 一般
4巻7号(1976年7月発行)
技術講座 一般
4巻6号(1976年6月発行)
技術講座 一般
4巻5号(1976年5月発行)
技術講座 一般
4巻4号(1976年4月発行)
技術講座 一般
4巻3号(1976年3月発行)
技術講座 一般
4巻2号(1976年2月発行)
技術講座 一般
4巻1号(1976年1月発行)
技術講座 一般
3巻12号(1975年12月発行)
技術講座 一般
3巻11号(1975年11月発行)
技術講座 一般
3巻10号(1975年10月発行)
技術講座 一般
3巻9号(1975年9月発行)
技術講座 一般
3巻7号(1975年8月発行)
特集 必修 日常検査の実技
3巻6号(1975年6月発行)
技術講座 生理
3巻5号(1975年5月発行)
技術講座 一般
3巻4号(1975年4月発行)
技術講座 一般
3巻3号(1975年3月発行)
技術講座 一般
3巻2号(1975年2月発行)
技術講座 一般
3巻1号(1975年1月発行)
技術講座 一般
