新しい知見
壊死性筋膜炎(NF:necrotizing fasciitis)を起こす感染原因菌の1つであるVibrio vulnificusはVibrionaceae科のVibrio属に含まれるグラム陰性桿菌で海水や魚介類から検出される.わが国におけるVibrio vulnificus感染症は,立山らの調査1)によると,1978年に河野らが初めて報告して以来現在まで100症例を越え,熊本県下の報告例も1981年に竹下らが報告して以来15例とまれな疾患ではなくなってきた.本感染症は急激な転帰を生じ,死亡率も高いため,救急,集中治療部門で注目されている感染症である.しかし一般的には認識が低く,日本救急医療学会のアンケート調査ではVibrio vulnificus感染症を認識できた臨床家は10数%に留まっている.本感染症の治療には早期の診断が必須であり,本菌の迅速な分離,同定が最も重要である.
Vibrio vulnificusによる感染が2001年の6~10月にかけて熊本県内で9症例発生し,死亡者が4名に達した.同時期に多発した事例はめずらしく,われわれはその内4症例を経験した.
雑誌目次
検査と技術31巻9号
2003年09月発行
雑誌目次
病気のはなし
Vibrio vulnificus感染症
著者: 佐藤泰彦 , 森口美琴
ページ範囲:P.774 - P.779
技術講座 生化学
CDTの測定法
著者: 糸賀栄 , 野村文夫
ページ範囲:P.781 - P.786
新しい知見
1979年Stiblerらによって大酒家の血清中に等電点電気泳動で移動度の異なるトランスフェリンが高率に見出されCDT(carbohydrate-deficient transferrin,糖鎖欠損トランスフェリン)と名付けられた.比較的簡便なイオン交換カラムを用いた測定キットが開発され,CDTは欧米では日常検査として測定されている.欧米の報告では健常人で1日60 g以上の飲酒を1週間以上続けると高率にCDTが出現し,大酒家では肝障害の有無にかかわらずCDTが増加することから,血清CDT値の測定は,大酒家を最も特異的に検出する飲酒の生化学的マーカーとされている.しかし,日本人では同じ飲酒習慣であっても血清CDT値が低い傾向にあるという報告もあり,未だ普及していない.今後,測定法の自動化,人種差の生じる原因が解明されCDT値の測定が日本においても普及することが望まれる.
病理
乳がんパラフィン標本におけるHercepTestとFISH法の比較
著者: 伊藤緑 , 柴田典子 , 秋野真也 , 林香織 , 石田廣次 , 谷田部恭
ページ範囲:P.787 - P.792
新しい知見
近年の目覚ましい分子生物学の進歩に伴って,分子標的薬として多数の薬剤が開発されつつあり,一部では臨床応用されている.CD20を標的としたリトキシマブ(rituximab),EGFRを標的としたゲフィチニブ(gefitinib),bcr/ablを標的としたグリベック(R)(メシル酸イマチニブ),今回取り上げたHER2/neuに対するトラスツズマブ(trastuzumab)などが抗腫瘍薬として現在すでに使われている.しかしながらその作用機序はいまだ不明な点が多く,効果が期待できる症例の選択に苦慮することもある.ゲフィチニブは効果のある人には数週間で腫瘍の消失をもたらすにもかかわらず,その予測は臨床的に不可能である.また,間質性肺炎などの副作用を生じる症例もある.このような薬剤はすべて高価であり,費用対効果を考えるうえで,効果のあがる症例を抽出する検査が重要となる.
一般
髄液一般検査の新たな展開
著者: 大田喜孝 , 稲垣清剛 , 油野友二 , 奈良豊 , 石山雅大
ページ範囲:P.793 - P.800
新しい知見
髄液一般検査は中枢神経系の病態を知るうえで重要な役割を担う検査法であるが,その方法論は画一的ではなく,各施設が過去の慣習のまま独自に実施しているのが現状であった.2002年8月,日本臨床衛生検査技師会より「髄液検査法2002」1)が出版された.本書は髄液一般検査の標準化を目的としたガイドラインであり,これまで疑問視されてきた細胞算定法,細胞数の表現法をはじめとし,髄液の取り扱い法,化学物質の測定意義などについて,理論に基づいた明確な見解が示された.
オピニオン
輸血療法委員会と適正輸血―新たな「血液法」施行をふまえて
著者: 比留間潔
ページ範囲:P.780 - P.780
適正輸血はなぜ必要か?
医療はすべて適正であるべきだが,輸血療法には特段の適正性が求められる.血液製剤は献血により得られた人体の一部であるため倫理的観点から他の薬剤以上に適正な使用が求められる.また,免疫性副作用や感染性副作用など一定の不可避的な危険性を有するため,真に必要な場合だけ使用する必要がある.さらに,わが国ではアルブミンや血漿製剤の使用過多が問題になっており,特にアルブミン製剤は60%以上を輸入に依存している.いわゆる薬害エイズを引き起こした非加熱血液凝固因子製剤はすべて輸入製剤であった.
血液製剤適正使用を定めた血液法の実施
適正輸血を進めるために厚生省(現厚生労働省)は血液製剤の使用指針(1999年)を発行しているが,これが必ずしも臨床現場に浸透しているとはいえない.筆者の病院では新人医師を対象に1時間の輸血ガイダンスを行い,輸血業務ルール一般とこの使用指針の概略を説明している.しかし,この使用指針の存在自体を知っている医師は常に半数以下である.これは,輸血医学教育の貧困さも原因と思われるが,医療現場で適正な輸血療法を浸透させる強力なプログラムの必要性を示している.
ラボクイズ
細胞診 6
著者: 亀井美由紀 , 藤井華子
ページ範囲:P.802 - P.802
症例1:34歳,女性.1妊1産.
臨床診断:子宮腟部びらん
主訴:特になし
材料:子宮頸部綿棒擦過標本
図1,2はパパニコロウ染色(Papanicolaou stain)で,対物40倍である.
問題1 下記のうち,どれが最も考えられるか.
① 正常頸管円柱上皮
② 上皮内癌
③ 頸部腺癌(分化型)
④ 子宮体内膜腺癌
⑤ 大腸癌の転移
8月号の解答と解説
著者: 大家辰彦 , 犀川哲典
ページ範囲:P.803 - P.803
【問題1】 解答:③
解説:本例の心電図は上段の四肢誘導記録時には非持続性多形性心室頻拍であり,下段の胸部誘導記録時には洞調律となっている.心室頻拍時も心室性期外収縮2発目が1発目の期外収縮のST部分より生じておりいわゆる R on T から心室頻拍が誘発されている. 洞調律時の心電図を見るとQTが延長しており(QTc=640msec),左から2番目の心室性期外収縮出現直後のQRS波形後のST部分の延長は特に著明である.
このような心電図上QT時間の著明な延長を来す疾患をQT延長症候群と呼び,本例のような多形性心室頻拍(Torsades de Pointes)を生じ失神発作や突然死の原因となる疾患である.通常バゼットの補正式(Bazett's formula)により心拍数補正をした修正QT時間(QTc=QT/√RR)が440msec以上の場合にQT延長と定義する.
絵で見る免疫学 基礎編 45
自然免疫機構と獲得免疫機構の橋渡し(1)―TLR
著者: 高木淳 , 玉井一
ページ範囲:P.804 - P.805
生体は病原体(抗原)に対してまず非特異的な免疫応答が対応し,次いで特異的な免疫応答で防御する.非特異的な免疫応答にかかわるのは自然免疫系におけるマクロファージ,ナチュラルキラー(NK:natural killer)細胞,樹状細胞など抗原特異的なレセプターを持たない細胞である.特異的な免疫応答は獲得免疫系における抗原特異的なレセプターを有するT細胞とB細胞によって行われる.地球上には獲得免疫機構を持っていない多くの生物が存在し,彼らは自然免疫機構だけで病原体を認識して排除している.その機構は食細胞に存在する補体,レクチン,スカベンジャーレセプターを介する貪食作用,そして今回述べるTLR(Toll-like receptor,Toll様レセプター)である.
TLR
ハエは生物が腐敗して微生物が繁殖している場所を好んで生息しわれわれから忌み嫌われている.しかし,このハエにもTollと呼ばれるレセプターが存在し,感染防御をしている.すなわち,ハエは細菌など微生物表面の特異的な分子をTollと呼ばれるレセプターで感知し,抗菌ペプチドを産生し微生物を排除する.最近,ヒトの細胞にもToll様レセプター,すなわちTLRが発見され,Tollと同様に病原微生物に存在する特異的な分子構造を識別する.TLRは,ヒトの多くの細胞,マクロファージ,樹状細胞やT細胞,B細胞などの免疫細胞表面や細胞質内のファゴゾーム(食胞)に存在し,現在10種類のTLRの存在が確認されている.TLRは膜貫通型のレセプターで病原体由来の分子を認識すると細胞質内の多くの物質を経て核に伝達される.種々のサイトカインを発現し,食細胞には細菌のオプソニン化を促すほか,補体系にも活性化を促し,自然免疫系を活性化させて,感染防御機構を誘導する.また,免疫系細胞には活性化に必要なTNF(tumor necrosis factor,腫瘍懐死因子)-α,IL(interleukin)-6,IL-12などの炎症性サイトカインの分泌を促し,獲得免疫系の促進を促す.
検査データを考える
Bicytopenia
著者: 通山薫
ページ範囲:P.813 - P.817
はじめに
赤血球・白血球・血小板3血球系のうちいずれか2つの血球系が減少している状態をbicytopenia,3血球系とも減少している状態を汎血球減少(pancytopenia)という.血球減少の基準としては,成人男子では赤血球数400万個/μl未満またはヘモグロビン濃度13.0g/dl未満,成人女子では赤血球数350万個/μl未満またはヘモグロビン濃度12.0g/dl未満,男女ともに白血球数4,000個/μl未満,血小板数10万個/μl未満が一般的である.貧血の基準は必ずしも統一的ではないが,酸素運搬能に鑑みて赤血球数よりもヘモグロビン濃度のほうが重視されるべきである.
このように複数血球系が減少している場合は,しばしば造血機能自体に重大な問題が生じている可能性がある.あるいは重篤な全身性病変の現れかもしれない.以下に検査上のポイントと日常診療の場で遭遇する疾患について概説する.
けんさアラカルト
薬剤副作用と尿検査
著者: 太田宜秀 , 富野康日己
ページ範囲:P.826 - P.827
薬剤の副作用
最近,医薬品の副作用に関する報道が非常に多い.医薬品を使用したとき,本来の治療目的である治療効果のほかに,目的以外の作用が発現し人体に悪影響を及ぼすことがある.これを総称して医薬品の副作用と呼んでいる.副作用情報は,医薬品の適正使用において重要なものであり,厚生労働省副作用・感染症報告制度としてシステム化されている1).
尿所見に異常がある薬剤
われわれは,日本医薬品集のデータベースを使用し検討した結果,医薬品を服用した際に定期的に尿検査が必要な薬剤および副作用として蛋白尿や血尿がみられる薬剤があることを報告した2).医薬品を服用した際,定期的に尿検査が必要な薬剤は53剤あり,そのうち40剤が非ステロイド性抗炎症薬(nonsteroidal anti-inflammatory drug;NSAID)と呼ばれている解熱鎮痛消炎剤であった.蛋白尿や血尿を引き起こす薬剤とミオグロビン尿を引き起こす薬剤を表に示した.
ラテックス免疫比濁法によるエラスターゼ1
著者: 祖父江晋 , 佐藤悦子 , 針田達行
ページ範囲:P.828 - P.829
はじめに
エラスターゼは,結合組織の弾性線維エラスチンを分解するセリンプロテアーゼで,膵臓・白血球・血小板・脾臓などに存在します.
膵エラスターゼ(EC番号3.4.21.36)は,顆粒球エラスターゼ(EC番号3.4.21.11)とは酵素化学的および免疫化学的に異なる酵素で,さらにエラスターゼ1とエラスターゼ2に分類されます.膵炎や膵癌などの膵疾患において,エラスターゼ1は病態を反映して血中での量が変動するため臨床的意義が見出されています1).エラスターゼ1は血中ではα1 アンチトリプシン(α1AT)などのプロテアーゼインヒビターと結合しているため,アミラーゼのように酵素活性を測定することは不可能です2).
ラテックス免疫比濁法を測定原理とする汎用自動分析装置用のエラスターゼ1測定試薬イアトロIRE1は,血中に存在するα1 AT・エラスターゼ1複合体に対して特異性の高い2種類のモノクローナル抗体をラテックス粒子に感作した試薬です.この試薬により,10分で血中のα1 AT・エラスターゼ1複合体を測定することが可能です(図,表)3).
私の必要な検査/要らない検査
微生物検査―臨床医の立場から
著者: 青木泰子
ページ範囲:P.833 - P.835
感染症の診断と治療に必要な検査は何かという問題は診療における価値観によっても異なり,断定は困難である.一例を挙げれば,市中肺炎における喀痰培養検査の有用性の評価が米国胸部疾患学会ガイドラインでは低く,感染症学会ガイドラインでは高い.一般に感染症専門医は,治療に不可欠な情報かどうかにかかわらず,起因微生物の確定を追求する傾向がある.一方,cost benefitを重視し,感染症であるかどうか,起因微生物が何であるかを確定できなくても,有効な可能性が高く,害にならない治療を選択すればよいので診断確定にはこだわらないという考えもありうる.後者の立場でも,変貌する感染症の起因微生物を捕らえてベストの治療を見いだし続けるために,一定のサーベイランスは必要であるが,その対象,頻度,費用は誰が負担すべきかということは議論の余地があるかもしれない.
以上の理由から,以下の記述は私見であるが,1つのサンプルとして提示する.
微生物検査―検査医の立場から
著者: 菅野治重
ページ範囲:P.836 - P.838
感染症は急性疾患であり迅速な診断と正確な治療が要求される疾患である.しかし現在の培養法を中心とした感染症の検査体系は検査結果を得るまでに時間を要することから,感染症の初期治療に役立つ検査ではない.この反省から迅速性に優れる塗抹検査や抗原検査が見直されている.日本でもDRG/PPS(diagnosis related group/prospective payment system,疾患群別定額払い制度)の導入が予定されており,検査の効率化が急務である.本稿では感染症に関連する検査を整理してみた.
感染症診療の工程
感染症を疑う患者に対する診断と治療法の決定までの工程を以下に示す.
臨床検査フロンティア 検査技術を生かせる新しい職種
健康運動指導士
著者: 河又國士
ページ範囲:P.844 - P.845
資格取得の動機
ある年齢に達したとき自分の老化を感じた.かなり以前に日本医科大学老人病研究所の金子 仁所長が厄年の科学(光文社,1976)を出版され,これを読んで見ろと単行本を手渡された.その中に老化は或る日パッタリ(突然)と記載されていた.
当時はそんなものかナーと思ったくらいで,本当のことは理解できなかった.時が移り,子どもと一緒に歩いている自分が少し遅れているのに気付いても,素直に老化を認めたことはなかった.何人かの友人たちとの会話のなかで最近どうも○○で……などと事例が出て来たころ肉体的老化を認めざるをえなくなり,金子先生のいっておられたことを思い出した.そのころからヒトの老化に興味を持つようになり,マスメディアも高齢化問題や老人医療問題を取り上げることが多くなっていた.
復習のページ
Clue cellが教えてくれたこと―細菌性腟症と妊婦の婦人科細胞診
著者: 渥美鈴恵
ページ範囲:P.846 - P.847
[細菌に導かれて]
細胞診は本来,悪性腫瘍のスクリーニングが目的であるが,顕微鏡下での標本中にはいろいろな病態が反映されており,いわゆる非腫瘍性疾患(感染症など)に対しても推定病変を付記することが浸透しつつある.その1例として,clue cell(平上皮細胞に糸玉状に無数の菌が群がっている細胞)はガルドネレラ(Gardnerella)による非特異性腟炎の指標とされている.しかし,日頃より細菌に親“菌”感(親近感)を持っていた私は,菌の形や大きさ,並び具合などに注目すると,clue cellに違いがあると感じていた.そこで,今回グラム染色(Gram stain)およびパパニコロウ染色(Papanicolaou stain)が同時実施された3,000例について再検討を行ってみた.
[標本中に見られたclue cell(図1~3)]
clue cellを形成する細菌は以下に大別された.
Laboratory Practice 血液:骨髄塗抹標本の見かた
FAB分類 [7]M5a,M5b
著者: 後藤文彦 , 西村敏治
ページ範囲:P.806 - P.809
はじめに
FAB分類は,芽球の形態的特徴を基本にペルオキシダーゼ染色や脂肪染色また非特異的エステラーゼ染色などの細胞化学染色所見を参考として客観的に病型分類を行うことを目的に提唱された1).また今日では電子顕微鏡や免疫細胞化学的所見,遺伝子解析などを適応して分類されるようになった.
本稿では FAB 分類の急性単球性白血病(AMoL:acute monocytic leukemia)の未分化型(M5a)と分化型(M5b)の症例について述べる.
病理:細胞像からここまでわかる
尿(2) 尿路結石症
著者: 堀内啓 , 原田弥生 , 松谷章司
ページ範囲:P.810 - P.812
はじめに
尿路結石症には,腎盂結石症,尿管結石症,膀胱結石症などがある.いずれも,血尿と腰背部痛が主な症状である.尿路系の閉塞を伴う場合には,尿のうっ滞をきたし,水尿管症や水腎症を合併することもある.腎盂炎や膀胱炎などの炎症を合併することも稀でない.診断は,経静脈的腎盂造影やCTなどの画像診断,膀胱鏡で結石を確認することでなされる.尿路結石症に伴い出現する移行上皮細胞はしばしば異型を伴い,移行上皮癌との鑑別に苦慮する場合が多い.したがって,臨床医から尿路結石症の有無についての情報を事前に得ておくことが重要である.
トピックス
インフルエンザ菌ワクチン
著者: 石和田稔彦
ページ範囲:P.848 - P.849
はじめに
インフルエンザ菌は,小児細菌感染症の主要な起炎菌である.インフルエンザ菌のうち,特に病原性の強い血清型b型(Hib)に対するワクチンは1980年代に開発され,現在世界の多くの国々で使用されて劇的な効果をあげている.しかし,残念ながらわが国には未だこのワクチンは導入されていない.一方,気道感染の主体となる無莢きょう膜まく株(NTHi)に対するワクチンは,現在開発途上にある.
本稿ではHibおよびNTHiワクチンについて,その現況を中心に概説する.
秋田(Mody)マウスとインスリン遺伝子異常症
著者: 泉哲郎
ページ範囲:P.849 - P.851
糖尿病モデル・秋田マウスの発見とその原因遺伝子解明
秋田(別名Mody)マウスは,小泉昭夫博士(現京都大学大学院医学研究科)により秋田大学C57BL/6マウスコロニーから発見された,単一遺伝子性糖尿病マウスである1).本マウスは,500mg/dl前後の極めて高い随時血糖値を示し,それに伴い多飲・多尿を呈する.肥満,インスリン抵抗性は示さないが,血中インスリン値,単離膵島からのグルコース刺激に対するインスリン分泌反応は,著しく低下している.遺伝学的解析により,秋田マウス糖尿病の原因遺伝子は,第7番染色体に存在することが明らかにされた.その遺伝形式(常染色体優性遺伝),発症時期(若年発症),病態(膵β細胞の機能異常が一次的原因と考えられる)が,ヒトにおけるMODY(maturity-onset diabetes of the young)と呼ばれるタイプの糖尿病に類似していることから,原因遺伝子座はmouse Modyと命名された.
われわれは,小泉博士と共同でMody遺伝子の同定に取り組み,インスリン2遺伝子の一方の対立遺伝子の点突然変異が,秋田マウス糖尿病の原因であることを発見した2).この変異は,インスリンA鎖第7番目のシステイン残基をチロシン残基に置換し,A・B鎖間の分子内ジスルフィド結合〔S-S〕の1つを形成させなくし,立体構造を大きく変化させることが推察された(図).
キシレン代替剤の検討
著者: 奥野万里子
ページ範囲:P.852 - P.856
はじめに
われわれは病理検査室でブロック作製や各種染色においてキシレンを使用する.キシレンの危険性,有害性については,環境汚染はもちろんのこと,作業環境中の曝露により検査作業従事者に健康障害を引き起こす可能性があることを,従事者自身が軽視することなく認識し,防御のための方法を検討する必要がある.
今月の表紙
精索静脈瘤(varicocele)
著者: 星川久義
ページ範囲:P.801 - P.801
【解説】 図1-a(正面像),b(後面像)は正常者の陰囊部で,陰囊皮膚温は左右対称を示し,温度差が見られない.図2-a(正面像),b(後面像)は触診でGradeと診断された陰囊部で左側の温度が高く,非対称を呈している.図 3-a(正面像),b(後面像)はGrade,図4-a(正面像),b(後面像)はGradeと病態が悪いほど左側の温度が高く,非対称性が顕著となっていることがわかる.
精索静脈瘤(varicocele)とは
精索の静脈が怒張する疾患で,一般に蔓状静脈叢が異常拡張すると考えられているが,挙睾筋静脈が怒張するとする考えかたもある.本症は男性不妊症の原因となることが知られている.
検査じょうほう室 免疫:レベルアップに役立つ免疫検査の基礎知識
蛋白分画データのパターン解析の重要性
著者: 米川修 , 谷脇寛子
ページ範囲:P.818 - P.820
はじめに
血清蛋白分画の目的,臨床検査において必要とされる背景・意義,解析に必要な基本的事項について解説し,当院の症例を基にパターン認識の重要性を示したい.なお,蛋白分画の系統的解析法に関しては文献1を,より詳しい内容については文献2,3にあたることを勧めたい.
血漿中には80種類以上の蛋白が存在し,主なものには,アルブミン,免疫グロブリン,リポ蛋白などがある.これらは,それぞれ重要な生理的機能を果たしている.生体内では,生合成,異化,体内分布などによりバランスが保たれ,一定濃度を維持している.蛋白の異常(欠損症,異常症)は,生理的機能の破綻を来し,なんらかの病態を招く可能性がある.また,各種の病的状態では,動的平衡が崩れ,病態に対応する蛋白の異常が生じることになる.
したがって,蛋白分画に限らず,一連の蛋白の検査は,疾患の診断,病態の把握,治療の効果判定などの重要な情報源となる.なかでも蛋白分画は,病態を反映する蛋白の反応や変化を少ない検体量で簡便に安価に,また総合的に把握できるため病態解析に有益な検査であり,日常初期診療における臨床検査の使い方基本的検査(日本臨床検査医学会)にも収載されている.ただし,迅速性に欠ける面がある.さらに,多発性骨髄腫,ネフロ―ゼ症候群の診断には有用ではあるが,蛋白分画のみで特定の疾患を推定するには無理があり,臨床情報に加え,他の検査データと併せて解析する姿勢が望まれる.
生化学:おさえておきたい生化学の知識
市販漢方強心薬にご注意!
著者: 伏見了
ページ範囲:P.821 - P.823
はじめに
現在,すべての臨床検査は患者の診断,処置および治療において必要不可欠となっているが,これは検査の正確性や精度の向上に尽力された幾多の先人の努力の賜物であり,また試薬や装置の開発や改良に取り組んできた関連企業の方々の功績によるものである.
臨床検査は総合科学に基づく学問であり医学,薬学,生物学,免疫学,電気化学および精密工学などの最新知識の集合体として構成されているが,生化学検査の場合には検査対象が約7g/100mlもの高濃度の蛋白質を含む血清であり,さらに,構造の類似した物質も多数存在する中から特定の物質だけを正確に測定するのはかなり困難なことである.そして,日本国内に限ってもそれぞれの地域で独特の生活習慣や食習慣が存在しており,これらの要因と臨床検査成績とのかかわりを解析することも非常に難しいことと思われる.これに加えて,毎年多くの薬剤が認可され患者に投与されているが,これらの薬剤が使用されているすべての測定法に対して影響があるか否かも当然であるが確認できない.
臨床検査はかなり成熟した学問であるが,このような背景から「摩訶不思議な検査成績」が突然現れる危険性が潜在しており,本稿においてその1例を紹介する.
一般:一般検査のミステリー
一般検査室で遭遇した「変な検体」について
著者: 藤岡鉄男
ページ範囲:P.824 - P.825
はじめに
検査室に提出される検体の多くは医師・看護師・検査技師が患者様から直接採取したものであり,もし臨床症状と矛盾する検体があれば何らかの過誤を疑ってみることも必要となります.
しかし,患者様が自身で採取して提出される尿・便・痰などの場合エッ! と思う「変な検体」に遭遇することがままあります.
ワンポイントアドバイス
栄養サポートチーム(NST) その2 NSTの立ち上げ
著者: 東口髙志
ページ範囲:P.830 - P.831
Metabolic Clubの発足
栄養サポートチーム(NST:nutrition support team)の設立に際して最大の問題となるのは,医師をはじめとするすべての職種における代謝・栄養管理に対する“関心の欠如”である1,2).そこで,まず院内に栄養管理の有用性や正しい栄養管理法を啓発する勉強会“Metabolic Club”を発足することが必要となる.この勉強会の目的は,NST設立まではあくまで病院職員の栄養管理に対する意識を目覚めさせることであり,①毎月1回など定期的に必ず行うこと,②誰にでも理解できるように内容が簡潔であること,③栄養管理の基本がglobal standard(世界標準,日本静脈経腸栄養学会TNTプロジェクトの内容を参照)であることなどが大切なポイントである.
Potluck Party Method(PPM)の導入
わが国においては,いわゆるチーム医療の経験が少なく,その歴史も浅い.したがって各診療科間の壁を取り去った病院全体でのNSTの運営は困難なことが多い.また,欧米と同様の“専属チーム型”のNSTを設立することは,人員削減が叫ばれる今日においてはさらに難しいことである.そこでわが国におけるNSTの新しい形として“Potluck Party Method(PPM)”を考案した1~6).すなわち,各部署・各病棟から1~2名ずつのメンバーを選定し,一般業務を行いながらNSTの仕事も遂行して,各部署や病棟における栄養管理にかかわる問題点や問題症例の抽出を行いNSTの回診やmeetingにてその解決や対策を講じる.また,教育の立場から各部署のNSTメンバー以外の病棟スタッフにも問題点や対策を,また新たに得られた知識などを紹介する.このように“あたかも1皿ずつの料理を持ち寄ってパーティーを行うように,少しずつだが各部署から人・知恵・力を持ち寄ってNSTを運営するシステム”を“Potluck Party Method(持ち寄りパーティー方式)”という名称で呼ぶこととしている1~5).このPPMを導入することによって各部署にできるかぎり迷惑をかけず,しかも参加メンバーの知識や技術を増やし,それが各部署にフィードバックされ,病院全体のレベルアップにつながるような医療チームの結成が可能となる.
けんさ質問箱Q&A
アルシアン青染色の大動脈への応用
著者: 鈴木慶二
ページ範囲:P.839 - P.840
Q アルシアン青染色の大動脈への応用
主として上皮粘液細胞の分泌するムチンなどの証明に用いられるアルシアン青染色(多糖類染色)を大動脈など血管に応用する場合,どのような意義があるのでしょうか.また,どのようなところを観察するのに使うのでしょうか.教えてください.(名古屋市 T. K. 生)
A アルシアン青染色のアルシアン青8GSは,塩基性で水溶性のphthalocyanine系色素で,銅イオンを持ち,組織中に存在する親水性で陰性荷電を有するグリコサミノグリカン〔glycosaminoglycan,酸性ムコ多糖(mucopolysaccharide)〕を染色します.アルシアン青8GSはpH2.5でカルボキシル基と硫酸基の両者と結合し,pH1.0では硫酸基とのみ結合します.そのため組織染色においては,pH2.5アルシアン青染色では組織中のグリコサミノグリカンは強く染色され,pH1.0では染色が弱くなります.
耳音響反射検査の進めかたと結果の読みかたは
著者: 渡辺尚彦
ページ範囲:P.840 - P.842
Q 耳音響反射検査の進めかたと結果の読みかたは
耳音響反射検査では自発音反射,誘発音響反射,結合音響反射(DPOAE)を行いますがこれらの進めかたと結果の読みかたを教えてください.(福岡市 Y. K. 生)
A はじめに
誘発耳音響反射(transient evoked otoacoustic emissions;TEOAE)は1978年Kemp1) により報告された内耳発振の音響現象である.
コーヒーブレイク
山歩き・街道歩き―30 登山口
著者: 勝田祐年
ページ範囲:P.843 - P.843
「車の運転免許証を持っていない」というと,「エッ!」と,驚かれてしまう.驚かれついでに,パスポートもなし,携帯電話も持っていないことも告白する.「今時,珍しいですね,博物館物ですよ」.
そんな“博物館展示物”が登山をするには登山口までの足は電車,バス,タクシー,徒歩ということになる.貧乏登山なのでタクシーは利用したことがない.バス便がない場合は登山口まで10kmぐらい歩くのはざらである.ようやく辿り着いた登山口周辺の山林が土地開発され,1戸建てや高層の家屋が建ち並び,自然が都会に侵食されている光景に出くわす.登山口がどこにあるかわからない.団地の外延に沿って歩き回り,登山口を探す羽目になる.個人の敷地内に入り込んでしまったり,犬に吠えられることも度々ある.犬に吠えられたとき,猫の鳴き真似をする.さらに激しく吠える犬と,キョトンとした顔で押し黙る犬とがある.飼い主もキョトンとしているにちがいない.
基本情報
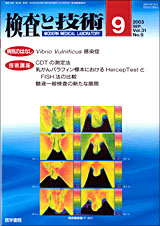
バックナンバー
52巻12号(2024年12月発行)
技術講座 生理
52巻11号(2024年11月発行)
技術講座 生理
52巻10号(2024年10月発行)
技術講座 生理
52巻9号(2024年9月発行)
増大号 臨床医に伝わりやすい 検査報告書とパニック値報告の心得
52巻8号(2024年8月発行)
技術講座 生理
52巻7号(2024年7月発行)
技術講座 生理
52巻6号(2024年6月発行)
技術講座 生理
52巻5号(2024年5月発行)
技術講座 その他
52巻4号(2024年4月発行)
技術講座 生理
52巻3号(2024年3月発行)
増大号 POCUSの決め手。 早く、正確な診断のために
52巻2号(2024年2月発行)
技術講座 生理
52巻1号(2024年1月発行)
技術講座 その他
51巻12号(2023年12月発行)
技術講座 生理
51巻11号(2023年11月発行)
技術講座 生理
51巻10号(2023年10月発行)
技術講座 その他
51巻9号(2023年9月発行)
増大号 匠から学ぶ 血栓止血検査ガイド
51巻8号(2023年8月発行)
技術講座 生理
51巻7号(2023年7月発行)
技術講座 生理
51巻6号(2023年6月発行)
技術講座 生理
51巻5号(2023年5月発行)
技術講座 生理
51巻4号(2023年4月発行)
技術講座 生理
51巻3号(2023年3月発行)
増大号 症例から学ぶ 疾患と検査値の推移
51巻2号(2023年2月発行)
技術講座 その他
51巻1号(2023年1月発行)
技術講座 生理
50巻12号(2022年12月発行)
技術講座 その他
50巻11号(2022年11月発行)
技術講座 生理
50巻10号(2022年10月発行)
技術講座 生理
50巻9号(2022年9月発行)
増大号 希少例と特殊像がわかる! エコーの撮り方完全マスター
50巻8号(2022年8月発行)
技術講座 生理
50巻7号(2022年7月発行)
技術講座 生理
50巻6号(2022年6月発行)
技術講座 生理
50巻5号(2022年5月発行)
技術講座 生理
50巻4号(2022年4月発行)
技術講座 生理
50巻3号(2022年3月発行)
増大号 見て学ぶ 一般検査学アトラス—外観検査から顕微鏡検査まで
50巻2号(2022年2月発行)
技術講座 その他
50巻1号(2022年1月発行)
技術講座 生理
49巻12号(2021年12月発行)
技術講座 生理
49巻11号(2021年11月発行)
技術講座 生理
49巻10号(2021年10月発行)
技術講座 生理
49巻9号(2021年9月発行)
増刊号 病態別 腹部エコーの観察・記録・報告書作成マスター
49巻8号(2021年8月発行)
技術講座 生理
49巻7号(2021年7月発行)
技術講座 生理
49巻6号(2021年6月発行)
技術講座 生理
49巻5号(2021年5月発行)
技術講座 生理
49巻4号(2021年4月発行)
技術講座 一般
49巻3号(2021年3月発行)
増刊号 First&Next Step 微生物検査サポートブック
49巻2号(2021年2月発行)
技術講座 微生物
49巻1号(2021年1月発行)
技術講座 病理・生理
48巻12号(2020年12月発行)
技術講座 その他
48巻11号(2020年11月発行)
技術講座 生化学
48巻10号(2020年10月発行)
技術講座 生理
48巻9号(2020年9月発行)
増刊号 学会発表・論文執筆はもう怖くない! 臨床検査技師のための研究入門
48巻8号(2020年8月発行)
技術講座 遺伝子
48巻7号(2020年7月発行)
技術講座 その他
48巻6号(2020年6月発行)
技術講座 輸血
48巻5号(2020年5月発行)
技術講座 生化学
48巻4号(2020年4月発行)
技術講座 生理
48巻3号(2020年3月発行)
増刊号 採血のすべて—手技から採血室の運用まで徹底解説
48巻2号(2020年2月発行)
技術講座 微生物
48巻1号(2020年1月発行)
技術講座 生理
47巻12号(2019年12月発行)
技術講座 病理
47巻11号(2019年11月発行)
技術講座 生理
47巻10号(2019年10月発行)
技術講座 生理
47巻9号(2019年9月発行)
増刊号 染色画像を比べて学ぶ 体腔液アトラス
47巻8号(2019年8月発行)
技術講座 病理
47巻7号(2019年7月発行)
技術講座 一般
47巻6号(2019年6月発行)
技術講座 血液
47巻5号(2019年5月発行)
技術講座 血液
47巻4号(2019年4月発行)
技術講座 血液
47巻3号(2019年3月発行)
増刊号 エキスパートが教える 心・血管エコー計測のノウハウ
47巻2号(2019年2月発行)
技術講座 病理
47巻1号(2019年1月発行)
技術講座 微生物
46巻12号(2018年12月発行)
技術講座 生理
46巻11号(2018年11月発行)
技術講座 輸血・遺伝子検査
46巻10号(2018年10月発行)
技術講座 その他
46巻9号(2018年9月発行)
増刊号 現場で“パッ”と使える 免疫染色クイックガイド
46巻8号(2018年8月発行)
技術講座 輸血・遺伝子検査
46巻7号(2018年7月発行)
技術講座 生理
46巻6号(2018年6月発行)
技術講座 管理
46巻5号(2018年5月発行)
技術講座 生化学
46巻4号(2018年4月発行)
技術講座 一般
46巻3号(2018年3月発行)
増刊号 感染症クイックリファレンス
46巻2号(2018年2月発行)
技術講座 輸血
46巻1号(2018年1月発行)
技術講座 病理
45巻12号(2017年12月発行)
技術講座 生理
45巻11号(2017年11月発行)
技術講座 一般
45巻10号(2017年10月発行)
技術講座 微生物
45巻9号(2017年9月発行)
増刊号 循環器病院の技師が教える メディカルスタッフのための心電図教室
45巻8号(2017年8月発行)
技術講座 栄養
45巻7号(2017年7月発行)
技術講座 病理
45巻6号(2017年6月発行)
技術講座 病理
45巻5号(2017年5月発行)
技術講座 細胞治療・管理
45巻4号(2017年4月発行)
技術講座 遺伝子・染色体検査
45巻3号(2017年3月発行)
45巻2号(2017年2月発行)
技術講座 細胞治療
45巻1号(2017年1月発行)
技術講座 病理
44巻13号(2016年12月発行)
技術講座 免疫
44巻12号(2016年11月発行)
技術講座 微生物
44巻11号(2016年10月発行)
技術講座 微生物
44巻10号(2016年9月発行)
増刊号 はじめて出会う 検査画像
44巻9号(2016年9月発行)
技術講座 管理・その他
44巻8号(2016年8月発行)
技術講座 微生物
44巻7号(2016年7月発行)
技術講座 生理
44巻6号(2016年6月発行)
技術講座 微生物
44巻5号(2016年5月発行)
技術講座 生理
44巻4号(2016年4月発行)
技術講座 微生物
44巻3号(2016年3月発行)
技術講座 生理
44巻2号(2016年2月発行)
技術講座 微生物
44巻1号(2016年1月発行)
技術講座 微生物
43巻13号(2015年12月発行)
技術講座 生化学
43巻12号(2015年11月発行)
技術講座 生化学
43巻11号(2015年10月発行)
技術講座 一般
43巻10号(2015年9月発行)
増刊号 血液形態アトラス
43巻9号(2015年9月発行)
技術講座 生理
43巻8号(2015年8月発行)
技術講座 生理
43巻7号(2015年7月発行)
技術講座 生理
43巻6号(2015年6月発行)
技術講座 微生物
43巻5号(2015年5月発行)
技術講座 移植医療
43巻4号(2015年4月発行)
技術講座 病理
43巻3号(2015年3月発行)
技術講座 血液
43巻2号(2015年2月発行)
技術講座 管理
43巻1号(2015年1月発行)
技術講座 病理
42巻13号(2014年12月発行)
技術講座 生化学
42巻12号(2014年11月発行)
技術講座 病理
42巻11号(2014年10月発行)
技術講座 血液
42巻10号(2014年9月発行)
増刊号 超音波×病理 対比アトラス
42巻9号(2014年9月発行)
技術講座 生理
42巻8号(2014年8月発行)
技術講座 免疫
42巻7号(2014年7月発行)
技術講座 生理
42巻6号(2014年6月発行)
技術講座 生理
42巻5号(2014年5月発行)
技術講座 病理
42巻4号(2014年4月発行)
技術講座 輸血
42巻3号(2014年3月発行)
技術講座 血液
42巻2号(2014年2月発行)
技術講座 微生物
42巻1号(2014年1月発行)
技術講座 病理
41巻13号(2013年12月発行)
技術講座 生理
41巻12号(2013年11月発行)
技術講座 生化学
41巻11号(2013年10月発行)
技術講座 生化学
41巻10号(2013年9月発行)
増刊号 解剖と正常像がわかる! エコーの撮り方完全マスター
41巻9号(2013年9月発行)
技術講座 微生物
41巻8号(2013年8月発行)
技術講座 生理
41巻7号(2013年7月発行)
技術講座 生理
41巻6号(2013年6月発行)
技術講座 微生物
41巻5号(2013年5月発行)
技術講座 一般
41巻4号(2013年4月発行)
技術講座 生化学
41巻3号(2013年3月発行)
技術講座 生理
41巻2号(2013年2月発行)
技術講座 生理
41巻1号(2013年1月発行)
技術講座 生理
40巻13号(2012年12月発行)
技術講座 血液
40巻12号(2012年11月発行)
技術講座 生理
40巻11号(2012年10月発行)
技術講座 生理
40巻10号(2012年9月発行)
増刊号 この検査データを読めますか?―検査値から病態を探る
40巻9号(2012年9月発行)
技術講座 生理
40巻8号(2012年8月発行)
技術講座 細胞診
40巻7号(2012年7月発行)
技術講座 生理
40巻6号(2012年6月発行)
技術講座 生理
40巻5号(2012年5月発行)
技術講座 生理
40巻4号(2012年4月発行)
技術講座 血液
40巻3号(2012年3月発行)
技術講座 生理
40巻2号(2012年2月発行)
技術講座 輸血
40巻1号(2012年1月発行)
技術講座 遺伝子
39巻13号(2011年12月発行)
疾患と検査値の推移
39巻12号(2011年11月発行)
疾患と検査値の推移
39巻11号(2011年10月発行)
疾患と検査値の推移
39巻10号(2011年9月発行)
増刊号 緊急報告すべき検査結果のすべて―すぐに使えるパニック値事典
39巻9号(2011年9月発行)
疾患と検査値の推移
39巻8号(2011年8月発行)
疾患と検査値の推移
39巻7号(2011年7月発行)
疾患と検査値の推移
39巻6号(2011年6月発行)
技術講座 生理
39巻5号(2011年5月発行)
技術講座 生理
39巻4号(2011年4月発行)
疾患と検査値の推移
39巻3号(2011年3月発行)
疾患と検査値の推移
39巻2号(2011年2月発行)
疾患と検査値の推移
39巻1号(2011年1月発行)
疾患と検査値の推移
38巻13号(2010年12月発行)
疾患と検査値の推移
38巻12号(2010年11月発行)
疾患と検査値の推移
38巻11号(2010年10月発行)
疾患と検査値の推移
38巻10号(2010年9月発行)
増刊号 免疫反応と臨床検査2010
38巻9号(2010年9月発行)
疾患と検査値の推移
38巻8号(2010年8月発行)
疾患と検査値の推移
38巻7号(2010年7月発行)
疾患と検査値の推移
38巻6号(2010年6月発行)
疾患と検査値の推移
38巻5号(2010年5月発行)
疾患と検査値の推移
38巻4号(2010年4月発行)
疾患と検査値の推移
38巻3号(2010年3月発行)
疾患と検査値の推移
38巻2号(2010年2月発行)
疾患と検査値の推移
38巻1号(2010年1月発行)
疾患と検査値の推移
37巻13号(2009年12月発行)
疾患と検査値の推移
37巻12号(2009年11月発行)
疾患と検査値の推移
37巻11号(2009年10月発行)
疾患と検査値の推移
37巻10号(2009年9月発行)
増刊号 顕微鏡検査のコツ―臨床に役立つ形態学
37巻9号(2009年9月発行)
疾患と検査値の推移
37巻8号(2009年8月発行)
疾患と検査値の推移
37巻7号(2009年7月発行)
疾患と検査値の推移
37巻6号(2009年6月発行)
疾患と検査値の推移
37巻5号(2009年5月発行)
疾患と検査値の推移
37巻4号(2009年4月発行)
疾患と検査値の推移
37巻3号(2009年3月発行)
疾患と検査値の推移
37巻2号(2009年2月発行)
疾患と検査値の推移
37巻1号(2009年1月発行)
疾患と検査値の推移
36巻13号(2008年12月発行)
疾患と検査値の推移
36巻12号(2008年11月発行)
疾患と検査値の推移
36巻11号(2008年10月発行)
疾患と検査値の推移
36巻10号(2008年9月発行)
増刊号 これから広がる生理検査・新たにはじまる生理検査
36巻9号(2008年9月発行)
疾患と検査値の推移
36巻8号(2008年8月発行)
疾患と検査値の推移
36巻7号(2008年7月発行)
疾患と検査値の推移
36巻6号(2008年6月発行)
疾患と検査値の推移
36巻5号(2008年5月発行)
疾患と検査値の推移
36巻4号(2008年4月発行)
疾患と検査値の推移
36巻3号(2008年3月発行)
疾患と検査値の推移
36巻2号(2008年2月発行)
疾患と検査値の推移
36巻1号(2008年1月発行)
疾患と検査値の推移
35巻13号(2007年12月発行)
疾患と検査値の推移
35巻12号(2007年11月発行)
疾患と検査値の推移
35巻11号(2007年10月発行)
増刊号 メタボリックシンドローム健診検査技術マニュアル
35巻10号(2007年10月発行)
疾患と検査値の推移
35巻9号(2007年9月発行)
疾患と検査値の推移
35巻8号(2007年8月発行)
疾患と検査値の推移
35巻7号(2007年7月発行)
疾患と検査値の推移
35巻6号(2007年6月発行)
疾患と検査値の推移
35巻5号(2007年5月発行)
疾患と検査値の推移
35巻4号(2007年4月発行)
疾患と検査値の推移
35巻3号(2007年3月発行)
疾患と検査値の推移
35巻2号(2007年2月発行)
疾患と検査値の推移
35巻1号(2007年1月発行)
疾患と検査値の推移
34巻13号(2006年12月発行)
技術講座 生理
34巻12号(2006年11月発行)
技術講座 一般
34巻11号(2006年10月発行)
増刊号 新しい臨床検査・未来の臨床検査
34巻10号(2006年10月発行)
疾患と検査値の推移
34巻9号(2006年9月発行)
疾患と検査値の推移
34巻8号(2006年8月発行)
疾患と検査値の推移
34巻7号(2006年7月発行)
疾患と検査値の推移
34巻6号(2006年6月発行)
疾患と検査値の推移
34巻5号(2006年5月発行)
疾患と検査値の推移
34巻4号(2006年4月発行)
疾患と検査値の推移
34巻3号(2006年3月発行)
疾患と検査値の推移
34巻2号(2006年2月発行)
疾患と検査値の推移
34巻1号(2006年1月発行)
疾患と検査値の推移
33巻13号(2005年12月発行)
疾患と検査値の推移
33巻12号(2005年11月発行)
疾患と検査値の推移
33巻11号(2005年10月発行)
増刊号 一線診療のための臨床検査
33巻10号(2005年10月発行)
疾患と検査値の推移
33巻9号(2005年9月発行)
疾患と検査値の推移
33巻8号(2005年8月発行)
疾患と検査値の推移
33巻7号(2005年7月発行)
疾患と検査値の推移
33巻6号(2005年6月発行)
疾患と検査値の推移
33巻5号(2005年5月発行)
疾患と検査値の推移
33巻4号(2005年4月発行)
疾患と検査値の推移
33巻3号(2005年3月発行)
疾患と検査値の推移
33巻2号(2005年2月発行)
疾患と検査値の推移
33巻1号(2005年1月発行)
疾患と検査値の推移
32巻13号(2004年12月発行)
技術講座 血液
32巻12号(2004年11月発行)
技術講座 病理
32巻11号(2004年10月発行)
技術講座 血液
32巻10号(2004年9月発行)
増刊号 細胞像の見かた―病理・血液・尿沈渣
32巻9号(2004年9月発行)
技術講座 生化学
32巻8号(2004年8月発行)
技術講座 免疫
32巻7号(2004年7月発行)
技術講座 微生物
32巻6号(2004年6月発行)
技術講座 病理
32巻5号(2004年5月発行)
技術講座 病理
32巻4号(2004年4月発行)
技術講座 病理
32巻3号(2004年3月発行)
技術講座 微生物
32巻2号(2004年2月発行)
技術講座 生化学
32巻1号(2004年1月発行)
技術講座 微生物
31巻13号(2003年12月発行)
技術講座 微生物
31巻12号(2003年11月発行)
技術講座 病理
31巻11号(2003年10月発行)
技術講座 微生物
31巻10号(2003年9月発行)
増刊号 包括医療と臨床検査
31巻9号(2003年9月発行)
技術講座 一般
31巻8号(2003年8月発行)
技術講座 微生物
31巻7号(2003年7月発行)
技術講座 病理
31巻6号(2003年6月発行)
技術講座 免疫
31巻5号(2003年5月発行)
技術講座 一般
31巻4号(2003年4月発行)
技術講座 病理
31巻3号(2003年3月発行)
技術講座 生化学
31巻2号(2003年2月発行)
技術講座 免疫
31巻1号(2003年1月発行)
技術講座 免疫
30巻13号(2002年12月発行)
技術講座 生理
30巻12号(2002年11月発行)
技術講座 生理
30巻11号(2002年10月発行)
技術講座 生化学
30巻10号(2002年9月発行)
増刊号 誰でもわかる遺伝子検査
30巻9号(2002年9月発行)
技術講座 微生物
30巻8号(2002年8月発行)
技術講座 生化学
30巻7号(2002年7月発行)
技術講座 微生物
30巻6号(2002年6月発行)
技術講座 生化学
30巻5号(2002年5月発行)
技術講座 微生物
30巻4号(2002年4月発行)
技術講座 一般
30巻3号(2002年3月発行)
技術講座 生化学
30巻2号(2002年2月発行)
技術講座 一般
30巻1号(2002年1月発行)
技術講座 免疫
29巻13号(2001年12月発行)
技術講座 病理
29巻12号(2001年11月発行)
技術講座 生理
29巻11号(2001年10月発行)
技術講座 病理
29巻10号(2001年9月発行)
技術講座 病理
29巻9号(2001年8月発行)
技術講座 病理
29巻8号(2001年7月発行)
技術講座 生理
29巻7号(2001年6月発行)
増刊号 病理組織・細胞診のための日常染色法ガイダンス
29巻6号(2001年6月発行)
技術講座 微生物
29巻5号(2001年5月発行)
技術講座 生理
29巻4号(2001年4月発行)
技術講座 病理
29巻3号(2001年3月発行)
技術講座 微生物
29巻2号(2001年2月発行)
技術講座 微生物
29巻1号(2001年1月発行)
技術講座 一般
28巻13号(2000年12月発行)
技術講座 病理
28巻12号(2000年11月発行)
技術講座 病理
28巻11号(2000年10月発行)
技術講座 免疫
28巻10号(2000年9月発行)
技術講座 微生物
28巻9号(2000年8月発行)
技術講座 微生物
28巻8号(2000年7月発行)
技術講座 生理
28巻7号(2000年6月発行)
増刊号 血液検査実践マニュアル
28巻6号(2000年6月発行)
技術講座 免疫
28巻5号(2000年5月発行)
技術講座 血液
28巻4号(2000年4月発行)
技術講座 一般
28巻3号(2000年3月発行)
技術講座 生理
28巻2号(2000年2月発行)
技術講座 生化学
28巻1号(2000年1月発行)
技術講座 一般
27巻13号(1999年12月発行)
技術講座 病理
27巻12号(1999年11月発行)
技術講座 一般
27巻11号(1999年10月発行)
技術講座 生化学
27巻10号(1999年9月発行)
技術講座 免疫
27巻9号(1999年8月発行)
技術講座 病理
27巻8号(1999年7月発行)
技術講座 病理
27巻7号(1999年6月発行)
増刊号 緊急検査実践マニュアル
27巻6号(1999年6月発行)
技術講座 生化学
27巻5号(1999年5月発行)
技術講座 血液
27巻4号(1999年4月発行)
技術講座 一般
27巻3号(1999年3月発行)
技術講座 生理
27巻2号(1999年2月発行)
技術講座 微生物
27巻1号(1999年1月発行)
技術講座 生理
26巻13号(1998年12月発行)
技術講座 一般
26巻12号(1998年11月発行)
技術講座 病理
26巻11号(1998年10月発行)
技術講座 病理
26巻10号(1998年9月発行)
技術講座 生理
26巻9号(1998年8月発行)
技術講座 生理
26巻8号(1998年7月発行)
技術講座 生理
26巻7号(1998年6月発行)
増刊号 病理組織・細胞診実践マニュアル
26巻6号(1998年6月発行)
技術講座 病理
26巻5号(1998年5月発行)
技術講座 一般
26巻4号(1998年4月発行)
技術講座 病理
26巻3号(1998年3月発行)
技術講座 一般
26巻2号(1998年2月発行)
技術講座 生理
26巻1号(1998年1月発行)
技術講座 血液
25巻13号(1997年12月発行)
技術講座 一般
25巻12号(1997年11月発行)
技術講座 一般
25巻11号(1997年10月発行)
技術講座 生理
25巻10号(1997年9月発行)
技術講座 血液
25巻9号(1997年8月発行)
技術講座 一般
25巻8号(1997年7月発行)
技術講座 一般
25巻7号(1997年6月発行)
増刊号 輸血検査実践マニュアル
25巻6号(1997年6月発行)
技術講座 免疫
25巻5号(1997年5月発行)
技術講座 生理
25巻4号(1997年4月発行)
技術講座 生理
25巻3号(1997年3月発行)
技術講座 微生物
25巻2号(1997年2月発行)
技術講座 生理
25巻1号(1997年1月発行)
技術講座 一般
24巻13号(1996年12月発行)
技術講座 生理
24巻12号(1996年11月発行)
技術講座 一般
24巻11号(1996年10月発行)
技術講座 生理
24巻10号(1996年9月発行)
技術講座 管理
24巻9号(1996年8月発行)
技術講座 生理
24巻8号(1996年7月発行)
技術講座 生理
24巻7号(1996年6月発行)
増刊号 感染症検査実践マニュアル
24巻6号(1996年6月発行)
技術講座 病理
24巻5号(1996年5月発行)
技術講座 生理
24巻4号(1996年4月発行)
技術講座 生理
24巻3号(1996年3月発行)
技術講座 生理
24巻2号(1996年2月発行)
技術講座 生理
24巻1号(1996年1月発行)
技術講座 一般
23巻13号(1995年12月発行)
技術講座 生理
23巻12号(1995年11月発行)
技術講座 病理
23巻11号(1995年10月発行)
技術講座 微生物
23巻10号(1995年9月発行)
技術講座 生理
23巻9号(1995年8月発行)
技術講座 一般
23巻8号(1995年7月発行)
技術講座 免疫
23巻7号(1995年6月発行)
技術講座 生理
23巻6号(1995年5月発行)
技術講座 一般
23巻5号(1995年4月発行)
増刊号 臨床生理検査実践マニュアル画像検査を中心として
23巻4号(1995年4月発行)
技術講座 病理
23巻3号(1995年3月発行)
技術講座 病理
23巻2号(1995年2月発行)
技術講座 一般
23巻1号(1995年1月発行)
技術講座 生理
22巻13号(1994年12月発行)
技術講座 一般
22巻12号(1994年11月発行)
技術講座 一般
22巻11号(1994年10月発行)
技術講座 一般
22巻10号(1994年9月発行)
技術講座 一般
22巻9号(1994年8月発行)
技術講座 生理
22巻8号(1994年7月発行)
技術講座 病理
22巻7号(1994年6月発行)
技術講座 一般
22巻6号(1994年5月発行)
技術講座 一般
22巻5号(1994年4月発行)
増刊号 免疫検査実践マニュアル
22巻4号(1994年4月発行)
技術講座 生理
22巻3号(1994年3月発行)
技術講座 免疫
22巻2号(1994年2月発行)
技術講座 一般
22巻1号(1994年1月発行)
技術講座 生理
21巻13号(1993年12月発行)
技術講座 一般
21巻12号(1993年11月発行)
技術講座 一般
21巻11号(1993年10月発行)
技術講座 一般
21巻10号(1993年9月発行)
技術講座 生理
21巻9号(1993年8月発行)
技術講座 一般
21巻8号(1993年7月発行)
技術講座 病理
21巻7号(1993年6月発行)
技術講座 一般
21巻6号(1993年5月発行)
技術講座 生理
21巻5号(1993年4月発行)
増刊号 臨床化学実践マニュアル
21巻4号(1993年4月発行)
技術講座 生理
21巻3号(1993年3月発行)
技術講座 病理
21巻2号(1993年2月発行)
技術講座 生理
21巻1号(1993年1月発行)
技術講座 生理
20巻13号(1992年12月発行)
技術講座 一般
20巻12号(1992年11月発行)
技術講座 一般
20巻11号(1992年10月発行)
技術講座 一般
20巻10号(1992年9月発行)
技術講座 一般
20巻9号(1992年8月発行)
技術講座 一般
20巻8号(1992年7月発行)
技術講座 血液
20巻7号(1992年6月発行)
技術講座 一般
20巻6号(1992年5月発行)
増刊号 尿検査法
20巻5号(1992年5月発行)
技術講座 生理
20巻4号(1992年4月発行)
技術講座 生理
20巻3号(1992年3月発行)
技術講座 病理
20巻2号(1992年2月発行)
技術講座 一般
20巻1号(1992年1月発行)
技術講座 生理
19巻13号(1991年12月発行)
技術講座 管理
19巻12号(1991年11月発行)
技術講座 生理
19巻11号(1991年10月発行)
技術講座 生理
19巻10号(1991年9月発行)
技術講座 一般
19巻9号(1991年8月発行)
技術講座 一般
19巻8号(1991年7月発行)
技術講座 生理
19巻7号(1991年6月発行)
増刊号 臨床血液検査
19巻6号(1991年6月発行)
技術講座 生理
19巻5号(1991年5月発行)
技術講座 生理
19巻4号(1991年4月発行)
技術講座 一般
19巻3号(1991年3月発行)
技術講座 生理
19巻2号(1991年2月発行)
技術講座 生理
19巻1号(1991年1月発行)
技術講座 一般
18巻13号(1990年12月発行)
技術講座 生理
18巻12号(1990年11月発行)
技術講座 微生物
18巻11号(1990年10月発行)
技術講座 生理
18巻10号(1990年9月発行)
技術講座 一般
18巻9号(1990年8月発行)
技術講座 一般
18巻8号(1990年7月発行)
技術講座 一般
18巻7号(1990年6月発行)
技術講座 一般
18巻6号(1990年5月発行)
増刊号 血液・尿以外の体液検査法
18巻5号(1990年5月発行)
技術講座 一般
18巻4号(1990年4月発行)
技術講座 一般
18巻3号(1990年3月発行)
技術講座 血液
18巻2号(1990年2月発行)
技術講座 生理
18巻1号(1990年1月発行)
技術講座 生理
17巻13号(1989年12月発行)
技術講座 一般
17巻12号(1989年11月発行)
技術講座 一般
17巻11号(1989年10月発行)
技術講座 一般
17巻10号(1989年9月発行)
技術講座 一般
17巻9号(1989年8月発行)
技術講座 生理
17巻8号(1989年7月発行)
技術講座 血清
17巻7号(1989年6月発行)
技術講座 一般
17巻6号(1989年5月発行)
感染症の検査法 Ⅲ 検査法各論
17巻5号(1989年5月発行)
技術講座 一般
17巻4号(1989年4月発行)
技術講座 生理
17巻3号(1989年3月発行)
技術講座 病理
17巻2号(1989年2月発行)
技術講座 一般
17巻1号(1989年1月発行)
技術講座 生理
16巻13号(1988年12月発行)
技術講座 一般
16巻12号(1988年11月発行)
技術講座 一般
16巻11号(1988年10月発行)
技術講座 一般
16巻10号(1988年9月発行)
技術講座 生理
16巻9号(1988年8月発行)
技術講座 一般
16巻8号(1988年7月発行)
技術講座 一般
16巻7号(1988年6月発行)
免疫化学検査法 資料
16巻6号(1988年6月発行)
技術講座 一般
16巻5号(1988年5月発行)
技術講座 一般
16巻4号(1988年4月発行)
技術講座 病理
16巻3号(1988年3月発行)
技術講座 生理
16巻2号(1988年2月発行)
技術講座 一般
16巻1号(1988年1月発行)
技術講座 血液
15巻13号(1987年12月発行)
技術講座 一般
15巻12号(1987年11月発行)
技術講座 病理
15巻11号(1987年10月発行)
技術講座 細胞診
15巻10号(1987年9月発行)
技術講座 一般
15巻9号(1987年8月発行)
技術講座 細胞診
15巻8号(1987年7月発行)
技術講座 病理
15巻7号(1987年6月発行)
技術講座 病理
15巻6号(1987年5月発行)
技術講座 病理
15巻5号(1987年4月発行)
臨床生理検査と技術 座談会
15巻4号(1987年4月発行)
技術講座 生理
15巻3号(1987年3月発行)
技術講座 血液
15巻2号(1987年2月発行)
技術講座 一般
15巻1号(1987年1月発行)
技術講座 病理
14巻13号(1986年12月発行)
技術講座 一般
14巻12号(1986年11月発行)
技術講座 病理
14巻11号(1986年10月発行)
技術講座 血清
14巻10号(1986年9月発行)
技術講座 血清
14巻9号(1986年8月発行)
技術講座 生理
14巻8号(1986年7月発行)
技術講座 血清
14巻7号(1986年6月発行)
技術講座 病理
14巻6号(1986年5月発行)
技術講座 生理
14巻5号(1986年4月発行)
形態学的検査と技術 血液と病理
14巻4号(1986年4月発行)
技術講座 病理
14巻3号(1986年3月発行)
技術講座 細菌
14巻2号(1986年2月発行)
技術講座 病理
14巻1号(1986年1月発行)
技術講座 細菌
13巻12号(1985年12月発行)
技術講座 病理
13巻11号(1985年11月発行)
技術講座 病理
13巻10号(1985年10月発行)
技術講座 生理
13巻9号(1985年9月発行)
技術講座 病理
13巻8号(1985年8月発行)
技術講座 病理
13巻7号(1985年7月発行)
技術講座 血液
13巻6号(1985年6月発行)
技術講座 一般
13巻5号(1985年5月発行)
技術講座 病理
13巻4号(1985年4月発行)
技術講座 一般
13巻3号(1985年3月発行)
技術講座 血液
13巻2号(1985年2月発行)
技術講座 一般
13巻1号(1985年1月発行)
技術講座 血液
12巻12号(1984年12月発行)
技術講座 血液
12巻11号(1984年11月発行)
技術講座 病理
12巻10号(1984年10月発行)
技術講座 輸血
12巻9号(1984年9月発行)
技術講座 一般
12巻8号(1984年8月発行)
技術講座 細菌
12巻7号(1984年7月発行)
技術講座 細菌
12巻6号(1984年6月発行)
技術講座 生理
12巻5号(1984年5月発行)
技術講座 一般
12巻4号(1984年4月発行)
技術講座 病理
12巻3号(1984年3月発行)
技術講座 血液
12巻2号(1984年2月発行)
技術講座 一般
12巻1号(1983年12月発行)
技術講座 血清
11巻12号(1983年12月発行)
技術講座 一般
11巻11号(1983年11月発行)
技術講座 細菌
11巻10号(1983年10月発行)
技術講座 細胞診
11巻9号(1983年9月発行)
技術講座 一般
11巻8号(1983年8月発行)
技術講座 血清
11巻7号(1983年7月発行)
技術講座 細菌
11巻6号(1983年6月発行)
技術講座 一般
11巻5号(1983年5月発行)
技術講座 病理
11巻4号(1983年4月発行)
技術講座 一般
11巻3号(1983年3月発行)
技術講座 血液
11巻2号(1983年2月発行)
技術講座 一般
11巻1号(1983年1月発行)
技術講座 血液
10巻12号(1982年12月発行)
技術講座 一般
10巻11号(1982年11月発行)
技術講座 生理
10巻10号(1982年10月発行)
技術講座 血清
10巻9号(1982年9月発行)
技術講座 細菌
10巻8号(1982年8月発行)
技術講座 一般
10巻7号(1982年7月発行)
技術講座 病理
10巻6号(1982年6月発行)
技術講座 細菌
10巻5号(1982年5月発行)
技術講座 病理
10巻4号(1982年4月発行)
技術講座 血清
10巻3号(1982年3月発行)
技術講座 生化学
10巻2号(1982年2月発行)
技術講座 病理
10巻1号(1982年1月発行)
技術講座 生化学
9巻12号(1981年12月発行)
技術講座 細菌
9巻11号(1981年11月発行)
技術講座 生理
9巻10号(1981年10月発行)
技術講座 一般
9巻9号(1981年9月発行)
技術講座 血清
9巻8号(1981年8月発行)
技術講座 血清
9巻7号(1981年7月発行)
技術講座 生理
9巻6号(1981年6月発行)
技術講座 細菌
9巻5号(1981年5月発行)
技術講座 一般
9巻4号(1981年4月発行)
技術講座 一般
9巻3号(1981年3月発行)
技術講座 血清
9巻2号(1981年2月発行)
技術講座 一般
9巻1号(1981年1月発行)
技術講座 生化学
8巻12号(1980年12月発行)
技術講座 一般
8巻11号(1980年11月発行)
技術講座 生理
8巻10号(1980年10月発行)
技術講座 検体の取り扱いと保存
8巻9号(1980年9月発行)
技術講座 病理
8巻8号(1980年8月発行)
技術講座 生化学
8巻7号(1980年7月発行)
技術講座 一般
8巻6号(1980年6月発行)
技術講座 生理
8巻5号(1980年5月発行)
技術講座 生化学
8巻4号(1980年4月発行)
技術講座 血清
8巻3号(1980年3月発行)
技術講座 病理
8巻2号(1980年2月発行)
技術講座 一般
8巻1号(1980年1月発行)
技術講座 生化学
7巻12号(1979年12月発行)
技術講座 一般
7巻11号(1979年11月発行)
技術講座 一般
7巻10号(1979年10月発行)
技術講座 細菌
7巻9号(1979年9月発行)
技術講座 生理
7巻8号(1979年8月発行)
技術講座 病理
7巻7号(1979年7月発行)
技術講座 生理
7巻6号(1979年6月発行)
技術講座 一般
7巻5号(1979年5月発行)
技術講座 血液
7巻4号(1979年4月発行)
技術講座 生理
7巻3号(1979年3月発行)
技術講座 病理
7巻2号(1979年2月発行)
技術講座 細菌
7巻1号(1979年1月発行)
技術講座 生化学
6巻12号(1978年12月発行)
技術講座 細菌
6巻11号(1978年11月発行)
技術講座 病理
6巻10号(1978年10月発行)
技術講座 血清
6巻9号(1978年9月発行)
技術講座 細菌
6巻8号(1978年8月発行)
技術講座 生化学
6巻7号(1978年7月発行)
技術講座 一般
6巻6号(1978年6月発行)
技術講座 病理
6巻5号(1978年5月発行)
技術講座 生理
6巻4号(1978年4月発行)
技術講座 一般
6巻3号(1978年3月発行)
技術講座 病理
6巻2号(1978年2月発行)
技術講座 一般
6巻1号(1978年1月発行)
技術講座 病理
5巻12号(1977年12月発行)
技術講座 生理
5巻11号(1977年11月発行)
技術講座 一般
5巻10号(1977年10月発行)
技術講座 細菌付録
5巻9号(1977年9月発行)
技術講座 一般
5巻8号(1977年8月発行)
技術講座 生理
5巻7号(1977年7月発行)
技術講座 一般
5巻6号(1977年6月発行)
技術講座 一般
5巻5号(1977年5月発行)
技術講座 一般
5巻4号(1977年4月発行)
技術講座 一般
5巻3号(1977年3月発行)
技術講座 一般
5巻2号(1977年2月発行)
技術講座 一般
5巻1号(1977年1月発行)
技術講座 一般
4巻12号(1976年12月発行)
技術講座 一般
4巻11号(1976年11月発行)
技術講座 一般
4巻10号(1976年10月発行)
技術講座 一般
4巻9号(1976年9月発行)
技術講座 一般
4巻8号(1976年8月発行)
技術講座 一般
4巻7号(1976年7月発行)
技術講座 一般
4巻6号(1976年6月発行)
技術講座 一般
4巻5号(1976年5月発行)
技術講座 一般
4巻4号(1976年4月発行)
技術講座 一般
4巻3号(1976年3月発行)
技術講座 一般
4巻2号(1976年2月発行)
技術講座 一般
4巻1号(1976年1月発行)
技術講座 一般
3巻12号(1975年12月発行)
技術講座 一般
3巻11号(1975年11月発行)
技術講座 一般
3巻10号(1975年10月発行)
技術講座 一般
3巻9号(1975年9月発行)
技術講座 一般
3巻7号(1975年8月発行)
特集 必修 日常検査の実技
3巻6号(1975年6月発行)
技術講座 生理
3巻5号(1975年5月発行)
技術講座 一般
3巻4号(1975年4月発行)
技術講座 一般
3巻3号(1975年3月発行)
技術講座 一般
3巻2号(1975年2月発行)
技術講座 一般
3巻1号(1975年1月発行)
技術講座 一般
