新しい知見
クリプトコッカス症は真菌であるCryptococcus neoformansを吸入することによって発症する感染症で,肺病変,髄膜炎,全身播種の主たる病型がある.診断のためにはクリプトコッカスの莢膜抗原を検出するキットが有用である.肺病変では血清を用いて検出し,髄膜炎や全身播種ではこれに加えて髄液を用いた検出が行われる.治療効果の判定には髄液抗原価の推移がある程度有効である.これに対して真菌に共通した血清診断法であるβ-グルカン検出法は陽性率,陽性時の値とも低く,他の真菌と比べて有用性が低い.確定診断には培養検査が必要である.肺病変では肺胞洗浄液や肺組織切片の培養,髄膜炎では髄液の培養,全身播種ではこれらに加えて血液や尿の培養が行われる.
雑誌目次
検査と技術32巻1号
2004年01月発行
雑誌目次
病気のはなし
クリプトコッカス病
著者: 安岡彰
ページ範囲:P.6 - P.9
技術講座 免疫
抗リン脂質抗体の測定法
著者: 桑名正隆
ページ範囲:P.11 - P.16
新しい知見
抗リン脂質抗体症候群の疾患概念が提唱されて今年で21年目となる.その間に一般臨床の場では広く認められる疾患となった.抗リン脂質抗体の多くはリン脂質そのものに対する抗体ではなく,リン脂質に結合することにより構造が変化した血清蛋白を認識するということが明らかにされた.抗リン脂質抗体は多様な特異性を持つ抗体の総称であり,すべてを一括して検出できる測定法はない.現在までに特定の特異性を有する抗リン脂質抗体を検出する測定法が数多く開発されている.そのため,個々の測定法の原理を理解したうえで結果を解釈する必要がある.
生理
初心者のための脳CT
著者: 石山綾 , 安達真人 , 細矢貴亮
ページ範囲:P.17 - P.24
新しい知見
現在,CTはsingle helical CTの時代から多検出器を備えたmulti-detector row CT(MD-CT)へと急速に進歩しつつある.MD-CTの特徴は,薄いスライス厚で広い範囲を高速に撮像し,volume dataとして情報を獲得できることにある.得られたデータから,任意の撮像断面の再構成(multi-planar reformation,MPR)や臓器の三次元表示が可能になった.
病理
迅速細胞診断のためのultrafast Papanicolaou染色法
著者: 小林省二
ページ範囲:P.25 - P.28
新しい知見
細胞診断は初期には剥離細胞を対象として,癌のスクリーニングに威力を発揮してきたが,近年になり病理診断の目的で組織診断と同様に重視されるようになってきた.そのため穿刺や擦過で採取した細胞の診断が要求され,従来から行われてきたディフ・クイック染色やパパニコロウ染色の欠点を補い,長所を取り入れた新しい染色法として,ultrafast Papanicolaou(超迅速パパニコロウ)染色が考案された.この染色法は従来の方法に比べ,短時間で,細胞の損失が少なく,赤血球の障害を除き,美しく染色できる特色がある.穿刺,擦過細胞診や術中迅速細胞診などに威力を発揮し,細胞診断の利用価値を高め,さらにその可能性を広げつつある.
微生物
セラチア(Serratia)の検査法 1.細菌学的特徴および臨床材料からの分離・同定法
著者: 三澤成毅
ページ範囲:P.29 - P.33
新しい知見
臨床材料から分離されるSerratiaはS. marcescensがほとんどであり,かつては赤色色素を産生することで特徴づけられていた.しかし,近年では臨床材料由来株のほとんどが色素非産生株で占められるようになった.また,最新の分類学では本菌種の亜種が追加されたことで,正式な菌名がS. marcescens subsp. marcescensに変更されている.本菌は臨床材料からは呼吸器系および泌尿器系材料から多く見いだされる.一方では,敗血症のアウトブレイクが報告され,病院感染における重要性が再認識されている.微生物検査室では,本菌の蔓延をいち早く察知すべく努力しなければならない.
検査データを考える
クレアチニンクリアランス短時間法
著者: 菊池春人
ページ範囲:P.59 - P.63
はじめに
現在わが国では糸球体濾過量(glomerular filtration rate,GFR)を求める方法として,クレアチニンクリアランス(creatinine clearance,Ccr)が最も一般的に用いられている.その測定には以下で述べるように,24時間蓄尿法と短時間法とがある.短時間法は外来や病棟の診療側で実施されて,検体検査として実施されている施設が多いと思われるが,当検査室では従来より一般検査室で患者検査として行ってきている.
以下本稿では,その経験をふまえて短時間法Ccrの意義,およびデータチェックのポイントを中心に,データについての考えかたを述べてみたい.
オピニオン 病理部門の臨床検査技師の今後を考える 第1回
病理医と病理技術者
著者: 台丸裕
ページ範囲:P.10 - P.10
私は,日本三景・安芸の宮島の対岸にあります中規模病院で病理医をやっております.病理医は私一人で,臨床検査技師は4名で全員細胞検査士の資格を持っております.
日常業務は,手術標本の切り出し・生検材料の処理・細胞診の3部門に分けて1か月ごとのローテーションにしております.臨床検査技師は,すべての作業工程を覚え,仕事量や技能も平均化します.当院には,電子顕微鏡もなくまた分子病理学的手法などの特殊検査に投資する機運もありませんが,貴重症例には外注で対応しております.術中の迅速検査・診断に関しましては,手術室と検査室をエアーシューターで?いで対応しております.術中迅速診断は,時間と診断精度を競う緊張した瞬間で,まさに,“guiding the surgeon's hand”ということです.急な要請にも対応しており,病院病理の醍醐味とも言えます.
絵で見る免疫学 基礎編(49)
TH1とTH2のバランス(3) サイトカインの果たす役割
著者: 高木淳 , 玉井一
ページ範囲:P.36 - P.37
サイトカイン(cytokine)
生体防衛にかかわる免疫細胞は,病原体の侵入に備えて血液や体液の流れに乗ってリンパ節などいろいろな組織を絶えずパトロールしている.抗原提示細胞(antigen presenting cell,APC)である樹状細胞やマクロファージが病原体を捕捉すると,この情報を免疫細胞の司令塔であるナイーブCD4陽性T細胞に伝える.APCがナイーブCD4陽性T細胞へ情報を伝達する手段には2つある.1つはAPCが病原体をペプチド断片にしてT細胞レセプター(T-cell antigen receptor,TCR)に直接伝達する手段である.もう1つは,APCが産生・分泌する分子量8~80×103の液性蛋白質のサイトカインが,周辺に存在するナイーブCD4陽性T細胞のサイトカインレセプターに伝達する手段である.前者はケーブルを使った電話,後者は電波を使った携帯電話による情報伝達のようなものである.
サイトカインは単に情報を伝達するのみならず,伝達を受けた細胞は分化・成熟や抑制など多様な調節を行う(図1).サイトカインの多くはインターロイキン(interleukin,IL)と名付けられている.“inter(細胞間)”と“leukin(白血球)”の意味であり,現在IL-1~18まで同定されている.しかし,ILの命名法が決まる以前に名付けられたインターフェロン(interferon,IFN),腫瘍壊死因子(tumor necrosis factor,TNF),増殖因子(growth factor,GF),コロニー刺激因子(colony-stimulating factor,CSF)やケモカインなどの名称は現在でもそのまま使われている(表).
けんさアラカルト
酸化lipoprotein(a)の測定
著者: 北川文彦 , 石井潤一 , 大島久二
ページ範囲:P.72 - P.73
はじめに
lipoprotein(a)〔Lp(a)〕は,動脈硬化進展の危険因子として考えられている1).近年,動脈硬化の進展において酸化Lp(a)〔oxidized Lp(a),OxLp(a)〕の関与が報告され2,3),リスクマーカーとして,また動脈硬化評価の指標として注目されている.
ワンポイントアドバイス
ISO9001認証取得のポイント 第1回 ISOマネジメントシステムの特徴
著者: 苅谷文雄
ページ範囲:P.74 - P.75
はじめに
国際標準規格であるISO規格は,これまで物の性能や機能に対する規格として発行され,ISOネジ,ISO100のフィルム感光度,クレジットカードなど身近な物にも適用されている.一方,品質保証や環境管理を行う活動の仕組み,すなわちマネジメントシステム規格として,ISO9001(品質),14001(環境)に関する規格が普及し,経営的側面からISO9001や14001認証取得に取組む医療機関が増えてきている.
そこで,本稿ではISO9001に関心を持たれる臨床検査関係の方々にISO9001を理解していただくために,ISOマネジメントシステムの特徴を概説する.
今月の表紙
百聞は一見に如かず・1 乳頭状の腺癌
著者: 松谷章司
ページ範囲:P.55 - P.55
百聞は一見に如かず
今日,検体検査は鋭敏かつ高精度な検査がしかも微量な検体で可能となってきている.検査結果も自動化により極めて短時間に得られるのも当たり前となっている.目に見えない物質を可視化,数値化する方法は今後も進歩していくと思われる.
その点,病理組織検査学は臓器,組織そして細胞形態学に立脚し,方法論的にはほぼ完成したものということができるのではないだろうか.ヘマトキシリン-エオジン染色パラフィン標本(以下,HE標本)で診断する方法が基本であることは今後も変わらないからである.病理形態所見はこのHE標本での見えかたの解釈によっている.これまでに電子顕微鏡,蛍光抗体法,酵素抗体法,in situ hybridizationなど種々の方法が導入されたが,これらの方法を用いて理解したものは再びHE標本に反映され,その形態変化の理解がさらに深まり,最終診断が今後もHE染色で行われていくのに変わりはない.しかしながら,病理検査に発展の余地がないのかというと,そうではなく,病理診断の精度は技師の作製する美しい標本に依存し,病理診断医の知識と判断によるところが大きく,それぞれ個人が経験を積み重ねていく努力には終わりがないのである.
Laboratory Practice 血液 骨髄塗抹標本の見かた
8.骨髄液中に見られる異常細胞と関連疾患 [2]神経芽細胞腫,肥満細胞症
著者: 清水長子
ページ範囲:P.38 - P.41
はじめに
骨髄標本をカウントするに当たり,弱拡大で引き終わりや辺縁部を注意して鏡検し,巨大細胞や細胞の集しゅう簇ぞくの有無を確認することが大切である.
本稿では比較的遭遇しやすい悪性腫瘍と,大変稀な症例を提示する.
病理 細胞像からここまでわかる
尿(4) 前立腺癌
著者: 堀内啓 , 伊藤光洋 , 松谷章司
ページ範囲:P.42 - P.44
前立腺癌は,高齢者に好発する代表的な男性ホルモン依存性腫瘍である.原因はほとんどわかっていない.発生頻度は人種や地域による差が大きく,欧米では高くアジアでは低いのが特徴であったが,近年,日本では人口の高齢化や生活習慣の欧米化により,発生頻度は増加している.症状はないことが多いが,排尿障害や残尿感,頻尿,血尿などで気づかれることもある.高頻度に骨転移をきたすことも特徴の1つで,これによる腰痛で発見される場合もある.
前立腺癌の診断は,PSA(prostate specific antigen,前立腺特異抗原)などの腫瘍マーカー,画像診断,細胞診・組織診などが主要な方法である.最近では,血清PSA値測定によるスクリーニングが行われるようになり,PSA高値を契機として発見される前立腺癌の症例が増加している.
生化学 これからの臨床協力業務事例集
検査情報(相談)室の開設
著者: 染谷洋子 , 〆谷直人
ページ範囲:P.45 - P.47
はじめに
現代の情報化社会において,医療情報に関するニーズは年々高まっている.そこで,北里大学病院臨床検査部では臨床サイドの要望に応え,診療支援の一環として,1995年7月に「検査情報(相談)室」を開設した.当時としては,専任の臨床検査技師と臨床検査医が常駐する検査情報室の中央化システムがわが国で初めての試みであったため,今後の臨床検査部の1つのパイロットケースとして注目された.
検査情報(相談)室開設当時の北里大学病院では,現在のようにIT(information technology)が発展しておらず,院内オーダリングシステムは整備されてはいたもののイントラネットやインターネットシステムは未整備であった.当時を振り返り,現状を鑑みながら検査情報(相談)室の立ち上げについて述べる.
生理 超音波像の読みかた
肝臓 1)び漫性良性疾患
著者: 奥田近夫 , 竹内和男
ページ範囲:P.48 - P.54
超音波検査(ultrasonography,以下US)は肝の局在性病変の診断に大変有用であるが,それだけでなく,び漫性肝疾患の診断においても有益な診断情報を与えてくれる.び漫性肝疾患の診断上のチェックポイントとしては,肝の大きさと表面・辺縁の性状,肝内部の門脈枝・肝静脈枝などの走行と形態,肝実質のエコーレベルやエコーパターンなどがある.さらに随伴所見としての他臓器(胆嚢,脾臓,リンパ節など)の異常や門脈系側副血行路などにも目を向ける必要がある.以下,代表的なび漫性肝疾患について,臨床的事項の要点とUS診断のポイントについて述べる.
急性肝炎
急性肝炎は,各種肝炎ウイルス(A,B,C型など)あるいはEpstein-Barr virus(EBV)などのウイルス感染や薬剤が原因で起こる.臨床症状としては感冒様症状が先行し,その後全身倦怠感,肝酵素の上昇,黄疸などがみられる.A型肝炎ウイルスや薬剤性のもの,成人のB型急性肝炎は慢性化することはない.一方,かつて輸血が原因で蔓延したC型肝炎ウイルスによる急性肝炎では,慢性化率が高い.
トピックス
血圧・脈波測定法
著者: 正田孝明
ページ範囲:P.83 - P.85
はじめに
脈波検査は古くて新しい検査項目である.脈波検査は大きく分けて容積脈波(指尖,加速度脈波)検査,圧脈波(頸動脈,股動脈,足背動脈など)検査および心機図検査などが日常検査として行われている.脈波の形状,振幅,速度などから循環器機能,血管・脈管の状態を推測,観察することが可能なため,多くの研究者によって利用されてきた,1).
脈波検査は歴史的には古く,この検査から得られる情報量は多いものの,再現性と精度および術者による測定結果にばらつきがみられたことから,脈波検査はしだいに低迷してきた.
しかし近年,脈波検査が再評価されるようになったのは,測定精度が向上し,上下肢(四肢)血圧測定,心音図,頸動脈波から収縮期,拡張期血圧,脈圧,脈波伝播速度(pulse wave velocity,PWV)およびABI(ankle brachial index,足関節部血圧/上腕血圧比)などの測定が容易となり「血圧・脈波測定法」が日常検査法として利用されるようになったからである.血圧・脈球検査は動脈硬化,糖尿病,高血圧など生活習慣病,閉塞性動脈硬化症などの臨床症状を反映し,また治療効果を示す結果が主治医および患者さんに提供されることから,改めて脈波検査が注目されている.
Acinetobacter baumanniiによる院内感染
著者: 渡邊正治
ページ範囲:P.85 - P.86
はじめに
医療技術や治療法の進歩,普及により病院内にはイムノコンプロマイズドホスト(immunocompromised host,易感染宿主)や医療器具などの異物が挿入されている患者が増加している.このため,通常健康なヒトに感染症を起こすことが稀な菌が,院内感染の起炎菌となることが多い.グラム陽性球菌では,Staphylococcus属,Enterococcus属など,グラム陰性桿菌ではSerratia属,Citrobacter属,Enterobacter属,Pseudomonas aeruginosaなどのブドウ糖非発酵グラム陰性桿菌などが挙げられる.これらの菌は,皮膚・腸管の常在菌や環境・土壌に生息している場合が多く,また薬剤耐性菌も多い.
本稿では,最近各種β-ラクタマーゼを産生し重要となっているAcinetobacter baumannii(A. baumannii)について述べる.
ケトライド系抗菌薬テリスロマイシン
著者: 井上松久 , 兼子謙一 , 村上洋介 , 佐藤義則 , 中野竜一 , 須田和美 , 保坂美生
ページ範囲:P.86 - P.88
はじめに
ケトライド系抗菌薬テリスロマイシンは,新しい範疇に属する抗菌薬である,1).本剤は,2001年に最初にドイツで市販され,2003年現在フランス,イタリアなどのヨーロッパ諸国,中南米およびアジア・オセアニアにおいても既に臨床応用されている.日本においても2002年に申請されており,2003年12月初旬に販売された.本剤は,呼吸器および耳鼻咽喉科感染症の原因菌(グラム陽性球菌,ヘモフィルス,非定型微生物,細胞内寄生性細菌)に対して強い抗菌力を示す.しかも,テリスロマイシンは既存の抗菌薬とは交差耐性を示さない特徴を有する.
近年,ペニシリン耐性肺炎球菌(penicillin-resistant Streptococcus pneumoniae,PRSP)やマクロライド耐性肺炎球菌(erythromycin-resistant Streptococcus pneumoniae,ERSP)が臨床上大きな問題になっている.ケトライド系抗菌薬であるテリスロマシン(telithromycin,以下TEL)は,ペニシリンやマクロライド系抗菌薬,あるいはキノロン系抗菌薬耐性の肺炎球菌に対しても強い活性を発揮するため注目されている.ケトライドという名称は,1950年代に発見されたpikromycinやnarbomycinに由来する2,3).
失敗から学び磨く検査技術 病理標本作製法
薄切切片裏面の気泡
著者: 広井禎之
ページ範囲:P.56 - P.58
薄切切片裏面に気泡が認められる.このような切片裏面の気泡は切片を水に浮かべた時点では確認できず,伸展終了時,その存在に気づくこともある.また,このような現象は気温の低い冬季に多発する傾向がみられる(図1~4).
考えられる原因
A. 薄切切片を浮かべる水を数日間も同じものを使用し続けたため.
検査じょうほう室 病理:病理標本に見られる不思議な現象
切れ味はコーティングで決まり!
著者: 梅宮敏文
ページ範囲:P.64 - P.65
はじめに
ミクロトーム刀は1本刀から替刃式ミクロトーム刀に移行してかれこれ25年以上になります.替刃は毎日の日課であったメス研ぎの煩わしさを解消した画期的な発明と言えるでしょう.初めから替刃を使用している若い方にはピンとこないと思いますが,一本刀の時代のメス研ぎは,それはそれは危険がいっぱいの毎日でした.
今回は,毎日なんの気なしに使っている「ミクロトーム替刃」についてのお話です.
生化学:おさえておきたい生化学の知識
HOMA-RとGA値
著者: 髙加国夫
ページ範囲:P.66 - P.68
はじめに
糖尿病はインスリン作用の不足による慢性高血糖を主徴とし,特有の合併症を引き起こし大血管症など全身に障害をもたらす疾病である.1999年に日本糖尿病学会は糖尿病の新たな分類を発表し,(1)1型糖尿病,(2)2型糖尿病,(3)そのほかの特定の機序,疾患によるもの,(4)妊娠糖尿病とした.1型糖尿病は膵β細胞破壊を特徴とし,2型糖尿病はインスリンの分泌低下と感受性低下(抵抗性の増大)の両者が発症にかかわると定義されている.インスリン抵抗性は2型糖尿病にみられる病態を特徴とし,高脂血症,高血圧症などと密接に関連している.インスリン抵抗性を表す指標には75g経口ブドウ糖負荷試験(75gOGTT),グルコースクランプ法,SSPG(steady-state plasma glucose)法,ミニマルモデル法などいくつかあり,それぞれ長所・短所を有している.Matthewsら1)が提唱したhomeostasis model assessment(HOMA)は糖の許容力をFPG(fast-ing plasma glucose,空腹時血糖値)とFIRI(fast-ing insulin resistance index,空腹時インスリン値)の積で示し,その標準分子量との比をindex化したもので,HOMA-Rと呼ばれ,実用的に優れた指標として注目されてきた.一方,血糖コントロールの指標として従前よりFPG,食後血糖値,HbA1c値,1,5AG値などいくつかの検査とその組み合わせが用いられているが,最近ではグリコアルブミン(GA)が注目されている.アルブミンはヘモグロビンに比し半減期が短く,糖化物であるGAも細胞内糖化物のHbA1cより明らかに短い.血糖コントロールの短期指標としてGAの有用性が再評価されている.
緊急:現場から学ぶ対処法
救急領域における初療時血液ガス血糖同時測定の意義
著者: 久保田芽里 , 福田篤久
ページ範囲:P.69 - P.71
当センターに搬入される患者のうち,その割合が最も高いのは,意識障害を主訴とする患者です.その中でも原因不明の意識障害に遭遇することは稀ではありません.今回,意識障害の原因が臨床検査によって判明する代謝性異常によるもの,その中でも特に「低血糖によるもの」を取り上げ,血糖値報告までの時間や患者搬入からの時間経過などを紹介しようと思います.
当センターの血糖値報告
当センターでは,患者搬入後直ちに全身状態を把握する目的で,動脈血血液ガス分析(ABG)用血液(以下「血液ガス検体」)の採取が行われ,その後(ほぼ同時の時もある),生化学や血算,止血検査などの採血(約15ml)が行われます.
ラボクイズ
心電図[3]
著者: 大家辰彦 , 犀川哲典
ページ範囲:P.34 - P.34
症 例:32歳男性.運転中に意識を消失し,精査加療目的で当科入院となった.10年前の健診時は,図1の心電図であった.入院時の電気生理検査で,右室流出路からの頻回刺激により図2の不整脈が誘発され,血圧低下,意識障害をきたした.この不整脈は電気的除細動により洞調律に復帰した.同時に施行した冠動脈造影検査では有意狭窄はなく,またアセチルコリンによる冠攣縮誘発試験も陰性であった.さらに左室造影検査における左室の壁運動は良好で,明らかな局所壁運動低下は認められなかった.
問題1 図1の心電図より考えられる疾患はどれか.
12月号の解答と解説
著者: 川元博之 , 谷村晃
ページ範囲:P.35 - P.35
【問題1】 解答:(3)(図1,2)
解説:背景には,壊死とは異なるライトグリーン淡染性の蛋白様物質(lymphoglandular body)が見られます.やや大型でN/C比の高いもしくは裸核様の単一な類円形細胞が,孤立散在性に出現しています.一部の核にはくびれが見られ,クロマチンは微細顆粒状,核小体は大型で目立ちます.浸潤性小葉癌に見られるようなICL(intracytoplasmic lumen)や結合性は認められません.髄様癌は,背景に異型のないリンパ球が見られますが,ほかに疎な結合を示す大型の腫瘍細胞が認められます.腺癌との鑑別になる粘液物質も見られず,細胞も大型であることより,悪性リンパ腫大細胞型が考えられます.この症例は加えて,び漫性B細胞型でした.乳癌に発生する悪性リンパ腫のほとんどがB細胞性でび漫性大細胞型が最も多いです.特徴は,節性の悪性リンパ腫と同様です.この症例に関しては,原発かどうかは不明で,ほかには肝,肺,消化管,リンパ節としては後腹膜リンパ節に見られました.
けんさ質問箱Q&A
貧血では血小板が多いか
著者: 川合陽子 , 清水長子
ページ範囲:P.76 - P.79
Q貧血では血小板が多いか
貧血では血小板が多いように見受けられますが,なぜでしょうか.その理由を教えてください.(茂原市 Y. F.生)
はじめに
貧血とは,血液中のヘモグロビン(Hb)濃度が低下した状態のことをいいます.WHO(World Health Organization,世界保健機関)の基準では,成人男性で13g/dl未満,成人女性で12g/dl未満を貧血と定義しています.ヘモグロビンは体の中の筋肉や組織に酸素を供給する大切な役目を担っていますが,貧血の程度や原因は多様です(図).原因は大きく分けて,(1)血球産生の低下,(2)赤血球の破壊の増大(溶血),(3)血液の喪失,に分類できます.血球産生の低下は,造血幹細胞の異常や幹細胞に対する抗体などで引き起こされますが,造血に必要なサイトカインの低下やビタミンB12・葉酸・鉄などのDNA合成やヘモグロビン合成の材料不足なども貧血の原因となります.つまり幹細胞から赤血球に至るどの成熟過程が障害されても貧血を発症します.一方,赤血球の破壊の増大は,種々の原因による溶血が造血能力を上回ると貧血となります.血液の喪失は,急性失血では急激な貧血となりますが,慢性に持続するゆっくりとした出血では鉄欠乏性貧血となることが多いようです.
ご質問のように,末梢血の血球算定(血算,CBC測定)をしている時,貧血の検体の中にしばしば血小板数の増加を認めることがあります.しかし,すべての貧血患者が血小板増多を呈するわけではありません.貧血時に血小板増多を呈する理由や詳細なメカニズムは不明のことが多いようですが,その原因の1つに,炎症性サイトカインやエリスロポエチン(erythropoietin,EPO)の関与が考えられています1~4).
運動負荷試験とT波の動き
著者: 福田恵津子 , 小笠原憲
ページ範囲:P.79 - P.82
Q運動負荷試験と T波の動き
運動負荷試験で,負荷後にT波が増高するのはなぜですか.また,虚血性心疾患や左心室肥大で陰性T波が陽性化するのはなぜですか.その理由と,それらの所見の臨床的意義を教えてください.(福岡県飯塚市H. K.生)
▲運動負荷時のT波の変化について
T波は性,年齢,体型,体位,呼吸などで容易に変動するため,正常T波といえる波形を分類することは難しいことがあります.同様に,運動によってもT波は容易に変化するため,その臨床的意義を考えるには心電図の全所見や臨床データを参考に総合的に判断する必要があります.運動によるT波の変化の影響としては,心拍数の増加,交感神経の緊張,血行動態の変化,代謝産物などが考えられます.運動負荷におけるT波の変化を表1)にまとめました.正常T波は安静時,,V4-6で上向きで,それらは通常運動で平低化するといわれています.しかし,激しい運動を行った後にT波はむしろ高くなります.特に運動後の回復期にT波の増高が見られ,それは安静時に平低傾向にあるT波で目立ちます.運動時のT波の変化を考えるときにこれら生理的反応とそれ以外の病的反応(虚血反応)であるかを鑑別する必要があります.これらT波の変化をベクトル心電図で説明している文献もありますが,今回は心筋活動電位で考えてみたいと思います.
基本情報
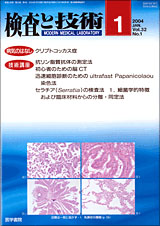
バックナンバー
52巻12号(2024年12月発行)
技術講座 生理
52巻11号(2024年11月発行)
技術講座 生理
52巻10号(2024年10月発行)
技術講座 生理
52巻9号(2024年9月発行)
増大号 臨床医に伝わりやすい 検査報告書とパニック値報告の心得
52巻8号(2024年8月発行)
技術講座 生理
52巻7号(2024年7月発行)
技術講座 生理
52巻6号(2024年6月発行)
技術講座 生理
52巻5号(2024年5月発行)
技術講座 その他
52巻4号(2024年4月発行)
技術講座 生理
52巻3号(2024年3月発行)
増大号 POCUSの決め手。 早く、正確な診断のために
52巻2号(2024年2月発行)
技術講座 生理
52巻1号(2024年1月発行)
技術講座 その他
51巻12号(2023年12月発行)
技術講座 生理
51巻11号(2023年11月発行)
技術講座 生理
51巻10号(2023年10月発行)
技術講座 その他
51巻9号(2023年9月発行)
増大号 匠から学ぶ 血栓止血検査ガイド
51巻8号(2023年8月発行)
技術講座 生理
51巻7号(2023年7月発行)
技術講座 生理
51巻6号(2023年6月発行)
技術講座 生理
51巻5号(2023年5月発行)
技術講座 生理
51巻4号(2023年4月発行)
技術講座 生理
51巻3号(2023年3月発行)
増大号 症例から学ぶ 疾患と検査値の推移
51巻2号(2023年2月発行)
技術講座 その他
51巻1号(2023年1月発行)
技術講座 生理
50巻12号(2022年12月発行)
技術講座 その他
50巻11号(2022年11月発行)
技術講座 生理
50巻10号(2022年10月発行)
技術講座 生理
50巻9号(2022年9月発行)
増大号 希少例と特殊像がわかる! エコーの撮り方完全マスター
50巻8号(2022年8月発行)
技術講座 生理
50巻7号(2022年7月発行)
技術講座 生理
50巻6号(2022年6月発行)
技術講座 生理
50巻5号(2022年5月発行)
技術講座 生理
50巻4号(2022年4月発行)
技術講座 生理
50巻3号(2022年3月発行)
増大号 見て学ぶ 一般検査学アトラス—外観検査から顕微鏡検査まで
50巻2号(2022年2月発行)
技術講座 その他
50巻1号(2022年1月発行)
技術講座 生理
49巻12号(2021年12月発行)
技術講座 生理
49巻11号(2021年11月発行)
技術講座 生理
49巻10号(2021年10月発行)
技術講座 生理
49巻9号(2021年9月発行)
増刊号 病態別 腹部エコーの観察・記録・報告書作成マスター
49巻8号(2021年8月発行)
技術講座 生理
49巻7号(2021年7月発行)
技術講座 生理
49巻6号(2021年6月発行)
技術講座 生理
49巻5号(2021年5月発行)
技術講座 生理
49巻4号(2021年4月発行)
技術講座 一般
49巻3号(2021年3月発行)
増刊号 First&Next Step 微生物検査サポートブック
49巻2号(2021年2月発行)
技術講座 微生物
49巻1号(2021年1月発行)
技術講座 病理・生理
48巻12号(2020年12月発行)
技術講座 その他
48巻11号(2020年11月発行)
技術講座 生化学
48巻10号(2020年10月発行)
技術講座 生理
48巻9号(2020年9月発行)
増刊号 学会発表・論文執筆はもう怖くない! 臨床検査技師のための研究入門
48巻8号(2020年8月発行)
技術講座 遺伝子
48巻7号(2020年7月発行)
技術講座 その他
48巻6号(2020年6月発行)
技術講座 輸血
48巻5号(2020年5月発行)
技術講座 生化学
48巻4号(2020年4月発行)
技術講座 生理
48巻3号(2020年3月発行)
増刊号 採血のすべて—手技から採血室の運用まで徹底解説
48巻2号(2020年2月発行)
技術講座 微生物
48巻1号(2020年1月発行)
技術講座 生理
47巻12号(2019年12月発行)
技術講座 病理
47巻11号(2019年11月発行)
技術講座 生理
47巻10号(2019年10月発行)
技術講座 生理
47巻9号(2019年9月発行)
増刊号 染色画像を比べて学ぶ 体腔液アトラス
47巻8号(2019年8月発行)
技術講座 病理
47巻7号(2019年7月発行)
技術講座 一般
47巻6号(2019年6月発行)
技術講座 血液
47巻5号(2019年5月発行)
技術講座 血液
47巻4号(2019年4月発行)
技術講座 血液
47巻3号(2019年3月発行)
増刊号 エキスパートが教える 心・血管エコー計測のノウハウ
47巻2号(2019年2月発行)
技術講座 病理
47巻1号(2019年1月発行)
技術講座 微生物
46巻12号(2018年12月発行)
技術講座 生理
46巻11号(2018年11月発行)
技術講座 輸血・遺伝子検査
46巻10号(2018年10月発行)
技術講座 その他
46巻9号(2018年9月発行)
増刊号 現場で“パッ”と使える 免疫染色クイックガイド
46巻8号(2018年8月発行)
技術講座 輸血・遺伝子検査
46巻7号(2018年7月発行)
技術講座 生理
46巻6号(2018年6月発行)
技術講座 管理
46巻5号(2018年5月発行)
技術講座 生化学
46巻4号(2018年4月発行)
技術講座 一般
46巻3号(2018年3月発行)
増刊号 感染症クイックリファレンス
46巻2号(2018年2月発行)
技術講座 輸血
46巻1号(2018年1月発行)
技術講座 病理
45巻12号(2017年12月発行)
技術講座 生理
45巻11号(2017年11月発行)
技術講座 一般
45巻10号(2017年10月発行)
技術講座 微生物
45巻9号(2017年9月発行)
増刊号 循環器病院の技師が教える メディカルスタッフのための心電図教室
45巻8号(2017年8月発行)
技術講座 栄養
45巻7号(2017年7月発行)
技術講座 病理
45巻6号(2017年6月発行)
技術講座 病理
45巻5号(2017年5月発行)
技術講座 細胞治療・管理
45巻4号(2017年4月発行)
技術講座 遺伝子・染色体検査
45巻3号(2017年3月発行)
45巻2号(2017年2月発行)
技術講座 細胞治療
45巻1号(2017年1月発行)
技術講座 病理
44巻13号(2016年12月発行)
技術講座 免疫
44巻12号(2016年11月発行)
技術講座 微生物
44巻11号(2016年10月発行)
技術講座 微生物
44巻10号(2016年9月発行)
増刊号 はじめて出会う 検査画像
44巻9号(2016年9月発行)
技術講座 管理・その他
44巻8号(2016年8月発行)
技術講座 微生物
44巻7号(2016年7月発行)
技術講座 生理
44巻6号(2016年6月発行)
技術講座 微生物
44巻5号(2016年5月発行)
技術講座 生理
44巻4号(2016年4月発行)
技術講座 微生物
44巻3号(2016年3月発行)
技術講座 生理
44巻2号(2016年2月発行)
技術講座 微生物
44巻1号(2016年1月発行)
技術講座 微生物
43巻13号(2015年12月発行)
技術講座 生化学
43巻12号(2015年11月発行)
技術講座 生化学
43巻11号(2015年10月発行)
技術講座 一般
43巻10号(2015年9月発行)
増刊号 血液形態アトラス
43巻9号(2015年9月発行)
技術講座 生理
43巻8号(2015年8月発行)
技術講座 生理
43巻7号(2015年7月発行)
技術講座 生理
43巻6号(2015年6月発行)
技術講座 微生物
43巻5号(2015年5月発行)
技術講座 移植医療
43巻4号(2015年4月発行)
技術講座 病理
43巻3号(2015年3月発行)
技術講座 血液
43巻2号(2015年2月発行)
技術講座 管理
43巻1号(2015年1月発行)
技術講座 病理
42巻13号(2014年12月発行)
技術講座 生化学
42巻12号(2014年11月発行)
技術講座 病理
42巻11号(2014年10月発行)
技術講座 血液
42巻10号(2014年9月発行)
増刊号 超音波×病理 対比アトラス
42巻9号(2014年9月発行)
技術講座 生理
42巻8号(2014年8月発行)
技術講座 免疫
42巻7号(2014年7月発行)
技術講座 生理
42巻6号(2014年6月発行)
技術講座 生理
42巻5号(2014年5月発行)
技術講座 病理
42巻4号(2014年4月発行)
技術講座 輸血
42巻3号(2014年3月発行)
技術講座 血液
42巻2号(2014年2月発行)
技術講座 微生物
42巻1号(2014年1月発行)
技術講座 病理
41巻13号(2013年12月発行)
技術講座 生理
41巻12号(2013年11月発行)
技術講座 生化学
41巻11号(2013年10月発行)
技術講座 生化学
41巻10号(2013年9月発行)
増刊号 解剖と正常像がわかる! エコーの撮り方完全マスター
41巻9号(2013年9月発行)
技術講座 微生物
41巻8号(2013年8月発行)
技術講座 生理
41巻7号(2013年7月発行)
技術講座 生理
41巻6号(2013年6月発行)
技術講座 微生物
41巻5号(2013年5月発行)
技術講座 一般
41巻4号(2013年4月発行)
技術講座 生化学
41巻3号(2013年3月発行)
技術講座 生理
41巻2号(2013年2月発行)
技術講座 生理
41巻1号(2013年1月発行)
技術講座 生理
40巻13号(2012年12月発行)
技術講座 血液
40巻12号(2012年11月発行)
技術講座 生理
40巻11号(2012年10月発行)
技術講座 生理
40巻10号(2012年9月発行)
増刊号 この検査データを読めますか?―検査値から病態を探る
40巻9号(2012年9月発行)
技術講座 生理
40巻8号(2012年8月発行)
技術講座 細胞診
40巻7号(2012年7月発行)
技術講座 生理
40巻6号(2012年6月発行)
技術講座 生理
40巻5号(2012年5月発行)
技術講座 生理
40巻4号(2012年4月発行)
技術講座 血液
40巻3号(2012年3月発行)
技術講座 生理
40巻2号(2012年2月発行)
技術講座 輸血
40巻1号(2012年1月発行)
技術講座 遺伝子
39巻13号(2011年12月発行)
疾患と検査値の推移
39巻12号(2011年11月発行)
疾患と検査値の推移
39巻11号(2011年10月発行)
疾患と検査値の推移
39巻10号(2011年9月発行)
増刊号 緊急報告すべき検査結果のすべて―すぐに使えるパニック値事典
39巻9号(2011年9月発行)
疾患と検査値の推移
39巻8号(2011年8月発行)
疾患と検査値の推移
39巻7号(2011年7月発行)
疾患と検査値の推移
39巻6号(2011年6月発行)
技術講座 生理
39巻5号(2011年5月発行)
技術講座 生理
39巻4号(2011年4月発行)
疾患と検査値の推移
39巻3号(2011年3月発行)
疾患と検査値の推移
39巻2号(2011年2月発行)
疾患と検査値の推移
39巻1号(2011年1月発行)
疾患と検査値の推移
38巻13号(2010年12月発行)
疾患と検査値の推移
38巻12号(2010年11月発行)
疾患と検査値の推移
38巻11号(2010年10月発行)
疾患と検査値の推移
38巻10号(2010年9月発行)
増刊号 免疫反応と臨床検査2010
38巻9号(2010年9月発行)
疾患と検査値の推移
38巻8号(2010年8月発行)
疾患と検査値の推移
38巻7号(2010年7月発行)
疾患と検査値の推移
38巻6号(2010年6月発行)
疾患と検査値の推移
38巻5号(2010年5月発行)
疾患と検査値の推移
38巻4号(2010年4月発行)
疾患と検査値の推移
38巻3号(2010年3月発行)
疾患と検査値の推移
38巻2号(2010年2月発行)
疾患と検査値の推移
38巻1号(2010年1月発行)
疾患と検査値の推移
37巻13号(2009年12月発行)
疾患と検査値の推移
37巻12号(2009年11月発行)
疾患と検査値の推移
37巻11号(2009年10月発行)
疾患と検査値の推移
37巻10号(2009年9月発行)
増刊号 顕微鏡検査のコツ―臨床に役立つ形態学
37巻9号(2009年9月発行)
疾患と検査値の推移
37巻8号(2009年8月発行)
疾患と検査値の推移
37巻7号(2009年7月発行)
疾患と検査値の推移
37巻6号(2009年6月発行)
疾患と検査値の推移
37巻5号(2009年5月発行)
疾患と検査値の推移
37巻4号(2009年4月発行)
疾患と検査値の推移
37巻3号(2009年3月発行)
疾患と検査値の推移
37巻2号(2009年2月発行)
疾患と検査値の推移
37巻1号(2009年1月発行)
疾患と検査値の推移
36巻13号(2008年12月発行)
疾患と検査値の推移
36巻12号(2008年11月発行)
疾患と検査値の推移
36巻11号(2008年10月発行)
疾患と検査値の推移
36巻10号(2008年9月発行)
増刊号 これから広がる生理検査・新たにはじまる生理検査
36巻9号(2008年9月発行)
疾患と検査値の推移
36巻8号(2008年8月発行)
疾患と検査値の推移
36巻7号(2008年7月発行)
疾患と検査値の推移
36巻6号(2008年6月発行)
疾患と検査値の推移
36巻5号(2008年5月発行)
疾患と検査値の推移
36巻4号(2008年4月発行)
疾患と検査値の推移
36巻3号(2008年3月発行)
疾患と検査値の推移
36巻2号(2008年2月発行)
疾患と検査値の推移
36巻1号(2008年1月発行)
疾患と検査値の推移
35巻13号(2007年12月発行)
疾患と検査値の推移
35巻12号(2007年11月発行)
疾患と検査値の推移
35巻11号(2007年10月発行)
増刊号 メタボリックシンドローム健診検査技術マニュアル
35巻10号(2007年10月発行)
疾患と検査値の推移
35巻9号(2007年9月発行)
疾患と検査値の推移
35巻8号(2007年8月発行)
疾患と検査値の推移
35巻7号(2007年7月発行)
疾患と検査値の推移
35巻6号(2007年6月発行)
疾患と検査値の推移
35巻5号(2007年5月発行)
疾患と検査値の推移
35巻4号(2007年4月発行)
疾患と検査値の推移
35巻3号(2007年3月発行)
疾患と検査値の推移
35巻2号(2007年2月発行)
疾患と検査値の推移
35巻1号(2007年1月発行)
疾患と検査値の推移
34巻13号(2006年12月発行)
技術講座 生理
34巻12号(2006年11月発行)
技術講座 一般
34巻11号(2006年10月発行)
増刊号 新しい臨床検査・未来の臨床検査
34巻10号(2006年10月発行)
疾患と検査値の推移
34巻9号(2006年9月発行)
疾患と検査値の推移
34巻8号(2006年8月発行)
疾患と検査値の推移
34巻7号(2006年7月発行)
疾患と検査値の推移
34巻6号(2006年6月発行)
疾患と検査値の推移
34巻5号(2006年5月発行)
疾患と検査値の推移
34巻4号(2006年4月発行)
疾患と検査値の推移
34巻3号(2006年3月発行)
疾患と検査値の推移
34巻2号(2006年2月発行)
疾患と検査値の推移
34巻1号(2006年1月発行)
疾患と検査値の推移
33巻13号(2005年12月発行)
疾患と検査値の推移
33巻12号(2005年11月発行)
疾患と検査値の推移
33巻11号(2005年10月発行)
増刊号 一線診療のための臨床検査
33巻10号(2005年10月発行)
疾患と検査値の推移
33巻9号(2005年9月発行)
疾患と検査値の推移
33巻8号(2005年8月発行)
疾患と検査値の推移
33巻7号(2005年7月発行)
疾患と検査値の推移
33巻6号(2005年6月発行)
疾患と検査値の推移
33巻5号(2005年5月発行)
疾患と検査値の推移
33巻4号(2005年4月発行)
疾患と検査値の推移
33巻3号(2005年3月発行)
疾患と検査値の推移
33巻2号(2005年2月発行)
疾患と検査値の推移
33巻1号(2005年1月発行)
疾患と検査値の推移
32巻13号(2004年12月発行)
技術講座 血液
32巻12号(2004年11月発行)
技術講座 病理
32巻11号(2004年10月発行)
技術講座 血液
32巻10号(2004年9月発行)
増刊号 細胞像の見かた―病理・血液・尿沈渣
32巻9号(2004年9月発行)
技術講座 生化学
32巻8号(2004年8月発行)
技術講座 免疫
32巻7号(2004年7月発行)
技術講座 微生物
32巻6号(2004年6月発行)
技術講座 病理
32巻5号(2004年5月発行)
技術講座 病理
32巻4号(2004年4月発行)
技術講座 病理
32巻3号(2004年3月発行)
技術講座 微生物
32巻2号(2004年2月発行)
技術講座 生化学
32巻1号(2004年1月発行)
技術講座 微生物
31巻13号(2003年12月発行)
技術講座 微生物
31巻12号(2003年11月発行)
技術講座 病理
31巻11号(2003年10月発行)
技術講座 微生物
31巻10号(2003年9月発行)
増刊号 包括医療と臨床検査
31巻9号(2003年9月発行)
技術講座 一般
31巻8号(2003年8月発行)
技術講座 微生物
31巻7号(2003年7月発行)
技術講座 病理
31巻6号(2003年6月発行)
技術講座 免疫
31巻5号(2003年5月発行)
技術講座 一般
31巻4号(2003年4月発行)
技術講座 病理
31巻3号(2003年3月発行)
技術講座 生化学
31巻2号(2003年2月発行)
技術講座 免疫
31巻1号(2003年1月発行)
技術講座 免疫
30巻13号(2002年12月発行)
技術講座 生理
30巻12号(2002年11月発行)
技術講座 生理
30巻11号(2002年10月発行)
技術講座 生化学
30巻10号(2002年9月発行)
増刊号 誰でもわかる遺伝子検査
30巻9号(2002年9月発行)
技術講座 微生物
30巻8号(2002年8月発行)
技術講座 生化学
30巻7号(2002年7月発行)
技術講座 微生物
30巻6号(2002年6月発行)
技術講座 生化学
30巻5号(2002年5月発行)
技術講座 微生物
30巻4号(2002年4月発行)
技術講座 一般
30巻3号(2002年3月発行)
技術講座 生化学
30巻2号(2002年2月発行)
技術講座 一般
30巻1号(2002年1月発行)
技術講座 免疫
29巻13号(2001年12月発行)
技術講座 病理
29巻12号(2001年11月発行)
技術講座 生理
29巻11号(2001年10月発行)
技術講座 病理
29巻10号(2001年9月発行)
技術講座 病理
29巻9号(2001年8月発行)
技術講座 病理
29巻8号(2001年7月発行)
技術講座 生理
29巻7号(2001年6月発行)
増刊号 病理組織・細胞診のための日常染色法ガイダンス
29巻6号(2001年6月発行)
技術講座 微生物
29巻5号(2001年5月発行)
技術講座 生理
29巻4号(2001年4月発行)
技術講座 病理
29巻3号(2001年3月発行)
技術講座 微生物
29巻2号(2001年2月発行)
技術講座 微生物
29巻1号(2001年1月発行)
技術講座 一般
28巻13号(2000年12月発行)
技術講座 病理
28巻12号(2000年11月発行)
技術講座 病理
28巻11号(2000年10月発行)
技術講座 免疫
28巻10号(2000年9月発行)
技術講座 微生物
28巻9号(2000年8月発行)
技術講座 微生物
28巻8号(2000年7月発行)
技術講座 生理
28巻7号(2000年6月発行)
増刊号 血液検査実践マニュアル
28巻6号(2000年6月発行)
技術講座 免疫
28巻5号(2000年5月発行)
技術講座 血液
28巻4号(2000年4月発行)
技術講座 一般
28巻3号(2000年3月発行)
技術講座 生理
28巻2号(2000年2月発行)
技術講座 生化学
28巻1号(2000年1月発行)
技術講座 一般
27巻13号(1999年12月発行)
技術講座 病理
27巻12号(1999年11月発行)
技術講座 一般
27巻11号(1999年10月発行)
技術講座 生化学
27巻10号(1999年9月発行)
技術講座 免疫
27巻9号(1999年8月発行)
技術講座 病理
27巻8号(1999年7月発行)
技術講座 病理
27巻7号(1999年6月発行)
増刊号 緊急検査実践マニュアル
27巻6号(1999年6月発行)
技術講座 生化学
27巻5号(1999年5月発行)
技術講座 血液
27巻4号(1999年4月発行)
技術講座 一般
27巻3号(1999年3月発行)
技術講座 生理
27巻2号(1999年2月発行)
技術講座 微生物
27巻1号(1999年1月発行)
技術講座 生理
26巻13号(1998年12月発行)
技術講座 一般
26巻12号(1998年11月発行)
技術講座 病理
26巻11号(1998年10月発行)
技術講座 病理
26巻10号(1998年9月発行)
技術講座 生理
26巻9号(1998年8月発行)
技術講座 生理
26巻8号(1998年7月発行)
技術講座 生理
26巻7号(1998年6月発行)
増刊号 病理組織・細胞診実践マニュアル
26巻6号(1998年6月発行)
技術講座 病理
26巻5号(1998年5月発行)
技術講座 一般
26巻4号(1998年4月発行)
技術講座 病理
26巻3号(1998年3月発行)
技術講座 一般
26巻2号(1998年2月発行)
技術講座 生理
26巻1号(1998年1月発行)
技術講座 血液
25巻13号(1997年12月発行)
技術講座 一般
25巻12号(1997年11月発行)
技術講座 一般
25巻11号(1997年10月発行)
技術講座 生理
25巻10号(1997年9月発行)
技術講座 血液
25巻9号(1997年8月発行)
技術講座 一般
25巻8号(1997年7月発行)
技術講座 一般
25巻7号(1997年6月発行)
増刊号 輸血検査実践マニュアル
25巻6号(1997年6月発行)
技術講座 免疫
25巻5号(1997年5月発行)
技術講座 生理
25巻4号(1997年4月発行)
技術講座 生理
25巻3号(1997年3月発行)
技術講座 微生物
25巻2号(1997年2月発行)
技術講座 生理
25巻1号(1997年1月発行)
技術講座 一般
24巻13号(1996年12月発行)
技術講座 生理
24巻12号(1996年11月発行)
技術講座 一般
24巻11号(1996年10月発行)
技術講座 生理
24巻10号(1996年9月発行)
技術講座 管理
24巻9号(1996年8月発行)
技術講座 生理
24巻8号(1996年7月発行)
技術講座 生理
24巻7号(1996年6月発行)
増刊号 感染症検査実践マニュアル
24巻6号(1996年6月発行)
技術講座 病理
24巻5号(1996年5月発行)
技術講座 生理
24巻4号(1996年4月発行)
技術講座 生理
24巻3号(1996年3月発行)
技術講座 生理
24巻2号(1996年2月発行)
技術講座 生理
24巻1号(1996年1月発行)
技術講座 一般
23巻13号(1995年12月発行)
技術講座 生理
23巻12号(1995年11月発行)
技術講座 病理
23巻11号(1995年10月発行)
技術講座 微生物
23巻10号(1995年9月発行)
技術講座 生理
23巻9号(1995年8月発行)
技術講座 一般
23巻8号(1995年7月発行)
技術講座 免疫
23巻7号(1995年6月発行)
技術講座 生理
23巻6号(1995年5月発行)
技術講座 一般
23巻5号(1995年4月発行)
増刊号 臨床生理検査実践マニュアル画像検査を中心として
23巻4号(1995年4月発行)
技術講座 病理
23巻3号(1995年3月発行)
技術講座 病理
23巻2号(1995年2月発行)
技術講座 一般
23巻1号(1995年1月発行)
技術講座 生理
22巻13号(1994年12月発行)
技術講座 一般
22巻12号(1994年11月発行)
技術講座 一般
22巻11号(1994年10月発行)
技術講座 一般
22巻10号(1994年9月発行)
技術講座 一般
22巻9号(1994年8月発行)
技術講座 生理
22巻8号(1994年7月発行)
技術講座 病理
22巻7号(1994年6月発行)
技術講座 一般
22巻6号(1994年5月発行)
技術講座 一般
22巻5号(1994年4月発行)
増刊号 免疫検査実践マニュアル
22巻4号(1994年4月発行)
技術講座 生理
22巻3号(1994年3月発行)
技術講座 免疫
22巻2号(1994年2月発行)
技術講座 一般
22巻1号(1994年1月発行)
技術講座 生理
21巻13号(1993年12月発行)
技術講座 一般
21巻12号(1993年11月発行)
技術講座 一般
21巻11号(1993年10月発行)
技術講座 一般
21巻10号(1993年9月発行)
技術講座 生理
21巻9号(1993年8月発行)
技術講座 一般
21巻8号(1993年7月発行)
技術講座 病理
21巻7号(1993年6月発行)
技術講座 一般
21巻6号(1993年5月発行)
技術講座 生理
21巻5号(1993年4月発行)
増刊号 臨床化学実践マニュアル
21巻4号(1993年4月発行)
技術講座 生理
21巻3号(1993年3月発行)
技術講座 病理
21巻2号(1993年2月発行)
技術講座 生理
21巻1号(1993年1月発行)
技術講座 生理
20巻13号(1992年12月発行)
技術講座 一般
20巻12号(1992年11月発行)
技術講座 一般
20巻11号(1992年10月発行)
技術講座 一般
20巻10号(1992年9月発行)
技術講座 一般
20巻9号(1992年8月発行)
技術講座 一般
20巻8号(1992年7月発行)
技術講座 血液
20巻7号(1992年6月発行)
技術講座 一般
20巻6号(1992年5月発行)
増刊号 尿検査法
20巻5号(1992年5月発行)
技術講座 生理
20巻4号(1992年4月発行)
技術講座 生理
20巻3号(1992年3月発行)
技術講座 病理
20巻2号(1992年2月発行)
技術講座 一般
20巻1号(1992年1月発行)
技術講座 生理
19巻13号(1991年12月発行)
技術講座 管理
19巻12号(1991年11月発行)
技術講座 生理
19巻11号(1991年10月発行)
技術講座 生理
19巻10号(1991年9月発行)
技術講座 一般
19巻9号(1991年8月発行)
技術講座 一般
19巻8号(1991年7月発行)
技術講座 生理
19巻7号(1991年6月発行)
増刊号 臨床血液検査
19巻6号(1991年6月発行)
技術講座 生理
19巻5号(1991年5月発行)
技術講座 生理
19巻4号(1991年4月発行)
技術講座 一般
19巻3号(1991年3月発行)
技術講座 生理
19巻2号(1991年2月発行)
技術講座 生理
19巻1号(1991年1月発行)
技術講座 一般
18巻13号(1990年12月発行)
技術講座 生理
18巻12号(1990年11月発行)
技術講座 微生物
18巻11号(1990年10月発行)
技術講座 生理
18巻10号(1990年9月発行)
技術講座 一般
18巻9号(1990年8月発行)
技術講座 一般
18巻8号(1990年7月発行)
技術講座 一般
18巻7号(1990年6月発行)
技術講座 一般
18巻6号(1990年5月発行)
増刊号 血液・尿以外の体液検査法
18巻5号(1990年5月発行)
技術講座 一般
18巻4号(1990年4月発行)
技術講座 一般
18巻3号(1990年3月発行)
技術講座 血液
18巻2号(1990年2月発行)
技術講座 生理
18巻1号(1990年1月発行)
技術講座 生理
17巻13号(1989年12月発行)
技術講座 一般
17巻12号(1989年11月発行)
技術講座 一般
17巻11号(1989年10月発行)
技術講座 一般
17巻10号(1989年9月発行)
技術講座 一般
17巻9号(1989年8月発行)
技術講座 生理
17巻8号(1989年7月発行)
技術講座 血清
17巻7号(1989年6月発行)
技術講座 一般
17巻6号(1989年5月発行)
感染症の検査法 Ⅲ 検査法各論
17巻5号(1989年5月発行)
技術講座 一般
17巻4号(1989年4月発行)
技術講座 生理
17巻3号(1989年3月発行)
技術講座 病理
17巻2号(1989年2月発行)
技術講座 一般
17巻1号(1989年1月発行)
技術講座 生理
16巻13号(1988年12月発行)
技術講座 一般
16巻12号(1988年11月発行)
技術講座 一般
16巻11号(1988年10月発行)
技術講座 一般
16巻10号(1988年9月発行)
技術講座 生理
16巻9号(1988年8月発行)
技術講座 一般
16巻8号(1988年7月発行)
技術講座 一般
16巻7号(1988年6月発行)
免疫化学検査法 資料
16巻6号(1988年6月発行)
技術講座 一般
16巻5号(1988年5月発行)
技術講座 一般
16巻4号(1988年4月発行)
技術講座 病理
16巻3号(1988年3月発行)
技術講座 生理
16巻2号(1988年2月発行)
技術講座 一般
16巻1号(1988年1月発行)
技術講座 血液
15巻13号(1987年12月発行)
技術講座 一般
15巻12号(1987年11月発行)
技術講座 病理
15巻11号(1987年10月発行)
技術講座 細胞診
15巻10号(1987年9月発行)
技術講座 一般
15巻9号(1987年8月発行)
技術講座 細胞診
15巻8号(1987年7月発行)
技術講座 病理
15巻7号(1987年6月発行)
技術講座 病理
15巻6号(1987年5月発行)
技術講座 病理
15巻5号(1987年4月発行)
臨床生理検査と技術 座談会
15巻4号(1987年4月発行)
技術講座 生理
15巻3号(1987年3月発行)
技術講座 血液
15巻2号(1987年2月発行)
技術講座 一般
15巻1号(1987年1月発行)
技術講座 病理
14巻13号(1986年12月発行)
技術講座 一般
14巻12号(1986年11月発行)
技術講座 病理
14巻11号(1986年10月発行)
技術講座 血清
14巻10号(1986年9月発行)
技術講座 血清
14巻9号(1986年8月発行)
技術講座 生理
14巻8号(1986年7月発行)
技術講座 血清
14巻7号(1986年6月発行)
技術講座 病理
14巻6号(1986年5月発行)
技術講座 生理
14巻5号(1986年4月発行)
形態学的検査と技術 血液と病理
14巻4号(1986年4月発行)
技術講座 病理
14巻3号(1986年3月発行)
技術講座 細菌
14巻2号(1986年2月発行)
技術講座 病理
14巻1号(1986年1月発行)
技術講座 細菌
13巻12号(1985年12月発行)
技術講座 病理
13巻11号(1985年11月発行)
技術講座 病理
13巻10号(1985年10月発行)
技術講座 生理
13巻9号(1985年9月発行)
技術講座 病理
13巻8号(1985年8月発行)
技術講座 病理
13巻7号(1985年7月発行)
技術講座 血液
13巻6号(1985年6月発行)
技術講座 一般
13巻5号(1985年5月発行)
技術講座 病理
13巻4号(1985年4月発行)
技術講座 一般
13巻3号(1985年3月発行)
技術講座 血液
13巻2号(1985年2月発行)
技術講座 一般
13巻1号(1985年1月発行)
技術講座 血液
12巻12号(1984年12月発行)
技術講座 血液
12巻11号(1984年11月発行)
技術講座 病理
12巻10号(1984年10月発行)
技術講座 輸血
12巻9号(1984年9月発行)
技術講座 一般
12巻8号(1984年8月発行)
技術講座 細菌
12巻7号(1984年7月発行)
技術講座 細菌
12巻6号(1984年6月発行)
技術講座 生理
12巻5号(1984年5月発行)
技術講座 一般
12巻4号(1984年4月発行)
技術講座 病理
12巻3号(1984年3月発行)
技術講座 血液
12巻2号(1984年2月発行)
技術講座 一般
12巻1号(1983年12月発行)
技術講座 血清
11巻12号(1983年12月発行)
技術講座 一般
11巻11号(1983年11月発行)
技術講座 細菌
11巻10号(1983年10月発行)
技術講座 細胞診
11巻9号(1983年9月発行)
技術講座 一般
11巻8号(1983年8月発行)
技術講座 血清
11巻7号(1983年7月発行)
技術講座 細菌
11巻6号(1983年6月発行)
技術講座 一般
11巻5号(1983年5月発行)
技術講座 病理
11巻4号(1983年4月発行)
技術講座 一般
11巻3号(1983年3月発行)
技術講座 血液
11巻2号(1983年2月発行)
技術講座 一般
11巻1号(1983年1月発行)
技術講座 血液
10巻12号(1982年12月発行)
技術講座 一般
10巻11号(1982年11月発行)
技術講座 生理
10巻10号(1982年10月発行)
技術講座 血清
10巻9号(1982年9月発行)
技術講座 細菌
10巻8号(1982年8月発行)
技術講座 一般
10巻7号(1982年7月発行)
技術講座 病理
10巻6号(1982年6月発行)
技術講座 細菌
10巻5号(1982年5月発行)
技術講座 病理
10巻4号(1982年4月発行)
技術講座 血清
10巻3号(1982年3月発行)
技術講座 生化学
10巻2号(1982年2月発行)
技術講座 病理
10巻1号(1982年1月発行)
技術講座 生化学
9巻12号(1981年12月発行)
技術講座 細菌
9巻11号(1981年11月発行)
技術講座 生理
9巻10号(1981年10月発行)
技術講座 一般
9巻9号(1981年9月発行)
技術講座 血清
9巻8号(1981年8月発行)
技術講座 血清
9巻7号(1981年7月発行)
技術講座 生理
9巻6号(1981年6月発行)
技術講座 細菌
9巻5号(1981年5月発行)
技術講座 一般
9巻4号(1981年4月発行)
技術講座 一般
9巻3号(1981年3月発行)
技術講座 血清
9巻2号(1981年2月発行)
技術講座 一般
9巻1号(1981年1月発行)
技術講座 生化学
8巻12号(1980年12月発行)
技術講座 一般
8巻11号(1980年11月発行)
技術講座 生理
8巻10号(1980年10月発行)
技術講座 検体の取り扱いと保存
8巻9号(1980年9月発行)
技術講座 病理
8巻8号(1980年8月発行)
技術講座 生化学
8巻7号(1980年7月発行)
技術講座 一般
8巻6号(1980年6月発行)
技術講座 生理
8巻5号(1980年5月発行)
技術講座 生化学
8巻4号(1980年4月発行)
技術講座 血清
8巻3号(1980年3月発行)
技術講座 病理
8巻2号(1980年2月発行)
技術講座 一般
8巻1号(1980年1月発行)
技術講座 生化学
7巻12号(1979年12月発行)
技術講座 一般
7巻11号(1979年11月発行)
技術講座 一般
7巻10号(1979年10月発行)
技術講座 細菌
7巻9号(1979年9月発行)
技術講座 生理
7巻8号(1979年8月発行)
技術講座 病理
7巻7号(1979年7月発行)
技術講座 生理
7巻6号(1979年6月発行)
技術講座 一般
7巻5号(1979年5月発行)
技術講座 血液
7巻4号(1979年4月発行)
技術講座 生理
7巻3号(1979年3月発行)
技術講座 病理
7巻2号(1979年2月発行)
技術講座 細菌
7巻1号(1979年1月発行)
技術講座 生化学
6巻12号(1978年12月発行)
技術講座 細菌
6巻11号(1978年11月発行)
技術講座 病理
6巻10号(1978年10月発行)
技術講座 血清
6巻9号(1978年9月発行)
技術講座 細菌
6巻8号(1978年8月発行)
技術講座 生化学
6巻7号(1978年7月発行)
技術講座 一般
6巻6号(1978年6月発行)
技術講座 病理
6巻5号(1978年5月発行)
技術講座 生理
6巻4号(1978年4月発行)
技術講座 一般
6巻3号(1978年3月発行)
技術講座 病理
6巻2号(1978年2月発行)
技術講座 一般
6巻1号(1978年1月発行)
技術講座 病理
5巻12号(1977年12月発行)
技術講座 生理
5巻11号(1977年11月発行)
技術講座 一般
5巻10号(1977年10月発行)
技術講座 細菌付録
5巻9号(1977年9月発行)
技術講座 一般
5巻8号(1977年8月発行)
技術講座 生理
5巻7号(1977年7月発行)
技術講座 一般
5巻6号(1977年6月発行)
技術講座 一般
5巻5号(1977年5月発行)
技術講座 一般
5巻4号(1977年4月発行)
技術講座 一般
5巻3号(1977年3月発行)
技術講座 一般
5巻2号(1977年2月発行)
技術講座 一般
5巻1号(1977年1月発行)
技術講座 一般
4巻12号(1976年12月発行)
技術講座 一般
4巻11号(1976年11月発行)
技術講座 一般
4巻10号(1976年10月発行)
技術講座 一般
4巻9号(1976年9月発行)
技術講座 一般
4巻8号(1976年8月発行)
技術講座 一般
4巻7号(1976年7月発行)
技術講座 一般
4巻6号(1976年6月発行)
技術講座 一般
4巻5号(1976年5月発行)
技術講座 一般
4巻4号(1976年4月発行)
技術講座 一般
4巻3号(1976年3月発行)
技術講座 一般
4巻2号(1976年2月発行)
技術講座 一般
4巻1号(1976年1月発行)
技術講座 一般
3巻12号(1975年12月発行)
技術講座 一般
3巻11号(1975年11月発行)
技術講座 一般
3巻10号(1975年10月発行)
技術講座 一般
3巻9号(1975年9月発行)
技術講座 一般
3巻7号(1975年8月発行)
特集 必修 日常検査の実技
3巻6号(1975年6月発行)
技術講座 生理
3巻5号(1975年5月発行)
技術講座 一般
3巻4号(1975年4月発行)
技術講座 一般
3巻3号(1975年3月発行)
技術講座 一般
3巻2号(1975年2月発行)
技術講座 一般
3巻1号(1975年1月発行)
技術講座 一般
