細胞診断,血液診断および尿沈渣診断はいずれも高度な形態学的診断能力を要求される検査です.本増刊号は連載「Laboratory Practice」の病理『細胞診でここまでわかる』(2000年4月号~2004年3月号),血液『骨髄塗抹標本の見かた』(2000年1月号~2004年1月号)そして2000年1月号から2001年12月号までの2年間にわたり本誌の表紙を飾った『今月の表紙―尿沈渣』を一冊にまとめたものです.各号それぞれ,疾患の具体的な解説に加えて厳選されたきれいな画像を添えることを基本として,必要に応じて疾患概念や知識のまとめを概説したものでしたが,このような充実した内容であったことが再認識され,執筆者全員に改めて敬意を表したい気持ちと同時に,系統的に再構成されて参考書あるいは教科書ともいえる出来栄えに仕上がったことにわれわれ編集委員一同,一種の達成感を感じています.
わが国の細胞診断は国際的な流れと異なり,依然パパニコロウ分類に準拠したクラス分類を行っています.このような現状にあって,もっとも大切なことは推定組織診断を明記することや臨床診断にとって有意義なコメントを併記することであると思われます.そのためにも臨床的知識や病態の理解が必要とされます.そして細胞診断経験を確実にするために,生検や手術検体の組織診断を確認することによって絶えず細胞診断能力にフィードバックをすることも必要と考えます.
雑誌目次
検査と技術32巻10号
2004年09月発行
雑誌目次
増刊号 細胞像の見かた―病理・血液・尿沈渣
序 フリーアクセス
著者: 松谷章司
ページ範囲:P.879 - P.879
第1章 病理 細胞像からここまでわかる 1.子宮頸部
1)正常組織・細胞
著者: 都竹正文 , 手島英雄
ページ範囲:P.882 - P.883
子宮腟部のコルポ像(図2)
コルポスコープ(子宮腟部拡大鏡,図1)を用いた正常子宮腟部像である.肉眼的に中心部は赤く見え(矢印(1)),外側は白く見える(矢印(2)).赤く見える部分を子宮腟部ビランと表現するが,粘膜が欠損する“真のビラン”ではなく,1層の高円柱上皮で被覆されているためにビラン様に赤く見える“偽ビラン”である.
外側は重層扁平上皮で構成されるために白く見える.両者の境界部分を移行帯(transformation zone)と呼び,扁平上皮化生(squamous metaplasia)が生ずる部分である(矢印(3)).
2)良性細胞・組織
著者: 都竹正文 , 手島英雄
ページ範囲:P.884 - P.885
老人性萎縮の組織と細胞像
子宮腟部の重層扁平上皮は,有経婦人(初経から閉経まで)では20~30層と厚く,基底膜上の基底細胞から傍基底,中間層,表層細胞へと成熟する(図1).老人性萎縮とは,卵巣機能の停止(閉経)に伴い,腟粘膜の扁平上皮は成熟機能が失われて萎縮し,数層の薄い上皮へと変化した状態をいう(図2).そのため,感染に対して抵抗力が弱く,容易に炎症を起こしやすくなる.したがって,腟粘膜の細胞成熟度指数(maturation index,MI)は100/0/0の傍基底型を示し,感染による炎症性背景を伴っている.炎症刺激を受けた傍基底型細胞は核増大,クロマチンの粗米造化,核縁の不整などを示すため,N/C比(nuclear-cytoplasmic ratio,核-細胞質比)が大きくなり,しばしば悪性細胞との判別が難しくなることがある(図3-a).したがって,このような場合はエストロゲン投与によってその回復状態を観察することも必要となる.また,剥離細胞標本では背景に炎症細胞に加え,滲出物が見られ,傍基底細胞の細胞質の好酸化,核の膨化,核濃縮,核破砕,脱核細胞などの萎縮・変性によるいろいろな細胞変化も見られ,細胞像は多彩となる(図3-b).このため,扁平上皮癌との鑑別が必要となる.
平上皮化生細胞と組織
化生変化とは,正常な組織細胞が異種の組織細胞に置き換えられる現象である.婦人科領域にあっては,偽ビランを伴う慢性頸管炎の場合に起こる.すなわち,円柱上皮下の予備細胞が増殖し,細胞を新生し▲平上皮に分化していく過程である(図4,初期化生の組織像:(1)円柱上皮下に(2)予備細胞が重層化して▲平上皮に変化している).このように化生変化を起こした場所から▲脱した細胞が化生細胞であるが,これは慢性頸管炎に必ず随伴するものではなく,むしろ出現頻度は低い.それは,化生途上にある組織細胞は結合力が強く,成熟した▲平上皮細胞のように容易に▲離することはないからである.
3)炎症と細胞診
著者: 都竹正文 , 手島英雄
ページ範囲:P.886 - P.887
濾胞性(リンパ球性)頸管炎(図1)
慢性頸管炎では表層上皮に真性ビランや偽ビラン,化生などの変化が生ずる.粘膜固有層にはリンパ球,形質細胞,単球,好中球の浸潤が見られる.通常,萎縮性腟炎の慢性化に起因して起こることが多い.細胞像は傍基底細胞主体の萎縮像を呈し,多数の成熟リンパ球と少数の類大型リンパ球,形質細胞および核の破砕物(cell debris)を貪食した組織球が散見される.これらの炎症細胞は標本中の数か所に集簇して見られる(図1-a).悪性リンパ腫との鑑別は,出現しているリンパ球の主体が成熟型であり,その他の炎症細胞の混在が見られるなど単一性に欠ける.特に核の破砕物を貪食した組織球(tingible body macrophages,矢印)の存在(図1-b)は悪性リンパ腫を否定するポイントとなる.
4)HPV感染の細胞診
著者: 都竹正文 , 手島英雄
ページ範囲:P.888 - P.889
はじめに
HPV(human papilloma virus,ヒト乳頭腫ウイルス)が子宮頸癌の発癌過程に深く関与していることは,今日広く受け入れられている.特に前癌病変においては,細胞診でHPV感染を診断することが可能である.koilocyte,parakeratocyte(dyskeratocyte),smudged nucleus,giant cell,二核あるいは多核細胞の出現をもって細胞診断がなされている.
HPVにはおよそ100種類があり,うち子宮頸癌と特に関係があるとされるタイプは16,18,33,52,58型であり,これらのタイプが前癌病変で確認された場合は厳密な臨床管理,フォローアップが必要である.HPVは前癌病変の90~95%に確認されている.尖形コンジローマからはHPV6,11型が確認されているが,このタイプのHPV型は発癌には関与しないとされている.図1に見られる腟壁の白色の隆起性病変(矢印(1))および子宮腟部の白色上皮層(矢印(2))が尖形コンジローマの病変で,いわゆるSTD(sexulally transmitted disease,性行為感染症)として臨床的に扱われる.この病変からは癌化しない.治療はレーザー蒸散術,凍結療法や抗DNA療法などが考慮される.
子宮頸癌および前癌病変と関係があるとされるタイプにはHPV-DNAの16,18,33,52,58型があり,それを証明したものが図2,3である.図2は子宮頸部に発生した中等度異形成であるが,ヘマトキシリン-エオジン染色(hemato-xylin-eosin stain,HE染色)での組織像ではHPVの感染の証拠を見いだすことは困難である.図3は同様の組織にHPV-DNA(16,18型)を証明するためのin situ hybridization(ISH)法を施行したもので,異形成由来細胞の核はHPV-DNAに置換され黒く染まって見える.したがって,HPV感染の事実が明らかである.HPVの検出にはこの他にサザンブロット法(Southern blotting),PCR(polymerase chain reaction,ポリメラーゼ連鎖反応法)などの分子生物学的手法がある.
5)子宮頸部異形成-上皮内癌の細胞診
著者: 都竹正文 , 手島英雄
ページ範囲:P.890 - P.891
はじめに
子宮頸部の異形成(dysplasia)は炎症性とも腫瘍性とも,また良性とも悪性とも判断しかねる扁平上皮の異型病変を呼び,境界病変として位置づけられている.異形成は病理組織学的に上皮の各層において細胞成熟過程の乱れと核の異常を示す病変である.すなわち,極性の消失,多形性,核クロマチンの粗大顆粒状化,核形不整,異常分裂を含む核分裂像が見られるのを特徴とする.異形成はその程度により軽度(mild=slight),中等度(moderate),高度(severe)に分けられる.
子宮頸癌取扱い規約(1997年10月,改訂第2版)では異形成(dysplasia)-上皮内癌(carcinoma in situ)は子宮頸部上皮内腫瘍(cervical intraepithelial neoplasia,CIN)として取り扱われており,軽度異形成(mild dysplasia;CIN1),中等度異形成(moderate dysplasia;CIN2),高度異形成(severe dysplasia;CIN3),上皮内癌(carcinoma in situ;CIN3)に分類されている.本規約ではHPV感染による細胞異型であるコイロサイトーシス(koilocytosis, koilocytotic atypia)は軽度異形成に含まれる.高度異形成と上皮内癌はCIN分類ではCIN3として包括されている.
婦人科細胞診の新しい記載法であるベセスダ方式(The Bethesda System)では従来用いられてきた上皮内病変の記載方式である異形成-上皮内癌(CIN)分類を扁平上皮内病変(squamous intraepithelial lesions)とし,軽度扁平上皮内病変(low grade squamous intraepithelial lesion,LSIL)と高度扁平上皮内病変(high grade squamous intraepithelial lesion,HSIL)の二つに分類されている.HPVに特徴的な細胞の変化,軽度異形成および両者の共存は軽度扁平上皮内病変(low grade squamous intraepithelial lesion,LSIL)とされる.中等度異形成,高度異形成-上皮内癌(CIN2 and 3)は高度扁平上皮内病変(high grade squamous intraepithelial lesion,HSIL)とされている.また,本規約ではHPV感染による細胞異型であるコイロサイトーシスが軽度異形成に含まれるため,軽度異形成の範囲が前規約より広くなった.
臨床的に,軽度および中等度異形成は経過観察とされ,その多くは消退していく.高度異形成は経過を追うと他の異形成よりも癌が発生する危険性が高いとされ,上皮内癌に準じた臨床的扱いを受ける.これらの病変は30歳台に多く,近年,さらに若年化の傾向にある.異形成-上皮内癌の好発部位は子宮腟・頸部の扁平・円柱上皮境界(squamo-columnar junction,SCJ)の円柱上皮側である.
6)子宮頸部扁平上皮癌の細胞診
著者: 都竹正文 , 手島英雄
ページ範囲:P.892 - P.894
微小浸潤平上皮癌
子宮頸部の微小浸潤扁平上皮癌(microinvasive squamous cell carcinoma)は微小浸潤を示す扁平上皮癌である(図1;矢印).
子宮頸癌取扱い規約(1997年,改訂第2版)では,微小浸潤とは癌細胞の間質内浸潤を組織学的に確認することができ,かつ浸潤の深さが表層基底膜より計測して5mmを超えず,またその縦軸方向の拡がりが7mmを超えないものとされている.本病変は臨床進行期ではIa期に分類される.なお,さらに浸潤の深さが3mmを超えないものをIa1期,それ以外のものをIa2期と定めている.
7)子宮頸部腺癌の細胞診
著者: 都竹正文 , 手島英雄
ページ範囲:P.895 - P.897
はじめに
子宮頸部の腺異形成(glandular dysplasia)は扁平上皮の異形成に匹敵する良性とも悪性とも判断しかねる腺上皮の異型病変を呼び,境界病変として位置付けられている.腺異形成は,子宮頸癌取扱い規約の組織分類と診断基準のなかで,核の異常が反応性異型よりも高度であるが,上皮内腺癌の診断基準を満たさない腺上皮の病変をいう,とある.腺異形成の診断に際しては,反応性異型および上皮内腺癌との鑑別が問題となる.これらの鑑別には,細胞および核の大きさ,形状,N/C比(nuclear-cytoplasmic ratio,核-細胞質比),核クロマチンの状態,核小体の形態,核分裂像などの細胞異型と,細胞の重層化,乳頭状や篩状構造などの構造異型を参考とし,さらに共存する炎症反応の有無とその程度なども参考にする.著しい炎症や放射線照射により生じる内頸腺上皮の反応性異型は,核の大型化,多核化,クロマチンの増量,核小体の出現を伴うが核分裂像に乏しく,細胞の重層化などの構造異型はほとんどない.
これに対し腺異形成では,核の変化が反応性異型よりもさらに強く核分裂像も出現するが,上皮内腺癌よりも軽度である.細胞の偽重層性は見られるが,乳頭状や篩状構造は見られない,とされている.細胞診による腺異形成の診断は現段階では極めて困難であり,組織学的診断基準の細胞異型と同様に,上皮内腺癌よりも軽度であるといった程度の極めて曖昧な表現にせざるを得ない.
2.子宮体部
1)子宮内膜の正常組織・細胞
著者: 都竹正文 , 平井康夫
ページ範囲:P.898 - P.900
子宮体部の構造
子宮体部の壁は内腔側から,子宮内膜(endometrium),子宮筋層(myometrium),子宮外膜(perimetrium)の順で構成されている.
子宮筋層は厚さ1cmを超える平滑筋の層である.子宮外膜は結合組織から成っており,子宮の上部では漿膜が最外層を被っている.子宮内膜(以下,内膜)は被覆上皮,内膜腺,間質から構成される.被覆上皮および内膜腺は単層の円柱上皮で,線毛細胞と分泌機能を有する細胞から成るが,内膜腺では後者がほとんどを占める.内膜はまた月経時に剥離しないで残る深層の基底層と,月経時に剥離,放出される表層の機能層とに分けられる.基底層の内膜腺は月経周期によってほとんど変化せず,増殖期初期の内膜腺に類似した像を呈する.
2)子宮内膜の腫瘍関連病変
著者: 都竹正文 , 平井康夫
ページ範囲:P.901 - P.903
子宮内膜増殖症と子宮内膜異型増殖症
子宮体癌取扱い規約(改訂第2版,1996年3月)では,子宮内膜の上皮性腫瘍と関連病変には,悪性腫瘍としての子宮内膜癌,関連病変としての子宮内膜増殖症,子宮内膜異型増殖症および子宮内膜ポリープが含まれるとある.子宮内膜の過剰増殖を上皮細胞の異型(細胞の増大,極性の乱れ,N/C比(nuclear-cytoplasmic ratio,核-細胞質比)の増大,大きさと形の不均一,円形化,輪郭の不規則,クロマチンの増量と核膜の肥厚,核小体の肥大など)の有無により,子宮内膜増殖症(以下,内膜増殖症)と子宮内膜異型増殖症(以下,異型増殖症)の二つの範疇に分ける.さらに各々の範疇は,腺構造の異常の程度により単純型と複雑型で表す.
単純型:腺の嚢胞化と軽度ないし中等度の構造不整を示すものを含む.
3)子宮内膜の上皮性腫瘍
著者: 都竹正文 , 平井康夫
ページ範囲:P.904 - P.906
子宮内膜癌
子宮体癌取扱い規約(改訂第2版,1996年3月)では,子宮内膜の上皮性悪性腫瘍には子宮内膜癌(endometrial carcinoma)がある.子宮内膜癌は子宮内膜に発生する癌腫で,子宮内膜の悪性腫瘍のうちでは最も頻度が高い.
類内膜癌(endometrioid carcinoma)
類内膜癌は類内膜腺癌と扁平上皮への分化を伴う類内膜腺癌とに分けられる.
4)子宮内膜の間葉性腫瘍および上皮性・間葉性混合腫瘍
著者: 都竹正文 , 平井康夫
ページ範囲:P.907 - P.910
子宮内膜の間葉性腫瘍と関連病変
子宮体癌取扱い規約(改訂第2版,1996年3月)では,子宮内膜の間葉性腫瘍と関連病変は,子宮内膜間質腫瘍,平滑筋腫瘍,子宮内膜間質・平滑筋混合腫瘍,アデノマトイド腫瘍およびその他の間葉性腫瘍に分類される.
1. 子宮内膜間質腫瘍(endometrial stromal tumour)
子宮内膜間質腫瘍は,子宮内膜間質結節,低悪性度子宮内膜間質肉腫,高悪性度子宮内膜間質肉腫に分類される.
3.乳 腺
1)浸潤性乳管癌:硬癌
著者: 都竹正文 , 秋山太
ページ範囲:P.911 - P.913
はじめに
乳癌取扱い規約(改訂第14版,2000年9月)では,乳腺腫瘍の組織学的分類(表)では,. 上皮性腫瘍はA. 良性腫瘍,B. 悪性腫瘍に分類され,さらに. 結合織性および上皮性混合腫瘍,. 非上皮性腫瘍,. 分類不能腫瘍,. 乳腺症,. 腫瘍様病変に分類されている.悪性腫瘍は1 . 非浸潤癌,2 . 浸潤癌,3 . Paget病に分類されている.1 . 非浸潤癌はa. 非浸潤性乳管癌とb. 非浸潤性小葉癌に細分類されている.2 . 浸潤癌はa. 浸潤性乳管癌とb. 特殊型に分類され,浸潤性乳管癌は,さらにa1. 乳頭腺管癌,a2. 充実腺管癌,a3. 硬癌に亜分類されている.b. 特殊型はb1. 粘液癌,b2. 髄様癌,b3. 浸潤性小葉癌,b4. 腺様嚢胞癌,b5. 扁平上皮癌,b6. 紡錘細胞癌,b7. アポクリン癌,b8. 骨・軟骨化生を伴う癌,b9. 管状癌,b10. 分泌癌,b11. その他に亜分類されている.悪性腫瘍のうち,非浸潤癌,浸潤癌の発生頻度は非浸潤癌約10%,浸潤癌90%の割合である.浸潤癌のうち,浸潤性乳管癌の発生頻度は乳癌全体の約80%で,乳頭腺管癌約20%,充実腺管癌約20%,硬癌約40%で1:1:2の関係である.特殊型は乳癌全体の約10%で,粘液癌約4%,浸潤性小葉癌約4%,その他全部合わせて約2%と極めて少数である.
今回は乳腺の悪性腫瘍のうち最も発生頻度の高い硬癌を取り上げ解説する.
2)浸潤性乳管癌:充実腺管癌
著者: 都竹正文 , 秋山太
ページ範囲:P.914 - P.916
浸潤性乳管癌:充実腺管癌
乳腺の悪性腫瘍のうちで硬癌に次いで頻度の高い充実腺管癌を取り上げ解説する.
充実腺管癌(solid-tubular carcinoma)は充実性癌巣の周囲組織への圧排性・膨張性増殖を特徴とする癌で,髄様癌の特徴を示さないものをいう.組織学的分化度は中分化ないし低分化乳癌に相当し,予後は乳頭腺管癌と硬癌の中間に位置する.乳癌の約20%占め,組織学的特徴は癌巣の周囲の辺縁部は全周にわたって境界が明瞭で癌巣内部は主に大型の充実性癌胞巣の密在から成り,間質結合織の乏しいものをいう.充実性癌胞巣の大部分は浸潤性癌胞巣であり,充実腺管癌と非浸潤性乳管癌との鑑別が問題となる例はほとんどない.
3)浸潤性乳管癌:乳頭腺管癌
著者: 都竹正文 , 秋山太
ページ範囲:P.917 - P.919
浸潤性乳管癌:乳頭腺管癌
乳腺の悪性腫瘍のうち充実腺管癌と並んで頻度の高い乳頭腺管癌を取り上げ解説する.
乳頭腺管癌(papillotubular carcinoma)とは乳管内増殖を特徴とする癌である.乳頭状および腺腔形成性増殖が著しい癌で,間質結合織の増生の乏しいものをいい,その多くは乳管内増殖が著しいものである.乳頭腺管癌は高分化乳癌に相当し,予後はよい.わが国では乳癌の約20%を占めている.乳房X線画像(マンモグラフィ)上,本型は腫瘍内に微細石灰化を伴うことがあり,また,時に乳房内に広く微細石灰化や拡張乳管像として認めることがある.なお,微細石灰化像は良性病変でも生ずることがあることは周知のとおりである(図1,2).
4)特殊型乳癌:粘液癌
著者: 都竹正文 , 秋山太
ページ範囲:P.920 - P.922
浸潤性乳管癌:粘液癌
特殊型乳癌のうち比較的頻度の高い粘液癌を取り上げ解説する.
粘液癌(mucinous carcinoma)は浸潤性乳管癌の特殊型乳癌である.本疾患が粘液癌と呼ばれるのは腫瘍細胞が産生した粘液が通常,肉眼的にも顕微鏡的にも豊富に見られるためである.本疾患は細胞外への粘液産生を特徴とする浸潤性乳管癌をいうが,非浸潤性乳管癌のうちにも乳管内に豊富な粘液貯留を呈するものがごく稀にみられる.これらは,現在の規約では,粘液癌に分類しないことになっている.また,いわゆる浸潤性乳管癌癌巣の一部に粘液癌と同じ組織像を認めるものも比較的多くみられるが,このような症例に対してはinvasive ductal carcinoma associated with partially mucus producting features(図8,9)と診断される.すなわち,現在の乳癌取扱い規約では,腫瘍内に粘液産生性癌巣が大部分を占め,これが優位なものを粘液癌としている.本疾患の亜型分類については,一般に純型(pure type)と混合型(mixed type)とに分類されている.純型は癌巣全体が粘液膠様のものをいう.また,混合型は癌胞巣が粘液巣に包まれることなく,その一部に通常の浸潤性乳管癌癌巣が観察される.すなわち,粘液癌と浸潤性乳管癌との混在したものである.
5)特殊型乳癌:浸潤性小葉癌
著者: 都竹正文 , 秋山太
ページ範囲:P.923 - P.926
浸潤性小葉癌
(invasive lobular carcinoma)
特殊型乳癌の浸潤性小葉癌を取り上げ解説する.
本型は1941年にFooteとStewartによってその概念が初めて提示されたが,小葉癌の浸潤型である.浸潤癌・特殊型に分類されている.他の特殊型乳癌の組織型が基本的には乳管上皮から発生するなかで浸潤性小葉癌のみは小葉内細乳管上皮から発生する癌である点が異なっている.Stewartが乳癌の組織型を乳管癌と小葉癌とに大別し,それぞれを非浸潤と浸潤とに分類したことでもわかるように,本型は浸潤癌・特殊型のなかでも特異な存在であるともいえる.
6)パジェット病
著者: 都竹正文 , 秋山太
ページ範囲:P.927 - P.930
概念および臨床的事項
乳癌取扱い規約(改訂第14版,2000年9月)では,乳腺腫瘍の組織学的分類(911頁の表を参照)では,. 上皮性腫瘍はA. 良性腫瘍,B. 悪性腫瘍に分類され,さらに. 結合織性および上皮性混合腫瘍,. 非上皮性腫瘍,. 分類不能腫瘍,. 乳腺症,. 腫瘍様病変に分類されている.悪性腫瘍は1 . 非浸潤癌,2 . 浸潤癌,3 . Paget病に分類されている.
パジェット病(Paget's disease)は臨床的には乳頭部の湿疹様皮膚病変を示し,組織学的には乳管癌細胞の乳頭表皮への進展を特徴とする乳癌の一型である.本症が癌と関係あることを初めて記載したのはSir James Pagetであり1874年に報告している.これがパジェット病の名の由来とされている.
7)乳管内乳頭腫
著者: 都竹正文 , 秋山太
ページ範囲:P.931 - P.933
概念および臨床的事項
乳管内乳頭腫(intraductal papilloma,IDP)は乳腺発生の代表的な良性腫瘍である.この腫瘍は拡張した乳管壁から血管結合組織より成る茎が突出して樹枝状に伸び,その表面が筋上皮細胞と上皮細胞との二層構造でおおわれた乳管内の増殖性病変である.乳頭に近い大きい乳管に見られる病変はしばしば嚢胞状に拡張するので嚢胞内乳頭腫(intracystic papilloma,ICP)と呼ばれる.したがって,嚢胞内乳頭腫は基本的には乳管内乳頭腫の変化したものである.通常,単発性で血性分泌物や腫瘤触知を主訴とする.肉眼的に観察されるような大きさの乳管内乳頭腫は孤立性乳頭腫とも呼ばれている.一方,末梢の小葉間乳管に至るまでの小乳管にしばしばみられる末梢乳管の乳頭腫は,小さく顕微鏡的に観察され,多発性乳頭腫(multiple papilloma)としてみられることが多い.このように末梢部にみられる乳頭腫は癌に合併してみられたり,上皮過形成(epithelial hyperplasia)を伴うことが多く,通常は乳腺症あるいは線維嚢胞症として腫瘤を形成する病変群の一つの所見として観察されることが多い.しかし,これらの病変のうちで,血管結合織性の茎を持たない乳管上皮の過形成は乳管乳頭腫症(duct papillomatosis)と呼ばれ乳管内乳頭腫と混同されやすいが,両者は明確に区別するべきである.
大きな乳管,特に乳頭直下の乳管内乳頭腫は2~3mmから2~3cmの大きさになるが,腫瘍の大小にかかわらず,乳頭血性分泌物を主訴とする.大きな乳管内乳頭腫や嚢胞内乳頭腫は乳腺内腫瘤として触知されることも多いが超音波検査で発見されることもある.治療としては,これらの大きな孤立性乳頭腫は腫瘤切除が行われる.発生年齢は40~50歳の中年にみられるが,高齢者の場合,上皮過形成や癌を合併することが多いといわれている.特に,末梢乳管に発生する多発性乳管内乳頭腫は癌発生のリスク病変としての報告がみられ,これらは異型を伴う上皮過形成と合併することが多いことから前癌性病変としてとらえ,注意深く経過観察する必要がある.一般に乳管内乳頭腫と癌の関係については,大きな乳管で孤立性のものより,末梢乳管で多発するもののほうが癌化の危険性が高いと考えられている.
8)線維腺腫
著者: 都竹正文 , 秋山太
ページ範囲:P.934 - P.937
概念および臨床的事項
線維腺腫(fibroadenoma)は乳腺組織の間質線維性結合組織(以下,間質結合織)と上皮(乳管上皮)との両成分で構成される良性腫瘍である.臨床的には20~40歳代の女性に多く発生し,可動性良好で薄い被膜で被われた限局性腫瘤である(図1~3).通常,乳房内に孤立性(稀に両側性,多発性)の境界明瞭な2~4cm大の腫瘤として触知される.腫瘤の硬度は弾性硬から硬まで種々の硬さを呈する.若い女性に発生する線維腺腫は時に急速に発育増大し,8~10cm大の巨大な腫瘍を形成することもあり,特に重さが500g以上もある場合には巨大線維腺腫(giant fibroadenoma)と呼ばれる.若年性線維腺腫(juvenile fibroadenoma)は青年期に発生し,急速に増大し,対側の乳房の2~4倍の大きさとなり,皮膚のひきつれや乳頭の偏在などを示すもので,組織学的には間質の細胞密度が比較的高いもので特別なものではない.
この腫瘍はエストロゲンを主体とするホルモン環境により増大,退縮傾向を示すことからエストロゲンに対する局所的感受性増大に起因するものであろうと考えられている.近年,わが国では線維腺腫が増加の傾向にあり,しかも上皮成分の増殖の著しい症例が増加の傾向にある.これは,わが国の生活様式や食生活の欧米化に伴うホルモン環境の変化によるものと考えられている.
9)葉状腫瘍
著者: 都竹正文 , 秋山太
ページ範囲:P.938 - P.941
概念および臨床的事項
葉状腫瘍(phyllodes tumor)は従来,葉状嚢胞肉腫(cystosarcoma phyllodes)といわれていた.肉腫という言葉が使われているにもかかわらず葉状嚢胞肉腫という名称自体は良性のものを指している.現在,乳癌取扱い規約では良性・悪性を含め,正式名称は葉状腫瘍とされており,葉状嚢胞肉腫も同義語として用いてもよいことになっている.なお,葉状腫瘍の間質成分が悪性化したものが悪性葉状腫瘍である.葉状腫瘍では組織像と生物学的性状とが完全に一致しない例もみられるが,組織形態から良性,境界病変,悪性に分類される.
悪性の判定は間質結合組織成分の細胞密度,細胞異型,核分裂像の頻度,腫瘍辺縁での周囲組織への浸潤性,さらに腺上皮成分と間質結合組織成分のバランスを乱しての間質結合組織成分の一方的増殖などから総合的に判断される.ただし,葉状腫瘍の良性・悪性の組織形態学的判定基準の線引きについては病理学者の間でも必ずしも意見の一致をみておらず,良性,境界病変,悪性の鑑別点について一定の線引きを示すことは,典型例を除き困難であるといわざるをえない.従来の判定基準より良性と診断されたものが悪性と診断されたものに比べて圧倒的に多い傾向にある.
10)顆粒細胞腫
著者: 都竹正文 , 秋山太
ページ範囲:P.942 - P.945
概念および臨床的事項
顆粒細胞腫(granular cell tumor)は,以前は顆粒細胞性筋芽腫(granular cell myoblastoma)といわれており,最初Abrikossoffが筋芽腫性筋腫(myoblastenmyom)と呼んだ腫瘍である(アブリコソフ腫瘍,Abrikossoff tumor).従来,筋原性が考えられたが,最近は電子顕微鏡(電顕)所見などからシュワン細胞(Schwann cell)起源を考える人が多い.しかし,平滑筋細胞やエナメル上皮(顆粒細胞性エナメル上皮腫,granular cell ameloblastoma)にも同様の顆粒が出現することが知られており,この腫瘍が単一細胞起源でないという人もいる.舌に最も多く,ほかに乳房,外陰,消化管,皮膚,皮下などにも発生する.皮下など軟部のものは胸壁,腹壁など躯幹に多い.乳房や皮下では被包された腫瘍塊(図1,2)を作るが,舌などでは被膜を有しないものが多い.大きさは直径10~20mmのものがほとんどであり,巨大にはならない.
顆粒細胞腫は原則として良性であるが,軟部に発生したものでは極めて稀に転移を起こすことがある.こういうものを悪性型として区別する.女性での頻度が高く,40mmを超える大きなものが多く,これらは浸潤性で壊死を認めることもある.組織形態は良性例のそれとほぼ同様であるが,N/C比(nuclear-cytoplasmic ratio,核-細胞質比)の増加,核の多形性,大型の核小体,分裂像の増加,紡錘形細胞の出現,壊死の存在が挙げられており,このうち三つ以上の所見を認めるものが悪性とみなされる.
4.呼吸器
1)正常組織・細胞と反応性変化
著者: 堀内啓 , 荒井政和 , 松谷章司
ページ範囲:P.946 - P.947
呼吸器系の組織構造
呼吸器系は大別して気道と肺とに分かれ,前者は鼻腔,咽頭,喉頭,気管および気管支から成る.鼻腔は多列線毛円柱上皮により覆われている.咽頭は上・中・下咽頭に分けられ,上咽頭は多列線毛円柱上皮,中・下咽頭は重層扁平上皮に覆われている.喉頭はその大部分が杯細胞を含む多列線毛円柱上皮に覆われ,一部(喉頭蓋前面,声帯ヒダ,室ヒダの一部)に重層扁平上皮が存在し,輪状軟骨を境に気管となる.気管はさらに,気管支,細気管支,終末細気管支,呼吸細気管支,肺胞道,肺胞・肺胞嚢となる.気管の粘膜は,杯細胞を含む線毛円柱上皮に覆われ,基底膜側に予備細胞が存在する.これらの上皮を取り囲むように軟骨や線維性結合組織が存在し,その中に気管付属腺や平滑筋がある(図1).気管支の上皮は,基本的に気管と同様ではあるが,細気管支を境に軟骨は消失し,杯細胞は減少し,それに代わってクララ細胞(Clara cell)が出現する.また,付属腺も徐々に消失する.気管から細気管支に至るまで,リンパ装置が結合組織中に認められ,bronchus-associated lymphoid tissue(BALT)と呼ばれる.肺胞はガス交換を司る扁平な型肺胞上皮細胞と,オスミウム酸好性のサーファクタントを分泌する立方状の型肺胞上皮細胞で覆われている.また,肺胞腔内には炭粉を含む肺胞マクロファージ(dust cell)が存在する(図9).
正常な細胞像
細胞診に提出される呼吸器の検体としては,喀痰,気管支擦過物,気管支洗浄液,気管支肺胞洗浄液(bronchoalveolar lavage,BAL),経気管支的穿刺吸引細胞診,経皮的穿刺吸引細胞診などがある.これらの検体に出現しうる細胞には,上皮系細胞としては口腔由来の▲平上皮細胞,気道系由来の線毛円柱上皮細胞,杯細胞,肺胞上皮細胞などがあり,間葉系細胞としては筋細胞,軟骨細胞,線維芽細胞,血球系の細胞としては赤血球,好中球,好酸球,リンパ球,組織球,巨核球などがある.喀痰は健常人ではほとんど出ない.検体中にdust cellが含まれていることが,肺から採取された検体であることの根拠になり,この細胞が存在しない検体は,肺の細胞診検体としては不適切といえる.
2)扁平上皮癌
著者: 堀内啓 , 荒井政和 , 松谷章司
ページ範囲:P.948 - P.950
臨床的特徴
肺の扁平上皮癌は50~60歳台に好発し,男性に多い.好発部位は肺門部近傍の中枢部だが,女性では,末梢肺野に発生する場合が多い.他の組織型の肺癌に比べて,転移率はやや低い.重要な初発症状に血痰がある.危険因子には,喫煙がよく知られている.また,職業性肺癌としてクロム肺癌がある.扁平上皮癌では,ときに高カルシウム血症を伴うことがある.これは,腫瘍が副甲状腺ホルモン関連蛋白(parathyroid hormone related protein,PTH related protein)を産生するためである.放射線および化学療法は比較的有効とされている.
正常平上皮の特徴
扁平上皮癌は,扁平上皮への分化を示す悪性腫瘍である.扁平上皮への分化は,病理学的には角化と細胞間橋の形成がその指標となる.正常な角化型扁平上皮では,基底側から表面に向かって,基底細胞層,有棘細胞層,顆粒細胞層,角化層という層構造が見られる.細胞間橋は有棘細胞層において明瞭で,隣接する細胞の細胞膜の間に,細胞膜に直行する等間隔の突起として認められる.細胞膜と細胞間橋は全体として梯子状に見える.角化層では,細胞質の好酸性が増す.一般に,角化自体は細胞質に見られる現象であるが,角化するとともに核も濃染して小型化し,いずれ消失する(図1).錯角化(parakeratosis)や異角化(dyskeratosis)などの異常角化では,核が消失せず濃縮状の小型核が認められる.細胞全体の形状も,基底側では立方形あるいは球形に近いが,表面に移行するとともに円盤状の扁平な細胞に変化する.扁平上皮組織では,このような基底細胞層から角化層へ至る成熟過程が存在し,このような成熟傾向の有無を“極性がある・ない”と表現する.
3)腺 癌
著者: 堀内啓 , 荒井政和 , 松谷章司
ページ範囲:P.951 - P.953
腺癌の臨床的特徴と分類
腺癌は肺癌の約30%を占める.肺の末梢領域に好発し,喫煙との関係は不明である.男女比は約2:1で発症年齢は扁平上皮癌よりやや若い.
肺の腺癌は管状構造,乳頭状構造を示すか,これらの構造がなくとも上皮性の粘液を産生する悪性腫瘍と定義されており,改訂WHO分類(1999年)では,腺房(管状)腺癌,乳頭腺癌,細気管支肺胞癌,粘液産生性充実癌,混合型腺癌,特殊な腺癌(胎児型腺癌など)に分類される.粘液産生性充実癌は,旧WHO分類では大細胞癌に分類されていた腫瘍である.本稿では,これらの中で頻度が高い,乳頭腺癌,細気管支肺胞癌を中心に解説する.
4)小細胞癌
著者: 堀内啓 , 荒井政和 , 松谷章司
ページ範囲:P.954 - P.956
臨床的特徴と分類
肺に発生する小細胞癌は,神経内分泌系(Kulchitsky細胞)への分化を示す腫瘍で,全肺癌の15~25%を占め,小型でN/C比(nuclear-cytoplasmic ratio,核-細胞形質比)が高いことが特徴である.好発年齢は40~60歳台が多く,男女比は4~5:1で男性に多い.喫煙との相関は扁平上皮癌に次いで強いとされている.化学療法,放射線療法の感受性が非常に高い腫瘍であるが,再発の頻度が高く,最も予後の悪い悪性腫瘍の一つでもある.最近では,集学的治療の成果により,発見が早ければ30%程度の5年生存率が得られる場合がある.小細胞癌はイートン-ランバート(Eaton-Lambert)症候群や,ACTH,カルシトニン,セロトニン,抗利尿ホルモンなどの生理活性物質の分泌による種々の腫瘍随伴症候群(paraneoplastic syndrome)を起こすことがある.
旧WHO分類で,小細胞癌は燕麦細胞型,中間細胞型,混合型燕麦細胞癌の3亜型に分類されていたが,亜型分類の再現性が低く臨床経過との関連性が乏しいことから,新WHO分類では小細胞癌の亜型分類は削除され,特殊型として混合型小細胞癌が記載されるのみとなった.わが国の肺癌取扱い規約では,燕麦細胞型と中間細胞型に分類されているが,将来的には新WHO分類に準じた方向に改定される可能性がある.
5)大細胞癌
著者: 堀内啓 , 荒井政和 , 松谷章司
ページ範囲:P.957 - P.959
臨床的特徴と分類
大細胞癌は,腫瘍が特定の分化傾向を示さず,扁平上皮癌,小細胞癌,腺癌の特徴的所見を欠く悪性上皮性腫瘍であり,他の組織型に分類することが不可能な,分化傾向を失った癌に対するゴミ箱(wastebasket)的な診断名といえる.したがって,生検で大細胞癌と診断されても,他の組織型の低分化成分を見ている可能性はあり,手術材料で特徴的な分化像が見つかれば,他の組織型に分類されることも稀ではない.
肺癌取扱い規約では,大細胞癌を粘液形成型と粘液非形成型に分類し,腫瘍細胞内に粘液が認められても,管腔形成がなければ腺癌とはしないが,WHO分類では,強拡大2視野中に5個以上粘液を持つ腫瘍細胞があれば腺癌に分類される.また,肺癌取扱い規約では,大細胞癌の中に巨細胞型という亜型を設けているが,WHO分類では巨細胞癌は大細胞癌とは別の項目で取り扱われている.WHO分類では,大細胞癌の亜型として,large cell neuroendocrine carcinoma, basaloid carcinoma, lymphoepithelioma-like carcinoma, clear cell carcinoma, large cell carcinoma with rhabdoid phenotypeが記載されている.
6)腺様嚢胞癌
著者: 堀内啓 , 荒井政和 , 松谷章司
ページ範囲:P.960 - P.962
臨床的特徴
腺様嚢胞癌は,気管支付属腺由来で,唾液腺型の特殊な肺癌の1つであり,他には粘表皮癌がこのグループに属する.発生率は原発性肺癌全体の0.2%以下である.通常は,気管下部や主気管支・葉気管支などの太い気管支に発生し,それより末梢に発生することは稀である.症状は,気道閉塞あるいは気道刺激に起因する症状を呈する.腫瘍が気管支内に発育するため,単純X線写真では腫瘤を見つけにくいが,気管支ファイバーでは容易に発見できる.腺様嚢癌は,しばしば気管支壁に沿って浸潤性に発育するため,不完全な切除となりやすく,術後何年も経過してから局所再発を起こすことも時に経験される.遠隔転移はまれである.予後は,通常の肺癌よりは良いが,他の気管支腺由来の腫瘍と比べると悪い.担癌状態で長期生存する症例もあり,通常の肺癌とは生物学的態度が異なる.
細胞像
(1)豊富な腫瘍細胞の出現
7)カルチノイド
著者: 堀内啓 , 荒井政和 , 松谷章司
ページ範囲:P.963 - P.965
臨床的特徴
カルチノイドは低悪性度の神経内分泌系腫瘍で,細胞質に神経内分泌顆粒を持つのが特徴である.カルチノイドは全肺腫瘍の1~2%を占め,発病年齢は腺癌より若く,男性にやや多い.発生部位により,中枢型と末梢型とに分かれるが,前者の方が多い.病理学的には,定型的カルチノイドと異型カルチノイドとに細分類され,後者はより悪性度の高い腫瘍であり,カルチノイド全体の約10%を占める.カルチノイドは,十分な切除が行われれば,予後は比較的良好である.
臨床症状は無症状のことが多く,血痰や腫瘍による閉塞性肺炎の症状が比較的頻度が高い.特徴的なのは,カルチノイドの産生するホルモンにより,カルチノイド症候群などの内分泌症状を示すことである.ただし,これらの腫瘍随伴症候群を呈する頻度は低く,カルチノイドの2~7%と報告されている.本症候群はカルチノイドから分泌されるセロトニンにより惹起されると考えられており,血中セロトニンの増加と,その終末産物である5-ヒドロキシインドールアセティックアシッド(5-hydroxyindol acetic acid,5-HIAA)が尿中に増加する.
8)粘表皮癌
著者: 堀内啓 , 荒井政和 , 松谷章司
ページ範囲:P.966 - P.968
臨床的特徴
粘表皮癌は,肺門部の主気管支や葉気管支などの太い気道に発生し,粘液を分泌する腺細胞,扁平上皮細胞,およびそれらの中間的な性格の細胞(中間型細胞)から成る腫瘍である.頻度は稀で,原発性肺癌の0.1~0.2%程度といわれている.若年者に好発し,約半数の症例では発症年齢が30歳以下である.太い気道の閉塞症状(咳,血痰,発熱)を示すことが多く,閉塞性肺炎を伴いやすいが,無症状のこともある.病理学的には,低悪性度と高悪性度との腫瘍に大別されるが,大部分は低悪性度の腫瘍で,全体の75~80%を占める.低悪性度の粘表皮癌では,リンパ節や他臓器に転移することは稀で,完全に切除されれば予後は良好である.
細胞像
【低悪性度粘表皮癌】
(1)粘液や細胞破砕物を含む背景
9)肺硬化性血管腫
著者: 堀内啓 , 荒井政和 , 松谷章司
ページ範囲:P.969 - P.971
臨床的特徴
肺硬化性血管腫は肺の良性腫瘍であり,その本態については,当初,血管内皮細胞の腫瘍性増殖と考えられ,硬化性血管腫と命名されたが,現在では,肺胞上皮への分化を示す上皮成分を主体とし,血管成分を種々の程度に含む腫瘍と考えられている.したがって,硬化性血管腫という名称は不適切であるが,歴史的にこの病名が広く用いられてきたので,現在でも硬化性血管腫という名称が用いられることが多い.肺硬化性血管腫は80%以上が女性に発生し,年齢は40~50代の中年に多い.好発部位は右下葉である.多くの場合,無症状で,胸部単純撮影で境界明瞭な円形あるいは楕円形の腫瘤影を偶然発見されることが多い.症状がある場合には,咳,胸痛,血痰,風邪様症状などがみられる.大部分は良性の経過をとるが,ごくまれに,肺門リンパ節転移を起こすことが知られている.
細胞像
(1)赤血球,泡沫細胞,ヘモジデリン貪食細胞が背景に出現
10)肺過誤腫
著者: 堀内啓 , 荒井政和 , 松谷章司
ページ範囲:P.972 - P.974
臨床的特徴
肺過誤腫は気管支周囲の間葉系組織に由来する腫瘍であり,軟骨,線維性結合組織,脂肪,平滑筋や,腫瘍内に取り込まれた気管支上皮が種々の程度に混合して腫瘤を形成する病変で,肺に結節性陰影を呈する疾患の7~14%を占める.男女比は2~4:1で,男性に多い.小児には稀で成人に好発し,50歳台に最も多い.末梢肺に発生するもの(肺実質型)と,気管支内に発育するもの(気管支内型)とがあり,前者のほうがより多く,無症候性の結節性病変として発見されるのが典型的である.気管支内型は,肺過誤腫全体の10~20%を占め,気管支閉塞に起因する症状(咳,血痰,呼吸困難,閉塞性肺炎など)を呈することが多い.
細胞像
(1)成熟した軟骨組織
11)肺アミロイド結節
著者: 堀内啓 , 荒井政和 , 松谷章司
ページ範囲:P.975 - P.976
臨床的特徴
アミロイドーシスには全身性のものと局所性のものとがあり,本稿で取り上げる肺アミロイド結節は局所性アミロイドーシスの一種である.本疾患では,肺あるいは気管支壁に,単発あるいは多発性の結節状のアミロイド沈着が見られるのが特徴である.臨床的には,成人に多く,胸部X線で単発あるいは多発性の結節影を呈し,そのため,種々の肺腫瘍との鑑別が問題となる.大きさは直径1~4cmのものが多く,年余にわたり緩徐に増大する.約10%では血清あるいは尿中に単クローン性の免疫グロブリンが検出される.生化学的には,沈着しているアミロイドは,AL型のアミロイド蛋白質であることが大部分である.
細胞像
(1)不規則な斑状の無構造物の出現
12)肺結核症
著者: 堀内啓 , 荒井政和 , 松谷章司
ページ範囲:P.977 - P.979
臨床的特徴
肺結核症は結核菌によって引き起こされる感染症である.日本での肺結核症の発生は,衛生状態の改善や有効な薬剤の開発により第二次世界大戦前に比べて激減したとはいえ,最近は逆にわずかながら増加傾向を示し,若年者での発症や集団感染の報告もあり,社会的にも軽視できない疾患である.AIDS(acquired immunodeficiency syndrome,後天性免疫不全症候群)などの免疫不全を背景として,肺結核が発症することもよく知られている.肺結核症には,結核性胸膜炎,粟粒結核,増殖性病変,滲出性病変などいろいろな病型がある.この中で,腫瘍と鑑別を要し,細胞診の対象となる場合があるのは,胸部X線で肺野に孤立性の結節影を形成する場合である.臨床的には,発熱・盗汗・血痰・咳嗽などがみられ,血沈の亢進やCRP(C-reactive protein,C反応性蛋白質)高値などの炎症を反映した検査所見を呈する.確定診断は喀痰中の結核菌を,喀痰塗沫標本の抗酸菌染色や,小川培地での培養で同定することであるが,塗沫標本での抗酸菌染色は検出率が低く,結核菌の培養には長期間を要するため,最近では喀痰中の結核菌由来のDNAをPCR法(polymerase chain reaction,ポリメラーゼ連鎖反応)で増幅して検出する方法も用いられている.PCR法による結核菌の検出は,鋭敏ではあるが,一方,検体中に結核菌のDNAが混入することなどによる偽陽性の可能性もある.確定診断を得るために気管支鏡により直接病変から組織を採取し,細菌培養や塗沫標本,さらに病理標本を作製することもしばしば行われている.類縁疾患に肺非定型抗酸菌症があるが,これは結核菌以外の抗酸菌による肺の感染症で,組織学的所見は肺結核と類似している.
細胞像
(1)背景の炎症性滲出物,乾酪壊死
13)肺クリプトコッカス症,肺アスペルギルス症
著者: 堀内啓 , 荒井政和 , 松谷章司
ページ範囲:P.980 - P.982
肺クリプトコッカス症
1. 臨床的特徴
クリプトコッカス症は,酵母型真菌の一種であるCryptococcus neoformansの感染症である.鳩の糞便中に菌体が含まれ,経気道的にヒトに感染する.肺クリプトコッカス症は,単発性の境界明瞭な結節を形成し,肺癌との鑑別が問題となる.自然治癒する場合もある.
2. 細胞像
(1)直径5~20μmの酵母様真菌
5.体腔液
1)体腔液に出現する非腫瘍性細胞
著者: 堀内啓 , 原田弥生 , 松谷章司
ページ範囲:P.984 - P.987
体腔の解剖―組織学
体腔には,胸腔,腹腔,心嚢,関節腔があるが,本稿では,関節腔を除く体腔について解説する.これらの体腔は,漿膜に覆われた体内の腔であり,その表面には中皮が存在する.中皮は発生学的には中胚葉由来であり,病理学的には非上皮性組織に属する.
組織学的には,中皮細胞の基底側には基底膜が見られる.中皮細胞の下には中皮下層(submesothelial layer)があり,ここには線維芽細胞とともに,豊富な膠原線維や弾性線維が見られる.胸腔と腹腔とは,臓側と壁側とでは漿膜の構造が異なる.臓側の漿膜は,中皮細胞が連続して表面を覆っているが,壁側では中皮細胞が非連続で,そこにstomaという直径2~12μmの穴があり,リンパ管が開口している.stomaは特に横隔膜の腹側面で発達している(図1).
2)悪性中皮腫
著者: 堀内啓 , 伊藤光洋 , 松谷章司
ページ範囲:P.988 - P.991
臨床的特徴
悪性中皮腫は胸腔,腹腔,心嚢の表面を覆う中皮から発生する悪性腫瘍である(図1).アスベストを扱う職業の人に多く発生し,アスベストへの曝露と悪性中皮腫の発生が関連していると考えられている(図2).アスベストへの曝露から発症まで平均35年を要す.好発年齢は50~70歳で,男性が女性より数倍多い.症状は緩徐で,初発症状は胸痛と呼吸困難が最も多い.90%くらいの症例で,病初期に体腔液の貯留を伴い,診断における細胞診の役割が重要となる.予後は非常に悪く,平均生存期間は発症から12~15か月である.悪性中皮腫は,漿膜に多発性の結節として発生し,進行すると漿膜全体に腫瘍が浸潤して肥厚し,体腔内の臓器を取り囲むようになる.組織学的には,悪性中皮腫は多彩な組織像を示し,鑑別すべき腫瘍も多く,診断が難しい腫瘍の一つである.
細胞像
(1)豊富な細胞集塊の出現
3)転移性癌
著者: 堀内啓 , 牛島友則 , 松谷章司
ページ範囲:P.992 - P.997
はじめに
腹腔,胸腔などの体腔に液体が貯留する状態は腔水症と呼ばれる.この原因は,心不全や腎不全,肝硬変などの非腫瘍性疾患による場合と,腫瘍の体腔への転移による場合とがある.両者の鑑別には,細胞診による悪性細胞の検出が決め手となる.
体腔へ転移する頻度が高い腫瘍を,小児と成人とで男女別にまとめたのが,表である.小児では,胸腔・腹腔とも白血病・リンパ腫などの血液疾患と,小円形細胞腫瘍との頻度が高いが,成人では,腹腔では消化器癌や卵巣癌,胸腔では肺癌の頻度が高い.
体腔液中の腫瘍細胞は,もはやその由来した臓器を離れており,原発巣の細胞とは形態が異なってくる.体腔液中に浮遊して存在する腫瘍細胞は培養液中と同じような状態であり,多くの腫瘍細胞は類円形になる.したがって,本来の細胞形態学的特徴が不明瞭となる場合が稀ではない.
あらゆる腫瘍が体腔へ転移する可能性を持っており,そのすべてを述べることは,本稿では不可能である.したがって,頻度の高い腫瘍,鑑別診断上重要と考えられる腫瘍について記述する.
4)白血病・リンパ腫
著者: 堀内啓 , 牛島友則 , 松谷章司
ページ範囲:P.998 - P.1002
はじめに
体腔液中に白血病あるいは悪性リンパ腫の細胞が出現することは,癌腫に比べれば頻度は低い.しかし,鑑別診断においては,常に念頭に置くべき疾患である.特に小児では,これらの疾患が原因となる体腔液貯留が成人に比べて頻度が高く,重要である.白血病やリンパ腫の体腔への浸潤は,進行した病期に発生することが多いが,時には体腔液の貯留が初発症状のこともある.悪性リンパ腫の場合,体腔以外の部位に腫瘤を形成する原発巣があり,それが体腔へ浸潤することがほとんどであるが,稀に,体腔液中にリンパ腫細胞が出現するが,ほかに腫瘤を形成する原発巣がなく,原発性体腔液リンパ腫(primary effusion lymphoma)と呼ばれる疾患も知られている.また,白血病・リンパ腫の細胞形態の観察には,パパニコロウ染色(Papanicolaou stain)だけではなく,ギムザ染色(Giemsa stain)や免疫細胞化学も重要であり,標本作製の際に留意が必要である.
6.尿
1)尿中に出現する非腫瘍性細胞
著者: 堀内啓 , 原田弥生 , 松谷章司
ページ範囲:P.1003 - P.1006
尿路の解剖と組織学
尿路系とは,尿が生成されて排出される経路を構成する臓器の総称であり,腎臓・尿管・膀胱・尿道より成る.腎臓は左右一対あり,後腹膜に位置している.
腎臓は外側の皮質と,内側の髄質より成る.皮質には,ボーマン嚢(Bowman's capsule)に包まれた糸球体があり,ここで尿の元となる原尿が生成される.原尿は,近位尿細管,ヘンレの係蹄(Henle's loop),遠位尿細管を経て集合管に至る.この間に再吸収・分泌作用を受ける.集合管は腎盂に開口する.近位尿細管は立方上皮より成り,細胞質は好酸性で顆粒状,内腔側に刷子縁を持つ.遠位尿細管の上皮は立方状で,近位尿細管より丈が低く,細胞質は淡好酸性である.刷子縁は見られない(図1).集合管の上皮は,立方状から円柱状で,細胞境界が明瞭で,細胞質は淡明であり,核は類円形で中心に位置している.
2)尿路結石症
著者: 堀内啓 , 原田弥生 , 松谷章司
ページ範囲:P.1007 - P.1009
はじめに
尿路結石症には,腎盂結石症,尿管結石症,膀胱結石症などがある.いずれも,血尿と腰背部痛が主な症状である.尿路系の閉塞を伴う場合には,尿のうっ滞をきたし,水尿管症や水腎症を合併することもある.腎盂炎や膀胱炎などの炎症を合併することも稀でない.診断は,経静脈的腎盂造影やCTなどの画像診断,膀胱鏡で結石を確認することでなされる.尿路結石症に伴い出現する移行上皮細胞はしばしば異型を伴い,移行上皮癌との鑑別に苦慮する場合が多い.したがって,臨床医から尿路結石症の有無についての情報を事前に得ておくことが重要である.
3)移行上皮癌
著者: 堀内啓 , 伊藤光洋 , 松谷章司
ページ範囲:P.1010 - P.1014
尿路系悪性腫瘍の大部分は移行上皮癌であり,膀胱癌では90%を占める.移行上皮癌は中高年以降に好発し,男性に発生する頻度が高い.初発症状は,血尿,排尿障害などである.移行上皮癌のリスク因子には,アニリン色素やフェナセチン・ベンチジンなどの化学物質への曝露,喫煙などがある.サイクロフォスファマイドやブスルファンなどの抗癌剤も危険因子である.
移行上皮癌はしばしば多中心性の発育を示す.これは癌原物質への曝露により,尿路系全体が前癌性変化から癌へと向かう過程をたどっているという考えを支持するもので,このような現象を“field change(field cancerization)”という.
4)前立腺癌
著者: 堀内啓 , 伊藤光洋 , 松谷章司
ページ範囲:P.1015 - P.1017
前立腺癌は,高齢者に好発する代表的な男性ホルモン依存性腫瘍である.原因はほとんどわかっていない.発生頻度は人種や地域による差が大きく,欧米では高くアジアでは低いのが特徴であったが,近年,日本では人口の高齢化や生活習慣の欧米化により,発生頻度は増加している.症状はないことが多いが,排尿障害や残尿感,頻尿,血尿などで気づかれることもある.高頻度に骨転移をきたすことも特徴の1つで,これによる腰痛で発見される場合もある.
前立腺癌の診断は,PSA(prostate specific antigen,前立腺特異抗原)などの腫瘍マーカー,画像診断,細胞診・組織診などが主要な方法である.最近では,血清PSA値測定によるスクリーニングが行われるようになり,PSA高値を契機として発見される前立腺癌の症例が増加している.
5)腎 癌
著者: 堀内啓 , 伊藤光洋 , 松谷章司
ページ範囲:P.1018 - P.1020
腎癌の好発年齢は50歳台であり,男女比は1.6:1である.最も重要な危険因子は喫煙である.多くの腫瘍は染色体異常を示し,淡明細胞型では3番染色体の異常が多い.フォンヒッペル-リンダウ病(von Hippel-Lindau disease)では,高率に腎癌を合併することが知られている.腎癌は無症状のまま長期間潜伏し,進行すると血尿や腰背部痛を来す.発熱,体重減少,悪心,倦怠感などの非特異的な全身症状もしばしばみられる.血沈の亢進がみられることもある.腎癌は時に生理活性物質を産生し,エリスロポイエチン産生に起因する多血症や,PTHrP産生による高カルシウム血症を随伴することがある.
腎癌の病理学的分類は,日本の癌取扱い規約では,腎細胞癌と集合管癌とに大別され,腎細胞癌はさらに淡明細胞癌,顆粒細胞癌,嫌色素細胞癌,紡錘細胞癌,嚢胞随伴性腎細胞癌,乳頭状腎細胞癌に分類される.
第2章 血液 骨髄塗抹標本の見かた 1.骨髄穿刺法
骨髄穿刺法
著者: 北原光夫
ページ範囲:P.1022 - P.1023
骨髄検査の目的
骨髄液あるいは骨髄切片を鏡検すると,血液疾患あるいは他の疾患の診断に大いに役だつ.しかし,われわれには骨髄のほんの一部をながめているにすぎないという限界がある.
骨髄検査の適応と限界,禁忌
1 . 骨髄穿刺の適応と限界(表)
貧血の検索,異常白血球の存在,血小板減少の存在を認めるときは骨髄穿刺の適応となる.
2.骨髄穿刺液の処理
骨髄穿刺液の処理
著者: 西村敏治
ページ範囲:P.1024 - P.1027
はじめに
骨髄検査は血液疾患の鑑別,種々の血液疾患に対する治療効果の判定,再発の有無の確認など造血の動態を知る最も有用な検査である.また,悪性リンパ腫や癌などの骨髄転移の有無,あるいは血液疾患のrule out時にも検索される.
骨髄穿刺液は主に血液細胞学的検索と病理組織学的検索が行われる.細胞構成,異常細胞の有無,細胞の形態的変化について各々観察し,的確な病態把握のためにはこれらの多くの所見から診断および治療効果が評価される.また,疾患によっては細胞表面マーカー,染色体,遺伝子検査などが行われる(図1).本項では血液細胞学的検索と病理組織学的検索について概説する.
3.骨髄塗抹標本の染色法
骨髄塗抹標本の染色法
著者: 清水長子
ページ範囲:P.1028 - P.1030
はじめに
骨髄の血球形態の詳細な観察には,普通染色法〔ロマノフスキー染色(Romanowsky stain)〕を正しく行うことが基本であり,骨髄塗抹標本作製時には最低10枚ほどの標本を作製しておくのが望ましい.3~4枚をロマノフスキー染色に使用し,残りの標本は特殊染色に用いる.
骨髄の普通染色法には二重染色であるライト・ギムザ染色(Wright-Giemsa stain)またはパッペンハイム染色(Pappenheim stain)〔メイ・グリュンワルド・ギムザ染色(May-Grunwald-Giemsa stain)〕法を用い,細胞数の多い標本では染色時間を長めにするとよい(図1).まず最初に普通染色法の観察により,細胞分布,細胞形態異常のチェックを行い,異常が認められれば,次のステップとして形態学的特徴を検索するために目的に応じた特殊染色(細胞化学染色,免疫組織染色)を行う.
4.骨髄液中に見られる正常細胞
1)顆粒球系細胞
著者: 大畑雅彦
ページ範囲:P.1031 - P.1034
はじめに
顆粒球系細胞1~5)判別のポイントは,細胞質顆粒の特徴と核構造およびその形状である.成熟段階順に典型的な細胞像の特徴を概説するが,成熟は連続的であり,移行形の細胞も存在することは念頭に置く必要がある.
図1は好中球系細胞の成熟と形態学的特徴をイラストにまとめたものである.
2)赤芽球系細胞
著者: 大畑雅彦
ページ範囲:P.1035 - P.1036
はじめに
赤芽球系細胞は分裂を繰り返しながら成熟し,脱核し赤血球となる.顆粒球系細胞と同様に形態学的特徴に応じた名称が与えられているが,その鑑別上のポイントは細胞質の染色性と核クロマチン構造である.また,赤芽球全体を通しての特徴として,(1)核,細胞質とも類円形で,核は中心性に位置する.(2)正常では,細胞質内に顆粒を認めない.ことが挙げられる.
3)巨核球系細胞
著者: 大畑雅彦
ページ範囲:P.1037 - P.1039
はじめに
巨核球は,核の分裂に伴う細胞質の分裂が行われないため大型細胞となる.骨髄中の造血細胞の中で,巨核球系細胞のみが8~64N,稀に128Nの核の倍数体が存在する.巨核球の形態学的特徴を把握するうえで重要なポイントは,細胞質の変化である.巨核球は成熟とともに細胞質の量の増大が観察される.さらに,顆粒の増加や細胞質の塩基性の消失が見られる.
巨核球の形態分類には,血小板産生能を見る森田の分類や寺田の分類と,細胞質の成熟状態を観察する,いわゆる成熟度分類とがある.従来用いられていた森田らの分類は,どの程度血小板生成の指標になりうるか疑問である1).
以下に巨核球の各成熟段階の形態学的特徴を記載する.
4)リンパ球と形質細胞
著者: 西村敏治 , 松谷章司
ページ範囲:P.1040 - P.1041
リンパ球(lymphocyte)
骨髄のリンパ球は骨髄有核細胞(平均値20万/μl)の10~20%の比率で見られる.実数換算では2~4万/μl相当で,その多くは成熟リンパ球である.骨髄中のリンパ芽球はごく少数と思われるが,リンパ芽球が存在しても,形態的に骨髄芽球と鑑別することは困難である.また,成熟過程においてもリンパ球系は顆粒球系のように形態的特徴が明瞭ではなく,幼若球から成熟球に至るまでの段階を詳細に分画することはできない.
骨髄生検標本でリンパ濾胞(リンパ球が集合した部分・B細胞,図1)を見ることはあるが,骨髄塗抹標本でリンパ濾胞を見ることはない.
5)その他の細胞
著者: 清水長子
ページ範囲:P.1042 - P.1045
はじめに
正常骨髄標本,またはなんらかの疾病がある場合でも,いろいろな物質を貪食した細胞が標本中に認められる.標本の観察は,あらかじめ弱拡大で標本の全視野を観察し,その際標本の引き終わりや辺縁にどのような巨大細胞や細胞集団が出現しているかチェックし,巨大細胞や細胞集団があれば強拡大で確認する.
骨髄中に認められる巨大細胞としては,
(1)骨髄巨核球
(2)マクロファージ
(3)破骨細胞
(4)骨芽細胞の集団
(5)癌細胞の集団
(6)ホジキン細胞(Hodgkin cell)
(7)骨髄細胞の腫瘍性細胞
などが挙げられる.本稿では正常骨髄中に認められるその他の細胞(細網細胞・マクロファージなど)1~4)について写真を示して解説する.
5.骨髄細胞密度の評価(低形成・正形成・過形成)
骨髄細胞密度の評価(低形成・正形成・過形成)
著者: 西村敏治 , 松谷章司
ページ範囲:P.1046 - P.1049
はじめに
骨髄は全身に分散し,全重量1,600~3,700g1)(体重の約5%に相当)の臓器である.骨髄組織は造血系細胞,脂肪細胞,血管,神経,網内系細胞などから構成されている.通常は約1/2が造血細胞で占められている(年齢,部位,栄養状態によって異なる).需要に相応して骨髄内の造血能力は5~10倍にもなるといわれている1).また顆粒球系や赤芽球系の構成比も種々の病態で変化し,白血病細胞など腫瘍性細胞により置換され,本来の造血系が低形成性となることがある.
造血系細胞には顆粒球,赤芽球,巨核球の三系統があり,顆粒球系や赤芽球系は血球同士が比較的集団をつくる形で分布している.赤芽球はマクロファージを中心に特に密な小集団(赤芽球島)を形成する傾向にある.
6.異常細胞の見かた
1)赤芽球系の異常(1)数の異常―①増加と減少
著者: 清水長子
ページ範囲:P.1050 - P.1051
はじめに
正常な赤血球の寿命は約120日であり,老化に伴う膜変化が目印となり,マクロファージに貪食され死滅する.赤血球の膜破壊により寿命が短くなることを溶血(hemolysis)という.寿命前に死滅する赤血球が増え,循環する赤血球が減少すると,それを補おうとして骨髄における赤血球産生能が旺盛となる.
赤血球の死滅が産生を上回ったとき貧血が生じる.ただし,溶血があっても貧血を認めないときもある.骨髄液中における赤血球系の数の異常は,骨髄系細胞:赤芽球細胞の比率(M/E比)または赤芽球の割合(正常域20%±5%)が指標の一つとなる.
1)赤芽球系の異常(2)数の異常と形態異常―①赤芽球の増加と小型化
著者: 西村敏治 , 松谷章司
ページ範囲:P.1052 - P.1054
はじめに
異常骨髄像には数(量)の異常,または形態(質)の異常,あるいは両者が同時に見られる場合がある.赤芽球の数の異常(過形成)は赤芽球の絶対数の増加とともに,成熟段階の比率の異常,形態的には核形の異常,赤芽球の大型化・小型化,赤芽(血)球の染色性の異常など多彩な像が見られる.
1)赤芽球系の異常(2)数の異常と形態異常―②赤芽球の増加と形態異常
著者: 大畑雅彦
ページ範囲:P.1056 - P.1059
形態学的所見(図1)
著しく大型で多核の赤芽球の増生が見られる.多核赤芽球は各成熟段階で観察される.また核・細胞質の成熟解離,いわゆる巨赤芽球様変化も観察される.赤芽球系細胞の形態異常は,細胞質の異常と核の異常に大別されるが,図1からはその両方の異常が認められる.しかし,本例の血球異常は赤芽球に限って見られ,顆粒球系や巨核球血小板系細胞の異常は認められない.
このような異常を呈する疾患
赤芽球が過形成で,特に巨赤芽球様変化など異形成を呈する疾患を表1に示した.
1)赤芽球系の異常(2)数の異常と形態異常―③赤芽球の減少と形態異常
著者: 大畑雅彦
ページ範囲:P.1060 - P.1063
形態学的所見(図1)
図1から特徴ある所見を二つ挙げることができる.第一に核の濃染した赤芽球系細胞が観察されないこと,第二に中央にある強い好塩基性の細胞質を有した異常な巨大細胞が認められる点である.この巨大細胞は,細胞質の好塩基性の程度,核のクロマチン構造や核小体の形状から巨大前赤芽球と判断できる.本症例は小児で,血小板数の著減を指摘され,骨髄穿刺を施行した症例である.中央の巨大細胞の判別が診断的プロセスのポイントとなる.
このような異常を呈する疾患
骨髄では赤芽球系細胞のみが著減しているので赤芽球癆を考慮すべき骨髄像である.通常,赤芽球癆の診断は赤芽球比率が骨髄細胞の5%以下である点から行われる.表1の2~6が,その代表的な疾患である.また,巨大前赤芽球の存在は,パルボウイルスB19感染症の診断的根拠となりうる(表1-1).
2)顆粒球系の異常(1)数の異常―①増加と減少
著者: 清水長子
ページ範囲:P.1064 - P.1066
はじめに
白血球は大きく顆粒球と単球とリンパ球に分けられる.顆粒球は骨髄中で顆粒球系前駆細胞(colony-forming unit granulocyte,CFU-G)がコロニー刺激因子(colony-stimulating factor,CSF)の刺激を受けて分化・成熟し,さらに特殊顆粒(二次顆粒)の染色性により好中球,好酸球,好塩基球と区別ができる.顆粒球系細胞のうちで骨髄球までは分裂能を持っており,末梢血中に桿状核球より流出する.
2)顆粒球系の異常(2)形態異常―①細胞質と核の異常
著者: 中竹俊彦
ページ範囲:P.1067 - P.1069
はじめに
顆粒球系の異常は,顆粒の産生段階での異常が主である.代表的な異常は中毒性顆粒(toxic granule)と,顆粒のない(低顆粒)好中球である.また,細胞質にデーレ小体(Dohle body)や空胞形成(vacuolation)なども見られる.
一方,核の形態異常は,倍数性の異常に基づく成熟好中球の過分葉(hyper segmentation)と,稀には2個の核を持つ異常がある.また,核の成熟異常にペルゲルの核異常(Pelger anomaly)に似た偽ペルゲル異常(pseudo-Pelger anomaly)がある.
形態異常の判断には,正常な細胞分裂と核の倍数性との関係を知ることも大切である.ヒト体細胞の倍数性は,染色体数23本の精子や卵子の核(n=23;N)を基準にして,その倍数で表す.正常な体細胞の核は染色体の23対(46本)に相当し,その倍数性(ploidy)は2倍体(2N)である.2Nの細胞は細胞分裂の前にはDNA合成で正確に4Nになり,核の2分裂に細胞質も同調して2分裂する.分裂後は2Nの細胞が2個できる.
正常な造血では,巨核球系を例外として通常は2Nから4Nに倍加してから細胞分裂する.好中球は完全に成熟したとき倍数性は2Nで分葉は3~4分葉である.分裂の異常で4Nの核のままで成熟すると6~8分葉(過分葉核)になる.
3)リンパ球系の異常(1)数の増加―①慢性リンパ性白血病
著者: 大畑雅彦
ページ範囲:P.1070 - P.1073
形態学的所見(図1)
直径15Lm前後の小型リンパ球が増多している.顆粒球系幼若細胞は,この視野に認められず,リンパ球の形態学的特徴からも成熟リンパ球の相対的・絶対的増加が考えられる.
このような異常を呈する疾患
表1に示すように成熟リンパ球の増多する症例には多くの類縁疾患がある.これらの大部分は,FAB分類1)(1989年)の慢性リンパ性白血病群(chronic lymphocytic leukemias,CLLs)に属し,表1の1~7がB細胞性,8~12がT細胞性に分類される.また,顆粒リンパ球増多症(granular lymphocyte proliferative disorders,GLPD)は,細胞の帰属よりT細胞型とNK細胞型に大別される.良性疾患で小児例に多い百日咳では,小型の成熟リンパ球が著増することがあり,標本観察時には年齢の把握も重要である.
3)リンパ球系の異常(2)数の異常と形態異常―①細胞質の異常(1)
著者: 清水長子
ページ範囲:P.1074 - P.1076
はじめに
リンパ球の異常には数の異常,形態異常,機能の異常がある.リンパ球増加はリンパ球の絶対数が4,000/μl以上,リンパ球低下は1,500/μl以下と定義されている.リンパ球増加は単クローン性増加と多クローン性(反応性)増加とに大別され,単クローン性増加をきたす疾患群としては悪性リンパ腫の白血化や,慢性リンパ性白血病群の(1)慢性リンパ性白血病(chronic lymphoid leukemia,CLL),(2)前リンパ性白血病(prolymphocytic leukemia,PLL),(3)毛様(有毛)細胞白血病(hairy cell leukemia,HCL),(4)大顆粒リンパ球性白血病(large granular lymphocytic leukemia,LGLL)が,多クローン性増加をきたす疾患としてはウイルス性疾患が挙げられる.
3)リンパ球系の異常(2)数の異常と形態異常―②細胞質の異常(2)
著者: 大畑雅彦
ページ範囲:P.1077 - P.1082
形態学的所見(症例1:図1)
ごく一部の細胞の細胞質にはアズール顆粒が認められ,核の異型性を認める異常な細胞も存在する(矢印).核小体を有する細胞も見られるが,核のクロマチン構造からは幼若な印象はない.骨髄全体の細胞構成としては,顆粒球系と赤芽球系細胞の著減がある(異常細胞は,ペルオキシダーゼ染色陰性).
このような異常を呈する疾患
鑑別を要する代表的な疾患を表1に示した.さらにアズール顆粒の増多を示す疾患の臨床的,細胞学的な鑑別ポイントを表2にまとめた.
3)リンパ球系の異常(2)数の異常と形態異常―③細胞質の異常(3)
著者: 清水長子
ページ範囲:P.1083 - P.1085
はじめに
異常リンパ球,異型リンパ球の観察では,核の異常(核小体の有無,核膜不整の有無,クロマチンの構造),細胞質の異常(封入体,空胞の有無,顆粒の大きさや数,色調)の観察をする.一般に腫瘍性のリンパ球が出現する場合同一形態の細胞像として見られるが,末梢血液中リンパ球が非腫瘍性に増加する病態を示す反応性リンパ球増多症の場合はDowney~型が混在して見られる.反応性の異型リンパ球は,リンパ球がなんらかの抗原刺激に反応した細胞変化像とみなされ,健常成人でも1%以下に見られるといわれている.Downeyは,異型リンパ球を型:単球様,型:形質細胞様,型:芽球様の3型に分類している.異型性のあるリンパ球が見られた場合は,その異型性が腫瘍性のものか反応性のものかを判別することが重要である.
3)リンパ球系の異常(2)数の異常と形態異常―④核の異常
著者: 長野美恵子 , 西村敏治
ページ範囲:P.1086 - P.1089
はじめに
リンパ球系腫瘍の中で,特徴的な形態異常を示す疾患は,リンパ性白血病,リンパ腫,骨髄腫などがある.細胞の形態学的特徴は,大きさ,細胞質の色調,顆粒の有無,核構造などが挙げられる.なかでも成人T細胞白血病/リンパ腫,菌状息肉症,セザリー症候群(Sezary syndrome)は,核形,核構造に異常が見られ,花弁状,脳回状,クルミ状とも形容される特徴ある細胞が出現し鑑別には注意を要する.
3)リンパ球系の異常(2)数の異常と形態異常―⑤悪性リンパ腫の白血化(1)
著者: 清水長子
ページ範囲:P.1090 - P.1092
はじめに
悪性リンパ腫はリンパ細網組織に原発する非上皮性腫瘍である.
病理組織学的には,非ホジキンリンパ腫(non-Hodgkin's lymphoma,NHL)とホジキンリンパ腫(Hodgkin's lymphoma,HD)とに大別される.
組織に原発する疾患である悪性リンパ腫が疑われる症例において,末梢血,骨髄の形態学的検査を実施する理由として,主病変が精査困難なときに末梢血または,骨髄血中に異常リンパ球が認められればstageと判定され治療方法が異なるためである.
しかし,悪性リンパ腫のうちでも病型により末梢血,骨髄への浸潤する頻度は異なる.HDでは約3%の骨髄浸潤が認められるが,末梢血への浸潤は稀である.
3)リンパ球系の異常(2)数の異常と形態異常―⑥悪性リンパ腫の白血化(2)
著者: 大畑雅彦
ページ範囲:P.1093 - P.1098
形態学的所見
(症例1:図1-a,症例2:図1-b)
顆粒球系細胞が主体を成す骨髄中で,N/C比(nuclear-cytoplasmic ratio,核-細胞質比)大で核の切れ込みや彎入,さらに核の立体構造を示す細胞が見られる.図1-b(弱拡大)では,核の切れ込みの程度や核クロマチン構造は十分に判別できない.
このような異常を呈する疾患
リンパ球系腫瘍細胞を含む異常細胞を示唆する所見として
(1)細胞の大きさの異常:同一成熟段階の細胞でありながら著明な大小不同を伴う.
3)リンパ球系の異常(2)数の異常と形態異常―⑦形質細胞の異常(1)
著者: 大畑雅彦
ページ範囲:P.1099 - P.1109
形態学的所見
1. 骨髄標本(図1-a)
核偏在性で核周明庭を有する,いわゆる成熟傾向を示す形質細胞が増多している.二核の形質細胞も存在する(矢印).赤芽球系,顆粒球系細胞は十分に存在し,骨髄中の正常細胞の構築は良好である.
2. 末梢血(図1-b)
強い連銭形成と小型で核偏在性の形質細胞様細胞が5個認められる.核のクロマチン構造は十分判別できないが,結節状凝集を示す細胞も散見される.細胞質は強い好塩基性である.提示した症例は,初診時より末梢血に形質細胞様細胞を85.8%認めた.その形態学的特徴は,多発性骨髄腫(multiple myeloma,MM)の骨髄に見るMM細胞より明らかに小型である.本症例は,核偏在性の形質細胞様細胞の比率と絶対数を踏まえて種々の疾患との鑑別をする必要がある.
3)リンパ球系の異常(2)数の異常と形態異常―⑧形質細胞の異常(2)
著者: 中竹俊彦
ページ範囲:P.1110 - P.1115
はじめに
Bリンパ球系の異常は,(1)Bリンパ球になるまでの段階で腫瘍化したもの(急性・慢性リンパ性白血病),さらにBリンパ球から以降に(2)二次的(反応性)に生じた異常,および分化の最終段階で(3)形質細胞の本質的な異常,すなわち腫瘍性に起こった病態に分けて考えることができる.
成熟Bリンパ球は,備えられた性質に対してリンパ節で特異的な抗原刺激を受けると,主に血液を経由して骨髄へ回帰して定着(ホーミング)し,その分化と成熟を支持する骨髄の支持細胞の働きインターロイキン6(interleukin-6,IL-6)を受けて,形質細胞へと分化・成熟する.代表的な分化の異常は多発性骨髄腫で,前項の「形質細胞の異常(1)」として解説された.
ここでは,Bリンパ球から形質細胞に至る分化・成熟過程で慢性リンパ性白血病と多発性骨髄腫との中間にある高γ-グロブリン血症を示すさまざまな病態を解説する.
4)巨核球系の異常(1)数の異常
著者: 西村敏治 , 松谷章司
ページ範囲:P.1116 - P.1120
はじめに
巨核球系細胞は顆粒球系・赤芽球系細胞と異なり,核の倍数性や細胞質容積の増大を伴って成熟する.増殖・成熟過程においてMeg-CSF(megakaryocyto colony stimutaing factor,巨核救コロニー刺激因子)・インターロイキン(interleukin,IL)-3・IL-6・IL11・トロンボポエチンなど複数の増殖刺激因子が作用する.巨核球の幼若段階では細胞質のリボソームが増加(細胞質が好塩基性)しているが,成熟とともにアズール顆粒などさまざまな顆粒を合成する.1個の巨核球から2,000~5,000個の血小板が産生されるといわれるが,血小板数は巨核球数の増減はもちろんのこと,形態的には核の倍数性(2N・4N・8N・16N・32N・64N)や血小板分離膜の発達の程度にも影響される.巨核球の成熟段階では凝固関連因子であるフォン・ウイルブランド因子(von-Willebrand factor,vWF)や,細胞の活性および増殖を刺激する血小板由来増殖因子(platelet derived growth factor,PDGF)などを産生する.
4)巨核球系の異常(2)形態異常
著者: 大畑雅彦
ページ範囲:P.1121 - P.1127
形態学的所見(図1-a,b)
他院にて特発性血小板減少性紫斑病(idiopathic thrombocytopenic purpura,ITP)と診断され脾摘を受けるが無効であった17歳の男性.小学校ごろより聴力障害(感音性難聴)があった.
末梢血には赤血球と同等サイズ以上のいわゆる巨大血小板がみられ,成熟好中球にはデーレ(Dohle)様封入体が認められた.骨髄像では顆粒球系細胞(図1-a)に,末梢血と同様の封入体が存在している.封入体の位置は細胞の辺縁に位置することが多く,形状や明瞭性はさまざまであった.図1-bには巨核球を示した.しかし,通常一般的に見る巨核球に比し,細胞質の顆粒の分布状態から顆粒産生巨核球まで成熟しているのにもかかわらず,“好塩基性の斑(マダラ)”が存在する.筆者はこの模様を“トラ斑模様”と呼んでいる1).このように顆粒球系細胞と巨核球に形態学的異常が観察された症例が今回のテーマである.
5)2系統以上の細胞の異常(1)数の異常―①増加(1)
著者: 清水長子
ページ範囲:P.1128 - P.1130
形態学的所見(図1,2)
図1の骨髄像は,過形成を呈しており巨核球も多数見られる.M/E比は著しく高値を示した.巨核球の著しい形態異常はないが正常のものと比べやや小型である.中拡大にすると各種成熟段階の顆粒球系細胞があり好酸球,好塩基球なども認められる(図2).リンパ球,赤芽球系の細胞の減少がみられる.
このような形態学的所見を呈する疾患
顆粒球系細胞の各成熟段階を認められる疾患としては,慢性骨髄性白血病,幼若顆粒球系の出現する類白血病反応,慢性骨髄増殖性疾患(慢性骨髄単球性白血病,真性多血症,本態性血小板血症,骨髄線維症)顆粒球系増多を来す細菌感染症などが挙げられる.
5)2系統以上の細胞の異常(1)数の異常―②増加(2)
著者: 清水長子
ページ範囲:P.1131 - P.1135
はじめに
慢性骨髄性白血病(chronic myeloid leukemia,CML)は慢性期と移行期および急性転化後の急性期に分けることができる.表1に慢性骨髄性白血病の病期分類を示した.移行期,急性期は経過中に原因不明の発熱,脾腫の増大,体重減少など多彩な症状を示すようになる.また血液学的検査で白血球数の増多,血小板数の減少,貧血の進行などの所見を示す移行期後,末梢血,骨髄に芽球が増加する急性転化期に至る.急性転化は,骨髄性白血病が一番多く,次にリンパ性,巨核球性,単球性と続く.また,骨髄外に腫瘤を形成することもある.この章では特に骨髄性とリンパ性の急性転化の症例について示す.
5)2系統以上の細胞の異常(1)数の異常―③増加(3)
著者: 大畑雅彦
ページ範囲:P.1136 - P.1143
臨床像と形態学的所見
(症例1:図1-a,b,症例2:図1-c,d)
症例11):CML(chronic myelocytic leukemia,慢性骨髄性白血病)と診断後,脾摘と化学療法が施行された.経過観察中に一見裸核に見える異常細胞(矢印)が出現し,以後血小板の増多とともに大型の芽球も漸次増加していった(図1-a).末梢血に増多した血小板は,大小不同,巨大血小板のほかに,血小板特殊顆粒の減少や空胞変化なども見られた.その後発熱および関節痛と体重減少が増強し,腹部には3~4cmのゴム様硬の腫瘤を多数認め,また鼠径部リンパ節も腫大していた.骨髄穿刺では,至る所に図1-bのような細胞の集塊が観察された.
症例22):CMLの慢性期を約14年間,安定して経過していたが,鼠径部の腫瘤を自覚するようになってから白血球数が増加し,急性転化を疑い骨髄穿刺を施行した(図1-c).N/C比(nuclear-cytoplasmic ratio,核-細胞形質比)が大きく,一部の芽球には核の彎入や切れ込み,立体構造が観察され,POX(peroxidase,ペルオキシダーゼ)染色陰性,Td-T(terminal deoxynucleotidyl transferase)染色陽性,抗MPO(myeloperoxidase)染色陰性より,リンパ性急性転化と診断したが,一部に細胞形態上問題を残すものも見られた.VP(ビンクリスチン+プレドニゾロン)療法を3コース施行後には,CMLの慢性期の骨髄に戻った.その後,経過観察中に,大型で好塩基性の強い前赤芽球様の細胞が出現し始め,再度骨髄穿刺を施行した(図1-d).
5)2系統以上の細胞の異常(1)数の異常―④減少
著者: 清水長子
ページ範囲:P.1144 - P.1147
形態学的所見
症例1の骨髄像は,低形成を呈している.骨髄巨核球は著減しており脂肪滴の部分が多い(図1).症例2の骨髄像は,やや低形成を呈しており赤血球や血小板を貪食した組織球が右に認められる(図2).
このような形態学的所見を呈する疾患
末梢血中で汎血球減少を起こす疾患としては,再生不良性貧血,発作性夜間血色素尿症,重症感染症,炎症性疾患,白血病,骨髄異形成症候群,巨赤芽球性貧血,骨髄癆などが挙げられる.
5)2系統以上の細胞の異常(2)形態異常―①巨赤芽球性貧血
著者: 菊地美幸 , 西村敏治
ページ範囲:P.1148 - P.1151
はじめに
赤芽球,顆粒球,巨核球の三系統の細胞は多能性幹細胞から派生する.赤芽球,顆粒球は最終成熟細胞に至るまでには,数回にわたる細胞分裂を経て分化・成熟する.この分化・成熟過程において造血細胞に障害が起こると,形態異常を伴う細胞が出現することがある.これらの細胞が疾患特有の形態異常を示すものもあり,細胞の形態異常を捕らえることは血液疾患の診断に有用な情報となる.
7.FAB分類
1)WHO分類とFAB分類の比較
著者: 栗山一孝 , 朝長万左男
ページ範囲:P.1152 - P.1157
はじめに
骨髄異形成症候群(myelodysplastic syndrome,MDS)と急性白血病の分類は,French American British(FAB)分類1~5)が世界共通に使用されてきた.FAB分類は,細胞形態学を基本とした臨床的分類法であるが,染色体・遺伝子変異の臨床的重要性が明らかになってくるにつれ,これらも組み込んだ分類法の必要性も高まってきた.世界保健機構(World Health Organization,WHO)は,1999年MDSを含む造血器・リンパ組織悪性腫瘍の分類法を発表した6,7).このWHO分類では,FAB分類に含まれない病型や特定の染色体・遺伝子変異を有する病型を取り上げた新たな包括的な分類法と位置づけられる.
2)MDSに見られる形態異常―(1)顆粒球系の異常
著者: 西村敏治
ページ範囲:P.1158 - P.1160
形態学的所見(図1,2)
骨髄は正形成,赤芽球系の細胞が乏しく多くは顆粒系の細胞である.円形核の細胞が多数見られ桿状核球や分葉核球は少数で,顆粒球系の成熟抑制と判断される.形態的には(核)クロマチンが強く濃縮した細胞や核形の異常がある.また,顆粒形成が減少した成熟細胞も見られる.
このような形態学的所見を呈する疾患
骨髄が正形成ないし過形成で明らかな形態異常を呈する代表的疾患は骨髄異形成症候群(myelodysplastic syndrome,MDS)である.MDSは最も未分化な造血細胞である多能性造血幹細胞の異常による後天的な造血異常である.骨髄あるいは末梢血には細胞の量的異常や質的異常が見られる1).
2)MDSに見られる形態異常―(2)赤芽球系の異常
著者: 清水長子
ページ範囲:P.1161 - P.1164
はじめに
骨髄異形成症候群(myelodysplastic syndrome,MDS)は,造血幹細胞を源に発するクローン性疾患で,無効造血と血球形態異常を特徴とする疾患である.
無効造血とは,造血細胞が骨髄中で正常な成熟過程を経る以前に破壊されてしまう状態であり,汎血球減少と多彩な形態学的異形成(dysplastic change)とを特徴とする.血球3系統に量的,質的異常をきたしMDSの診断の大きな根拠となる.表1にMDSの病型分類を示す.本項では赤芽球系の異常について症例を交えて解説したい.
2)MDSに見られる形態異常―(3)巨核球
著者: 黒山祥文 , 大畑雅彦
ページ範囲:P.1165 - P.1167
形態学的所見
図1-aでは,やや好塩基性が残る単核の巨核球が1視野に相当数認められる.表に示す検査データでは,血小板数が7.6×104/μlで骨髄中の巨核球数(1,922/μl)との間には,明らかな乖離が存在する(無効造血の所見).さらに注目すべきは,細胞質にはアズール顆粒が認められるまで成熟傾向を示すが,核の分葉は全く見られない点である.また中央には,成熟好中球の2倍程度の微小巨核球(矢印)(micromegakaryocyte,以下m-megと略)も存在している.図1-bでは,円形の核が個々に分離した,いわゆる円形(分離)多核巨核球が認められる.
今回は,巨核球系細胞に種々の形態異常が観察された症例を提示し,そのアプローチを考察する.
3)L1~L3
著者: 清水長子
ページ範囲:P.1168 - P.1171
はじめに
急性白血病は,血液細胞の腫瘍であり骨髄中で腫瘍性に増殖する疾患である.
大きく急性リンパ性白血病(acute lymphoblastic leukemia,ALL)と急性骨髄性白血病(acute myelocytic leukemia,AML)の2群に分けることができ,ALLは未熟なリンパ球系芽球の腫瘍性増殖をきたす疾患である.
FAB(French American British)分類1)ではALLとAMLの区別は,芽球のペルオキシダーゼ反応で区別されペルオキシダーゼ反応陽性芽球が3%未満のものをALLとする.しかし,一部のAMLのうちでペルオキシダーゼ反応陰性の疾患もあるためALLの確定診断には,芽球の表面形質2,3)での確認が必要である.
ALLは塗抹標本の形態特徴によりL1~L3の3型に分類される.1981年に一致率の向上のためにscoring systemが加えられた4).
表1に細胞の特徴を示した.
4)M0,M1
著者: 野木岐実子 , 島津千里
ページ範囲:P.1172 - P.1174
急性白血病の分類は広くFAB分類が用いられている.この分類は1976年に提唱され,その後改定追加がなされたもので,細胞形態とミエロペルオキシダーゼ染色(myeloperoxydase stain,MPO stain)などの細胞化学所見を基本としている.
芽球のMPO陽性率3%以上をAML(acute myelocitic leukemia,急性骨髄性白血病),3%未満をALL(acute lymphocitic leukemia,急性リンパ性白血病)と診断する.さらにAMLのM0,M5a,M6,M7ではMPO陽性率が3%未満であるため,MPO以外の補助診断が必要となる.
ここではM0とM1について解説する.
5)M2,M3,M3 variant
著者: 清水長子
ページ範囲:P.1175 - P.1179
はじめに
正常造血は多能性造血幹細胞により維持されている.白血病は,この幹細胞の1個が形質転換し白血病幹細胞となり増殖し,骨髄,末梢血にも流れ増加していく病態である.
本稿では,FAB分類の急性骨髄性白血病(acute myeloid leukemia,AML)であるM2(分化型骨髄芽球性白血病,myeloblastic leukemia with maturation)とM3(前骨髄球性白血病,hypergranular promyelocytic leukemia)について示したい.
6)M4,M4eo
著者: 清水長子
ページ範囲:P.1180 - P.1183
はじめに
骨髄単球性白血病(myelomonocytic leukemia:M4)は骨髄中に骨髄球系と単球性の幼若な細胞が混在する疾患でありM4は骨髄所見と末梢血所見で診断する.表1に診断基準を示した.単球が骨髄中で20%に満たないときがあり,この場合は末梢血所見で単球が5,000/μl以上または,血清,尿リゾチーム値が正常上限の3倍以上あればM4と診断する.骨髄所見がM2で末梢血所見とリゾチームよりM4の場合がある.
M4の一部には骨髄中に好酸球増多(5%以上)示すM4eoがある.
7)M5a,M5b
著者: 後藤文彦 , 西村敏治
ページ範囲:P.1184 - P.1187
はじめに
FAB分類は,芽球の形態的特徴を基本にペルオキシダーゼ染色や脂肪染色また非特異的エステラーゼ染色などの細胞化学染色所見を参考として客観的に病型分類を行うことを目的に提唱された1).また今日では電子顕微鏡や免疫細胞化学的所見,遺伝子解析などを適応して分類されるようになった.
本稿ではFAB分類の急性単球性白血病(AMoL,acute monocytic leukemia)の未分化型(M5a)と分化型(M5b)の症例について述べる.
8)M6
著者: 大畑雅彦
ページ範囲:P.1188 - P.1195
図1-a,bに今回提示した症例の骨髄像を示す.上段(図1-a:弱拡大)は好塩基性赤芽球が目立ち,明らかな赤芽球の過形成像である.二核の赤芽球も散見される.下段(図1-b)には核と細胞質との成熟障害を示す赤芽球,いわゆる巨赤芽球様変化が見られる.さらに重要な所見は,アウエル小体(Auer body)を有した芽球(矢印)の存在である.
考えられる疾患
表1には赤芽球系細胞が著増し,さらに芽球成分の増多も観察される疾患を記した.鑑別ポイントとしては赤芽球系細胞の比率が最も重要であるが,本症例では全赤芽球の比率が86.6%認められた(表2).FAB分類では赤芽球系細胞が骨髄全有核細胞の50%以上の場合は,リンパ系,赤芽球系を除く細胞中(非赤芽球成分,non-erythroid cell,NEC)の骨髄芽球%を算定する.芽球比率が30%未満であればMDS(myelodysplastic syndrome,骨髄異形成症候群)に,30%以上であればM6(赤白血病)と定義される.今回提示した症例は,NECの比率が37.3%であり,さらに芽球にはアウエル小体が存在することより典型的なM6と診断される.FAB分類ではM6で増生する芽球は骨髄芽球とされており,今回示したアウエル小体を有した芽球はその典型ともいえる.
9)M7
著者: 清水長子
ページ範囲:P.1196 - P.1199
はじめに
急性巨核芽球性白血病〔acute megakaryocytic leukemia,AML(acute myeloid leukemia):M7〕は形態学的に同定が困難な病型である.骨髄は線維化増加のためdry tapのことがあり診断に適さないことがある.AML:M7の頻度は,全急性骨髄性白血病(AML)の1~3%であり,確定診断には電子顕微鏡(電顕)を使用した方法が必要であったが,巨核球と血小板に特異性の高いマーカー(CD41,CD42a,CD61)が発見されたことによりFAB分類に追加された疾患である.
8.骨髄液中に見られる異常細胞と関連疾患
1)骨髄癌腫症
著者: 忍田和子 , 東克巳 , 米山彰子
ページ範囲:P.1200 - P.1203
はじめに
骨髄癌腫症は腫瘍細胞が骨髄内に多発性かつび漫浸潤性転移をきたした状態をいう.
骨髄には血行性に悪性細胞の転移が起こりやすいが,一般的に未分化なものほど骨髄への転移が多く,組織型では腺癌が多い.骨髄癌腫症を来しやすい腫瘍として,上皮性腫瘍では,胃癌,肺癌,乳癌,前立腺癌,甲状腺癌,腎癌など,非上皮性腫瘍では神経芽細胞腫,横紋筋肉腫,ユーイング肉腫(Ewing's sarcoma),骨肉腫などが挙げられる1~4).
2)神経芽細胞腫,肥満細胞症
著者: 清水長子
ページ範囲:P.1204 - P.1207
はじめに
骨髄標本をカウントするに当たり,弱拡大で引き終わりや辺縁部を注意して鏡検し,巨大細胞や細胞の集しゅう簇ぞくの有無を確認することが大切である.
本稿では比較的遭遇しやすい悪性腫瘍と,大変稀な症例を提示する.
第3章 尿沈渣 これだけは知っておきたい成分と症例
1.変形赤血球と赤血球円柱
著者: 今井宣子
ページ範囲:P.1210 - P.1210
症 例:内科,46歳,女性.
診 断:慢性糸球体腎炎(IgA腎症).
尿外観:赤色,混濁.
尿定性検査所見:pH6,比重1.022,蛋白(3+),糖(-),潜血(3+),ケトン体(-),ウロビリノゲン(±),ビリルビン(-),亜硝酸塩(-),白血球エステラーゼ(-).
2.ガラス円柱(1)
著者: 今井宣子
ページ範囲:P.1211 - P.1211
症 例:内科,80歳,男性.
診 断:動脈硬化.
尿外観:淡黄色,透明.
尿定性検査所見:pH6,比重1.023,蛋白(-),糖(-),潜血(-),ケトン体(-),ウロビリノゲン(±),ビリルビン(-),亜硝酸塩(-),白血球エステラーゼ(-).
尿沈渣所見:赤血球0~1/HPF,白血球0~1/HPF,尿細管上皮細胞(1+),ガラス円柱(多数),顆粒円柱(1+),上皮円柱(1+).
3.ガラス円柱(2)
著者: 今井宣子
ページ範囲:P.1212 - P.1212
症 例:外科,48歳,男性.
診 断:食道癌術後.
尿外観:淡黄色,透明.
尿定性検査所見:pH6,比重1.022,蛋白(-),糖(-),潜血(-),ケトン体(-),ウロビリノゲン(±),ビリルビン(-),亜硝酸塩(-),白血球エステラーゼ(-).
尿沈渣所見:赤血球0~1/HPF,白血球0~1/HPF,尿細管上皮細胞(1+),ガラス円柱(多数),顆粒円柱(1+),上皮円柱(1+).
4.ガラス円柱(3)
著者: 今井宣子
ページ範囲:P.1213 - P.1213
症 例:整形外科,60歳,男性.
診 断:リウマチ性関節炎,慢性腎炎,慢性腎不全(非透析状態).
尿外観:淡黄褐色,やや濁.
尿定性検査所見:pH6,比重1.010,蛋白(3+),糖(-),潜血(1+),ケトン体(-),ウロビリノゲン(±),ビリルビン(-),亜硝酸塩(-),白血球エステラーゼ(-).
5.蝋様円柱(1)
著者: 今井宣子
ページ範囲:P.1214 - P.1214
症 例:外科,55歳,男性.
診 断:胃癌術後.
尿外観:淡黄色,透明.
尿定性検査所見:pH6,比重1.012,蛋白(1+),糖(-),潜血(1+),ケトン体(-),ウロビリノゲン(±),ビリルビン(-),亜硝酸塩(-),白血球エステラーゼ(-).
尿沈渣所見:赤血球1~5/HPF,白血球0~1/HPF,尿細管上皮細胞(2+),ガラス円柱(1+),顆粒円柱(3+),上皮円柱(3+),?様円柱(2+).
6.蝋様円柱(2)
著者: 今井宣子
ページ範囲:P.1215 - P.1215
症 例:小児科,9歳,男性.
診 断:慢性腎炎症候群,ネフローゼ症候群.
尿外観:淡黄褐色,やや濁.
尿定性検査所見:pH6,比重1.015,蛋白(3+),糖(-),潜血(3+),ケトン体(-),ウロビリノゲン(±),ビリルビン(-),亜硝酸塩(-),白血球エステラーゼ(-).
尿沈渣所見:赤血球多数,白血球1~5/HPF,尿細管上皮細胞(3+),卵円形脂肪体(1+),ガラス円柱(3+),顆粒円柱(3+),上皮円柱(3+),脂肪円柱(1+),蝋様円柱(1+).
7.蝋様円柱と上皮円柱
著者: 今井宣子
ページ範囲:P.1216 - P.1216
症 例:外科,69歳,男性.
診 断:食道癌術後.
尿外観:淡黄褐色,やや濁.
尿定性検査所見:pH6,比重1.018,蛋白(3+),糖(-),潜血(3+),ケトン体(-),ウロビリノゲン(±),ビリルビン(-),亜硝酸塩(-),白血球エステラーゼ(3+).
尿沈渣所見:赤血球多数,白血球多数,尿細管上皮細胞(3+),ガラス円柱(多数),顆粒円柱(3+),上皮円柱(3+),蝋様円柱(2+).
8.白血球円柱(1)
著者: 今井宣子
ページ範囲:P.1217 - P.1217
症 例:整形外科,60歳,男性.
診 断:リウマチ性関節炎,慢性腎炎,慢性腎不全(非透析状態).
尿外観:淡黄褐色,やや濁.
尿定性検査所見:pH6,比重1.010,蛋白(3+),糖(-),潜血(1+),ケトン体(-),ウロビリノゲン(±),ビリルビン(-),亜硝酸塩(-),白血球エステラーゼ(-).
9.白血球円柱(2)
著者: 今井宣子
ページ範囲:P.1218 - P.1218
症 例:外科,52歳,男性.
診 断:慢性腎炎症候群,食道癌および舌癌の術後.
尿外観:淡黄褐色,やや濁.
尿定性検査所見:pH6,比重1.015,蛋白(2+),糖(-),潜血(3+),ケトン体(-),ウロビリノゲン(±),ビリルビン(-),亜硝酸塩(-),白血球エステラーゼ(-).
10.空胞変性円柱
著者: 今井宣子
ページ範囲:P.1219 - P.1219
症 例:眼科,55歳,男性.
診 断:糖尿病性網膜症,糖尿病性腎症.
尿外観:淡黄褐色,微濁.
尿定性検査所見:pH6,比重1.015,蛋白(3+),糖(3+),潜血(-),ケトン体(-),ウロビリノゲン(±),ビリルビン(-),亜硝酸塩(-),白血球エステラーゼ(-).
11.扁平上皮細胞
著者: 今井宣子
ページ範囲:P.1220 - P.1220
症 例:内科,50歳,女性.
診 断:高血圧症.
尿外観:淡黄色,透明.
尿定性検査所見:pH6,比重1.014,蛋白(-),糖(-),潜血(-),ケトン体(-),ウロビリノゲン(±),ビリルビン(-),亜硝酸塩(-),白血球エステラーゼ(-).
12.扁平上皮細胞(良性異型)
著者: 今井宣子
ページ範囲:P.1221 - P.1221
症 例:婦人科,50歳,女性.
診 断:子宮頸部癌,放射線療法中.
尿外観:黄褐色,やや濁.
尿定性検査所見:pH6,比重1.023,蛋白(1+),糖(-),潜血(1+),ケトン体(-),ウロビリノゲン(±),ビリルビン(-),亜硝酸塩(-),白血球エステラーゼ(-).
13.扁平上皮癌細胞
著者: 今井宣子
ページ範囲:P.1222 - P.1222
症 例:婦人科,55歳,女性.
診 断:子宮頸部癌,角化型扁平上皮癌.
尿外観:淡黄褐色,濁.
尿定性検査所見:pH6,比重1.020,蛋白(1+),糖(-),潜血(3+),ケトン体(-),ウロビリノゲン(±),ビリルビン(-),亜硝酸塩(-),白血球エステラーゼ(2+).
14.移行上皮細胞
著者: 今井宣子
ページ範囲:P.1223 - P.1223
症 例:小児科,6歳,男児.
診 断 非定型麻疹.
尿外観:黄褐色,濁.
尿定性検査所見:pH5,比重1.030,蛋白(±),糖(-),潜血(-),ケトン体(-),ウロビリノゲン(±),ビリルビン(-),亜硝酸塩(-),白血球エステラーゼ(-).
15.移行上皮細胞(良性異型)
著者: 今井宣子
ページ範囲:P.1224 - P.1224
症 例:皮膚科,30歳,男性.
診 断:足挫滅創の手術後,バルーンカテーテル挿入中.
尿外観:黄褐色,やや濁.
尿定性検査所見:pH6,比重1.020,蛋白(-),糖(-),潜血(±),ケトン体(-),ウロビリノゲン(±),ビリルビン(-),亜硝酸塩(-),白血球エステラーゼ(-).
16.移行上皮癌細胞(典型例)
著者: 今井宣子
ページ範囲:P.1225 - P.1225
症 例:泌尿器科,65歳,男性.
診 断:膀胱癌.移行上皮癌(G3).
尿外観:黄褐色,濁.
尿定性検査所見:pH6,比重1.015,蛋白(2+),糖(-),潜血(3+),ケトン体(-),ウロビリノゲン(±),ビリルビン(-),亜硝酸塩(-),白血球エステラーゼ(3+).
17.移行上皮癌細胞
著者: 今井宣子
ページ範囲:P.1226 - P.1226
症 例:泌尿器科,60歳,男性.
診 断:膀胱癌,移行上皮癌(G2).
尿外観:淡黄褐色,濁.
尿定性検査所見:pH6,比重1.025,蛋白(1+),糖(-),潜血(2+),ケトン体(-),ウロビリノゲン(±),ビリルビン(-),亜硝酸塩(-),白血球エステラーゼ(1+).
18.尿細管上皮細胞
著者: 今井宣子
ページ範囲:P.1227 - P.1227
症 例:特殊救急部,45歳,男性.
診 断:自殺目的で昇汞(塩化第二水銀)を飲んで意識不明となり救急車で来院.
尿外観:黄褐色,やや濁.
尿定性検査所見:pH6,比重1.025,蛋白(±),糖(-),潜血(-),ケトン体(-),ウロビリノゲン(±),ビリルビン(-),亜硝酸塩(-),白血球エステラーゼ(-).
19.腺癌細胞
著者: 今井宣子
ページ範囲:P.1228 - P.1228
症 例:泌尿器科,52歳,男性.
診 断:前立腺癌(分化型).
尿外観:黄褐色,濁.
尿定性検査所見:pH6.5,比重1.012,蛋白(1+),糖(-),潜血(2+),ケトン体(-),ウロビリノゲン(±),ビリルビン(-),亜硝酸塩(-),白血球エステラーゼ(2+).
20.ウイルス感染細胞
著者: 今井宣子
ページ範囲:P.1229 - P.1229
症 例:小児科,10歳,男児.
診 断:白血病.同種骨髄移植後,無菌室にて経過観察中.
尿外観:淡黄褐色,透明.
尿定性検査所見:pH6,比重1.018,蛋白(-),糖(-),潜血(-),ケトン体(-),ウロビリノゲン(±),ビリルビン(-),亜硝酸塩(-),白血球エステラーゼ(-).
21.脂肪円柱と卵円形脂肪体
著者: 今井宣子
ページ範囲:P.1230 - P.1230
症 例:腎臓内科,45歳,男性.
診 断:ネフローゼ症候群.
尿外観:淡黄褐色,やや濁.
尿定性検査所見:pH6,比重1.015,蛋白(3+),糖(-),潜血(-),ケトン体(-),ウロビリノゲン(±),ビリルビン(-),亜硝酸塩(-),白血球エステラーゼ(-).
22.類デンプン小体
著者: 今井宣子
ページ範囲:P.1231 - P.1231
症 例:泌尿器科,70歳,男性.
診 断:前立腺肥大症.
尿外観:淡黄褐色,やや濁.
尿定性検査所見:pH6,比重1.025,蛋白(±),糖(-),潜血(3+),ケトン体(-),ウロビリノゲン(±),ビリルビン(-),亜硝酸塩(-),白血球エステラーゼ(3+).
23.乳糜尿
著者: 今井宣子
ページ範囲:P.1232 - P.1232
症 例:内科,62歳,女性.
診 断:成人Tリンパ球白血病,甲状腺癌,高脂血症,大動脈瘤解離.
尿外観:淡黄色,強度乳濁.
尿定性検査所見:pH5.5,比重1.022,蛋白(2+),糖(2+),潜血(3+),ケトン体(-),ウロビリノゲン(±),ビリルビン(-),亜硝酸塩(-),白血球エステラーゼ(-).
24.ワムシ
著者: 今井宣子
ページ範囲:P.1233 - P.1233
症 例:小児科,14歳,男性.
診 断:ネフローゼ症候群.
尿外観:水様無色,やや濁.
尿定性検査所見:pH6.5,比重1.002,蛋白(-),糖(-),潜血(-),ケトン体(-),ウロビリノゲン(±),ビリルビン(-),亜硝酸塩(+),白血球エステラーゼ(-).
基本情報
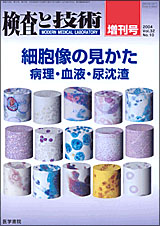
バックナンバー
52巻12号(2024年12月発行)
技術講座 生理
52巻11号(2024年11月発行)
技術講座 生理
52巻10号(2024年10月発行)
技術講座 生理
52巻9号(2024年9月発行)
増大号 臨床医に伝わりやすい 検査報告書とパニック値報告の心得
52巻8号(2024年8月発行)
技術講座 生理
52巻7号(2024年7月発行)
技術講座 生理
52巻6号(2024年6月発行)
技術講座 生理
52巻5号(2024年5月発行)
技術講座 その他
52巻4号(2024年4月発行)
技術講座 生理
52巻3号(2024年3月発行)
増大号 POCUSの決め手。 早く、正確な診断のために
52巻2号(2024年2月発行)
技術講座 生理
52巻1号(2024年1月発行)
技術講座 その他
51巻12号(2023年12月発行)
技術講座 生理
51巻11号(2023年11月発行)
技術講座 生理
51巻10号(2023年10月発行)
技術講座 その他
51巻9号(2023年9月発行)
増大号 匠から学ぶ 血栓止血検査ガイド
51巻8号(2023年8月発行)
技術講座 生理
51巻7号(2023年7月発行)
技術講座 生理
51巻6号(2023年6月発行)
技術講座 生理
51巻5号(2023年5月発行)
技術講座 生理
51巻4号(2023年4月発行)
技術講座 生理
51巻3号(2023年3月発行)
増大号 症例から学ぶ 疾患と検査値の推移
51巻2号(2023年2月発行)
技術講座 その他
51巻1号(2023年1月発行)
技術講座 生理
50巻12号(2022年12月発行)
技術講座 その他
50巻11号(2022年11月発行)
技術講座 生理
50巻10号(2022年10月発行)
技術講座 生理
50巻9号(2022年9月発行)
増大号 希少例と特殊像がわかる! エコーの撮り方完全マスター
50巻8号(2022年8月発行)
技術講座 生理
50巻7号(2022年7月発行)
技術講座 生理
50巻6号(2022年6月発行)
技術講座 生理
50巻5号(2022年5月発行)
技術講座 生理
50巻4号(2022年4月発行)
技術講座 生理
50巻3号(2022年3月発行)
増大号 見て学ぶ 一般検査学アトラス—外観検査から顕微鏡検査まで
50巻2号(2022年2月発行)
技術講座 その他
50巻1号(2022年1月発行)
技術講座 生理
49巻12号(2021年12月発行)
技術講座 生理
49巻11号(2021年11月発行)
技術講座 生理
49巻10号(2021年10月発行)
技術講座 生理
49巻9号(2021年9月発行)
増刊号 病態別 腹部エコーの観察・記録・報告書作成マスター
49巻8号(2021年8月発行)
技術講座 生理
49巻7号(2021年7月発行)
技術講座 生理
49巻6号(2021年6月発行)
技術講座 生理
49巻5号(2021年5月発行)
技術講座 生理
49巻4号(2021年4月発行)
技術講座 一般
49巻3号(2021年3月発行)
増刊号 First&Next Step 微生物検査サポートブック
49巻2号(2021年2月発行)
技術講座 微生物
49巻1号(2021年1月発行)
技術講座 病理・生理
48巻12号(2020年12月発行)
技術講座 その他
48巻11号(2020年11月発行)
技術講座 生化学
48巻10号(2020年10月発行)
技術講座 生理
48巻9号(2020年9月発行)
増刊号 学会発表・論文執筆はもう怖くない! 臨床検査技師のための研究入門
48巻8号(2020年8月発行)
技術講座 遺伝子
48巻7号(2020年7月発行)
技術講座 その他
48巻6号(2020年6月発行)
技術講座 輸血
48巻5号(2020年5月発行)
技術講座 生化学
48巻4号(2020年4月発行)
技術講座 生理
48巻3号(2020年3月発行)
増刊号 採血のすべて—手技から採血室の運用まで徹底解説
48巻2号(2020年2月発行)
技術講座 微生物
48巻1号(2020年1月発行)
技術講座 生理
47巻12号(2019年12月発行)
技術講座 病理
47巻11号(2019年11月発行)
技術講座 生理
47巻10号(2019年10月発行)
技術講座 生理
47巻9号(2019年9月発行)
増刊号 染色画像を比べて学ぶ 体腔液アトラス
47巻8号(2019年8月発行)
技術講座 病理
47巻7号(2019年7月発行)
技術講座 一般
47巻6号(2019年6月発行)
技術講座 血液
47巻5号(2019年5月発行)
技術講座 血液
47巻4号(2019年4月発行)
技術講座 血液
47巻3号(2019年3月発行)
増刊号 エキスパートが教える 心・血管エコー計測のノウハウ
47巻2号(2019年2月発行)
技術講座 病理
47巻1号(2019年1月発行)
技術講座 微生物
46巻12号(2018年12月発行)
技術講座 生理
46巻11号(2018年11月発行)
技術講座 輸血・遺伝子検査
46巻10号(2018年10月発行)
技術講座 その他
46巻9号(2018年9月発行)
増刊号 現場で“パッ”と使える 免疫染色クイックガイド
46巻8号(2018年8月発行)
技術講座 輸血・遺伝子検査
46巻7号(2018年7月発行)
技術講座 生理
46巻6号(2018年6月発行)
技術講座 管理
46巻5号(2018年5月発行)
技術講座 生化学
46巻4号(2018年4月発行)
技術講座 一般
46巻3号(2018年3月発行)
増刊号 感染症クイックリファレンス
46巻2号(2018年2月発行)
技術講座 輸血
46巻1号(2018年1月発行)
技術講座 病理
45巻12号(2017年12月発行)
技術講座 生理
45巻11号(2017年11月発行)
技術講座 一般
45巻10号(2017年10月発行)
技術講座 微生物
45巻9号(2017年9月発行)
増刊号 循環器病院の技師が教える メディカルスタッフのための心電図教室
45巻8号(2017年8月発行)
技術講座 栄養
45巻7号(2017年7月発行)
技術講座 病理
45巻6号(2017年6月発行)
技術講座 病理
45巻5号(2017年5月発行)
技術講座 細胞治療・管理
45巻4号(2017年4月発行)
技術講座 遺伝子・染色体検査
45巻3号(2017年3月発行)
45巻2号(2017年2月発行)
技術講座 細胞治療
45巻1号(2017年1月発行)
技術講座 病理
44巻13号(2016年12月発行)
技術講座 免疫
44巻12号(2016年11月発行)
技術講座 微生物
44巻11号(2016年10月発行)
技術講座 微生物
44巻10号(2016年9月発行)
増刊号 はじめて出会う 検査画像
44巻9号(2016年9月発行)
技術講座 管理・その他
44巻8号(2016年8月発行)
技術講座 微生物
44巻7号(2016年7月発行)
技術講座 生理
44巻6号(2016年6月発行)
技術講座 微生物
44巻5号(2016年5月発行)
技術講座 生理
44巻4号(2016年4月発行)
技術講座 微生物
44巻3号(2016年3月発行)
技術講座 生理
44巻2号(2016年2月発行)
技術講座 微生物
44巻1号(2016年1月発行)
技術講座 微生物
43巻13号(2015年12月発行)
技術講座 生化学
43巻12号(2015年11月発行)
技術講座 生化学
43巻11号(2015年10月発行)
技術講座 一般
43巻10号(2015年9月発行)
増刊号 血液形態アトラス
43巻9号(2015年9月発行)
技術講座 生理
43巻8号(2015年8月発行)
技術講座 生理
43巻7号(2015年7月発行)
技術講座 生理
43巻6号(2015年6月発行)
技術講座 微生物
43巻5号(2015年5月発行)
技術講座 移植医療
43巻4号(2015年4月発行)
技術講座 病理
43巻3号(2015年3月発行)
技術講座 血液
43巻2号(2015年2月発行)
技術講座 管理
43巻1号(2015年1月発行)
技術講座 病理
42巻13号(2014年12月発行)
技術講座 生化学
42巻12号(2014年11月発行)
技術講座 病理
42巻11号(2014年10月発行)
技術講座 血液
42巻10号(2014年9月発行)
増刊号 超音波×病理 対比アトラス
42巻9号(2014年9月発行)
技術講座 生理
42巻8号(2014年8月発行)
技術講座 免疫
42巻7号(2014年7月発行)
技術講座 生理
42巻6号(2014年6月発行)
技術講座 生理
42巻5号(2014年5月発行)
技術講座 病理
42巻4号(2014年4月発行)
技術講座 輸血
42巻3号(2014年3月発行)
技術講座 血液
42巻2号(2014年2月発行)
技術講座 微生物
42巻1号(2014年1月発行)
技術講座 病理
41巻13号(2013年12月発行)
技術講座 生理
41巻12号(2013年11月発行)
技術講座 生化学
41巻11号(2013年10月発行)
技術講座 生化学
41巻10号(2013年9月発行)
増刊号 解剖と正常像がわかる! エコーの撮り方完全マスター
41巻9号(2013年9月発行)
技術講座 微生物
41巻8号(2013年8月発行)
技術講座 生理
41巻7号(2013年7月発行)
技術講座 生理
41巻6号(2013年6月発行)
技術講座 微生物
41巻5号(2013年5月発行)
技術講座 一般
41巻4号(2013年4月発行)
技術講座 生化学
41巻3号(2013年3月発行)
技術講座 生理
41巻2号(2013年2月発行)
技術講座 生理
41巻1号(2013年1月発行)
技術講座 生理
40巻13号(2012年12月発行)
技術講座 血液
40巻12号(2012年11月発行)
技術講座 生理
40巻11号(2012年10月発行)
技術講座 生理
40巻10号(2012年9月発行)
増刊号 この検査データを読めますか?―検査値から病態を探る
40巻9号(2012年9月発行)
技術講座 生理
40巻8号(2012年8月発行)
技術講座 細胞診
40巻7号(2012年7月発行)
技術講座 生理
40巻6号(2012年6月発行)
技術講座 生理
40巻5号(2012年5月発行)
技術講座 生理
40巻4号(2012年4月発行)
技術講座 血液
40巻3号(2012年3月発行)
技術講座 生理
40巻2号(2012年2月発行)
技術講座 輸血
40巻1号(2012年1月発行)
技術講座 遺伝子
39巻13号(2011年12月発行)
疾患と検査値の推移
39巻12号(2011年11月発行)
疾患と検査値の推移
39巻11号(2011年10月発行)
疾患と検査値の推移
39巻10号(2011年9月発行)
増刊号 緊急報告すべき検査結果のすべて―すぐに使えるパニック値事典
39巻9号(2011年9月発行)
疾患と検査値の推移
39巻8号(2011年8月発行)
疾患と検査値の推移
39巻7号(2011年7月発行)
疾患と検査値の推移
39巻6号(2011年6月発行)
技術講座 生理
39巻5号(2011年5月発行)
技術講座 生理
39巻4号(2011年4月発行)
疾患と検査値の推移
39巻3号(2011年3月発行)
疾患と検査値の推移
39巻2号(2011年2月発行)
疾患と検査値の推移
39巻1号(2011年1月発行)
疾患と検査値の推移
38巻13号(2010年12月発行)
疾患と検査値の推移
38巻12号(2010年11月発行)
疾患と検査値の推移
38巻11号(2010年10月発行)
疾患と検査値の推移
38巻10号(2010年9月発行)
増刊号 免疫反応と臨床検査2010
38巻9号(2010年9月発行)
疾患と検査値の推移
38巻8号(2010年8月発行)
疾患と検査値の推移
38巻7号(2010年7月発行)
疾患と検査値の推移
38巻6号(2010年6月発行)
疾患と検査値の推移
38巻5号(2010年5月発行)
疾患と検査値の推移
38巻4号(2010年4月発行)
疾患と検査値の推移
38巻3号(2010年3月発行)
疾患と検査値の推移
38巻2号(2010年2月発行)
疾患と検査値の推移
38巻1号(2010年1月発行)
疾患と検査値の推移
37巻13号(2009年12月発行)
疾患と検査値の推移
37巻12号(2009年11月発行)
疾患と検査値の推移
37巻11号(2009年10月発行)
疾患と検査値の推移
37巻10号(2009年9月発行)
増刊号 顕微鏡検査のコツ―臨床に役立つ形態学
37巻9号(2009年9月発行)
疾患と検査値の推移
37巻8号(2009年8月発行)
疾患と検査値の推移
37巻7号(2009年7月発行)
疾患と検査値の推移
37巻6号(2009年6月発行)
疾患と検査値の推移
37巻5号(2009年5月発行)
疾患と検査値の推移
37巻4号(2009年4月発行)
疾患と検査値の推移
37巻3号(2009年3月発行)
疾患と検査値の推移
37巻2号(2009年2月発行)
疾患と検査値の推移
37巻1号(2009年1月発行)
疾患と検査値の推移
36巻13号(2008年12月発行)
疾患と検査値の推移
36巻12号(2008年11月発行)
疾患と検査値の推移
36巻11号(2008年10月発行)
疾患と検査値の推移
36巻10号(2008年9月発行)
増刊号 これから広がる生理検査・新たにはじまる生理検査
36巻9号(2008年9月発行)
疾患と検査値の推移
36巻8号(2008年8月発行)
疾患と検査値の推移
36巻7号(2008年7月発行)
疾患と検査値の推移
36巻6号(2008年6月発行)
疾患と検査値の推移
36巻5号(2008年5月発行)
疾患と検査値の推移
36巻4号(2008年4月発行)
疾患と検査値の推移
36巻3号(2008年3月発行)
疾患と検査値の推移
36巻2号(2008年2月発行)
疾患と検査値の推移
36巻1号(2008年1月発行)
疾患と検査値の推移
35巻13号(2007年12月発行)
疾患と検査値の推移
35巻12号(2007年11月発行)
疾患と検査値の推移
35巻11号(2007年10月発行)
増刊号 メタボリックシンドローム健診検査技術マニュアル
35巻10号(2007年10月発行)
疾患と検査値の推移
35巻9号(2007年9月発行)
疾患と検査値の推移
35巻8号(2007年8月発行)
疾患と検査値の推移
35巻7号(2007年7月発行)
疾患と検査値の推移
35巻6号(2007年6月発行)
疾患と検査値の推移
35巻5号(2007年5月発行)
疾患と検査値の推移
35巻4号(2007年4月発行)
疾患と検査値の推移
35巻3号(2007年3月発行)
疾患と検査値の推移
35巻2号(2007年2月発行)
疾患と検査値の推移
35巻1号(2007年1月発行)
疾患と検査値の推移
34巻13号(2006年12月発行)
技術講座 生理
34巻12号(2006年11月発行)
技術講座 一般
34巻11号(2006年10月発行)
増刊号 新しい臨床検査・未来の臨床検査
34巻10号(2006年10月発行)
疾患と検査値の推移
34巻9号(2006年9月発行)
疾患と検査値の推移
34巻8号(2006年8月発行)
疾患と検査値の推移
34巻7号(2006年7月発行)
疾患と検査値の推移
34巻6号(2006年6月発行)
疾患と検査値の推移
34巻5号(2006年5月発行)
疾患と検査値の推移
34巻4号(2006年4月発行)
疾患と検査値の推移
34巻3号(2006年3月発行)
疾患と検査値の推移
34巻2号(2006年2月発行)
疾患と検査値の推移
34巻1号(2006年1月発行)
疾患と検査値の推移
33巻13号(2005年12月発行)
疾患と検査値の推移
33巻12号(2005年11月発行)
疾患と検査値の推移
33巻11号(2005年10月発行)
増刊号 一線診療のための臨床検査
33巻10号(2005年10月発行)
疾患と検査値の推移
33巻9号(2005年9月発行)
疾患と検査値の推移
33巻8号(2005年8月発行)
疾患と検査値の推移
33巻7号(2005年7月発行)
疾患と検査値の推移
33巻6号(2005年6月発行)
疾患と検査値の推移
33巻5号(2005年5月発行)
疾患と検査値の推移
33巻4号(2005年4月発行)
疾患と検査値の推移
33巻3号(2005年3月発行)
疾患と検査値の推移
33巻2号(2005年2月発行)
疾患と検査値の推移
33巻1号(2005年1月発行)
疾患と検査値の推移
32巻13号(2004年12月発行)
技術講座 血液
32巻12号(2004年11月発行)
技術講座 病理
32巻11号(2004年10月発行)
技術講座 血液
32巻10号(2004年9月発行)
増刊号 細胞像の見かた―病理・血液・尿沈渣
32巻9号(2004年9月発行)
技術講座 生化学
32巻8号(2004年8月発行)
技術講座 免疫
32巻7号(2004年7月発行)
技術講座 微生物
32巻6号(2004年6月発行)
技術講座 病理
32巻5号(2004年5月発行)
技術講座 病理
32巻4号(2004年4月発行)
技術講座 病理
32巻3号(2004年3月発行)
技術講座 微生物
32巻2号(2004年2月発行)
技術講座 生化学
32巻1号(2004年1月発行)
技術講座 微生物
31巻13号(2003年12月発行)
技術講座 微生物
31巻12号(2003年11月発行)
技術講座 病理
31巻11号(2003年10月発行)
技術講座 微生物
31巻10号(2003年9月発行)
増刊号 包括医療と臨床検査
31巻9号(2003年9月発行)
技術講座 一般
31巻8号(2003年8月発行)
技術講座 微生物
31巻7号(2003年7月発行)
技術講座 病理
31巻6号(2003年6月発行)
技術講座 免疫
31巻5号(2003年5月発行)
技術講座 一般
31巻4号(2003年4月発行)
技術講座 病理
31巻3号(2003年3月発行)
技術講座 生化学
31巻2号(2003年2月発行)
技術講座 免疫
31巻1号(2003年1月発行)
技術講座 免疫
30巻13号(2002年12月発行)
技術講座 生理
30巻12号(2002年11月発行)
技術講座 生理
30巻11号(2002年10月発行)
技術講座 生化学
30巻10号(2002年9月発行)
増刊号 誰でもわかる遺伝子検査
30巻9号(2002年9月発行)
技術講座 微生物
30巻8号(2002年8月発行)
技術講座 生化学
30巻7号(2002年7月発行)
技術講座 微生物
30巻6号(2002年6月発行)
技術講座 生化学
30巻5号(2002年5月発行)
技術講座 微生物
30巻4号(2002年4月発行)
技術講座 一般
30巻3号(2002年3月発行)
技術講座 生化学
30巻2号(2002年2月発行)
技術講座 一般
30巻1号(2002年1月発行)
技術講座 免疫
29巻13号(2001年12月発行)
技術講座 病理
29巻12号(2001年11月発行)
技術講座 生理
29巻11号(2001年10月発行)
技術講座 病理
29巻10号(2001年9月発行)
技術講座 病理
29巻9号(2001年8月発行)
技術講座 病理
29巻8号(2001年7月発行)
技術講座 生理
29巻7号(2001年6月発行)
増刊号 病理組織・細胞診のための日常染色法ガイダンス
29巻6号(2001年6月発行)
技術講座 微生物
29巻5号(2001年5月発行)
技術講座 生理
29巻4号(2001年4月発行)
技術講座 病理
29巻3号(2001年3月発行)
技術講座 微生物
29巻2号(2001年2月発行)
技術講座 微生物
29巻1号(2001年1月発行)
技術講座 一般
28巻13号(2000年12月発行)
技術講座 病理
28巻12号(2000年11月発行)
技術講座 病理
28巻11号(2000年10月発行)
技術講座 免疫
28巻10号(2000年9月発行)
技術講座 微生物
28巻9号(2000年8月発行)
技術講座 微生物
28巻8号(2000年7月発行)
技術講座 生理
28巻7号(2000年6月発行)
増刊号 血液検査実践マニュアル
28巻6号(2000年6月発行)
技術講座 免疫
28巻5号(2000年5月発行)
技術講座 血液
28巻4号(2000年4月発行)
技術講座 一般
28巻3号(2000年3月発行)
技術講座 生理
28巻2号(2000年2月発行)
技術講座 生化学
28巻1号(2000年1月発行)
技術講座 一般
27巻13号(1999年12月発行)
技術講座 病理
27巻12号(1999年11月発行)
技術講座 一般
27巻11号(1999年10月発行)
技術講座 生化学
27巻10号(1999年9月発行)
技術講座 免疫
27巻9号(1999年8月発行)
技術講座 病理
27巻8号(1999年7月発行)
技術講座 病理
27巻7号(1999年6月発行)
増刊号 緊急検査実践マニュアル
27巻6号(1999年6月発行)
技術講座 生化学
27巻5号(1999年5月発行)
技術講座 血液
27巻4号(1999年4月発行)
技術講座 一般
27巻3号(1999年3月発行)
技術講座 生理
27巻2号(1999年2月発行)
技術講座 微生物
27巻1号(1999年1月発行)
技術講座 生理
26巻13号(1998年12月発行)
技術講座 一般
26巻12号(1998年11月発行)
技術講座 病理
26巻11号(1998年10月発行)
技術講座 病理
26巻10号(1998年9月発行)
技術講座 生理
26巻9号(1998年8月発行)
技術講座 生理
26巻8号(1998年7月発行)
技術講座 生理
26巻7号(1998年6月発行)
増刊号 病理組織・細胞診実践マニュアル
26巻6号(1998年6月発行)
技術講座 病理
26巻5号(1998年5月発行)
技術講座 一般
26巻4号(1998年4月発行)
技術講座 病理
26巻3号(1998年3月発行)
技術講座 一般
26巻2号(1998年2月発行)
技術講座 生理
26巻1号(1998年1月発行)
技術講座 血液
25巻13号(1997年12月発行)
技術講座 一般
25巻12号(1997年11月発行)
技術講座 一般
25巻11号(1997年10月発行)
技術講座 生理
25巻10号(1997年9月発行)
技術講座 血液
25巻9号(1997年8月発行)
技術講座 一般
25巻8号(1997年7月発行)
技術講座 一般
25巻7号(1997年6月発行)
増刊号 輸血検査実践マニュアル
25巻6号(1997年6月発行)
技術講座 免疫
25巻5号(1997年5月発行)
技術講座 生理
25巻4号(1997年4月発行)
技術講座 生理
25巻3号(1997年3月発行)
技術講座 微生物
25巻2号(1997年2月発行)
技術講座 生理
25巻1号(1997年1月発行)
技術講座 一般
24巻13号(1996年12月発行)
技術講座 生理
24巻12号(1996年11月発行)
技術講座 一般
24巻11号(1996年10月発行)
技術講座 生理
24巻10号(1996年9月発行)
技術講座 管理
24巻9号(1996年8月発行)
技術講座 生理
24巻8号(1996年7月発行)
技術講座 生理
24巻7号(1996年6月発行)
増刊号 感染症検査実践マニュアル
24巻6号(1996年6月発行)
技術講座 病理
24巻5号(1996年5月発行)
技術講座 生理
24巻4号(1996年4月発行)
技術講座 生理
24巻3号(1996年3月発行)
技術講座 生理
24巻2号(1996年2月発行)
技術講座 生理
24巻1号(1996年1月発行)
技術講座 一般
23巻13号(1995年12月発行)
技術講座 生理
23巻12号(1995年11月発行)
技術講座 病理
23巻11号(1995年10月発行)
技術講座 微生物
23巻10号(1995年9月発行)
技術講座 生理
23巻9号(1995年8月発行)
技術講座 一般
23巻8号(1995年7月発行)
技術講座 免疫
23巻7号(1995年6月発行)
技術講座 生理
23巻6号(1995年5月発行)
技術講座 一般
23巻5号(1995年4月発行)
増刊号 臨床生理検査実践マニュアル画像検査を中心として
23巻4号(1995年4月発行)
技術講座 病理
23巻3号(1995年3月発行)
技術講座 病理
23巻2号(1995年2月発行)
技術講座 一般
23巻1号(1995年1月発行)
技術講座 生理
22巻13号(1994年12月発行)
技術講座 一般
22巻12号(1994年11月発行)
技術講座 一般
22巻11号(1994年10月発行)
技術講座 一般
22巻10号(1994年9月発行)
技術講座 一般
22巻9号(1994年8月発行)
技術講座 生理
22巻8号(1994年7月発行)
技術講座 病理
22巻7号(1994年6月発行)
技術講座 一般
22巻6号(1994年5月発行)
技術講座 一般
22巻5号(1994年4月発行)
増刊号 免疫検査実践マニュアル
22巻4号(1994年4月発行)
技術講座 生理
22巻3号(1994年3月発行)
技術講座 免疫
22巻2号(1994年2月発行)
技術講座 一般
22巻1号(1994年1月発行)
技術講座 生理
21巻13号(1993年12月発行)
技術講座 一般
21巻12号(1993年11月発行)
技術講座 一般
21巻11号(1993年10月発行)
技術講座 一般
21巻10号(1993年9月発行)
技術講座 生理
21巻9号(1993年8月発行)
技術講座 一般
21巻8号(1993年7月発行)
技術講座 病理
21巻7号(1993年6月発行)
技術講座 一般
21巻6号(1993年5月発行)
技術講座 生理
21巻5号(1993年4月発行)
増刊号 臨床化学実践マニュアル
21巻4号(1993年4月発行)
技術講座 生理
21巻3号(1993年3月発行)
技術講座 病理
21巻2号(1993年2月発行)
技術講座 生理
21巻1号(1993年1月発行)
技術講座 生理
20巻13号(1992年12月発行)
技術講座 一般
20巻12号(1992年11月発行)
技術講座 一般
20巻11号(1992年10月発行)
技術講座 一般
20巻10号(1992年9月発行)
技術講座 一般
20巻9号(1992年8月発行)
技術講座 一般
20巻8号(1992年7月発行)
技術講座 血液
20巻7号(1992年6月発行)
技術講座 一般
20巻6号(1992年5月発行)
増刊号 尿検査法
20巻5号(1992年5月発行)
技術講座 生理
20巻4号(1992年4月発行)
技術講座 生理
20巻3号(1992年3月発行)
技術講座 病理
20巻2号(1992年2月発行)
技術講座 一般
20巻1号(1992年1月発行)
技術講座 生理
19巻13号(1991年12月発行)
技術講座 管理
19巻12号(1991年11月発行)
技術講座 生理
19巻11号(1991年10月発行)
技術講座 生理
19巻10号(1991年9月発行)
技術講座 一般
19巻9号(1991年8月発行)
技術講座 一般
19巻8号(1991年7月発行)
技術講座 生理
19巻7号(1991年6月発行)
増刊号 臨床血液検査
19巻6号(1991年6月発行)
技術講座 生理
19巻5号(1991年5月発行)
技術講座 生理
19巻4号(1991年4月発行)
技術講座 一般
19巻3号(1991年3月発行)
技術講座 生理
19巻2号(1991年2月発行)
技術講座 生理
19巻1号(1991年1月発行)
技術講座 一般
18巻13号(1990年12月発行)
技術講座 生理
18巻12号(1990年11月発行)
技術講座 微生物
18巻11号(1990年10月発行)
技術講座 生理
18巻10号(1990年9月発行)
技術講座 一般
18巻9号(1990年8月発行)
技術講座 一般
18巻8号(1990年7月発行)
技術講座 一般
18巻7号(1990年6月発行)
技術講座 一般
18巻6号(1990年5月発行)
増刊号 血液・尿以外の体液検査法
18巻5号(1990年5月発行)
技術講座 一般
18巻4号(1990年4月発行)
技術講座 一般
18巻3号(1990年3月発行)
技術講座 血液
18巻2号(1990年2月発行)
技術講座 生理
18巻1号(1990年1月発行)
技術講座 生理
17巻13号(1989年12月発行)
技術講座 一般
17巻12号(1989年11月発行)
技術講座 一般
17巻11号(1989年10月発行)
技術講座 一般
17巻10号(1989年9月発行)
技術講座 一般
17巻9号(1989年8月発行)
技術講座 生理
17巻8号(1989年7月発行)
技術講座 血清
17巻7号(1989年6月発行)
技術講座 一般
17巻6号(1989年5月発行)
感染症の検査法 Ⅲ 検査法各論
17巻5号(1989年5月発行)
技術講座 一般
17巻4号(1989年4月発行)
技術講座 生理
17巻3号(1989年3月発行)
技術講座 病理
17巻2号(1989年2月発行)
技術講座 一般
17巻1号(1989年1月発行)
技術講座 生理
16巻13号(1988年12月発行)
技術講座 一般
16巻12号(1988年11月発行)
技術講座 一般
16巻11号(1988年10月発行)
技術講座 一般
16巻10号(1988年9月発行)
技術講座 生理
16巻9号(1988年8月発行)
技術講座 一般
16巻8号(1988年7月発行)
技術講座 一般
16巻7号(1988年6月発行)
免疫化学検査法 資料
16巻6号(1988年6月発行)
技術講座 一般
16巻5号(1988年5月発行)
技術講座 一般
16巻4号(1988年4月発行)
技術講座 病理
16巻3号(1988年3月発行)
技術講座 生理
16巻2号(1988年2月発行)
技術講座 一般
16巻1号(1988年1月発行)
技術講座 血液
15巻13号(1987年12月発行)
技術講座 一般
15巻12号(1987年11月発行)
技術講座 病理
15巻11号(1987年10月発行)
技術講座 細胞診
15巻10号(1987年9月発行)
技術講座 一般
15巻9号(1987年8月発行)
技術講座 細胞診
15巻8号(1987年7月発行)
技術講座 病理
15巻7号(1987年6月発行)
技術講座 病理
15巻6号(1987年5月発行)
技術講座 病理
15巻5号(1987年4月発行)
臨床生理検査と技術 座談会
15巻4号(1987年4月発行)
技術講座 生理
15巻3号(1987年3月発行)
技術講座 血液
15巻2号(1987年2月発行)
技術講座 一般
15巻1号(1987年1月発行)
技術講座 病理
14巻13号(1986年12月発行)
技術講座 一般
14巻12号(1986年11月発行)
技術講座 病理
14巻11号(1986年10月発行)
技術講座 血清
14巻10号(1986年9月発行)
技術講座 血清
14巻9号(1986年8月発行)
技術講座 生理
14巻8号(1986年7月発行)
技術講座 血清
14巻7号(1986年6月発行)
技術講座 病理
14巻6号(1986年5月発行)
技術講座 生理
14巻5号(1986年4月発行)
形態学的検査と技術 血液と病理
14巻4号(1986年4月発行)
技術講座 病理
14巻3号(1986年3月発行)
技術講座 細菌
14巻2号(1986年2月発行)
技術講座 病理
14巻1号(1986年1月発行)
技術講座 細菌
13巻12号(1985年12月発行)
技術講座 病理
13巻11号(1985年11月発行)
技術講座 病理
13巻10号(1985年10月発行)
技術講座 生理
13巻9号(1985年9月発行)
技術講座 病理
13巻8号(1985年8月発行)
技術講座 病理
13巻7号(1985年7月発行)
技術講座 血液
13巻6号(1985年6月発行)
技術講座 一般
13巻5号(1985年5月発行)
技術講座 病理
13巻4号(1985年4月発行)
技術講座 一般
13巻3号(1985年3月発行)
技術講座 血液
13巻2号(1985年2月発行)
技術講座 一般
13巻1号(1985年1月発行)
技術講座 血液
12巻12号(1984年12月発行)
技術講座 血液
12巻11号(1984年11月発行)
技術講座 病理
12巻10号(1984年10月発行)
技術講座 輸血
12巻9号(1984年9月発行)
技術講座 一般
12巻8号(1984年8月発行)
技術講座 細菌
12巻7号(1984年7月発行)
技術講座 細菌
12巻6号(1984年6月発行)
技術講座 生理
12巻5号(1984年5月発行)
技術講座 一般
12巻4号(1984年4月発行)
技術講座 病理
12巻3号(1984年3月発行)
技術講座 血液
12巻2号(1984年2月発行)
技術講座 一般
12巻1号(1983年12月発行)
技術講座 血清
11巻12号(1983年12月発行)
技術講座 一般
11巻11号(1983年11月発行)
技術講座 細菌
11巻10号(1983年10月発行)
技術講座 細胞診
11巻9号(1983年9月発行)
技術講座 一般
11巻8号(1983年8月発行)
技術講座 血清
11巻7号(1983年7月発行)
技術講座 細菌
11巻6号(1983年6月発行)
技術講座 一般
11巻5号(1983年5月発行)
技術講座 病理
11巻4号(1983年4月発行)
技術講座 一般
11巻3号(1983年3月発行)
技術講座 血液
11巻2号(1983年2月発行)
技術講座 一般
11巻1号(1983年1月発行)
技術講座 血液
10巻12号(1982年12月発行)
技術講座 一般
10巻11号(1982年11月発行)
技術講座 生理
10巻10号(1982年10月発行)
技術講座 血清
10巻9号(1982年9月発行)
技術講座 細菌
10巻8号(1982年8月発行)
技術講座 一般
10巻7号(1982年7月発行)
技術講座 病理
10巻6号(1982年6月発行)
技術講座 細菌
10巻5号(1982年5月発行)
技術講座 病理
10巻4号(1982年4月発行)
技術講座 血清
10巻3号(1982年3月発行)
技術講座 生化学
10巻2号(1982年2月発行)
技術講座 病理
10巻1号(1982年1月発行)
技術講座 生化学
9巻12号(1981年12月発行)
技術講座 細菌
9巻11号(1981年11月発行)
技術講座 生理
9巻10号(1981年10月発行)
技術講座 一般
9巻9号(1981年9月発行)
技術講座 血清
9巻8号(1981年8月発行)
技術講座 血清
9巻7号(1981年7月発行)
技術講座 生理
9巻6号(1981年6月発行)
技術講座 細菌
9巻5号(1981年5月発行)
技術講座 一般
9巻4号(1981年4月発行)
技術講座 一般
9巻3号(1981年3月発行)
技術講座 血清
9巻2号(1981年2月発行)
技術講座 一般
9巻1号(1981年1月発行)
技術講座 生化学
8巻12号(1980年12月発行)
技術講座 一般
8巻11号(1980年11月発行)
技術講座 生理
8巻10号(1980年10月発行)
技術講座 検体の取り扱いと保存
8巻9号(1980年9月発行)
技術講座 病理
8巻8号(1980年8月発行)
技術講座 生化学
8巻7号(1980年7月発行)
技術講座 一般
8巻6号(1980年6月発行)
技術講座 生理
8巻5号(1980年5月発行)
技術講座 生化学
8巻4号(1980年4月発行)
技術講座 血清
8巻3号(1980年3月発行)
技術講座 病理
8巻2号(1980年2月発行)
技術講座 一般
8巻1号(1980年1月発行)
技術講座 生化学
7巻12号(1979年12月発行)
技術講座 一般
7巻11号(1979年11月発行)
技術講座 一般
7巻10号(1979年10月発行)
技術講座 細菌
7巻9号(1979年9月発行)
技術講座 生理
7巻8号(1979年8月発行)
技術講座 病理
7巻7号(1979年7月発行)
技術講座 生理
7巻6号(1979年6月発行)
技術講座 一般
7巻5号(1979年5月発行)
技術講座 血液
7巻4号(1979年4月発行)
技術講座 生理
7巻3号(1979年3月発行)
技術講座 病理
7巻2号(1979年2月発行)
技術講座 細菌
7巻1号(1979年1月発行)
技術講座 生化学
6巻12号(1978年12月発行)
技術講座 細菌
6巻11号(1978年11月発行)
技術講座 病理
6巻10号(1978年10月発行)
技術講座 血清
6巻9号(1978年9月発行)
技術講座 細菌
6巻8号(1978年8月発行)
技術講座 生化学
6巻7号(1978年7月発行)
技術講座 一般
6巻6号(1978年6月発行)
技術講座 病理
6巻5号(1978年5月発行)
技術講座 生理
6巻4号(1978年4月発行)
技術講座 一般
6巻3号(1978年3月発行)
技術講座 病理
6巻2号(1978年2月発行)
技術講座 一般
6巻1号(1978年1月発行)
技術講座 病理
5巻12号(1977年12月発行)
技術講座 生理
5巻11号(1977年11月発行)
技術講座 一般
5巻10号(1977年10月発行)
技術講座 細菌付録
5巻9号(1977年9月発行)
技術講座 一般
5巻8号(1977年8月発行)
技術講座 生理
5巻7号(1977年7月発行)
技術講座 一般
5巻6号(1977年6月発行)
技術講座 一般
5巻5号(1977年5月発行)
技術講座 一般
5巻4号(1977年4月発行)
技術講座 一般
5巻3号(1977年3月発行)
技術講座 一般
5巻2号(1977年2月発行)
技術講座 一般
5巻1号(1977年1月発行)
技術講座 一般
4巻12号(1976年12月発行)
技術講座 一般
4巻11号(1976年11月発行)
技術講座 一般
4巻10号(1976年10月発行)
技術講座 一般
4巻9号(1976年9月発行)
技術講座 一般
4巻8号(1976年8月発行)
技術講座 一般
4巻7号(1976年7月発行)
技術講座 一般
4巻6号(1976年6月発行)
技術講座 一般
4巻5号(1976年5月発行)
技術講座 一般
4巻4号(1976年4月発行)
技術講座 一般
4巻3号(1976年3月発行)
技術講座 一般
4巻2号(1976年2月発行)
技術講座 一般
4巻1号(1976年1月発行)
技術講座 一般
3巻12号(1975年12月発行)
技術講座 一般
3巻11号(1975年11月発行)
技術講座 一般
3巻10号(1975年10月発行)
技術講座 一般
3巻9号(1975年9月発行)
技術講座 一般
3巻7号(1975年8月発行)
特集 必修 日常検査の実技
3巻6号(1975年6月発行)
技術講座 生理
3巻5号(1975年5月発行)
技術講座 一般
3巻4号(1975年4月発行)
技術講座 一般
3巻3号(1975年3月発行)
技術講座 一般
3巻2号(1975年2月発行)
技術講座 一般
3巻1号(1975年1月発行)
技術講座 一般
