新しい知見
マイコプラズマ肺炎の病変成立には宿主免疫反応,とくにさまざまなサイトカインの関与が考えられている.最近マクロライド耐性Mycoplasma pneumoniaeの報告が注目されているが,臨床経過の遷延はなく治癒を左右する因子にはならないようである.マクロライド系薬剤の持つ抗炎症作用により病態形成の免疫応答が速やかに抑制されたため,治療効果が現れたのではないかと考えられている.
雑誌目次
検査と技術32巻13号
2004年12月発行
雑誌目次
病気のはなし
マイコプラズマ肺炎
著者: 黒崎知道
ページ範囲:P.1428 - P.1432
技術講座 一般
―初心者のための尿沈渣検査のコツ 第10回(最終回)―ステップアップ法
著者: 油野友二
ページ範囲:P.1433 - P.1438
新しい知見
患者さまの病態をより早く診断し適切な処置を行うためには,腎尿路系の病態把握に役立つわかりやすい形に加工された検査情報が求められており,そのためには血液検査・生化学検査などの各種検査情報を加味した総合的な判断が求められる.このような視点で尿沈渣検査を考えることがステップアップの原点と考える.
輸血
ゲルカラム凝集法を用いた輸血検査の自動化
著者: 小黒博之
ページ範囲:P.1439 - P.1446
新しい知見
輸血に先立って実施される血液型検査,不規則抗体スクリーニング,交差適合試験などの検査(輸血前検査)は,従来,試験管を用いて赤血球凝集反応の有無を判定する試験管法が用いられてきた.しかし,試験管法には,判定に熟練を要し,判定の個人差が結果に及ぼす影響が大きい,などの問題点があった.近年,客観的な判定,操作法の標準化・簡略化を目的とした新しい輸血検査法として,ゲルカラム凝集法が急速に普及してきている.また,ゲルカラム凝集法によって,従来の試験管法では困難であった輸血検査の自動化およびトータルシステム化が可能となり,輸血業務の効率化・リスクマネジメントの観点から,全自動輸血検査装置についても導入が進みつつある.
病理
オートプシーイメージングを基盤とした臓器画像診断(CT,MRI)に同期させた脳の切り出し方法
著者: 清水一範 , 江澤英史
ページ範囲:P.1447 - P.1452
新しい知見
三次元CT1)やマイクロCT2)など画像診断装置の進歩により,診断画像は組織画像に大きく近づいている.これらの技術をより精密にするための基盤として,病理診断との正確な対比は,これからますます重要になっていくだろうと思われる.画像診断に同期した臓器スライスの作製技術は,これに大きく貢献する.また,当院で実施されているオートプシーイメージングという試みは,こうした画像病理同期システムを構築するにあたり,有益な場を提供する3).
血液
血液細胞のPAS染色法と読みかた
著者: 阿南建一
ページ範囲:P.1453 - P.1457
新しい知見
血液分野での細胞化学染色は全般にわたって新しい知見たるものは見当たらない.しかし,PAS染色は従来に比べると診断的意義が広範囲に活用されてきたといえる.すなわち急性リンパ性白血病(acute lymphocytic leukemia,ALL)におけるリンパ芽球,骨髄異形成症候群における赤芽球や小型巨核球,また骨髄転移性腫瘍(腺癌,横紋筋肉腫など)には有効な診断的所見として用いられている.ALLのなかではFAB分類(French-American-British classification)でL1の形態をとり,CD10陽性のB-pre ALL(従来のcommon ALL)のなかで過ヨウ素酸シッフ染色(PAS染色)強陽性例は予後良好とされる.
検査データを考える
血小板減少症
著者: 浅妻直樹
ページ範囲:P.1471 - P.1475
血小板は生理的止血や病的血栓形成に中心的な役割を果たす血液細胞であり,血小板の異常は出血性疾患や虚血性心疾患,脳梗塞などの動脈血栓症の発症に密接に関わる.血小板は血管壁の安定性にも重要な役割を果たしており,血小板減少の場合止血困難な状態を生じ,血管壁傷害の有無に関係なく出血傾向を生じることになる.
一般に末梢静脈血中の血小板数の基準値は,15~35万/μlであるが,血小板数が10万/μl以下を血小板減少(thrombocytopenia)という.血小板減少であっても,血小板数が5万/μl以上であれば,出血傾向はほとんどみられず,外科手術も可能である.3~4万/μlに減少すると,粘膜,皮膚に粘膜出血,出血斑が出現し,歯肉出血,鼻出血,血尿などが認められるようになり,2万/μl以下の高度の血小板減少症では,頭蓋内出血,消化管出血などの重篤な出血症状を呈するようになり,病態によっては早急に血小板輸血が必要になる.しかし,日常の臨床検査業務で遭遇する血小板減少の中には,血小板が少なく算定される結果生じる,見かけ上の血小板減少(偽性血小板減少)も認められている.
オピニオン
これからの臨床化学
著者: 濱崎直孝
ページ範囲:P.1459 - P.1459
太古の時代から人類は病気の原因を追究してきたはずであり,その追究の手段は「観察と記録」であったと思われる.観察の対象は,最初は,患者そのものであったはずだが,17世紀後半頃から患者が出す尿,糞便などの生体成分にも対象が広がってきている.「観察」の行き着くところは「分析」であり,今日の「臨床化学」という学問体系に育ち上がったわけである.臨床化学体系の確立に決定的な役割を果たしたのは,1934年のFollingによるフェニルケトン尿症の発見である.患者の尿を分析することで病気の本態を突き止めることができる実例を示し,以後,臨床化学は確固たる学問体系として確立し今日に至っている.最近では,学問が細分化され「臨床化学とは生化学検査に関する学問」と勘違いする人々が多くなっているが,決してそうではなく,「臨床化学とは生体成分を化学的(科学的)に分析して,疾病発症の機序を明らかにするとともに疾病の診断治療に指針を提供する学問」である.
臨床化学(臨床検査といってもよい)の基本は生体成分の科学的定量分析であり,科学的定量分析に必要なものは「正確性」と「精密性である.分析された結果の測定値は再現性があり,その測定単位(dimension)が同じであれば,その数字を単純に比較検討できなければならない.残念ながら,これまでの臨床化学分析は科学的定量分析とは言い難い部分があった.「臨床検査測定値はそれぞれの病院に特有なものであり,患者が転院すれば検査はやり直すのが当然で,別の病院の臨床検査データは利用できない」のがこれまでの臨床化学分析であった.しかしながら,現在では,検査試薬の整備と分析機器の発達により臨床化学分析に普遍性が備わり,別の病院の臨床検査データを共通に利用できる(臨床検査データの標準化)環境が整ったといってよい.臨床検査に関わっているわれわれの認識を改めるだけで,臨床検査データの全国的な標準化は可能になりつつある.臨床化学の当面の重要課題の一つは,地味ではあるが,臨床検査データの国内的な標準化の完成である.検査データの標準化が進めば,臨床検査のデータベースが完備し疾病の診断・治療基準が標準化され,日本の医療の質が格段に上がることになる.
絵で見る免疫学 基礎編(60)
宿主とウイルスの攻防(5) インフルエンザウイルス その2
著者: 高木淳 , 玉井一
ページ範囲:P.1462 - P.1463
昨年末にわが国の養鶏業界および関係者を騒がせたのがH5N1型ウイルス(以下H5N1)である.無論ヒトはこの株のウイルスに対する抗体を持っていないのでヒトへの感染が懸念された.しかし,幸いなことにヒトへの感染の報告はなかった.なぜH5N1型ウイルスはこれほどまでに騒がれまたヒトへの感染がなかったのであろうか.その理由は,H1,H2およびH3株は局所感染しか起こさないが,H5N1は脳を含む全身の臓器に感染する毒性の強い株であることがトリで確認されているからである.インフルエンザウイルスが宿主に感染するためには,まずウイルスのHA(hemagglutinin,ヘマグルチニン)が宿主細胞表面のシアル酸と結合し,続いて宿主の分解酵素がウイルスのHAを開裂させることが必須である(32巻12号1367頁,図2参照).H1,H2およびH3型ウイルスのHAを開裂させる分解酵素は,呼吸器および腸管にのみ存在するので局所にしか感染しない(図1).これらの株の開裂部分のアミノ酸組成は,……アルギニン・グルタミン酸・トレオニン・アルギニン〈開裂部分〉グリシン……である.しかし,H5N1が強毒株といわれる所以は,HAを開裂させる分解酵素が脳を含む多くの臓器に存在するために全身に感染するからである.H5N1の開裂部分のアミノ酸組成は,……アルギニン・アルギニン・アルギニン・リジン・リジン・アルギニン〈開裂部分〉グリシン……で,開裂部分のアミノ酸組成と臓器に存在する分解酵素の基質特異性とが感染後の症状を左右するのである.
トリインフルエンザウイルスはヒトではあまり増殖しないのではないかと考えられている.それは,トリ-トリ間で感染するウイルスとヒト-ヒト間で感染するウイルスとのHAとシアル酸との結合の特異性に違いがあるからである.トリ-トリ間で感染するHAはシアル酸がガラクトースα2-3に結合したもの(α2.3Gal)を,ヒト-ヒト間で感染するHAはシアル酸がガラクトースにα2-6結合したもの(SAα2.6Gal)を特異的に認識する(図2).したがってH5N1のヒトへの散発的感染報告は東南アジアであるが大流行には至らなかったと考えられる.しかし,1997年に香港でトリH5N1がヒトSAα2.6Galを認識して感染したことが確認されているので,インフルエンザウイルスのHAとシアル酸-ガラクトースの結合の特異性はあまり厳密なものではないのかもしれない1).
けんさアラカルト
AGE その3 機器分析法
著者: 川上寿子 , 関根恭一
ページ範囲:P.1468 - P.1470
はじめに
本稿では,代表的AGE(advanced glycation end products,糖化反応最終産物)の機器分析を行う際に注意すべき点について述べる.
今月の表紙
百聞は一見に如かず・12 病理に馴染みの病原体たち(1)
著者: 松谷章司
ページ範囲:P.1458 - P.1458
われわれは外界に直接あるいは間接的に接している皮膚や気道,口腔,消化管,泌尿生殖器などの粘膜面に細菌を持っています.これを正常細菌叢(normal bacterial flora)あるいは常在細菌叢(indigenous bacterial flora)と呼んでいます.これらはバランスのとれた保菌状態にあって,感染予防,代謝,免疫賦活作用など,われわれにとって友好的に働いてくれています.健常な人でも口腔にはStreptococcus salivariusを筆頭として,Staphylococcus,Neisseria,Actinomyces,Veillonella,Candidaなど,極めて多数の細菌が生息していて,その数を聞くと途端に食欲がなくなってしまうほどです.しかし,宿主の免疫能が低下すると,これらの病原体は日和見感染病原菌になりえます.つまり,健常人にとって病原性を示さないか病原性の弱い微生物であっても,感染防御機能が低下すると,日和見感染症(opportunistic infection)が成立するのです.
この項では気道感染を起こす油断できない身近な真菌に触れます.
Laboratory Practice 生理 超音波像の読みかた
婦人科―良性疾患
著者: 堀川隆 , 箕浦茂樹
ページ範囲:P.1476 - P.1481
はじめに
超音波検査は侵襲がなく簡便に施行でき,近年の検査装置の発達により,産婦人科領域において視診・内診と並ぶ重要な診断法となった.
超音波検査はその簡便さからスクリーニング的に行われることが多いが,婦人科臓器の異常所見を見つけた場合はつねに悪性疾患の可能性を考えることが重要である.婦人科良性疾患と一言でいっても子宮・卵巣・卵管それぞれの機能性・炎症性・腫瘍性疾患などさまざまな疾患があるが,本稿では婦人科で目にする機会の多い良性疾患を中心にその超音波像の解説を行う.悪性疾患との鑑別については他稿を参照されたい.
生化学 これからの臨床協力業務事例集
チーム医療への参画
著者: 金光房江
ページ範囲:P.1482 - P.1486
倉敷中央病院検査部におけるチーム医療参画の経緯
倉敷中央病院検査部がチーム医療を始めたのは1980年に新棟が完成し,輸血検査室と生理検査室とが業務を開始したときに遡ります(表1).当時の病院検査部は高度成長時代で,チーム医療という言葉はほとんど使われていませんでした.新築に伴い輸血検査室は輸血センターに併設され,臨床検査技師(以下,技師)は医師,看護師,薬剤師と同じ部屋でチーム医療を始めました.生理検査室は心臓カテーテル(以下,心カテ)室と同じエリアに設置され,技師は生理検査に加えて心カテ時の検査も担当することになりました.いずれも設計当時,診療の内容や流れを考慮して効率的な医療を提供するためでした.
チーム医療の概要
現在当検査部が参画しているチーム医療を表1~4に示しました.最初に取り組んだ輸血センターと心カテ室との業務から,2004年に始まった栄養評価業務まで,およそ17の業務に技師が参画しています.輸血センターはその後業務を拡充したことから血液治療センターと改名しました.生理検査室は循環器系検査と呼吸器系検査とを担当する第1生理検査室と,それ以外を担当する第2生理検査室に分かれました.第1生理検査室は新設された心臓病センターの一部として業務を行っており,第2生理検査室は消化器内科や内分泌内科などと広くチーム医療を組んでいます(表2).
トピックス
初心者に必要な採血法の知識
著者: 小宮山豊 , 吉賀正亨 , 吉岡貞子
ページ範囲:P.1501 - P.1504
はじめに
最近発行された日本臨床検査標準協議会(Japanese Commitlee for Clinical Laboratory Standards,JCCLS)の「標準採血法ガイドライン(第1版)」の緒言が「適正な検体採取が検体検査の基本であるとすれば」で始まることからわかるように,血液検体検査は採血時より始まる1).したがって,検査部門職員は積極的に採血に関与しなければならない.臨床検査技師が採血する利点は,採血不良検体(凝固や量の不足や採血管間違い)の防止や採血困難時の採血管の共用(測定原理の理解による他管種での流用)が考えられる.一方で採血管の細菌汚染問題は,2003年秋に報道され,全国の病院で混乱を招いた2).これらの背景から,本稿で解説する採血法は標準法ではないが,われわれが新人や医学生および看護師に採血訓練をした経験を踏まえ,新しく採血業務に取り組む臨床検査技師が安全に採血を実施するための手順・注意事項を記した.なお,筆者は,初心者の場合,注射器採血が基本であると考えるため,さらに,適正に行えば,注射器・真空採血管採血ともに安全であることから,本稿は,注射器による採血法を取り上げた.採血に関するわが国の標準法は,2004年7月にJCCLSから発行された「標準採血法ガイドライン(第1版)」である.ぜひ参照していただきたい1).
〔レプチン/アディポネクチン〕比の臨床的有用性
著者: 織田直久 , 堀川幸男 , 伊藤光泰
ページ範囲:P.1504 - P.1506
近年,脂肪細胞から分泌される生理活性物質が,肥満,糖尿病,動脈硬化などの病態と深く関わりがあることが明らかになり,その生理活性物質は総称して,アディポサイトカインと呼ばれている1).その中でも,レプチン,アディポネクチンが特に注目されている.
血清中のレプチン,アディポネクチンは抗肥満作用が期待されることから善玉ホルモンと考えられている.女性は男性よりも高い値を示す.レプチン,アディポネクチンは脂肪細胞で造られるにもかかわらず,肥満の病態においては,レプチンは脂肪細胞の増加により上昇する2)一方,アディポネクチンは脂肪細胞の増加により減少する3)ことが確認されている.
失敗から学び磨く検査技術 病理標本作製法
固定時に生ずるアーティファクト 固定不良 短すぎる固定による組織障害
著者: 吉村忍
ページ範囲:P.1464 - P.1467
図1は肝臓のヘマトキシリン・エオジン染色(hematoxylin-eosin stain,以下HE染色)標本のマクロ像である.中心部は円形の穴が空いている標本となっている.図2は同じブロックより作製したマッソン-トリクローム染色(Masson-trichrome stain)のミクロ像である.中心部の円形空隙辺縁部は厚さが不均一に薄く,細胞質は間隙の目立つ内容物が溶出した染色性の悪い状態で,膠原線維の染色性は消失している.核は核膜が薄くクロマチンが不均等に溶出した間隙の多い状態となっている.細胞層にして15~30層程度外側で赤色系色素の染色状態も青色の膠原線維も正常な染色性を示し,本来の細胞状態が観察されている.いずれも標本としては総合的に見た場合使用不可と考えられるアーティファクトの強い標本である.
考えられる原因
パラフィンの浸透不良が直接の原因である.浸透不良のまま強引な薄切処理で標本を作製した結果,パラフィンが浸透していなかった中心部の組織が欠落した標本となっている.ホルマリンによる固定を十分に行い,24時間程度の脱水・パラフィン包埋処理を行ってあればこのような状態になることは考えにくい.
ラボクイズ
尿沈渣[6]
著者: 中島哲也 , 加藤裕一 , 内藤愼二
ページ範囲:P.1460 - P.1460
症 例:16歳,男性,頭痛,嘔吐がみられ近医を受信し尿検査で尿蛋白4+,X線写真上心不全,体重増加がみられるため当医院紹介入院となった.表に入院時の検査所見を示した.
問題1 図1で見られる尿中成分で正しいのはどれか.
(1)赤血球円柱
(2)上皮円柱
(3)顆粒円柱
(4)硝子円柱
(5)白血球円柱
11月号の解答と解説
著者: 東克巳
ページ範囲:P.1461 - P.1461
【問題1】 解答:(2)サプレッサーT細胞
解説:細胞表面マーカー検査の結果ではCD3(T細胞マーカー)陽性,CD8(サプレッサーT細胞マーカー)陽性なので,間違いなくサプレッサーT細胞の増加である.また,活性化マーカーの一つであるHLA-DRがCD8のほとんどで陽性であることより,異型リンパ球は活性化サプレッサーT細胞の増加といえる.
この結果から確かに単クローン性の増殖の可能性も考えられる.しかし,検査所見でリンパ球増加,特に種々の異型リンパ球の増加がヒントとなる.単クローン性の増殖であれば増殖する細胞はコピーなので異型リンパ球はほぼ同じ細胞形態を示すはずである.しかし,種々の形態とあるので反応性のほうが推定される.フローサイトメトリーでは細胞形態を見ることなく分析・解析することは非常に危険である.もちろん,フローサイトメトリーだけでは診断されないが診断と直結する場合もあるので注意が必要である.本症例がよい例である.
形態検査結果デジタル処理の臨床応用・5
病理部門におけるシステム化
著者: 國井重男 , 橋本庄太 , 和田大介
ページ範囲:P.1487 - P.1496
はじめに
「形態検査結果デジタル処理の臨床応用シリーズ」の最後である.今回は「病理部門におけるシステム化の進めかた」についてより具体的に紹介する.基本は第2回の「放射線部門におけるシステム化」,本誌9月号に掲載した「システム導入作業工程のポイント」を病理部門に合わせて説明する.
けんさ質問箱Q&A
硬い黄色靱帯の薄切法は
著者: 河原元
ページ範囲:P.1497 - P.1499
組織の硬い黄色靱帯の薄切はどのようにすればよいでしょうか,教えてください.また,脱灰はできないのでしょうか.(福島県郡山市 K. N.生)
■黄色靱帯とは
1 . 解剖学的定義
椎弓間靱帯とも呼ばれ,上方椎弓の下縁前面から起こり,下方椎弓の上縁に着く.前端は関節突起関節包の前面に始まり,後端は正中線で棘間靱帯と結合する1).多量の弾性線維を含むために黄色を呈する.弾性が強いので脊柱の屈伸により棘突起間の距離が変わってもゆるむことはない2).
糖尿病患者の血糖測定と採血時刻の定義は
著者: 石井周一
ページ範囲:P.1499 - P.1500
糖尿病患者さんの採血時刻の定義を教えてください.「食後○時間」時の採血は,時間の起点をどこに置けばよいのでしょうか,食べ始めた時刻でしょうか,食べ終わった時刻でしょうか.食事に長時間かかる人では測定値に影響が出ているのではないでしょうか.「空腹時」とは,例えば8時間眠って起床してから食事直前だけをいうのでしょうか.「食後」とは何時間まで使うのでしょうか.
また,抗凝固剤入り採血管(灰色キャップ)採血とプレイン採血とで血糖値はどこまで相関するのでしょうか.そして,プレイン全血放置と血清放置とで差が出るでしょうか.(北海道富良野市 K. U.生)
コーヒーブレイク
チャールズリバーのほとりで [7]再びの
著者: 坂本秀生
ページ範囲:P.1507 - P.1507
縁があり再びボストンで過ごすことになった.今度はチャールズリバー沿いに建つ日本でいうマンションに暮らし,河面を蝶のように行き交う小型ヨットを目の当たりにする生活が始まった.タイトルどおりにチャールズリバーのほとりでこの原稿を執筆するとは想像していなかったので,一種の驚きでもある.
久しぶりのボストンは相変わらず歴史が漂う街並みに加えて,進化し続けていることを実感している.
基本情報
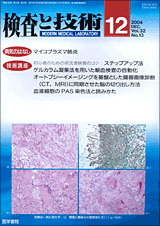
バックナンバー
52巻12号(2024年12月発行)
技術講座 生理
52巻11号(2024年11月発行)
技術講座 生理
52巻10号(2024年10月発行)
技術講座 生理
52巻9号(2024年9月発行)
増大号 臨床医に伝わりやすい 検査報告書とパニック値報告の心得
52巻8号(2024年8月発行)
技術講座 生理
52巻7号(2024年7月発行)
技術講座 生理
52巻6号(2024年6月発行)
技術講座 生理
52巻5号(2024年5月発行)
技術講座 その他
52巻4号(2024年4月発行)
技術講座 生理
52巻3号(2024年3月発行)
増大号 POCUSの決め手。 早く、正確な診断のために
52巻2号(2024年2月発行)
技術講座 生理
52巻1号(2024年1月発行)
技術講座 その他
51巻12号(2023年12月発行)
技術講座 生理
51巻11号(2023年11月発行)
技術講座 生理
51巻10号(2023年10月発行)
技術講座 その他
51巻9号(2023年9月発行)
増大号 匠から学ぶ 血栓止血検査ガイド
51巻8号(2023年8月発行)
技術講座 生理
51巻7号(2023年7月発行)
技術講座 生理
51巻6号(2023年6月発行)
技術講座 生理
51巻5号(2023年5月発行)
技術講座 生理
51巻4号(2023年4月発行)
技術講座 生理
51巻3号(2023年3月発行)
増大号 症例から学ぶ 疾患と検査値の推移
51巻2号(2023年2月発行)
技術講座 その他
51巻1号(2023年1月発行)
技術講座 生理
50巻12号(2022年12月発行)
技術講座 その他
50巻11号(2022年11月発行)
技術講座 生理
50巻10号(2022年10月発行)
技術講座 生理
50巻9号(2022年9月発行)
増大号 希少例と特殊像がわかる! エコーの撮り方完全マスター
50巻8号(2022年8月発行)
技術講座 生理
50巻7号(2022年7月発行)
技術講座 生理
50巻6号(2022年6月発行)
技術講座 生理
50巻5号(2022年5月発行)
技術講座 生理
50巻4号(2022年4月発行)
技術講座 生理
50巻3号(2022年3月発行)
増大号 見て学ぶ 一般検査学アトラス—外観検査から顕微鏡検査まで
50巻2号(2022年2月発行)
技術講座 その他
50巻1号(2022年1月発行)
技術講座 生理
49巻12号(2021年12月発行)
技術講座 生理
49巻11号(2021年11月発行)
技術講座 生理
49巻10号(2021年10月発行)
技術講座 生理
49巻9号(2021年9月発行)
増刊号 病態別 腹部エコーの観察・記録・報告書作成マスター
49巻8号(2021年8月発行)
技術講座 生理
49巻7号(2021年7月発行)
技術講座 生理
49巻6号(2021年6月発行)
技術講座 生理
49巻5号(2021年5月発行)
技術講座 生理
49巻4号(2021年4月発行)
技術講座 一般
49巻3号(2021年3月発行)
増刊号 First&Next Step 微生物検査サポートブック
49巻2号(2021年2月発行)
技術講座 微生物
49巻1号(2021年1月発行)
技術講座 病理・生理
48巻12号(2020年12月発行)
技術講座 その他
48巻11号(2020年11月発行)
技術講座 生化学
48巻10号(2020年10月発行)
技術講座 生理
48巻9号(2020年9月発行)
増刊号 学会発表・論文執筆はもう怖くない! 臨床検査技師のための研究入門
48巻8号(2020年8月発行)
技術講座 遺伝子
48巻7号(2020年7月発行)
技術講座 その他
48巻6号(2020年6月発行)
技術講座 輸血
48巻5号(2020年5月発行)
技術講座 生化学
48巻4号(2020年4月発行)
技術講座 生理
48巻3号(2020年3月発行)
増刊号 採血のすべて—手技から採血室の運用まで徹底解説
48巻2号(2020年2月発行)
技術講座 微生物
48巻1号(2020年1月発行)
技術講座 生理
47巻12号(2019年12月発行)
技術講座 病理
47巻11号(2019年11月発行)
技術講座 生理
47巻10号(2019年10月発行)
技術講座 生理
47巻9号(2019年9月発行)
増刊号 染色画像を比べて学ぶ 体腔液アトラス
47巻8号(2019年8月発行)
技術講座 病理
47巻7号(2019年7月発行)
技術講座 一般
47巻6号(2019年6月発行)
技術講座 血液
47巻5号(2019年5月発行)
技術講座 血液
47巻4号(2019年4月発行)
技術講座 血液
47巻3号(2019年3月発行)
増刊号 エキスパートが教える 心・血管エコー計測のノウハウ
47巻2号(2019年2月発行)
技術講座 病理
47巻1号(2019年1月発行)
技術講座 微生物
46巻12号(2018年12月発行)
技術講座 生理
46巻11号(2018年11月発行)
技術講座 輸血・遺伝子検査
46巻10号(2018年10月発行)
技術講座 その他
46巻9号(2018年9月発行)
増刊号 現場で“パッ”と使える 免疫染色クイックガイド
46巻8号(2018年8月発行)
技術講座 輸血・遺伝子検査
46巻7号(2018年7月発行)
技術講座 生理
46巻6号(2018年6月発行)
技術講座 管理
46巻5号(2018年5月発行)
技術講座 生化学
46巻4号(2018年4月発行)
技術講座 一般
46巻3号(2018年3月発行)
増刊号 感染症クイックリファレンス
46巻2号(2018年2月発行)
技術講座 輸血
46巻1号(2018年1月発行)
技術講座 病理
45巻12号(2017年12月発行)
技術講座 生理
45巻11号(2017年11月発行)
技術講座 一般
45巻10号(2017年10月発行)
技術講座 微生物
45巻9号(2017年9月発行)
増刊号 循環器病院の技師が教える メディカルスタッフのための心電図教室
45巻8号(2017年8月発行)
技術講座 栄養
45巻7号(2017年7月発行)
技術講座 病理
45巻6号(2017年6月発行)
技術講座 病理
45巻5号(2017年5月発行)
技術講座 細胞治療・管理
45巻4号(2017年4月発行)
技術講座 遺伝子・染色体検査
45巻3号(2017年3月発行)
45巻2号(2017年2月発行)
技術講座 細胞治療
45巻1号(2017年1月発行)
技術講座 病理
44巻13号(2016年12月発行)
技術講座 免疫
44巻12号(2016年11月発行)
技術講座 微生物
44巻11号(2016年10月発行)
技術講座 微生物
44巻10号(2016年9月発行)
増刊号 はじめて出会う 検査画像
44巻9号(2016年9月発行)
技術講座 管理・その他
44巻8号(2016年8月発行)
技術講座 微生物
44巻7号(2016年7月発行)
技術講座 生理
44巻6号(2016年6月発行)
技術講座 微生物
44巻5号(2016年5月発行)
技術講座 生理
44巻4号(2016年4月発行)
技術講座 微生物
44巻3号(2016年3月発行)
技術講座 生理
44巻2号(2016年2月発行)
技術講座 微生物
44巻1号(2016年1月発行)
技術講座 微生物
43巻13号(2015年12月発行)
技術講座 生化学
43巻12号(2015年11月発行)
技術講座 生化学
43巻11号(2015年10月発行)
技術講座 一般
43巻10号(2015年9月発行)
増刊号 血液形態アトラス
43巻9号(2015年9月発行)
技術講座 生理
43巻8号(2015年8月発行)
技術講座 生理
43巻7号(2015年7月発行)
技術講座 生理
43巻6号(2015年6月発行)
技術講座 微生物
43巻5号(2015年5月発行)
技術講座 移植医療
43巻4号(2015年4月発行)
技術講座 病理
43巻3号(2015年3月発行)
技術講座 血液
43巻2号(2015年2月発行)
技術講座 管理
43巻1号(2015年1月発行)
技術講座 病理
42巻13号(2014年12月発行)
技術講座 生化学
42巻12号(2014年11月発行)
技術講座 病理
42巻11号(2014年10月発行)
技術講座 血液
42巻10号(2014年9月発行)
増刊号 超音波×病理 対比アトラス
42巻9号(2014年9月発行)
技術講座 生理
42巻8号(2014年8月発行)
技術講座 免疫
42巻7号(2014年7月発行)
技術講座 生理
42巻6号(2014年6月発行)
技術講座 生理
42巻5号(2014年5月発行)
技術講座 病理
42巻4号(2014年4月発行)
技術講座 輸血
42巻3号(2014年3月発行)
技術講座 血液
42巻2号(2014年2月発行)
技術講座 微生物
42巻1号(2014年1月発行)
技術講座 病理
41巻13号(2013年12月発行)
技術講座 生理
41巻12号(2013年11月発行)
技術講座 生化学
41巻11号(2013年10月発行)
技術講座 生化学
41巻10号(2013年9月発行)
増刊号 解剖と正常像がわかる! エコーの撮り方完全マスター
41巻9号(2013年9月発行)
技術講座 微生物
41巻8号(2013年8月発行)
技術講座 生理
41巻7号(2013年7月発行)
技術講座 生理
41巻6号(2013年6月発行)
技術講座 微生物
41巻5号(2013年5月発行)
技術講座 一般
41巻4号(2013年4月発行)
技術講座 生化学
41巻3号(2013年3月発行)
技術講座 生理
41巻2号(2013年2月発行)
技術講座 生理
41巻1号(2013年1月発行)
技術講座 生理
40巻13号(2012年12月発行)
技術講座 血液
40巻12号(2012年11月発行)
技術講座 生理
40巻11号(2012年10月発行)
技術講座 生理
40巻10号(2012年9月発行)
増刊号 この検査データを読めますか?―検査値から病態を探る
40巻9号(2012年9月発行)
技術講座 生理
40巻8号(2012年8月発行)
技術講座 細胞診
40巻7号(2012年7月発行)
技術講座 生理
40巻6号(2012年6月発行)
技術講座 生理
40巻5号(2012年5月発行)
技術講座 生理
40巻4号(2012年4月発行)
技術講座 血液
40巻3号(2012年3月発行)
技術講座 生理
40巻2号(2012年2月発行)
技術講座 輸血
40巻1号(2012年1月発行)
技術講座 遺伝子
39巻13号(2011年12月発行)
疾患と検査値の推移
39巻12号(2011年11月発行)
疾患と検査値の推移
39巻11号(2011年10月発行)
疾患と検査値の推移
39巻10号(2011年9月発行)
増刊号 緊急報告すべき検査結果のすべて―すぐに使えるパニック値事典
39巻9号(2011年9月発行)
疾患と検査値の推移
39巻8号(2011年8月発行)
疾患と検査値の推移
39巻7号(2011年7月発行)
疾患と検査値の推移
39巻6号(2011年6月発行)
技術講座 生理
39巻5号(2011年5月発行)
技術講座 生理
39巻4号(2011年4月発行)
疾患と検査値の推移
39巻3号(2011年3月発行)
疾患と検査値の推移
39巻2号(2011年2月発行)
疾患と検査値の推移
39巻1号(2011年1月発行)
疾患と検査値の推移
38巻13号(2010年12月発行)
疾患と検査値の推移
38巻12号(2010年11月発行)
疾患と検査値の推移
38巻11号(2010年10月発行)
疾患と検査値の推移
38巻10号(2010年9月発行)
増刊号 免疫反応と臨床検査2010
38巻9号(2010年9月発行)
疾患と検査値の推移
38巻8号(2010年8月発行)
疾患と検査値の推移
38巻7号(2010年7月発行)
疾患と検査値の推移
38巻6号(2010年6月発行)
疾患と検査値の推移
38巻5号(2010年5月発行)
疾患と検査値の推移
38巻4号(2010年4月発行)
疾患と検査値の推移
38巻3号(2010年3月発行)
疾患と検査値の推移
38巻2号(2010年2月発行)
疾患と検査値の推移
38巻1号(2010年1月発行)
疾患と検査値の推移
37巻13号(2009年12月発行)
疾患と検査値の推移
37巻12号(2009年11月発行)
疾患と検査値の推移
37巻11号(2009年10月発行)
疾患と検査値の推移
37巻10号(2009年9月発行)
増刊号 顕微鏡検査のコツ―臨床に役立つ形態学
37巻9号(2009年9月発行)
疾患と検査値の推移
37巻8号(2009年8月発行)
疾患と検査値の推移
37巻7号(2009年7月発行)
疾患と検査値の推移
37巻6号(2009年6月発行)
疾患と検査値の推移
37巻5号(2009年5月発行)
疾患と検査値の推移
37巻4号(2009年4月発行)
疾患と検査値の推移
37巻3号(2009年3月発行)
疾患と検査値の推移
37巻2号(2009年2月発行)
疾患と検査値の推移
37巻1号(2009年1月発行)
疾患と検査値の推移
36巻13号(2008年12月発行)
疾患と検査値の推移
36巻12号(2008年11月発行)
疾患と検査値の推移
36巻11号(2008年10月発行)
疾患と検査値の推移
36巻10号(2008年9月発行)
増刊号 これから広がる生理検査・新たにはじまる生理検査
36巻9号(2008年9月発行)
疾患と検査値の推移
36巻8号(2008年8月発行)
疾患と検査値の推移
36巻7号(2008年7月発行)
疾患と検査値の推移
36巻6号(2008年6月発行)
疾患と検査値の推移
36巻5号(2008年5月発行)
疾患と検査値の推移
36巻4号(2008年4月発行)
疾患と検査値の推移
36巻3号(2008年3月発行)
疾患と検査値の推移
36巻2号(2008年2月発行)
疾患と検査値の推移
36巻1号(2008年1月発行)
疾患と検査値の推移
35巻13号(2007年12月発行)
疾患と検査値の推移
35巻12号(2007年11月発行)
疾患と検査値の推移
35巻11号(2007年10月発行)
増刊号 メタボリックシンドローム健診検査技術マニュアル
35巻10号(2007年10月発行)
疾患と検査値の推移
35巻9号(2007年9月発行)
疾患と検査値の推移
35巻8号(2007年8月発行)
疾患と検査値の推移
35巻7号(2007年7月発行)
疾患と検査値の推移
35巻6号(2007年6月発行)
疾患と検査値の推移
35巻5号(2007年5月発行)
疾患と検査値の推移
35巻4号(2007年4月発行)
疾患と検査値の推移
35巻3号(2007年3月発行)
疾患と検査値の推移
35巻2号(2007年2月発行)
疾患と検査値の推移
35巻1号(2007年1月発行)
疾患と検査値の推移
34巻13号(2006年12月発行)
技術講座 生理
34巻12号(2006年11月発行)
技術講座 一般
34巻11号(2006年10月発行)
増刊号 新しい臨床検査・未来の臨床検査
34巻10号(2006年10月発行)
疾患と検査値の推移
34巻9号(2006年9月発行)
疾患と検査値の推移
34巻8号(2006年8月発行)
疾患と検査値の推移
34巻7号(2006年7月発行)
疾患と検査値の推移
34巻6号(2006年6月発行)
疾患と検査値の推移
34巻5号(2006年5月発行)
疾患と検査値の推移
34巻4号(2006年4月発行)
疾患と検査値の推移
34巻3号(2006年3月発行)
疾患と検査値の推移
34巻2号(2006年2月発行)
疾患と検査値の推移
34巻1号(2006年1月発行)
疾患と検査値の推移
33巻13号(2005年12月発行)
疾患と検査値の推移
33巻12号(2005年11月発行)
疾患と検査値の推移
33巻11号(2005年10月発行)
増刊号 一線診療のための臨床検査
33巻10号(2005年10月発行)
疾患と検査値の推移
33巻9号(2005年9月発行)
疾患と検査値の推移
33巻8号(2005年8月発行)
疾患と検査値の推移
33巻7号(2005年7月発行)
疾患と検査値の推移
33巻6号(2005年6月発行)
疾患と検査値の推移
33巻5号(2005年5月発行)
疾患と検査値の推移
33巻4号(2005年4月発行)
疾患と検査値の推移
33巻3号(2005年3月発行)
疾患と検査値の推移
33巻2号(2005年2月発行)
疾患と検査値の推移
33巻1号(2005年1月発行)
疾患と検査値の推移
32巻13号(2004年12月発行)
技術講座 血液
32巻12号(2004年11月発行)
技術講座 病理
32巻11号(2004年10月発行)
技術講座 血液
32巻10号(2004年9月発行)
増刊号 細胞像の見かた―病理・血液・尿沈渣
32巻9号(2004年9月発行)
技術講座 生化学
32巻8号(2004年8月発行)
技術講座 免疫
32巻7号(2004年7月発行)
技術講座 微生物
32巻6号(2004年6月発行)
技術講座 病理
32巻5号(2004年5月発行)
技術講座 病理
32巻4号(2004年4月発行)
技術講座 病理
32巻3号(2004年3月発行)
技術講座 微生物
32巻2号(2004年2月発行)
技術講座 生化学
32巻1号(2004年1月発行)
技術講座 微生物
31巻13号(2003年12月発行)
技術講座 微生物
31巻12号(2003年11月発行)
技術講座 病理
31巻11号(2003年10月発行)
技術講座 微生物
31巻10号(2003年9月発行)
増刊号 包括医療と臨床検査
31巻9号(2003年9月発行)
技術講座 一般
31巻8号(2003年8月発行)
技術講座 微生物
31巻7号(2003年7月発行)
技術講座 病理
31巻6号(2003年6月発行)
技術講座 免疫
31巻5号(2003年5月発行)
技術講座 一般
31巻4号(2003年4月発行)
技術講座 病理
31巻3号(2003年3月発行)
技術講座 生化学
31巻2号(2003年2月発行)
技術講座 免疫
31巻1号(2003年1月発行)
技術講座 免疫
30巻13号(2002年12月発行)
技術講座 生理
30巻12号(2002年11月発行)
技術講座 生理
30巻11号(2002年10月発行)
技術講座 生化学
30巻10号(2002年9月発行)
増刊号 誰でもわかる遺伝子検査
30巻9号(2002年9月発行)
技術講座 微生物
30巻8号(2002年8月発行)
技術講座 生化学
30巻7号(2002年7月発行)
技術講座 微生物
30巻6号(2002年6月発行)
技術講座 生化学
30巻5号(2002年5月発行)
技術講座 微生物
30巻4号(2002年4月発行)
技術講座 一般
30巻3号(2002年3月発行)
技術講座 生化学
30巻2号(2002年2月発行)
技術講座 一般
30巻1号(2002年1月発行)
技術講座 免疫
29巻13号(2001年12月発行)
技術講座 病理
29巻12号(2001年11月発行)
技術講座 生理
29巻11号(2001年10月発行)
技術講座 病理
29巻10号(2001年9月発行)
技術講座 病理
29巻9号(2001年8月発行)
技術講座 病理
29巻8号(2001年7月発行)
技術講座 生理
29巻7号(2001年6月発行)
増刊号 病理組織・細胞診のための日常染色法ガイダンス
29巻6号(2001年6月発行)
技術講座 微生物
29巻5号(2001年5月発行)
技術講座 生理
29巻4号(2001年4月発行)
技術講座 病理
29巻3号(2001年3月発行)
技術講座 微生物
29巻2号(2001年2月発行)
技術講座 微生物
29巻1号(2001年1月発行)
技術講座 一般
28巻13号(2000年12月発行)
技術講座 病理
28巻12号(2000年11月発行)
技術講座 病理
28巻11号(2000年10月発行)
技術講座 免疫
28巻10号(2000年9月発行)
技術講座 微生物
28巻9号(2000年8月発行)
技術講座 微生物
28巻8号(2000年7月発行)
技術講座 生理
28巻7号(2000年6月発行)
増刊号 血液検査実践マニュアル
28巻6号(2000年6月発行)
技術講座 免疫
28巻5号(2000年5月発行)
技術講座 血液
28巻4号(2000年4月発行)
技術講座 一般
28巻3号(2000年3月発行)
技術講座 生理
28巻2号(2000年2月発行)
技術講座 生化学
28巻1号(2000年1月発行)
技術講座 一般
27巻13号(1999年12月発行)
技術講座 病理
27巻12号(1999年11月発行)
技術講座 一般
27巻11号(1999年10月発行)
技術講座 生化学
27巻10号(1999年9月発行)
技術講座 免疫
27巻9号(1999年8月発行)
技術講座 病理
27巻8号(1999年7月発行)
技術講座 病理
27巻7号(1999年6月発行)
増刊号 緊急検査実践マニュアル
27巻6号(1999年6月発行)
技術講座 生化学
27巻5号(1999年5月発行)
技術講座 血液
27巻4号(1999年4月発行)
技術講座 一般
27巻3号(1999年3月発行)
技術講座 生理
27巻2号(1999年2月発行)
技術講座 微生物
27巻1号(1999年1月発行)
技術講座 生理
26巻13号(1998年12月発行)
技術講座 一般
26巻12号(1998年11月発行)
技術講座 病理
26巻11号(1998年10月発行)
技術講座 病理
26巻10号(1998年9月発行)
技術講座 生理
26巻9号(1998年8月発行)
技術講座 生理
26巻8号(1998年7月発行)
技術講座 生理
26巻7号(1998年6月発行)
増刊号 病理組織・細胞診実践マニュアル
26巻6号(1998年6月発行)
技術講座 病理
26巻5号(1998年5月発行)
技術講座 一般
26巻4号(1998年4月発行)
技術講座 病理
26巻3号(1998年3月発行)
技術講座 一般
26巻2号(1998年2月発行)
技術講座 生理
26巻1号(1998年1月発行)
技術講座 血液
25巻13号(1997年12月発行)
技術講座 一般
25巻12号(1997年11月発行)
技術講座 一般
25巻11号(1997年10月発行)
技術講座 生理
25巻10号(1997年9月発行)
技術講座 血液
25巻9号(1997年8月発行)
技術講座 一般
25巻8号(1997年7月発行)
技術講座 一般
25巻7号(1997年6月発行)
増刊号 輸血検査実践マニュアル
25巻6号(1997年6月発行)
技術講座 免疫
25巻5号(1997年5月発行)
技術講座 生理
25巻4号(1997年4月発行)
技術講座 生理
25巻3号(1997年3月発行)
技術講座 微生物
25巻2号(1997年2月発行)
技術講座 生理
25巻1号(1997年1月発行)
技術講座 一般
24巻13号(1996年12月発行)
技術講座 生理
24巻12号(1996年11月発行)
技術講座 一般
24巻11号(1996年10月発行)
技術講座 生理
24巻10号(1996年9月発行)
技術講座 管理
24巻9号(1996年8月発行)
技術講座 生理
24巻8号(1996年7月発行)
技術講座 生理
24巻7号(1996年6月発行)
増刊号 感染症検査実践マニュアル
24巻6号(1996年6月発行)
技術講座 病理
24巻5号(1996年5月発行)
技術講座 生理
24巻4号(1996年4月発行)
技術講座 生理
24巻3号(1996年3月発行)
技術講座 生理
24巻2号(1996年2月発行)
技術講座 生理
24巻1号(1996年1月発行)
技術講座 一般
23巻13号(1995年12月発行)
技術講座 生理
23巻12号(1995年11月発行)
技術講座 病理
23巻11号(1995年10月発行)
技術講座 微生物
23巻10号(1995年9月発行)
技術講座 生理
23巻9号(1995年8月発行)
技術講座 一般
23巻8号(1995年7月発行)
技術講座 免疫
23巻7号(1995年6月発行)
技術講座 生理
23巻6号(1995年5月発行)
技術講座 一般
23巻5号(1995年4月発行)
増刊号 臨床生理検査実践マニュアル画像検査を中心として
23巻4号(1995年4月発行)
技術講座 病理
23巻3号(1995年3月発行)
技術講座 病理
23巻2号(1995年2月発行)
技術講座 一般
23巻1号(1995年1月発行)
技術講座 生理
22巻13号(1994年12月発行)
技術講座 一般
22巻12号(1994年11月発行)
技術講座 一般
22巻11号(1994年10月発行)
技術講座 一般
22巻10号(1994年9月発行)
技術講座 一般
22巻9号(1994年8月発行)
技術講座 生理
22巻8号(1994年7月発行)
技術講座 病理
22巻7号(1994年6月発行)
技術講座 一般
22巻6号(1994年5月発行)
技術講座 一般
22巻5号(1994年4月発行)
増刊号 免疫検査実践マニュアル
22巻4号(1994年4月発行)
技術講座 生理
22巻3号(1994年3月発行)
技術講座 免疫
22巻2号(1994年2月発行)
技術講座 一般
22巻1号(1994年1月発行)
技術講座 生理
21巻13号(1993年12月発行)
技術講座 一般
21巻12号(1993年11月発行)
技術講座 一般
21巻11号(1993年10月発行)
技術講座 一般
21巻10号(1993年9月発行)
技術講座 生理
21巻9号(1993年8月発行)
技術講座 一般
21巻8号(1993年7月発行)
技術講座 病理
21巻7号(1993年6月発行)
技術講座 一般
21巻6号(1993年5月発行)
技術講座 生理
21巻5号(1993年4月発行)
増刊号 臨床化学実践マニュアル
21巻4号(1993年4月発行)
技術講座 生理
21巻3号(1993年3月発行)
技術講座 病理
21巻2号(1993年2月発行)
技術講座 生理
21巻1号(1993年1月発行)
技術講座 生理
20巻13号(1992年12月発行)
技術講座 一般
20巻12号(1992年11月発行)
技術講座 一般
20巻11号(1992年10月発行)
技術講座 一般
20巻10号(1992年9月発行)
技術講座 一般
20巻9号(1992年8月発行)
技術講座 一般
20巻8号(1992年7月発行)
技術講座 血液
20巻7号(1992年6月発行)
技術講座 一般
20巻6号(1992年5月発行)
増刊号 尿検査法
20巻5号(1992年5月発行)
技術講座 生理
20巻4号(1992年4月発行)
技術講座 生理
20巻3号(1992年3月発行)
技術講座 病理
20巻2号(1992年2月発行)
技術講座 一般
20巻1号(1992年1月発行)
技術講座 生理
19巻13号(1991年12月発行)
技術講座 管理
19巻12号(1991年11月発行)
技術講座 生理
19巻11号(1991年10月発行)
技術講座 生理
19巻10号(1991年9月発行)
技術講座 一般
19巻9号(1991年8月発行)
技術講座 一般
19巻8号(1991年7月発行)
技術講座 生理
19巻7号(1991年6月発行)
増刊号 臨床血液検査
19巻6号(1991年6月発行)
技術講座 生理
19巻5号(1991年5月発行)
技術講座 生理
19巻4号(1991年4月発行)
技術講座 一般
19巻3号(1991年3月発行)
技術講座 生理
19巻2号(1991年2月発行)
技術講座 生理
19巻1号(1991年1月発行)
技術講座 一般
18巻13号(1990年12月発行)
技術講座 生理
18巻12号(1990年11月発行)
技術講座 微生物
18巻11号(1990年10月発行)
技術講座 生理
18巻10号(1990年9月発行)
技術講座 一般
18巻9号(1990年8月発行)
技術講座 一般
18巻8号(1990年7月発行)
技術講座 一般
18巻7号(1990年6月発行)
技術講座 一般
18巻6号(1990年5月発行)
増刊号 血液・尿以外の体液検査法
18巻5号(1990年5月発行)
技術講座 一般
18巻4号(1990年4月発行)
技術講座 一般
18巻3号(1990年3月発行)
技術講座 血液
18巻2号(1990年2月発行)
技術講座 生理
18巻1号(1990年1月発行)
技術講座 生理
17巻13号(1989年12月発行)
技術講座 一般
17巻12号(1989年11月発行)
技術講座 一般
17巻11号(1989年10月発行)
技術講座 一般
17巻10号(1989年9月発行)
技術講座 一般
17巻9号(1989年8月発行)
技術講座 生理
17巻8号(1989年7月発行)
技術講座 血清
17巻7号(1989年6月発行)
技術講座 一般
17巻6号(1989年5月発行)
感染症の検査法 Ⅲ 検査法各論
17巻5号(1989年5月発行)
技術講座 一般
17巻4号(1989年4月発行)
技術講座 生理
17巻3号(1989年3月発行)
技術講座 病理
17巻2号(1989年2月発行)
技術講座 一般
17巻1号(1989年1月発行)
技術講座 生理
16巻13号(1988年12月発行)
技術講座 一般
16巻12号(1988年11月発行)
技術講座 一般
16巻11号(1988年10月発行)
技術講座 一般
16巻10号(1988年9月発行)
技術講座 生理
16巻9号(1988年8月発行)
技術講座 一般
16巻8号(1988年7月発行)
技術講座 一般
16巻7号(1988年6月発行)
免疫化学検査法 資料
16巻6号(1988年6月発行)
技術講座 一般
16巻5号(1988年5月発行)
技術講座 一般
16巻4号(1988年4月発行)
技術講座 病理
16巻3号(1988年3月発行)
技術講座 生理
16巻2号(1988年2月発行)
技術講座 一般
16巻1号(1988年1月発行)
技術講座 血液
15巻13号(1987年12月発行)
技術講座 一般
15巻12号(1987年11月発行)
技術講座 病理
15巻11号(1987年10月発行)
技術講座 細胞診
15巻10号(1987年9月発行)
技術講座 一般
15巻9号(1987年8月発行)
技術講座 細胞診
15巻8号(1987年7月発行)
技術講座 病理
15巻7号(1987年6月発行)
技術講座 病理
15巻6号(1987年5月発行)
技術講座 病理
15巻5号(1987年4月発行)
臨床生理検査と技術 座談会
15巻4号(1987年4月発行)
技術講座 生理
15巻3号(1987年3月発行)
技術講座 血液
15巻2号(1987年2月発行)
技術講座 一般
15巻1号(1987年1月発行)
技術講座 病理
14巻13号(1986年12月発行)
技術講座 一般
14巻12号(1986年11月発行)
技術講座 病理
14巻11号(1986年10月発行)
技術講座 血清
14巻10号(1986年9月発行)
技術講座 血清
14巻9号(1986年8月発行)
技術講座 生理
14巻8号(1986年7月発行)
技術講座 血清
14巻7号(1986年6月発行)
技術講座 病理
14巻6号(1986年5月発行)
技術講座 生理
14巻5号(1986年4月発行)
形態学的検査と技術 血液と病理
14巻4号(1986年4月発行)
技術講座 病理
14巻3号(1986年3月発行)
技術講座 細菌
14巻2号(1986年2月発行)
技術講座 病理
14巻1号(1986年1月発行)
技術講座 細菌
13巻12号(1985年12月発行)
技術講座 病理
13巻11号(1985年11月発行)
技術講座 病理
13巻10号(1985年10月発行)
技術講座 生理
13巻9号(1985年9月発行)
技術講座 病理
13巻8号(1985年8月発行)
技術講座 病理
13巻7号(1985年7月発行)
技術講座 血液
13巻6号(1985年6月発行)
技術講座 一般
13巻5号(1985年5月発行)
技術講座 病理
13巻4号(1985年4月発行)
技術講座 一般
13巻3号(1985年3月発行)
技術講座 血液
13巻2号(1985年2月発行)
技術講座 一般
13巻1号(1985年1月発行)
技術講座 血液
12巻12号(1984年12月発行)
技術講座 血液
12巻11号(1984年11月発行)
技術講座 病理
12巻10号(1984年10月発行)
技術講座 輸血
12巻9号(1984年9月発行)
技術講座 一般
12巻8号(1984年8月発行)
技術講座 細菌
12巻7号(1984年7月発行)
技術講座 細菌
12巻6号(1984年6月発行)
技術講座 生理
12巻5号(1984年5月発行)
技術講座 一般
12巻4号(1984年4月発行)
技術講座 病理
12巻3号(1984年3月発行)
技術講座 血液
12巻2号(1984年2月発行)
技術講座 一般
12巻1号(1983年12月発行)
技術講座 血清
11巻12号(1983年12月発行)
技術講座 一般
11巻11号(1983年11月発行)
技術講座 細菌
11巻10号(1983年10月発行)
技術講座 細胞診
11巻9号(1983年9月発行)
技術講座 一般
11巻8号(1983年8月発行)
技術講座 血清
11巻7号(1983年7月発行)
技術講座 細菌
11巻6号(1983年6月発行)
技術講座 一般
11巻5号(1983年5月発行)
技術講座 病理
11巻4号(1983年4月発行)
技術講座 一般
11巻3号(1983年3月発行)
技術講座 血液
11巻2号(1983年2月発行)
技術講座 一般
11巻1号(1983年1月発行)
技術講座 血液
10巻12号(1982年12月発行)
技術講座 一般
10巻11号(1982年11月発行)
技術講座 生理
10巻10号(1982年10月発行)
技術講座 血清
10巻9号(1982年9月発行)
技術講座 細菌
10巻8号(1982年8月発行)
技術講座 一般
10巻7号(1982年7月発行)
技術講座 病理
10巻6号(1982年6月発行)
技術講座 細菌
10巻5号(1982年5月発行)
技術講座 病理
10巻4号(1982年4月発行)
技術講座 血清
10巻3号(1982年3月発行)
技術講座 生化学
10巻2号(1982年2月発行)
技術講座 病理
10巻1号(1982年1月発行)
技術講座 生化学
9巻12号(1981年12月発行)
技術講座 細菌
9巻11号(1981年11月発行)
技術講座 生理
9巻10号(1981年10月発行)
技術講座 一般
9巻9号(1981年9月発行)
技術講座 血清
9巻8号(1981年8月発行)
技術講座 血清
9巻7号(1981年7月発行)
技術講座 生理
9巻6号(1981年6月発行)
技術講座 細菌
9巻5号(1981年5月発行)
技術講座 一般
9巻4号(1981年4月発行)
技術講座 一般
9巻3号(1981年3月発行)
技術講座 血清
9巻2号(1981年2月発行)
技術講座 一般
9巻1号(1981年1月発行)
技術講座 生化学
8巻12号(1980年12月発行)
技術講座 一般
8巻11号(1980年11月発行)
技術講座 生理
8巻10号(1980年10月発行)
技術講座 検体の取り扱いと保存
8巻9号(1980年9月発行)
技術講座 病理
8巻8号(1980年8月発行)
技術講座 生化学
8巻7号(1980年7月発行)
技術講座 一般
8巻6号(1980年6月発行)
技術講座 生理
8巻5号(1980年5月発行)
技術講座 生化学
8巻4号(1980年4月発行)
技術講座 血清
8巻3号(1980年3月発行)
技術講座 病理
8巻2号(1980年2月発行)
技術講座 一般
8巻1号(1980年1月発行)
技術講座 生化学
7巻12号(1979年12月発行)
技術講座 一般
7巻11号(1979年11月発行)
技術講座 一般
7巻10号(1979年10月発行)
技術講座 細菌
7巻9号(1979年9月発行)
技術講座 生理
7巻8号(1979年8月発行)
技術講座 病理
7巻7号(1979年7月発行)
技術講座 生理
7巻6号(1979年6月発行)
技術講座 一般
7巻5号(1979年5月発行)
技術講座 血液
7巻4号(1979年4月発行)
技術講座 生理
7巻3号(1979年3月発行)
技術講座 病理
7巻2号(1979年2月発行)
技術講座 細菌
7巻1号(1979年1月発行)
技術講座 生化学
6巻12号(1978年12月発行)
技術講座 細菌
6巻11号(1978年11月発行)
技術講座 病理
6巻10号(1978年10月発行)
技術講座 血清
6巻9号(1978年9月発行)
技術講座 細菌
6巻8号(1978年8月発行)
技術講座 生化学
6巻7号(1978年7月発行)
技術講座 一般
6巻6号(1978年6月発行)
技術講座 病理
6巻5号(1978年5月発行)
技術講座 生理
6巻4号(1978年4月発行)
技術講座 一般
6巻3号(1978年3月発行)
技術講座 病理
6巻2号(1978年2月発行)
技術講座 一般
6巻1号(1978年1月発行)
技術講座 病理
5巻12号(1977年12月発行)
技術講座 生理
5巻11号(1977年11月発行)
技術講座 一般
5巻10号(1977年10月発行)
技術講座 細菌付録
5巻9号(1977年9月発行)
技術講座 一般
5巻8号(1977年8月発行)
技術講座 生理
5巻7号(1977年7月発行)
技術講座 一般
5巻6号(1977年6月発行)
技術講座 一般
5巻5号(1977年5月発行)
技術講座 一般
5巻4号(1977年4月発行)
技術講座 一般
5巻3号(1977年3月発行)
技術講座 一般
5巻2号(1977年2月発行)
技術講座 一般
5巻1号(1977年1月発行)
技術講座 一般
4巻12号(1976年12月発行)
技術講座 一般
4巻11号(1976年11月発行)
技術講座 一般
4巻10号(1976年10月発行)
技術講座 一般
4巻9号(1976年9月発行)
技術講座 一般
4巻8号(1976年8月発行)
技術講座 一般
4巻7号(1976年7月発行)
技術講座 一般
4巻6号(1976年6月発行)
技術講座 一般
4巻5号(1976年5月発行)
技術講座 一般
4巻4号(1976年4月発行)
技術講座 一般
4巻3号(1976年3月発行)
技術講座 一般
4巻2号(1976年2月発行)
技術講座 一般
4巻1号(1976年1月発行)
技術講座 一般
3巻12号(1975年12月発行)
技術講座 一般
3巻11号(1975年11月発行)
技術講座 一般
3巻10号(1975年10月発行)
技術講座 一般
3巻9号(1975年9月発行)
技術講座 一般
3巻7号(1975年8月発行)
特集 必修 日常検査の実技
3巻6号(1975年6月発行)
技術講座 生理
3巻5号(1975年5月発行)
技術講座 一般
3巻4号(1975年4月発行)
技術講座 一般
3巻3号(1975年3月発行)
技術講座 一般
3巻2号(1975年2月発行)
技術講座 一般
3巻1号(1975年1月発行)
技術講座 一般
