新しい知見
劇症1型糖尿病は2000年に筆者らが最初に報告した1型糖尿病に属する新しいサブタイプ(亜型)である1).本疾患は,ケトーシスを伴って発症する日本人1型糖尿病の15~20%を占め,糖尿病関連抗体陰性,ケトアシドーシスを伴って非常に急激に発症,発症時に著明な高血糖を認めるにもかかわらず,HbA1cは正常または軽度上昇,発症時に既に内因性インスリン分泌は枯渇といった特徴を有する疾患である.非常に急激に発症し,激烈な症状を示すことから,この名前が付けられた.インスリンを分泌する膵β細胞が破壊されることにより発症し,インスリン注射による治療が必須である.
雑誌目次
検査と技術33巻13号
2005年12月発行
雑誌目次
病気のはなし
劇症1型糖尿病
著者: 今川彰久 , 花房俊昭
ページ範囲:P.1446 - P.1449
技術講座 微生物
淋菌の感受性検査
著者: 村谷哲郎 , 松本哲朗
ページ範囲:P.1451 - P.1457
新しい知見
キノロン耐性株出現後の淋菌経口治療の切り札であった第三世代経口セフェムは,現在でも日本以外では耐性株がほとんど報告されていない.しかし,われわれは1999年5月に第三世代経口セフェムであるセフジニル(cefdinir)を使用したにもかかわらず無効であった症例を経験し,その翌月には,アズトレオナム(aztreonam)静注を行い無効であった症例を経験した1).これら2症例を経験した後,このような耐性淋菌は急速に広がり,現在わが国では4%に達している.その耐性機序はPBP-2の遺伝子penAの大部分が他のNeisseria属の遺伝子とキメラ化を起こしていることにある.これらと同様の薬剤感受性を示す株は,ハワイで4例報告されている2)だけであり,日本特有の耐性株である.
輸血
輸血と感染症マーカー
著者: 押田眞知子 , 鍵田正智
ページ範囲:P.1459 - P.1463
新しい知見
輸血による感染性副作用を防止するために献血者のB型およびC型肝炎ウイルス,ヒト免疫不全ウイルス(human immunodeficiency virus,HIV)について血清学的検査が陰性の場合は核酸増幅検査(nucleic acid amplification test,NAT)が実施されている.しかしながら,献血者が感染初期のウインドウピリオドである場合は検査で検出できず,輸血後に感染症を発症する場合がある.このような事実から2004年7月に厚生労働省から「輸血医療の安全性確保のための総合対策報告書」が示され,「輸血療法の実施に関する指針」1)が改正2)され,医療機関において輸血前後のB型肝炎,C型肝炎,HIV検査を実施することが求められた.そして2005年9月に「血液製剤遡及調査ガイドライン」3)を踏まえて「血液製剤の実施に関する指針」4)が改定された.
一般
血尿における尿検査の考えかた―尿中赤血球形態の見かた
著者: 油野友二
ページ範囲:P.1465 - P.1469
新しい知見
尿中赤血球形態は血尿の原因鑑別の情報として有用である.JCCLS尿沈渣作業部会は本年,現状の尿沈渣検査法指針GP1-P3における尿中赤血球形態の判定基準に関する改定試案をとりまとめた.
疾患と検査値の推移
糖尿病腎不全と血液透析
著者: 原茂子
ページ範囲:P.1475 - P.1481
はじめに
腎機能が高度に障害された状態は腎不全と呼称され,進展すると尿毒症となり自己腎では生命維持が困難で代替療法が必要となる.腎不全には経過から急性腎不全と慢性腎不全とに分けられ,急性腎不全では,透析療法が必要となることがあっても腎機能が回復し離脱しうる.一方,慢性腎不全では代替療法として腎移植や透析療法が必要となる.わが国では腎移植の普及は困難で透析療法が主体である.
透析療法はダイアライザーを使用する血液透析療法か自己の腹膜を用いる持続携行式腹膜透析療法かのいずれかで治療される.近年糖尿病罹患者の増加に伴い,糖尿病腎症による腎不全から透析導入を要する例の増加が著しい.
本稿では糖尿病慢性腎不全の血液透析療法による検査の意義と推移とについて述べる.
オピニオン
イギリスにおける上級CT制度を考える
著者: 小林忠男
ページ範囲:P.1450 - P.1450
はじめに
イギリスの医療制度がかつての「揺りかごから墓場まで」を掲げる理想の国から大きくずれが生じてきていることは,意外と知られていない.すなわち,各国の医療費の国内総生産(gross domestic product,GDP)比からみると先進7か国のうち,イギリスは医療費が最下位の第7位で,日本は第6位に位置している.イギリスの一部の医療制度をお手本とした日本の医療改革が疑問視されているのもここに一つの原因があるといわれている.また,2000年に5年かけて医療費を1.5倍に増やす政策の結果がそろそろ出るらしい.もしこれが成功したならば日本は多分,医療費で先進7か国中,最下位になるともいわれている.一方,イギリスの医療従事者,特に医師やナースの不足は深刻なものがある.国際学会などでよくNHS(National Health Service,国民保健サービス)から「イギリスで医師として働きませんか」などの呼びかけパンフレットや景品などが配布されているのをよく目にする.さらに,イギリスのナースの多くが外国人である話も「出稼ぎフィリピン人ナース」(地域によってはや7割がフィリピン人看護師)としてあまりにも有名である.しかし,ナース同様にイギリスから流出する医師などの影響によって,国内の医師不足も深刻で,特に細胞診の専門医の不足も例外でなく問題となっている.
絵で見る免疫学 基礎編72
IgEを介したアレルギー反応 3.アレルギー疾患とTH1とTH2のバランス
著者: 高木淳 , 玉井一
ページ範囲:P.1470 - P.1471
TH1細胞への誘導と自然免疫系
アレルギー疾患の病態は個体が全体としてTH2優位の状態にあり,TH1側への誘導がうまく行われていない状態にあると考えられている.侵入した病原体に最初に接触するマクロファージや樹状細胞のTLR(Toll-like receptor),特にTLR2,4は病原体のリポ蛋白質やLPSなどのパターンを認識しIL(interleukin)-12を産生し主にTH1細胞を活性化し個体の免疫系をTH1側へと誘導する(図1).感染初期に駆動する自然免疫系の応答はTH1細胞の分化・誘導に重要であることがわかってきた(33巻9号832-833頁参照).
TH1と TH2分化への要因
アレルギー疾患や自己免疫疾患など多くの疾患がTH1/TH2のバランスの崩れに起因することがわかってきた.TH1またはTH2を活性化する因子を表に示す.特に最近の清潔な環境がTH1/TH2バランスを破綻しアレルギー疾患を増加させている原因の一つであるとする考えが支持されてきた.特に幼児期における結核菌など微生物への感染頻度の減少がTH1反応を低下させTH2反応を優位に誘導していると考えられている.結核菌の抽出抗原に対するツベルクリン反応はTH1細胞による遅延型反応であり,陽性反応はTH1反応が強く誘導されたことを示す.そして,ツベルクリン反応陽性者は陰性者に対してアレルギー疾患率,IgE反応性やTH2細胞が産生するサイトカイン(IL-4,IL-10,IL-13)のレベルが優位に低く,逆にTH1細胞が産生するサイトカインであるIFN(interferon)-γの有意の上昇が見られる.最近の抗菌剤の使用もTH1反応を弱めTH1/TH2バランスを崩すとの考えも支持されている.2歳までの抗生物質の経口投与歴がアレルギー疾患率を高めているとの報告がある.これは,抗生物質の経口投与は腸内細菌フローラを破壊するからであり,乳酸菌,ビフィズス菌の重要性もわかってきた(表).また,抗原提示細胞が提示する抗原ペプチドの量とアミノ酸配列がTH1とTH2の分化に影響を与える.抗原提示細胞上に多量のペプチドが高密度で提示されるとTH1に,少量のペプチドが低い密度で提示された場合はTH2に誘導される傾向がある.また,アミノ酸配列によりTCR(T-cell receptor,T細胞受容体)に強く結合するペプチドはTH1への分化を,弱く結合する場合はTH2に誘導する傾向がある(33巻10号922-923頁参照)(図2).
ワンポイントアドバイス
―ISO15189認定登録のポイント・4 第4回―ISO15189認定登録に必要なこと(その3)(全5回)
著者: 苅谷文雄
ページ範囲:P.1494 - P.1496
ISO15189では,検査サービスの質を確保するために,要員に対していろいろな機会を捉えて教育訓練が行われ力量の確保の努力がなされるだけではなく,これらを客観的に証明することが重要になる.
今回は,この要員の力量を管理し,かつ証明するための具体的な方法について説明する.
けんさアラカルト
異常値となるメカニズム 6.HBs抗原およびHBe抗原ELISA法での非特異反応
著者: 北橋繁
ページ範囲:P.1526 - P.1527
はじめに
日頃,日常検査上で非特異反応を経験することは稀ではあるが,原因検索まで検討し試薬改良することは皆無である.また,何か変なデータだなと思うことがあっても再測定や精度管理上問題がなければ,そのまま結果報告することが多いと思われる.今回紹介する症例に関しても最初は,詳細な検討もせずに非特異反応例と判断したものである.異常と感ずることができる背景には,日常,何を異常な結果と考えるかがある.生体内の濃度として考えられない測定値,測定機器からの警告,他の検査結果との乖離,臨床状態との不一致による医師からの問い合わせなどで異常の存在に気付く.特に,ブラックボックス化した自動分析装置からの測定値に含まれている意味を十分に理解していることと,臨床とのコミュニケーションとが大切である.本稿では,血液疾患でHBs抗原(Ag)およびHBe抗原の測定において非特異反応の原因を検討し,試薬の改良を経験したので紹介する1).
今月の表紙
百聞は一見に如かず・24 50歳以上の男性は高齢者?
著者: 松谷章司
ページ範囲:P.1458 - P.1458
前立腺は胡桃大で膀胱の直下に位置している.いわゆる「前立腺肥大症」というものは病理学的には前立腺の過形成である.これは尿道近くの内腺領域に発生するので排尿障害が出やすい.これに対し,癌の多くは外側の外腺領域に好発する.日本人の前立腺癌発症頻度はアメリカの約1/10で,死亡患者数はアメリカの約1/4といわれる.近年,高齢者の増加,動物性脂肪(肉類,ミルクなど)の摂取増加に伴い発症率が著増していて,2015年には1995年の約3倍になると推定されている.前立腺癌は他の癌に比べて成長速度が遅いとはいえ,5年生存率は診断時の病期と関連し,前立腺内に限局している場合は70~90%,前立腺周囲に拡がっている場合は50~70%,リンパ節転移がある場合は30~50%,骨や肺などに遠隔転移がある場合では20~30%と言われる(国立がんセンターの資料より).
早期診断には前立腺特異抗原(prostate specific antigen,PSA:分子量33,000の糖蛋白質,kinin-karllikrein familyに属するserine protease)の測定が重要である.これは前立腺分泌液の中に含まれており,一部が血中に出現するので,産生や放出が多いと検査値に反映される.前立腺肥大症や前立腺炎などでも上昇する.一方,前立腺摘除術後は消失するので,再発の早期発見にも有用である.一般に4ng/ml以上になると癌の可能性が高くなる.ところが,安心できない調査結果がアメリカから出された.つまり,PSAの値が3.0ng/ml以下の55歳以上の健康男性を7年間追跡し,PSAの値が4.0ng/ml以下の男性に前立腺生検をしたところ,5,587人中1,225人に癌を発見したというデータである.分析結果から4.0ng/mlを基準とした際,前立腺癌患者の20.5%しか発見できないことがわかった.この癌の中に早期の癌も含まれると思われるが,正常値といっても安心できないのである.確定診断には,通常左右ぞれぞれ6か所前後の前立腺針生検の病理組織診断が必要になる.これにより,癌の有無と癌の異型度を評価する.手術摘出前立腺では,癌の浸潤範囲(病期)とを判定する.前立腺癌の悪性度を評価するのに,グリーソン分類(Gleason grade;最低2~最高10;数字が大きいほど悪性度が高く,癌が転移する確率も高くなる)が用いられている.7以上の癌では,15年以内の死亡率が80%に達するといわれる.
Laboratory Practice 生理 超音波像の読みかた
頸動脈疾患
著者: 長束一行
ページ範囲:P.1482 - P.1487
はじめに
わが国では従来,頸動脈病変が少ないとされてきたが,生活の欧米化に伴い生活習慣病が増え,頸動脈の粥状硬化病変も増えつつある.頸動脈は最も体表に近い動脈の一つで粥状硬化の好発部位でもある.
頸動脈の超音波エコーは手軽に検査を行え,脳血管障害の診断にも必須であるが,全身の動脈硬化を知るうえでの指標としても注目されている.頸動脈エコー検査は微細な病変から高度な病変まで,簡便で無侵襲的に頸動脈病変を診断でき,頸動脈病変を診断する場合の第一選択の検査となっている.
生化学 自動分析装置での検査データの質を上げるためのポイント
新しい担当者へのメンテナンスのトレーニング
著者: 白井秀明
ページ範囲:P.1488 - P.1491
はじめに
自動分析装置の保守(メンテナンス)は,安定な状態で分析を維持することを目的としている.自動分析装置のメンテナンスは,大別すると装置のメンテナンスとデータのメンテナンスとに分けることができる.装置のメンテナンスは,各パーツの清掃(洗浄),交換や光学系(セルブランクや光量チェック)などの管理が主な作業である.一方,データのメンテナンスは,試薬の管理,管理試料データの管理やキャリブレーションの管理が主な作業となる.
これらのメンテナンス作業は,分析装置を扱った経験者にとっては繁雑な作業ではないが,新人や分析装置になれていない方にはやっかいな作業である.個々のメンテナンスの方法や異常データの取り扱いかたについては,本シリーズで詳しく述べてあるので,ここでは新しい担当者に早く技術を身に付けられるトレーニング方法を紹介する.
検査室の安全管理・9
電気設備の安全管理・その2 臨床検査における電気設備と医用電気機器
著者: 山本誠一
ページ範囲:P.1497 - P.1500
はじめに
臨床検査で使用する医用電気機器(ME機器)および電気設備は日本工業規格〔JIS T0601-1 医用電気機器―第1部:安全に関する一般的要求事項(1999年改定)とJIS T1022 病院電気設備の安全基準(1996年)〕に定められている.JIS T0601-1は国際規格であるIEC 6060-1を翻訳したものである.この規格に合った電気設備と医用電気機器とを設置し,機器操作マニュアルに沿って正しく使用することが大切である.
臨床検査は生理機能(生体)検査と検体検査とに大別される.生理機能検査は患者にME機器の電極などを直接取り付けて検査するので,特に,電撃(電気ショック)事故防止が大切である.その他の問題として,静電気,磁気,携帯電話の電波によるME機器の誤動作などがある.一方,検体検査では,検者の電撃事故防止,電気による引火爆発,火災などがある.また,共通したものとして停電による影響も大きい.これらの問題と対策とについて解説する.
トピックス
ES細胞の未来
著者: 下里大輔 , 丹羽仁史
ページ範囲:P.1533 - P.1536
はじめに
胚性幹細胞(ES細胞:embryonic stem cell)とは,①初期発生過程の胚に由来する,②多能性の,③幹細胞株,と定義される.ES細胞は胚盤胞と呼ばれる着床直前の胚の内部細胞塊(inner cell mass,ICM)をin vitroで増殖可能にした細胞株であり,三胚葉(外胚葉・中胚葉・内胚葉)それぞれに属する少なくとも1種の細胞に分化できる多能性と,自分と同じ分化能を持つ細胞を生み出す「自己複製能」とを併せ持つ細胞である1).1998年のヒトES細胞樹立の報告により2),現在「再生医療への応用」という形で注目されている.
輸血関連急性肺障害
著者: 岡崎仁
ページ範囲:P.1536 - P.1539
はじめに
輸血関連急性肺障害(transfusion related acute lung injury,TRALI)は,比較的稀な非溶血性輸血副作用である.近年,輸血の安全性がかなり向上してきたことを反映して,重篤な副作用として注目され始めた.TRALIは輸血開始後数時間で起こる非心原性の急激な肺水腫(胸部X線上では両側肺浸潤影)による呼吸困難と低酸素血症を呈することで特徴づけられる病態である.1950年代より症例の報告はあったが,1983年にPopovskyらによりTRALIの呼称が提唱され,1985年に彼らの36例の症例報告により,独立した一つの病態として認識されるようになった1~3).
TRALIの典型的症状および臨床所見としては急性の呼吸困難,重篤な低酸素血症,血圧低下,発熱,そのほかにも多呼吸,チアノーゼ,胸部聴診上湿性ラ音などがある.これらの症状は輸血中もしくは輸血後数時間以内に発生し,通常は一過性であり,早期発見と適切な酸素療法,呼吸補助療法により回復することが多いとされている.呼吸困難を呈する他の病態との鑑別も重要であり,輸血関連循環過負荷(transfusion associated circulatory overload,TACO),輸血以外の原因による心不全,アナフィラキシーショック,汚染された血液製剤による細菌感染などを念頭に置き鑑別診断をしなければならない.
TRALIの発症頻度は輸血血液1単位当たり0.014~0.08%といわれており,死亡率は十数%とされている4~6).しかしTRALIの診断基準が報告により異なっているために正確な頻度についてははっきりとしない.米国では過去三年間における輸血関連死亡のうちTRALIは一番の原因となっている.米国FDA(Food and Drug Administration,食品医薬品局)への報告は輸血関連死亡の場合のみであり,TRALIの発生頻度や死亡率に関するデータはないが,死亡率から考えると,致死的でないものを含め実際の発生数はかなり多いと思われる7).英国では最新のSHOT(Serious Hazard of Transfusion)の報告によると1996年から2003年の過去8年間に139例のTRALIが報告され,32例が死亡している8).フランスでは2003年には15例のTRALI報告例のうち3例が死亡している9).病態の認識の高まりとともに今後症例報告が増える可能性はある.
2004年の4月にカナダのトロントでTowards an understanding of TRALI,Consensus Conferenceが開催され,統一したTRALIの診断基準の提唱がなされた.この診断基準は1994年に提唱されたThe American-European Consensus Conference on ARDSの定義との整合性を持たせて作成されており,TRALIの診断基準の推奨案として2004年の12月のTransfusionに発表された.推奨された診断基準を表に示す10).NHLBI(National Heart, Lung and Blood Institute)からも診断基準が提唱されているが,基本的な部分に関しては同じである11).
TRALIの病因については現在までに二つの異なった案が提唱されている.一つは免疫学的機序によるもので,もう一つは非免疫学的機序によるものである.
免疫学的機序によるものはなんらかの抗原抗体反応が肺障害を引き起こしているという仮説である.ドナー由来の抗白血球抗体もしくは患者がもともと持っている抗白血球抗体が原因となり,それぞれ,患者白血球もしくは製剤中に残存している白血球との相互作用により,白血球の活性化が起こり,補体の活性化,肺毛細血管への付着およびその傷害,血管透過性の亢進などを惹起し,非心原性の肺水腫を起こすという説である.
Popovskyらの報告では,89%の症例においてドナーに抗白血球抗体を見いだしている3).抗好中球抗体と抗HLA class I 抗体とが原因として提唱されたが,すべてのケースで特異性が一致したわけではなかった.抗HLA class I 抗体の関与するTRALI症例については1970年頃より報告があり,抗好中球抗体に関しても今までに抗HNA-1a,-1b,-2a,-3a抗体によるTRALIが報告されている12).1999年にKopkoらは抗HLA class II 抗体によるTRALIの発症を報告し,その後相次いで抗HLA class II 抗体によるTRALIの報告がなされている5,13~16).単球(Monocyte)に対する抗体もTRALI症例で見いだされている17).患者側に抗体が見いだされたTRALIのケースも少数であるが報告されている.さらに片肺移植10週間後の患者で抗HLA-B44抗体陽性の血液を輸血され,HLA class I (B44)が一致した移植肺のみにTRALIを発症したという報告もあり,血球系以外の細胞と抗体との反応でもTRALIが起こる可能性を示唆している18).また,二人以上のドナーからの輸血を受けた患者がドナーの血液間の抗原抗体反応による免疫複合体の形成によりTRALIを起こした可能性がある例も報告されている19).このように免疫学的機序にもさまざまな抗原抗体反応がかかわっていると推定され,いまだ認識されていない抗体が誘因となっている可能性もある.Grimmingerらの報告では抗5b抗体〔抗HNA(human neutrophil antigen)-3a抗体〕を用い,顆粒球と肺動脈血管内皮細胞との共培養でロイコトリエン(leukotriene)C4などの血管透過性を亢進する物質が放出されることを見いだしている20).また,Nishimuraらは抗HLA-class II 抗体と可溶性HLA抗原とにより形成されるimmune complexが顆粒球と肺毛細血管内皮細胞との共培養で内皮細胞の傷害を起こすことを示している21).さらにKopkoらは抗5b抗体が顆粒球のprimingに関与していることを示している22).このようにいくつかの知見が得られているが,発症の詳細な機序に関してはっきりとした答えは出ていない.
免疫学的機序による動物モデルも作成されており,Seegerらによるex vivoのrabbit lungを用いた抗5b抗体(抗HNA-3a抗体)と5b陽性の白血球を用いた系とではrabbit plasmaの存在下に肺水腫モデルを作成している23).またBuxらはrat lungを用い,マウスモノクローナル抗HNA-2a抗体とHNA-2a陽性率70%以上の白血球とを灌流することにより肺水腫を生じさせている24).SusskindらはBALB/c mouseを用い,mouse MHC class I mAbのinjectionによりTRALI様の病態を生じさせている25).
ヒトでのTRALIを目的とした検討ではないが,新生児の溶血性疾患の治療のために有用と思われている抗HLA抗体,抗単球抗体を健常者に投与しその効果をみる実験で,予期しなかった副作用としてTRALIが発症した事例が報告されている.これは抗体だけで健常者にもTRALIが発症することを示唆しており,抗体説を支持するものと考えられる26,27).
非免疫学的機序によるものは,Sillimanらのグループにより主に提唱されているのだが,TRALI症例の病因として,患者の状態(例えば,感染症,直近の手術,サイトカインの投与,大量の輸血,炎症など)と,製剤のなかに蓄積される活性脂質の存在が重要であるという説である28).この仮説の動物モデルとしては,保存された赤血球と血小板製剤とをLPS(lipopolysaccharide,リポ多糖)投与後にratの肺に灌流すると肺障害が起きるというものである.保存された血液製剤中のlysophosphatidylcholine(リソホスファチジルコリン,lyso-PC)が,活性物質であるとしている29,30).
in vitroのモデルでは,肺毛細血管内皮細胞を用いた好中球との共培養実験系で,肺血管の障害にはLPSとlyso-PCとによる好中球の活性化と,肺血管内皮細胞の活性化が関与するとしている31).
非免疫学的機序を支持する根拠としては,Sillimanらの90例のTRALIについての報告がある.4年間に一つの病院で90例のTRALI症例を集積しており,その頻度は1:1,120であった.抗白血球抗体検出率は25%であり,特異性が確認できたのは3.6%にすぎなかった6).
副作用自発報告に基づく日本赤十字社への報告のなかで,TRALIが疑われる症例は1997年よりこの病態が臨床的に認識されるようになるとともに増えてきており,最近では年間約30例程度の報告がある.診断基準が最近まで統一されていなかったため,表の診断基準に基づき,TRALI,possible TRALIに分けて見直し,2004年までの8年間に99例のTRALI, 27例のpossible TRALIを診断した.
どうする?パニック値 生化学
6.血中K濃度異常値
著者: 阿部雅紀 , 海津嘉蔵
ページ範囲:P.1492 - P.1493
カリウムは細胞内の主なイオンで,体内の総K量の90%が細胞内にあり,血清中のKは0.4%にすぎない.細胞内K濃度は約150mEq/l,細胞外液は約4mEq/lである.細胞内外で約40倍近いKの濃度差によって細胞膜静止電位が生じており,細胞の脱分極・過分極などの興奮性を調節する.K欠乏状態では,筋脱力や麻痺が生じ,尿濃縮力障害が生じる.高K状態では脱力感や四肢のしびれ感のほか,心毒性があり,心室細動から心停止をきたすため緊急を要する.
加齢による変動は乳幼児でやや高値となるが,それ以降はほぼ一定で変動しない.また性差は認められない.
検査じょうほう室 血液:自動血球分析装置のフラッグ処理で困ったこと
血小板フラッグで困ったこと
著者: 原田佳代子 , 有村義輝 , 三島正輝
ページ範囲:P.1508 - P.1511
はじめに
近年,自動血球計数装置の精度・性能はめざましく向上し,血球計算に加えて白血球5分類,網赤血球測定なども同時測定できる装置が主流となっています.鹿児島市医師会臨床検査センターでは,Sysmex XE-2100を使用しており,分析装置の信頼性に加えて,その機種の特性を踏まえたうえでさまざまなIPメッセージ(インタープリティブメッセージ)を基にデータ解析を行っています.
今回は,血小板凝集をテーマに述べます.血小板減少には,病的なもののほかに,抗凝固剤,特にEDTA(ethylenediaminetetraacetic acid,エチレンジアミン四酢酸)加採血時にみられるEDTA依存性血小板減少症があります.両者の判別を早く正確に行うことは,その後の検査や診断に大きな影響を与えます.
血小板凝集の有無判定については,分析装置のフラッグや前回値比較などを基にして判断しますが,場合によってはフォニオ法(Fonio method)や血液塗抹標本で凝集の有無確認を行っています.検査センターのように大量検体を扱う施設や検査技師の作業効率化を考えるうえでは,極力手作業による処理は軽減したいものです.
生理:超音波検査のステップアップ
虚血性心疾患
著者: 片貝佳代
ページ範囲:P.1512 - P.1516
虚血性心疾患の病態
虚血性心疾患は,心筋への酸素の供給が不足し,心筋虚血を生じることより起こる.多くは冠動脈疾患,特に冠動脈硬化による狭窄,閉塞,血栓および冠動脈の攣縮が原因である.軽度の心筋虚血状態では,虚血部の収縮期壁運動の低下,収縮期壁厚増加の低下などが観察されるが,多くの場合非虚血心筋において代償的に壁運動が亢進するため,左室全体としてのポンプ機能は正常範囲に保たれる.しかし,冠動脈の完全閉塞のような強度の心筋虚血では,虚血部の壁運動異常はさらに高度となり,収縮期壁厚増加が消失し,左室壁内方運動も消失,時には外方へ突出し,逆運動を呈することがある.
一過性,可逆性の心筋虚血により生じたものが狭心症であり,虚血状態が長時間続き心筋に不可逆的壊死を生じたものが心筋梗塞である.狭心症は労作性狭心症(多くは動脈硬化に起因した冠動脈の狭窄のために,運動などによる心筋酸素消費量増加に対して心筋虚血が生じる),冠攣縮性狭心症(冠動脈に器質的な狭窄はないが,冠動脈が攣縮を起こして狭窄または閉塞することにより心筋虚血が生じる),不安定狭心症(心筋梗塞への移行や急死する可能性の高い病態の狭心症であり,内膜障害や粥腫の破錠部位における血小板凝集や血栓形成により急激に進行する冠動脈の狭窄および閉塞が原因となる)に分類される.心筋梗塞は侵される心筋壁の深さによって分類され,心筋壁全層にわたって障害されたとき,これを貫壁性梗塞と呼ぶ.これに対して,通常心筋壊死は心内膜側から心外膜側に進行するため心内膜側に限局して障害された場合を非貫壁性梗塞と呼ぶ.
診療支援
登録衛生検査所における緊急報告値の検証と統一案
著者: 桑名房一 , QM研究会
ページ範囲:P.1517 - P.1522
はじめに
1975年にLundbergは「患者診療中心の検査室運営」で,“Panic values”という検査医学用語を用い,即時治療を要する検査異常値の報告システムを提唱し,パニック項目と範囲を報告している1).わが国においても1980年頃から報告され始め2),1983年にはAST,ALT,LD,CKなどが追加されたパニック値が報告されている3).衛生検査所における緊急報告値は1986年(昭和61年)4月15日,「臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について」(同年10月施行令)において,検査案内書への掲載が関係法規4)で義務付けられた.これを受けて当時の衛生検査所間で協議が持たれ,松田5)らによる「パニック値の決め方,考え方」などが引用されて現在に至っている.
QM研究会(衛生検査所13社により精度管理などの問題を検討する会:代表 金村茂)では標準化の一環として緊急報告値の見直しを行い,衛生検査所が一般的に利用できる項目と範囲とを策定したので報告する.
生化学:臓器マーカー
膵疾患マーカー
著者: 三宅一德
ページ範囲:P.1523 - P.1525
はじめに
膵臓は,かつてはその疾患の診断や治療が困難なことから「暗黒の臓器」と呼ばれていた.近年では,多くの膵疾患マーカーが日常検査でも測定されるようになり,画像診断技術の著しい進歩もあって,膵疾患の診断は容易になったようにみえる.しかし,最近の統計でも,重症急性膵炎患者の死亡率は20%を超え,膵癌は手術可能な例に限っても5年生存率はわずか13%であり,そもそも切除率自体が30~40%と非常に低い1).治療の困難さがその主因といえるが,検査診断にかかわる問題点の存在―膵疾患マーカーの進歩とその診断特性を反映した効率的な診断が普及していないこと―の関与が指摘されている2).
近年,日本腹部救急医学会,日本膵臓学会,厚労省研究班により,EBM(evidince-based medicine,根拠に基づく医療)の手法に基づく急性膵炎についての診療ガイドライン3)が出版された.その作成課程で膵疾患診断マーカーにかかわるエビデンスの網羅的検索が行われ,診断特性の再評価が行われた.ここでは,この再評価の知見を主体に,膵疾患マーカーの特性を整理したい.
臨床検査技師のための実践医療データベース論
第12章 データマイニング入門
著者: 片岡浩巳
ページ範囲:P.1501 - P.1507
はじめに
データマイニングとは,膨大なデータのなかに潜む価値ある情報を発見することを目的とした研究活動と定義され,その情報処理技術は,幅広い研究分野で活用されている.これらの技術は,統計,機械学習,データベース,高速計算のためのソフトウェア技術やハードウェア技術などの総合的な学問領域で築き上げられた領域である.医学分野では,古くから過去の事例を基に新たな診断基準を発見する研究が進められ,1990年代では,EBM(evidence-based medicine,根拠に基づく医療)として体系化されてきた.しかし,情報処理技術からの視点で評価すると小規模な統計処理技術の範疇を脱していなかった.新たな展開が期待され始めたのは,遺伝子やプロテオミクス分野を中心にデータマイニング技術が数多く利用されるようになったここ最近のことである.
データマイニング研究を成功させるためには,解析対象となるデータベースがいかに正しく整備され,解析可能な形式で記録できているかという点にある.整備されていないデータベースをいくら解析しても,正しい結果を得ることは不可能なのである.これは,データの発生源である検査室に大きな責任があることを意味し,現場に携わる技師がデータベースを理解して整備することが未来のEBMを支える重要な鍵を握っていることになる.この最終章では,これまで学んできたデータベースを利用してデータマイニング技術を活用した事例を紹介し,この連載企画のまとめを行う.
ラボクイズ
一般検査 2
著者: 吉野一敬
ページ範囲:P.1472 - P.1472
今回は2症例とも,左肺下葉に広範な肺炎症状が見られる患者の膿様の胸水です.
問題1 症例1:80歳,女性
図1のような外観です.総蛋白1.7g/dl,LD1,630IU/l,糖48mg/dl,参考として同時測定した血糖値は82mg/dlです.図2はギムザ染色(Giemsa stain)です.
11月号の解答と解説
著者: 吉澤梨津好
ページ範囲:P.1473 - P.1473
【問題1】 解答:④細胞質内封入体細胞
解説:本症例は,回腸導管術後尿で,矢印の成分は回腸上皮細胞由来の細胞質内封入体細胞である.無染色で見ると白血球の分葉核(好中球)が多数出現しているようにも見えるが,細胞質は厚く,硬い感じがする.細胞質の大きさに大小不同があるが,細胞質の厚さはほぼ一定であることから,上皮系の細胞が示唆される.また,設問の膀胱全摘術後という記載から,回腸上皮細胞由来の細胞質内封入体細胞と推定できる.
回腸導管術とは,膀胱全摘術に伴い行われる尿路変更術の一つで,合併症や上行性の感染が少なく,腎機能が長期にわたって保たれることから,標準的な尿路変更術として広く行われている.回腸の一部を膀胱の代用としているため,回腸由来の円柱上皮細胞が孤立散在性または集塊状に認められる.手術後初期には円柱上皮細胞として比較的容易に鑑別可能であるが,手術経過とともに変性や崩壊像を示し,細胞が丸みを帯び,白血球と区別がつきにくくなる.ステルンハイマー染色(Sternheimer stain)を行うと核は濃染し,封入体は細胞質と同系色の赤紫色に濃く染まり,封入体細胞であることがよくわかる(図).
けんさ質問箱Q&A
抗不整脈薬の作用機序と心電図変化
著者: 野村昌弘 , 中屋豊 , 中安紀美子 , 河野智仁
ページ範囲:P.1528 - P.1531
不整脈治療薬を服用している患者さんのECGにはどのような変化が生じているのでしょうか.不整脈治療薬の作用機序とECG変化とについて教えてください.また,検査するうえで注意すべき点も併せて教えてください.(京都市 M.H.生)
■抗不整脈薬の新たな分類―ヴォーン-ウィリアムス分類(Vaughan-Williams classification,VW分類)からシシリアンギャンビット分類(Sicilian Gambit classification)へ
抗不整脈薬の標準的分類法として,従来からVaughan-Williams分類がよく使用されていた.このVaughan-Williams分類とは,心筋の細胞膜に存在するイオンチャンネルに対する抑制効果による分類法であり,I群薬はNaチャンネル抑制薬,II群薬はβ受容体遮断薬,III群薬は活動電位の持続を延長させる薬剤,IV群薬はCa拮抗薬に分類される.また,最近では,Naチャンネルへの結合・解離速度による分類が追加されるようになった(表1).
血小板凝集時のクエン酸血を用いた場合の補正法とは
著者: 後藤文彦
ページ範囲:P.1531 - P.1532
本誌9月号(vol.33 no.9,pp860-862)の後藤,他論文「検査じょうほう室」の「その血小板値だいじょうぶですか?」のなかで「クエン酸血を用いて測定し,補正値を報告する」ように書かれてありますが,その補正の方法を教えてください.(山形県 I.O.生)
ご質問の答えから申し上げますとクエン酸ナトリウム加血(以下,クエン酸血)を用いての補正値とは,血液が抗凝固剤クエン酸ナトリウムによって希釈された分の補正のことです.一般的にクエン酸ナトリウム(109mmol/l)は,血液凝固線溶検査(以下,凝固検査)や血小板凝集能検査などに用いられる脱カルシウム作用を有する液状の抗凝固剤です.また,その使用に当たっては血液9容に対して,クエン酸ナトリウム1容(血液9:クエン酸1)の割合とします.そのため抗凝固剤としてクエン酸ナトリウムを用いると血液は希釈され,同時に血小板も希釈されてしまいます.そこで希釈に対する補正が必要になる訳です.
コーヒーブレイク
いちびり
著者: 内波健二
ページ範囲:P.1464 - P.1464
大阪市港区築港3丁目に天保山公園があり,その中に天保山(標高4.5m)がある.当コラム「山歩き・街道歩き」の2002年6月号と1997年12月号で紹介されている.その天保山の「登頂証明書」を求めて挑戦した.
服装は散歩スタイルで十分だ.秋晴れ登山日和のある日,地下鉄中央線「大阪港」駅で下車し公園へ向けて歩き始めた.西入り口の階段,13段を登ると,江戸時代(天保年間)にこの場所が人々の憩いの場として賑わっていた風景を描いているタイル画がある.
チャールズリバーのほとりで [10]異国での母国語
著者: 坂本秀生
ページ範囲:P.1474 - P.1474
マヤ語で蛇という意味のカンクーンはメキシコのユカタン半島にあり,その名のように東西平均幅約400mに対し南北約23kmと長細い.海から昇る朝日を部屋の窓から望め,海辺に沈む夕日を別のベランダから眺めることは滅多にできない体験だろう.真っ白な砂浜に覆われた美しい島では,カリブ海の青色が遠浅の白い砂浜で一段と美しさを増している.
帰国すれば二度と訪れることもないだろうと,唯一この地で五つ星にランクされるリッツ・カールトンホテルを大奮発して予約しておいた.空港にはメキシカンらしい陽気さだけでなく,ホスピタリティーに富んだ2人組みのホテルマンの出迎えでリゾート気分は高まる一方だ.私たち夫婦の出迎えに,2人で出迎えとは驚いたが,チェックインを済ませ遺跡ツアーの申し込みにコンシェルジュを訪れると,流ちょうな日本語で応対し日本語ツアーも用意してくれるというのでまた驚いた.異国での母国語での対応に感激したが,これが予想しない出来事の序章だった.
小児の脳波検査
著者: 石郷景子
ページ範囲:P.1500 - P.1500
みなさん,こんにちは.私は脳波計の頭子で~す.私の仕事を紹介します.午前中は大人,午後は小児の脳波検査をしているの.お昼のひと時くつろぐ暇なしに「赤ちゃん寝てしまいました.」って,受付のお姉さんが呼びにくるの.休む暇なく午後の仕事に突入,少しは休ませろって感じです.
大人と違って小児,特に乳幼児から幼児の検査は人一倍疲れちゃうわ.異常波が最も出やすいのは,覚醒から睡眠に入る過程が多いでしょ.だから,起きている小児に電極を付けなければならないの.そうよ,みなさんできればそうしてね.い~え,絶対にそうして欲しいわ.だってよいデータを取るこつですもの.
知ッ得?ヒストリー「輸血編」
著者: 新屋博明
ページ範囲:P.1522 - P.1522
輸血史も他の科学史同様,戦争を抜きに語ることはできない.輸血ではさらに,血液という道徳的にも宗教的にも意義深いものを扱うだけに,輸血史は奥が深く,示唆に富んでいるのである.
死体血輸血はほんとうに行われていたのか?
1930年3月23日,ロシアのセルゲイ・ユーディンは自殺を図って手首を切ったエンジニアの若い男性に死体血を輸血した.供血者は6時間前にバスに轢かれて死亡した60歳の男性だった.脈が触れず意識のなかった患者は,輸血後意識が戻り顔色もよくなった.そして,2日後には退院した.(スゲエ!)
基本情報
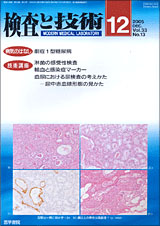
バックナンバー
52巻12号(2024年12月発行)
技術講座 生理
52巻11号(2024年11月発行)
技術講座 生理
52巻10号(2024年10月発行)
技術講座 生理
52巻9号(2024年9月発行)
増大号 臨床医に伝わりやすい 検査報告書とパニック値報告の心得
52巻8号(2024年8月発行)
技術講座 生理
52巻7号(2024年7月発行)
技術講座 生理
52巻6号(2024年6月発行)
技術講座 生理
52巻5号(2024年5月発行)
技術講座 その他
52巻4号(2024年4月発行)
技術講座 生理
52巻3号(2024年3月発行)
増大号 POCUSの決め手。 早く、正確な診断のために
52巻2号(2024年2月発行)
技術講座 生理
52巻1号(2024年1月発行)
技術講座 その他
51巻12号(2023年12月発行)
技術講座 生理
51巻11号(2023年11月発行)
技術講座 生理
51巻10号(2023年10月発行)
技術講座 その他
51巻9号(2023年9月発行)
増大号 匠から学ぶ 血栓止血検査ガイド
51巻8号(2023年8月発行)
技術講座 生理
51巻7号(2023年7月発行)
技術講座 生理
51巻6号(2023年6月発行)
技術講座 生理
51巻5号(2023年5月発行)
技術講座 生理
51巻4号(2023年4月発行)
技術講座 生理
51巻3号(2023年3月発行)
増大号 症例から学ぶ 疾患と検査値の推移
51巻2号(2023年2月発行)
技術講座 その他
51巻1号(2023年1月発行)
技術講座 生理
50巻12号(2022年12月発行)
技術講座 その他
50巻11号(2022年11月発行)
技術講座 生理
50巻10号(2022年10月発行)
技術講座 生理
50巻9号(2022年9月発行)
増大号 希少例と特殊像がわかる! エコーの撮り方完全マスター
50巻8号(2022年8月発行)
技術講座 生理
50巻7号(2022年7月発行)
技術講座 生理
50巻6号(2022年6月発行)
技術講座 生理
50巻5号(2022年5月発行)
技術講座 生理
50巻4号(2022年4月発行)
技術講座 生理
50巻3号(2022年3月発行)
増大号 見て学ぶ 一般検査学アトラス—外観検査から顕微鏡検査まで
50巻2号(2022年2月発行)
技術講座 その他
50巻1号(2022年1月発行)
技術講座 生理
49巻12号(2021年12月発行)
技術講座 生理
49巻11号(2021年11月発行)
技術講座 生理
49巻10号(2021年10月発行)
技術講座 生理
49巻9号(2021年9月発行)
増刊号 病態別 腹部エコーの観察・記録・報告書作成マスター
49巻8号(2021年8月発行)
技術講座 生理
49巻7号(2021年7月発行)
技術講座 生理
49巻6号(2021年6月発行)
技術講座 生理
49巻5号(2021年5月発行)
技術講座 生理
49巻4号(2021年4月発行)
技術講座 一般
49巻3号(2021年3月発行)
増刊号 First&Next Step 微生物検査サポートブック
49巻2号(2021年2月発行)
技術講座 微生物
49巻1号(2021年1月発行)
技術講座 病理・生理
48巻12号(2020年12月発行)
技術講座 その他
48巻11号(2020年11月発行)
技術講座 生化学
48巻10号(2020年10月発行)
技術講座 生理
48巻9号(2020年9月発行)
増刊号 学会発表・論文執筆はもう怖くない! 臨床検査技師のための研究入門
48巻8号(2020年8月発行)
技術講座 遺伝子
48巻7号(2020年7月発行)
技術講座 その他
48巻6号(2020年6月発行)
技術講座 輸血
48巻5号(2020年5月発行)
技術講座 生化学
48巻4号(2020年4月発行)
技術講座 生理
48巻3号(2020年3月発行)
増刊号 採血のすべて—手技から採血室の運用まで徹底解説
48巻2号(2020年2月発行)
技術講座 微生物
48巻1号(2020年1月発行)
技術講座 生理
47巻12号(2019年12月発行)
技術講座 病理
47巻11号(2019年11月発行)
技術講座 生理
47巻10号(2019年10月発行)
技術講座 生理
47巻9号(2019年9月発行)
増刊号 染色画像を比べて学ぶ 体腔液アトラス
47巻8号(2019年8月発行)
技術講座 病理
47巻7号(2019年7月発行)
技術講座 一般
47巻6号(2019年6月発行)
技術講座 血液
47巻5号(2019年5月発行)
技術講座 血液
47巻4号(2019年4月発行)
技術講座 血液
47巻3号(2019年3月発行)
増刊号 エキスパートが教える 心・血管エコー計測のノウハウ
47巻2号(2019年2月発行)
技術講座 病理
47巻1号(2019年1月発行)
技術講座 微生物
46巻12号(2018年12月発行)
技術講座 生理
46巻11号(2018年11月発行)
技術講座 輸血・遺伝子検査
46巻10号(2018年10月発行)
技術講座 その他
46巻9号(2018年9月発行)
増刊号 現場で“パッ”と使える 免疫染色クイックガイド
46巻8号(2018年8月発行)
技術講座 輸血・遺伝子検査
46巻7号(2018年7月発行)
技術講座 生理
46巻6号(2018年6月発行)
技術講座 管理
46巻5号(2018年5月発行)
技術講座 生化学
46巻4号(2018年4月発行)
技術講座 一般
46巻3号(2018年3月発行)
増刊号 感染症クイックリファレンス
46巻2号(2018年2月発行)
技術講座 輸血
46巻1号(2018年1月発行)
技術講座 病理
45巻12号(2017年12月発行)
技術講座 生理
45巻11号(2017年11月発行)
技術講座 一般
45巻10号(2017年10月発行)
技術講座 微生物
45巻9号(2017年9月発行)
増刊号 循環器病院の技師が教える メディカルスタッフのための心電図教室
45巻8号(2017年8月発行)
技術講座 栄養
45巻7号(2017年7月発行)
技術講座 病理
45巻6号(2017年6月発行)
技術講座 病理
45巻5号(2017年5月発行)
技術講座 細胞治療・管理
45巻4号(2017年4月発行)
技術講座 遺伝子・染色体検査
45巻3号(2017年3月発行)
45巻2号(2017年2月発行)
技術講座 細胞治療
45巻1号(2017年1月発行)
技術講座 病理
44巻13号(2016年12月発行)
技術講座 免疫
44巻12号(2016年11月発行)
技術講座 微生物
44巻11号(2016年10月発行)
技術講座 微生物
44巻10号(2016年9月発行)
増刊号 はじめて出会う 検査画像
44巻9号(2016年9月発行)
技術講座 管理・その他
44巻8号(2016年8月発行)
技術講座 微生物
44巻7号(2016年7月発行)
技術講座 生理
44巻6号(2016年6月発行)
技術講座 微生物
44巻5号(2016年5月発行)
技術講座 生理
44巻4号(2016年4月発行)
技術講座 微生物
44巻3号(2016年3月発行)
技術講座 生理
44巻2号(2016年2月発行)
技術講座 微生物
44巻1号(2016年1月発行)
技術講座 微生物
43巻13号(2015年12月発行)
技術講座 生化学
43巻12号(2015年11月発行)
技術講座 生化学
43巻11号(2015年10月発行)
技術講座 一般
43巻10号(2015年9月発行)
増刊号 血液形態アトラス
43巻9号(2015年9月発行)
技術講座 生理
43巻8号(2015年8月発行)
技術講座 生理
43巻7号(2015年7月発行)
技術講座 生理
43巻6号(2015年6月発行)
技術講座 微生物
43巻5号(2015年5月発行)
技術講座 移植医療
43巻4号(2015年4月発行)
技術講座 病理
43巻3号(2015年3月発行)
技術講座 血液
43巻2号(2015年2月発行)
技術講座 管理
43巻1号(2015年1月発行)
技術講座 病理
42巻13号(2014年12月発行)
技術講座 生化学
42巻12号(2014年11月発行)
技術講座 病理
42巻11号(2014年10月発行)
技術講座 血液
42巻10号(2014年9月発行)
増刊号 超音波×病理 対比アトラス
42巻9号(2014年9月発行)
技術講座 生理
42巻8号(2014年8月発行)
技術講座 免疫
42巻7号(2014年7月発行)
技術講座 生理
42巻6号(2014年6月発行)
技術講座 生理
42巻5号(2014年5月発行)
技術講座 病理
42巻4号(2014年4月発行)
技術講座 輸血
42巻3号(2014年3月発行)
技術講座 血液
42巻2号(2014年2月発行)
技術講座 微生物
42巻1号(2014年1月発行)
技術講座 病理
41巻13号(2013年12月発行)
技術講座 生理
41巻12号(2013年11月発行)
技術講座 生化学
41巻11号(2013年10月発行)
技術講座 生化学
41巻10号(2013年9月発行)
増刊号 解剖と正常像がわかる! エコーの撮り方完全マスター
41巻9号(2013年9月発行)
技術講座 微生物
41巻8号(2013年8月発行)
技術講座 生理
41巻7号(2013年7月発行)
技術講座 生理
41巻6号(2013年6月発行)
技術講座 微生物
41巻5号(2013年5月発行)
技術講座 一般
41巻4号(2013年4月発行)
技術講座 生化学
41巻3号(2013年3月発行)
技術講座 生理
41巻2号(2013年2月発行)
技術講座 生理
41巻1号(2013年1月発行)
技術講座 生理
40巻13号(2012年12月発行)
技術講座 血液
40巻12号(2012年11月発行)
技術講座 生理
40巻11号(2012年10月発行)
技術講座 生理
40巻10号(2012年9月発行)
増刊号 この検査データを読めますか?―検査値から病態を探る
40巻9号(2012年9月発行)
技術講座 生理
40巻8号(2012年8月発行)
技術講座 細胞診
40巻7号(2012年7月発行)
技術講座 生理
40巻6号(2012年6月発行)
技術講座 生理
40巻5号(2012年5月発行)
技術講座 生理
40巻4号(2012年4月発行)
技術講座 血液
40巻3号(2012年3月発行)
技術講座 生理
40巻2号(2012年2月発行)
技術講座 輸血
40巻1号(2012年1月発行)
技術講座 遺伝子
39巻13号(2011年12月発行)
疾患と検査値の推移
39巻12号(2011年11月発行)
疾患と検査値の推移
39巻11号(2011年10月発行)
疾患と検査値の推移
39巻10号(2011年9月発行)
増刊号 緊急報告すべき検査結果のすべて―すぐに使えるパニック値事典
39巻9号(2011年9月発行)
疾患と検査値の推移
39巻8号(2011年8月発行)
疾患と検査値の推移
39巻7号(2011年7月発行)
疾患と検査値の推移
39巻6号(2011年6月発行)
技術講座 生理
39巻5号(2011年5月発行)
技術講座 生理
39巻4号(2011年4月発行)
疾患と検査値の推移
39巻3号(2011年3月発行)
疾患と検査値の推移
39巻2号(2011年2月発行)
疾患と検査値の推移
39巻1号(2011年1月発行)
疾患と検査値の推移
38巻13号(2010年12月発行)
疾患と検査値の推移
38巻12号(2010年11月発行)
疾患と検査値の推移
38巻11号(2010年10月発行)
疾患と検査値の推移
38巻10号(2010年9月発行)
増刊号 免疫反応と臨床検査2010
38巻9号(2010年9月発行)
疾患と検査値の推移
38巻8号(2010年8月発行)
疾患と検査値の推移
38巻7号(2010年7月発行)
疾患と検査値の推移
38巻6号(2010年6月発行)
疾患と検査値の推移
38巻5号(2010年5月発行)
疾患と検査値の推移
38巻4号(2010年4月発行)
疾患と検査値の推移
38巻3号(2010年3月発行)
疾患と検査値の推移
38巻2号(2010年2月発行)
疾患と検査値の推移
38巻1号(2010年1月発行)
疾患と検査値の推移
37巻13号(2009年12月発行)
疾患と検査値の推移
37巻12号(2009年11月発行)
疾患と検査値の推移
37巻11号(2009年10月発行)
疾患と検査値の推移
37巻10号(2009年9月発行)
増刊号 顕微鏡検査のコツ―臨床に役立つ形態学
37巻9号(2009年9月発行)
疾患と検査値の推移
37巻8号(2009年8月発行)
疾患と検査値の推移
37巻7号(2009年7月発行)
疾患と検査値の推移
37巻6号(2009年6月発行)
疾患と検査値の推移
37巻5号(2009年5月発行)
疾患と検査値の推移
37巻4号(2009年4月発行)
疾患と検査値の推移
37巻3号(2009年3月発行)
疾患と検査値の推移
37巻2号(2009年2月発行)
疾患と検査値の推移
37巻1号(2009年1月発行)
疾患と検査値の推移
36巻13号(2008年12月発行)
疾患と検査値の推移
36巻12号(2008年11月発行)
疾患と検査値の推移
36巻11号(2008年10月発行)
疾患と検査値の推移
36巻10号(2008年9月発行)
増刊号 これから広がる生理検査・新たにはじまる生理検査
36巻9号(2008年9月発行)
疾患と検査値の推移
36巻8号(2008年8月発行)
疾患と検査値の推移
36巻7号(2008年7月発行)
疾患と検査値の推移
36巻6号(2008年6月発行)
疾患と検査値の推移
36巻5号(2008年5月発行)
疾患と検査値の推移
36巻4号(2008年4月発行)
疾患と検査値の推移
36巻3号(2008年3月発行)
疾患と検査値の推移
36巻2号(2008年2月発行)
疾患と検査値の推移
36巻1号(2008年1月発行)
疾患と検査値の推移
35巻13号(2007年12月発行)
疾患と検査値の推移
35巻12号(2007年11月発行)
疾患と検査値の推移
35巻11号(2007年10月発行)
増刊号 メタボリックシンドローム健診検査技術マニュアル
35巻10号(2007年10月発行)
疾患と検査値の推移
35巻9号(2007年9月発行)
疾患と検査値の推移
35巻8号(2007年8月発行)
疾患と検査値の推移
35巻7号(2007年7月発行)
疾患と検査値の推移
35巻6号(2007年6月発行)
疾患と検査値の推移
35巻5号(2007年5月発行)
疾患と検査値の推移
35巻4号(2007年4月発行)
疾患と検査値の推移
35巻3号(2007年3月発行)
疾患と検査値の推移
35巻2号(2007年2月発行)
疾患と検査値の推移
35巻1号(2007年1月発行)
疾患と検査値の推移
34巻13号(2006年12月発行)
技術講座 生理
34巻12号(2006年11月発行)
技術講座 一般
34巻11号(2006年10月発行)
増刊号 新しい臨床検査・未来の臨床検査
34巻10号(2006年10月発行)
疾患と検査値の推移
34巻9号(2006年9月発行)
疾患と検査値の推移
34巻8号(2006年8月発行)
疾患と検査値の推移
34巻7号(2006年7月発行)
疾患と検査値の推移
34巻6号(2006年6月発行)
疾患と検査値の推移
34巻5号(2006年5月発行)
疾患と検査値の推移
34巻4号(2006年4月発行)
疾患と検査値の推移
34巻3号(2006年3月発行)
疾患と検査値の推移
34巻2号(2006年2月発行)
疾患と検査値の推移
34巻1号(2006年1月発行)
疾患と検査値の推移
33巻13号(2005年12月発行)
疾患と検査値の推移
33巻12号(2005年11月発行)
疾患と検査値の推移
33巻11号(2005年10月発行)
増刊号 一線診療のための臨床検査
33巻10号(2005年10月発行)
疾患と検査値の推移
33巻9号(2005年9月発行)
疾患と検査値の推移
33巻8号(2005年8月発行)
疾患と検査値の推移
33巻7号(2005年7月発行)
疾患と検査値の推移
33巻6号(2005年6月発行)
疾患と検査値の推移
33巻5号(2005年5月発行)
疾患と検査値の推移
33巻4号(2005年4月発行)
疾患と検査値の推移
33巻3号(2005年3月発行)
疾患と検査値の推移
33巻2号(2005年2月発行)
疾患と検査値の推移
33巻1号(2005年1月発行)
疾患と検査値の推移
32巻13号(2004年12月発行)
技術講座 血液
32巻12号(2004年11月発行)
技術講座 病理
32巻11号(2004年10月発行)
技術講座 血液
32巻10号(2004年9月発行)
増刊号 細胞像の見かた―病理・血液・尿沈渣
32巻9号(2004年9月発行)
技術講座 生化学
32巻8号(2004年8月発行)
技術講座 免疫
32巻7号(2004年7月発行)
技術講座 微生物
32巻6号(2004年6月発行)
技術講座 病理
32巻5号(2004年5月発行)
技術講座 病理
32巻4号(2004年4月発行)
技術講座 病理
32巻3号(2004年3月発行)
技術講座 微生物
32巻2号(2004年2月発行)
技術講座 生化学
32巻1号(2004年1月発行)
技術講座 微生物
31巻13号(2003年12月発行)
技術講座 微生物
31巻12号(2003年11月発行)
技術講座 病理
31巻11号(2003年10月発行)
技術講座 微生物
31巻10号(2003年9月発行)
増刊号 包括医療と臨床検査
31巻9号(2003年9月発行)
技術講座 一般
31巻8号(2003年8月発行)
技術講座 微生物
31巻7号(2003年7月発行)
技術講座 病理
31巻6号(2003年6月発行)
技術講座 免疫
31巻5号(2003年5月発行)
技術講座 一般
31巻4号(2003年4月発行)
技術講座 病理
31巻3号(2003年3月発行)
技術講座 生化学
31巻2号(2003年2月発行)
技術講座 免疫
31巻1号(2003年1月発行)
技術講座 免疫
30巻13号(2002年12月発行)
技術講座 生理
30巻12号(2002年11月発行)
技術講座 生理
30巻11号(2002年10月発行)
技術講座 生化学
30巻10号(2002年9月発行)
増刊号 誰でもわかる遺伝子検査
30巻9号(2002年9月発行)
技術講座 微生物
30巻8号(2002年8月発行)
技術講座 生化学
30巻7号(2002年7月発行)
技術講座 微生物
30巻6号(2002年6月発行)
技術講座 生化学
30巻5号(2002年5月発行)
技術講座 微生物
30巻4号(2002年4月発行)
技術講座 一般
30巻3号(2002年3月発行)
技術講座 生化学
30巻2号(2002年2月発行)
技術講座 一般
30巻1号(2002年1月発行)
技術講座 免疫
29巻13号(2001年12月発行)
技術講座 病理
29巻12号(2001年11月発行)
技術講座 生理
29巻11号(2001年10月発行)
技術講座 病理
29巻10号(2001年9月発行)
技術講座 病理
29巻9号(2001年8月発行)
技術講座 病理
29巻8号(2001年7月発行)
技術講座 生理
29巻7号(2001年6月発行)
増刊号 病理組織・細胞診のための日常染色法ガイダンス
29巻6号(2001年6月発行)
技術講座 微生物
29巻5号(2001年5月発行)
技術講座 生理
29巻4号(2001年4月発行)
技術講座 病理
29巻3号(2001年3月発行)
技術講座 微生物
29巻2号(2001年2月発行)
技術講座 微生物
29巻1号(2001年1月発行)
技術講座 一般
28巻13号(2000年12月発行)
技術講座 病理
28巻12号(2000年11月発行)
技術講座 病理
28巻11号(2000年10月発行)
技術講座 免疫
28巻10号(2000年9月発行)
技術講座 微生物
28巻9号(2000年8月発行)
技術講座 微生物
28巻8号(2000年7月発行)
技術講座 生理
28巻7号(2000年6月発行)
増刊号 血液検査実践マニュアル
28巻6号(2000年6月発行)
技術講座 免疫
28巻5号(2000年5月発行)
技術講座 血液
28巻4号(2000年4月発行)
技術講座 一般
28巻3号(2000年3月発行)
技術講座 生理
28巻2号(2000年2月発行)
技術講座 生化学
28巻1号(2000年1月発行)
技術講座 一般
27巻13号(1999年12月発行)
技術講座 病理
27巻12号(1999年11月発行)
技術講座 一般
27巻11号(1999年10月発行)
技術講座 生化学
27巻10号(1999年9月発行)
技術講座 免疫
27巻9号(1999年8月発行)
技術講座 病理
27巻8号(1999年7月発行)
技術講座 病理
27巻7号(1999年6月発行)
増刊号 緊急検査実践マニュアル
27巻6号(1999年6月発行)
技術講座 生化学
27巻5号(1999年5月発行)
技術講座 血液
27巻4号(1999年4月発行)
技術講座 一般
27巻3号(1999年3月発行)
技術講座 生理
27巻2号(1999年2月発行)
技術講座 微生物
27巻1号(1999年1月発行)
技術講座 生理
26巻13号(1998年12月発行)
技術講座 一般
26巻12号(1998年11月発行)
技術講座 病理
26巻11号(1998年10月発行)
技術講座 病理
26巻10号(1998年9月発行)
技術講座 生理
26巻9号(1998年8月発行)
技術講座 生理
26巻8号(1998年7月発行)
技術講座 生理
26巻7号(1998年6月発行)
増刊号 病理組織・細胞診実践マニュアル
26巻6号(1998年6月発行)
技術講座 病理
26巻5号(1998年5月発行)
技術講座 一般
26巻4号(1998年4月発行)
技術講座 病理
26巻3号(1998年3月発行)
技術講座 一般
26巻2号(1998年2月発行)
技術講座 生理
26巻1号(1998年1月発行)
技術講座 血液
25巻13号(1997年12月発行)
技術講座 一般
25巻12号(1997年11月発行)
技術講座 一般
25巻11号(1997年10月発行)
技術講座 生理
25巻10号(1997年9月発行)
技術講座 血液
25巻9号(1997年8月発行)
技術講座 一般
25巻8号(1997年7月発行)
技術講座 一般
25巻7号(1997年6月発行)
増刊号 輸血検査実践マニュアル
25巻6号(1997年6月発行)
技術講座 免疫
25巻5号(1997年5月発行)
技術講座 生理
25巻4号(1997年4月発行)
技術講座 生理
25巻3号(1997年3月発行)
技術講座 微生物
25巻2号(1997年2月発行)
技術講座 生理
25巻1号(1997年1月発行)
技術講座 一般
24巻13号(1996年12月発行)
技術講座 生理
24巻12号(1996年11月発行)
技術講座 一般
24巻11号(1996年10月発行)
技術講座 生理
24巻10号(1996年9月発行)
技術講座 管理
24巻9号(1996年8月発行)
技術講座 生理
24巻8号(1996年7月発行)
技術講座 生理
24巻7号(1996年6月発行)
増刊号 感染症検査実践マニュアル
24巻6号(1996年6月発行)
技術講座 病理
24巻5号(1996年5月発行)
技術講座 生理
24巻4号(1996年4月発行)
技術講座 生理
24巻3号(1996年3月発行)
技術講座 生理
24巻2号(1996年2月発行)
技術講座 生理
24巻1号(1996年1月発行)
技術講座 一般
23巻13号(1995年12月発行)
技術講座 生理
23巻12号(1995年11月発行)
技術講座 病理
23巻11号(1995年10月発行)
技術講座 微生物
23巻10号(1995年9月発行)
技術講座 生理
23巻9号(1995年8月発行)
技術講座 一般
23巻8号(1995年7月発行)
技術講座 免疫
23巻7号(1995年6月発行)
技術講座 生理
23巻6号(1995年5月発行)
技術講座 一般
23巻5号(1995年4月発行)
増刊号 臨床生理検査実践マニュアル画像検査を中心として
23巻4号(1995年4月発行)
技術講座 病理
23巻3号(1995年3月発行)
技術講座 病理
23巻2号(1995年2月発行)
技術講座 一般
23巻1号(1995年1月発行)
技術講座 生理
22巻13号(1994年12月発行)
技術講座 一般
22巻12号(1994年11月発行)
技術講座 一般
22巻11号(1994年10月発行)
技術講座 一般
22巻10号(1994年9月発行)
技術講座 一般
22巻9号(1994年8月発行)
技術講座 生理
22巻8号(1994年7月発行)
技術講座 病理
22巻7号(1994年6月発行)
技術講座 一般
22巻6号(1994年5月発行)
技術講座 一般
22巻5号(1994年4月発行)
増刊号 免疫検査実践マニュアル
22巻4号(1994年4月発行)
技術講座 生理
22巻3号(1994年3月発行)
技術講座 免疫
22巻2号(1994年2月発行)
技術講座 一般
22巻1号(1994年1月発行)
技術講座 生理
21巻13号(1993年12月発行)
技術講座 一般
21巻12号(1993年11月発行)
技術講座 一般
21巻11号(1993年10月発行)
技術講座 一般
21巻10号(1993年9月発行)
技術講座 生理
21巻9号(1993年8月発行)
技術講座 一般
21巻8号(1993年7月発行)
技術講座 病理
21巻7号(1993年6月発行)
技術講座 一般
21巻6号(1993年5月発行)
技術講座 生理
21巻5号(1993年4月発行)
増刊号 臨床化学実践マニュアル
21巻4号(1993年4月発行)
技術講座 生理
21巻3号(1993年3月発行)
技術講座 病理
21巻2号(1993年2月発行)
技術講座 生理
21巻1号(1993年1月発行)
技術講座 生理
20巻13号(1992年12月発行)
技術講座 一般
20巻12号(1992年11月発行)
技術講座 一般
20巻11号(1992年10月発行)
技術講座 一般
20巻10号(1992年9月発行)
技術講座 一般
20巻9号(1992年8月発行)
技術講座 一般
20巻8号(1992年7月発行)
技術講座 血液
20巻7号(1992年6月発行)
技術講座 一般
20巻6号(1992年5月発行)
増刊号 尿検査法
20巻5号(1992年5月発行)
技術講座 生理
20巻4号(1992年4月発行)
技術講座 生理
20巻3号(1992年3月発行)
技術講座 病理
20巻2号(1992年2月発行)
技術講座 一般
20巻1号(1992年1月発行)
技術講座 生理
19巻13号(1991年12月発行)
技術講座 管理
19巻12号(1991年11月発行)
技術講座 生理
19巻11号(1991年10月発行)
技術講座 生理
19巻10号(1991年9月発行)
技術講座 一般
19巻9号(1991年8月発行)
技術講座 一般
19巻8号(1991年7月発行)
技術講座 生理
19巻7号(1991年6月発行)
増刊号 臨床血液検査
19巻6号(1991年6月発行)
技術講座 生理
19巻5号(1991年5月発行)
技術講座 生理
19巻4号(1991年4月発行)
技術講座 一般
19巻3号(1991年3月発行)
技術講座 生理
19巻2号(1991年2月発行)
技術講座 生理
19巻1号(1991年1月発行)
技術講座 一般
18巻13号(1990年12月発行)
技術講座 生理
18巻12号(1990年11月発行)
技術講座 微生物
18巻11号(1990年10月発行)
技術講座 生理
18巻10号(1990年9月発行)
技術講座 一般
18巻9号(1990年8月発行)
技術講座 一般
18巻8号(1990年7月発行)
技術講座 一般
18巻7号(1990年6月発行)
技術講座 一般
18巻6号(1990年5月発行)
増刊号 血液・尿以外の体液検査法
18巻5号(1990年5月発行)
技術講座 一般
18巻4号(1990年4月発行)
技術講座 一般
18巻3号(1990年3月発行)
技術講座 血液
18巻2号(1990年2月発行)
技術講座 生理
18巻1号(1990年1月発行)
技術講座 生理
17巻13号(1989年12月発行)
技術講座 一般
17巻12号(1989年11月発行)
技術講座 一般
17巻11号(1989年10月発行)
技術講座 一般
17巻10号(1989年9月発行)
技術講座 一般
17巻9号(1989年8月発行)
技術講座 生理
17巻8号(1989年7月発行)
技術講座 血清
17巻7号(1989年6月発行)
技術講座 一般
17巻6号(1989年5月発行)
感染症の検査法 Ⅲ 検査法各論
17巻5号(1989年5月発行)
技術講座 一般
17巻4号(1989年4月発行)
技術講座 生理
17巻3号(1989年3月発行)
技術講座 病理
17巻2号(1989年2月発行)
技術講座 一般
17巻1号(1989年1月発行)
技術講座 生理
16巻13号(1988年12月発行)
技術講座 一般
16巻12号(1988年11月発行)
技術講座 一般
16巻11号(1988年10月発行)
技術講座 一般
16巻10号(1988年9月発行)
技術講座 生理
16巻9号(1988年8月発行)
技術講座 一般
16巻8号(1988年7月発行)
技術講座 一般
16巻7号(1988年6月発行)
免疫化学検査法 資料
16巻6号(1988年6月発行)
技術講座 一般
16巻5号(1988年5月発行)
技術講座 一般
16巻4号(1988年4月発行)
技術講座 病理
16巻3号(1988年3月発行)
技術講座 生理
16巻2号(1988年2月発行)
技術講座 一般
16巻1号(1988年1月発行)
技術講座 血液
15巻13号(1987年12月発行)
技術講座 一般
15巻12号(1987年11月発行)
技術講座 病理
15巻11号(1987年10月発行)
技術講座 細胞診
15巻10号(1987年9月発行)
技術講座 一般
15巻9号(1987年8月発行)
技術講座 細胞診
15巻8号(1987年7月発行)
技術講座 病理
15巻7号(1987年6月発行)
技術講座 病理
15巻6号(1987年5月発行)
技術講座 病理
15巻5号(1987年4月発行)
臨床生理検査と技術 座談会
15巻4号(1987年4月発行)
技術講座 生理
15巻3号(1987年3月発行)
技術講座 血液
15巻2号(1987年2月発行)
技術講座 一般
15巻1号(1987年1月発行)
技術講座 病理
14巻13号(1986年12月発行)
技術講座 一般
14巻12号(1986年11月発行)
技術講座 病理
14巻11号(1986年10月発行)
技術講座 血清
14巻10号(1986年9月発行)
技術講座 血清
14巻9号(1986年8月発行)
技術講座 生理
14巻8号(1986年7月発行)
技術講座 血清
14巻7号(1986年6月発行)
技術講座 病理
14巻6号(1986年5月発行)
技術講座 生理
14巻5号(1986年4月発行)
形態学的検査と技術 血液と病理
14巻4号(1986年4月発行)
技術講座 病理
14巻3号(1986年3月発行)
技術講座 細菌
14巻2号(1986年2月発行)
技術講座 病理
14巻1号(1986年1月発行)
技術講座 細菌
13巻12号(1985年12月発行)
技術講座 病理
13巻11号(1985年11月発行)
技術講座 病理
13巻10号(1985年10月発行)
技術講座 生理
13巻9号(1985年9月発行)
技術講座 病理
13巻8号(1985年8月発行)
技術講座 病理
13巻7号(1985年7月発行)
技術講座 血液
13巻6号(1985年6月発行)
技術講座 一般
13巻5号(1985年5月発行)
技術講座 病理
13巻4号(1985年4月発行)
技術講座 一般
13巻3号(1985年3月発行)
技術講座 血液
13巻2号(1985年2月発行)
技術講座 一般
13巻1号(1985年1月発行)
技術講座 血液
12巻12号(1984年12月発行)
技術講座 血液
12巻11号(1984年11月発行)
技術講座 病理
12巻10号(1984年10月発行)
技術講座 輸血
12巻9号(1984年9月発行)
技術講座 一般
12巻8号(1984年8月発行)
技術講座 細菌
12巻7号(1984年7月発行)
技術講座 細菌
12巻6号(1984年6月発行)
技術講座 生理
12巻5号(1984年5月発行)
技術講座 一般
12巻4号(1984年4月発行)
技術講座 病理
12巻3号(1984年3月発行)
技術講座 血液
12巻2号(1984年2月発行)
技術講座 一般
12巻1号(1983年12月発行)
技術講座 血清
11巻12号(1983年12月発行)
技術講座 一般
11巻11号(1983年11月発行)
技術講座 細菌
11巻10号(1983年10月発行)
技術講座 細胞診
11巻9号(1983年9月発行)
技術講座 一般
11巻8号(1983年8月発行)
技術講座 血清
11巻7号(1983年7月発行)
技術講座 細菌
11巻6号(1983年6月発行)
技術講座 一般
11巻5号(1983年5月発行)
技術講座 病理
11巻4号(1983年4月発行)
技術講座 一般
11巻3号(1983年3月発行)
技術講座 血液
11巻2号(1983年2月発行)
技術講座 一般
11巻1号(1983年1月発行)
技術講座 血液
10巻12号(1982年12月発行)
技術講座 一般
10巻11号(1982年11月発行)
技術講座 生理
10巻10号(1982年10月発行)
技術講座 血清
10巻9号(1982年9月発行)
技術講座 細菌
10巻8号(1982年8月発行)
技術講座 一般
10巻7号(1982年7月発行)
技術講座 病理
10巻6号(1982年6月発行)
技術講座 細菌
10巻5号(1982年5月発行)
技術講座 病理
10巻4号(1982年4月発行)
技術講座 血清
10巻3号(1982年3月発行)
技術講座 生化学
10巻2号(1982年2月発行)
技術講座 病理
10巻1号(1982年1月発行)
技術講座 生化学
9巻12号(1981年12月発行)
技術講座 細菌
9巻11号(1981年11月発行)
技術講座 生理
9巻10号(1981年10月発行)
技術講座 一般
9巻9号(1981年9月発行)
技術講座 血清
9巻8号(1981年8月発行)
技術講座 血清
9巻7号(1981年7月発行)
技術講座 生理
9巻6号(1981年6月発行)
技術講座 細菌
9巻5号(1981年5月発行)
技術講座 一般
9巻4号(1981年4月発行)
技術講座 一般
9巻3号(1981年3月発行)
技術講座 血清
9巻2号(1981年2月発行)
技術講座 一般
9巻1号(1981年1月発行)
技術講座 生化学
8巻12号(1980年12月発行)
技術講座 一般
8巻11号(1980年11月発行)
技術講座 生理
8巻10号(1980年10月発行)
技術講座 検体の取り扱いと保存
8巻9号(1980年9月発行)
技術講座 病理
8巻8号(1980年8月発行)
技術講座 生化学
8巻7号(1980年7月発行)
技術講座 一般
8巻6号(1980年6月発行)
技術講座 生理
8巻5号(1980年5月発行)
技術講座 生化学
8巻4号(1980年4月発行)
技術講座 血清
8巻3号(1980年3月発行)
技術講座 病理
8巻2号(1980年2月発行)
技術講座 一般
8巻1号(1980年1月発行)
技術講座 生化学
7巻12号(1979年12月発行)
技術講座 一般
7巻11号(1979年11月発行)
技術講座 一般
7巻10号(1979年10月発行)
技術講座 細菌
7巻9号(1979年9月発行)
技術講座 生理
7巻8号(1979年8月発行)
技術講座 病理
7巻7号(1979年7月発行)
技術講座 生理
7巻6号(1979年6月発行)
技術講座 一般
7巻5号(1979年5月発行)
技術講座 血液
7巻4号(1979年4月発行)
技術講座 生理
7巻3号(1979年3月発行)
技術講座 病理
7巻2号(1979年2月発行)
技術講座 細菌
7巻1号(1979年1月発行)
技術講座 生化学
6巻12号(1978年12月発行)
技術講座 細菌
6巻11号(1978年11月発行)
技術講座 病理
6巻10号(1978年10月発行)
技術講座 血清
6巻9号(1978年9月発行)
技術講座 細菌
6巻8号(1978年8月発行)
技術講座 生化学
6巻7号(1978年7月発行)
技術講座 一般
6巻6号(1978年6月発行)
技術講座 病理
6巻5号(1978年5月発行)
技術講座 生理
6巻4号(1978年4月発行)
技術講座 一般
6巻3号(1978年3月発行)
技術講座 病理
6巻2号(1978年2月発行)
技術講座 一般
6巻1号(1978年1月発行)
技術講座 病理
5巻12号(1977年12月発行)
技術講座 生理
5巻11号(1977年11月発行)
技術講座 一般
5巻10号(1977年10月発行)
技術講座 細菌付録
5巻9号(1977年9月発行)
技術講座 一般
5巻8号(1977年8月発行)
技術講座 生理
5巻7号(1977年7月発行)
技術講座 一般
5巻6号(1977年6月発行)
技術講座 一般
5巻5号(1977年5月発行)
技術講座 一般
5巻4号(1977年4月発行)
技術講座 一般
5巻3号(1977年3月発行)
技術講座 一般
5巻2号(1977年2月発行)
技術講座 一般
5巻1号(1977年1月発行)
技術講座 一般
4巻12号(1976年12月発行)
技術講座 一般
4巻11号(1976年11月発行)
技術講座 一般
4巻10号(1976年10月発行)
技術講座 一般
4巻9号(1976年9月発行)
技術講座 一般
4巻8号(1976年8月発行)
技術講座 一般
4巻7号(1976年7月発行)
技術講座 一般
4巻6号(1976年6月発行)
技術講座 一般
4巻5号(1976年5月発行)
技術講座 一般
4巻4号(1976年4月発行)
技術講座 一般
4巻3号(1976年3月発行)
技術講座 一般
4巻2号(1976年2月発行)
技術講座 一般
4巻1号(1976年1月発行)
技術講座 一般
3巻12号(1975年12月発行)
技術講座 一般
3巻11号(1975年11月発行)
技術講座 一般
3巻10号(1975年10月発行)
技術講座 一般
3巻9号(1975年9月発行)
技術講座 一般
3巻7号(1975年8月発行)
特集 必修 日常検査の実技
3巻6号(1975年6月発行)
技術講座 生理
3巻5号(1975年5月発行)
技術講座 一般
3巻4号(1975年4月発行)
技術講座 一般
3巻3号(1975年3月発行)
技術講座 一般
3巻2号(1975年2月発行)
技術講座 一般
3巻1号(1975年1月発行)
技術講座 一般
