新しい知見
抗M2抗体(antiM2):抗ミトコンドリア抗体の主要な標的抗原はミトコンドリア内膜に存在するピルビン酸脱水素酵素,2-オキソグルタル酸脱水素酵素,分枝鎖2-オキソ酸脱水素酵素のE2成分である.従来,検出法は免疫蛍光法であったが,近年,ELISA(enzyme-linked immunosorbent assay,固相酸素結合)法(測定キット商品名MESACUP(R)-2テスト:ミトコンドリアMu2)が日常診療に使われるようになった.ELISA法は上記の三つの2-オキソ酸脱水素酵素のリコンビナントE2成分を固相化して抗体を検出する方法である.これによって測定された抗体は抗M2抗体(antiM2)と呼ばれる.抗ミトコンドリア抗体の標的抗原にはM1からM9まであるが,このうちM2はミトコンドリア内膜にある2-オキソ酸脱水素酵素構成分であり,これに対する抗体(antiM2)は抗ミトコンドリア抗体であることにはかわりはない.原発性胆汁性肝硬変(primary biliary cirrhosis,PBC)の新しい診断基準では免疫蛍光法で検出される抗体,ELISA法で検出される抗体を区別せず,抗ミトコンドリア抗体と呼ぶこととなった.
雑誌目次
検査と技術33巻7号
2005年07月発行
雑誌目次
病気のはなし
自己免疫性肝疾患
著者: 戸田剛太郎
ページ範囲:P.616 - P.623
技術講座 生化学
尿中微量アルブミン測定法
著者: 舛方栄二
ページ範囲:P.625 - P.630
新しい知見
尿中微量アルブミンは,持続する高血糖による糸球体基底膜のチャージバリアーの破綻とそれに伴う糸球体内圧上昇による基底膜透過性の亢進により出現し,糖尿病性腎症の病期分類に採用されている.さらに最近では脳梗塞や頸動脈内膜中膜複合体肥厚度(intima media thickness,IMT)上昇を認める本態性高血圧患者において微量アルブミン尿が高値傾向であるとの報告1)や,左室肥大の程度2),さらには高感度CRP(C-reactive protein,C反応性蛋白)値とも有意な相関がある3)ことなどがしだいに明らかにされ,高血圧治療ガイドライン2004(JSH2004)では高血圧による臓器障害の評価のための特殊(精密)検査として記載されるに至っている.以上より尿中微量アルブミン測定は,糖尿病のみならず高血圧などによる臓器合併症の指標としても広く利用できる有用な検査であるといえよう.
一般
精液検査(不妊症と関連して)
著者: 坂本英雄 , 吉田英機
ページ範囲:P.631 - P.635
新しい知見
デンマークのグループが年代とともに精子濃度が減少していることを報告してから,環境ホルモンとの関連性も含め世界的に注目され,追試がなされたが結果はさまざまで精子数の減少傾向に関して結論は出ていない.これを契機に精液検査が標準化されていないため,異なる施設間で測定された精子数のデータを単純に比較できないことが認識された.多施設間でのデータの比較には精液検査法の精度管理が重要で,各国で精液検査の標準化について検討がなされ,わが国でも精液検査の標準化ガイドラインが作成された.また,無精子症症例の約40%で,採取した精巣組織中に精子が発見され,精子を採取できた場合,顕微授精により挙児を得る可能性が出てきている.
疾患と検査値の推移
血球貪食症候群
著者: 坂田顕文 , 河敬世
ページ範囲:P.637 - P.641
疾患概念
発熱,肝脾腫などの症状を呈し,肝機能障害,汎血球減少,高フェリチン血症,高LDH(lactate dehydrogenase)血症,高トリグリセリド血症,播種性血管内凝固症候群(disseminated intravascular coagulation,DIC)などの検査所見を特徴とする.リンパ網内系組織(骨髄,肝臓,脾臓,リンパ節)において組織球の増殖と血球貪食とが認められる.これらは種々の原因によるT細胞およびマクロファージの異常活性化による高サイトカイン血症に起因することが明らかとなってきた1).
病 因
病因は大きく表1のように3つに分けられる.すなわち一次性,二次性と移植後のHPSである.
オピニオン
臨床検査技師教育の立場から臨床実習病院への期待
著者: 安松弘光
ページ範囲:P.624 - P.624
附属病院を持たない臨床検査技師養成校は数か所の総合病院にその実習をお願いしているのが現状である.そこには学校側と実習病院との間に少なからず問題が生じているようである.本校ではこのようなことをできるだけ少なくするため,実習病院の技師長あるいは教育責任者と,毎年実習施設責任者会議を開催している.実習病院側からは毎年同じようなことが話題になっている.それは実習生に対して,「挨拶をしない」「積極性がない」「基本ができていない」などの意見が出される.実習をお願いしている学校側からは本音での発言をお願いすることはいろいろな面で困難であると思う.今回は思い切って実習終了後,学生に対してアンケートを実施してみた.その内容をいくつか紹介してみたい.
1 . 実際の現場を体験して
「臨床検査技師の仕事の重要さ,責任の大きさを改めて感じた」「漠然としていたものが明確になった」など,ほとんどの学生がこのように述べている.臨床実習を体験することで臨床検査業務あるいは臨床検査技師というものがより深く理解されており,その目的の大部分が達成されている.
絵で見る免疫学 基礎編67
自然免疫の細胞と役割(1) 自然免疫におけるパターン認識レセプターその1
著者: 高木淳 , 玉井一
ページ範囲:P.644 - P.645
免疫系には絶えず侵入する異物に対して迅速に働く自然免疫と,異物が侵入してから数日後に作動する獲得免疫に分類される.初めての病原体が侵入した際,ただちにT細胞やB細胞を主とする感染防御機構すなわち獲得免疫が作動するわけではない.自然免疫は多くの病原微生物を認識しこれを迅速に排除し,炎症を起こす一連のシグナル蛋白質,すなわちサイトカインによって獲得免疫機構へ誘導する.最近,自然免疫には多くの発見があり,感染症や自己免疫疾患の解明に新たな進展が期待されている.
微生物の侵入に対する最初のバリアーは皮膚表層の角質である.さらに,組織には好中球やマクロファージなどの貪食細胞,樹状細胞,NK(natural killer)細胞,γδT細胞などが待ち構えている.化膿菌と呼ばれているブドウ球菌,肺炎球菌,連鎖球菌,緑膿菌,大腸菌などが皮膚のバリアーを破って侵入したとき,最初に対処するのが常に体内を循環している好中球である.細菌を捕らえた好中球やマクロファージはIL(interleukin)-8(ケモカイン),TNF(tumor necrosis factor,腫瘍壊死因子)-αやIL-1などを産生する.IL-8は応援を乞うべく血流中の好中球やマクロファージを感染部位に誘引する物質である.TNF-αは感染組織近傍の血管内皮細胞に接着分子を発現させ遊走してきた仲間を接着して引き止め,さらに血管の透過性を亢進させて感染組織に誘引する.接着分子とはTNF-αにより血管内皮細胞上にセレクチンおよびLFA(lymphocyte function-associated antigen,リンパ球機能関連抗原)-1を発現させて好中球に発現しているシアリルルイスxおよびICAM(intercellular adhesion molecule,細胞間接着分子)-1をそれぞれ結合する(第33巻第2号,第3号参照).IL-1,IL-8およびTNF-αは炎症性サイトカインと呼ばれ,免疫担当細胞を活性化し炎症反応を起こして病原体感染の拡大を防いでいる(図1).
ワンポイントアドバイス
アームダウンに適した採血法の工夫
著者: 谷脇清助 , 藤井誠治 , 戌角幸治
ページ範囲:P.682 - P.682
真空採血管による採血は,穿刺中の静脈圧を変化させてしまうと採血管内の血液が逆流し,汚染事故に繁がる可能性があると勝田ら1,2)により報じられた.2004年7月にJCCLS(日本臨床検査標準協議会)から標準採血法ガイドライン2)が発行され,現在このガイドラインに沿って採血が行われている.われわれも汚染問題が報道された後,この対策に取り組み2004年1月より傾斜式腕枕の試作を用いた採血を導入.また採血ホルダーを患者様ごとに交換することを決定した.これらはMTJ(Medical&Test Journal)883号,2004年2月に報告されたが,現在行っているアームダウン方式について紹介する.
テレビ,新聞などで採血の汚染問題が報道されて以後,採血に対する関心と不安を持つ患者様が多くなり,いかに患者様の不安を取り除きながら採血を行うかが問われている.現在,われわれが用いているアームダウン方式は採血用枕を三角形(図1)とし,その一辺に腕を添わせたとき採血管内の内容物が逆流しないように角度を工夫したものである.
けんさアラカルト
―異常値となるメカニズム 2.分析機器エラー情報からの異常値の事例・3―プロゾーン現象―その検出と対処法
著者: 宮下徹夫
ページ範囲:P.678 - P.680
最近の汎用生化学自動分析装置による免疫学的測定には,免疫比濁(turbidimetric immunoassay,TIA)法やラテックス免疫比濁(latex immunoturbidimetric assay,LIA)法を原理とする試薬が用いられている.これらの試薬を利用する場合の注意点の一つにプロゾーン現象がある.本稿では,われわれが過去に行った若干の検討結果を基に自動分析装置におけるプロゾーン現象検出のメカニズムを紹介し,検出が困難な場合の対策についても述べてみたい.
■プロゾーン現象
抗原抗体反応において,抗原または抗体のどちらか一方が過剰のために反応が抑制される濃度領域が現れることを,地帯現象(zone phenomenon)といい,抗体過剰による反応抑制領域を前地帯(prozone),抗原過剰による場合を後地帯(postzone)というが1),両者を区別せずプロゾーン現象(prozone phenomenon)ということが多い.図1に示したように,抗体量が一定のときの抗原濃度と吸光度との関係は,最適比を頂点とする上に凸の曲線となる.通常,抗原を定量するときの反応の場は抗体過剰領域である.この領域のスロープはS字状となるが,感度が高く吸光度が直線的に変化する部分,すなわち濃度C1からC2までの箇所が検量範囲として利用される.抗原濃度が最適比を超えると抗原過剰により吸光度は減少に転じる.これが臨床検査でいうプロゾーン現象である.目的成分の臨床的にありうる最高濃度Cmaxが,検量範囲上限の吸光度Ec2(=Ec3)まで低下する濃度C3より低い場合には,検量上限値より外れた高値検体を希釈して再測定すればよい.しかし,Cmaxが図のようにC3より高い場合には吸光度が検量範囲であるEcpz(=Ecmax)まで低下する検体が存在する可能性(測定値の潜り込み)があるので,プロゾーン現象の有無を確認(プロゾーンチェック)する必要がある.プロゾーンチェックが実施できない場合には検量範囲の上限濃度をC2から測定値の潜り込みを考慮した濃度であるCpzまで下げる必要がある.
チーム医療と臨床検査技師
著者: 朝山均
ページ範囲:P.681 - P.681
わが国の医療は,国民皆保険制度という所得に関係なく全国民があまねく比較的高水準の医療を受けることができ,また各医療機関へのアクセスフリー(利便性が高い)が可能な一律平等の制度を維持しつつ今日を迎えている.このことは一方で医療費高騰を招き,医療経済が逼迫状況になったのも事実である.この間,医療改革も第1次~第4次へと移り変わり医療費抑制のための政策が打ち出され,とりわけ臨床検査界は極めて厳しい状況下にある.
臨床検査は,1980年代初期を境に前後10数年で科学,技術の急激な進歩により用手法から自動化へと大きく変貌した.これを受けて検査部,臨床検査技師は多検体,多項目の処理という日常検査に埋没されるに至ったのである.この背景には検査を実施すれば収益が上がるという検査出来高払い制度があったが,かたや診断・治療への臨床検査としての貢献度も大なることは確実であった.
今月の表紙
百聞は一見に如かず・19 名付け親の多いリンパ腫
著者: 松谷章司
ページ範囲:P.636 - P.636
名前も多いし,経緯も変わっているリンパ腫として血管免疫芽球性T細胞性リンパ腫(angioimmunoblastic T-cell lymphoma,AILT),IBL様T細胞リンパ腫(IBL-like T-cell lymphoma)という疾患がある.これは,歴史的に相前後して多くの研究者たちが同様病態をそれぞれ独自性を主張して発表したため実に多くの名称が残っている病変に由来する.免疫芽球性リンパ節症(immunoblastic lymphadenopathy,IBL),異常蛋白血症を伴う血管免疫芽球性リンパ節症(angio-immunoblastic lymphadenopathy with dysproteinemia,AILD),血管免疫芽球性リンパ節症(angioimmunoblastic lymphadenopathy,AIL),リンパ肉芽腫症X(lymphogranulomatosis X),免疫異形成症(immunodysplastic disease),リンパ異形成症候群(lymphodysplastic syndrome)など.多クローン性の免疫グロブリン異常を伴っていることが多く,組織像も単一な細胞の増殖ではなく,多彩なリンパ球系細胞増生,好酸球浸潤,腫大した内皮細胞の血管増生などの所見から,ただちに単クローン性の細胞増殖による腫瘍とは考えにくかったため,当初,反応性,良悪性境界あるいはリンパ腫前段階の病変と考えられていた.しかし,T細胞受容体遺伝子(T cell receptor gene,TCR gene)の再構成を示す症例が多いことから,多くはT細胞リンパ腫であることがわかっている.そこで,血管免疫芽球性T細胞性リンパ腫(AILT)などの長々しい名称が用いられている.年余にわたりリンパ節腫大が出没する経過を有する症例もあり,本疾患が前段階の病変から推移するのか,de novoに発症するのかは意見の分かれるところであるが,診断時には全身リンパ節腫大と後述する症状を伴っており,T cell lymphomaの証拠が認められることが多い.
組織像はリンパ濾胞/胚中心の減少,萎縮あるいは痕跡的な残存,高内皮細胞性細静脈の樹枝状増生,免疫芽球の増殖,小型リンパ球,類上皮細胞集塊,形質細胞や好酸球の浸潤が見られる.好酸性物質の沈着所見は欧米に比してわが国の症例では少ない.リンパ球様細胞の中に淡明で広い細胞質とくびれた小型核を有する細胞(淡明細胞:clear cell,pale cell)の増生巣が認められることも特徴の一つに挙げられる.患者は男性,中高齢者に多く,発熱,皮疹,全身リンパ節腫脹,肝脾腫,自己免疫性溶血性貧血,多クローン性高γグロブリン血症を呈し,予後は悪く,感染などで死亡することが多い.
Laboratory Practice 生理 超音波像の読みかた
甲状腺―悪性疾患
著者: 田中久美 , 福成信博 , 清水一雄
ページ範囲:P.646 - P.651
はじめに
甲状腺疾患における画像診断には,頸部軟X線をはじめ,超音波・CT・MRI・核医学検査に至るさまざまなmodality(手法・手段)が臨床応用されている.そのなかでも一般臨床およびスクリーニングとして幅広く用いられているのが,超音波検査である.特に,最近の超音波機器の進歩は目覚ましく,画像分解能の高さからみてもCTやMRIを大きく引き離している.最新機器のBモード画像では,2~3mmの微小病変を十分に捉えることが可能であり,病理のマクロ写真と比較しても実物に限りなく迫ったものとなってきた.また,基礎となるBモード画像だけではなく,リアルタイムに血流情報を捉えることができるカラードプラー(color-Doppler)法は,既に臨床において幅広く応用されており,新たな診断的価値を見いだしている.さらにハードウェアの改善に伴い3-Dイメージングや組織弾性を評価できるelastographyなどの新しい技術が次々に実現化され,新しい臨床情報を与えるものとして期待されている.
ここでは,甲状腺悪性病変における特徴的な超音波所見を解説するとともに,各疾患における臨床病理学的特徴を踏まえて,他のmodalityを含めた画像診断について述べる.
生化学 自動分析装置での検査データの質を上げるためのポイント
免疫反応系での異常反応の検出例
著者: 山本慶和
ページ範囲:P.652 - P.654
はじめに
異常反応が検出される場合として次のようなものが考えられる.反応過程をモニターし異常な反応曲線を検出する,関連する項目との関係からの乖離を検出する,異常高・低値を検出する,および医師から臨床所見と乖離の指摘などがある.いずれも重要なデータ保証のきっかけとなる.
ここでは免疫反応系の異常値例を取り上げ,反応過程モニターおよび項目間乖離による異常値検出方法と原因解析に用いられる技術とを併せて説明する.
検査室の安全管理・4
ISO15190:2003臨床検査室 安全に対する要求事項・その4
著者: 久保野勝男
ページ範囲:P.655 - P.658
はじめに
臨床検査室は多くの薬品や機器・器具を使用して測定を行うため,さまざまな危険を伴う作業を実施している.加えて感染性の高い検体を日常的に取り扱うことでは,他の試験施設や校正機関と大きく異なっている.このことは検査室勤務者だけでなく,検査室に立ち入る外来者に対する安全性についても十分配慮されなければならない.
第1回(vol.33 no.4,pp349-352)に述べたように,米国では臨床検査に関連した多くの国内規格や指針があり,CLSI(Clinical and Laboratory Standards Institute:旧名称NCCLS,National Committee for Clinical Laboratory Standards)は1996年にCAP(Collage of American Pathologists:米国臨床病理医会)の会員向け安全マニュアルを基にした文書「GP17-A:Clinical Laboratory Safety;Approved Guideline」を発行した.ISO/TC212で,このGP17-Aを旧NCCLSとの合意に基づいて国際規格として策定したのが現在のISO15190:2003である.ISO15190:2003は,臨床検査室の安全性を確保するために留意すべき要件はすべて含まれている.
前回までにISO15190:2003に記載されている各要求事項について,国内法規や現在の検査室の状況を踏まえて詳しく解説してきたが,今回はISO15190:2003の総括をする意味で,これらを実際の臨床検査室の中に取り込むための参考となる手順について解説する.
トピックス
敗血症におけるプロカルシトニン測定
著者: 久志本成樹
ページ範囲:P.687 - P.690
はじめに
敗血症(sepsis)は集中治療を要する重症病態における最大の死亡原因である.この15年,敗血症の病態に重要な炎症性メディエーターに対する多くの拮抗,除去療法が試みられたが,活性化プロテインC1)や,最近報告されたTNF(tumor necrosis factor,腫瘍壊死因子)-αモノクローナル抗体2)で予後の改善が期待されるにとどまっている.
敗血症の診断は,感染の証明と,体温,白血球数,心拍数と呼吸数で定義される全身性炎症反応症候群(systemic inflammatory response syndrome,SIRS)によってなされる3).しかし,敗血症によって生じる全身性炎症反応とそのパラメーターの変化は,その原因が感染であることを示すものではない.プロカルシトニン(procalcitonin,以下,PCT)は敗血症の原因が細菌感染症によることを示すマーカーであるとともに,その重症度を反映することから注目を集めている.
酸化ストレスマーカーとしてのバイオピリン
著者: 山口登喜夫
ページ範囲:P.690 - P.693
はじめに
多くの活性酸素種は寿命が極めて短く,さまざまな生体成分と速やかに反応するので,生体防御のためには発生の抑制か発生局所での分解処理が必要となる.このため,多量の酸素を使うヒトをはじめとする好気的生物は,活性酸素種が発生する組織細胞内局所に高濃度のスカベンジャーや抗酸化酵素を有しており,酸素毒性を発生することのないように,エネルギー代謝における防御能としてレドックス(酸化・還元)・バランスを保持している.しかし各種疾患では,これら酸化ストレスに対するレドックス・バランスが破綻し,活性酸素種が非特異的に生命機能を破壊し病態発現の引き金となっている可能性がある.そこで,生体内レドックス状態を示す標準的指標(standard index)としての酸化ストレスマーカーが求められている.
どうする?パニック値 血液
4.白血球数減少
著者: 松尾収二
ページ範囲:P.676 - P.677
白血球(white blood cell,以下,WBC)の減少は,実際には好中球の減少であり,感染症に罹患する危険性が高いため速報しなければならない.
当院の基準
WBC減少:1,000/μl以下
設定値はおおむね1~2%の出現頻度である.
検査じょうほう室 血液:自動血球分析装置のフラッグ処理で困ったこと
EDTA加採血管中の情報をすべて読み取る
著者: 丸茂美幸
ページ範囲:P.665 - P.667
はじめに
自動血球計数器は,多くの検査室で使用されており,迅速検査に果たす役割は大きい.また白血球分類は,末梢血白血球を,顆粒球,好酸球,好塩基球,単球,リンパ球の五つに分類するが,それぞれの細胞は目視法分類とよく相関することから,スクリーニング検査として大きな役割を果たしている.一方,私たちが毎日扱っている検体にはさまざまな疾患のものが含まれており,病態によって,細胞の形態や,自動血球計数器から得られる情報はさまざまで,自動血球計数器による白血球五分類結果をそのまま報告できないことや,目視再検の基準を血球計数器のフラッグ情報だけに頼るわけにはいかないことも日々経験している.そういった現状のなかで,「EDTA加採血管中にある血液の異常細胞や重要な情報を見逃さないようにするためにはどうすればよいのか」について,当院の事例を紹介しながら述べてみたい.
生化学:臓器マーカー
腎疾患マーカー
著者: 上原由紀 , 矢内充
ページ範囲:P.668 - P.670
はじめに
腎臓は腰背部の後腹膜腔内に左右一つずつ存在し,内部は糸球体およびそれに続く尿細管から構成されるネフロンと呼ばれる基本構造の集合で成り立っている.腎臓は,ネフロンからの尿の生成によって水分や電解質の調整を行い体液の恒常性を維持するほか,さまざまなホルモンの産生も担っている.
腎疾患は,検診や外来で尿検査を行った際に偶然異常が見つかるという場合が最も多い.時には浮腫や尿の肉眼的異常,末期腎不全における尿毒症症状などの自覚症状が出現したり,高血圧や貧血などの他覚症状を呈したりして発見される場合もある.現在,非常に多くの検査が腎疾患マーカーとしてその有用性を報告されている(表).本稿ではこれらのうち特に検査を行ううえで注意すべき点,最近話題になっている点について解説していく.
生理:超音波検査のステップアップ
乳腺
著者: 白井秀明
ページ範囲:P.671 - P.673
はじめに
よく「乳癌はどんなふうに見えますか?」と尋ねられることがある.乳腺腫瘤において乳癌はもちろんのこと,他の腫瘤を含め種類が非常に多くその形態も多彩であり,すべてについて説明することは容易ではない(表).しかし,ある程度それぞれの腫瘤における増殖形態を理解すれば,画像の傾向も捉えることは可能と考えている.そのために筆者が最も近道として用いているのが,手術によって摘出された病変の病理組織標本と超音波画像との対比である.
そこで今回は代表的な乳腺腫瘍症例を用いて,実際に病理標本との対比を紹介し,そのうちで特に重要と考える画像的な特徴について説明する.
臨床検査技師のための実践医療データベース論
第7章 データベースの設計
著者: 片岡浩巳
ページ範囲:P.659 - P.663
はじめに
目的に応じて正しく設計されたデータベースを用いれば,多くの論理的な質問を短時間に解くことが可能である.逆に,設計の悪いデータベースを利用すると,集計結果が方法によって合わない事態が発生する場合や,検索に膨大な時間を費やしてしまう場合がある.データベースの設計は,冗長なデータを排除することとテーブルとテーブルとの関係を明確にし,テーブル構造を単純化することとが基本的な考えかたである.本章では,これらの設計に関して,データベースにどのようなテーブルを作成すれば,矛盾のない情報検索が可能となるかという課題について,データベース論理設計の基本的な理論である「正規化」理論を中心に述べる.
ラボクイズ
フローサイトメトリー 2
著者: 東克巳
ページ範囲:P.642 - P.642
症 例:2歳,男児.
1週間前から微熱があり,近医で抗生剤の投薬を受けた.しかし全身倦怠感,食欲不振が出現したため,当院小児科受診.検査の結果,貧血と血小板著減のため当日緊急入院となった.
緊急検査の結果は,末梢血血算では,白血球数5,200/μl,赤血球数282万/μl,ヘモグロビン7.1g/dl,血小板数1.2万/μlであった.血液像検査では骨髄球3.5%,後骨髄球1.0%,桿状核好中球7.0%,分節核好中球36.5%,好酸球1.0%,単球4.5%,リンパ球4%,異型リンパ球0.5%が見られた.ただちに骨髄穿刺が行われ,図1に示すような細胞が98%を占めた.細胞化学検査のペルオキシダーゼ反応は陰性であった.また,細胞表面マーカーの結果ではCD56が陽性以外は腫瘍細胞の陽性所見は認めなかった.図1にメイ-ギムザ染色(May-Giemsa stain)像を,図2にSSC/CD45スキャッターグラムを示す.
6月号の解答と解説
著者: 秋山利行
ページ範囲:P.643 - P.643
【問題1】 解答:①小型球状赤血球(破砕含)
解説:赤血球を50℃以上に熱すると破砕赤血球,球状赤血球が生じる.その程度は,温度と温度にさらされている時間とにより変形度合いが違い,浸透圧や物理的刺激に対して脆弱となる.球状・楕円など,赤血球形態変形は細胞骨格蛋白質を含む赤血球膜蛋白質の減少,あるいはその不安定性によるものとされる.赤血球膜の構造と機能との概要を以下に述べる.
赤血球膜は脂質の二重層で構成され,内側は細胞骨格により裏打ちされている.その細胞骨格はフィラメント,すなわちα,βスペクトリンから成る網目構造をなす.フィラメントには球状蛋白質粒子であるアンキリンが付着し,フィラメントの両端にはアクチンとバンド4,1の結合体が接着している.これらは末梢性蛋白質と総称される.
けんさ質問箱Q&A
抗M抗体の性状は
著者: 石井規子
ページ範囲:P.683 - P.684
血液型検査にEDTA-2Kを抗凝固剤として採血した検体を使用しています.抗M抗体はEDTAと反応してウラ試験で凝集を起こすことがあると聞きましたがどういう機序によるのでしょうか,教えてください.また,抗M抗体は低温でしか反応しないので臨床的意義はないといわれ,また溶血性副作用があるとのことですがどうなのでしょうか,併せて教えてください.(長野県上田市 Y.T.生)
■抗M抗体とは
抗M抗体はMNSs血液型のM抗原に対して産生される抗体です.MNSs血液型は40種類の抗原で構成される複雑な赤血球の血液型ですが,臨床的に重要なのはM,N,S,s抗原です.表1にM,N抗原の頻度を示します.M抗原,N抗原は赤血球膜の脂質二重層を貫通する糖蛋白であるグリコフォリンA(GPA)に存在し,S,s抗原は同様にグリコフォリンB(GPB)に存在1)します.ブロメリンやフィシンなどの蛋白分解酵素を作用させるとこれらの糖蛋白が特定の位置で切断されるためM,N抗原が消失します(S,s抗原については意見が統一されていません).抗M抗体や抗N抗体を酵素法で検出できないのはこのためです.
携帯電話が及ぼす医療機器への影響
著者: 古幡博
ページ範囲:P.684 - P.686
各種医療機器は携帯電話の電磁波の影響を受けるといわれていますが,具体的には医療機器のどのような機能に影響を及ぼすのでしょうか.例えばHolter心電図の波形などにはどの程度影響してくるのでしょうか.(千葉県松戸市 E.N.生)
はじめに
携帯電話はさまざまな機能を持つようになり社会生活の多様な場面で使用され,病院内においても例外ではありません.携帯電話はその発信する電磁波が医用電気機器に影響を与えることが心配されています.しかし,現在は携帯電話にも医療機器にもさまざまな対策が施されてきています.
学会印象記 第54回日本医学検査学会
異分野間のチームワークから生まれる独創性
著者: 芝田宏美
ページ範囲:P.694 - P.694
第54回日本医学検査学会が,2005年5月13,14日京都で開催された.ほぼ期日を同じくして,京都三大祭の一つ,葵祭があり,京都はいつも以上に雅の趣を呈し,好天にもめぐまれ,まつりごとには相応しい好日となった.国立京都国際会議場は洛北に位置し,新緑の山々に囲まれた美しい景観を有している.会場では多くのスタッフの方々が各コーナーに立ち,にこやかに大きな声で挨拶をされていた様子が快く,会場内にある満開のつつじの花の出迎えと同様に印象的であった.
検査学会ではここ数年,チーム医療にかかわる報告が多くみられる傾向にある.今大会でも医療連携・診療支援・糖尿病療養指導といったテーマが目立った.そこでチーム医療を中心にその他いくつかの演題に参加し,特に印象に残った知見について紹介したい.
初参加の日本医学検査学会で刺激・活力を得て,自分なりの考えに
著者: 佐野あゆみ
ページ範囲:P.695 - P.695
第54回日本検査医学学会が2005年5月13日と14日の2日間,京都国際会館で開催されました.私は,13日の業務終了後,職場の先輩方とともに静岡を出発し,京都へは同日の夜に到着しました.よって学会へは翌14日,1日のみの参加となりました.学会会場は京都駅から地下鉄で20分ほどと立地がよく,周囲は緑豊かで,清々しい気持ちにさせてくれました.
本学会へは初めての参加であり,今回の目的の一つは,演者として示説発表を行うことでした.昨年の中部学会での口演発表の経験はありましたが,示説発表は初めての経験でした.ポスター展示会場に行き,発表風景を目の当たりにしてみると,示説発表は聴衆の方々との距離がかなり近いことに驚きました.大勢の人たちが人垣をつくり,演者を注目しています.私の発表の番が近づくにつれて,さらに大勢の方が集まっているように感じました.そして,私のポスターを見入ってくださる姿を見て,私の発表内容に興味を持ってくださっていることを嬉しくも思い,同時に厳しい質問をされるのではないかとよりいっそう緊張が高まりました.いよいよ私の番になりました.大勢の方に囲まれ,緊張はピークに達していましたが,とにかく大きな声で,自信をもって発表することを心掛けました.そして,上司や先輩方に見守られ,無事に発表を終えることができました.発表後,他施設の方々から,質問やアドバイスをいただき,貴重な意見交換の場として交流を深めることができ,大変有意義な時間となりました.
古き土地で未来を考える
著者: 石垣宏之
ページ範囲:P.696 - P.696
薄暗い山の陰から特急に乗り,山に陽の当たる場所に出る.そこから新幹線に乗り換え京都に着くまで約3時間半.いつもなら座席に着いた途端にプシュッと缶ビールのプルトップのはじける音をさせるのだけれど,今日は午後から座長という大切な役目があるので,お茶で我慢しながら抄録集に目を通す.簡単に眠りに落ちてしまい,気がついたら京都駅.
地下鉄烏丸線で国際会議場を目指す.車中で和服の女性の多さに目が留まる.和服を着用していると,何かと特典があるらしく,特典のために和服を着用する人が増加する.京都には,和服の女性がよく似合う.これも知恵と創造で京都の未来を考えてのことだろう.
コーヒーブレイク
血球計数機の数男くん
著者: 衣幡美貴
ページ範囲:P.664 - P.664
は,はじめまして.自動血球計数機の数男と申します.検査室に来て半年のまだまだ新米検査機器です.僕の仕事は全血算(complete blood count,CBC)の測定です.白血球,赤血球,血小板数,ヘモグロビン(Hb),ヘマトクリット(Ht)などを測定し,同時にMCV,MCH,MCHCなどの赤血球恒数を算出しております.用手法と比べると,短時間で多数の検体の処理が可能で,今や検査室にはなくてはならない機器といわれています.
ぼ,僕の算出するデータが患者さんの治療に繁がると思うと,毎日ドキドキしながら検査しています.僕の算出するデータしだいで,患者さんの治療が変わってしまうんですものね.緊張せずにはいられません.
基本情報
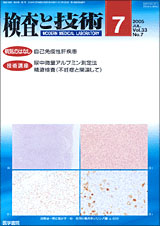
バックナンバー
52巻12号(2024年12月発行)
技術講座 生理
52巻11号(2024年11月発行)
技術講座 生理
52巻10号(2024年10月発行)
技術講座 生理
52巻9号(2024年9月発行)
増大号 臨床医に伝わりやすい 検査報告書とパニック値報告の心得
52巻8号(2024年8月発行)
技術講座 生理
52巻7号(2024年7月発行)
技術講座 生理
52巻6号(2024年6月発行)
技術講座 生理
52巻5号(2024年5月発行)
技術講座 その他
52巻4号(2024年4月発行)
技術講座 生理
52巻3号(2024年3月発行)
増大号 POCUSの決め手。 早く、正確な診断のために
52巻2号(2024年2月発行)
技術講座 生理
52巻1号(2024年1月発行)
技術講座 その他
51巻12号(2023年12月発行)
技術講座 生理
51巻11号(2023年11月発行)
技術講座 生理
51巻10号(2023年10月発行)
技術講座 その他
51巻9号(2023年9月発行)
増大号 匠から学ぶ 血栓止血検査ガイド
51巻8号(2023年8月発行)
技術講座 生理
51巻7号(2023年7月発行)
技術講座 生理
51巻6号(2023年6月発行)
技術講座 生理
51巻5号(2023年5月発行)
技術講座 生理
51巻4号(2023年4月発行)
技術講座 生理
51巻3号(2023年3月発行)
増大号 症例から学ぶ 疾患と検査値の推移
51巻2号(2023年2月発行)
技術講座 その他
51巻1号(2023年1月発行)
技術講座 生理
50巻12号(2022年12月発行)
技術講座 その他
50巻11号(2022年11月発行)
技術講座 生理
50巻10号(2022年10月発行)
技術講座 生理
50巻9号(2022年9月発行)
増大号 希少例と特殊像がわかる! エコーの撮り方完全マスター
50巻8号(2022年8月発行)
技術講座 生理
50巻7号(2022年7月発行)
技術講座 生理
50巻6号(2022年6月発行)
技術講座 生理
50巻5号(2022年5月発行)
技術講座 生理
50巻4号(2022年4月発行)
技術講座 生理
50巻3号(2022年3月発行)
増大号 見て学ぶ 一般検査学アトラス—外観検査から顕微鏡検査まで
50巻2号(2022年2月発行)
技術講座 その他
50巻1号(2022年1月発行)
技術講座 生理
49巻12号(2021年12月発行)
技術講座 生理
49巻11号(2021年11月発行)
技術講座 生理
49巻10号(2021年10月発行)
技術講座 生理
49巻9号(2021年9月発行)
増刊号 病態別 腹部エコーの観察・記録・報告書作成マスター
49巻8号(2021年8月発行)
技術講座 生理
49巻7号(2021年7月発行)
技術講座 生理
49巻6号(2021年6月発行)
技術講座 生理
49巻5号(2021年5月発行)
技術講座 生理
49巻4号(2021年4月発行)
技術講座 一般
49巻3号(2021年3月発行)
増刊号 First&Next Step 微生物検査サポートブック
49巻2号(2021年2月発行)
技術講座 微生物
49巻1号(2021年1月発行)
技術講座 病理・生理
48巻12号(2020年12月発行)
技術講座 その他
48巻11号(2020年11月発行)
技術講座 生化学
48巻10号(2020年10月発行)
技術講座 生理
48巻9号(2020年9月発行)
増刊号 学会発表・論文執筆はもう怖くない! 臨床検査技師のための研究入門
48巻8号(2020年8月発行)
技術講座 遺伝子
48巻7号(2020年7月発行)
技術講座 その他
48巻6号(2020年6月発行)
技術講座 輸血
48巻5号(2020年5月発行)
技術講座 生化学
48巻4号(2020年4月発行)
技術講座 生理
48巻3号(2020年3月発行)
増刊号 採血のすべて—手技から採血室の運用まで徹底解説
48巻2号(2020年2月発行)
技術講座 微生物
48巻1号(2020年1月発行)
技術講座 生理
47巻12号(2019年12月発行)
技術講座 病理
47巻11号(2019年11月発行)
技術講座 生理
47巻10号(2019年10月発行)
技術講座 生理
47巻9号(2019年9月発行)
増刊号 染色画像を比べて学ぶ 体腔液アトラス
47巻8号(2019年8月発行)
技術講座 病理
47巻7号(2019年7月発行)
技術講座 一般
47巻6号(2019年6月発行)
技術講座 血液
47巻5号(2019年5月発行)
技術講座 血液
47巻4号(2019年4月発行)
技術講座 血液
47巻3号(2019年3月発行)
増刊号 エキスパートが教える 心・血管エコー計測のノウハウ
47巻2号(2019年2月発行)
技術講座 病理
47巻1号(2019年1月発行)
技術講座 微生物
46巻12号(2018年12月発行)
技術講座 生理
46巻11号(2018年11月発行)
技術講座 輸血・遺伝子検査
46巻10号(2018年10月発行)
技術講座 その他
46巻9号(2018年9月発行)
増刊号 現場で“パッ”と使える 免疫染色クイックガイド
46巻8号(2018年8月発行)
技術講座 輸血・遺伝子検査
46巻7号(2018年7月発行)
技術講座 生理
46巻6号(2018年6月発行)
技術講座 管理
46巻5号(2018年5月発行)
技術講座 生化学
46巻4号(2018年4月発行)
技術講座 一般
46巻3号(2018年3月発行)
増刊号 感染症クイックリファレンス
46巻2号(2018年2月発行)
技術講座 輸血
46巻1号(2018年1月発行)
技術講座 病理
45巻12号(2017年12月発行)
技術講座 生理
45巻11号(2017年11月発行)
技術講座 一般
45巻10号(2017年10月発行)
技術講座 微生物
45巻9号(2017年9月発行)
増刊号 循環器病院の技師が教える メディカルスタッフのための心電図教室
45巻8号(2017年8月発行)
技術講座 栄養
45巻7号(2017年7月発行)
技術講座 病理
45巻6号(2017年6月発行)
技術講座 病理
45巻5号(2017年5月発行)
技術講座 細胞治療・管理
45巻4号(2017年4月発行)
技術講座 遺伝子・染色体検査
45巻3号(2017年3月発行)
45巻2号(2017年2月発行)
技術講座 細胞治療
45巻1号(2017年1月発行)
技術講座 病理
44巻13号(2016年12月発行)
技術講座 免疫
44巻12号(2016年11月発行)
技術講座 微生物
44巻11号(2016年10月発行)
技術講座 微生物
44巻10号(2016年9月発行)
増刊号 はじめて出会う 検査画像
44巻9号(2016年9月発行)
技術講座 管理・その他
44巻8号(2016年8月発行)
技術講座 微生物
44巻7号(2016年7月発行)
技術講座 生理
44巻6号(2016年6月発行)
技術講座 微生物
44巻5号(2016年5月発行)
技術講座 生理
44巻4号(2016年4月発行)
技術講座 微生物
44巻3号(2016年3月発行)
技術講座 生理
44巻2号(2016年2月発行)
技術講座 微生物
44巻1号(2016年1月発行)
技術講座 微生物
43巻13号(2015年12月発行)
技術講座 生化学
43巻12号(2015年11月発行)
技術講座 生化学
43巻11号(2015年10月発行)
技術講座 一般
43巻10号(2015年9月発行)
増刊号 血液形態アトラス
43巻9号(2015年9月発行)
技術講座 生理
43巻8号(2015年8月発行)
技術講座 生理
43巻7号(2015年7月発行)
技術講座 生理
43巻6号(2015年6月発行)
技術講座 微生物
43巻5号(2015年5月発行)
技術講座 移植医療
43巻4号(2015年4月発行)
技術講座 病理
43巻3号(2015年3月発行)
技術講座 血液
43巻2号(2015年2月発行)
技術講座 管理
43巻1号(2015年1月発行)
技術講座 病理
42巻13号(2014年12月発行)
技術講座 生化学
42巻12号(2014年11月発行)
技術講座 病理
42巻11号(2014年10月発行)
技術講座 血液
42巻10号(2014年9月発行)
増刊号 超音波×病理 対比アトラス
42巻9号(2014年9月発行)
技術講座 生理
42巻8号(2014年8月発行)
技術講座 免疫
42巻7号(2014年7月発行)
技術講座 生理
42巻6号(2014年6月発行)
技術講座 生理
42巻5号(2014年5月発行)
技術講座 病理
42巻4号(2014年4月発行)
技術講座 輸血
42巻3号(2014年3月発行)
技術講座 血液
42巻2号(2014年2月発行)
技術講座 微生物
42巻1号(2014年1月発行)
技術講座 病理
41巻13号(2013年12月発行)
技術講座 生理
41巻12号(2013年11月発行)
技術講座 生化学
41巻11号(2013年10月発行)
技術講座 生化学
41巻10号(2013年9月発行)
増刊号 解剖と正常像がわかる! エコーの撮り方完全マスター
41巻9号(2013年9月発行)
技術講座 微生物
41巻8号(2013年8月発行)
技術講座 生理
41巻7号(2013年7月発行)
技術講座 生理
41巻6号(2013年6月発行)
技術講座 微生物
41巻5号(2013年5月発行)
技術講座 一般
41巻4号(2013年4月発行)
技術講座 生化学
41巻3号(2013年3月発行)
技術講座 生理
41巻2号(2013年2月発行)
技術講座 生理
41巻1号(2013年1月発行)
技術講座 生理
40巻13号(2012年12月発行)
技術講座 血液
40巻12号(2012年11月発行)
技術講座 生理
40巻11号(2012年10月発行)
技術講座 生理
40巻10号(2012年9月発行)
増刊号 この検査データを読めますか?―検査値から病態を探る
40巻9号(2012年9月発行)
技術講座 生理
40巻8号(2012年8月発行)
技術講座 細胞診
40巻7号(2012年7月発行)
技術講座 生理
40巻6号(2012年6月発行)
技術講座 生理
40巻5号(2012年5月発行)
技術講座 生理
40巻4号(2012年4月発行)
技術講座 血液
40巻3号(2012年3月発行)
技術講座 生理
40巻2号(2012年2月発行)
技術講座 輸血
40巻1号(2012年1月発行)
技術講座 遺伝子
39巻13号(2011年12月発行)
疾患と検査値の推移
39巻12号(2011年11月発行)
疾患と検査値の推移
39巻11号(2011年10月発行)
疾患と検査値の推移
39巻10号(2011年9月発行)
増刊号 緊急報告すべき検査結果のすべて―すぐに使えるパニック値事典
39巻9号(2011年9月発行)
疾患と検査値の推移
39巻8号(2011年8月発行)
疾患と検査値の推移
39巻7号(2011年7月発行)
疾患と検査値の推移
39巻6号(2011年6月発行)
技術講座 生理
39巻5号(2011年5月発行)
技術講座 生理
39巻4号(2011年4月発行)
疾患と検査値の推移
39巻3号(2011年3月発行)
疾患と検査値の推移
39巻2号(2011年2月発行)
疾患と検査値の推移
39巻1号(2011年1月発行)
疾患と検査値の推移
38巻13号(2010年12月発行)
疾患と検査値の推移
38巻12号(2010年11月発行)
疾患と検査値の推移
38巻11号(2010年10月発行)
疾患と検査値の推移
38巻10号(2010年9月発行)
増刊号 免疫反応と臨床検査2010
38巻9号(2010年9月発行)
疾患と検査値の推移
38巻8号(2010年8月発行)
疾患と検査値の推移
38巻7号(2010年7月発行)
疾患と検査値の推移
38巻6号(2010年6月発行)
疾患と検査値の推移
38巻5号(2010年5月発行)
疾患と検査値の推移
38巻4号(2010年4月発行)
疾患と検査値の推移
38巻3号(2010年3月発行)
疾患と検査値の推移
38巻2号(2010年2月発行)
疾患と検査値の推移
38巻1号(2010年1月発行)
疾患と検査値の推移
37巻13号(2009年12月発行)
疾患と検査値の推移
37巻12号(2009年11月発行)
疾患と検査値の推移
37巻11号(2009年10月発行)
疾患と検査値の推移
37巻10号(2009年9月発行)
増刊号 顕微鏡検査のコツ―臨床に役立つ形態学
37巻9号(2009年9月発行)
疾患と検査値の推移
37巻8号(2009年8月発行)
疾患と検査値の推移
37巻7号(2009年7月発行)
疾患と検査値の推移
37巻6号(2009年6月発行)
疾患と検査値の推移
37巻5号(2009年5月発行)
疾患と検査値の推移
37巻4号(2009年4月発行)
疾患と検査値の推移
37巻3号(2009年3月発行)
疾患と検査値の推移
37巻2号(2009年2月発行)
疾患と検査値の推移
37巻1号(2009年1月発行)
疾患と検査値の推移
36巻13号(2008年12月発行)
疾患と検査値の推移
36巻12号(2008年11月発行)
疾患と検査値の推移
36巻11号(2008年10月発行)
疾患と検査値の推移
36巻10号(2008年9月発行)
増刊号 これから広がる生理検査・新たにはじまる生理検査
36巻9号(2008年9月発行)
疾患と検査値の推移
36巻8号(2008年8月発行)
疾患と検査値の推移
36巻7号(2008年7月発行)
疾患と検査値の推移
36巻6号(2008年6月発行)
疾患と検査値の推移
36巻5号(2008年5月発行)
疾患と検査値の推移
36巻4号(2008年4月発行)
疾患と検査値の推移
36巻3号(2008年3月発行)
疾患と検査値の推移
36巻2号(2008年2月発行)
疾患と検査値の推移
36巻1号(2008年1月発行)
疾患と検査値の推移
35巻13号(2007年12月発行)
疾患と検査値の推移
35巻12号(2007年11月発行)
疾患と検査値の推移
35巻11号(2007年10月発行)
増刊号 メタボリックシンドローム健診検査技術マニュアル
35巻10号(2007年10月発行)
疾患と検査値の推移
35巻9号(2007年9月発行)
疾患と検査値の推移
35巻8号(2007年8月発行)
疾患と検査値の推移
35巻7号(2007年7月発行)
疾患と検査値の推移
35巻6号(2007年6月発行)
疾患と検査値の推移
35巻5号(2007年5月発行)
疾患と検査値の推移
35巻4号(2007年4月発行)
疾患と検査値の推移
35巻3号(2007年3月発行)
疾患と検査値の推移
35巻2号(2007年2月発行)
疾患と検査値の推移
35巻1号(2007年1月発行)
疾患と検査値の推移
34巻13号(2006年12月発行)
技術講座 生理
34巻12号(2006年11月発行)
技術講座 一般
34巻11号(2006年10月発行)
増刊号 新しい臨床検査・未来の臨床検査
34巻10号(2006年10月発行)
疾患と検査値の推移
34巻9号(2006年9月発行)
疾患と検査値の推移
34巻8号(2006年8月発行)
疾患と検査値の推移
34巻7号(2006年7月発行)
疾患と検査値の推移
34巻6号(2006年6月発行)
疾患と検査値の推移
34巻5号(2006年5月発行)
疾患と検査値の推移
34巻4号(2006年4月発行)
疾患と検査値の推移
34巻3号(2006年3月発行)
疾患と検査値の推移
34巻2号(2006年2月発行)
疾患と検査値の推移
34巻1号(2006年1月発行)
疾患と検査値の推移
33巻13号(2005年12月発行)
疾患と検査値の推移
33巻12号(2005年11月発行)
疾患と検査値の推移
33巻11号(2005年10月発行)
増刊号 一線診療のための臨床検査
33巻10号(2005年10月発行)
疾患と検査値の推移
33巻9号(2005年9月発行)
疾患と検査値の推移
33巻8号(2005年8月発行)
疾患と検査値の推移
33巻7号(2005年7月発行)
疾患と検査値の推移
33巻6号(2005年6月発行)
疾患と検査値の推移
33巻5号(2005年5月発行)
疾患と検査値の推移
33巻4号(2005年4月発行)
疾患と検査値の推移
33巻3号(2005年3月発行)
疾患と検査値の推移
33巻2号(2005年2月発行)
疾患と検査値の推移
33巻1号(2005年1月発行)
疾患と検査値の推移
32巻13号(2004年12月発行)
技術講座 血液
32巻12号(2004年11月発行)
技術講座 病理
32巻11号(2004年10月発行)
技術講座 血液
32巻10号(2004年9月発行)
増刊号 細胞像の見かた―病理・血液・尿沈渣
32巻9号(2004年9月発行)
技術講座 生化学
32巻8号(2004年8月発行)
技術講座 免疫
32巻7号(2004年7月発行)
技術講座 微生物
32巻6号(2004年6月発行)
技術講座 病理
32巻5号(2004年5月発行)
技術講座 病理
32巻4号(2004年4月発行)
技術講座 病理
32巻3号(2004年3月発行)
技術講座 微生物
32巻2号(2004年2月発行)
技術講座 生化学
32巻1号(2004年1月発行)
技術講座 微生物
31巻13号(2003年12月発行)
技術講座 微生物
31巻12号(2003年11月発行)
技術講座 病理
31巻11号(2003年10月発行)
技術講座 微生物
31巻10号(2003年9月発行)
増刊号 包括医療と臨床検査
31巻9号(2003年9月発行)
技術講座 一般
31巻8号(2003年8月発行)
技術講座 微生物
31巻7号(2003年7月発行)
技術講座 病理
31巻6号(2003年6月発行)
技術講座 免疫
31巻5号(2003年5月発行)
技術講座 一般
31巻4号(2003年4月発行)
技術講座 病理
31巻3号(2003年3月発行)
技術講座 生化学
31巻2号(2003年2月発行)
技術講座 免疫
31巻1号(2003年1月発行)
技術講座 免疫
30巻13号(2002年12月発行)
技術講座 生理
30巻12号(2002年11月発行)
技術講座 生理
30巻11号(2002年10月発行)
技術講座 生化学
30巻10号(2002年9月発行)
増刊号 誰でもわかる遺伝子検査
30巻9号(2002年9月発行)
技術講座 微生物
30巻8号(2002年8月発行)
技術講座 生化学
30巻7号(2002年7月発行)
技術講座 微生物
30巻6号(2002年6月発行)
技術講座 生化学
30巻5号(2002年5月発行)
技術講座 微生物
30巻4号(2002年4月発行)
技術講座 一般
30巻3号(2002年3月発行)
技術講座 生化学
30巻2号(2002年2月発行)
技術講座 一般
30巻1号(2002年1月発行)
技術講座 免疫
29巻13号(2001年12月発行)
技術講座 病理
29巻12号(2001年11月発行)
技術講座 生理
29巻11号(2001年10月発行)
技術講座 病理
29巻10号(2001年9月発行)
技術講座 病理
29巻9号(2001年8月発行)
技術講座 病理
29巻8号(2001年7月発行)
技術講座 生理
29巻7号(2001年6月発行)
増刊号 病理組織・細胞診のための日常染色法ガイダンス
29巻6号(2001年6月発行)
技術講座 微生物
29巻5号(2001年5月発行)
技術講座 生理
29巻4号(2001年4月発行)
技術講座 病理
29巻3号(2001年3月発行)
技術講座 微生物
29巻2号(2001年2月発行)
技術講座 微生物
29巻1号(2001年1月発行)
技術講座 一般
28巻13号(2000年12月発行)
技術講座 病理
28巻12号(2000年11月発行)
技術講座 病理
28巻11号(2000年10月発行)
技術講座 免疫
28巻10号(2000年9月発行)
技術講座 微生物
28巻9号(2000年8月発行)
技術講座 微生物
28巻8号(2000年7月発行)
技術講座 生理
28巻7号(2000年6月発行)
増刊号 血液検査実践マニュアル
28巻6号(2000年6月発行)
技術講座 免疫
28巻5号(2000年5月発行)
技術講座 血液
28巻4号(2000年4月発行)
技術講座 一般
28巻3号(2000年3月発行)
技術講座 生理
28巻2号(2000年2月発行)
技術講座 生化学
28巻1号(2000年1月発行)
技術講座 一般
27巻13号(1999年12月発行)
技術講座 病理
27巻12号(1999年11月発行)
技術講座 一般
27巻11号(1999年10月発行)
技術講座 生化学
27巻10号(1999年9月発行)
技術講座 免疫
27巻9号(1999年8月発行)
技術講座 病理
27巻8号(1999年7月発行)
技術講座 病理
27巻7号(1999年6月発行)
増刊号 緊急検査実践マニュアル
27巻6号(1999年6月発行)
技術講座 生化学
27巻5号(1999年5月発行)
技術講座 血液
27巻4号(1999年4月発行)
技術講座 一般
27巻3号(1999年3月発行)
技術講座 生理
27巻2号(1999年2月発行)
技術講座 微生物
27巻1号(1999年1月発行)
技術講座 生理
26巻13号(1998年12月発行)
技術講座 一般
26巻12号(1998年11月発行)
技術講座 病理
26巻11号(1998年10月発行)
技術講座 病理
26巻10号(1998年9月発行)
技術講座 生理
26巻9号(1998年8月発行)
技術講座 生理
26巻8号(1998年7月発行)
技術講座 生理
26巻7号(1998年6月発行)
増刊号 病理組織・細胞診実践マニュアル
26巻6号(1998年6月発行)
技術講座 病理
26巻5号(1998年5月発行)
技術講座 一般
26巻4号(1998年4月発行)
技術講座 病理
26巻3号(1998年3月発行)
技術講座 一般
26巻2号(1998年2月発行)
技術講座 生理
26巻1号(1998年1月発行)
技術講座 血液
25巻13号(1997年12月発行)
技術講座 一般
25巻12号(1997年11月発行)
技術講座 一般
25巻11号(1997年10月発行)
技術講座 生理
25巻10号(1997年9月発行)
技術講座 血液
25巻9号(1997年8月発行)
技術講座 一般
25巻8号(1997年7月発行)
技術講座 一般
25巻7号(1997年6月発行)
増刊号 輸血検査実践マニュアル
25巻6号(1997年6月発行)
技術講座 免疫
25巻5号(1997年5月発行)
技術講座 生理
25巻4号(1997年4月発行)
技術講座 生理
25巻3号(1997年3月発行)
技術講座 微生物
25巻2号(1997年2月発行)
技術講座 生理
25巻1号(1997年1月発行)
技術講座 一般
24巻13号(1996年12月発行)
技術講座 生理
24巻12号(1996年11月発行)
技術講座 一般
24巻11号(1996年10月発行)
技術講座 生理
24巻10号(1996年9月発行)
技術講座 管理
24巻9号(1996年8月発行)
技術講座 生理
24巻8号(1996年7月発行)
技術講座 生理
24巻7号(1996年6月発行)
増刊号 感染症検査実践マニュアル
24巻6号(1996年6月発行)
技術講座 病理
24巻5号(1996年5月発行)
技術講座 生理
24巻4号(1996年4月発行)
技術講座 生理
24巻3号(1996年3月発行)
技術講座 生理
24巻2号(1996年2月発行)
技術講座 生理
24巻1号(1996年1月発行)
技術講座 一般
23巻13号(1995年12月発行)
技術講座 生理
23巻12号(1995年11月発行)
技術講座 病理
23巻11号(1995年10月発行)
技術講座 微生物
23巻10号(1995年9月発行)
技術講座 生理
23巻9号(1995年8月発行)
技術講座 一般
23巻8号(1995年7月発行)
技術講座 免疫
23巻7号(1995年6月発行)
技術講座 生理
23巻6号(1995年5月発行)
技術講座 一般
23巻5号(1995年4月発行)
増刊号 臨床生理検査実践マニュアル画像検査を中心として
23巻4号(1995年4月発行)
技術講座 病理
23巻3号(1995年3月発行)
技術講座 病理
23巻2号(1995年2月発行)
技術講座 一般
23巻1号(1995年1月発行)
技術講座 生理
22巻13号(1994年12月発行)
技術講座 一般
22巻12号(1994年11月発行)
技術講座 一般
22巻11号(1994年10月発行)
技術講座 一般
22巻10号(1994年9月発行)
技術講座 一般
22巻9号(1994年8月発行)
技術講座 生理
22巻8号(1994年7月発行)
技術講座 病理
22巻7号(1994年6月発行)
技術講座 一般
22巻6号(1994年5月発行)
技術講座 一般
22巻5号(1994年4月発行)
増刊号 免疫検査実践マニュアル
22巻4号(1994年4月発行)
技術講座 生理
22巻3号(1994年3月発行)
技術講座 免疫
22巻2号(1994年2月発行)
技術講座 一般
22巻1号(1994年1月発行)
技術講座 生理
21巻13号(1993年12月発行)
技術講座 一般
21巻12号(1993年11月発行)
技術講座 一般
21巻11号(1993年10月発行)
技術講座 一般
21巻10号(1993年9月発行)
技術講座 生理
21巻9号(1993年8月発行)
技術講座 一般
21巻8号(1993年7月発行)
技術講座 病理
21巻7号(1993年6月発行)
技術講座 一般
21巻6号(1993年5月発行)
技術講座 生理
21巻5号(1993年4月発行)
増刊号 臨床化学実践マニュアル
21巻4号(1993年4月発行)
技術講座 生理
21巻3号(1993年3月発行)
技術講座 病理
21巻2号(1993年2月発行)
技術講座 生理
21巻1号(1993年1月発行)
技術講座 生理
20巻13号(1992年12月発行)
技術講座 一般
20巻12号(1992年11月発行)
技術講座 一般
20巻11号(1992年10月発行)
技術講座 一般
20巻10号(1992年9月発行)
技術講座 一般
20巻9号(1992年8月発行)
技術講座 一般
20巻8号(1992年7月発行)
技術講座 血液
20巻7号(1992年6月発行)
技術講座 一般
20巻6号(1992年5月発行)
増刊号 尿検査法
20巻5号(1992年5月発行)
技術講座 生理
20巻4号(1992年4月発行)
技術講座 生理
20巻3号(1992年3月発行)
技術講座 病理
20巻2号(1992年2月発行)
技術講座 一般
20巻1号(1992年1月発行)
技術講座 生理
19巻13号(1991年12月発行)
技術講座 管理
19巻12号(1991年11月発行)
技術講座 生理
19巻11号(1991年10月発行)
技術講座 生理
19巻10号(1991年9月発行)
技術講座 一般
19巻9号(1991年8月発行)
技術講座 一般
19巻8号(1991年7月発行)
技術講座 生理
19巻7号(1991年6月発行)
増刊号 臨床血液検査
19巻6号(1991年6月発行)
技術講座 生理
19巻5号(1991年5月発行)
技術講座 生理
19巻4号(1991年4月発行)
技術講座 一般
19巻3号(1991年3月発行)
技術講座 生理
19巻2号(1991年2月発行)
技術講座 生理
19巻1号(1991年1月発行)
技術講座 一般
18巻13号(1990年12月発行)
技術講座 生理
18巻12号(1990年11月発行)
技術講座 微生物
18巻11号(1990年10月発行)
技術講座 生理
18巻10号(1990年9月発行)
技術講座 一般
18巻9号(1990年8月発行)
技術講座 一般
18巻8号(1990年7月発行)
技術講座 一般
18巻7号(1990年6月発行)
技術講座 一般
18巻6号(1990年5月発行)
増刊号 血液・尿以外の体液検査法
18巻5号(1990年5月発行)
技術講座 一般
18巻4号(1990年4月発行)
技術講座 一般
18巻3号(1990年3月発行)
技術講座 血液
18巻2号(1990年2月発行)
技術講座 生理
18巻1号(1990年1月発行)
技術講座 生理
17巻13号(1989年12月発行)
技術講座 一般
17巻12号(1989年11月発行)
技術講座 一般
17巻11号(1989年10月発行)
技術講座 一般
17巻10号(1989年9月発行)
技術講座 一般
17巻9号(1989年8月発行)
技術講座 生理
17巻8号(1989年7月発行)
技術講座 血清
17巻7号(1989年6月発行)
技術講座 一般
17巻6号(1989年5月発行)
感染症の検査法 Ⅲ 検査法各論
17巻5号(1989年5月発行)
技術講座 一般
17巻4号(1989年4月発行)
技術講座 生理
17巻3号(1989年3月発行)
技術講座 病理
17巻2号(1989年2月発行)
技術講座 一般
17巻1号(1989年1月発行)
技術講座 生理
16巻13号(1988年12月発行)
技術講座 一般
16巻12号(1988年11月発行)
技術講座 一般
16巻11号(1988年10月発行)
技術講座 一般
16巻10号(1988年9月発行)
技術講座 生理
16巻9号(1988年8月発行)
技術講座 一般
16巻8号(1988年7月発行)
技術講座 一般
16巻7号(1988年6月発行)
免疫化学検査法 資料
16巻6号(1988年6月発行)
技術講座 一般
16巻5号(1988年5月発行)
技術講座 一般
16巻4号(1988年4月発行)
技術講座 病理
16巻3号(1988年3月発行)
技術講座 生理
16巻2号(1988年2月発行)
技術講座 一般
16巻1号(1988年1月発行)
技術講座 血液
15巻13号(1987年12月発行)
技術講座 一般
15巻12号(1987年11月発行)
技術講座 病理
15巻11号(1987年10月発行)
技術講座 細胞診
15巻10号(1987年9月発行)
技術講座 一般
15巻9号(1987年8月発行)
技術講座 細胞診
15巻8号(1987年7月発行)
技術講座 病理
15巻7号(1987年6月発行)
技術講座 病理
15巻6号(1987年5月発行)
技術講座 病理
15巻5号(1987年4月発行)
臨床生理検査と技術 座談会
15巻4号(1987年4月発行)
技術講座 生理
15巻3号(1987年3月発行)
技術講座 血液
15巻2号(1987年2月発行)
技術講座 一般
15巻1号(1987年1月発行)
技術講座 病理
14巻13号(1986年12月発行)
技術講座 一般
14巻12号(1986年11月発行)
技術講座 病理
14巻11号(1986年10月発行)
技術講座 血清
14巻10号(1986年9月発行)
技術講座 血清
14巻9号(1986年8月発行)
技術講座 生理
14巻8号(1986年7月発行)
技術講座 血清
14巻7号(1986年6月発行)
技術講座 病理
14巻6号(1986年5月発行)
技術講座 生理
14巻5号(1986年4月発行)
形態学的検査と技術 血液と病理
14巻4号(1986年4月発行)
技術講座 病理
14巻3号(1986年3月発行)
技術講座 細菌
14巻2号(1986年2月発行)
技術講座 病理
14巻1号(1986年1月発行)
技術講座 細菌
13巻12号(1985年12月発行)
技術講座 病理
13巻11号(1985年11月発行)
技術講座 病理
13巻10号(1985年10月発行)
技術講座 生理
13巻9号(1985年9月発行)
技術講座 病理
13巻8号(1985年8月発行)
技術講座 病理
13巻7号(1985年7月発行)
技術講座 血液
13巻6号(1985年6月発行)
技術講座 一般
13巻5号(1985年5月発行)
技術講座 病理
13巻4号(1985年4月発行)
技術講座 一般
13巻3号(1985年3月発行)
技術講座 血液
13巻2号(1985年2月発行)
技術講座 一般
13巻1号(1985年1月発行)
技術講座 血液
12巻12号(1984年12月発行)
技術講座 血液
12巻11号(1984年11月発行)
技術講座 病理
12巻10号(1984年10月発行)
技術講座 輸血
12巻9号(1984年9月発行)
技術講座 一般
12巻8号(1984年8月発行)
技術講座 細菌
12巻7号(1984年7月発行)
技術講座 細菌
12巻6号(1984年6月発行)
技術講座 生理
12巻5号(1984年5月発行)
技術講座 一般
12巻4号(1984年4月発行)
技術講座 病理
12巻3号(1984年3月発行)
技術講座 血液
12巻2号(1984年2月発行)
技術講座 一般
12巻1号(1983年12月発行)
技術講座 血清
11巻12号(1983年12月発行)
技術講座 一般
11巻11号(1983年11月発行)
技術講座 細菌
11巻10号(1983年10月発行)
技術講座 細胞診
11巻9号(1983年9月発行)
技術講座 一般
11巻8号(1983年8月発行)
技術講座 血清
11巻7号(1983年7月発行)
技術講座 細菌
11巻6号(1983年6月発行)
技術講座 一般
11巻5号(1983年5月発行)
技術講座 病理
11巻4号(1983年4月発行)
技術講座 一般
11巻3号(1983年3月発行)
技術講座 血液
11巻2号(1983年2月発行)
技術講座 一般
11巻1号(1983年1月発行)
技術講座 血液
10巻12号(1982年12月発行)
技術講座 一般
10巻11号(1982年11月発行)
技術講座 生理
10巻10号(1982年10月発行)
技術講座 血清
10巻9号(1982年9月発行)
技術講座 細菌
10巻8号(1982年8月発行)
技術講座 一般
10巻7号(1982年7月発行)
技術講座 病理
10巻6号(1982年6月発行)
技術講座 細菌
10巻5号(1982年5月発行)
技術講座 病理
10巻4号(1982年4月発行)
技術講座 血清
10巻3号(1982年3月発行)
技術講座 生化学
10巻2号(1982年2月発行)
技術講座 病理
10巻1号(1982年1月発行)
技術講座 生化学
9巻12号(1981年12月発行)
技術講座 細菌
9巻11号(1981年11月発行)
技術講座 生理
9巻10号(1981年10月発行)
技術講座 一般
9巻9号(1981年9月発行)
技術講座 血清
9巻8号(1981年8月発行)
技術講座 血清
9巻7号(1981年7月発行)
技術講座 生理
9巻6号(1981年6月発行)
技術講座 細菌
9巻5号(1981年5月発行)
技術講座 一般
9巻4号(1981年4月発行)
技術講座 一般
9巻3号(1981年3月発行)
技術講座 血清
9巻2号(1981年2月発行)
技術講座 一般
9巻1号(1981年1月発行)
技術講座 生化学
8巻12号(1980年12月発行)
技術講座 一般
8巻11号(1980年11月発行)
技術講座 生理
8巻10号(1980年10月発行)
技術講座 検体の取り扱いと保存
8巻9号(1980年9月発行)
技術講座 病理
8巻8号(1980年8月発行)
技術講座 生化学
8巻7号(1980年7月発行)
技術講座 一般
8巻6号(1980年6月発行)
技術講座 生理
8巻5号(1980年5月発行)
技術講座 生化学
8巻4号(1980年4月発行)
技術講座 血清
8巻3号(1980年3月発行)
技術講座 病理
8巻2号(1980年2月発行)
技術講座 一般
8巻1号(1980年1月発行)
技術講座 生化学
7巻12号(1979年12月発行)
技術講座 一般
7巻11号(1979年11月発行)
技術講座 一般
7巻10号(1979年10月発行)
技術講座 細菌
7巻9号(1979年9月発行)
技術講座 生理
7巻8号(1979年8月発行)
技術講座 病理
7巻7号(1979年7月発行)
技術講座 生理
7巻6号(1979年6月発行)
技術講座 一般
7巻5号(1979年5月発行)
技術講座 血液
7巻4号(1979年4月発行)
技術講座 生理
7巻3号(1979年3月発行)
技術講座 病理
7巻2号(1979年2月発行)
技術講座 細菌
7巻1号(1979年1月発行)
技術講座 生化学
6巻12号(1978年12月発行)
技術講座 細菌
6巻11号(1978年11月発行)
技術講座 病理
6巻10号(1978年10月発行)
技術講座 血清
6巻9号(1978年9月発行)
技術講座 細菌
6巻8号(1978年8月発行)
技術講座 生化学
6巻7号(1978年7月発行)
技術講座 一般
6巻6号(1978年6月発行)
技術講座 病理
6巻5号(1978年5月発行)
技術講座 生理
6巻4号(1978年4月発行)
技術講座 一般
6巻3号(1978年3月発行)
技術講座 病理
6巻2号(1978年2月発行)
技術講座 一般
6巻1号(1978年1月発行)
技術講座 病理
5巻12号(1977年12月発行)
技術講座 生理
5巻11号(1977年11月発行)
技術講座 一般
5巻10号(1977年10月発行)
技術講座 細菌付録
5巻9号(1977年9月発行)
技術講座 一般
5巻8号(1977年8月発行)
技術講座 生理
5巻7号(1977年7月発行)
技術講座 一般
5巻6号(1977年6月発行)
技術講座 一般
5巻5号(1977年5月発行)
技術講座 一般
5巻4号(1977年4月発行)
技術講座 一般
5巻3号(1977年3月発行)
技術講座 一般
5巻2号(1977年2月発行)
技術講座 一般
5巻1号(1977年1月発行)
技術講座 一般
4巻12号(1976年12月発行)
技術講座 一般
4巻11号(1976年11月発行)
技術講座 一般
4巻10号(1976年10月発行)
技術講座 一般
4巻9号(1976年9月発行)
技術講座 一般
4巻8号(1976年8月発行)
技術講座 一般
4巻7号(1976年7月発行)
技術講座 一般
4巻6号(1976年6月発行)
技術講座 一般
4巻5号(1976年5月発行)
技術講座 一般
4巻4号(1976年4月発行)
技術講座 一般
4巻3号(1976年3月発行)
技術講座 一般
4巻2号(1976年2月発行)
技術講座 一般
4巻1号(1976年1月発行)
技術講座 一般
3巻12号(1975年12月発行)
技術講座 一般
3巻11号(1975年11月発行)
技術講座 一般
3巻10号(1975年10月発行)
技術講座 一般
3巻9号(1975年9月発行)
技術講座 一般
3巻7号(1975年8月発行)
特集 必修 日常検査の実技
3巻6号(1975年6月発行)
技術講座 生理
3巻5号(1975年5月発行)
技術講座 一般
3巻4号(1975年4月発行)
技術講座 一般
3巻3号(1975年3月発行)
技術講座 一般
3巻2号(1975年2月発行)
技術講座 一般
3巻1号(1975年1月発行)
技術講座 一般
